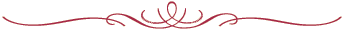
| 党派間ゲバルト考 |
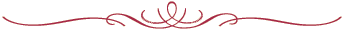
更新日/2024(平成31.5.1栄和改元/栄和6)年7.28日
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
「検証内ゲバ」は次のように記している。
70年安保闘争の頃より瀰漫し、70年代に満展開した「党派間のゲバルト」は、今日、一時より下火になっている。恐らく今後は再燃することはないだろう。とするならば、「党派間ゲバルト」考察の意義も減じているように見える。が、実際にはさにあらず。「党派間ゲバルト」が日本の左派戦線の昂揚に水を差し、そのことだけが理由ではないにせよ主因の一つであることは間違いないとして、今や新旧左翼共々が歴史的遺制にされようとしていることを思えば、左派戦線再構築の為にも「党派間ゲバルト」の歴史的総括が必要なのではないかと思われる。 そういう意識が獲得されつつある今日タイムリーにも、2001.11.25日「検証内ゲバ」(社会批評社)が出版された。早速この本を手にし読み進めているが、上述のような観点からの問題意識でアプローチしていることが分かった。だがしかしここに本章を設ける理由は、れんだいこは「検証内ゲバ」の著者達と少し見解を異にしている為である。併せて共々読み進めていただくならば得るところ大であろう。 れんだいこの捉え方との違いは、次のことにある。「検証内ゲバ」は題名から分かるように、あってはならない「内ゲバ」問題を今後どのように再発生させないかの観点から考察しようとしており、れんだいこは「党派間ゲバルト」と銘打つように避けられないものとして今後どのように対応していくべきかという観点から考察しようとしているという違いにある。この違いは見た目より案外と大きい。 が、この両見解の是非を論ずる前に、「党派間ゲバルト」がどのような史実を持っているのか客体としての認識を正確にしておきたい。「内ゲバを発生させてきた思想と運動・組織の根本的原因の分析・解明」(「検証内ゲバ」)に向かうこととする。 2005.3.2日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 目次 | |
| コード№ | 項目 |
| 「党派間ゲバルト」発生の土壌について | |
| れんだいこの「党派間ゲバルト理論」考 | |
| 「党派間ゲバルト問題」考としての黒寛理論考 | |
| 党派間ゲバルト考その1、戦後から1969年初まで | |
| 党派間ゲバルト考その2、1969年から1974年まで | |
| 党派間ゲバルト考その3、1975年から1979年まで | |
| 党派間ゲバルト考その4、1980年以降 | |
| 中核派と第四インターの「党派間ゲバルト」の経過と実態について | |
| 「党派間ゲバルトの感性」について | |
| 「党派間ゲバルト被害資料」 | |
| 「党派間ゲバルトの論理とその虚妄について」 | |
| 第四インターの「内ゲバ反対論」について | |
| 日本共産党の取締強化国会質疑考その1 | |
| 日本共産党の取締強化国会質疑考その2 | |
| 日本共産党の取締強化国会質疑考その3 | |
| 「検証内ゲバ」を廻る諸見解について | |
| 「蔵田計成氏の党派間ゲバルト見解」考 | |
| 「党派間ゲバルト」を促す公安戦略について | |
| 「党派ゲバ、内ゲバ抑止の試み史考」 | |
| 連合赤軍内粛清事件について | |
| ブント内「内ゲバ」事件について | |
| 社青同解放派内「内ゲバ」事件について | |
| ソ共におけるスターリン派とトロツキー派の抗争について | |
| 中国における「国共内戦」について | |
| 中国における「文化大革命」について | |
| Re守るも攻めるもテロの流れ(日本幕末時の倒幕志 士と新撰組の抗争について) |
|
| 山村政明焼身自殺事件/考 | |
| 「海老原俊夫君リンチ虐殺事件」考 | |
| 別章【川口大三郎君事件考】 | |
| 中核派対革マル派の新橋駅集団会戦考 | |
| 東京簡易裁判所 昭和48年(ろ)634号 判決 | |
| 東京地方裁判所 昭和62年(刑わ)2398号 判決 | |
| 「この手口の精神構造を問おう」 | |
| 「革マル派系活動家・水本潔(日本大学生)変死事件考」 | |
| 「白井朗氏へのテロ」考 | |
| 「小西誠への質問状」考 | |
| インターネットサイト | |
| 関連著作本 | |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)