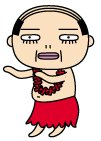
| 別章【ルネサンス(Renaissance)の研究】 | 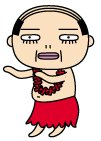 |
|
| ニシオノユウコ作 |

(最新見直し2005.10.24日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ルネサンスの意義が案外粗末にされている。れんだいこの見るところ、ルネサンスの後と以降は人類史の面貌を大きく変えている。そういう意味で、ルネサンスの史的意義はもっと確認されねばならない。ルネサンスは一朝一夕に為されたものではなく数世紀を経て醸成された近代精神のはしりである。 このルネサンスの経験と継承したが故に西欧諸国はその後、世界史の舞台全面に踊り出ることに成功したのではないのか。この点でアジア、イスラム、アフリカ諸国は画然と差をつけられており、この傾向は21世紀初頭の今日まで続いており、政体において例えて云えば大人と子供と稚児ほどの差を示しているのではないのか。その心は、人民大衆への規制緩和と自由闊達、創意工夫力の引き出し如何にある。 だがしかし、21世紀初頭に至って、そのルネサンスの歴史的高みが壊されようとしている気がしてならない。今や世界を牛耳る国際金融資本体とその現象態である米英ユ同盟が、元々はルネサンス的新秩序の中から生まれたのにも拘わらず、今や反ルネサンス的なネオ・シオニズムの純化思想で世界を統制し始めている。それは、近代から現代へ培われたルネサンスに対する「上からの反革命」と位置づけられるべき事象ではなかろうか。 ルネサンスの研究はこの観点から為さねばならない一里塚のように思えてならない。 2003.10.9日、2005.10.24日再編集 れんだいこ拝 |
| いろいろ思うにつけ、文明的に観て、ルネサンスの洗礼を受けた民族とこれを経過させていない民族の間には大きな溝があるのではなかろうか。今日のアングロ・サクソン民族の興隆の背景にあるものとしてルネサンス運動を再評価してみたくなった。 どういう意味かというと、ギリシャ・ローマ文明以降ヨーロッパ諸国はキリスト教国家として分立していくことになった。キリスト教は、ユダヤ教に対する対抗イデオロギーとしてヨーロッパ諸国の王朝理論として採用されていくことになった。 この時期を世界史的視野から見れば、ヨーロッパは低迷期に入っていたことになる。これはイデオロギー国家が持つ負の面であると思われる。この時代トルコ、アラブ、中国、日本における国家興隆の方が社会変革的であった。しかしながら、15世紀になってルネサンスを経由したヨーロッパは俄然活動期に入ることになり、相対的にその他諸国の方が安定期に入る。以降、この落差は今日まで続いており、今やアングロ・サクソン文明が世界史に蓋いつつあるやに見受けられる。 れんだいこは、文明にはそれを活性化させる態度と不燃化させるそれとがあって、不燃態度を受容した文明はいつしか滅びていくことになる。逆に、活性態度を継続せしめる限り文明は発展し続けていくのではなかろうか、との仮説を立てている。この文明生命力の秘密を探って見たいと思っている。 文明生命力とは、自然的な生命力(バイタリティ)に意志の力が加わり「やる気ないし覇気」に転じたものと考えられる。ラテン語で「ヴィルトゥス(Virtus)」、イタリア語で「ヴィルトゥ(Virtu)」と云われるものであるが、マキャベリは、この「ヴィルトゥ(Virtu)」は古代ならばギリシャからローマへ、ルネサンス期にはフィレンツェからローマへというように「民族間を移動する」と観察していた(塩野七生「ルネサンスとは何であったのか」)。この移動要因を考察することは興味ある課題ではなかろうか。主因に経済力があるとしても、それだけでは説明のつかない情動的なものに起因するプラスアルファ因子もあるのではなかろうか。 してみれば、我々が文明(狭義における社会)に変革を願う限りにおいて、何が発展を約束する因子で、何が停滞に導く因子であるかを分別し、これを賢明に操り社会に適応させる知恵を持たねばならないのではなかろうか。ルネサンスはその恰好の教材であり、人類史上の叡智と因子がここに結晶している、とれんだいこは見なしている。この観点から、ヨーロッパで経由したルネサンスの概要を、主に哲学・思想的観点からアプローチして見たい。 れんだいこは、今日の我が社会に覆う低迷は、政治的にも、経済的にも、文化的にも、思想的にも非ルネサンス的な統制原理が社会の隅々にこびりついたが故と考えている。従って、本稿の考究は恐らく自ずと、その苔・垢を剥離させることに向かうだろう。そうならないとならば我が洞察の及ばないが故であると自責せねばならぬ。 ここにルネサンスの何たるかを見事に表現した言葉がある、暫し愚考せよ。我々には「ゴンドラの唄」として知られている次の歌は、メディチ家当主ロレンツォの直々の作「バッカス(酒神)の歌」が原語である。
2005.3.5日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)