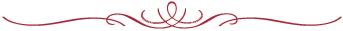
| ベネチアの歴史、ベネチアの黒い貴族の正体について |
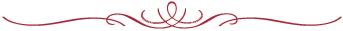
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
○いわゆる十字軍戦争の本当の演出者は、カトリックキリスト教会、
東ローマ帝国の東方正教キリスト教会、そしてイスラム世界の奥
深く浸透して居た「ベネチアの黒い貴族」である。
○このベネチアの黒い貴族の系統は、今はなお、「三百人委員会」
世界権力の中枢に存在する。
○彼等「三百人委員会」の戦略目標は、ユダヤキリスト教とイス
ラムの前面対決を導火線として、第三次世界大戦へと、地球人類
を誘導することだ。
カナン人
|
[ カテゴリ未分類 ] |
| 太田龍・氏の「時事寸評」の2005.3.1日付論考「シオニスト・キリスト教と言うこの現代の化け物が、宗教改革以来の、イルミナティの人工的産出物であると言う秘密」で次のような興味深い指摘が為されている。これを紹介しておく。趣旨不明であるが「無断転載厳禁」とあるので、れんだいこが意訳要約する。 1986年、グレース・ハルセル著「PROPHECY AND POLITICS(預言と政治)」が出版され、1989年、越智道雄訳で「核戦争を待望する人びと――聖書根本主義派潜入記」(朝日新聞社)として紹介された。グレース・ハルセルは、現代アメリカのプロテスタントキリスト教徒の女性であるが、彼女は、本書で、ハルマゲドン主義キリスト教徒、親シオニズム系キリスト教徒の言動に対して、鋭い批判を加えて居る。従って、当然のことながら、彼女は、今や米国国家社会の主流と成ったシオニストキリスト教陣営によって敵視されている。 同書は、202〜3Pで、いわゆる宗教改革によって登場したプロテスタントキリスト教徒がユダヤ教化して行く、その過程を指摘して居る。近年の米国の反ユダヤ反イルミナティ反NWO陣営の研究は、16世紀のカトリックキリスト教会の分裂は、イルミナティによって人工的に演出されたことを明らかにしているので、彼女の言説の正しさが裏付けられている。 プロテスタント運動には、二人の主要な指導者が生れた。一人は、ドイツのルターである。ルターは、最初、ユダヤ人勢力によって操作されて居たが、晩年、ユダヤの危険な正体に気付いて、激しくユダヤを批判するように成った。この問題については、ルターの「ユダヤ人と彼らの嘘」(雷韻出版)がある。 二人目は、スイス=フランスのカルヴィンである。カルヴィンは、れっきとしたユダヤ人であり、カルヴィン派キリスト教は、限りなくユダヤ化されたものである。このユダヤ的キリスト教としてのカルヴィン派は、オランダに入り、それから、英国に浸透して、クロムウェルのいわゆるピューリタン革命を起した。グレース・ハルセルは、同書204Pで、クロムウェルが、パレスチナにユダヤ人が帰還すればキリスト再臨の序曲になると明言している。この指摘は正しく、クロムウェルの時に、今日の米国のハルマゲドン主義者、シオニストキリスト教につながる起点を見出すことが出来る。 カルヴィン派のユダヤ化されたキリスト教は、英国からアメリカに渡った。従って、アメリカのキリスト教の中には、当初からカルヴィン派即ちユダヤ化されたキリスト教の勢力が存在する。 プロテスタント派キリスト教の大きな特徴は、ドイツ語、英語、フランス語など、各国ごとの国語に翻訳された聖書によって、新約のみならず旧約聖書を含む聖書が信徒の中に強力に注入されたことである。グレース・ハルセルは、そのことによって、プロテスタントキリスト教徒が急速にユダヤ化して行ったことを指摘している。 太田氏は次のように結ぶ。
|
|
|
|
「黒い貴族」によって仕組まれたプロテスタント宗教革命
こういった淫らなカルト宗教は、その多くが麻薬、とりわけアヘンとメスカリンの使用を薦める。
メスカリンは人格変容タイプの幻覚剤の一種だ。ただし、LSDは実はメスカリンではなく、エル
ゴタミンという、偏頭痛などの治療薬に今日広く使われている化学物質を元にしている。
ほとんど議論されることはないが、米国の殖民地が戦争に踏み切った理由は、彼らがイギリスの
アヘン政策に反対したためだ。ここでは、アヘン政策はイギリスの公式文書によるものだったと述
べておこう。これはもちろん、アヘン貿易のことだ。「ティー・クリッパー」といわれた有名な中国
からの快速帆船は、通常は茶ではなく、インドのベンガル地方から中国にかけての各地で積み込ん
だアヘンを、喫水線まで満載していた。別の著作でわたしは、ジョン・ジェイコブ・アスター一族
やラッセル家など、いわゆるアメリカの 「貴族」 ファミリーがこの 「死の貿易」 で果たした役割に
ついても論じている。アメリカ独立戦争時にイギリスの傭兵となったへッセン人への支払いは、実
はイギリスがアヘン貿易で蓄積した金から出たものだった。これは、東インド会社のスパイの元締
めから経済学者に転じたアダム・スミスが、その著『国富論』で明らかにしている。アダム・スミ
スは、まず何よりもアへソのプロモーターであり、経済学は二の次だった。
キリスト教原理主義者が歴史に最初に登場するエピソードのひとつは、イエズス会で訓練を受け
た宣教師がアヘン貿易に関わっていれというものだ。イエズス会はそれ自体、ヴェネチアの黒い貴
族によって、キリスト教世界を内側から破壊する目的で設立された教団だった。原理主義の宣教師
らが中国とのアヘソ貿易で働いていたのとまったく同じように、現代の中央アメリカでも、実に多
くのキリスト教原理主義宣教師がエルサルバドルやホンジュラスの政治に深く関わっている。大多
数は真撃な人物で、この点では、宗教的「大義」 のために三〇年戦争を戦った熱心な信者と変わら
ない。また、操られているという点も同じだ。
キリスト教原理主義者は、わたしが 「宗教もどき」とよぶ、この誤った考えを繰り返す傾向が特
に強い。そしてもうひとつ、キリスト教原理主義者が受け入れ、説いているなかで非常に悪質なの
が、流血や戦争(およびその噂) は「キリスト再臨がちかい」 ことを示す「計数器」だ、というも
のだ。これは平和の原動力とはならない。エルサルバドルやグアテマラでは、多くのキリスト教原
理主義者が 「カトリックと戦って」 いて、これも、同地域できわめて深刻な脅威となっている。
こういったプロテスタソト原理主義者のうちの何人が、プロテスタント宗教革命が仕組まれたも
のであったことを知っているのだろう。わたしは意図的に 「仕組まれた」 ということばを使ったが、
仕組んだのはヴェネチアとジェノアの黒い貴族ファミリーで、イエズス会の創始者であるイグナチ
ウス・ロヨラも彼らが作り上げたものだ。公平に見て、プロテスタソト原理主義とローマカトリッ
クのとの間の抗争は、地上でのキリストの業を広めるものではなく、むしろその敵であるカルト宗
教や秘密結社、そしてその主人 〔=地上でのキリストの業を憎む者ども) の手のなかで踊ることに
なる、と言うべきだろう。
現在も隠然とはぴこる悪魔崇拝のカルト宗教
このあたりは、これまでで、もっとも異論の多いテーマをあつかうことに
なるだろう。断っておくが、わたしは、さまぎまな教義や信仰に関する議論を始めるつもりはない。
ただ、陰謀家どもがキリスト教原理主義運動に対してやっていることを幅広く概観し、他のいくつ
かの宗教と同様に、連中がいかに卑劣かつ残酷にこれを悪用しているかを伝えたいだけだ。
この点については何度か自分の考えを発表してきたし、おそらくはそのために多くの批判を受け
てきたというのも確かなことだ。通常ならば、避けて通るのがベストな課題だが、中東や中央アメ
リカでの事件がクライマックスに達しょうとする今、すすんで困難に立ち向かう時がきたようだ。
同意するか、別の考えを取るかは読者にまかせるとして、少なくともわたしの視点を述べる機会だ
けはあたえてもらいたいと思う。
原理主義は、宗教においては何ら新しいものではないし、宗教的な熱情が燃え上がって戦争にな
ることも昔からあった。そのような戦争でもっとも重要な例は、ヴェネチアとジェノアの 「黒い貴
族」が煽動した三〇年戦争だ。これはヴェネアの 「黒いゲルフ」 であるバルデイス家やペレジス
家が宗教戦争を計画し、当時の原理主義者である熱狂的信者が戦ったものだが、その唯一の目的は、
信仰を広めることではなく、単一の教会がすべてを支配する「国家なき世界」という目的を堆進す
ることだった。それが三〇年戦争の狙いであり目的だった。それは、現在中央アメリカで進行中の
戦争ーわたしはよくこれを、第二の三〇年戦争とよんでいる − の狙い・目的でもある。この狙
いが達成されれば、教会は、黒い貴族やイギリスの石油ファミリーなど、銀行家ファミリーの絶対
権力下におかれる。
教会の支配について理解するには、ヘンリー八世の行動を見れば事足りる。ヘンリー八世は、表
向きはイギリス王であり、わたしも「王」ということばを使うが、実際にはヴェネチアやジェノア
の贈賄者や高利貸し、たとえばジェノアのゲルフであるバラピッチーニ家などの手に、しつかりと
握られていた。昔の黒いゲルフはその大多数(全部ではないにしろ) が、真の生ける神を信じてい
なかったし、現在も信じてはいない。神に対するリップサービスで教会へは行くが、見せかけだけ
だ。彼らが本当に信じているのは邪悪なカルト 「宗教」 だ。それはエジプトおよびメソポタミアに
源を発するもので、これをイエス・キリストが厳しく非難したことは、新約聖書を読めば分かる。
悪魔を崇拝するこのカルト宗教には、ホルス、カルデアン、ルシファー、アスタルテ、イシス、デ
イオニソス、マグナマーテルなど、さまざまな呼び名の神がいる。
これら邪悪な悪魔崇拝のカルト宗教は、その多くが、今日でも盛んにおこなわれている。実際に
は、キリストが地上に遣わされた時代よりも強力になっていると言ってもよい。これらはすべて人
間を不正に堕落させるもので、その中心は「狩猟採集社会」の 「地獄の九番目の輪」信仰を中心と
している。今ここで、こういった誤ったカルト宗教を詳しく説明することはしないが、いつか内々
の会を開いてこのテーマに興味のある人を集め、すべてを詳しく語ることもあるだろう。自分で何
か読んでみたいというなら、ブラヴァツキー夫人の『ヴエールを脱いだイシス 古代および現代の
科学および神学の神秘へのマスターキー』を読むのがよいだろう。宣伝するつもりはないが、実に
その内実がよく分かり、目を開かされる。それからもうひとつ、『セクシュアリティー、魔術、倒錯』
がある。著者はフランシス・キングという人物だ。
南ボヘミアのフス派が、どうにか一つの紐帯で結ばれつつあるとき、プラハでは事態がますます深刻化していた。
1419年11月上旬、皇帝ジギスムントは、王妃ジョフィエとチェコ大貴族たちの会議体を「ボヘミアの代理政権」と認定し、摂政ジョフィエに対し、速やかなる王位の引渡しを要請した。もちろん、王妃はこれを受け入れざるを得ない。
しかし、ジギスムントが「プラハ13箇条」に返答を寄越さないことに苛立ったプラハ市は、王妃の判断に不満であった。
11月下旬、ジギスムントは、王宮の整備のため、配下の騎士団をプラハ城に派遣した。ところが、この騎士団は棍棒や石礫で武装した市民たちと衝突し、入城できぬまま追い返されたのであった。
これは、旧市街や新市街の参事会の意図を越える偶発事件であった。一般市民たちの皇帝に対する敵意と憎悪は、それほどまでに深く激しかったのである。
しかし、民主主義政体であるプラハ市議会は、民衆の意向を重視した。彼らは、市の城壁の周囲に頑丈な防柵や陣地を築き、皇帝の報復に備えたのである。
「なんということでしょう・・・」旧市街王宮で、王妃は沈鬱な表情を隠せなかった。「あの者たちは、神聖ローマ皇帝に戦争を挑もうというのですか。プラハを、いや、このチェコ全土を戦火の炎にさらそうというのですか」
「市民たちは、神聖ローマ皇帝の恐ろしさを知らないのです」チュニック卿は、玉座の前にかしづいている。「ここは、最も重要な局面です。直ちに皇帝に使者を送り、その怒りを和らげてもらいましょう」
「チュニック卿よ、もはや、そなただけが頼りです」王妃は、目を潤ませた。「なんとか、この国を救ってたもれ・・・」
12月、ジョフィエ摂政と貴族会議の特使が、モラビア地方(現在のチェコ東部)の都ブルノに飛んだ。皇帝ジギスムントは、公用でブルノに滞在していたのである。
ジギスムントは、剣もほろろの態度で特使と会見した。
「プラハ市を統治する力量を持たぬ摂政と交渉して、この朕に何の得があるというのか」禿げかけた頭を前後に振りながら、厳しい叱正を吐く。「プラハ市は、まったくけしからん。フス派などと称する暴徒の跳梁跋扈を許してきたのみならず、今や、これを後押ししていることは明白ではないか。帝都の治安を揺るがせにしたその罪は、万死に値する」
そして彼は、次のような要求を打ち出したのである。
「追放されたカトリック派聖職者や市民を市に帰還させること。市が最近構築した城外の防御施設を撤去破壊すること。市の治安を揺るがせた主導者を処罰すること」
そして、プラハ13箇条については、
「朕の不在中に、勝手に取り決めた決議は全て無効である」
と宣言し、その効力を全面的に否定したのであった。これは、ジョフィエ王妃と貴族会議の権威を認めた11月の声明を覆す発言であった。
プラハ市は、正統な王位継承者であるジギスムントによって、その政治成果を完全に否定されてしまったのである。
王宮で特使の帰還を待ちわびていた王妃は、その口から悲観的な復命を受けると、ショックのあまり気を失ってしまった。
やがて意識を取り戻した王妃は、まだ30代の若さだというのに、老婆のように老け込んだ様子で、摂政の地位を降りることを宣言したのである。もはや、この事態を収拾できる自信は皆無だった。
貴族会議も、もはやどうにもならなかった。困り果てた貴族たちは、やがて長期不在中の領地の様子が不安になり、三々五々、騎士たちを連れて引き上げていった。
チュニック卿は最後まで市に留まり、そしてプラハ市議会にジギスムントの勧告を受け入れるようにと説得した。しかし、無駄だった。いきり立った市民たちには、ようやく勝ち得た自由を手放す気は、さらさら無かったのだ。
「戦争になるのだぞ・・・」チュニック卿は、額に眉を寄せた。
「望むところだ」新市街代表のジェリフスキーは、鋭い視線で大貴族を見た。「ジグムント(ジギスムントのチェコ語読み)は、黙示録に登場する『赤き龍』であろう。これを叩き潰すことこそ、我ら正しいキリスト教徒の使命なのだ」
「戦争のことなど何も知らぬそなたに、一体、何が分かるというのだ」チュニックは、濃い顎鬚を震わせた。「プラハの市民は、女子供を含めて総勢4万。どうやって、ドイツやハンガリー騎士団の精鋭と刃を交えるというのだ」
「正しい信仰は、何よりも強力な武器なのだ」ジェリフスキーは、その雷光のような視線を、大貴族から外そうとしなかった。「悪魔の群れに、負ける道理が無い」
チュニック卿が寂しげに首を左右に振ったそのとき、早馬が悲報をもたらした。
「一大事です。クトナー・ホラで、二重聖餐派の修道士たちが皇帝の配下に捕えられ、そして、古い坑道に突き落とされて皆殺しにされました」
「おお・・・」チュニックは嘆声をあげた。「もはや、事態はここまで進んでしまったというのか。皇帝は、我らを異端と認定したというのかっ」
「ジグムントめ」ジェリフスキーは、眦を裂いた。「神の怒りを知らぬ愚か者があ」
だが、年が明けて1420年に入ると、事態はますます悪化の一途を辿った。
皇帝の勅使はボヘミア全土に飛び、そして各都市や貴族に対し、「フス派の処刑」を厳命したのである。この事態を前に、それまで中立を守っていた都市や貴族たちは、続々とカトリック派に傾いていった。
プラハから所領の西ボヘミアに戻っていたロジュンベルク家のオルトシフ卿は、公然とカトリック派の旗を翻した。彼は、フス派を裏切ったのである。
それまで西ボヘミアのプルゼニを拠点としていたジシュカが、ターボルに引き移ることを決意したのも、実はこの情勢を慮った上での決断であった。
憂慮すべき事態は、これだけに留まらなかった。
3月、ローマ教皇マルティヌス5世は、イタリアのフィレンツェで『十字軍勅書』を発行したのである。
「忠実なる全キリスト教徒に告ぐ。ボヘミア王国は、今や危険な異端者によって乗っ取られようとしている。この異端を撲滅するために、教皇庁は十字軍の派遣を決定した。参加する者には、永遠の『贖罪』が与えられようぞ・・・」
戦争を奨励して『贖罪』とは、ほとんど笑い話みたいだが、この当時のヨーロッパ世界では、これが当たり前だった。ほとんどの欧州人が、教皇の言うことに疑いを持とうとはしなかった。教会の言うなりになって生きることが、神への道だと信じ込んでいたのである。
教皇マルティヌス5世は、コンスタンツ公会議の席上において、ジギスムントの推薦のお陰で教皇位に就いた人物であるから、皇帝の要請に応えてチェコへの出兵に協力することは当然であった。その行為が、いかに神の道に反しているかなどとは、少しも考え及ばなかったのである。もはや、そういう問題では無かったのである。
教皇特使ルカや司教フェルディナンドは、全欧州の宮廷を訪れて、十字軍への参加を懇請して回った。彼らの熱意は多くの封建諸侯の心を動かし、熱狂的な情熱に身を焦がす騎士たちが、次々に従軍志願していったのである。
参加国数35を越える巨大な軍隊が、今日の国連軍に匹敵する威力を持っていたことは間違いない。当時の世界で、これだけの破壊力を受け止めて無事でいられる存在が、あろうはずは無かった・・・。
ジギスムントが、チェコとプラハ市に対して強硬姿勢を取ったのは、この情勢を知悉していたからに他ならない。
全欧州の狂った情熱と偏見の炎が、今やこの小さな国を焼き尽くそうとしていた。
そのような事態が進行中だとは、南ボヘミアの人々は夢にも思っていなかった。
3月下旬に入ると、いよいよターボル市がその威容を見せ始めた。地下道や下水道が整備され、建物の礎石や石畳の舗装も目処がついたのである。中央広場の正面には、明るい彩色がなされた質朴な市民教会がそそり立つ。
アウスティ城とその郊外に寄宿する人々は、この知らせを受けて大いに喜び、我先にと荷車を引いて『真実の街』への行程を辿った。もちろん、ミクラーシュやジシュカの兵士たちが、周囲に警戒の眼を光らせながら護衛したことは言うまでもない。
そんなある日。
「うるさいウルリッヒの奴、この城を明け渡せば、大人しくなるやろか」アウスティの広間で、プロコプが呟いた。
「それは無理だろうな」ジシュカは首を左右に振った。「皇帝ジグムントは、ボヘミア各地に二重聖餐派の処刑を厳命している。もはや、ウルリッヒとて引っ込みは付かないだろう」
「そやな」プロコプは吐息をついた。「叔父とは、やはりここで雌雄を決するべきやな」
ウルリッヒと、この付近のカトリック派の中貴族たちから成る連合軍300騎は、先刻からアウスティ城下で喚声をあげていた。
「オチーク、パヴェク」ジシュカは、馴染みの腹心たちを振り返った。「出陣の準備をしろ。また、先陣にはピーシャラチを持たせろ」
「了解」2人の部下は、笑顔で敬礼をした。
アウスティ城の軍勢は、ジシュカやミクラーシュが引き連れてきた60名ほどの歩兵と、ヨハン親子の50騎を除けば、みな、棍棒をかついだ農民自警団である。まともに正面衝突したなら、とてもカトリック派連合軍に適うはずは無かった。
しかし、歴戦の戦巧者であるジシュカには、必勝の秘策があった。
跳ね橋を下ろして城外に飛び出したフス派連合軍は、かなたの丘陵地帯に陣を張るウルリッヒ軍の手前で陣形を組んだ。プロコプが率いる騎士団を後陣に据え、その前面と左右にベテラン歩兵団、さらに最後尾に、農具を抱えた農民兵を配置した。その総勢は300である。
ウルリッヒは、その有様を丘の上から眺めていた。
「見ろ、あの農民兵どもの恐々とした動きを。ヤン・ジシュカと言えど、あれではどうにもなるまい。一気に駆け下りて、蹴散らしてやろうぞ」
援軍に来てくれた騎士たちも、笑顔でうなずいた。彼らは、皇帝に要求する恩賞について胸算用を始めていた。
三列に並んだ騎士たちは、左右に従兵を連れ、長槍を頭上に振りかざし、兜を下げ、そしてラッパの音と共に突撃を開始したのである。
「いきなりチャージか。思ったとおりだ」眼前の丘から駆け下りてくる津波のような300騎を見ても、ジシュカは笑みを崩さない。そして、頃合を見て右手を高く上げた。
そのとたん、フス派軍の左右に陣取っていた10名づつの歩兵たちが、黒く細長い筒をその手に取った。その先端を敵騎士団に向けた次の瞬間、轟音と火煙があがり、そして馬から振り落とされた騎士たちで草原は埋め尽くされていた。
「なんだ」丘の上のウルリッヒは、事態が理解できずに当惑した。
彼の騎士団は、一瞬にして戦闘力を失っていた。次々に鳴り響く轟音と火煙に怯えた馬たちは、口から泡を吹いていきりたち、騎乗者たちを次々に振り落とすのである。そして、分厚い甲冑に覆われた騎士たちは、落馬したが最後、自力で起き上がることはできない。助け起こそうとした従者たちは、反撃を開始したプロコプの騎士団の馬蹄に踏まれていった。後続の農民兵たちは、鋤や鍬や鎌を振りながら、泥にまみれてうめく騎士たちに圧し掛かり、その装甲の隙間から致命的な一撃を与えていく。
「ちくしょう、土百姓ども、よくも」
絶叫したウルリッヒは、自ら騎乗の人となって、予備隊とともに丘を駆け下った。
敵の騎馬団と今まさに鉾を交えようとした彼の視界に、左横の木陰から3人ほどの歩兵が歩み出た。その両手には、黒い筒が握られている。
「なんだ、あれは」
次の瞬間、轟音と火煙が周囲を包み、馬から投げ出されたウルリッヒの体は、激しく大地に叩きつけられていた。その上に、真っ赤な血を吹きながら愛馬が倒れこんで来る。
「そうか、鉄砲か」
薄れ行く最期の意識の下で、ウルリッヒは己の敗因を知った。
全滅状態になったカトリック派の騎士たちの埋葬を終えた後、プロコプは、まだ熱を保ったままの黒い筒をその手にしていた。
「これが、ピーシャラチか」
「ヴェネチア人どもは、鉄砲と呼んでいるらしいが、俺は、もっと優雅にそう呼んでいるのだ」ジシュカは、笑顔で答えた。
「わいは、初めて見ました。イタリア人の発明品なのですか」
「もとは、トルコの武器だろう。そのトルコは、キタイ(中国)あたりから導入したらしいな。本場の奴は、もっと大きくて重い。小型軽量化したのは、イタリア人の智恵だろう。イタ公は、年がら年中戦争ばかりやっているから、そういう才には長けているのだ」
「どうやって使うのやろか」
「筒の先に、穴が開いているだろう。そこに、この鉄の玉を入れるんだ」ジシュカは、胸ポケットから弾丸を取り出した。「こうして、筒の先を上に向けて入れる。そして、この火縄だ。ここに火打石で火を点けると、ここの火薬に点火して、ズドンだ。一発撃ったら、火薬の燃えカスを掃除しなければならない」
「連射は出来へんのか」プロコプは落胆した。「そんなら、弓矢のほうが遥かに役に立つやありまへんか」
「そうかな。さっきの戦果を見ただろう」
「あれは、敵の騎士の数が少なくて、しかも戦場が狭かったからや」
「あははは、正にそのとおりだ。これから、ピーシャラチの数を増やし、そして、もっと効果的な戦法を考えなければならない。プロコプくん、協力してくれるな」
「ええ、それはもちろんや」
確かに、数さえ揃えば、かなりの威力が発揮できるだろう。また、これなら、戦闘経験の乏しい農民たちにも使いこなせるかもしれない。
「あと100丁は欲しいところだが」ジシュカは言った。「プルゼニの市議会から巻き上げて来たカネで、なんとかそれくらいは出来るだろう」
「あはは、ジシュカどの、悪やねえ」
「その悪のお陰で、今の君がいるんだぞ」
「それは、感謝しています。本当に」プロコプは、丘の上に立てられた十字架を見た。これは、ウルリッヒの墓石代わりと同時に、戦勝記念碑でもある。「奴も、死んで救われたのかもしれへんな・・・間違った信仰に縋って生きるより、死の安息のほうがマシやもんなあ。・・・あかん、こんなことペトルさんに知れたら怒られる」
「ん?ペトルの奴は、相変わらず奇麗事の非暴力主義なのか」
「ああ、あの人は、この戦いのことを知ったら、さぞかし悲しむやろう」
「頑固な若造だ。まあ、それが奴の良いところでもある」
二人は哄笑した。
しかし、ターボルで作事に励むペトルは、その全容を見せ始めた美しい街の様子に夢中になっていたので、戦場の動向など関心の外であった。
簡素な造りの市民教会は、プラハ旧市街のベトレヘム礼拝堂をモデルに建立された。ここの演壇に立つペトルは、作業の合間に労務者を集めて、チェコ語の説教を行った。聴衆は、目を輝かせながらペトルの講話に聞き入ってくれる。
「俺は、少しでもフス先生に近づきたい。そして、その理想をこの世界全体に広めていきたい。そして、このターボルこそ、第一歩なのだ」
そう思えるとき、ペトルは幸せだった。
「そういえば、プラハはどうなっているのだろう。イジーやトマーシュから、最近は便りが来なくなった。マリエさんは、そろそろ出産だと思うが、元気にやっているのだろうか。あいつらも、いっそのこと、この街に来れば良いのに・・・」
そのプラハ新市街では、マリエが無事に分娩を終えていた。産まれた男の子は、丸々と太って元気な声で泣いている。
「気が進まないわ」マリエは呟いた。
「どうしてだい」イジーは、赤ん坊をあやしながら妻を見やった。
「ジェリフスキーさん、なんだか恐いわ。昔の優しさが、少しも見えなくなった」
「でも、彼に洗礼をしてもらうのが、道理というものだろう。何しろ、新市街の聖務は、全て彼が取り仕切っている」
「あんな人に洗礼を受けて、この子は本当に幸せになれるかしら」
「そんなに嫌なら、旧市街の聖職者に頼んでみるか。プシーブラム先生もヤコウベク先生もいるし、なんなら、イギリス人のピーター先生でも」
「・・・あなたに任せるわ」産褥からあがったばかりの妻は、そう言ってため息をついた。
父のヤロスラフは、新市街の執政官になって以来、店をほったらかして市庁舎に入り浸っている。ウ・クリムは、母と15歳にもならない弟のヤンが見ている始末だ。そして、孫の顔さえろくに見に来ない。
ヤン・ジェリフスキーは、もっと酷い。修道士のくせに、最近は説教もしなくなった。それだけではない。時々、甲冑を纏って城門近くをウロウロしているらしい。いったい、どういうつもりなのだろうか。
「あなた」マリエは、気がかりなことを尋ねた。「戦争になるって、本当なの」
「・・・・・」イジーは、寝入った赤ん坊の頬を指で撫でた。
「プラハに皇帝が攻めてくるって、本当なの」
「お前は、そんなこと気にする必要はない」イジーは、きっぱりと言った。「例え世界がどうなろうと、お前とこの子の命は、この俺が必ず守ってみせる・・・」
彼には、そう言ってやることしか出来なかったのである。
だが、外界では、もはや戦争は不可避になっていた。
4月2日、ジェリフスキーは新市街の『雪の聖母マリア教会』で、久しぶりに攻撃的な演説を披露した。多数の聴衆を熱狂に導いたその内容は、皇帝ジギスムントを悪魔と断定し、徹底抗戦を呼びかけるものであった。皇帝を憎む新市街の人々は、むしろ恩師たちを惨死させたジギスムントとの戦争に大賛成だったのである。
4月3日、旧市街広場に、各市街のフス派教徒たち5千人が集結し、徹底抗戦を叫び続けた。そして、群衆の前に進み出たプラハ大学のヤン・プシーブラムは、次のような声明を発したのである。
「我々は、この命に代えても二重聖餐を守り続けねばならぬ。神の理想の国を守り続けなければならぬ。そのために、かつてフス師やイエロニーム師を見殺しにし、そして今も、我々を異端と呼んでいるジグムントの即位は否定されなければならない。さあ、みんな立ち上がって、永遠の団結を誓い合おうではないか」
割れんばかりの大歓声が、大学教授を包んだ。
そして、その日のうちに戦時体制が決定された。各市街に4人づつの執政官を任命し、この合議の下に戦争準備を推進することになったのだ。
4月20日、この新しい政体は、ボヘミアとモラビアの各共同体に決戦への参加と団結を呼びかけた。この連帯には、有力なフス派貴族たちも加わってくれた。
チェコのフス派は、今やひとつの巨大な紐帯で結ばれていた。国中が、正義を求める熱狂で溢れかえらんばかりであった。
一方、プラハ大学では、最近頭角を現した才人、ロキツアナのヤン助教授を中心に、いわゆる「プラハ13箇条」の改定作業を行っていた。その内容を整理しすっきりさせ、二重聖餐派として絶対に譲れない線を確立するためである。
5月、プラハ大学は、大貴族たちやプラハ市議会との討議の末、いわゆる「プラハの四か条」をチェコ全土に向けて公表した。
その内容は、次の通り。
第一条・・・神の言葉は、チェコ全土において、自由に妨げられることなく、聖職者によって述べられ、語られるべきである(教会の利害得失に制約されない自由な布教活動)。
第二条・・・尊い聖体である神の肉と血は、パンと葡萄酒の両種によって、あらゆる忠実なキリスト教徒に自由に与えられるべきである(二重聖餐)。
第三条・・・多くの聖職者や修道士は、世俗の法に基づいて多くの財産を所有し、キリストの教えに反し、聖職者としての務めを損ない、また世俗の領主身分を大きく妨害している。これらの不正な財産は、奪われるべきである(腐敗した教会の浄化)。
第四条・・・死に値する罪を犯した人々、そして神の法に背いた人々は、どのような身分であれ、然るべく方法で捕えられ、処罰されるべきである。俗人に関しては、淫行、暴食、盗み、殺人、偽誓、不正利得。聖職者に関しては、聖職売買、秘蹟や教会職務に対する謝礼の要求、贖罪状販売などがこれに当たる(神の教えの厳格な実践)。
この中で議論が紛糾したのは、第一条の内容である。ジェリフスキーを中心とする新市街の急進派は、「聖職者に限らず、誰でも自由に説教を行える」旨を主張したのだが、旧市街の大学教授らは、そこまでの大胆な改革には乗り気でなかったのである。
それでも、この「プラハ四か条」は、いわゆるフス派の統一綱領となった。
四か条の内容は、我々現代人の目から見ると、それほど非常識とは思えない。むしろ、当然の主張のように見える。しかし、当時の中世世界では、この考え方は「異端」以外の何者でもなかった。特に、既得権益を保持する教会勢力にとっては、決して認めることの出来ない反逆であった。
チェコ人たちは、近世の母胎とも言えるこの四か条を守るため、全ヨーロッパの保守勢力との闘争に乗り出そうとしていたのである。