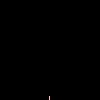
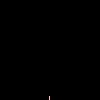 |
別章【新日和見主義事件解析】 |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.10.5日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「新日和見事件考」は、完結見解として世に出し得た論文としては、れんだいこの処女作である。れんだいこはこの事件の渦中にいたこともあって、この事件に対する思い入れが深い。そこで長年の宿題を解くかのようにして考察を試みた。ほぼ解明できたと思っている。云えることは、この事件を通してだけでも現下宮顕ー不破党中央の変態性を見て取ることができるということである。ところが、「一事万事」で、この事件も含めせっかくの教材に「恵まれ」ていながら、何もかもが流されている。そういう訳で、千年一日の如くな饒舌をはびこらせている。歴然として変態な現下宮顕ー不破党中央を一貫して支持し続ける連中が相変わらず一見マジメそうな政治談議を遣り取りしている。 しかしなぁ、政治の要諦は理論と実践と検証に対する責任性こそが本当のマジメであり、それを欠いているお前たちは最も恥ずべきウソマジメでしかない。そういうお前たちの懲りない説教なぞ聞きとうない、そんなことではどうもならんではないか、そう思っている。しかし、これが現実だ。貧困というか寒すぎる。 2006.9.27日再編集 れんだいこ拝 |
| (れんだいこのショートメッセージ) | ||||
|
この章の理論的貢献は、日本の戦後学生運動が、「現下日本共産党中央の胡散臭い素性」を的確に認識しえず、「左翼内右派系の民族路線型統制運動」とみなしつつも、あくまで指導党的な範疇で捉え、「一定の評価と敬意で遇して来たことの間違い」を指摘しているところにある。 |
||||
|
| 関連サイト | 【戦前日本共産党史考】 | 【戦後政治史検証】 | 【戦後学生運動論】 |
| 【宮本顕治論】 | 【不破哲三論】 | 【原水禁運動考】 | |
| 【マルクス主義再考】 | 【政党運動の在り方考】 | 【党派運動の再生の為に】 |
| 目次 | |
| 以下の読み取りの前に「戦後学生運動の考察」に目を通していただければ、なお的確な認識に至ると思います。長文ですので太字のところだけを読み進めても概要が分かるようにしています。留意点強調部分は赤字にしました。 | |
| 第1部 | 序文 |
| 第2部1 | 「新日和見主義事件」概観、「新日和見主義者の解析私論」 |
| 第2部2 | 補足「党の強権論理の根拠理論」 |
| 第2部3 | 補足「1969年愛知県党内騒動事件」 |
| 第3部1 | 事件の発端と「年齢引き下げ問題」 |
| 第3部2 | 「査問」の様子、被査問者の査問実感 |
| 第3部3 | 「党中央の新日和見主義者批判キャンペーン」考 |
| 第4部1 | 「処分とその後」、「事件のその後」 |
| 第4部2 | 「事件余話」 |
| 第4部3 | 補足「加藤教授の『査問の背景』」他 |
| 第5部1 | 民青同の右派的本質の追跡 |
| 第5部2 | 査問考 |
| 第5部3 | 「我々は、この事件を評して何を総括すべきか」 |
| 第6部1 | 川上−油井論争発生考 |
| 第6部2 | 平田勝「未完の時代――1960年代の記録」証言考 |
| 参考文献 | |
| インターネットサイト | |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)