|
新日和見主義事件は運動としては「双葉の芽」のうちにつぶされたので、 党史から見ればさほど重要な位置を占めない。つまり、たいした事件とはならなかったということである。が、この事件も間違いなく宮顕の号令一下で始められた査問事件であったことを踏まえる必要がある。宮地氏は次のように解析している。
| 概要「この事件の共同正犯は3人である。クーデターの主犯宮本顕治、査問統括検事役下司順吉、思想検事役上田耕一郎である」。 |
もう一つ。新日和見主義事件は、党指導下の青年学生組織に対して取られた党による極反動的な統制政策であり、これ以来30年間近くにわたって今日にまで至る党指導下の青年学生運動の低迷を作り出した直接の原因である。このことに思いを馳せれば、新日和見主義事件はこの両面において象徴的な反動的政治的事件であったという重要性を帯びており、かなり底流的に重みがあると思われる。
一体、宮顕を調べていけば行くほど、こうした「統制好きな面」と「査問好きな面」が浮かび上がってくる。氏の行動が左翼運動の前進的発展に寄与した面について私は少しも知れない。度々お願いしているが、どなたか、いや実はこういう貢献があるというものがあったら本当に教えて欲しい。なぜこんな人物が「無謬」だとか「獄中12年」の神話化人物になるのだろう。不思議というか考えられないことなのだけど、そのからく りについても教えていただけたらありがたい。これはマジで言ってます。私には、インテリジェンスのあるいい大人が何でいとも易々そういう論理を受け入れているのか理解不能なのです。ましてや今日の党路線に批判的な者でさえ、こと宮顕の評価となると絶対的基準で氏を擁護する姿勢が見られるようである。誰かこの現象を整合的に説明してくれないだろうか。
もとへ。70年安保闘争以降、戦後の社会運動に一定の影響力を持ち続けた青年学生運動のうち、急進主義を担った勢力はより先鋭的方向に引きずられていく ことによっていよいよ大衆から分離し、この間いかなる経過にも惑わされずひたすら愚頓直に党の指導に従ってきていた民青同のその中に僅かに残されていた戦闘的良質部分がこの新日和見主義事件による鉄槌の結果最終的に瓦解させられ、以降この両面からの打撃で今日にまで続く青年運動の低迷を招くに至っているということを考え合わせると、新日和見主義事件は歴史的な政治的重要性を残しているように思われる。
これを系統的に証明するとなるとかなり大がかりな難事となる。が、突き動かすものがある故に取り組まざるをえない。この作業の結果、今日低迷する青年運動の核心に触れるものが見いだされる筈であり、宮顕式路線の反動的本質がレリーフされる筈である。そういう歴史的な教訓を汲み出すために拙かろうともいざ出航する。
もっとも事件のこうした受け止め方は個別私のそれであり、同時代のあの仲間達の認識として共有されていたとはとても思えない。それが証拠に、当時の多くの活動家は何が何だか分からないうちに党の一片の公式見解に唯々諾々してしまい、事件はアッという間にうやむやな歴史の彼方に放擲されてしまった。つつがなく今日まで経過させてしまっていることによっても一般的な受け止め方ではないことが裏付けられる。当時の赤旗紙面が手元にないが、私が受けた印象は、既述したこともあると思われるが、批判しやすいように改竄された新日和見主義者なる者が得手勝手に措定され、読む者をして、そんな馬鹿げたことを連中は言っているのかと容易に受け取らせしめる詐術でもって文章構成されたものだったと記憶している。
翌日のキャンパスで、対立セクトの連中から、「何だぁ、てめえらの思想は。もう少しましかと思っていたが云々」と揶揄されたことを不思議と今日まで覚えている。私の場合、個人的事情も重なって丁度この頃運動から離れていった経過があるが、この時「こんな党をいつまでも相手してられないわ」という思いが忽然と湧いていたように思う。私の場合、55年時の「六全協」後の革共同ないしはブント系運動創出活動家達ほどの能力も情熱もなく、以来左翼運動そのものから遠ざかることとなった。たまたまパソコンを手にした喜びでかっての関心を呼び起こし、たまたまこの「さざ波通信」と出会うまで個人的な生活費闘争に明け暮れつつ今日まで至っている。もっともお陰様でというべきか少しは世間を広く知ったような気もしている。
そのことはともかく、結果は語る。新日和見主義事件は、その後の民青同の急速な低迷を招き、青年運動に負の遺産をしっかりと刻み込んだ。このことにつき現執行部党中央は、苦衷を感じているように思われない。むしろ、60年安保闘争・70年安保闘争の経過で見せた青年運動の盛り上がりが勃発することを二度と期待していないようにさえ思われる。青年運動の低迷と新日和見主義事件の関係を関連づけて捉えようとする動きは掣肘されれたまま今日に至っているように思える。
付言すれば、新日和見主義事件を当時の世相一般に解消したり、ないしは右傾運動化の流れの中で止むを得なかった的に受け止める論調が散見されなくもない。こうした論は、新日和見主義事件の本質をぼかす論調であり、到底納得できない。この事件は、明確に宮顕・不破一派によって引き起こされた作為事件であり、「70年代の遅くない時期での民主連合政府樹立運動」に対する党中央側からの破壊工作であった(なぜ、左様なことを作為するのかの考察はまた別の時に考察したい)という面を見ない限り、真実像は見えてこないと断言したい。
この新日和見主義事件が脚光を浴びたのは、おおよそ25年後に事件の被主役であった川上徹氏(民青系の再建全学連の初代委員長であり、この当時民青同中執のリーダー格として影響力を持っていた)が、著作「査問」によって事件の真相を自ら世に知らしめたことによってである。ただし、「査問」を読む限り、失礼ながら当人である川上氏にとってさえいまだに事件の深層が理解されていない風がある。私から見ればそう見える。川上氏が明らかにしたことは、「党の正式な査問として、云われるほどの咎もないのにかようなことがされた」という内部告発であって、多くの者もその範囲で理解しようとしているように見える。つまり、問題にされているのは「査問の真相」であって、「事件の深層にあったもの」についてではないように思われる。
最近新たに油井喜夫氏の「汚名」が出版されたようである。まだ手にしていないが「さざ波通信」によって一部了解している。本来読了してから言うべきことかと思うが、貴重な証言がなされているようである。つまり、新日和見主義事件の査問者側の複数員が何と!公安のスパイであったということがより詳しく明かされている。こんなことは果たして偶然であろうか。さもありなんではないのか。私の推論はほぼ知られていると思うので繰り返さないが、この根本の所から疑惑し直さないと党の再生はありえない、ということが言いたいわけだ。
今私は戦後の学生運動を通史として読み直している。気づくことは、党の指導からいち早く離れて新党を結成していった数多くの諸セクトも、党を追われた者も自ら出ていった者もこの点では皆な読み誤っているように思われる。ここに私の考究の意味がある。私は、この一連の投稿によって、査問の背景にあったと思われる「事件の深層」について迫ってみようと思う。低迷する今日的左翼の現状打破につながるキーがここに隠されているように思うから。この「深層」を切開することはかなり難しいが、新旧左翼の垣根を越えて評価に耐えうる投稿文を書き上げたいと思う。エラそうに言えるほどのものは何も持ち合わせていないが、場面によってはそういう提言をなさねばならない箇所に出会うことになる予感がしている。そう言うときには割り引いてご理解願いたい。
まず、戦後の学生運動の概括をしておくことにする。この流れを掴まないと新日和見主義事件の本質が見えてこないと思われるからである。全体をまとめることはできないので、その時々の全学連運動の特質と指導部の党派性に注意を払いながら見ていくことにする。今日の如く雲散霧消させられた学生運動の現況と現代若者のインテリジェンス水準から見えてくることは、当時の学生がいかに天下国家を熱く論じていたのかという良質性である。
私が思うに、あの当時の活動家が夢見ていたような革命が起ころうが起こるまいが、二十歳前後の頃からの一定時期に自身と社会との関係についてあるいはまた国家とか世界との関連の中で、自身の一個としての存在の社会的関わりを徹底的に見つめておくことは、人間としての弁証法的成長の過程に必要なことなのではなかろうか、ということである。今社会全体にこうした議論が少なくなってきており、こうした風潮にあきたらない思いの者が没政治主義的にオウム真理教やライフ・スペース等の宗教的活動や最近隆盛しつつあるネットワーク商法やその他諸々のコミュニケーション活動に向かっているのではなかろうか、とさえ思われる。
人間の存在的根源にコミュニケーション活動があり、こうした活動は何時の時代でも何らかの形で立ち現われるものであり、むしろ人の成長過程としての健全性を証左しているものであり、学生運動もまたその一つの表現だったのではなかろうか。一世風靡した学生運動は当時の社会が許容していた「明日の国造りに有益な社会的投資」活動の一環として位置づけられる国益上有益にして民族の活力の源泉のようなものではなかったか、とさえ思われる。私は、今に継続されている韓国・中国等の青年のエネルギッシュな行動に明日のかの国の発展が見えてきそうだという感慨を抱いている。
ところで、大きく見てそのように意義づけられる学生運動に携わった者も、学生運動に立ち現れた分裂状況に制約されて、自身が属した党派の側からの一方的な視点の了解の仕方でしか学生運動を把握しえていないのではなかろうか。私がそうだからそうであろうということに一般性があるのかどうか分からないが、私はそのように了解している。この辺りをできるだけ多面的にウォッチしてみようと思う。
|
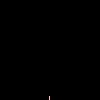
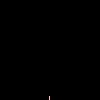

![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)