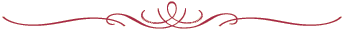
| 別章【囲碁落語】 |
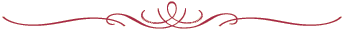
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).8.29日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで、囲碁落語を確認しておく。 2005.6.4日 2013.6.04日再編集 囲碁吉拝 |
| 目次 | |
| № | 項目 |
| 囲碁逸話その1 | |
| 囲碁逸話その2 | |
| 碁打ちの上の空 | |
| 囲碁吉定番/碁泥(ごどろ) | |
| その他/碁泥(ごどろ) | |
| 囲碁吉定番/笠碁 | |
| その他/笠碁 | |
| 囲碁吉定番/柳田格之進 | |
| その他/柳田格之進 | |
| 囲碁吉定番/文七元結 | |
| 谷風の人情相撲(佐野山) | |
| 寛蓮の弥勒寺建立物語 | |
| 史上の囲碁口入れ騒動譚 | |
| 本能寺の変の予兆としての三コウ事変 | |
| からみの鬼吉 | |
| 夫婦(めおと)碁 | |
| 中山典之「実録囲碁講談」の「第三話 落碁 ある稽古先の話」 | |
| 「久米幸太郎の仇討ち (石巻市祝田) 」 | |
| 囲碁書籍史 | |
| 囲碁ソフト | |
| インターネットサイト | |
| 関連著作 | |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
囲碁の格言とか囲碁に由来する慣用表現がいろいろありますねえ。確認しておきませう。
| 布石 (ふせき) |
序盤、戦いが起こるまでの石の配置。転じて、将来のためにあらかじめ用意しておくこと。また、その用意。 |
| 定石 (じょうせき) |
布石の段階で双方が互角の手を打つことでできる石の配置。転じて、物事に対するお決まりのやり方。 |
| 捨石 (すていし) |
対局の中で、不要になった石や助けることの難しい石をあえて相手に取らせること。転じて、一部分をあえて犠牲にすることで全体としての利益を得ること。 |
| 死活 (しかつ) |
石の生き死にのこと。転じて、商売などで、生きるか死ぬかという問題ごとにも用いられる。 |
| 目算 (もくさん) |
自分と相手の地を数えて形勢判断すること。転じて、目論見や見込み、計画(を立てること)を指す。 |
| 駄目 (だめ) |
自分の地にも相手の地にもならない目の意から、転じて、役に立たないこと、また、そのさま。 |
| 駄目押し (だめおし) |
既に勝利を得るだけの優勢にあり、相手の戦闘意思をなくすような手を打つこと。 |
| 駄目詰め (だめツメ) |
終局後、計算しやすいように駄目に石を置いてふさぐこと。転じて、念を入れて確かめること。 |
| 八百長 (やおちょう) |
江戸時代末期、八百屋の長兵衛、通称八百長なる人物が、相撲の親方と碁を打ち、相手に勝てる腕前がありながら、手加減してご機嫌を取ったところから、相撲その他の競技において、あらかじめ対戦者と示し合わせて、表面上真剣に勝負しているかのように見せかけることをいう。 |
| 大局観 (たいきょくかん) |
的確な形勢判断を行う能力・感覚のこと。転じて、物事の全体像(俯瞰像)をつかむ能力のこと。 |
| 三手の読み | 着手決定し打つ前に必ず相手の受け手に対する次の手を考えることう云います。 |
| 岡目八目 (おかめはちもく) |
対局者としてではなくそばで見ていると、冷静だから対局者の見落としている手も見え、八目ぐらい強く見える意から、当事者よりも第三者の方がかえって物事の真実や得失がよく分かる。当事者は全体が見えなく、観戦者は全体が見える例え。 |
| 大場より急場 | お互いの生死に関わる地点は最優先に打つべき。 |
| 一目置く (いちもく おく) |
棋力に差のある者が対局する場合、弱い方が先に手合相当のハンデ石を置いてから始めることから、相手を自分より優れていると見なして敬意を表すること。その強調形の『一目も二目も置く』が使われることもある。 |
| 下手を打つ (へたをうつ) |
拙い手を打ち失敗すること。 |
| 先手を打つ (せんてをうつ) |
手番が先になるよう手段を講じて打つこと。 |
これらはいずれも碁から生まれ、一般にも広く使われています。囲碁には、人生に例えると役に立つ格言、ことわざの類が際だって多いです。