| �P�Q�� |
���w���^���U�����̂R |
�P�X�U�Q�i���a�R�V�j�|�P�X�U�R�i���a�R�W�j�N |
| �@�S�w�A�̎O��������Œ艻 |

�@�i�ŐV�������Q�O�O�W�D�X�D�P�P���j
�@������O�́A�u�U�����̂Q�A�}���w���S�w�A�̊m���v�ɋL���B
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
| �@�����ŁA�P�X�U�Q�i���a�R�V�j�N����P�X�U�R�i���a�R�W�j�N�܂ł̊w���^���j���T������B��������Ɂu���w���^���U�����̂R�A�S�w�A�̎O�������T���v�Ɩ�������B�ژ_�́u�S�w�A�̎O�������Ɩ��n�S�w�A�́u�Č��v�v�A�T�_�́u�S�w�A�̎O��������Œ艻�v�ɋL���A���̎����̐��v�������̂�グ��͂���B�S�̗̂���́A�u��㐭���j�����v�̊Y���N���ɋL���B�@ �@ |
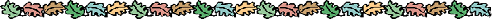
| �y���̎����̑S�̂Ƃ��Ă̐����^���z |
| �@���̎���̐��������̐��v���]���Ă����B�w���^���j�̗\���m���Ƃ��Ēm���Ă����K�v������ǖʂ𒊏o����B |
�@�P�X�U�Q�i���a�R�V�j�D�V�D�P���A��U��Q�c�@�I���B���̎��A�v�����S���ς���v���I�c���`�������ɁA���c���ꎁ��S���悩��o�n�����Ă����B�A���A���[���͂Q���R�Q�U�T�[�ŗ��I�B����{�����}���ق̐Ԕ��q�͂P�Q���Q�T�R�Q�[�B
�@�V�D�P�R���A�����͑�R�����ŁA���{���Y�}�n���S�O���N�ɂ������Ă��̑������B�u�S�̊��v���߁A�j�̘H���̕��y�ƓO�ꉻ���͂���B�u�S�̊��v�Ƃ́A
�P�D���锽�Ɛ�̐l���̖����`�v���̊��A�Q�D�c���̐^�̓Ɨ��Ɛl���̏����̕ۏ�ł��閯�����哝�����̊��A �R�D�����I�v�z�I�g�D�I�ɋ��łȋ���ȓ��{���Y�}�̌��݂̊��A
�S�D�A�����J��擪�Ƃ���鍑��`�ɔ����閯������ƕ��a�̍��ۓ������̊� �Ƃ��Ē莮�����ꂽ�B
| �y��W�����֎~���E���ŁA�\�A�̊j���������Ћ����Η��z |
|
�@�W�D�P�|�U���A��W�����֎~���E���ŁA�����́A�\�A�j�����ւ̍R�c�ɔ����ĎЉ�}�D���]�n�ƑΗ�����B�Љ�}�D���]�n��������鍑�̊j�����ɔ��Σ���咣���A�\�A��\����������㉟�����Ă����B�����}�����ƌ������͢�\�A�͕Ē�ƌ����A�����̑��낤�Ƃ��Ă��飂Ƃ��钆����\�̌����ɓ������Ĕ������B���\�Η������E���\�Η��ւƔ��W�������ƂɂȂ����B
�@�\�A�̊j�����ĊJ�ɑ��āA��c�k��Y�������̎��̓}�̗�����ق��Ģ�\�����j������f�Ŏx������ ��_���\���Ă���i�匎���X�u�}���N�X��`�ƕ��a�^���v�o�D�P�Q�P�`�P�Q�U�A�u�O�q�v�P�X�U�Q�D�P�O���������u�Q�̕��a���ƏC����`���_�v�̂R��\�A�j�����ƎЉ��`�̌R���͂̕]����̍��j�B��c�͂��̌㍡���܂Ő����ƌ�����ς��Ă��邪�A���̘_���Ƃ̗��݂ł̎��Ȕᔻ�͈���Ă��Ȃ��B
|
�@�W���A���\�_�������B
| �y�L���[�o��@�z |
|
�@�P�O���A�L���[�o��@�����������B�P�X�T�X�N�ɃJ�X�g���ɂ��v�����������Ĉȗ��A�L���[�o�͔��āE�Љ��`������̂�\�A�E�����ɐڋ߂��Ă����B�A�����J�ƃL���[�o�̍����͒f�₵�Ă������A�P�O�D�Q�Q���A�P�l�f�B�[�哝�̂́A�\�A���~�T�C����n�����݁A����Ƀ\�A�D���L���[�o�ނ��~�T�C�����^��ł���̂����A�����j�~���邽�߂ɂP�O�D�Q�Q���u�L���[�o�C�㕕���v��錾���A�P�O�D�Q�S���A�L���[�o�̊C�㕕���ɓ��ݐ����B�������ăL���[�o��@�����������B
�@�đ哝�̃P�l�f�B�[�ƃ\�A�t���V�`���t�̐��x�ɘj�鋦�c�̌��ʁA�P�O�D�Q�W���A�t���V�`���t����A�����J�̃L���[�o�s�N��M�����āA�U���p�����P�����飂ƌ����A�u�A�����J���L���[�o�N�����s�Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ������ɂ��ăL���[�o�̃~�T�C����P�����邱�ƂɂȂ����B����ɂ�蕕�����������@���������邱�ƂɂȂ����B���ǁA�t���`�V���t�̑Ë��ɂ���Ċ�@�͂��炭��������ꂽ�B�l�ނ͎��̕��ɗ����邱�Ƃꂽ�B
|
| �y�������\�����v�_�ᔻ�z |
|
�@�P�Q�D�R�P���A�����l������А��u�g���A�b�`���u�Ƃ����̈Ⴂ�ɂ��āv�\���A�C�^���A���Y�}�̍\�����v�_�����̂悤�ɘ_����B
| �@�T�v��ނ�́A�}���N�X�D���[�j����`�̊�{�����͊��Ɂw����x��x���ƍl���A�}���N�X�D���[�j����`�̒鍑��`�Ɋւ���w���A�푈�ƕ��a�Ɋւ���w���A���ƂƊv���Ɋւ���w���A�v�����^���A�[�g�ƍقɊւ���w������₂��Ă��܂����B�����̃C�^���A�ł̓v�����^���A�v����ʉ߂����邱�ƂȂ��A�u���W���A�W�[�̍��Ƌ@�\�ӂ��鎖�Ȃ��A�v�����^���A�[�g�ƍق�ł����Ă鎖���Ȃ��ɁA�C�^���A���@�͈͓̔��Łw��A�̉��v�x���s���A���ƕ���̍��L�������s���A�o�ς̌v�扻�Ɩ����`�̊g����o�߂���������A�w�Q�i�I�Ɂx�A�w���a�I�Ɂx�Љ��`���������Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B���������l���́A���ۂɂ́A�܂������鍑��`�҂Ɣ����h�̗v���ɉ�������̂ł���B�Ⴆ�C�^���A���@�̒��ɂ������̔���������˂�������Ƃ��Ă��A�Ɛ�u���W���A�W�[�����Ƌ@�\������A�Ɛ�u���W���A�W�[�����S�ɕ������Ă��邱�̂悤�ȏ����̂��Ƃł́A�ނ�͎��Ȃ̕K�v�ɉ����āA�@�������A���@�̓��R�Ɛ錾���邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��A�g���A�b�e�B���u��͂��̂��Ƃ���������Y��Ă��܂��Ă��飁B |
|
�@�P�X�U�R�i���a�R�W�j�D�P�D�Q�T���A�r�c�͑�ǖ@��o�̌���������肵���B
�@�Q�D�P�R�|�P�T���A��������T�����J�ÁB�ѓc���璆�\�_���̌o�ߕ��ׂ��ꂽ�B�����ɒ����Ƃ��Ă͂��߂Ē��\�_���̖���F�߁A����c���邱�ƂɂȂ����B�\�A�h�ƒ����h���Փ˂����B
| �y���{���������ŎЋ����Η��z |
�@�Q�D�Q�P���A���{����������C�ψ�����J���A�Љ�}�n�Ƌ��Y�}�n�̊Ԃʼn^����������Ë��������B�����v�ŁA�P�E�����Ȃ鍑�̌������ɂ������A�������̊��S�֎~���͂���B�Q�E�Љ�̐��̈قȂ鍑�ƊԂ̕��a�����̂��ƂŒB���ł��闧��ɂ��B�R�E���N�̓w�͂̐��ʂ��ӂ܂��A������O�ƂƂ��ɐ^��������߂�B���Ƃ����q�Ƃ����u�Q�D�Q�P�����v������A���䗝���������������B����Ɠ����Ɏ����I�u���莖���v���m�F�����B�@
�@�Q�D�Q�W���A���{���������É��s�őS����C��������J���A�u���ׂĂ̍��̊j�����ɔ��v���R�D�P���̃r�L�j�E�f�[�錾�ɓ���邩�ǂ������c�������A�Љ�}�Ƌ��Y�}���ĂёΗ������B���Y�}�n��C�������u�Q�D�Q�P�����v�̂Ȃ��́u�����鍑�̊j�����ɔ�����v�����ɔ����Ă䂸�炸�A�u���莖���v�ɂ��Ă��ًc�����������߉�c���܂Ƃ܂炸�A���Ɉ���藝���������ӂ�\�����A�S����C�������S�����C����ɂ�����A���{�������Ƃ��ẮA���ꂵ���r�L�j�W����J�Âł��Ȃ��Ȃ����B�R�D�P���A�r�L�j�W����{�������Ƃ��ĊJ�Âł����A��ɕ�����ĊJ���ꂽ�B |
| �y�g���R�h�����}�z |
�@�R�D�W���A���ꌧ�̑O�����ψ��g���R�Ƃ��̃O���[�v���E�}�����\�����B�����́A�}�w�����͍����H���ł̕��a�^���D�J���^���̎w���Ԃ̌��ɂ���āA�����ې���ł̃��X�N�������ւ̔w���ƃ\�A�H���ւ̈�w�ɂ���āA�u���͂�}���N�X�D���[�j����`�Ɩ����̂��̂ɓ]�����Ă���v�ƒf�����B�����āA�{�����}�^�c�����̂悤�ɔᔻ�����B
| �@�T�v����݂̓}�����́A�S���}���g��^���ɏW������A�}���D�����͂��D�ǂ����j�ł̊g�劄�蓖�Đ����̏����������S�ĂƂȂ��Ă���B����Γ}���͓ƑP��`�Ɗ�����`�̓}�����̓���Ɖ����Ă���B�}�������`�͔j��A�K��ɕۏ��ꂽ���_�̎��R�͑S���Ȃ��B����ȏ�}�ɂƂǂ܂��ē}�����P��������͌��������Ȃ���ƁA���̗��}�̗��R�𖾂炩�ɂ����i�u�^�̑O�q�����݂̂��߂Ɂ|���{���Y�}�𗣂��ɍۂ��Đ�������v�j�B |
|
�@�S���A�\�A���Y�}�̒������Y�}�����Ȃ̌��\�[�Ƃ��āA���\���}�̌��J�_�����W�J���ꂽ�B
�@�T���A���R���������B��ʌ�����s�ŏ��q���Z�����c�P�}����̎��̂��_���Ŕ�������A���̔Ɛl�Ƃ��Ĕ퍷�ʕ����̐ΐ��Y�N���ߕ߂��ꂽ�B��ɁA���R�����ւƔ��W����B�@
| �y�āD�\�D�p�������I�j������~���z |
�@�V�D�P�T���A�āD�\�D�p�ŕ����I�j������~���B���̏��̈Ӌ`�́A����܂ł̑�C���ł̊j�������u�l�ނɈ��e��������ڂ�����Ƃɗ��ӂ��č����C���ł̎������֎~����Ƃ����Ƃ���ɂ������B�ĉp�\�R��������������A�x��Ċj�����Ƃ��Ƃ��Ă��������́u���卑�̊j�Ɛ肾�v�Ɣ������Ă������ƂɂȂ�B
�@�\�A�̂��̏������̕]��������ă\�A���Y�}�Ɠ��{���Y�}���Η����Ă������ƂɂȂ�B�\�A���Y�}�����^�����e�����Y�}�ɗv�����ĉ��A�}�����͂���ɓ��ӂ��Ȃ��������������B���̂��Ƃ���o���̌��������̉��V���W�J����Ă������ƂɂȂ����B�������֎~�^��������ŕ������Ă������ƂɂȂ�B�@�V�D�Q�X���A�A�J�n�^�咣�A�u�����I�j���������~���ɂ��āv�\�B |
| �y��X�����֎~���E���ŎЋ��Η�������I�ɂȂ�z |
�@�W�D�Q�|�V���A��X�����֎~���E���J�Â��ꂽ�B�u�����Ȃ鍑�̊j�����ɂ����v���ǂ���������ĕ��������B�����́A��������������d�����n�L���ɑ��荞��ŁA�����x���̗��ꂩ��w�����J�n�����B���̎��A�����́A�u�A�����J�̊j�͋����̕��킾���A�Љ��`���̊j�͂��̖h�q�̕��킾�v�Ƃ̊ϓ_���碂����Ȃ鍑�̊j�����ɂ����ɔ��Σ���Ă���B
�@���ۉ�c�Łu���j�v���߂��蒆�\���_�ƂȂ����B�}������������\�c���x�����A�Љ�}�D���]�n�͂����F�߂��A�r���őޏꂵ�E�ނƂȂ����B�����Č����։^���͕��邱�ƂɂȂ����B���̌��ʁA���̌����։^���̕���́A�}�����̂��̌�̒����H���̋����ƍ��킹�āA���{��e������ۋ�����c�ɂ��d��ȉe����^���Ă������ƂɂȂ����B���̕���̐ӔC������āA�{���|�s�j�n�͍����Ȃ��k�ق�M���ċ����葱���Ă���B
�@
�@�W�D�R���A�����́A��������ŕ����j����s�x����\������B�u�j����S�ʋ֎~�̊����f����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�\�B�}�Ƃ��ď��߂Ē��\�_���ɑ��颒�����裂̌�����\�������B���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�T�v������I�j����̐����a�ւ̑O�i�Ƃ݂Ȃ��ӌ��́A���E�Ɠ��{�̐l���̔F����傫����点����̂ł���B�䂪���ɂ����ẮA�w�����Ȃ鍑�̊j�����ɂ�������x�Ƃ�������ƁA�����I�j������x������Ƃ�������Ƃ́A�����v�z�Ɠ��������I����ɍ������Ă���B��X�͂��̂悤�Ȍ����ɒf�Ŕ����飁B |
|
�@�W�D�T���A�ĉp�\�O���A���X�N���ŕ����I�j������~���B
�@�X�D�Q�R���A�{�����{�m�g�j����e���r�ŏ��߂Ģ����Ɨ���̗���̌��t���g���B�����{���̐挩�����؍�����p��Ƃ��ĕ]������Ă��邪�A���j�I�������猩��A����͖ё�����͍X������]���A�C���h�l�V�A���Y�}�̃A�C�W�b�g����Ɨ����壂Ɖ]���Ă����̂�����������������B
| �y�������u�\�A�ᔻ�D�e�����H���_���v���\�z |
�@�P�P�D�P�O���A�A�J�n�^�咣�A�V�����Ɋ�Â��āA�u���ۋ��Y��`�^���̐^�̒c���ƑO�i�̂��߂Ɂv�\�B�����j�łɂ�����Ɨ��̖��̉��Ƀ\�A�ᔻ�D�����H�������̘_�����ڂ���B���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�T�v����ۋ��Y��`�^���̒��ɂ́A�S�Ă̌Z��}���F�߂Ă���悤�Ɏw������}���w�������}���Ȃ��B�Z��}�̊W�ɂ��āA�ǂ̂悤�ȓ}���A����𑼂̑S�Ă̌Z��}�̏�ɒu�����Ƃ͏o���Ȃ��B�܂�����}����ʂ̒n�ʂɂ܂肠���邱�Ƃɂ���āA���̓}������ɏ]�킹�邱�Ƃ��o���Ȃ���B |
| �@�T�v��`�g�[��h�́A���X�N���錾�ɑΏ����Ă���ꂽ���̏C����`�I�j�̗̂�����ˑR�Ƃ��ČŎ����Ă���A���X�N���錾�ƃ��X�N�������̊v���I�����ɔ�����ԓx�������ĕς��Ă��Ȃ��B����玩�g���A�����̊�{�I�Ȑ����I�v�z�I���ꂪ�킩���Ă��Ȃ����Ƃ��J��Ԃ��������Ă���B���X�N���錾�́A�u���W���A�W�[�̉e�������邱�Ƃ��C����`�̍����I�����ł���A�鍑��`�̈��͂ɍ~�����邱�Ƃ��A���̑ΊO�I�ȍ����ł���Əq�ׂĂ���B���[�S�X���r�A�C����`�҂ɋb��ʂ���ȂǁA�C����`�̍��ۓI�����ƌ��т����ƂŁA�����́A���ۋ��Y��`�^��������I�ɕ��邱�ƂɗB��̊�]�������āA�䂪�}�̔j����Ă��飁B
|
|
| �y�P�l�f�B�[�哝�̈ÎE�����z |
| �@�P�P�D�Q�Q���A�P�l�f�B�[�č��哝�̈ÎE�����B�e�L�T�X�B�_���X�ŗV�����_�����ꂽ�B��P���Ԕ���A�_�O���X�s�x�́A���[�E�g�E�I�Y�����h��Ɛl�Ƃ��čS���������A�����Ɉڑ����A�W���b�N�E���r�[�ɂ��ˎE���ꂽ�B�W�����\�����哝�̂����i���A����������u�E�H�[�����ψ���v��ݒu���A���N�X�D�Q�U���A�������I�Y�����h�̒P�Ɣƍs�Ƃ��钲�����ʂ�����B�������A�^�f�������M�ߐ����^���Ă���B�A�����J�͂��̌�A�x�g�i���푈�g��Ɍ��������ƂɂȂ�B��C�Ƀ����h�D�W�����\������R�U��哝�̂ɏA�C�B�P�P�D�Q�T���A���V���g���Œr�c�D�W�����\����k�B |
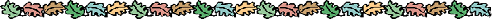
| �y���̎����̊w���^���̓����z |
�@���̎���̊w���^���̐��v���]���Ă����B
�@�P�X�U�Q�N���_���S�w�A�̍ē���̓���������A���ꂼ��̓}�h�������I�Ɏ��͔��W���Ă������ƂɂȂ�B���̊��̓����́A�����S�w�A���s�����}���w������߁A�����͕ʓr�ɑS���A�������w�A�o�R�őS�w�A���Č�������B����ɑ��āA���}���w���ň�v�����Њw���Č��h�A�А��A�\�����v�h���O�h�A�����S�w�A�̓����͍����Ă������A�}���w���Ƃ̊Ԃɐ܂荇���������t�ɋْ������܂����ƂȂ�B
�@�P�X�U�R�N�A�v�����S���ς����j�h�Ɗv�}���h�ɕ���B���j�h�Ɗv�}���h�̑Η��̔w�i�ɂ͎��̂悤�Ȋϓ_�̑��Ⴊ��݂��Ă����B�u�v�����̒��ɂ����H�h�Ə��ց|�]�_�h�Ƃ̑Η�������A���ꂪ��̒��j�h�Ɗv�}���h�Ƃ̑Η��ɂȂ��Ă������Ƃ̂��Ɓv�i���j�̏،��u���g�D�É�j�ł���B��O�^���̐i�ߕ��ɂ��傫�Ȋϓ_�̑��Ⴊ���݂��Ă����B����ɂ��ẮA�u���j�h�Ɗv�}���h�̑Η��l�v�ɋL���B�@
�@�����Ŋv�}���h�ɂ��Č��y���Ă����B�@�P�X�U�R�D�S�D�P�|�Q���́u�v�����̑�O������v�ɂ��v�}���h���a���������A����ɂ��v�����̎嗬���Q�����������c�Ƃ���}�h�֒H�蒅�����Ƃ��݂Ȃ��悤�B���̌o�܂̐���͂Ƃ������Ƃ��āA�v�}���h�Ƃ͂����������҂��낤���B���{���h�^���̈�h�Ȃ̂��낤���B���{���h�^���o�Ő������|�Ƃ��Ĉ������U�����h�}�h�Ȃ̂��낤���A����ɂ����ʂ��番�͂��Ă���_����m��Ȃ��B����ɂ��ẮA�u�v�}���h�l�v�ɋL���B
�@���j�h���\�����v�h�̑���ɑ�u���g�n�o�h�A�А��h�Ƃ̋�������Ɍ������A�V�O�h�A������������B���̊ԁA�����h�������w�A���o�Ď��O�̑S�w�A���������A�S�w�A�́A�v�}���n�A�����n�A�V�O�h�A���n�̎O�b�ŋ������n�߂�B���̌o�܂�������B |
| �y�����n�������w��������������������z |
�@
> HOME >DATABASE
�u���u���g�v�^�ԌR
�m���u���g�W�n
��ꎟ�u���g�i1958�N10�������j������ۓ�����ɂ����镪����A�u���g���n���ψ��1962�N4���Ɋ����Y��`�ғ����Ƃ��Č��������i���u�Б�w�E�_���Y�c���j�B���u���g�����S�ƂȂ�A1965�N8���ɋ��Y������ψ�����������B�����āA1966�N9���ɂ͑�u���g���Č������B1968�N8���̋��Y���ԌR�h�����ɍۂ��Ă͊��u���g�n�����S�ƂȂ�B
���O�c�T��
19690605
�u���u���g�͑�O�Ƌ��ɂ��낤�Ƃ����v�w�G�����_���48�x���H��
�E��㒆�d�i��㒆���d��ǁj�u���܁Z�N�ɒ��d�ɓ����āA�����̓��b�h�p�[�W�̒���ŋ��Y�}�̍זE����ł��Ă���Ȃ��ŁA�����̒��Ԏl�A�ܐl�Ƌ��͂��čזE���Č����Ă������킯�����ǁA�������ꎟ��㒆�d�J���i�J���^��������j�́A���Ԋw�Z�ɒʂ��Ă���A�������S�������B�v�ip.158�j
�@��53�N�~�`56�N
�E57�N���c�ۓ����A58�N�x�E�@�����A60�N�ݖK�Ĕ��Γ�����ʂ��ċ��Y�}�����ƑΗ�
�@����J���i�\�����v�h�E��l�C���^�[�E�u���g���А��E��l�C���^�[�E�u���g�j
�u����ꂪ�u���g���������̂́A�����̑O�q�}�_�����̂܂܈����p������ŁA���������̐V�����O�q�}���ǂ���邩�Ƃ������Ƃ��������A��J���̉ۑ�́A���̓}����̓I�ȑ�O�^���Ƃ̂���݂łǂ����̂��Ƃ������Ƃ������B�����������Ř_�c�ɂȂ����̂��A����ꂪ���g�D�Ƃ͈�̉��ȂƁB�܂��͈꒩��[�ɂ��Ă͂ł��Ȃ����낤�B���ꂪ��B����Ƒ��͑g�D�������ړI�ɂȂ�ׂ��ł͂Ȃ��A�^���Ƃ̂���݂łǂꂾ���v���ł���^�����Ƃ����̂��o�Ă���B�v�ip.162�j
�E���я��w�f�w�n�сx
�u�������Y�����n���ψ���J�Ε��Ƃ������O������������œƗ����悤�A���n���ψ���̘J�Ε��Ƃ��đS���̘J���ҕ����ƘA�����Ƃ��āA����ꂪ���Y�}���番����Ă�肾������Ƃ́A������̓����łԂ������̂ł͂Ȃ��͂���A�Ƃ������Ƃł����͋��Y��`�ғ����̖��O�͎̂ĂȂ����c���Ƃ������c��Z��N�̎n�߂��炢�ɂ���B����Ɋ��̊w���������āA����Ō��I�g�D�Ƃ��Ċ��J���ҋ���Ƃ����̂�����B�����ǂ��\�������̂��A����Ύ��A�����_��A��c�^�J�V�A����Ǝ��炩�ȁB�v�ip.163�j
�E�w���^���ƘJ������Ƃ̊Ԃ̋T��
�u�J������̏ꍇ�͖�E��S���Ă����邪�u���g�̃����o�[�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���ꂪ��O�Ɏ�����Ȃ������炻�̐����͂͂Ȃ��Ȃ�킯���B�v�ipp.165�|166�j
�������F��
20030331 �w�ԌR�h�n���L�\���c�������40�N�x
�ʗ���
�u�w���u���g�x�͗��_�I�Ȑ��i��́w�v���ʁx�̗���ŁA�w�v���ʁx�������ɐ������������̂��w�����ߒ��_�x�ł��B�g�[�^���Ȕ\�͂������Ă���Ƃ����̂��ȁB�����̐����ƌ������A���ǂ남�ǂ낵���Ƃ�����"�����I"�ȗ��_�����݂����Ȃ��̂���͑��ΓI�ɗ���Ă�������A����ʂł́A�q�ϓI�ɂ��̂��݂����B���肩�����ɂȂ�܂����A�l�̒m���Ă���w�����ߒ��_�x�́A��O�^���͑�ŁA��O��ϊv���Ď�̓I�ɓ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A����������p�������B���������킯�ŁA�}���݂Ƃ��J���^����g�D���A�K���I�ɕϊv����Ƃ��A���̕���������ƕ]������Ƃ������͕s��ɂ���Ă���ʂ�����܂����B�v�ip.30�j
�u�w���u���g�x�́A�l���I�ɂ��Ǝ��̓��������Ă����B��ꎟ�u���g�����A�Њw�������낢�땪�Ă��܂������A��ꎟ�u���g�́w���n���ψ���x�͊ہX�c���Ă���킯�B����A�S�����Ȃ��Ȃ��Ă��w���u���g�x�Ɩ���낤�Ƃ������ƂɂȂ����Ǝv���B62�N�ɂ́w�����Y��`�ғ����x���ł��Ă��܂��B��{�I�ɋ���Ɠ��u�ЂƑ��s�傪���ł����B�J������́A�O�c�T���̑�㒆���d��ǂł��B�v�ipp.30�\31�j
�u��ǖ@������ʂ��āw���u���g�����ɂ���x�Ƃ������ƂɂȂ����B���u���g�̌������Ƃ͓����̘A���݂͂�ȕ����Ƃ����悤�Ȋ����ŁA�l�炪������e�h�̑�\�݂����Ȃ̂���ɗ��Ă��낢��ӌ�����������A�Ƃ����W�ł����B�v�ip.47�j
�u�ꉞ���u���g�́A���̂��ߐl�̂��߂őS�w�A�����A�u���g���ĕ҂���A�����������z����������ł���B�����������z���u���g�̒��Ŗ����Ȃ������炾�߂ɂȂ����B�v�ip.74�j
�������F��
19690605 �u���E�ԌR�����������v�w�G�����_���48�x���H��
���c���F�_���W�������s�ψ���i�y�����F�A�������N�A��c��Y�j�@20051021�@�w���u���g�E�c���F�_���W�u�v�����^���A�ƍقւ̓����T���v�x�@���Ԏ�
�@�ڎ�
�������@��c��Y
�c���F�i�������v�j���N��
���Y��`�ғ����̑����ƍj�̖��i1969�N5��3���j
�v�����^���A�[�g�̐��E�ƍق̂��߂̓����i1969�N10��22���j
�v�����^���A�[�g�ƍقւ̓����V���i1970�N3��15���j
����v���̏����ƎЉ��`�i1970�N3��10���j
�T�C�o�l�e�b�N�X���v�����^���A�[�g�̓ƍق��i1971�N5��6���j
��v�_���A�p���t���b�g�ژ^
���c���F�_���W�������s�ψ���i�y�����F�A�������N�A��c��Y�j�@20061130�@�w���u���g�E�c���F�_���W�u�v�����^���A�ƍقւ̓����U���v�x�@���Ԏ�
�@�ڎ�
�������@��c��Y
�鍑��`�Ǝ��R���E�i1961�N11���j
���㎑�{��`�i���̈�j�i1961�N10���j
���㎑�{��`�i���̓�j�i1962�N3���j
����̒�����\���Y��`�ғ����͉��𖾂炩�ɂ������i1962�N�j
���ۋ��Y��`�^���ƈꍑ�Љ��`�i1963�N�j
���{�́u�Ǘ��ρv�Ɓu���Y�͎v�z�v�i���̈�j�i1965�N12���j
���{�́u�Ǘ��ρv�Ɓu���Y�͎v�z�v�i���̓�j�i1965�N12���j
���㐢�E�̍\���i���̈�j�i1966�N2���j
���㐢�E�̍\���i���̓�j�i1966�N2���j
�v�����^���A�ƍفi1966�N6���j
�v�����^���A�ƍقւ̓����T���u�����v�u���Ƃ����v�i1966�N7���j
�v�����^���A�ƍقւ̓��@����v���̏����i1967�N2���j
�v�����^���A�ƍقւ̓��\�䂪�����ً̋}�̔C���ɂ��āi1967�N6���j
�����K�x�g�i���K�Ď��͑j�~�����ɑ��鋤�Y��`�ғ������n���ψ���̊�{�ԓx�i1967�N11���j
�Љ��`�̓��ʂ���Ŕ��̉ۑ�i1967�N11���j
10�E8�A11�E12�����ƌ��͂̓����Ɖ�X�i1967�N12���j
��㎑�{��`�̌��i�K�i1967�N12���j
���{�J���ҊK���ɑ��鋤�Y��`�ғ����̔C���i1968�N1���j
������7����Ɖ�X�̉ۑ�i1968�N2���j
�Љ��`�Ɖ�X�̑ԓx�i1968�N6���j
��v�_���A�p���t���b�g�ژ^
�m�ԌR�W�n
�����Y��`�ғ����ԌR�h�i�v���푈�ҏW�ψ���j�ҏW�@19731010�@�w�ԌR�\���Y��`�ғ����ԌR�h�������_�@�֎����W�x
�ԌR��1
�@�T�@��X�̗��r���ׂ��n�_
�@�U�@�v�����^���A���E�����{�v���̓��Ɖ�X�ً̋}�ȔC��
�@�V�@����U���^���E�v���Ɖ�X
�@�W�@����v���c�V
�ԌR��2
�@�T�@���h�����̍����I�Ӌ`�Ɛ��E�v���푈
�@�U�@�ԌR�h���u�ւ̎��̎��Ȕᔻ�@��{��
�ԌR��4
�@�j�̊m���̂��߂Ɂi1�j�\�ߓn�����E�ƃv�����^���A�\�}
�@���́@����v���_�ւ̕��@�I���_
�@���́@���E�j�I�K�������̒i�K�Ƃ��Ẳߓn�����E�A���̓�̗��j�I���Ր�
�@��O�́@����鍑��`�\����鍑��`����
�@��l�́@�ߓn�����E�\���̗��j�I�W�J
�ԌR��5
�@�O�i�K�����I�N�\��X�̔s�k�̋��P�\���ۍ����n�\�I�N�̌R���\�n������
�@�T�@�O�i�K�I�N�Ɛ��E�v���푈�\�v���̋��P���T��
�@�U�@�I�N�̏����Ƃ��̊J�n�\�v���̋��P���U��
�ԌR��6
�@������n�߂Ȃ���Ȃ�ʂ��\�O�i�K�I�N�s�k�̋��P�Ɛ��E�}�\���E�ԌR����
�@�u�I�N�̌R���v�͔@���Ɍ��݂���Ă����˂Ȃ�Ȃ����\�����R�͂ǂ̗l�Ɍ��݂���Ă�����
�ԌR��7
�@�T�u���ۍ����n�E�I�N�̌R���A���ےn���g�D�v�̎O�̋��P�̕�����
�@�@�ǒn�I���v�����N���}���푈�E�̐��Ԑ푈�ւ̐��E�K����@���A70�N�O�i�K�����I�N�ŁA���E�v���푈�i�Λ��j��!
�@�U�@����J�E�c�L�[��`���\���B�G�g�^����`�A�����`�҂ӂ��A3���v������i���j�������Ɍ��W��!
�ԌR��8
�@�T�@���Y���A���h�ᔻ�W
�@�U�@��_
�@�@�@�@�����ւ̉�X�̎��Ȕᔻ
�@�@�A�@�X�^�[������`�Ǝl���ϋc��
�ԌR���ʍ��@1970�N6��10��
�@���E�}���݁E���E�ԌR���m�֔��Ă���
�@�@�v���I�㓯�u�̏o���錾
�ԌR8���@1971�N3��5���i���Y��`�ғ����ԌR�h���{�ψ���j
�@���@�v���푈�̊J�n��!
�@���@��E��ܖI�N�푈�A�����������������W��
�@�@�@�v������E���l���ۋ�����������
�@���@�O���˓����A�уA�s�[��
�e�i�n�����j�@1971�N7��15���i���s�E�u�ԌR�v������`���j
�@���{�v���푈�̖{�i�I�J�n�Ɍ�����
�@�v���}���݁\�u�ԌR�v�����A���W�������Ƃ낤!
���p�g���V�A�E�X�^�C���z�t�i1991****�w���{�ԌR�h�\���̎Љ�w�I����x�͏o���[�V�Ё��j20031016�@�w���ւ̃C�f�I���M�[�\���{�ԌR�h�x�i�ؑ��R���q��j�@��g���X
�@�ڎ�
��g���㕶�ɔłւ̂܂�����
�{���ɂ��āi����ᩎi�j
�@�v�����[�O
��ꕔ�@���{���O�\���E�����v���̖�
�@1�@���{���O�ւ̃C���^�����[
�@2�@���{�l�̐ӔC�ӎ�
��@�ԌR�h�\�v���R���m�Ƃ����C���[�W
�@3�@�ԌR�h�����̃C�f�I���M�[
�@4�@�u�R�v�Ƃ��Ă̍s��
�@5�@���
��O���@�A���ԌR�\�l�����߂�������ꂽ�W�c�̍l�@
�@6�@�A���ԌR�Ƃ����g�D
�@7�@���Ɏ��鎩�Ȕᔻ
�@8�@�\�͂Ɨ��_�Â��̑��ݍ�p
�@9�@���r�E�X�̊�
��l���@�r�Ő�\���̃A�C���j�[
�@10
�l���̏I���
�@11 �����R���ď�
�@12
�u�閧�v�̍���
��ܕ��@�ӔC�\�I���̂Ȃ�����Â���
�@13�@�]���Ƃ������
�@14�@�ӔC�̂�����
�@15�@�C�f�I���M�[�̊댯�Ȗ���
�@�G�s���[�O
����\�ߌ��r��
�Q�l����
�������^���@20010131�@�w������ԌR���m�\��{��������x�@�ʗ���
�@�ڎ�
���́@�ԌR�h��
�@�F�a���̕��y�̒���
�@�㋞
�@�u���g�i���Y��`�ғ����j�ɉ���
�@�ԌR�h�̒a��
���́@�x�����攪�E��@�����Ɏ���
�@�s�[�X�ʔ��e�����
�@�V�h�x�@���P��
�@�x�����攪�E��@�����ɂ�
�@���e�𓊝�
��O�́@���F���R���P��
�@���@�苒�v��
�@������Ɍ��W
�@�R���P���ƑS���ߕ�
�@�_���u�V�����̃X�^�C���v
�@�s�s�v���̐퓬�`��
��l�́@�������
�@�ԌR�h�̍Č�
�@������œ��ق��̎d�����n�߂�
�@�{�{��q�Ƃ̏o�
�@�S�`�p���ݎx����������
�@���[�������̊J�X
�@������ԌR
�@�A���ԌR����
�@�Η�ؑg����
�@�������R�c�\��
��́@���E���蒬��Ԕ��j
�@�u�v���푈�v�̍ĊJ
�@���e�̍ޗ��W��
�@�W���[�X�ʔ��e����
�@��ԏP��
�@�n�����s
�@�ߕ�
��Z�́@�A���ԌR�����Ɠ}������
�@�������Z���^�[���j�����ƙl��
�@���h������
�@�A���ԌR�����̑���
�@�����ψ���̌���
�@PLO�^�̓�����
�@������ԌR�h�̉��U
�@�u�v�����^���A�v���h�v�ւ̔ᔻ�掵�́@�����ґg���̌���
�@�h���{�[�g��
�@�����҂̓�����p
�@�g������������!
�@���߂Ă̓���s��
�@�����ґg���Ƌ����i�אl�̉�̑Η�
�攪�́@�s�[�X�ʔ��e�����̐^�Ɛl�،�
�@�y�c�E���ԁE�s�[�X�ʔ��e����
�@���{��
�@�l�߂Ɠ����\���l�̔퍐
�@�������v�E�t���[���A�b�v
�@����
�@�،��ւ̓�
�@�^�Ɛl�Ƃ��Ă̏،�
�@������̖q�c�،�
�@���͂̔ƍ�
�@�S�����߂̔���
���́@�}���A�ւ̎莆
�@���u�E�{�{��q
�@����������
�@�}���A�̕�
�@���R�̒��Ő����邱��
�@�}���A�ւ̈�
�@��������
�@�ʂ�
�@����
��\�́@�A�i�[�L�X�g�錾
�@�Ǘ�
�@�u���{�Љ��`�J���g���������v�����̒��
�@�����҂̂��߂̃^���|�|�}����
�@����
��\��́@�J���ҐH���̍ĊJ
�@�Ăъ������
�@�J���ҐH���E��
�@�}���A�Ƃ̍ĉ�
�@�čՂ�
�@���ݕ}�����i���c��̌Ăт���
�@�g�~����̎�
��\��́@�A���f�X�Ɏ���
�@��������l�̗�����
�@�t�W���������̐���
�@���}�̋���
�@�Z���f���E���~�m�\
�@�����J�C������T�e�B�|��
�@�댯�n��̃A���g�p�E������
�@���̋A��
�@������ł̒Ǔ���
�@��{�����̗��z�Ɠ���
�Q�l����
���Ƃ���
�m�����W�n
���ۓ����̐������_�Ƃ��Ă̑���
���s�{�w�A���s�ψ���
���Z��N��������
���S�w�A�\������ɂău���g���n���ψ���n�����s�{�w�A�̑ΈĂƂ��Ē�o�B
�i���M�͓��u�Б�w�̎R�{����j
�@���ۓ������u�\�z�O�̍��g�v�������Ƃ������̌��t�́A���ۓ����̑����̍�����A���������Ă��̏d�v�����A�[�I�ɕ\�����Ă���B�u�����͌o�ς̏W���I�\���ł���v�Ƃ������Ƃ��h�O�}�`�b�N�ɗ������āA�k�o�ϕs�����J���҂̐�����Ԃ̈������J���ҊK���̍��g�l�Ƃ����o�ό���_�ł́A���ۓ����͉�������肦�Ȃ������B�o�ϓI�ɂ́u���x�����v�Ƃ�����D���ǖʂɂ������̂��B������A�ނ�ɂƂ��ẮA�܂��Ɂu�\�z�O�̍��g�v�ł������肦�Ȃ������B�������ł�������`�ᔻ�̑ԓx���Ƃ�}���N�X��`�҂Ȃ�A���{�̃}���N�X��`���u�������_�Ƃ��Ċm�����Ă��Ȃ��v�����߂ɁA�u�����ߒ��̓Ǝ��̉^���@�����Ƃ炦�邱�Ƃ��ł����A���������āA������̋}���ȓW�J�̉\���ɂ��ė\�����A�]���Đ��������ɂ����錈��I�Ȏ��_�̔c���v���ł��Ȃ��������Ƃ��A���炻�̔j�Y��錾����������Ȃ������B�i�w�v�z�x
�Z��N���ɂ������]�u�T�v�́u���H���Ƃ����Ă̐������_�̔��ȁv�j
�@�u����͂ɂ�����q�ώ�`�A���j�ɂ������ώ�`�v�u���N����_�v���邢�́u����E�������v������̊��H�͂����ɔj�Y��鍐���ꂽ�������_�������̎�Ŋm�����鎖�A����ɂ�萭�������̌��ʂ��������Ƃɂ���B�������_�Ƃ́A��������K�������̑����u���Ȃ킿�A�����̖ڂ̑O�ł����Ȃ��Ă�����j�I�^���̈�ʓI�\���v�i�u���Y�}�錾�v�j�ɂق��Ȃ�Ȃ��B���ۓ��������̊ϓ_���瑍�����Ȃ������ƁA�����ɐ������_�̂��ׂĂ�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���ۓ����͌���̓��{�ɂ����鐭�������Ƃ��Ă͍ő�̌o���������̂�����B
�i��j���������̍L���Ɛ[���ɂ���
�@���ۓ����́A�u�v����v�ƍ��o����҂��������قǂ̑哬���ł������B����ǂ��A��̂ǂ̒��x�Ɂu�哬���v�������̂��A�܂�������ɂ�����������̂��B���̖��͌�����{�ɂ����鐭�������̔��W�ߒ��A�܂萭���ߒ��̋�̓I�𖾂ł���A��������̂݁A����̓��{�̐��������̌��ʂ�����������B
�@
�@���̐��������́u���ʂ��v�́A�����܂ł��Ȃ��A��ϓI��]�ɂ��ƂÂ������ӓI�ȗv�f�̂܂������܂܂�Ă��Ȃ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�X�ɂ���́A�P�Ȃ��ʘ_�ł͂Ȃ��A����Ƃ�������́A���{�Ƃ�������́A�����A�܂��Ɂu����v�̖��łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�Ȋϓ_����W�J����Ƃ�������̐������_�Ȃ���̂́A���{�ɂ����鐭�������̍ő�̌o���ł�����ۓ����́u�̑�ȋ��P�v
�̗��_���ɂ��u����v�ւ̐ڋ߂ł���B
�ia�j���{�̌��͍\���Ƃ��̐��i
�@�܂��ŏ��ɁA���{�̌��͍\�����c��\���t�\���{�\�x�@�i���q���j��
��
���̐��i�ɂ��ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă����K�v������B�Ȃ��Ȃ�A���������Ƃ́A���ƌ��͂��߂����Ă̑S���I�K�������ł���A�X�ɁA�u�O�q�s�݁v�ƌ����錻��̓��{�ɂ����ẮA��������K�������́A���[�j���̌����u�g����`�I�����v�̂��߂̓����A�������Ǔ����Ƃ��Ă����W�J���꓾�Ȃ��B���ۓ����������̘_�҂����łɖ��炩�ɂ��Ă���悤�ɁA���R�����I�ȁA�]���ď��u���I�Ȑ��������Ƃ��ēW�J���ꂽ���̂ł���B���̂悤�Ȑ��������̔��W�ߒ���������{�̐����ߒ��͓��{�̌��͍\���̋�̓I�ȕ��͂��ʂ��ɂ��Ă͌�肦�Ȃ��B���{��`���Ƃɉ�����c��̖{���ɂ��āA���[�j���́w���ƂƊv���x�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�x�z�K���̂ǂ̐������c��Ől����}�����A���W���邩���A���N�ɂ�����x���߂邱�Ɓ\���̓_�ɋc����������͂��ߍł�����I�ȋ��a���ɂ����Ă��u���W���A�c���`�̐^�̖{��������B�v�����ɖ��A���[�j���̓��V�A�\���v���O��́A�܂莑�{��`�̒鍑��`�i�K�ւ̕ϑJ�Ƃ������j�I�Ȏ����ɂ�����c��ɑ��āA�u�c��͂��łɎG�k��ɕς��Ă��܂����v�Ƃ����A�X�Ɂu���̎G�k��Ƃ����ł̌��c�ł����Ĕn�������ȕS�������܂����Ă���v�Əq�ׂĂ���B���̃��[�̋c��ɑ���_�k�́A���炩�Ɍ�����Ȃ��L���Ȗ{���_�ł���B����ǂ���������A�u�u���W���A�c��͂�����ׂ�̏ꏊ�v�ł��邩��A�u�c��i���Z���X�v�Ƃ��߂��邱�Ƃɂ���Ă��Ƒ����Ƃ���Ȃ�A����̋�̓I���͂�ӂ���������`�Ƃ��Ĕᔻ�̑ΏۂƂȂ�˂Ȃ�Ȃ��B
�@�����{�ɂ����ẮA�C�^���[�A�׃��M�[���Ɠ����������`�����@�Ƃ��Ē�^������Ă���A�c������`���x���m�����Ă���B���̂��Ƃɂ����ẮA�u���W���A�W�[�̐����I�A�R���I����́A�`���I�ɂ���A�c���ʉ߂���B�]���Čx�E�@�ɂ�����ۂɂ���A�����\�@�ɂ��Ă������ł��������A�c��̒��ł̓��_�E������߂����ē����̎R�������A�܂��������ɑ��Ă��A��̓I�ɂ͋c��ɂ����Č��o����邪�̂ɂ��̔��Γ����͋c������`�i��̗��ꂪ�x�z�I�ƂȂ�₷���B�����`�������S�āA�����`�i��Ƃ������u���I���i���������̂��A�����`�����@�Ƃ��Ē�^������Ă��邪�̂ł���B
�@�\���I���ǘ_�҂́A�}���N�X��`���Ȋw�Ƃ��ė����������A���{��`�����ƓƐ莑�{��`�Ƃ��ĉ��������i�K�ł̏��X�̐V�������ۂƈꎞ�I�ɉh�ɂ܂ǂ킳��A�����̖����`�̂�����x�̌��@�Ƃ��Ă̒蒅�����炭�鍑�Ƃ́A�Ƃ��ɋc��̂���w�傫���Ȃ������z���Ɏ��猶�z����������u���v�z�̓T�^�ł���B
�@�ޓ��́A�c���ʂ��Ă̕��a�v�����\�ł���Ƃ������z�I�ϓ_����A�}���N�X��`���Ƙ_�̏C���ɂƂ肩����B
���ƌ��͂����I���i�ƊK���x�z�Ƃɕ�������A�K���x�z�����A�ނ��낱�̌��I���i�����Ƃ̖{���Ƃ��Ď咣�����B�����ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃ́A����̏��X�̐V�������ۂ�{���_�Ƃ̊֘A�Ŏ��H�I�Ή��̖��Ƃ��Ĕc�����邱�Ƃł���B
�@���̐����I�����`�̌��@���̎��H�I�Ӌ`�́A�Љ��`�v���̂��߂̗L���ȏ����ƍL�Ăȋ�̓I�_�@�̑��݂Ƃ��ė�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�c��Ɍ`���I�Ȍ��茠�͔F�߂��Ă��邪�A�u���W���A�W�[�̐����v�����i����j�͓Ɛ�u���W���A�W�[�Ƃ̋��͂œ��t�ɂ���Č��肳���B���������āA���������͓�������ΐ��{�����Ƃ��đS���I�Ȑ��������Ƃ��ēW�J���������ɂ���B
�@���̂悤�Ȍ��͍\�����S�̂Ƃ��āu��ʂɋ��ʐ��Ƃ������z�I�`�ԁv�i�}���N�X�w�h�C�c�C�f�I���M�[�x�j���Ƃ��č��Ƃ��`�����Ă���B����ǂ��u���ʂ́A���z�I�ŋ��ʂ̗��Q�ɁA�����������I�ɑΗ����Ă������ȗ��Q�̂������ł̎��H�I�ȓ������A���ƂƂ��Ă̌��z�I�w���Q�x�ɂ����H�I�Ȋ��Ɛ���Ƃ�K�v�Ȃ炵�߂�v�i�}���N�X�w�h�C�c�C�f�I���M�[�x�j�B
�@���́u���H�I�Ȋ��Ɛ���v�Ƃ́A��̓I�ɂ̓��[�j���̂����u���������l�Ԃ̓��ꕔ���v���u�\�͑��u�v�Ƃ��Ă̏���R�A�x�@�A�����Q�ł���u����R�ƌx�@�Ƃ́A���ƌ��͂̏d�v�ȕ���ł���v�i���[�w
���ƂƊv���x�j���́u���ƌ��͂̕���v�́A����̓��{�ɂ����ẮA���̌��z�������Ȃ��肷�ĂāA�x�@�̎����e���A���㎩�q���̍��������ւ̐�O���A�X�ɉE���\�͔j�ւ̓]����������āA�\�͉����Ă���B���������́A���̍��ƌ��̖͂\�͉��Ƃ����܂��āA�s��I��"�\�͓I�`��"�̐��i�����т�������Ȃ��B�]���āA���ƌ��́A�E���̖\�͓I�e�������������̔��W�̈�̏d�v�Ȍ_�@�ƂȂ�B
�@�ib�j����ɂ����鐭�������̔��W�ߒ�
�ȏ�̂悤�Ȑ��i�������͍\���̒��ŁA���ۓ����͍��Ƃ̖{�����u�x�z�K���̈ӎu�v
�ɑΌ����āA���ƌ��́��u�ł����x�ɑg�D���ꂽ�\�́v�i�}���N�X�w ���{�_�x�j
�Ɉ������Ɠ������Ă������B���̐i�W�̉ߒ����A�Ό��̖͂����œ_�ɁA����ɂ����鐭�������̔��W�ߒ��Ƃ��āA���̂悤�ɒ��ۉ�������B
�@�i1�j���Έӎu�̑S���I�g�D���̒i�K�B��`�A����𒆐S�ɂ����[�֊�������A�������ӓ����Ƃ��āA����ɑ�K�͂ȏW��A�X���f���ւƔ��W���Ă����B
�@�i2�j�c��̌��z���ɑ��āw���a�Ɩ����`�x�Ƃ����A����Ȃ錶�z�����̂��̂��������Ă̑S���I���������̓W�J�����i�K�B�W��A�X���f���𒆐S�Ƃ����������A�c��ł̓��_�̐i�s�ߒ��ɏƉ����������̎R���`�����Ȃ��甭�W����B���̉ߒ��Ōx���̖W�Q�������A"���ƌ��̖͂\�͉�"�ɂ��"��O�̖\��"����������B������_�@�ɋc��̌��z�����\�I����A�����͎��̒i�K�֔��W������������n����B
�@�����Œ��ڂ��ׂ����Ƃ́A�c��̌��z�������ł͂Ȃ��A�����������}�̌��z�����������ɖ\�I�������Ƃł���B�c��̌��z�����\�I���ꂽ�i�K�ɂ����ĉ����Ȃ��ׂ����B�܂肻�̎��_�ł̐�p���O���v������B����ɓ������Ȃ��w�����͑�O�̖ʑO��"���\��"�Ƃ��Ď��Ȃ̎p�����炯�o���B����O�q�}�̕��_�����������Ăĕ��͂��߂�B���̊��������̕��_���̕���́A���R�̌��ʂƂ��āA�����w�����ɂ���炸�A�Ǝ��ɐ��������̋ǖʂ�ŊJ���Ă�荂�������ɐi�W������Ƃ���L�Ăȑ�O�A�Ƃ��ɃC���e���𒆐S�ɂ�����������̐����I�����Ƃ��ēo�ꂳ����B���̒����͎v�z�I�Ɂu�^�̑O�q���}�v
�̊m���Ƃ����Ƃ���܂ō��߂��"�g���c�L�Y���^��"���`������B
�@�u�S�w�A�v�͂܂��ɂ��̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ēo�ꂵ���̂ł���B�������}�̖��\�A�Ƃ������́A�ނ��듬���̎��I���W�̈ӎ��I����̒��ɂ����āA���Ƃ����ċǖʂ�ŊJ���悤�ƓƎ��ł��̂��߂̐�p��Nj������B���̐�p���s���ɂ����ہA��̏�Q�ɒ��ʂ����B�u����ƒc���v�Ƃ����_�b�ł���B�S�w�A�͂��̐_�b���A�������_�̘`�����Ƃ��Ĕj�����A�������̗��̉��Ƃ����ϓ_����A�������}�Ƃ��̃G�s�S�[�l���ɂ��"�n�l�A�K��"�A"�g���b�L�X�g"���̔����ނ��낻�̐�p�̗L�����̃����N�}�[���Ƃ��A�Ǝ��̐�p�̋�̉��ɓw�͂��������B11�E27
�A1�E16 �A6
�E15�A�����͏p���f���̐�p�ɂ����Ȃ������Ƃ͂����A���ۓ����̎��I���W�������炵������I�v���ł������B�����炱���A�S�w�A�͏�ɉ^���̒��S�ƂȂ����̂ł���A���̑S�w�A�̉^�����ʂ��ɂ��ẮA���ۓ����̎��̒i�K�ւ̔��W�͍l�����Ȃ��B
�@�i3�j���ƌ��͂��̂��́A�܂�\�͂ƒ��ڑΌ�����i�K�B���ƌ��͂��܂��܂��\�͉�����̂Ƃ����܂��āA��O�̊X���f���̂���w�̖\�͉��̒��ŁA�u���W���A�W�[�͈��ۂ��Ȃɂ��Ȃ�ł����������˂Ȃ�Ȃ��K�R������A�c������`�̘g�̒��ł́A�����A���z����ێ������܂܂ł͂����ʉ߂����邱�Ƃɐ����������A���ɁA����c��̌��z�������āA�u�P�ƍٌ��v�Ƃ����A���ƌ��̖͂{���ł���"�\��"�ɑi����������Ȃ��B���̖����`�j��̖\���́A�v�`�u���̖����`�ӎ���傫���h�����A�����͔������ӓ����̎�������A�}���ɓ��t�œ|�����ւƓ]������B��O�̖\�͉��͍X�ɔ��W���A�v�`�u���̊X���s���ƕ����I�ȘJ���҂̎��͍s�g�ɂ���āA���ɓ��t��@���o������B
�@���̒i�K�ɂ����ẮA�����̐i�W�͌��͂Ƃ̒��ړI�Ό��ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B���ۓ����̏����̓W�]�́A���ƌ��͂Ƃ����\�͂ɂ���Ă��炸�����Ă���u���W���A�W�[�̎x�z�̐���ے肷�邱�ƁA�����v���ȊO�ɂȂ������̂ł���B�Z�E���̎��R������O�ɂ��āA������Ƃ�͂ˑ�ȘJ���ҁA�w����O�́A���ɉ��������Ȃ����Ȃ������B�s�k�̈�u�ł���B
�@���ۓ����́A���͂Ƃ̍t�˂��I�Ɋ܂݂Ȃ���A���������ĖG��I�Ȋv���I���g�݂Ȃ�����A���͂Ƃ̑S�ʓI�A���ړI�Ό��Ƃ��ẮA���[�j���̂����u�v���I���g�v
�݂������ƂȂ��s�k���Ă������B
�@�ic�j���������́w�L���Ɛ[����͉��ɂ���Č��肳��邩�H
���������́u�L���v�́A���̓������ǂꂾ���̏��K�����܂�����œW�J���ꂽ���Ƃ������Ƃł���A�u�[���v�́A�Ό��͂Ƃ̊֘A�ŁA���ۓ����ɓT�^�����ꂽ�k�x�z�K���̈ӎu�ɑΗ������x�z�K���̈ӎu�̑S���I�g�D�����Ƃ̌��z���ɑ������Ȃ錶�z���������Ă̓��������Ƃ̌��z���̖\�I�����ƌ��͂Ƃ̒��ړI�A�S�ʓI�Ό��l�Ƃ�������ɂ����鐭�������̔��W�ߒ��̂ǂ̒i�K�܂Ői�W�������Ƃ������Ƃł���B
�@���������̐[�x�̖��́A���̓�_�A�����̎�̂Ƌq�̖̂�肩��⑫����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�܂����ɁA�����̎�̖̂��A�ǂ̗l�Ȋϓ_���瓬��ꂽ�̂��Ƃ������ł���B���ۓ����́A���̎��I�]���k�v�`�u�������ӎ����v�����^���A�����ӎ��l�����������Ȃ������B�v�`�u�������ӎ��̍��g�ɂ��ƂÂ��A�v�`�u����̂̍���f���Ƃ����X���s���ɂ���Ă����t�œ|�͎�������Ƃ������Ƃ����ۓ����͎�����Ɠ����ɁA�c������`�̕����Ƃ��Ắk���t�œ|��������U�����I���l�Ƃ����c���`�R�[�X���x�z�I�ƂȂ�A���������������̂ł����Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�u�O�q�s�݁v�̂��Ƃł̐������������Ǔ����̌��E�Ƃ��āA���ɐ擪�ɗ����ē����������w���ɂ́A�w���^���̌��E���Ƃ��ċ������B�v�`�u�������ӎ��̃v�����^���A�����ӎ��ւ̓]���ɂ́A�c��̌��z���̖\�I�Ɠ����ɁA�����ɎQ�����Ă����̂������̎����Ă���v�`�u�������ӎ����܂����z�ł������肦�Ȃ����Ƃ������邱�ƁA���̂��߂̐�p���K�v�ł���B�H��ł́A�X���ł̎��R�����I�Ȑ�������b�Ƃ��āA�v�����^���A���͂̋�̓I�`�Ԃ��܂߂��A�܂�u���W���A���͑œ|��́u���ԓI���{�v����A�ߓn�I�[�u�A�X�ɒ��ړI�Ȍ��͂ւ̍s���܂Ŋ܂܂ꂽ��A�̐�p�A������"�j��"�̑��݂���Ώ����ł���B����������́A���̐�p����̉�������O�q���}�Ƃ��āA����̓I�Ɍ����Ȃ�A�V�������A�J���҂̂Ȃ��Ɋm�ł���g�D���m�����Ă���A������x�̘J�g�łփQ���j�[���Ƃ邱�Ƃ��ł�����x�̏�Ԃɂ����ĂłȂ���A������"�j��"�Ȃ���̂��쐬����"�O�q���}"�̖��̂�������Ă݂Ă��A���Ӗ����Ƃ������Ƃł���B
�@���ɁA�����̋q�̖̂��́A�x�z�K���̎x�z�\�͂��ǂꂾ�����h�������ł���A���̊ԑ�͐��������́u�[���v
�ɂ��Č���I�ɏd�v�ł���B�u���Ƃ́c
�ꎞ��̎s���Љ�S�̂��W��Ă���`�Ԃł���B�����猋�ʂƂ��Ă��ׂĂ̋��ʂȐ��x�͍��Ƃɂ���Ĕ}���A��̐����I�Ȍ`�Ԃ��Ƃ邱�ƂɂȂ�v�i�}���N�X�w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�j�}���N�X�������ŏq�ׂĂ��鍑�Ƃ̏W�̑r���������I�ɂǂ̒��x�܂Ői�s�������ł���B
�@����`�F�́A���ۓ����̓W�]�Ƃ��āu���݁A�x�z�w�����ɔ��W�����鐭���Η����A���ۉ�����Ǝ��R�����Ȃǂ��_�@�ɂЂ낪��A���������g�債�[�������Ă䂭���Ɓv�i�w�������_�x60
�N5
�����j��B��̊�Ƃ��Ĉ��ۓ����̐[�����͂����Ă����B����ǂ��ނɂ́A���̎x�z�w�����̑Η��̖����A�S�̓I�Ȑ����ߒ��Ƃ̊֘A�ŁA�u���W���A�W�[�̎x�z�\�͂̓��h�Ƃ��Ė��m�Ɉʒu�Â��鐭�����_���Ȃ��A�����ĉ������\���I���ǘ_�҂���ނɂƂ��ẮA���̎����}�̓����Η��ւ̎��H�I�Ή��́A�����}�̔��嗬�h�ɊÂ����z�������������Y�}�̂����u�����}���̗ǐS�I�����v�Ƃ������E�����Ȃ������B�����炵�Ă��̊��҂�������ƁA�u�����}���̔��嗬�h����\���Ă��闧��͒����u���W���A�W�[��Ȃ�炩�̍����I�ȑΗ��Љ�K�w�̂���ł͂Ȃ��A���̓_�ł͎嗬�h�Ɠ������Ɛ�u���W���A�W�[�̊K���I����ł������v�i�w���j�w�����x
60 �N9
�����j�ƁA������Ȃ���̋��������Ȃ�ׂ�������Ȃ������̂��B�u���Ƃ̏W�v�Ƃ������Ƃ̎��H�I��������A�r�����ꂽ�u���Ƃ̏W�v���v�����^���A���͂̂��ƂɏW�Ȃ����Ƃ����v���I�ϓ_����̔c�����K�v�Ȃ̂��B
�@���ۓ����́A���t��@�܂Ŕ��W�������A�݂̑ސw�A�r�c�̓o��ɂ��A�u���W���A�W�[�̎x�z�\�͂̓��h�͊ȒP�ɉ��ꂽ�B���̒��x�̓��h�ɂ����Ȃ������̂ł���B����w�̊�@�̐[���i���t��@�����{��@���̐���@�j���o�������Ȃ������̂́A�O�ɏq�ׂ����Ƃ������̎�̂̏��������݂��Ȃ��������ƂƓ����ɋq�̂̏��������݂��Ȃ������̂ł���B
�@�q�̖̂��ɂ��ă��[�j���́w���Y��`�́u���������a�v�x�ɂ����Ď��̂悤�ɂ����Ă���B
�@�u���ׂĂ̊v���A�Ƃ��ɓ�\���I�̎O�̃��V�A�v���ɂ���Ċm�����ꂽ�v���̊�{�@���͂����ł���B���Ȃ킿��悳��A�}������Ă����O�����܂܂łǂ���ɐ����ł��Ȃ����Ƃ����o���āA�ύX��v�����邾���ł́A�v���ɂƂ��ĕs�\���ł����āA���҂����܂܂łǂ���ɐ������A�x�z���邱�Ƃ��o���Ȃ����Ƃ��A�v���ɂƂ��ĕK�v�ł���B�w���w�x
���Â����̂��̂��܂��w��w�x�̂Ƃ��ɂ͂��߂āA�v���͏������邱�Ƃ��ł���v�B
�@���ۓ����͂���Ɍo�ϓI�ɂ́u���x�����v�Ƃ�����D���ǖʂɂ����Ă�������ꂽ�̂ł���A�u��w�v���Ȃ킿�x�z�K���u���W���A�W�[���u���܂܂Œʂ�ɐ������A�x�z���邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ƃ�����@�I��͐����I�ɂ��o�ϓI�ɂ����݂��Ȃ������̂ł���B���������āA���ۓ����̍ŏI�ǖʂł̍��g���v���I��ƍ��o���āA�v�����\���Ƃ������z��������҂�����Ƃ���Ȃ�u�v�`�u���}�i��`�v�Ƃ��Ĕᔻ���ꂴ������Ȃ��B�u�ꎞ��̎s���Љ�S�̂��W��Ă���`�ԁv�Ƃ��Ă̍��Ƃ��A���̏W��r������ő�̎����́A�s���Љ�̊�b�ł���o�ς̏W���j���Ƃ��A�������Q�ł���B��������A���Q�͍ő�̊v���̏���������q�ϓI�����ł���B
�id�j���������̋�̓I�_�@�Ƃ��Ă̈��ۉ���
�@���ۓ������ȏ�̂悤�ȁu�L���Ɛ[���v�����������������Ƃ��ēW�J���ꂽ���Ƃ̊m�F�̏�ɗ����āA�ēx�A���ۉ��肻�̂��̂̂����������̋�̓I�_�@�Ƃ��Ă̈Ӌ`���A���ۉ��肪���ꂾ���́u�哬���v�킴������Ȃ������K�R�����A�����̖��Ƃ��ĉ𖾂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���ۉ���́u���{�̈��]���_�ł���v�Ƃ����錾�t�̒��ɁA�o�ϓI�D���ǖʂɂ�������炸�A���ۓ��������ꂾ���̍L�Ăȑw���܂�����ł̓����Ƃ��ēW�J���ꂽ���Ƃ̉𖾂̗̓M������B
�@���ۉ���͈��܌ܔN�ȍ~�̓��{���{��`�̌o�ωߒ���������̂ł������B�܌ܔN�ȍ~�A�{�i�I�ɊJ�n���ꂽ�ߑ㉻�ɂ��Γ��c���̉ߒ����W���A�ΊO�c���ւ̓]���ł���A�������A����́A���鍑��`�̕s�ϓ����W�̌��ʂƂ��Čܔ��N�Ȍ�W�J����Ă��鎩�R���Ƃ������a�I�`�Ԃł̒鍑��`�I�����̌����ɂ�荑�ۓI�ɂ��]�������܂��Ă����̂ł���B
�@���̍ہA�Ɛ�u���W���A�W�[�͂��̓]���̐�����A�鍑��`�I�����̔��W�̃R�[�X�Ƃ��āA���{�����S�̂̋��ʗ��Q�Ƃ��Ē�N������Ȃ��B�]���Ă���́A�S�Ă̊K���ɑ��ė��Q�W�����B���ۉ���͂��̂悤�ȓ��{�����S�̂̕��������肷��u���]���_�v�ł������B����̂ɁA���̖����I�_�@�ɂ���ĂЂ��������ꂽ���ۓ����́A���̐��i����K�R�I�ɁA���ꂾ���́u�L���v�������������������A�x�z�w�����ɂ����Η�����������Ȃ������̂ł���B
�@���ۉ��肪�����̖��Ƃ��āA���������N������A���̌�̑������O�N�Ԃɂ�����A���̑��̏��X�̐��������̋�̓I�_�@�i�鍑��`�I����A�����I�������A�Ɛ�{�ʂ̌o�ϐ���j�́A���ׂĂ��̍ő�̋�̓I�_�@�ł�����ۉ���Ƃ̊֘A�ɂ����Ė��Ƃ���A���ۉ���́A����ɐ����ߒ��̒��j�ƂȂ�A���������̏œ_���`������B���������Ĉ��ۉ���́A���{�̌o�ωߒ��Ɠ����ɁA�����ߒ������W��Ƃ������i���������̂ł���B
�@�������Ĉ��ۉ���́A���{�����̕������A�ŏI�I�ɂ͓��{�����̐����I�͊W�ɂ���āA���������ɂ���Č���������ׂ����̂Ƃ��Ē�N����Ă����̂ł���B�����炱���A���ꂾ���́u�[���v�����������������Ƃ��āA"�\�z�O�̍��g"�������̂ł͂Ȃ��A���̍��g�́u���������̑S�Ă̏����ɂ���ď������ꂽ���́v�ł���A���{���{��`�́u����܂ł̔��W�S�̂ɂ���ĕK�R�I�Ɏ䂫�N���ꂽ���́v�A�u�܂������@���ɂ��Ȃ������́v�i���[�j���w�v���I���g�x�j�Ƃ��Ĕc������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i��j
���������ɂ�������p�Ə���p�ɂ���
�@�����͈��ۓ����̔��W�ߒ�������ɂ����鐭���ߒ��Ƃ��ĉ𖾂��钆�ŁA���������̎��I���W�ɂƂ��Č���I�ɏd�v�Ȃ̂͐�p�ł���Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����B��O�^���̑��s�͓��R���̓�����Q���I�ɐ[��������B�������Ȃ���A����݂̂ɂ���Ă͓����̎��I���W�͂��肦�Ȃ��B���́u�ʂ��玿�ւ̓]���v���Ȃ킿�u���v�������炵������́A���ꂱ���������̌�����p�ł���B���̊ϓ_���琭�������ɂ������p�_�̏d�v�����m�F����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�܂������́u���������̍L���Ɛ[���v�̒Nj��̉ߒ��ŁA�X�̐��������̋K�͂������鐭���I�A�o�ϓI�����̋�̓I���͂ɂ�茩�ʂ����邱�ƁA�����čŌ�ɂ����̏��X�̐��������̒��ŁA�ł��[���������������ʂ��A���̑��̏��X�̐��������͂��̍ő�̋�̓I�_�@���߂����Đ��������ɂǂ��Ή����ׂ����Ƃ����ϓ_����̈ʒu�t�����K�v�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���ꂼ��̐��������̍L���Ɛ[���ɉ�������p���Ƃ邱�Ƃɂ��A�S�̂Ƃ��čł��[�����������A�����v���̏�������������̑��݂��鎞�_�ł̊v���I��p������������܂ł̐����ߒ��ɂ����̐��������ɂ������p�𐳂����ʒu�t���A�����I�ȁA���m�ȁu���ʂ��v�����������������̓W�J���K�v�Ȃ̂ł���B
�ia�j
��p�͉��ɂ��ƂÂ��Ă������Ă���ׂ����H
�@��������p�͗�O�I�Ɏ���������̂��A�ʂ��ĉF��O���̂����@���A�D�ꂽ���H�Ƃ̒����ɂ��ȊO�ɂ��肦�Ȃ��̂��낤���H���̖��͐������_�ɂ������{�I�ۑ�ł���B���[�j���́w�J�[���E�}���N�X�x
�ɂ�����"�v�����^���A�K���̐�p"�Ƃ������ڂ������Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�w�}���N�X�́c �c
�v�����^���A�I�K�������̐�p�̖��ɐ₦���钍�ӂ����B�c �c
�v�����^���A�[�g�̐�p�̎�v�ȔC�����}���N�X�́A�ނ̗B���_�I���E�ς̑S�Ă̑O��������Ɉ�v�����ċK�肵���B����^����ꂽ�Љ�̑S�Ă̊K���̑��ݘA�ւ��ꏏ�ɂ����S�̂̋q�ϓI�Ȍڗ��A���������Ė��A���̎Љ�̋q�ϓI�Ȕ��W�i�K�̌ڗ��A�Ȃ�тɁA���̎Љ�Ƒ��̎Љ�Ƃ̊Ԃ̑��ݓI���A�ւ݂̂���i�I�K���̐�������p�̂��߂̊�b�Ƃ��Ė𗧂��Ƃ��ł���B�x
�@�����ɐ�p�_�̍��{���A��������p�͉Ȋw�I�Ɏ��������邱�ƁA���̂��߂ɕK�v�ȏ���͉͂����Ƃ������Ƃ��Ȗ��ɂׂ̂��Ă���B����Ƀ��[�j���́w���Y��`�́u���������a�v�ɂ����āA���̌��������V�A�̊v���^���̋��P����A���̂悤�Ɋm�F���Ă���B
�@�u��O�̊ԂɊv���I�ȋC�����Ȃ��A���̂悤�ȋC���̍��܂���������鏔�������Ȃ���A�ܘ_�v���I��p���s���Ɉڂ����Ƃ͏o���Ȃ����A�����́A���V�A�ŗ]��ɂ������ꂵ�����݂ǂ�̌o���ɂ���Ċv���I�C����ɂ��ƂÂ��Ċv���I��p���������Ă邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�v
�Ȋw�I���͂��K�v�Ȃ̂��B���̍ہA�u���̍��Ƃ̑S�Ă̊K�����́v�A��������������̊K���Ԃ̗͊W�̕��͂�����I�ɏd�v�ł���Ƃ������ƁA�����A����ꂪ��p���s���Ɉڂ���Ƃ��鐭���ߒ��̋�̓I���͂�����Ƃ��K�v�ȏ����ł���Ƃ������Ƃ��ēx�m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ib�j��p�_�Ƃ��ĉ��Ǔ����Ɗv��
�@�u�O�q�s�݁v�̂��Ƃɂ�����K�������́A���Ǔ����Ƃ��Ă����W�J���ꂦ�Ȃ��Ƃ��������̊m�F���ɂ��āA���Ǔ����̓i���Z���X������v���^�����ƁA�ő���j�݂̂̂�����ł݂Ă��A���̊v���_�́A�����ۂɂȂ炴������Ȃ��B���̊v���������Ɉˋ������������Ȃ�����ł���B
�@�\���I���ǘ_�҂́A���Ǔ����݂̂��Ηǂ��Ǝ咣����B���Ǔ����̉ʎ��̐ςݏd�˂��Љ��`�������炷�Ƃ������ǎ�`�I�ϓ_����B
�@���łɖ��炩�ɂ����@�������`�����Ƃ��ēW�J���ꂽ���ۓ����́A���u���I���i�����������Ȃ�����A���̓����̉ߒ��ō��Ƌ@�ւ�ʂ��ĕ\�킳��鍑�Ƃ̖{���ւ̓������A��p�ɂ���č��ƌ��͂Ƃ̒��ړI�Ό��܂ō��߂�ꂽ�B���̑Ό���S�ʓI�Ό��܂ŁA���������Ċv���I���g�܂ō��߂��邱�ƂȂ��s�k���Ă��������A���̈��ۓ����̌o���́A���Ǔ����̓O��I���s�͊v���ȊO�ɉ��������Ȃ����_�܂ł̓����̔��W�������炵����Ƃ������Ƃ��A�����ɋ����Ă���B
�@���[�j���́w���ƂƊv���x�̒��ŁA�G���Q���X�̃p���E�R���~���[���ɑ���]���i�w
�t�����X�̓����x��O�ŏ����j�����p���āA�u�G���Q���X�͂����œO�ꂵ�������`������ł͎Љ��`�֓]�����A�����ł͎Љ��`��v������Ƃ�������������E�_�ɐڋ߂��Ă���v�Əq�ׁA�X�Ɂu�����`��O��I�ɔ��W�����A���̂悤�Ȕ��W�̏��`�Ԃ�v�����A���̏��`�Ԃ����H�ɂ���āA�_�����铙�X�A�S�Ă����́A�Љ�v���̂��߂̓����̏��C�����\������v�f�̈�ł���v�Əq�ׂĂ���B
�@���[�j���������ɂ����u�O�ꂵ�������`�v�Ƃ́u��d���́v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�u���W���A�W�[�̎x�z�\�͂̓��h��@���k���t��@���̐���@�l�ւƔ��W����ߒ��ŁA�����̓����Ƀv�����^���A���͂̑g�D���L���A�r�����ꂽ���Ƃ̏W���v�����^���A�[�g�ƍق̂��ƂɏW�Ȃ������ƁB���V�A�v���̋��P���烌�[�j���ɂ���Ĕ������ꂽ
���́u��d���́v�̏�Ԃ́A������Ȃ��L���ȃv�����^���A�v���̊�{�@���ł���B���̓�d���͂̏�Ԃ�}������ău���W���A�c��ɂ����ēƐ��ǂ��ߌǗ������ĎЉ��`�ւȂǂƂ������Ƃ͉��ǎ�`�̌��z�ɂ����Ȃ��B
�@���̊v����ɂ�����A���[�j���̂����u�v���I��p�v����p�Ƃ�сA���̑��p������������ɂ����鐭���ߒ��ł̐�p������p�Ƃ��ċ�ʂ��邱�Ƃɂ���B
�@�������Ă����̂�����p�_�Ƃ��Ẳ��Ǔ����Ɗv���̊֘A�͂����ł���B�S�Ă̏����i�Ƃ��ɐ����̖�肪�d�v�j�̌����̒�����A����̐��������̂������̓I�_�@�ƁA���̌_�@���߂����Ắu���������̍L���Ɛ[���v�����ʂ��B���̏�ɂ����āA�X�̉��Ǔ����ł̏���p���A�ł��[�����������A�v���I��ɂ�������p�̎���������������̂Ƃ��Ĉʒu�Â���B
�@�����͉��Ǔ�����S�͂�s���Ď��g�ށB����ǂ�����́A���Ǔ����̉ʎ����̂��̂�ړI�Ƃ���̂ł͂Ȃ����Ǔ������p�ɂ���āA��荂�������ɁA��萭���I�ɁA�܂�Ό��͂Ƃ̒��ړI�A�S�ʓI�Ό������Ĕ��W�������̉ߒ��Ŋv���̏������������A�S�̂Ƃ��đ��p�ւƔ��W�������߂ł���B
�@�ic�j�w�헪�Ɛ�p�x�_�ɂ���
�����͂Ȃ��u�헪�Ɛ�p�v�Ƃ��킸�ɁA���Ƃ���Ɂu���p�Ə���p�v�Ƃ��Đ�p�_��W�J����������Ȃ������̂��B����͎��̗��R�ɂ��B
�@�u��p�ɂ����Č���Ă��헪����������c�v�Ƃ������_�́A�ʂ��Ă��̐��������������邾�낤���B�����͔ۂł���B���j�͂���Ԃ��������Ȃ��B�������p�ɂ���ĂЂ��������ꂽ�����ߒ��́A�����Ă��Ƃւ��ǂ�����"�헪"���̂��̂�����ꂴ������Ȃ��B����ɂ��̗��_�́A�ő���j�̎�`�́A���������ɂ������p�̌y���Ɛ�p�ɂ�������̍������ɑ��Ă��̐������̗��_�I��������Ă���B
�@�v�����^���A�[�g�̊K�������̐�p�_�Ƃ��āu�헪�Ɛ�p�v�Ƃ������t���͂��߂ēo�ꂵ���̂́A���[�j������̑�O�C���^�[��Z����ɃX�^�[��������Ă����A��O�C���^�[�̐V�����j�̑��Ăɂ����Ăł������B�}���N�X�����[�j�����A�v�����^���A�[�g�̊K�������̐�p�_���A�헪�Ɛ�p�ɕ������Ę_�������Ƃ͈�x���Ȃ������B
�@�����͂��́u�헪�Ɛ�p�v�_���X�^�[���j�Y���ɂ���p�_�̘c�ȂƂ��Ĕj�����A�}���N�X�E���[�j���̐�p�_�̌������������̎��݂Ƃ��āA�u���p�Ə���p�v�Ƃ����A�v�����^���A�ƍق̎����ւ������A�̐�p�_�Ƃ��ēW�J�����B
���������A�Љ�������\��O���w���^���_
�Њw�����n���ψ���
���Z�ܔN�l��
������u���g�n�Њw���@�֎��w�Ԍ��x�ɉ����F�炪���\�i���Z�ܔN�O���j�B
�i1�j���ݓ�̏W��J�Â���t�̑�O�l�̊���`�����悤�Ƃ��Ă���B
�@��͋��s�{�w�A�\�s�w�A�Č������ψ����Â̔��E��`�O�O���[�v�ɂ����ؓ�������ɂ����S�������ƏW��i�O�E�O���E�����ɂāj�ł���A���܈�͑S����w���������g���A����̏����ɂ�鋳����[�~�i�[���i�O�E��l�A��܁A��Z�j�ł���B��҂͈��N�ȗ��V�܂��Ă����w�����������W�A�l�̑S���I�A�т����悤�Ƃ�����̂ł���B
�@
�@���{���{��`�̑ΊO����ɑ��铬�����A�����ł̊w���̎Љ������ĂыN�������w���������A�@���Ȃ�������ł����ē��ꂵ�Ă䂭���͊����Ƃ̌����I�Ȗ��ɂȂ����B���������̗��������ǂ��炩�Ɉ�ʉ�����Ă����X���͏�̕��G�����̂��̂ɋN�����Ă���B�����̐V�������h�̓��ؓ����ɂ���_�˔j�S�ʓW�J�����ɗv���w�������x����F���̍���ɂ́A��N�S����̏������ɂ�����ꂽ�@���A���{���{��`�̉ߏ萶�Y�̐��n��
�l�E�ꎵ�ւ̔��������̗����̉����Ƃ��Ă̌��������̋���ȗ�����H�������E��ł̊�@�̔����Ɛ��������ւ̃i�_�����݁��K�������̍V�g�Ƃ������`�[�t�����݂���B����̂ɂ����A�ޓ��͏��w��������������̔C���Ƃ��Đݒ肷�邱�Ƃ͏o���Ă��A���̓����ɓƎ��I�Ȑ����������邱�ƂɎ��s���Ă���B�ɒ[�Ɍ�����Ȃ�Ίw���������̐؎̂āA�Ȃ����͂��̓����̐��������ւ̗��p�̈���o�Ă��Ȃ��̂ł���B
�@��������[�~���哱���鋤�\�t�����g�̏��N�́A�����܂ł��Ȃ��ޓ��̍��ƓƐ莑�{��`�_�\���Ƙ_����̊w���̍\�����v��hegemony�̊m�����s���Љ�̉e�������������Ƃ����l�����������Ă��邱�Ƃ͏O�ڂ̈�v����Ƃ���ł��邪�A���ꂪ�ɂ߂Č��݂̋ǖʁ\�\
�����������_�C�i�~�b�N�Ȕ��W����L���Ȃ����E���Ɗw�������̍V�g�\�ɏƉ����Ă��邪�̂ɔޓ��͊w��M
�̐V���Ȕ��W�̉���w�������Ɉꌳ�����悤�Ƃ��Ă���B�������̂��Ƃ́A����A�W�A�̊�@�����ɂ������ۓI�Ȕ��v���Ɠ��{���{��`�̂���ւ̋�������Ƃ��̊O�𐭍����ӂ̓����ɂ����{���{��`�̐S�����ł̖�����\�I���邱�Ƃ���s�p�I�Ȑ����ӎ��̌`�����l�O���N�g���邱�ƂɂȂ�B�X�Ɋw�������̌��E���͍���̐����ߒ��֑�O���Q�������߂邱�ƂɎ��s���A�w����`�ɓ]�����Ă��܂����낤�i���݂�������������Ȃ����j�B���������̂��Ƃ͋ɂ߂ďd�v�ł��邪�A���݂̊w�������͔ޓ��̐M����h�O�}���t���Ȃ����i�̂��̂ł���B���̂��Ƃɂ��Č���q�ׂ�B
�@���ݕĒ鍑��`�����Ƃ������ۓI���v���A���Q�̓����́A�C�M���X�A���{�Ȃǂ̌��\
�������v�������������Ē�ɂ���āA���x�����z���Ėk�׃g�i���̐N�����Ӑ}������̂ɂ�������B�X�ɓ��؉�k�͂��̗����ɑΏ�����Ē�A�p�����̑��}�̗v���Ƃ��ē��{�u���W���A�W�[��˂��������Ă���B���؉�k�̋}���Ȑi�W�͎Q�@�I�����}���Ȃ�������̃e���|�͕ς��Ȃ����낤�B
�@�������x��������̐��ݗ������C���t���A�����ĘJ���ҊK���̘J�������\�������\�����}���A�X�ɒ�����ƁA�_���̊�@�͋���ȎЉ�s���������N����
�A�Љ�������Ƃ������鐫�i��M���N������B
�@��X���������Ă��鏊�̏t����̐��������\�w�������Ƃ́A���ɑO�҂���L�̏ւ̑Ή��Ƃ��āA��҂���q�̎Љ�������̊O���I�\���Ƃ��ẮA"����"�ւ̑Ή��Ƃ��Č����Ă���B
�@�J���]�_�ƁA�����T�O�i�w����̊�x�O�����u�Ɛ�̍����x�z�Ɗv�V���́v�j�́A�u���܂̐��E�̂��܂̓��{�̒��ł́A�v�V�����w���ɂ�����l�B�͈���ł͍��ۏ�ɋ@�q�ɑΉ����ĊX���s����g�D����͗ʂ����Ɠ����ɁA�����ł͍��ƓƐ莑�{��`�̐����I�o�ϓI�����I�x�z�̑S����ɃX�L�Ԃ��������ʐ헪�z�u���s���Ď��v��𐋍s���闼�ʂ̔������K�v�ł���B�����Ēʏ�̏ꍇ�A���̓ʂ̓����ɂ͋@�B�I�Ɍ����ł��Ȃ��Ǝ��̗̈悪����A�����ɖژ_��̂ނ�������������Ɠ����ɁA���̂��Ǝ��g��"���܂̐��E"�Ƃ��܂̓��{�̓���I�c����݂点�A�����̑S�ʓW�J���\�ɂ���헪�I�������Ȃ킹��댯����ɕ��݂��邱�Ƃɏ\�����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂����̂��Ƃ͐��{��@���̐��̐�����@�ɔ��W������{�I�����������߂�K���Ƃ��Ȃ肤��̂ł���v�ƁA�ނ�"���ĎЉ��`�v��"�̐헪�ڕW�͂Ƃ������Ƃ��āA���݂��������������ƎЉ�������Ƃ̓��ꂵ���w���̓���Ə�̕��G�����s���w�E���Ă���B
�@��X�͓����̐V�����������̏��N�̔@�����݂̏�i��̓I�Ȗ��܂Ŋ܂߂āj��]������킯�ɂ͂����Ȃ��B�X�Ɍ����\�t�����g�A�V�������h�A�����Ă̊w��M
�̐����������ɋ��ʂ��Ă����邱�ƂƂ��āA��N����X���w�E���������K�������̉�̂ƍĕҁA���̂��Ƃ������N�����Ă��鏊�̓��{���{��`�̐��ڂƂ����ɐ��N���鏔�K���\���K�w�̑����̖��������O���ւ̖����̕ώ��ƐV���ȍ��x�ł��[�������̌`���ɑΉ����Ă̑�O���̎w�����̑n�o�ɑ��đS�����F���\���v�z�ł��邱�Ƃł���B
�@���̂��ƂɓK������Ƃ����M
�̎w�����́A���Y��`�ғ����\���ۑS�w�A�̗��r�����Ƃ���̉i�v�v���_���̂��̂̔ے��ʂ��Ă����l�������ׂ����̂ł���B
�@�u���m�̂悤�ɁA�����۔h���_�ɂ�锪���ϋ���H���͌����̊K�������̒��ŘJ�w��g�Ɛ�쐫���_����e�Ƃ���]���H���ւƓ]�������̂ł������B�����Ă��̉ߒ��͓����ɁA�w���t���N���i�v�v���_�̓k�ƂȂ�ߒ��ł������B���̂Ȃ���̒i�K�ɂ�����w��M
�͐퓬�I�X���s���Ƃ��ēW�J����A���J���ҊK����M
�����A���Y�����ぁ�������ɂ݂����āA�������ɑË����A��̒��グ�����{�̋��e����͈͂ł����Ƃ�Ƃ����o�ϓ����ƁA���̂悤�Ȍo�ϓ����̎コ��⊮������̂Ƃ��ĊX���I���������Ƃ��ēW�J����A�������ĘJ���҂Ɗw�����w�s���x
�Ƃ��ĕ����ɊX����ŋ�������Ƃ����X�^�C�������݂��Ă����B�����Ċw���́A���̘J���ҊK���̎コ�ɑ��āA�X���s����O�ꉻ�����邱�Ƃɂ���ė������������炵�A�����Č��͂ɓ������悤�Ƃ����̂ł������B���������̂悤�ȓ����������ɓO�ꉻ���Ă݂Ă��A�X���s���Ɏ~�����͐^�̘J���ҊK���̎p����������̂ł͂Ȃ��B�ɂ��S�炸�A���̂悤�ȊX����̓O�ꂵ�������͘J���ҊK���Ɍ��͂̎��Ԃ��I�ł���A�o�N�����AM
�̔����`�����邱�Ƃ��ł��A�X�ɐ��Y�_�ł̓����Ɋҗ�����\����L���Ă����B�u���h���߂����Ă������̂́A���ɂ��̂悤�Ȍ`��M
�̔��W�ł������B�܂�s���I���������̒��ł̍ō��h�i���u���}�i��`���W���R�o����`�j�̂փQ��A���I�Ƀv�����^���A�[�g�̂փQ���j�[�Ɉڍs�����悤�Ƃ����̂ł������B����͐��ɉi�v�v���_�ł������v�i�w��m�xNo.5�咣�u��O�̓]���_�Ɖ�X�̉ۑ�v�j�B���������ꓙ�̉i�v�v���^��M
�͌܁�
�N��̎s���I���������Ɛ퓬�I�g����`�̑S�ʊJ�ԂƂ��Ă̈��ہ\�O�r�����ł̔s�k�ł����ďI�����A�g����`��ʂ́A���u���W���A�W�[��ʂ́A�s����`��ʂ̔s�ނɘA�Ȃ����̂ł������B���̔s�ނ��_�@�ɂ��āA�܁�
�N�㒆���ȍ~�i�s���͂��߂����Y������ƍ������ƐE���x�z�̋����͐��n���A���{�ɂ��J���҂̕��f�Əc�f�I�c�[�I�ȐE��̖��[�܂ł̂����낵���ו������ꂽ���ꖖ�[�̐���ʎY���A��������Ɋ�ƒ����E��ƕ�d�W�c�������W�߁A�����őa�O���ꂽ��Q�́u�E��v���v�U�����āu�K���I����v�Ɍ����J�x��z�����ʂƂ��āA�u�����I���S�w�v�̍�דI�i�o���͂��铙�X���x�̍����V�^�e����̌n�����X�ƍ��o����Ă����B�X�ɐV�H�ꌚ�݂��n��Z���̗��Q�W�f���A�Â��n��Љ�𐡒f���A�u�c����v�n��n�݂��s�Ȃ��A���������{�̎s���Љ�ւ̒��ڂ̎x�z�́A���ڌٗp����J���҂����ł͂Ȃ��A�L�Ăȏ��K�w�̒��Ɍ��݂̗��Q�Ə����̐����v��ɃL���ׂ����x�z�̈�o�����B
�@���̂悤�ȘJ���ҊK���̏c�[�I���f�x�z�Ǝs���Љ�̎��{�̒��ڎx�z�̐i�s�́A���]�����̑g�D�I��̉��Ǝ��{�ւ̋�����Ƃ��Ă̑S�J���A�Љ�}�\�쌛���S���{�̋��Ɩ��Ё\������c�̈�̉��ݗ��Ƃ��A�i�v�v���^�̕�̂ł���S�w�A�\���]�\�����ւ̎s���I�u���b�N�̉�̂�]�V�Ȃ����ꂽ�B
�@�ꌩ���{�̌��łȎx�z�̐����m�����ꂽ���̔@���������A������x�z�̗l���̒�����A�J���ҊK���\���K�������K�w�̐V���Ȗ����̗ݐς������I�Ɍ`������A����̓C���t���A�J���������������A��ꕔ���̉ߏ萶�Y�Ƃ��Č��݉����A�X�ɒ�����ƁA�_���̊�@���ĂыN�����A��N�l�E�ꎵ�̌o�ϓ����ɓ��������������Љ�\�o�ϐ����������W�J����n�߂��B
�@��X�̉i�v�v���^��M
�̎~�g�Ƃ������ӎ��́A�u���h�c�}�̘J��M �ւ̉���Ƃ��������Ŗ͍�����A�����w��M
�̎w���̎��H���̒��ŒNj�����Ă����B
�@�s���I�u���b�N�̉�̂͒��ړI�Ɋw��M �̐��I�@�\�̑r���Ƃ��̗��Ԃ��Ƃ��Ă̊w��M
�̃_�C�i�~�b�N�Ȕ��W��a�O�����Ă����B
�@������S���I�\�S�Љ�IM ����n��I�\���f�IM
�ւ̒�؏̂ɑ�O�̐����ӎ������U������A�H�������Ă���Ԍ���˂��āA���{�̎x�z�̊�]�ƑΊO�����\�͋����ɑΉ����ׂ���w�̒��ڎx�z����ɂ��Ă̍U���͊w����O��̐����������Ă��Ă���B
�@�ɂ��S�炸�A�������؏�˂��j���Ă̈��N�ȗ��̂��₩��"�V�����g"�̍V�܂肪�m�F�����B
�@���\�����Ɍ�����M
�̈��̍V�g�́A���؏�̌����ɑΉ�������Ȃ�����̑ΊO����̋}���Ȑi�W�ɂ���A����͈��ۈȍ~��������������̑�O�����W������̂Ɉ����x�����������B
�@
�@���������ڂ��Ȃ���Ȃ�ʂ̂́A�����鐭�����������܂��S��O�̂��̂ɂȂ�炸�A�����Ƒ�O�Ƃ̊Ԃɕ��f�����݂��邱�Ƃł���B
�@�����Č��������Ŗ��炩�ɂȂ����@���A�ꁛ�E��l�S���������[�ւ�M
�Ƃ��đS���I�ɓW�J����Ȃ���A���͓����̋ǖʓ˓��̓˔j���Ƃ��Ă̈��E�����{�ꓬ�����_�@�ƂȂ�A���ꂪ��O����i�����i�K�ֈ����グ�A���킹�Č�����`�j�~�̌��n��������O�̎Q���𔗂���̂��A����͕����I�ȗ����ݏo�����ɂƂǂ܂�A�S�̂Ƃ��Ă͖��S����ᔻ�I�ł����������B��X�͔ᔻ�I�ł��������Ƃ����Ƃ���Ɏ��グ�ĉ��{�ꓬ����ᔻ����C�͂���ɂȂ����i���̂Ȃ���E�������͂��̋ǖʂɂ����Ēf���Ƃ��Đ��i����˂�M
�̓˔j���͗v������Ȃ���������j�A���͂�����ᔻ�I�ȕ����܂Ō�������ŁA���̂��Ƃ�ʂ��Ď��͑j�~��M
��W�J�����邾���́A��X�̎�̓I�W�]���ǂ��ɂ����݂��Ȃ��������ƁA������M �͈��A���A��O�Ək���Đ��Y����A�����A���Ɠ���ǂ����Ƃɑ�O��M
���牓�������Ă������B���̓����̉ߒ��Ŋm�F����˂Ȃ�Ȃ��͈̂�т���M
�ɘA�����Ɣ��W�����r�����A����ΐ�p�̘A���I�O�ꐫ�̒��Ō��͂ɓ��ǂ��Ă����Ƃ���̐��Y�͂͑S�̂Ƃ��ĕs�݂ł���A�����Ƃ͓����̊�ǂ����ɑ�O���番�����A�����̏W���I�e�������U���������Ă��������Ƃł���B
�@���s�ł͓����Ƒ��Ⴕ��O�I������@�\�̎����I�ȕێ��̏�ɓW�J���ꂽ���̂ɁA�����s�Ƃ����n�����������āAM
�̔��W��ǂ����ɑ�O�Ɗ����ƂƂ̕��������o���A�I�����܂ꂽ�B
�@�ő���̐�p�̉s�p�I�ȓW�J�ɂ���Ċw����O�����W�A���킹�ĘJ��M
�ւ̉e����^����Ƃ�����p�������i�v�v���^�̎w������M
�̋ǖʂɂ����ĕK�v�ɂ��S�炸�L������r�����Ă��邱�Ƃ��͂�����ƕ�����Ă���B���̂��Ƃ̗��ʂɂ́A�ܘ_���\�@�����ȍ~���߂ĎЉ�}�\���]���n�b�X�����J���ҊK���̗������`�����ꂽ�Ƃ͂����A���ۈȍ~�̘J���ҊK���̌��͂̎x�z�̋��ł���邱�Ƃ��w�E����˂Ȃ�Ȃ��B
�@�������̂��Ƃ��m�F�����Ƃ���ŁA��������̕����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B"��쐫���_��������邩�ۂ�"���̕s�тȘ_����f�����āA�����������ĉ�X���m�F���Ȃ���Ȃ�ʂ̂́A��쐫�̗L�����͑r���������̂́A���̐��I�\�͂͑r�����Ă��炸�����O��I�ɒNj����邱�ƁA�X�ɂ��̂��Ƃɂ����"��"�����ݏo���Ȃ������̌���ΊX���������x�����O�̌������̎x�����l������Ƃ���̌����I����ł���B
�@���̂��Ƃ͒P�ɋZ�p�I�Ή��ɂ���Đ蔲��������̂ł͂Ȃ��A��X��M
�̎w�������i�v�v���^��M
�̎~�g�Ƃ��Ă̎v�z�I����̊m���ɂ���B
�@�����̏������̏��N�ɂ͂��̂悤�ȔF���̌��@�Ƃ������炭�鐭���������������x�����O�̎x���̂Ȃ��P���ȉi�v�v���^�̂����"�ł�"�̕\���Ƃ��ẮA�P�ɊX�����������`���⏬���������؈�_�˔j�S�ʓW�J�����͑��Ӗ����������悹�Ă��邱�Ƃ�t�����Ă������B
�@�����đ����ł̐V�����g���\������M
�͊w����O�̊��ӂ��痧���̂ڂ��Ă���Ƃ���̊w���ł�M
�ł���B
�@�{�N�ꌎ�̓����ł̃o�X��l�グ���Γ����ɎQ�����������s���ꁛ���l�ɋy��"��������M"�A�����Čc����w�̂قƂ�ǑS��O���������Ƃ���̎��Ɨ������A�����ĐÑ�ł̎������ɂ��S�炸�ꌩ���ׂɂ������闾�̐����w�̐������S��肪�w������X�g���C�L�ɂ܂Ŕ��W������A�̎����́A���N�ȗ��̑S���I�ɕ��f����ēW�J���ꑱ���Ă����w���̎Љ���������V���ȋǖʂ��悵�n�߂��Ƃ������Ƃł���B
�@���ꓙ�ɋ��ʂȂ��Ƃ͑�O�I�Ȑ��i��тшُ�Ȑ����͂������Ă��鎖���ł���B
�@���̂悤�Ȋw����O�̈�A��M
�͐[���ɘJ���ҊK���̘J�������\�l�������\����cut�ɋy�Ԑ������Infla
�ɂ����D�̓�d�̐����ւ̈����̊O�����Ƃ��Ă̊w���̐����̊�@����Ղɒu�����̂̒��ڂ̌_�@�́A��w�̍H�ꉻ�Ƃ�������ׂ����玑�{�����͕��������E���犯���ƓƐ莑�{�̖����ɂ�鎑�{�̊w�⌤���̒��ڂ̗��p�Ƃ����ʂ��Ă̊w����O�̑̐������ƓK�ȘJ���͂̐��Y��ړI�Ƃ���Ɛ莑�{�{���玑�{�i�����͕��������j�̍H��̐E���x�z�ƒ����}���ɕC�G���鏊�̊w���̎��{�A���Ƃ̒��ڂ̏����Ǝ��D�̐���ɑ��Ă̊w���̕s���̗ݐς�����s������Ǝ��D����ɑ��Ĕ������Ă���̂ł���B
�@�]���Ă����铬���͍���\���I�ɍĐ��Y����A�Љ�I���i��L������̂ł���A����Έ��܁��N��̋����@�i�l�j����O�@�i�ܘZ�j�\
�Ε]�i���\���j�\
��ǖ@�i�Z��j�Ɍ�����A���K�������̍V�g�̒��ŏ�����������@�Ƌ����{�@�̗��O�ɕ\�������A��w���x�̈��̐i�����ƓƎ����ɑ��Ă̍��ƌ��J�̊ە����I�Ȃ锽���I��������ɑ��錛�@���O��Βu����M
�ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȑ��i�̓����͌��\���N������n�܂�Z��N������S�ʉ�������w�̎��{�̒��ڎx�z�ƍ������\�E���x�z�Ƃ�������ׂ���w�̎x�z�̐��̕ω����N�������̂ł���A����Ύ��{�̐����I�U���ƌo�ϓI�U������̉����ēW�J����A����ւ̊w���̐����I�o�ϓI�Ή�����̉����đΉ����邪�̂ɁA�����ł̑Ό��͖��m�Ȏ��{�̑��݂��ӎ������Ă����̂ł���B���̂悤�ȓ����͐��ɎЉ�������Ƃ���������̂ł���B���̂悤�Ȏ��{�Ɗw���Ƃ̑Ή��W�̒��Ŋw���̈ӎ��͎��Ȃ̌��݁\�����ɘi���Ď��{��`�Љ�̂��̂̕]�����s�f�ɒ��ړI�ɖ₢��������B
���@�܁Z�N��̊w���̐��������A�o�ϓ����i�]�葶���Ȃ��������j�ւ̊ւ�荇���́A���{��`��O��I�Ȃ��̂Ƃ��ĔF�����A���̏�ɗ����Ď��{��`�̏����������̑��̂Ƃ��Ă̘J�����ɑ��A�u�����`�h�q�v������W�J�����B���̂��Ƃ͎��{��`�̕������ł̗]�T�Ǝs���Ƃ��Ă̐����s���������Ȃ�����S�̂Ƃ��ē������Ă������{��`�̐[���̒i�K�ł������B���J���҂̔���������ɓ����������g����`�I�J��M�̘g��u���Ă̌o�ϓ����\�s���Ƃ��Ă̐��������ł������B
�@����̂ɂ����J���ҊK���́A"��ƈӎ�"�Ɠ����������ӎ������݂��A���̈ӎ������z���邱�Ƃɂ���Ă������߂Ă��ꓙ�̎Љ�������͎����I�ȏ�����������邱�Ƃ��o����B���ꓙ�̓����̐��i�͘J���ҊK���̔��������\���グ�ɓ������Ɨގ����������A�J���ҊK���̏ꍇ���ꂪ��̖̂��`���̂ɍ������̃V���Ƃ��ĕЖʓI�Ɍo�ϓ����ɂ̂����Ă���A�K���W�̃u���W���A�I�����Ƃ��Ă̍��Ƃ̑����{�I���ꂩ��̏��K���̗}������ւ̓��������������ɑ����f����A�����グ�A�������ߒ�����̈ꌳ�I�ȓ����̔��W�Ƃ��Ă̐��������͑�O�I�����Ƃ��Ēזłɋ߂����w��M
�̏ꍇ�͂��܂��������hege�D�̋��͂��̂Ɏ��{�̒��ړI�Ȉ�̐��������������I�\�o�ϓI�U���ɑ��Ă�����������ē����͗ʂ�L���A�X�Ɋw�������o�ϓ����̓����I�Ȕ��鐫�𐭎������ɉ����锽�鐫�Ɠ��ꂵ�đ�O�ɔF�������邱�Ƃ��o����B
�@��������N���Ă���Ƃ���̉i�v�v���^�̎w�����́A�ے�̔ے�Ƃ��Ă̎~�g�̖��́A���ݓI�ɂ͂��ꓙ�̎Љ�������I�Ȋw�������Ɠ��ؑj�~�A�x�g�i���푈���̐��������Ƃ̓��ꂵ���w�����Ƒ�O�̒��ł̓��ݓI�ɓ��ꂳ�ꂽ����̐����ӎ��̌`�������A���̂��Ƃ́A��쐫���_�̗L�����̑r���̒��ł����I�Ȑ��������̓W�J�ߒ��ł�����̑�O�̒��ł̋��ƕ������������A�S�̂Ƃ��Ă̐����I�W��̉\�����J�����Ă���̂ł���B
�@�ܘ_�A���݂ɉ��āA���ꓙ���������ƎЉ�������������I�Ɍ������A������������Љ�������ցA�Љ���������琭�������ɔ��W�Z�����铙�Ɣn���������Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��B��������̑�O�̒��ł̐����I�փQ���j�[�̊m���͎Љ���������ɂ��Ă��A�������������̏ۂ��Ă���蓾���A���҂̓Ǝ��I�ȓO��I�W�J�Ɨ��҂ɑ��݂��锽�鐫�����҂̓Ǝ��I�O�ꐫ���ɂ��Ă͌`�����꓾�Ȃ��̂ł���
�@���̖��́A�{���I�Ɋv���I�V�g���ɉ�����O�����V��[�U�����������Ƃ���̌���v���́u���ǂƊv���v�̓��ꂵ���w�����̊m���̓��e���N���Ă���B
�@���Ă��̖��ɑ��Ă̓��ꂵ�������I�\���̎��݂ɂ��Ă͍Ō�ɏq�ׂ邱�Ƃɂ��āA���ꓙ�̐��������A�Љ�������̍���ɉ�����A���Ƃ��̓����I�Ȕ��鐫�̑��݂�����T�����邱�Ƃɂ���Ă݂Ă݂悤�B
�@(
2
�j��ɓ���O�ɓ����Ⓦ���̐V�������h�̓��؈�_�˔j�S�ʓW�J�����ɉ������]���̊�{�I�߂���t�����Ă������B
�@�u�m���ɓS�z�E���D�E�Ζ��E���@�E�Z�����g�E�d�@���قƂ�ǂ����镪��ʼnߏ萶�Y���������邵���Ȃ�A���낻�댸�Y�̐��ւ̐芷���������n�߂Ă���̂�������v�i�o�σZ�~�i�u�j�]�ɋ߂Â����{���{��`�v����́j���̎w�E����͎̂����ł���B����͑����̓��{���{��`�̍s�l�肪�A�������̂��Ƃ������Ă��ē����̔@���ߏ萶�Y���Q�_���璼���I�ɓW�J���u���{��`���E�̐��̕����Ɛ��ނ̐[���v�i�w�O�q�x3
�����j�Ɍ��_���鎖�Ԃł͂Ȃ��B�Ԍ`�Y�ƕ���ɂ݂���ݔ��ߏ�\�ɑ����̖��͎����㑶�݂��A�X�ɂ��Ƃ��Αϋv����ޕ���̌ܔ��N�Ȍ㓊�����O������𑱂��Ă������̂��Z�l�N�ɂ͋�E�ꁓ�ɂȂ��Ă���B���������ꓙ�͑����{����݂�Όi�C��^�Y�ƂƂ��Ă͎Ηz���������݂̏����̑Ώۂł����Ȃ��B
�@���{���ƓƐ莑�{��`�͂��̂Ȃ������I�ȘJ���ҊK���̕��f�I�c�[�I�x�z�Ƒ��]�����̑S�J�����������Ё\������c���琬���邱�Ƃɂ���ĉ������Ȃ��玟�̌i�C�哱�Y�Ƃ��J�����邱�Ƃɏ��o������B���{�����o�όv��̎傽��Ӑ}�͏d���w�H�ƕ���y�яZ��ݕ�����o�ϔ��W�̎哱����Ƃ��āA�̐������X�Ƃ��Đ��������߂��A����u�Љ�J���v�͂����������̃u���W���A�I���W�̐��Ǘ��_�ł���B�����o�όv��͒P�ɍ��x�����H���̌p���ɂ�钆���˔j�i�͐Β��j�����ł���̂ł͂Ȃ��ɁA���́u�Ђ��݁v�������Ƃ̎��ȐӔC�ɂ���ĉ����Ԃ��Ȃ���V�o�ϑ̐����˂炤�Ƃ���̂��̂ł���B���Ԏ��{�ɑ��ẮA���Y�ߏ�ƃV�F���[�����ɑ��āA���ł��A�Д����J�������ĂɁA���c�A���ƒc�̊g�[�A�s���@�\�̑�K�͉��ƂȂ��ŗ��q�⋋���x�̊m�������ɂȂ������I�Ɍ��ĂȂ������͂����Ă���B
�@�ȏ�ł����Ă��Ă��S�ʓI�ߏ萶�Y���ΊO�c���i�����{�A�o�j�A�Љ�I��@�̑S�ʉ���
���؈�_�˔j�S�ʓW�J�����̕]���̉߂��͖��炩�ł���B
�@��X�͏t�ȍ~�S�͂������ē��ؓ����Ɏ��g�ނ��A������Ƃ����ē����̏��N�̔@�����ؓ����ɂ���OM
�̔����I�W�J�����҂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��X�͂�����s�p�I�ړI�ӎ��I�ȓ�����W�J����ߒ��œ��ؓ����A�����������̐ςݏグ����A���{���{��`�̖c���Ɣ��v���̏�����̐i�s�Ə������̏W��_�Ƃ��Ă̑�O�����ۑj�~�̐����ӎ��̌`�����߂����ł��낤�B��X����N���w�E������̍���̓����_�Ƃ��āu���ې����o�Ϗ��������ɒ��ڔ��f���A�X�ɍ����̐��������\�o�ϓ������������Ĕ��W���鎞��ɓ��{���{��`���˓������v�Ƃ�����̔c���̍��ꐫ�͔ے肷�ׂ����Ȃ��B���������̂��Ƃ����݂̋ǖʂɉ��ċ@�B�I���ړI�ɓK�p���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�p�����ƕĒ邩��̓��؉�k���i�̗v���A�����̓��{�z�u����A�̓��{�u���W���A�W�[�̑ΊO����́A�[���ɉߏ萶�Y�\�ݔ����C�O�s��l���̗v���������Ȃ���A���ړI�ɂ͂׃g�i���̗�������Ƃ����ɓ����瓌��A�W�A�ɋy�Ԗ�����������̐V���ȗ����ɑ��Ă̍��ۃu���W���A�W�[�̔��v�������̋����H������ĂыN������Ă�����̂ł���B
�@�׃g�i���ł̃A�����J���x���ɂ����Ƃ���̔��v���A���R�̌�ނ͌��݂̏�ł́A������"�����|��"�I�Ȗ����������}���Ȋv�����̕�����SEATO
�����̊�@�����������߂邪�̂ɁA�׃g�i���푈���Ƃ����푈�́\�\���ݑ���N�����̗l����тт��邪�\�����I�Ȑ푈�̐��i���������̂ł���B���݂̋ǖʂɉ��ĉs���ΊO������Ղ��������Ă���v�������{���{��`�̓��I�������̒��ړI�S��I�����Ƃ��Ă̖c�����Ɠ���A�W�A����ɓ��ւ̔��v�����̈�̐��ɂ���̂ł͂Ȃ��A�ނ����҂ɒ��ړI�v����u���Ă���Ƃ������Ƃ͍���W�J�����ΊO������߂��鏔�����̐��i�����肷��B
�@��i���Ɏ���u�������ۓI�����ւ̓���̑Ή��ɑ��ď��K���\���K�w�͔��R�Ƃ����Љ�s���������Ȃ���������I�ӎ��ɂ܂ōV�܂��Ȃ��A�������ۏ��������֔��f����ꍇ�����x���f����Ւf����Ă���A���߂č�����ɓ��e����\�]���đ�O�̓��ݓI���W���������Ȃ�������ꂪ�e�Ղ�M������Ȃ����ƁA����̂ɋ}�i�����������I��O��c���Ă��S��O�������Ȃ��A�ɂ߂ċǓx�ȖړI�ӎ��I�����i��ʂɉ��Ĝ��ӓI�ȑ��ʂ����j�Ƃ��ēW�J���ꂴ��Ȃ��v���́A��i�鍑��`�̎s��ĕ҂̐V���Ȓi�K�ł̊�@�̓������̉��ł̓��{���ƓƐ莑�{��`�̖����̐��n�̒i�K�Ǝx�z�̗l���ɋN��������̂ł���B
�@���Z�l�N�x�̏�͌����̒��ɓW�J���ꂽ�B���E���{��`�̖����̐[���Ɛ����h���ۋ��Y��`�����̖����̌��������̒��S�ł������B���̓�ɂ�M
�͊e�X�Ǝ��ɓW�J����Ȃ�����A�����Ő[���֘A���Ă���B�������ۋ��Y��`M
�����̕���́A���ɓI�ɂ͂܂���������Ă��Ȃ����E�v���ɂ����̂ł���A���ɍ����ł͐��E���{��`�̊֘A�œW�J����Ă���B�����Ă��̐��E���{��`�́A���ܔ��N���R���i�K�ւ̓˓��Ƌ��ɁA���̎��{��M
���~�ς��Ă������������݉�������B���ےʉݐ��x�̊�@�ɂ��̖����͏W��Ă���B�h����@����n�܂�A�|���h��@�Ɏ��鍑�ےʉݐ��x�̊�@�́A���ǂ͐�㐢�E���{��`�̔��W�̌��_�ł���B
�@�A�����J�ɑ���EEC�����A���{�̗҉�A�����ł̐��E���{��`�̕s�ϓ����W�͗v��A���̐��Y�́������͔��W�ɂ��A�A�����J����̋��̗��o�A�h����@�����݉������B���ےʉ݂̕���Ƃ͉����B����̓u���b�N�o�ς��Ӗ����A���ۖf�Ղ̌��ϋ@�\�̔j����Ӗ�����B�N���I�ȐA���n����Ƃ��̏�ł̃u���b�N�o�ς��͂��ɐ��Y�̔��W���x���A�A���n�s��̑��D�������Ē鍑��`�푈�����̓����ł���B�����č��یo�ς͍L�搫�ɂ����i�A�����J�������āj�C���t���[�V������K�R�����������s������߂�����ɓ����B�K����̌����͒鍑��`�푈�ɑ��铬���ƂƂ��ɁA�v�������ɔ��W����B
�@�ȏ�̔@�����j�I�Ș_���������ےʉݐ��x�̕���ɑ��A�����̕���̔��W�i���Y�͂̔��W�j�Ƃ����킹�āA���ۃu���W���A�W�[�͏��i�����Ƌ��ɋ��͂����x�z�̎�i�Ƃ�����Ȃ��B���ۓI�ȍ��ƓƐ莑�{��`�̋@�\�A���ꂪIMF
�ɏW��A�ʉݐ��x�̊�@�������������Ƃ��Ă���B�ɂ��S�炸�|���h�~�ς�EEC�����ɂƂ�A�����ւ̃C�M���X�̋����͋����������Ƃ����ẮA���̋��͂́A���̖{���ɂ͂�����ɂɏ[�������̂ƂȂ炴��Ȃ��B���ےʉݐ��x�̊�@�́A�͂��������������������Ă���B
�@���̂悤�Ȑ��E���{��`�̋�ɂɖ����������̈��������́A�e���̍��ƓƐ莑�{��`�̊�{�I�����ɂȂ��Ă���B���������ł͂Ȃ������I�Ȗ����̌��݉��ɂ��K���I���˂���_�ɏW�邱�Ƃ����点�鍑���������Ƃ��Ă���B�ɂ��S�炸���E���{��`�̎ア�������I���ێ��x�̐Ԏ��y�уC���t���ɔY�ތ�i���ɂƂ��ẮA���̂悤�Ȗ����̈��������͕s�\�ł���B�����u���W���A�W�[�ɂ�閯�����Ƃ̎������e�ՂɈ��肳�ꂸ�����̒��ɂ����i�����́A�鍑��`�����Ԃ̎x�z�̈��͌̂Ɂu��k���v�Ƃ�����@�����E�I�Ȓ�ӂƂ��Ă̖�������A���E�I�ȊK�������̌����̒��ɂ���B�����Č��i�K�ɂ�����K�������́A���ꓙ��i�����ƍ��ۓƐ�̂̂Ȃ������I����̂����炷�����̏W���I�Ȕ����_�A�e�������ɂ������i�����ƂɌ��݉����Ă���B�A�����J�̍��l�̓����A����A�W�A�̓����A�t�����X�_���̓����A���{�̒�����ƁA�����͐ΒY�Y�ƘJ���҂̓����Ȃǂ�����O���ɂ���B
�@�ȏ�̔@�����E�I�Ȏ��{��`�̎ア�ɉ����閵���̌��݉��ƊK�������̔��W�͌��݂܂��܂��L�������B�Ⴆ�Γ��{�̗���Ƃ��Ă��A���݂̒�����Ƃ̓|�Y�A�_�Ɩ��̐[�����́A���łɎЉ�s���Ƃ��Ď�X�ɐ����ߒ��ɔ��f���Ă���i�����}�̌����Ȃǁj�B�����A��X�����݂̊K�������̒��������ʂ����_�́A�P�Ɉȏ�̔@���ア�ɂ݂̂���̂ł͂Ȃ��B����͊������R���i�K�ւ̎��{��`�̓˓��̂����炵���A���E�I�ȊK�������̍V�g�i�K�������o�ϓI��@�Ƃ͌������Ă��Ȃ������Ƃ���́A�����t�����X�̃A���W�F���A�����A���h�S�[�������A�C�^���A�̔��l�I�t�@�V�Y�������A�x���M�[�̃R���S���ƑS���I�[�l�X�g�A���{�̈��ۓ����Ȃǁj�ɕC�G����悤�Ȑ��E�I�ȐV���ȊK�������̍V�g�ɂ�������B
�@�����̐��E���{��`�����ʂ��Ċт������́A�N���[�s���O�E�C���t���[�V�����ƌĂ��A�Ȃ������I�ȃC���t�����^����J���Ґl���̈��������������ʂ��̂ɂȂ��Ă��邱�ƁA�������ۋ����ւ̑Ή��������炵�Ă���J�������ɂ�鈳���̑���A�X�ɕ����I�Ɍ��݉�������ߏ萶�Y�ł���B���̂悤�Ȋ�{�I�ȏ������Ƒ����ł̎ア�̖����Ƃ���������Ƃ����ƓƐ莑�{��`�̂Ȃ������I����͏d��ȍ���Ɋׂ邾�낤�B�����閵���ւƈ�����K���������V�g����Ƃ������Ƃ́A���ꂪ���ےʉݑ̐��ɒ������鎞�A�S���E�I�ɔg�y���閵���̌��݉��Ƃ����W�J����������̂ł���B
�@�Ȃ�������{�I�ȏ������Ǝア�Ƃ��Ă̌�i������M
�i��i���A�������Ƃ킸�j
�����������A���ےʉ݊�@�ɒ���������W�]�́A���݂̓��{�K�������ɉ��Ĕ@���Ȃ���e�Ƃ��ĔF������˂Ȃ�ʂ̂��B
�@�i3�j���ƓƐ莑�{��`�̊�{�����ƌ�i�����炭��ア�̖����Ƃ̌����̐[���́A���ےʉ݊�@�������������ۓI�ȊK�������̓W�]���J���\����L���Ă��邱�Ƃ��w�E�������A�ɂ��S�炸���݉�������ߏ萶�Y�����ꓙ�������ɑ��铬���́A�܂������I�ɂ��������Ă��Ă��Ȃ��B�ۂ���݂̂ł͂Ȃ��A�Ɛ�u���W���A�W�[�̎x�z�́A���̕����I�ȓ����ɑ��đS�ʓI�ȘJ���g���̑̐������A�������݂̐���𐄂��i�߂Ă����̂ł���B�����Ƃɑ��鋐��g���̑Ή��̒��ŁA�I���Ȏ��{�ٌ�_�I�ȘJ���g���������琬����Ă����B�V���ȓ����̒S����́A���ꓙ�����I�����Ƃ̓�����ʂ��Ă̂ݓo�ꂵ�悤�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�����I�ȁA���ƓƐ莑�{��`�̎x�z�̋��ł��́A�����̖��������ۓI�ȕ���ɂ����Ă̂��݉������Ă���B���{�ɂ����鍑���Ɛ�̎x�z�̐������̗�O�ł͂Ȃ��B
�@���a�O���N��̐ݔ������𒆎��Ƃ�����{�o�ς̍��x�����́A�����ɖ��ԑ��Ƃ̘J���Ǘ��i�ߑ㉻�j�̊m���ł���A�J���ߒ��ɉ�����E����ʂ��Ă̎��{�x�z�̋����ł������B���̓��I�̐��������Ă��Ă͂��߂ċΖ��̓��㐧�A�t����]�̍��x�����͉\�ł������B���{�̓Ɛ�u���W���A�W�[�����ۓ����̍V�g���A�����w�����̖��w���ɏ������Ȃ������A����ɏ���������f�����̂��A���̂悤�Ȗ��ԓƐ��Ƒ̂ɂ�����x�z�i�O�r�̌Ǘ����̐����j�ƌ�����Ƒ́A�J���g���ւ̍��ƌ��͂ɂ��e���i�X�g���֎~�j�ł������B������������c���ւ̓]����������ʂ��ĂȂ��Ƃ��A���������낵�����ƓƐ莑�{��`�̉����́i�����́j���ւ������{�Ɛ�u���W���A�W�[���A�͂₭�����������������������ւ̓]���������n�߂��B�������A���n�r���̏����̉��ō����s�����ΏۂƂ���o�ϐ����ɐ������A�S�j�̐��Y���E��O�ʂɂ܂œ��B�������{���ƓƐ莑�{��`�͊J���o�ϑ̐��̖��̉��ɂ��̊�����ɉߏ萶�Y��������B
�@����͐��Y�̊g��ɂ��ٗp�̑������x���Ă��������s������āA�ϋv������̉ߏ萶�Y���ɉ�����z�|���v���ɑ��Ă̓S�|���Y�̉ߏ艻�Ȃǂ̊֘A��ʂ��Č����Ă���B
�@���������Y�̑���ƍ��ێ��x�Ƃ̏h���I�Ȉ��z�Ƃ����܂��āA�����Ăѓ��{���{��`��"�s��"������j�I�ɉ�ڂ���������Ȃ��B����A�W�A�����͓��{�鍑��`�̗v�ł��������Ƃ��B
�@�ȏ�̔@������܂݂Ȃ�����A���₩�ȍD���̒��ɂ��鐢�E���{��`�s��̊g��Ƃ��������́A�Z�l�N�̓��{�o�ς̍�����A�����J�ւ̗A�o�����ɂ��蔲���Ă����B�����Ă��̗A�o�̂̂тɂ��A�ߏ萶�Y���I�Ȃ��̂Ƃ��Ă̂��݉�������ɂƂǂ߂邱�Ƃɐ������Ă���B
�@�ɂ��S�炸�A���N�x�t���̃G�l���M�[����I�Ɍ`�������߂����{�Ɛ莑�{��`���̍��ۓI�ȃN���[�s���O�E�C���t���[�V�����̌����Ƃ��ẮA�����̏���ҕ����l�グ�̔g�́A���x�����̏�����ʂւ̌����A�����͘J�������ʂւ̌����ɑ���J���҂̕s����傫�����N���Ă���B�����Ă�����Ƃ�܂����̂Ƃ��Ē�����Ƃ̋L�^�I�ȓ|�Y��_���̍s���Â܂�i�ĉ������グ�̂͂˂�����j������B
�@�ȏ������Ȃ�A�l�E�ꎵ�����A�����V�[�h���S�������`�j�~�����͓��{�Ɛ莑�{��`�̖�����[����������n�_������������邱�ƁA���������̗����̓������������Ȃ����ɂ����A�Ɛ�̎x�z�̗v�����邱�Ƃ����炩�ł���B
�@(4�j�l�E�ꎵ�����̓����́A����ɂ����Ă��̓����̃G�l���M�[�����ƓƐ莑�{��`�̍��Ǝ��D�ɑ��鋐��Ȓ�R�A�����h�q�̈ӎ�����ł����̂ł��邱�ƁA�����đ����ł͂���ɂ��S�炸�����̔ƍߓI�ȗ���ɏ������Ȃ���A�������ˑR�Ƃ��ē����̂��肠������{�X���̎�i�Ƃ��Ĉ��E���Ă��鏊�ɂ���B�����Ă��̖����w���Ƒ�O�����V�g�Ƃ̖����͍��⌰�݉������鏊����A���{�ƊK���͍����̏�̒��S�ɂ����ē�����c��{���Ɍ����邪���ۓI�Ȏ��{�̋����ߒ��ɂ������ƍ����Ȃǂ�ʂ��A�s��x�z���ێ��������Ȃ��������������̒��S�ɂ����悤�Ƃ��Ă���B
�@�����Đ������݉��̈������Ȃ������I�ɕ����I�ɓ]���������I�Ȏx�z��ۂ��A�l�X�Ȏs�ꐭ���W�J���悤�Ƃ��Ă���̂ł���B���̖��Ɋւ��Ắi2�j�̏���͂̍��ŏq�ׂ��Ƃ���̌܁��N��������̎哱�Y�ƂƂ��Ă̓S�|�E�@�B�E���D�E�@�ۓ��ɂ�鐬���ƌܘZ�\���N���̉ߏ萶�Y���A��������w���@�A�d�@�A�����ԁA�Ζ����Ɏ哱�Y�Ƃ�芷���ĘZ���N�㍂�x���������o�����A�X�ɂ��ꂪ�ߏ萶�Y�Ɋׂ錻���_�ɂ����Č������ƕ���i���ɏZ��j�����đ���ڂ̎哱�Y�ƕ���̌��Ł\���Ƃ̒��ړI�Z������A�������s��̈�w�����ȊJ�ɂ���Ȃ�������ɂ��āA���Ē������ƁA�V���Ȕ��W�̕����A�r�c���t��荲�����t�ւ̌p���͍����I�ɂ͌o�c�A���͂��߂āA��������ɂ��Č��y���邪�@���A�����͍��ےʉ݂̊�@�Ƃ������āA�����̉ߏ萶�Y�̒��̑傫�ȕs�������Ɛ�u���W���A�W�[�̗v���ɂ��݂��邪�@����̓]�����Ӗ����邱�Ƃ͊m���ł���B
�@�܂����ۖʂł��ޓ��ɂƂ��Ē����̊j�����A�C���h�l�V�A�̊j�����錾�A�x�g�i���̗������A����A�W�A�̗����́A�K����������A�W�A�ւ̐i�o�ւ̓r���e�ՂłȂ����Ƃ������Ă���B
�@�Z�l�N���������Z�ܔN�̏t���ւ̓r�͍��ƌ��͂̒e���������Ă��Ă������x�z����s���ʌ��J���J���҂̓����A���ԉߏ萶�Y����E������ƘJ���҂̐퓬���ƁA������Ղ͒~�ς���Ă����B
�@���݂̑ΊO�c���������̊�͊m�F�������@���A���ړI�ɂ͓���A�W�A�̗������@���ɂ������v���A���̐��i�Ƃ��č��킹�ăA�����J�̈��̌�ނ̒��ŁA�����ʂ��ē���̐헪�I�ȈӖ��ł̐����I�R���Ihege.�̓���A�W�A�ւ̊m����ڂ������̂ł���B���������ۓI�Ȏ��{�̖��̉��ɂ����߂����i�����̐V�x�z�i�s�ꑈ�D�j�A��i���Ԃ̒�J�����哑���͂������傫�Ȓ�R���ĂԂ��낤�B
�@�������āi3�j���Ŋm�F�����Ƃ���̊�{�����ƌ�i�I�����Ƃ̌��������߂�ׂ��K�������̊�{�I�Ȑ��i�y�їv�́A�鍑��`�̑ΊO����ɑ��铬���ƍ����ɂ�����K�������̌����ɂ�����˂Ȃ�Ȃ��B�ɂ��S�炸���{���ƓƐ莑�{��`�̐������閵���Ƃ��̖����̂Ȃ������I�����̐��ݏo���V���Ȗ����̗ݐςƂ��Ă̐l���̖�������R�̉�����X�ɂ����Đ��ݗ����A�����I�Ɍ��݉����V���ȎЉ�������̔g���`�����Ȃ�������̓������A�ΊO����ւ̐��������Ɛ[���ɒu���Đ[���������Ȃ�����A���ݓI�ɂ͏�ɕ������A�����ɂ����Ɛ�̎x�z�̗v���u����Ă���v���́A���ɓ��{���ƓƐ莑�{��`�̂Ȃ������I�����I���������ޓ��̎x�z�͂̋��ł��Ƒ��܂��Đ������A�S�̂Ƃ��Ă�����Љ�J���^�̎哱�Y�Ƃ̐芷���Ƒ���ڂ̐헪�Y�Ƃ̐V���ȃe�R���ꂪ�s�\���Ƃ͌������������邱�ƁB���Ɋ����w�����̑̐������̐i�s�̒��ŘJ���҂��̑����K���A���K�w���퓬���������Ȃ�������{�̉��ɏ�������B�t���ɂ���Ă���A��̖̂����n�ɂ���B
�@���Ă��̌X�������ݓI�ɓ˂��j����\���́A���ɍ��ےʉݑ̐��̊�@�A���ɐ�i���J���ҊK���̍V�g�����Ƃ��ꍑ�I�K�͂ł��W�J����邱�Ƃ�ʂ��Ă̐V���ȑS���E�I��M
�̍V�g�A���Ƃɕč��̓S�|�X�g���_�@�ɂ��Ĉꉞ�͗\�z�����B��O�ɓ��{�u���W���A�W�[�̓]���Ƃ��ẴC���t������f�t������ւ̓]���ł���i�܂��l�����Ȃ��j�B�Ƃ���Ȃ�A����ΐ����T�O���̏q�ׂ鏊��"�Ǝ��̗̈�"�̑��݂Ƃ͈ȏ��_�ɋN�����鏊�̍��ƓƐ莑�{��`�́i�x�z�̋��ł����܂߂Ắj���ł��Ƃ���̍��ۓI�����������I�ɂ͎Љ�������Ɛ����������[���ɂ����Č�������v���������Ȃ�����A���{���ƓƐ莑�{��`�̐��E��Ƃ̈ʑ�����d��I�ł���Ƃ������Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ���̎�v�ȗv���ł��邾�낤�B�������̂悤�ȍ��ƓƐ莑�{��`�̖����̂Ȃ������I���������Ɛ��������ƌo�ϓ����̕����ɂ��x�z�̕���́A���̂��Ǝ��̂��V���ȍ��x�ɂ��Đ[���������`�������ɂ͂��Ȃ��B����͖����ɏ����̌��@�\���ۓ����̐[���ƍL�����\�����Ă����̂ł���B���Ă��̂��Ƃ��m�F���āA�Ăѐ����������Љ�������̓���Ə����ɂ����錋���̕����Ƃ��̎w�����Ɉڂ낤�B(5)���ێO�r�ȍ~�̑S�����̕���̉��ɂ����Ă͐퓬�I�ȓ����͎O�r�����^�Ƃ��Ă̂݉\�ł������B����͊w��M
�ɋ��s�{�w�A�̐퓬�I�Ƒ��̐���S�������铬���ł��������A�������̊�ƍ����̒��ł̓Ƒ��̐��𒆐S�ɂ���S�Y�Ɠ��ꓬ�����u������O�H���D�J�g�Ќ��̓����̂���ł������B�����Ƒ��̐��ւ̍��ƌ��́����{�̏W���U���ŎO�r�ȍ~�̓����́A��ɑS���I���ꓬ���ւ̔��W�Ƃ����ۑ��v������Ă����B�J��M
�A�w��M
�̑�O�����Ƃ��Ă̑S�����͑S���I�Ȑ����w���̊m���A�S���I�Ȑ����g�D�̊m�������킹�ėv������B���̉ۑ�͍����̘J���҂��A�g�����Ƃɑ̐���������A�����͊w�������Y�w�����̒��ő̐�����������邱�Ƃ��v���A����I�ɏd�v�ł���B
�@��X
�͂�����ɂ����đ����K�����������Ȃ���A�����ɑS���ɎU�݂���퓬�I�v���I���������W���邱�Ƃɂ���O�������`�����邱�Ƃ�ڕW�ɁA�w��M
�ɂ����Ă͑�O���̎Њw���̌����Ɣ��铝�����S�w�A�̍Č��ɂ�鎩�炪��O�̒������������Ă������Ƃ����݂��B�������A���͂�����H����s�f�̌��݂̍���ȑ�O�̏̒��Ŏ������Ă����Ƃ���̎w�����ł��邵�A�X�̑�O�ɂ����锽��I�Ȏ��ԓI�Ȑ���ł������B
�@�����ĉ�X�����ݖ��ɂ��Ă���Ƃ���̂���́A�P�Ɋ���̋�_�Ƃ��Ẳi�v�v���^M
�̎w�����̍����̖��ł͂Ȃ��A�ɂ߂Č����̗v�����瓱�������Ƃ���́A�����A���ɐ��������̌���I�Ȏ��͓I�ȓ������v�������ɂ��S�炸�AM
�̏�����̒�����ꂽ�Ƃ͂����A�S�̂Ƃ��Ă̊K�������̒�،̂ɁA���̐�i�I�ȓ��������W�����������t�ɑ�O�Ƃ̈��̕����������炷�A���ɁA�w����O�ɂ�����̐��������i�݁A���{�E���Ƃ̑�w�̒��ڎx�z���A�E���Ƃ�������ׂ����{�̊w����O�̏��������ɔ����k���Ȍ^�Ő[�����A�w��M
�̒����Ƃ�����ׂ��w����O�̐����Ɏ��I�ȕω��������炵���邱�ƁA��O�ɁA������̑O�i�I�ȗv�f�Ƃ��Ċm�F����鏊�́A���݂̎Љ���̊�@�����ɒu���ẮA��w�̎��{�̎x�z�̋����Ǝ��D�ւ̖����̗ݐςƂ��Ĉ�̉��������玑�{�ƓƐ莑�{�A���ƌ��͂ɑ��đ�O�I�Ȕ��t���J�n����n�߂����Ƃł���B���Q���ł͂��邪����������������X���������Ă��Ă��邱�ƁA���ꓙ�^����ꂽ�����̒��Ō��ݓI�Ȗ��Ƃ��ē��ؓ����A�w���Љ���������i���݂ł͑S�����҂͂��ꎩ�̓Ɨ����Ă���A�ʓI�ɐ����i�߂˂Ȃ�Ȃ����j�@���ɓ��ꂵ�Ă������A���̖��͋Z�p�I�ɑΏ�����Ȃ�����ꂩ����Ɉ�ʉ�����Ă��܂����A���̂��Ƃ͎��Ƃ��č���A���ꓙ�Ɠ��l�̎��Ƃ��Ă̐��������ƎЉ�������Ƃ̓��ꂵ���w�����ɂ��邪�A��������Ƃ��Ẳi�v�v���^M
�̎v�z���̎~�g�ł���B
�@���čēx�ڂ����w�������̐��i���݂Ă݂悤�B����͊�{�I�Ɍ܁��N��ɓW�J����Z��N��ǖ@�Ɍ�������������������ɑ��Ă̖����`���O�̔����Ƃ��ẮA���������̎��Ԑ��A����͌l�̓����ɑ��݂��錶�z�������ƊK�����̑Η��R�����Ɍ��������A���̂��Ƃ͍��Ƃ̌��z���@���A���Ƃ̊K���Η��̔�a�𐫂̎Y���Ƃ��āA����̂ɂ�����}���҂ɂƂ��ĊO�݉������a���ȃu���W���A�W�[�̎x�z�̖\�͐���{���Ƃ����Y���ł��邱�Ƃ̔F���ւ̖G��Ƃ��āA�����Ă��̖G��͌l�̎Љ�W�̑��̂ւ̔F���Ɏ��炵�߁A���̍���͎��Ȃ̉���Y�W�̑������L���Y���̔p�₩�ۂ��ɔ���Ƃ���̖{���������Ă��邪�\���̎��Ԑ����s���Ƃ��Ă̍��Ƃ̌��z�������̒��ɓ��ʉ����ꂽ��ł̋^���I�ȁA�����u���W���A�Љ��O��ɂ��ẮA����̂Ɍ��@�I�ȉ��l�ړx�������āA�u���W���A�W�[�̉��l�ւ̔j��ɑ��Ă̒D�ғI�����Ƃ��Ă̎s���I�����ł��������̂��A�c�́E�Љ�ْ̋��W�̐V���Ȏ��ւ̓]���Ƃ��̊O�����Ƃ��Ă̎��{�ւ̕s�f�̒��ړI�w�⌤���̗����Nj��ւ̌������Ƃ��Ă̂ݗv�������Ƃ��A�����Ő�������Ƃ���̊w����O�͎��{����a�O����A�ˑ��Ɣ��������I�a�O�ӎ��A�����������Y�W�Ɋ����J���҂̑a�O�Ɠ����������������̂��`�������B����͖����̐����̓W�]�������ړI�ɓ���Ă��邪�̂Ɏ��{�ւ̊w���̈ːS���������B���̂��Ǝ��g�͐����̎��Ԑ���L���Ă��邪�̂ɂ��̑a�O�̔����͖{���I�ɂ͎��{��˂������āA���̐����I�Љ�I���͂Ƃ��Ă̍��Ƃւ̔ᔻ�ւƓ˂��i�ނ��̂ł���B
�@�����钊�ې��̌��ۂ͋�����̗�����E���������ւ̋�������������E���������̐�����x������Ƃ���̋����w�̔y�o�ƍ��ƁE�Ɛ�̍����I�������Ă̌����\�[�~�̓W�J�Ɗw����O�̂���ւ̌��ʂ�ʂ��Ă̋����\�Ɛ莑�{�̊w���̖��[�ł̏W��A�����ꓙ�̎x�z�̍�����ʂ��Ă̊w�����c�̂̎������̑r���ƕώ��ɂ���w�s���Љ�̍��Ǝ��{�̒��ړI�x�z�Ƒ�w�̋^���H�ꉻ�ƍ������̐i�W�Ƃ��Č����Ă��邪�A���ꓙ�̔��t�͍��Ƃ̕��g�I�@�\�Ƃ��Ă̎Љ�ƁA���{�̑�w�ւ̎Љ�I���͂ւ̑Ό��ƈ��̐����ӎ��͌`���������̂́A���܂����Ƃ̐����I���͂ւ̓����ɐ����������W�J����Ȃ�����A����͌���I�ɕs�\���ł���A���������݂͂̂ւ̑Ό��́A�w����O�̒����ł̎x�z�������Ă��邪�̂ɕ����I�퓬�I�����̌��W�Ɍ��肳��Ă��܂��B������O���̐V���ȋْ��W�̎��A������[�j���́u�v���I�V�g�v�̓��ݐ��̌`���́A���̂��Ƃ͎��{�̐E��x�z�����Ƃ̎x�z���̓����I�����ɂ��E��̖��[����̒�R�̓����I�����Ɋ�Â����������ւ̔��W�̉\���A�X�ɁA���������̓���̎�����̎��{�Ƃ̓����ւ̐i�]���A�[�܂�Ƃ̓���̉\����L���Ă��邪�̂ɁA�Љ�I���͂Ɛ����I���͂̓����I����I�F���̉\�������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ̔F���͉䂪�����̌��J���ł̕s�f�̔����������������Ɛ��������̓W�J�̍���ȏ���l���������̂ł��邪�A��X�͂��̐��������A�Љ�������̓��ꂵ�����ԓI�\���`�ԂƂ��āA������O�̊j�Ƃ��Ă̕��U���ƕ������ɑ��āA��̏��������v�����^���A�[�g�S�̂̊K���I�s���ւƔ��W�����A��O�̗v�����Љ�I�\�����I����Ɍ����Ċт��A�����̐����\�Љ�͂̑ɂɃv�����^���A�[�g�̎��Ȍ��́\�v�����^���A�����`�̐��ݓI�\���A�@�\�Ƃ��Ă̈ӎ����A�g�D���A�S�̐���^������̂Ƃ��ĘJ���Ґ����g�D�����o�����̂ł��邪�A���Ɍ��J���ł̉�X�̓��u�����������Ƃ���̖��͓������������Ċw��M
�ɂ��K�������ׂ����̂ł���B
�@�X�ɂ��̂��Ƃɂ��Ắw��m�xNo.4�́u�h�C�c�v���̔s�k�ƃ��[�U�v�i���ؑ��Y�j�ɂ���ēI�m�ɕ\������Ă��邪�A�u�H��ɂ�����Ƃ���̌����̊g���O�ꂳ���A���̂��Ƃɂ���č��ƌ��͂̏Փ˂ւƔ��W���A�ʎ��{�ƍ��ƌ��͂Ƃ̓��ꐫ���F������˂Ȃ�Ȃ��B���[�U���v���̑��i�K�̓X�g���C�L�ɂ��o�ϓ����ł���Ƃ����̂́A�o�ώ�`�ł͂Ȃ�����v���̖@���ł���B�X�ɂ��̂悤�Ƀu���W���A�W�[�̓��h�ɂ��S�炸�s���Љ�ɂ����čĐ��Y���s������Ƃ�������������̂ł���B���Ɍ���v���͍H��ɂ�����J���҂̑g�D�A���[�e�����ɂ����Ă����B�������Ȃ��̂ł���v�B�X�ɔނ͌��_�Ƃ��āu����v���͉i�v�v���_�̒�N�����_�C�i�~�b�N�Ȑ�p�ɂ��M�̋}�i�����W���R�o����`�A���C���^�[�̒�N�����u�����^���A�[�g�̓Ǝ������g�D��̓����Ƃ��āA�������ꂽ�}�ɂ�鐭���I�Ȑ�`�A��Ƌ��ɉ��Ǔ����v�ɂ��H��ł̌����g��A�v����ɂ������O�X�g���C�L���烌�[�e�ւƕK�R�I�ɔ��W����̂ł���B����ɂ�������ǂ̂ݏd�˂݂̂ł͊v���ɂ͌����Ă�����Ȃ����A�������Ǔ�����ʂ��Ă̍H��ɂ����錠���̊g����ɂ��ẮA�P�Ȃ�A�����W�c�ƂȂ邩���͌��͂ɕ��ӂ���邩�̂����ꂩ�ł���B���[�U��M�Ă���А��̏��N�A���̂��Ƃ͏d�傾�I
�@��X�͂����������Ă�����V���Ɋl�����ꂽ�w�����̉��ɍ���Љ�I�Ȑ��������ɂ���w�\�s���Љ�֒����I�Ȑ����I�o�ϕ����Ihegemony
�̊m����O�ꂵ�����{�����Ƃ̒��ڂ̎x�z�Ǝ��D�ɑ��Ă̓�����ʂ��Ċl�����邱�ƂƓ����ɁA���s���Ĕ@�I�ȓ��ؑj�~�A�׃g�i���푈���̐���������W�J���邾�낤�B���ꓙ�̓����̓O��I�[���̒��Ō��@�\���ۓ����������Ă������낤�B���̂��Ƃ̎v�z�����l�����A���������̓��I�֘A����c�����邱�ƂȂ��ɐ�����`�A�w����`��ᔻ���Ă݂Ă��s�тł���B
�쐬�F�R�{���L�i�����ّ�w��[�����w�p�����ȁj
UP:20051022�@Rev:20051024,1105,20070210,0212,0213�@http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/d/kbund.htm
TOP
�@HOME(http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/)��
|
|
�@�P�X�U�Q�D�T�D�Q���A�\�����v�h�n�̎Љ��`�w������i�t�����g�j�����������B�㕔�c�͓̂���Љ��`�����B�����𗽂������������Ă������ƂɂȂ�B
�@�T�D�P�P���A�u���g�n�Њw���ƎЉ�}�n�А��A�\�����v�h�̔��}���w���O�h�A���������j�~�����Ŏ����}�{���ɓ˓��B�T�O�������قɖʉ��v�������َ��苒�A�S�U�����ߕ߂����B
�@�T�D�Q�T���A�S�w�A���퓝��s���A�����W��k�����J�����l�ɐ疼�Q���A�đ�g�كf�����@�����ɑj�~����������O���荞�݁B���w�A���A�ĎD�y�̎��قɐ��S���̍R�c�f���A����łS�T�O���̎s���f���A�O�h�A���A�����j�~�S�s�w������s���A�疼���X��������W�E����J�����܂Ńf���B
| �y�����n�������w��������������������z |
�@�T�D�Q�T���A�r�c�́A��w�Ǘ����Ƃ��āu��w���Ԃ̉����v�ɂȂ��Ă���Ƃ��đ�w�Ǘ��@�̕K�v�������������B�����n�́A���̑�ǖ@�����ɐ^����Ɏ��g�݁A���̉ߒ��łU�D�P���A�S���A����̌���ē����w�����������𐳎��ɔ����������i�����Ƃ́u���۔��E���a�Ɩ����`�����v�Ƃ�������j�B
�@���̓������V�D�P�S�|�P�T���A�u�w���������̂��߂̑S�����N�l��c�v�J�ÂւƂȂ����B�S�����V�O�]������Q���B�u���۔��E���a�Ɩ����`�����S���w���A����c�v�i�����w�A�j�������Ăъ|���A���U�R�N�����w�A����������邱�ƂɂȂ�B���Ȃ݂ɂ��̎���ǖ@�������d�������͖̂����n�ƍ\�����v�h�n�����ł���A������g���n�͓����ۑ�ɐݒ肵�Ȃ������悤�ł���B |
| �y�����q�q�Ǔ�����N�z |
|
�@�U�D�P�T���A��U�D�P�T�������q�q�Ǔ�����N������c����ŊJ���ꂽ�B�w���A�J���ҁA�s���̖�疼���Q�������B���̎��A�őO����߂��}���w���S�w�A�V�O�O���́A�Љ�}�c��Y�̈��A���₶��|���A�Њw���̍��|�s�ψ����̈��A�ɂ͒d��ł̉��肠���������A���������Y�̍u�����قƂ�Ǖ������Ȃ��L�l�ƂȂ����B�����\����Ƃ��銒�r�Y�v�ȁD�g�{�����D���������Y����͔ᔻ�����\���A�T�v��}���w���̋��M�҂������S�w�A�̖���G�̂��Â��邱�Ƃ������ׂ��łȂ���Ƃ܂ŁA�������e�N���Ă���B
�@�}���w���̖��炩�Ƀu���g�Ƃ͈Ⴄ�S�w�A�^���̈�ʂ��_�Ԍ�����B��̊v�}���h�ɗ�Ȃ�Ǝv����}���w���̂炵�����ے�����o�����ł���A�u���g�^�������̌_�@�Ƃ��Ȃ����B
|
| �y���}���w���O�h�A���̓����z |
�@�V���A���}���w���ň�v�����Њw���Č��h�A�А��A�\�����v�h�̎O�h���A�����āu�S����v���J�Â����B�ނ�͑S�w�A�Č����č������������A�܂���̑�ǖ@�Ɏ��g�ނ̂��ǂ������߂����Ẳ^�����j�H���Ⴂ���������ŏI�I�ɖ\�͓I�ȕ���ɔ��W�����B�u���g�͌��@������j�~������{�����咣���A�\�����v�h����ǖ@�����ւ̎��g�݂��咣�����B�u���g���������������ɓ������āA�\�����v�h�h��@���o�����B�������āA�A����������̎O�h�A���͋��������B
�@����ɂ��āA�M�҂͂����v���B���̓������画�邱�Ƃ́A�u���g�̑g�D�_�ɂ�����v���I�Ȍ��א��ł���B��̑S�̃u���g�n�́A�U�O�N���ۓ�����������������܂܍��Ɏ�����l���ܗ���܂��܂��[�ߓ����\�͂������Ȃ��B�ӌ��A�����A�w�j�̈Ⴂ�����}�����˂Ȃ�Ȃ��Ƃł����Ⴂ���Ă��镗������A���炭�u���R�̑叫�v���ɐ��̐��قǓ}�h����肽���̂��낤�B�Ȃ��A�ӌ��̑���ɂ��ẮA�Q�o���g�ɂ���Č������������悤�ł�����B�������A�c�O�Ȃ��班���h�������邱�Ƃɂ��A���̃Q�o���g�ɂ����Ă��}���w���ɑ��Ď��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����o�܂������Ă������ƂɂȂ�B
�@�����ɂ��A�L�����p�X���ɂ����锽�Δh���E���Ȃ��ƍߓI�ł��邩�Ƃ����ƁA���q�����悤�ɂ��v�����A�E����@���^���Ƃ����绂ɂ͖��ڒ��ł�������ӎ��̎����傪�e�����鎖�ɂ��A���ʂƂ��č����^�����o�����邱�ƂɂȂ邩��ł���B��̂ɂ����Ċw�����̍��h�n�ӎ��̎���͑S�̂̂Q��������Ηǂ����ł���A���̂Q�����Œ@�����������邱�Ƃɂ��M�d�Ȑl�m�̔y�o����������邱�Ƃɖ��ڒ��߂���̂��P�V�J���i�C�Ǝv���B
�@��������q�������A���X�u���g�́A�J�I�X�I���E�ς���ɂ��ĉ^���̋}�i��`���哱�I�ɒS���Ă����Ƃ����o�߂�����B�u�U�O�N���ۓ����v�̗̓��ɂ́A���Δh�̑��݂͋������ǂ��납������O��Ƃ���̓I�Ȏ��h�̉^����n�o���Ă������Ƃɂ�舳�|�I�Ȏx�����l�����Ă����Ƃ������M�������Ă����̂ł͂Ȃ������̂��B���̑O������e�����Ȃ��Ȃ����u���g�͂��͂�u���g�ł͂Ȃ��A��O���猩����������̗]��������̓��֎���]�����Ă������ƂɂȂ����Ƃ��Ă��v�������Ȃ��낤�B���̌o�߂����������Ɍ��Ă������肾�B |
| �y�����̘I���ȍ\�����v�h�r���z |
�@���̔N�Ă̐��E�N�w�����a�F�D�Փ��{���s�ψ���ŁA�����}�����̎w���Ɋ�Â��Ė����̑�\�́A���̊Ԃ܂ʼn^�����ꏏ�ɒS���Ă����\�����v�h�n�w�v�V��c�̎Q����r�������B�v�z�A�M���A���}�A�}�h�̂�����ɂ������Ȃ��A���a�F�D�Ղ͌��X���a�ƗF�D�̃X���[�K���̉��ɕ��L���N�����W����F�D�Չ^���ł��������A���R���ӂ���Ă���B�v�V��c�̓t�@�V�X�g�c�̂ł���ƌ����ĎQ�������ۂ����B����܂ňꏏ�Ɂu���a�Ɩ����`�v�̊�����f���ē����Ă��������u�������A����X�؉���������Ƃ������R�����l�����Ȃ����A����X���������t�@�V�Y���Ƃ������s����`�O�i�_�@�ɂ��t�@�V�X�g�����r���̗��R�Ƃ����B
�@����ɂ��āA�M�҂͂����v���B������u�O����I�ȍd�������v�l�}���v�Ƃ����Ĕᔻ����҂����邪�A���ɂ́A�{���́u�H��_�v�l�@�Ŗ��炩�ɂ����悤�ɁA�{���̓T�^�I�ȁu�r���̋����_���v�̌���Ƃ��Ă����l�����Ȃ��B���̘_���͓��{�����i�悻�̍��ł͂ǂ��Ȃ̂���������Ȃ��̂łƂ肠���������������Ƃɂ���j�̏h�A�Ǝ��͍l���Ă���B������ɂ���A���̕��a�F�D�Ղɂ͎����}�n�̐N�^�����Q�����Ă����悤�ł��邩��A�{�����������_�́u�E�ɂ₳�������Ɍ������v�����I�{���������ł����Ď���ł��낤�B
�@���̂��Ƃ́A��W�����E�����߂����Ă̎А��ɑ���x�������U���ɂ�������Ă���B�J���g���^���ɂ���A�N�^���ɂ���g�D�I���含��ۏႷ�邱�Ƃ́A�}�̎w�������ł���ׂ����Ƃł͂��邪�A�����̏ꍇ�A���C�Ȃ����i�̎��ɂ͎������̂̈꒩�����鎞�͂��Ȃ���̂Ă���Ƃ����o�߂����Ď�邱�Ƃ��ł���B��̃J�I�X�E���S�X�ςŎd��ƁA�{���̏ꍇ�ɂ̓��S�X�h�̌n���ł��芎�����t�F�`�Ƃ��������Â������������B |
| �y�}���w���S�w�A���A��Ԃ̍L�ꣂŃ\�r�G�g�̊j�����ɍR�c�f���z |
| �@�W���A���ۊw�A���ɏo�Ȃ������{�ψ����ق��R�����A���X�N���̢�Ԃ̍L�ꣂŢ�\�r�G�g�̊j�����ɍR�c���飃f�����s���Ă���B |
| �y�v�����O�S���ō����h�Ɩ{���h�̑Η������z |
| �@�X���A�u��R��v�����S���ϑ���v�i�O�S���j���_�ŁA�v�����S���ς̒��S�l���ł����������Ƈ��Q�̖{�����̊ԂŔ��������Ȃ�Ȃ��ӌ��Η������������B��̑�ǖ@�����ɉ����āA�}���w�����O�h�Ƌ������������g�l�h�A��������āA���̐��_���ƂȂ范�����Ă������ƂɂȂ����B�����h�̑S�w�A�ψ����E���{�m�͎l�h�A��������ǂ��Ƃ����A����������i�߂��{���h�̏��L���E����c�ƑΗ����Ă������ƂƂȂ����B�O�҂͌�҂��u��O�^����`�v�Ɣ��A��҂͑O�҂��u�Z�N�g��`�v�Ɣ����B�}���w�������̂��̑Η������ΐ��ƂȂ��ė��N�Ɋv�����̑�O���������炳��Ă������ƂɂȂ�B |
| �y�Њw���S�����J�Â���A�����C���ψ����ɏA�C�z |
|
�@�X�D�P�U���A�Њw���S�����J�Â���A�����C���ψ����ɑI�o���ꂽ�B���錾�̒��ŁA�T�v��S�w�A�̎w�������������}���w���́A�^���̉ߒ��Ŗ����������悤�Ƃ����A�P�Ȃ�w���锽�X�^�j�́x�̊ϔO�I�v�l�Ɉ��Z���A�w���������ƕς��ʂ��v�z�I���������Ɏ������x�̂ŁA�S�w�A�^���̒��������炵����Ɣᔻ�����B�����ɂ��ẮA����ē������������邱�Ƃɂ���Ď����㍑�ƌ��͂ɑ���L���ȓ�����������Ă��飂Ɣᔻ�����B���̂��т̎Њw���͂����ă}����h�Ɣ��}����h(�l�k�h)�ւƕ��Ă������ƂɂȂ�B
|
| �y�А������@������j�~������W�J�z |
|
�@�������������̒��ŁA�А������{���̊w�Β������X�،c�����̎w������А��S���w���Nj��c��i�����āu�w���v�j�����S�ƂȂ�A���E���É����̌��@������j�~������W�J�����B���͓�����S�ʓI�ɔے肵���@�́u���S���{�v�����߂���Ǔ������ʓI�ɐςݏグ�Ă������Ƃ��A�����ɑ���쌛�̓����ł���Ƃ��钆���{���Ƃ̘H���Η�������ɑN���ɂ��Ă������̂ł���B���̒����{���ƑS���w���̘H���Η��͎���ɘJ���ғ������ɂ��g�y���Ă������B
|
| �y��w�Ǘ��@�����z |
�@�P�O���A��������R�c���ǖ@���\���o���Ă���ȂLj�i�ƌ������𑝂����ƂɂȂ����B������āA���̎������E�����n�́A��ǖ@�����ɑ�X�I�Ɏ��g��ł������Ƃ��w�j�ɂ����B�P�P�D�P�R���A�����w�A�����Ɍ����Ắu�S���n���u���b�N��\�҉�c�v���J�Â����B���̎��A�U�R�N���̑S�w�A�Č����j�����c�����B�P�P�D�P�V���A�u��w�Ǘ����x�������ӑS������s���v�����肵�A�����͓����R�疼�A�S���V�n��ŏW��A�R�c�f����W�J�����B
�@����������Ǔ����̐���オ������āA�O�h�A�����A�X�ɒx��ă}���w�������̓����ɎQ�����Ă��邱�ƂƂȂ����B�P�P�D�R�O���A�}���w�����܂߂��l�h�A�����`������A��S�疼�̏W������ꂽ�B���O�u�w���^���v�́A���̎l�h�A���ɑ��Ď��̂悤�ɝ������Ă���B
| �@�u����^���̑O�i���Ă���Ƃ���ɂ́A�w�Ȃ�ł��x�w�ǂ��ł��x������čs���A����܂ł̎��������́w�_���x���w���x���ӂɉ�Ȃ��g���c�L�X�g�e�h�̖��ߑ��Ԃ�������Ă��܂肠�����v�B |
�@����ɂ��āA�M�҂͂����v���B��Ǔ����Ɏ��g�ގp���̈Ⴂ�̔w�i�ɁA�����n�Ƃ�����g���n�ɂ́u��w�̎����v�Ɋւ���ϓ_�̑��Ⴊ���邱�Ƃ����̌㎟��ɂ͂����肵�Ă������ƂɂȂ�B������₷�������A�����n�͊w�����剻�������d�����A�g���n�͂�����y������Ƃ������͋\�ԑ̐��Ƃ݂Ȃ����͋@�\��ʂƓ������Ŕj�̑ΏۂƂ��Ă����Ƃ������炢�ɐ^���̗���ɗ��B���̌ケ�̍������掟��Ɋg�����Ă������ƂɂȂ�B���̖����܂������^�����̖��𖾂ȗ��_�I����ł���A���݂Ɋ���I�ɔ��������������ō����Ɏ����Ă���悤�Ɏv����B���̏�������܂�Ȃ����{�I�ƌ�����悤�Ɏv���B
�@�����ɐ^�����ȍ��h���o�ꂵ�Ă���A�����{�̌��@�������v���Љ��`�ƋK�肵�A����̌쎝�Ɛ��甭�W�������ׂ��ł������ł��낤�B����ɂ��A�w�����剻���������ł���A�̐��ϊv�^�������ł��낤�B�A���A�y���ݒn��`�I�Ȉꍑ�ɂ��č��ێ�`�ɒʗp����悤�Ȋv����ڎw���ׂ��ł������ł��낤�B�ǂ������A�����������ɑ������i����^���̂����Ȃ������B |
�@�P�X�U�R�D�P�D�P�X���A�s�w�A�Č����k�Ŏ�����فl�B�Њw���E�А��E�\���h��̓s���P�R��w�Q�U������X�S���Q���B�P�D�Q�S�X�g���玎���{�C�R�b�g�ւƑ�ǖ@�������i��������i�ψ����E���䐟�j�B
| �y��c�t�|�S�w�A���m�̂��̌㣎����z |
�@�Q���A�s�a�r���W�I���^���\����c�t�|�S�w�A���m�̂��̌㣂�������A���ۓ������̑S�w�A�ψ������������Y�ɂ��āA�ނ��c�������i��O�̕������Y�}����̈ψ����ł��������A�����œ]�����A���̌�s���E���Ɗ��Ă����l���j���瓬�������̉������Ă������ƁA���ی�ɂ͓c���̌o�c����y����Ђɋ߂Ă��邱�ƂȂǂ�\�I�����B
�@����ɓ�������т��A��g���c�L�X�g�̐��͉̂E���̎�棂��ƁA��ʂɘ^���e�[�v��z�z���A�@�֎���A�J�n�^��ŘA�����̖������グ���B������Ȃ�A�{�����̐l�̌ӎU�L����₢�A����𑈂����A����P���u���g�̖ʁX�͓����ᔻ�ɑ����ł��ł����A������݂������ł��Ȃ������B
�@����ɂ��A�M�҂Ȃ炩�����_����B
�@��c���������́A���Ȃ������̓}�̑O�g�ł����O�̕������Y�}����̂�����Ƃ����}�ψ����ł���A�]���㐭���I�������`�҂Ƃ��Ĉڂ��g���Ă���
���ƂɂȂ����B����͔ނ̃h���}�ł���A��X�̊֒m����Ƃ���ł͂Ȃ��B���̔ނ��A�����ɂ����Ă͐����I������قɂ�����̂́A�����̉�X�̃u���g�^���Ɏ��g�̎Ⴋ�����J���J�`���A���������ʎ�����\���o�����̂ƎƂ߂Ă���B���́w���ƕS�N�̌v�x���Ȃ��J���̏�̑R�炵�߂����̂ł��������B�u���g�́A����ɂ�萭���I�e������؎Ȃ��������A�����̍�����@��Ԃɂ����Ă͗L���\���o�ł������B
�@�����A�����s���Ƃ����̂ł���A�{���̐�O�̓}�����i�o�ߒ��Ɛ��̓}������̍��۔h����̏���Ȏ����A�g���b�N�����ւ̊֗^�A���̑������ւ̃\�A���Y�}�������[�g���X�ɂ��ċ������Ă����p�ӂ�����B�����A�{���̐�O�̏��������ψ������`�v�������ɂ͏d��ȋ^�f������A�����O��𖾂��Ă������ӂł��飁B |
�@�������_���ׂ��Ƃ���A�{�����u��O�B�ꖳ��̔�]���ō��w���ҁv�Ə���Ɍ��z���Đ��������闝�_���x���ł����Ȃ���������A��Ԃ��Ȃ������B���_�̕n�������H�̕n���Ɍq����i�D��ł��낤�B����ɂ��A�ژ_�u�������i��c�t�|�S�w�A���m�̂��̌�j�l�v�ŊT�q����B |
| �y�v�����S���ς����j�h�Ɗv�}���h�ɕ���z |
�@�Q�D�Q�O���A�O�N�U�Q�D�X���́u�v�����S���ώO�S���v���_�ł̇��P�w���ҁE�����Ƈ��Q�w���ҁE�{���ԂɁu�l�h�A�����v�ΐ��Ƃ���_���A�R�����������A���j�h�Ɗv�}���h�ɕ��邱�ƂɂȂ����B������u�v�����̑�O������v�Ɖ]���B����ɂ��A�ژ_�u�v�����̑�O������l�v�ɋL���B
�@���̍R���͎��̂悤�Ɍ������邱�ƂɂȂ�B�v�����S���ς̐����Ǔ����ł͖{���h���������߁A�u�T���h�v�O���[�v�̖؉�����i�쓇�O�Y�j�A����N�i�R�����j�A�ѓ��P���Y�i�L�c�@�L�j�A����c�Ҏj�i�k��@�o�j�A��P���u���g�̓c��a�v�A���R����i�ݖ{����j�A������v�i���c�V�j�炪�A�������B�����h�ɂ����̂͌���JR���J�g�Ŋ������Ă���q��āi���薾�j�A�X��̏����ł������B�����h�́A�v�����S���ς���o�ĐV���Ɋv�����E�v���I�}���N�X��`�h�i�v�}���h�j���������邱�ƂɂȂ����B���ꂪ�v�}���h�̒a���ł���B
|
| �y�v�}���h�S�w�A�̒a���z |
�@�}���w���̏㕔�w���g�D�̊v�����S���ςŘH���Η����N�������Ƃɂ��}���w�������ɂ��Η����g�y���Ă������ƂɂȂ����B�}���w���ł͋t�̌��ۂ��N���A�v�����S���ςł͏����h�����������h�̓}���w���ł͑����h�ƂȂ����B����ɂ��A�{���h�̕����}���w���S�w�A����ǂ��A�}���w�����j�h���������邱�ƂɂȂ����B
�@�S�D�P�|�Q���A�}���w���S�w�A��R�S���ς��J����A����s����������U���̒������Ƃ���Ƃ�������������ꂽ�B����s����썇��ɉ߂��ʂƔ������{�h(���v�}���h)�ƁA����ɔ������Ģ�Z�N�g��`����Ɣ��𓊂��Ԃ�������c�h(�����j�h)�Ɋ��S�ɕ��邱�ƂɂȂ����B�����̖��A�v�}���h�͒��j�h�U���̒�����Ƃ����肵���B����ɂ��}���w���S�w�A�͊v�}���h�ƒ��j�h�ɕ��邱�ƂƂȂ�A�v�}���h�������S�w�A�̊���Ɛ肵�����A����c��w�����_�Ɋv�}���h�S�w�A�Ƃ��đ��݂��֎��������Ă������ƂɂȂ�B�v�}���h�j�͋@�֎��u����v��n������B���̎������j�h�͑S�w�A�w���^�����Ɂu��������ԁv�ɂȂ����B
�@�V�D�T�|�W���A�S�w�A�Q�O����i�ψ����E���{�m�j�Ŋv�}���h���哱���m���A���{�m�i�k�C���w�|��j���ψ����ɑI�o�����B�v�}���h�͒��j�h�P�R�O���̓�������͑j�~���A�U�����̔�Ƃ����F�����B���j�h�͑S�w�A�嗬�h�����N�����J�Ái�P�E�Q���ځ������J��فA�R���ځ��@����l���A�v�}���h�P�Ƒ���s���Ɣ���B |
| �y���j�h�Ίv�}���h�̕���l�z |
�@���j�h�Ɗv�}���h�̑Η��̔w�i�ɂ͎��̂悤�Ȋϓ_�̑��Ⴊ��݂��Ă����B�u�v�����̒��ɂ����H�h�Ə��ց|�]�_�h�Ƃ̑Η�������A���ꂪ��̒��j�h�Ɗv�}���h�Ƃ̑Η��ɂȂ��Ă������Ƃ̂��Ɓv�i���j�̏،��u���g�D�É�j�ł���B��O�^���̐i�ߕ��ɂ��傫�Ȋϓ_�̑��Ⴊ���݂��Ă����B���j�h�́A��ʂɈړ����Ă����u���g�̉e���ɋ��������̂����X�̃g�b�v���[�_�[�{�����̋C���Ƃ��Ă��������̂�������Ȃ����A���}�h�Ƌ������钆�ŋ����I�Ɏw�������l�����Ă������Ƃ��ĉ^���̐���g���̑�����ʂ��d�����悤�Ƃ��Ă����B�c����ɂ����g�ގp����������B�����̎�̐��_�Ɋ�Â��u���}�h��̘H���v�͑�O�̎��̃v�`�u���I��̐��ł���A�u�Z�N�g��`�A���_�t�F�`�A���a����`�v�ł���Ɣᔻ�����B
�@����ɑ��A�v�}���h�́A���j�h�͍������_�̐������Ƃ��]���ׂ���̐��_���������u��O�ǐ���`�A�ߌ���`�v�ł���Ɖ]���B�Ⴆ�A���̎����}���w���͑��}�h�̏W��ɉ����|���������铙�̍s��������ꂽ���A����͑��}�h�͗��_�I�ɍ��������ׂ��ᔻ�̑Ώۂł���A��Ɏ��h�̎��ʓI���W�����������ł���Ƃ���u�������_�v�I�ϓ_����Ȃ���Ă�����̂ł������B�v�}���h�ɂƂ��ẮA���́u���}�h��̘H���v�͗��_�̌������Ƃ��Ċv���I��̗��_�ƕs���s���̊W�ɂ���A�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��^����̐�Ί�����ł���A�����ɂ��u���c��v�͎ד��ł����Ȃ��Ɖ]���B
�@�^���_�̂�����������͓��R�g�D�_�ɂ��Ă��H���Ⴂ�������邱�ƂɂȂ�B����͂ɂ��Ă��ϓ_�̑��Ⴊ���݂��Ă����B���j�h�͊v�}���h�ɑ��āA�u��@�łȂ��Ƙ_�ؗ͐����Ē鍑��`�Ɛ��Ȃ����a����`�v�Ɖ]���A�v�}���h�́A���j�h�ɑ��āA�u��ϓI�A�M�O�Ɋ�Â����N��@���̐��藧�āv�Ɖ]���B
�@������̑Η����_�ɂ��Ă��q�ׂĂ����B���h�Ƃ��j�̘H���Ƃ��āu����E���X�^��`�v���f���邪�A���h�Ƃ��u����E���X�^�v�̔�d�ɂ��ē����I�ɒB������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ͂�����̂́A���������j�h�͒鍑��`��v�Ō��_������_���d���ɋ߂��A�v�}���h�̓X�^�[���j�X�g��v�Ō��_�����X�^���d���ɋ߂��Ƃ�������̈Ⴂ���������悤�ł���B���̗��h�̑Η��̔w�i�ɁA�����n�����w�A�̐i�o�ɑ���Ή��̎d���̈Ⴂ���W���Ă����Ƃ̌���������B���j�h�̏���c��́A����ɑΏ�����ɂ͎O�h�Ƃ̋������K�v�Ǝ咣���A�v�}���h�̍��{��́A�@���Ȃ闝�R�t���ɂ��摼�}�h�Ƃ̗��_������a���ɂ���悤�ȑË���r���A�f�Ŏv�z������W�J���邱�Ƃ̕K�v�������������B
�@�����̎咣�́A���ɂ́A�ǂ��炪�������Ƃ������肷�邱�Ƃ��s�\�ȋC���̈Ⴂ�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����B��̃J�I�X�E���S�X���ʂɏ]���A���j�h�̓J�I�X�h�̗���ɗ����Ă���A���̈Ӗ��ł͑�ʈړ������u���g�̉e���������炵�����̂Ƃ��l������B
�@�܂�A�u���g���v�����S���ς���{���h�������A��Đ�c�A�肵���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��o���邩������Ȃ��B���ۂɁA���j�h�̈ȍ~�̓�����������u���g�I�s���Ɨ��_��W�J���Ă������ƂɂȂ�B�����Ȃ�Ɠ}�̌��ݕ��j����J���^����p���牽���牽�܂őΗ����Ă������ƂɂȂ�̂��s�v�c�ł͂Ȃ��B���Ă݂�A�v�}���h�̕����v�����̐����̗���������p���ł���A���̊Ԃ̃u���g�̈ړ��ƒ��j�h�Ƃ��Ă̕����̉ߒ��͔��G��̈Ⴄ�҂����Ǐo�Ă������Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł���B |
| �y�����n�������w�A�������z |
|
�@�V�D�P�U�|�P�W���A�����n�S�w�A�̐��I�`�ԂƂ��āA����۔��D���a�Ɩ����`�����S���w��������A����i�u�����w�A�v�j����������A�䓌�̈�قő�P����J�Â��ꂽ�B�ψ����ɐ��O��I�o�����B���̑��ɂ́A�V�Q��w�A�P�Q�P������A�Q�R�O���̑�c�����Q�����A�T���҂R�T�O�O�����z�����B
�@�����w�A�́A������Ɋւ��鎟�̂悤�ȋK���m�ɂ��Ă����B
| �P |
�@������͊w���̂����閯��I�v�������ݏグ�������邱�ƁA������݂͂�Ȃ̂��́A�݂�Ȃ̗��v�������́A�Ƃ����ϓ_�̖��m���B |
| �Q |
�@���吨�͂Ƃ̓��ꋭ���B���ۋ�����c�Ɍ��W���A�l���̗��v�̒��ł����w���̗��v������邱�Ƃm�ɂ��邱�ƁB |
| �R |
�@���ۊw�A�Ƌ��ɔ��镽�a�̍��ۓ������Ƃ��Ă̈ꗃ�Ƃ��āA�S���E�w���Ƃ̘A�ы����B |
| �S |
�@������̖���I�^�c��O��I�ɕۏႷ�邱�ƁB���̗�����т����߂ɂ́A�w���̕������ȖړI�ɂ��������`�҂̐��̂�f�����������A�����Ǖ�����
�������K�v�ł���B |
�@����ɂ��āA�M�҂͂����v���B�M�҂́A���̎咣�ɂ�����P���́u������̖���I�^�c�̓O��I�ۏ�v���x������B�A���A���̍��ڂ��S���́u�����`�҂̐��̂�f�����������A�����Ǖ����铬�����K�v�v�ƌ��т����邱�Ƃɓ��ӂ��Ȃ��B���̎咣�̓Z�N�g�I�ȗ���̕\���ł���A���̕��͂��ڑ�����邱�Ƃɂ��u������̖���I�^�c�̕ۏ�v�̓}�k�[�o�[�ɓ]�������߂��Ă���A�������������̃Z�N�g�I�Ή��ł����Ȃ��ƉM���B���Ă݂�A�u�g�D�̖���I�^�c�Ǝ��s���������_�v�̉𖾂͍��Ȃ��d��ȉۑ�Ƃ��ē˂������Ă���Ǝv����B���̕����̉𖾂��Ȃ������獶�h�^���͈�C�ɉ؊J���Ă�
�����Ƃ��ł��邩������Ȃ��Ƃ��v���B |
�@�X�|�P�O���A�O�h�A�v�}���h�A�������ꂼ�ꂪ���؏���y���Γ�����W�J����B
| �y�����J���������z |
|
�@�X�D�P�R���A�����J�����������������Ă���B�����J�����ŁA�A���S�h�i���j�h�E�Њw���E�А�����h�E�\�����v�h�j���S�s�����N�W��łQ�T�O�������W���Ă���Ƃ���ցA�v�}���h�P�T�O���������������d�苒�A�p�ނœn�荇���������ԂƂȂ����B�̂����h���O�サ�ē���J�����܂Ńf���B�v�}���h�̑��}�h�ւ̖\�͓I���肱�݂͂����Ƃ���̂ł͂Ȃ��낤���B
|
�@�X�D�P�R�i�P�T�j���A�������̎u��h�̔�яo�����A���咆�S�̊����Ƃ������n���痣�E���A�����`�w�������i�u���w���v�j�����������B�u���w���v�́A���P�X�U�S�D�V���A�u��n����{�̐���h�ƍ�������B���h�͂��̌�A���Y��`�J���Ҍn�Ƣ���{�̐���h�Ƃɕ��A�P�O���A�t�����g�Ƌ��ɑS������������������A�\�����v�h�n�V�����A��������`������B
�@�P�Q���A�u�v���ʔh�v����эh��炪����Ģ���Y��`�̊��h����������Ă������A���{���Y�J���}�\���Y��`�ғ������o�đS���Љ�Ȋw������������ꂽ�B����́A�P�X�V�Q�D�V���A�u�^�̑O�q�}�Â����ڂ����v�Ƃ��āu�}���J���v�i�}���N�X��`�J���ғ����ƂȂ�A���̌�ИJ�}�ւƎ���B
�@�������́A�u�U�����̂S�A�V�O�h�A�������A���n�S�w�A�̒a�� �v�ɋL���B
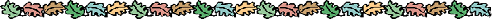



 (���_�D����)
(���_�D����)


![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)