
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元、栄和5)年.1.21日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
第二次ブントは、第一次ブントとは違う別の彩りを添える。今日的に見て、第一次ブント時代は幾分か牧歌的な反体制運動であった。権力闘争に立ち向かう方法も素手のスクラムしかなく、党派間闘争も基本的に言論戦であり、正義は競り合いで証されていた。これを勝利的に押し進めたのが第一次ブントであった。これに比して、第二次ブント時代になると、急進主義系運動の主流は革共同全国委系から発生した中核派と革マル派であり、社会党系社青同から出自した社青同解放派であり、第二次ブントはそれらの後塵を拝することを余儀なくされていた。
その第二次ブントは常に分裂含みであり、第一次ブント的結集を見せることはなかった。但し、れんだいこが興味を覚えるところであるが、その複雑な分岐がそれなりに意味があり、それらの極化運動を通じて案外と示唆的な運動軌跡を残しているように思われる。この辺りを検証していきたい。
2008.1.31日 れんだいこ拝 |
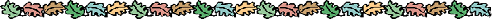
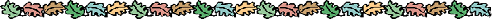



 (私論.私見)
(私論.私見)
初出は、『戦旗』340号(1973年12月5日号、戦旗社)。『共産主義 共産主義者同盟(戦旗派)重要論文集』1巻(戦旗社、1983年)から。
七三年日向カクマル主義者の組織的脱落に関する声明
日向カクマル主義―解党派粉砕し、同盟の革命的再生を 共産同(戦旗派)中央委員会_
六月十二CC以降日向一派を先頭とする諸グループは同盟より脱走と逃亡を開始た。「中央委員会の開催など何の意味もない」(日向)として、中央指導部を分裂させ(六月)、更に党協議会設置の提起(八月)に一貫して反対し、連絡会議をもってこれに代行させ(九月下旬)、今日に至っては、この「連絡会議」からも逃亡している(十一月)。中央学生組織委員会のボイコット(八月)による反帝戦線の分断、部落解放組織委員会のボイコット(七月)による「克服すべき課題」に対する反動的居直りと大衆闘争機関の分断を強行し、その他の一切の党機関から逃亡。「編集局会議の決定なしには戦旗は発行しない」との確認(十月下旬)にもかかわらず勝手に発行し(戦旗・三三八号)、われわれの批判によって自己批判し(十月下旬)その結果、戦旗・三三九号が「合同編集局」によって発行されたにもかかわらず、今度はこの編集局会議をボイコットし(十月二十九日)編集局からも、最終的に逃亡。日向一派の「中央指導部の解体」に始まり、「戦旗編集局の分断」に終る解党的行為を断じて許すことはできない。わが共産主義者同盟戦旗派中央委員会(多数派)は、ここに公然と声明を発表し、一切の合法主義、一切の「左」右の解党主義と闘い抜く。わが同盟の一部に発生したカクマル主義者・経済主義者の連合を打ち破り、中央集権党を堅持し、七〇年代階級闘争を担う。
全ての人民に訴える ―同盟は健在であり同盟は不滅である
わが同盟はいま、同盟建設三年間の闘いの中で最も重大な試練に直面している。この「党の試練」は、同盟建設三年間の闘いを清算するのか、同盟建設三年間の闘いを堅持し発展させるのか、社会排外主義者=カクマルに屈服し、共産主義者同盟十余年の歴史を清算するのか、社会排外主義者=カクマルと闘い共産主義者同盟十余年の歴史を防衛・継承するのか、という根本的にしてかつ本質的な問題をわれわれに突きつけている。
七二年六月、日向一派の中央派結成に始まる戦旗派内分派闘争に示される事態は、わが同盟内の一部日和見主義者―日向一派、城山―篠沢グループ、そして渋谷グループ(いわゆる国際主義派)。帝国主義に屈服しカクマル主義に屈服した経済主義者・カクマル主義者。
革命勢力の「武装遊撃戦を端緒とする戦略的反攻を戦取」せんという、極めて厳しく、同時にわれわれにとっては、光栄ある闘いの現段階に突入しつつある。わが同盟が十・八羽田闘争以降の武装闘争を継承し「死闘の七〇年代」を真に指導しうるのか否かということなのであり、もっと積極的にいうならば、わが同盟をこの武装闘争の最前衛として創りあげ打ち鍛えていく「決意」があるのかどうなのか、「能力」があるのかどうなのかということなのである。
党建設―非合法党建設からの脱走を許さず、党の統一をかちとろう。
カクマル主義を粉砕せよ ―二つの解党派とわれわれの道
わが同盟は、六九年七・六第二次共産主義者同盟の崩壊以降、「党の革命」をかかげ、一切のメンシェビキ的・ローザ的前衛党組織観と闘い、真の前衛党組織建設をめざして闘い抜いてきた。レーニン・ボルシェビキ党組織建設に向け、分派闘争を非和解的に推進してきた。党内日和見主義分派=赤軍派、叛旗派、情況派、野合右派(関地区派、左派、蜂起派)と他ならぬ党組織建設を巡って闘い抜き、これら諸雑派を同盟外に放逐し、党内闘争に勝利してきた。
わが同盟は、「軍事を孕み共産主義を組織する党」、「武装闘争の前衛部隊としての党」を掲げ、権力に対して武装しきることと、同時に政治闘争・武装闘争を結合させ、労働者階級を組織的実体としたところの革命勢力を創出させることを二つの重大任務と設定し闘いを強化してきた。党組織建設のための闘い(党のための闘い)と、革命勢力を強化・拡大していく闘い(党としての闘い)という、党組織にとっての二つの闘い、二重の任務を組織してきた。
同盟の一部に発生した主体形成主義、その発展としてのカクマル主義。われわれはこの党内闘争を通じて9CC、10CC、11CCを主体形成主義・カクマル主義との訣別の組織的集約環としてかちとってきた。
つまり、第二次ブンドの破産という歴史的現実に規定された、主体形成主義的傾向・サークル主義的傾向からの主体的訣別、その到達点としての不動の前衛的立場の確立、前衛党的位置への発展。この前衛党的位置から把え返しての主体形成主義的傾向、サークル主義的傾向の克服。いかに「戦う党」を創り出すのかということであった。つまり、「第二次ブンドは戦術左翼集団だった」として総括した同盟理論(とりわけ「編集局への手紙」のなかに見られる日向理論)の中では、戦術左翼集団の否定、カクマルにも通じる本質的に日和見主義であるこの体質、この思想といかに闘い抜くのかという問題であったのである。日向より日向的であった同盟内活動家(S・S・Aら)が最もカクマル的=最右派であったことは、このことを如実に示している。戦術左翼集団であった第二次ブンドをのり越えんとしたとき、この方法において、二つの傾向が同盟内には常に潜在的・顕在的に存在していたのである。すなわち一方には、学習会と主体形成のみを問題とするカクマル主義・サークル主義であり、他方においては、革命的党的立場からこの「戦術」を把えかえし物質化していくレーニン主義の立場である。まさに問われていたことは、カクマル式党建設と闘うことであったのだ。
このわれわれ的党建設の仕方とカクマル式党建設の異なりは、戦旗派内部に構造的対立をもたらしていった。9CC政組、10CC政組、11CC路線という形で一部の誤まった傾向・カクマル主義的党建設の傾向は徐々に克服されてきた。特に11CCでは、カクマル主義発生の根拠たる恒武闘争論(その理論的根拠としての日向イズム・スコラ的観念論、党組織と階級組織の同一化)の誤りを克服し、「戦う党」への端緒をつくりあげた。だが、われわれの闘いの不徹底さ故に、彼らのカクマル主義への成長・転化を許してしまった。
日向一派は、軍事問題に対する完全なる日和見主義故に、一切軍事問題を清算し軍事清算派へ転落し、政治闘争、武装闘争まで清算する腐り切った経済主義にまで純化発展をとげている。日向一派は「上からの解党主義」として党の合法化を推し進め、わが同盟の非合法党建設に敵対している。城山グループは「下からの解党主義」として同盟の解散を求め、日本階級闘争を清算し、同盟を風化・解体させようとしている。城山グループの最右派篠沢グループはいまではほんもののカクマルの手先となり、戦旗派内に初期より存在した偏向との闘いの重大さをわれわれに痛感させている。日向一派―城山グループとは、カクマル主義・経済主義では共通し、「第二次ブンドは余りにも左翼的・戦闘的であった」と総括する点で、非合法党建設に反対する点では共通であり、政治闘争・武装闘争の継承と発展の全面的清算というところで共通している。違いといえば、たかだか日向一派が城山グループほどほんもののカクマルに純化できないだけであり、同盟を城山グループが「下から」解体させようとしているのに対して、日向一派は同盟を「上から」解体させようとしていることぐらいである。
戦旗派内分派闘争の本質的意義は中央集権党建設・全国単一党建設、「軍事を孕み共産主義を組織する党建設」「武装闘争を組織する党建設」の目的意識的闘いの継承、発展をなしとげるということであり、これを巡る闘いの中での二つのカクマル主義者の逃亡ということである。
同盟の革命的団結を ―解党派と闘い戦列を強化せよ
ところで、われわれは、(1) 戦旗派三年間の歴史的意義を確認し、(2)
戦旗派建設の歴史的前進の結果としての二つのカクマル主義の発生の事実問題を明らかにし、(3)
戦旗派建設の意義のおし進めと、共産同の全歴史を二つのカクマル主義から防衛するものとしての、わが分派の結成とその後のわが分派による党内―分派闘争の組織化の全経過を全プロレタリアート人民共通の問題として明らかにしたい。
同盟の闘いと日和見主義
わが同盟は、六九年七・六第二次共産同の崩壊以降、「戦術指導部の党」という第二次共産同の歴史的限界を克服するものとして、党組織建設の独自的闘いをおし進めてきた。五・二九外務省突入をもって切り開かれた「党としての闘い」は、六・一七宮下公園における武装闘争の展開、秋期十・二一、十一・一九「公―非闘争の推進」と沖共闘の左翼的牽引、更に翌年三・一三西部方面隊突入闘争、三月全関東叛軍を動員しての現地北熊本闘争の確固とした指導、そして又、これらの全成果をかけての五・一三神田武装遊撃戦と七・一五北熊本闘争、息つくひまもない連続的な敵権力との死闘の闘いであった。とりわけ、五・一三武装遊撃戦は、「七〇年代が機動隊せん滅戦の時代」「武装遊撃戦を通じて戦略的反攻を戦取する闘いの時代」として七〇年階級闘争の基軸的方向性を提起し、一切の中間諸派の権力による「火炎ビン立法」によるどう喝の前での逃亡をのりこえ闘い抜かれたのである。党としての闘いの全成果をかけて、権力の一二九名にも及ぶ大量逮捕―大弾圧をものともせず闘い抜いた同盟の精神こそ、七〇年代階級闘争を闘うわれわれの確信である。
ところで同盟は、鉄火の七〇年代階級闘争の中におけるこの党組織建設の独自の闘いと、革命勢力を強化、拡大させていく闘いという二つの任務を遂行するなかで、多くの試練と困難につき当った。それは第一に、わが同盟が、軍事武装闘争をいかに組織していくのかという問題であり、第二に、かかる政治的性格を有したものとしての党組織建設の独自的建設の問題であり、第三に革命勢力を創出していくうえでの問題であり、第四に、七〇年代における戦略的総路線に基礎づけられた「総路線」の確立の問題であった。この四つの課題の中で、革命的傾向と日和見主義的傾向は明らかとなったのである。すなわち、革命的部分は、生起した課題が、われわれの全同盟の活動の勝利的前進ゆえの「当然の帰結に」他ならないと把握し、この四つの課題をガッチリと主体的に把え返し、前進せんとしたのである。「恒武闘争論(路線)」に孕まれた悟性主義的・カクマル主義的偏向の克服、つまり論理主義・スコラ的観念性の克服の必要性であり、路線問題、戦術問題に対するカクマル主義的無方針の克服ということである。
これに対する日和見主義(主要には党内カクマル主義)は、生起した課題を、わが同盟の全活動の勝利的前進の成果として見るのではなく、同盟の破産・敗北の結果として見ること、つまり同盟活動に対する不確信と動揺にその本質的性格を有しているのである。
すなわち日和見主義的部分は第一に、わが同盟の軍事武装闘争組織化の苦闘を一切清算し、軍事問題、武装闘争の問題を語ることすらしない完全なる合法主義に転落し、第二に、非合法党建設、中央集権党建設を否定し、「広汎な民主主義要求派」として党を合法化させ、党組織を階級組織と混同し解党主義の思想を持ち込み、第三には、鉄火の階級闘争の中で革命勢力を構築するのではなく、この現実的任務の重大性と緊急性を見ないで「運動と組織の弁証法的理解」とかいうスコラ論議でお茶を濁して闘いから逃亡しようとし、第四には、現実に展開されている労働者人民の闘いに接近し、確固とした「計画としての戦術」による指導ということを全く放棄し、小ブル的自己確認に党的立場を陥しこめ、その結果として、一切階級的責任を負わないセクト主義的傾向として立ちあらわれたのである。
11CCの日向中央派の性格
日向一派は、第一に、わが同盟の軍事闘争・武装闘争の組織化について口先だけで認め、その裏では清算し、第二に、非合法党建設・中央集権党を語りながら、その実、「上からの党の合法党への改組」を企て、第三に、革命勢力の強化・拡大の任務においては、政治闘争・武装闘争にあいまいな態度をとり、階級との結合に対してスコラ的理論をもっての啓蒙主義におちいり、その裏返しとしてセクト主義、排外主義を構造化させ、第四に、実践的な「総路線」の確立の追求に対して、「党的世界」なるスコラ的自己充足の世界を対置せんとしたのである。
わが同盟は(1) 軍事武装闘争の推進、(2)
非合法党、中央集権党建設の推進、(3) 革命勢力の強化・拡大のための指導の強化、一切の排外主義の克服、(4)
「総路線」の確固とした確立、という四点の問題に直面し、この解決を目的意識的に追求せねばならなかった。
七二年一月、当時の最高責任者の日向の「入院」という名目での逃亡の中。この中で中央指導部は二つの傾向に分岐した。同盟の全成果の上に四つの課題を推し進めんとする部分と、旧来のスコラ的「恒武闘争論」に固執、これに内包されている論理主義的傾向を防衛・固執せんとした自己保身的部分である。その後、前者の部分=四人委員会による断固たる党内闘争の組織化によって「11CC路線」は確立されたのである。すなわち11CC路線の確立によってカクマル主義的偏向を内包していた恒武論は敗北し、わが同盟にとって画期的路線が採用されたのである。
11CC路線においては、軍事武装闘争推進上における戦役主義克服の方向性と同時に、政治闘争と武装闘争との結合の方向性の鮮明化、(2)
党組織建設における「水増し化」の克服の方向性、同盟=KIM論に見られる解党主義、合法主義組織論―組織路線の克服の方向性、そして又、中央指導部から末端細胞まで、革命党の党員は正規軍的質で武装されねばならないことの鮮明化、あくまでも現実に接近し現実の階級闘争の中で革命党と革命勢力の任務を明らかにしていくという態度の堅持と強化、つまり「理論主義的偏向」「論理主義的偏向」又「前衛ショービニズム」の克服の方向性を鮮明化せんとしたのである。だがしかし、四人委員会の闘いによって、11CC路線という「左派路線」が確立されつつも、にもかかわらず四人委員会はこの意義を徹底化し、意識化し、日和見主義、主体形成主義の完全なる克服をなしとげることができず、党内闘争は中途挫折し妥協的形態へと変質せしめられた。
ところで日向は、この「11CC路線」の意義の徹底化―「恒武論」の敗北の原因の本質的把え返しが、当然にも自己の全論理体系の破産につながるのではないかと直感し、その予防措置として分派結成に踏みきったのである。
その後、日向中央派は、路線的には「セクト的実行委員会方式」の採用を目論み、軍事闘争はもちろんのこと政治闘争までをも清算し始めたのである。日向一派は、11CC路線を清算して右派路線を採用する際に、城山―篠沢があまりにも右派で日和見主義であったのとわれわれの闘いにはばまれ難行し、結局、「右派を批判しながら右派路線をとる」といったスターリン型党運営に走ったのであった。
七月、I、Sの九州・北海道への追放(これは四人委員会の闘いの不徹底さ故の必然の結果であるが)七月、九州での地区代表者会議の席上における「怪文書」の配布等を公然と推し進めつつ、裏ではH―NOによる「Sを除名するための確証を把め!!」として○CAP・Oをオルグしたり、NTが「○○○○は反対派の拠点だからいつでもゲバルトをやれる体制をつくれ」と言ってオルグしたり、果てはNAに至っては、○において、「四人委員会が金が使い込んだ」などという全く見えすいた信じられるはずもない、うそとデタラメでオルグするという形で「反対派狩り」という名の下に自己の分派への分派的オルグを強行したのである。
七二年六月〜十一月までの期間は日向中央派内の「左翼バネ」として機能していたNTの動向によって、それなりに11CC路線の物質化という表象を党活動に与えていたわけであるが、七二年十一月以降は、「キム凍結」をメルクマールに、11CC路線を清算し、党内右派路線を構造化させたのである。とくに、地域主義的傾向を色濃く有した○○方式が全同盟に普遍化されるに至っては、路線的にも経済主義、カクマル主義に屈服したということであった。だから、日向中央派のデマを軸とした分派的同盟運営に疑問を抱き、○○型セクト的実行委方式の全同盟的採用に反対する部分によって、同盟内反日向中央派分派活動は開始されたのである。
われわれの分派闘争
かかる党的混乱の事態の中で、われわれは七三年三月末、日向中央派の分派的組織運営=分裂主義と対決すべく、戦旗派内左派分派として自己を形成したのである。第一に党組織建設の独自活動を通じて機関の確立を、非合法党、中央集権党を建設しきること、第二に「路線問題に対する態度」、路線の内容に関して、「スコラ的観念論」「論理主義」と闘い、11CC路線を堅持し、より一層の深化、発展をかちとること。第三に軍事武装闘争の一切の清算に反対しきること、つまり「公―非の展開」を主体的に受けとめきること、第四に日向中央派の分派的意志統一が相当「堅い」ことを根拠として、来る拡大中央委員会の開催までは非公然の分派闘争形態を基軸とした分派活動を考えること、第五に、当時の反日向中央派と目されていた部分が色濃く有していた反官僚主義、反中央集権主義的傾向、つまり解党主義的傾向と闘い、これを克服すること。組織的には城山―篠沢を中心に当時結成されていた「反ブンド主義カクマル主義フラクション」と断固として闘い、政治・組織上において勝利すること、第六に、城山・篠沢グループ解体の組織戦術の一環として合同討論の場を設定し、又、12CC獲得のための戦術協定を行うこと等であった。
12CCにおいて、われわれは日向一派の「予防反革命」としての分派結成の事実問題、日向一派による軍事武装闘争の身をもっての清算―同盟の権力への合法化の事実を明らかにし、その後の分派闘争の全同盟的方向性を責任をもって提起したのである。
ところで、12CC以降の分派闘争の同盟内部での公然たる展開の中で、わが分派は本格的分派建設、党建設に突入したのである。城山―篠沢グループは七二年秋期より七三年春期にかけて、同盟より脱落した解党主義グループ=渋谷グループに対する態度において常に中間主義的態度をとり続け、彼らの解党主義を擁護さえしたのである。七三年六月12CC以降は、戦旗派内部に様々な傾向性をそれとして純化させた。すなわち、革命的なものはより一層革命的となり、日和見主義的なものはより一層日和見主義的なものとなった。まず日向中央派は、中間派連合故に「左翼バネ」たるNT、「重鎮」たるNOが脱落し文字通り陰然たる「上からの解党派」、「小ブル排外主義者」に純化したし、又、城山―篠沢グループは「カクマルへの参加の仕方」をめぐって分裂したのである。
革命的党組織建設を―日向カクマル主義を粉砕せよ
七〇年代中期「支配階級との激突の時代」を控えて、日和見主義者は「同盟活動の全成果」に対する不確信故の逃亡を計り、清算をおし進めた。日向一派は非合法党建設を清算し、又もや、あの古き「妖雲亭フラク」に党を解体させようとしている。城山グループは党建設そのものを清算し、共産主義者同盟の全歴史を清算し、完全なるカクマル主義へ転落した。全ゆる党機関から逃亡し、全ゆる戦線から脱走している。全ゆる党機関からの逃亡、全ゆる階級指導からの召還という現実の中にこそ彼らの解党主義としての本質があるのであり、レーニン主義的原則からの逃亡があるのだ。
日向一派がいっているように「党建設を言いすぎた」。むしろ、日向一派の如く「戦旗派の党建設は小ブル急進主義だった」として、また、結果解釈し、合法主義カクマル主義(それもフロント化した)に屈服し、脱走を計る清算主義分子を許してはならないということなのだ。われわれは必ずや、「軍事を組織する党」「労働者階級の党」という観点をマルクス・レーニン主義の諸原則で正しく統一し、戦旗派内カクマル分子の掃討をなしとげ、第二次共産同の分裂を止揚し、社共に変る日本における唯一の前衛党を創り出すであろう。
一九七三年十二月十八日 共産主義者同盟戦旗派中央委員会(多数派) 〔『戦旗』第三四〇号(一九七三年十二月五日)に掲載〕_
合赤軍事件に関する特別報告
はじめに
共産主義者同盟赤軍派としての結成以来の歩み――とくに連合赤軍の歩み――を総括。
連合赤軍の同志殺害に関する問題。同志殺害という行為は、当時の政治思想上、路線上の問題ときってもきりはなせない。軍事第一主義・観念的共産主義・大衆からの召喚主義等々の誤まった政治・思想上、路線上の問題にその起因があることはいうまでもない。同志殺害の行為の責任を問うことと、亡き一二名の同志(日共革命左派神奈川県常任委員会系の同志たちも含めて)の名誉回復を確認する。
〔1〕 連合赤軍同志殺害の事実経過とその分析
連合赤軍のゲリラ戦は、大衆闘争の武装闘争への転化をある程度促進した。その指導性を軍事のエスカレートに求め、その活動は軍事活動に一面化していった。戦術的には大衆運動から召喚し、人民から孤立し、山岳アジトへの撤退を余儀なくされていった。我々は軍事第一主義的な建軍革命戦争路線の根本的な路線転換が要求されていた。この要求に赤軍派・日共革命左派神奈川県常任委の指導部がこたえられなかったため、両組織は自らの内部矛盾を激化させていき、それは中央軍・人民革命軍、連合赤軍に最も集中して現われた。 結論からいえば、我々は一連の同志殺害を同志殺害という形をとった連合赤軍指導部と「下部」兵士との党内闘争であり、又指導部による党内闘争の暴力的圧殺であると分析する。
連合赤軍同志殺害は七一年夏、向山茂徳同志・早岐やす子同志に対して人民革命軍指導部によって行なわれた事に端を発している。この理由は、両同志の戦線離脱による権力への通報を恐れたものだった。これは七一年一二月二六日の以後の一連のいわゆる「総括」→同志殺害の直接のきっかけをなすものであった。
だが、この理由は一二名の同志殺害にとっては外因として作用していたにすぎない。真の内在的理由は別の処にある。
七一年一二月二〇日、共産同赤軍派の中央軍と日共革命左派神奈川県常任委の人民革命軍は組織合同を決定した。その政治的・軍事的基調は以下である。(1)
合同軍事訓練を展開し、新党建設・銃によるせん滅戦をかちとる。(2)
かかる飛躍を短期間に果たすために厳しい自己批判―相互批判を通して兵士の小ブル性を払拭し、隊内共産主義をかちとる。革命左派の加藤能敬同志・尾崎充男同志がまずこの方針に反対した。加藤同志は爆弾闘争の多発化による大衆闘争の武装化と武装闘争派の統一を主張し、尾崎同志は反米愛国路線の堅持を主張した。連赤指導部は戦術的には爆弾闘争の重視を右翼日和見主義、思想的には反米愛国の堅持を毛沢東教条主義と批判し、軍―共産主義の母胎論の思想を対置した。だが、彼らは思想(綱領)・戦術・組織全般にわたる党内矛盾を解決するのではなく、反対派を暴力的に圧殺していく、銃をもてる軍隊への飛躍、兵士の小ブル性の払拭という隊内共産主義論はすでに赤軍派にあっては七〇年秋第二次綱領論争において路線化されているが(新聞『赤軍七号』)、実践的にはこれは自分の反対派を暴力的に圧殺していく口実以外の何物でもなかった。何か個人の禁欲主義的修養によって小ブル性が克服され、しかも暴力的に行えばより徹底して行えると考えるのである。この「共産主義論」はマルクス主義とは縁もゆかりもない。連赤指導部はあるべき共産主義的人格を我流に規定し、それに適応しない点を恣意的に並べたて、あるべき人格と違うからといって暴力をふるい、次々と同志を殺害していくのである。森・永田両名は、この「共産主義化の闘い」の中で全く自己の小ブル性は問わないのである。ということは、彼らは資本主義社会が必然的に刻印するブルジョアイデオロギー、習慣等から完全に超越している「共産主義的」人格である、ということになる。森は、この点を上申書で自己批判し、自己批判―相互批判の作風がなかった、病を治して人を救うという観点がなかったからだといっているが、何故そのような大原則をふみにじったのか? それは、相互批判をすれば永遠の相互告発運動になり、その過程で路線をめぐる意見の対立が拡大していく以外にないからだ。したがって、一方的な糾弾になっていくのである。このとき、党内論争を圧殺するためにそのような誤まった共産主義観をおしつけたのか、それとも逆なのかというのはさして問題ではない。誤まった共産主義観と党内闘争の圧殺は密接に結びついていることを確認しておけばよい。
加藤同志に対しては、パクられたとき権力と雑談した。尾崎同志には「総括」されているが、加藤同志をなぐったとき口走った言葉が問題だ。小嶋和子同志に対しては加藤同志に接吻されたことを報告するときにうれしそうなそぶりをした、等々の理由で、まず自己の小ブル性の総括を要求し、次に全員でなぐり、ロープでしばり死亡させていくのである。
かくして、連赤指導部は、銃によるせん滅戦という極左的戦術に対する批判とまともに論争せず、マルクス主義と全く無縁な隊内共産主義論という小ブル的修養思想を対置し、指導部の指導放棄からくる連合赤軍の行きづまりの責任を被指導部兵士の人格的欠陥になすりつけ転嫁していくのである。
以下、同志殺害を通して連赤の内部矛盾がどのように拡大し、内部崩壊していくかをあとづけてみよう。
◎進藤同志に対して 彼が横浜寿町で活動していたことをとりあげルンプロ的個人主義的であると批判し、暴行を加える過程で死亡。(赤軍派最初の処罰)
◎遠山同志に対して 彼女は女性であることに甘えていて兵士の自覚が足りないと批判され、暴力を加えられ、七二年一月七日死亡。
◎行方同志に対して (1)
いつも第二線にいる、(2)
女性関係がルーズ等の理由で七二年一月三日から九日にかけて暴力的に批判され死亡。
(この三人の同志は森らの「共産主義論」にだまされ、その要求に必死になって応えようとしながらその過程で殺害された。だが、内部矛盾は更に拡大していく。)
◎寺岡恒一同志に対して 彼は野心家であり、女性を蔑視している、という理由で中央委員でありながらそのような小ブル性の責任は大きいとして、一月七日森によって死刑宣告され、殺害される。
◎山崎順同志に対して 優等生的である。女性関係がルーズであると総括を要求。(一・一八)(一九日某同志が戦線離脱=いわゆる「脱走」)その時、彼が「六名を殺した。自分も殺される。」といった事を把え、総括―共産主義化の意義が他の殺害された同志に比べて全然分っていない。だから脱走して敵権力に通報する可能性がある、とし、彼も死刑宣告され殺害。(この二同志の場合、進藤、遠山、行方同志の場合と比べて内部矛盾に質的違いがある。この過程で(1)
某同志の戦線離脱があり、(2)
二同志とも死刑という事で意識的に殺害されている。これは指導部は人民的内部の矛盾を「通報する恐れ有り。」の理由で意識的に敵対矛盾にまで転化したこと。被指導部の方からは、一つは戦線離脱という形で、もう一つは「殺される」とはっきり言った事で、「総括」が「共産主義化」でも何でもなく同志殺しの口実にすぎない事を意識し始めたということ、を意味している。加藤同志の戦線問題を巡る指導部批判は今や、無意識的ではあれ思想的批判にまで深刻化しだしたのである。党内闘争・内部矛盾は客観的には、指導部の共産主義に対する思想的立脚基盤を巡る対立に発展していった。)
◎金子みちよ同志に対して 妊娠中であるにもかかわらず兵士として山岳ベースに結集した彼女に対して「妊娠をたてにとって甘えている」と総括を要求し、その過程で暴力を加えられ、死亡寸前になっている彼女の胎内から子供を取り出す事まで検討するが、二月四日死亡。
◎大槻節子同志に対して (1)
戦術上は右翼日和見主義 (2)
服装等趣味がブルジョア的として総括を迫るが、終止反抗的な中で死亡、一月三〇日。(指導部に対する思想的批判を正しく党内論争として解決できず、又、する気もない連赤指導部は、矛盾が拡大すれば益々その解決方法は醜悪なものになり、且つ、殺害される方はそれに対する批判的姿勢を強めていく。)
◎山本順一同志に対して 彼は初めて総括―同志殺しが誤まりである事を政治主張として述べる(一・二二〜二六)。指導部は、殊ここに至っても自己の誤りを認めず、逆エビにしばり総括を要求。一月三〇日死亡。
◎山田孝同志に対して 一月三一日に実践能力がない、理論主義的、官僚主義的として総括を要求。→二・二中央委員辞任。二・一二死亡。(山本同志の真正面からの批判にも答え様としなかった指導部は益々思想的堕落を深め、同志殺しは寺岡同志に続き、中央委の側にまで波及し始めた。連赤は今や内部崩壊を起こし始めたのだ。)
〔2〕 亡き一二名の同志たちの名誉回復について
以上の同志殺害の事実経過をもとに、以下の一二名の同志たちの名誉回復を提案し、決議するよう要請する。殺害された同志たちの名誉回復については次のとおりである。
(イ) 進藤隆三郎同志について 進藤同志は革命的兵士であって、いわゆる「総括」の「革命兵士の資質」に関する「個人主義的」とか「ルンプロ的」とかの恣意的な口実は全くあてはまらない。進藤同志は革命兵士として闘い、連合赤軍指導部の誤まった指導のために二十二歳の若き生涯を終えた。
(ロ) 遠山美枝子同志について 遠山同志は赤軍派結成当初からのきわめて献身的で革命的な同志であった。遠山同志の「総括」理由にのべられた「服装や化粧や態度」に「女性としてのブルジョア性」がみられることとか、「戦士としての独立性、行動力に欠けている」等の恣意的な口実はすべてあてはまらない。遠山同志は、革命兵士としてたたかい、連赤指導部の誤まった指導のために二十五歳の若き生涯を終えた。
(ハ) 行方正時同志について 行方同志は、革命的な兵士であって、連赤指導部が下した「革命兵士の資質」に欠ける云々の理由は全く恣意的であり、全くあてはまらない。行方同志は、革命兵士として闘い、連赤指導部の誤まった指導のために二十二歳の若き生涯を終えた。
(ニ) 山崎順同志について 山崎同志は、革命的な兵士であって、同志殺害に関して批判的な観点にたとうとしていた。山崎同志の「革命兵士の資質」に欠ける云々の連赤指導部の恣意的判断は全くあてはまらない。山崎同志は革命兵士として闘い、連赤指導部の誤まった指導のために二十一歳の若き生涯を終えた。
(ホ) 山田孝同志について 山田同志は連合赤軍指導部の一員として同志殺害に関する責任はまぬがれないが、山田同志自身、後に連赤指導部の誤まった指導のために二十七歳の若き生涯を終えた。山田同志になされた「革命兵士の資質」に欠ける云々や、「官僚主義」云々の恣意的な判断・口実は全くあてはまらない。山田同志は、一九六七年以降一貫して共産同の献身的な一員であり分裂前は中央委員・京都府委員会委員長であった。又、赤軍派結成以降の革命家・革命兵士であった。
(ヘ) 日共革命左派神奈川県常任委員会・人民革命軍の七名の同志たち(加藤能敬同志・尾崎充男同志・寺岡恒一同志・金子みちよ同志・大槻節子同志・小嶋和子同志・山本順一同志)について 七名の同志とも革命家・革命兵士としての道を歩んだ。連赤指導部の誤まった指導のために若き生涯をおえた。
〔3〕 同志殺害を指導した部分と、同志殺害に加担した部分に対する組織処分について
同志殺害の事実経過をもとにして、以下のことを提案し、決議するよう要請する。
(イ) 森恒夫は、連合赤軍における一連の同志殺害を組織し、呵責なく実行した最高責任者であり、その責任はまぬがれることはできない。彼は一九七三年一月一日東京拘置所において死去した。
(ロ) 坂東国男は連合赤軍の中央委員会の一員として同志殺害を指導し参加した。この行為を厳しく弾劾し、彼を共産同赤軍派より除名する。
(ハ) 植垣康博は、連合赤軍の一員として同志殺害に加担した。この行為を厳しく弾劾し、彼を共産同赤軍派より除名する。
(ニ) 青砥幹夫は、連合赤軍の一員として同志殺害に加担した。かつ、彼は警察に逮捕後、思想的に屈服し、極めて多くの自供により、諸同志を国家権力に売りわたした。こうした行為を断固として厳しく弾劾し、彼を共産同赤軍派より除名する。
(ホ) 坂東国男、植垣康博両名は、現在拘置所にあり、日々ブルジョア政府の仮借ない攻撃の下におかれている。また彼らは、獄中闘争・公判闘争における同志殺害の自己批判を通じ、革命的観点にたつべく努力している。
(ヘ) 青砥幹夫は、現在拘置所にあり、日々、ブルジョア政府の仮借ない攻撃の下におかれている。同盟は、この攻撃から彼を防衛し、彼が国家権力に屈服している状態から脱却するよう援助する。
附記
右の特別報告は、一九七三年×月×日、共産同赤軍派臨時総会において採択され、決議された。なお、この決議と同時に、共産同赤軍派結成時の中央委員(臨時総会現在、獄外で再建活動に組織的に従事している中央委員)の、自らの政治的責任を明らかにした辞任も採択され、決議された。
共産主義者同盟赤軍派中央委員会_ (「臨時総会報告集」)


![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)