なぜ、この世の中には結婚という制度があるのか?を、動画にしました。
よろしければ御覧ください。
以下は動画の文字起こしで、かなりの長編ですが添えておきます。
最近は同性婚、LGBTQ理解増進法といったことが言われているが、そんな議論の中で、一番大事なことが無視されていることが、気になる。
人類はなぜ、男女が夫婦となる結婚という制度あるいは風習といったものを作ったのか?ということだ。
キリスト教の『旧約聖書』によれば、人類はその太初アダムとイブ(エバ)から結婚という制度があったことになっているが、これはそのときの様子をちゃんと自分の目で見た人が書いたのではなく、後世に想像で作られたお話に過ぎない。
それも、ユダヤという極く限られ地域の少数の人たちの伝承である。
しかし西洋では、全世界人類の根本がそうだったと信じて疑わず、この前提で論理を展開している。
本当に人類は、その太初から男女間に結婚という制度、風習があったのだろうか?
こんなことを言うと、結婚しなければ子供が生まれないじゃないか、と訝しく思われるかもしれない。
しかし、少なくとも日本や中国では、人類は太初から結婚という制度があった、とは考えていなかった。
中国古典、五経のひとつに、『易経』がある。
易の理論、いわゆる易占いの基本を書いた本だ。
その『易経』の「序卦伝」というところに、結婚、夫婦という単位についての気になる文章があるのだ。
天地有て然る後に万物有り、万物有りて然る後に男女有り、男女有て然る後に夫婦有り、夫婦有りて然る後に父子有り、父子有りて然る後に君臣有り、君臣有りて然る後に上下有り、上下有りて然る後に礼と義を錯く所有り、
大雑把に言うと、
この世界はまず天と地、空と大地ができて、やがてその間にいろいろなものができた。
いろいろなものができて、やがて人間の男女ができた。
男女ができて、やがて夫婦という単位ができた。
夫婦という単位ができて、やがて父子の関係が成立した。
父子の関係が成立すると、それに擬えて君臣の関係が成立し、
さらに君臣の関係が成立すると上下の関係が成立し、
上下の関係が成立することによって、人は礼と義を考えるようになった。
ということである。
夫婦というのは、一緒に暮らす男女のこと、要するに結婚である。
結婚するとその夫婦の間に子が生まれる。
すると、その子を生んだ女性の夫と、その生まれた子の間に、父子の関係が生じる。
しかし結婚すなわち夫婦とならなくても子供は生まれる。
夫婦というのは、女性が夜を共にする相手をひとりに限定することであって、そんなことをせず、女性が不特定多数の男性と夜を過ごしても、子は生まれる。
ただし、この場合、子の父親は特定できない。
だからここでは、ことさら夫婦有りて然る後に父子有り、としているのである。
したがって、夫婦すなわち結婚は、生まれて来る子の父親を特定するために考案された風習、制度だと、ここでは示しているのだ。
それ以前は、夫婦という単位を構成せず、女性は気分に任せて夜毎異なる男性と寝床を共にするとか、大勢の男女が入り乱れて雑魚寝していたので、生まれて来る子の父親は判然とせず、そのために社会には父親という存在がなかった、ということである。
父親が存在しないので、男性には子の親としての地位はなく、責任もないのだから、男性の地位は低く、子を産める女の子だけが大切にされ、必然的に家督は母から娘へと受け継がれ、社会は言うなれば女尊男卑となっていたのである。
このような社会を母権制社会と言う。
対する現在のように、結婚、夫婦ということで、女性が特定の男性とだけ夜を共にして、生まれて来る子の父親を特定し、父系の血統を重視する社会を父権制社会と言う。
それでも少数の部族単位で暮らしていた時代ならば、男性にしても性的には満足できただろうし、特に問題はなかったのだろう。
西洋にそういう母権制社会があったという記録はないようだが、
日本や中国には、そういう部族が居たことを歴史書の片隅に書き残している。
司馬遷の『史記』の「商君列伝」というところに、次のような記事がある。
商君曰く、始め秦は戎翟の教えにして、父子の別なく、室を同じくして居る。
今、我、其の教えを更めて制して、その男女の別を為し、大いに冀闕(きけつ)を築き、營むを魯衞の如くす、
意味は、
中国を統一した始皇帝を生んだ秦は、元々は父子の別がなく、男女が入り乱れて同じ部屋で寝起きする野蛮で未開な国だったが、やがて商君という人が官吏として政治を行うようになると、孔子が居た魯や衞を見倣って、男女の別をきちんとするようにとおふれを出し、その後は父子の関係を大切にする正しい風俗の国になった。
ということである。
とすると、秦だけが野蛮で未開な国だったのだろうか?
いや、そんなことはない。
魯や衞にしても、はるかな昔は、野蛮で未開だったからこそ、このようなことが言えるのだ。
それが、なんらかのきっかけで、周辺の部族よりも先に野蛮で未開な母権制の風習から抜け出し、男女が夫婦となって父子の関係を成立させるようになり、そうなると周辺の部族を野蛮で未開だと見下し、周辺の部族も見下されたことにより、自分たちが野蛮で未開なことに気づき、その風俗を改めて行った、というふうに歴史は流れるものである。
日本でも『日本書紀』の景行天皇四十年秋七月条に、東の蝦夷の様子として、
男女交わり居り、父子の別無く、冬は則ち穴に宿(ね)、夏は則ち樔に住み、
云々とある。
物語では、ヤマトタケルによって蝦夷は滅ぼされるのだが、天皇を中心とする日本は、父子の別があり、父系で相続しているのだから、父権制社会、男女交わり居り父子の別が無いのは、夫婦という単位を有しない母権制社会である。
したがって、この蝦夷征伐は、父権制社会が母権制社会と戦い、母権制社会を滅ぼした、と言っているのだ。
蝦夷は日本人なのか、日本人とは別の民族が日本列島に居たのか、という議論もあるようだが、少なくとも母権制社会が日本列島に存在したからこその記事である。
歴史学の政治的宗教的忖度による建前を気にしないで言えば、日本も、太古はすべからく母権制社会だったのであって、それが何らかのきっかけで父権制社会に移行した、ということである。
おそらく、母権制社会だと、他部族と険悪な関係になったときには、血の繋がりのない他人同士として、簡単に武力衝突、戦争が起きたのではないだろうか。
そんな中で、戦争はなるべく回避したい、何かよい手段はないかと考えて、思いついたのが、生まれて来る子の父親を特定し、父系の血統を重んじる、ということだったのだろう。
父系の血統を重んじれば、双方の有力者同士が結婚して双方の血を引く子を誕生させることで、親戚関係を構築できる。
いわゆる政略結婚である。
親族同士の部族であれば、互いに譲り合える面もできて、武力衝突を回避する有効な手段になったのではないだろうか。
また、父親という存在に価値を見出したことで、男性の地位も向上したのだろう。
『日本書紀』では、奈良時代当時の豪族はすべからく神々や古代の天皇の子孫だと書いている。
皇位継承が父系なのも、女尊男卑の母権制社会に戻らないよう、父権制社会を確かなものにするためだった、と考えれば、すんなり腑に落ちるではないか。
日本で最初に母権制社会からの脱却を試みたのが後の天皇家を中心とする部族で、それに賛同して父権制社会に移行した部族と、あくまでも反対して母権制社会を死守しようとした部族が居て、その間で抗争が続いた時期があり、やがて父権制社会がほぼ日本全国を掌握すると、日本はその始まりから父権制社会であったとするフィクションの歴史書を作成し、その母権制社会側を、蝦夷と表現したのだろう。
司馬遷の『史記』も、そんなふうに歴史物語を作成したものだったから模倣した、ということではないだろうか。
としても日本は、西洋キリスト教社会や中国のような厳格な男尊女卑にはならなかった。
例えば夫婦というのは漢語で、男性である夫か女性である婦の上にあり、男尊女卑を表している。
しかし、夫婦茶碗という言葉があるように、日本では夫婦と書いて「めおと」と訓じた。
「めおと」を漢字で書けば、女夫になる。
女性が男性より上位である。
江戸時代までの日本は、男尊女卑と女尊男卑が入り混じった社会で、家庭内では女性の方が男性より上位だから、女夫=めおと、と訓じたのだ。
恋人同士を意味する妹背(いもせ)という言葉も、女性である妹が上で、背=男性の背中が下で、やはり女性上位である。
男性が背中に女性をおんぶしている様子、といったところだろうか。
また神社では、六月末や大晦日に、延喜式の大祓祝詞に基づいて大祓という儀式が行われるが、この大祓祝詞には、すべての人間を対象とした罪穢れのほかに、男性のみを対象とした罪穢れがあり、その罪穢れを祓うのは、女性の神様三人と性別記載のない神様一人なのだ。
男性が、女性の神様に 罪穢れを祓い清めてください、とお願いできるのは、女性の方が男性よりも上だと認識されているからに 他ならない。
これは、平安時代の延喜年間、醍醐天皇の頃には、善悪の最終決定権は女性にあり、それに基づいて社会は運営するのものだ、という考えがあったからこそのことだろう。
なお現在神社で読まれる大祓祝詞では、罪穢れの具体的な内容は削除している
大正時代に、西洋キリスト教社会に対して恥ずかしい、といったことで、削除されたらしい。
詳細はwikipediaで、天津罪 国津罪 で検索すれば出て来る。
念のために付け加えると、伊勢神宮の御祭神、古事記日本書紀が皇室の御先祖様とする天照大御神も女性の神様である。
が、それはともかく話を母権制社会に戻そう。
中国の雲南省の奥地、ルグフ湖という湖の辺には、かつて、父親という単語すら存在しない母権制社会を営んでいたモソ族という少数民族がいる。
険しい道なき道を数日かけて歩いてやっとたどり着ける場所だったので、近代文明とは無縁の昔ながらの生活をしていた とのこと。
それが、30年ほど前に、中国政府によって車が通行できる道路が開通した。
すると近代文明の凄さに圧倒されつつ、共産主義の下で中国語と父権制の価値観を植え付けられ、今は観光客向け母権制社会を演じている、といったようになったようだが…。
とにかく洋の東西を問わず、人類の太初はすべからく女性が不特定多数の男性と夜を共にすることが当たり前の、女尊男卑の母権制社会だったのであって、それがやがて、例えば文字ができて物事を記録することを覚え、子の名前や性格とかを書き記しているうちに、父親の違いによって違いがあることに気付いたりして、父親というものを意識するようになり、父系の血統を書き残すことに意義を感じるようになると共に、その父系の血統を重視することで、他部族と親族関係になって戦争を回避できる利点も見出すなどして、父権制社会へと移行したのだろう。
そのためには、女性が夜を共にする相手をひとりにすることを納得させる必要がある。
最初は武力で威嚇したり、掟といったものを作ったりなども考えたのかもしれないが、結局あまりうまく行かず、試行錯誤の末に、愛とか貞操といった概念が考え出されたのだろう。
としても、とにかく生まれて来る子の父親を特定するための制度・風習なのだから、一夫一妻でも一夫多妻でもよいのである。
そうして母権制社会から脱却すると、父権制をより強固なものにするために、母権制社会時代を歴史上から抹殺し、人類はその太初から父権制社会だったとする歴史書や宗教書を作成したのだろう。
したがって結婚は、女性が夜を共にする男性を限定し、生まれて来る子の父親が特定できるようにするために作られた風習・制度なのであって、子が生まれない関係、同性婚は、この結婚の本来の意味を言わば冒瀆しているのである。
子が生まれない同性婚を認めれば、結婚の意味が変わってしまい、価値が下がり、そうなると、女性が特定の男性の子を生みたいという気持ちは希薄になり、さらに未婚でも一人で子育てできるように環境を整えれば、やがて多くの女性が結婚を望まないようになるだろうことは、容易に推測できよう。
事実、同性婚や夫婦別姓を認める欧米では、結婚する女性の数は年々減り続け、父親不明の子が増えている。
父親不明の子が増加すれば、社会での男性の地位は下がり、やがて男女平等を通り越して女尊男卑の母権制社会になるだろう。
男女平等は男尊女卑から女尊男卑への通過点に過ぎず、この社会は、女性が生まれて来る子の父親を特定することに価値を見出せば男尊女卑、見出さなければ女尊男卑になる、ということである。
父系の血統の価値が下がれば、家族は母子の関係だけになり、男女間に心の繋がりがなくなり、それが人間関係をギスギスさせ、社会のほんの数%の権力の側の者以外、生き地獄のような暮らししかできなくなろうことは容易に推測できる。
母権制から父権制への移行年代は、地域や環境によって多少違いはあるとしても、とにかく人類の太初は女尊男卑の母権制社会だったのだ。
LGBTQにしても、そもそも日本はキリスト教国ではないので、差別したことはないし、江戸時代までは男色が武士の嗜みのひとつとされたり、陰間茶屋という同性愛の遊び場もあった。
同性愛者は、いわゆる内縁関係で一緒に暮らせばよいだけである。
愛し合う男女でも、結婚なんかしないで、内縁関係のほうがよいと考える人も普通にいる。
宗教的戒律で男女は男尊女卑の下、教会の許可を得て一夫一婦制の結婚をするものだ、としてきた西洋キリスト教社会では、男女の気楽な内縁関係も禁止の、とても息苦しい社会だった。
その呪縛から逃れたくて欧米では、民主主義、人権、男女平等同性婚と、進んだのだ。
ましてLGBTQ理解増進法には、女湯や女子トイレに、身体は男性の女性が入ることによる本当の女性が抱く恐怖や、女子スポーツに身体は男性の女性が参加する理不尽さ、という問題もある。
西洋では、現実の幸不幸よりも論理的整合性が優先し、論理的に完璧な社会に生きることこそ幸福なのだ、という考え方があるらしい。
しかしそれは、宗教を信じ、宗教に縛られて生きることこそ幸福なのだ、ということと同じではないか。
日本人が昔から大切にしてきた書物、『論語』の「先進第十一」には、過ぎたるは猶及ばざるが如し、という有名な言葉がある。
この言葉を当てはめれば、人権も民主主義も、振りかざして行き過ぎれば、顧みないのと同じだ、ということになる。
この世の中には、絶対に正しいと言い切れることは何もないのだ。
易六十四卦はこの世の中の様子を⚋陰⚊陽の記号の組み合わせで表現したものなのだが、どれひとつを取っても完璧に素晴らしいと言える卦はない。
人間には長所と短所があるわけで、そんな人間が作り出すものに、長所だけのものなどあるはずがないのだ。
宗教も思想も法律も、みんな長所と短所があるものだ。
善悪も、取り敢えず善いこと、悪いこと、としたほうが世の中が落ち着く、というだけのこと。
明治維新までの日本はそれでやってきた。
だから幕末にやってきた欧米人は、日本は欧米よりも人々が穏やかで幸福そうだ、という感想を持ったのだろう。
とにかく、人権も平等も民主主義も、長所と短所があり、このLGBTQと女性専用スペースや女性スポーツとの問題によって、人権の短所が炙りだされたわけだ。
そんなイデオロギーに固執せず、これまでの人間が刻んできた歴史を検証して、自由な発想で世の中を考えてほしいと願うばかりである。
誰一人取り残さない、と言われれば、期待してしまう面もあるが、現実にはそんな世の中は有り得ない。
あちらを立てればこちらが立たず、という言葉があるように、誰かが得をすれば、必ず誰かが損をするのが世の中である。
法律が平等に扱っても、必ず得をする人と、その法律が作られたことで損をする人がいるものだ。
とすれば、どういう人が得をして、どういう人が損をするのかを考えて、物事は判断しないといけない、と、江戸時代までは考えていた。
世の中は論理的な整合性を追求するのではなく、適当なところで妥協しないといけないのだ。
大事なのは、公徳心を大切にして、より多くの人々が安心して暮らせる世の中にすること。
それが孔子の願いであり、易を学ぶ者の願いでもある。
過去から現在に至るまで、あらゆる病を治そうと医師たちは奮闘してきた。しかし現代医療が生まれるまでの試行錯誤の過程で、人命を奪いかねない危険な治療法があまた考案され、それらがまかり通っていたのもまた事実だ。
【写真】この記事の写真を見る(5枚)
ここでは、米国出身の医師リディア・ケイン氏とジャーナリストのネイト・ピーダーセン氏による共著 『世にも危険な医療の世界史』 (文春文庫)より一部を抜粋。悪名高き「ロボトミー手術」を生み出した医師たちはいかなる人物なのか――。(全2回の1回目/ 2回目 に続く)
◆◆◆
患者の脳を壊死させたノーベル賞医師
1930年代後半から40年代前半にかけて、アメリカの内科医は崖っぷちに立たされていた。施設に収容されている精神疾患患者が40万人に達したのだ。国内のどこの病院でも、精神障害の患者が病床の半数以上を占めていた。効果的な薬物療法はないうえに、家族や精神科病院にとって、精神疾患患者は精神的にも、肉体的にも、経済的にも大きな負担となっていた。患者はしばしば劣悪な環境で治療を受けていた。が、その状況を救った人物がいる。酒がたんまり入った注射器を愛用する、痛風持ちのポルトガル人神経科学者だ。
1935年、エガス・モニスは、精神疾患患者に新しい精神外科療法を試すことにした。ルコトミーだ(ギリシャ語で「白を切除する」の意。白とは脳白質のこと)。最初に選ばれた患者は、長年のうつ病で疲弊していた女性の入院患者。モニスの手は痛風で変形していたため、別の外科医に指示して、患者の頭頂付近の脳に穴を空けさせ、純粋なエタノールを注射して前頭葉の一部を壊死させたのだ(そう、ワインに含まれるあのエタノールだ。とはいえ、赤ワインをグラス一杯飲んでも脳細胞が死ぬことはないので、ご安心を)。
後にモニスらは白質切断用メスと呼ばれる器具を使用するようになる。白質切断用メスとは便利な金属棒で、これを柔らかい脳に挿入すると、ワイヤループが飛び出して回転し、ほどよく脳をかき回してくれる。プリン液を攪拌する泡立て器というよりも、熟しすぎたメロンの果肉をほじくり出すくり抜き器といった感じだろうか。後にアメリカ人外科医ジェームズ・ワッツが語った話によると、脳の質感は「冷蔵庫から取り出したあとに常温で放置したバターみたい」だったという。
モニスの手術を受けた患者の多くは、術後すぐに精神科病院に送り返されたにもかかわらず、彼はノーベル生理学・医学賞を受賞した。医学界はまたしてもこの術式に恐れおののいたが、モニスはブルクハルト(編注:1888年に脳葉にメスを入れる精神外科手術を行ったスイス人医師)のように表舞台から消えたりはしなかった。それどころか、自説を広めてまわったのだ。
ロボトミー手術を生んだ2人の男
モニスの教えを聞いた医師のなかには、ウォルター・フリーマンもいた。のちにローズマリー・ケネディのロボトミー手術を執刀することになる、アメリカ人神経科医だ。フリーマンは脳神経外科医のジェームズ・ワッツと組んで、モニスの術式をアメリカで広めることにした。2人は1936年に最初の手術を行ったが、患者が生き延び、症状にも改善が見られたことから(患者は不安を訴えなくなり、健康そうにも見えたが「怒りっぽくて、夫に口やかましく言うようになった」)、手術を続行することにした。もっとも、多くの患者は改善していないか、改善してもごくわずかだった。多くは自発的な行動をしなくなり、幻覚症状が治らないケースも多々あった。
この楽観的な2人組は、手術に失敗してもひるむことはなかった。手術をわずか6件こなしたところで、フリーマンとワッツは、自分たちの実績を大々的に宣伝してまわった。『ワシントン・ポスト』紙や『タイム』誌にいくつもの記事が掲載された。彼らが参加する会合には、「ぶ厚い札入れを持った熱狂的な医師たち」がわんさと押し寄せたという。5件目の手術を受けた者は、改善のきざしがなく、さらには癲癇と失禁の症状が出るという悲惨な結末に終わったが、2人の人気が衰えることはなかった。
2人は間もなく有名人となり、フリーマンは自身の術式に「ロボトミー」という名前までつけた。モニスのルコトミーからイメージを刷新することで、フリーマンはこのポルトガル人医師から距離を置き、結果的にロボトミーはフリーマンの代名詞となった。すぐれた宣伝マンであり営業マンでもあった彼は、アメリカ中の精神科病院に宛てて何千通もの手紙や記事を送り、機会があれば積極的にこの手術に関する講演を行った。
1938年、フリーマンとワッツは術式を変更することにした。頭蓋骨のてっぺんに穴を空ける代わりに、こめかみを切開することにしたのだ。モニスが使っていた白質切断用メスは、堅さに問題があった。脳内で折れることがたびたびあったのだ。そこで彼らは細身のバターナイフのような器具を使うことにした。ローズマリー・ケネディもこの器具で執刀されている。ケイト・クリフォード・ラーソンが書いたローズマリーの伝記によると、こめかみに空けた穴から「幅6ミリの弾力性のあるへら」が差し込まれ、「ワッツはそれを脳の奥に押し込み、ぐいと回転させて脳をえぐり取った」という。手術中、ローズマリーは物語を語ったり、詩をそらんじたり、歌ったりするよう指示された。だが、脳を切りすぎてしまったところ、「彼女はろれつがまわらなくなった。そして徐々にしゃべらなくなった」。
こうしてローズマリーの人格は失われた。
術後、彼女は歩くことも話すこともできなくなり、死ぬまで障害者施設に収容されることとなる。無理矢理忘れ去ろうとしたかのように、ケネディ家の手紙にも一切出てこなくなった。だが、このような失敗をしたからといって、フリーマンは手術をやめる気はなかった。それどころか、術式を大きく変更しようとしていた。
眼球の上部からアイスピックを突き刺す
ある日、キッチンの引き出しをかきまわしていたフリーマンは、アイスピックを見つける。完璧な器具じゃないかと彼は思った。鋭利だが鋭すぎず、強くてちょうどいい細さ。モニスの白質切断用メスは何度も折れたし、細身のバターナイフで執刀するときは、脳神経外科医という口うるさい同伴者が必要になる。フリーマンはこうした面倒ごとから解放されたかった。
こうして生まれたのが「アイスピックロボトミー(経眼窩術式)」だ。電気ショック療法を施して患者が意識を失ったのを確認したところで、フリーマンはまぶたを持ち上げて眼球の上部からアイスピックを突き刺し、ハンマーでやさしく叩いて眼窩の薄い骨に穴を空け、脳組織まで刺し貫くのだ(フリーマンはいつもここで手を止めて写真を撮らせた)。それからアイスピックを左、右、上、下へと動かしたあと、もう片方のまぶたでも同じことを繰り返す。術後、患者の目のまわりにはあざができるが、成功すればおとなしい人間に変貌した。
フリーマンの相棒ワッツは、この新しい術式には手術室も自分も不要になると腹を立てたが、フリーマンは気にもとめなかった。今や彼は、国中でこの奇跡の治療法を指導してまわりながら、好きなだけロボトミー手術ができるのだ。さらに彼は自分の車を「ロボトモバイル」と呼び、手術道具を一式詰め込んで旅先でも執刀できるようにした。おまけにロボトミー手術を行った患者を「トロフィー」と呼ぶ始末……。
だが、フリーマンにも反対者がいなかったわけではない。脳細胞を切ってかきまわしただけで、「正常な精神状態」に戻れるはずがないと考える人は多かった。米国医師会(AAA)の会合では、医師らはフリーマンを手厳しく批判した。のちにある内科医がこう嘆いたという。「この手術でゾンビにされた患者の数を見ると、胸が締め付けられる思いだ。今やロボトミー手術は世界中で行われているが、治った患者よりも、精神が破壊された人の方が多いのではないだろうか」
やり方は残酷だったものの、フリーマンは詐欺師ではなかった。精神医学界がかかえる大きな問題、すなわち患者が多すぎて家族と社会の重荷になっていることを解決するのはロボトミーだと、彼は心底から信じていたのだ。
だが、この手術によって再起不能となった患者や、出血多量で死んだ患者は少なくなかった。その多くは女性だ。ロボトミー手術は脳が発達しきっていない子どもにも行われ、一番幼い患者はわずか4歳の幼児だった。知能が低い、または手に負えない性格で「頭痛の種」となる親族や子どもは、ロボトミー手術を受けさせられた。ローズマリー・ケネディと同じように。
ハワード・ダリーは、『ぼくの脳を返して――ロボトミー手術に翻弄されたある少年の物語』(WAVE出版)と題する伝記を執筆した。この本のなかでは、精神的に問題がない12歳の少年が、そのやんちゃな性格ゆえに継母に疎んじられる。6人の精神科医が少年は精神疾患ではないと診断したが、継母は少年にロボトミー手術を受けさせたがった。4人の精神科医が、治療が必要なのは継母の方だと診断したが、結局継母は、フリーマンを説得して少年のロボトミー手術を執刀させた。
最後の犠牲者
フリーマンは1967年に、彼の手術によって女性患者が脳出血で亡くなるまでロボトミー手術を続けた。だが、その時すでにロボトミー手術は寿命が尽きようとしていた。クロルプロマジンと呼ばれる化合物が誕生したからだ(製品名は〈コントミン〉)。〈コントミン〉は史上初の効果的な抗精神病薬で、完璧ではないものの、これを使えばロボトミーよりもはるかに人道的に治療ができた。
今日の脳神経外科学では、科学的根拠に則って厳密できめ細かな治療が行われている。かつての穿頭術のような処置とは比べものにならない。また、複雑な脳の仕組みや精神疾患への理解が深まったことと、複数の分野にまたがるセラピーや投薬治療が可能になったことで、精神医学も大きく変わった。外科手術は今もあるが、ごくまれにしか行われていない。
アイスピックはもう長いこと使われていない。
「誤って患者の睾丸やアシスタントの指を切り落とした」一度の手術で3人の命を奪った有名外科医が、それでも人気だったワケ――医療の世界史 へ続く
リディア・ケイン,ネイト・ピーダーセン,福井 久美子/文春文庫
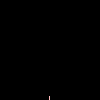 アイヌ学院
アイヌ学院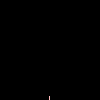 アイヌ学院
アイヌ学院
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)