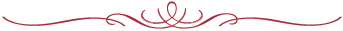
更新日/2022(平成31.5.1日より栄和元/栄和4).2.5日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
|
ここで、「在任中の流れ2、1973年の動き」を確認する。
2012.7.6日再編集 れんだいこ拝
|
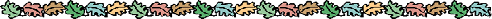
1月、共産党が、赤旗紙上で「料亭政治追放」キャンペーンを開始する。
1.11日、北京に在中日本大使館が38年ぶりに開設される。
1.12日、日銀が、47年の卸売り物価の年間上昇率8.5%と発表。
1.15日、超大型の48年度予算案を決定。一般会計14兆140億円(前年比24.6%増)、財政投融資6兆9248億円(28.3%増)
| 【初の施政方針演説】 |
|
1.27日、第71回特別国会再開。衆参両院本会議で初の施政方針演説。
| 「現代社会は、大きく深い変化を経験しつつある。内に外に変革期の課題は山積している。新しい時代の創造は大きな困難と苦痛を伴うものである。しかし、私は敢えて困難に挑戦し、国民のために政治を決断し実行する」。 |
|
1.27日、米、南.北ベトナム、臨時革命政府の4代表がベトナム和平協定と議定書に調印。
1.28日、48年度経済見通し決定。(国民総生産109兆2500億円、名目成長率16.4%、実質10.7%、沖縄を除く)
| 【中国が東京に在日大使館を開館設】 |
| 2.1日、中国が東京に在日大使館を開館設する。3.27日、陳楚駐日大使が着任した。3.31日、日本の小川平四郎駐中国大使が北京に着任した。
|
2.14日、円が変動相場制に移行。「ドルショック」と云われている。
2.19日、キッシンジャー米大統領補佐官が来日、田中、大平と会談。
| 【商社の投機・買占めなどに関連する緊急質疑】 |
| 1973(昭 和48)年、通産省が行き過ぎた活動の自粛を要請、三菱商事、三井物産、 伊藤忠商事、丸紅、住友商事、日商岩井の6社に対して調査を実施し、
「大手商社の営業活動の実態調査について」とするレポートを公表した。 |
| 3.1日、衆院本会議で、商社による投機・買占めなどに関連する緊急質疑が行われる。 |
| 3.9日、閣議で、「生活関連物資の買占め及び売り惜しみに関する緊急措置法」(投機防止法)を決定。 |
| 4.11日、衆院物価問題特別委が設置され、大手6大商社の経営陣代表を参考人として呼び、土地や商品に対する買い占めや売り惜しみの問題につい ての質疑が行われ、買占め責任を追及した。総合商社で構成する日本貿易会は、これらの批判に対応して「総合商社行動基準」を発表し、「土地・株式・生活関連物資などの取り扱いに当たっては、経営の理念と機能に照らしてとくに慎重に配慮
する」と自主規制を敷いた。 |
| 5.25日、政府が、物価抑制を経済政策の最優先課題とすることを決定。 |
|
7.6日、投機防止法施行。
|
| 8.31日、物価安定緊急対策を閣議決定。 |
| 10.3日、通産省が、灯油元売り13社に「9月末の卸売り価格以上の値上げを認めない」と凍結令。 |
| 10.6日、第4次中東戦争発生(10.24日、停戦)。オイル・ショック発生。 |
| 10.31日、兵庫県尼崎市のスーパーで、トイレットペーパーの買占め騒ぎ発生、全国にパニックが波及。 |
| 11.16日、閣議で、「緊急石油対策推進本部」を設置、石油緊急対策要綱を決定。この頃、全国で洗剤、トイレットペーパーの買いだめが生まれる。
|
| 11.27日、公取委が石油連盟と日石など元売り13社を独禁法違反容疑で強制捜査する。 |
| 11.30日、「実質成長率6%程度」と経済見通しを改定。 |
| 12.18日、石油緊急二法(石油需給適正化法、国民生活安定緊急措置法)を衆院で可決。12.22日、「国民生活安定緊急対策本部」を設置し、田中首相が本部長に就任。 |
3.4日、宮城県知事選で、自民が勝利。
3.6日、アメリカでウォーターゲート事件表面化。
3.6日、田中首相がソ連のブレジネフ書記長に親書を送る。
3.9日、閣議で、「生活関連物資の買占め及び売り惜しみに関する緊急措置法」(投機防止法)を決定。
| 【日華関係議員懇談会が発足】 |
3.14日、自民党親台湾派議員による日華関係議員懇談会(以下、日華懇と略称)が発足した。日本政府は、日中国交正常化以来、中国政府が台湾大使館跡地を使用しないよう中国政府の説得に努めたが、これに失敗し、同大使館跡地を中国政府が使用する権利を認める決定を下した。そして、1973年3
月14 日に、日本政府は、北京及び東京において交流協会を通じて亜東関係協会に対しこの決定を通告した。
3.19日、発足した日華懇が総会を開き、亜東関係協会代表・馬樹禮を招き、大使館跡地問題に関する台湾の立場につき詳細な説明を受けた。また、日華懇は、馬樹禮から台湾の対応策を決定するにあたり、同会と協議し、同会の意向を十分に尊重するという言質を得た。
4.10日、日華懇は、合計3回の総会を開催した上でこの日、「旧中華民国大使館跡地処理問題についての見解」を採択し、日本政府に対し、処理方針を改めるよう強く求めた。結果、日華懇は、政府の決定を覆せなかったが、以後、台湾を一つの独立国家と見做し、台湾との友好関係維持の活動を展開する。 |
3.16日、ウォーターゲート事件が表面化。
3.27日、閣議で、「新国土総合開発法」を決定。
3.28日、首相が、小選挙区制採用を骨子とする選挙法改正準備を指示。
3.29日、アメリカのベトナム介入が終わり、駐ベトナム米軍が全て引き上げる。
3.31日、暫定予算成立。
4.1日、田中首相が党三役と小選挙区制を検討。4.3日、田中首相が、政務次官との懇談で小選挙区制実現への決意を示す。4.4日、政府与党連絡会議に諮る。
| 【地価公示価格が前年比30.9%暴騰】 |
| 4.2日、建設省の地価公示価格が発表される。全国5490地点の全国平均上昇率が前年比30.9%の暴騰を記録した。首都圏に限れば35%も暴騰した。 |
| 【野党の小選挙区制反対の動き】 |
4.10日、社会党の成田委員長が小選挙区制反対を表明。
4.13日、共産党の宮顕、民社党の春日両委員長が小選挙区制反対を表明。
4.17日、公明党の竹入委員長も反対表明。
4.24日、社共公民四党が、「選挙制度改悪・小選挙区制粉砕」を目指す国会内共闘に合意する。 |
4.11日、予算成立。
4.11日、衆院物価問題特別委が設置され、大手6大商社の経営陣代表を参考人として呼び、土地や商品に対する買い占めや売り惜しみの問題につい て質疑が行われ、買占め責任を追及した。これらの批判に対応して、総合商社で構成する日本貿易会は「総合商社行動基準」を発表し、「土地・株式・生活関連物資など
の取り扱いに当たっては、経営の理念と機能に照らしてとくに慎重に配慮 する」と自主規制を敷いた。 衆院物価問題特別委が、大手6商社の代表を参考人として呼び、買占め責任を追及。
4.22日、名古屋知事選で、社共推薦の本山政雄氏が保守現職を破って当選する。
4.24日、日中友好議員連盟結成(会長・藤山愛一郎)。
4.24日、社会、共産、公明、民社の4党が小選挙区制阻止で共闘体制。
4.27日、ウォーターゲート事件が政治スキャンダルに発展。
4.27日、自民党総務会が、小選挙区区割り表を含む公選法改正案を国会提出するよう政府に申し入れる。
4月、田中内閣の支持率は27%に落ち込んでいた。
5.11日、小選挙区制導入への選挙法改正問題で国会審議止まる。5.12日、小選挙区区割り案作成のための「区割り委員会」が発足。国会は5.11日より審議ストップ。5.16日、田中首相が小選挙区制導入を断念。5.22日、区割り案委員会を廃止する。
5.11日、47年の全国高額所得者の上位100名のうちの94名が土地成金。
5.25日、政府は、物価抑制を経済政策の最優先課題とすることを決定。
東京都区部の5月消費者物価が前年同月比11.6%上昇。4月の全国消費者物価も9.4%アップ。
5.29日、中村衆院議長が辞任。後任は前尾繁三郎。増原恵吉防衛庁長官も天皇内奏問題で辞任。後任は山中貞則。
6.2日、石油輸出国機構(OPEC)とメジャー石油会社の交渉で、原油価格11.9%引き上げ。6.11日、リビアが、米国石油会社を国有化。
6.10日、神戸市長の宮崎辰雄が、11月の再選で、社会党の石橋書記長と揃って記者会見し、自民推薦から「反自民・反安保」に鞍替え宣言。
6.17日、参議院青森地方区補選で、自民候補が勝利。同日の大阪補選で、共産党の沓脱タケ子が自民の森下泰を1万4千票差で破る。一議席を争う国政レベルの選挙で、自民党が共産党に負けた初事例となった。
6.22日、衆議員文教委員会が筑波大学法案を、内閣委員会が防衛二法案を混乱のうちに採択。
7.2日、公定歩合を0.5%引き上げて年6%に。4月から3ヶ月間に計3回、1.75%引き上げた。
| 【大平外相の朝鮮民族の祖国統一支持答弁】 |
|
7.4日、大平外務大臣が、衆議院法務委員会で、金日成の提案した「祖国統一・五大綱領」に関する日本社会党赤松勇委員の質問に対し、「案ずるに、朝鮮民族といたしまして祖国の統一ということが最高の念願である、それを具体的に提唱されたことに対しまして評価されたことと私は思います」と答弁した。この頃、韓国との関係では金大中事件や文世光事件での曖昧な対応が結果的に日韓両国の強い反発を招いていた。
|
| 【首相就任1周年発言】 |
7.5日、首相就任1周年。内閣支持率が発足当時の60%台から20%台に急落。田中首相は、記者会見の場で次のように発言した。
| 概要「物価は世界の主要先進工業国の平均以下に抑え、経済成長率と国民所得は先進国の2倍ぐらいにしたい。物価は、今進めている金融引き締めや財政支出繰り延べなどの総需要抑制策を続けていけば、10、11月には抑え得る」と言い切った。(内閣支持率が発足当時の60%台から20%台に急落に対して)国民の声には謙虚に耳を傾けるが、支持率が5%でも1%でも、やるべきことはやる。生産と賃金は先進10カ国の2倍程度の成長を続けながら、物価上昇率は10カ国の平均を下回るようにする」。 |
|
7.6日、投機防止法施行。
7.8日、東京都議選。自民党が善戦し改選前の現有議席51を確保。(自民51、公明26.、共産24、社会20、民社2、無所属2)
|
【自民党内に「青嵐会」結成される】
|
| 7.17日、自民党内に党内若手タカ派の思想的行動集団「青嵐会」が結成される。趣意書に血判を押す。代表世話人には、中川一郎、渡辺美智雄、玉置和郎、湊徹郎、藤尾正行。座長・中尾栄一、幹事長・石原慎太郎、事務局長・浜田幸一。その他中山正あき。衆参31名が結集し、反田中運動を始めた。 |
7.24日、自民党が国会会期の65日間再延長を単独裁決。
7.25日、通産省資源エネルギー庁発足。
| 【田中・大平が日米首脳会談のため訪米】 |
| 7.29日、田中・大平が日米首脳会談のため訪米(外遊交渉3)。7.31・8.1日、ワシントンで田中.ニクソン会談。天皇訪米、ニクソン来日で合意。
|
8.1日、石油精製会社が灯油、軽由、A重油の卸売価格を1キロリットル千円値上げする方針を打ち出す。
| 【金大中事件】 |
8.8日、1971年春の韓国大統領選挙において540万票を集め、現職の朴大統領を僅か94万票の得票差にまで追い詰めた韓国野党の第1人者政治家キム・デジュン(金大中)氏が、白昼(午後1時半ごろ)東京・飯田橋九段下のホテルグランドパレス)から拉致されるという事件が発生した。これを「金大中事件」と云う。部屋には北朝鮮のタバコとバッジが置かれてあり、北朝鮮の仕業に見せかけられていた。当初は金大中氏の生存を悲観視する見方が多かった。しかし、意外なことに若干の傷を負いつつも、事件から5日後の8.13日夜、本人が無事にソウルの自宅に現れた。9.5日、金大中事件で、日本政府が容疑者として金東雲・駐日韓国大使館1等書記官の出頭を申し入れる。韓国側は拒否する。
首謀者はKCIA(韓国中央情報部)部長・李厚洛による事件であったことが判明した。2007.1月、当時の毎日新聞ソウル特派員であった古野貴政氏の著作「金大中事件の政治決着」(東方出版)によると、事件のあった1973年に朴大統領の政敵である金大中のみならず大統領のすぐ下を支えていた四天王ともいうべき有力者がすべて粛清されている。「金大中事件」は、この政治ドラマに関わっていると思われるので簡単に確認しておく。
李厚洛は、学徒動員による旧日本軍の陸軍少尉として終戦を迎え、戦後、米軍が開設した軍事英語学校を卒業、李承晩政権下では大邱陸軍本部の情報局の次長をつとめ、米国へ留学した。その後、教育総本部参謀長、駐米大使館付き武官、さらに韓国における最初の情報部である国防部直轄の「79部隊」の機関長を歴任して、61年に少将で予備役編入、張勉政権下では中央情報委員会研究室長となった。いわば、韓国情報機関の生え抜きのプロフェッショナルである。朴軍事政権の5.16クーデターでは、最初は反革命分子として逮捕された。しかし、初代KCIA部長の金鐘泌により釈放され、最高会議公報室長として朴正熙将軍の配下に入った。革命後の1963年に朴大統領が青瓦台に入城して以来、終始、朴大統領を支える主要人物の1人となり、1963.12月、秘書室長。1970.12月、KCIA部長。朴政権下では、後述する警備室長の朴鐘圭と対立するが、知力・業務処理能力などの力量において、李厚洛は朴鐘圭をはるかに越える大物であり、それを知る朴大統領はこの2人を牽制・競争させて利用したようである。つまり朴政権下のすさまじい権力闘争を生き抜いてきた人物である。1968.8.15日、「国土統一院」設置。1970.8.15日、「8.15平和統一宣言」。
1972.5.2日、ピョンヤンを極秘に訪問して北朝鮮の首相である金日成と実弟のナンバー・スリーの金英柱と会談を行い、7.4日、自主的な民族統一をうたった南北平和統一に関する共同声明の発表まで持ち込んでいる。北朝鮮の金日成首相は、決死の覚悟で単身ピョンヤンに乗り込んだ李厚洛の態度に驚き、「わがほうにこのような勇者はいない」と羨ましがったという話が伝えられている(「朝日新聞」72年12月12日)。李厚洛は北朝鮮との交渉を成功させ、1972.7.4日、南北平和統一に関する共同声明の発表。8.30日、南北赤十字会談。この業績は、1970年代初頭の韓国において朴大統領に次ぐナンバー2と見られていた尹必鏞将軍に高く評価され、尹必鏞と李厚洛という朴政権の後継者の連携ができあがった。
尹必鏞将軍は、1961.5月の朴正熙の軍事革命に中領として参加した陸士8期組の1人であり、朴政権のナンバー2に位置する将軍として、朴長期独裁の基盤をつくった実力者でもある。70年以降は首都警備司令官をつとめており、72年10月の「維新革命」では、ソウル地区の戒厳司令官になった。この尹必鏞将軍が、1973.4月、突然、反逆罪で逮捕されて軍事裁判にかけられるという事件が起こり、韓国国民を驚愕させた。4.28日、普通軍法会議は、首都警備司令官・尹必鏞をはじめとする高級将校11名に、横領・収賄・職権乱用・軍務離脱罪を適用して、懲役15年から2年の刑を宣告した。それに付随して、尹必鏞将軍配下の31名が退役させられて、尹派が軍から一掃された。
この状況下で「金大中事件」が発生している。KCIA(韓国中央情報部)部長・李厚洛自身が策謀したのか、追い落としのための策謀に乗せられたのかが焦点になる。李厚洛は1973.12月、金大中事件によりKCIA部長を解任される。尹将軍、李厚洛に続いて、朴政権を支える四天王ともいうべき警備室長の朴鐘圭も、1974.8月の文世光事件の責任をとって抹殺された。1975.12月、初代KCIA部長で首相の大物政治家・金鐘泌が解任されている。こうして、朴大統領の維新体制側近派が1975年までにすべて抹殺された。尹将軍は、1975.2月、刑の執行停止。1980年春、全、慮政権下で復権、道路公社社長、たばこ人参公社理事長。
1973.10.17日、北朝鮮の侵略の危険性に対して全国に戒厳令を宣布。10.27日、非常国防会議を開き、憲法改正案を議決した(「維新改憲」)。11.23日、維新憲法による初の統一主体国民会議を開催し、第8代朴大統領を終身制として正式に決定した。11.30日、南北調節委員会が正式に発足した。
韓国内の在地権力派と国際金融資本御用聞き派の暗闘を見てとるべきではなかろうか。
|
8.9日、人事院が公務員給与を15.39%(14493円)引き上げを勧告。政府は受け入れた。
8.22日、ロジャーズ米国務長官辞任、ヘンリー.キッシンジャーが後任。
8.28日、公定歩合を1%引き上げて7%に。
8.31日、物価安定緊急対策を閣議決定。
9.7日、札幌地裁の福島裁判長が、長沼ナイキ基地訴訟で、自衛隊違憲判決。
9.14日、ガット東京宣言が出される。
9.18日、国鉄、健保両法案が、参院で修正のうえ成立。
(1973年における年金制度と老人福祉法の大改正)
9.23日、防衛二法成立。
9.25日、筑波学園都市の各法案が成立。
9月、チリのアジュンデ人民連合政権が軍事クーデターによって崩壊。
| 【欧州3カ国とソ連外遊】 |
9.26日~田中首相西欧・ソ連歴訪に出発(外遊交渉4)。9.27-28日、フランス(ポンピドー大統領)。9.30-10.3日(10.1日)、英国(ヒース首相)。10.3-5日(10.4日)、西ドイツ(ブラント首相)と首脳会談。10.7-10日、ソ連。欧州3カ国とソ連訪問。いわゆる「資源外交」を行う。
これについては「諸国友好外遊「自主全方位外交」、新潮流外交」、「資源外交」で詳述する。 |
| 【フランスのポンピドー大統領とパリで会談】 |
この時、田中首相は、フランスのポンピドー大統領とパリで会談し、濃縮ウランの委託加工を決定している。当時の1973年9月28日付け朝日新聞記事が次のように記している。
| 「日本がフランスに濃縮ウランの委託加工を依存することは、米国の『核支配』をくつがえすことをねらったフランスの原子力政策を一段と推進するばかりか、米国の核燃料独占供給体制の一角が崩れることを意味し、世界的に与える影響は極めて大きい」。 |
|
ポンピドゥー仏大統領主催午餐会における田中総理大臣挨拶(1973年9月28日)は次の通り。
ポンピドゥー大統領閣下,御列席の皆様
わが国が19世紀の後半近代化に着手した当時,西欧のすぐれた文物を学ぶため,わが国より幾多有為の青年が欧州に派遣されましたが,彼等は実に数カ月の船旅の後,欧州に到着したものであります。今日,めざましい交通手段の発達は僅か15時間にして東京-パリ間の飛行を可能ならしめております。通信衛星等の出現による通信手段の改善も目をみはらせるものがあります。こうして,現代の交通通信手段の発達は世界の空間的,時間的距離を大幅に縮小し,洋の東西を問わず,一地域に起つた現象は,極めて短時間の中に他の地域に伝達されるようになつています。
世界は今や激しい変革の中にあります。社会体制を異にする国々との交流も段々に進展しており,先進自由世界は急速に一本化の途をあゆんでいるのであります。このような転換期において,瞬時も私の脳裏を離れないのは,今日主要工業国の一員として,応分の貢献と寄与をなしうる立場にある日本が,平和の享受者たるにとどまることなく,平和の創造と世界経済秩序の再建に,いかにして積極的に参画し,その責務を果すべきかということであります。この観点から偉大なフランス,更には欧州全体との関係を濃密にすることは,私に課せられた最大の課題の一つであり,今回私が貴国を訪問するに至つた動機もまたここにあるのであります。
世界は,いま,通商,通貨,インフレーション,エネルギー・資源の枯渇化,地球的規模での汚染の進行,南北問題などに直面しております。これらの世界がかかえている重要な問題,あるいは人類社会に生起しつつある新しい危機は,いずれも一国の力では解決することが不可能なのであります。解決の方途は国際協調に求められるのであります。とりわけ,時代の尖端を歩むフランスとの協調を私はきわめて重視するものであります。したがいまして,今日,ポンピドゥー大統領閣下をはじめ,フランスの指導者と率直な話合いの機会を持ちうることは,私の無上のよろこびとするところであります。
幸い,日仏関係は伝統的に良好であります。百年来,フランスはわが国近代化の先覚でありましたし,文芸,学術の分野においても,わが国に多大の影響を与えてきております。その後も日仏の交流は着実に発展を遂げております。一昨年の天皇,皇后両陛下の訪仏に際し,貴大統領閣下をはじめ,貴国民が示された暖い接遇振りは,まさに日仏友好を象徴するものであります。明年は,貴大統領閣下並びに同令夫人をわが国にお迎えすることになつております。
私は,昨年7月,総理に就任して以来,国際政治の分野では,アジアの平和に暗影をなげかけておりました日中の不正常な関係に終止符をうち,経済の分野では,一層の開放と自由化を指向する一連の措置を強力に推進してまいりました。開放的対外経済政策の追求は,わが国経済政策の重要課題である国民生活の質的向上,物価の安定,産業構造の高度化,国土の総合開発などの国民的要請にも合致するものであります。しかも,私は,成長第一から福祉優先へ,輸出偏重から輸入重視へと経済政策の大転換を進め,外に対しては「平和」内に向つては「福祉」の基本路線を堅持しております。このようにわが国は,アジアにおける平和的な安定勢力として,また,世界にむかつて開かれた
経済社会を形成し,拡大してやまない市場を提供することによつて,世界の繁栄と平和のために積極的な貢献をしてまいります。
日仏両国は,国際社会におけるそれぞれの地位と責務を自覚しつつ,21世紀に向う人類社会の前進のための先駆的役割を果していかねばなりません。そのための日仏協力の可能性は,通商,通貨,エネルギー,公害防止,科学技術等の分野において無限であると信じております。
ポンピドゥー大統領閣下をはじめ,皆様が私共一行に与えられましたご歓待に感謝の意を表するとともに,日仏両国の相互協力を日欧関係の支柱とすることの念願を表明してご挨拶を終りたいと存じます。御静聴有難うございました。 |
日仏プレス・コミュニケ (1973年9月29日)は次の通り。
田中角栄日本国総理大臣は,9月26日から29日までフランスを公式訪問した。
田中総理大臣は,滞仏中,ジョルジュ・ポンピドゥー・フランス共和国大統領と会見した。田中総理大臣は,また,ピエール・メスメール首相と会談した。田中総理大臣は,さらに,フランス全国経営者連盟の首脳と会見した。田中総理大臣は,無名戦士の墓に花輪をささげた。
日本国総理大臣の共和国大統領及び首相との会談は,きわめて親密かつ相互信頼にあふれた雰囲気のなかで行なわれ,当面の主要国際問題及び日仏関係につきつっこんだ意見の交換が行なわれた。これらの会談の結果広範な見解の一致が明らかになるととも に,政治,経済,文化及び科学における両国間の関係を発展させ,かつ,これらの分野における相互間の協議を強化することを双方が希望する旨確認された。
双方は,いろいろな形態における工業諸国相互間の協力及び発展途上国のための工業諸国間の協力に関し意見の交換を行なつた。この点に関し,双方は,通商及び通貨に関する多国間交渉が成功することを共に希望していることを確認するとともに,欧州経済共同体と日本との間の協力が重要なることを強調した。双方は,また,資源・環境等の 工業諸国が直面する新たな諸問題の解決に寄与するため協調することに合意した。
去る5月の両国外務大臣の会談の結果に基づき,かつ,日本政府の要請により,共和国大統領は,レオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザを日本に貸し出し1974年春東京において展示することに決定した。内閣総理大臣は,感謝の念をもつてこれを受諾した。
内閣総理大臣は,日仏交流の促進のためにはフランスにおける日本研究を促進し,か つ,深めることが必要であることを確信し,フランスの大学及び高等教育機関における日本研究の促進に寄与するため,国際交流基金を通じ,三億円相当額の寄贈を行なうとの意向を表明した。共和国大統領は,田中総理大臣のこの発意が両国間の接触,相互理解及び知的交流を奨励するものとしてこれを歓迎した。
双方は,日本国総理大臣の訪問により両国関係の友好的性格が再確認されたことに満足の意を表するとともに,この訪問が両国関係を深めることに貢献したとの確信を表明した。
共和国大統領はこのような見通しに立つて,同大統領が来年4月に日本を公式訪問することをきわめて重要視している旨強調した。 |
|
|
2018.4.2日付け「小長秘書官の証言(16)、さぁ次は英国 北海油田だ(田中角栄のふろしき)」
開けっ広げだった。「こりゃホンモノだ」。1973年9月29日、日本の首相、田中角栄が生まれて初めて「本物」のモナリザを鑑賞した時のこと。角栄はレオナルド・ダビンチの傑作と対峙すると周囲の目もはばからず感嘆した。前日、フランスの大統領ポンピドーと会談でモナリザを借り受けることで同意を取り付けた角栄。「日本の国民に大きなお土産ができた」と気をよくし、もともと入っていた娘の真紀子のルーヴル美術館見学の予定に便乗し、やってきたのだった。それにしても角栄の足は速かった。秘書官の小長啓一はこの時、42歳。角栄とは同じ午(うま)年で一回り若かったが、それでもついて行くのがやっとだった。「本当に田中さんはいつも元気で、せっかちだなあ」。ただ角栄は実際、忙しかった。フランスの後は間髪入れずに英国だ。そこでは北海油田が待っている。「何としてでも日本はこの北海油田の開発に入り込む」。今回の角栄の資源外交の大きな目標が待ち構えていたのだった。すでに海外石油開発社長の今里広記や日本興業銀行相談役の中山素平、それに田中清玄など資源派財界人は英国入りしていた。相手の動向を探り「角栄の資源外交には好意的」との情報を送ってくれていた。角栄もぼやぼやしてはいられなかった。
「フランスではほぼ思い通りの成果を収めた。さあ次は英国だ」――。パリ郊外の日航特別機でオルリ空港を出発したのは29日午後3時、その1時間後にはロンドンのヒースロー空港に到着した。ヒースローでは首相のヒースらが出迎えに来ていた。握手をし挨拶(あいさつ)をするとそのまま宿舎「チェッカーズ」へ。チェッカーズは首相の公式別邸で、ロンドンの北西65キロメートルにあり、19世紀末にアーサー・リーが政府に寄贈、以後、代々の首相の別邸となっていた。賓客だけを泊める。角栄の後にそこに招かれた日本の首相は現在の安倍晋三だけ。安倍までには一人もいない。英国もフランスに劣らぬ厚遇ぶりだった。チェッカーズ別邸ではこんな話がある。別邸の一室にはルーベンスが描いた罠(わな)にかかったライオンの絵が飾ってあるのだが、首相のヒースがその絵を指さしてこう言ったのだ。「絵をよく見てごらんなさい。ネズミが描かれているでしょう。それは元首相のチャーチルがこの別邸を使っていた時、ちゃめっ気を出して描き加えたのです」。さらにこう続けた。「モナリザよりもおもしろくないですか」――。「フランス以上に実のある会談を」というヒースのメッセージだった。
ヒースとの対面を終えた翌9月30日は角栄にとって欧州で初めての休日。外相の大平正芳を伴いゴルフに出かけた。コースはロイヤル(王室)セントジョージ・ゴルフクラブで1887年創設の由緒あるコースだった。外遊はとにかく疲れる。せっかくの休日なら静養していればいいようなものだが角栄は違う。「ストレス解消にはゴルフが一番」と疲れている時ほどコースに出た。もちろん若い頃からゴルフ好きだったわけではない。角栄が新潟から上京、働いていた時には当然、ゴルフなどする余裕はなかった。政治家になってもしばらくは「あんな貴族がするようなものは俺の性に合わない」と取りあわなかった。しかしある時、「やる」と決める。自民党の幹事長の頃だ。そして秘書に「ありったけの本を買ってこい」と命ずる。決めたら徹底的にやるのが角栄。秘書が両手いっぱい、買ってきた本を片っ端から隅々まで読んだ。これで半年だ。次に実践編。レッスンプロにつき手ほどきを受ける。熱心に通い詰めこれも半年。合わせて1年の準備期間を経てコースに出た時には初めからスコア100を切った。角栄の「集中力のなせる技」だった。小長が通産相の秘書官として角栄につき始めた頃にはすでに角栄は相当の腕前になっていた。小長はゴルフは「やるにはやっていた」が、それほどの腕前でもなく最初、角栄が誘ってきた時も「私はご一緒できるほどではございません」と断った。すると角栄は「いやいや、君は『秘書官ゴルフ』でいいんだよ」。角栄が言う「秘書官ゴルフ」とはこうだ。まず、先に角栄が打つ。ボールはフェアウエー真ん中で先まで飛ぶ。次に小長。少しそれて手前にボールが落ちる。普通のルールなら次は小長が打ち、角栄に追いつく。ところが角栄は小長を待たない。小長が「さあ打とう」と思うと角栄はもうとっくに先を歩いている。ボールが大臣にあたれば一大事。危なくて打てるはずはない。では、どうするか。走るのだ。ボールを持って角栄のボールがあるところまで走る。そしてそこからまた角栄と一緒にスタートする。これが角栄の言う「秘書官ゴルフ」だった。「うまい下手は気にしなくていい。何度かコースに出ているうちにうまくなるさ」という角栄の気配りだった。実際、2、3度コースに出た後、小長も無理せず角栄とコースをまわれるようになった。ただ小長の腕は少し上がったが体力はついていかなかった。夏休み、時間があれば角栄は4ラウンド回る。並大抵の体力ではなかった。小長も最初の2ラウンドは何とかついていけたがあと2ラウンドは別の秘書官に交代となった。さて、肝心の英国での角栄のゴルフ。スコアは珍しく悪かった。午前のハーフは55。ドーバー海峡からの強風が角栄の調子を狂わせた。それは翌日から始まる英国との会談を暗示しているかのようだった。=敬称略(前野雅弥) |
|
9.27日、第71特別国会が280日の会期を終えて閉幕。
9.29日、西電力、四国電力、大阪ガスが料金値上げ。
9.30―10.3日、自民党の国会議員訪台団が台湾を訪問した。訪台団(団長・灘尾弘吉)は、台北で蒋経国行政院長と会談した際、「日本が昨年中国を承認したことを謝罪し、日台の協力関係を深めるよう努力すると約束した」とされ、日華懇は帰国後の総会で、台湾訪問後の同会の活動方針を協議した結果、「日中航空協定問題にからんで日台空路の現状を変更することはしない」との方針を確認し、政府に働きかけることを申し合わせた。
| 【在ロンドン・プレス協会主催午餐会における田中総理大臣演説】 |
(1973年10月2日)、「在ロンドン・プレス協会主催午餐会における田中総理大臣演説(欧州との新しいパートナーシップ)」。
イングラム会長,ブラトナー会長,御列席の皆様
このたび伝統ある在ロンドン・プレス協会の午餐会にお招きいただき,会員の皆様にお話しできることは,私の喜びであり,また,光栄とするところであります。ちょうど一年前,ヒース首相がはじめて英国の首相として訪日され,日英交流は大きく前進いたしました。今回は,私がヒース首相の好意ある御招待により,20年振りにな
つかしい英国を訪問いたしましたが,まことに,感慨無量であります。私は,ロンドン到着以来,英国官民の心暖まるおもてなしに深く感謝しております。同時にこの国の整つた市街と緑おりなす山野の美しさにあらためて驚嘆しております。高度工業社会において,これだけ見事に自然と人工とが調和しているのは,この国の人
達の伝統的英知によるものと考えます。
日本は,かつて英国をはじめとする西欧諸国から制度,文物をとり入れ,これに国民の勤勉と創意を加えて成長してまいりました。私どもにとつて西欧諸国は,古き良き師であり友人であつたのであります。こうした西欧との関係は,一時期相対的に稀薄になりましたが,日欧双方とも再び相互の存在価値を見直しつつ,グローバルな課題にとり組んでゆくべきときを迎えているのではないかと考えます。私は,今回の訪欧が日欧関係の転換点となることを希望しております。私は,わが国が「古き友人との新しいパートナーシップ」の確立を求めていることを皆様に訴えたいのであります。
第2次大戦後,すでに四半世紀余の歳月が過ぎました。その間,国際政治は,力による対立の時代を経て,多極化と平和共存の段階へ移行してきました。人類の英知は,明らかに,力による対決の不毛を悟りつつあります。われわれは,力の抑止による均衡以外に,軍備の縮小・管理,政治,経済,文化面での幅広い国際協力の強化により,真に永続する平和を創造してゆかねばなりません。
私は,1年前,毛沢東主席,周恩来首相と会談して,アジアの平和に,暗影を投げかけていた日本と中国との不正常な関係に終止符を打ち,両国間の親善友好関係の基盤を固めました。また,近く訪ソしてブレジネフ書記長と会談し,日ソ関係の改善をはかりた いと念願しております。他方,日本と米国は,政治,経済,社会,文化の各分野において深い関係をもつておりますが,この1年来両国間に存在した経済的摩擦を取り除くことに成功し,いまや日米間の伝統的友好関係は一層強固なものになつております。アジアにおいて,米国,中国,ソ連にとりかこまれた日本は,今後ともアジアにおける平和的な安定勢力としての役割を力強くになつていく決意であります。
ガットとIMFの体制に支えられて,史上かつてみない拡大と発展を記録することのできた世界経済も,いま,通商,通貨,インフレーション,エネルギー・資源,食糧,環境,開発協力などの分野において解決を必要とする問題に直面しております。これら は,われわれにとつて共通の関心事でありますが,いずれも世界的規模の難事業であります。
第2次大戦後の世界の歩みに,主導的な役割を果してきたのは,アメリカでありました。しかし,いまや,欧州や日本は,重要な経済単位として,世界の繁栄の動向を左右する新たな極となりつつあります。これらの難問題は,世界の主要な経済単位の相互協力なくしては解決できないのであります。とりわけ日欧米三者の密接な協力を必要としております。こうした文脈のなかで,去る9月14日,ガット閣僚会議において,新国際ラウンドの開始をつげる東京宣言が採択され,通貨改革と並行して通商の側面から国際経済の新しい体制づくりに向つて画期的な一歩を踏みだしたことは,歴史的にも重要な意義をもつものであります。永続する平和の構造を築くためには,日欧米の三先進工業 地域が相互の利益,相互の約束,および全般的な相互主義の原則に基づき,普遍的,開放的な経済秩序を建設してゆくことが必要であります。
1950年5月9日,当時フランス外相であつたロベール・シューマンは,ライン・ルールとアルザス・ロレーヌ間の無用な競争を物理的にも不可能とするため,「西ドイツ,フランスの生産するすべての石炭と鉄鋼を共同管理機関のもとにおき,この機関は他の 欧州諸国も加盟できるものとする」という提案を行ないました。この提案から2年後の52年にECSCが誕生し,その精神が発展してEECとなり,次いで拡大ECの形成となつたのであります。この歴史的発展の推移をみるとき,巨大な経済単位である欧州は,世界経済の拡大発展と繁栄の維持のためにも,世界に向つて開かれた経済社会を形成してゆくことが期待されております。
今日,主要工業国の一員となつた日本も,たんに平和の享受者にとどまることなく,平和の創造と世界経済秩序の再建に,すすんで参画し,その責務を果すべきものと考えます。第2次大戦後,日本は,復興経済から高度成長経済へ,さらに国際経済へと3段 とびをなしとげる過程で,ひたすら歩んできた成長の延長線上にめざす果実があるものと信じ,1日も早くそれに到達しようと努めてきました。そうした過程でわが国産業の国際競争力と生産力は飛躍的に伸長し,労働者の時間あたり賃金も1ポンド弱になり,欧州諸国の水準に達したのであります。しかし,日本の国土面積は,37万平方キロメートルで,イタリーよりもやや広いのでありますが,その国土のわずか1パーセントの地域に,フランスの総人口をやや下回る数の人間が集中するに至りました。この結果,巨大都市は,過密のルツボで病み,公害,住宅,ごみ処理,物価などの問題が発生しており,半面,農山村は,若者が減つて,成長のエネルギーを失なおうとしております。他方,所得水準の上昇にともない国民の求める豊かさの質も,フローの豊かさからストックの豊かさへ,物質的豊かさから心の豊かさへと,多様化し,かつ高度化しつつあります。こうした情勢に対処して,私は,生産第一,輸出優先から生活優先,福祉充実へと政策の重点を切りかえ,うるおいのある生活空間と多彩な余暇空間を積極的に創造することを内政の最大目標として,日本列島改造を提唱しております。
このように国内経済を充実させ,国民の福祉を増進させてゆくことは,世界とくに欧州の商品,資本および技術に対し,人口1億の将来性にとんだ巨大な市場を提供することを意味するのであります。しかも私は,わが国経済の一層の開放化と自由化を指向する一連の措置を強力に推進しております。この結果,わが国の輸入は激増し,本年上半期の輸入は,前年同期よりも52パーセントも増加いたしました。国際収支の不均衡は,予想を上廻るテンポで是正が進み,2月末190億ドルに達した外貨準備も,9月末には 150億ドルを割つたのであります。わが国は,今後とも,世界に向つて開かれた経済社会を形成し拡大を続ける市場を提供することにより,積極的に世界貿易の拡大,とくに日欧貿易の拡大均衡に貢献してまいりたいと考えます。
飜つて,日,欧関係をみますと,日米,欧米の濃密な関係に比べて,不吊り合いな程に疎遠であります。日欧間の経済交流は,マージナルな規模でしかなく,日欧貿易量は,日本および欧州の貿易量のそれぞれ10パーセントおよび3パーセントにすぎないの であります。また,日本と欧州との関係は,歴史的に長いのでありますが,開けゆく日欧関係の要請をみたしえないコミニュケーション・ギャップが存在するのであります。日本の近代化は,欧州先進国の制度,文物を学ぶことによつて達成され,たしかに個々の日本人の心の中には古き良き欧州のイメージが定着しております。それだけに日本人は,古くからの知識に安住して躍進する欧州の現実の姿に目を向けることが少なかつたと言えましょう。他方,欧州人の日本に関する判断は,過去につくられたイメージの上に構築されているきらいがあり,また日本に関する知識は一握りの知日家の手に委ねられ,広い国民的基盤による交流は限られているのであります。72年に英,仏,独の3国から日本を訪れた旅行者は,7万1千人にとどまつており,日本からこれら3国への旅行者も12万7千人にすぎません。たしかに,両者は,文化,歴史の背景を歴然と異にし,言語の障壁もこえがたいものがあります。しかしながら,お互いが,共通の目的をもつて理解に努め,努力をおしまないならば,その相違を克服できないはずはありません。このためにこそ,ひとり首脳同士だけではなく,政府,言論人,民間経済人,学者など国民各層において間断なき,かつダイナミックな対話を行なう必要があります。私は,このような見地から,英国に対しては,英国の大学における日本研究を促進するためのささやかな貢献として,国際交流基金を通じて,3億円に相当する基金の贈与を行ないたいと考えます。
日英貿易関係は,英国政府のめざましい努力及び業界間の交流によつて最近徐々にではありますが改善の方向に向つております。ここ1~2年における日英両国政府首脳間の交流は,目を見張るものがあります。また,先般東京に英国トレード・センターが開 設され,ケント公御夫妻が開所式に臨まれたことは英側の対日輸出努力を盛り上げる上で非常に印象的でありました。
日英両国の接触は,遠く永禄7年の英国船の来航,慶長5年のウイリアム・アダムス の渡来にまでさかのぼるのであります。この絆は,最近,ヒース首相の来日を契機として目に見えて強化されつつあります。
今後,日本,欧州は,相互の交流,協力関係を,量,質ともに拡大するとともに,もてる経済力,技術力を開発途上国に対する経済協力に投入し,本当に役に立つ援助を誠実に,かつきめ細かく実行することが必要であります。そして,われわれは,公正で合理的な国際分業の再編成を求める開発途上国の声に耳を傾け,互恵平等,自他ともに繁栄できる道をさぐりながら,これら諸国の追加的利益の確保に協力していかねばなりません。
歴史家アーノルド・トインビー博士の言をまつまでもなく,今日,われわれは,祖国に対する忠誠心と人類に対する新たな忠誠心の二つをあわせもつことが必要であります。地球的規模での環境汚染の拡大,エネルギー・資源の枯渇化の懸念など,人類社会 に生起しつつある重要問題は,いずれも「自分さえよければ……」という利己的な態度では決して解決できないのであります。環境問題を克服するためには,大気や水が世界の共有物であり,それを汚すことは人類の危機につながるとの認識が必要であります。 また資源問題も,狭いナショナリズムにとらわれず,資源の効率的活用と公平な分配をめざして協力し協調してゆかねばならないと思います。このような全人類の連帯意識は,一朝一夕には生まれるものではありませんが,いま大切なのは,そのためのあらゆ る努力であります。日欧米は,国際社会におけるそれぞれの地位と責務を自覚して,21 世紀に向う人類社会の前進のために,そしてまた,国際社会の協調と融和のために,先駆的かつ主導的役割を果してゆく必要があると思います。私は,これこそ多極世界にお ける日欧の新しい役割であると信じて疑いません。御静聴有難うございました。 |
|
(1973年10月3日)、「日英共同声明」は次の通り。
田中角栄日本国総理大臣は,英国政府の招待により9月29日から10月3日まで英国を公式訪問した。この訪問は,1972年9月のヒース首相の日本訪問に対する答礼としてなされた。田中総理大臣には大平外務大臣が随行した。
田中総理大臣及び大平外務大臣は,10月2日女王陛下に謁見を賜わつた。両国首相は,女王及びエディンバラ公が1975年の春に国賓として訪日されるようにとの招待に対しこの招待をよろこんで受諾する用意がある旨述べられたことに大いなる満足の意をもつて留意した。
両国首相は,9月29日,10月1日及び2日に会談を行なつた。10月2日田中総理大臣は,デービスEC問題担当相及びサー・ジェフリー・ハウ貿易・消費者担当相と個別に会談を行なつた。10月2日大平外務大臣とサー・アレック・ダグラス・ヒューム外務大臣は,第10回日英定期協議を行なつた。
これらの会談は,率直かつ友好的零囲気のもとに行なわれ,両国間に存在する友誼と 信頼の関係を改めて示した。
両国首相は,国際社会が直面している主要課題は全ての国家及び社会が安全保障の増大及び繁栄の増進を享受することができる条件を確保することにあるということについて合意した。両国首相は,かかる条件を成就するための助力にあたつて協力することを誓つた。両国首相は,更に既に両国間に存在する緊密な友好の絆を強化することを誓つた。
両国首相は,両国が共通の関心を有する広範囲の問題について討議した。両国首相 は,すべての先進工業民主主義諸国の間で友好な関係及び緊密な協力を維持することの重要性を強調した。この関連で,田中総理大臣は,先進工業民主主義諸国間の将来の協力の指針となるべき諸原則の策定の必要性に対する理解を表明した。同首相は,日本と英国その他の欧州共同体加盟諸国との間のこの問題についての緊密な協議が望ましい旨述べた。ヒース首相は,この一般的問題に関し米国と欧州共同体加盟諸国との間及び北大西洋同盟において行なわれている作業を説明した。
両国首相は,欧州及びアジアにおける緊張緩和に向つての前進について意見を交換した。ヒース首相は,欧州安全保障協力会議及び中央ヨーロッパにおける相互均衡兵力削減のための来たるべき交渉に関する最近の進展について田中総理大臣に説明した。田中総理大臣はインドシナ及び朝鮮における最近の進展に対する日本政府の態度について述べた。両国首相は,パリ協定の忠実な実施がインドシナにおける安定しかつ永続的な平和の確立をもたらし,かつ朝鮮における対話の継続が緊張緩和と朝鮮半島の究極的再統一に貢献するようにとの希望を表明した。
両国首相は,エネルギー資源などの重要供給物の調達分野で両国が直面している問題に関し,意見を交換した。両者はこの分野での世界的協力が必要であるということにつき同意した。この関連で,田中総理大臣は,日本が北海石油開発事業に参加し,これと併せて英国内の開発地域に投資することを希望する旨述べた。ヒース首相は,英国政府の関心を示し,田中総理大臣の提案が進展を見ることを希望する旨述べた。両国首相は,また,原子力の分野での協力につき討議した。両者は,これら双方の問題につき近く政府レベル及び関係産業界の間で話合いが行なわれるべき旨合意した。
ヒース首相は,田中総理大臣に欧州共同体及び共同体加盟国としての英国の役割と責任について概説した。同首相は,1970年代の末までに加盟国間の関係の性格を変えようという共同体加盟9カ国の基本的目的及び国際問題について共同体に独自の役割を与えようという加盟国の意図を強調した。同首相は更に共同体の目的が欧州の経済的発展にのみ限定されるものでないことを強調した。田中総理大臣は,共同体の拡大及びその現在の目的の追求が国際的安定と繁栄に寄与するようにとの希望を表明した。
両国首相は,現在貿易と通貨の分野で行なわれている多角的交渉が成功することの重要さを再確認した。両国首相は,9月に開催されたガット閣僚会議で発表され,新国際ラウンドを発足させることとなつた東京宣言を歓迎した。両国首相は更に国際通貨制度の改革に関しなされた進展及び1974年7月31日までに未解決の意見の相違を解決しようとのナイロビでの各国閣僚の約束を歓迎した。両国首相は,これらのいずれの事業においても早期かつ建設的な結果が確保されるようすべての関係国と協調して努力を行なうことを約した。
両国首相は,また,1972年9月の日本における前回会談以来の両国間における政治,経済関係の進展振りを顧みた。両者は,両国の閣僚,国会議員及び産業界指導者の行なつた幾多の訪問に満足の意を表明した。両者は,両国間で広範囲にわたる貿易の拡大と投資の増大を促進するための努力が引続き必要であることを再確認した。
この関連で田中総理大臣は,東京における英国トレード・センターの設立など,英国の対日輸出の奨励のため英国政府が最近とつた活発な措置に対し歓迎の意を表明した。一方,ヒース首相は,日本への輸出及び投資を奨励するために過去一年の間に日本政府がとつた措置に歓迎の意を表明した。
田中総理大臣は,両国間の交流を拡大し,相互理解を強化することを希望し,日本国政府が英国の大学における日本研究を促進するために邦貨3億円に相当する英ポンド貨の基金を国際交流基金を通じ贈与する意図であることを表明した。ヒース首相はこの寛大で想像力にとむ意思表示に対し感謝の意を表明した。 |
|
10.3日、通産省が、灯油元売り13社に「9月末の卸売り価格以上の値上げを認めない」と凍結令。
|
(1973年10月4日)、ブラント・ドイツ連邦共和国首相主催晩餐会における田中総理大臣挨拶
連邦首相閣下,令夫人,ご列席の皆様
本夕は首相閣下のお招きを受けましたのみならず,只今はブラント首相から誠にご懇篤なお言葉を戴きましたことを光栄に存じます。
このたび貴国の地を踏みまして以来の貴国官民の心暖まるご厚意,そして本日の貴首相との卒直かつ建設的な意見の交換を通じて,貴国とわが国を結びつける伝統的な友好のきずなが,いかに強固なものであるかを改めて確認した次第であります。
それにつけても想起されますのは,一昨年秋,天皇,皇后両陛下が貴国を公式訪問された際に,貴国政府及び国民各層よりたまわつたご懇切なご歓待でありまして,この機会をかり日本国民を代表して心からお礼申し上げます。
私自身も20年前に初めて貴国を訪問し,このボンをはじめとする貴国の主要都市を視察して,祖国復興のために挺身しておられる貴国国民のご努力とその成果に深い感銘を受けたのでありました。有名なアウトバーン,ライン河にかけられていた千メートル・ 1スパーンの吊橋,ハンプルグにおける戦災復興住宅の建設ぶりなどは,いまでも脳裏に鮮やかであります。そのときの体験は,わが国の国土総合開発に生かされており,また私の提唱している日本列島改造論の基礎ともなつているのであります。
今回貴国を再び訪問し,その後20年間の貴国の発展ぶりに改めて感銘と敬意の念を覚えたのであります。
今や両国は,共に自由世界の一員として,共通の価値観と理想を分ち合いつつ,世界平和促進のために協力する立場にあります。今回貴国が国際連合に加盟されたことは,このような協力の場が更に一つ増えたことを意味するものであり,ここに衷心からお祝いを申しのべます。
しかしながら貴国とわが国の協力は,政治の分野のみにとどまるものではありません。経済の分野での交流の拡大と促進こそ,われわれの将来にかかわる共通の課題なのであります。貴国は,西欧におけるわが国の最大の貿易相手国であり,両国間の貿易量
は年々拡大の一途を辿つております。しかしながら,その規模は両国の持つ経済力に対応するものとは言えず,なお相互に拡大することが必要であり,かつ可能と考えるものであります。
貴国の一部には最近,両三年の日独貿易のインバランスや,わが国の特定商品の急激な輸出増加に危惧感を持つ向もあるかのようであります。しかし,これらの問題は長期的な発展の過程における一時的な現象であります。たしかに,日独貿易は71年以来,日本側の出超となつていますが,53年から72年までの20年間のバランスでみると,西ドイ
ツの方が8億ドル余の出超であります。しかもわが国は,内政の重点を,生産第一,輸出から福祉優先,輸入拡大へと転換しております。また,わが国経済の一層の開放化と自由化を指向する一連の措置を強力に推進しております。したがつて,人口1億を有し,GNPも貴国とほぼ同じ規模である日本は,ドイツ商品,資本,および技術にとつて魅力ある市場であります。両国が,自由貿易の原則にのつとつて貿易の拡大均衡と秩
序ある発展に努力する限り,必ずや問題は解決されるものと確信いたします。
われわれ両国は,この他,先進工業国としての数多くの共通の課題に直面しておりま す。それは,通貨,資源,科学技術の諸問題であり,また現代文明への挑戦である環境問題であります。われわれは,これらの諸領域において,新しい国際経済秩序のために応分の貢献を行なわねばなりません。
今回の貴国訪問が,自由と民主主義という共通の理念で結ばれている日独両国の協力と伝統的な友好関係の一層の強化の契機となりうるならば幸甚これに過ぐるものはございません。
首相閣下,ご列席の皆様 ここに杯を挙げて連邦大統領閣下,連邦首相閣下ご夫妻のご健康とドイツ国民の幸多き将来と繁栄を祈念いたします。 |
(1973年10月5日)、「日独プレス・リリース」
田中日本国総理大臣は,ブラント・ドイツ連邦共和国首相の招待により,1973年10月3日より,7日までの日程でドイツ連邦共和国を公式訪問中である。
田中総理大臣は,滞在中ハイネマン大統領に謁見し,ブラント首相と会談した。大平日本国外務大臣は,10月5日,シェール独外相と第6回日・独外相定期協議を行なつた。
会談は,両国間に存在する伝統的な友好関係を反映して,極めて良好な雰囲気のうちに進められ,国際情勢一般について率直な意見の交換が行なわれた。その際,田中総理大臣は欧州における平和秩序の確立と欧州統合を指向する連邦政府の努力に深い理解と敬意を示し,また,ブラント首相は,アジア・太平洋地域の安定と発展に寄与せんとする日本政府の努力を心から歓迎した。
ブラント首相は,日本政府がドイツ民族の一体性に関する連邦政府の態度に理解と支持を与えていることに対して,田中総理大臣に感謝の意を表明した。
田中総理大臣とブラント首相は,将来の欧州共同体と日本の関係及び先進工業民主主義国の緊密な協力について建設的な関心をもつて意見を交換した。田中総理大臣とブラント首相は欧州共同体,日本及び米国の共同のイニシアティヴに基づき,最近東京で開始された新国際ラウンドが成功裡に終結することが世界貿易の自由化の促進と拡大及び諸国民の生活水準の向上にとり重大な意義を有することにつき意見の一致をみた。田中総理大臣とブラント首相は,その際,発展途上国の利害に特別の考慮が払われなければならないことを強調した。また同時に国際通貨制度改革のための交渉が順調に進展する必要性が強調された。また経済分野のほか,文化,学術,科学技術,環境の諸分野での交流が益々発展しつつあることに満足の意が表明されるとともに,これらの諸交流および世界平和に寄与するための両国の協力が引続き強化される必要性が確認された。
両国政府首脳は,世界的な需要の増大にかんがみ天然資源及びエネルギー供給問題の重要性を強調した。双方は天然資源及びエネルギー供給の分野における協力の可能性を検討する合同委員会を設立することに合意した。この委員会には後日関連産業の代表も招請されることができる。
田中総理大臣は,両国間の相互理解を増進することを希望し,ドイツの大学における日本研究を一層促進するために,日本国政府が邦貨3億円に相当するドイツ・マルク貨の基金を国際交流基金を通じ,贈与する意図を表明した。
田中総理大臣は,ブラント首相を日本への公式訪問に招待し,ブラント首相はこれを受諾した。訪日の期日は追つて決定される。 |
|
|
| 【第4次中東戦争発生、「第一次オイルショック」発生】 |
| 10.6日、第4次中東戦争発生(10.24日、停戦)。10.12日、サウジアラビアのファイサル国王が、「イスラエルに武器を売れば対米石油輸出を停止する」と警告。10.14日、サウジアラビアのファイサル国王が、石油戦略発動を示唆。10.16日、ペルシャ湾岸6カ国が、原油価格の21%の値上げを一方的に宣言。オイル・ショック発生。第4次中東戦争の影響であった。10.17日、アラブ石油輸出国機構(OPEC)が緊急閣僚会議で、石油の原油生産削減と原油価格の大幅引き上げ(中東原油の公示価格をアラビアン・ライトで、1バーレル3.011ドルから5.119ドルへと約70%引き上げ)を発表。「石油戦略」を決定。10.20日、アラブ産油国が、イスラエル支持国への一方的石油輸出停止を決定。イスラエルを支援する西側諸国を牽制した。10.23日、国際石油資本の日本に対する原油価格値上げ、供給削減通告が為される。オイル・メジャーのエクソンとシェル両社が原油価格の30%引き上げを通告。他のメジャーもこれに追随し、10.25日には10%の供給削減を通告するという事態となった。この国際石油資本の日本に対する原油価格値上げ、供給削減通告を「オイル・ショック」という。これにより1バーレル2ドル40セントだった原油価格が一ぺんに4倍に跳ね上がった。 |
|
| (10月8日)、ソ連側主催午餐会における田中総理大臣挨拶 (於クレムリン大宮殿・グラナヴィータヤの間) |
ブレジネフ書記長閣下 ポドゴルヌイ議長閣下 コスイギン首相閣下 御列席の各位
ただ今は,御懇篤な御挨拶を頂戴し,厚く御礼申し上げます。私は本席をお借りしてあらためて私に対するソ連政府のご招待に対し心から感謝申し上げます。
かえりみますれば,今から17年前の同じ10月,日ソ間に外交関係が回復されて以来,両国の関係は年を追つて緊密なものとなつてまいりました。しかし,日ソの最高首脳による相手国への訪問はこれまで実現をみるに至りませんでした。変動する世界情勢の中にあつて,それぞれの国の最高責任者が膝を交えて,相互間の問題のみならず,共通の関心事である世界平和の問題について隔意なき意見交換を行なう必要性は益々増大しております。私がこのたびソ連政府のご招待を欣然と受諾し,モスクワにまいつたのもひとえにこのような理由によるものであります。わが国は,体制の垣根を越えてすべての国との間に友好関係を増進し,広く人類の平和と繁栄に寄与することを外交の基本としております。とりわけ隣国である貴国との間に,内政不干渉及び互恵平等の基礎の上に善隣友好関係を打ちたてることは,わが国が一貫して追求する目標であります。
1956年に国交が回復されて以来,日ソ間の関係は,幅広い分野にわたり,当時何人も予測できなかつたような急速な発展を遂げてまいりました。貿易の分野でもわが国は,貴国の最大のパートナーの一つとなるに至りました。更にシベリア開発協力につきましては,日ソ間に既にいくつかのプロジェクトが実施されているほか,より大きな規模の計画についても話合いが進められております。
しかしながら,私は,これをもつて満足するには未だ十分ではないと考えております。日ソ両国は,単に隣国であるにとどまらず,経済的にも稀にみる相互補完の関係にあります。われわれが双方のたゆまぬ努力により真の相互信頼を築き上げることができるならば,日ソ関係は,より一層明るい展望に満ちていることは疑問の余地がありません。
私は,両国関係の将来について述べるとき,やはり未解決の平和条約の締結の問題に触れざるをえません。 平和条約締結の交渉とは,ブレジネフ書記長閣下がソ連邦結成50周年記念式典において述べられた通り,「第二次大戦の時から残つた懸案を解決し,われわれ両国の関係に条約的基礎を置くこと」を目的とするものであります。日ソ平和条約の締結こそは両国国民の総意であり,われわれ両国の指導者に課せられた厳粛な課題であると考えます。私はこの問題は,双方が相互理解と信頼に基づいて臨むならば必ずや解決される問題であり,また解決されなければならないと信じます。それによつて日ソ両国がゆるぎない善隣友好関係を確立することは,日ソ両国民の共通の利益に答えるばかりでなく,極東,ひいては世界の平和と繁栄に役立つと信じて疑いません。今日の国際社会は,人類の英知が創り出した科学技術の進歩それ自体によつても,新たな転機を迎えようとしております。かつてわが国からモスクワに赴くには,はるばるシベリア鉄道によつて半カ月もの旅を重ねたものでしたが,現在,空の旅は,その距離を僅か9時間に縮めました。このような情勢下にあつて,国際社会におけるコミュニケーションの拡大と相互依存関係の高まりは,言わば時代の要請であり,歴史の必然でもあると申せましよう。また,人類の英知は,力の対決が最早不毛であり,時代遅れのものであることを悟りつつあります。今やわれわれ人類は,国民生活の向上,食糧,環境,資源,発展途上国に対する協力,人間復権の新しい文明社会の創造などの解決すべき困難な問題に直面しております。現在,世界が抱えているこれらの諸問題のどれをとっても一国のみで解決することはできないのであります。日本とソ連のごとく,世界有数の成長を遂げた国は,硬直することなく、独断をかなぐりすて,柔軟,かつ積極的に対応していく責務があります。私は,日ソ両国が相互の関係の完全な正常化の上に立って,人類の理想の実現のため,それぞれの立場から建設的な役割を果していくことを強く願うものであります。終りに臨み,私共に対し,関係各位から示されたあたたかいおもてなしに対し深い感謝の意を表するとともにここに皆様のお許しを得てブレジネフ書記長閣下,ポドゴルヌイソ連邦最高会議幹部会議長閣下及びコスイギンソ連邦大臣会議議長閣下の御健康,御列席のソ連の友人各位の御健康,更に日ソ関係の発展並びにソ連邦共和国とその国民の一層の繁栄をお祈りして皆様とともに乾杯したいと思います。乾杯-
|
(10月9日)、日本側主催午餐会における田中総理大臣挨拶 (於 レーニン丘政府迎賓館)
コスイギン首相閣下御列席の各位
御多忙のおりにもかかわらず,コスイギン首相閣下他ソ連党・政府の首脳の方々,並びに当国の著名な方々をお迎えして,ここに午餐を共にする機会を得ましたことは,私の大きな喜びとするところであります。
昨日私のあいさつの中で指摘いたしました通り,今回のソ連訪問の最大の眼目は両国最高指導者間の対話の開始でありました。
私は右に際し,ブレジネフ書記長閣下をはじめ,ソ連党・政府首脳の方々と日ソ間の最大の懸案である領土問題の解決を含む平和条約の締結をはじめ,両国間の諸問題につき卒直な意見交換の機会を持つたことに重要な意義を認めております。
昨日,ブレジネフ書記長閣下は,私どもを招いた心暖まる午餐会の席上,平和条約の締結が日ソ関係発展のためのより強固な基礎となるとの趣旨を述べられました。私は書記長閣下の深い御理解に対し,改めて敬意を表するものであります。
何故ならば,日ソ千年にわたる真の善隣友好関係の確立を心から願うものにとつてこの問題をさけて通ることは出来ないと考えるからであります。くり返して申すまでもなく,わが国にとつて平和はかけがえのないものであります。
戦後わが国の国民総生産は,実質で年間10%以上の成長率を維持し,米ソにつぐ地位を占めるに至りましたが,これは働き蜂のような日本人一人一人のバイタリティに加え,歴代のわが国政府が効率的な経済運営を行ない,もてる力をすべて平和な国民経済発展のために集中してきた一貫した政策のたまものによるものであります。
平和国家に徹し,世界の平和と福祉に貢献することはわが国不動の方針であります。私は,かかるわが国の真摯な姿勢に対しソ連の皆様方の充分な御理解を得たいと思います。終りに際し相互理解と信頼に基礎を置く日ソ間の永久の善隣友好関係の確立を祈念しつつ,また,コスイギン首相閣下及び御列席の各位のために杯をあげて乾杯したいと思います。 |
|
| 【日ソ共同声明発表】 |
10.10日、訪ソ。日ソ共同声明発表。北方領土返還問題は未解決であり継続交渉に委ねられることを確認させた。 これについては「日ソ平和・北方領土返還交渉」で詳述する。
日ソ共同声明(1973年10月10日 モスクワにおいて)
田中角栄目本国内閣総理大臣は,ソヴィエト連邦政府の招待により,1973年10月7日から10日までソヴィエト連邦を公式訪問した。田中総理大臣には,大平正芳外務大臣及びその他の政府職員が随行した。田中総理大臣及び大平外務大臣は,L・I・ブレジネフソ連邦共産党中央委員会書記長,A・N・コスイギンソ連邦共産党中央委員会政治局員兼ソ連邦大臣会議議長及びA・A・グロムイコソ連邦共産党中央委員会政治局員兼ソ連邦外務大臣と平和条約締結交渉を含む日ソ間の諸問題及び相互に関心を有する主要な国際問題について率直かつ建設的な話合いを行なつた。また,田中総理大臣及び大平外務大臣は,N・V・ポドゴルヌイソ連邦共産党中央委員会政治局員兼ソ連邦最高会議幹部会議長と会見した。大平外務大臣とグロムイコ外務大臣との間に第三回の定期協議が行なわれた。
友好的雰囲気の中に行なわれたこれらの会談において,双方は,日ソ関係が,1956年の日ソ共同宣言により外交関係が回復して以来,広範な分野において順調な発展を遂げており,特に,近年においては,政治,経済及び文化の面において両国間の関係の進展が著しいことに満足の意を表明した。双方は,内政不干渉及び互恵平等の原則に基づき日ソ間の善隣友好関係を増進することは,日ソ両国民の共通の利益に応えるのみならず,極東ひいては世界の平和と安定に大きく貢献するものであることを認め,このために両国関係の一層の発展に努力する旨の決意を表明した。
1 双方は,第二次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して平和条約を締結することが両国間の真の善隣友好関係の確立に寄与することを認識し,平和条約の内容に関する諸問題について交渉した。双方は,1974年の適当な時期に両国間で平和条約の締結交渉を継続することに合意した。
2 双方は,日ソ間経済協力の拡大の方途につき意見交換を行なつた。その結果,双方は,互恵平等の原則に基づく両国間の経済協力を可能な限り広い分野で行なうことが望ましいと認め,特に,シベリア天然資源の共同開発,貿易,運輸,農業,漁業等の分野における協力を促進すべきである旨意見の一致をみた。双方は,日ソ及びソ日経済協力委員会の活動を高く評価した。このような両国間の経済協力の実施に当たつては,双方は,それぞれの政府の権限の範囲内で日本の企業(又はそれらによつて組織される団体)とソ連邦の権限ある当局及び企業との間で契約が締結されることを促進すること,かかる契約の円滑な,かつ,適時の実施を促進すること及び右契約の実施に関連して政府間協議が行なわれるべきことについても意見の一致をみた。また,双方は,特にシベリアの天然資源の共同開発に関連して,日ソ間の経済協力が第三国の参加を排除しないことを確認した。
双方は,日ソ漁業に係る諸問題の解決の方途につき意見交換を行なつた。その結果,双方は,長期かつ安定した北洋漁業の確立のため,漁獲量を定める問題を含め,適切な措置をとることに合意し,両国主管大臣間の協議を可及的速やかに開催することにつき意見の一致をみた。
双方は,別途合意される水域における日本人漁夫の操業についての従来から開始されている交渉に関し意見を交換し,この問題についての交渉を継続することに合意した。
双方は,科学技術の分野における政府間の交流の拡大を有益と認め,10月10日日本側大平外務大臣とソ連側グロムイコ外務大臣との間で科学技術協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定が署名されたことを高く評価した。
双方は,文化の分野における交流の順調な発展を満足の意をもつて指摘し,10月10日に両国の外務大臣の間で署名された学者及び研究者の交換,公の刊行物の交換,並びに広報資料の配布に関する取極の意義を高く評価した。
双方は,自然の保護及び人間環境の保全の分野における日ソ間の接触の増大が必要であることを認め,このための協力の第一歩として,10月10日両国の外務大臣の間で渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類,並びにその生息環境の保護に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約が署名されたことを高く評価した。
双方は,高度に効率的なエネルギー源の開発が世界的なエネルギー問題の解決に貢献することができることを認識して,原子力の平和利用の分野における協力を拡大する必要性を認めるとともに,その第一歩として,両国の科学者及び技術者の交換,並びに情報の交換を行なうことが有意義である旨強調した。
双方は,各層にわたる日ソ間の人的交流を積極的に評価し,両国間の一層幅広い交流を奨励すべきである旨意見の一致をみた。 双方は,1966年に両国外務大臣間で合意された両国外務大臣間の協議の定期的な実 施に賛意を表明した。
ソ連側は,人道的考慮に基づき,ソ連邦に居住する未帰還邦人の日本への帰国及び 従来から実施されている日本人墓地への遺族の墓参に関する田中総理大臣の要請に関して,今後もこれらの問題を然るべき注意をもつて検討する用意がある旨を確認した。
3 双方は,現在の国際情勢の主要な,かつ,双方が関心を有する諸問題につき意見を 交換した。双方は,近年国際情勢が全体として緊張緩和の方向に向かつていること及び異なつた社会体制を有する国家間の関係正常化が一層進展したことに満足の意を表した。同時に,双方は,現在世界の若干の地域で紛争が続いていることに憂慮の念を示すとともに,すべての国が,国連憲章に従い,その相互関係において紛争を交渉により解決するとの原則及び武力による威嚇又は武力の行使を慎むとの原則を遵守する必要性のあることを強調した。
双方は,国際間の緊張緩和を一層促進し,永続的な世界平和を実現することがすべ ての国民の利益に係わる現代の根本問題であるとみなしている。また,双方は,国際 連合が世界平和の維持と国際協力の促進のため重要な貢献を行なつていることを認め,同機構の有効性を強化するため引き続き努力することにつき意見の一致をみた。
双方は,世界の恒久的平和を確立するために,有効な国際的管理の下における軍縮の達成,特に核軍縮の早期実現の重要性を認識して,この目標に向かつて努力する旨 を表明した。
双方は,戦略兵器制限交渉(SALT)関係諸合意及び核戦争防止に関する米ソ協定を含む軍備管理及び紛争の回避の分野でなされた前進に対し満足の意を表明した。
双方は,アジア情勢に関する意見交換において,ヴィエトナム和平協定並びにラオスの和平協定及び同協定の実施議定書の締結について満足の意を表明した。双方は,これらの協定がすべての当事者により厳格に履行されるならば,インドシナにおける恒久平和確立の可能性を開くものであり,また,ヴィエトナム,ラオス及びカンボデ ィアの問題の解決は,外部から如何なる干渉もなしにこれら諸国の国民によつて実現されるべきであるとの見解を表明した。
双方は,朝鮮半島において南北の間に対話の途が開かれたことを歓迎した。
双方は,南アジア亜大陸における緊張緩和についての関係諸国の努力に対する歓迎の意を表明した。
双方は,また,アジア諸国の自主性の尊重の上に立つてこれら諸国の自助努力に積極的に協力することこそアジアにおける平和と安定のために大きく貢献する方途であ る旨を強調した。
双方は,中東における軍事行動の発生に対して大きな懸念を表明し,現在の事態ができる限り速やかに解決されるべきであるとの希望を表明した。双方は,中東における公正かつ永続的平和ができる限り早期に確立されるようにとの希望を表明した。
双方は,国際間の永続的な平和と福祉を増進するため建設的な貢献を行なうとの決意を表明した。
4 双方は,率直かつ建設的な精神で行なわれた両国最高首脳間の直接の対話が極めて有益であり,かつ,両国関係の発展にとつて重要な貢献を行なつた旨を満足の意をもつて表明した。双方は,両国最高首脳間の対話が継続されるべきである旨を強調した。
田中総理大臣は,ソ連邦訪問中に受けた暖かい接遇に対し感謝の意を表明した。
田中総理大臣は,日本国政府の名において,ブレジネフソ連邦共産党中央委員会書記長,ポドゴルヌイソ連邦最高会議幹部会議長及びコスイギンソ連邦大臣会議議長に対し,別途合意される時期に日本国を訪問するよう招待した。これらの招待は謝意をもつて受諾された。
1973年10月10日にモスクワで
日本国内閣総理大臣 (署名)
日本国外務大臣 (署名)
ソヴィエト社会主義共和国連邦大臣会議議長 (署名) ソヴィエト社会主義共和国連邦外務大臣 (署名)
|
|
10.31日、兵庫県尼崎市のスーパーで、トイレットペーパーの買占め騒ぎ発生、全国にパニックが波及。
| 10.12 |
サウジアラビアのファイサル国王が、「イスラエルに武器を売れば対米石油輸出を停止する」と警告。 |
| 10.14 |
サウジアラビアのファイサル国王が、石油戦略発動を示唆。 |
| 10.16 |
ペルシャ湾岸6カ国が、原油価格の21%の値上げを一方的に宣言。オイル・ショック発生。第4次中東戦争の影響であった。 |
| 10.17 |
OPEC緊急閣僚会議で、石油の生産削減「石油戦略」を決定。 |
| 10.20 |
アラブ産油国が、イスラエル支持国への一方的石油輸出停止を決定。 |
| 10.23 |
国際石油資本の日本に対する原油価格値上げ、供給削減通告が為される。 |
10.29日、小沢一郎が、新潟県の有力建設会社・福田組の長女・和子とホテルニュー大谷で結婚式を挙げる。仲人は二階堂夫妻、角栄は親代わりを務めた。
10.31日、兵庫県尼崎市のスーパーで、トイレットペーパーの買占め騒ぎ発生、全国にパニックが波及。
11.1日、巨人がV9達成。
| 【二階堂官房長官が、中東政策を発表】 |
| 11.6日、二階堂官房長官が、中東政策を発表。1・武力による領土拡大反対、2・イスラエル軍の占領地からの撤退決めた国連安保決議の早期実施、3・パレスチナ人の領土と自決を認める国連決議支持を打ち出した。
|
11.13日、青嵐会メンバーの中川、玉置、浜田が首相官邸に押しかける。「アンタが独断専行だから、今や閣僚も党三役も物価問題で口もきけなくなっている」。「誰がそんなことを云っているんだ」。1時間半にわたって押し問答する。
| 【キッシンジャー国務長官の恫喝】 |
11.14-15日、キッシンジャー国務長官は、アラブ、イスラエル、ソ連、西欧諸国、中国を飛び回るシャトル外交の合間の中国の帰途、日本に立ち寄って、田中首相と会談し次のような遣り取りをしている。
| キ |
概要「われわれは中東紛争の解決に全力を傾けている。今アメリカは中東和平工作を進めているので、日本がアラブ寄りに外交方針を変えることは控えて欲しい。無理をすると日米関係にもヒビガ入る。自分が和平仲介している間、日本は何もしないで黙ってみていてくれ」。 |
| 角栄 |
概要「日本の中東に対する石油依存度が極めて高く、アメリカが石油の代替供給をしてくれない限り、日本はアラブ寄りにならざるを得ない。仮に日本がアメリカと同じような姿勢を続け禁輸措置を受けたら、アメリカは日本に石油を回してくれるのか」。 |
| キ |
「それはできない」。 |
| 角栄 |
「事態の進むままに任せるのでは国民の理解は得られない。何も手をうたなければ日本が窒息死するのを黙認するようなものだ。なんらかの形でアラブの大義に共感を表す必要がある。日本は独自の外交方針をとるしかない」。 |
田中とキッシンジャーの会談は物別れに終わった。大平外相は、「日米友好の基軸に変わりはないが、日本の問題は日本が考える」とコメントした。 |
| 【全国で洗剤、トイレットペーパーの買いだめ騒動】 |
| 11.16日、閣議で、「緊急石油対策推進本部」を設置、石油緊急対策要綱を決定。この頃、全国で洗剤、トイレットペーパーの買いだめが生まれる。
|
| 【新中東政策策定】 |
|
11.20日、サウジアラビアのヤマニ石油鉱業相が、日本に「断交を含む対イスラエル制裁措置」を要求。
11.22日、政府部内をまとめ、閣議で、わが国のアラブ支持を明確にした新中東政策となった中東政策の全面的転換を決定。二階堂官房長官が発表。①・武力による領土の獲得及び占領反対。②・1967年戦争の全占領地からのイスラエル兵力の撤退。③・同域内の全ての国の安全保障措置。④・パレスチナ人の正当な権利の承認と尊重。これについては「中東政策」で詳述する。
また田中内閣の副総理兼環境庁長官三木武夫を中東八カ国へ歴訪させた。後に「油乞い外交」と云われたが、日本はこの経験に懲りて以後、米国追随の中東政策の軸足をイスラエルからアラブ諸国に移し始めた。同時に「日の丸石油」(民族系資本)開発に力を入れることになった。
2001.10.25日朝日新聞の「テロは世界を変えたか」記事で、中曽根元首相の次のような回顧談が載っている。参考資料として引用する。「73年の石油危機の際、アラブの国々が日本への石油を禁輸した。私は通産大臣で非常に困って、アラビア石油の水野惣平社長にサウジアラビアに飛んでもらい、ファイサル国王に『日本経済が危ない。解禁してくれ』と頼んで、国王は『それじゃぁ、政府声明を出して欲しい』と。水野さんが政府声明の案文を持ってきた。その中には『パレスチナの自治(autonomy)を認める』とあった。角さんに『これ呑めや』と電話すると、角さんは『呑もう。大平をくどいてくれ』。外務省はアメリカに遠慮して承知しなかったが、押し切って二階堂官房長官談話を出した」。
中曽根の癖として自己を過剰演出するところがあるが、そこら辺りを割り引いて読めば当時の雰囲気が伝わる。
|
| タカ派系のお粗末さにアングリ、叩き潰そう |
れんだいこ |
2003/03/07 |
小泉はんの親米ポチ化政策はとどまるところを知りませんが、振り返って銘記しておきたいことを書き付けてみます。我が国の中東問題外交史上、前代未聞の親アラブ政策を見せた一時期があります。恐らく専門家は、「だから云わんこっちゃない、葬られることになったのだ」として冷笑的評価しかしていないと思われますが、れんだいこには逆に見えます。オヤジあなたは偉かった、よくぞそういう見解を披瀝し、政策を採れたものだと。
どなたかというと、云わずもがな角栄でござんす。それには次のような背景がありました。1973.10.16日「第一次オイルショック」が発生致します。この日アラブ石油輸出国機構(OPEC)が緊急閣僚会議で、石油の原油生産削減と原油価格の大幅引き上げ(中東原油の公示価格をアラビアン・ライトで、1バーレル3.011ドルから5.119ドルへと約70%引き上げを一方的に発表。第4次中東戦争の結果、対抗措置として「石油戦略」を決定しました。続いて、10.20日アラブ産油国が、イスラエル支持国への一方的石油輸出停止を決定。イスラエルを支援する西側諸国を牽制した。
これを受けて、オイル・メジャーのエクソンとシェル両社が原油価格の30%引き上げを通告。他のメジャーもこれに追随し、10.25日には10%の供給削減を通告するという事態となった。この国際石油資本の日本に対する原油価格値上げ、供給削減通告を「オイル・ショック」という。これにより、1バーレル2ドル40セントだった原油価格が一ぺんに4倍に跳ね上がった。
11.14日キッシンジャー国務長官は、中国訪問の帰途日本に立ち寄って、田中首相と会談し、「今アメリカは中東和平工作を進めているので、日本がアラブ寄りに外交方針を変えることは控えて欲しい。無理をすると日米関係にもヒビが入る」と強調した。これに対し、田中は、日本の中東に対する石油依存度が極めて高く、アメリカが石油の代替供給をしてくれない限り、日本はアラブ寄りにならざるを得ないと訴えた。
11.16日田中内閣は閣議で、「緊急石油対策推進本部」を設置、石油緊急対策要綱を決定。
11.22日田中内閣はこの日閣議で、新中東政策を策定し発表した。それまでの中東政策を転換し、アラブ支持を明確にしていた。二階堂官房長官が次のような声明を発表。①・武力による領土の獲得及び占領反対。②・1967年戦争の全占領地からのイスラエル兵力の撤退。③・同域内の全ての国の安全保障措置。④・パレスチナ人の正当な権利の承認と尊重。
続いて、田中内閣の副総理兼環境庁長官三木武夫を中東八カ国へ歴訪させた。これはあまり役に立たなかったようである。後に批判派からは「油乞い外交」と云われたが、この時以来日本は一時的とはいえ、米国追随の中東政策の軸足をイスラエルからアラブ諸国に移し始め、「日の丸石油」(民族系資本)開発に力を入れることになった。
2001.10.25日朝日新聞の「テロは世界を変えたか」記事で、中曽根元首相の次のような回顧談が載っている。参考資料として引用する。「73年の石油危機の際、アラブの国々が日本への石油を禁輸した。私は通産大臣で非常に困って、アラビア石油の水野惣平社長にサウジアラビアに飛んでもらい、ファイサル国王に『日本経済が危ない。解禁してくれ』と頼んで、国王は『それじゃぁ、政府声明を出して欲しい』と。水野さんが政府声明の案文を持ってきた。その中には『パレスチナの自治(autonomy)を認める』とあった。角さんに『これ呑めや』と電話すると、角さんは『呑もう。大平をくどいてくれ』。外務省はアメリカに遠慮して承知しなかったが、押し切って二階堂官房長官談話を出した」。
中曽根の癖として史実を無視して自己を過剰演出するところがあるが、そこら辺りを割り引いて読めば当時の雰囲気が伝わる。
さて、戦後ハト派の真骨頂とも云える国際協調的親アラブ政策が一時期といえどもあった、と云うことになる。戦後、親米の枠内で、主としてハト派系がこう云う努力を積み重ねてきたからこそアラブ諸国の親日性が保たれている、少なくとも今日までは。れんだいこはそう考えている。
それをに思えば、小泉内閣の親米ポチ化政策が何と矮小な売国路線を邁進していることか。日本の政策は、本当に今のようなブッシュ傾倒イエスマン方式で良いのだろうか、それしか無いのだろうか。れんだいこには、日本のタカ派の正体見たり枯れ尾花のやうに見える。
我々は今や、昂然と怒るべきではないのか。小泉だろうが石原だろうがタカ派系にこの国の運営を任せて良いのか。口先で愛国と民族精神の称揚を云う連中が、実際には如何にチグハグな反民族的売国的親米ポチ化政策へ忠勤していることか。それは何も外交だけではない。経済政策も政局運営も然りではないのか。我々は、新植民地主義の率先的水先案内人として立ち回るこの愚者どもへ鉄槌を下すべきではないのか。
思えば、幕末から明治維新の過程は、その後の舵取りさえ間違わなければ、政治的変動を半暴力的半平和的に為し遂げた類稀なる世界史一級の叡智的史実ではなかったか。かの時失政していれば、日本もまた西欧列強の植民地にされる危機が多分に有った。それを未然に防ぎ、繰り返すが暴力的に且つ内戦を避けながら大局観宜しく為し遂げた。まさに偉業であったのではないのか。
ああだがしかし、今や我等が社会のお偉方がこぞってその遺産を潰そうとしているように見える。愛民族愛国を云う者が、靖国を詣でる精神の他方で戦争狂ブッシュに自ら馴化飼育されることを望みつつある。それはまさに変人的姿態であろう。今や構造改革論の内実が、左様な風に更に我が国を変えようとするものであることがはっきりしているが、この場に及んでもなおしっかりせぇとエールを送る自称インテリがそれに列なっているとは。氷嚢氷嚢これ無くしては今日も眠れない。 |
| 【田中政権の資源外交考】 |
田中政権の資源外交はアメリカの不興を買った。これにつき中曽根の「天地有情」は次のように記している。
| 「田中君は、国産原油、日の丸原油を採るといってメジャーを刺激したんですね。そして、さらに、彼はヨーロッパに行った時、イギリスの北海油田からも日本に入れるとか、ソ連のムルマンスクの天然ガスをどうするとか、そういう石油外交をやった。それがアメリカの琴線に触れたのではないかと思います。世界を支配している石油メジャーの力は絶大ですからね。後にキッシンジャーは、『ロッキード事件は間違いだった』と密かに私に言いました」。 |
角栄自身が「田中角栄回想録」で次のように語っている。
| 「アメリカの核燃料支配に頼ってきた日本への姿勢が厳しくなってきた訳だ。まぁそれは仕方のないことだけど。(中略)しかし、あんなにアメリカがキャンキャンいうとは思わなかったなぁ。(中略)後ろからいきなりドーンとやられたようなものだ。しかし、それも又しょうがない。そこまで考えて怯えていたら資源外交なんかできないもの。それぞれの国家は己の利害のために働いている。(中略)私の資源外交に対して、アメリカのメジャーからいろんな横やりがあるだろうとは分かっていたが、それはしょうがない。こっちは初志貫徹だ。私だっていつまでも総理大臣の職にあるわけじゃないし、殺されないうちに逃げればいいんだと思っていた。短兵急だったかな」。 |
|
| 【愛知蔵相急逝、福田が後釜に坐る】 |
| 11.23日、キッシンジャーの離日から間もないこの日、田中政権の右腕、愛知揆一蔵相が急性肺炎で急逝した。死因は急性肺炎と報道された。 |
|
 (私論.私見) 愛知揆一蔵相急死考 (私論.私見) 愛知揆一蔵相急死考
|
| これは病死か変死か分からない、とすべきだろう。こう問う政論家は今のところ小生を除いてはいない。 |
| 【福田蔵相登場】 |
|
その日の深夜、角栄は、群馬に帰省していた福田に電話を入れ、愛知蔵相の後釜を懇請した。
そのやり取りを福田著「回顧90年」、増田「伝説の角栄」、「田中角栄という男」(別冊宝島編集部、2016.10.10)、小林吉弥「田中角栄 侠の処世№56」その他で補足する。れんだいこがこれらを意訳する。
| 角栄 |
「容易ならぬ事態になった。力を貸して助けて欲しい。すまんが、あなたに大蔵大臣を引き受けてもらいたい」。 |
| 福田 |
「経済の運営は乗馬と同じで、手綱が二本ある。一本の手綱は物価であり、もう一本の手綱は何だと云うと、これは国際収支だ。人で云えば呼吸が物価、脈拍は国際収支である。(中略)今はその日本の手綱が滅茶苦茶になつてきた。その根源は何だ。あなたはどう思うか」。 |
| 田中 |
「石油ショックでこうなって云々」。 |
| 福田 |
「そうじゃないんだ。あんたは石油ショックというけれど、あれは追い打ちだ。あんたが掲げた列島改造論で、昨年7月に内閣をつくって以来1年しか経たないのに、物価は暴騰に次ぐ暴騰で、国際収支が未曾有の大混乱に陥っている。この(日本列島改造の)旗印に象徴される超高度成長的な考え方を改めない限りインフレ加速が避けられず、よって事態の修復はできない」。 |
|
「大蔵大臣を引き受けても良いが条件がある。今の狂乱物価を押さえる為には3つのことが必要だ。上がる予定になっている米価の据え置き、同じく国鉄料金の据え置き、それから公共事業予算が前年比25%以上の伸びになっているが、それを前年と同額にできないか」、「そしてもう一つ。大蔵大臣になるからには、一切、角さんには口出ししてもらいたくない。私に全権を任せてもらいたい」(「当時の大蔵省主計局長・相沢英之氏の証言」)。 |
| 角栄 |
「しかし、列島改造の一枚看板を下ろすわけにはいかない」。 |
| 福田 |
「それではとても蔵相を引き受けられない」。 |
| 角栄 |
「明日、また会おう」。 |
| ト書き |
翌朝、首相官邸で二人は再び会った。 |
| 角栄 |
(しばし沈黙の後)「日本列島改造論を撤回する。今後、自分は経済問題については、一言も物を云わない。一切、福田新蔵相に任せたい。そういう前提で一つ大蔵大臣をやって欲しい」。 |
| 福田 |
「あんたがそこまで言うなら、引き受けましょう」。 |
|
「国のためなら政敵をも退けない、角さんの懐の大きさを見た思いでした」(「当時の大蔵省主計局長・相沢英之氏の証言」)。 |
|
 (私論.私見) 福田蔵相登場考 (私論.私見) 福田蔵相登場考 |
|
| 【第二次田中内閣の第一次改造】 |
|
11.25日、第二次田中内閣の第一次改造。幹事長二階堂進、総務会長鈴木善幸留任。政調会長・山中貞則。官房長官・竹下登。内閣官房副長官・大村襄治、川島廣守。
法務大臣・中村梅吉、外務大臣・大平正芳、大蔵大臣・福田赳夫、文部大臣・奥野誠亮、厚生大臣・齋藤邦吉、農林大臣・倉石忠雄、通商産業大臣・中曽根康弘、運輸大臣・徳永正利、郵政大臣・原田 憲、労働大臣・長谷川峻、建設大臣・近畿圏整備長官([昭49.6.26 同本部廃止])・中部圏開発整備長官([昭49.6.26 同本部廃止])・首都圏整備委員会委員長([昭49.6.26 同委員会廃止]
)亀岡高夫*、自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官・町村金五*、総理府総務長官・沖縄開発庁長官・小坂徳三郎*、・亀岡高夫*、行政管理庁長官・保利 茂、防衛庁長官・山中貞則、経済企画庁長官・内田常雄、科学技術庁長官・森山欽司、環境庁長官・三木武夫、国土庁長官([昭49.6.26 国土庁設置])・西村英一、内閣法制局長官・吉國一郎、川島廣守、総理府総務副長官・小渕恵三、宮崎清文。保利氏が行管庁長官に就任。
愛知揆一の急逝により、田中内閣発足から1年4ヵ月後福田氏が蔵相になった。福田氏は経済政策の見直しを表明。記者会見の場で、概要「列島改造論は田中総理の個人的見解であり、私論だ。日本経済は全治三ヵ年」と云いきり、列島改造政策から総需要抑制政策へ転換を言明した。中曽根通産大臣。
|
11.27日、公取委が石油連盟と日石など元売り13社を独禁法違反容疑で強制捜査。
11.30日、「実質成長率6%程度」と経済見通しを改定。
需要抑制・省エネルギー政策へ転換し、電源開発促進税法等電源3法を成立させ柏崎刈羽原子力発電所への補助金へ当てる。
| 【福田氏の総需要抑制経済政策】 |
|
蔵相に就任した福田は、インフレ抑制を錦の御旗として、直ちに総需要抑制政策を採用した。公定歩合の引き上げ(7%→9%)と緊縮財政への転換でこれを推し進めた。その結果、「日本経済は全治3年のヤケドを負い、高度成長は終わった」とされている。
|
| 【所信表明演説】 |
|
12.1日、第72回通常国会開会。所信表明演説の一節は次の通り。 『消費は美徳』からの180度の転換を指針させた。
| 概要「経済的にも、社会的にも歴史的転換期にある。この際、創造力と適応力に富む国民の総力を結集して、産業活動においては省資源・省エネルギーへの構造的転換を為し遂げ、国民生活においては生活感覚を適応させて資源の浪費を排し、『節約は美徳』の価値観を定着させなければならない」。 |
|
12.10日、三木副総理を派遣して、アラブ諸国8カ国歴訪の石油の供給削減の緩和を求める外交を展開させた。これについては「中東通商交渉」で詳述する。
|
12.10日、一九七三年の第四次中東戦争が引き起こした石油ショックを受け、当時の田中角栄首相が同年十二月十日付で当時のヒース英首相への書簡で、英北海油田開発への日本企業参加に強い意欲を示していた。「北海油田開発は民間ベースで英国企業と交渉を行わせたいので、支援をお願いする」。
2005.1.1日、英公文書館が公開した両首相の往復書簡で明らかになったもので、石油を中東からの輸入に依存してきた日本政府が供給元の多角化に躍起になっていた実態を裏付けている。ヒース首相はこれに先立つ十一月二十日付の書簡で、開発をめぐる企業への認可の可否では、その企業による英国経済への貢献が重要と指摘。これに対し田中首相は「積極的に日本企業の対英投資を進めたい」と強調した。
|
12.11日、イラン政府が、49年の直接販売石油を1バレル16ドル-17ドル40セントで契約したと発表。各国も大幅値上げへ動く。
12.14日、補正予算成立。
| 【「狂乱物価」】 |
| 1973(昭和48)年に第四次中東戦争に端を発した石油危機の結果、「狂乱物価」と言われる激しいインフレに陥った。総合商社に対する社会的批判が一層強くなり、公正取引委員会が独占禁止法の改正を視野に調査を実施し、最終的には独占禁止法が改正され、事業会社の株式保有総額制限が制度化されることになった。 |
12.15日、ストレスと疲労による顔面神経痛。東京逓信病院へ入院する。
| 【石油緊急二法(石油需給適正化法、国民生活安定緊急措置法)公布・施行】 |
12.18日、石油緊急二法(石油需給適正化法、国民生活安定緊急措置法)を衆院で可決。12.21日参院で可決、12.22日、公布・施行。日々上昇する物価に不安を感じ始めた消費者の日用品の買いだめ、物不足現象が引き起こされている事態を受けて、1・石油、電力の20%供給削減。2・公共料金値上げの6ヶ月間延期などの対策を決定。生活関連物資などの価格と補給の調整を図る国民生活安定緊急措置法、石油の消費節約や価格の安定を目的とする石油需給適正化法を成立させ、この日公布した。
12.22日、「国民生活安定緊急対策本部」を設置し、田中首相が本部長に就任。1・石油、電力の20%供給削減。2・公共料金値上げの6ヶ月間延期などの対策を決定。公定歩合を2%引き上げ。
|
12.22日、予算案の大蔵省原案が内示された。17兆994億3千万円。「物価安定は、まず公共事業の圧縮から」という福田蔵相の大号令で、総額が0.9%減の2兆8156億円、48年度の公共事業費が前年度より32.2%増だったのに比べると歴然たる政策転換となった。
12.25日、OPECが、日本を「アラブの友好国」と宣言。日本への必要量の石油供給を決定した。
12.26日、第7回日韓定期閣僚会議開催。
12.29日、49年度予算案決まる。一般会計17兆994億円。財政投融資7兆9200億円。
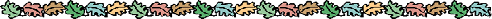



 (私論.私見)
(私論.私見)
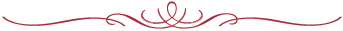
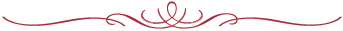
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)