
更新日/2017(平成29).8.30日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、日本の名歌、音楽論その他を確認しておく。
2011.03.15日 れんだいこ拝 |
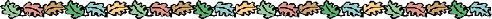
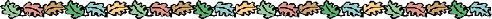



 (私論.私見)
(私論.私見)
日本の軍歌
日本の代表的な軍歌
明治初年〜日清戦争
明治維新を迎えた明治時代初期の大日本帝国の軍歌は、古来からの長い古風な歌詞と、西洋風の旋律が組み合わさった古雅なものが多い。また日清戦争以前の古い曲の中には、唱歌や童謡と同じように、欧米の曲を流用して歌詞をつけた例もまま見られる。
- 戊辰戦争の際、有栖川宮熾仁親王が錦の御旗を先立てて進軍する様子を歌ったもの。1868年(明治元年)作と伝え、事実上の日本初の近代軍歌である。
- 西南戦争の田原坂の戦いにおける警視庁抜刀隊の活躍を歌ったもの。新体詩で有名な外山の歌詞に、当時のお雇い外国人であるルルーが曲をつけたもので、日本初の洋式音楽と言われる。また完成度が高く庶民の間でも広く愛唱され、明治天皇も御前演奏にて大変気に入っていた事でも有名である。後には扶桑歌の曲を合体させた行進曲「陸軍分列行進曲」に編曲され、帝国陸軍の正式行進曲として採用された。現在も陸上自衛隊と日本警察の公式行進曲として使用されている。
- 陸軍教導団に勤務していた石黒が1891年(明治24年)に作った曲。歌詞には未だ意味が完全に解析されていない部分がある。本来の曲は永井作曲のものだが、三善和気作曲の「凱旋」の曲を流用したもののほうがよく歌われた。
- 外国の曲を流用して作られた軍歌(戦闘歌)の一例。曲は童謡「むすんでひらいて」と同一である。同メロディーの曲として「進撃追撃行進曲」という行進曲もある。
- 1886年(明治19年)発表の八章の新体詩から、作曲者が三章を選び出し曲をつけた。抜刀隊(陸軍分列行進曲)とともに明治を代表する軍歌、陸海軍双方で第二次世界大戦終戦時まで長く歌われた(大本営陸海軍部発表時に使用されている)。旧制中学校以来の歴史の古い高校などでは、今でも応援歌として使用しているところがいくつかある。
- 日清戦争前の1890年代に、国民鼓舞の目的から元寇撃退を記念する運動が起こった際作られた曲。日清戦争を戦った将兵の士気の大きな原動力ともなり、内地の国民の間でも幅広く愛唱された。
- 国歌の君が代を行進曲に編曲したもの。重厚ともすれば鈍重とも取られがちな君が代を、軽快に威厳を損なわずまとめあげている。トリオ部分には軍歌の「来たれや来たれ」が流用されているが、歌が稚拙で古すぎたのとこの行進曲にあまりに自然に組み込まれているため、今では元の曲自体が忘れ去られ「君が代行進曲」の一部分としてのみ認知されている。
日清戦争後
軍歌としての目的以外に、一般国民に対する戦況報道も兼ねていたため叙事詩的なものが多い。曲も洋式音楽が煮詰まってきた時期であり、後世に歌い継がれる秀逸なものが増えてきた。
- 黄海海戦時に巡洋艦松島艦上で戦死した三浦虎次郎三等水兵の壮烈な最期の模様を歌った曲。軍民問わず大変広く愛唱された。1929年(昭和4年)に作詞者の手で歌詞が改訂されている。漫画のらくろの「のらくろの歌」の曲としても使用された。
- 黄海海戦時の砲艦赤城と、艦長坂元八郎太少佐の奮戦の模様を歌ったもの。なお、作家内田百間が気に入っていた歌であり、冒頭の一節は「けぶりか浪か」という随筆集の題にも引用されている。
- 軍歌作詞の趣味もあった明治天皇の手になる作品。極めて長い一連の叙事詩。
- 読売新聞誌上に載った歌詞に曲をつけたもので、作詞者の「佐戦児」は投稿した軍人のペンネームであり、誰であるかは不明。威海衛襲撃をテーマに取った勇ましい歌詞と、水雷艇の襲撃を思わせるスピード感ある曲で知られる。のちの太平洋戦争時には、海軍予備学生の間で特に人気があった。
- 日清戦争時、第2軍司令部軍楽隊員として従軍した永井建子がその己の体験を元に作った歌。厭戦(えんせん)歌そのもののような、軍歌としては異色の歌詞が特徴。長らく将兵[2]に愛唱されていたが「勇壮でない」とされ、昭和に入り歌詞が一部改訂(「どうせ生かして還さぬ積り」が「どうせ生きては還らぬ積り」にされた)され、さらに太平洋戦争中には歌唱禁止となったがあくまで建前であるため終戦まで歌唱された。八甲田雪中行軍遭難事件を題材とした戦後の映画『八甲田山』の劇中歌としても使用された。
- 1893年(明治26年)に小学唱歌として発表された歌詞に、1897年(明治30年)、瀬戸口が曲をつけさらに1900年(明治33年)に行進曲に改められたもの。一般には通称「軍艦マーチ」として親しまれている。海軍の公式行進曲で、海軍はもとより民間でも愛唱された、現在は海上自衛隊の公式行進曲である。完成度・知名度が高く日本国内ではしばしば「世界三大行進曲のひとつ」と見なされることがあるが、世界三大事物そのものがそうであるようにこれには明確な根拠は無く、主に日本国内を中心に出回っている風説である。
- 赤十字社の従軍看護婦を歌った世界的にも珍しい異色な歌。作詞者が駅で戦地に出陣する看護婦の姿を見て感動し、一晩で一気に書き上げたもの。赤十字の精神についても言及がある。
- 鉄道唱歌の作詞者として有名で、のちに多数の軍歌を手がけることになる大和田の作詞。出征兵士の壮行歌や凱旋歌としても多用された。当時の陸軍の兵科(憲兵を除き兵科でなく各部である衛生部を含む)や兵種を歌詞で謳っている。昭和に入り、メロディーはそのままに戦車兵(機甲兵)や機関銃隊、爆撃隊(航空兵)など新時代に合わせて藤田まさとが新たに歌詞を数番付け足した派生歌である「新日本陸軍」が存在する。
- 上の日本陸軍と対になる作品。日露戦争直前の全軍艦名を歌い込んであり(その為やや歌詞に無理がある)、あまりに歌詞が長いため、発表このかた一度も全歌詞を録音されたことがない。また、北朝鮮では「日本海軍」の曲を流用[3]した「朝鮮人民革命軍」という軍歌ある。
日露戦争後
こちらも叙事詩的な性格のものが多いが、同時に将兵に対する訓戒のような軍歌も増えてきた。全体的にさらに曲が洗練され、七五調・文語体の長大優美な歌詞のものが多い。なお、海軍省は佐佐木信綱や大和田建樹などに制式海軍軍歌の制作依頼を出しており、このため一連の海軍軍歌の制作年代は明治末であるが、軍歌集による公布は大正時代初めとなっている。
- 本来は、一人の兵士が出征後負傷して凱旋し、村長となるまでを歌った一連の極めて長い「戦績」という唱歌の中の「戦友」という一篇であった。戦友を失う兵士の哀愁を切々と歌い込む歌詞と、同じく哀切極まりない曲とで長く歌い継がれた。日本軍歌一の名軍歌とも言われ、広く愛唱されている。昭和に入り歌詞にある軍紀を無視する箇所が不適当と該当箇所が差し替えられ、さらに太平洋戦争中は歌唱禁止にされたが、「雪の進軍」と同じく将兵に広く歌い継がれた。
- 第1回目の旅順港閉塞作戦を歌った叙事詩。淡々とした曲と、情感豊かな歌詞とで悲壮ながらも軽快な曲となっている。戦い前の将兵の心境とよくマッチしたと見え、のちの太平洋戦争時の開戦前夜や、重大な決戦前には必ずと言ってよいほど歌われた。
- 旅順港閉塞作戦で戦死し、軍神として称揚された広瀬武夫海軍中佐を讃える曲。大正時代成立の同名の有名な唱歌とは別の曲であり、海軍内ではこちらが歌われたが、一般に幅広く歌われ親しまれたのは唱歌のほうであった。
- 陸の軍神である橘周太陸軍中佐の壮烈な戦いぶりを描き、讃える曲。上が19番に下が13番と非常に長い歌詞であり、上と下にそれぞれ別の曲がついている。のちに静岡歩兵第34連隊の部隊歌となった。
- 海軍省の依頼で作られた制式海軍軍歌の一つ。日本海海戦を経過順に歌いこんであり、鉄道唱歌の流れをくむ軽快なものに仕上がっている。主に海軍内で歌われ、一般には同名の唱歌の方が親しまれた。一番の歌詞に「寄こせし敵こそ健気なれ」という敵を讃美する部分があり、当時の日本の世情を表している。瀬戸口の手により行進曲に作り変えられた「日本海海戦記念行進曲」もあり、気ヲ著ケ(きをつけ)の喇叭の出だしと、トリオ部分に君が代を使用するなど、独創的に仕上がっている。
- 海軍軍人の心構えを示した曲で、海軍制式軍歌の一つ。歌いやすく明るい単調な歌詞と曲で、海軍内で終戦まで歌い継がれ「海軍といえばこの曲」というほどに定着した。
大正時代
日独戦争(第一次世界大戦)を迎えるものの。大正時代の日本は全体的に平和な時代であり、この時期作られた軍歌は少ない。兵科ごとの曲や、軍学校の校歌や寮歌の類が目立つ。
昭和初期
中国大陸での紛争・戦争が始まったため、軍歌が急速に作られるようになってきた。時代に合わせて口語体のものも多少出てきており、また曲は歌謡曲に近いものになってきている。戦局の泥沼化を反映してか、後期には悲壮な曲調のものが多い。レコードの大衆への普及に伴いヒット曲となる速度が非常に速くなっており、数十万枚単位で売れるベストセラー作がいくつも誕生している。
- 1930年(昭和5年)に作られた、昭和維新を題材とした革命歌。作者の三上卓は五・一五事件の反乱海軍将校の一人。二・二六事件後は「反乱をあおる危険な歌」とされ歌唱が禁止されたが、歌自体の完成度の高さもあり当時から現代まで愛唱されている。
- 「勝ってくるぞと勇ましく」の歌詞で始まる、まさにこの時期を体現するような曲。泥沼化を反映した悲壮極まりない曲であり、将兵や民間人の心情に訴えかけわずか半年間で60万枚を売り、出征兵士の歓送会でも盛んに使用された。レコードのA面は「進軍の歌」というものであったが、B面であったこちらのほうがはるかに人気があった。昭和を代表する軍歌(戦時歌謡)のひとつに数えられる。
- 1932年(昭和7年)2月、上海事変において、攻めあぐねていた中国国民党軍陣地に対し、あらかじめ点火した破壊筒を抱き合い鉄条網に突入、爆破し自らも爆死をとげた、久留米第24旅団・久留米工兵第18連隊の江下武二、北川丞、作江伊之助工兵一等兵らの武功を讃えた歌。当時、この爆弾三勇士の武功を謳った歌を毎日、報知、朝日の3新聞社がそれぞれ公募・発表したが、毎日によるものがもっともヒットした(朝日による公募歌は「肉弾三勇士」という)。なお、毎日が歌詞を懸賞募集したところ与謝野鉄幹が応募してきたため、選者の北原白秋が困り果てて一等当選にしたという余談もある。
- 1937年(昭和12年)12月に内閣情報部によって詞曲ともに公募・選定・発表された。作曲者は「軍艦行進曲」を作曲した瀬戸口藤吉。レコードは各社から様々な形で吹き込まれて発売され、売り上げは累計すると100万枚を超える。行進曲の名手の作であり曲は非常に評判が良かったが、歌詞は「一般国民が歌うのに難解すぎる」と、一部の文壇や国文学者などからの評判は芳しくなかった。また、歌詞選定を行った北原白秋と佐佐木信綱が、歌詞の手直しをめぐって論争から大喧嘩になり、両者とも死ぬまで口を利かなかったという逸話もある。
- 大伴家持の古歌に曲をつけたもの。本来は士気を鼓舞するための曲だったが、大本営発表などで玉砕を発表する時に使用され、すっかりそちらのイメージで有名になった。現在でも鎮魂歌として使われることが多い。荘重な古歌に上質な曲を組み合わせたもので、非常に格調高く仕上がっている。マッカーサーがアメリカ極東陸軍(米比軍)の軍事顧問時代、この歌詞から日本軍の戦闘心理を理解したという逸話がある。
- 後に太平洋戦争末期の硫黄島の戦いにおける最高指揮官として有名になる、騎兵出身の栗林忠道陸軍大将がかかわった事で有名。歌詞コンクールをして一等入選だったものに曲をつけた。軽快な曲と、軍馬に対する愛情がにじみ出ているようなこれぞ騎兵といった歌詞で人気を博した。
- 1940年(昭和15年)の松竹映画「征戦愛馬譜 暁に祈る」の主題歌として作られた。これは陸軍省馬政課が軍馬に対する認識を喚起するためにバックアップした映画だったが、歌詞中で馬をうたった部分が少なく曲調も哀愁漂う旋律だったため、父や兄弟を戦場へ送り出した家族や望郷の思いにかられる兵士達に受け入れられ、映画を離れて広く長く支持された。
- 大日本雄弁会講談社(後の講談社)が公募・選定した曲。作詞者が駅に日参して歌詞を作ったとされる。極めて勇壮な歌詞とメロディーに作曲者でもある林伊佐緒の豪快な歌唱も相まり、戦後吹き込み版(キングレコードの林伊佐緒・ボニー・ジャックス)は街宣右翼が好んで使用しているなど、一般での知名度も高い。完成度の高さから日本軍歌を代表する曲の一つである。
- 戦線の将兵たちの心情をうたった歌。後に「いやじゃありませんか軍隊は」ではじまる同じメロディーの替え歌「軍隊小唄」としてうたわれ、戦後はザ・ドリフターズがこの替え歌を歌っていた。
- 関東軍参謀部が選定・発表した歌。作曲者及び創唱歌手は「我等のテナー」として、当時から日本を代表する有名なオペラ歌手藤原義江。中国戦線で匪賊討伐にあたる将兵の姿を描いている。雪の進軍と同じくまるで厭戦・反戦歌のような歌詞・曲調であるが、民間製作の多くの戦時歌謡とは異なり、討匪行は軍制定の純粋な軍歌である。軍民双方で愛唱された。食事も補給もなく愛馬も倒れ、時には空を仰ぎながら涙を流し、戦友と生きて再会出来た喜びに歓喜しながらも黙々と泥濘の道を往く様子や、敵の死体に花を手向けて弔うなど前線を実感的に表している。
太平洋戦争期
太平洋戦争開戦とともにさらに数多くの軍歌・戦時歌謡が作られた。日中戦争時とは打って変わり、明るく軽快もしくは勇壮な歌詞・曲のものも多い。ただし、優秀な曲が多く生まれたと同時に、時局に合わせただけの粗製濫造の曲も非常に多く、その多くは歌い継がれることなく消滅していった。また、「勇壮でない」と睨らまれた曲はたとえ軍歌でも弾圧を受け、明治以来の優秀な軍歌がいくつも歌詞改訂・歌唱禁止にされるなど、暗い面も残している。
- 開戦とほぼ同時に製作された[4]、国民の憤激や戦意高揚を歌った歌。国民精神総動員などの国民酷使の体質や軍国主義体質がよく現れている軍歌である。
- 「南洋航路」という歌謡曲が原曲である。
- ラバウル海軍航空隊 作詞:佐伯孝夫 作曲:古関裕而
- 佐伯孝夫と灰田勝彦はビクターレコードの、古関裕而はコロムビアレコードの専属であったが放送用の曲であったため制作が実現した。後にビクターがコロムビアに対し信時潔の曲を提供するという条件で、1944年(昭和19年)1月にビクターレコードより発売された。南方の前線航空基地を彷彿とさせる軽快な歌詞と曲で流行したが、その時期には皮肉にもラバウルから海軍航空部隊が撤退した時期であった。
- 大本営海軍部発表にて台湾沖航空戦で大勝利(実際は虚構)を収めたと発表されたのを記念して作られた。当時の戦況を打開できる目処がついた明るい調子に仕上がっている。ニッチク(日本コロムビア)が戦前実質的に販売した最後のレコード。
- 読売新聞が軍の依頼を受けて西條と古関に依頼した。フィリピン戦を目前にして国民の士気を煽る必要から、敵将ニミッツとマッカーサーの名前を入れるように要望があった。しかし打ち合わせで西條がそれを断ると出席していた陸軍報道部の親泊中佐がその場で「いざ来いニミッツ、マッカーサー出てくりゃ地獄に逆落とし」と代筆してこの曲が出来上がった。1944年(昭和19年)12月17日に発表会が行われ、同年12月26日に酒井弘、朝倉春子、ニッチク合唱団によってレコーディングされた。フィリピン戦が行われている間は連日ラジオで放送していたが、現在までにレコードは1枚も発見されていない。レコードの発売予定は物資欠乏が深刻化した1945年(昭和20年)3月。同時期発売のレコードも一切発見されていない所を見ると、発売は中止されたようである。
- 「敗戦と共に楽譜は全て廃棄された」(楽譜に関しては古関裕而記念館に展示されている他、「昭和二万日の全記録⑥太平洋戦争」(講談社)のグラビアページに楽譜とレーベル原稿の写真が掲載されていることから、少なくとも完全な「廃棄」は誤りと言える)、「西條と古関が戦犯指名される」との噂も飛び交ったが、当のマッカーサーは全く関心をもたずに何も起こらなかった。後にレコード会社が古関裕而の全集を発売する時、許諾のため古関本人に尋ねたところ「もうこの歌だけは勘弁してくれ」とレコード化を拒否されたという。なお、本作は古関の死後に戦後50周年企画として新たに吹き込まれている(この際、江口夜詩の息子で作曲家の江口浩司が編曲している)他、藍川由美、小沢昭一がその前後にレコーディングをしている。
軍歌の終焉
1945年(昭和20年)8月15日の終戦、その年の11月30日をもって、明治以来の大日本帝国陸海軍は解体・消滅。軍歌が新たに作られることは少なくなった。しかし、戦前中の歌に慣れ親しんだ国民により引き続き歌唱され、パチンコ店で軍艦行進曲が流されるなど軍歌自体の寿命はまだまだ続いていた。
- 終戦直後、将兵の気持ちを静める目的で軍楽隊によって作られた。
- 1946年(昭和21年)、戦犯としてシンガポールに行かねばならなくなった元帥寺内寿一陸軍大将を見送る際に作られた曲。軍楽隊による最後の軍歌であり、これ以降、狭義の意味での軍歌軍楽は作られていない。
- シベリアに抑留された将兵たちによって収容所で歌われていた曲。戦後の1948年(昭和23年)、ある一人の復員兵がNHKのど自慢で歌い、一挙に大評判となった。作曲者は当初不明のままレコード化されたが、のちに吉田正元陸軍伍長が引き揚げてきて、原曲となった「大興安嶺突破演習の歌(今日も昨日も)」の作曲者だと判明した。シベリアでの辛抱を表すような哀切極まる歌詞と曲で、いまだ元将兵の心をつかんでいる。1949年(昭和24年)には、全国高等学校野球選手権大会の入場行進曲にも選ばれた。
- B/C級戦犯として捕縛され、フィリピン・モンテンルパのニュービリビット刑務所に収監されていた元将校の代田と伊東によって作詞作曲され、収容されていた日本軍将兵によって歌われていた曲。1952年(昭和27年)1月、来日したフィリピンの国会議員ピオ・デュランから同刑務所に収容されている日本軍将兵がいることを聞いた歌手の渡辺はま子が、オルゴールを差入れとして贈ったところ、「ぜひ渡辺さんに歌っていただきたい」という手紙とともに、歌詞と楽譜が渡辺のもとに送られ、これを受けてビクターより渡辺と宇都美清のデュエットでレコード化され新東宝により映画化もされた。
- 1940年(昭和15年)に林伊佐緒によって歌われた「東京パレード」の替え歌で、シベリアでの抑留生活を歌った曲。原曲よりも近江俊郎が歌った「ハバロフスク小唄」の方が有名になった。軽快な曲調が逆に抑留生活の悲哀を感じさせる。ちなみに、曲名は「ハバロフスク」だが曲中では「ハバロスク」と歌われることが多い。
日本の軍歌は、その支配権から独立した韓国、北朝鮮、ミャンマーなどの軍歌のルーツになったとする見方もある。朝鮮人民軍は日本統治時代の旧日本軍出身者が多く、軍歌の作り方もそれに沿ったものであったとされている。また、前述の「日本海軍」や「鉄道唱歌」などから曲を流用している例も散見される。


![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)