
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.6.21日
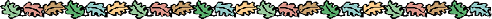
| 【日露戦争に関する論達2号発布】 |
2.13日、日露戦争が始まつた(2010日)のを受けて日露戦争に関する論達2号発布。
| 我が教会のつとに以て神祇を敬崇し群集を化導るところのものは、神明の付与し給えるところの霊魂と神明より借り受けたるところの肢体とをあげてこれを国家に殉すの誠意に他ならず。 |
教内で、250万余円の国債を消化し、陸海軍に数万円の献金、寄付金を納めた。この前後、教勢は、台湾からアモイを経て中国大陸に伸び、亦釜山を拠点に朝鮮にも進出した。
|
「創象16」P12「高野友治」(1983.私家版)が次のように記している。
| 信者たちが、命がけで捧げた金はとこへ行ったのか。献金をめぐって東北地方では、何カ所かで警察拘留問題があり、未決へ収容されたものもあり、これは関東にもあり、近畿のある布教者は、奈良監獄で出直している。その金はどうなったのか。どうも明治41年11月27日の天理教一派独立運動に関係があるのでないかと思う。それまで天理教会は、神道本局の部属だった。それが、このとき神道本局から分離して、国家公認の神道の一派天理教として独立したのだ。国家の公認の宗教になるためには、それだけ国家に貢献する実を形で示さねばならなかったのではないか。そんなとき、たまたま上村福太郎著「潮の如く」(上)を見ていたら、天理教が明治37年に国債を250万円応募したという記事を見た。更に、3月8日夜、本部員会議に於て、国庫債券の募集に応じ戦費を補うべく議決したが、これが応募総額は、実に250万5千円以上に達し、又、別に、恤兵(じゅっぺい)金額は、1万2400円以上であった」(74ページ)。ただし神崎
一作著「神道六十年史要」では恤兵金額は「120万円以上に達し」と記している。(同書160頁)。それで、これなる哉と思った。250万円というと大きい金だ。日露戦争の戦費が、ある本では20億いったと書いてあった。そうすると250万円は、その800分の1に相当する。その国債購入のことは、天理教の直轄教会史、部属教会史には出ていない。それはどういうわけであろうか。多分みんなは神さまのためといって上げたものだと思う。それが、天理教教会本部に上がり、神道本局に上がり、お国のお役に立っていたものと思う。 |
|
| 【天理教会長に対し内務省よりの達し】 |
2.25日、お指図。「この度神道本局より天理教会長に対し内務省よりの達しには、教長是非上京せよとの事に付き、明日より上京する事御許しの願い」。
| 今一時尋ねる事情の指図、今度一つのぼると云う、いかな事情どういう事情、どんな事情でも、おめ恐れは一つもするやない。時という旬という一つ理を聞き分け。長らえ/\年来に知らしてある。筆先に知らしてもある。もう落ちはない。皆速やか諭してある。どういう事情こういう事情始め掛けたら、大きい事情、大き事情治まる事情何処にある。よう聞き分けて、皆々心を治め。この度世界も一つ、ぢばも一つ。大層/\、大層の事件あると言うたる。この日もあろ。言うただけでは忘れる。ふでさきに詳しく皆知らしてある。嘘は一つも無い。もう日が近づけば/\、もう日柄来たると言う。もう一つ大変。そこで精神一つ理を持たず、怖わき処も無くばならん。恐きところでも恐れはない。何でもないところは恐い。大きところほど、恐くない。親にもたれつけ々。これほど丈夫あろまい。どんな事も知らしてあれど、あちらへ納しこちらへ納し、今日のさしづは年来に一つ積もり/\たさしづである。明日からという処は、おめ恐れはするやない。心置き無う行って来るがよい。親が連れて行く、どんな事もこんな事も、うんうん云うてこい。 |
|
| 【不良教師追放事件】 |
1904(明治37)年、平野樽蔵らが「天理教会本部の打ち出す教理を説かない者は不良教師である。辞任してお詫びせい」と迫った。これにより、教祖派の高弟として知られていた泉田藤吉(中津支教会長。おたすけ人の鑑と云われていた)、万田万吉(島ヶ原会長、中和大教会の植田平一郎の兄弟)らが異端者、本部の方針に謀反する不良教師であるとして会長を辞任させられ、1400名の教師(よふぼく、取次人)が放逐された。教祖の教理を受け継ぐ者が大弾圧され、中には自殺する者も出た。
泉川藤吉は、11もの直属教会を布教して作った名お助け人だった。東本の道人にとって、東本の初代会長中川よしの旦那の中川禰吉が、中川よしがまだ布教しないうちに、泉田藤吉と、南の松永と中川彌吉の三人で、
御津大教会を始めとして中津大教会に至るまで直属教会を作る布教の旅をしていた履歴を遺している。大教会「中津」の会長を辞任させられる経緯を持つ泉田藤吉は、おぢばに帰って本席になだめられたが一ヵ月後の4.26日、おぢばで出直した(享年65歳)。「島ヶ原」の会長であった万田万吉は刀で追われて教内から消えた。 |
「稿本中山眞之亮伝」296pは次のように記している。
「教内の郭清を実施し、教師の行状を正さねばならぬ、という事になって、
1、教師たるの品性を欠き、性行不良なるもの
2、教会の命を用いず、教規教制を守らざるもの
3、有名無実にして、教師の職責を尽くさざるもの
右に該当する者、千四百余名を淘汰辞職せしめた。これは頗る困難な問題であったので、綿密な上にも綿密な調査の上、一切の情実因縁を排除して断行した」。 |
当時、天理教一派独立の為に政府とのやりとりをしていた中心人物は、松村吉太郎。(独立運動に関する詳細は「高安大教会史」に詳しく載っている。「稿本中山眞之亮伝」の文章も315pにぼ同じ形で載っている)。明治29年に発令された内務省訓令による天理教弾圧が、ようやく落ち着いてきた明治32年5月、神道本局より一派独立を促された。そのため、天理教は一派独立するため本格的に動き始めるが、独立を出願する度に政府から様々な注文を付けて突き返されていた。その注文の一つが不良教師の淘汰だった。「どうも天理教は、やたらに教師を造るのだね。粗製濫造だよ。だから、絶えず世間の問題を引き起こすのだ」。このように言われた松村氏は、「言外には、それ(教師の整理)を敢行しなければ、教義も制度も組織も認め難いという意味が汲み取れた」と苦しい胸の内を明かしている。「道の八十年」に次のように記している。
| 「信徒といい教師といい、教祖様の教えを奉じて、ただたすけ一条に、まっしぐらにすすんでいる。宗教の世界を、法規で画一的に整理しようとは無理も甚だしい。殊に、身を捨てて伝道に従っている人びとを、どうして捨てられよう。苦慮に苦慮を重ねた。そうして、有名無実者、死亡者などを拾い上げて、千四百名の淘汰を完了したことを報告した」。 |
明治33.12.31日時点で18,335人が教師として登録されていた。当時の教師数は軽く2万人を越えていたことが予想される(「教史点描」参照)。この出来事の詳細は松村氏の自伝「道の八十年」185〜187pに詳しく載っている。道友社が出版している「教史点描」215~216Pにも詳細が書かれている。 |
| 2月、日露戦争が勃発する。天理教団は戦争協力体制へ進んでいくことになり、「借金をしてでも戦時国債を買え」という本部方針の下で250万円以上の戦時国債を買い協力した。日露戦争後、真柱の真之亮に勲六等の勲章が出される。 |
3月、第2回教師講習会。
【本部】天理教婦人会活動のはしり(日露戦争の軍人遺族、
戦死者等の救済に従事)
|
| 口には言われん、筆に書き尽くせん道を通りて来た。……五十年の間の道を、まあ五十年三十年も通れと言えばいこまい。二十年も十年も通れと言うのやない。まあ十年の中の三つや。三日の間の道を通ればよいのや。僅か千日の道を通れと言うのや。千日の道が難しいのや。ひながたの道より道がないで。何程急いたとて急いだとていかせんで。(前同) |
|
| 【お供えが金平糖から洗米に代わる】 |
4.3日、「金平糖を御洗米に改めることの願い」伺いに対するお指図。
| 「道と云う、あちら変わりこちら変わり、流れる水も同じ事。ごもく流れて、澄んだ水流れば道と云う、濁りた水はどうもならん。(中略)一時、泥水の中で、澄んだ水待つ心、そこで願い通り皆々の心、道と云う心と云う二つ理、それでならんところ無理と云う事情、ごもくの中の濁りた水飲まにゃしょうまい。(中略)どうこうなりと、今のところ皆の心に任せおこう々」。 |
| 「お供えと云うは大変の理なる、皆々も聞いているやろ。さあさあ何もお供え効くやない。心の理が効くのや。気の休め、心の理の休まりに出したるものや。すれば、分量はかりた薬味に出すのやない。どうしたてこうしたて、何もいやせん。三つ三つこれだけ知らしておく。出すが良い々」。 |
4.10日、御供(ごく)が、金平糖から洗米に代わる。
|
4月、天理教講習会会則を制定し、直属教会講習会を各地で開催。
| 【天理教本部が前川菊太郎の依頼で前川家屋敷を買い取る】 |
| 4-6月頃、既に橋本と共に本部に辞表を突きつけて去っていた前川菊太郎が、本部に対し、「負債で困っているから、前川の家屋敷を本部で買い取って貰いたい。私は大坂へ出て商売するつもりとの申し出がなされている。6.4日、本部は受け入れ、真柱名義で買い入れ登記した。
|
8.1日、第3回請願書提出。松村吉太郎を全権委員に任命。8.13日、請願書取り下げ。
| 【お供えが金平糖から洗米に代わる】 |
8.23日、「日露戦争に付き、天理教会に於いて出征軍人死者の子弟学費補助会組織致したくの願い」に対するお指図。
| 「さあさあ尋ねる事情々、いかな事も尋ねにゃ分からん。さあさあ今この一時一つ世界と云う中に、一つと云う理は世界にある。そこで、これまでどんな事も言葉に述べた処が忘れる。忘れるから筆先に知らしおいた。筆先というは軽いようで重い。軽い心持ってはいけん。話の台であろう。取り違いありてはならん。この台、世界の事情、もうどう成ろうかこう成ろうか、一つの台。敵は大きもの、全国に於いても大層と言う。古き古き事に年限から諭してある。この一つの心得は今日の事や。ある事言うた事はない。紋型ないところから順序追うて来たる道。難しい事望んで、難儀苦労さす道を付けたのやない。ほのかに諭して居るやろう。理は一つに纏まりてくれにゃならん。皆々よう聞き分けてくれにゃならん。道という、道は楽の道は通りよい。難しい道は通り難くい。難しい道の中に味わいある。よう聞き分け。敵と言うて、睨み合い/\という。一時のところ旨いように思う。旨い事やない。何でも彼でもという。これまで諭し置いたる理は、仮名な柔らかい中に、要(かなめ)々の言葉諭してある。一時の処言葉だけでは忘れ易い。書きた事は忘れんもの。(中略) 一時どうもならんという。余儀なく理ある。来ん先から前に諭してある。思案してみよ。道という道は、どんな中も運んでやらにゃならん。又一つ所々、又一つ志や/\、理が思うから、志早いやない、遅れてある。そこで、よく聞き分け。もう一時尋ねる事情、それは何時にても許しおこう。大き事すっきり、これではどうもならんというところまで行ってみよ。これではどうもならんというところまで行かにゃ分かりゃせんで」。 |
|
12.16日、第4回請願書提出。
| 【本部節会(おせち)見合わせ願い】 |
12.16日、お指図。「本部節会(おせち)の事に付き、一同協議の結果本部長へ申し上げ、本年に限り節会見合わす事願い」。
| 「さあさぁ尋ねる事情事情事情は、それは余儀なき事情であろう/\。この世一つ始まりてから、一つ全国に於いて大変々々の理、大変というは五年十年二十年やない。これまでだん/\諭したる。ようよぅの日どうもならん日に及んだる。道は六十年以来から始め掛けたる。皆諭し詰めたる。残念々々現れたら、どうもならん日になる、と諭したる。この道月日が出てこゝまで働いたるは、容易の事やない。道という、又一つ全国の事情に於て大変の事、万事扶け合いと言うたる」。 |
|
| (道人の教勢、動勢) |
| 4.26日、泉田籐吉が出直し(亨年65歳)。天保11年(1840)5月11日、摂津国東成郡大今里村(現・大阪市東成区大今里)生まれ。明治4年(1871)、入信。小松駒吉(御津大教会初代)、茨木基敬(北大教会初代)、寺田半兵衛(綱島分教会初代)、中西金次郎(大江大教会初代)等を導く。中津布教事務取扱所(現大教会)初代会長。 |
| 5.4日、山本利八が出直し(亨年86歳)。文政2年(1819)11月3日、河内国志紀郡柏原村(現・大阪府柏原市)生まれ。明治6年(1873)、長男・利三郎(後の柏原分教会(現・中河大教会)初代会長)の三年越しの病を教祖に助けられる。 |
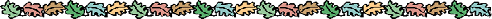
| (当時の国内社会事情) |
| 1904(明治37)2.6日、日露国交断絶を通告。2.8日、陸軍が朝鮮の仁川に上陸開始、連合艦隊は旅順港外のロシア艦隊を攻撃。2.10日、日本がロシアに宣戦布告(〜明治38年9月5日)。重税による財政難、破産続出。 |
| (田中正造履歴) |
| 1904(明治37)年、64歳の時、谷中村に住む。遊水地化反対運動に励む。 |
| (宗教界の動き) |
| 日蓮宗大学林設立→立正大学。露国宣戦布告に関し神職・各宗派管長に注意。森鴎外歌舞伎『日蓮上人辻説法』。カトリック高松司教区設置。 |
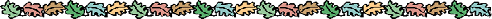



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)