○
あしひきの山行きしかば山人の朕に得しめし山づとぞこれ 〔巻二十・四二九三〕 元正天皇
大和国添上郡山村(今の帯解町辺)に行幸(元正天皇)あらせられた時、諸王臣に和歌を賦して奏すべしと仰せられた。その時御みずから作りたもうた御製である。(この御製歌は天平勝宝五年五月はじめて輯録されたから、孝謙天皇の御代になって居り、従って万葉集には元正天皇を先ノ太上天皇と記し奉っている。そして此歌の次に舎人親王の和え奉った御歌が載って居り、親王は聖武天皇の天平七年に薨去せられたから、此行幸はそれ以前で元正天皇御在位中のことということになる。)
一首の意は、朕が山に行ったところが山に住む仙人どもがいろいろと土産を呉れた。此等はその土産である、というので、この山裹というのは、山の仙人の持つようなものをぼんやりと聯想し得るのであるが、宣長は、「山づとぞ是とのたまへるは、即御歌を指して、のたまへる也」(略解)と云ったのは、「それ諸王卿等、宜しく和歌を賦して奏すべしと、即ち御口号に曰く」と詞書にある、その「御口号」をば直ぐ山裹と宣長が取ったからこういう解釈になったのであろう。併し山裹の内容はただ山の仙人に関係ある物ぐらいにぼんやり解く方がいいのではあるまいか。そこで下の舎人親王の「心も知らず」の句も利くのである。舎人親王の和え御歌は、「あしひきの山に行きけむ山人の心も知らず山人や誰」(巻二十・四二九四)というので、前の「山人」は天皇の御事、後の「山人」は土産をくれた山の仙人の事であろう。そこで、「山に御いでになった陛下はもはや仙人でいらせられるから俗界の私どもにはもはや御心の程は分かりかねます。一体その山裹と仰せられるのは何でございましょう。またそれを奉った仙人というのは誰でございましょう」というので、御製歌をそのまま受けついで、軽く諧謔せられたのであった。御製歌は、「山村」からの聯想で、直ぐ「山人」とつづけ、神仙的な雰囲気をこめたから、不思議な清く澄んだような心地よい御歌になった。
○
木の暗の繁き尾の上をほととぎす鳴きて越ゆなり今し来らしも 〔巻二十・四三〇五〕 大伴家持
大伴家持が霍公鳥を詠んだもので、鬱蒼と木立の茂っている山の上に霍公鳥が今鳴いている、あの峰を越して間も無く此処にやって来るらしいな、というので、気軽に作った独詠歌だが、流石に練れていて旨いところがある。それは、「鳴きて越ゆなり」と現在をいって、それに主点を置いたかと思うと、おのずからそれに続くべき、第二の現在「今し来らしも」と置いて、一首の一番大切な感慨をそれに寓せしめたところが旨いのである。霍公鳥の歌は万葉には随分あるが、此歌は平淡でおもしろいものである。家持の作った歌の中でも晩期のものだが、稍自在境に入りかかっている。
○
我が妻も画にかきとらむ暇もが旅行く我は見つつ偲ばむ 〔巻二十・四三二七〕 防人
天平勝宝七歳二月、坂東諸国の防人を筑紫に派遣して、先きの防人と交替せしめた。その時防人等が歌を作ったのが一群となって此処に輯録せられている。此歌は長下郡、物部古麿という者の作ったものである。一首は、自分の妻の姿をも、画にかいて持ってゆく、その描く暇が欲しいものだ。遙々と辺土の防備に行く自分は、その似顔絵を見ながら思出したいのだ、というので、歌は平凡だが、「我が妻も画にかきとらむ」という意嚮が珍らしくもあり、人間自然の意嚮でもあろうから、此に選んで置いた。「父母も花にもがもや草枕旅は行くとも ごて行かむ」(巻二十・四三二五)も意嚮は似ているが、この方には類想のものが多い。また、「母刀自も玉にもがもや頂きて角髪の中にあへ纏かまくも」(同・四三七七)というのもある。 ごて行かむ」(巻二十・四三二五)も意嚮は似ているが、この方には類想のものが多い。また、「母刀自も玉にもがもや頂きて角髪の中にあへ纏かまくも」(同・四三七七)というのもある。
○
大君の命かしこみ磯に触り海原わたる父母を置きて 〔巻二十・四三二八〕 防人
これも防人の歌で、助丁、丈部造人麿という者が作った。一首は、天皇の命を畏こみ体して、船を幾たびも磯に触れあぶない思をし、また浪あらく立つ海原をも渡って防人に行く。父も母も皆国元に残して、というのであるが、かしこみ、触り、わたる、おきてという具合に稍小きざみになっているのは、作歌的修練が足りないからである。併し此歌では、「磯に触り」という語と、「父母を置きて」という語に心を牽かれて取っておいた。この男は妻のことよりも「父母」のことが第一身に応えたのであっただろう。また「磯に触り」の句は、「大船を榜ぎの進みに磐に触り覆らば覆れ妹によりてば」(巻四・五五七)という例があるが、「磯毎にあまの釣舟泊てにけり我船泊てむ磯の知らなく」(巻十七・三八九二)があるから、幾度も碇泊しながらという意もあるだろう。しかし「触り」に重きを置いて解釈してかまわない。一寸前にも云ったが、防人の歌に父母のことを云ったのが多い。「水鳥の立ちのいそぎに父母に物言ず来にて今ぞ悔しき」(巻二十・四三三七)、「忘らむと野行き山行き我来れど我が父母は忘れせぬかも」(同・四三四四)、「橘の美衣利の里に父を置きて道の長道は行きがてぬかも」(同・四三四一)、「父母が頭かき撫で幸く在れていひし言葉ぞ忘れかねつる」(同・四三四六)等である。
○
百隈の道は来にしをまた更に八十島過ぎて別れか行かむ 〔巻二十・四三四九〕 防人
防人、助丁刑部直三野の詠んだ歌である。一首の意は、これまで陸路を遙々と、いろいろの処を通って来たが、これからいよいよ船に乗って、更に多くの島のあいだを通りつつ、とおく別れて筑紫へ行くことであろうというので、難波から船出するころの歌のようである。専門技倆的に巧でないが、真率に歌っているので人の心を牽くものである。この歌には言語の訛が目立たず、声調も順当である。
○
蘆垣の隈所に立ちて吾妹子が袖もしほほに泣きしぞ思はゆ 〔巻二十・四三五七〕 防人
上総市原郡、上丁刑部直千国の作である。出立のまぎわに、蘆の垣根の隅の処に立って、袖もしおしおと濡れるまで泣いた、妻のことが思出されてならない、というので、「蘆垣の隈所」というあたりは実際であっただろう。また、「泣きしぞ思はゆ」も上総の東国語であるだろう。或は前にも「おも倍由」というのがあったから、必ずしも訛でないかも知れぬが、「泣きしぞ思ほゆる」というのが後の常識であるのに、「ぞ」でも「思はゆ」で止めている。「しほほ」も特殊で、濡れる形容であろうが、また、「しおしおと」とか、「しぬに」とも通うのかも知れない。
○
大君の命かしこみ出で来れば我ぬ取り着きていひし子なはも 〔巻二十・四三五八〕 防人
上総周淮郡、上丁物部竜の作。下の句は、「我に取り着きて言ひし子ろはも」というのだが、それが訛ったのである。「我ぬ取り着きていひし子なはも」の句は、現実に見るような生々したところがあっていい。当時にあっては今の都会の女などに比して、感動の表出が活溌で且つ露骨であったとおもうのは、抑制が社会的に洗練せられないからであるが、歌として却って面白いのが残っている。「道のべの荊の末に這ほ豆のからまる君を離れか行かむ」(同・四三五二)も同じような場面だが、この豆蔓の方は間接に序詞を使って技巧的であるが、それでも、豆蔓のからまるところは流石に真実でおもしろい。
○
筑波嶺のさ百合の花の夜床にも愛しけ妹ぞ昼もかなしけ 〔巻二十・四三六九〕 防人
常陸那賀郡、上丁大舎人部千文の作である。「夜床」をユドコと訛ったから、「百合」のユに連続せしめて序詞とした。併し、「筑波嶺のさ百合の花の」までは、ただの空想でなく郷土的実際の見聞を本としたのが珍らしいのである。「かなしけ」は、「かなしき」の訛。一首の意は、夜の床でも可哀いい妻だが、昼日中でもやはり可哀いくて忘れられない、というので、その言い方が如何にも素朴直截で愛誦するに堪うべきものである。このいい方は巻十四の東歌に見るような民謡風なものだから、或はそういう既にあったものを書き記して通告したとも取れるが、若しこの千文という者が作ったとすると、東歌なども東国の人々によって作られたことが分かり、興味も亦深いわけである。「旅行に行くと知らずて母父に言申さずて今ぞ悔しけ」(巻二十・四三七六)の結句が、「悔しき」の訛で、「かなしき」を「かなしけ」と云ったのと同じである。
○
あられ降り鹿島の神を祈りつつ皇御軍に吾は来にしを 〔巻二十・四三七〇〕 防人
前と同じ作者である。鹿島の神は、現在茨城県鹿島郡鹿島町に鎮座する官幣大社鹿島神宮で、祭神は武甕槌命にまします。千葉県香取郡香取町に鎮座する官幣大社香取神宮(祭神経津主命即ち伊波比主命)と共に、軍神として古代から崇敬至ったものであった。防人等は九州防衛のため出発するのであるが、出発に際しまた道すがらその武運の長久を祈願したのであった。土屋文明氏によれば、常陸の国府は今の石岡町にあったから、そこから鹿島郡軽野を過ぎ、下総国海上郡に出たようだから、途中鹿島の神に参拝することが出来たのである。
一首の意は、武神にまします鹿島の神に、武運をば御いのりしながら、天皇の御軍勢のなかに私は加わりまいりましたのでござりまする、というのである。
結句の「を」は感歎の助詞で、それを以て感奮の心を籠めて結句としたものである。併し若しこの「来にしを」を、「来たものを」、「来たのに」というように余言を籠もらせたと解釈するなら、「皇御軍のために我は来しますらをなるを、夜昼ともに悲しと思ひし妻を留めて置つれば心弱く顧せらるゝ事を云ひ残して含めるなるべし」(代匠記)か「鹿島の神に祈願て官軍に出て来しものをいかでいみじき功勲を立てずして帰り来るべしや」(古義)かのいずれにかになる。「あられ降り」を「鹿島」の枕詞にしたのは、霰が降って喧しいから、同音でつづけた。カマカマシ、カシカマシ、カシマシとなったのだろうと云われて居る。こういう技巧も既に一部に行われていたものか、或はこの作者の発明か。
○
ひなぐもり碓日の坂を越えしだに妹が恋しく忘らえぬかも 〔巻二十・四四〇七〕 防人
他田部子磐前という者の作。「ひなぐもり」は、日の曇り薄日だから、「うすひ」の枕詞とした。一首は、まだようやく碓氷峠を越えたばかりなのに、もうこんなに妻が恋しくて忘れられぬ、というのであろう。当時は上野からは碓氷峠を越して信濃に入り、それから美濃路へ出たのであった。この歌は歌調が読んでいていかにも好く、哀韻さえこもっているので此辺で選ぶとすれば選に入るべきものであろう。「だに」という助詞は多くは名詞につくが、必ずしもそうでなく、「棚霧らひ雪も降らぬか梅の花咲かぬが代に添へてだに見む」(巻八・一六四二)、「池のべの小槻が下の細竹な苅りそね其をだに君が形見に見つつ偲ばむ」(巻七・一二七六)等の例がある。
○
防人に行くは誰が夫と問ふ人を見るが羨しさ物思ひもせず 〔巻二十・四四二五〕 防人の妻
昔年の防人の歌という中にあるから、天平勝宝七歳よりもずっと前のものだということが分かる。またこれは防人の妻の作ったもののようである。一首は、見おくりの人だちの立こんだ中に交って、防人に行くのは誰ですか、どなたの御亭主ですか、などと、何の心配もなく、たずねたりする人を見ると羨しいのです、というので、そういう質問をしたのは女であったことをも推測するに難くはない。まことに複雑な心持をすらすらと云って除けて、これだけのそつの無いものを作りあげたのは、そういう悲歎と羨望の心とが張りつめていたためであろう。「物思ひもせず」と止めた結句も不思議によい。
○
小竹が葉のさやぐ霜夜に七重着る衣にませる子ろが膚はも 〔巻二十・四四三一〕 防人
これも昔年の防人歌だと注せられている。一首は、笹の葉に冬の風が吹きわたって音するような、寒い霜夜に、七重もかさねて着る衣の暖かさよりも、恋しい女の膚の方が暖い、というので、膚を中心として、「膚はも」と詠歎したのは覚官的である。また当時の民間では、七重の衣という言葉さえ羨しい程のものであっただろうから、こういう云い方も伝わっているのである。この歌も民謡風で防人が出発する時の歌などに似ないこと、前に出した、「かなしけ妹ぞ昼もかなしけ」(巻二十・四三六九)の場合と同じである。ただの東歌に類した民謡をば、蒐集した磐余伊美吉諸君が、進上された儘に防人の歌としたものであろう。
○
雲雀あがる春べとさやになりぬれば都も見えず霞たなびく 〔巻二十・四四三四〕 大伴家持
これは家持作だが、天平勝宝七歳三月三日、防人を 校する勅使、并に兵部使人等、同に集える飲宴で、兵部少輔大伴家持の作ったものである。一首は、雲雀が天にのぼるような、春が明瞭に来たのだから、都も見えぬまでに霞も棚びいている、というので、調がのびのびとして、苦渋が無く、清朗とでもいうべき歌である。「さやに」は清に、明かに、明瞭に、はっきりと、などの意で、この句はやはり一首にあっては大切な句である。なぜ家持はこういう歌を作ったかというに、その時来た勅使(安倍沙美麿)が、「朝なさな揚る雲雀になりてしか都に行きてはや帰り来む」(巻二十・四四三三)という歌を作ったので其に和したものである。勅使の歌が形式的申訣的なので家持の歌も幾分そういうところがある。併し勅使の歌がまずいので、家持の歌が目立つのである。なお此時家持は、「含めりし花の初めに来しわれや散りなむ後に都へ行かむ」(同・四四三五)という歌をも作っているが、下の句はなかなか旨い。 校する勅使、并に兵部使人等、同に集える飲宴で、兵部少輔大伴家持の作ったものである。一首は、雲雀が天にのぼるような、春が明瞭に来たのだから、都も見えぬまでに霞も棚びいている、というので、調がのびのびとして、苦渋が無く、清朗とでもいうべき歌である。「さやに」は清に、明かに、明瞭に、はっきりと、などの意で、この句はやはり一首にあっては大切な句である。なぜ家持はこういう歌を作ったかというに、その時来た勅使(安倍沙美麿)が、「朝なさな揚る雲雀になりてしか都に行きてはや帰り来む」(巻二十・四四三三)という歌を作ったので其に和したものである。勅使の歌が形式的申訣的なので家持の歌も幾分そういうところがある。併し勅使の歌がまずいので、家持の歌が目立つのである。なお此時家持は、「含めりし花の初めに来しわれや散りなむ後に都へ行かむ」(同・四四三五)という歌をも作っているが、下の句はなかなか旨い。
○
剣刀いよよ研ぐべし古ゆ清けく負ひて来にしその名ぞ 〔巻二十・四四六七〕 大伴家持
大伴家持は、天平勝宝八歳、「族に喩す歌」長短歌を作った。これは淡海真人三船の讒言によって、出雲守大伴古慈悲が任を解かれた、古慈悲は大伴の一家で宝亀八年八月に薨じた者だが、出雲守を罷めさせられた時に家持がこの歌を作った。歌は句々緊張し、寧ろ悲痛の声ということの出来る程であり、長歌には、「聞く人の鑒にせむを、惜しき清きその名ぞ、凡に心思ひて、虚言も祖の名断つな、大伴の氏と名に負へる、健男の伴」というような句がある。この一首は、剣太刀をば愈ますます励み研げ、既に神の御代から、清かに武勲の名望を背負い立って来たその家柄であるぞ、というので、「清けく」は清く明かにの意である。この短歌は、長歌の方でいろいろ細かく云ったから、大要的に結論を云ったようなものだが、やはり句々が緊張していていい。大伴家の家運が下降の向きにある時だったので、ことに悲痛の響となったのであろう。この短歌も威勢のよいのと同時に底に悲哀の韻をこもらせているのはそのためである。
○
現身は数なき身なり山河の清けき見つつ道を尋ねな 〔巻二十・四四六八〕 大伴家持
大伴家持が、「病に臥して無常を悲しみ修道を欲して作れる歌」二首の一つである。「数なき」は、年齢の数の無いということ、年寿の幾何もないこと、幾ばくも生きないことである。人間というものはそう長生をするものではない。よって、濁世を厭離し、自然山川の清い風光に接見しつつ、仏道を修めねばならぬ、というのである。「道を尋ねな」と日本語流にくだいたのも、既に当時の人の常識になっていたともおもうが、なかなかよい。この歌には前途の安心を望むが如くであって、実は悲哀の心の方が深く滲みこんでいる。また仏教的の本性清浄観をただ一気にいっているようで、実は病痾を背景とする実感が強いのであるから、読者はそれを見のがしてはならない。この歌と並んで、「渡る日のかげに競ひて尋ねてな清きその道またも遇はむため」(巻二十・四四六九)という歌をも作っている。「わたる日の影に競ひて」は、日光のはやく過ぎゆくにも負けずに、即ち光陰を惜しんでの意。「またも遇はむため」は来世にも亦この仏果に逢わんためという意で、やはり力づよいものを持っている。こういうものになると一種の思想的抒情詩であるからむずかしいのだが、家持は一種の感傷を以てそれを統一しているのは、既に古調から脱却せんとしつつ、なお古調のいいものを保持しているのである。
○
いざ子ども戯わざな為そ天地の固めし国ぞやまと島根は 〔巻二十・四四八七〕 藤原仲麿
天平宝字元年十一月十八日、内裏にて肆宴をしたもうた時、藤原朝臣仲麿の作った歌である。仲麿は即ち恵美押勝であるが、橘奈良麿等が仲麿の専横を悪んで事を謀った時に、仲麿の奏上によってその徒党を平げた。その時以後の歌だから、「いざ子ども」は、部下の汝等よ、というので、「いざ子どもはやく日本へ」(巻一・六三)、「いざ子ども敢へて榜ぎ出む」(巻三・三八八)、「いざ子ども香椎の潟に」(巻六・九五七)等諸例がある。「戯わざなせそ」は、戯れ業をするな、巫山戯たまねをするな、というので、「うち靡ひ縁りてぞ妹は、戯れてありける」(巻九・一七三八)の例がある。一首は、ものどもよ、巫山戯たことをするなよ、この日本の国は天地の神々によって固められた御国柄であるぞ、というので、強い調子で感奮して作っている歌である。併し、「戯わざな為そ」という句は、悪い調子を持っていて慈心が無い。とげとげしくて増上の気配があるから、そこに行くと家持の歌の方は一段と大きく且つ気品がある。「剣大刀いよよ研ぐべし」や、「丈夫は名をし立つべし」の方が、同じく発奮でも内省的なところがあり、従って慈味が湛えられている。仲麿は作歌の素人なために、この差別があるともおもうが、抒情詩の根本問題は、素人玄人などの問題などではない。よって此歌を選んで置いた。
○
大き海の水底深く思ひつつ裳引きならしし菅原の里 〔巻二十・四四九一〕 石川女郎
「藤原宿奈麿朝臣の妻、石川女郎愛薄らぎ離別せられ、悲しみ恨みて作れる歌年月いまだ詳ならず」という左注のある歌である。宿奈麿は宇合の第二子、後内大臣まで進んだ。「菅原の里」は大和国生駒郡、今の奈良市の西の郊外にある。昔は平城京の内で、宿奈麿の邸宅が其処にあったものと見える。一首は、大海の水底のように深く君をおもいながら、裳を長く引き馴らして楽しく住んだあの菅原の里よ、というので、こういう背景のある歌として哀深いし、「裳引ならしし菅原の里」あたりは、女性らしい細みがあっていい。ただこういう背景が無いとして味えば、歌柄の稍軽いのは時代と相関のものであろう。
○
初春の初子の今日の玉箒手に取るからにゆらぐ玉の緒 〔巻二十・四四九三〕 大伴家持
天平宝字二年春正月三日、孝謙天皇、王臣等を召して玉箒を賜い肆宴をきこしめした。その時右中弁大伴家持の作った歌である。正月三日(丙子)は即ち初子の日に当ったから「初子の今日」といった。玉箒は玉を飾った箒で、目利草(蓍草)で作った。古来農桑を御奨励になり、正月の初子の日に天皇御躬ずから玉箒を以て蚕卵紙を掃い、鋤鍬を以て耕す御態をなしたもうた。そして豊年を寿ぎ邪気を払いたもうたのちに、諸王卿等に玉箒を賜わった。そこでこの歌がある。現に正倉院御蔵の玉箒の傍に鋤があってその一に、「東大寺献天平宝字二年正月」と記してあるのは、まさに家持が此歌を作った時の鋤である。「ゆらぐ玉の緒」は玉箒の玉を貫いた緒がゆらいで鳴りひびく、清くも貴い瑞徴として何ともいえぬ、というので、家持も相当に骨折ってこの歌を作り、流麗な歌調のうちに重みをたたえて特殊の歌品を成就している。結句は全くの写生だが、音を以て写生しているのは旨いし、書紀の瓊音※々[#「王+倉」、U+7472、下-183-13]などというのを、純日本語でいったのも家持の力量である。但し此歌は其時中途退出により奏上せなかったという左注が附いている。
○
水鳥の鴨の羽の色の青馬を今日見る人はかぎり無しといふ 〔巻二十・四四九四〕 大伴家持
同じく正月七日の侍宴(白馬の節会)の為めに、大伴家持が兼ねて作った歌だと左注にある。「水鳥の鴨の羽の色の」は「青」と云わんための序である。「青馬」は公事根源に、「白馬の節会をあるひは青馬の節会とも申すなり。其の故は馬は陽の獣なり。青は春の色なり。これによりて、正月七日に青馬を見れば、年中の邪気を除くという本文侍るなり」とある。馬の性は白を本とするといったから、当時アヲウマと云って、白馬を用いていたという説もあるが、私には精しい事は分からない。「限りなしといふ」とは、寿命が限無いというのであるが、この結句は一首の中心をなすものであり、据わりも好いし、恐らく、これと同じ結句は万葉にはほかになかろうか。中味は、「今日見る人は」とこの句のみだが、割合に落着いていて佳い歌である。家持は、こういう歌を前以て作っていたということを正直に記してあるのも興味あり、このくらいの歌でも、即興的に口を突いて出来るものでないことは実作家の常に経験するところであるが、このあたりの家持の歌の作歌動機は、常に儀式的なもののみであるのも、何かを暗指しているような気がしてならない。「いふ」で止めた例は、「赤駒を打ちてさ緒引き心引きいかなる兄か吾許来むと言ふ」(巻十四・三五三六)、「渋渓の二上山に鷲ぞ子産とふ翳にも君が御為に鷲ぞ子生とふ」(巻十六・三八八二)があるのみである。
○
池水に影さへ見えて咲きにほふ馬酔木の花を袖に扱入れな 〔巻二十・四五一二〕 大伴家持
大伴家持の山斎属目の歌だから、庭前の景をそのまま詠んでいる。「影さへ見えて」の句も既にあったし、家持苦心の句ではない。ただ、「馬酔木の花を袖に扱入れな」というのが此歌の眼目で佳句であるが、「引き攀ぢて折らば散るべみ梅の花袖に扱入れつ染まば染むとも」(巻八・一六四四)の例もあり、家持も「白妙の袖にも扱入れ」(巻十八・四一一一)、「藤浪の花なつかしみ、引き攀ぢて袖に扱入れつ、染まば染むとも」(巻十九・四一九二)と作っているから、あえて此歌の手柄ではないが、馬酔木の花を扱入れなといったのは何となく適切なようにおもわれる。併し全体として写生力が足りなく、諳記により手馴れた手法によって作歌する傾向が見えて来ている。そして其に対して反省せんとする気魄は、そのころの家持にはもう衰えていたのであっただろうか。私はまだそうは思わない。
○
あらたしき年の始めの初春の今日降る雪のいや重け吉事 〔巻二十・四五一六〕 大伴家持
天平宝字三年春正月一日、因幡国庁に於て、国司の大伴家持が国府の属僚郡司等に饗した時の歌で、家持は二年六月に因幡守に任ぜられた。「新しき」はアラタシキである。新年に降った雪に瑞兆を託しつつ、部下と共に前途を祝福した、寧ろ形式的な歌であるが、「の」を以て続けた、伸々とした調べはこの歌にふさわしい形態をなした。「いや重け吉事」は、益々吉事幸福が重なれよというので、名詞止めにしたのも、やはりおのずからなる声調であろうか。また、「吉事」という語を使ったのも此歌のみのようである。謝恵連の雪賦に、盈レ尺ニ則呈二瑞ヲ於豊年一云々の句がある。
此歌は新年の吉祥歌であるばかりでなく、また万葉集最後の結びであり、万葉集編輯の最大の功労者たる家持の歌だから、特に選んで置いたのであるが、この「万葉秀歌」で、最初に選んだ、「たまきはる宇智の大野に馬なめて」の歌に比して歌品の及ばざるを私等は感ぜざることを得ない。家持の如く、歌が好きで勉強家で先輩を尊び遜って作歌を学んだ者にしてなお斯くの如くである。万葉初期の秀歌というもののいかなるものだかということはこれを見ても分かるのである。
万葉後期の歌はかくの如くであるが、若しこれを古今集以後の幾万の歌に較べるならば、これはまた徹頭徹尾較べものにはならない。それほど万葉集の歌は佳いものである。家持のこの歌は万葉集最後のものだが、代匠記に、「抑此集、初ニ雄略舒明両帝ノ民ヲ恵マセ給ヒ、世ノ治マレル事ヲ悦ビ思召ス御歌ヨリ次第ニ載テ、今ノ歌ヲ以テ一部ヲ祝ヒテ終ヘタレバ、玉匣フタミ相称ヘル験アリテ、蔵ス所世ヲ経テ失サルカナ」と云っている。 |
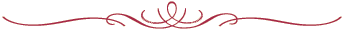
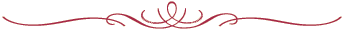
![]()
 旅
旅


 は
は
 校
校![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)