| 1969年 |
戦後学生運動史第8期前半期 |
| 東大闘争クライマックスとその顛末 |

更新日/2024(平成31.5.1栄和改元/栄和6)年.6.26日
これより前は、「全共闘運動の盛り上がり期(2)」に記す。
| (れんだいこのショートメッセージ) |
この時期は、「70年安保闘争」のクライマックスとなる。つまり、実際の70年はこの69年に及ばなかったということになるが、この経過の昂揚と衰退の陰りの要点を見ておくことにする。年明けの1.18日東大で「安田砦攻防戦」が闘われた。この闘いは、東大闘争の決戦としてのみならず、全国学園闘争の頂点として注視の中で戦い抜かれた。全共闘運動はこれ以降封鎖解除と再封鎖を交錯させつつ全国全共闘結成により「60年安保闘争」を上回る闘争を指針させようとしていくことになる。この間4つ目の全学連として誕生していた
反帝全学連の内部で社学同と社青同解放派の対立が激化し、3月、社学同側が単独で大会を開催し社学同派全学連を発足。7月には社青同解放派も解放派全学連として独立させた。この年は国立大学75校中68校が、公立大学
34校中18校が、私立大学270校中79校という実に全大学の半数(紛争校165校、うち封鎖・占拠されたもの140校)でストライキ-バリケード闘争が頻出
した。当時の全国の大学総数の37パーセントの大学で学内にバリケードが構築されたことになる。
全共闘運動は、ノンセクト・ラジカルと多岐多流のセクト潮流を結合させて、9. 5日、全国全共闘連合の結成に成功した。ここまでが70年安保闘争の正の面であったと思われる。ところが、私論ではあるが、全国全共闘連合は結成の瞬間より70年を待つことなく自壊していくことになった。その理由として三要因が考えられる。後述するが一つは、結集した各派セクトが自派の勢力の拡張と指導権をとることを優先させ、金の卵全共闘運動を自らついばんで行くことになった。全共闘運動はあまりに大きく結成されたこともあってか、共同的な運動を御していくことが出来なかった。個々の自立的な運動から始まったノンセクト・ラジカルが組織活動を担わねばならなくなった自己矛盾であったかも
しれない。一つは直前に誕生した共産主義者同盟赤軍派による更なる突出化闘争の否定的影響である。もう一つは、この頃から革マル派と社青同解放派、中核派間に公然ゲバルトが始まり、70年を目前に控えた最も肝心な69年後半期という不自然な時期にオカシなことが起こったことである。これらが否定現象となりつつ、長期化する闘争にノンセクト・ラジカルが脱落し始め、一般学生のサイレント・マジョリティーが民青同の動きを支持し始める流動局面が生まれていった。
70年安保闘争はこうして本番の70年を向かえるまでもなく急速に大衆闘争から「浮き」始めていた。私は、どこまで意図・誘導したのかどうかまでは分からないが公安側の頭脳戦の勝利とみる。同時に日本左翼は本当のところ「自己満足的な革命ごっこ劇場」を単に欲しているだけなのではないかと見る。併せて、いわゆる内ゲバ=党派間ゲバルトについて、それを起こさせない能力を左翼が初心から獲得しない限り、不毛な抗争により常に攪乱されるとみる。往年の総評指導者太田薫は、「現在の学生運動と労組の実情から見れば、1970年に十年前の安保闘争を期待することはできない。もっと他の闘争方法を考えなければならない」との言葉を残している。
|
| 「戦後学生運動の歴史(1969年1月-3月)」、「戦後学生運動の歴史(1969年4月-6月)」その他参照。 |
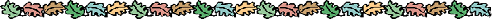
| お知らせ |
| 当時の政治状況については「戦後政治史検証」の「1969年通期」に記す。本稿では、当時の学生運動関連の動きを記す。特別に考察したい事件については別途考察する。 |
全国で15大学がバリケード封鎖で越年した。越年したのは次の通り。東京大学、東京教育大学、東京外国語大学、電気通信大学、日本大学、中央大学、明治学院大学、青山学院大学、芝浦工業大学、山梨大学、富山大学、大阪大学、神戸大学、完済学院大学、長崎大学。
1.4日、法学部の加藤総長代行による非常事態宣言が発表され、東大闘争が決戦化の流れに入った。加藤代行と坂田文相との入試中止決定には、1.15日までに事態収拾の場合は再協議という条件が付されていた。スト解除による正常化をして入試を実施したい大学側は、事態収拾を急いでいた。
1.5日午前2時頃、九州大学のファントム機残骸が突然何者かによって引き降ろされる事件が発生した。
1.6日、沖縄「いのち守る」県民共闘会議が、B2撤去を求め、2.4日ゼネスト実施を決定。
1.9日、民青同都学連と右翼の混成部隊約1000名が北寮、明寮を占拠して駐留。
| 【東大で全共闘と日共が激突】 |
| 1.9日、大学当局と日共系、一般学生との闘争収拾工作は着々と進み、共闘会議は苦境にたった。「7学部集会」を翌日に控えたこの日、都内9大学の全共闘と各派3千人が安田講堂前で「東大闘争・日大闘争勝利全都総決起集会」を開催した。日共系学生も3千人を動員して対峙し、全共闘は安田講堂、日共系学生は教育学部と理学部の建物にたてこもった。「非妥協的に闘いぬくほかない」強硬なノンセクト・ラジカルズの突き上げに各セクトが足なみをそろえ、全共闘は「闘争の圧殺者、民青を実力粉砕」という強硬方針をうち出し機動隊導入の危険をあえておかしても学内の民青勢力を攻撃することを申し合わせた。 |
| 午後7時過ぎ、東大闘争勝利総決起集会後、全都から動員した数千人の反日共系ゲバ部隊(革マル派を含む)が民青同の根拠地化していた教育学部奪還闘争の挙に出て教育、経済両学部になだれこみ民青同と激突、激烈な流血の乱闘になった。重軽傷100名余。東大闘争での内ゲバで火炎瓶が初めて使用される。午後8時、機動隊が導入され構内をかけぬけて安田講堂前に集結した。講堂の中は安田城攻撃かと緊張したが、機動隊は催涙ガスを乱射しただけで撤退した。 |
| 【東大に機動隊導入】 |
|
1.9日午後8時16分、加藤総長代行は、「第一に経済学部で危険な状態にある学生の救出、第二に教育学部で包囲されている学生の救出、およびそれに伴う必要な措置をとるため警察力の出動を要請する」旨を警察当局に伝えた。これによって、全共闘系の学生のみが51名逮捕された。日共系学生の窮地を救った。この時の機動隊導入は、学生運動内部のゲバルト抗争に対してなされたものであり、それまでの対大学当局と学生間の抗争に関連しての導入ではないという内容の違いが注目される。
この経過に関して、日共が次の様に対応したことを明確に述べている。
|
「東大では、学生、教職員自ら暴力集団の襲撃を阻止し、 校舎封鎖を解消する闘いを進め、1.9日には、7学部代表団と大学当局との交渉を妨害する為に各地から2千人をかき集めて経済学部、教育学部を襲った暴力集団の襲撃を正当防衛権を行使して机やいすのバリケードなどで跳ね返した」、「党は、これらの闘争が正しく進むよう積極的に援助した」(「日本共産党の65年」257P)。
|
「野次馬雑記」は次のように記している。
| 「午後11時。とつぜん現われた民青の大ゲバルト部隊800人が隊列をととのえて安田講堂に攻撃をかけた。講堂内の守備部隊は30人余り。主力は同夜行われた共闘会議派の駒場の民青攻めに参加していた。民青系はそのすきをついた。新式の投石器などをつかって講堂正面に石の雨をふらせ、突撃部隊がかん声をあげてつっこんだ。共闘会議派もバルコニーの上から投石で反撃、火炎ビンを初めて使った。かなりの負傷者を出した民青系は午前2時攻撃を中止。講堂正面のガラス窓はほとんど破れたが守備隊は無傷。安田城の堅固さが改めて証明された形になった」。 |
|
| 【東大で「7学部集会」開催され、民主化行動委と当局の間で十項目確認書に署名】 |
| 1.10日、昨年末の昨年末の加藤代行と坂田文相会談での翌年の1月15日までの事態収拾如何による東大入試の中止決定問題に決着をつけるべく、東京青山の国立秩父宮ラグビー場で約8000名の学生を集めて東大「東大7学部学生集会」が開かれ、医・文・薬の3学部を除いた7学部、2学科、5院生の学生・院生の代表団と東大当局の間で「確認書」が取り交わされた。民青同がこれを指導し、泥沼化する東大紛争の自主解決の気運を急速に盛り上げていくことになった。予想以上に多くの学生が結集したと言われている。紛争疲れと展望なき引き回しを呼号し続ける全共闘運動に対する厭戦気分が反映されていたものと思われる。 |
「7学部集会」での「十項目確認書」の内容は次の通リ。
|
大学当局は、大学の自治が教授会の自治であるという従来の考え方が誤りであることを認め、学生・院生・職員も、それぞれ固有の権利を持って大学の自治を形成していることを確認する。 |
| 2 |
学内での学生も自治活動に関する警察の調査や捜査については、これに協力せず、警察の要請があった場合にも原則的にこれを拒否する。 |
| 3 |
大学当局は、原則として学内「紛争解決の手段として警察力を導入しないことを認める。 |
|
| 【全共闘が「闘争収拾の為の代議員大会粉砕」指針】 |
| 「十項目確認書」の内容は当初全共闘側が目指していたものであるが、全共闘運動はいつの間にかこうした制度改革闘争を放棄し始め、この頃においては「オール・オア・ナッシング」的な政治闘争方針に移行させていた。 |
| この時、全共闘約3000名は、「闘争収拾の為の代議員大会粉砕」を掲げて参加を拒否、安田講堂の封鎖解除強行にそなえて防衛体制を固めつつ全都総決起集会を開催した。粉砕行動の反帝学評系149名が青山通りで逮捕された。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| この頃全共闘は、民青同ペースの「7学部集会」に反発するばかりで、制度改革闘争を含めた今後の東大闘争に対する戦略-戦術的な位置づけでの大衆的討議を放棄していた観がある。なぜかは分からないが、運動の困難に際したときに、決して大衆的討議の経験を持とうとしないというのが新旧左翼の共通項、と私は思っている。この頃より一般学生の遊離が始まったと私はみる。それと、全共闘運動がなぜ制度改革闘争を軽視する論理に至ったのかが私には分からない。果たして、我々は戦後人民的闘争で獲得した制度上の獲得物の一つでもあるのだろうか。反対とか粉砕とかは常に聞かされているが、逆攻勢で獲得する闘争になぜ向かわないのだろう。 |
| 【東大駒場でも安田講堂を占拠する全共闘に民青同系学生が襲撃】
|
1.10日、東大駒場で安田講堂を占拠する全共闘と民青の間で乱闘(民青同系学生が安田講堂を襲撃、文一・二号館の封鎖解除を強行)。民青は寮の屋上からピッチングマシンで投石し、全共闘側は捕まえた民青を殴打し、拷問した。
同日夜の午後11時、民青の大ゲバルト部隊800人が隊列をととのえて安田講堂に攻撃をかけ、東大本郷でも全共闘と民青が乱闘。民青系は午前2時攻撃を中止。 |
「荒岱介 2001」が次のように証言している。
| 日共民青はそれを阻止せんとしゲバルト部隊が派遣されていた。集会後全共闘は法および経済学部に突入し、再占拠を企てた。本郷全体でゲバルトになったのである。タ闇の中、教育学部屋上で民青との問に火炎ピンの投げ合いになったのを思い出す。火炎ビンは安田講堂内ではこのとき既に、多量に作られていたが、表だって使用されてはいなかった。(略)バリケードを築き、投石し合う中、村松はライターで布切れに火をつけたウイスキーピンを投げた。ガチャン、ボワ!と青い炎が広がり、投げつけられた民青はワァ!と後方に逃げて行った。追いかける私たち、そして再び火炎ビンが投げられたが、今度は不発だった。途中で火が消えてしまったのだ。それを拾った暗闇の中の民青は、火をつけて逆にこちらに投げ返した。放物線を描いて小さな炎が飛んで来て、それが私の足許に落ちた。次の瞬間、ボワァと青い炎が私の足許に広がった。「ワァ!」と思わず飛びのいた。「民育が火炎ピン投げんのか」と叫ぶと、「そっちが投げたんだろ」と聞の中から言い返してきた」()。 |
| 10日夜から日共民青は安田講堂に対しても攻撃をかけ、これは占拠中の東大全共闘と支援に駆けつけた中大会中闘でしのいだが、リヤカーにピッチングマシンを積んで撃ちながら攻めてきたという。法文一、二号館のバリケードがその結果解除された。この攻撃は11日午前中まで続き、全共闘側は火炎ピンを投げて抵抗した。本郷にやってきたのは地区民(地域の日共党員)
で、1000名はゆうにこえる大部隊だったという。 |
|
1.11日、駒場寮の屋上で行われた教養学部の代議員大会では、ストライキ解除提案が491票で可決されたとされる。このストライキ解除決議は、駒場の全学生の投票での確認が必要であり、1.15日の開票によって、有効投票数3775のうち賛成3178、反対329、保留249、白表19という結果になった。1.11-14日、東大医・文学都を除く八学部であいついでスト解除となる。
1.12日、東大、民青同と右翼系が「防衛隊」を組織し、その護衛下で6学部のスト解除、封鎖解除等を目指す「全学投票」を寮食堂及び北寮で行う。投票者が極めて少なかった。民青同5号館占拠。この頃より安田講堂の封鎖解除を促すために大学当局より機動隊導入が予告された。
1.13日、依然投票者少なく、防衛隊が投票所防衛の名目で正門から北寮への通りを武力制圧、第8本館への投石始める。駒場共闘の300名がこれに抗議してデモを行う。防衛隊の阻止線を突破して八本前集会を行う。民青同は、一研、5号館を占拠し泊り込み。
1.14日、東大加藤代行が”機動隊導入してでも入試実施“を表明。
1.14日、警視庁、”七〇年闘争にそなえ“機動隊二千五百名、公安私服千名の增員、全国で八万五千名に完全装備・出動態勢を決定。
1.14日、夕方から民青同の総攻撃が開始される。駒場共闘200名が八本前に結集し、バリケード構築し徹夜集会を行う。
1.14日付け秘密公電が2000.6.9日開示された。文書は、ジョンソン駐日大使がラスク国務長官へ送ったもので、それによると、佐藤首相は、「非核三原則はナンセンス」と明言している。同大使が離日の挨拶に訪れた際、保利茂官房長官らを交えて会談した際の発言。佐藤首相は、67.12.11日の衆院予算委員会で、非核三原則を表明していた。電文は、米政府内で懸念されていた日本の核武装論を打ち消す形で、「これで日本が核兵器を持ちたがっていると解釈すべきではない」とコメント付けされている。
1.15日、八本前に結集した400名に民青同の武装部隊が襲い掛かり、委員長・今村他数名がリンチされる。防衛隊は1階に入り、電気水道を止める。
| 【1.15日、東大安田講堂前で「全国学園闘争勝利労学総決起集会」】 |
1.15日、学外者の構内立入り禁止告示を蹴って、東大の安田講堂前で「東大闘争勝利・全国学園闘争勝利労学総決起集会」が開かれ、11・22についで再び全共闘系3千5百名の学生、青年労働者が集まった。東大全共闘は、機動隊が導入されるという情報を得て、法学部研究室、工学部列品館、法文二号館、医学部図書館、安田講堂のバリケードを強化し、資材と食糧を運び込んだ。
安田講堂に残って全員逮捕を覚悟で闘う東大全共闘約150名、各派から500名近くの籠城部隊が決まり籠城した。講堂に残るか出るかの任務分担は上からの指令でなく、各グループごとに話しあい、すべて納得づくで決められた。全共闘は今後の闘いのために活動家の半数以上を温存し、機動隊導入のさいは講堂から撤退させることにした。こうして全共闘運動は東大安田講堂決戦(東大時計台闘争)でクライマックスを迎えることになった。中核派は法研、ML派は列品館、革マル派は法文2号館というように、各派が主要な建物を一つずつ受け持っていた。この頃、山本義隆東大全共闘議長に逮捕状が出た。当局の掲示により、日共系学生は学外から退去した。
|
籠城組の防衛の様子が次のようにルポされている。
| “解放講堂死守”戦術は何度もの代表者会議で確認されていた。機動隊の攻勢にできる限り長く抵抗し10日間は籠城できるような体制をとった。500名が10日間は持ちこたえるくらいの食料が運び込まれた。米、ニギリメシ、パン、インスタントラーメン、カンパン、ミカン・・・時計塔の一部屋が食料庫にあてられた。ガス、水道、電気が断たれるのを覚悟して飲料水、石油、ロウソクも容易され、炊事、医療班として女子学生10余人も籠城組に加わった。バリケードも考えられる限りの補強をした。階段という階段にはロッカーや机がぎっしりと積み上げられ太い針金でしばりつけられた。スキマにはセメントを流し込みコンクリート固めした。火炎ビン、硫酸、塩酸などが用意された。バリがこわされたあと、これらを投げつけ機動隊を寄せつけないための“時間かせぎ武器”とした。2階から3階へ階段も同じように固められた。窓という窓にはベニヤ板が2枚、3枚と重ねて打ち付けられた。ビニール・テープで十分な目張りも行われた。 |
|
1.16日、東大当局は、依然、占拠を続ける全共闘学生との意見の合致は不可能と判断し警察力の導入を決断。午後1時、加藤代行らは警察へ出向き、警視庁に正式に機動隊の出動要請をした。
1.17日午後11時5分、加藤総長代行名で退去命令がだされた。
1.17日、全共闘系の学生は、決戦を控えて守備隊を配置し、他の者は学外へ出た。その後の闘争指導のため学外に出る者も必要だった。安田講堂には志願者を、医学部図書館と法文二号館には医学部と文学部の部隊が入り、教養学部では、第八本館を全共闘駒場部隊が防衛していたので、安田講堂はそれ以外の学部で防衛しなければならなかった。安田講堂に、学外からの支援学生が続々と到着するなかで、東大全共闘の学生たちの数は減っていった。最後の日に安田講堂に入ってきた東大の学部学生は約40人だった。東大全学学生解放戦線の今井澄が安田講堂防衛隊長に指名された。
1.17日、民青同、右翼系がガスを止める。この頃、教養教授会で民青同の対全共闘包囲作戦を討議。この時反対した教官は衛藤審吉ら数名。その論拠は珍奇であったと伝えられているが不明。
1.18日午前6時、民青同が教育学部より石などを運び出し、赤門前路上を掃き清めて全員逃亡。
| 【安田攻防戦前の民青同と革マル派のおかしな動き】 |
この時の民青同の動きが次のように伝えられている。機動隊の安田講堂突入の事前情報をつかんだ宮顕は、再び川上氏に直接指令を出し、“ゲバ民”側の鉄パイプ、ゲバ棒1万本を一夜の内に隠匿、処分させた。平井啓之ら教官立会いの元に角材を焼いて、鉄パイプを捨てるというセレモニーを行った。
この時の革マル派の動きが次のように伝えられている。「ウィキペディア・東大安田講堂事件」は次のように記している。
| 全共闘系内部においては早稲田革マルの藤原が中心となって、全学バリケード封鎖反対の説得を各派に恫喝的に説得する。
結果的に全学バリケード封鎖は中止となり、背景を知らない学生の一部では「栗田艦隊謎の反転」と語られる。民青系に敗北したと言うより、民青系と衝突してでも強行しようという意思が、内部から崩壊したのである。 |
直前にも、次のような不審な動きを見せている。
| 概要「東大では、革マル派は他のセクトと共に、全共闘のメンバーになっていた。そして、安田講堂決戦の日には、安田講堂を全共闘が守り、大きなセクトがそれぞれ、中核派は法研、МL派は列品館というように、主要な建物を各セクトが一つずつ受け持った。革マル派が守備することになったのは法文2号館で、安田講堂と法研の間にある重要な地点だった。同派はこの時他セクトとともに全共闘守備隊に入っており、16日夜の東大全共闘の最終確認に対して『50人から100人の部隊を必ず出す』と約束していたが、機動隊導入の前夜に担当していた法文2号館から退去、そこに機動隊が陣取ることで封鎖されていた隣の法研・安田講堂の封鎖解除を容易にさせるという不自然な動きを示した。やすやすと法文2号館の屋上に陣取った機動隊は、ここから隣の法研に居た中核派に催涙ガスを打ち込むことになった」。 |
|
革マル派の黒田寛一は、「革命的マルクス主義とは何か?」の中で、全共闘運動を「左翼急進主義」と規定して、その暴力や破壊を次のように批判している。
| 学園や経営などを少数精鋭主義的に「占拠」することを自己目的化するだけではなく、 バリケードによってつくられた箱庭的小空間を<コミューン>とか<解放区>とかとするにいたっては、本質上、子供の遊びとなんらえらぶところがない。それは、まさにコミューンのカリカチュアでしかない。…中略…そうした「占拠」によって偶然的な自由を獲得し持続することの直接的な延長戦上に、権威もなく権力も存在しない社会の創造を、政府が経済的有機体に解消された無政府的社会の出現を、夢想することは、明らかに、すでにプロレタリア階級闘争の歴史そのものによって破産を宣告された小ブルジョア社会主義の時代おくれの復活でしかなく、またアナルコ・サンディカリズムの轍をふむ以外のなにものでもありえない。 |
|
| 【安田攻防戦前の第二次ブントの動き】 |
| この時の第二次ブントの動きが次のように伝えられている。8回大会で指導部となっていた仏(さらぎ)徳二、松本礼二、田原芳らが、小川町の中大学館の同盟政治局に学対責任者にして現場指導者であった荒、高原浩之を呼び出し、「革マル派は撤退した。社学同も早く出ろ。出ないなら俺は知らん」と指示している。これに対し、荒らの社学同全国委部分は安田講堂死守戦貫徹に向かう。(荒岱介編著「ブントの連赤問題総括」参照) |
| 【安田攻防戦前の打ち合わせと籠城の様子】 |
「野次馬雑記」が、「安田攻防戦前の打ち合わせと籠城の様子」を次のように伝えている。
「安田講堂に残って、全員逮捕を覚悟で戦う籠城部隊は約400人と決まった。東大全共闘も約150人近くの籠城組を決めた。全共闘は今後の闘いのために活動家の半数以上を温存し、機動隊導入のさいは講堂から撤退させることにした。講堂に残るか出るかの任務分担は上からの指令でなく、各グループごとに話しあい、すべて納得づくで決められた。家庭の事情、身体の調子が考慮に入れられ、個人の自発的意思が尊重された。講堂をでるものに、戦線離脱者としての後ろめたい気持ちはまったくなかった。むしろ外へ出る組にはこれからもつらい苦しい戦いが待っている。学生たちは長い闘争にすでにかなり消耗していた。籠城して戦えばともかくそこで一区切りつく、疲れた学生たちの頭にはそんな考えすらあった。籠城組に決まった者は逮捕に備えて身辺を整理した。長年、家庭教師をやってきた教え子に、しばらく会えないからと後任を見つけに走るものもいた。
籠城組の“解放講堂死守”戦術は何度もの代表者会議で確認されていた。圧倒的な機動隊の攻勢にできる限り長く抵抗すること。警察側の持久戦法も想定して10日間は籠城できるような体制をとったが、全面的な攻撃に対してせめて1日間は持ちこたえたいと幹部は考えていた。そして500人が10日間は持ちこたえるくらいの食料が運び込まれた。米、ニギリメシ、パン、インスタントラーメン、カンパン、ミカン・・・時計塔の一部屋が食料庫にあてられた。ガス、水道、電気が断たれるのを覚悟して飲料水、石油、ロウソクも容易され、炊事、医療班として女子学生10余人も籠城組に加わった。
バリケードも考えられる限りの補強をした。1階の窓や出入口は多すぎて、完全防衛はとても不可能なこと。したがって、1階が破られることは覚悟したが、要は5つの階段をがっちり固め、2階以上に機動隊を上げなければいいのだ。階段という階段にはロッカーや机がぎっしりと積み上げられ、太い針金でしばりつけられた。そのうえ、スキマにはセメントを流し込み、コンクリート固めしたうえで、文字通り“砦”とする予定だったが、これだけは資金不足と時間不足で十分なことはできなかった。代わりに火炎ビン、硫酸、塩酸などが用意された。バリがこわされたあとも、これらを投げつけ、機動隊を寄せつけないための“時間かせぎ武器”だ。
2階から3階へ階段も同じように固められた。したがって2階防衛班は1階からの階段が陥落したらもう逃げるところはない。“退路”を断ったうえでの徹底抗戦の構えだ。3階、4階組も同じ。窓という窓にはベニヤ板が2枚、3枚と重ねて打ち付けられた。ビニール・テープで十分な目張りも行われた。催涙ガスへの備えも一応は十分である。
1月17日午後11時5分、加藤総長代行名で退去命令がだされた。いよいよ機動隊との対決の時がせまった。安田講堂の出入りが激しくなり夜明けまで続いた。「がんばれよ」「お前もな」残る者、去る者、それぞれが目顔であいさつし、短い言葉を交わして別れていく」。 |
|
「No 322-1 ある「元中核派活動家」の回想 1967-1969 その3」の「東大闘争への関わり」が次のように証言している。
| 私は1月9日に、中核派の行動隊として安田講堂に入った。いよいよ1月15日、成人式の日、私も覚悟しました。それまでは何とか切り抜けて来たけれども、1月15日は東大で玉砕しようと思って、安田講堂に決死部隊として立てこもった。15日に機動隊が来るということで、私が選ばれて、安田講堂の中段のバルコニーのところで中核旗の下に哨兵のように立っていた。ヘルメットを被って、機動隊の放水車の放水に飛ばされないように足には鎖を巻いた。中核派の部隊はメインの部隊で、講堂の中の階段はコンクリートでふさいだ。結局、その日は機動隊は入らなかった。夜、東京部隊は除隊となり、私は夜の12時頃、最終電車で帰った。中核派の地方部隊はそのまま寝泊まりした。18日の朝、下宿で機動隊が安田講堂に入ったことを聞いた。それで、すぐに御茶ノ水に行った。御茶ノ水の明大通りから石を持って安田講堂に向かおうとして、機動隊と闘ったが前に進む事は出来なかった。安田講堂にいた中核派の部隊は地方部隊が主力です。 |
|
| 【安田攻防戦が二日間にわたって激闘】 |
| 1.18日-19日、東大闘争の決戦として安田砦攻防戦が闘われた。安田講堂は、1925(大正14)年に財閥・安田善次郎の寄付により完成した鉄筋コンクリート造4階建てで、特徴的な時計台を持つ事で知られるいわばアカデミズムの権威を象徴する建築物であった。全共闘はこれを闘う砦として占拠し、解放区としていた。 |
|
1.18日午前5時45分。安田講堂のいわゆる「時計台放送」は次のように叫んだ。これが幕あきとなった。
| 「こちらは時計台防衛司令部。ただいま、機動隊は全部、出動しました。すべての学友諸君は戦闘配置についてください。われわれのたたかいは歴史的、人民的たたかいである」。 |
|
午前7時前、警視庁警備部は8個機動隊8500名を動員し東大本郷構内に導入した。東大全共闘の主力は、その後の闘争の継続に備えて学外にでた。安田講堂など4つの建物にたてこもる全共闘学生を機動隊が排除に向かった。(これに先立ち、加藤総長代行がハンドマイクで説得するセレモニーを行っている。時日は今のところ不明)
午前7時頃、医学部総合中央館と医学部図書館からバリケードの撤去が開始された。機動隊は、投石・火炎瓶などによる学生の抵抗を受けつつ一万発以上の催涙彈射撃・
空陸からのガス液放射。80名のピストル部隊等官憲の全面攻撃により医学部本館・工学部列品館・法学部研究室・経済学部等の各学部施設の封鎖を解除し安田講堂を包囲した。
午前8時20分頃、機動隊が構内に姿を現わしてまもないこの時刻、正門前にいた青年・学生たちが警備線を突破して約300名デモを組み、講堂前まで進んだ。彼らと講堂の屋上の学生たちは互いに手を振りあった。
午後1時頃、安田講堂への本格的な封鎖解除が開始された。しかし強固なバリケードと学生の予想以上の抵抗に機動隊は苦戦を強いられた。
午後3時すぎ、占拠学生二百五十六名逮捕。東大支援総決起集会〔中大〕に各派学生2千名結集、のち労学市民五千名で神田周辺にバリケード構築、解放区闘争で69名逮捕。
午後5時40分、警備本部は作業中止を命令した。やむなく一旦撤収、放水の続行を残し作戦を翌日に持ち越す。その日の攻撃は中止となった。 |
1.19日、安田講堂に終夜放水攻撃を続けた機動隊は未明から弾圧を再開した。 午前6時30分、各セクトから選ばれた500名の学生が立てこもる中、機動隊8500名が封鎖解除再開した。この日も学生の激しい抵抗があったが電気ドリル、切断機を使ってバリケードを破り、12時30分には2階まで侵入。2時50分には4階まで制圧した。
安田講堂防衛隊長に指名されていた東大全学学生解放戦線の今井澄氏が午後5時 50分、次のようにメッセージした。
機動隊の制圧・破壊の中、屋上で最後まで抵抗していた学生たちは「インターナショナル」を歌いながら今井澄行動隊長の指揮に従って抵抗を終えた。午後5時46分、学生90名検挙、374名全員逮捕、屋上の赤旗が外され、二日間35時間にわたる激闘後落城した。
この間の様子は全国にテレビ放送され釘付けになった。全共闘の闘いぶりと機動隊の粛々とした解除と学生に対する生命安全配慮ぶりが共感を呼んだ。東大安田講堂攻防戦等の二日間の学生側の負傷者総数269名(重傷76名)、内訳は火傷109(35)、打撲87(17)、裂傷65(24)、骨折8、眼球損傷19(「安田講堂1968-1969」島泰三著)。この闘いで、全共闘各派の767名(東大生38名、女性17名)が逮捕、そのうち616名が起訴された。一審では133名が最高懲役4年の実刑、12名が無罪となった。負傷者は警察官710名に対し、学生側は47名ともある。
|
安田講堂事件の逮捕者数につき、「東大安田講堂の攻防戦から半世紀、東大生逮捕「わずか9人」は本当か」が次のように記している。
| 当初はマスコミによってばらばらだったが、377人と結論づけている。そのうち東大生については「わずか9人」とか「20人」などと報じられたことがあったが、実際には65人が起訴され、逮捕者は80人以上。法学部だけでも20人が捕まったという。和田さんは未決囚として中野刑務所に69年8月まで勾留され、独房生活。72年に控訴審判決が出て75年に執行猶予期間が満了した。「私は六九年から六年かけて、安田講堂攻防戦の責任をとったことになる」と書いている。
|
|
| (参考資料) |
2009.1.26日付け週刊「前進」(2376号)の「東大安田決戦40周年許されぬ歴史の偽造 東大闘争元被告 山本卓雄」を転載しておく。
1969年1月18~19日の東大安田決戦から、早くも40周年を迎え、マスコミもテレビや新聞が幾つも特集を組んだ。そのほとんどが現在につながらない過去の消耗な回想だったが、なかでも日本テレビが1月14日に放送した「東大落城」という2時間のドラマ仕立ての特別企画は、特にひどかった。歴史の偽造そのものでもあった。
一方の主役が権力側の現場指揮官だった佐々淳行(警視庁警備一課長)で、その言動なども怒りに堪えなかったばかりか、学生側の主役が工学部列品館に立て籠(こも)ったML派(毛沢東主義派)だったことも、安田決戦の実際の主軸とはかけ離れていた。列品館は重傷者が出たりしたため、早々と白旗を掲げて落城した。しかもML派はとっくに消滅し、現在の階級闘争とは無縁だ。
法文2号館から一人残らず敵前逃亡したカクマルは問題外だが、最大の主役の一人である東大全共闘の山本義隆議長も、最大部隊の中核派も、まったく出てこない。思い返せば、わが中核派は全国結集した二百数十人の部隊で、70人以上が籠城(ろうじょう)した東大全共闘とともに、最後まで責任を取り切って闘った。中核派は、安田砦防衛の最重要部署である2階と、時計塔の6階、そして正門を入って右側の要衝、法研(法学部研究室)を受け持ち、大量の火炎瓶、鉄パイプと、石やブロック片で徹底抗戦し闘った。
2日間の逮捕者総数は786人、起訴は540人。私の大学は東大全共闘に次ぐ50人の部隊が上京して籠城し、法研砦(とりで)死守戦を軸に奮戦。私自身は1年8カ月近く未決勾留され、2年の実刑をくらった。「安保粉砕・日帝打倒」「帝大解体」などのスローガンを掲げて闘われた東大闘争の歴史と精神は、革命勝利をめざす現在の革共同と中核派の闘いの中に生き生きと継承されている。 |
|
「1・19と私 野坂昭如」(サンデー毎日1969.2.20号)転載。
1月19日午前六時半、近くに住む週刊記者A氏が迎えにきた。この日、東大構内へ入るには、報道の腕章が必要で、それを貸してもらうべく、また、ぼくは警察機動隊のそばへ近づいたことがこれまでなく、A氏は安保改定以来、羽田、新宿とたびたび経験しているから、今日の先達とたのむ気持ちもある。(中略)赤門前の、隊員の列を分けて、構内に入る。職員と腕章を付けた老人が一人いるだけ。道を横切って、ふくらみきった太いホースが五本延びている。歩くにつれ催涙ガスが眼にしみるが、そのよどみ方はきまぐれで、涙が出たりひっこんだりする。映画の撮影現場の如く、安田講堂の周辺だけが、放水投石怒号でごったがえし、ほんの二百メートルはなれると、大学構内日曜の朝にふさわしく、深閑としずまっていて、なにやら現実感がうすい。(中略)NHKの腕章がやたら目立ち、トランシーバーで連絡をとりあっている。後詰めの隊員が、アルバムに貼られた、学生活動家の写真をながめている。放水は水圧の関係か、二、三分勢いいいが、すぐに老人の小水の如く、しぼんでしまう。(中略)大型ヘリコプターがドラム缶のようなものを吊り下げ、飛来して、催涙液を散布する。こちらまでしぶきがとんで、眼が痛い。「ああ、ヘリコプターよりの催涙液は、さして効果なく、かえって地上に被害ある故、中止されたし、どうぞ」、「了解、なおこの交信は傍聴されているおそれあり、気をつけるように、どうぞ」、「わかりました、どうぞ」。隊員の一人が、大型トランシーバーで連絡をとる。ヘリコプターは二度、三度まわって、今度は、乗員の一人が、ねらいさだめて、催涙弾を投下する。(中略)
お茶の水に向かう。本郷三丁目を中心に、おびただしい機動隊がいて、通行人も歩道いっぱいにあふれている。立ち止まることは許されず、中にはあからさまに文句を言う男がいる。お茶の水駅の近くで喫茶店に入る。明治大学の通りは、商店すべて店を閉めているが、横丁は、シャッター半ば降ろしながらも、営業し、A氏に注意されて、みると駅前の交番が、打ちこわされ、中からおびただしい水が流れ出ている。コーヒーいっぱい飲んで、中央大学へ向かい、ここも、ここも門をバリケードで固め、人一人ようやく通れる入口からのぞくと、ヘルメット姿の学生が、いわゆる集会中で、十人、二十人と少数ながら、旗押したてた連中が、つぎつぎと吸い込まれ、入ろうとしたら、「闘う意志のない者は、駄目」と、さえぎられる。フランス人記者があらわれ、やはりフランス語で断りをくう。(中略)
また東大へもどる。(中略)目にみえる、屋上の投石者たちはまだいい、くらがりの中で、絶対に勝ち目のない闘いいどもうとする若者は、なにを心の支えとしているのか、ぼくは、よほど、安田講堂に籠城しようかと、考えた、機動隊の側からばかり見ていては片手落ちで、全共闘と共にいる、たとえば報道関係者がいてもいいはず、いや、当然必要であろう。籠城側がゆるさなかったのかもしれないが、このおびただしい腕章の群れを見ると、不思議な気がする。(中略)指揮者が、マイクで放水の目標を指示する。左側の屋上に、男が仁王立ちとなり、なにかしゃべっているが、ききとれぬ「かえりたまえ、すぐ、立ち去れ」とだけわかり、自分にいわれているようで、まともに男を見られない。なんのために、ぼくはここにいるのか、いやしくも全共闘支持を、たとえ心情的共感にしろ、ゆるぎないはずなのに、「頑張れ」と、声ひとつかけられない、機動隊が怖いのだ。(中略)ふいに、時計台右側の窓から、スピーカーがあらわれ、男の声でしゃべりはじめる、よくききとれない。放水車がスピーカーを狙うがとどかぬ。スピーカーは赤い布団でおおわれている。「お茶の水で、バリケード構築中の学生が一人死んだ」。報道の一人がいう。「しばらくこのままですね。もう一度お茶の水へ行きましょうか」。A氏が提案し、腹が減ったからにぎり飯をほばりつつ、本郷三丁目を過ぎて、ふと前方を見ると、道いっぱいに群衆がいて、十字路になった角の、ガソリンスタンドを中心に、二方向で楯をかまえる機動隊と、対峙している。 |
|
| 【吉本隆明氏の東大闘争論】 |
吉本隆明氏は、著書「情況」の中の「収拾の論理」の項で、東大闘争の一部始終を評して次のように述べている。(「第1174回 2009/01/24 昭和の抵抗権行使運動(87)東大闘争(4)」)
ここ数年来火をふきだした大学紛争の過程で、大学教授研究者たちが、ジャーナリズムと戦後社会から過剰に甘やかされて育てられた、社会常識以下の判断力しかもたない過保護な嬰児にすぎないことが暴露された。
急進的な学生たちを先頭とする〈学閥支配体制を解体せよ〉・〈学問研究の専門的な分野以外のところでは、教授研究者と学生とは人間的に対等であるという原則を認めよ〉というような、それ自体きわめて感性的な要求から発して、大学制度改革の項目をつきつけられたとき、かれら大学教授研究者たちは、まったく不可解な人種の言葉を耳にしたときのように、為すすべを知らず右往左往した。
かれらのうちただ一人も、大正リベラル・デモクラシイの原理が戦争期になめた苦渋な体験と、戦後二十数年のあいだ磨きをかけてきたはずの市民民主主義思想に根ざして、急進的な学生たちの前面に立ち、まさに思想原理的に対決する姿勢をしめしたものはいなかった。また学生たちから不信任をつきつけられ、〈おまえ〉呼ばわりされたとき、学生たちと人間的対等の立場に駒をすすめて、自力でこれを粉砕しようとする者もいなかった。また、〈おれはこんな頓馬な学生たちに教えるのは御免だ〉と公言して辞表をたたきつける者もなかったのである。
かれらが社会に身をもって示したのは、怯懦・女々しさ・小狡さ・非常識、ようするに特権的な知識人が共有する最大の悪徳だけであった。かれらは戦争期とまったくおなじように、思想と感性との二重底を使いわけることで、ただ当面する事態を巧みにすりぬけようとする態度を公然としめした。
それは戦後市民民主主義の思想が、戦争体験を忘れ、戦後二十数年をただ徒食のうちに空費しただけであることを見事に露呈した。安保条約を論じ、日韓間題を規定し、ベトナム反戦を唱和しているあいだは、どうせ他人事であるため、ただ現実認識のお粗末さを露呈しただけで、かれらの醜悪な本性はまだ覆われていた。しかしかれらが、じかに足もとから市民民主主義思想を問いつめられたとき、完膚ないまでにその思想的な根底の脆さをさらけだしたのである。
現在、大学紛争の根底にあるのは、戦後の大学の理念として潜在してきた市民民主主義思想のなか身の問題である。かれらは学問研究の自由、思想の自由という名目のうちにある特権を、じっさいに大学が温存してきた前近代的な学閥支配体制の解体のために行使せずに、「プレスティジ」のある地位を保守するために逆用してきたのである。総体的な社会の大衆のなかに、どんな自由も自治も存在しないときに、大学の自由や自治などが現実に存在しうるはずがない。ただ理念としてだけ自由と自治の仮象が大学構内に流通しうるにすぎない。
したがって大学紛争の本質は、大学理念の担い手である教授研究者たちの市民民主主義思想が、理念と現実性のあいだに口をあけている裂けめの問題である。制度としての大学がどうあるべきかなどということは、もともとわたしの知ったことではない。わたしは現在の大学紛争のなかで、試練に立たされている市民民主主義理念が、どのように思想的な原理を貫きつつ、急進的な学生たちに押しまくられて果敢に沈没するか、あるいは急進的な学生たちをおさえきって公然と本来の面目にたちかえるかにもっとも関心をいだいた。
現在、スターリン主義として世界的に展開されたロシア・マルクス主義が、思想的には問題にならない以上、市民民主主義思想の去就は全情況の象徴でありうるといえる。わたしは大学の教授研究者の挙動のうちに、市民民主主義の思想原理が確乎として貫徹される姿をどんなに願ったか知れない。それはわたしにとっていつも思想的な敵対物であり、批判と反批判の対象であったが、どんな思想も敵対する思想の媒介なしにじぶんを成熟させることはできない。
もともと戦後の市民民主主義の思想が、ろくでもない戦争体験に蓋をして出発したもので、ときに応じて体制と反体制の補填物として機能する双頭の蛇であることはわかりきっていた。しかしわが国では思想の根底が問われるときは、体制的か反体制的かが問題なのではない。思想がその原則を現実の場面で貫徹できるだけの肉体をもっているかどうかが問題なのだ。
わずかひとりの大学知識人の挙動によってでもよいから、戦後民主主義が思想として定着した姿をみることができれば、というわたしの願望は空しかった。大学教授研究者たちがみせたのは、戦後民主主義の予想できる最悪の姿だったといっていい。
かれらは急進的な学生たちのごくあたりまえの要求を、まるで異邦人の言葉のように仰天してきき、はじめは脅しによってなだめようとし、それが不可能と知ると、なし崩しに学生たちの要求をうけいれるようなポーズをとり、それが拒否されると臆面もなく機動隊のもつ武装した威圧力を導入して、事態を技術的にだけ収拾しようとしたのである。
おそらく急進的な学生たちが、大学教授研究者たちに本質的につきつけたのは、学問の知的な授受以外の場面では、教授するものと教授されるものとは、いかなる特権的な学閥体制も人間関係をももつべきではないという感性に根ざした要求であったとおもえる。そしてこの感性的な要求は、感性的であるがゆえに教授研究者たちにとってもつとも受けいれがたく、また了解しがたいものであった。なぜならば、かれらが知的優位と知的特権とを、社会的優位と社会的特権に無意識のうちにすりかえて保ってきた心性は、急進的な学生たちのこの感性的な要求によってのみ転倒され得るもので、大学の制度的な改善の具体的項目によっては、けっして侵害されないものだからである。学生処分のやり方と原因とが紛争の過程で固執されたのは、おそらく、それが教授研究者たちと学生たちの感性的なせめぎ合いの焦点として大きな意味をもつものだったからである。
東大紛争の過程で、加藤一郎、大内力、坂本義和、篠原一、寺沢一らは、かれらの思想的な同類とともに、戦後民主主義の思想原理をじぶんの手で最終的に扼殺したといいうる。
かれらは東大入試決定の期限切れという、それ自体が全社会的には三文の価値もない問題を焦慮するあまり、学生同士の流血の衝突を回避するため、という名目をつけて、機動隊の武装力を要請して全共闘の急進的な部分を制圧し、日共系学生たちの寝返りにたすけられて、機動隊の保護下に学生集会を開き、事態を技術的に処理しようと試みた。
入試を実施するか否かという問題は、東京大学の学内問題ではありえても、大学紛争の本質とはなんのかかわりもないことである。またそこには一片の思想原理的な課題も含まれえないことは明瞭である。
はじめに、大学紛争の本質的な課題を解決するポーズで登場したかれらは、束の間のうちに東京大学さえ存続すれば、ほかのことはどうなってもいいという、なりふりかまわぬ破廉恥漢に変貌した。
かれらはじぶんの学生の一部を、じぶんの手で処分することも説得することもできないと知るや、武装した官憲に懇願して、これを武装力によって拘置所におくつたのである。
それ以後、かれらの採用した態度は、すでに社会的な非常識を超えて、精神病理学上の廃疾者の態度であった。かれらは戦後民主主義の思想的原理を、じぶんの手で扼殺することで、じぶんで幻想した大学の理念を扼殺しただけではない。おおよそ人間的な感性を喪失した人格崩壊者としての本質をさらけ出したのである。
|
1月18日、かれらは持ち込まれた危険物を排除するという名目で、ふたたび八千余の機動隊の導入を懇願し、安田講堂に籠つた全共闘主導下の学生たちを武装暴力の攻撃の手にゆだね、みずからはこれを傍らで見物していた。
学生たちの果敢なそして節度のある抵抗が、機動隊の完備された装備のまえで徐々に追いつめられていったとき、かれらは平然として眉をひそめるふりをした〈良識的な〉ジャーナリズムとかけ合いで、学生暴力談義にうつつをぬかし、加藤一郎のごときは〈学生諸君、無駄な抵抗はやめて下さい〉などと臆面もなくマイクで呼びかけさえしたのである。
このとき、かれらを支えたのは、日共の支持であるのか、偽造された世論であるのか、東京大学エゴイズムであるのか、自己保身であるのか知らない。かれらはただ入試の存廃、授業の再開という大学の本質の問題とも全社会的な問題ともかかわりない一連の事態収拾の論理のうえを走ったのである。東京大学の入試が実施されようと、授業が再開されようと、そんなことは社会的には三文の値打もない問題で、もちろんわたしの知ったことではない。また、つまらぬ一国立大学の存廃などは、当事者以外には社会的な考察に価しはしない。
ただ、安田講堂に籠つた急進的な学生たちの抵抗が、機動隊の装備と威圧力のまえに次第に追いつめられ排除されてゆく姿と、無量の思いでそれを傍観しているおのれの姿のなかに、全情況の象徴をみていたのである。もし東大紛争のなかに、貴重な社会的、政治的、思想的課題が含まれているとすれば、この光景と、これをとりまくさまざまな思想的または政治的位相のなかに集約されていた。この場面で、すでに、大学教授研究者たちにより喧伝され、流布されてきた戦後民主主義の理念は、自身で破産して、〈情況〉から退き、機動隊の武装威力に自身を肩代りさせていたのである。
そのあと加藤一郎、大内力らがやったことは、たんに保守権力によってのみではなく、全社会的大衆によって正常な神経を疑われるような、まったくの茶番であった。かれらは全共闘主導下の急進的学生たちを、機動隊の手に引きわたしたあと、その汚れた掌の乾かぬうちに、政府に暴力学生は始末したから入試の復活をしたいと申し入れたのである。
現在の保守政府の政治委員会が、どんなに頓馬の集まりであっても、加藤一郎らの打った破廉恥な猿芝居が見抜けないはずがない。かれらは政府から自治能力の無さと精神的な頽廃を指摘されて、入試復活どころのさわざではないではないかと拒まれたのである。わたしと一緒になりたいなら、ほかの女と手を切って頂戴などと女に言われて、手を切ったまではよかったが、女のほうでは、いっこうにぐうたら男の意を迎えてくれなかった、というのが加藤らと政府の関係である。加藤と追従する教授研究者たちが、入試問題に干渉するのは、大学自治の侵害だなどといまさらのように騒いでも、なんの意味もあるわけがない。かれら自身が、先ずじぶんの手で、大学正常化を武装暴力にゆだねた張本人であり、かれらこそ戦後民主主義思想をみずから扼殺した元凶だからだ。
新聞ジャーナリズムにあらわれた偽装された世論なるものは加藤らの処置を是認しているようにみえたかもしれない。しかし真の社会的な大衆の世論は、加藤ら大学教授研究者たちを、じぶんの大学の学生たちすら統御できない無能力者と見做して、紛争の最大の責任を、古風な教師像にてらして加藤らの処置に集中していたのである。
いうまでもなく、大学教授研究者たちの挙動から実証された戦後民主主義理念の終末は、戦後大学の理念の終焉である。そのあとの空洞が、より保守的なまたはより反動的な大学理念によってみたされたとしても、責任はかれら大学教授研究者たちが負うべきである。わたしたちは愚者の楽園などに三文の社会的な値うちも認めないのだ。
そしてこの現在の全社会の〈情況〉が、大学紛争のなかで鏡にうつされているのだとすれば、その〈情況〉については、かれら大学教授研究者たちの判断をいっさいたたき出しても、〈情況〉の本質を固執しなければならない。かれらが愚者の楽園から首をだしてふたたびジャーナリズムのうえで進歩的幻想をふりまきにかかったとき、かれらは苛酷にその本質を粉砕されなければならない。
加藤一郎らは、大河内一男の退場のあとに登場するにあたって「従来のいきさつにとらわれず、学生諸君の提起した要求項目について討議する」全学的な集会を開催するポーズをしめした。ところが、紛争が長びき入試中止かどうかを決定すべき期限の問題が、公然と保守政府と新聞ジャーナリズムによってとりあげられるようになると、わが国のいかなる大学教授研究者たちの類型にも当てはまらないような、凄まじい豹変ぶりをしめした。
そこでは民主的思想原理を貫ぬき、紛争の解決のために、急進的な学生たちによって提起された大学の制度的改革と、大学知識人の感性的な変革を要求する声の、矢表てに、悪びれずに直面するポーズは突如かなぐり捨てられ、しゃにむに事態を収拾し入試を強行し、大学が存続する社会的条件を名目だけでもとりそろえる目的のために、大学そのものを機動隊の武装威力の管理下に置くという最悪の手段を思いついたのである。
このすさまじい豹変の論理と、鉄面皮な手段は、わが国の知識人のとりうる態度のうちでも、最低のものであったといえる。かつてわたしたちが共通に所有している知的な慣行例のうち、これほど無惨な手口を厚かましく行使した知識人たちは、皆無であったといっていい。じぶんの大学の学生たちから、行動について一片の信任をもえられていない教授研究者たちの執行首脳部が、学生の信任をえられていないことにすこしも責任を感ずることもなく、平然と積極的に機動隊の武装威力によってのみ事態を収拾しようとする厚かましさ、無神経さをまざまざとみて、怪奇な化けものをみたときのように、しばらくぼう然としたといってよい。
|
|
| 【安田攻防戦、革マル派の逃亡が批判される】 |
革マル派は肝心なところで「利敵行為」と「敵前逃亡」という二つの挙動不審
(安田決戦敵前逃亡事件)を為したことにより、これ以後全国の大学で同派は全共闘から排除され、本拠=早稲田大でも革マルをはずして早大全共闘がつくられた。革マル派は、この事件以降それまで批判していた武闘的闘争を少数の決死隊によって行なうようになったが、アリバイ闘争と非難される始末となった。
但し、革マル派の本領はこれから発揮されることになった。以降、いわゆる新左翼内で、革マル派と反革マル派との間にゲバルトが公然と発生する事態となった。いざゲバルトになると革マル派は強かった。街頭での穏健な行動とのアンバランスはかえって他党派の怒りを買うことになった。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| れんだいこは、「革マル派の利敵敵前逃亡」を批判しない。なぜなら、この党派は民青同の右派系運動対策党派、革マル派の左派系運動対策党派とみなしているから。こうみなさいと、流れとしての史実が理解できない。 |
| 【安田決戦支援の神田カルチェラタン解放区闘争貫徹される】 |
1.18日午前11時頃から、東大の急を聞きつけた学生たちが武装デモで続々と神田に集結、東大安田講堂の攻防戦を支援し、それに呼応するかたちで各派が東大闘争支援決起集会を開き、その後解放区闘争を展開した。この時の二日間にわたる闘争を神田解放区闘争(又はいわゆる神田カルチェ・ラタン闘争)と云う。(カルチェ・ラタンの元はフランスのパリのセーヌ左岸の学生街「カルチェ・ラタン」から。これはその年の5月、フランス68年5月革命の発生地パリのカルチェ・ラタンを擬して、東京の文京区、千代田区一帯の大学街をさしたものである) 神田“解放区”闘争は、機動隊6500人を動員して行われた東大安田講堂封鎖実力解除いわゆる「安田城攻め」に対し、東大―日大―中大を結ぶ“鉄の三角地帯”を騒乱状態にすることによって牽制をはかり、安田講堂への進撃を勝ち取ろうというものであった。
まず、お茶の水駅前交番が焼き討ちされ、日本医科歯科大学前には車を倒したバリケードが組まれた。リーダーの笛を合図に「ウワッー」と喚声をあげて赤ヘル約50名がお茶の水交番を急襲した。5分後、東大安田講堂包囲のため待機していた第八機動隊150名が駆けつけ明大旧学館前の小路に陣をかまえる。続いて四機、三機が来たが、中大方向から背後を断たれるのを恐れてか早々に退散した。数十分後、武装学生250名のデモ隊が再度お茶の水交番・駿河台下交番を襲い、メチャメチャにこわし中大方向に引きあげた。
正午過ぎ、東大支援のため中大に集結し集会を開いていた中大、日大、上智大、明大などの「武装」学生約1000名が駿河台一帯に進出、午前中の前哨戦に続いて戦闘を開始、周辺に十数ヶ所のバリケードを構築し、いわゆる“解放区”を創出した。日大全共闘、中大全中闘が防衛任務につき、それ以外の部隊は本郷の東大に向かった。
午後2時頃、国電のお茶の水駅前の道路上にバリケードを築き、東大から転進してきた機動隊2000名に対して激しい投石を行った。お茶の水駅前に陣どり催涙ガスを連発する機動隊に学生3000名が明大旧学館と大学院付近を中心に投石・バリケードで対抗する。止まっていた4台の都バスに運転手を乗せ、青ヘルの学生が誘導し横づけに斜めに止めた。その後、戦線は一進一退を続けた。
午後3時30分ごろ、機動隊約50名が明大旧学館に乱入。学生会、学苑会室にまで侵入したが学生のゲバ棒、投石の抵抗にあって退却。その折3人が逃げそこねて学生に捕まり殴られた。
午後6時、学生に“逮捕”された私服警官を取り戻しに第四機動隊100名が再度本学学館中庭に侵入、ガス弾を連射し1・2階を制圧、「帰れ帰れ」の大合唱の中を私服を取り戻して引きあげた。
午後10時過ぎ、明大学生会館横に構築した中型乗用車2台を横転させたバリケードに立てこもって抵抗を続けていた学生集団が引きあげ、駅前などに残る数千の群集が機動隊と対峙し深夜まで投石を続けた。機動隊に追われた群集などがお茶の水駅構内へ逃げ込んだため国電が一時ストップし、ダイヤが混乱した。
1.19日、二日目、前日からの熱気のまま、集会、デモ、機動隊との衝突が繰り返され、神田地区一帯にバリケードが作られ、神田解放区は終日、学生、労働者、市民であふれた。“進撃”部隊はまもなく本郷2丁目で機動隊と衝突、追い散らされたが、順天堂医院前の車・イス・机・敷石などで築かれたバリケード(大きいものは高さが2メートル以上もあった)に拠って機動隊に激しく投石、これを退けた。ヘルメット姿の学生を市民群集が取り囲む形となり、お茶の水駅付近では最大時1万人が結集し、機動隊も手が出せなかった。
午後7時ごろ、本郷方面から進出した機動隊に青ヘル中心の学生がバリケードから火炎ビンで抵抗した。パッと炎が闇の中に閃めくたびに群集から歓声があがる。交通は完全に麻痺状態となり混乱は午後7時過ぎまで続き、夜9時半過ぎ、市街戦が収束した。
午後10時、機動隊が攻勢に転じた。学生たちは少し前からひきあげを開始しており、これと対峙したのは市民群集約1000名で「帰れ帰れ」とシュプレヒコールを繰返し、発射された催涙弾を投げ返した。手をやいた機動隊はガス弾を連発、「ウオー」と声をあげて突撃、市民群集をけ散らしたが散発的な抵抗は深夜まで続いた。東大紛争に多くを充てていた機動隊は、600名を出動させるが4人に1人が負傷するという惨事になった。神田での検挙者768名(85名逮捕)。
1.20日、新左翼系各派はセクトごとに総括集会を開いた後、それぞれの拠点大学に引き上げ、「神田カルチェラタン闘争」は終息した。(18、19の記述が入れ替わりして正確でないかもしれない) |
「No324-2 東大安田講堂攻防戦外伝」の「1.19と私 野坂昭如」が次のように記している。
| たまに石が投げられ、とても届かなくて、両軍の中間におちる。「直ちに退去しなさい、石を投げてはいけない、こら」切り口上につい感情がまじって、指揮車の、金網の中でマイクがさけぶ、「各人投石者を確認の上、逮捕せよ」しごく無表情な声がひびいたかと思うと、突如、隊員の列は、我がちにときの声をあげ、催涙弾を発射しつつ、駈け出して、口々に「この野郎」「ぶち殺すぞ」「ふざけやがって」示威なのか、恐ろしいつぶやきをもらし、もとより群衆、あっという間に、横丁に逃げこみ、退き、すると、「中隊現在位置にもどれ」また命令があって、いとあっさり引きかえす。私服が背の高い男を両脇から固めて連行し、男は重病人のように頬あおざめていた。報道の腕章にものをいわせて、機動隊の列戦を突破し、群衆側にうつると、そのすぐ後にバリケードがあって、全学連各派の旗が、ならんでいる。バリケードの内側では、闘士たち、敷石をはいで打ちつけ、投石の準備に大わらわ。両側の塀に見物人が鈴なり。あちらこちらに、派ごとの小集会があって、気勢をあげ、お茶の水駅を中心にして、あらゆる道がバリケードで封鎖されているのだ。とんまな車が近づくと、まず二人ばかり、すごい剣幕で怒鳴り立て、それを一人がなだめて、運転者に丁寧に説明する。これはどうも、やくざの手口に似ていて、計算の上のことだろう。さきほどの喫茶店も表を閉め、交番に、解放区の札がかかる。さまざまなデモの隊列と、色とりどりの旗が錯綜して、それとまるで、水と油の感じ、着かざった娘や、子供連れの父親、恋人が、楽しそうにながめている。なにやら、お祭りめいていて、たとえばここに機動隊が押し寄せたら、大混乱となるだろうに、毛ほども心配していない様子。ぼくは、歩きながら、常に逃げ道を考えているのだが、よほど、臆病にできているとみえる。(中略)(再び東大へ向かい、落城後、お茶の水へ向かう)学生の数を、ラジオでは千五百人とといっていたが、とてもそれではきかぬ。加えて何万かの弥次馬、まともにぶつかれば、大混乱となるだろうし、どうせ危ないとみれば、いち早く逃げ出すにしろ、この目で見ておきたい。さっきまでやりあっていたガソリンスタンド近辺、すっかり平穏になって、激しく車が行きかい、さらに医科歯科大横のバリケードもなくなっている。弥次馬だけが右往左往していて、機動隊もどこにひそむのか姿がみえぬ。戦線がのびすぎたと、バリケードをお茶の水駅近くに移し、それだけに内側は、ごったがえす騒ぎで、おどろいたことに、まだ子供連れの男、老人がうろうろしている。「私服の野郎けとばしてやった」「いやあ、さっきは、俺のこの肩のところにまで、機動隊の手がとどいてよ、びっくりしたのなんの、聖橋まで走って、足ががくがくよ」先のとがった靴、野暮ったい身なりの若者が、楽しそうにいう。ぼくは駿河台下のバリケードまで歩いて、いざとなれば山の上ホテルへ逃げ込むA氏との約束、ホテルのバアへ立ち寄り、ウイスキー二はい飲んで、さすがに人気のないロビー、今、見てきた東大の、TVニュースをながめ、さてと、もう一度表に出たら、なんと、学生はすべて消えていて、一般群衆ばかり、明治大学近くに群がり、バリケードはあっさり突破されたらしくて、お茶の水駅に、ジュラルミンの楯がならんでいる。声も出さず、石も投げず、ただ、機動隊とにらめあうだけで、二度、三度、隊員が突っこんでくるが、いったんは逃げても、すぐに元通り、道いっぱいにたちはだかり、異様な静けさのままいる。これは機動隊にとってもかなり気味のわるいものではないか。午後11時をまわった頃、群衆は、ふいにやめたという風に、遊びにあきたといった態で、ぞろりぞろり帰りはじめ、その後は、投光器に照らし出された路上、無数の石ころが、それぞれ影を抱いて美しい模様をえがき出していた。中央大学のバリケードは固く閉ざされ、日大は窓から食糧を運んでいた。山の上ホテルで飲み直すつもり、坂を中途まで登ったら、二十人ばかりの隊員が駈足で追いすがり、思わずたちすくんだら、かまわず追い抜いて、ホテル横のバリケード撤去にかかり、ものの三分とかからず、道をあけ、たちまちまた、黒いつむじ風のように坂を駆けおりる。機動隊は、たしかに、市民対し、無敵の強さを持つ、あれは強すぎるのではないか。「デモといっても近頃は、すぐサンドイッチにされて、護送されてるみたいなものですからねぇ」A氏がつぶやいた。サンドイッチのハムほどの、自由、戦前のパンばかりよりはましだけれども。 |
|
秋山祐徳太子の「通俗的芸術論」の中にが1・18-19に関する記述がある。次のように記している。
| 60年代末から70年代にかけて、東大安田講堂占拠を頂点に学園闘争は花盛りであった。花盛りと言うと不真面目にきこえるだろうが、絶対に学生自治会の存続など考えられなかった日大でさえ、学部占拠がつづいていた。この中でノンセクト・ラジカルという派が大活躍をし、神田周辺は、カルチェ・ラタンと称して、その花が咲き乱れた。ぼく達の学生運動のころは、ヘルメット、ゲバ棒というものは存在せず、今から見ると古いスタイルで闘っていたものである。ヘルメットもカラフルでセクトが1目で分かるように色分けしてあるし、セクト名も大きくなかなかデザイン的にきちんと書いてある。「中核」というのも目立つけど「ML」というのもよく目立つ。それが一勢に神田カルチェ・ラタンにデモるとなると、人間というよりロボットが動き出すみたいだ。(中略)それはともかく、神田一帯には日大、明大、中大などがあり、とくに明大前からお茶の水にかけての通りなどは、連日学生と機動隊とのぶつかり合いがつづいていた。その日はそれまでで一番大きな闘いになるだろうといわれていた。明大前のカルチェ・ラタンにはバリケードの山が築かれて、機動隊に応戦する構えができていた。機動隊の方も装甲車をくりだした。昼過ぎになると機動隊の大部分がジリジリとバリケード側に近づいてきた。学生側もゲバ棒で武装しながら近づいていった。学生と機動隊との距離が30メートルくらいになったときに双方の動きがピタリと止まった。ちょうど真ん中のバリケードの山が双方の間に割って入った形であった。見ると緑色の人形がその天辺に立っている。コルゲンコーワのカエルの人形であった。手を両手に広げたような格好で立っている。そのとき、ぼくは<これだ!>と直感してしまった。政治的、そして物理的関係の真っただ中に、エア・ポケットが現出していた。パロディとかナンセンスすら超越しているカエルはまったくの異次元にあるようにキ然と立っていた。学生と機動隊との距離はなかなか詰まらない。ほんとうは双方、あのカエルのおかしさに見とれてしまって、攻撃を仕かけられないのではあるまいかと思った。ぼくは双方ぶつかり合わないうちにその場を離れた。もし、学生も機動隊もあのカエルのために一勢に笑いころげて、今日はお互いに衝突をさけたとしたら、すばらしいことだと思いながら・・・。しかしあの日、双方に負傷者が大勢出たという。あのカエルも人並みに怪我をしてしまったのか。それにしても一匹のカエルのオブジェが物理的次元にカエル空間を現出してのけたことは見事であった。あれ以来ぼくの心の中には、ぼくのハプニングも、取締りにきたお巡りさんも笑ってしまうくらいでなければ真のナンセンスたりえないのだ、という思いがある。 |
|
東工大、横浜大、京大教養学部、阪大教養学部など無期限スト。また専門学校、高校で学園闘争始まる。
1.19日、「早朝より民青の攻撃激化、工事現場、七本、一本の上から投石。他方で民青は、殺虫剤バルサンをたきつつ1階2階を上ってきた。しかし断固撃退。夜を徹して抗戦。助手共闘他30数名、食糧搬入のために、八本に接近したが、内3名、八本1階に連れ込まれてリンチされる」(「全共闘グラフィティー」)。
1.20日、東大教養第八本館を民青同系学生が兵糧攻め、全共闘350名の救援行動も機動隊によって阻止、5名逮捕される。
1.20日、「駒場共闘250名が駒場正門前に結集、正門前で機動隊の規制にあい6名逮捕される。ベ平連等数十名、差し入れに来るも入れず」(「全共闘グラフィティー」)。
1.20日、東京外大学生集会〔久保講堂〕で右翼・民青同系のスト解除策動に全共闘抗議行動、機動隊導入で会場より学生排除さる。
|
【東大が開学以来初の入試中止決定】
|
| 1.20日、佐藤首相・ 坂田文相、東大構内を視察、政府・自民党、東大入試の中止を決定。 |
1.20日、東大が文部省と会談。東京大学と東京教育大学(体育学部を除く)の入試中止を最終決定した。1.22日、加藤代行は次のような声明をだした。
| 「遺憾ながら、1月20日、政府の入試試験中止の決定によって、入学試験の実施は事実上不可能になった。これは諸君にとっても、大きな衝撃であったとおもう」。 |
|
これ以降広島大、早稲田大、京都大などでも全国学園砦死守闘争が展開された。この経過で「60年安保闘争」を上回る「70年安保闘争」が課題となり、ノンセクト・ラジカルと反代々木系各派(革マル派を除く)は運動の統一機運を盛り上げようと連携していくことになった。「60年安保闘争」を上回る闘争を目指して多岐多流の潮流がうねりとなって9.5日の全国全共闘連合になだれ込んでいった。これが69年における「70年安保闘争」の「正」の面であった。
1.20日、京大にも機動隊導入。
1.20日、ニクソンが米大統領に就任。
1.21日、「『1.21全国ゼネスト』のため午前11時半、外の部隊と合流して駒場集会を追及、民青の妨害、テロ、リンチ、投石などを粉砕し、入試中止を勝ち取った」(「全共闘グラフィティー」)。
1.21日、この日、お茶の水付近が反日共系学生のデモで騒乱状態が予想されるとの噂がとび、機動隊は午前4時に明大通りに待機した。午後3時、中大で「東大奪還・
全国学園ゼネスト支援全都総決起集会勝利集会」が東大の全共闘をはじめ、日大全共闘、中大全中闘のヘルメット学生2000名が講堂に結集した。明大スト隊も和泉での決起集会後中大に合流した。午後6時集会終了。一時デモ隊は無届で明大前通りに進出したが、機動隊の強力な規制に阻まれて再び中大に退却を余儀なくされた。
1.21日、東大奪還・全国学園闘争勝利全関西決起集会〔京大正門前〕千五百名参加、逆バリの民青同系学生と衝突。
1.21日、東大全共闘が、駒場教養学部第8号館から撤去。これにより全学部で封鎖解除される。
1.22日、佐藤首相が東大確認書認めずと表明。自民党総務会も破棄を東大に申入れ。
1.23日、フランスのパリ大学ソルボンヌ校の学生が大学総長室占拠。逮捕者約200名。西ドイツのベルリンでも学生が警官隊と衝突した。
1.24日、スペインで、学生運動制圧の為の3ヶ月間非常事態宣言出される。
1.25日、ベトナム戦争を廻ってアメリカと北ベトナムに南ベトナム、解放戦線を加えた拡大パリ和平会談始まる。
1.26日、沖繩県民共闘亀甲議長が二・四ゼネスト回避のため上京。1.28日、屋良主席も上京、関係各方面と協議。
1.26日、1.18-19神田解放区闘争で中大・ 明大学館・ 日大理工学部が強制搜査される。中大二号館では抗議した学生29名が逮捕される。
1.28日、中核系全学連主催・全都学生総決起集会〔日大理工学部〕に四百名参加、二月全国学園バリスト・ 沖繩闘争方針等を確認。
1.28日、日米京都会談粉砕全関西総決起集会〔京大〕に各派学生千名参加、全関西労働者集会〔円山公園〕に合流、のち都ホテルに抗議デモ、32名逮捕。
1. 29日、全国各地の大学で闘争激化。東工大無期限スト突入。横国大全学部無期限スト。
1.30日、京大教養学部スト突入。
1.31日、阪大教養無期限スト。
1.31日、東大当局が全共闘学生を器物損壊で告訴。
これより後は、「圧巻の全国全共闘結成と内部溶解の兆し」に記す。
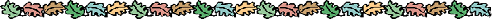



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)