| 1966年 |
全学連運動史第7期その2 |
| 全学連の転回点到来 |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.4.7日
これより前は、「第7期その1、べ平連、反戦青年委員会結成される」に記す。
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| この年、大学紛争が本格的に始まる。私立の早大、明大、中大、官立の横国大、東大で火の手が上がる。ベトナム反戦闘争が活性化し、三里塚闘争が始まる。新三派系全学連が立ち上がる。キャンパスの内外が政治闘争化し始めた。この過程を検証する。 |
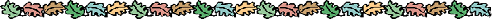
| お知らせ |
| 当時の政治状況については「戦後政治史検証」の「1966年通期」に記す。本稿では、当時の学生運動関連の動きを記す。特別に考察したい事件については別途考察する。 |
| (自治会執行部の争奪の動きとその関連) |
この頃の各派全学連と傘下自治会は次のようになっていた。早大闘争が始まり、東大闘争、横国大闘争その他諸闘争を点火していくことになった。
| 【この頃の各派全学連と傘下自治会】 |
この頃の各派全学連と傘下自治会は次のようになっていた。主要党派をゴシック文字で記す。
| 民青系 |
以下に記すその他の自治会。 |
| 革マル派全学連 |
早大(一文.二文.一商.二法).金澤大(教養).鹿児島大.宮崎大.奈良女子大.法政(二部).岐阜大.秋田大(学芸)等の自治会を傘下にしていた。 |
| 中核派 |
立命大(経).京大(医).三重大.法政大(文.経).山梨大.横浜国大(教養.経.教.工).広大(教養.工)等の自治会を傘下にしていた。 |
| 社学同 |
東京医歯大.京大(文.教育.農).京都府立医大.桃山学院大.専大.小樽商大.東大(医).中大.明大.同志社大(文.経.商工).滋賀大(経).和歌山大(経).大分大(経).徳島大.香川大(除教育).富山大(教養).法政大(法).お茶の水大等の自治会を傘下にしていた。 |
| 社青同解放派 |
早大(一政.二政).東女大.関大(法).関学大(法)等の自治会を傘下にしていた。 |
| 社青同協会派系 |
長崎大(経.医).佐賀大。 |
| 構造改革派.フロント系 |
立命館大(法.経営.理工.文).法大(社).新潟大。 |
| 構造改革派.共青系 |
神戸大全学部。 |
| 構造改革派.民学同系 |
阪大(除医).大阪市大全学部.岡山大(中執).関学(中執)。 |
|
|
1.11-12日、全学連(革マル系)第四十二回中央委〔東京〕、日韓闘争の敗北を総括。
1.19日、慶大日吉・国学院大・都立大・東大教養学部生ら反日共系学生百五十名、私鉄運賃値上げ反対で渋谷駅構内集会・デモで抗議。
| 【横浜国大闘争】 |
|
1月-3月にかけて横浜国大で、学部の学芸学部の学部名変更に反対する紛争がおこり、学生がキャンパスを封鎖、教職員を排除して、学生の自主管理を約1か月余にわたって強行した。この自主管理下のキャンパスでは、学生自治会が編成した自主カリキュラムによる学習が進められるという画期的なものとなった。
|
| 【早大で学費値上げ反対闘争始まる】 |
| 「早稲田大学百年史」の「第十編 新制早稲田大学の本舞台/第十八章 「学費・学館紛争」(下)/一 厳戒態勢下の入学試験」その他を参照する。 |
|
1.18-20日、早大で、「学生会館の管理運営権獲得」に加えて学費値上げ反対闘争が始まった。これは、前年の12月に、早大理事会が教授会にも諮らず、学生が冬休みに入ってから大幅な学費値上げを発表したことに対する憤激から始まった。約5ヶ月に亘って続くことにり、「早稲田を揺るがした150日(足掛け7ヶ月)」として刻印されている。
広谷俊二氏の「現代日本の学生運動」は次のように記している。
| 「『庶民の大学』という伝統に強い愛着を感じている学生たちは、値上げによって授業料、入学金などが慶応大学以上に高くなることに憤激し、また、このような大幅な値上げが、学生はもちろん、教授会にすらはかられることなく強行されたことに憤激して、全学をあげて、ストライキに立ち上がった。三万を越える学生が団結して闘い、多くの学生は、これまでにかってない積極性、創意性を発揮して闘争に参加した」。 |
民青同系全学連加盟自治会であった第一法学部と教育学部自治会が無期限ストライキ突入。この時、日共の指導の下で高野孟らが民青同系を指揮している。
1.20日、続いて三派系の全学共闘会議 (大口昭彦議長)も一政.一商を無期限ストに導いた。革マル派系の一文、二文も同調した。
1.21日、理工学部もストに入った。こうして1.21日までに全学部がストライキに入った。中核派、社学同、ML派も存在したが、自治会執行部を掌握するまでには至っていない。早大闘争は、民青同系と全学共闘会議系が競うように運動を盛り上げていったことに特徴が見られる。しかし、闘争の後半になると、革マル派と社青同解放派が対立し始めている。
学年末試験は1.24日からであったが試験はボイコットされた。全学部で入り口にバリケードが築かれ、ピケ隊が入館する学生一人ひとりに学生証を提示させて検問する体制に入った。布団を持ち込んでの泊り込みが常態化し、連日約5千名の抗議集会が開かれるようになった。
2.4日、「総長説明会」が開かれたが、1万2千名の学生は強硬挑発的な大浜発言に一層怒りを高めた。
2.5日、大浜総長の説明会が行われた翌日、全学共闘会議が分裂した。「反日共系」が十日から本部を封鎖して、近づいてきた入学試験願書の受付などすべての事務を阻止し、大学に多大の打撃を与えようと主張したのに対して、「日共系」(民青系)が本部封鎖に強く反対して、私学に対する公費助成を獲得するための国会請願路線(「私学への国庫補助獲得運動」)を主張する等の路線の違いによる。「反日共系」が、「日共系」運動は大学当局の路線に暗に追従するものであり、これまでの団結を破壊するものであると主張すれば、「日共系」は、入試事務を阻止することは社会の批判を浴び結局敗北に至ると主張して平行線をたどることになった。
2.8日、共闘会議派代表と大学側とで第一回の会談が行われた。
2.10日、第2回目の会談が持たれた。しかし30分で決裂し、全学共闘会議派の学生約4百名が本部に突入して各入口にバリケードを築き、いわゆる「本部封鎖」を敢行し籠城した。他方、民青系の学生は本部封鎖に反対して「大学の自治」と題する講演と映画の会を大隈講堂で開催し、独自の路線を採り始めた。
2.11日朝、昨夜来の本部封鎖により、本部の職員約百名が大隈会館書院に集合して理事と各部課長の指示を受けた。同日10時過ぎ、人事、庶務両部長が封鎖解除の説得を学生達に行ったが拒否されたため、大学は、本部が平常にもどるまで学生のアルバイト、下宿の斡旋、奨学金の交付、留学生の渡航証明書事務など本部事務の一切を停止するのやむなきに至ったことを学内に掲示した。新聞、テレビなどの報道で本部封鎖を知って駆けつけた一般学生の間では「あまりにもヒステリックなやり方だ」として非難する者が少くなかった。
この日午後2時、これまで母校の成行きに心を痛め個別に動いてきた国会稲門会が赤坂プリンスホテルで緊急会議を開いて、会としてまとまって調停に乗り出すことにした。参集したのは超党派の五十余人で、これだけ多数の稲門議員が調停目的のために一堂に会したのは初めてのことであった。
同日、稲門体育会も共闘会議に本部より退去するよう勧告し、翌日には本部占拠を排除しようとする運動部学生約250名と共闘会議の学生が大乱闘する事態となった。そして一時バリケードが撤去されたが、共闘会議はすぐさま再構築した。
2.14日、国会稲門会は大学側と共闘会議派の代表を招いて具体的な調停を行った。稲門会は、双方から白紙委任を取りつけようとしたが双方とも回答を保留した。そして、共闘会議派内では調停をめぐって社青同系と革マル系が対立して、セクト間の争いは運動を一層の混迷に導いていった。この日、国会稲門会が大学側と学生側双方に「白紙委任」の取りつけを要請したが、委任の正式回答は保留された。国会稲門会議員の仲介の労も為す術がなかった。
2.15日午前11時、大浜総長が、大隈講堂に全教職員の出席を求めて所信を明らかにした。この中で、本部占拠の学生に言及して次のように述べた。
| 概要「このさい学生運動の実体を身をもって感じとってもらいたい。かれらの運動は大学を人民管理にまで持って行こうとするもので大学の総力をあげて対処しなければならない。しかしながら、その排除のための力の行使は最後の手段であって、一般学生に対する影響、世論の批判も考えねばならず、今日まで自重してきた。(国会稲門会からの白紙委任での調停案については、)校友国会議員の母校愛には敬意を表するが、ここで調停案を受け入れることは私が総長のイスを去ったあとまで禍根を残すことになるだろう。必要なときはこちらからお願いするからしばらく静観してほしいと、今朝まとめ役の方に伝えた。24日からの学部入学試験では妨害も充分考えられるので協力してほしい。今回の紛争を通じて学内の結束が強められ、禍を転じて福とすることを望みたい」(早稲田学報/昭和41年3月発行、第759号44-46頁)。 |
このあと、事態を憂慮した比較的若手の教職員から、総長・理事者の一層の努力を懇望するとの発言があり、最後に割れんばかりの拍手を浴びて総長以下理事達は12時に退場して散会した。この日午後2時より評議員会が東京会館で開かれ、学費値上げを既定方針通り進めることを確認し、国会稲門会の調停案についての理事者の意見を支持することを決めた。
2.16日、学願書の出頭受付が朝から大隈講堂で開始され、テレビ放送車のカメラの砲列の中を受験志願者や父兄などが続々と訪れて、幾重にも蛇行する行列ができあがり、夕方5時頃までに約1万8千人の受付が終った。この行列の周りで共闘会議の学生が「学費値上げ反対を勝ちとろう」とアジ演説していた。志願者の出足は順調だった。
2.17日、大浜総長が、国会稲門会早大対策小委員会の野田武夫委員長(大一二法、自民党議員)に、入学試験が円滑に実施できるよう全学生と共闘会議に呼びかけたいので大学側の努力を更に静観してほしい旨を伝え、事実、18、19の両日、精力的に共闘会議と接触して事態打開に努力した。
2.18日、この日の入学願書の出頭受付だけでも8千人を超え、累計8万2187人を数えた。この日、大学側は、非公式に神沢学生部長などを通じて共闘会議と折衝し、授業料の値上げは撤回できないが施設費の納付額は再考し、返済しなくてもよい奨学金制度を新設するという案を提示した。大学としての初めての譲歩であった。しかし直ちに拒否された。
同日、中立系の学生達が、入試を控えているので何としても警察力の導入を避けようとして「有志連帯準備会」を結成し、これに約五百人が参加して討論会を開き、翌日には二千人の署名を集めて大学と学生の話合いを申し入れるなど学生の間にも新たな動きが現れてきた。
2.19日、この頃結成された学苑生の母親達を主体とする父兄の会「白いハンカチの会」のメンバーが神沢学生部長と大口全学共闘会議議長を訪れて、警察官の導入を避けて何としてでも話合いで解決し、入学試験に影響が及ばないようにと双方に強く訴えた。この日午後、警視庁では、警備、公安部長はじめ各機動隊長ら幹部が会議を開いて、学苑当局から占拠学生の排除を要請された場合に備えて実力行使の際の体制や注意事項などについて協議した。
2.20日、入試開始四日前のこの日の慌ただしい模様を早稲田学報第759号(昭和41.3月発行)の「激動の八十日」は次のように記録している。
| 入試準備が限界に達し、関係者はいらだった面持ち、学内のあちこちに地方から駆けつけた校友の心配顔が見られる。午後1時半、大学と共闘会議の間で話合いがつき、神沢学生部長、佐久間〔和三郎〕経理部長、学生側代表などが立ち会い、経理課金庫から2.10日到着分の入学願書約千五百通がはいった郵袋が運び出された。大学ではすぐにこれらを処理し、志願者に電報、速達で願書受取りを通知した。午後6時、大隈会館での記者会見で、時子山理事が「国会稲門会の諸先輩に今日まで静観をお願いしてきたが、十万人の受験生に対する責務を考え、理事会は国会稲門会の調停をうける用意がある」と発表し、最後まで話合いによる解決に努力する大学側の態度を表明した。一方共闘会議は、午後8時過ぎ、大隈会館で待ちうけていた国会稲門会代表八氏(海部俊樹、川崎秀二、佐藤観次郎、多賀谷真稔、戸叶武、中村高一、野田武夫、武藤山治の各氏)に調停案拒否の回答をした。国会稲門会ではなお共闘会議学生の説得にあたるため学生集会場の政経学部103教室へ出かけたが、入室を拒まれた。この後一行は隣室で幹部たちと面会したが、学生側の強い拒否態度に説得をあきらめた。10時過ぎ、一行は大隈会館で記者会見し、「大学側、共闘会議側のいい分を聞いて公平な案をつくったつもりだが、共闘会議側に聞き入れられなかった。これによって最悪の事態を迎えるのではないかということが大変残念だ。最後まで紛争解決に努力したい」と語った。大学側で十時からこの日三度目の記者会見をし、時子山理事が議員団の調停が不調に終わった連絡をうけたと発表、集まった報道関係者の間にもいよいよ最悪の事態と緊張した動きが見られ、居残っていた教職員の表情は連日の疲れと来るところまで来たという気分がないまぜになり言葉少なかった。(56-57頁) |
この時、国会稲門会の示した調停案は、値上げ予定の学費から、授業料1万円値下げ、施設費1万円値下げ、奨学金を五百人分増加、学生の退学・除籍などの処分は行わない、学生会館の運営委員は教員・学生同数とする、3年間に5億円の寄附を集める、国会議員団は国の助成金増額に努力する(朝日新聞2.21日号朝刊)という内容であった。不成功に終った調停を新聞各紙はほぼ紙面の半分以上を費やして、「双方の胸のうちは/折れた大学当局、強気の学生側」、「国会稲門会はこう動いた/裏切られた自信」、「なぜ断わった学生側/結局、過激派がひきずる」、「『カベ』は堅かった/頭をかかえる先輩議員」などの見出しで、数葉の写真を添えて報道した。譲歩した大学側にとって、この調停不成立は時間的に万事休すであった。大学側は、入試会場確保のためには、警察の力を借りるより外に選択の途がなく、この夜警視庁に警官隊の出動を正式に要請した。小雨のそぼ降る構内は警官隊の導入を予期してか騒然たる雰囲気に包まれ、6百人ほどの学生が泊り込んだ。
2.21日早朝5時頃、学苑を取り囲むように装甲車で集結していた警視庁の警官隊約2500名が、テレビ各局のライトに照らし出されて正門前に隊列を組み終った。学生達の「警官帰れ」の怒号の中、5時30分に正門前では職員によって総長名による「入学試験の実施に差しつかえるので、ただちにこの場所から退去しなさい」と記されたプラカードが占拠派学生に示され、南門では占拠派の学生に学生部奨学課長立合の下で執行令状が渡されて、警官隊が一気に構内に突入し、占拠派学生約5百人のジグザグ・デモによる抵抗を巧みに分断して、正門に誘導していった。そして、その他の学生も含めて合計約1200名が構内から排除され、本部をはじめとする各建物のバリケードが撤去され、各校舎では直ちに現場検証が行われた。本部は一階の経理部、校友課、二階の人事部だけが被害はなかったが、総長室、理事室、秘書課、庶務部、教務部、学生部、募金事務局などは台風に見舞われたような惨憺たるありさまで、他の建物も布団が散らばったり、週刊誌・漫画本が散乱していたりして、商学部地下のホールには異臭が漂っていた。検証が終ると校舎の整備作業が開始され、入試会場の準備が始まった。
他方、鶴巻町方向に押しやられていたデモ隊は、文学部構内の記念会堂前で約3千人を集めて抗議集会を行い、非占拠派の学生達は門外で警戒を続けている警官隊に罵声を投げかけたり、警察力導入の原因を作ったのは過激な共闘会議の占拠派であるとして非難の演説を繰り返した。大学側は、3.6日の入試完了まで学生の構内立入りの禁止措置を告示して各出入口を閉鎖して、いわゆるロックアウト態勢を布いた。大隈小講堂でこの措置に関する総長の記者会見が行われ、漸く入試準備の作業の見通しのついた午後3時30分頃、昨夜来から出動していた機動隊が撤収していった。こうして機動隊が導入されバリケードが解かれた。
ところが、ガードマンが鉄条網を張り巡らし始めたことに反発し、本部前で「警察官導入抗議」集会が開かれ再占拠となった。あっという間に約三千人の学生で膨らんだ。そして、ジグザグ・デモの渦となり、占拠・非占拠両派双方の戦術をめぐる非難のヤジ演説の応酬合戦が展開され、やがて、占拠派は再占拠の行動に出て、受験番号が張られたばかりの机や椅子を本部・各校舎の入口に持ち出し、またもやバリケードを築いた。警官隊の撤収僅か二時間後のことである。職員や警備員は建物から追い出され、これを見つめる一般学生の表情はきわめて複雑であった。大学当局は再び機動隊の出動を要請するしかなかった。
2.22日午前7時頃、正門前に装甲車が続々と集結し、本部構内には警官輸送用のトラック21台をはじめパトカーなどの警察の車がひしめいた。二度目の機動隊導入となり、9時頃までに本部構内と文学部構内の占拠派学生を警棒を用いて排除し、他大学の学生を含めて203名の逮捕者が出た。一度にこれだけの検挙者が出たのは学生運動史上初めてのことであった。新聞は「早大紛争/怒号とバ声のアラシ/『戒厳令』なみ、通行証出す」、「根こそぎ検挙で学生総くずれ」との見出しと、「じゅずつなぎの大量検挙者」との説明つきの騒然とした光景の写真を掲載して大々的に報道した(東京新聞2.22日号夕刊)。また、こうした模様はテレビのトップ・ニュースで全国の茶の間に放映された。この日ロック・アウト。
この21、22日の機動隊出動について、学苑を所轄の対象とする戸塚警察署の一署員は次のように記している。
| 戸塚警察には当庁としても重要である警備対象が二つある。一つはいうまでもない早大であり、他は、下落合にある東京学生会館である。……警備部隊出動の場合その連絡方法は非番の一般部隊員に対しては、居住地より本署に電話連絡をし確認の上出署することとなっていた。二十一日午前六時出署の指示を受け、当日私は西武新宿線花小金井駅を一番列車に乗った。電車は出署する警察官と、早大ストに参加するとみられる学生達でほぼ一ぱいである。「呉越同舟だな」と思った。高田馬場駅では殆んど全部の客が下車した。皆んな自然に駆け足になって、私もそれにならって本署に到着した。署の庭には多数の輸送車が並んでいて、しかも鉄かぶとを背負った他署員が警戒配置について緊迫した雰囲気であった。私は影山小隊二橋分隊に編成され、小隊は雨上りの明けたばかりの戸塚の町を警備本部のある早稲田の森へと行進を起した。……二十二日は当番員は普通に出署し看取係は平常通り交代した。しかし早大では前日駆逐された学生が警備部隊が引揚げた後再占拠したことから、この不法行為に対し二百数名という大検挙者のでることを予想し、井上刑事課長命令で長南部長を中心に被疑者留置について検討してあった。施設の点検、通謀、或いはせん動などの事故防止策等、特に分散留置に備え嘱託留置の手続関係書類一切を準備してあったが、検挙者は当署及び牛込署に連行の上全員分散留置された。
(菅沢正夫「早大事件警備を顧みて」戸塚警察署/第六次早稲田大学事件回顧文集――230名×180日の警備――」81-83頁)
|
2.22日午後2時過ぎ、佐藤観次郎(昭三政、社会党)が、国会衆議院の本会議で、校友代議士学苑の紛争に関連して広く私学振興についての緊急質問を行っていた。佐藤議員は佐藤栄作首相、中村梅吉文相に、私学に対する財政援助および寄附金の免税措置等について政府の姿勢を質した。次いで午後4時過ぎには、中村文相が事務次官、大学学術局長同席の上、大浜総長を参議院別館の政府委員室に招き、「早大の入学試験が平穏に行なわれるよう、大学側も学生側も努力してほしい」と要請し、学苑の紛争について事情を聞いて早期解決を要望するとともに、入学試験の見通しなど具体策を質した。総長は「目下解決のため努力している最中だが、入学試験だけはなんとか無事に行なえるようにしたい」と述べ、「この紛争を契機に、政府の私学振興策をさらに促進してほしい」と要望した(朝日新聞2.23日号朝刊)。
2.25日、佐藤首相が閣議で私学に対する政策の検討を指示し、26日には中村文相が文部省内の事務担当者に私学振興緊急措置を検討するよう指示した。
2.24日~3.6日、完全なロックアウト体制で、学外は機動隊の厳重な警戒と、学内は教職員や警手の警備によって入学試験が開始された。この朝、多数の新聞社やテレビ局の車とカメラの砲列に囲まれて受験生が次々と各受験会場に黙々と入場して、第1日目の第一政治経済学部の入試に臨んだ。この日から3.6日までの試験期間、受験生と入試関係業務の者、教職員以外は構内立入禁止となり、受験生も試験時間中は学外に出られないことになった。入試は、十日余りに亘り各学部とも妨害を受けることなく3.6日の社会科学部を最後に終了することができた。警備に当った戸塚警察署員は、「大隈講堂の地下の小講堂に待機しながら各種の警備に参加し、あの十万人をこえる受験生の入学試験を厳重なる警備警戒に従事したが、大した事故もなく新入生の試験が無事終り、地方から上京して来た親達のあかるい顔を見たときは、本当に自分の責任をはたしたような気持でほっとした」(久我寅夫「平和な学園を祈る」/第六次早稲田大学事件回顧文集159-160頁)と記している。この間大学側は、40数人の処分を強行した。
3.1日、中村文相は臨時私学振興方策調査会に対して42年度予算で措置すべき当面の応急策について答申を要望した。3.8日、大蔵省が私学に対する寄附金の取扱いについて優遇措置を講ずる構想を発表するなどの姿勢を示した。私大側も、日本私立大学連盟、日本私立大学協会、私立大学懇談会の三団体の代表者が、3.17日、佐藤首相に対して私立大学経常費の一部国庫負担を実施してほしいと要望するなど、学苑の激しい紛争は文教関係当局や私学界を揺り動かすものとなった。
3.6日夕方、大浜総長は大隈講堂に教職員の参集を求めて、入試が無事に終ったことについて謝意を表し、同日付で大学は入試無事終了の「声明書」を学苑内外に発表した。これは、多方面に対する謝辞を目的にして出されたものである。ここには、大学の対応が五項目に亘って記されており、その第二項で決意が次のように披歴されていた。
|
「今回の事態は、大学の歴史上の一大不祥事といわなければならない。大学としては犠牲も大きかったが、他面、学ぶべき点、反省を要する点もすくなくない。学生の間から、提起された諸問題や社会の各方面から寄せられた批判に対しては謙虚な態度で耳を傾け、大学教育の在り方、大学の機構、学内秩序の問題等々につき、反省と再検討の上改善すべき点は改善につとめ、再びかかる事態を招くことのないように万全をきしたい」。
|
3.7日、封鎖を解かれた学内に学生がもどった。諸事の禁止掲示をよそに昼過ぎには共闘会議や民青系の学生が集会を開いた。そして、共闘会議は第一政治経済学部自治会室で記者会見を行って、一般学生の対応が分散してきているとの認識を示した。2.4日の総長説明会を境として共闘会議が分裂し戦術をめぐって占拠派と非占拠派に分かれ、2.14日には共闘会議の占拠派が調停に応じる姿勢を見せたので社青同系と革マル系とが対立し、こうしたセクト間の争いが表面化してくるのに伴い、一般学生は学費値上げには憤りを覚えつつも、セクト間の争いに食傷する気分も醸成されていった。共闘会議にとって、この状況を打開し、いかにして組織を再構築するかということが大きな課題となった。共闘会議は、来る25日の卒業式は大学に対する弾劾の集会にすると発表した。
3.9-10日、各学部の合格発表が行われ、学内は受験生や父兄で終日ごったがえした。9日の教育学部、理工学部の合格発表後、合格者の入学手続と学費納入が10日から開始された。大学では混乱を避けるため、学費はすべて所定の銀行に振り込ませ、その領収証を持参の上入学手続を済ませた者に学生証を交付することにした。今回より施設費の分割払いを認めたものの、紛争の焦点であった授業料値上げ額は原案通りで、教育学部は初年度納入金として14万100円、理工学部は17万3千円(学科により実験等の違いで若干異る)、施設費の分割は教育学部3万円、理工学部7万円を二年次または三年次に払うということになった。このように授業料納入手続が原案の金額通りに実施されたことは、結局、この紛争が学生側の「敗北」に帰したことを意味するものとなった。すなわち、学費値上げ阻止の目標を事実上失ったわけである。共闘会議は、この日、「新しい目標に『人間回復』、『学内民主化』、『教育内容の民主化』を掲げ、25日の卒業式、4.1日からの期末試験ボイコットなどを中心に分裂状態の組織を再編成していく方針」(『日本経済新聞』3.10日号夕刊)を明らかにした。
3.11日午後、かねて指名手配中の大口全学共闘会議議長が集会に出席したところを他の全学共闘会議の事務局員とともに逮捕された。
一方、法学部では、大野実雄第一法学部長と有倉遼吉第二法学部長が揃って学部長の辞任を明らかにし、同時に教務主任・副主任の四教授も行動をともにしていたが、3.15日、この辞任と後任人事が定時評議員会で承認された。六教授の辞任は「健康上の理由」となっているが、各紙は「こんどの紛争で一、二法学部の連合教授会は先月〔二月〕十八日『大学側は値上げを再検討すべきだ。また学生は本部占拠をやめよ』との声明を発表、また大野一法学部長は一月末の学部長会で大浜総長に『一歩後退も考えるべきだ』と個人的に進言、二月十五日の評議員会では、学部を代表して『値上げを再検討すべきだ』と発言するなど、『既定方針は変えない』とする理事会に対して、批判的な空気があり、独自の働きかけを続けていたが、結局、理事会にはこの意見は反映されないままとなっていた」(読売新聞3.14日号夕刊)とのいきさつのあったことを報道している。
学部にこうした内情をも抱えていた大学当局は、卒業式を控え、各学部ごとに学生に総長説明会を行うことによって学生の理解を得る手立てを考えた。先ず3.16日午前11時から教育学部を対象に(約3百人出席)、21日午前10時からは商学部を対象に(約2千人出席)説明会を開催した。会場入口では共闘会議による一般学生に対する入場阻止の動きもあったが、総長が「今後はお互いに不信感を除き、信頼できる学園作りに努力したい」と述べると、全般に肯定的な反応が示された。
3.16日夜、共闘会議と四年生連絡協議会の幹部が記者会見して、「来る卒業式は従来のような儀式とせず、総長、学部長への代表質問などで四年間の早稲田生活を総括する場とする」と発表した。
3.18日、大学当局は「学生諸君保証人各位に訴えたい」(全12頁)を在学生と父兄に発送して、学費値上げの事情とこれまでの経緯を説明して理解を求めた。
3.19日、学部長会は、父兄も出席する25日の卒業式は紛争のあおりから大混乱になる恐れがあるため取り止めることを決定した。各学部では、卒業式での学生総代を選定するなどの準備を進めていたのであったが、遂に全学の統一卒業式の挙行はこの年度は幻に終った。
3.22日、連日の新聞やテレビ、ラジオによる学苑の紛争に関する詳しい報道で、私学振興策に具体的に本腰を入れる姿勢を示さなければならなくなっていった。
3.25日、自主卒業式。例年ならば、晴れやかな雰囲気で学部合同の統一卒業式が挙行される日であった。しかし、商学部のみが大隈講堂で学部卒業式を行っただけであった。同学部以外は卒業式に類する行事は実施せず、卒業生は各学部事務所で学生証と引換えに卒業証書を受け取ったのであった。
午後1時頃から共闘会議を中心とする卒業生が使用禁止の記念会堂に入り込んで、「早大統一総括卒業式」を教育評論家や詩人等をゲストに招いて行った。終了後、校歌を斉唱して、晴れ着姿の女子学生も交えて戸塚通り(現早稲田通り)、安部球場を経て本部キャンパスを巡る形で正門まで各クラスや専攻の色とりどりのプラカードを先頭にしてデモ行進を行った。
この日、大学は大浜総長名で、「卒業生諸君へ」と題する文書にして卒業生に配布した。次のような餞の言葉を贈っている(「続・激動の八十日」早稲田学報昭和41年5月発行第761号33頁)。
| 「大学の卒業式は、卒業生諸君にとっては人生における大きな節づけともいうべきものであり、社会的にもその意義は大きい。……この意義のふかい式典を急に取りやめることにしたのは、学生の一部に、この式典を妨害する動きがあるからである。……学部長会は、これら諸般の情勢を考慮に入れたうえで、慎重審議の結果、卒業生諸君に対してはまことに申訳のないことではあるが、慣例による全学的の卒業式はこれを中止することにした。卒業生諸君の心境を察すれば、おそらく、このままでは去るに忍びないという気持で一杯であろうと思う。せめて卒業式だけでも、従来の方式によってこれを挙行し、温たかい雰囲気のなかで諸君の門出を祝し、父兄の方々とよろこびを共にしたいと念願してきたが、それさえできなくなったことは、まことに痛恨に堪えない」。 |
| 「このうえとも精進につとめられ、各自の運命を開拓し、幸福な生涯を送られることを祈り、併せて世界の平和と民族の繁栄、さらに文化の向上に貢献されることを期待してやまない」。 |
3月下旬、在校生の関心は4.1日以降に延期されていた学年末試験であった。
3.28日、各学部で受験可否をめぐる討論が行われ始めた。
3.28日、政権政党の自民党内の私立大学出身の国会議員有志が私大振興策を協議して運動に乗り出した。
3.29日、第一政治経済学部の拡大クラス委員総会が試験反対のためにバリケードの再構築を確認して、学部校舎入口に再び築き、校舎内に泊り込みを始めた。
3.30日、第一文学部自治会も校舎にバリケードを築いた。同日、第一商学部拡大クラス委員総会でも試験ボイコットを決定し、校舎でバリケードを造る学生とスト反対の一商ゼミナール有志連合会の学生が衝突し若干の負傷者を出した。
3.31日、法学部、商学部、理工学部にバリケードが相次いで築かれた。
4.1日、教職員の説得も不調に終って、全学の学年末試験の実施は不可能となった。
4.2日、理工学部で十人ほどの学生が受験したが、妨害で試験会場に入れなかった学生は中庭や隣の保善高等学校等を借りて、教員を囲んで説明会や討論会を開いた。商学部でも早稲田実業で説明会を行った。この夜、緊急学部長会が開かれ、試験は日程通り実施する方針であるが、実施不可能の場合は教員が学年別、クラス別などで学生との話合いの場を持つように努力することを申し合せた。
4.3日、体育局の試験が中止となり、教育学部にもバリケードが築かれ、またしても全学ストが現出した。以後十日ほどの間、各学部で試験が延期を重ねていった。この間、学部別に説明会が行われ、また、新四年生の間から、就職活動期が迫ってきているので試験を受けたいという声が高まってきた。
4.4日、学部長会が、学年末試験は各学部、学年で一斉に行う方針に固執することなく実施し得る学部、学年で個別に行ってもよいとの方針を決定した。
共闘会議が「全学バリスト」による「試験粉砕」強行を叫んでも、「試験ボイコット」に踏み切った一月段階とは明らかに異ってきていた。ここに至って学費値上げ反対という現実の目標がなくなり、「転機」が訪れていることを運動の担い手達も自覚せざるを得なくなった。「全学バリスト」は「試験粉砕」のために行われている観があり、かつてのような熱気を伴った積極性はなかった。
4.5日、『大学の当面の課題と対策について』(全12頁)が全学生に発せられた。これは、3.6日の「声明書」を承ける形で、「第一 教育の在り方に関する問題点と改善策」、「第二 学費の値上げと予算の概要」、「第三 学生厚生センターとレクリエーション施設の計画」、「第四 施設費の軽減問題について」、「第五 学生会館の管理運営について」の五項目が記されていた。大学の抱えているこうした問題点は、やがて、大学問題研究会で盛んに論議されていくことになるが、大学としてはその当面の基本姿勢を取敢えず示すことによって、「紛争」の治癒に努める姿勢を表した。
4.8日頃から受験の可否があらためて各学部で投票に付されていった結果、受験賛成の声が多くなっていった。4.8日と11日の両日に理工学部で受験可否の投票が行われ、受験賛成派が多数を占めた。4.9日、11日、12日の三日間の投票で商学部も受験賛成が多数となった。4.13日に商学部、4.14日に理工学部のバリケードが学生の手によって撤去されだした。4.18日、両学部とも試験を実施した。4.21日、教育学部も新四年生の分離試験を早稲田実業で行い、次第にスト解除の気運が全学的な趨勢となってきた。
4.23日、大浜総長が学部長会で辞意を表明した。翌24日の臨時理事会で全理事も総長に辞表を提出し、大学の最高執行部は総退陣することが内定した。12年に及んだ学苑の「大浜時代」は、「学費・学館紛争」の終息を控えて、ここに終りを告げた。
5.1日、紛争で延び延びになっていた昭和41年度の学部入学式が一ヵ月遅れで、記念会堂で午前と午後の二回に分けて挙行された。開式に先立ち、グリー・クラブ、コール・フリューゲルによって校歌の指導が行われ、早大交響楽団の奏でる校歌とともに教職員が久しぶりに式服に威儀を正して入場して壇上の席に着いた。教務部長の開会の辞に続き、既に辞意を表明している大浜総長に代って時子山常任理事が式辞を述べた。「最初にお詫びしなければなりませんことは、清新潑剌たる諸君をお迎えするに当りまして、まだ学園の正常化が十分ではなく、バリケードなども残っていることでありますが、現在各学部で学園の正常化と改善に努力しておりますし、また、大学全体としても、今回の事件から学びとりましたいろいろな教訓に顧みまして諸君を迎えるにふさわしい大学づくりを目指していますので、今日から名実とも早稲田大学学生の一員となられた諸君は、新しい早稲田大学の歴史づくりに加わるのだという意気込み、自負をもって、今後四年間の学生生活を実り多いものにして頂きたいのであります」(『早稲田学報』昭和41.6月発行第762号10頁)と謝罪の言葉を述べたあと、「『永遠」の今を生き抜こう」との内容の新入生歓迎の式辞を行った。最後に全員が起立し校歌を斉唱して式を終えた。この入学式は、本部校舎にバリケードを残したままで挙行されたが、学苑はこの日を待ちわびた一万余の新入生とその父兄達で賑わい、あちこちで記念撮影がなされ、またサークルの勧誘が盛んに行われたりして華やいだ空気が溢れた。式場の記念会堂の前では共闘会議派の学生が集会を開いたが、妨害もなく式は二回とも無事に終了した。なお、大学院と専攻科の入学式は、学部に先立って4.18日に21号館(現10号館)の大教室で既に挙行済みであった。
5.10日、銀座東急ホテルで開催された臨時評議員会で辞表が受理され、同時に総長代行に阿部賢一評議員会長が選出された。毎日新聞5.11日号朝刊は次のように報じている。
| 「母校の『難局』を憂いながらも『火中のクリを拾う』ことにしり込みする関係者の中にあって、その誠実で温厚な人柄をかわれ評議員、理事の有力者『絶対多数』の支持で臨時総長に選ばれた阿部さんは、『迷惑しごく。ほかに有能な人物がいくらでもいるのに……』と不服そうだが、『引き受けた以上は、この老人、最後の奉仕をする覚悟』とことば少なに語る」。 |
各紙朝刊は、「学生の声を聞く/わたしは態度で示すよ」、「根気よく取組む/早大総長代行阿部さん語る」、「早大阿部総長代行語る/血の通う大学に」、「阿部氏が総長代行/凍った感情ときたい」などの見出しで総長代行就任の抱負を伝えた。阿部総長代行は、就任の翌日早速登校して、学生の前にその姿を現したばかりでなく、更に共闘会議の集会に前触れもなく、いわば分け入る形で出席するという積極的な行動を採った。
毎日新聞5.12日号朝刊が、この光景を大きな写真入りで次のように報道している。
「どこへでも出かけて、だれの声でも聞くよ」とフランクな姿勢で登場した早稲田大学の臨時総長阿部賢一さんは、初登校の十一日、さっそく学生の前に姿を見せ「いっしょに紛争を解決していこう」と呼びかけた。この日の阿部さんは、共闘会議のアジ演説を聞き、抗議の立看板をながめながら、構内を歩き回った。昨年末から、総長の姿が構内から消えてしまったワセダで、何ヵ月ぶりかの「キャンパスの総長」だ。
午後三時すぎ、阿部さんが近所の床屋から大学に帰ってくると、共闘会議の学生が「新総長の話を聞こう」と本部前にイスを並べて待ち構えていた。一般学生もこれまで「総長の顔」をほとんど見たことがなかっただけに、約千五百人の学生が本部前を埋めた。阿部さんは学生の求めに応じて気軽に壇上にあがり、マイクの前へ。「大学もヘマをしたけど、君らには苦労をかけるね。君たちがいろんな希望を持っていることは知っている。どんな思想、行動も自由だ。しかし、行きすぎはいけない。君たちは私の孫みたいなもんだ。ときどき手に負えなくなる。だが、ものわかりのよい学生であってほしい。せかずに、じっくり話し合おうじゃないか。具体策は、新理事と相談しないうちに私一人で放談するわけにはいかないが、どうするにせよ、ひとにぎりの理事者だけではできない。君たちと一緒にやっていこうじゃないか。大学は諸君らによって守られなければ……。一人一人が早大生の自覚を失わないでほしい」とへだてのない調子で話しかけた。「先輩、期待しているよ」と学生からヤジがとぶと、ヤジった学生の顔をさがして「ウン、やる」といちいち受け答えする。「ぼくは毎日、本部へくるのに、本部前に机を並べて出入りを監視されているようなのは困るね」との注文には、共闘会議の学生もニガ笑い。約十分話したあと「総長だから毎日くるよ。いつでも会う。きょうはこれでもういいね。それじゃあ」とニコニコしながら手を振って壇を降りると、学生たちはその背に盛んな拍手。理事者が集会に出てくるとなかなか放さない共闘会議の学生も、この日は立ち去る総長を引きとめない。こじれにこじれたワセダ紛争の解決に、なにか明るいきざしを思わせるような「総長と学生たち」の出会いのシーンだった。 |
阿部総長代行は、昭和初年の政治経済学部の新進の教授時代、大山郁夫教授の辞職(「大山事件」)が議題に上った政治経済学部教授会で、大山の辞職を求める高田早苗総長の教授会への臨席を不都合として高田に退席を求め、教授会の大勢に抗して大山を擁護し、また、毎日新聞(大阪毎日新聞、東京日日新聞)の主筆時代、対米英宣戦布告を直前に察知し、身体を張って、東条英機首相の弾圧を覚悟の上で開戦の一大スクープを国民に報知した、まさに昭和ジャーナリズム史上にその名を留めている人で、学識の豊かさ(本学苑が付与した経済学博士の第一号)に加えてその見識と気骨あるりベラルな人柄は知る人ぞ知るで、こうした人柄が、いきり立っていた学生達に期せずして好感を以て迎えられた。阿部の総長代行としての登場は学苑に爽風を吹き込む役割を果した。僅か十分ばかりの学生とのこの初の「対話集会」を伝える新聞が、「阿部さんニコニコ、学生もニコニコ/一緒にやろうよ/早大臨時総長、マイクに立つ」、「阿部さん、学生に第一声/魂のふれ合いを/ワセダを守るのは君たち/学生さかんな拍手」、「なごやかに学生と話し合う阿部総長代行/『阿部調』に爆笑と拍手/学生二千人に顔見せ」、「『名誉を回復しよう」/阿部早大総長代行集会で気軽な第一声」等々の見出しで詳報した。かくして、大浜総長の辞任の英断に続く阿部総長代行の登場は、紛争の流れを変える上で一大エポックとなった。
5.13日、阿部総長代行を中心とする新理事会が発足した。阿部は新理事とともに紛争解決に向けて積極的に行動した。
5.16日、阿部総長代行名で「学生諸君」と題する一文を掲示し、左の如く訴えた。
| 学費問題のみならず、学生会館問題などの自余の問題については引きつづき検討を続けてゆくが、ここに憂慮される緊急の事態は、予定された大学の行事のうち、最低必要とするものさえその実行があやぶまれてきたことである。すでに体育実技のある種のものは遂行不能におちいっているが、このまま日を送れば例年行っている夏季学期は、これを八月中に行うものとしても日数がなく、そのために単位不足により留年の止むなきに至る学生数は数千に及ぶことになる。この関係は第二学部では夏季学期が正規の授業時数のうちに予定されているだけに、一層深刻である。これによってこれら学友のうける時間と経費の損害は意想外に大きいのである。学生諸君は一日もはやく、一人のこらず登校し、大学の庭に見られる現実を直視し、慎重に考慮するとともに、最終の期限である五月二十三日(月)を目標に正規の授業が開始されるように協力しなければなるまい。授業を行う一方で話し合いを続けることは決して不可能ではない。極端な闘争手段によらなくても、何時でも話し合うつもりであるから、大学を信じ、諸君の良識による局面の打開を考えてほしい。……重ねていうならば、今が最終の態度決定の時である。過去の早稲田大学の歴史において今日ほどの危機に出あったことはなかったのである。(早稲田大学広報/昭和41.5.16日号外) |
阿部総長代行の言う「5.23日」は重要な意味を持つものであった。学苑当局は、実は、「五月危機」に直面していた。一つは、阿部が自伝「新聞と大学の間」で次のように回想している。
| 大学側の一つの懸念としては、次に紛争長期化に伴う心配があった。六カ月以上授業を行わなかった場合、文部省は学校に対して閉鎖を命ずることができるという法律がある。学校教育法の一カ条であるが、大学はバリケードで各学部が封鎖され、五カ月にわたって、八月二十三日がその期限になる。むろんそう簡単に早稲田に閉鎖命令を出すとは誰も考えないが、それを無視することはできない。といって、紛争処理に焦って、このことを吹聴すべきではない。大学側が期限内の処理に急ぐとなると、多数の学生はこれを理解するかも知れないが、過激各派はこれを大学の弱味の暴露とみて、おそらく、もう一押しすれば勝てると、一段と気勢を高めるに相違ないとも考えた。 (二一八―二一九頁) |
学校教育法第13条に、「六箇月以上授業を行わなかつたとき」には「監督庁は、学校の閉鎖を命ずることができる」と定められており、また一方、大学設置基準第27条では、「一年間の授業日数は、定期試験等の日数を含め、三十五週にわたり二百十日を原則とする」と定められていて、大学の存立に直接関わる非常事態に直面していた。この段階では、「学校教育法」に抵触するまでには暫くの日時が残されていたが、大学設置基準に違反する恐れは目前に迫っているという緊急事態にあった。従って、学苑はこの事態を学生達に十分に理解させ、現状打開を早急に訴えなければならなかった。「5.23日」の重要な意味を学生に周知徹底せしめるため、各学部では更に詳しく説明した掲示を張り出した。例えば第一政治経済学部では、28日付で、「学年度の完結について」と題する掲示を出している。こうした中でも、かつての規模ほどではないものの、少人数のデモが断続的に繰り返され、バリケードはそのままであった。
5.17日、阿部総長代行は教職員に就任の挨拶をして解決への協力を求めるとともに、記念会堂で第一、第二商学部学生に説明会を行ったのを皮切りに、18日に第一、第二文学部、19日に第二政治経済学部、21日に教育学部、27日に第一法学部等々と次々に説明会に出席して、紛争収拾への協力を説き続けた。
5.19日、あるセクトが「学費・学館、処分撤回問題」の討論集会を開いた。
5.20日、共闘会議派(約四百人)と民青系(約千五百人)がそれぞれ他大学の学生の応援を得て集会とデモ行進を行い、これに対して、彼らの参加を非難する全国早稲田大学学生会連盟との間に一時険悪な睨み合いが続くなど、事態は決して楽観できるまでには至らなかった。しかし、ほぼこの日を以て大きな混乱はなくなった。
5.21日頃から学生の間に収拾の具体的な動きが現れるようになってきた。この日、第一商学部学生によるスト可否の投票が実施され、バリケードが撤去されだし、第二政治経済学部の新2年生、新3年生の期末試験の受験可否の投票が圧倒的多数で受験と決定し、23日の授業再開の目標日には、全学部には至らなかったが、第一商学部と理工学部の学部全体と一政・一法・二文の各一部が実際の授業を行うことができた。
5.23日、大学は「学生諸君へ」と題する次のような告示を掲示した。
学園の校舎の入口を閉ざしていた障害物は学生諸君の自治的な手続きによって撤去された。しかしこれによって大学が正常化したと考えることは早計である。教室で授業が行なわれるようになったとはいえ、失われた時間をとりもどすためには並々ならぬ努力と忍耐を必要とすることだろう。またこの度の事件の原因とみられる諸問題についても引き続き検討を要するものが多い。
学費の値上げに関連して、私立大学の経営に対する論議がさかんになったが、これは一大学内の問題にとどまるものではなく、その困難の原因の多くは戦後の社会情勢の急激な変動にある。したがってこれが根本的な解決をみるにはなお多くの時間を要することはいうまでもないが、これを促進するためにもひろく経営の実情を訴え、私学の立場を理解してもらうことが望ましい。経理内容の概要を公開することは、この方針に沿うて今後も続けるつもりである。
学生会館の運営については、まだ審議が最終の段階に達していなかったことでもあり、今後もこれを継続する。良識による規程のもとで、学生諸君が最も効果的に会館を使用できるよう、学生の代表者と関係者が充分話しあい、具体的な運営の方法を定めてゆく。話しあいの機会をもつことは、学生会館問題に限らず、学生生活のすべての面で必要であるから、諸君の意見が教授会に反映し、さらに理事会にも反映するよう各方面になお一層の配慮を願うこととした。教育の府である大学においては、人間関係をそこなうことのないよう、組織のいたるところにつねにこまかい神経のゆきわたるよう努めなければならない。
(早稲田大学広報/昭和41.6.23日号外)
|
| 「学問の独立」の意味を考え、学生の総意が教育と研究に支障のない洗練された形式を生み出すような「正しい自治の実行」が実現できるよう強く要望し、更に、「大学の教育の現状については、この事件を通じて鋭い批判をあびた。これらの問題こそこの度の事件の真の原因であったと解釈する。したがって正常化は、教育の刷新、機構の改革を通して行なわれるべきである。なかでも教育の問題は各学部教授会ですでに取りあげられているが、大学においても特別の委員会をもうけ、各学部の総意を交換し、その実現に強力しあう体制をとる」と声明し、「五ヵ月にわたるながい苦しみを、幸に転じうるか否かは、これからの努力にかかっている。全学の諸君が勇気と希望をもって前進することを期待してやまない」と最後を結んだ。この日から全学揃っての授業が再開された。 |
5.23日、全学一斉の授業再開日となったこの日、定時評議員会が開かれ、阿部新体制は学費の中の施設費を2万円引き下げる方針を打ち出した。この件は、この後、7.15日の評議員会で正式に決議され、即日施行となった。
5.25日、第一文学部新4年生、第二政治経済学部新2年生・新3年生の期末試験が実施された。
5.28日午後2時から21号館で共闘会議主催のティーチ・インが阿部総長代行と各理事が出席して開かれた。処分問題、学費値上げ・学生会館問題、機動隊導入問題について学生との質疑応答があり、堂々巡りの議論で阿部総長代行の疲労も加わり、遂に11時30分頃医師が制止して阿部総長代行の退場となった。翌日午前2時頃まで高木純一常任理事が代って答弁するという長時間集会となった。
6.1日、大学側と学生達のティーチ・インが行われ、各学部での学生大会も頻繁に開かれた。大学当局の熱心な働きかけと一般学生の授業再開への努力が次第に実り始めた。
6.4日、第一政治経済学部が、5日から7日にかけて第二文学部が、14日に第一法学部・教育学部(民青系)・第二政治経済学部が、15日に教育学部(革マル系)がそれぞれスト中止を決議した。そして、最後まで去就が注目された第一文学部では19日の学生大会が遂に深夜にまで及び、このため多くの女子学生も帰宅できない事態となり大隈会館や校舎内で宿泊あるいは仮眠する者が続出し、20日付で第一文学部長名による、「下記の者は、昨夜の当学部学生大会に参加し、深夜に及び、帰宅できなかったことを証明します」との証明書まで発行することになってしまった。こうした大会を経て、22日午後2時までに学生投票が終了してスト中止と決定し、同5時に学苑最後のバリケードが撤去された。ここに1.18日の第一法学部・教育学部のスト突入以来の断続して打たれてきた全学ストが155日ぶりに解除された。6月、最後となった文学部のスト解除で決着を見たが、「早稲田を揺るがした150日(足掛け7ヶ月)」として刻印されている。 |
| 百五十五日にも及んだ紛争の意味と、この事件がもたらした教訓。 |
「学館問題」のその後の推移。
紛争終結後の41年10.14日、学部長会の要請に基づいて学生会館問題委員会が設置された。同委員会は各学部および体育局の教員代表、学生の会の会長代表、教務担当常任理事、学生部長、庶務部長ら24名から成り、以後、翌年5.6日まで19回委員会が開催された。しかし、学生側との折衝は実を結ばなかった。その後、44年に再検討され「学生会館管理運営大綱案」が作成されて、建物の管理責任・人事および予算の最終決定は大学側にあるが、実際の使用上の問題は、学生代表によって構成される運営委員会によって運営され、規約や予算などは大学と運営委員会との間に設けられた協議会によって協議されることが提案された。しかし、その後も、学生側との折衝がうまくいかなかったばかりか、引き続く学苑紛争によって閉館もやむを得ない状態が長年続いた。この間、46年夏に建物保全のため外装の一部が補修され、更に55年に1階から5階にかけて改修が施されて、遂に秋より、竣工以来実に15年ぶりに開館の運びとなった。 |
| 【早大闘争に対する各派の理論】 |
この背景は次のように考えられる。自民党政府の教育行政政策は、この時期増大し続けるベビーブーマーの大学生化に対して何ら有効な受け入れ対策をなしえず、私学へ追いやってきた。一方で、戦後直後の社会的合意でもあった「大学の自治」に対する介入を強め、お得意の官僚的統制を進めつつあった。「アメリカさんから頂いたものは日本の風土に合わぬ」というばかりの逆行コースへシフト替えしつつあった。私学経営者は、「大量入学→マスプロ教育→設備投資→
借入金増→学費値上げ→大量入学」という悪循環に陥っていくことになった。
自民党政府によるこうした教育費の切りつめという反動的な大学政策の一方で、財政投融資、軍事費にはどんどんと国家予算を投入していた。これらの動きにどのように対応していくのかが早大闘争の課題であった。
民青同系は、1.教育機会均等の破壊、2.大学運営の非民主的やり方、教授会及び学生自治会の自治権に対する侵害、3.一部理事による闘争弾圧の為の機動隊導入及び国家権力の介入等への批判を組織していくこ
とを指針させた。併せて、4.ひものつかない国庫補助の大幅増額等を要求する学園民主化闘争を指針させていた。
社青同解放派は、資本と労働の対立という観点からの大学=教育工場論に基づき、闘争を、教育工場を経営する個別権力資本=早大当局と個別労働=学生の闘いであり、教授一般は労働下士官と捉えたようである。こうした「個別資本からの解放」、「産学協同路線粉砕」という理論は、その後学園闘争に対するストライキ、バリケー
ド、武装、コンミューンの樹立へと発展する理論的基礎となった。民青同は、
社青同解放派のこうした理論を先鋭理論と位置付け、自民党政府の反動的貧困な大学政策に対する闘いを放棄し、免罪していると批判した。
革マル派は、国家政策としての大学管理化とこれに呼応する大学当局の産学協同政策に対する闘いとして位置付け、「学問を独占的な産業に従属させ、創造的で自由な、権力に抵抗するような学問を封じ込める結果になる」という立場から批判していた。
この後明大闘争を担うことになったブントは、この時の早大闘争を次のように総括した。
| 概要「各クラス における闘争組織という各自治会学年別連絡協議会方式が指揮系統を混乱させ、ひいては全学共闘の機能をマヒさせた。従って、まさしくあらゆる闘争において、まず第一に要求されるものは、(自治会ではなく)強固な中央集権的な組織の存在である」。 |
この理論はやがて「ポツダム自治会破産論」 を導き出していくことになった。こうした諸理論の発展が、後の全共闘運動とその大学解体論の下地をつくっていくことになった。
|
その他、長崎大=学館問題、同志社大=学館・寮開放、山形大=自衛隊説明会中止・寮問題、東京農大=新寮建設問題、近畿大=総長選問題、群馬大=学館問題、東北大=移転反対問題、高崎経済大=不正入学・私学化反対、都留文科大=新校舎落成式反対などさまざまな問題をとらえて闘争が展開された。その数、実に全国で65校に及んだ。
1.21日、都学連(三派系)主催・公共料金値上げ反対、原潜・原子力空母寄港反対決起集会〔清水谷公園〕、二百五十名結集、国会デモで四名逮捕。
1.23日、全国実行委主催・米原子力艦隊寄港阻止横須賀集会〔臨海公園〕に都学連(三派系)等五百名参加、米軍基地ゲート前で機動隊と衝突、二名逮捕。
|
【東大で、インターン制廃止闘争始まる】
|
|
1.24日、東大医学部自治会、インターン配置問題をめぐって卒業試験ボイコ ット闘争。これが後の東大全学部を巻き込んだ東大紛争→東大闘争に発展していくことになった。「全共闘グラフティー」は次のように記している。
| 「東大闘争は医学部における青年医師連合の基本的権利を守る闘いと、医療部門における人民収奪の強化、及び医学部における研究教育体制の合理化-帝国主義的改編への闘いを発端として火の手を挙げた。そして独立資本との産学協同を推進する『国立大学協会自主規制路線』のもとに、この闘いを圧殺しようとした東大当局に対する叛乱として展開される」。 |
1月から3月にかけて横浜国大で学部の名称変更に反対する紛争が起こり、学生がキャンパスを占拠、教職員を排除して学生の自主管理を約1ヶ月余にわたって強行した。その自主管理下のキャンパスでは、学生自治会が編成した、自主カリキュラムによる学習が進められるという画期的な事態が発生していた。3月には、民青系全学連、全寮連、大学生協連の共催で、大学自治と学生生活を守るゼミナールが開かれた。6.24日青医連・医学連、インターン制廃止統一行動。10月東大の大学院生を主とする「東大ベトナム反戦会議」が所美都子らの手で立ち上げられた。この動きが後の全共闘のさきがけとなって行く。
|
1.28日、教員養成制度改悪阻止全都学生総決起大会〔麻布公会堂〕、横浜国大学芸学部生中心に七百名参加、学芸学部の教育学部格下げ反対・教員免許法政悪阻止等を決議、文部省・国会にデモ。
2.1日、原水禁、結成.=あらゆる国の核実験反対。
2.2日、医学連関東ブロック主催・インターン制完全撤廃決起集会〔清水谷公園〕に千五百名参加、文部省デモで一名逮捕。
2.2-4日、郡学連(民青同系)第二回臨時大会〔東京経大〕、六大学八自治会脱退の自己批判、早大闘争支援を決議。
2.20日、都学連(三派系)主催・大学設置基準改悪・教員免許法粉砕全都決起集会〔清水谷公園〕 に五百名参加、文部省デモで三名逮捕。
2.21日、全学連(民青同系)・全寮連、在日朝鮮人弾圧の学校教育法改悪反対で政府に抗議。
3.12-13日、全学連(民青同系)第五回中央委〔明大〕、全国学園闘争重視を討議、中執三名辞任に伴い委員長代行に梓沢和幸決定。
3.14日、青学代表者会議主催・青学総決起集会〔日比谷野音〕に民青同系八百名参加、早大闘争支援を決議。
3.20日、諸要求貫徹全国大統一行動、中央集会〔晴海埠頭〕に全学連(民青同系)六千名参加等、全国各地で一万三千名が集会・デモ。
| 【日本のこえ派と社革、統社同が結集】 |
| 3.21日、日本のこえ派と社革、統社同が結集して「共産主義者の大同団結を呼びかける全国活動者会議」開催。組織統一準備委員会発足。委員長・志賀義雄。 |
3.26-28日、大学自治と学生生活を守る第一回全国学生ゼミ〔東京〕に民青同系千名参加、教育の軍国主義化反対等を決議。
3.27日、都学連(三派系)第十五回臨時大会〔法政大〕、日韓闘争を総括、大学設置基準改悪阻止・十二月全学連再建等を決定。
3.28日、都学連(三派系)・京都府学連共催・全国自治会代表者会議〔東京〕、構改系を除く各派四百名参加、十二月全学連再建を確認。
3.30日、民主主義学生同盟第6回大会。
4.2-3日、全学連(革マル系)第四十三回中央委〔東京〕、早大闘争の支援強化等を決議。
4.18日、全学連(民青同系)大学の自治を守れ等全国統一行動、全国各大学で学内集会・デモ。
4.20日、反日共系各派、大学設置基準改悪・教免法改悪反対で決起集会〔清水谷公園〕に三百名結集、文部省デモで三名逮捕。
4.22日、中央実行委主催・春闘勝利等総決起集会〔日比谷野音〕 に民青同系千名参加。
4.26日、国労スト支援に反日共系各派百五十名、品川駅構内で坐り込み・集会、機動隊の実力行使で三名逮捕、民青同系七百名、品川駅前で集会。
4.28日、早大共闘会議・反日共系各派、大学設置基準・教免法改悪粉砕・早大闘争勝利全都総決起集会〔早大〕 に千五百名参加、のち早大生先頭に日比谷公園までデモ・五名逮捕、全学連(民青同系)等主催・早大闘争勝利を目指す中央集会〔早大〕に八百名参加、新宿までデモ。
5.10日、全学連(革マル系)百名、中国水爆実験に抗議し新橋駅構内で集会、のち華僑総会本部に抗議デモ、無届デモとして四名逮捕。
5.13日、全学連(民青同系)主催・早大闘争勝利・教免改悪反対等諸要求貫徹決起集会〔日比谷公園〕に千名参加し国会請願。
5.16日、中共中央委員会が、中央文化革命小組み設置を下部組織に通達。論争から実際の奪権に向かい、これが文化大革命の始まりとなる。文化大位革命は、トロツキーの永続革命論を採り入れ、更に進化させた継続革命論に依拠していた。次のように述べている。
| 「社会主義社会は相当長期らわたる歴史段階である。社会主義というこの歴史段階に於いては、依然として階級、階級闘争が存在し、社会主義と資本主義との二つの道の闘争が存在し、資本主義復活の危険性が存在している」(「北京周報」18号)。 |
5.17日、反戦青年委主催・ベトナム侵略反対総決起集会〔日比谷野音〕に労学四千名参加、国会デモ。
5.18日、都学連(三派系)主催・教免法改悪反対・大学設置基準改悪阻止全都決起集会〔清水谷公園〕に千五百名結集、国会・文部省に抗議デモ、十二名逮捕。
5.20日、早大共闘会議・反日共系各派、早大闘争支援全都総決起集会〔早大〕に二千五百名参加、国会・文部省にデモ、民青同系三千名も集会〔早大〕・米大使館デモ。
5.27日、都学連(民青同系)等主催・米原潜横須賀寄港阻止全都緊急集会〔清水谷公園〕に五百人参加、米大使館にデモ三名逮捕。
5.29日、原潜寄港阻止社共統一行動、横須賀大集会に反日共系各派五百名結集、基地ゲート前で機動隊と衝突、五名逮捕。
5.30日、労・学1万5000名が次第に数を増しながら原潜寄港抗議行動。反日共系各派百名が、横須賀基地正門突破・基地内でデモ展開、刑特法違反で11名逮捕、夜、集会〔臨海公園〕の後、正門前デモで機動隊と投石・旗竿等で衝突、四名逮捕、革マル系五百名正門前坐り込み。
5.31日、原潜寄韓阻止社共統一行動、横須賀大集会に民青同系千名参加。1 反日共系各派二千名、原潜寄港阻止決起集会〔横須賀〕、機動隊に規制されつつも基地正門ゲート前坐り込み展開、四名逮捕。
6.2日、全学連(民青同系)主催・原潜寄港阻止中央決起集会〔日比谷野音〕に千二百名参加。
6.4日、共青が掌握していた教育大の文・理自治会失陥。共青系指導が崩壊。
|
| 6.7日、社革内の統一反対派である西川彦義、中村丈夫らが分裂。西川らが日本勤労者解放連盟を結成。11.12-14日、前期結党大会開催。 |
| 6.8日、平和と社会主義をめざす学生同盟が統一共産同盟に改称。 |
6.9日、都学連(三派系)主催・祝日法粉砕エンプラ寄港阻止決起集会〔日比谷野音〕に四百名参加、清水谷公園までデモ。
6.15日、六・一五記念集会実行委主催・安保六・一五記念政治集会〔九段会館〕、都学連(三派系)等の学生、労働者二千名参加、十二月全学連再建等のスローガン採択。
6.21日、全学連(民青同系)全国統一行動、中央集会〔日比谷野音〕に二千名参加し大学の自治を守れ等決議、代表団文部省で抗議文朗読。
6.23日、都学連(三派系)主催・エンプラ寄港阻止・小選挙制粉砕全都決起集会〔清水公園〕に六百名参加、日比谷公園までデモ・一名逮捕。
6.24日、青医連、医学連が、インターン制廃止統一行動。
6.29日、アメリカが、北ベトナムの首都ハノイを爆撃。
6.30日、反日共系各派百五十名、ハノイ・ハイフォン爆撃緊急抗議行動、米大使館にデモ。
7.1日、ハノイ 爆撃機抗議緊急集会。各派数千名。全国実行委主催・ハノイ爆撃抗議緊急集会〔清水谷公園〕に都学連(三派系)二百名参加、反戦青年委とともに米大使館にデモ。
7.2日、全寮連の第8回大会が開かれた。この時民青系と反民青系との間に暴力事件が発生している。
7.4日、政府が突然、新東京国際空港り建設地を、千葉県成田市三里塚と隣接する芝山町に閣議決定する。当初1965.11月に富里に内定していたが、地元住民の反対に遭い変更された。三里塚の住民には事前に何の打診、事前説明、協議も無いままの発表となり、地元が猛反発していくことになる。三里塚には明治初期から三里塚御料牧場があり、天皇・皇室用の農産物を確保するために広く国が管理している直轄地で、そこに戦後入植した農民たちが農業を営んでいた。土地収用をやり易いと見たのか三里塚に白羽の矢が立った。その情報を得て、閣議決定の前の6.28日、農民たちは「三里塚・芝山連合空港反対同盟」を結成した。この地域の農民は、戦争では大陸へと狩り出され後、開拓民として入植し、やっと農民としての生活を営んで来た人々が多かった。農具商で画家、クリスチャンの戸村一作さんが、みなに推されて反対同盟の委員長になった。農民の戦いは千葉県の社会党、共産党、労働組合も支持した。
7.5日、反戦青年委主催・ハノイ爆撃抗議集会〔清水谷公園〕に都学連三派系)百名参加、米大使館デモ。
7.5日、中央実行委主催・ハノイ爆撃抗議集会〔明治公園〕 に全学連(民青同系)九百名参加。
7.5日、日米合同委反対社共統一行動、京都府学連千六百名、集会〔京都洛北高校前〕、のち国際会館にデモ。
7.14-17日、全学連(革マル系)第二十三回全国大会(委員長・成岡庸治)、日韓闘争・早大闘争を総括、三派系の十二月全学連再建粉砕等を決議。68大学・121自治会。
7.14日、民青系全学連が第17回大会(委員長・平田勝)を開いている。75大学・163自治会(189ともある)、オブザーバー自治会140、一般傍聴者を含めて千数百名が参加した。軍国主義復活につながる小選挙区制反対・全学連とIUSの正常な関係回復等を決議。
7.14-17日、都学連(三派系)第十六回大会〔明大〕、小選挙区制粉砕等を決議、十二月に全学連再建を確認。
7.18日、都学連(三派系)・京都府学連共催・全国自治会代表者会議〔明大〕、十月全学連再建準備会開催・十二月再建大会開催を決定。
7.19日、和井田史朗さんが日韓条約反対闘争で死去する。7.20日、都学連(三派系)主催・故和井田史朗追悼抗議集会、のち百五十名で警視庁に抗議デモ。
| 【「三里塚・芝山連合新東京国際空港反対同盟」が結成される】 |
| 7.20日、閣議決定と同時に、地元の約千戸3千名の農民・住民によって、「三里塚・芝山連合新東京国際空港反対同盟」(委員長・戸村一作)が結成された。これが後に成田闘争へと繋がることになる。 |
8.2日、8.2反戟集会〔九段会館〕、中核派系学生・労働者千五百名参加。
8.6日、八・六広島反戦集会〔広島〕、反戦青年委・学生八百名参加、十月ベトナム反戦全国ゼネスト決議。
8.26-27日、社学同(マル戦派)第二回全国大会〔東京〕、社学同統一派との合同を決議。3 社青同東京地方本部第七回大会〔社会文化会館〕、反主流・協会派が演壇占拠し混乱、主流・解放派がこれを実力排除し大会を続行(18日社青同中央本部、東京地本解散を決定)
| 【第二次ブント再建】 |
9.1日、 既に昨年4月関西派は、「マル戦派」と「ML派」の一部を結合して「社学同全国委員会」(社学同統一派)を結成していたが、このような曲折ののち更にこのたび「社学同統一派」と「マル戦派(マルクス主義戦線派)」の残存部分との合同がなって、ブントは「第6回共産同再建全国大会」(ブント再建大会)を開催するに至った。ここに、ブントは6年ぶりに組織統一をみるに至った。「社学同統一派」と呼ばれる。
これが、「第二次ブント再建」といわれるものである。
この経過は次のように簡潔にまとめられている。
「1962年ころから、共産同の残存者によって、まず社学同の再建が進められ、学生活動家を中心に「東京社学同」と「関西社学同」が結成されました。1963年には、「東京社学同」の一部に、“従来の共産同路線は政治闘争偏重主義であり、日共系学生運動に対抗するためにも、路線の見直しが必要である”と主張する「マルクス主義戦線派」(マル戦派)が台頭してきました。これに対抗して、「東京社学同」の多数派は「新しい前衛党の建設」を主張して、「マルクス・レーニン主義者同盟」(ML派)を結成しました。マル戦派も、ML派も、互いに自派が、共産同の正統派であると主張し、譲りませんでした。
共産同の関西地方委員会を中心とする「関西グループ」は、このような中央の混乱の影響を受けることなく、結束して活動を続け、1962.4月、「関西共産主義者同盟」(関西派)を結成して「社学同派」の盟主となりました。1965.4月、関西派は、「マル戦派」と「ML派」の一部を結合して、「社学同全国委員会」(社学同統一派)を結成、更に、1966.9月には、「統一派」「マル戦派」の残存者をも結合して、「共産同第6回全国大会」(再建大会)を開催するに至りました。ここに、共産同は6年目にして、組織の統一を果たしました。これを『第二次ブント』と呼んでおります」。 |
他方、「ML派」の一部は、こ のブントの統合に反対し、毛沢東の思想である「人民戦線路線」を取り入れ党の路線とし、「帝国主義を打倒するための人民革命」を目的として、68年「日本マルク
ス・レーニン主義者同盟」(ML同盟.書記長鈴木*夫)、・学生部隊=学生解放戦線を結成し、
「第二次ブント」とは違った方向に進むことになる。 |
9.3日、東京地本大会乱闘で、社青同解放派が組織敵に排除され、以降解放派は社会党とは別の組織となった。
9.4日、都学連(三派系)百五十名、原潜寄港阻止緊急抗議行動〔横須賀〕、正門前デモで二名逮捕。
9.5日、都学連(三派系)六十名、横須賀基地正門にデモ・三名逮捕、夜、社共統一集会〔臨海公園〕に合流、六百五十名で再度基地正門にデモ・六名逮捕。
9.7日、原潜横須賀寄港抗議闘争。ベトナム戦争反対・総評ゼネスト支持中央集会に3万名。民青同系五百名、三派系千二百名参加、新三派系1200名が基地ゲート前でジグザグデモ。この頃各地の大学で抗議闘争発生。
9.14日、社学同統一再建実行委主催・全都学生討論集会〔明大〕に三百五十名参加、社学同の統一・十二月全学連再建を決議。
9.22日、新三派系全学連再建決議。全学連再建実行委主催・ベトナム反戦・小選挙区制粉砕全都総決起集会〔清水谷公園〕に七百名結集、全学連再建に反対する草マル派と衝突、機動隊介入し兇器準備集合罪で十数名逮捕。
9月、成田空港反対同盟の初総決起集会が三里塚公園で開かれ、農民千五百名が参加した。老人行動隊も組織された。
10.2日、成田空港反対同盟-三里塚.芝山連合新東京国際空港反対同盟結成後初の総決起集会。
10.7-8日、全学連(革マル系)全国自治会代表者会議〔早大〕、十月闘争方針を決定、二日目、百五十名で明大構内デモ・三派全学連再建を弾劾。
10.7-8日、全学連(民青同系)全国自治会代表者会議〔日本橋公会堂〕、大学の危機突破等を討議。
10.8-9日、全学連(三派系)再建準備会結成大会〔明大〕、十二月再建大会結集のアピール採択、準備会役員(委員長・斎藤克彦)を選出。
10.14日、ベトナム反戦社共統一行動、中央集会〔明治公園〕 に全学連(革マル系)四百名、都学連(三派系)九百名、ベトナム反戦学生共闘委(構改系)二百五十名、全学連(民青同系)三千名が参加。
10.19日、ベトナム反戦直接行動委(アナキスト系)、武器の生産中止を要求し田無の日特金属工業に突入、三名逮捕。
10.20日、新三派系が全学連再建準備会を56自治会で開き、12月再建方針を確立。全学連(三派系)再建準備会主催・ベトナム反戦・総評統一スト支援総決起中央集会〔日比谷公園〕に二千五百名結集、米大使館に向かうも機動隊と衝突、銀座デモで十七名逮捕、全学連(革マル系)五百名、日比谷野音に結集、清水谷公園までデモ、全学連(民青同系)三千名、芝公園で集会・デモ。
10.21日、ベ トナム戦争阻止・総評・中立労連第三次統一行動に全学連再建準備会1600名参加。
10.21日、全学連(革マル系)三百五十名、国労支援で大宮操車場構内集会・デモで三名逮捕。
10.21日、総評主催の中央決起集会〔日比谷野音〕に三派系千名・構改系三百五十名結集、米大使館デモ・坐り込みで六名逮捕、京都府学連(三派系)千二百名、集会・デモで九名逮捕、大阪府学連(反日共系)千名、集会・デモ。
10.24日、紀元節復活公聴会阻止闘争、全学連、東京・大阪・広島・札幌で紀元節復活公聴会阻止闘争。広島大生ら三百名、会場〔広島婦人会館〕にデモ、一部会場内突入で四名逮捕、大阪府学連六十名、会場〔府庁〕内デモ・坐り込みで一名逮捕。
11月、明大にも学費闘争が発生した。
11.4日、米国務次官バンディ来日反対でベトナム反戦共闘委(構改系)二十名、米大使館に抗議行動。
11.9日、全学連再建準備会(三派系)主催・ベトナム反戦集会〔清水谷公園〕に三百名結集、全学連(革マル系)百五十名合流、米大使館に抗議デモ、山王下で機動隊と衝突し六名逮捕、全関西決起集会〔神戸〕に六百名結集し米領事館デモ・三名逮捕。
11.12日、「社革新」と「日本の声」 派が合同し、「共産主義労働者党(共労党)」結成。議長に内藤知周、書記長にいいだもも氏が選出される。党内には、多様な考えが共存するユニークな「前衛党」であったが、構造改革路線を支持する者が多数であったため、外部からは「構造改革路線の党」と目されていた。
11.18日、ベトナム反戦共闘委(構改系)七十名、輸送船建造契約破棄を要求し、三菱重工業ビル正門前で抗議行動、機動隊と衝突し三名逮捕。
| 【明大.中大闘争】 |
|
11.18日、全明大臨時学生大会が開かれ、賛成271.反対138.保留38.棄権1で先制的ストライキに突入した。
11.23日、約9000名の学生で和泉校舎封鎖、11.28日5000名で生田校舎封鎖、1 1.30日、駿河台校舎を封鎖し、明大全学闘争委員会が学費値上げ阻止の大衆団交を開いている。4000名結集。この闘争は越年することになった。
12.9日、中大自治会、学費値上げ反対、学生会館の学生管理・処分撤回を要求して全学スト突入。社学同の指導によって最終的に大学側に「学生の自主管理」を認めさせ、処分の白紙撤回を勝ち取るという学生側が勝利を飾った。
その他にも関西学院大や西南学院大では学部新設反対の闘争が起こり、また各医大ではインターン制反対闘争が続いており、東京医歯大はストに突入といった状況を現出しつつあった。
|
11.19日、東学館館生大会、地裁の強制立退き仮処分執行にバリケード構築で阻止を決議(20日機動隊導入、支援学生とともに三百名で枚動隊と衝突・一名逮捕、明大学館で抗議集会の後、奪還デモ・二名逮捕)。
11.23日、反戦高協主催・ベトナム反戦・能研テスト反対全都高校生集会〔日本橋公会堂〕 に高校生五百名参加、全国四百万高校生へのアピール等採択。
11.24日、東学館生・早大生ら三百名、東学館強制執行に抗議して学徒援護会にデモ、新東学館に突入し三名逮捕。
11.25日、反戦青年委主催・全都反戦決起集会〔両国公会堂〕に反日共系各派二千名参加、錦糸町までデモ。
12.2日、全学連(三派系)再建準備会主催・ベトナム反戦全都決起集会〔清水谷公園〕に八百名結集、米大使館にデモ・三名逮捕。
12.9日、全学連(三派系)再建準備会・東学館自治会共催・教育学園闘争勝利全関東学生総決起集会〔中大〕に千五百名結集、文部省デモで四名逮捕。
12.9日、中大自治会、学費値上げ反対、学生会館の学生管理・処分撤回を要求して全学スト突入。社学同の指導によって最終的に大学側に「学生の自主管理」を認めさせ、処分の白紙撤回を勝ち取るという学生側が勝利を飾った。その他にも関西学院大や西南学院大では学部新設反対の闘争が起こり、また各医大ではインターン制反対闘争が続いており、東京医歯大はストに突入といった状況を現出しつつあった。
| 【全学連(三派)再建大会開催】 |
|
12.17日、既に三派都学連を結成させていた新三派連合(社青同解放派・
社学同・中核派)は、明治大学で全学連再建大会を開き、この頃ML派なども合流させた上で三派系全学連を結成
した。これで三つ目の全学連の誕生となった。35大学.71自治会・178代議員他1800名。この時、党派はそれぞれの色のヘルメットを着用した。これが学生運動でヘルメットが着用された最初となった。
この時点での各党派と掌握自治会数、活動家数、動員力は次の通り。
| 党派 |
掌握自治会 |
活動家数 |
動員力 |
| 中核派 |
36 |
2.000 |
6.500 |
| 革マル派 |
30 |
1.800 |
3.500 |
| 社学同 |
41 |
1.500 |
4.200 |
| ML系 |
4 |
400 |
1.300 |
| 社青同解放派 |
19 |
900 |
2.800 |
| 第4インター系 |
6 |
300 |
800 |
| フロント(構改派) |
38 |
1.000 |
13.600 |
この「全学連再建大会」は結成されたものの呉越同舟的な寄り合い所帯の諸問題をはらんでいた。まず、再建大会を第何回大会として位置付けるかをめぐって対立した。社学同と社青同はマル学同が独占した17回大会以後を否認した。マル学同中核派は20回大会以降を否認した。何時の時点で破産したかの認識が異なっていたからであった。これにより明示できなかった。なお、60年安保闘争の総括が蒸し返され見解が一致しなかった。こうした対立を乗り越えて、総括を中核派の秋山勝行が、状勢分析を社青同の高橋幸吉が、行動方針を社学同の斎藤克彦という分担制で妥協しつつ何とか「三派系全学連」の結成に漕ぎ着けるという多難な出航となった。
人事には各派のバランスが図られ、委員長にはブントの斉藤克彦氏、書記長には中核派の秋山勝行氏、副委員長社青同解放派の高橋、社学同の蒲池氏が選出された。中央執行委員数も各派のバランスを配慮していた。社学同は9名で、明大の斉藤克彦、中沢満正、同志社大の蒲池祐治、藤本敏夫、松本弘、秋吉治男(大分大)、佐竹修(立正大)、滝本文造(和歌山大)、山下浩志(医学連)。中核派は8名で、秋山勝行(横浜国大)、広島大の青木忠、石田敏雄、大熊寿年(西南大)、吉羽忠(東工大)、向山和光(山梨大)、山口紘一(法大)、橋本利昭(京大)。社青同解放派は3名で、早大の高橋幸吉、北村行夫、東野信(学芸大)。翌
67.2.19日、斉藤氏が失脚し以降中核派の秋山勝行氏が委員長に就任する。
この時の議案書は次のように宣言していた。
| 「全学連とは、結成されてよ り今日まで、どのような紆余曲折があれ、それは日本の闘う学生・人民の砦であった。日本労働者階級、全ての人民の闘いに全学連の旗が立たなかったことはない」、「50年のレッド・パージ阻止闘争を見よ! 56年の砂川を! 60 年の安保を! 全学連の闘いは、常に、日本労働者階級と共にあり、その先頭に立った」、「我々再建全学連は、その輝かしい闘いの歴史に恥じず、今まで以上にその闘いの方向に向かって、怒濤の如く驀進して行くだろう」(新左翼20年史67P)。 |
こうして、この時期全学連は、革マル派、民青同、新三派系の三つの全学連を誕生させることとなった。そのうち三派系全学連が最も行動的な全学連として台頭していくことになり、この過程で中核派の主導権掌握がなされていくことになった。この頃よりベトナム戦争が本格化していき、これに歩調を合わすかの如くベトナム反戦闘争に向かうことになった。
|
| 確か三派全学連の結成準備会か結成大会、それぞれの党派の代表が招待されてアジり、ブントは水沢なんだかさんという人で宙だけを睨んで絶叫、解放派は佐々木慶明(けいめい)さんという頭の中は立派だがいざとなると腰が据わらぬ御仁、中核派は本多延嘉さんが気張らずソフトな印象で演説をした。 |
12.17-19日、全学連(革マル系)第四十五回中央委〔早大〕、中大・明大闘争支援、三派全学連結成弾劾等を決議。
12.18日、ベトナム反戦共闘百名、三菱重工の米ロッキード社との兵器買付け契約に抗議し本社前で集会・デモ、機動隊の実力排除で四名逮捕。
1966年から70年にかけてGNP実質成長率が年平均11.5%と推移し、「いざなぎ景気」と呼ばれる超大型景気をもたらした。新三種の神器としてカラーテレビ、カー、クーラーという言葉が登場した。
これより後は、「第7期その3、ベトナム反戦闘争と学生運動の激化」に記す。
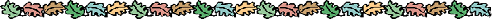



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)