| ��V�����̂P |
�P�X�U�T�N |
�S�w�A�^���j��V�����̂P |
| �ו��A�A����N�ψ��������� |

�@�X�V���^�Q�O�Q�Q�i�����R�P�D�T�D�P�h�a����/�h�a�S�j�N�D�S�D�V��
�@������O�́A�u��U�����̂S�A�V�O�h�A�������A���n�S�w�A�̒a���v�ɋL���B
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
�@��V���́A�P�X�U�T�N����n�܂����B���ۓ����̎��̐V�����͂U�S�N�ő��Ƃ��A�قڢ����h�����ɂȂ����̂����̂U�T�N����ł���B���̊��̓����́A���͂�O�����ɕ��������w���^���̓���@�^���ŏI�I�ɔj�Y�����A�w���^�����V���ȏo�������Ă������Ƃm�ɂ��������ƂɔF�߂���B�V���ɐV�O�h�A�����a���������Ƃ��S�w�A�^���̓]��_�ƂȂ����B�А�����h�Ɣ���N�ψ���E�x���A���a�������̂����̎����ł���B
�@�U�T�N�������̌c����w�̊w��l�グ���Γ����͂��̌�ɑ���������w�n�̓��해���̃n�V���ƂȂ����B���̍����碃}�X�v����w�̏���裂����サ�n�߁A�w���^���͖��o���̓����ɗ����������Ă������ƂɂȂ����B�Ȃ��A�Q���ɃA�����J�̃x�g�i�����勤�a���ɑ��锚�����J�n����A�����锽�퓬���Ɠ��؉�k�j�~�����Ƃ��������ۑ肪�A���ۓ�����̒�����Ă����w���^����Ԃ����Ă������ƂɂȂ����B
�@���̍����ɓ}�h�I�ȉ^���\�͂��l�����Ă����̂��v�}���E�����E�Њw���E�А��E���j�h�̌ܔh�����ł���A�����̃Z�N�g���v���v���̗��_�Ɠ������j�����������Ĉȍ~�̉^����g�D���Ă������ƂɂȂ����B���ł��A��҂̐V�O�h�n������N�ψ��� �Ƃ̓��ꓬ�����l�����䓪�������Ă������ƂɂȂ�A���̔{�����鐨���� �U�U�N���V�O�h�A���ɂ��S�w�A��a���������B�������Ď��̑S�w�A���O�n���m������邱�ƂɂȂ�A���ꂼ�ꂪ�������w���^����S���Ă����Ƃ����w���^���̓]��_�ɓ��B����ɓ������B
�@���̍��V���ɁA�}�̒������Y�}�Ƃ̋T��ɔ����ёv�z�̎��H�������咣����e�����n�̓������h�n�O���[�v���o�ꂷ�邱�ƂɂȂ�A�w���^�����ɂ��e����^���Ă������ƂɂȂ����B���̊ԃx�g�i���푈���G�X�J���[�g���Ă�������Ő��E�I�ɔ��퓬���̋C�^�����܂�A���̉e����������Ă킪���̊w���^������w���M�����Ă������ƂƂȂ����B |
|
�@���̂U�T�N���_���A�����������ʂ��A�����čs�Ȃ��Ă������ƂɂȂ�B
�����ǐՂ���Ύ����𑝂₷����ƂȂ�̂ŃG�|�b�N�I�Ȏ����o�ߏ��Ɍ��Ă������Ƃɂ���B�Ȃ����̔N�ȍ~�́A�w�������̗���y�ю�����s�����D�̓����Ƃ��̊֘A�A�}�h�̌`�����ꂭ����ɂ��A���������̗�����敪���Č��������������₷���̂œ\���Ƃ���B
|
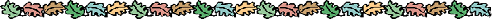
| �y�P�X�U�T�i���a�S�O�j�N�̓����z |
| �@���m�点 |
| �@�����̐����ɂ��Ắu��㐭���j�����v�́u�P�X�U�T�N�ʊ��v�ɋL���B�{�e�ł́A�����̊w���^���֘A�̓������L���B���ʂɍl�@�����������ɂ��Ă͕ʓr�l�@����B |
| �i������s���̑��D�̓����Ƃ��̊֘A�j |
| �@���̍��̊e�h�S�w�A�ƎP��������͎��̂悤�ɂȂ��Ă����B�v�}���h�S�w�A�͎P���̎�����������������Ă���B��̎O�h�n�S�w�A(�����s�w�A�Č�������A���s�{��w�A�A��B�w�A�|���j�h�D�Њw���D�А�)���L�͎���̎�����𑫊|����ɑٓ��������n�߂Ă����B�����n�S�w�A���ꕔ�̍�����w�ƒn����w�𒆐S�ɑg�D�����������B���̔N�͋���D����D����ȂǂŖ��n���傫���L�тĂ������ƂɂȂ����B |
�@�P�D�X�|�P�O���A�S�w�A�i�����n�j������c�A�@�֎��u�c���Ɗw��̂��߂Ɂv�����E����S���w��������c�̎O���J�Ó�������i30���u�c�w�v������ꍆ�j�B
�@�P�D�P�P�|�P�Q���A�S�w�A�i�v�}���n�j��O�\����ρk�����l�B
�@�P�D�Q�W���A�s�w�A�Č������ρE�����n�]�w���E�А����ÁE���؉�k���ӑS�s�J���Ҋw�������N�W��k����J�쉹�l�A�w���ܕS���Q�����Ĕ��d�F���܂Ńf���B
�@�P�D�R�O���A�S�w�A�i�����n�j�̉����g�D�Ƃ��Ă̓s�w�A�����̂��ߓ����s�w���������A����c�����A�O�\�������\�Q���A�Z���������m�F�B
�@�P���A�c����w�Ŏ��Ɨ��l�グ���Γ������u�������B�ꋓ�ɂR�{�߂��w��l�グ���c���吶�𗧂��オ�点�邱�ƂɂȂ����B�P�D�R�O���A����̣�S�w�������X�g�˓��B�Q�D�T���I���������A���ꂪ�w����̐�삯�ƂȂ����B���̌o�߂ɂ͍����m���̢���݂̊w���ɑ���l�グ�ł͂Ȃ��B���O�B�ɂ͊W������Ƃ����_���ł̋����I�Ȍ�����������𑣂����悤�ł���B
�@�Q�D�P���A�s�w�A�Č������ρA����������ۊ�`�ɋً}�R�c�W��k����J�����l�B
�@�Q�D�Q���A�s�w�B�Č������ρA������`�ɋً}�R�c�W��k����J�쉹�l�A�ܕS�����W���O���ȂɌ��������Ƃ��ċ@�����ƏՓˁE�����ߕ߁A�����n�疼�A�����f���B
| �y��S�C���^�[��P���ψ���z |
|
�@�Q�D�R���A���h�i�v�������h�j�́A�Ő����ɂ͐疼�̃����o�[���ւ��Ă����O�����Љ��`�N�����������w�����Ă������c�h�iICP�j�ƂƂ��Ɋv�������ē��ꂵ�A��l�C���^�[���{�x�����������B
�@�Q�D�Q�W���A��S�C���^�[�����R�����A��P���ψ���J���ꂽ�B���c�́A���̂悤�ȋc�Ă��o�����B
�@�u���ɓ����A�Ē鍑��`�͖k�x�g�i���������J�n�����B�w���E�v���x�͎��̂悤�ɏ������B�w���u�Ԃ̐��E��̓����́A�哱�����ă\����A�����𒆐S�Ƃ���A���n�v���̑��Ɍ���I�Ɉڍs�����Ƃ����_�ɂ���Ɖ�X�͔��f����B����͌��I�Ȉ�u�ł���x�B�܂��ɂ��̂悤�ȏu�Ԃɂ����A�P��́A�ō��ɋٖ��ɒc�������A���͂Ȓ����w�����̎w�߂̂��ƂɈ�̂ƂȂ��ē�������v���I�O�q�}�̌����������A�͂���m��ʏd��ȈӋ`�����̂ł���B���̂��Ƃ�\���������䂦�ɁA��X�͘Z�O�N�H�ȗ��A�P��̋��͂ȓ��{�x���̌��݂��ꍏ�����������������ƁA�S���𒍂��ŗ����̂��B
�@��X�͓�\�����A�P��̓��{�x�������ɂ����Ƃ����B��X�͐h�����ĊԂɍ������̂��B��X�͊낤�����Ԃɍ������̂��B���n�܂���鐭���I�������ύt�̕��v���O�I��ւ̔��W�̒��ŁA�K�������S�̂̎哱�����������ׂ������Ƃ��āA�܂��Ɏ��Ԑꐡ�O�ɂ��ׂ荞�ނ��Ƃ��ł����̂��v�B |
|
�@�u��X�̍����I�ۑ�́A�����ɓ��{�̘J���ҊK�����Đ��{��@�W�����鐭���I�@�������{���邱�Ƃł���B��X�͂�������_�n��ɂ����āA���_�P�ʂɂ����āA�悤�₭�A�[���I�`�Ԃɂ����Ăł͂��邪�n�߂悤�Ƃ��Ă���B��X�͂������ƍ\���Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�]�_�ƓI�ɊO���璭�߁A���ӔC�ȁA�����I�Ș_�]�����Ė������Ă��邱�Ƃ͒f���ċ�����Ȃ��B��X�͂��܁A�܂��Ɏ��X���X�A�v���I�O�q�Ƃ��Ẳ��l���ꎩ�g�����Ă���v�B |
| �@�u�ČR���_�i���Ɍ��q�C��z�������Ƃ��������͌�̃��V���g���̌����i��ǂ̏œ_�̓_�i���Ɉڂ�Ƃ��錩���j�ƌ��т���Ȃ�A����ׂ������I�Ȏ��Ԃ����̈�A���̂����ɓW�J�����ł��낤�Ɖ�X�͔��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B |
| �@�u��X�͎��̐������̊K�������̌����̒��ŁA�Z�E��܂��͂邩�ɂ̂肱����悤�ȓG���͂Ƃ̖\�͓I�Փ˂��w�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�X���ł̏Փ˂ƁA�w���Y�_�ł̓����x�Ƃ͐������ُؖ@�I�ɓ��ꂳ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�w�J���ҊK���x���[�l�X�g�𐮑R�ƑłƂ��떘���n���A������̂��ɏ\���ɏ������ꂽ���͓������W�J�����A�Ƃ����悤�Ȑ}����`��f�łƂ��č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�J���҂͋t�ɊX���Œ��ڂɍ��ƌ��͂ƑΌ����铬����ʂ��āA��Ƃ����������ʎ��{�ւ̑����݂��������K���ӎ��֔��B�����炻�ꂪ���ɂ͊�Ƃ������������X���[�K���̂��߂̃X�g���C�L�̈ӎ��𐬏n������̂ł���v�B |
| �@�u��X�̓x�g�i���N�����Γ����ɗ��B�A�����J��g�قւ̍R�c�s�����s�X��֓]�������˂Ȃ�Ȃ��B�����čX�ɕČR��n�ɑ�����͍s���̃C�j�V�A���Ƃ�˂Ȃ�Ȃ��v�B |
�@�ꒆ�ϋc�ẮA�̑�����Ȃ������B���k�Ɗ�������ɔ����A�����́A���i�q���ӂ��߂āA�c�Ă̗������{�I�ɂ͎x���������i�����̋��i�q�́A�X���s���ƃX�g���C�L�̊W�ɂ��Ă̑��c�̕��j�ɂ������Ă����ۗ������j�̑��ɕt�����A���j�Ƃ��Ă͂��̓��e�Ŋ֓������H�ɂ������Ƃɓ��ӂ��邱�ƂőË������������B
�@�ꒆ�Ϗ��ẮA������ɗ\�肳��Ă����O�����ł̊�n�����ɂ��āA�����̋@����悤�Ƃ���˂炢���A���ڂɂ͂����Ă����B���̓����͌܌��\�����ɍs�Ȃ���͂��ɂȂ��Ă���A���{�̔��퓬���̐V�����n���\�\�ČR�Ɠ��{�̑�O�̒��ړI�Փ˂��Ђ炭�ړI�ŁA�����n�ɂނ��Čv�悳��Ă����̂ł���B�܂肱�̋c�ẮA�O�����А��^���̐����I���_���Ӗ����Ă����B�Z�O�N�ȍ~�̐����I�ˏo�̍ō��̒n�_���A�܁E�ꔪ�̔������f���ł���A���̗��_�I���Â����ꒆ�Ϗ��Ăł������B������h�b�o�O���[�v�́A�@����ɂ͂�������Ă͂��Ȃ������B���������̓����̐������e�R�ɁA�����S�̂c�H���Ŋl�����Ă������Ƃ���ӗ~���c�Ă͐錾���Ă����̂ł���B�����ɂނ����āA�O�����А��̓��O�ɂ����鐭���I�ْ��́A���債�Ă������B�x�@���́A�Ж������A���������̘_���A�����ĐV���ɁA�А������n�{�𒆐S�̕���Ƃ���A�Љ��`����h�Ƃ̕��h�������͂��܂��Ă����B
|
| �y�A�����J���{�i�I�Ȗk�����J�n����z |
| �@�Q�D�V���A��x�g�i�����������A��x�g�i���u���[�N�̕ČR��n���U���A�ĕ��V�������S�A���������������B�A�����J�͕�ɏ��o���A�ȍ~�k�x�g�i�������i�k���j�����퉻�����B�ŏ��A��x�g�i�����{�R�̌ږ�c�Ƃ��āA�x�g�R���ɂ�������퓬��W�J���Ă������A�k�x�g�i���ɂ������Ē��ړI�ȍU�����͂��߂��B�A�����J�͓�x�g�i���ɒn��R�h���Đ푈���g�傳���Ă����B |
�@�Q�D�P�O���A�Љ�}�E���]�n�̌�����`�j�~�����W��k����J�쉹�l�ɎO�h�A���ܕS�����W�A�̂��f���ŋ@�����ƏՓˁE�O���ߕ߁A�L�y���w�ō��荞�݁B
�@�Q�D�P�T���A�Q�D�P�V�Ŗ��K�ؑj�~�S�s���N�W��k�@����l�A�}����h�ܕS�����W�i16�����勳�{�ɔ��荞�݁j�B
�@�Q�D�P�V���A�s�w�A�Č�������𒆐S�Ƃ���w�����Ŗ��K�ؑj�~�H�c���n���͓����ɂU�O�O���Q���B���勳�{�E����ɔ��荞�O�h�E�v�}���n���S�����������H�c�X���ŋ@�����ƏՓˁA�R�X���ߕ߁E�S���\�������B
�@�Q�D�Q�S���A��㋤�A���w���Ƃ̓���\�B
�@�Q�D�Q�W���A��������S�����k���c�J�斯��فl�B
�@���Y���}����h�EML�h�E�����Y���E�v�����S���ρE���D�Ќ��̌ܒc�̂œ��؉�k���Γ������c����B
�@���̏t�̋��哯�w�����I���Ŗ����n�����s�������������B �����n�́A�R���i�K�łW�Q��w�P�V�S����������������ƕ���Ă���B
�@�R�D�Q�W���A�V�O�h�i���j�h�E�Њw������h�E�l�k�h�E�А��j���S�w�A�����Ɍ����đS���������\�҉�c�J�ÁB
�@�R�D�T���A���؉�k���Γ������c���ÁE���؉�k���ӘJ���ҁE�w�����N�W��k���J�ω�فl�A�}����h�n�ܕS���Q���B
�@�R�D�T���A���w���S�����J�ÁA���w�Ƃ��Ă̊w���^���̎w���I���j�������Ǝ��F�A�g�D�������j��������B�@
| �y���_�����E�z |
�@�R�D�U���A�Ŗ��K�ؑj�~�H�c�����ŁA�@�����ɂ��@�d�����ӂ���ē��@���A�މ@��P�O���ځA���j�h�̉��l�s���吶�E���_�������̓����E�����i���N�Q�P�U�����j�B�s���R���Z2�N�̍��A�����q�q�̎��ɉe�������ۓ����ɎQ������B���l�s����w��͊v�����̊����ƂƂ��Ċ����ɓ����ɉ����B���̌�̊v�����̕���̍ہA���͒��j�h�i�P�X�U�R�D�V���A�}���N�X��`�w���������j�h�����j�A���吶�̗��l�͊v�}���h�Ɉڍs���g�D�̑Η����������邱�ƂɂȂ����B
�@�P�X�U�T�D�Q�D�P�V���A�Ŗ��x�O�Y�O���̖K�ؑj�~�H�c�����̍ۂɌx�����Ɍx�_�ʼn����A�@�d�����ӂ�����@���邱�ƂɂȂ�B�މ@��A�v���ʂ��͂邩�ɒ�����u���o�����i������j�p���J�[�l�[�V������������߂Ď����Ŏ��E�����B�P�X�U�T�D�P�O���A���㊧�s���ꂽ���̈�e�W�u�t�̕�W�v�i���Y�t�H�Ёj�̓����O�Z���[�ƂȂ����B����Ƃ̂������ւ��i1948�`2010�j�̃y���l�[���́A���̖�����ؗp�����Ƃ����B |
�@�R�D�V���A�A�����J���n�㕔���𓊓����A��x�g�i���S�y�ŕČR��̖̂{�i�I�Ȑ퓬���J�n�����B�ȍ~�A�������͂��}�����A��N��ɂ͂T�O���l���邱�ƂɂȂ����B
| �y�l�k�h�̈ꕔ�ƓƗ��h�̋����ɂ��Њw������h�����z |
| �@�R�D�P�R���A�Њw����Z��s���J����A�U�S�N�Ƀ}����h�A�l�k�h�A�Ɨ��h�A���h�ɂS�������Ă������A�����Њw�����A�l�k�h�̈ꕔ�ƓƗ��h�̋����ɂ��Њw������h����������B����́A���̌�J���҃O���[�v�������u���g�̓��ꐄ�i�t���N���`������B����h�ɎQ�����Ȃ������l�k�h�̈ꕔ�͖ё�`�ւ̌X��[�߂Ă����A�U�W�N�ɂl�k�����i�w���������j����������B |
�@�R�D�P�V�|�P�W���A�А���P��w�Ε����E�w���ǒ�������c�A�����Η����R���B
�@�R�D�P�X���A��Q��S���w��������c���J���ꂽ�B
�@�R�D�Q�U���A�s�w�A�Č������ρA���؉�k���ӂŕđ�g�فE�O���ȂɍR�c�f���B
�@�R�D�Q�U���A�}����h�A�Њw���S���ό����i�ψ����E�{�c�j��j�B
�@�R�D�Q�U���A�x�g�i���N�����E�����j�~�E�t�������S���N�w�l�w������s���A�����W��k����J�쉹�l�ɖ����E�S���A�疼�Q���A���d�F���܂Ńf���B
�@�R�D�Q�W���A���s�w���ρE���w���ςƖ��w���S���ςŒP��w�����������̂��߂̑S����\�҉�c�J�Ák���l�A���a�����E���Ɛ薯���`���߂����P��w���������������c�B
�@�R�D�R�O���A�s�w�A�Č����b�ρE���s�{�w�B��ÁE���؉�k���ӁE�x�g�i���N�����ΑS�������N�W��k�@����l�A�\���h�������������n�e�h�Q���A���j�E�}����h�͎����s�w�A�E�S�w�A�ꋓ�Č����咣�A�v�}���h���ŕ����A���E�x�g�i���E�����ŋ��������c�B
| �y�А�����h�����������z |
�@�R�D�R�O���A�Љ�}�̐N�g�D�ł���u�Љ��`�N�����v�̐퓬�I���q���h���А�����h���������Ă���B���̍��А��w���Nj��c��́A ����E���哙�𒆐S�ɑg�D���g�債�Ă������Œ���������h�ƑΗ����n�߁A�������������R���̌��ʓ��ؓ����̌o�߂ŋ}�i��`�^�������h�����A�А�����h�����������Ƃ����o�߂ƂȂ����B�А�����h�́A���̌�U�V�D�P�O���A�����c�̂Ƃ��Ċv���I�J���ҋ���i�v�J���j���������āA���N�P�Q���A�P���̊w���g�D�Ƃ��Ĕ���w�]�����邱�ƂɂȂ�B�i�А��w���Ǔ����h�Ƃ��ĉ���h�����i4��10���@�֎��u����v�n���j�j
�@���Ƃ��ƎА��́A���{�Љ�}���U�O�N���ۓ�����ɁA�w���p���[�ɖڂ�t���ē}�̎�Ԃ���͂����đn�݂��ꂽ���̂ł��邪�A�����퓬�I�ȉߌ��w�����ǂ�ǂ�������Ă��āA�А������ʼn���h�����������Ƃ����̂��j���̂悤�ł���B����h�́A�А������Œ��X�Ɛ��͂�L�������A�����n�{��苒����܂łɎ���B�Ȃ��A��l�C���^�[�n�̉�����p�ʼn���h�𗣂ꂽ���������邪�A�u���g�n�ɔ䂵�Ắu�l���ܗ�v�͏��Ȃ��B�u�А�����h�v�́A���̌㐭���c�̂Ƃ��āu�v���I�J���ҋ���v�A�P���̊w���g�D�Ƃ��āu����w�]�v����������B |
�@�R���A�R�z����|�����ō��̂T�O�O���~�̕����������ē|�Y�����B
�@�S�D�R�|�S���A�S�w�A�i�v�}���h�n�j��l�\���ρk�����l�B
�@�S�D�V���A�s�w�A�Č������ς��B���؉�k���ӁE�x�g�i���N�����Ό��N�W��k�����J�����l�ɂQ�T�O���i�S�O�O���Ƃ�����j���W�A�f���ŕđ�g�قɌ��������Ƃ��ċ@�����ƏՓˁA�S���ߕ߁B
�@�S���A�A�����J�ŁA�x�g�i������̓P�ނ�v�����锽��^��������ɂȂ��B���̓��A���V���g���łP���l�̔���f�����s���A�u�x�g�i���������A�ČR�P�ށv������A�e�n�Ŕ���f�����g�債�Ă������B�x�g�i������ƕ���ŁA�l�퍷�ʂɔ������鍕�l�\�������������B
�@�S�D�P�R���A����o�ϑ�ŁA��L�͎҂̌��Y���ƒn���D��𗝗R�ɖ��������w��������w���ǂ̌�����ɔ��������w�����A�s�����w���Ζ������X�g�ɓ˓����Ă���B
�@�S�D�P�T���A�S�w�A�i�����n�j��ÁE�C���h�V�i�N�����E���؉�k���ӁE��w�̊떇�˔j�S������s���A�����W��k�Ō����l�ɐ疼�Q���A����J�����܂Ńf���B
�@�S�D�P�U���A�s�w�A�Č������ρA���؉�k���ӁE�x�g�i���N�����ΑS�������N�A�����W��k�Ō����l�ɐ疼���W�A�������O���荞�݂ŏ\�ߕ߁B
�@�S�D�P�W���A���{���a�ρE����������ÁE�x�g�i���N�����E���؉�k���ӓ���s���k����J�쉹�l�ɖ����n�O�疼�Q���B
�@�S�D�Q�Q���A�S�w�A�i�����n�j���X�g�E�����j�~�H�c�f���A��`�����r�[�łR�O�O�O������������X�g�D�A�ꣃf���B�@�����ɔr������B
| �y��x���A������z |
| �@���{���{�́A�A�����J�̃x�g�i���푈���x�����A�x�g�i���푈�̂��߂̍ݓ��ČR��n�̎g�p��F�߂Ă����B���ۓI�Ȕ���@�^�̂Ȃ��A�ő�̕⋋��n�ł�����{�ɂ����Ă��A��O�I�Ȕ���^�������R���܂����B |
|
�@�S�D�Q�S���A�x���A�i�x�g�i���ɕ��a���I�s�������c�̘A���A�P�O���Ƀx�g�i���ɕ��a���I�s���A���ɉ��́j�����̃f���s�i�B ���N�l�́A���c���A�ߌ��r��A�J�����A�@�c�P�q�A�����a�ȁE�c���_�ȂǁB�����ǒ��Ð�E�ꎁ�B�x�g�i���푈���A�������}��g�D�ɑ����Ȃ����}�h�s���ɂ�锽�핽�a�����g�D�u�ו��A�v�𗧂��グ�A�����J�����ŏW��J�Â��ꂽ�B���̍�����
�Z�N�g�̘g�ɂƂ���Ȃ���ʎs���Q���^�̔���^���������������Ă������ƂɂȂ����B�@
|
 �i���_�D���ρj�@�ו��A�^���̕]���ɂ��� �i���_�D���ρj�@�ו��A�^���̕]���ɂ��� |
|
�@���̃x���A�^���́A�������猩�ċM�d�ȃ��b�Z�[�W�M���Ă��� ���Ƃ�������B��́A�x���A�������ۑ���u�x�g�i���ɕ��a���I�v�Ɩ��m�ɂ������Ƃɂ��A���̌�̃x�g�i�����퓬���̋���Ȃ��˂��n�o�����锭�M���ƂȂ����Ƃ����v���p�K���_���ł���B��́A�u�Z�N�g�̘g�ɂƂ���Ȃ��v�Ƃ����^���_��n�o�������Ƃł���B
�@�������A���̎��_�ł́A�Z�N�g���Q���Z�N�g�����l�����������Ă����Ƃ����u�w���x�����v�̎����ł������̂ł��قǕ]������邱�ƂȂ��x���A���܂��Z�N�g�I�ɗ����グ���Ă������ƂɂȂ������A�Z�N�g�^�����u�w���x�̈�Y�v����������n�߂���ފ������͂��Ȃ荇���I�ȑ��ݗ͂������������̌����ł������Ǝv����B
�@�Ƃ͂����A�x�g�i���푈���I������Ƌ��Ƀx���A���I�����Ă������ƂɂȂ����̂��ɂ����Ǝv���B���ǂ�����̑��ʂł�������i�����L�́u��ʎs���Q���^�v�^���̌��E�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��낤�B����������Ȃ炻��ō�����ł����ǂ̗]�n�͑傢�ɂ���Ǝ��͍l���Ă���B
|
�@���������x���A�^���n�o�̍��A�Љ�}�E���]�n�̂���A���Y�}�n�̂�����܂��܂���̓��ؓ����𗍂߂�����s����g�D���n�߁A�u�U�O�N���ۓ����v�ȗ��̑�O�^���������o���Ă������ƂƂȂ����B�v�}���h�n�A�����n�A�V�O�h�n���ꂼ������g�݂����߂Ă������ƂɂȂ����B���ł��V�O�h�n�̓����͂����܂�A�펞�R�O�O�O���K�͂̍R�c�f�����l�����Ă������ƂɂȂ����B����܂Ő��N���S���K�͂Ő��ڂ��Ă������Ƃ��l����Ηl�ς��ƂȂ����B
�@�S�D�Q�U���A�Љ�}�E���]�n�̃x�g�i���N�����Γ���s���Ɍĉ����Ĕ������n�e�h�Q�疼�A����J�쉹�Ɍ��W�A�������O���荞�݁A��疼���J���҂ƂƂ��ɓ������O�Ş������Ɨ����A�Q�T���ߕ߁B
�@�S�D�Q�W���A�s�w�A�Č������ρA���؉�k���ӁE�x�g�i���N�����ΑS������s���A�����W��k����J�쉹�l�ɐ疼���W�A�����J�����܂Ńf���E�ߕ߁A�S�w�A�i�����n�j����s���A�����W��k�Ō����l�ɐ疼�Q���A�đ�g�ّO�Ŏl�E���f���w���҈ꖼ�ߕ߁B
|
�@�S���A���Њw���̉����F�玁������u���g�n�Њw���@�֎��E�Ԍ��Ɂu���������A�Љ�������|��O���w���^���_�v�\�B�u�u���u���g�v�^�ԌR�v���T�C�g�A�b�v���Ă���A�]�ڂ��Ă����B
���������A�Љ�������\��O���w���^���_
�@�i1�j���ݓ�̏W��J�Â���t�̑�O�l�̊���`�����悤�Ƃ��Ă���B
�@��͋��s�{�w�A�\�s�w�A�Č������ψ����Â̔��E��`�O�O���[�v�ɂ����ؓ�������ɂ����S�������ƏW��i�O�E�O���E�����ɂāj�ł���A���܈�͑S����w���������g���A����̏����ɂ�鋳����[�~�i�[���i�O�E��l�A��܁A��Z�j�ł���B��҂͈��N�ȗ��V�܂��Ă����w�����������W�A�l�̑S���I�A�т����悤�Ƃ�����̂ł���B
�@
�@���{���{��`�̑ΊO����ɑ��铬�����A�����ł̊w���̎Љ������ĂыN�������w���������A�@���Ȃ�������ł����ē��ꂵ�Ă䂭���͊����Ƃ̌����I�Ȗ��ɂȂ����B���������̗��������ǂ��炩�Ɉ�ʉ�����Ă����X���͏�̕��G�����̂��̂ɋN�����Ă���B�����̐V�������h�̓��ؓ����ɂ���_�˔j�S�ʓW�J�����ɗv���w�������x����F���̍���ɂ́A��N�S����̏������ɂ�����ꂽ�@���A���{���{��`�̉ߏ萶�Y�̐��n��
�l�E�ꎵ�ւ̔��������̗����̉����Ƃ��Ă̌��������̋���ȗ�����H�������E��ł̊�@�̔����Ɛ��������ւ̃i�_�����݁��K�������̍V�g�Ƃ������`�[�t�����݂���B����̂ɂ����A�ޓ��͏��w��������������̔C���Ƃ��Đݒ肷�邱�Ƃ͏o���Ă��A���̓����ɓƎ��I�Ȑ����������邱�ƂɎ��s���Ă���B�ɒ[�Ɍ�����Ȃ�Ίw���������̐؎̂āA�Ȃ����͂��̓����̐��������ւ̗��p�̈���o�Ă��Ȃ��̂ł���B
�@��������[�~���哱���鋤�\�t�����g�̏��N�́A�����܂ł��Ȃ��ޓ��̍��ƓƐ莑�{��`�_�\���Ƙ_����̊w���̍\�����v��hegemony�̊m�����s���Љ�̉e�������������Ƃ����l�����������Ă��邱�Ƃ͏O�ڂ̈�v����Ƃ���ł��邪�A���ꂪ�ɂ߂Č��݂̋ǖʁ\�\
�����������_�C�i�~�b�N�Ȕ��W����L���Ȃ����E���Ɗw�������̍V�g�\�ɏƉ����Ă��邪�̂ɔޓ��͊w��M
�̐V���Ȕ��W�̉���w�������Ɉꌳ�����悤�Ƃ��Ă���B�������̂��Ƃ́A����A�W�A�̊�@�����ɂ������ۓI�Ȕ��v���Ɠ��{���{��`�̂���ւ̋�������Ƃ��̊O�𐭍����ӂ̓����ɂ����{���{��`�̐S�����ł̖�����\�I���邱�Ƃ���s�p�I�Ȑ����ӎ��̌`�����l�O���N�g���邱�ƂɂȂ�B�X�Ɋw�������̌��E���͍���̐����ߒ��֑�O���Q�������߂邱�ƂɎ��s���A�w����`�ɓ]�����Ă��܂����낤�i���݂�������������Ȃ����j�B���������̂��Ƃ͋ɂ߂ďd�v�ł��邪�A���݂̊w�������͔ޓ��̐M����h�O�}���t���Ȃ����i�̂��̂ł���B���̂��Ƃɂ��Č���q�ׂ�B
�@���ݕĒ鍑��`�����Ƃ������ۓI���v���A���Q�̓����́A�C�M���X�A���{�Ȃǂ̌��\
�������v�������������Ē�ɂ���āA���x�����z���Ėk�׃g�i���̐N�����Ӑ}������̂ɂ�������B�X�ɓ��؉�k�͂��̗����ɑΏ�����Ē�A�p�����̑��}�̗v���Ƃ��ē��{�u���W���A�W�[��˂��������Ă���B���؉�k�̋}���Ȑi�W�͎Q�@�I�����}���Ȃ�������̃e���|�͕ς��Ȃ����낤�B
�@�������x��������̐��ݗ������C���t���A�����ĘJ���ҊK���̘J�������\�������\�����}���A�X�ɒ�����ƁA�_���̊�@�͋���ȎЉ�s���������N����
�A�Љ�������Ƃ������鐫�i��M���N������B
�@��X���������Ă��鏊�̏t����̐��������\�w�������Ƃ́A���ɑO�҂���L�̏ւ̑Ή��Ƃ��āA��҂���q�̎Љ�������̊O���I�\���Ƃ��ẮA"����"�ւ̑Ή��Ƃ��Č����Ă���B
�@�J���]�_�ƁA�����T�O�i�w����̊�x�O�����u�Ɛ�̍����x�z�Ɗv�V���́v�j�́A�u���܂̐��E�̂��܂̓��{�̒��ł́A�v�V�����w���ɂ�����l�B�͈���ł͍��ۏ�ɋ@�q�ɑΉ����ĊX���s����g�D����͗ʂ����Ɠ����ɁA�����ł͍��ƓƐ莑�{��`�̐����I�o�ϓI�����I�x�z�̑S����ɃX�L�Ԃ��������ʐ헪�z�u���s���Ď��v��𐋍s���闼�ʂ̔������K�v�ł���B�����Ēʏ�̏ꍇ�A���̓ʂ̓����ɂ͋@�B�I�Ɍ����ł��Ȃ��Ǝ��̗̈悪����A�����ɖژ_��̂ނ�������������Ɠ����ɁA���̂��Ǝ��g��"���܂̐��E"�Ƃ��܂̓��{�̓���I�c����݂点�A�����̑S�ʓW�J���\�ɂ���헪�I�������Ȃ킹��댯����ɕ��݂��邱�Ƃɏ\�����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂����̂��Ƃ͐��{��@���̐��̐�����@�ɔ��W������{�I�����������߂�K���Ƃ��Ȃ肤��̂ł���v�ƁA�ނ�"���ĎЉ��`�v��"�̐헪�ڕW�͂Ƃ������Ƃ��āA���݂��������������ƎЉ�������Ƃ̓��ꂵ���w���̓���Ə�̕��G�����s���w�E���Ă���B
�@��X�͓����̐V�����������̏��N�̔@�����݂̏�i��̓I�Ȗ��܂Ŋ܂߂āj��]������킯�ɂ͂����Ȃ��B�X�Ɍ����\�t�����g�A�V�������h�A�����Ă̊w��M
�̐����������ɋ��ʂ��Ă����邱�ƂƂ��āA��N����X���w�E���������K�������̉�̂ƍĕҁA���̂��Ƃ������N�����Ă��鏊�̓��{���{��`�̐��ڂƂ����ɐ��N���鏔�K���\���K�w�̑����̖��������O���ւ̖����̕ώ��ƐV���ȍ��x�ł��[�������̌`���ɑΉ����Ă̑�O���̎w�����̑n�o�ɑ��đS�����F���\���v�z�ł��邱�Ƃł���B
�@���̂��ƂɓK������Ƃ����M
�̎w�����́A���Y��`�ғ����\���ۑS�w�A�̗��r�����Ƃ���̉i�v�v���_���̂��̂̔ے��ʂ��Ă����l�������ׂ����̂ł���B
�@�u���m�̂悤�ɁA�����۔h���_�ɂ�锪���ϋ���H���͌����̊K�������̒��ŘJ�w��g�Ɛ�쐫���_����e�Ƃ���]���H���ւƓ]�������̂ł������B�����Ă��̉ߒ��͓����ɁA�w���t���N���i�v�v���_�̓k�ƂȂ�ߒ��ł������B���̂Ȃ���̒i�K�ɂ�����w��M
�͐퓬�I�X���s���Ƃ��ēW�J����A���J���ҊK����M
�����A���Y�����ぁ�������ɂ݂����āA�������ɑË����A��̒��グ�����{�̋��e����͈͂ł����Ƃ�Ƃ����o�ϓ����ƁA���̂悤�Ȍo�ϓ����̎コ��⊮������̂Ƃ��ĊX���I���������Ƃ��ēW�J����A�������ĘJ���҂Ɗw�����w�s���x
�Ƃ��ĕ����ɊX����ŋ�������Ƃ����X�^�C�������݂��Ă����B�����Ċw���́A���̘J���ҊK���̎コ�ɑ��āA�X���s����O�ꉻ�����邱�Ƃɂ���ė������������炵�A�����Č��͂ɓ������悤�Ƃ����̂ł������B���������̂悤�ȓ����������ɓO�ꉻ���Ă݂Ă��A�X���s���Ɏ~�����͐^�̘J���ҊK���̎p����������̂ł͂Ȃ��B�ɂ��S�炸�A���̂悤�ȊX����̓O�ꂵ�������͘J���ҊK���Ɍ��͂̎��Ԃ��I�ł���A�o�N�����AM
�̔����`�����邱�Ƃ��ł��A�X�ɐ��Y�_�ł̓����Ɋҗ�����\����L���Ă����B�u���h���߂����Ă������̂́A���ɂ��̂悤�Ȍ`��M
�̔��W�ł������B�܂�s���I���������̒��ł̍ō��h�i���u���}�i��`���W���R�o����`�j�̂փQ��A���I�Ƀv�����^���A�[�g�̂փQ���j�[�Ɉڍs�����悤�Ƃ����̂ł������B����͐��ɉi�v�v���_�ł������v�i�w��m�xNo.5�咣�u��O�̓]���_�Ɖ�X�̉ۑ�v�j�B���������ꓙ�̉i�v�v���^��M
�͌܁�
�N��̎s���I���������Ɛ퓬�I�g����`�̑S�ʊJ�ԂƂ��Ă̈��ہ\�O�r�����ł̔s�k�ł����ďI�����A�g����`��ʂ́A���u���W���A�W�[��ʂ́A�s����`��ʂ̔s�ނɘA�Ȃ����̂ł������B���̔s�ނ��_�@�ɂ��āA�܁�
�N�㒆���ȍ~�i�s���͂��߂����Y������ƍ������ƐE���x�z�̋����͐��n���A���{�ɂ��J���҂̕��f�Əc�f�I�c�[�I�ȐE��̖��[�܂ł̂����낵���ו������ꂽ���ꖖ�[�̐���ʎY���A��������Ɋ�ƒ����E��ƕ�d�W�c�������W�߁A�����őa�O���ꂽ��Q�́u�E��v���v�U�����āu�K���I����v�Ɍ����J�x��z�����ʂƂ��āA�u�����I���S�w�v�̍�דI�i�o���͂��铙�X���x�̍����V�^�e����̌n�����X�ƍ��o����Ă����B�X�ɐV�H�ꌚ�݂��n��Z���̗��Q�W�f���A�Â��n��Љ�𐡒f���A�u�c����v�n��n�݂��s�Ȃ��A���������{�̎s���Љ�ւ̒��ڂ̎x�z�́A���ڌٗp����J���҂����ł͂Ȃ��A�L�Ăȏ��K�w�̒��Ɍ��݂̗��Q�Ə����̐����v��ɃL���ׂ����x�z�̈�o�����B
�@���̂悤�ȘJ���ҊK���̏c�[�I���f�x�z�Ǝs���Љ�̎��{�̒��ڎx�z�̐i�s�́A���]�����̑g�D�I��̉��Ǝ��{�ւ̋�����Ƃ��Ă̑S�J���A�Љ�}�\�쌛���S���{�̋��Ɩ��Ё\������c�̈�̉��ݗ��Ƃ��A�i�v�v���^�̕�̂ł���S�w�A�\���]�\�����ւ̎s���I�u���b�N�̉�̂�]�V�Ȃ����ꂽ�B
�@�ꌩ���{�̌��łȎx�z�̐����m�����ꂽ���̔@���������A������x�z�̗l���̒�����A�J���ҊK���\���K�������K�w�̐V���Ȗ����̗ݐς������I�Ɍ`������A����̓C���t���A�J���������������A��ꕔ���̉ߏ萶�Y�Ƃ��Č��݉����A�X�ɒ�����ƁA�_���̊�@���ĂыN�����A��N�l�E�ꎵ�̌o�ϓ����ɓ��������������Љ�\�o�ϐ����������W�J����n�߂��B
�@��X�̉i�v�v���^��M
�̎~�g�Ƃ������ӎ��́A�u���h�c�}�̘J��M �ւ̉���Ƃ��������Ŗ͍�����A�����w��M
�̎w���̎��H���̒��ŒNj�����Ă����B
�@�s���I�u���b�N�̉�̂͒��ړI�Ɋw��M �̐��I�@�\�̑r���Ƃ��̗��Ԃ��Ƃ��Ă̊w��M
�̃_�C�i�~�b�N�Ȕ��W��a�O�����Ă����B
�@������S���I�\�S�Љ�IM ����n��I�\���f�IM
�ւ̒�؏̂ɑ�O�̐����ӎ������U������A�H�������Ă���Ԍ���˂��āA���{�̎x�z�̊�]�ƑΊO�����\�͋����ɑΉ����ׂ���w�̒��ڎx�z����ɂ��Ă̍U���͊w����O��̐����������Ă��Ă���B
�@�ɂ��S�炸�A�������؏�˂��j���Ă̈��N�ȗ��̂��₩��"�V�����g"�̍V�܂肪�m�F�����B
�@���\�����Ɍ�����M
�̈��̍V�g�́A���؏�̌����ɑΉ�������Ȃ�����̑ΊO����̋}���Ȑi�W�ɂ���A����͈��ۈȍ~��������������̑�O�����W������̂Ɉ����x�����������B
�@
�@���������ڂ��Ȃ���Ȃ�ʂ̂́A�����鐭�����������܂��S��O�̂��̂ɂȂ�炸�A�����Ƒ�O�Ƃ̊Ԃɕ��f�����݂��邱�Ƃł���B
�@�����Č��������Ŗ��炩�ɂȂ����@���A�ꁛ�E��l�S���������[�ւ�M
�Ƃ��đS���I�ɓW�J����Ȃ���A���͓����̋ǖʓ˓��̓˔j���Ƃ��Ă̈��E�����{�ꓬ�����_�@�ƂȂ�A���ꂪ��O����i�����i�K�ֈ����グ�A���킹�Č�����`�j�~�̌��n��������O�̎Q���𔗂���̂��A����͕����I�ȗ����ݏo�����ɂƂǂ܂�A�S�̂Ƃ��Ă͖��S����ᔻ�I�ł����������B��X�͔ᔻ�I�ł��������Ƃ����Ƃ���Ɏ��グ�ĉ��{�ꓬ����ᔻ����C�͂���ɂȂ����i���̂Ȃ���E�������͂��̋ǖʂɂ����Ēf���Ƃ��Đ��i����˂�M
�̓˔j���͗v������Ȃ���������j�A���͂�����ᔻ�I�ȕ����܂Ō�������ŁA���̂��Ƃ�ʂ��Ď��͑j�~��M
��W�J�����邾���́A��X�̎�̓I�W�]���ǂ��ɂ����݂��Ȃ��������ƁA������M �͈��A���A��O�Ək���Đ��Y����A�����A���Ɠ���ǂ����Ƃɑ�O��M
���牓�������Ă������B���̓����̉ߒ��Ŋm�F����˂Ȃ�Ȃ��͈̂�т���M
�ɘA�����Ɣ��W�����r�����A����ΐ�p�̘A���I�O�ꐫ�̒��Ō��͂ɓ��ǂ��Ă����Ƃ���̐��Y�͂͑S�̂Ƃ��ĕs�݂ł���A�����Ƃ͓����̊�ǂ����ɑ�O���番�����A�����̏W���I�e�������U���������Ă��������Ƃł���B
�@���s�ł͓����Ƒ��Ⴕ��O�I������@�\�̎����I�ȕێ��̏�ɓW�J���ꂽ���̂ɁA�����s�Ƃ����n�����������āAM
�̔��W��ǂ����ɑ�O�Ɗ����ƂƂ̕��������o���A�I�����܂ꂽ�B
�@�ő���̐�p�̉s�p�I�ȓW�J�ɂ���Ċw����O�����W�A���킹�ĘJ��M
�ւ̉e����^����Ƃ�����p�������i�v�v���^�̎w������M
�̋ǖʂɂ����ĕK�v�ɂ��S�炸�L������r�����Ă��邱�Ƃ��͂�����ƕ�����Ă���B���̂��Ƃ̗��ʂɂ́A�ܘ_���\�@�����ȍ~���߂ĎЉ�}�\���]���n�b�X�����J���ҊK���̗������`�����ꂽ�Ƃ͂����A���ۈȍ~�̘J���ҊK���̌��͂̎x�z�̋��ł���邱�Ƃ��w�E����˂Ȃ�Ȃ��B
�@�������̂��Ƃ��m�F�����Ƃ���ŁA��������̕����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B"��쐫���_��������邩�ۂ�"���̕s�тȘ_����f�����āA�����������ĉ�X���m�F���Ȃ���Ȃ�ʂ̂́A��쐫�̗L�����͑r���������̂́A���̐��I�\�͂͑r�����Ă��炸�����O��I�ɒNj����邱�ƁA�X�ɂ��̂��Ƃɂ����"��"�����ݏo���Ȃ������̌���ΊX���������x�����O�̌������̎x�����l������Ƃ���̌����I����ł���B
�@���̂��Ƃ͒P�ɋZ�p�I�Ή��ɂ���Đ蔲��������̂ł͂Ȃ��A��X��M
�̎w�������i�v�v���^��M
�̎~�g�Ƃ��Ă̎v�z�I����̊m���ɂ���B
�@�����̏������̏��N�ɂ͂��̂悤�ȔF���̌��@�Ƃ������炭�鐭���������������x�����O�̎x���̂Ȃ��P���ȉi�v�v���^�̂����"�ł�"�̕\���Ƃ��ẮA�P�ɊX�����������`���⏬���������؈�_�˔j�S�ʓW�J�����͑��Ӗ����������悹�Ă��邱�Ƃ�t�����Ă������B
�@�����đ����ł̐V�����g���\������M
�͊w����O�̊��ӂ��痧���̂ڂ��Ă���Ƃ���̊w���ł�M
�ł���B
�@�{�N�ꌎ�̓����ł̃o�X��l�グ���Γ����ɎQ�����������s���ꁛ���l�ɋy��"��������M"�A�����Čc����w�̂قƂ�ǑS��O���������Ƃ���̎��Ɨ������A�����ĐÑ�ł̎������ɂ��S�炸�ꌩ���ׂɂ������闾�̐����w�̐������S��肪�w������X�g���C�L�ɂ܂Ŕ��W������A�̎����́A���N�ȗ��̑S���I�ɕ��f����ēW�J���ꑱ���Ă����w���̎Љ���������V���ȋǖʂ��悵�n�߂��Ƃ������Ƃł���B
�@���ꓙ�ɋ��ʂȂ��Ƃ͑�O�I�Ȑ��i��тшُ�Ȑ����͂������Ă��鎖���ł���B
�@���̂悤�Ȋw����O�̈�A��M
�͐[���ɘJ���ҊK���̘J�������\�l�������\����cut�ɋy�Ԑ������Infla
�ɂ����D�̓�d�̐����ւ̈����̊O�����Ƃ��Ă̊w���̐����̊�@����Ղɒu�����̂̒��ڂ̌_�@�́A��w�̍H�ꉻ�Ƃ�������ׂ����玑�{�����͕��������E���犯���ƓƐ莑�{�̖����ɂ�鎑�{�̊w�⌤���̒��ڂ̗��p�Ƃ����ʂ��Ă̊w����O�̑̐������ƓK�ȘJ���͂̐��Y��ړI�Ƃ���Ɛ莑�{�{���玑�{�i�����͕��������j�̍H��̐E���x�z�ƒ����}���ɕC�G���鏊�̊w���̎��{�A���Ƃ̒��ڂ̏����Ǝ��D�̐���ɑ��Ă̊w���̕s���̗ݐς�����s������Ǝ��D����ɑ��Ĕ������Ă���̂ł���B
�@�]���Ă����铬���͍���\���I�ɍĐ��Y����A�Љ�I���i��L������̂ł���A����Έ��܁��N��̋����@�i�l�j����O�@�i�ܘZ�j�\
�Ε]�i���\���j�\
��ǖ@�i�Z��j�Ɍ�����A���K�������̍V�g�̒��ŏ�����������@�Ƌ����{�@�̗��O�ɕ\�������A��w���x�̈��̐i�����ƓƎ����ɑ��Ă̍��ƌ��J�̊ە����I�Ȃ锽���I��������ɑ��錛�@���O��Βu����M
�ł͂Ȃ��A���̂悤�Ȑ��i�̓����͌��\���N������n�܂�Z��N������S�ʉ�������w�̎��{�̒��ڎx�z�ƍ������\�E���x�z�Ƃ�������ׂ���w�̎x�z�̐��̕ω����N�������̂ł���A����Ύ��{�̐����I�U���ƌo�ϓI�U������̉����ēW�J����A����ւ̊w���̐����I�o�ϓI�Ή�����̉����đΉ����邪�̂ɁA�����ł̑Ό��͖��m�Ȏ��{�̑��݂��ӎ������Ă����̂ł���B���̂悤�ȓ����͐��ɎЉ�������Ƃ���������̂ł���B���̂悤�Ȏ��{�Ɗw���Ƃ̑Ή��W�̒��Ŋw���̈ӎ��͎��Ȃ̌��݁\�����ɘi���Ď��{��`�Љ�̂��̂̕]�����s�f�ɒ��ړI�ɖ₢��������B
���@�܁Z�N��̊w���̐��������A�o�ϓ����i�]�葶���Ȃ��������j�ւ̊ւ�荇���́A���{��`��O��I�Ȃ��̂Ƃ��ĔF�����A���̏�ɗ����Ď��{��`�̏����������̑��̂Ƃ��Ă̘J�����ɑ��A�u�����`�h�q�v������W�J�����B���̂��Ƃ͎��{��`�̕������ł̗]�T�Ǝs���Ƃ��Ă̐����s���������Ȃ�����S�̂Ƃ��ē������Ă������{��`�̐[���̒i�K�ł������B���J���҂̔���������ɓ����������g����`�I�J��M�̘g��u���Ă̌o�ϓ����\�s���Ƃ��Ă̐��������ł������B
�@����̂ɂ����J���ҊK���́A"��ƈӎ�"�Ɠ����������ӎ������݂��A���̈ӎ������z���邱�Ƃɂ���Ă������߂Ă��ꓙ�̎Љ�������͎����I�ȏ�����������邱�Ƃ��o����B���ꓙ�̓����̐��i�͘J���ҊK���̔��������\���グ�ɓ������Ɨގ����������A�J���ҊK���̏ꍇ���ꂪ��̖̂��`���̂ɍ������̃V���Ƃ��ĕЖʓI�Ɍo�ϓ����ɂ̂����Ă���A�K���W�̃u���W���A�I�����Ƃ��Ă̍��Ƃ̑����{�I���ꂩ��̏��K���̗}������ւ̓��������������ɑ����f����A�����グ�A�������ߒ�����̈ꌳ�I�ȓ����̔��W�Ƃ��Ă̐��������͑�O�I�����Ƃ��Ēזłɋ߂����w��M
�̏ꍇ�͂��܂��������hege�D�̋��͂��̂Ɏ��{�̒��ړI�Ȉ�̐��������������I�\�o�ϓI�U���ɑ��Ă�����������ē����͗ʂ�L���A�X�Ɋw�������o�ϓ����̓����I�Ȕ��鐫�𐭎������ɉ����锽�鐫�Ɠ��ꂵ�đ�O�ɔF�������邱�Ƃ��o����B
�@��������N���Ă���Ƃ���̉i�v�v���^�̎w�����́A�ے�̔ے�Ƃ��Ă̎~�g�̖��́A���ݓI�ɂ͂��ꓙ�̎Љ�������I�Ȋw�������Ɠ��ؑj�~�A�x�g�i���푈���̐��������Ƃ̓��ꂵ���w�����Ƒ�O�̒��ł̓��ݓI�ɓ��ꂳ�ꂽ����̐����ӎ��̌`�������A���̂��Ƃ́A��쐫���_�̗L�����̑r���̒��ł����I�Ȑ��������̓W�J�ߒ��ł�����̑�O�̒��ł̋��ƕ������������A�S�̂Ƃ��Ă̐����I�W��̉\�����J�����Ă���̂ł���B
�@�ܘ_�A���݂ɉ��āA���ꓙ���������ƎЉ�������������I�Ɍ������A������������Љ�������ցA�Љ���������琭�������ɔ��W�Z�����铙�Ɣn���������Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��B��������̑�O�̒��ł̐����I�փQ���j�[�̊m���͎Љ���������ɂ��Ă��A�������������̏ۂ��Ă���蓾���A���҂̓Ǝ��I�ȓO��I�W�J�Ɨ��҂ɑ��݂��锽�鐫�����҂̓Ǝ��I�O�ꐫ���ɂ��Ă͌`�����꓾�Ȃ��̂ł���
�@���̖��́A�{���I�Ɋv���I�V�g���ɉ�����O�����V��[�U�����������Ƃ���̌���v���́u���ǂƊv���v�̓��ꂵ���w�����̊m���̓��e���N���Ă���B
�@���Ă��̖��ɑ��Ă̓��ꂵ�������I�\���̎��݂ɂ��Ă͍Ō�ɏq�ׂ邱�Ƃɂ��āA���ꓙ�̐��������A�Љ�������̍���ɉ�����A���Ƃ��̓����I�Ȕ��鐫�̑��݂�����T�����邱�Ƃɂ���Ă݂Ă݂悤�B
�@(
2
�j��ɓ���O�ɓ����Ⓦ���̐V�������h�̓��؈�_�˔j�S�ʓW�J�����ɉ������]���̊�{�I�߂���t�����Ă������B
�@�u�m���ɓS�z�E���D�E�Ζ��E���@�E�Z�����g�E�d�@���قƂ�ǂ����镪��ʼnߏ萶�Y���������邵���Ȃ�A���낻�댸�Y�̐��ւ̐芷���������n�߂Ă���̂�������v�i�o�σZ�~�i�u�j�]�ɋ߂Â����{���{��`�v����́j���̎w�E����͎̂����ł���B����͑����̓��{���{��`�̍s�l�肪�A�������̂��Ƃ������Ă��ē����̔@���ߏ萶�Y���Q�_���璼���I�ɓW�J���u���{��`���E�̐��̕����Ɛ��ނ̐[���v�i�w�O�q�x3
�����j�Ɍ��_���鎖�Ԃł͂Ȃ��B�Ԍ`�Y�ƕ���ɂ݂���ݔ��ߏ�\�ɑ����̖��͎����㑶�݂��A�X�ɂ��Ƃ��Αϋv����ޕ���̌ܔ��N�Ȍ㓊�����O������𑱂��Ă������̂��Z�l�N�ɂ͋�E�ꁓ�ɂȂ��Ă���B���������ꓙ�͑����{����݂�Όi�C��^�Y�ƂƂ��Ă͎Ηz���������݂̏����̑Ώۂł����Ȃ��B
�@���{���ƓƐ莑�{��`�͂��̂Ȃ������I�ȘJ���ҊK���̕��f�I�c�[�I�x�z�Ƒ��]�����̑S�J�����������Ё\������c���琬���邱�Ƃɂ���ĉ������Ȃ��玟�̌i�C�哱�Y�Ƃ��J�����邱�Ƃɏ��o������B���{�����o�όv��̎傽��Ӑ}�͏d���w�H�ƕ���y�яZ��ݕ�����o�ϔ��W�̎哱����Ƃ��āA�̐������X�Ƃ��Đ��������߂��A����u�Љ�J���v�͂����������̃u���W���A�I���W�̐��Ǘ��_�ł���B�����o�όv��͒P�ɍ��x�����H���̌p���ɂ�钆���˔j�i�͐Β��j�����ł���̂ł͂Ȃ��ɁA���́u�Ђ��݁v�������Ƃ̎��ȐӔC�ɂ���ĉ����Ԃ��Ȃ���V�o�ϑ̐����˂炤�Ƃ���̂��̂ł���B���Ԏ��{�ɑ��ẮA���Y�ߏ�ƃV�F���[�����ɑ��āA���ł��A�Д����J�������ĂɁA���c�A���ƒc�̊g�[�A�s���@�\�̑�K�͉��ƂȂ��ŗ��q�⋋���x�̊m�������ɂȂ������I�Ɍ��ĂȂ������͂����Ă���B
�@�ȏ�ł����Ă��Ă��S�ʓI�ߏ萶�Y���ΊO�c���i�����{�A�o�j�A�Љ�I��@�̑S�ʉ���
���؈�_�˔j�S�ʓW�J�����̕]���̉߂��͖��炩�ł���B
�@��X�͏t�ȍ~�S�͂������ē��ؓ����Ɏ��g�ނ��A������Ƃ����ē����̏��N�̔@�����ؓ����ɂ���OM
�̔����I�W�J�����҂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��X�͂�����s�p�I�ړI�ӎ��I�ȓ�����W�J����ߒ��œ��ؓ����A�����������̐ςݏグ����A���{���{��`�̖c���Ɣ��v���̏�����̐i�s�Ə������̏W��_�Ƃ��Ă̑�O�����ۑj�~�̐����ӎ��̌`�����߂����ł��낤�B��X����N���w�E������̍���̓����_�Ƃ��āu���ې����o�Ϗ��������ɒ��ڔ��f���A�X�ɍ����̐��������\�o�ϓ������������Ĕ��W���鎞��ɓ��{���{��`���˓������v�Ƃ�����̔c���̍��ꐫ�͔ے肷�ׂ����Ȃ��B���������̂��Ƃ����݂̋ǖʂɉ��ċ@�B�I���ړI�ɓK�p���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�p�����ƕĒ邩��̓��؉�k���i�̗v���A�����̓��{�z�u����A�̓��{�u���W���A�W�[�̑ΊO����́A�[���ɉߏ萶�Y�\�ݔ����C�O�s��l���̗v���������Ȃ���A���ړI�ɂ͂׃g�i���̗�������Ƃ����ɓ����瓌��A�W�A�ɋy�Ԗ�����������̐V���ȗ����ɑ��Ă̍��ۃu���W���A�W�[�̔��v�������̋����H������ĂыN������Ă�����̂ł���B
�@�׃g�i���ł̃A�����J���x���ɂ����Ƃ���̔��v���A���R�̌�ނ͌��݂̏�ł́A������"�����|��"�I�Ȗ����������}���Ȋv�����̕�����SEATO
�����̊�@�����������߂邪�̂ɁA�׃g�i���푈���Ƃ����푈�́\�\���ݑ���N�����̗l����тт��邪�\�����I�Ȑ푈�̐��i���������̂ł���B���݂̋ǖʂɉ��ĉs���ΊO������Ղ��������Ă���v�������{���{��`�̓��I�������̒��ړI�S��I�����Ƃ��Ă̖c�����Ɠ���A�W�A����ɓ��ւ̔��v�����̈�̐��ɂ���̂ł͂Ȃ��A�ނ����҂ɒ��ړI�v����u���Ă���Ƃ������Ƃ͍���W�J�����ΊO������߂��鏔�����̐��i�����肷��B
�@��i���Ɏ���u�������ۓI�����ւ̓���̑Ή��ɑ��ď��K���\���K�w�͔��R�Ƃ����Љ�s���������Ȃ���������I�ӎ��ɂ܂ōV�܂��Ȃ��A�������ۏ��������֔��f����ꍇ�����x���f����Ւf����Ă���A���߂č�����ɓ��e����\�]���đ�O�̓��ݓI���W���������Ȃ�������ꂪ�e�Ղ�M������Ȃ����ƁA����̂ɋ}�i�����������I��O��c���Ă��S��O�������Ȃ��A�ɂ߂ċǓx�ȖړI�ӎ��I�����i��ʂɉ��Ĝ��ӓI�ȑ��ʂ����j�Ƃ��ēW�J���ꂴ��Ȃ��v���́A��i�鍑��`�̎s��ĕ҂̐V���Ȓi�K�ł̊�@�̓������̉��ł̓��{���ƓƐ莑�{��`�̖����̐��n�̒i�K�Ǝx�z�̗l���ɋN��������̂ł���B
�@���Z�l�N�x�̏�͌����̒��ɓW�J���ꂽ�B���E���{��`�̖����̐[���Ɛ����h���ۋ��Y��`�����̖����̌��������̒��S�ł������B���̓�ɂ�M
�͊e�X�Ǝ��ɓW�J����Ȃ�����A�����Ő[���֘A���Ă���B�������ۋ��Y��`M
�����̕���́A���ɓI�ɂ͂܂���������Ă��Ȃ����E�v���ɂ����̂ł���A���ɍ����ł͐��E���{��`�̊֘A�œW�J����Ă���B�����Ă��̐��E���{��`�́A���ܔ��N���R���i�K�ւ̓˓��Ƌ��ɁA���̎��{��M
���~�ς��Ă������������݉�������B���ےʉݐ��x�̊�@�ɂ��̖����͏W��Ă���B�h����@����n�܂�A�|���h��@�Ɏ��鍑�ےʉݐ��x�̊�@�́A���ǂ͐�㐢�E���{��`�̔��W�̌��_�ł���B
�@�A�����J�ɑ���EEC�����A���{�̗҉�A�����ł̐��E���{��`�̕s�ϓ����W�͗v��A���̐��Y�́������͔��W�ɂ��A�A�����J����̋��̗��o�A�h����@�����݉������B���ےʉ݂̕���Ƃ͉����B����̓u���b�N�o�ς��Ӗ����A���ۖf�Ղ̌��ϋ@�\�̔j����Ӗ�����B�N���I�ȐA���n����Ƃ��̏�ł̃u���b�N�o�ς��͂��ɐ��Y�̔��W���x���A�A���n�s��̑��D�������Ē鍑��`�푈�����̓����ł���B�����č��یo�ς͍L�搫�ɂ����i�A�����J�������āj�C���t���[�V������K�R�����������s������߂�����ɓ����B�K����̌����͒鍑��`�푈�ɑ��铬���ƂƂ��ɁA�v�������ɔ��W����B
�@�ȏ�̔@�����j�I�Ș_���������ےʉݐ��x�̕���ɑ��A�����̕���̔��W�i���Y�͂̔��W�j�Ƃ����킹�āA���ۃu���W���A�W�[�͏��i�����Ƌ��ɋ��͂����x�z�̎�i�Ƃ�����Ȃ��B���ۓI�ȍ��ƓƐ莑�{��`�̋@�\�A���ꂪIMF
�ɏW��A�ʉݐ��x�̊�@�������������Ƃ��Ă���B�ɂ��S�炸�|���h�~�ς�EEC�����ɂƂ�A�����ւ̃C�M���X�̋����͋����������Ƃ����ẮA���̋��͂́A���̖{���ɂ͂�����ɂɏ[�������̂ƂȂ炴��Ȃ��B���ےʉݐ��x�̊�@�́A�͂��������������������Ă���B
�@���̂悤�Ȑ��E���{��`�̋�ɂɖ����������̈��������́A�e���̍��ƓƐ莑�{��`�̊�{�I�����ɂȂ��Ă���B���������ł͂Ȃ������I�Ȗ����̌��݉��ɂ��K���I���˂���_�ɏW�邱�Ƃ����点�鍑���������Ƃ��Ă���B�ɂ��S�炸���E���{��`�̎ア�������I���ێ��x�̐Ԏ��y�уC���t���ɔY�ތ�i���ɂƂ��ẮA���̂悤�Ȗ����̈��������͕s�\�ł���B�����u���W���A�W�[�ɂ�閯�����Ƃ̎������e�ՂɈ��肳�ꂸ�����̒��ɂ����i�����́A�鍑��`�����Ԃ̎x�z�̈��͌̂Ɂu��k���v�Ƃ�����@�����E�I�Ȓ�ӂƂ��Ă̖�������A���E�I�ȊK�������̌����̒��ɂ���B�����Č��i�K�ɂ�����K�������́A���ꓙ��i�����ƍ��ۓƐ�̂̂Ȃ������I����̂����炷�����̏W���I�Ȕ����_�A�e�������ɂ������i�����ƂɌ��݉����Ă���B�A�����J�̍��l�̓����A����A�W�A�̓����A�t�����X�_���̓����A���{�̒�����ƁA�����͐ΒY�Y�ƘJ���҂̓����Ȃǂ�����O���ɂ���B
�@�ȏ�̔@�����E�I�Ȏ��{��`�̎ア�ɉ����閵���̌��݉��ƊK�������̔��W�͌��݂܂��܂��L�������B�Ⴆ�Γ��{�̗���Ƃ��Ă��A���݂̒�����Ƃ̓|�Y�A�_�Ɩ��̐[�����́A���łɎЉ�s���Ƃ��Ď�X�ɐ����ߒ��ɔ��f���Ă���i�����}�̌����Ȃǁj�B�����A��X�����݂̊K�������̒��������ʂ����_�́A�P�Ɉȏ�̔@���ア�ɂ݂̂���̂ł͂Ȃ��B����͊������R���i�K�ւ̎��{��`�̓˓��̂����炵���A���E�I�ȊK�������̍V�g�i�K�������o�ϓI��@�Ƃ͌������Ă��Ȃ������Ƃ���́A�����t�����X�̃A���W�F���A�����A���h�S�[�������A�C�^���A�̔��l�I�t�@�V�Y�������A�x���M�[�̃R���S���ƑS���I�[�l�X�g�A���{�̈��ۓ����Ȃǁj�ɕC�G����悤�Ȑ��E�I�ȐV���ȊK�������̍V�g�ɂ�������B
�@�����̐��E���{��`�����ʂ��Ċт������́A�N���[�s���O�E�C���t���[�V�����ƌĂ��A�Ȃ������I�ȃC���t�����^����J���Ґl���̈��������������ʂ��̂ɂȂ��Ă��邱�ƁA�������ۋ����ւ̑Ή��������炵�Ă���J�������ɂ�鈳���̑���A�X�ɕ����I�Ɍ��݉�������ߏ萶�Y�ł���B���̂悤�Ȋ�{�I�ȏ������Ƒ����ł̎ア�̖����Ƃ���������Ƃ����ƓƐ莑�{��`�̂Ȃ������I����͏d��ȍ���Ɋׂ邾�낤�B�����閵���ւƈ�����K���������V�g����Ƃ������Ƃ́A���ꂪ���ےʉݑ̐��ɒ������鎞�A�S���E�I�ɔg�y���閵���̌��݉��Ƃ����W�J����������̂ł���B
�@�Ȃ�������{�I�ȏ������Ǝア�Ƃ��Ă̌�i������M
�i��i���A�������Ƃ킸�j
�����������A���ےʉ݊�@�ɒ���������W�]�́A���݂̓��{�K�������ɉ��Ĕ@���Ȃ���e�Ƃ��ĔF������˂Ȃ�ʂ̂��B
�@�i3�j���ƓƐ莑�{��`�̊�{�����ƌ�i�����炭��ア�̖����Ƃ̌����̐[���́A���ےʉ݊�@�������������ۓI�ȊK�������̓W�]���J���\����L���Ă��邱�Ƃ��w�E�������A�ɂ��S�炸���݉�������ߏ萶�Y�����ꓙ�������ɑ��铬���́A�܂������I�ɂ��������Ă��Ă��Ȃ��B�ۂ���݂̂ł͂Ȃ��A�Ɛ�u���W���A�W�[�̎x�z�́A���̕����I�ȓ����ɑ��đS�ʓI�ȘJ���g���̑̐������A�������݂̐���𐄂��i�߂Ă����̂ł���B�����Ƃɑ��鋐��g���̑Ή��̒��ŁA�I���Ȏ��{�ٌ�_�I�ȘJ���g���������琬����Ă����B�V���ȓ����̒S����́A���ꓙ�����I�����Ƃ̓�����ʂ��Ă̂ݓo�ꂵ�悤�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�����I�ȁA���ƓƐ莑�{��`�̎x�z�̋��ł��́A�����̖��������ۓI�ȕ���ɂ����Ă̂��݉������Ă���B���{�ɂ����鍑���Ɛ�̎x�z�̐������̗�O�ł͂Ȃ��B
�@���a�O���N��̐ݔ������𒆎��Ƃ�����{�o�ς̍��x�����́A�����ɖ��ԑ��Ƃ̘J���Ǘ��i�ߑ㉻�j�̊m���ł���A�J���ߒ��ɉ�����E����ʂ��Ă̎��{�x�z�̋����ł������B���̓��I�̐��������Ă��Ă͂��߂ċΖ��̓��㐧�A�t����]�̍��x�����͉\�ł������B���{�̓Ɛ�u���W���A�W�[�����ۓ����̍V�g���A�����w�����̖��w���ɏ������Ȃ������A����ɏ���������f�����̂��A���̂悤�Ȗ��ԓƐ��Ƒ̂ɂ�����x�z�i�O�r�̌Ǘ����̐����j�ƌ�����Ƒ́A�J���g���ւ̍��ƌ��͂ɂ��e���i�X�g���֎~�j�ł������B������������c���ւ̓]����������ʂ��ĂȂ��Ƃ��A���������낵�����ƓƐ莑�{��`�̉����́i�����́j���ւ������{�Ɛ�u���W���A�W�[���A�͂₭�����������������������ւ̓]���������n�߂��B�������A���n�r���̏����̉��ō����s�����ΏۂƂ���o�ϐ����ɐ������A�S�j�̐��Y���E��O�ʂɂ܂œ��B�������{���ƓƐ莑�{��`�͊J���o�ϑ̐��̖��̉��ɂ��̊�����ɉߏ萶�Y��������B
�@����͐��Y�̊g��ɂ��ٗp�̑������x���Ă��������s������āA�ϋv������̉ߏ萶�Y���ɉ�����z�|���v���ɑ��Ă̓S�|���Y�̉ߏ艻�Ȃǂ̊֘A��ʂ��Č����Ă���B
�@���������Y�̑���ƍ��ێ��x�Ƃ̏h���I�Ȉ��z�Ƃ����܂��āA�����Ăѓ��{���{��`��"�s��"������j�I�ɉ�ڂ���������Ȃ��B����A�W�A�����͓��{�鍑��`�̗v�ł��������Ƃ��B
�@�ȏ�̔@������܂݂Ȃ�����A���₩�ȍD���̒��ɂ��鐢�E���{��`�s��̊g��Ƃ��������́A�Z�l�N�̓��{�o�ς̍�����A�����J�ւ̗A�o�����ɂ��蔲���Ă����B�����Ă��̗A�o�̂̂тɂ��A�ߏ萶�Y���I�Ȃ��̂Ƃ��Ă̂��݉�������ɂƂǂ߂邱�Ƃɐ������Ă���B
�@�ɂ��S�炸�A���N�x�t���̃G�l���M�[����I�Ɍ`�������߂����{�Ɛ莑�{��`���̍��ۓI�ȃN���[�s���O�E�C���t���[�V�����̌����Ƃ��ẮA�����̏���ҕ����l�グ�̔g�́A���x�����̏�����ʂւ̌����A�����͘J�������ʂւ̌����ɑ���J���҂̕s����傫�����N���Ă���B�����Ă�����Ƃ�܂����̂Ƃ��Ē�����Ƃ̋L�^�I�ȓ|�Y��_���̍s���Â܂�i�ĉ������グ�̂͂˂�����j������B
�@�ȏ������Ȃ�A�l�E�ꎵ�����A�����V�[�h���S�������`�j�~�����͓��{�Ɛ莑�{��`�̖�����[����������n�_������������邱�ƁA���������̗����̓������������Ȃ����ɂ����A�Ɛ�̎x�z�̗v�����邱�Ƃ����炩�ł���B
�@(4�j�l�E�ꎵ�����̓����́A����ɂ����Ă��̓����̃G�l���M�[�����ƓƐ莑�{��`�̍��Ǝ��D�ɑ��鋐��Ȓ�R�A�����h�q�̈ӎ�����ł����̂ł��邱�ƁA�����đ����ł͂���ɂ��S�炸�����̔ƍߓI�ȗ���ɏ������Ȃ���A�������ˑR�Ƃ��ē����̂��肠������{�X���̎�i�Ƃ��Ĉ��E���Ă��鏊�ɂ���B�����Ă��̖����w���Ƒ�O�����V�g�Ƃ̖����͍��⌰�݉������鏊����A���{�ƊK���͍����̏�̒��S�ɂ����ē�����c��{���Ɍ����邪���ۓI�Ȏ��{�̋����ߒ��ɂ������ƍ����Ȃǂ�ʂ��A�s��x�z���ێ��������Ȃ��������������̒��S�ɂ����悤�Ƃ��Ă���B
�@�����Đ������݉��̈������Ȃ������I�ɕ����I�ɓ]���������I�Ȏx�z��ۂ��A�l�X�Ȏs�ꐭ���W�J���悤�Ƃ��Ă���̂ł���B���̖��Ɋւ��Ắi2�j�̏���͂̍��ŏq�ׂ��Ƃ���̌܁��N��������̎哱�Y�ƂƂ��Ă̓S�|�E�@�B�E���D�E�@�ۓ��ɂ�鐬���ƌܘZ�\���N���̉ߏ萶�Y���A��������w���@�A�d�@�A�����ԁA�Ζ����Ɏ哱�Y�Ƃ�芷���ĘZ���N�㍂�x���������o�����A�X�ɂ��ꂪ�ߏ萶�Y�Ɋׂ錻���_�ɂ����Č������ƕ���i���ɏZ��j�����đ���ڂ̎哱�Y�ƕ���̌��Ł\���Ƃ̒��ړI�Z������A�������s��̈�w�����ȊJ�ɂ���Ȃ�������ɂ��āA���Ē������ƁA�V���Ȕ��W�̕����A�r�c���t��荲�����t�ւ̌p���͍����I�ɂ͌o�c�A���͂��߂āA��������ɂ��Č��y���邪�@���A�����͍��ےʉ݂̊�@�Ƃ������āA�����̉ߏ萶�Y�̒��̑傫�ȕs�������Ɛ�u���W���A�W�[�̗v���ɂ��݂��邪�@����̓]�����Ӗ����邱�Ƃ͊m���ł���B
�@�܂����ۖʂł��ޓ��ɂƂ��Ē����̊j�����A�C���h�l�V�A�̊j�����錾�A�x�g�i���̗������A����A�W�A�̗����́A�K����������A�W�A�ւ̐i�o�ւ̓r���e�ՂłȂ����Ƃ������Ă���B
�@�Z�l�N���������Z�ܔN�̏t���ւ̓r�͍��ƌ��͂̒e���������Ă��Ă������x�z����s���ʌ��J���J���҂̓����A���ԉߏ萶�Y����E������ƘJ���҂̐퓬���ƁA������Ղ͒~�ς���Ă����B
�@���݂̑ΊO�c���������̊�͊m�F�������@���A���ړI�ɂ͓���A�W�A�̗������@���ɂ������v���A���̐��i�Ƃ��č��킹�ăA�����J�̈��̌�ނ̒��ŁA�����ʂ��ē���̐헪�I�ȈӖ��ł̐����I�R���Ihege.�̓���A�W�A�ւ̊m����ڂ������̂ł���B���������ۓI�Ȏ��{�̖��̉��ɂ����߂����i�����̐V�x�z�i�s�ꑈ�D�j�A��i���Ԃ̒�J�����哑���͂������傫�Ȓ�R���ĂԂ��낤�B
�@�������āi3�j���Ŋm�F�����Ƃ���̊�{�����ƌ�i�I�����Ƃ̌��������߂�ׂ��K�������̊�{�I�Ȑ��i�y�їv�́A�鍑��`�̑ΊO����ɑ��铬���ƍ����ɂ�����K�������̌����ɂ�����˂Ȃ�Ȃ��B�ɂ��S�炸���{���ƓƐ莑�{��`�̐������閵���Ƃ��̖����̂Ȃ������I�����̐��ݏo���V���Ȗ����̗ݐςƂ��Ă̐l���̖�������R�̉�����X�ɂ����Đ��ݗ����A�����I�Ɍ��݉����V���ȎЉ�������̔g���`�����Ȃ�������̓������A�ΊO����ւ̐��������Ɛ[���ɒu���Đ[���������Ȃ�����A���ݓI�ɂ͏�ɕ������A�����ɂ����Ɛ�̎x�z�̗v���u����Ă���v���́A���ɓ��{���ƓƐ莑�{��`�̂Ȃ������I�����I���������ޓ��̎x�z�͂̋��ł��Ƒ��܂��Đ������A�S�̂Ƃ��Ă�����Љ�J���^�̎哱�Y�Ƃ̐芷���Ƒ���ڂ̐헪�Y�Ƃ̐V���ȃe�R���ꂪ�s�\���Ƃ͌������������邱�ƁB���Ɋ����w�����̑̐������̐i�s�̒��ŘJ���҂��̑����K���A���K�w���퓬���������Ȃ�������{�̉��ɏ�������B�t���ɂ���Ă���A��̖̂����n�ɂ���B
�@���Ă��̌X�������ݓI�ɓ˂��j����\���́A���ɍ��ےʉݑ̐��̊�@�A���ɐ�i���J���ҊK���̍V�g�����Ƃ��ꍑ�I�K�͂ł��W�J����邱�Ƃ�ʂ��Ă̐V���ȑS���E�I��M
�̍V�g�A���Ƃɕč��̓S�|�X�g���_�@�ɂ��Ĉꉞ�͗\�z�����B��O�ɓ��{�u���W���A�W�[�̓]���Ƃ��ẴC���t������f�t������ւ̓]���ł���i�܂��l�����Ȃ��j�B�Ƃ���Ȃ�A����ΐ����T�O���̏q�ׂ鏊��"�Ǝ��̗̈�"�̑��݂Ƃ͈ȏ��_�ɋN�����鏊�̍��ƓƐ莑�{��`�́i�x�z�̋��ł����܂߂Ắj���ł��Ƃ���̍��ۓI�����������I�ɂ͎Љ�������Ɛ����������[���ɂ����Č�������v���������Ȃ�����A���{���ƓƐ莑�{��`�̐��E��Ƃ̈ʑ�����d��I�ł���Ƃ������Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ���̎�v�ȗv���ł��邾�낤�B�������̂悤�ȍ��ƓƐ莑�{��`�̖����̂Ȃ������I���������Ɛ��������ƌo�ϓ����̕����ɂ��x�z�̕���́A���̂��Ǝ��̂��V���ȍ��x�ɂ��Đ[���������`�������ɂ͂��Ȃ��B����͖����ɏ����̌��@�\���ۓ����̐[���ƍL�����\�����Ă����̂ł���B���Ă��̂��Ƃ��m�F���āA�Ăѐ����������Љ�������̓���Ə����ɂ����錋���̕����Ƃ��̎w�����Ɉڂ낤�B(5)���ێO�r�ȍ~�̑S�����̕���̉��ɂ����Ă͐퓬�I�ȓ����͎O�r�����^�Ƃ��Ă̂݉\�ł������B����͊w��M
�ɋ��s�{�w�A�̐퓬�I�Ƒ��̐���S�������铬���ł��������A�������̊�ƍ����̒��ł̓Ƒ��̐��𒆐S�ɂ���S�Y�Ɠ��ꓬ�����u������O�H���D�J�g�Ќ��̓����̂���ł������B�����Ƒ��̐��ւ̍��ƌ��́����{�̏W���U���ŎO�r�ȍ~�̓����́A��ɑS���I���ꓬ���ւ̔��W�Ƃ����ۑ��v������Ă����B�J��M
�A�w��M
�̑�O�����Ƃ��Ă̑S�����͑S���I�Ȑ����w���̊m���A�S���I�Ȑ����g�D�̊m�������킹�ėv������B���̉ۑ�͍����̘J���҂��A�g�����Ƃɑ̐���������A�����͊w�������Y�w�����̒��ő̐�����������邱�Ƃ��v���A����I�ɏd�v�ł���B
�@��X
�͂�����ɂ����đ����K�����������Ȃ���A�����ɑS���ɎU�݂���퓬�I�v���I���������W���邱�Ƃɂ���O�������`�����邱�Ƃ�ڕW�ɁA�w��M
�ɂ����Ă͑�O���̎Њw���̌����Ɣ��铝�����S�w�A�̍Č��ɂ�鎩�炪��O�̒������������Ă������Ƃ����݂��B�������A���͂�����H����s�f�̌��݂̍���ȑ�O�̏̒��Ŏ������Ă����Ƃ���̎w�����ł��邵�A�X�̑�O�ɂ����锽��I�Ȏ��ԓI�Ȑ���ł������B
�@�����ĉ�X�����ݖ��ɂ��Ă���Ƃ���̂���́A�P�Ɋ���̋�_�Ƃ��Ẳi�v�v���^M
�̎w�����̍����̖��ł͂Ȃ��A�ɂ߂Č����̗v�����瓱�������Ƃ���́A�����A���ɐ��������̌���I�Ȏ��͓I�ȓ������v�������ɂ��S�炸�AM
�̏�����̒�����ꂽ�Ƃ͂����A�S�̂Ƃ��Ă̊K�������̒�،̂ɁA���̐�i�I�ȓ��������W�����������t�ɑ�O�Ƃ̈��̕����������炷�A���ɁA�w����O�ɂ�����̐��������i�݁A���{�E���Ƃ̑�w�̒��ڎx�z���A�E���Ƃ�������ׂ����{�̊w����O�̏��������ɔ����k���Ȍ^�Ő[�����A�w��M
�̒����Ƃ�����ׂ��w����O�̐����Ɏ��I�ȕω��������炵���邱�ƁA��O�ɁA������̑O�i�I�ȗv�f�Ƃ��Ċm�F����鏊�́A���݂̎Љ���̊�@�����ɒu���ẮA��w�̎��{�̎x�z�̋����Ǝ��D�ւ̖����̗ݐςƂ��Ĉ�̉��������玑�{�ƓƐ莑�{�A���ƌ��͂ɑ��đ�O�I�Ȕ��t���J�n����n�߂����Ƃł���B���Q���ł͂��邪����������������X���������Ă��Ă��邱�ƁA���ꓙ�^����ꂽ�����̒��Ō��ݓI�Ȗ��Ƃ��ē��ؓ����A�w���Љ���������i���݂ł͑S�����҂͂��ꎩ�̓Ɨ����Ă���A�ʓI�ɐ����i�߂˂Ȃ�Ȃ����j�@���ɓ��ꂵ�Ă������A���̖��͋Z�p�I�ɑΏ�����Ȃ�����ꂩ����Ɉ�ʉ�����Ă��܂����A���̂��Ƃ͎��Ƃ��č���A���ꓙ�Ɠ��l�̎��Ƃ��Ă̐��������ƎЉ�������Ƃ̓��ꂵ���w�����ɂ��邪�A��������Ƃ��Ẳi�v�v���^M
�̎v�z���̎~�g�ł���B
�@���čēx�ڂ����w�������̐��i���݂Ă݂悤�B����͊�{�I�Ɍ܁��N��ɓW�J����Z��N��ǖ@�Ɍ�������������������ɑ��Ă̖����`���O�̔����Ƃ��ẮA���������̎��Ԑ��A����͌l�̓����ɑ��݂��錶�z�������ƊK�����̑Η��R�����Ɍ��������A���̂��Ƃ͍��Ƃ̌��z���@���A���Ƃ̊K���Η��̔�a�𐫂̎Y���Ƃ��āA����̂ɂ�����}���҂ɂƂ��ĊO�݉������a���ȃu���W���A�W�[�̎x�z�̖\�͐���{���Ƃ����Y���ł��邱�Ƃ̔F���ւ̖G��Ƃ��āA�����Ă��̖G��͌l�̎Љ�W�̑��̂ւ̔F���Ɏ��炵�߁A���̍���͎��Ȃ̉���Y�W�̑������L���Y���̔p�₩�ۂ��ɔ���Ƃ���̖{���������Ă��邪�\���̎��Ԑ����s���Ƃ��Ă̍��Ƃ̌��z�������̒��ɓ��ʉ����ꂽ��ł̋^���I�ȁA�����u���W���A�Љ��O��ɂ��ẮA����̂Ɍ��@�I�ȉ��l�ړx�������āA�u���W���A�W�[�̉��l�ւ̔j��ɑ��Ă̒D�ғI�����Ƃ��Ă̎s���I�����ł��������̂��A�c�́E�Љ�ْ̋��W�̐V���Ȏ��ւ̓]���Ƃ��̊O�����Ƃ��Ă̎��{�ւ̕s�f�̒��ړI�w�⌤���̗����Nj��ւ̌������Ƃ��Ă̂ݗv�������Ƃ��A�����Ő�������Ƃ���̊w����O�͎��{����a�O����A�ˑ��Ɣ��������I�a�O�ӎ��A�����������Y�W�Ɋ����J���҂̑a�O�Ɠ����������������̂��`�������B����͖����̐����̓W�]�������ړI�ɓ���Ă��邪�̂Ɏ��{�ւ̊w���̈ːS���������B���̂��Ǝ��g�͐����̎��Ԑ���L���Ă��邪�̂ɂ��̑a�O�̔����͖{���I�ɂ͎��{��˂������āA���̐����I�Љ�I���͂Ƃ��Ă̍��Ƃւ̔ᔻ�ւƓ˂��i�ނ��̂ł���B
�@�����钊�ې��̌��ۂ͋�����̗�����E���������ւ̋�������������E���������̐�����x������Ƃ���̋����w�̔y�o�ƍ��ƁE�Ɛ�̍����I�������Ă̌����\�[�~�̓W�J�Ɗw����O�̂���ւ̌��ʂ�ʂ��Ă̋����\�Ɛ莑�{�̊w���̖��[�ł̏W��A�����ꓙ�̎x�z�̍�����ʂ��Ă̊w�����c�̂̎������̑r���ƕώ��ɂ���w�s���Љ�̍��Ǝ��{�̒��ړI�x�z�Ƒ�w�̋^���H�ꉻ�ƍ������̐i�W�Ƃ��Č����Ă��邪�A���ꓙ�̔��t�͍��Ƃ̕��g�I�@�\�Ƃ��Ă̎Љ�ƁA���{�̑�w�ւ̎Љ�I���͂ւ̑Ό��ƈ��̐����ӎ��͌`���������̂́A���܂����Ƃ̐����I���͂ւ̓����ɐ����������W�J����Ȃ�����A����͌���I�ɕs�\���ł���A���������݂͂̂ւ̑Ό��́A�w����O�̒����ł̎x�z�������Ă��邪�̂ɕ����I�퓬�I�����̌��W�Ɍ��肳��Ă��܂��B������O���̐V���ȋْ��W�̎��A������[�j���́u�v���I�V�g�v�̓��ݐ��̌`���́A���̂��Ƃ͎��{�̐E��x�z�����Ƃ̎x�z���̓����I�����ɂ��E��̖��[����̒�R�̓����I�����Ɋ�Â����������ւ̔��W�̉\���A�X�ɁA���������̓���̎�����̎��{�Ƃ̓����ւ̐i�]���A�[�܂�Ƃ̓���̉\����L���Ă��邪�̂ɁA�Љ�I���͂Ɛ����I���͂̓����I����I�F���̉\�������Ă���̂ł���B���̂��Ƃ̔F���͉䂪�����̌��J���ł̕s�f�̔����������������Ɛ��������̓W�J�̍���ȏ���l���������̂ł��邪�A��X�͂��̐��������A�Љ�������̓��ꂵ�����ԓI�\���`�ԂƂ��āA������O�̊j�Ƃ��Ă̕��U���ƕ������ɑ��āA��̏��������v�����^���A�[�g�S�̂̊K���I�s���ւƔ��W�����A��O�̗v�����Љ�I�\�����I����Ɍ����Ċт��A�����̐����\�Љ�͂̑ɂɃv�����^���A�[�g�̎��Ȍ��́\�v�����^���A�����`�̐��ݓI�\���A�@�\�Ƃ��Ă̈ӎ����A�g�D���A�S�̐���^������̂Ƃ��ĘJ���Ґ����g�D�����o�����̂ł��邪�A���Ɍ��J���ł̉�X�̓��u�����������Ƃ���̖��͓������������Ċw��M
�ɂ��K�������ׂ����̂ł���B
�@�X�ɂ��̂��Ƃɂ��Ắw��m�xNo.4�́u�h�C�c�v���̔s�k�ƃ��[�U�v�i���ؑ��Y�j�ɂ���ēI�m�ɕ\������Ă��邪�A�u�H��ɂ�����Ƃ���̌����̊g���O�ꂳ���A���̂��Ƃɂ���č��ƌ��͂̏Փ˂ւƔ��W���A�ʎ��{�ƍ��ƌ��͂Ƃ̓��ꐫ���F������˂Ȃ�Ȃ��B���[�U���v���̑��i�K�̓X�g���C�L�ɂ��o�ϓ����ł���Ƃ����̂́A�o�ώ�`�ł͂Ȃ�����v���̖@���ł���B�X�ɂ��̂悤�Ƀu���W���A�W�[�̓��h�ɂ��S�炸�s���Љ�ɂ����čĐ��Y���s������Ƃ�������������̂ł���B���Ɍ���v���͍H��ɂ�����J���҂̑g�D�A���[�e�����ɂ����Ă����B�������Ȃ��̂ł���v�B�X�ɔނ͌��_�Ƃ��āu����v���͉i�v�v���_�̒�N�����_�C�i�~�b�N�Ȑ�p�ɂ��M�̋}�i�����W���R�o����`�A���C���^�[�̒�N�����u�����^���A�[�g�̓Ǝ������g�D��̓����Ƃ��āA�������ꂽ�}�ɂ�鐭���I�Ȑ�`�A��Ƌ��ɉ��Ǔ����v�ɂ��H��ł̌����g��A�v����ɂ������O�X�g���C�L���烌�[�e�ւƕK�R�I�ɔ��W����̂ł���B����ɂ�������ǂ̂ݏd�˂݂̂ł͊v���ɂ͌����Ă�����Ȃ����A�������Ǔ�����ʂ��Ă̍H��ɂ����錠���̊g����ɂ��ẮA�P�Ȃ�A�����W�c�ƂȂ邩���͌��͂ɕ��ӂ���邩�̂����ꂩ�ł���B���[�U��M�Ă���А��̏��N�A���̂��Ƃ͏d�傾�I
�@��X�͂����������Ă�����V���Ɋl�����ꂽ�w�����̉��ɍ���Љ�I�Ȑ��������ɂ���w�\�s���Љ�֒����I�Ȑ����I�o�ϕ����Ihegemony
�̊m����O�ꂵ�����{�����Ƃ̒��ڂ̎x�z�Ǝ��D�ɑ��Ă̓�����ʂ��Ċl�����邱�ƂƓ����ɁA���s���Ĕ@�I�ȓ��ؑj�~�A�׃g�i���푈���̐���������W�J���邾�낤�B���ꓙ�̓����̓O��I�[���̒��Ō��@�\���ۓ����������Ă������낤�B���̂��Ƃ̎v�z�����l�����A���������̓��I�֘A����c�����邱�ƂȂ��ɐ�����`�A�w����`��ᔻ���Ă݂Ă��s�тł���B |
|
�@�T�D�R���A�Њw���}����h����S���ψ���k����l�A���؉�k���ӌ܁E���S���X�g���^�����j����B
| �y�t���i���j�h�Ǝu��h���Љ��`����L�u����z |
| �@�T�D�R���A�������s�ψ���A�����{�w���ψ���A���w���S���ψ���̑�\�҂��u�P��w�������̂��߂̑S����\�҉�c�v���J�ÁB�\���h�w���^���̌�����ڎw���������ł���A��̎�����������q����B |
| �@�T�D�P�O���A���{�̂����h������X�ؔh�̌��W���Ăт����A����ɎЊv���ĉ��B |
| �@�T�D�P�P���A���Г����ł��t���⌴�����{�̂����h�̌Ăт����Ɍĉ����ĎЉ��`����L�u��������B |
�@�T�D�S���A�s�w�A�Č������ώ�ÁE�S���w�������Ɖ�c�k����l�A���؉�k���ӌ܁E�j�[�S���X�g�A�����s�w�A�Č���������i�\���n������A��B�w�A���s�Q���j�B
�@�T�D�P�T���A�S�w�A�i�v�}���h�n�j�A�����j�����R�c�ʼn؋�����Ƀf���B
�@�T�D�Q�O���A�S�w�A�i�����n�j�x�g�i���N�����ΑS������s���A�����W��k����J�쉹�l�Ɍܐ疼�Q���A���d�F���܂Ńf���A���O�{���w�A�i�������n�j���W��E�f���B
�@�T�D�Q�P���A�������n�e�h���A�x�g�i���N���j�~�E���؉�k���ӑS������s���A�����W��k����J�쉹�l�ɑS�s�ܐ疼���W�A�O���ȁE�đ�g�قɃf���B
�@�T�D�Q�T���A�Č��������ۊ�`�ɑS���e�n�ŋً}�R�c�s���A�����F���勳�{�E����E�@���哙�l�L���A�O���ȑO���荞�݁E�����ߕ߁A����F������S���A������`�j�~�E�����j�������̊w���W��A�������F��������S�\���A�����}���A�{���O�R�c�W��B
�@�T�D�Q�T���A���Y���}����h��ÁE�Љ��`�J���Ґ�������L�O�E���x�g�i�������W��k�����فl�ɌܕS���Q���A�v�����S���ρE���D�Ќ��E�l��N�v�����A�B
�@�U�D�S���A���O�{���w�A��ÁE�Ėk�����E���؉�k���ӑS�������N�W��k�~�R�����l�ɎO�疼���W�A���{�莛�O�܂ł̎s���f���ŋ@�����ƏՓˁA�O���ߕ߁B
�@�U�D�X���A�Љ�}�n�́u�����j�~�E�S�����s�ψ���v�Ƌ��Y�}�n�́u���۔��Β������s�ψ���v�̈���������������A��V�������Q���B�����n�S�w�A�͂P�������W�B�V�O�h�n����łW�O�O�O�����R�c�f���B
�������n�e�h�O�疼�A����J�����Ɍ��W�E�O���ȃf���A�ēx����J�ɖ߂�Љ�}�n�W��ɍ����A�e���ŋ@�����ƏՓˁE�\�O���ߕ߁A�S�w�A�i�����n�j�l�疼�A�W��k�Ō����l�E����J�܂Ńf���A�����n�W��ɍ����B���s�{�w�A�ܕS���A�W��k���u�Б�l�E�~�R�����܂Ńf���A�r���͌����ŋ@�����ƏՓˁE�l���ߕ߁A�����w�A�W��ɉ���A����W���e�N�B
| �y�S�w�A�e�h�̓��ؓ����z |
| �@�U�D�Q�Q���A���؉�k���Ì������B���̓��A�����n�S�w�A�͂U�O�O�O�����W���A�W��ƊO���ȁE�đ�g�قɃf�����s�Ȃ����B�V�O�h�n�����؏��{����j�~�����A���N�W��k�Ō����l�ɓ��ܕS�����W�A���@�Ɍ��������@�����ɑj�~���ꌃ�������Œ�R�E�\�����ߕ߁B����W�O�O�O�����R�c�f���A�Ƃ���i�v�}���h�n
�����R���g��ł��锤�ł��邪�茳�Ɏ������Ȃ��̂Ŋ�������j�B |
| �@�P�X�U�T�N�U���Q�Q���A�a��c�j�N�i�킢���E���낤�j�i���{�吶�A�}���w�����j�h�j�����؏��j�~�f���Ōx�@���s���ߕ߁A�E��ڕ������܂������Â��������A�E���ؒf�ƂȂ�P�N�ȏ㓬�a�A���N�V���P�X�������i���N�P�X�j�B |
�@�U�D�Q�T���A���厩����E�_�ˑ厩����E�����ّ�ꕔ�w�F��i�\���n�j�A�A���Ŋe��w������֓���S�w�A�����̂��߂ً̋}�A�s�[�������B
�@�U���A��x�g�i���ɃO�G���E�J�I�E�L�������i�������B
| �y�V�O�h�A���i�А�����h�E�Њw���E���j�h�j���s�w�A�Č�������������z�@ |
�@�V�D�W���A�s�w�A�Č���P�S����J����k�S�d�ʉ�فl�A�V�O�h�A���i�А�����h�E�Њw���E���j�h�j���s�w�A�Č���������������A���z���M�Ȃ��牽�Ƃ����Ď��O�̑�O�̑S�w�A��n�o�����悤�Ɗ�}�����B�@����(�o�D��)�D����(��)�D����(��@�D��)�D���H��ȂǂP�P��w�̂Q�U�������V�U��c���A��R�O�O���̊w�������W�����B���j�h���S�w�A�����Č��������咣���A����ɔ�����v�}���h������ڂ̓r������ޏꂵ�A�\�����v�h�͑�\�𑗂�Ȃ������B�v�}���h�͂������S�w�A�̂��߂̉A�d�Ƃ��āA�s�w�A�Č��͢�������I�Ȗ썇����ƌ������ᔻ�𗁂т����B���؏���y�j�~�����ɑ���S���w�F�ւ̃A�s�[���Ȃǂ̌��c�Ɠ����X���[�K�����̑��A���錾�����B
�@�ψ����ɎR�{�_�i(����D��@)�A���ψ����ɋg�H��(���H��)�A���L���ɍ֓����F(����)�A���������ɎR���h��(�@����D�o)��I�o�����B������A�����J�̃x�g�i���N���푈�ɍR�c���A
�đ�g�قւS�O�O�����f���B�V�O�h�n�͐܂���̃x�g�i�����퓬���ɍł����͓I�Ɏ��g��ł������ƂɂȂ�A���̎��_�ł͓��������Ȃ����̂̎���ɐ����𑝂��Ă������ƂɂȂ�B����̋C�������������L���b�`�����g�Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ƃ������n�S�w�A���A�S�D�Q�Q���A�����J�����Ȑ�����ψ������X�g�D�������Γ����Ɏ��g�݁A�H�c��`�ɂR�O�O�O�������A�R�c�f�����s�����B���������ė����������b�W�ɑ��Ă��A�����ăA�����J��g�قȂǂɍR�c�s�����s�����B |
�@�V�D�W�|�X���A�s�w�A�i�����n�j�������k���c�J�斯��فl�A��\���w�l�\�l�������\�Q���i�ψ����E���m�I�j�B
| �y�v�}���h����Q�Q����J�Áz |
| �@�V�D�X�|�P�Q���A�v�}���h����Q�Q����J�Ái�ψ����E���{�m�j�B�P�Q�S�������P�T�P��c�����Q�������Ɣ��\����Ă���B�ψ����ɂ͍��{�������C�B����ꕶ�𒆐S�ɁA�D�y���D�H�c��D���V��D�ޗǏ��q��D��������D���O�哙�����W���Ă����B���؏���y�j�~�𒆐S�Ƃ����^�����j������B |
| �y���n�S�w�A�̓����z |
|
�@�V�D�P�O���A���n�s�w�A�������J����A�Q�Q��w�D�R�X������̑�c���ƂS�O�O���̖T���҂��Q���B�ψ����ɑ��m�I(����D��)�A���ψ����ɓc�F�a�M(���o��)�ƐA�c��(����D��@)�A���L���ɋ��q��(����D��)��I�o�����B
�@�V�D�Q�R�|�Q�T���A�����n�S�w�A�ψ����E���O�j���A���ōČ���̑�P������J�ÁB�U�W��w�E�P�S�Q������A��P�T�O�O���Q���B������̑S�w�A��P�T����\�͂ɂ���ė����]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ������j�I����܂��āA���̑��Ő�̍Č������P�T����Ƃ��邱�ƂɌ��肵���B
�@���̑��ł́A�w���̐g�߂Ő؎��ȗv�������A�w�����剻���������������������ƁA�����ۑ�Ƃ��ĂP�O�D�T���̗Վ�����J������ē��؏���y�j�~�����ɑS�͂������Ď��g��ł������Ƃ����c�����B���̍�������w�̊w��l�グ���Γ����A�����I���K���P�p���������g�܂ꂽ�B�ψ����ɐ��O(���勳��)�A���ψ����Ɉ���a�K(�ꋴ��@)�ƎR�{���l(���O��)�A���L���ɘj������(���w��)��I�o�����B
|
| �y��S�C���^�[�̓����R���z |
|
�@�V���A��S�C���^�[�̎O�����̋��h�b�o�̎w���I�����o�[�A����A���\���ɂ���āu��l�C���^�[�i�V���i����E�ނ��A�V�����C���^�[�i�V���i�����߂����Ă����������v�Ƒ肷�镶���i�u����E���\����āv�j�����\���ꂽ�B���̕����́u��l�C���^�[�i�V���i���́A���Y�ł������v�Ƃ̎咣��W�J���Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ����B
| �@�u��l�C���^�[�i�V���i���́A���V�A�v�������[���b�p�v���Ɉ��������Ƃ����W�]�̂��Ƃőg�D���ꂽ�B���������̐��E�v���́A���[���b�p�̕����ɂނ����̂ł͂Ȃ��A�����v����˔j���Ƃ��ăA�W�A���A���n�v���̕����֔��W�����B��l�C���^�[�i�V���i���́A�v���̂��̓]�i�ɍ��Â����Ƃ��ł����A�y������Ȃ��Ă��܂����B���̂��߁A���̐��a�͈�̎��Y�ɂ����Ȃ������B����Ă����́A��l�C���^�[�i�V���i����E�ނ��ׂ����v�B |
�@�u����E���\����āv �́A���������A�Ƃ��ɎO�����̓����ɁA����ȃV���b�N��^���A�_���́A�P�Ȃ鑾�c�̐������j�̐�����߂�����̂���A���c��擪�Ƃ���}�����h�ƁA��ĎҒB�̉�}�h�Ƃ̘_���Ƃ������i�̂��̂ɋ}���ɕς����B�u��āv�c�͑�삱�тŗ��p�����B�ނ́A�T�D�P�W�����̎��s��_���̕Ћ��ɉ������A��}��`�U����ʂ��Ď���̌��Ђ��Ċm�����悤�Ƃ����B
�@���c�̂��������H���́A�����̑���S�����ŕ��ӂ��ꂽ�B�����O��A�{���c���c�́A�u��āv�̖���N�́A�������ӎ��������̂Ƃ��Ċ��}���A�p�����_�ɕt���ׂ����i�̂��̂ł��邱�ƁA���������̌��_�ɂ��Ă͂�������P��K�v�����邱�ƁA�܂����̓��_�̒��S���A���̊Ԃ̐������j�A���������̑����ɂ����ׂ����Ƃ��A����A���\���ɐ\������A�ӎu������͂������B
|
|
�@���̌�̌o�܂ɂ��Ď��̂悤�ɋL����Ă���B
�@��S�C���^�[�Q����́A�����ɔ����c�h�����ꂽ���Ƃɂ���āA�ꒆ�ςƂ͂��������͊W�ɂȂ��Ă����B���c�̋N�������c�ẮA������c�ɂ���Ă��̖�����Nj����ꂽ�B���Ȃ킿�c�Ă̑S�̂��u�Ē��푈�s��_�v�ł�ʂ���Ă���A����́u�|�T�_�X�h�v�̎咣�Ɠ��ꂾ���A�u�|�T�_�X�h�v���x������̂��A�Ƌl�₳��āA���c�́A�u���̓p�u�����x������v�Ƃ��������B�����́A�c�Ă��̑��ɂ����Ȃ����Ƃ����肵�A���_�̑f�ނƂ��đ��c����N���邾���̂��̂ƂȂ����B���̓��_�ł́A�c�Ăɂ������锽���A���i�q�̕������猃�����W�J���ꂽ���A���h�b�o�͑��c�i��̘_�w�炸�A���ق�������B
�@���́u����E���\����āv���p�����_�ɕt�����Ƃ����肵�A���̖��Ŕ����̃`�����X���������Ƃ������c�̌v��͍��܂����B����ɑ�O�̑Ō���������ꂽ�B���c�̕w�l�����o�[�ɂ������������l�I�w�����X�L�����_���Ƃ��Ė\�I����A�͂��������e�����̂ł���B���c�����₹��Ƃ����v����������ꂽ�B�����ɂ����đ��c�́A��̖�E����̎��C��\�������B���͂��������A���c�������c�ɕt�����Ƃ����肷��ƂƂ��ɁA�����������Ȃ����L�Ƃ��đ��c�������̏�ɂ��邱�Ƃ����肵�ĕ���B
�@�����ŋt�]����������ꂽ���ォ��A���c�̕��h�s�����J�n���ꂽ�B���h�b�o�O���[�v�̈ꕔ���A���c�̍s���ƘH����i�삵�A���c�h�i�̂��ɁA�a�k�h���{���V�F�r�L�E���[�j����`�h�Ǝ��́j�����������B������璚�x���N�ŁA�����͐V���ȕ���E���h�����̎���ɑ��ݍ��̂ł���B�V���ɑI�o���ꂽ�����́A�a�k�h�Ɣ��a�k�h�Ƃ̘_���̏�ɂȂ����B���ꂵ���������j���p����͓����Ȃ��Ȃ����B���������Ȃ��ŁA�H�̓��ؓ������W�J����Ă������B
�@����Ȃ��ƂɁA���s��I�ɐi�s���Ă������Z�ܔN�̏H�́A���k�Ɗ��̉����������傫���O�i���A�����ł���o���ꂽ�m���̑��ނ��A���������ɂ����āA�O�����𒆐S�Ƃ��铌���̎А��̑���Ǝn�߂č��������Ƃ��ł������B����O�̓����ŁA�����A�{��̎А��ƎO�����А��́A�ƂȂ荇�킹�ɍ��荞�B��������́A�܂��ɏ���ɂ���A�ӋC���V�̕����ł���A�����́A�ǂɂ�������A�w�������������Η����āA�������o�����Ȃ��������B�S���I�ȁu�����I�@���v���A�͂��߂��\�ɂȂ������̂Ƃ��ɁA�u�P��́A�ٖ��ɒc�����������w�����v���A�����낵�������ŕ��Ă������̂Ă���B |
|
�@�V�D�Q�X���A����̕ČR�Î�[��n����a�Q�����@�R�O�@���A���ڃx�g�i���֊C�m�����Ɍ������B
�@�V�D�R�P���A�Њw������h���A�s�w�A�Č��i�ψ����E�R�{�_�i�j����A�Њw���Č��S�����𓌋��ŊJ�Â��A��u���g�\�z�̉��ɓ���h�Ɗ��u���g�Њw���ꂵ�A���Y���}��ψ������������B
�@���j�h�̍��Z���g�D�E���퍂������
�@�W�D�P���A�W�D�P���s�ρi�������n���}�h�j�A�s�w�A�i�O�h�n�j���ÁE���؏���y�j�~�S���J���Ҋw�������N�W��k��i��فl�A�J���ҁE�w���疼�Q���B
�@�W�D�U���A��O�۔���W��k�ԍ����l�A�v�}���h�J���ҁE�w�����S���Q���B
�@�W�D�U���A�W�D�U�L������W��k�L���l�A���j�h�n�w���E�J���ҕS���\���Q���B
�@�W�D�V���A�L���w�����a�W��k�L���J����فl�A�O�h�n�w���l�S���Q���B
�@�W�D�W���A�x�g�i���N�����E���؏���y�j�~���J���Ҋw���W��k���s�l�A�����Y���n�J���ҁE�w���Q���B
�@�W�D�P�S���A���꒓���̕ĊC�������t�c����x�g�i�������ɏo���B
�@�W�D�P�S���A�ו��A��Ấu�푈�ƕ��a���l����O��W��v�B
�@�W�D�P�T���A���E��ܔ��镽�a�W��k�l�J����l�A�Њw��ML�h�n�w����S�\���Q���A��v�ی����܂Ńf���B
�@�W�D�P�X���A���A����ÁE���������R�c�������ɗ�����w����Q���A�[��܂ňꍆ���H��ō��荞�݂ōR�c�A�x�����̎��͍s�g�Ŋw���O�����܂ޏ\�Z���ߕ߁B
�@�W�D�Q�X���A�S�w�A�i�����n�j��ÁE�쒩�N�w�F�x���E���؏���y�j�~�ً}����s���A�����W��k�����J�����l�Ɏ��S�\���Q���A����J�����܂Ńf���B
�@�W�D�R�O���A�Љ�}�E���]�E�А����̌Ăт����Ńx�g�i���푈���E���؏���y�j�~�̂��߂̐N�ψ���i����N�ρj�����A�S�w�A�i�v�}���n�j�E�s�w�A�i�O�h�n�j���I�u�U�[�o�[�ŎQ���B
| �y�Њw������h(���Y��`�ғ�������ψ���)�����z |
| �@�W���A�Њw������h(���Y��`�ғ�������ψ���)���������ꂽ�B����͎Њw�����̃}����h�Ƃl�k�h�ɎQ�����Ȃ��Ɨ��h�̐��͂����債�A����Ɗ��u���g�Ƃ����ꂵ�Č������ꂽ���̂ł������B |
| �y����N�ψ�����z |
|
�@�W�D�R�O���A����N�ψ���������ꂽ�B������������ł͓��؏���y�j�~�̂��߂̉^���̓��ꂪ����Ă������A�Љ�}�E���]�Ɠ}�̊Ԃ͈��ۓ����̕���ȗ��̑Η����������A��������̒��x���o�Ȃ���Ԃ������Ă����B���̍��x�g�i���푈�������ۑ�Ƃ��ċ}���ɕ��サ�n�߂Ă����B���̂悤�ȏ̒��ŁA�Љ�}���N�ǁA���]�N�����A�А��̎O�҂̌Ăт����ɂ���āA�Љ�}�n�̐N�J���ґg�D�Ƃ��āA���Ȃ킿�u�x�g�i���푈���A���؏���y�j�~�ׂ̈́A���̓����ڕW�Ɏ^������S�Ă̐N�w���g�D�ɉ�����ꂽ�N�̎���I�����g�D�v�Ƃ��Ĕ���N�ψ���������ꂽ�B�Q���g�D�́A��L�O�c�̂̂ق����J�A�S���A�S�d�ʂȂǑ��]�n�J�g�P�S�P�Y�̐N�������W���Ă����B
�@����N�ψ���́A�N�J���҂̒��ւ̉e���Ƃ����u���Ɓv��i�߁A����Ɉ��̐��ʂ��_�ō����^���̗��j�ɏd�v�ȍv�������Ă��邱�Ƃ������ƒ��ڂ���ėǂ��悤�Ɏv����B����N�ψ���ɂ́u�����v�n�����������鍶���W�c�V�V�̒c�́E�l���Q�����Ă������ƂɂȂ����B�V���Ɍ������ꂽ����
�̐V�O�h�n�s�w�A���������Ă����B����{�̐���h���^�c�ψ��c�̂Ƃ��ĉ������Ă����B
�@�U�O�N��̐N�����^���́A�قƂ�NJw���^���Ɍ����Ă������A���̔���N�ψ�����������Ƌ}���ɘJ���҂̊ԂɐZ�����Ă������B����N�ψ���̂��̌�̌o�߂́A����ɒn��E�E��E�w�Z���Ɍ�������g�D���g�債�Ă����A����Ɠ����ɋ}�i��`�����n�߁A�Љ�}�y�ѓ��{���Y�}���u�c���`�J���p�j�A�h�v�Ɣl�|����Ɏ���A�����Ƃ́u����ȓ}�h�����Ƃ�����ѓO����Ǝ������̌��W�v���v���I�����̔C���ł���Ƃ���Ɏ���A���ɂ͎Љ�}�E���]�̓������y�Ȃ����ƂɂȂ����B
�@���̌o�߂ɂ��A�����\�i���̢�܌ܔN���}����Z���N�ɂ�������ݣ�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@��Z�E�����͎Q�c�@�I��������A�Ћ����]�͑I���ɂ��������𒍂����݁A�x�g�i�����퓬�����A���؏���y�j�~��������O�����Ƃ��ĂƂ肭�܂��A�����Q�c�@�I�����I���āA�Љ����قœ}���N�ǂ̎��ԋ@�ւł���N��ψ�����Ђ炭�B�����̐��N�ǒ��͓���V�����ł���A�N��ψ����͑O��Q�c�@�c���ł������B���̐N��ψ���͐��N�ǂ̏��L�Lj��A�А��̒����A���]�Ε��A�S���_�N���Ȃǂ̓}���ō\�����Ă����B
�@���̏��̉�c�ŁA�Љ�}�A���Y�}�A���]�����؏���y�j�~�ɂނ��ĉ����̓I�ȂƂ肭�݂��s�Ȃ��Ă��Ȃ����ƂɁA���ꂼ��̗��ꂩ�狭���ᔻ�̐������������B���̓��_�̌��ʁg�x�g�i���푈�ɔ����A���؏���y��j�~���邽�߂̐N�ψ���h�i���́A����N�ψ���j��������g����I�N���g�D�h�ɌĂт����Ă���A�S���e�n�ɑg�D���邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B
�@���́A�А������s�k���炢�v���Ԃ�̑�O�����Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��邱�Ƃɋ����ӗ|��R�₵���B�����ő�������͂͂��܂蔪���O�Z���Ɂg�S������N�ψ���h�͌������ꂽ�B���̎w����S�������ǂ͑��]�̎R�����N�A�А��̗��R�w�N����Ɏ��̎O�l�ł������B���̎O�����Lj��͉^���̔���I�O�i�̂Ȃ��Ŋ����ɂӂ邦�Ȃ���`�[�����[�N�ǂ����������B�S�������{���̌�����������̉����N�J���҂̒e���A�����E���̔��g���L�����y�[���Ȃǂ́A��ꌎ���ؓ����̑S�̓I�ޒ��Ƃ݂��߂����炵���s�k�̂Ȃ��őS������Ɍ��W����N�J���ҁA�w���̐퓬�I�G�l���M�[�̓����Ƃ̍��g�̑O�ɖ��ł͂Ȃ�������B |
�@����ۊv��������̢���{�v���I���Y��`�������j��͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�T�v�u���ؓ�����ʂ��āA�А������̎Љ��`����h�ƍ��h�k��l�C���^�[�h�Ɖ���h�̘A������j�Ƃ̑Η����A�����𒆐S�Ɍ������A�ꕔ�ł́A�\�͓I�ȏՓ˂������N���͂��߂��B�А��̕��h�����͈���I�ɐi��ł������B�s�J�A�ƌ������������А��̃f������A����h�͓����������҂��A�����̎А������́A���h�����̍\���ɂȂ��Ă������B
�@���ؓ����̂Ȃ��ŁA�S������N�ς��������ꂽ�B�����ɂ́A�����̐V�����Z�N�g���Ȃ�^����ꂽ�B�Ƃ�킯��������́A�퓬�I�ȐN�J���҂Ɗw���̋����̏�ƂȂ����B����h�́A�ߌ��h�ɊJ���ꂽ���̓�������ɂ������Ă��A�J�g�@�ւ�ʂ��ē������͂��낤�Ƃ����B�А������̕��h�����́A�������āA�O�ɂ܂ōL�����Ă������B
�@�g�債�[������А����h�����̈���ŁA�����̕��i�s���A�V�����͋@�\��Ⴢɂ�������������B���������̔��W�̂Ȃ��ł̓����̊�@�A���ꂪ�Z�ܔN������Â������̂ł������v�B |
�@���O�E���́u�w���^���v�́A���̓��������̂悤�ɕ]���Ă���B
| �@�u�V����������N�ψ����g�D�g��̏�Ƃ��āw�킽��ɏM�x�ŐH���������v�Ƃ��A�u�Љ�}���w�Ђ������
���ĕꉮ�������x���ƂɂȂ����v�Ƃ��A�u�w����N�ψ���x�̌����́A����
���ăg���b�L�X�g�̑��𐁂��Ԃ������Ƃ����_�ł��A���{�̐N�w���^���A����^���̓���̔��W�̂��߂ɂƂ��Ă��A�d��ȉЍ����c�����ƂɂȂ����v�B |
 �i���_�D���ρj�@ �i���_�D���ρj�@ |
�@�ʂ����Đ�㎁�̂悤�ɎƂ߂�ׂ��ł��낤���B�������������̎d�������Z�N�g�I�Ȃ���ł���Ǝv����B�ނ���A���̓�������オ��������N�^���ɒ��ڂ��Ċw���݂̂Ȃ炸�N�J���҂̎Љ�I�ӎ���|�{����ϓ_����A�u���}�Ƃ��Ă̗��j�I�ӔC�v���Љ�}���ʂ������̂ł���A�ނ�������y�і����́A�V��������̌��������������������ۂɉ���̎w���������悤�Ƃ��Ȃ��������肩�A�Љ�}�n���g�D��������N�ψ���^���ɃZ�N�g�I�ɓG�������Ă������Ƃ����̂��j���ł���A���̂��Ƃ������Ȃ��ׂ��ł͖����낤���B
�@�Ȃ�قǔ���N�ψ���͂��̌�̉^���̐���オ��̒��Ŋe�Z�N�g�̃I���O������ȂǂŎ������������A�V�����n�Z�N�g���Ƃ̐��͂ɕ��A�u�S������v�̓Z�N�g���w������u�n�攽��v�ւƕϖe���Ă������ƂɂȂ����B�������A�����甽��N�ψ���̌������u�d��ȉЍ����c�����ƂɂȂ����v�Ƒ�������Ƃ����͔̂����I�ł͂Ȃ��낤���B���ɂ́A
�u�������Љ�}�v�̐^�������_�Ԍ�����悤�Ɏv����B�����܂Ő������ĕ����邱�Ƃ́A�Љ�}�͉E�h�E���h�������ς̒��ňӊO�Ɨ��j�I�Ȗ������ʂ����Ă��Ă���Ƃ������Ƃ����߂Ēm�炳���Ƃ������Ƃł���B |
|
�@�W���A�č��̃��T���[���X�ō��l�\�����N���A���҂R�S���A�����҂P�R�Q�����o���B�X�g�N���[�E�J�[�}�C�P�������[�_�[�Ƃ���u���b�N�p���[���䓪���A�č����ō��l����^���ƃx�g�i�����퓬�������ݎn�߂�B
�@�X�D�Q���A�s�w�A�i�O�h�n�j�E���s�{�w�A���ÁE�S���������\�҉�c�k����l�A�\���n�������������n�e�h�Q���A���ؔ�y�j�~���͓����W�J��\���킷�B
�@�X�D�R���A�s�w�A�i�O�h�n�j�����S�ɁA�R�`�又���P���E�O�S���w�����N�W��k�R�`�l�J�ÁB
�@�X�D�R���A���۔��ΐw�����̍ĊJ������ڂ����w��\�҉�c�k�����l�A�S�w�A�i�����n�j�E�S���A�E�������O�\�ܒc�̎Q���B
�@�X�D�R�|�S���A�S�w�A�i�v�}���n�j��l�\����ρk�{���斯�فl�A�v���I���퓬���W�J�E���؏���y�j�~��������B
�@�X�D�P�P���A����N�ϑ���S����\�҉�c�k�����l�A�x�g�i������E���ؔ�y�j�~�������j������B
�@�X�D�P�Q���A�S���������s�ρi�����n�j��ÁE���؏���y�j�~���S������s���A�����W��k���C�u���l�ɑS�w�A�i�����n�j�ܐ疼�Q���A�����w�܂Ńf���B
�@�X�D�P�S���A�������n�e�h�A���؏���y�j�~�S������s���A�����W��k�����J�����l�ɐ疼���W�A����J�����܂Ńf���A�@�����ƏՓ˂������ߕ߁B
�@�X�D�Q�P���A����o�ϑ�w�Ŋw��l�グ���Γ����B�X�D�Q�Q���A�����̐����q��ŐV�w�����Ǘ��K��ɔ��̃X�g���C �L�˓����S���I�Ɋw���������������Ă���B�������|�R�`��D�����̐���A�w�ٓ����|���u�ЁD�����D�Q�n��D������D����D����A�w��l�グ�|�c����w������A���w�ڍs���Γ����|����o��A�ړ]���Γ����|���k��A�������̎����|�@����B
�@�X�D�Q�Q���A�����F�D�����ÁE���������E���؏���y�j�~���S�������N�W��k����J�쉹�l�A�S�w�A�i�����n�j�甪�S���Q���A�����w�܂Ńf���B
�@�P�O�D�T���A�Վ�����J��`���A�u���؏���y���Α����N�W��v���J�������n�P���l�̊w�����Q�������B���؏�Γ����ł́A���۔�������c���ĊJ���ꂸ�A�Ћ��̋������������炸�A�S���I����^���͑g�D����Ȃ������B
�@�S�w�A�i�v�}���n�j�E�s�w�A�i�O�h�n�j���ÁE���؏���y�j�~�S������s���A�����W��k�Ō����l�ɓ�疼���W�A�����J�����܂Ńf���A�А��n�J���҂ƍ���������f���A�Q�@�c�ʑO���荞�݂œ�\���ߕ߁A�W��A�O�h�E�v�}�����h�Փ˂���Ԃ��B�V�O�h�n�̘J�E�w�R�O�O�O��������f���B�ȍ~����ɐ��𑝂��Ă����P�`�Q�����K�͂̓����ւƔ��W���Ă����B���̍�����@�����̃f���K�����������Ȃ�A�f�����̗������T���h�C�b�`�ŃW�������~������
��ɕ��i���Ă������ƂɂȂ����B
�@�S�w�A�i�����n�j�́A���؏���y�j�~���S������s���A�����W��k����J�쉹�l�Ɏl��Z�S���Q���A�����f���B
�@�P�O�D�P�Q���A�S�����s�ρi�Љ�}�n�j��ÁE���؏���y�j�~���S������s���A�����W��k���������l�ɎO�h�n���S�Ɋw�����ܕS�����W�A����c�ʑO�Ŕ���N�ςƂƂ��ɍ��荞�݁A�\�㖼�ߕ߁B
�@�P�O�D�P�R���A�����w��\�҉�c��ÁE���؏���y�j�~���S�s�w���N�W��k����J�쉹�l�A�����n��ܕS���Q���A�����f���B
�@�P�O�D�P�T���A�S�w�A�i�v�}���n�j�E�s�w�A�i�O�h�n�j���ÁE���؏���y���ӑS������s���A�W��k����J�쉹�l�ɐ�ܕS�����W�E����f���B��A�����N�ώ�Â̌��N�W��ɍ����B����N�ψ�����㏉�̑S���N�����N�s���B�V�O�h�n�Q�U�O�O�����n�߁A�P���V�V�O�O��������c�ʑO���荞�ݓ����W�J�A�W�O�U�O�f���łP�V���ߕ߁B���s�{�w�A���N�W��k�~�R�����l�ɐ疼���W���s���f���A�O���ߕ�17�@�s�w�A�i�O�h�n�j�E���s�{�w�A���ÁE�S���������\�҉�c�k���u�Б�l�A��Z�E���S���[�l�X�g���j����A���s�ς������B
�@�P�O�D�Q�X���A���؏���y���ӑS������s���B�s�w�A�V�T�O�O��������փf���B
�@�P�O�D�Q�Q���A�؍����A��x�g�i���ɁA�Ő��s�����u�ҌՎt�c�v��h���B�A�����J�̗v���ɂ��x�g�i���h���������́A�I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h�A�t�B���s���ȂǂV�J���ɓo�����B���ł��؍��͍ő�K�̖͂�T���l��h�������B
�@�P�O�D�Q�T���A�S�w�A�i�v�}���n�j�E�s�w�A�i�O�h�n�j���ÁE���؏���y�j�~�S������s���A�����W��k����J�쉹�l�ɎO�疼���W�E����c�ʑO���荞�݁A���s�{�w�A���N�W��k�~�R�����l�ɐ疼���W�E�s���f���B
�@�P�O�D�Q�X���A�P�O�D�Q�X�S���[�l�X�g���s�ώ�ÁE���؏���y�j�~�S������s���A�����W��k����J�쉹�l�ɎO��ܕS�����W�E����f�����A�S����\��J���Ŕ��疼�Q���A�O�\�Z���ߕ�
�@�P�O�D�R�O���A�S�����s�ρE����N�ϋ��ÁE���؏���y�j�~����s���k����J�쉹�l�A�А��n�w���O�S���Q���A���d�F���܂Ńf��
�@�P�P�D�P���A�S�w�A�i�����n�j���؏���y�j�~�S������s���A�����W��k����J�쉹�l�Ɏl�疼�Q���A�����̌�A�������s�ώ�Â̏W��ɍ����B
�@�P�P�D�T���A����N�ώ�Â̓��؏���y�j�~��s�w�w�������N���k����J�쉹�l�A�s�w�A�i�O�h�n�j���S�ɎO�疼���W�i�P���V�疼�Ƃ�����j�A����ɂ킽�荑��f���E�Q�@�c�ʑO���荞�݁A�ꕔ�͋c�ʓ��ɓ˓����l�\�ߕ߁B���s�{�w�A���N�W��k�~�R�����l�ɐ疼���W�A�s�����O���ō��荞�݁E�l���ߕ߁B
�@�P�P�D�T���A�S�w�A�i�����n�j�O��ܕS���A���؏���y���ō����f���B
�@�P�P�D�U���A�S�w�A�i�v�}���n�j�E�s�w�A�i�O�h�n�j�A���؏��O�@���s�̑��ɋً}�R�c�s���A�O�疼������J�쉹�Ɍ��W�E����f���A�e���ŋ@�����ƏՓˁA��A�S�����s�ώ�Â̏W��ɍ����A�ēx����f���őߕߎҎO�\�O���B
�@�P�P�D�U���A�������s�ώ�ÁE�ً}�R�c�W��k�����J�����l�ɑS�w�A�i�����n�j�l�疼�Q���A�����f���B
�@�P�P�D�X���A���؏�s�̌��̖\���ɍR�c���ĎЋ��̈���������������A�S���R�Q�X�J���łQ�R���l������B�����ł͂P �W���l�̑�W��ƃf���B�����n�P���T�O�O�O�������W�����B�O�h�n���S�Ɏl�疼���A�����n�̃s�P��˔j���Ǝ��W��A����f���łT�P���ߕ߁B�A�����]�̐��ō���f���W�J�B
�@�P�P�D�X���A���{������w����A���U�U�N�x�̊e������w�̊w��ςP�R���l�グ����Ɣ��\�B
�@�P�P�D�P�P���A�S�����s�ώ�ÁE�ً}�R�c�s���A�����W��k����J�쉹�l�ɎO�h�n���S�ɓ�疼���W�E����f���A���U�n�����w����Ăуf���A�b�苴�t�߂ŋ@�����ƏՓˁE��\���ߕ߁B
�@�P�P�D�P�Q���A�S�w�A�i�v�}���n�j�E�s�w�A�i�O�h�n�j�A���؏��O�@���s�̌��R�c�W��k����J�쉹�l�ɓ��ܕS���Q���A����f���A�̂����J�x�������œ����w�v���b�g�z�[�����荞�݁E�W��A��\���ߕ߁B
�@�P�P�D�P�R���A���؏���y�j�~�E�Ћ�����s���A�����W��k���������l�ɖ����n���疼�A�������n�e�h��疼�Q���A����f���E�����ߕ߁B
�@�P�P�D�P�S���A�w��\�҉�c��ÁE���؏���y�j�~���N�W��ɖ����n���ܕS���Q���A�����f���B
�@�P�P�D�Q�U���A���؏���y�j�~�E�Ћ�����s���A�����W��k���������l�ɖ����n��疼�A�������n�e�h��ܕS���Q���A����f���E�����ߕ߁B
| �y����Ţ�w�ٓ�������R���z |
�@�P�P���A���̍����瑁��Ŋw����ق̊Ǘ������Ƃ��Ċw�ٓ������R�����Ă������ƂɂȂ����B���̍�����ł́A�R�h�C��������}���Ă����B�O�h�Ƃ́A�v�}���h�ƎА�����h�Ɩ����h�ł���A�v�}���h���ꕶ�D���A�����n������D��@���A���̑��͎А��𒆐S�Ƃ����O�h�n��������s�����������Ă����B�e������ƕ����c�̘A����D�T�[�N�����c��D�����D����c�Վ��s�ςȂǂɂ���Ģ�w�ً�������������ꂽ�B�c���ɂ͑�����F(��ꐭ�o�D�А�����h)���A�C�����B
�@�P�P�D�R�O���A�{���O�R�c�W�������A��������{�i�I�ȓ������J�n����Ă������ƂɂȂ����B������擯�u�Б�ł��w�ٓ������u�����Ă������A��w���ǂ̏����ɋ���Ì����Ă������A�����l�w���ȉ��̗�����Ǒ��͋����I�ł���A�w�������}�i��`�I�ɑΉ����Ă����点�Ă������ƂɂȂ����B�P�Q���ɂȂ�ƒc�������荞�݁��@���������ւƔ��W���Ă������B
�@�����������Ԃ̒��A�~�x�݂�O�ɂ����P�Q�D�Q�O���A�w��̑啝�l�グ�����肳��A��l�w���́A�L�҉�̐ȏ㢎��Ɨ��̒l�グ�͐V��������ł���A���N�Ƃ͊W������A��w�����N�S���������Ă��A���Ɨ��͒l�グ���飂Ɛ��������B���哖�ǂ̔��\�����l�グ�Ă͑啝�Ȃ��̂ł���A���w���A�{�ݔ�A���Ɨ����ŕ��ςT�V���̒l�グ���ƂȂ��Ă����B���U�U�N���X���瑁��͕����̂�ڂɂȂ��čs���B |
�@�P�Q�D�R���A�������n�e�h�ܕS���A���S�^���l�グ�ɔ����ē����w�\���ŏW��E�f���A�l���ߕ߁B
�@�P�Q�D�S���A���؏���y�j�~�Ћ�����s���A�����W��k����J�쉹�l�ɖ����n��疼�Q���A�������n�e�h�ܕS���A����f���ŎO���ߕ߁B
�@�P�Q�D�U���A�w��\�҉�c��ÁE���؏���y�j�~�������N�W��ɖ����n�ܕS���Q���B
�@�P�Q�D�V���A����N�ώ�ÁE���؏���y�j�~����s���A�����W��k����J�쉹�l�ɔ������n�e�h�Z�S�����W�A����c�ʑO���荞�݂ŏ\�㖼�ߕ߁B
�@�P�Q�D�P�P���A�����}�Ɩ��Г}���A�Q�c�@�ŁA���؏���y�����s�̌��B
�@�P�Q�D�P�V���A�s�w�A�i�O�h�n�j��y�������j�~�S�s�ً}�s���A���������Ɏ��S�����W�A�H�c�X���ŋ@�����ƏՓˁA�Z���ߕ߁B�Ŗ��K�؎��͑j�~���������g�܂�A�H�c��`�t�߂łP�O�O�O�����@�����ƏՓˁB
�@�P�Q�D�P�W�|�P�X���A�s�w�A�i�O�h�n�j�E���s�{�w�A���ÁE�S���������\�҉�c�k����l�A�Z�S���Q���A���ؓ����̔s�k���m�F�A�\���n�s�Q���E�v�}���n�r���ޏ�B
�@�P�Q���A���n�����É��Ŋw���W��B�P�W�O��w�A�R�T�O�������Q�T�O�O�����Q���B
�@���̔N�A�D�����������{�o�ς��ꎞ�I�ɕs���ɂ����������B���̔N�̂f�m�o�����������͂T�D�P���ƂU�O�N��O���̕��ϐ������P�P�D�V���Ɣ�r���đ啝�ɗ������B���{�͐�㏉�߂Ă̐Ԏ����s���A�����哱�ɂ��s��������ʂ����B���̌�A�U�O�N��������ďd�H�Ɛ��i�̗A�o�哱�ɂ��A���{�o�ς͑�̍��x�������Â���B
�@�U�T�N�P�P���A���{�e���r�Ɂu�P�P�o�l�v���o�ꂵ�C�ԑg�ɂȂ�B
�@�������́A�u��V�����̂Q�A�S�w�A�̓]��_�����v�ɋL���B
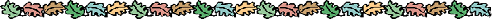



 (���_�D����)
(���_�D����)


![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)