| �P�X�U�O�N |
���w���^����T�����̂R |
| ��U�O�N���ۓ�����A�u���g�n�S�w�A�̖��W�J�Ɩ����n�̕����� |

�@�X�V���^�Q�O�Q�R�i�����R�P�D�T�D�P�h�a����/�h�a�T�j�N�D�P�D�S���@
�@������O�́A�u��T�����̂Q�A�V�����n���u���g�E�v�����n�S�w�A�̔��W�v�ɋL���B
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
| �@�T�X�N����U�O�N�ɏ����ɂ����ē��Ĉ��ۏ��̉����肪�A�}���ɐ��Ǖ��サ�������B���{�����}�́A���̂��т̈��ۉ���������̑Εď]���I���i�����P����ׂ̉���ł���Ɛ�`�����B�����������́A�V���ۏ��́A�ČR�̔��i�v�I���{��̂Ɗ�n�̑��݂�e�F������A�V���ɓ��{�ɌR���͂̑����Ɠ��ċ������̋`���킹�A����ɂ͌o�ϖʂł̑Εċ��͂܂ŋ`���Â���Ƃ����_�ŁA���Љ�̍��ӂł��錛�@�̑O�����_�ƂX���Ɉ�w����s���Ȃ��̂ł������B�P�X�U�O�N�A���ۉ���̔N���}�����B���Ĉ��ۏ��̉���������̂������Ȃ��̂�������Đ��ǂ����悢�旬�������n�߂�B |
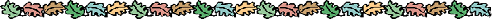
| �y�P�X�U�O�N�̓����z�i�����̊֘A�����j |
| �y���Ĉ��ۏ��̉�����̐��Ǖ���z |
|
�@ �T�X�N����U�O�N�ɂ����āA���Ĉ��ۏ��̉����肪�A����ɍ����I�ȉۑ�ƂȂ��ĉ����o����}���ɐ��Ǖ��サ�������B���Ĉ��S�ۏ���i�����j�́A�P�X�T�P�D�X���̃T���t�����V�X�R�ɂ����đΓ��u�a���Ɠ����ɒ��ꂽ���̂ŁA�A�����J�̑Γ��h�q�`���L���Ȃ��܂܂ɓ��{�ɃA�����J�̌R����n�����e������e���܂ނ��̂ł���A�A�����J�哱�̐�����Z���ɑтт���̂ł������B���{�̖h�q���S�̒��g�����炩�łȂ������B
�@���{�����}�́A������s�������Ƃ݂Ȃ��āA���Ă̊W��Ж��I�Ȃ��̂�����o�������A���̂��т̈��ۉ���������̑Εď]���I���i�����P�����含�����߂�ׂ̉���ł���Ɛ�`�����B�����A���{�����}�́A�P�X�T�T�N�A���R���t�̎����ɏd���O�����K�Ă����ݖh�q���ɂ������������ƒ�Ă��Ă���B�P�X�T�V�D�U���ɂ͊ݎK�Ď��ɁA�A�C�[���n���[�哝�̂Ɖ�k���A���ۏ�����̗v�]�����������Ă���B�P�X�T�W�N�̓��R�|�_���X��k�̌���ςݏd�˂Ȃ���A���{�̖h�q�ɉ������̐������悤�Ƃ��Ă����B���ꂪ���{���̗v�����A�����J�̑_���ł������̂��͐^�����M�̒��ł���B
�@���{���h�^���́B���{�����}�̘_�������ۂ����B�V���ۏ�A�ČR�̔��i�v�I���{��̂Ɗ�n�̑��݂�e�F������A�V���ɓ��{�ɌR���͂̑����Ɠ��ċ������̋`���킹�A����ɂ͌o�ϖʂł̑Εċ��͂܂ŋ`���Â���Ƃ����_�ň�w���ċٖ����Ɍ��������̂ł���A�������Љ�̍��ӂł��錛�@�̑O�����_�ƂX���Ɉ�w���邱�Ƃ��莋�����B
�@���̎��ݎ́A�����̂Ƃ���̘_�c������ċ����I�ɓ��Ĉ��ۏ��̉���Ɍ��������Ƃ��Ă����B���ꂪ������]�v�ɐ���ł������ƂɂȂ����B�P�D�U���A���R�O���ƃ}�b�J�[�T�[��g�̊Ԃ̓��Ĉ��ۏ���������I�����A�ݎ��n�Ă��Ē������ƂȂ����B���ɖ������ꂽ�ƂȂ�ƁA���t�̐ӔC�ɂ���ĊO�����{�Ƃ̊ԂŒ����������Ă͂��̎��_�ŗL���ł���B����ɂ͢�C�����͂Ȃ���Ƃ���̂��ʐ��ł���A���F���邩�A���Ȃ����̓�ґ��ꂵ�����\�͖����B���āA�ǂ����邩�Ƃ������Ƃ��ۑ�ƂȂ��ċ}���ɕ��サ���B
|
|
|
�@�P�D�P���A�u���g�͋@�֎��u����v��n������B�P���ŁA�u���E�v���̐V���ȓW�]���@���{�J���ҊK���̊v�����̂��߂�����}�i����@�P�X�U�O�N���ɓ������đS�Ă̋��Y��`�҂ɑi����v�\�B�u���g�̐����͌��C���������ł��͂�~�܂�Ȃ��B
|
| �y�u���g�̑S����\�҉�c�ŁA�����L�����ݖK�đj�~�������N�z |
|
�@�P�D�R���A�����L�����A�u���g�̑S����\�҉�c�����W�B���n�H�c�����ɂ��ݖK�đj�~������P�Ƃł��s���ƒ�N�����B�u�u���g�̑S�͗ʂ�q���������Ƃ��Ď��g�ށv���Ƃ𖾂炩�ɂ����B����Ɋ֘A���āA�����G�v���́u�V�����̈�Y�v�����䗠�𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@�u��������S�w�A�̐�p��c�̖͗l�ɂ��āA�u���g���n���ψ���L���ł���������o�͎��̂悤�ɏ����Ă���B���̎��ɂ́A�����S�w�A�ψ����͑ߕ߂���Ă��܂��āA���L���̐�����v����s�߂Ă����B�����́A�w�ő���ʁA�ŏ��]���x�Ƃ����K�������̐�p�I�������̂āA�Ȃ�Ɓw�ő�Ō��A�ő�]���x��p���Ƃ����B�����ł���B�����A���̖����Ȑ�p���A�ނ̌�����o��Ɗv���I�p�Y��`�ƂȂ����̂ł���B�����ƁA�Ȃ������q�w�������Ƃ͊��S�ɐ����Ă��܂����B�ނ́A�w�j�̒��̒j�x�ł������B�ނ̐�p�́A�S�w�A�����̑S���ߕ߂������čs���V���b�L���O�Ȃ��̂ł������B
�@����ɑ��āA����́A�w�w���R�v�^�[���`���[�^�[���A�ݎ̔�s�@�ɐƃ����K�𓊂��܂�����̔�s�@�͔�ׂȂ��Ȃ�x�ƑΈĂ��o�����B�]�������Ȃ����悤�Ƃ����Ăł���B�Ƃ��낪�A���̉�c�ɂ͏��q���p��w�̏��q�w���������o�Ȃ��Ă��āA�ނ̒�Ăɔ������B�w�|���i����̃y���l�[���j��Ĕ��B���B�̓Q�����ł͂Ȃ��A��O�^�������̂�x�Ɖ��F�����ŃM���@�M���@����A�V�~�^�P�i�����̒ʏ́j���w�|���Ăł͂Ȃ��A���̒�āA������`�̃��r�[�𐔕S�l�Ő苒���邱�Ƃł����x�ƍ̌����Ă��܂����B���q�w�������́w�L���|�x�Ɗ������������v�i�u���L�O���W�v�j�B |
|
�@�P�D�U���A�S�w�A�����ρA���Z�H�c�������m�F���S���I���O�n�߂�B�P�D�W���A�S�w�A���L�ǂ́A�u�c���ꂽ�����H�c�����̂��߂Ɏ��͂�s���v�\�B
�@�P�D�U�|�P�P���A���ۑj�~�w����������A������c�̕��j�ɏ]���ݓn�Ăɍۂ��H�c���������ƌ���B�P�D�W���̓����n�]������͎^�۔����ł������B
�@�P�D�P�O���A�S�w�A�A�Њw���A�Љ�}���a���u��L�u�A���{���a�ψ���L�ǁA�n�]��C������L�u�ɂ���āu�H�c�f�����s�ψ���v���������ꂽ�B�n�]�튲�L�u�ɂ́A�S���A�S����ʁA�S���J�A���ݘJ�A���w�����A����o�ł��̑������W�����B
�@�������āA�u���g���߂��������h����̌������������邩�ɂ݂������A����������Ɍ������ĂȂ�ӂ肩�܂킸�j��H����s�����B�����]�����n�]��{�C�ł��낤�Ƃ��Ă��邩��A�͂ˏオ��ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ����������f�b�`�グ�āA�}���������Ċe���j�ɏ�肾�����B���̂��߂ɁA���s�ψ���͑S�w�A���Њw���������Đ���������Ċ������Ă��܂����B
| �y����������c���A�ݎn�đj�~�����ňÓ]����z |
�@�P�D�P�Q���A����������c�́A�H�c�R�c�W����s�ψ�����������邱�Ƃ����߂��B���̌���͎Љ�}�̐���ɓ`����ꂽ���A�ނ́A��}�Ƃ��ẮA������c�̐����͂���邱�Ƃ͏o���Ȃ����A�c���l����O�ƌ��т��Ċ�������͓̂��R���B�傢�ɂ���Ă��ꣂƌ��サ���B�����̑Ή��ɔ�ׂ�ƁA�Љ�}�̂炵���ǂ��ł������Ɖ]����B
�@�������č�����c�͈�x�͉H�c���������肵�����A���E�{���R���r�̗�����������H�c���������ɔ��Ύw�����n�߁A�������s���̓}�����Ăт��Ģ���]���{�C�ɂȂ��āA���n�]�����낤�Ƃ��Ă��邩��A���ˏオ��ׂ��łȂ���Ɯ����������A���������ϒ��w���ŋ������c��A�n�拤�����K�^�K�^�ɐ�����ꂽ�B�������ē�������Ȃ����ƂɂȂ����B���ǁA�����Ƒ��]���H�c�����ɐK���݂��n�߁A������c������Ŕی�����邱�ƂɂȂ����B |
| �@�P�D�P�Q���A�x����������ێO��́A�S�w�A���L�ǂɕ�������͑j�~���v���Ƃǂ܂�悤�ɣ�ƈٗ�̐����ɗ��Ă���B |
�@�P�D�P�S���A���{���V���ۂ��t�c����A��\�c�K�Ă��P�T���ߑO�W���ƌ��肵���B������c��Ấu�n�Ē��R�c�c�������v�������E�n����\�Q�疼���W�߂ĕ�������ŊJ����A�S�w�A��\�́A�n����\�̘J���҂ƂƂ��ɉH�c������v���B������͉�ꍬ���������ɑ��Ő�A�H�c�������ۂ�������肵���B�S�w�A�̌������R�c�͈��|�I�ȋ����āA���͍����Ɠ{���̂����ɎU��錋�ʂɂȂ����B
| �y�������A�ݎn�đj�~�����̉��a�������ė��w���z |
|
�@�P�D�P�S���A�A�J�n�^�́A��P�U���ɂ̓f���̌`�ʼnH�c�������s��Ȃ��Ƃ��鍑��������c�̌�����A������x������䂪�}�̕��j�́A�����̖��吨�͂ɂ���Ď�����Ă��飐����\���Ă���B�P�D�P�U���A�ݑS���c�̓n�đj�~�̂��߂̑�O�^���v�悪���Ă�ꂽ�B���̎��A�{���n�����}�����͐M�����Ȃ����Ƃ����ǂ��A�ݑS���c�̓n�Ăɂł͂Ȃ��A�n�đj�~�����ɖґR�Ɣ��������āA�S�s�ψ��E�n��ψ������āA�g���̐������
�͂������Ƃ����j��������B
�@�u�A�J�n�^�D�U�O�D�P�D�P�R�v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@�u�i�ݎ̓n�ďo���ɍۂ��Ắj�S���吨�͂ɂ���đI�o���ꂽ��\�c�𒁏����R�ƉH�c��`�ɑ���A�݂̏o���܂���܂Ől���̍R�c�̈ӎu��ނ�ɂ��������邱�Ɓv�B |
 �i���_�D�����j�@�����̊ݎn�đj�~�����ɑ����k�ٍl �i���_�D�����j�@�����̊ݎn�đj�~�����ɑ����k�ٍl |
| �@����͕s�v�c�ȕ��͂ł���B����Ȃ��Ӑ}�����t�ł܂Ԃ��Ă���B������x���������҂����₽�Ȃ��B����͂Ƃ������A���������k�ق�J���A���a�ȑ���o�����j�����������ł��o���Ă���B |
|
| �y���]���A�ݎn�đj�~�������~���@����A�v�������H�c�����ɔ�����z |
|
�@���]���H�c�����̎��g�݂̒��~���@���肵���B�v�������Њw�����Δh�̖��ʼnH�c�����ɔ������B���ۉ���j�~������c�́A��������͢��K�͂ȃf���Ŋ݈ȉ��̑S���c�̓n�Ă�j�~���飕��j�����߂Ȃ���A����O�ɂȂ��āA�Ћ����}�D���]�����Ȃǂ̔��f�ł�����������A����オ�鉺�����������ɂ��������B��N���̢�P�P�D�Q�V�̍�������Č����Ă͍��飔z������ł������B����𢊲���̗��裂Ɠ{�邱�Ƃ͏o���Ă��A�s���Ŏ������Ƃ͏o���Ȃ������B
|
| �y�S�w�A�����P�R�Ŋݎn�đj�~�����Ɍ������z |
|
�@�S�w�A�w�����͗B�ꂻ�̓{��������A���ۍs���Ŏ������Ƃ����B���̎��u���g�͕K���ɂȂ��ď��ǂ݁A���ʂ���_�����B��p�@���ł͑S�w�A���ɕ���X�����[�܂邱�Ƃ����蓾���B�������A�u���g�͎��̂悤�Ɍ��_���܂Ȃ�����������B���̂悤�ɋL����Ă���B
| �@��Ћ��̗��肪��O�I�ȓ{����ĂыN�����Ă��錻��ł́A��������Ă��w�����オ��x����͂Ȃ��B�ō��̓����`�Ԃ��Ƃ�ׂ����B�u���g���S���ߕ߂���Ă��A����͈��ۓ�����i�߂邱�ƂɂȂ��Ă��B������邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ���B |
�@���̎��̂��Ƃ𓇎��́A��N���̂悤�ɏq�����Ă���B
|
�@��S���e�n���瓯�������W�߁A�w�Ǒg�D�𗇂̂܂܂Ԃ������̓�����A�����͏]���̏펯���炷��Ζ`����`�Ɣ����ɒl������̂ł������낤��A�����������p���猩��Ȃ�ד����̂��̂ł�������B
|
�@�����q�q��e�W�u�l�m�ꂸ���܂�v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@�u���ʂ̈��ۓ����|����́w�P�U���̊ݓn�Ă��H�c��`�őj�~����I�x�ł��B�ܘ_�A�P�U�����ɂ͏o�����Ă��܂��ł��傤�B�ł��A�ꍑ�̎�����ɏo������̂��A�����̐l���ɂ���āA�����Ԃł��x�ꂳ����ꂽ�A�Ƃ���D�D�D�D���̂��Ƃ͍��ۓI�ɉ]�X�D�D�D�D�ł͂Ȃ��āA���{�̘J���ҊK���Ɛl���ɂ����A�����i����ł��傤�B���ۂ�{���ɑj�~���铬������낤�ł͂Ȃ����A�ݐ��{��œ|���悤�ł͂Ȃ����A�ƁB�����āA���{�ƊK����œ|���铬���ɐ^���Ɏ��g�����ł͂Ȃ����A�ƁA���͌Ăт��������̂ł��v�B |
|
| �y�ݖK�đj�~�H�c�����ŁA�S�w�A����`���r�[�ɓ˓��z |
|
�@�S�w�A�́A�Ћ��̌�������j����ڂ��ɂ����A�ݓn�đj�~�H�c������Ǝ��s���Ƃ��Ď��g��ł������Ƃ����肵�A���ˏオ����������悤�Ƃ�������̓������͂˂̂��ĎP���̊e������ɋً}�����w�߂��A�S������R�c�c���㋞���n�߂��B
�@���������Ή^��������悤�Ɨ\��𑁂߁A�P�U�������ɂЂ����ɉH�c����o�����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��`������B�u�������ł͒x���I�@���邾�I�@�G�̋@��𐧂��đ����H�c��`�苒���ׂ��I�v�Ǝw�j�������B
�@�P�D�P�T���[����S�w�A�攭����V�O�O�����H�c��`���r�[���}�P���苒�A���荞�݂��J�n�����B�x�����Ƃ̓��������ł��������B�x��ĂS�T�O�����삯���A�R�O�O�����x�����̑j�~����j���č��������B�V���߂��ɂ́A��`���r�[�ɢ���Y��`�ғ�������זE��Ȃǂ̊����Ȃт��A�f�����Q�������B�㑱���������X�ƉH�c�։H�c�ւƌ��������B��t���ɂ͐�]����̂݁A��̓W�]�͂P�D�P�U�̉H�c�����J����飂Ƃ������ӂ̉��ɂȂ��ꂱ��ł������B
�@�S�w�A�����́A�x�@�̏P���ɔ����āA�o�����r�[�ւ̊K�i�Ɋ���C�X�Ńo���P�[�h��z���A�H���ɘU�邵���B����ɑ��A���ߑO�R���Q�O�O�O���̋@�������u�܂̃l�Y�~�v�ɓˌ������B���̓����ŁA���c�A�ЎR�A�É��u���g�������܂߂������ψ����A��w�A���s���A�S�w�A�̂V�V�����������ꂽ�B�����q�q���ߕ߂���Ă���B
�@���T�����A�X�ɑ������w���ƘJ���҂͖�Q�O�O�O���ƂȂ�A�U��o�����J�̒����ꋞ�l�����Ō������f����W�J�����B����ɋ@�������˂����ݖ閾���̗����ƂȂ����B�����̕����҂��o���B���̊Ԋݎ͗����ʗp�傩���`�ɓ����ї������B�ȏオ�T���ł���B������u�H�c�f�������v�Ɖ]���B���̉H�c�����������A���̌�̑S�w�A�̍s���ތ^���߂邱�ƂɂȂ����A�܂�q�i�^�ɂȂ����Ƃ����_�Ō��������Ƃ��o���Ȃ��B
�@�����͎��̂悤�ɐ��ʂ��m�F���Ă���B
| �@���X���������a���I�ȓ����ƍ�����c�����z���Đ킢�A�ݓn�ĂɑŌ���^������B |
| �@�u�S���V������O�����̌��o�������B���炩�Ɏ������u���g�̓����ɂ���āA�����ɂƂ��āA���ۓ����ɂƂ��āA�l���^���ɂƂ��ė�����������܂ꂽ�Ƃ����m�M�ł���B���炭�ЁE���ɂ���ė}������Ă����J���ґ�O���A����������j�����S�w�A�̍s����ʂ��āA�V�����������͂Ƃ��Ẵu���g�̑����͂����茩���ɈႢ�Ȃ��Ƃ��������ł���v�B |
| �@����B�́A�����Ƃ������̂��A�����Đ����Ƃ̗\������悤�ȑQ�i�I�Ȏd���œ������̂ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă����B����������������Ƃ��A��X�͕ێ�I�ȑ�O�����������o�������A����͂����Ȃ���̂������z���Đi�ނ��̂��Ɖ]�����Ƃ��m�M���Ă����B���̋@����悤�Ȑ����g�D�A����̐��͊g���ׂ̈ɂ̂ݓ����𗘗p���A����������~�߂���A���̂̂����肷��悤�Ȋ������}�|�܂��ɂ��̂悤�Ȃ��̂ɔ��t�����Ď��B�̑g�D���������̂��B�����炱���A��O�̗��ꂪ�܂��ɂ������������(�قƂ�)���Ƃ���Ƃ��A���B�͓q�����̂��B����Ɋ������ʑg�D�́A���ꂾ���Ŏ��ɒl������̂Ȃ̂ł��飁B |
| �@�u�u���g�ׂ͒ꂸ�A���Ԃ͂Ƃǂ܂�Ȃ������B�u���g����Ђ炢����́A���̃u���g���̂��̂�ۂݍ���Ŕ��W���Ă����v�B |
�@����c�v�ȒǓ��L�O���W��ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B���c���́B�Q���܂ōS�������B
| �@�����قǐT�d�Ŏv���[���A�P�O�N�ԓ}�w���҂Ƃ��Ă�����O�����Ȃ����x���ߕ߂��ꂽ���Ƃ̂Ȃ����c���A�H�c�����ł́w��Ƀp�N����ȁx�Ƃ̎w�����̌�����ǂ��ւ��A�����C�ɂȂ��ăf�����ɉ����A������̓W���Y�Ȃ��ɂȂ��Đ��܂�ď��߂ēؔ��ɓ���j�ڂɂȂ����̂��A���R�Ƃ͎v���Ȃ��B����܂ł̔ނ̎v���݂ɂ����Ă��܂��悤�ȔM�C���A�����̒��ɗO���Ă���̂�}���邱�Ƃ��o���Ȃ������̂ł��낤��B |
�@���o�́u���̗������v�̐؏��F�ҁA�Q�O�O�V�D�P�O�D�Q���t�����Q�u�w���^���v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@�u�ٗ�Ȑ�p�Ƃ�������܂ł����A���̎����ŁA�u���g���ٔ����鐭����ɖ��������Ȃ��v���[���[�ɂȂ������Ƃ͎��m�̒ʂ肾�v�B |
�@�ݖK�Ă��������Ƃ͂����A�S�w�A�̏\�����Ԃɋy�Ԍ����́A���O�Ɉُ�Ȕ������܂��N�������B���W�I�͐[��̎��������𗬂��A�O�d���u�����v���X�I�ɕ��B�Ȃ��ł��A�\�A�̃v���E�_�́u�݂̓J���V�J�������₭�������B����͉H�c�ɂ����鈤���҂̓����v���ƕ]���Ęb����܂����B�����̃A�J�n�^�́A�݂��u���ʂ肩��D�_�L�̔@���v���{���u�E�o�v����������Ȃ������̂́u���ۂɔ�����l���̐��_�ɂ����̂��v(1��17���j�Ɖ��ʂ��Ȃ��]�_�����B�@
�@�J���҂̂������ł��u���̓�����4�|5���ԂƂ������̂́A�E��ł͑S�w�A�̘b��ł������肾�����v(���葢�D�Ќ��u�H�c�̋�͔����������v)�Ƃ������Ԃ����o�����B
�@�����A������c�́A�\��ʂ����J�����W����J�Â����B�ߌ�P���A�T�疼���J���̏W������������A���������Q�O�O���̊w���ɂ���ĉ��d��苒����A������c�w�����͊w����J���҂��猃�������e����A���͍����̂����ɏI������B |
| �y���w���^���j�z |
�@�i���M�j
| �S�w�A���A60�N1��15���A�H�c��`�Ŋݎ̓n�đj�~������g�Ƃ��A��B�����20�l�قǎQ�����܂����B�ߕߎ҂������o���B��������w�A�̈ψ����Ƃ��Ď���ߕ߂��ꂽ�B���}��ԂŌx�����܂Ō쑗���ꂽ���A���������܂�20���Ԃقǂ��������B1��������s���̌x�@���ɗ��u���ꂽ�҂͊����Ă��܂�Ȃ������悤�����ǁA�킽�������u���ꂽ�x�����̒n���S�͒g�[�������Ă����B |
|
|
�@60�N1�����A���ő厖�����N�����B���@�������̒n���ɂ�������w�A���L�ǂ��H�c�����Ɋ֘A���đ{�����A�傫�ȑ����ɔ��W�����i60�N1��21���A���{��30�N�j�ł́u��厖���v�A���75�N�j�ł́u��w�A�����v�Ƃ��ďڂ����L�q����Ă���j�B���̂悤�ɏ،�����Ă���B
| �悭�����Ă��邪�A�����A��w�̋ߏ��ɂ���u�w�A�����v�ɁA�{�����������ƒm�点�������B�������܋삯���āA�w���̈��۔��̏�������܂މ����������������������o�����Ȃ��A�Ƃ������Ƃő{������{���̊w�����ɘA��Ă����ĕ����߂��B�{���ɍR�c����w�����ǂ�ǂ�W�܂��ė��Ď����ǖ{�������̘L���ɂ���肱�B��w�����W�҂������̂��߂ɐs�͂������A�{�����Ƃ̉����ⓚ�A���x�Ƃ̌��͏I���������B��ɂȂ��āA���x�@����������O�ɏo���A����ɑR���Đ���ɂ̓s�P�����B�������A�锼�����ɁA�@�������A����͕߂��Ă����̂ʼn��̛��̍�ݓ|���āA�w���ɓ˓����A�s�P��j��A�{�������ɍ��荞��ł���݂�Ȃ����ڂ��������āA�{������A��o�����������������������B���̍��͖����u��w�̎����E�w��̎��R�v�͐�ΓI�Ȃقǂɑ��d���ꂱ�����낤�Ƃ���p���A�C�T�͑�w���ɍs���n���Ă��܂����B�R�c���w���́A�x�@�̑{�����������Ƃ��Ɂu����J����v�ƌ������Ƃ����̂ŁA�������Njy����܂����B |
|
| �y�e�E�̔����z |
|
�@�����܂��ɂ��Ģ���_��͂��̑S�w�A�̓�����܂������ɂ����B�ǎ������l�͢�Ԃ�������Ɣᔻ�����B�}�X�R�~����ࢃn�l�オ��ǂ�(�����V��)�A��v���C�Ⴂ�ǂ�(�ǔ��V��)�A��Ԃ��\���V�(���o�V��)�A����N�U�w���^���ƣ(�����V��)�A������I�J�~�i���W�c�(�T�Ԓ���)�A��p�X�v���̎Q�d�{���(�T�ԓǔ�)���X�ƍ��]���ꂽ�B
�@�Љ�}�E���]�́A����s���𗐂��҂Ƃ��Ĉ��ۋ�����c����S�w�A�r���𐳎��Ɍ��肵���B�H�c������A�����́A�ĂёS�w�A���u�g���c�L�X�g�̒����s���E���v�������ҁE���吨�͂̒��ɑ��荞�܂ꂽ�G�̎��v�Ƃ��đ�X�I�ɔ����B�v�������A�u�Ꝅ��`�E�`����`�E�X����`�E�u�����L�Y���v�ȂǂƔ��Ă���B
|
�@�����A�ꕔ�̒m���l����́A�S�w�A��ˏo��������Ȃ����������g�D�̎w�����̂Ȃ��ɖڂ�����w�E���ׂ���Ă����B���ł����������Y���́A�S�w�A�����ۓ����̢�s�K�Ȏ��Ɩ������A��S�w�A�̂������ł���Ɣ������ĔM��ȃG�[���𑗂����B
�@���̐����������S�ɂȂ��āu���g�D�ւ̗v�]���v�𑗂��Ă���B�����ł́A���w���͔������S�w�A���u��Ȗ����̐��́v�Ɣ��f���Ă����B�������͂��̕���������ėl�X�ȗF�l�Ƙ_���ɂȂ�A�����x���h�́u���Y�}�́A�{���{�����Ă���悤�Ɍ����Ă��A���̂��������A�b�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����Ɍ��܂��Ă���v�Ƃ́u�s���̐_�b�Ɋ�M���v�̕ǂɓ˂����������Ə،����Ă���B |
| �y�H�c�����̖��Áz |
�@�H�c�����ŁA�u���g�y�ёS�w�A�̊������قƂ�Ǎ��������ߕ߂���Ă��܂��A���ۓ����̃��}�Ɍ������ߒ��ŏd��Ȋ�@�Ɋׂ����B�ێ߂�ٔ��Ɋւ��c��Ȕ�p�����O���ꂽ�B�������ɓ����L���������Ɂu���߂����v�Ɣᔻ���Ă���B
�@������ÂƂ���Ζ������܂ꂽ�B�卖�G�v���́u�V�����̈�Y�v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �������Ȃ���A��O���x���ł́w�u���g�������ɖ����m��Ȃ��l�X����̌���Ƌ����̃��b�Z�[�W��J���p�����������炸���Ă���x�A�w��ʂ̊����ߕ߂ɂ��S�炸�A�w�A���u���g�������₤�ɑ��銈���Ƃ����X�Ɓx������Ƃ������Ԃ����܂ꂽ�B���̂��߃u���g�́A�苷�ƂȂ���������������A�_�c�̑�ʂ�ɖʂ�����K���Ă̌����Ɉړ]�����B�����ē���́A�ӋC�g�X�ƑS���I���O�⓬���������B�ɔ�щ�����B���͓�����U��Ԃ��āA�w���N�����x��x�悤�Ȗʔ������X�̘A���ł������x�ƋL���Ă���B |
|
�@�P�D�P�V���A������c�S����\�҉�c���J�Â��ꂽ�B�w�������u��������Ȃ��������̂ɔ��Ȃ����߂�v�ƃ}�g�������悤�Ƃ������Ƃɂ������čR�c���܂��N�������B
�@�P�D�P�X���A�S�w�A�A���ے���E�s���e���ɍR�c���đS������s���A���ے���R�c�E�s���e�����ӑS���w�������N���A�����W��k�_�c�������l�A���ۉ��蔽�E�e���R�c�S���s�w���W��k�����ّ�l���S���ŏW��E�f���W�J�B
�@�P�D�P�X���A�V���ۏ���V���g���ɂ����āA�ݎƃA�C�[���n���[�哝�̂Ƃ̊ԂŒ��ꂽ�B�����Ă���ȍ~�̈��ۓ����́A����j�~�����y�j�~�ւƁA���̖ڕW���V�t�g�ւ����Ă������Ƃ�
�Ȃ����B�P�D�Q�Q�|�Q�U���}�́A�u��W�����v���J�Â��A�u���ʂ̈��ۓ����Ƒg�D�g��ɂ��āv�̌��c���̑��B�u���ۉ���ɔ����āA�A�����J���{�A�ݓ��t�ɍR�c���A����ɐ��肷�鏐���^����ϋɓI�ɑS���I�ȉ^���Ƃ��ēW�J�v���邱�Ƃ����肵���B
| �y�����̃g���c�L�X�g�ᔻ�Ɣ����I�������z |
�@�P�D�Q�R���A�A�J�n�^�́A��g���c�L�X�g�̒����Ɣj�h�@�ɂ��e����}�ɂ��ģ�Ƃ��������_���\���A�T�v��H�c�ɂ�����g���c�L�X�g�̒����s���́A�j�h�@�𐭕{�����߂Ď����o���A���吨�͂�e�����铹��Ɏg��������^������Ƃ��đS�w�A���U�������B
�@�m���l�ɂ���ĉH�c�����̑ߕߎ҂̋~���^�����n�߂����A�}�����́A�ߕ߂��ꂽ�w���̋~�ς����ۂ��A�ٌ�m�̎x�������𐧖��B���N�l�ɖ���A�˂Ă���}���̐�������͂���A�֍��E�|���E�吼�E�R�c�E�a�J
�Ȃǂ̐l�X�����N�l����艺����������Ȃ����ꂽ�B�����̒m���l�͌�X�}�����ɑ��錃�����ᔻ�҂ƂȂ����B |
 �i���_�D���ρj�@�U�O�N���ۓ����̍ۂ̋��Y�}�̉ʂ����������ɂ��� �i���_�D���ρj�@�U�O�N���ۓ����̍ۂ̋��Y�}�̉ʂ����������ɂ��� |
|
�@�������͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@��P�P�D�Q�V����P�D�P�U�Ɏ��鏏��ɂ����āA�����G�l���M�[�����߂��œ��������̉ʂ����������͑傫�������B����́A���̎��X�̏�ɂ���ėh�ꓮ�����]�E�Љ�}�w�����̎p���Ƃ͈���āA�܂��Ɉ�т��Ă����Ƃ����Ă悢�B�����Ă��̊�{�p���͈��ۓ����̑S���Ԃ�ʂ��āA�s���ł�������B |
|
�@�P�D�Q�P���A���ۑj�~�w����������A�H�c�����̋~���E�S�w�A�ւ̔j�h�@�K�p�R�c��������B
�@�P�D�Q�S���A�l�������O�́A��R���������̒���́A���{�R����`�����ɕ����������Ƃ̂��邵�ł���A���{�����ɃA�����J�̐N���I�ȌR���u���b�N�Ɍ��R�ƎQ���������Ƃ̂��邵�ł��飂Ƙ_�]�����B
�@�P�D�Q�S���A�ݑS���c���A���B�����}���P���T�O�O�O���Ŋ��}�W����J���Ă���B���̓��Љ�}�E�h�̐������L�炪�Љ�}�𗣓}���A�V�}�Ƃ��Ė���Љ�}�i���Г}�j����������Ă���B�ψ����ɐ������L��I�o�B����{��`�ƍ��E�̑S�̎�`�ƑΌ����飂Ƃ����j�̂��f�����B�������������I�G�|�b�N����O�ɂ��Ă̎Љ�}�̕��͎��R�ȗ���ƌ��������A���ǂ̍������ɂ��v��I�ɍ��o���ꂽ�Љ�}�̂Ђ��Ă͈��۔��Γ����̎�̉�����ł������B
�@�P�D�Q�S���A�Љ�}�E�h�̐������L�炪�Љ�}�𗣓}���A�V�}�Ƃ��Ė���Љ�}�i���Г}�j����������Ă���B�ψ����ɐ������L��I�o�B����{��`�ƍ��E�̑S�̎�`�ƑΌ����飂Ƃ����j�̂��f�����B�������������I�G�|�b�N����O�ɂ��Ă̎Љ�}�̕��͎��R�ȗ���ƌ��������A���ǂ̍������ɂ��v��I�ɍ��o���ꂽ�Љ�}�̂Ђ��Ă͈��۔��Γ����̎�̉�����ł������B
| �y�v�����S���ς��@�֎���O�i����s�z |
�@���̍��v�����S���ψ���h�́A�S�w�A�嗬�h�̗L�͊�������������܂����͂�}�A���������B�Q���Ɋv�����S���ψ���͐ӔC�ҍ��c�̂��Ƃɋ@�֎��u�O�i�v�s�B���̂悤�ɞ��������B
| �@�u��̊����̎w�����́A�K�������̉Ս��Ȍ����̑O�ɂ��̏X���Ȏp�����Ȗ\�I�����B���ۓ����A�O�r�����̂Ȃ��ŎЋ��w���̗������̂�����ɂ݂Ă����v�B |
| �@�u�i�J���ҊK���́j�Ɨ��⒆����\�����v�ł͂Ȃ��ɁA���m�ɓ��{�鍑��`�œ|�̊����������A�J���ҊK���̈�̓������������������ɂނ����đg�D���Ă������ƂȂ��ɂ́A�J���ҊK���͂˂Ɏ��{�̐ꐧ�ƍ��̂��Ƃə�Ⴕ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�B |
| �@�u��̌��F�̎w��������Ɨ������v���I�v�����^���A�}�������ƂȂ��ɂ́A���{�鍑��`��œ|���A�J���ҍ��Ƃ��������A���E�v���̓˔j��������Ђ炭�Ƃ������Ȃ̗��j�I�C���𐋍s���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B |
| �@�u�������������̈�Ƃ��ă}���N�X��`�I�ȐN�J���҂̑S���I�ȒP��̐N���������������v�B |
|
| �y�O�H���葢�D���זE�̑命�������}�A���}�E�E�}���������z |
| �@���̍��A�����}���ł́A�}�̈��ۓ����̎w���Ԃ���߂����Ę_�c�������N����A�}�����ᔻ���W�J���ꂽ�B�P�|�Q����������E�|�ǐ�S�ƕ���ŎO�勒�_�זE
�Ƃ���Ă����O�H���葢�D���זE�̑命�������}�����B���̒��S���q�́A���Y�}�͍��◝�_�I�ɂ����H�I�ɂ��v�����}�Ƃ��Ă̔\�͂���������Ɛ錾�B����Q�D�Q�Q���u���葢�D�Љ��`������v�Ȃ鎩���g�D������A�u���g�ւ̌��W�̓����������n�߂��B�����������ۂ͒�������n���ɁA�C���e���}������J���ғ}���ւƋ}���ɍL����A�w���זE�E�S���L�͑�w�̊w�ғ}���E�����J���Ԍo�c���痣�}�E�E�}�����������B |
�@�P�D�Q�T���A�O��z�R���O�r�Y�z�Ƀ��b�N�A�E�g�A�O�r�J�g�͖������S�ʃX�g�ɓ˓��B
�@�P�D�Q�W���A�S�w�A��y�j�~�������g�A���۔�y���E�s���e�����ӑS���w�������N�����W��k�����J�����l�����ߑS�����\�J���ŏW��E�f���B������c��\�҉�c�ł́A�u�H�c�֍s���v�Ƃ�����O���_�̌��ʂ��ӂ݂ɂ������w�����ւ̍R�c�A�u�H�c�����͂悭����������v���Ƃ����]���A�u�H�c�ɍs���ʂ��Ƃł́A�����ꂽ�ҁA�ڋ��҂͏��������̂ł���A�S�w�A�̍s���͂����҂ɂ͗E�C��^�����v�Ƃ��������A���ɁA���A���s�A�R���Ȃǂ̑�\���甭�����ꂽ�B
�@�Q�D�Q���A�u���ۍ���v�������������B��}�����s�����{��Njy�����B����Ɍĉ����č�����c������s����グ�Ă������ƂɂȂ����B
| �y�Њw����T��S�����A�v�������h������|�z |
|
�@�Q�D�X���A�Њw����T��S�����k�ڍ�����l�B�l���S���[�l�X�g�E�����̓f�����l���������j����A�������Δh�W���̑�c�����i���۔F����r���ޏꂷ��B�ψ����E���_��Y�A���ψ����E�R�c����A���L���E�����c�v��I�o����B
|
�@�Q�D�P�W���A�v�������h�n�������\�҉�c�k���o��l�A�����i�S�w�A�嗬�h�j�E�i���嗬�h�j�̓��a����`�Ɠ������Ɛ������\�B
�@�Q�D�Q�P���A�S�w�A�����ρA��y�j�~���g���\�����A�O���S�w�A���J�Ó����m�F�B
�@�Q�D�Q�V���A���{�Љ��`�N�����i���j�S���w���Nj��c�������B
| �y�S�w�A�Q�Q���ϊJ�ÁA�v�������h������|�z |
|
�@�Q�D�Q�W�|�Q�X���A�S�w�A��Q�Q���ς��J����Ă���k�ԍ����l�B�H�c�P�D�P�U�����̕]������b�ɍ���̈��ۓ����̓W�]���߂����Ę_�����ׂ���A�S�w�A�u���g�w�����́A��H�c�����͎x�z�K���̓O�ꂵ���e���������A���̂��Ƃ͈�w���͂Ȏ��͓I��O�s���݂̂��A�x�z�̍U���ӂł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ�����Ƒ������A���y�j�~�����ƂS���[�l�X�g��������Ăт������B�v�����h�́A�H�c�������Ꝅ��`�I�ӓ���`�Ɣᔻ���A���Y�_�ɂ�����J���҂̌��N��Βu�����ΈĂ��o���A�_���ƂȂ����B�����h�́A�S�w�A�̋ɍ��I��p���j����������s���̐���グ�Ƀ}�C�i�X�ɂȂ��Ă���Ɣᔻ���A���̊ϓ_����H�c�����̈Ӌ`��ے肵���B
�@���̎��A�P�D�P�U���̉H�c�����̃{�C�R�b�g�ɑ���ӔC�Njy�Ƃ��āA�v�������h�����̂W���i���]��j���Ƃ��铮�c���˔@�o����A�U�P�R�W�ʼn����ꂽ�B�������Ċv�������h���\�͓I�ɔ�Ƃ���A�����̓u���g�ɂ���Đ������ꂽ�B���̎��_�ł̑S�w�A�����̐��͔�́A�u���g�V�Q�A�����Q�Q�A�v�������h�P�U�A���̑��v�����S���ρE�w�����Ƃ����B
|
| �y�����{���̖��������z |
�@�Q�D�U���A�������h�Œ����嗬�ɔᔻ�I�Ȓ��J��_���w��������������������ѓc������ɑւ�����B
�@�Q�D�P�T���A�A�J�n�^�̊w���łƂ��]���ׂ��w���V����n���i�S������{���j�B
�@�R�D�Q�|�R���A�u��V��}����X�ϑ��v���J����A�u����N�����̊g�勭���̂��߂Ɂv�̌��c���̑������B���̌��c�̍̑��o�߂͕�����Ȃ����A���������������H������̒E���͍����悤�Ƃ��Ă�����������B�����̗ǎ������̓����Ƒ�������������₷���B���́u�X���ϑ����c�v�́A�u����܂ł̋{���|�ѓc���́w�s���I�����`�x
�_����́w�̂��A�x��̃T�[�N�����X���x��Ŕj���A�����̐V�����g�D�_�E�^���_���m�������b��z���A�����̊g�勭���̂��߂̐V�������j�����肵����I���W�������邱�ƂɂȂ����v�Ƃ���Ă���B
�@�������A���̖����������쐬������т����ƋK����߂����āA�܂����Ă��{�����L����������邱�ƂƂȂ����B���̎��{���́A�����ɑ��āA�ӎ��I�Ɏ��̂悤�ȉE�h�n���������Ă���B
| �P |
�@�Љ��`��ڎw���ē������Ƃ���������̂͊ԈႢ�ł���B�u��������v�̉ۑ���������ׂ��ł���Ƃ��A�u�K���I�����͖����I�����ɏ]������v�Ƌ��ق��Ă͂���Ȃ������B |
| �Q |
�@�u�}���N�X�E���[�j����`���w�ԁv�Ƃ������ڂ́A�}�̓Ǝ������ł��ׂ��ŁA�������g�̐��i�ɂ���͂������Ȃ邩��f���Ȃ��B |
| �R |
�@�����������A�u�}�̓�������v�Ɠ}�Ɠ����̊W�𖾂炩�ɂ�����ŁA�����̎��含�����������̂ɑ��A����ł͎����㋤�Y�N���������邩��Ƃ���ɔ������B�����A�{�����L������u��U����v�̕��j�Ɏ���M�����A
�N�������u�K���I����̓����ł͂Ȃ��A�s���I�����`��Nj����閯��I�g�D�v�Ƃ��A�����̐��i���u�l���̖����`�I�ۑ�̂��߂ɓ����v�Ƃ������̂�
�u�J���ҊK���𒆐S�Ƃ���l���̖����`�̗���ɗ��v�Ƌʒ��F�Ƃ����B |
|
 �@�i���_�D���ρj�@�{���̖��������ɂ��� �@�i���_�D���ρj�@�{���̖��������ɂ��� |
|
�@��̑S�̂��̌�m�́A��O��㍡���܂ʼn������邽�߂ɓ}�ɒ��� ���Ă���낤�A�Ǝ��͎v���B����������m������T�_�b�����Ă���g���b�N�������}�ɉ𖾂��ׂ��Ǝv����B
|
�@�R�D�P�O���A�A�J�n�^�咣�ŁA�A�C�[���n���[�̗������Γ������N�B
| �y�S�w�A��P�T����z |
|
�@�R�D�P�U�|�P�W���A�u�S�w�A��P�T��Վ����v�i�ψ����E���������Y�j���J����Ă���B��̉H�c�����ł̑ߕ߂���̕ێ߂�҂��ĊJ�Â��ꂽ�B���͂̂�������A�S�w�A�嗬�h�Ɩ����n�A�v�������h�n�Ƃ̊Ԃ̐[���ȑΗ��Ŏn�܂����B��c���̐F�����́A�嗬�h����Q�V�O���A���嗬�h����Q�R�O���������Ɖ]���Ă���B����ΐ^����Ɋ����h�R�W�ɂȂ��Ă����B�S�w�A�����́A�����n�̓��������A���啶�w���Ȃǂ̑�c���Ɂu������[�v�𗝗R�Ɏ��i���������A��������͑j�~�����B����ɍR�c���������n�A����Ɋv�������h�������Փ˂������N�����ꂽ�B�������ĊJ��O������O�ŗ������n�܂����B
�@�������āA�����n�Ɗv�������h�̔��嗬�h�̑�c���Q�R�P���i���O�u�w���^���v�ł͑�c���Q�R�S���j�����O�ɕߏo�������ŁA�������s�����B�����̒��̎嗬�h�i�u���g�n�E�v�����S���όn�E�w�����n�j��c���Q�U�P���i�V��c���͂P�W�P���j�ł������Ɖ]���B
�@���́A�X����ȍ~�̑S�w�A�̑O�i�����̂悤�ɑ������Ă����B
|
�@�u����͐����I�ۑ���I�Șg�������ł����Ƃ炦���Ȃ��X�����������Ă��钆�ŁA�������������ۓI�Ȋϓ_����Ƃ炦�A���a�^�����A�G�̂Ȃ��b�������^���ɉ�������X���ɍR�����B�鍑��`�҂̔����푈����ɑΌ�����C����S�w�A�̓����̒��S�C���ɂ����A�c���������Ƃ͉���I�Ȃ��Ƃł������c�c�B
�@�����ł͒N�������́w���`���x�����ɂ��镽�a�����ꂪ�����ɓ��X�ϑJ���鏔�K���̍��ۓI�����̌�������͂Ȃ�ČŒ艻�����Ȃ�A�����̐��������W�������Ƃǂ߂Ă����悤�ɂȂ�B�w�푈�ƕ��a�x�ł��ׂĂ������h�O�}�e�B�b�N�ɏ�͂��A���j�́i���a�i�쓬���j�𗧈Ă��闧�ꂩ��E�p���āA��X���Ƃ�܂���͎��͎��{�ƊK���ƘJ���ҊK���̌����������̐��E�ł��邱�ƁA���̉Q���̊w���̏��v�����J���ҊK���Ƃ̓����ƌł����݂Ɍ����������Ă��̔��W���ۏႳ��邱�ƁA�]���ĉ�X�͂��ׂĂ̏�a�i��̉ۑ���Ђ��������n����ł͂Ȃ��A���̎����ɂ�����J���҂Ǝ��{�Ƃ̗͊W�y�ёΌ��_�i����͐���������E����j�m�ɔc�����w���̉^���̕����������˂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����ɂ����炩�ɂ���Ă������B�P�P�����P�S����ɂ������N�Ԃ́A�Ε]�����A�x�E�@�����̎��H�̎����̒��ŁA���̂悤�Ȑ������v�z�����[���ɒNj�����Ă����ߒ��ł������B
�@�]���Ă��̑�\�l������߂���_���́A�܂��ɂ��̂悤�Ȋw���^���̔��W�̕����𐳂��������߂悤�Ƃ��镔���ƁA�����Ƃǂ߂悤�Ƃ��镔���̑Η��Ƃ��čs��ꂽ�B�����Ă���͓����ɁA���{���{��`�����̔��W�r��A���ۓI�n�ʂ̊m����_���čs���ė����Ƃ���̈��ۉ���ɑ��铬������萳���������ɑ�_�ɔ��W�����邩�ۂ��̑Η��Ƃ��Ă����ꂽ�̂ł���v�i��\�܉������W�j�B
|
�@���ʁA�u�S�w�A��P�T��Վ����v�́A�S�w�A�ɂ�����u���g�̎哱�����ł߁A�����˓��A�H�c�����𒆐S�Ƃ����S�w�A�̍s���͂܂�������������ƕ]�����A����۔�y�j�~�����̏������߂����ĂS���J�w�[�l�X�g��f�����������悤�A�ݒ鍑��`���t��œ|���悤�B�S�D�Q�U��S�w�A�̖��^��q���ē�����Ɛ錾�����B
�@�l���́A�ψ����E�����i�k��j���đI���A���ψ����E�������i����j�A�f�J�G���i����j�A���L���E������v�i����j��I�o�����B���́A������I���_���ł߂棂ƌč����A���ʂ̃X�P�W���[����������c�̑�P�S���D�P�T������s���ɂ��킹�A�S.�P�T���ɍ����f���A�Q�O���ɑS���X�g���C�L�A�u�S�D�Q�U���ɑS���[�l�X�g�ƍ���f���v���̕��j�����肵���B���ɂS.�Q�U����S�w�A�̉^���������ē�����ƌ��肵���B���̎����������A�ɗ����A�Ӑg�̗͂����߂ău���g�̈��ۓ����ւ̌��ӂ�\�������B
�@���̑��J�Âɐ旧���Ẳ��t�߂ł̎嗬�h�Δ��嗬�h�̏Փ˂́A�v�������h�A�����h�̔��嗬�h�̑�c���Q�R�P�������đ��{�C�R�b�g���Ǝ��W������ʂ����A��̑S�w�A��������������邱�ƂɂȂ����B
|
 (���_�D����) (���_�D����) |
| �@���Ă݂�A���̑��͊w���^���j�㎊�㉘�_���c�������ƂɂȂ�B�ӌ��̈Ⴂ��\�͂ʼn������邱�ƂƁA�����h�������h��ߏo�������Ƃɂ����āA�����������������ł���B���̎��_�ł́A�S�w�A�嗬�u���g�h�́A�����͉䂪�g�ɂȂ�ȂǂƂ͖��ɂ��v���Ă��Ȃ������Ǝv����B�����ł��邪�A�����^���̓����K�����Ƃ��āA�{�����̕ӂ�������Ƌ������ׂ��Ƃ��v�����A���������̐S�ȓ_�ɂ��čl�@���ꂽ���̂ɏo��������Ƃ��Ȃ��B |
�@�H�c�����̈ꃕ����ɂ́A�����̍����m���l���\����17���ɂ���āu���g�D�ւ̗v���v�����\����A���_����ɂ����Ă��O�q�}�_�b�̕���O�I�ɂ͂��܂������Ƃ������Ă����B
�ΐ�B�O�A���������Y�炪�S�w�A�x���A����������ᔻ�����B
�@�R�D�P�V���A �O�r�J�g�����A���g�������B
�@�R�D�Q�R�|�Q�S���A�Љ�}�Վ����B�ψ����ɐ����Y��I�o�B
�@�R�D�Q�W���A�O��z�R���Y�ĊJ�A���g���Ɨ����̌��ˁB�R�D�Q�X���A�O�r�����A���g�����v�ې����\�͒c���Ɏh�E�����B
�@�R�D�R�P���A���ۑj�~�w������ÁE���۔�y�j�~�E�f���K�����ӁE�ݓ��t�œ|�N�w������s���A�������N�W��k����J�쉹�l�Ɉꖜ���Q�����Ĕ��d�F���܂Ńf���B
| �y�u���g��S��Վ����z |
�@�S�D�Q�|�R���A�u���g��S��Վ����k���{��l���A�u�S������v��O�ɂ��āA�S�D�Q�U�w���[�l�X�g�E�����͂ɂ��J���ҊK���̌��N�𑣂����j�������肵���B�����L�������̂悤�Ɍč����Ă���B
| �@�T�v�u�L�͂ȑ�O�̃G�l���M�[�����������Ƃ��A������Ӗ��Œb����ꂽ�^�̃v���t�F�b�V���i���Ȋv���Ƃ��O�疼���݂���Ȃ�Ό��͊l���͕s�\�ł͂Ȃ��B���ۓ������Ȕ��Γ����ɏI��点�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u���g�͗Ⴆ�S����������Ă��A�ꎞ�I�ɑg�D������悤�Ȃ��Ƃ������Ă��A���̓�������蔲���v�i�u�u���g���j�v�j�B |
�@�A���A�����g�͌�Ɏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�T�v�u���̑��O��A���͂̒D��A�v�������сA�\�A�X�^�[�����������ƂłȂ��^�̎Љ��`���Ƃ̌��݂��咣���Ă������A����ł͔@���Ȃ�ߓn�����Ƃ�����A���̔p��Ɍ������̂��A�ɂ��ẴC���[�W��S�����ĂȂ�������u���g�ɋ^��������Ă����v�B |
|
�@�S�D�R���A�A�J�n�^���j�������s�A���S�������A�����j�łP�O�y�[�W���ĂƂȂ�B
�@�S�D�R���A�S�w�A���嗬�h���S�������҉�c�J�Ák�_�ˑ�l�A�S�w�A��c�B
�@�S�D�T�|�X���A�}�́u��P�O���v���J����A�u�O��O�r�J���҂̉p�Y�I�����̏����̂��߂ɑS���吨�͂̕��N��i����v���̑��B�S���̓}�g�D�ɎO�r�����ւ̎��g�݂��w�����A���א���̊����Ƃ����n�ɔh�����āA��ʎx���̑̐���������B���̍���O�r�̓����͈��ۓ������x���A���ۓ����ɕ�܂�ĎO�r�̓����͐i�ޣ�Ƃ����鎖�Ԃ����܂�������B
�@�S�D�P�O���A�}�`�n��ψ���u���g�Ɍ��W�B
�@�S�D�P�T���A�S�w�A�A��y�j�~�S������s���A�����ł͒n���S�@����c�����O�w�\���W��ɐ�ܕS���Q���A�W��㍑��f���Ɉڂ�@�����ƏՓˁA���s�ł͕{�w�A�W��k���u�Б�l�ɐ��S���Q���A������c�W��k�~�R�����l�ɍ����E�s���f�����S���ŏW��E�f���B
�@�S�D�P�U���A�}���N�X��`�w�������i�}���w���j����s����������B
| �y�������悤�₭���ۓ����ɍ����グ��z |
|
�@�S�D�P�V���A������ÂŁA����J��O���y���Łu�V���ۏ���y�j�~�����N���v���J���Ă���B���ӂ��ׂ��́A��N�}���̌�葐�ɐ��������悤�ł��邪�A�}�́u�U�O�N���ۓ����v
�͂��̎��_���獆�߈ꉺ�{�i�I�ɉғ������Ƃ݂Ȃ��ׂ��ŁA���]�E�Љ�}�E �S�w�A�ɂ��^���̐���オ������āu�o�X�ɏ��x�ꂶ�v�Ƃ���Q�������Ƃ����̂��j���ł��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B
�@�����̎��g�݂̒x��́A����܂ł̓}�����̕��j�Ǝw���ɂ������悤�ł���B���̎����̓}�����̕��j�Ǝw���́A���ۓ����S�̂������̘g�Ɍ���t���Ă���A����������x�z���͂ł�����{�Ɛ莑�{�Ƃ̊K�������Ƃ̗��݂Ŋݐ��{�œ|���^�[�Q�b�g�Ƃ���Ƃ������������Ƃ��Ă̈ʒu�Â�������Ă�����������B���̌��ʁA���ۓ�����J���҂̃w�Q���j�[�̂��Ƃɐ����I��@�ɐ���グ�Ă����悤�Ȋ�{�������I�グ����A�j�̘H���Ɋ�Â����ē����I�ʒu�Â��ň��۔j�����f���A ���������ʂ͈��۔j���ڂ̖ڕW�ɂ����A�ނ���u��������v���v�Ɍ����� �u�������哝�����v���`�������邱�Ƃ�n���ɖڕW�Ƃ��ׂ����Ƃ��Ă����B
�@���������ʒu�Â����炵�āA�ł��邾���L�͂Ȑl���w�̎Q�������邽�߂ɂƂ��������œ������̊�L��`�Ō��W�����A������p���w����N�J���� �̑S�Ă��Œ���̓���s���ɋK�����Ă������Ƃ��鐮�R����s���������w�j�������B�܂�A���ۓ��������Ƃ����Ēʏ�̃X�P�W���[�������̘g���Ɏ��߂悤�Ƃ��Ă����ς�����A����˓�������ɓ����u���g�I�w���Ƃ̗��ɒ[�ɂ������Ƃ����̂����ۂ̂悤�ł���B
�@�Ƃ͂����A�������ЂƂ��ѓ����n�߂�ƍs���͂��ʊ��ŁA���̎������S���P�V�O�O�����g�D�̂U�S�p�[�Z���g�܂Ő����������Ă����܂��w���������߂Ă�����
�ƂɂȂ����B�}�́A�����i�K�ł̓I�u�U�[�o�[�ł͂��������A�n���̋����g�D�ł͎Љ�}�ƕ���Œ��S�I�ʒu���ߎw���I�������ʂ����Ă������ƂɂȂ����B�������A�P�������͕ʂɂ��āA�}�̑O�q�����������^�̕��L�s����`
�ɂ��J���p�j�A��`�Ɛ��R�f���s���������A�퓬�I�Ȋw���E�N�E�J���҂̍s���Ǝ���ɑΗ��������������B�}�̎w�����邱�������u�����f���v�ɑ��āA�S�w�A�w�����ɂ��u���č��f���v�E�u�����f���v�̒ɔl�����т����邱�ƂɂȂ����B
|
�@�S������͑S���̒n����ۋ����g�D�������āA�g��I�ȁu�����f���v���J�n����Ă����B���̍����������Y��̌Ăт������Ȃ���Ă���B��������e�u���E�T�����w����������ց|����̂����߁x�v�́A�T�v�u����������֍s�����B�k�͖k�C������A��͋�B����A��Ɉꖇ�̐��菑���g�������{�l�̌Q�������֏W�܂��āA����c��������d�ɂ���芪������A�܂��A���̍s�s���邱�Ƃ�m��Ȃ�������A�����ɁA�����̂ɂ��R�����Ȃ������I���͂����܂�Ă���B����͐V���ۏ��̔�y��j�~���A���{�̋c����𐭓��ɗ����߂点��ŗL�낤��ƞ������Ă����B
�@�S�D�P�T���A���ۉ���j�~��P�T������s���B�S�w�A��P�T�O�O�����n���S�c�����O�w���琿��f���Ɉڂ������A�@�����ɑj�܂�A���������܂ʼn����Ԃ���Ă���B
| �y�v�����n��}���w��������������z |
�@�v�������h�́A�S�w�A�̓����𐭎���`�I�ɍ��s���A�ɍ��ӓ���`�A���u���I�ɍ��`����`�A�Ꝅ��`�I�ʍӎ�`�Ɣᔻ�����B�܂��A�H�c�������u���J���ғI�y�e���t�̍����v�ƌ��߂����B���j�Ƃ��ẮA�ꌎ���������Ė������X�g�ɓ˓������Y�J�O�r�����Ƃ̌������咣�������A�傫����ނ��Ă������B
�@�����A�v�����S���ς́A�S�D�P�U���A�u���g�̊w���g�D�Њw���ɑR����`�Ŏ��O�̊w���g�D�Ƃ��Ģ�}���N�X��`�w��������i�}���w���j��g�D�����B�@�֎���X�p���^�N�X��������B���̔��������T�S�]�̓������������Ɖ]���Ă���B�}���w���́A�������u�E���I�v�Ƃ��A�u���g�𢍶����_��`�I�X����A�u�X���ɍ���`�v�Ƃ��Ĕᔻ���w���𒆐S�ɑg�D���g�債�Ă������B
�@���̎��A���̂悤�Ȟ��������Ă���B
| �@�u��̊����̎w�����́A�K�������̉Ս��Ȍ����̑O�ɂ��̏X���Ȏp�����Ȗ\�I�����B���ۓ����A�O�r�����̂Ȃ��ŎЋ��w���̗������̂�����ɂ݂Ă����v�B |
| �@�u�i�J���ҊK���́j�Ɨ��⒆����\�����v�ł͂Ȃ��ɁA���m�ɓ��{�鍑��`�œ|�̊����������A�J���ҊK���̈�̓������������������ɂނ����đg�D���Ă������ƂȂ��ɂ́A�J���ҊK���͂˂Ɏ��{�̐ꐧ�ƍ��̂��Ƃə�Ⴕ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�B |
| �@�u��̌��F�̎w��������Ɨ������v���I�v�����^���A�}�������ƂȂ��ɂ́A���{�鍑��`��œ|���A�J���ҍ��Ƃ��������A���E�v���̓˔j��������Ђ炭�Ƃ������Ȃ̗��j�I�C���𐋍s���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v |
| �@�u�������������̈�Ƃ��ă}���N�X��`�I�ȐN�J���҂̑S���I�ȒP��̐N���������������v�B |
|
�@�S�D�P�X���A���ۑj�~�w����������A������c�̑�\������s���̕��j�����F�A�S�w�A�ɑ�����ɏ]���悤�\���������B�����A�S�w�A�����ρA������c��p���ς̇����č��f�������j�ԏ�A�l�E��Z�[�l�X�g�E�����̓f����P�ƂŌ��s���邱�Ƃ�����B
�@�S�D�P�X���A�쒩�N�\�E���ŁA������Ӑ��{�œ|���v������l���I�N���N�����Ă���B�킢�̉ΊW������̂͊w�������ł��������A�I�N�������̉̂悤�ɑS�y�ɍL�������B
�@�S�D�Q�O���A�S�w�A���嗬�h�P�R������������o���A�S�w�A�����̒P�ƍ���f����������A������c�E�N�w��������c�̉��ɍs������悤�Ăт����A�g�D�I�ȑR���s�����B
�@�S�D�Q�O���A���勳����R�T�R�������۔��̐����B
�@�S�D�Q�R���A�S�w�A����f���A���ܕS���Q���A�`���y���Z���^�[�O�ɍ��荞�݁A�̂��L�y���܂Ńf���B
| �y�u���g�����ۓ������͐�錾�z |
| �@�S�D�Q�S���A�u���g�̑�S����J����Ă���B���̎������̏��L�����Ȃ��ꂽ�B�u�R�疼�I�N���v�A�u���ۂ��Ԃ����A�u���g���Ԃ�邩�v�A�u�Ղ͎���Ŕ���c���A�u���g�͎���Ŗ����c���v�ƌ�N�����鉉�����Ԃ��ꂽ�Ɖ]���B���̑��Ɍ����ē}�̍`�n��ψ���Վ��n��}��c���J���A�u���g�Ƃ̍����𐳎��Ɍ���A�n��ψ���̉��U�����c���Ă���B���̗�������[�h
�����R��q�ψ����E�c��a�v���ψ����̗��n��ψ��͂����葁���}���珜������Ă���i�u�A�J�n�^�v�T�X�D�P�Q�D�P�U�j�B |
| �y�����n��s���A����������z |
|
�@ �S�D�Q�T���A�����n�S�w�A���嗬�h�́A�܂������s�ɂ����āu�����s�w��������A����c�v�i�s���A�A�c���ɍ��H��I�o�j�������Ă���B�ȍ~�����n�́A�u�U�O�N���ۓ����v��s���A��̎w���ɂ��^�����N�����悤�ɂȂ�B
�@�����n�́u�����s������A����c�v(�s���A)�̌����́A�S�w�A����ւ̑����ƂȂ����B�s���A�́A�u�S���吨�͂ɂ�铝�����`���̗L�͂Ȉꗃ���߂����ē����v(�s���A�ʒB)�Ǝ咣���A������c�̒����Ȑ����҂ƂȂ�A���̕��a�I�J���p�j�A�H���ɂ���ėʓI�g����͂������B�����āA�U�D�P�T�������O�܂ł́A�嗬�h�ƌ�����ׂ�قǂ̓��������l�����Ă������B
|
 (���_�D����)�@�s���A�����l (���_�D����)�@�s���A�����l |
| �@���̌o�߂͖����n�w�����̓Ǝ��̔��f�ł������̂��낤���A�}�̎w���ɋ��������̂Ȃ̂ł��낤���B���̎��S�w�A�^�������̋T��͐[���� ��A�����Ƒ������O�̉^�����N�����ׂ��ł�������������Ȃ����A�^���̍Œ��̂��Ƃł��邱�Ƃ��v���Ε���͔�����ׂ��ł����������m��Ȃ��B������ɂ���A�����������Ƃ������������Ă����K�v������Ǝv����B��s���A��́A���ۉ���j�~������c�̕��j�ɏ]���A����������邱�Ƃ�錾���A�S�w�A�w�������I�Ɣᔻ���A��P�ƍ���f����ɔ����Ă������ƂɂȂ����B |
| �y���ۉ���j�~����s���@�S�w�A�̊w���V�疼�������O�ŋ@�����ƏՓˁz |
�@�S�D�Q�U���A��P�T�����ۑj�~�S������s���B�P�O���l�̍����^�����s�Ȃ�ꂽ�B���̎�������c�͂V�O�O���̌x�������J��o���āA�f��������Ԋ��D�������D�v���b�J�[�h�Ȃǂ����グ�A���R��������������f�����s�����B�S�D�Q�V���̃A�J�n�^�́A�������c�̕��j�ɏ]��������s���ɂ͈�w���G��邱�Ƃ��o���Ȃ�������Ǝ����グ�Ă���B
�@�S�w�A�嗬�h�D���嗬�h�Ƃ����̎��f���̓���������������B�S�w�A�嗬�h�́A�� �̎��u���č�����肩�A�퓬�I����f�����v�Ɩ����N���A�u����Ȃ�������c�����z����v�A����N�w���ɑ�����ƃA�W�����B�S���W�Q��w�A�Q�O���Z�̑S�w�X�g�D���ƕ����łQ�T�����Q���A�s���ł̓`���x���Z���^�[�O�ɑS�w�A�V�疼�����W���A�x�����ƍ����O�Ō������Փ˂����B���勳�{�w���R�疼�̊w�����Q�����Ă����B
�@�O��̓��c�ɂ��āA���E�������̂悤�ɏ،����Ă���B
| �@�T�v�u���x�͌x�@���A���낢��Ə������Ă��邾�낤����A�P�P�D�Q�V�̂悤�ɊȒP�ɐ��ʓ˔j�ł���͂����Ȃ��B���ɂ��A�g���b�N�̐K�ɔ�ł��������̂����\�䂩���ׂĂ��邻�����B�ǂ����邩�Ƃ������ƂɂȂ����B.���b�̃u���g�́A���ɐ�p�I�ɔ��Δh�ɂȂ��Ă�������A���k�����Ȃ������B�S�w�A���L�ǂƁA����E����E����Ȃǂ̃u���g�זE�Ƙb���������̂����A����͓̂�����Ȃ��B�g���b�N��R�₷���A��щz���邩���A�ƒ�Ă����B�g�D��q������p�_�c�ƂȂ�A���ǂ́A��щz������j�ɂȂ����v�i��얾�j�u�S�w�A�v�j�B |
�@�S�w�A�ψ��������́A����x�����̑��b�Ԃ����z���āA���Q�������z���āA����ʑO�֑O�i���棂ƃA�W��A�����O�ɍ��荞�݂��ѓO�����B
�@�u�����Ǒz�W�v�͎��̂悤�ɏ،����Ă���B
| �@�u���ǁA���������������Ȃ��ƂȂ��āA�V�h�Ŗ������܂Ŏ������݂Ȃ���A�������w���͂���ɓq����B�g�b�v�o�b�^�[�ƂȂ��āA���b�Ԃ����z���č���\���֔�э~��邩��A���̌�͒N�A���͒N�x�ƁA�T�l���炢���߂܂��ĂˁB���l����э���ǖʂ��ς�邾�낤�ƁB����ƁA�{���ɑ��X�Ɖ���l�����S����э���ł������v�B |
�@�T�v�u�w�t��ǁx�Ŏ��X�_��������������閾����w�̑O���a�F���x�@�̑��b�Ԃ̏�ŃA�W���āA�����̒Z��̏��q�w���������Ɠ��̐_����������ăL���|�b�Ɣߖ��グ�Ȃ���E�E�|�b�ƍŏ��ɍ���\���ɂ���x���̊C�̒��֓˓������B�������z�������Ă�����ŁA����͂����������Ƃ��ɕ����ĂȂ���̂��Ƒ�w�R�ӎ��������Ă���ɑ������B����������������A�˓����邩�ǂ����ŖT��ŝ��߂Ă����S�w�A�̎w���҉�c�����ڂ��ɂ݂Ȃ���A�w���҉�c�Ȃ�Ă������炦���ƑS���ɓ˓����A�W�����B
�@�x�@���͂��̍s����S���\�z���Ă��炸�A���X�Ƒ����Ă���w���B�ɘT�����ē����������B���̒���A�x�����́A�w���B�̌��őԐ���g�ݒ����āA�w���B�ɏP���|�������B����ɂ���đ����̕����҂Ƒߕߎ҂��o���B���Ȃ݂ɂ��̎��˓��ɐT�d���������勳�{�w���ɐ�����ƂŁA����̓���R���v���b�N�X���ꎞ�I�ɂ���������ꂽ�Ƃ����v�B |
�@�u����c�̓m�̉�v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@�T�v�u���������Y���}�C�N������A��ʑ����ɂ��Č���ɑi���������B���̎��̓����̃A�W�e�[�V�����ɂ͋S�C������̂��������B����܂ŁA����قǐS�����ꂽ�A�W�����ɂ������Ƃ͂Ȃ������B�w���B�́A�܂�ŃR���T�[�g�̒��O�̂悤�ɓ����̑i���ɕ��������Ă����B�A�W�͏I������B��u�̐Î₪�x�z�����B�N���������Ƃ��Ȃ������B�Ƃ��낪���̏u�ԁA�w���B�͖y�g���b�N�ɂ悶�o��A�F�ŃE�E�@�|�Ƌ��тȂ���x�����̓���ڂ����Ĕ�э~�肽�v�B |
�@�����́A���̂悤�ɋL���Ă���B
| �@�u�������A�W���Ă���ȁA�ƌ��Ă�����A�w�����ǂ�ǂ�g���b�N�ɂ悶�̂ڂ��āA���������փs�����s������э~���B�������A�������ƎO�d���炢�ɂȂ��Ă���̂��A�s�����s���������Ă����B�����������ˁB���̎��́v�i�،��j |
| �@�u�����낮�u���g����K�ڂɎ����玟�ւƃo���P�[�h�ɂ悶�̂ڂ�A�x���̕ǂ�������Ƃ��鉽�疼�̊w���A�J���҂̎p�����āA�����̗]�莄�͗܂��o�Ă���̂��ւ����Ȃ������v�i�u�u���g���j�v�j�B |
�@������̑���ɉ�����Ă����s���A�����Ƃ��A�����ψ�����̍s���ɗ����ǂ��������A�����~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@���̓����œ����ψ����A���_��Y�Њw�����L����P�V�����ߕ߂���i���̌��ʁA�����D���͂P�P���܂ōS������鎖�ɂȂ����j�A�P�O�O���̊w�����d�y�������B���s�ł��A���傪����a�Q�T�N�̃��b�h.�p�[�W���Γ����ȗ��A�P�O�N�Ԃ裂Ɏ��v��O�W��ɖ�P�T�O�O�������W���A�{�w�A��Ẩ~�R���y���ł̏W��ɂ͂R�T�O�O���̏W����J���Ă���B���̓��؍��̎�s�\�E���ł��A�w����擪�ɂT�O���l�̃f��������A���ׂ̈ɗ��Q�V�������ӑ哝�̂����\��o�ւƒǂ����܂�Ă���B
�@���ڂ��ׂ��́A���̎����S�w�A���嗬�h�����n�w���P���P��]�͐����J�����ŏW��A�S�w�A�嗬�h�ƕʍs���ō�����c�Ƌ��ɍ����^����W�J���Ă��邱�Ƃł���B�܂�A�S�w�A�̍s���ɂ����颍s���̕���������̎����n�܂������ɂȂ�B�����n�̃f���͂Q�O����g�ɕ��U�������čs�i���镶���ʂ�́u���č��f���v�ł������B
�����́A�S�w�A�̂S�D�Q�U������K���ᔽ��Ƃ��ĐN�w��������c���珜������悤���͂������A�����n�s���A�����̑�s�ɂ����悤�Ɖ�n�߂��B
�@���̍��̃u���g�̏�ɂ��āA���c�v�����͎��̂悤�ɏ،����Ă���B
�@���Y���͎O�����{�A��O������J�Â��āu���ۂ��Ԃ�邩�A�u���g���Ԃ�邩�c�c�B�����A3000���̘J���ҕ���������������A���ۂ͂Ԃ���v(�����L��)�Ƃ������ӂ̂��ƂɁA�M���ۂ����_��W�J�����B�������A���͖��m�ȕ��j��W�]�����o�����Ȃ��܂܂ɖ�������B
�@���͈�_�ɂ��ڂ�ꂽ�B�����A�����͈��ە��ӂ̍Ō�̃��}�ꁁ�`�����X�́A�O�@�ł̔�y�i�K�Ɛݒ肵���B���̂��߂ɂ́A����̉�����ł���5��20���O����u����v�Ƃ��āA�S�w�A�����Ɠ����e�����̘J���ҕ������������āA���͓������������͂Ȃ��ƍl�����B�����A����ɂ��ẮA�J���ҕ����͗]��ɂ����シ�����B
�@�������ɋ��Y���͌����ȗ�1�N3�������o�߂��Ă����B�����A�w���^�����e�R�ɂ��������J���^���ւ̂䂳�Ԃ�͌��E��I�悵�Ă����B�w���^�������ʂɂ����Ĕ����������̂ɂ������āA�����̘J�Ί����͈ˑR�Ƃ��Ē���𑱂��Ă���A���҂̂������ɂ͊i�i�̍�������A�J�̊����͎肳����ɓ����������B
�@�u�w�����������Ƃ��Ă��C�ƒm�b��������A�J���҂̂���Ƃ���ł͂�����ł������ł���B���̖ڂ����̖ڂōŗǂȊv���I�J���҂�T���o���A����������ė������A����������Â鎮�ɑS�Ă̐퓬�I�ȘJ���҂����݂Ƃ邱�Ƃ��K�v���B�c�c�ǂ�Ȍ����m�炸�̐E��ł��J���҂͌����o����B�o���Ȃ��Ƃ���ΑӖ��ȊO�̉����̂ł��Ȃ��d�d�d�v�i���Y������זE�J�Ε��u����c��w�̓��u���N�I�@���Y��`�ғ����Ɍ��W�������N�́A���A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����v59�N8���j
�@���N�O�̘J�Ε��j�Ƃ͂����A�����́A���̂悤�ɂ��Ċl�������킸���̘J���҂Ɋ����������āA�S�w�A�����̍Ō���ɂ������āA�Ȃ�Ƃ����Č��H�����Ƃ����B���́A���ꂪ�u�J����3000�����������v�̎��̂������̂ł���B�����āA4�E26�����́A���̍ŏ��̎��݂������B
�@���̓��́A�w���ꖜ���̌���ɁA�S���{�Ўx���A��`�x���A�����x���A���J�A���g�A�S�_�сA�����A�����Ȃǂ̘J���Ґ��S�����Q�����A���č������܂����J���Ґ��疼�����ӂɂ��������B�����A���ǂ̓u���g���߂������u�J���^���ɂ�����v���I�����̌`���v�́A4��23���A26���̑S��������`�x���̓Ǝ��̑�O�f���A5��20���A����f�����s�ψ���̊��̉�3000���̎��@�f�������������ɂ������A�u���g�̍\�z�͂��Ɂu���̘J����3000�����������v�ɏI����Ă��܂����̂ł���B���������ǂ́A���̎��_�ł��̐����w���ɂ�������܂����F����������Ȃ������B���ە��ӂ̈�_�ɓ����̑�����q��������A���̍��܂͓��R�������Ƃ����悤�B
�@�i�����j �Ƃ��낪�A���ۓ����͍ŏI�ǖʂɂ����āA�����̗\�z���z����W�J�ߒ������ǂ邱�ƂɂȂ����B5�E19�̌����_�@�ɂ��ĈӊO�ȍ��g���������B���̍��g�̂Ȃ��ŁA�S�w�A���L�ǁ|�w���זE�𒆐S�ɂ�������w�����́A��O�I�����̍��܂�Ƃ���ɒǐ�����������c��6�E4�[�l�X�g�錾�A��O�I�����̊J�n�Ƃ������Ԃ̂Ȃ��ŁA�Ō�̎�����W�J���Ă������B
|
|
�@���̍��A���\�_���n�܂�B
�@�S�D�Q�V���A����u���g���}�����̕��j�ɔ��B
�@�S�D�Q�W���A���ꌧ�c�����A���c����B
�@�S�D�Q�X���A�S�w�A��Q�R�����J����k�ڍ�����l�A�S�D�Q�U�����܂ł̑������s���A����͂�J���p��A�ɂȂ邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�����w�����̓��a�������������蕂������ɂ�����ƕ��͂��A��T�D�P�R�����ۏO�@�ʉߐ�Αj�~�A�ݓ��t�œ|�̃[�l�X�g�Ǝ�s�ɂ����鍑��\����u�`�W��Ɍ��N���A����Ȍ�̂P�T�Ԃ�������p�����飍s�����j�����߂��B
�@�S�D�R�O���A���]�ً͋}�]�c������J���A�Љ�}�̕��j�ɓY���Ģ�A���T�O�O�O���ȏ�̐���s����y�тT�D�P�Q���̊e�P�Y��Ă̎����X�g�����肵���B���������̂��Ƃ܂������������ĕ��j���Ԃ�Ă���B
�@�S���A�Њw���u���_����v��T���i���s���F���x���V�I���ЁA���M�F�^���N�A���x�O�j���������B
�@�T�D�P���A��R�P�[�f�[�B���ە��ӁA������U�A�ݓ��t�ސw�̗v�����f��
�ĂT�O�O���̐��ō��̑�f�����S���e�n�ōs��ꂽ�B
�@�T�D�Q���A�S�w�A�����ρA�܁E��O����\�����R�c�W��̒��~������A�������O���R�c�W��ɂ��肩����B
�@�T�D�R���A�}���w������g��s����������i5���@�֎��u�X�p���^�N�X�v�n���j�B
�@�T�D�S���A�S�w�A�A�w�������痣�E��������i11���������������A�S�w�A�̓Ǝ��s����������c�ɑ��k�ƖA�w����������͗��E������ۗ��j�B
�@�T�D�T���A�\�A���{�́A�̋�ɐi�� �����A�����J�̃X�p�C�@�Q�@�̌��Ă\�B
�@�T�D�X���A�k���Ţ���ČR�������ɔ�������{�����x����̂P�O�O���l�W��B
�@�T�D�P�Q���A��P�U���S������s���B�S�U�O���̎Q���B�X�g���C�L�A�E��W��A�f���A���菑���^�����W�J���ꂽ�B���� ���A�������̍����f�������B�O�r�Y�z�ŃX�g���̑��g�����Ɍx�������P�����A�T�x�ڂ̑嗬���������������Ă���B�P�W�O�����d�y���B�ǔ��V���͢�͔�ьx�_���Ȃ飂Ɠ`���Ă���B
�@�T�D�P�R���A�S�w�A�Q�疼�����W�A���ۑj�~�S�w�A�S�������N�A����������č���f���B�����ł̓`���y���Z���^�[�O�ɓs���w���S�疼�Q���A�����Ɍ����ăf���A�̂������W��k����J�쉹�l�ɂT�疼�Q���A�����w�܂Ńf���A���s�ł͎s����w�[�l�X�g�Ō��N���k�~�R�����l�ɂT�疼�Q���B
�@�T�D�P�S���A�����n���A������c��\�Z������s���Ɍĉ����Đ����J�����łU�O�O�O���̊w�������W���ďW��B�̂�����J�쉹�Ŗ�ԕ��w���疼�ƍ����A�O��{�ЂɌ����ĎO�r�x���f���B
�@�T�D�P�T���A������ÂŁA����J��O���y���Łu�V���ۏ���y�j�~�����N���v�J���B�O�c�@�ł̈��ۏ�F�̌���j�~���悤�Ƃ��ĘA���̂悤�ɐ����̍���f�����������B
�@�T�D�P�T���A�Љ�}�̍]�c���L�����u�����ϊo��ň��ۑj�~�v�ƌ����B���]���A�T�D�Q�O���ɂɈ�ĂR�O���X�g����B
�@�T�D�P�T���A�S�w�A��Q�S�����J����k����l�A����ۋ��s�̌��̗\�z�����T�D�Q�O��������I�ȑg�D�������������Ƃ��Đݒ肵�A�J���ҁA�w���̃[�l�X�g�ƍ����̓f���ň��ۓ����̏����������镪��_(����̑啝�����j�~)�ɋN����Ƃ���T�D�Q�O���������c�����B�����A�w������̑g�D���ɐG��āA�@�E�s���A�����U���A���Ȕᔻ���s�����ƁA�A�E�K������A�S�w�A�ɑ��镪��s������ؒ�~���邱�ƁA�B�E������[����A�Ȃǂ̌x�����ׂ����B�@
�@�T�D�P�V���A�ă\������k�A�t�Q�^�@�̃X�p�C���ŕs�����B
�@�T�D�P�V���A�����}�A���ې����̂��߉�������ƏO�@�̑����ʉ߂̕��j���߂�B
�@�T�D�P�W���A�O�@�̏���x�����ĎЉ�}�����Ԑ����Ƃ�B
�@�T�D�P�W���A�w����������A�ڋ��Ε���Ăɂ��ĂёS�w�A���E���c�A���_�ł��B
| �y�����}�A���ۋ��s�̌��B�S�w�A�h��펖�Ԑ錾�h�������̓f���z |
|
�@�T�D�P�X���A���{�Ǝ����}�́A���ێ��R������_���āA������Y�O�@�c���̎w���Ōx���������Ė{��c���J���A�T�O���Ԃ̉���������c���B�Љ�}�c���A�鏑���S�{�E�����ɂ��āA�[�邩��Q�O�������߂��ɂ����ĐV���A����E��y���������s�̌������B�̌��ɉ�����������}�c���͂Q�R�R���A�ߔ������킸���T�����鐔�ŁA�{��c�ɉ�����R�c�͂P�S���Ƃ��������}�̃t�@�b�V���I�\���ł������B���̍̌��ɂ́A�Љ�E���ЁE���Y�e�}��������Ă��炸�A�^�}�Ŏ嗬�h�̎O�h(���A�O�A�͖�)�͓r���ޏ�Ƃ����̒��ōs��ꂽ�B���̎������}�͌x�����̑����t��Ȃǂ̖\�͒c���@���ɓ������Ă����B
�@���̎��A�Љ�}�A���Y�}�A������c�́A������ӂ���芪�����]�̃f�����ɒm�点�Ă��Ȃ��B�T�D�Q�O���뎞�R�O���߂��A�f�����͎O�x���c����ّO�ɏI���������A�f�����̒����碉���͉������ꂽ���A�V���ۂ��ʂ����Ƃ����̂ɁA�Ȃ��m�点�Ȃ��̂���Ɣ��̐����������Ă���B�b����Љ�}���L���]�c�A�ψ�����A���Y�}�̖��炪����Ă��āA���吭���̑���A���ۏ��̒ʉ߂�F�߂Ȃ��ȂǕ����̂킩��ɂ������������n�߁A���������̓����ɔ����Ẳ��U����Ăт����Ă���B�f�����͂�������ߑO�R���R�O���܂ō���O�ɍ��荞�݁A�Ō�܂Ŏc�����J�w�T�O�O�O���]�͍�����ӂŌx�����Ə����荇�����Ȃ���W�O�U�O�D�f�����J��Ԃ����B
�@���̌o�߂�����ɘA��āu�݂̂����͂Ђǂ��v�A�u�̌��͖������v�A�u��������U����v�Ƃ�����ʑ�O�ɂ܂ŋy�ԕ������ĂсA���̋@�����ɂ���܂Ńf���ɎQ���������Ƃ̂Ȃ��҂܂ł��ꋓ�ɑ���ɉ����n�߂��B�p�`���R���Ă����A���܂ł��ł��~�߂ăf���ɎQ�������Ƃ������Ă���B
�@�����̗l�q�����̂悤�ɓ`�����Ă���B
| �@��ݓ��t�œ|��A�������U��̃X���[�K�����}���ɑ�O�������B�[������J�E�w�Q���l�����̓f���B�u�P�W���̗[�����當���ʂ�n�`�ꂻ���ɖc��オ����������ӂ̐l�g�A�V���v���q�R�[���̌����A���̌������ɍ����̂悤�ɉ��X�ƘA�Ȃ���荞�݂̊w���B�v�i�ێR���j��e�������_�w�W�D�P�T�ƂT�D�P�X�x�j�B |
�@�}�X���f�B�A�́A���x�͊ݓ��t�̖\������Ăɔᔻ�����B
�@���̓�����ɁA������P�����ԃf�������A����������͂݁A�u�V���ۏ���y�j�~�E���t�ސw�E������U�v�̂��߂݂̂����̑S���I�ȍ����������W�J���Ă������ƂɂȂ����B
|
| �y�u���g�̑��߂���s�k�錾�z |
�@������������ɂ� ���āA�u���g���ǂ�����悤�ł���B��㎁�u�w���^���v�ɋ���A�S�w�A�����́A�T�D�P�X���̔ӂ̐V���ۏ���y�̕��m���u���۔s�k�錾�v���o���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B����זE�̒��ɂ́A�T�v�u���ۂ������ʉ߂��Ă��܂����ȏ�I���ŁA���̊ԃK�^�K�^�ɂȂ��Ă��܂����g�D������}��ׂ��v�Ƃ̌�����ł��o�����̂�����ꂽ�B���邢�́A���ی���������ďo�g������ł̐��͉����̂��߁A����ȏ�̃_���[�W��������ׂ���痣���҂��o�n�߂Ă����i���c�u�v���ۑS�w�A�|�U�O�N���ۓ����̑����ƂV�O�N�Г����̏œ_�j�B
�@����c��w�V���T.�Q�T������ʃg�b�v�̌��o���́A��V���ہA�����ʉ߂�����������A����ۓ����̍��܂ƍ�����c�̕�����A����܂͐��J���^���w���̏W�听��A��������w���w�̍�����ƂȂ��Ă���A��s�k������F�Z���ł��o����Ă���B����������s�����̢�s�k�̑�����ɑ��āA��������N�����N�x��ė͂��o�����A�݂��߂Ɏ��s����(�哇���̒k)���s�ł͈��������̓������A�s�[�����Ă����B�����ŕt������A���ۓ�����̑������ǂ��Ă݂邱�ƂɂȂ邪�A�s�k���ɒ��ݍ��ޓ����ƁA�S�苭���������鋞�s�Ƃ��Ⴂ�������邱�ƂɂȂ�B
�@�Ƃ��낪�A�܂��ɂ��̎���莖�Ԃ͑傫�����������A�u�J���^���w�������A�����`�i��ƍ�����U���f���āA�傫���v�����^���A��O�����o�����v�̂ł���B�u���g�ɂƂ��Ă��u���Ԃ̌�ɒǂ����Ă����̂�����t�v�Ƃ����ӑz�O�̂��˂�������炵�Ă����悤�ł���B�����L���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�u�T�D�Q�O���ۋ��s�̌������ɁA���{�̐����͐��ő�̎R��ɂ������������B�����グ�A�o�������̂����钪���������A������Ƃ��A���̊���������@���ׂ����߂ɂ����a�������u���g���A�����̂��̂̂Ȃ��Őh�����đ�O�Ƌ��ɕ������鑶�݂ł����Ȃ��Ȃ��Ă����B����ȂNJ��ɂȂ������v�i�u���W�v�j�B |
|
�@�T�D�P�X���A�S�w�A�A����펖�Ԑ錾����������c�ً̋}�����Ɍĉ�������Ɍܐ疼���ً}�����A�����ߑO�O�����܂ō����̓f���B
| �y�m���l�E�w�ҁE�����l��̓����z |
| �@�T�D�Q�O���A�T�D�U���ɓ����m���l�E�w�ҁE�����l��̓��������ڂ��ꂽ�B���̓��A���̋����A�������W�U�������{�^�}�̋��s�̌��ɔ����č�����U�v�������\�����B��w�����c�ɂ�邱�̎�̐������S���e�n�ő��������B�|���D�E�ߌ��r���͐��{�ɍR�c���đ�w���������C�����B�����̒m���l�̌ĉ��͢�����`�����闧�ꂩ��̂��̂ł���A�S�w�A�嗬�h�̌č����颈��ە��ӁD����œ|��Ƃ͎�̈Ⴄ���̂ł��������A�������ē��������悷�闬���ǖʂ����܂�čs�����ƂɂȂ����B |
| �y�S�w�A�̈ꕔ��R�O�O�������@�ɓ˓��z |
�@�T�D�Q�O���A�S�w�A���S���X�g�����A�����̓f���ɂQ���l���W�B�R�c�W���Q�����f���Ɉڂ����B�V�疼�̊w���f�����̈ꕔ��R�O�O�������@�ɓ˓��B
| �@��S�w�A�̐������L�������@�Ǝ����}�։ʊ��ȃf�����s������ƒ�Ă��A���Ă̐��������Ȃ��碂��̂܂܁A�삯���Ŏ��@���������B�A�����������x���������߂悤�Ƃ������A�R�O�O�l�قǂ�����ɓ��荞��B |
�@�����x�����̔r�����n�������A���̎��̗����łW���̊w���A�J���҂S�����ߕ߂���A�Q�U�����a�@�ɒS�����܂�A�S�O�����������Ă���B���ꂪ���@�P�������Ƃ�������̂ł���B
�@�������A���̉ʊ��ȓ������S�w�A�嗬�h�̎u�C�����߂邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł���B���̍����ɑS�w�A�嗬�h���ɕ��N�����Ă���A����I�Ȑ�p�w�����Ȃ����Ă��Ȃ������悤�ł���B����c�v�ȒǓ��L�O���W��̒��ŁA�����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�T�v�u������ӂ͊��S�Ƀf�����Ŗ��܂��Ă����B�g�D�������s����������Ă���B����܂ł̌����w�������v�悵�����萻�f���Ƃ͑S���������i�ł���B�{�肪�Q�����Ă���B�������Ȃ��B���X���X�����x�삷��x�����Ɍ������Ă��������˕Ԃ��ꂻ��ȏ�ǂ��ɕ������Ԃ��Ă悢�̂�������Ȃ��܂܍R�c�̐��������邾���ł���B�X�P�W���[�������͏��z�����A���N�O�����]�A����������O����̎�Ŏ��������̂��v�B |
| �@��T�D�Q�O���ۋ��s�̌������ɁA���{�̐����͐��ő�̎R��ɂ������������B�����グ�A�o�������̂����钪�����z���A�����鎞�A���̊���������@���ׂ����߂ɂ����a�������u���g���A�����̂��̂̂Ȃ��Őh�����đ�O�Ƌ��ɕ������鑶�݂ł����Ȃ��Ȃ��Ă����B����ȂNJ��ɂȂ�������B |
�
�@���̓��A�S���A���P���R�O�O�O�����W�߃f���B
�@���]���A�Q�O���ȍ~�̘A������������肵���B�Ȍ�A������ӁA�약����@�͍R�c�̃f���ɏI�����R�Ƃ���B |
�@�T�D�Q�P���A�S�w�A�嗬�h�n����\��P���������@��̓f���B�S�w�A�P�����A�s���A�P���T�O�O�O�������ꂼ��f���B
�@�T�D�Q�R���A�S�w�A�嗬�h��ܕS���A���@�f���Ōx�����ƏՓˁA�\�Z���ߕ߁B
�@�T�D�Q�S���A�w�ҒB�̈��ۖ�茤����ƍ�ƒB�̈��۔ᔻ�̉���b���ƂȂ��āA�u�ݓ��t�����E�v���E�V���ۍ̌��s���F�E�w�ҕ����l�W��v���J�Â����B�S�������Q�T�O�O�����W�܂����B�ێR�^�j���������āA�u���ۂ̖��́A���s�̌��̖�����Ƃ��āA����܂łƑS�����I�Ɉ�����i�K�ɓ������v���Ƃ��������B
�@�T�D�Q�T���A���]�w���E�А����̐N�J���ҁE�w���O�疼�A������c�̘g��˔j���Ď��@�f���B
�@�T�D�Q�U���A���ۉ���j�~������c��P�U���R�c�f�������s���ꂽ�B�P�V���]�̘J���ҁE�w���������͂��A������ӂ̘H���g�����ł��Ȃ��قǖ��߂�����O�̍����̓f���ƂȂ�B�S���łQ�O�O���̑�O����Ăɍs�����N���Ă���B�S�w�A�嗬�h�ꖜ���A�O�@�c�ʑO�Ɍ��W�A�I��������ӂ��W�O�U�N�f���A���嗬�h�s���A�ꖜ�ܐ疼�A����J�쉹�Ɍ��W���č�����ւċ���f���B
�@�����̓f���́A��f�����͉ʂĂ��Ȃ������A�ї�����Ԋ��A�v���J�[�h�̐��͍��X�Ƒ����Ă������B�]�]�]�ǂ̓����g�����ł��Ȃ��(�����V��)�L�l�ł������B�S�w�A�f�����͌������W�O�U�O�D�f�����J��Ԃ����ŁA�Ћ��̋c���⊲���͉{�����R�̂悤�ɍ����Ƃ��납�碃A���K�g�E�S�U�C�}�X�A�S�N���[�T���f�X��ƌJ��Ԃ��Ă����B���̖�A�m�g�j�̓f���̎����ƂƂ��ɁA���Y�}���L���{�{�̢���̂Ƃ���f���͐��R�ƌ����Ă��邯��ǂ��A�s���߂��̍s���̋N���鋰�ꂪ����̂ŁA�����������Ƃ̂Ȃ��悤�ɓw�͂��Ă���B�f���͋��炭���R�ƏI��邾�낤���������Ă���B
�@���������Œ��T�D�R�P���A�����̏�C������́A�u��������U���A�I���݈͊�h�������S�c��͂̑I���Ǘ����t�ōs���v�����\�A���Ƃ����ċc����̘g���Ɉ����߂����Ƃ����w�͂��Ă���`�Ղ�����B
�@�U�D�P���A�Љ�}��c�m�� �c�������E�̕��j������A�����ɑ�ꎟ���F���҂\�����B
�@�U�D�P���A�g�{������͂U���s���ψ����g�D�A�S�w�A�E�u���g�ƍs�������ɂ����B�����Z�Y�D�ێR�^�j��������オ�����B�u�A���|�@�n��
�^�C�v�̐��͎q���B�̗V�т̒��ł������悤�ɂȂ����B�����A���ʗ_�m�v��͋}�����炦�̉E���\�͑g�D������A�ʓ����Ƃ��đS�w�A���P���v��ŌR���������s�Ȃ��n�߂��B�u���g�́A�������i��p���č���˓���ڎw���A
�������̍��荞�݂����������j�̂��ƁA��O�I�ɂ͖k���H�q�S�w�A�ψ����㗝���f���̑��w���ɂ��āA�����u���g���s���͓��ʍs���������������B
������˓��̂��߂̋Z�p�������邩�ɐi�߂��B
| �y�S�w�A��X�疼�����@�˓������z |
| �@�U�D�R���A�S�w�A�X�疼�����N�W��k�O�@��ꖋ����ّO�l�̌�A���@�ɓ˓��B�w�������̓��[�v�œS�̖�������|���Ċ��@�̒��ɓ���A���b�Ԃ���������o�����B�x�������g���b�N�ŏP���Ă����S�ʃK���X�Ɋۑ���˂�����Ōx������ّ������Ă���B�����͂U���߂��܂ŌJ��Ԃ���A�P�R���̊w�����ߕ߁A�P�U�����~�}�ԑ���ƂȂ����B�x�����̕����X�R���Ɣ��\���ꂽ�B |
�@�U�D�S���A��P�V������s���͍��S�J���҂𒆐S�ɑS���łT�U�O���l���Q�� ���A���S�J�g�͈��ۉ���j�~�̏��̐����X�g���C�L��ł����B���]�́A�S���I�ɂP���Ԃ̐����[�l�X�g�����s�����B�S�w�A�R�T�O�O��������f�������S�X�g���x�������B�S�w�A�嗬�E���嗬�h�A���J�E���J�̂U�D�S�[�l�X�g�Ɋe��v�w�Ŏx���s���A�ߌ�嗬�h�R�疼�E���嗬�h�V�疼���ĉ����č���f���i�S�������T�U�O�����j�B
�@���̍��A���Y�}�́A�������������\��̃A�C�N�K���j�~�̊����N���ɂ����B���}�̍u�a����{�͔��A���n�A�]������K�肩�炷�锽�ēƗ������̏d���ł������B�Љ�}�Վ����A���]��������R�c�����Ɏ��g�ނ��Ƃ����߂��B�U�D�U���A�s���A���A�����A�C�N������Ȃ�H�c�f�������s���邱�Ƃ����肵���B
�@�������A���̎��u���g���v�������哝�̔鏑���n�K�`�[�E�A�C�N�K���j�~�����g��ł��Ȃ���������B����ɂ͐����I�����̑��Ⴊ����悤�ŁA�u�A�C�N�K���j�~�́A���݈��ۓ����̔��ē����ւ̘c�ȁv�Ƃ��Ă����悤�ł���B���炭�V�����́A�鍑��`�����_�ɂ�荑���̐������͂ɑ��铬��������������{�Ɛ莑�{��`�̑œ|�����`�Ƃ��Ă���A����ɑ��ē����́A�A�����J�鍑��`���̏]�����Ƙ_�ɂ��A�����������ēI�ȓ���������ڂƂȂ�Ƃ��Ă����悤�ł���B���̂��Ƃ́A����c�������̃C���^�r���[�ł��m��邱�Ƃł�����B�c�����́A�u���Y�}�͈��ۓ����ē����ɂ����Ă�������
�����B�S�w�A�̏��N�́A������ہA���݂Ƃ��������Ɏ����Ă������Ƃ����B
�����ɓ�̕�����ڂ������ł��v�i�U�R�D�Q�D�Q�U�D�s�a�r�C���^�r���[�j�ƓI�m�Ɏw�E���Ă���B
�@���̍��A�x�����̃g�b�v�O��x�����������ے����A�u���g�̎����ǂ�K��Ă���B��A�C�N�K���ɑ��đS�w�A�͂ǂ���������̒��ڎ����ł������B��w�u���g�͕ʂɉ������Ȃ��B�������A��O�̓{�肪�ǂ��������邩�́A������Ȃ��B��������w�����������Ǝv���Ă��A�S�D�Q�U�ȗ��A�u���g�̊����͂قƂ�ǃp�N���Ă��邶��Ȃ����B�A���𑁂��Ԃ��x�Ƃ����Ă�����B���̂������ǂ����͒m��Ȃ����A���܂��Ă����A���̂����A�����Ǝ��ȊO�́A�S�����ێ߂ɂȂ����(�����k)�Ɠ`�����Ă���B�܂��ɒ������~�̋삯�������s���Ă����B
| �y��n�K�`�[����������z |
|
�@�U�D�P�O���A���ۉ���j�~��P�W������s���B�S�w�A�T�O�O�O�������̓f���B������c��������ӂłQ�O�����l�f���B�A�C�[���n���[�K���̘I�������Ƃ��ăn�K�`�[�i�哝�̐V���W��鏑�j�́A�H�c��`�œ����n�J���ҁE�w���̐����̃f�����̍R�c�ɏo�}����ꂽ�B�n�K�`�[�̏�����Ԃ́A�ǂ������킯���x�����\������ʂ�ɓ������A�f�����̑���̒��ɓ˂����ݢ������ƂȂ����B�ČR�w���R�v�^�[�ƌx���̋~���ł���ƉH�c��E�o�A��������A�����J��g�قɓ���Ƃ���������
�i�u�n�K�`�[�����v�j�����������B
 �i���_�D���ρj�@�n�K�`�[�����ɂ��� �i���_�D���ρj�@�n�K�`�[�����ɂ��� |
�@���́u�n�K�`�[�����v�́A�u�U�O�N���ۓ����v�Ō����������y�і����̗B��Ƃ����ėǂ��퓬�I�s���ł������B�u�U�O�N���ۓ����v�Ɋւ����N�}���̌��́A�����ς炱�̎��̂��ƂɊ֘A���Ă���B����ȊO�̖ʂł̌��́A�}�̎w���Ƃ͊W�Ȃ��u��O�I�ɐ���オ�����v�����̕��͋C�����L����f�J
�_���X�ł����Ȃ��A�Ƃ������炨�������ł��傤���B�Ȃ��A���̎��̓}�n�퓬�I�w�������̎�͂́A���̌�̍\�����v�h���������̉ߒ��œ}�����яo���Ă������ƂɂȂ�\�����v�h�n�A������А���ёh�̌����ɂȂ镔���ł������B
�@�u��`�Y�̢���{���Y�}�j�o����ɋ���A��n�K�|�e�B�j�~�̌v��́A�������J��_�i�����A�}�����ψ���N�w�������j�Ƒ��k���ė��Ă����B�����A�n�K�|�e�B�͕K���w���R�v�^�[���g���Ƃ����\�z���L�����Ă����B���Ƀw���R�v�^�[����`�̌����̑O�ɂ����B���������́A�ނ��Ԃœ����֗�����̂Ɣ��f���āA���J��_�ɁA�ٓV����̓}�̐��s�����ڎw������悤�˗������B---�Y�Ɠ��H����ٓV���ւ����āA�Љ�}�n�̘J���g���Ȃǂ̕��������W���ĕ���ł����B�ނ�͋�`���̏���ɘA��A���֓��邱�Ƃ���]�����B����̋��Y�}�̕����͓����J���A�ނ�͋�`���ւƈړ������B���̈ړ������փn�K�|�e�B�悳������g�̎Ԃ������ɓ˂����̂��A���̗L���Ȏ����̔��[�ł��飂Ɩ�������Ă���B |
|
| �y �U�O�N���ۓ��������z |
| �@�U�D�P�O���A�����哱�ɂ��u�n�K�`�[�����v���A�u�� �g�n�S�w�A��傢�Ɏh��������������A�U�D�P�T������c����s���ɑS�͓������ӎv���ꂵ���B�k���H����S�w�A�ψ����㗝�Ɍ���i�����ψ����͑ߕߍS�����j�����B
�ȍ~��i�Ɠ����̃G�|�b�N�D���C�L���O�Ɍ������Ă������ƂƂȂ����B�S�w�A�w�����́A��J���҂̃X�g�̓_�����ɂ���ď��K�͂Ȃ��̂ɂ���Ă���B���Y�}�͈��ۓ����ē����ɂ��炵�A������c���E���I�ȃ_���N������Ԃ̒��Ŏ��R�������͂ޓ��͍���˓��ȊO�ɂȂ���ƃA�W�����B |
�@�U�D�P�P���A�S�w�A�̑S������s���B�S�w�A�A��[�f�[�Ɍĉ����S������s���A�����ł͎嗬�h���Q�@�c���o�@�j�~����f���̌�A�݁E�n�K�`���k�j�~�̂��߂T�疼�Ŏ��@��̓f���A���嗬�h�P�����͐_�{�G��ّO�Ɍ��W�̌�A����E�đ�g�قɃf���B
�@�U�D�P�Q���A�đ�g���ݎ�K��A�n�K�`�[���Ɉ⊶�̈ӂ�`����B
�@�U�D�P�Q���A�A�C�[���n���[�͗\��ʂ�K���̗��ɏo���A�U�D�P�S���A�}�j���ɓ����ҋ@�����B
�@�U�D�P�R���A�x�������A�n�K�`�[�����ō|�ǐ�S�J�g�A�����A�@�����{���B����吶���H�����ߕ߂����B
�@�U�D�P�S���A�u���g�s�w�ב��c�A�U�D�P�T����\���W��s���ŏI����A�P�T�������ɉ��U�A�e��w�ŏ����i�ށB
�@�U�D�P�S���A�S�w�A�̕s�����L���b�`�����x�����̎O�䂪�f���̋K�͂�T��Ƀu���g���L�ǂ�\�h���Ă���B
| �y�ݎ��A���q���o����v�����A���ۂ����z |
|
�@���̍��A�ݎ́A�h�q�������̐ԏ�@�����Ăт��A�A�C�N�K���̍ۂ̌x���Ɏ��q���̏o����v�����Ă���B�ԏ�́A�T�v�����́A�ł��܂���B���q���̐����R���Ƃ��Ă̓o��́A�x���������Ȃ��B���X�N���傫�����飂Ɠ����Ă���B���c�ꎟ���㖋�����������Ȃ������B
|
| �y�ݎ��A���ʗ_�m�v�ɉE���̎����o�����˗�����z |
|
�@�ݎ͎��q���o����f�O�������A�A�����J�哝�̃A�C�[���n���[�ƁA�ނ��H�c�܂ŏo�}����q���q�g���a�V�c����q���邽�߂ɉE���\�͒c�̑哮�����v�����A�u�X���ƐV���@���c�́v�����߂�悤�Ɏ����}�̊����Ɏw�������B���݂̊̈˗����������̂����ʗ_�m�v�ł���B�ނ͋}篁A�f�����j�~��̂��߁A���܂��܂ȉE���O���[�v�Ɩ\�͒c�̑g�D���ɏ��o�����B
�@�U�D�P�S���A�哌�m�𒆐S�ɁA�_�Ж{���A�����̉ƁA���F�A�A�������A���A�\�͒c���b�����������A�U�D�P�T���̈��۔��̃f������ւ̖\�͍U�����v�悵���B
|
| �y�S�w�A�̐擪���������ʗp��ɓ˓��A�@�����ƏՓˁB�����q�q�s�E�����z |
|
�@�U�D�P�T���A������c�̑�P�W������s���A���ۉ���j�~�̑�S���X�g�����s���ꂽ�B������c�A��18������s���B�������獑�J�D���J���X�g���C�L�ɓ˓����A���]�́A111�P�Y�S���T�W�O���̘J���҂������ɂȂ��ꍞ�Ɣ��\�����B�����ł́A�P�T���l�̍���f����������ꂽ�B��O�́A���R����f�����Ăт����鋤�Y�}��̎����n�߂Ă���A�Љ�}�ɂ����z��s�����Ă����B
�@�u���g�n�S�w�A�́u����˓����j�v��ł��o���A�嗬�h�P���V�疼���W�A�T��������ʗp��ɏW�������B���̎��A�ېV�s�����Ɩ����E�����A������ӂŃf�������P�������B�ߌ�T���߂��A�����ʍs���̃f�����ɁA���̢�ېV�s���ࣖ��̉E�������_���ӂ���ďP���|����A��W�O�������������B����Ɏh�����ꂽ�悤�Ȍ`�ɂȂ�A�擪�����������ʗp��ɓ˓��˔j�����B����D����D����̊w������͂Ƃ���T�疼���\���ɓ������B���s����ĂъĂ��������̖k��H�q������`�J�[�ɏ��w��������Ă����B�����̃f�����͑S���f��̏W�c�������B������̂̓X�N���������������B
�@�ߌ�V���߂��A�x������S�@���������͔r�����J�n�����B�S�w�A�����Ɍx�_�̉J���U�艺�낳�ꂽ�B���̌x�����Ƃ̏ՓˍŒ��Ƀu���g���������Ɠ��啶�w���R�N���ł����������q�q�i�Q�Q�A��e�W�u�l�m�ꂸ���܂�v�O�ꏑ�[�j�����S���鎖�����N�������B
�@�ߌ�W�����A�u����u���g�����ƁE�������v�̔߂��݂Ɠ{��ɔR�����R�疼�̊w���f���������ނ𐮂��A�Ăэ���\���ɓ���A�x�����̕�͂̒��ōR�c�W����J�����B��ʗp��t�߂ُ͈�ȋ����Ƌْ������܂��Ă����B
| �@��Љ�}�̑�c�m�̓I���I���������B���Y�}�����͐���f���̎��ɂ͉{�����R�݂����Ɏ��U���Ĉ��z�����ׂ�ȂɁA���̎��͒N��l�Ƃ��ďo�Ă��Ȃ�������B |
�@�ߌ�P�O���߂��A�ēx�̎��͔r�����s���A�s���̋~�}�Ԃ����������ꂽ�B���̓��̋]���҂͎��҂P���A�d�y���V�P�Q���A��ߕߎ҂P�U�V���B���̎��s���A�Ɍ��W�����P���T�疼�̊w���f�����͍�����c�̓����̂��Ƃō������s���Ă����B��P�P���߂�����A������A�@����A����Ȃǂ̋��������P�疼�������q��S�z���ċ삯�������A�x������S�@�����͂����ɂ��P���������Ă���B����̕W�҂������������Ă���B
�@
�@��O�ɉ����o���ꂽ�w���͖�W�疼�ō����O�ɍ��荞�B�P�P�����o���P�[�h����ɕ��ׂĂ������g���b�N�������o���ĉ��コ���Ă���B���̊ԗ����̍Œ��A����w������������E����Ă��܂��B�J���҂̊F������ꏏ�ɓ����Ă���������Ƌ����Ȃ���i���Ă���B�J���҃f�����͂���ɉ����Ȃ������B�Љ�}�c���͓��h�����R����f������Ăт������������ʼn��̖��ɂ������Ȃ������B
�@���̓��̑S�w�A�̓������A���c�v�����͎��̂悤�ɋL�^���Ă���B
�@�u�U���P�T���A�S�w�A�́A17000�������W���A���̂���1500�����\���ɓ˓������B�@�����͊w���ɏP��������A�x�_�̉J���~�点�A�����q�q���s�E�����B������712���A�ߕߎ�167���̑匃���ł������B
�@���̓����ƍD�ȑΏ̂��݂����̂��A�s���A�ł������B�s���A�́A�_�{�G��ّO��15000�����W�߂ďW����J���A����������߂Ĕ��d�F���܂ŕ��a�f�����s�������A�I���_�ł͎O���̈�Ɍ������Ă����B�u�w���s�E�v�̕�ɐڂ��Ď�������J�������A�V�K���Z�̖Ҕ��ɏo����āA�u�����Ԃ��č���Ɍ��������v�Ƃ������s����Ă�ی����A�S�w�A�̎�����َE���Ă��܂����v�B |
|
|
 (���_�D����)�@�ؑ����̏،� (���_�D����)�@�ؑ����̏،�
|
�@�����q�q�̎��S��ɕt���A�u���܂��s�v��ɁE�ؑ������M�d�،����Ă���B�ʐ��́A�u����̍\���Ōx�@���̌R�C�Ɠ��l�̌ł��C�ŏR��E����A�Ԃ̉��ɏR�荞�܂�Ă����v�Ƃ���Ă��邪�A�u�������v���咣���Ă���B���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�ڂ̑O�ŁA�x���́u�|����I�v�̍��߁A�~�̌x�_�ɓ�������ꂽ�w���̑��A�h�h�b�Əd�Ȃ��ē|��Ă����̂ł��B
�@�������_�J�_�̎ʐ^�W�A�w�{��Ɣ߂��݂̋L�^�x�Ɋւ��ẮA�u60�N���ۂŎS�E���ꂽ���吶�����q�q�����ꂩ��^���p���ʂ����ʐ^�����߂��v�Ƃ̔�]������܂����A40�N��Ƀ��t�g�v���X�����ł�60�N����40���N�̏o�����̍ہA�g��R�s�[�������̂��A���N�A�������Ă�����A�ŏ��ɁA�|�ꂽ�f��
���̒�����A�\���Ŋ����q�q������������ĉ^��ł����̂́A���ł����B�X�q�Ȃǂ���A���f�ł��܂��B���́A���O�r�[������Ă����̂ŁA��l�ɋ~���o�����̂ł��傤�B
�@�����̓����p���ȓ������ŁA�w��������̈ψ��̕��͂Ɖ�z�ɂ��ƁA�ޏ��́A�����A�댯�ȃf���ɂ͏��q�w�����Q�������Ȃ����ƂɂȂ��Ă����̂ɁA�����A�u�����v�ƌ���Ă����Ƃ̂��Ƃł��B�����́A�j�Ə��ł́A�g�̂̍�肪�����ɈႤ�̂ŁA�h�h�b�Ɠ|�ꂽ�ۂɁA���~���ɂȂ����̂ł��傤�B�ޏ��́A����˓��̕��j�����肵����ɂ����͂��ł�����A�����̐ӔC���A���������`�ʼnʂ������������̂ł��傤�B�c���ꂽ�����ɂ��ƁA���������L�͂ɂȂ�܂��B |
�@�v���ɁA�����ߒ��̎��҂ɑ��Ĉ�������C�����͉���ς��Ȃ��̂ł��邩��A�ߓx�ɐ������p����������߁i����͋p���Ė`���ł��낤�j�A���̏�������Ɍ����������m�F���`���邱�Ƃ��^�����̃}�i�[�앗�ɂ����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B���������Ӗ��ł́A�ؑ����̎w�E�͏d�v�ȏ،��ł���悤�Ɏv����B
�@�Q�O�O�T�D�W�D�R�O���@������q |
| �y�U�D�P�T�����A�����̏q���z |
|
�@���̎��̂��Ƃ𓇎��͂����L���Ă���B
| �@��Ō�̓y�d��ƂȂ������̓����ŁA�u���g�͊v���I�w���Ƌ��ɍ���ɓ˓������B�����ău���g�n���ȗ��̓��m�����q�q�����r�����B�E���Ȏ̂Đg�̓����ɂ��ւ�炸�A�@���o����A�����o���ꂽ�f�����́A���͂�w�����������Ȃ������B�����ł����ĉ��シ�鑕�b�Ԃ�O�ɁA�Ȃ����ނ𐮂��悤�Ƃ���w���̊Ԃɂ����āA���c�͊�ʂ��g�������A�{��Ȃ���E����������Q�W�̈�l�ł����Ȃ������B�₪�č×ܒe���������A�P���|����x�����ɒǂ��A�U��U��o���o���ɂȂ����f�������s�����Ă����Ƃ��A�ނ͂���ƂƂ��ɋ삯�����Ă�����l�̎s���ł����Ȃ������B�x�����ɑΛ������܂�Ƀf���̐擪�ŃX�N������g�݁A����������炸�w���w�����Ƃ��Ă������c�̎p�́A�����ł͌���ׂ��������B����͂����ɐ��c�����̎p�ł͂Ȃ������B���̓����̃u���g�̎p���̂��̂ł������̂��B�����āA�܂��A�P�X�U�O�N�̓��{�̊v���I��O�́A����ɂ͓��{�̍����^���̋Ïk�����}�ł͂Ȃ��������(����W�)�B |
| �@�u�����I�Ȏ��́A�v����ɐ����I�Ȏ��ł����āB�Ō�̎������A�N�̎�ɂ���āA�N�̞��_�ɂ���Đ��������́A�d�v�Ȗ��ł͂Ȃ��v�i�k�b�j�B |
�@���c���́A�u���g�@�֎��u����v�P�V���̒Ǔ����Ŏ��̂悤�ɒǓ����Ă���B
| �@�u�N���s�E�������{�l�A�ݎ��{�Ɠ��t��œ|���邽�߂ɁA�����Ɍ���z�u�ɂ��v�B |
�@�g�{�������́A�u�[���̏I���v�̒��Ŏ��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@�u�P�T���i�U���j��A���̐�[��������̍\���ɂ����āA������Ƃ肩���Q�́A�����炩�ɂ����炵���C���^�[�i�V���i���Y���̉Q�ł������B����͂Ȃɂ������������̎�̂�l���Ƃ��Ă̂��Ԃg�ƁA���̘A�тƂ��Ă̑�O�̂Ȃ��ɂ����A�����a�O���Ă��鍑�ƌ��͂̍��ƈӎu�i���ۏ��j�ɂ������Ă��������C���^�[�i�V���i���Y���̎p���ɂ�ʂ���Ă����B���@�̂܂����Ƃ����̉��ւȂ���Ă䂭�Q�́A�Љ��`���ƌ��Ƃ�����ȃn���`���E���������A���̂悤���̂��߂ɂ͎㏬�l���̍��ƌ��͂ɂ������邽������������ɋK�肵�A�܂��l���̗��v�Ɩ��W�ɂ�������ȋʏ��Ƃ��ČŎ�����ϑԓI�ȃi�V���i���Y���̖S���w���������̂����ɚ�������Ă����B����̓R�~���^�[�����̑����v����`�̕���Ō�̂��������ے�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ������B�����͂����Ȃ邽�������ɂ����Ă��A����������j�~���A�Ђ������O�����������̎w���������Ă�������Ȃ����Ƃ�]�݁A�Ђ����炽�������̌��ꂩ�牓�����낤�Ƃ���p���ɂ�ʂ���Ă����̂ł���v�B |
�@�g�{�������́A�u�V���[�Y�Q�O���I�̋L���v�����́u���{���{��`�ɋt�炤�Ɨ������v�̒��Ŏ��̂悤�ɋL���Ă���B
�@11��27��(1959�N)�ɑS�w�A�嗬�h������\���ɓ������s���Ȃǂ́A�l�͌��Ă��āw���������Ƃ�����ȁx�Ƃ����Ԃ�G������܂����B���߂Ă��A���������f���̂����Ɠ����̎d���́A�Ǝv���܂����B���������̂ɏ��߂ďo������Ƃ������ƂŁA����ŁA����Łu����͂����������x�Ǝv���Č��Ă������x�Ȃ炸���x������ł��B�������z�����z���݂����ɁA�����Ƃ��ߕ߂��ꂽ�肵�đŌ����Ă��܂����Ƃ����悤�ɑ����Ă��܂����B���ꂪ�����ƈ��ۓ�����S�̓I�ɐ���グ�錴���͂ɂȂ����Ǝv���܂����A�l�͋����h�����܂����B�ނ�͖��S�C�ŗ��\�ɂ݂��邯��ǂ��̂��������R�Ƃ������A���{�̌��F�����ɂ͐�ɂȂ����R���Ɩz��������������ł��B����łƂĂ��������A�w�����A�����������̂�����x�Ǝv���܂����B�w�������̂������ȁx�Ƃ�����������������ł��B
�@����ɓ��{�̍��������߂āA���������̍l���ōs�����A�Љ���̕s���ȂƂ���ɍU���������Ă������Ӗ��͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ����낤�A�Ǝv���Ă��܂��B���鐭���^�������������̑g�D����ł��Ă����݂����ɂ�����Ƃ����������s���l�����A���ꂪ���܌`�Ƃ��Ă��邩�Ȃ�������Ȃ��āA����͔��ɂ����炵�������������炵�āA����ł�����ς�����Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��B�����A�\�A�ɂ������ɂ��A�������ɂ����Ƃ����Ɨ������I�Ȏ咣�̓o�J�ɂ���܂������ǁA�������A���j�̓������݂�����Ȃ��Ă���ł��傤�B���ꂩ��ǂ��ς�邩�킩��܂��ǁA��͂�Ӗ��͂������Ǝv���܂��B�l�����Ƃ��Ă͂����Ƃ��̂Ƃ��ɏo���Ƃ������Ƃł��B |
�@�����\�i���́A��܌ܔN���}����Z���N�ɂ�������ݣ�Ŏ��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@������q�q���s�E���ꂽ�Z����ܓ���A���͏O�c�@�̋c���ʉ�̒��ɗՎ��~�����𓇓c�v�N�i�}�{�����L�j�Ȃǒ��ԂƂ�������ɐ݂��A�����̃u���h�n�̈�w�A�̏��N�ƈꏏ�ɖ�̖�����̂��m�炸�������B���̓��A�]�c�O�Y���ȂǎЉ�}�̍���c���c��Z�Z���͋@�����̕����𗁂т����Ȃ���x�@�@�����ɍR�c���A�c���ʉ�n���ɗՎ����u��Ƃ��Đݒu���ꂽ���ɂ��鑽���̏d�������J���ҁA�w���̑����ߕ���v�����ē������̂ł������B�]�c�O�Y���̔�����U�藐���ē����p�́A�����Ȃ����̋L���ɐ��X�����B���̓��A��ꎟ�̒e���ɍR�c���ďW�܂�����w�̋����A�������A�u�t�A�����������͂���ɑ�̒e�������炢�A���т��������d�y���҂��o�����̂ł������B�Ȃ��ɂ́A�R�w�@��̏��������A�����̒m���Ă���w�������������̂ł͂Ȃ����ƐS�z���ĎЉ�}�{���̂���O���ɗ����Ƃ���܁Z���̋@�����Ƀ����`���������d�������Ƃ������Ƃ���������B |
�@�r���������͂�������Ă���B
| �@�T�v���w���B�����ۂɈӋC����Ȃ��ƁA�e���ɒ��肸�ɂ���Ă����Ƃ������Ƃ́A���Ɋ������ė܂��o�邱�Ƃ������ł��B�l�����������Ⴉ������A�����Đg�̂������Ȃ�������A�w�����b�g���Ԃ��āA�Q�o�_�����ďo�����悤�Ǝv�����Ƃ�����܂���B�ق�ƂɁB�U�O�N���ۂ̎��ɁA����|�����܂�Ȃ��Ȃ��āA��яo�����Ƃ�����A�Ɠ��ɁA���̂悤�ȂV�O�߂����N��肪�o�čs�������āA�����̌x�_�ň�˂����ꂽ��A�������ł��܂������߂Ȃ����A�Ƃ����Ďv���Ƃǂ܂�܂���(��)��A��ǂ��̍��̋��Y�}�����āA�Ⴆ�v�z�I�ɈႨ�����A���������ƁA�}�W��A�g�D�̖ʂňႨ�����A���{�̌��͂Ɠ����Ă�����̂�r������Ȃ�āA����ȋ��Y�}�́A���͌������Ƃ������(����̐����ģ)�B |
�@���c�ȎO���́A�u�U�D�P�T�����@�����̉Q������\�@���̖ڂŌ����x�@���̖͂\�́@�\�v�Ƃ������͂������c���Ă���B���̈�߂͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�u�x�����͊拭�ȃN�c���͂��A�S�X�����Ԃ�A�R���_�������Ă����B���͑S�w�A�w�����̂����ɂ͔��̂��̂����A�������Q�����Ă��鐔��l�̊w���́A�Ƃɂ����A�܂������̑f��ł������B�w���̑����̓V���c�p�ł���A�N�c���^���O�c�A�Ȃ��ɂ̓n�_�V�̊w���������B�݂��ɘr��g��ʼn������ƈȊO�Ɋw���̇����́��͂Ȃ����B
(����)
�@�x�@�͎����������ɂ���āA���@�I�ɕ��͂�^�����Ă���̂��B�������͐g�̂Ɛ�������邽�߂ɍ��@�I�ɕ��͂��x�@�ɑ������B����䂦�ɁA���̕��͂����@�I�ɍs�g�����悤�v�����錠��������B�x���ɂ���ĕs�@�ɍs�g���ꂽ���͂����A���\�́��ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B�x���͖��炩�ɇ��\�́����s�g�����v�B |
�@
�@�����a�����́u�䂪�S�͐ɂ��炸�v�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�T���u�c��Ƃ������̂́A�����I���ɂ���Ė����o�ȍ����̌��������{�������A�c��Ƃ��������̏�]���l���Y�ދ@�ւ�}��ɂ��Ė@�������`������A�����̂킸���ꕔ�����s���������I�ɒn���L���҂ɂ�܂������̂ɂ����Ȃ��B�i�����j�������A������ƌ����āA��������ɔw�������Ă��邾���ł́A���͂̓Ɛ�ƏW���́A�s��ɂ�鍑�ƕ���Ƃ����悤�ȓV�r�n�ς̂Ƃ��܂ʼn��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i�����j���Ȃ��Ƃ��A���{���[���A�������[�Ől�X��ꑮ������A���z���ǂ����Œf���낤�Ƃ��鎎�݂͂��Ă݂Ă������B�i�����j�ꉞ����͌��݂̋c��x��e�F���āA�܂葽���������`�ɂ͔����Ȃ����ꂩ��i�����j�����������Ă����B�e�F���邱�Ƃ͐�Ύ����邱�ƂƂ͓����ł͂Ȃ��A�����Ȃ����Ƃ͂���ȏ�̐��x�����蓾�Ȃ��Ǝv���Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ȃ��B�i�����j�������͒�����j�������߂ɓ�������̂ł͂Ȃ��A���U�̒��������{���I�Ȓ����ɑւ��������߂ɓ����̂��v�B |
�@�����i����w���͎��̂悤�� �������Ă���B
�@�u���̎����Ōx���̍s���߂��͖��炩�ł���A�w����a����҂Ƃ��čR�c����B�w���̍s���͐ؔ�������@���� �����̂ŁA���̍s�����Ƃ点���̂͐V���ۋ��s�̌��ŋc���`����@�ɒǂ����݁A����ƍ�����V���������ɂ�������炸�A�����ӔC�҂�����̋@�\��������K�Ȏ�i�������Ƃ�Ȃ��������Ƃɂ���B
�@�Ⴆ�Ή��U�Ȃǂ��s���Ă���Ίw���͕����ȕ��@�ňӎv��\������@���^�����A�P�T���̂悤�ȍs���͂��Ȃ��� �����낤�B�Ƃ��낪���̑[�u���Ƃ�ꂸ�A���̏�A�C�N���������Ƃ������߁A�w���ɖ����`�̓w�͂����͂��Ƃ�����]����^�������̂Ŋw��������ӂ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���̂悤�Ȏ��Ԃł͑�w�͊w������̔C�� ���ʂ������Ƃ��ł��Ȃ�����łȂ��A�����ȂǂŊw���ɕ����ȍs�������߂Ă����ʂȂ��B���̎�|�Ɋ�Â��Đ����ӔC�҂������`�I�ӔC���������邱�ƈȊO�ɉ����͂Ȃ��A���̓w�͂����邱�Ƃ������v�]����v�B |
|
| �y�����q�q�s�E���������Ɍ����������{���̑Ή��z |
|
�@���Y�}�w���҂����́A��g���b�L�X�g�̒����ɏ��ȣ�ƃs�P�b�g���C����A�f����������������ʂɗ����������B��Í��̑�X�؉�����i�ґ�j�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@��f�����҂�����Ǝ�芪���A�Ђ��߂��Ă��鍑����ӂŁA���Ɠ����悤�Ȓn��ψ���Ζ����̑����̓��u�������A�Ԃ��r�͂������āA��ʐ����̂悤�Ȗ�����炳��Ă��܂����B����́A�ǂ�������ʐ����ł��邩�Ƃ����ƁA�̓����肷��悤�Ȍ������f��������ɂԂ��A�@�����ɂԂ��Ă���S�w�A�̈ꂩ���܂�̕����ƁA�l���͂���̏\�{�������āA���ւ̗���ׂ��č���߂����ăf�����Ă���J���g���̑啔���Ƃ̊ԂɁA�����ē����āi�����ē����ĂƂ������́A�\�߁A���x�ʍs�֎~�̗��ĎD�̂悤�Ɉ�������ė����Ă��āA�j�J���g���������̃f�����E�̂ق��ɉ~���ɗ��ꂳ���čs���A����������ʐ����ł�����B |
| �@��J���҂Ɗw���Ƃ���{�������Ȃ������B���̏��Ȃ��Ƃ���̌����́A���������Y�}�����g�������č���������w����ɂ������̂ł��B�킸���T�O���[�g���̊Ԋu�E�͂��Ȃ̂ɁA���̊Ԋu�����߂��A���ߐs������邱�Ƃ́A�U�O�N���ۓ����ł͂Ƃ��Ƃ�����܂���ł������ |
| �@��{�{���L�����A����f�����܂��܂��c��オ��A���R�Ƃ��n�߁A��s�̎��鏊���f���ɂ���Ă���ΐ�������n�߂����̎����A�܂�ŃZ�L������悤�ɐl�X���X���Ɉ��o�������̎����ɁA�}�{���ɑS���̐ӔC�҂��W�߂āA�w�W�O�U�O�f���͂܂���Ȃ��x�Ƃ������B���������A�Ƃ������Ƃ��A�����s�̖������畷�����ꂽ��A��{�������w���������Ƃ̃|�C���g�́A�W�O�U�O�f���͂�߂�A�Ƃ������Ƃ��A�Ƃ����̂ł��B���M���^�̎��Ɂ|�����āA�������̍��́A�W�O�U�O�Ȃǂ́w�����鐺�x���w���Ȃ����x���A���ł��q���ł����܂����Ă����̂ł����磁A�w�w�A�J�n�^�x�̌��Ђ���咣�́A���ۂ�@���ɓ������A�ł͂Ȃ��āA�{���ɁA�w�W�O�U�O�f���͂��������x�Ƃ������Ƃ��A���ꂾ�����咣���Ă����̂ł��B�����A�}�T�J�ł͂���܂���ł����B�ォ��v���A�{�{�_�Ƃ���}�����ɂƂ��āA�w�W�O�U�O�f�����~�߂�x�Ƃ����̂��w���ۂ�@���ɓ������x�̕��j�ɑ��Ȃ�Ȃ�������ł���B |
�@�������͂����ł��M�d�ȏ،����c���Ă���B
| �@����̂����w�w�����E���ꂽ�x�Ƃ̏�d���̂悤�ȑ����Ńf�����̒��𑖂�ʂ����B�Ƃ��낪�A�ł���B���Y�}�́A�w�����ɗ�����U�x�̎w�߂����ăf���̑�����ǂ�ǂ���U�ւƗU�����n�߂��̂ł���B�w�ӂ�����ȁx�A�w�A��ȁx�Ǝ��͕����������B���ɋ߂Â����Ƃ��邪�A���������ڂ̋@�������ɏR�U�炳��Ă��܂��B�]�]�]���̓A���ɔG�ꂽ���r�̘r�͂��Ђ���Ԃ��Ă����̐Ԃ��r�͂ɂ����B�w���{���Y�}�x�̘r�͂͂����Ȃ��B�w��������Ȕ�l���I�ȓ}�ɂ͂����Ȃ��x�A�Z�����Ԃł͂��������A���������͎����̊�����m���߂Ă�����B |
�@���̎��A�j���[�X�Ŏ��҂��o�����Ƃ��m�����{���D�ѓc�����R�Ǝ����Ԃł���Ă��āA�A�J�n�^�L�҂ɂ����R�Ƣ�����ԎE���ꂽ�ƕ��������A���l���̂���Ɛq�˂Ă���B�L�҂͢�悭������Ȃ����A�����ł͂�����m�F�ł����͈̂�l�����ł���Ɠ�����ƁA��ȂA��������l����A��g���b�L�X�g���낤�B�V�l�ʂƕ����Ă�������Ɠf���̂Ă�悤�ɂ����Č������ɂ����Ɠ`�����Ă���B
|
| �y�����q�q�s�E�ɍR�c�����ۉ����j�~���悤�Ƃ���J�E�w�ܖ��l�����̓f���z |
|
�@�U�D�P�U�|�P�V���A���A�����q�q�s�E�ɍR�c���A�J�E�w�T���l�������̓f�����s��ꂽ�B������ʗp��͊�����̎��𓉂ތ��ԂƏč��̉���Ŗ��߂�ꂽ�B�����q�q�̎��͏u���Ԃɓ`���A�����̐l�X�̐S���������B���ɓ���ł͋������w������ĂɍR�c�s���ɗ����オ��A�����͋���ۂɂȂ����B
�@���̎��֎����������Ă���B�����܂œ������u���g�n�w�����˂���ɋA�����U�D�P�U�������A�w�X�Ţ�������͑S�w�A�ł��B���̍���f���ő����̕����҂��o���܂����B�J���p�����肢���܂���Ƒi���Ă����w���������������A���嗬�h��X�،n�̖����̘A�������ł������B��P�S�O���~�]�W�܂����Ƃ����Ă��邪�A���̎��̃J���p����������c�ɋ~�����Ƃ��Ē��ꂽ�̂Ȃ�܂��������̌`�Ղ͖����B���������u���g�n����X�Ƀf�����삯�A����T�D�_��Ɣl���𗁂т������A�}�{�����牞�V�͖��������B����͢���T�D�_������Ɖ]���Ă���B
�@�����\�i���̢�T�T�N���}����U�V�N�ɂ�������ݣ�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �U�D�P�T�̗����A��w�A�A�S�w�A�̓����̏��L���k���H�q�N��ƂU�D�P�T�~���{�����Љ�}�{�����Ɉꎺ������Đ݂��A���̈ψ����ɂ͍�{�Q�c�@�c���i�����m�s���j�A���������ǒ��Ƃ������ƂŊ������J�n�����B�S���ɃJ���p���Ăт����A�P�T�O���~�߂��a�@�̎x�����Ȃǂ́A�w��Ƃ��̃J���p�̒�����x�������̂ł���B�����Ăقږ�ꃖ�N�̂������U�D�P�T�~���{���͊��������B���̋~���^���̑����Ƃ��āA�����͓}�����S�ƂȂ��āA�V���ȋ~���g�D���������ׂ��������͂��߂��B����Ƃ����̂��A���Y�}�n�́g�����~����h���������瑗���Ă����U�D�P�T�����̋]���҂ɑ���P�����i���{�~�łP�T�O���~�j�𐋂Ɏ��L���Ă��܂������ƂƁA�ނ�̋~���^�����g�g���c�L�X�g�̖ʓ|�͌��Ȃ��h�Ƃ������j�Ŗڂ̑O�ɏd���҂����Ă������n�́g����A�h�n�̈�t�͒m��������Ă���Ƃ������x����Z�N�g��`�ɑR����Ƃ������ƂƁA����ɂ͂��悢��V�O�N�ɂނ��ăt�@�b�V���I�Ȍ��͂̒e�����\�z����邱�Ƃɑ��č\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ�����A��Ƃ͂͂��߂�ꂽ�̂ł���B����́g�l��������h�Ə̂��āA�����E�Q�c�@�c�����ӔC�҂ƂȂ��ď����������߂��A�U�P�N�̎Љ�}���Ō��c�܂łȂ��ꂽ�̂ł������B |
|
| �y��U�D�P�T�����q�q�s�E������Ɋւ���Ћ��̑ԓx�z |
|
�@�����́A�U�D�P�T���̓����Ɗ����q�q�̎����߂����āA��Ђ̈����̈ӂ������������̂悤�ɔ����B
| �g���c�L�X�g�̒����s�ׁA�w����e����㩂ɂ��炵���S�w�A�����A�A�����J�鍑��`�̃X�p�C�ɐӔC������B |
| �䂪�}�́A���˂Ă���ݓ��t�ƌx�@�̒����Ƌ��\�Ȓe����\�z���āA���̂悤�ȑS�w�A�w�����̖`����`���J��Ԃ��ᔻ���Ă������A����̋M�d�ȋ]���҂��o�����ƂɊӂ݂Ă��A�S�w�A�w���������̂悤�ȍ�����c�̌���ɔ����镪��Ɩ`����`���J��Ԃ����Ƃ��A���吨�͖͂ى߂��ׂ��łȂ��B |
�@�Љ�}�́A�����q�q���̎��ɑ��ē}�Ƃ��Ă̎w���͗ʕs���ł���Ƃ��錩�����q�ׂĂ���B
| �Љ�}�͂����鎖�Ԃ�h�~���邽�ߐ���A�w�����y�ьx�@���ɐ��~�̂��߂̓w�͂������B�������͂����炸�ɐN�̌��𗬂��������Ƃ͍������N�ɑ��A�[���ӔC�������\����Ȃ��Ǝv���B |
|
| �y���{���Վ��t�c�ŁA�A�C�N�đ哝�̂�̖K�����~����z |
|
�@���{�́A�U�D�P�U���ߑO�뎞�߂�����}篗Վ��t�c���J���A�u�����q�q�����v�̏Ռ��ŕs���̎��Ԕ�����J�����邱�ƂƂȂ�A�A�C�[���n���[�đ哝�̖̂K�������v�������肵���B�����h�쑠���D�r�c���l�ʎY����̋��d�_�Ɠ��R����Y�O���D�Ό����ƌ����ψ�����̐����I���E�_���������钆�ŁA�A�C�N�đ哝�̂�̖K�����~�v�������܂����Ɠ`�����Ă���B
�@�U�D�P�V���A��\�͔r���Ɩ����`�i��Ɋւ��錈�c��������}�P�Ƃʼn������B���̓��A�o�c�A�ȂǍ��E�l�c�̂��A��\�͔r���Ƌc���`�i�죂̐����\���Ă���B
|
| �y�}�X�R�~����\�͂�r���A�c���`����ꣂƂ��������錾�𐺖��z�@ |
| �@�U�D�P�V���A���V�Ђ̑��V���Ёi�����A�ǔ��A�����A���o�A�Y�o�A�����A�����^�C���Y�j�́A���ʂɢ�\�͂�r���A�c���`����ꣂƂ��������錾�\�A�����ɂ͒n�������������āA�����錾���f�ڂ��Ă���B��U�D�P�T����̍�����O�ɂ����闬�������́A���̎��̈˂��Ă����鏊�Ȃ�ʂƂ��āA�c���`����@�Ɋׂ��ɍ����ł�������Ƃ��A���{�����łȂ��A��}�e�}�ɑ��Ăࢂ��̍ہA����܂ł̑��_�����炭�����̂āA���悵�č���ɋA��A���̐��퉻�ɂ�鎖�Ԃ̎��E�ɋ��͂��邱�ƣ�����߂Ă����B |
�@����f���͂��̌����O�̓��������������B�S���̊e��w�͎��R�����I
�ɖ������X�g�ɓ˓������B
�@�U�D�P�V���A�Љ�}�ږ���䑾�Y���E���Ɏh���ꕉ���B
�@���R���F�̓��͖ڑO�ɔ���������B����f���͂��̌����O�̓��������������B�S���̊e��w�͎��R�����I �ɖ������X�g�ɓ˓������B
�@�U�D�P�W���A������c�́A�u�ݓ��t�œ|�E������U�v���E���ۍٌ��s���F�E�s���e���R�c�v�̍�����������f����i�����B�O���̍�������~�n���x�[�X�Ƃ��đr�͂ƍ����{���̘J���ҁA�w���A�s���̉��ׂR�R���l�̃f�����������B�����q�q���j�̓��升���ԗ�Ղ��s��ꂽ�B�����q�q�s�E�R�c�E�ݓ��t�œ|�����N���k����J�����l�A�����W�A���R���F�ɍR�c���ĘJ���ҁE�w���E�s���l�����A�����́E�O�鍿�荞�݁B
| �y���ۏ�R�����B�J���ҁE�w���E�s���R�R���l���O��ō����̓f���z |
�@�U�D�P�X���A������c�́A��ݓ��t�œ|�D������U�v���D���ۍ̌��s���F�D�s���e���R�c��̍�����������f����i�����B�R�O���l���O��ō����̓f���������B����Ƃ�����K�w�̘V��j�����ّR�ƍ��荞�B���̎��A�����̖��́A��`�J�[�̏ォ�碂P�Q���܂ł͈��ۉ��蔽�Γ��������A�P�Q���ȍ~�́A���ۏ��j���̓����ł��飂Ɣn���������������Ă���B�������Ă��邤���ɂ����v�̐j�͉��A�P�Q�����z���Ƌ��ɐV���ۏ��͎��R���������B���̎��S���l�ȏ�̃f������������ӂ����͂�ł����B
�@���̎��̂��Ƃ𓇎��͂����L���Ă���
| �P�X�U�O�N�U.�P�W���A���ĐV���ۏ�R���F�̎������ꍏ�Ƌ߂Â��Ă������̖�A���͍������芪���������̊w���D�s���ƂƂ��Ɏ��@�̑O�ɂ����B�W�O�U�O�s�i�Ŋ��@�̎��͂𑖂�f������O�ɁA�����Ă܂��������ɂ��������Ă���w���̊ԂŁA���́A�ǂ����邱�Ƃ��o�����ɁA����ۂ݂̈���i��o���悤�Ƀw�h�������Ă����܂��Ă����B���̎��A���̉��ŁA�w���Y��`�ғ����x�̊��̋߂��ɂ������c���A�{�����悤�Ȋ���ŁA�r��U��Ȃ���w�{���A�{���A���̃G�l���M�[���I���̃G�l���M�[���A�ǂ��ɂ��ł��Ȃ��I�u���g���ʖڂ��I�x�ƒN�ɂ����ł��Ȃ��A�f���o���悤�ɋ���ł����B���̓{��Ƃ����}�Ƃ������ʂԂ₫�����ɂ������c(����W�)�B |
|
�@�U�D�Q�O���A�S�w�A�嗬�h�A�ݓ��t�œ|�E�x�����R�c�P�ƃf���A��疼���W���Ď��@�Ȃǂ֍R�c�f���B
�@�U�D�Q�P���A�S�w�A�嗬�h��疼�A���嗬�h��Z�S���A���@�E�O���ȂɍR�c�f���B
�@�U�D�Q�Q���A�s�����S��v�w�ō��J�X�g�x���̌�A�嗬�h�͍����O�A���嗬�h�͏O�@��ّO�ł��ꂼ��l�疼�����W���čR�c�W��B
�@�U�D�Q�Q���A��1�X������s���B���]�D�����J�A�������[�l�X�g��R�g�U�O�O���l�A�����f���P�O���l�B�}�́A�}�g�D��勓��������B�s���A�Ɍ��W�����w���͂W�O�O�O���B
�@�U�D�Q�R���A�V���ۏ��̔�y�������A�ݎ� �ސw�̈ӎv��\���B�V���ۏ��͍���Ŏ��R���F����A���������B�C�^���A�̢���D�i�`�I�[����L�҃R���h�D�s�b�c�l��͢�J�N���C�A�~�A�^���k��Ƒœd���Ă���B�����V���ɢ����ȐÂ��ȃf���͏��߂Ă��B�f���ɓ��m�I��߂�������ƃR�����g���Ă���B
| �y�����q�q�S�w�A�Ǔ��W��z |
�@�U�D�Q�R���A�����q�q������������J����ŊJ����A��P�������Q�������B�����L�����A�u���g�̑�\�Ƃ��āA�u���u����I�v����n�܂钢����ǂݏグ���B���Y�}�͕s�Q���B
�@���̖�A�S�w�A�嗬�h�w���Q�T�O�l���A�u�����q�q�i���Y��`�ғ����̎w�����q�j�̎��́A�����̋s�E�Ƃ������ʂƃg���c�L�X�g���ւ̔ᔻ���������Ă͂����Ȃ��B���̎��ɂ͑S�w�A�嗬�h�̖`����`�ɂ��ӔC������v�Ƃ����A�J�n�^�L���ɕ������āA�}�{���ɍR�c�f�����������B
�@�}�́A������g���c�L�X�g�̏P���Ƃ��Č��\���A�U�D�Q�T���A�J�n�^�ɓ}�����Ƃ��Ģ�S���\�l�̃g���c�L�X�g�w���������O�A�f�J�G��(�S�w�A����)�A���R����(���S�w�A�ψ���)�A�Њw�����L��������ɗ������ē}�{���Ƀf�����s���A�w�{�{�����o�ė����x�A�w���T�D�_�x�A�w�A�J�n�^�L�����������x�ȂǂƋ����A�}���J���҂ɂ���Ĕr�����ꂽ��]�X�Ɠ^����Ă���B
�@���Ȃ݂ɁA�U�D�Q�T���̢�l������́A����ۓ����ɂ����銒���q�q���w���{�̖����I�p�Y�x�Ə̂�����ё̒k�b���f�ڂ��Ă���B |
�@�U�D�Q�T������V�D�Q���ɂ����đ�Q�O������s���B�������A���R���F��A�܂��Ȃ��f���Q���҂��}���ɒ����������B���̕ӂ�Łu�U�O�N���ۓ����v�͊�{�I�ɏI�����A��͓����̑����������Ă������ƂɂȂ�B
| �y���ۓ����̈₵�����́z |
�@���ۓ����́A�쒩�N�̗����Ӑ��{�œ|�̓����Ƌ��ɍ��ۓI�ɂ������]�����ꂽ�B������c����������A�P�V���ɂ킽�铝��s����g�D���A�Ћ������������o���A���]���̏��g�D������Ɍ��������Ă����B���ۂ͉������ꂽ���A�A�C�[���n���[�哝�̗̂�����j�~���A�ݓ��t��œ|�������B�����I�Ȉ̑�Ȍo���ƌP���ݏo�����B���̎���̐��N�ɂ��傫���e����^���A�����I���o�𑣂����B���̎�������N����A�Ăъw���^���̐V�����V�g���������邪�A���̎������ꂽ�킪�������Ă������Ƃ��݂Ȃ���ł��낤�B
�@�����́A���̈�A�̌o�߂ň�т��āu�����ɏ��ȁv�Ƃ��u�`����`�ᔻ�v���������A�퓬��������O����u�O�q���i�v�E�u�O�q�s�݁v�̔l���𗁂т邱�ƂɂȂ� ���B�������Ĉ��ۓ����́A��㔽�̐��^���̉���I�����ƂȂ����B�u���z����ꂽ�O�q�v�͊v�V�W���[�i���Y���̗��s��ƂȂ����B�}���̎Q�����鑽���̐V���G���E�o�ŕ�������A�s���}�����h�ᔻ���������B |
| �y�g�{�������̈��ۓ��������z |
�@�݂�������S�w�A�ƂƂ��Ɉ��ۓ����ɎQ�悵���g�{�������́A�u�[���̏I���v�i�U�O�D�X���j�Ŏ��̂悤�ɒf�����B
| �@�P�T���i�U���j��A���̐�[��������̍\���ɂ����āA������Ƃ肩���Q�́A�����炩�ɂ����炵���C���^�[�i�V���i���Y���̉Q�ł������B����͂Ȃɂ������������̎�̂�l���Ƃ��Ă̂��Ԃg�ƁA���̘A�тƂ��Ă̑�O�̂Ȃ��ɂ����A�����a�O���Ă��鍑�ƌ��͂̍��ƈӎu�i���ۏ��j�ɂ������Ă��������C���^�[�i�V���i���Y���̎p���ɂ�ʂ���Ă����B���@�̂܂����Ƃ����̉��ւȂ���Ă䂭�Q�́A�Љ��`���ƌ��Ƃ�����ȃn���`���E���������A���̂悤���̂��߂ɂ͎㏬�l���̍��ƌ��͂ɂ������邽������������ɋK�肵�A�܂��l���̗��v�Ɩ��W�ɂ�������ȋʏ��Ƃ��ČŎ�����ϑԓI�ȃi�V���i���Y���̖S���w���������̂����ɚ�������Ă����B����̓R�~���^�[�����̑����v����`�̕���Ō�̂��������ے�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ������B�����͂����Ȃ邽�������ɂ����Ă��A����������j�~���A�Ђ������O�����������̎w���������Ă�������Ȃ����Ƃ�]�݁A�Ђ����炽�������̌��ꂩ�牓�����낤�Ƃ���p���ɂ�ʂ���Ă����̂ł���B |
| �@��O�h�̎w������[���O�q�B���A�\�����̘J���ҁE�w���E�s���̊�̑O�ŁA���Ɏ��瓬�����Ȃ����ƁA���瓬��������Â���\�̖͂������Ƃ��A���������܂łɖ��炩�ɂ����B |
�@���̌��t�������������ĎƂ߂�ꂽ�B�ȍ~�A�g�{�������́u�[���̏I���v�A�J���i����j�́u��^�̒����v�A���J�Y���i�͂ɂ�䂽���j�́u�����̂Ȃ��̐����v�Ȃǂ̒��삪�ǂ܂�Ă������ƂɂȂ�B |
| �y���{���꒘�u�J���@�v���`���v�z |
�@���{���꒘�u�J���@�v���`���v�B
�@���R�ƍ���������c�̘g����Ԃ��Č������W�J���ꂽ�S�w�A�̑�O�s���ƁA����ɂ��������̊����O�q�̗���I�Ȍ����A�����āA���̎w�����̑r���̊����Ȃ��܂ł̎��Ȗ\�I�������Ȃ�ꂽ�B�ނ���̂肱���đO�i����Ƃ����O�̋ÏW���ꂽ�G�l���M�[�̔����ɂ������āA���������u�g���c�L�X�g�̒����ɂ̂�ȁv��A������ɂ����Ȃ����������Ƃ������́u�O�q�v�_�b�̕��A�N�̖ڂɂ������炩�ɂȂ����B�����̎p���́u�G�͋���A�����͗v�Ƃ���������p���_�ł���A�u�����Ɨ�����v���v�z���A�߂����ׂ��́u�������哝�����v�̎����ł���A�����ĂȂɂ����A�}���̊g��ł������B���ۓ����́A���̑��`�I�ۑ�ɏ]�������ׂ��ł������B���̂��߁A�ނ�͓O�ꂵ���X�P�W���[��������`�A���@��`�ɓO�����B�ނ炪�A�B��A�����������咣�����̂́A�U���P�O���̃n�K�`�[�����ł������B�A�����J��G�_��헪�Ƃ���ނ�ɂƂ��āA�A�C�[���n���[�̖K���ɔ����铬���́A�n�K�`�[�������ɂނ����r�O��`�̂��������ɏW�ꂽ�B�������ۓ����̊��Ԃ������āA���̑����ł̓����`�ԂɊւ�������̓��a����`�A�c���`�A���Ė�����`�Ȃǂ̋\�ԓI�ȗ��O���̂肱���A�퓬�I�Ȋw���A�J���҂͓����̗ւ���d�ɂ��Ђ낰���B
�@�O��O�r�̓����ƂƂ��ɁA���j���悷��悤�ȑ哬���ɂ����āA���ۓ����̎�͂��ɂȂ����u���g��S�w�A�́A�O�̗͂����͂����������Ƃ���ɓ������������B����͈��ۉ���𐄐i�����ێ�w�c�̗͂ł���A������͍�����c�Ƃ���ꂽ���Y�}��Љ�}�Ȃǂ̊v�V�w�c�̗͂ł������B����Ƀu���g��S�w�A�Ȃǂ̐V���������̗͂ł���B�����āA����炻�ꂼ��̍��ƓI�헪�����̂悤�ɋ�ʂ��Ă����B�ێ�w�c���v�V�w�c���A�A�����J�A�\�A�̐�㐢�E�x�z�Ƃ����g�g�݂́A��ΓI�œ����Ȃ����̂ł���Ƃ����F���́A���ʂ̊�Ղł������B�����ɂ������āA�u���g��S�w�A�́A���ۉ���������āA���{�̑�O�̂قƂ�ǂ̊��҂𗠐��āA���{���{��`����������ɂ�āA�u�鍑��`�I�ȕ����v���Ƃ�����̂ƂƂ炦�Ă����B���������āA���ۉ���ɔ�����̂́A���{�̒鍑��`�I�ȕ�����j�~���邱�Ƃł������B����́A����Ӗ��ł͓��{�̕ێ�w�c���A�A�����J�Ƃ̊W�����P���Ȃ���A�̐��̋�����}�邱�Ƃ��A�[���鍑��`�I�ȕ����ƌ��Ȃ��Ă������ƂƓ����Ƃ�����B�������A�u���g��S�w�A�̗��O�ɂ́A���̃A�����J�A�\�A�̓x�z���A���O�I�Ɏx���鐢�E�ς␢�E����ے肵�悤�Ƃ���Ӑ}���������B�A�����J�͂������A�\�A�͎Љ��`�ł͂Ȃ��A�Ƃ����F�����j�ɂȂ��āA�����������O�̏펯�ɂ��Ă������E�ς␢�E����ے肵�Ă����̂ł���B����A���E���āA�\�̎x�z�Ƃ�����Θg�Ő������Ă���Ƃ������Ƃ�ے肵���̂ł���B
�@�u���g��S�w�A�̎咣���A���̃��W�J���ȍs���ƂƂ��ɑ�O�Ɏx�����ꂽ�̂́A�āA�\�̂ǂ��炩�ɉ��S����̂ł͂Ȃ��A�ǂ���̐푈�������Ƃ����A�s�퍑�̍����Ƃ��Ẵi�V���i���Ȉӎ����A�L�͂Ȍ`�ŁA�͂��߂đ�O�̗��j�̕\�ʂɓo�ꂳ��������ł���B������A�P�X�U�O�N�ȍ~�Ɂu�V�����v�����̐��E�ς␢�E����ے肵�A�Ǝ��̐��E�ς����߂�ꏊ���߂邱�Ƃ��ł����̂��A���́e�U�O�N���ۂ̑�O�̐����A�w�i�̈��͂Ƃ��Ă���������ł���B���̓����̌o�����A�u���E�j�I�v�Ɏ��������^���̂P�y�[�W�����������j�I�o���Ƃ��Ē~�ς���A�̂��̑S�����̑�O�I��Ղɂ��p����Ă������̂ł���B
�@������ӂ́A�A���A�R�c�̉Q�Ŗ��߂�ꂽ�B�����ĂU���P�X���́u���R���F�v���܂��ɂ��āA���吶�̊����q�q���x�����̖\�͂ɂ���ċs�E�����B�����������������s���̂Ȃ��Ŋݓ��t�͑ސw���A�A�C�[���n���[�哝�̖̂K���͒��~���ꂽ�B�������āe�U�O�N���ۓ����͒��É����Ă����B���ۓ����́A�^���Q���҂̂Ȃ��ɁA�������܊��Ɣs�k�����c�����܂܁A���ۂ͂��łɉߋ��̂��̂ɂȂ�������B
�@���������A���̈��ۓ����ƘA������悤�ɁA���{�ő�̒Y�z�ł����������̎O��O�r�Y�z�ɂ����Đ��ő�ōŌ�̘J�����c�����������B�Ƃ����̂́A�O�r�������͂��܂鐔�N�O����u�G�l���M�[�v���v�ɂ��A�����̒Y�z��������Ă����Ă�������ł���B�O�r�����͐ΒY�Y�Ƃ̐��ނɂ��ƂÂ��������ɂ���݁A�P�X�T�X�N�P���A�O��z�R���ǂ��J���g���ɂ������A�U�C�O�O�O�l�ɂ���Ԋ�]�ސE�����Ƃ߂���ꎟ�������Ă����������ɂ��������B���N�S���U���ɂ́A��ꎟ���������肪��������A����������Ȃ����Ƃ��m�ꂽ���A�W���A�o�c�ґ��͐E�ꊈ���Ƃ��ӂ��ނS�C�T�W�O�l�̊�]�ސE�̑�������Ă���Ă����B�g���͂�������ۂ����B���ǁA��Б��͂P�Q���A�P�C�Q�P�S�l�̎w�����ق������Ȃ����A�g���͉��ْʍ����ꊇ�ԏシ��B����ɂ������āA���P�X�U�O�N�P���Q�T���A��Б����S�R�̃��b�N�A�E�g��ʍ��������Ƃɂ���āA�J�g�Ԃ����ʂ���Η���ԂƂȂ����B����ɑg�������A�������X�g���C�L�������ĉ��������Ƃɂ���āA�{�i�I�ȓ����ɓ˓�����B
�@�}���N�X��`�Ҍ����Y�̉e���̂悢�g�����́A������`�I�ȃX���[�K���u�����{�Ƒ��J���v�̑Ό������сA���o�A���o�b�N�Ƃ����Б��ɂ������A���R������̐��i�ɂ��e�Y�Ƃ̍���������ƑS�ʑΗ������B�x�@�́A�\�͒c���o�b�N�ɁA�g���̐�������͂������ŁA���_����u������Б��̍U���ɂ��A�g���ψ�����E���҂��łĂ����B�R���P�V���A�����̃����o�[�𒆐S�ɑ��g�������܂ꂽ�B���̊����͑S�g�����̂S���̂P�ɂ�����R��U�S�l�ɂ̂ڂ����B�R���Q�W���A���g�����A�J�����s���悤�Ƃ��āA���g���̃s�P���ƏՓ˂��A���̍ہA�\�͒c���P���A�S�]�l�̏d�y���҂��ł��B�����ɂ͖\�͒c�����x�@�̌����˔j���āA���g���̃s�P���ɏP��������A�g�����v�ې�����̎h�E���������������B�������āA�O�r�̘J���҂́A�݂�����̐g����邽�߂ɖ\�͂ɂ���炴������Ȃ��Ȃ����B����ɁA��Б��́A���g�����̃z�b�p�[�ɂ��ΒY�̔��o�A�D���ɂ�鎑�ނ̔������s�������A�g�����͒��J�ς̂�������Ă����ۂ��āA�����Ԑ����������Ȃ������B�V���ɂȂ�ƁA��Б��́A�@���D�S�ǂő��g��������B�����悤�Ƃ��A���g���ƏՓ˂��A�x�������܂߂������ŁA�R�O�O�l�����������B�g�����͏o�Y�ĊJ���������Б��ɂ������āA�O��z�z�b�p�[���s�P�Ōł߁A�o�Y��j�~�����B����ɂ������A��Б��́A�s�P�̔r������e�Ƃ��鉼���������肵���B���]�A�Y�J���́A�S������Q���l�̑g���������ĉ������̎��͑j�~���͂������B�x�@�����P���l�����Ď��s�̎x���ɂ��Ȃ����B
�@�����ɂ������āA���ۂ̐����Ŋݓ��t���ސw������̒r�c���t�́A�O�r��̋}����������E�̗v���������āA���E�H��ɂ̂肾���A�J�g���Ƀs�P�̓P���ƁA���J�ς̂�������Ăɉ����邱�Ƃ���������ƂƂ��ɁA���̕��a�I�����ɓ�F�����߂��O��z�R������������B���{�̂��̑[�u�ɁA�W�]�����߂Ȃ��ł������]�����A���J�ςւ̉�����C�����ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������B�W���P�O���A���J�ς�������Ă������ꂽ���A���̓��e�͎w�����ق�F�߂���̂������B�P�P���P���A���]�A�Y�J�Ƃ��Ɏ�������߁A���ɎO�r���c�͎��E�ɂނ������B���̊ԁA�ō����ɂ͂P���P���l�ȏ�̌x��������������A�R������P�Q���ɂ����Ă̌x���������͉��ׂV�S���l�Ƃ����A���ۓ����s�[�N���̂S�R���l���͂邩�ɏ�����̂ł������B����ɂ������A���]�ȂǑg�����́A�S�����牄�ׂR�V���l�������Ƃ���ꂽ�B�O�r�����͐��P�T�N�Ԃ̘J���^���̑����Z�̈Ӗ��������Ă����B����A��ނ����闬��̏I���I�Ȕ����ł��������B
�@����A�O�r�����Ɠ��������A����여��̒n�����A�吳�Y�z�ɂ����Ă��O�r�J�g���̂肱����吳�s�����̓��������܂�Ă����B���̓������w�����Ă������l�̒J���́A�O�r�������A����܂ł̘J���^����������J���g�������Ȃǂ́u�O�q�v�Ɏw������A���̎w���̂��Ƃɐ��R���铝�����Ȃ���Ă������Ƃ��̂肱����ꂽ���Ƃ��݂ĂƂ��āA�O�q�}�ɂ���Ďw�������l���ƈقȂ�`�Ԃ��u��^�̒����v�ƌĂсA�^����g�D�����B�������A�P�Ȃ�J�����c�Ƃ��������ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��A���I���g���b�N�������āA�풆�̓V�c���t�@�V�Y���̂ӂƂ��뉜�[������߂Ƃ��Ă����A���O�̊v���I�G�l���M�[�o������悤�ȓ��{�^�i�A�W�A�^�j�v���̃C���[�W���d�˂݂Ă����B
�@�s�J���̔������v���́A����ł͒����́u�����n�v�݂A�����œV�c���t�@�V�Y���̊v���Ƃ��Č��o�������a�̓�E��Z���������C���[�W�Ƃ��ďd�˂���̂ł������B�u���Y��̐�̔������v�Ƃ������t�́A��̓�E��Z�Ƃ���ɂ���Ď��Y�i�e�E�Y�j�ɏ�����Ă������N���Z���A���炩�ɘA�z�����邾�낤�B�J���́A�u�Q�����_�����~���I�v�Ƃ����ĐN���Z���K�N������E��Z�������A�}���N�X��`�҂�ߑ��`�I�Ȑ�㖯���`�҂̂悤�Ɂu���v���v�Ƃ����āA��̂Ă���͂��Ȃ������B�N���Z�����́u���S�ɂ܂v�Ƃ�����]�̊v���́A�V�c�Ƃ����J���X�}���x�z�����ł���ƂƂ��Ɋv�������ł������A�`���ɂ���ꂽ�Љ�ɂ����Ă������܂ꂽ�̂ł���t
|
|
| �y���c�v�����̏،��z |
|
�@�U�D�P�U�|�U�D�Q�R���܂ł̓����̂���܂����A���c�v�����͎��̂悤�ɋL�^���Ă���B
�@���P�U���A�w���͈�ԓd�ԂŊw�Z�ɋA��A�u�s�E�R�c�A�ݑœ|�A���ە��ӁA�S���w���������X�g�v�ɒ��肵���B�U�D�P�T5�����̍Ő擪�œ��������吶�����́A���̓��̒��܂łɖ�Q�O��A�������̃r���A�����[�g���̗��ŔŃL�����p�X�߂������B���̑��̑�w�ł��A�S�O�O�O�|�Q�O�O�O���̕��������W���āA�ēx������ʗp��߂����A���̐��͓��ȏ�ɒB�����B
�@�U���P�W���͈��ێ��R�����̑O���������B�S�w�A�̑S�������Ɍĉ����āA�n����w�����X�㋞���A����J�����ɓ������W���āu�����q�q�s�E�R�c�A�ݓ��t�œ|�����N���v���J�ÁA���̂��ƍ���f�����s�����B�s�E�Ղ̓�ʗp�啍�߂ł́A�S�w�A�����͋�O���̎l�����ɂӂ���オ��A�J���҂�s�����ӂ��ߘZ�����ɂ��O��̍R�c�W������s�����B������c�����̓��O�Z����������f�����s�����B
�@�U���P�X���A�u���E��k���������\���ԁv�͏I������B�����͋}���ȑޒ����݂��A�Q�O�|�Q�R���܂ł͉J�̍~��Ȃ����A�S�w�A�͘A���A��A�W��ƃf���ɂ���Ĕ��������݂����A�����Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@����ȏ�ɋȎ��݂́A������c�U�D�Q�Q�[�l�X�g�ł������B���̎��͍s�g�́A���ۓ����̑S�ߒ���ʂ��āA�˂ɁA���ւƂ̂���A�u���x�����͑O�����܂��[�l�X�g���v�Ƃ����w�����̋�̍Ō�̎d�グ�ł���A����������߂����ŋ��̖������ɂ����Ȃ������B
�@�Ƃ͂����A�S�w�A��擪�Ƃ������ۓ����̋���ȍ��g�́A���ێ��R�����ƈ��������Ȃ���A�ݑœ|�A�A�C�[���n���[�������ӂ������Ƃ����B
�@�U���Q�R���A�S�w�A�͂U�O�O�O�������W���āA�ݑސw�\���̂��̓��A�u�����q�q�S�w�A�Ǔ��W��v���J�Â����B���̈ꕔ�́A�����{���Ƀf�����������B����́u�������҂��o�����ӔC�̓g���c�L�X�g�w�����ɂ���v�i�w�A�J�n�^�x60�N6��22���j�ɂ������鋁�ߖ��������B�܂��E�s���A�̒p���ׂ��s�ׂ����j�ɂƂǂ߂Ă����ׂ����낤�B
�@�s���A�́A�U�D�P�T�����Ȍ�͓������ɂ����Ă��}���ȑޒ��������A�X��������������҂��Ă������B�ނ�́A�S�w�A�̎������悻�ɁA���������ɊX���J���p���s���A�u�]���ҋ~���v��i�����B�s�����\�J���A���S���̃J���p�������肾���āA���S���~�������A�s���A�Ŏ��������A�S�w�A�̍R�c�ɂ���Ĉꕔ����[�����ɂ����Ȃ������B���ꂪ���̖������u���T�h���{�\�����v�ł���B���̃G�s�\�\�h�́A�����̓����h�̎��H�I�A�v�z�I�A���`�I�Ȕ��K�����������ے��I�Ȏ����ł���A���ۓ����̓����s���A�ő����Z�ł������B�����{���f���Ƃ����O�㖢���̍R�c�̐�����A���������R�ł������B |
|
| �y�X�c�����̉�z�z |
|
�@�X�c�����́A���̍��̂��ƂƂ��Ď��̂悤�ɉ�z���Ă���B
|
�@�P�X�T�U�N�̍��쓬������P�X�U�O�N�̈��ۓ����A���̌�̋��Y��`�ᔻ�̂Ȃ��ŁA���͐��������Ƃ��[���ڂ��A�����̂��Ƃ��w�B�U�O�N���ۓ����̒���ɐ����������璼�ڕ�������̌��t�����͖Y��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �w�l�Ԃ͎������g�̌o������͐�ɗ�����Ȃ��B���ꂪ�ǂ�ȂɎS�߂Ȃ��̂ł����Ă��̂Ă邱�Ƃ͕s�\���B�����Ȃ�̌��ł��낤�Ƃ����U�w�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��x�B���ꂩ��S�O�N�B���������̂��̌��t�́A���ɂƂ��Ĉ�̑�Ȑl���̎w�j�ƂȂ����B ���̂Q�A�R�N�O�܂Ŏ��̓}���N�X��`�̐M��҂������B���Y�}�̂Ȃ��ł́A����̑̌����d������p���́w�l��`�E�o����`�x�Ƃ��Č������ᔻ���ꂽ�B�}���l�̑̌��ɂ��ƂÂ��n���I�Ȓ�Ă̓}���N�X�A�G���Q���X�A���[�j���̌��t�������Ɍ����y�����ꂽ�B
�@���͂��̋��Y�}���̊ϔO�ߏ�̋�C�ɓ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���͂P�X�T�T�N�Ă̘Z�S���Ȍ�A�}�����ւ̌����������ᔻ�������s���A�����{���ƌ������Η����A���ɂP�X�T�W�N�ɒ����ψ���c�ɂ�菜�����ꂽ�B���Y�}���痣��Ď��R�ɂ��̂��l����悤�ɂȂ������A�����������璼�ژb���@������A���������̌o���d���̎v�l����傫�Ȏh�������B���������̕�ɂ́A���M�̎��̌��t�����܂�Ă���\�\�w�o���A���̐l�ԓI�Ȃ���́x�A�w�o���x�����������̐��U��ʂ��Ă̎v�������̒��S�ɂ�����Ă������Ƃ��A���̌��t�Ɏ�����Ă���B
|
�@�u�̌��ƌo���͌l�����̃��x���ł͓����Ӗ��ł���B�w�L�����x�i��g���X�j�́u�̌��v���u�������g�������Čo�����邱�ƁA�܂��A���̌o���v�ƒ�`���Ă���B�������A�N�w�̐��E�ł͏����Ⴂ������B�w��g�N�w�E�v�z���T�x�ɂ��ƁA���̍��͎��̂悤�Ȃ��̂ł���i�ێR���i�����M�j
�B�q�̌��r�T�O�́A�����̓_�Łq�o���r�T�O�Əd�Ȃ荇�����A����Ƃ̑���_�������ċ�������Ȃ�A���ڐ���X�����A��������̍ʂ�A�̌��҂ɑ��鋭�͂Ő[�r�ȉe���A����퐫�A�f�ސ��A�Ȃǂ̃j���A���X�������Ă���v
�B
�@�u�̌��͎��̐l�������Ă�������I�ȗv�f�Ȃ̂ł���B�̐��������Y�����̋����̂Ƃ���A�������g�̑̌��͂����Ȃ�̐l�̑̌����������Ƒ�ʼn��l�̍������̂ł���B�������A���Ƃ��������g�̑̌����ǂ�ȂɏX���p���ׂ����̂ł������Ƃ��Ă��A���ꂩ�瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ̑̌�����������Ǝ~�߁A����Ƌ�������ȊO�ɓ��͂Ȃ��̂ł���B���̔F���Ƌ������o�����ĂA�l���ꂼ��ɑO�����Ō�����l���𑗂邱�Ƃ��\�ɂȂ邾�낤�v�B
|
|
�@�������́A�u��U�����̂P�A���ۓ����������߂����đ卬�������v�ɋL���B
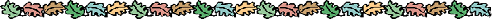



 (���_�D����)
(���_�D����)


![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)