
�@�X�V���^�Q�O�Q�Q�i�����R�P�D�T�D�P�h�a����/�h�a�S�j�N�D�S�D�V��
�@������O�́A�u��R���A�u�Z�S���v�̏Ռ��A�����P��n�S�w�A�̑g�D�I�����v�ɋL���B
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
| �@���w���^���̑�S�����̂R�́A�P�X�T�V�N�̊w���^���j���L���B�����̐����ɂ��Ắu��㐭���j�����v�́u�P�X�T�V�N�ʊ��v�ɋL���B�{�e�ł́A�����̊w���^���֘A�̓������L���B���ʂɍl�@�����������ɂ��Ă͕ʓr�l�@����B |
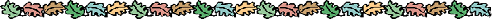
| �y�P�X�T�V�N�̓����z�i�����̌��؎����j |
�@�P�D�W���A�S�w�A�����ρA���ɉ����蓙�\�ڂ̌��J������o�B
�@�P�D�P�U���A�s�w�A�A�A�C�N�E�h�N�g�����ɔ��ŕđ�g�فE�O���ȂɃf���B
| �y�S�w�A��P�O���ρz |
|
�@�P�D�P�W�|�Q�P���A�S�w�A��P�O���ς��O�@��قŊJ���ꂽ�B���쓬��
�@���A����̉i�v��n�����E�p�N���X�}�X���j�������Γ����ڕW�ɐݒ�A�嗬�E���嗬�̘_���\�ʉ��B�����h�́A�A�����J�̃A�C�[���n���[�哝�̂̔N�������ɔ������āA����̉i�v������n�����A���{�{�y�̌�����n�����̓����ȂǃA�����J�̌������푈���������A�C�N�D�h�N�g�����ɔ����ē������Ƃ����S�w�A�̑��`�I�C���ł���Ƃ����^�����j�����肵���B�����h�͍��S�^���l�グ���ȂǁA�w�������̗i��▯���`����i�쓙�̉ۑ���咣�����B
|
| �y����{�g���c�L�X�g�A�������������z |
�@�P�D�Q�V���A�����g���c�L�Y�������Ŏv�z�I�ɋߐڂ��Ă������c�������c�p���E�x�Y�Z��Ƒ��c����̂R�O���[�v�����̓��A����{�g���c�L�X�g�A�������������������A����{�g���c�L�X�g�A������������B���̎嗬���킪���ɂ�����ŏ��ƂȂ������{�g���c�L�X�g�^���ݏo�����ƂƂȂ����B���c��̢���t�ң���A���@�֎��ƂȂ����B�R����̎O�����O���[�v�͎��������Ƃ��Č��W���Ă��Ȃ������B�����i�E���J�i��̊��O���[�v���Q�����Ă���̂́A���N�T�V�N�̂R�O���ȍ~�ł���B�������u�U�O�N���ۓ����v�̎O�N���O�̂��̎��_�œ��{���Y�}�I�^���Ɍ����t���A����Ɍ��ʂ��ē��{���Y�}�ɑւ��V�}�^����n�����邱�Ƃ��n�߂�ꂽ�Ɖ]����B
�@����{�g���c�L�X�g�A����́A��S�C���^�[�i�V���i�����{�x�����������鏀����Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă����B�����͎v�z���l�I�T�[�N���W�c�Ƃ��Ĕ��������B���{�g���c�L�X�g�A���́A���ۋ��Y��`�^���̘c�Ȃ̎匴�����X�^�[���j�Y���ɋ��߁A
�X�^�[�������쒀�����g���c�L�[�H���̕��ɋ��Y��`�^���̐������������������Ƃ��Ă����B���ꂪ��̓W�J���猩�ĐV�����̐��I�ȗ���ƂȂ����B
�@���̎咣������ɁA���̂悤�Ȏ��o��_���Ƃ��Ă����B
| �@�u�����̂����闝�_��v�z�́A��X�ɂƂ��Ă͖ӏ]����q�̑Ώۂł͂Ȃ��A�܂��ɔᔻ����ێ悳���ׂ��Ώۂł���B�����́A
��X�̂������ƂȂ��T���̉ߒ��ŁA���邢�͔j������A���邢�͌���������āA�V�����v�z�n���̊�b�ƂȂ�A�v���I���H�Ƃ��Č���������˂Ȃ�Ȃ��v�i�T���j�B |
|
 (���_�D����)�@���{�g���c�L�X�g�^���̕]����ɂ��� (���_�D����)�@���{�g���c�L�X�g�^���̕]����ɂ��� |
|
�@���̍���ɂ��������̂��u���{�ɂ�����v���I�w���̐����I���W�J���Y���ƁA�v�`�u���I�ϔO��`���Ɍ������Ĕ����������́v�Ƃ݂Ȃ����������邪�A
�������������̐���͕ʂƂ��āA���̒������n���͐��̓}�^������n�܂��Ă���A�}�I�^���̌��E�Ƌ^�₩�炢�������������Ă���Ƃ������Ƃ����܂����˂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
�@�{�����_�ɋ���A��т��ăg���c�L�Y�������Ĉِ��l�̔@���������킵���Ő������}�������O�ꂵ�A�g���c�L�X�g���u���{�����}�̉j��������v�̎�ɏ�锽�}�i�����͓������Ă���c���̒��j��
���i���������p�ł���c���̒��j��`�҂̔@���l�|���Ă������ƂɂȂ邪�A���͂����������������L�ł��Ȃ��B�O�q�����u�}�I�^���̌��E�Ƌ^�₩��̔����v�Ƃ������_�Ō��߂�K�v������B
�B
|
 �i���_�D���ρj�@�g���c�L�Y���a���̊ϕ��ɂ��� �i���_�D���ρj�@�g���c�L�Y���a���̊ϕ��ɂ���
|
�@�Ƃ���ŁA�����̎��_�ł͑Q���}���܂ߍ����l�̏펯�Ƃ��āu�X�^�[�����ᔻ�v�ɓ��ӂ���悤�ɂȂ��Ă��邪�A���ɂ͕s�\���Ȃ悤�Ɍ�����B�Ȃ��Ȃ�A�u�X�^�[�����ᔻ�v�́u�g���c�L�[�]���v�ƕ\���̊W�ɂ��邱�Ƃ��v���A�u�g���c�L�[�]���v�Ɍ�����Ȃ��u�X�^�[�����ᔻ�v�Ƃ͈�̉��Ȃ낤�B
�@
�����Ƃ��A�}�̏ꍇ�A���̑ւ��ɂ��ǂ����u�Ȋw�I�Љ��`�v��������悤
�ɂȂ��Ă����B�u�Ȋw�I�Љ��`�v�I�����̒��ňꉞ�́u�g���c�L�[�]���v���g�ݍ���ł�����肩������Ȃ��B���A����قǃg���c�L�Y����ᔻ�������Ă����j���������}�Ƃ��Ă̐ӔC�̎����Ƃ��Ă̓I�J�V�C�̂ł͂Ȃ��낤���B�X�^�[�����ƃg���c�L�[�Ɋւ��āA���ꂱ�������ӂ́u����Ɨ��I���O�́v�j�I���������Ă����ׂ��Ƃ����̂��Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B�u����Ɨ����_�v�̐^���͂��������ʂɂ����Ă������悵�Ĕ��������ׂ��ł͂Ȃ��̂��A�Ǝv���邪�@���ł��傤�B
�@���Ȃ݂ɁA���́A��X�̉^���ɂ����Ĉ�Ԋ̐S�ȃX�^�[�����ƃg���c�L�[�ƃ��[�j���̑傫�ȑ���ɂ��Ď��̂悤�ɍl���Ă��܂��B���̓�l�̑���́A
�}�^���̒��ł̌����Ƃ��w�j�̑�����u�ő���������悤�Ƃ���̂��v�u�ő���F�߂悤�Ƃ���̂��v���߂����Ă̋C���̂悤�ȈႢ�Ƃ��Ă̍D��ł͂Ȃ����ƁB���[�j���͂��X�^�[�����I�ɋ�̓I�ȏɉ����Ă��̗������g��������u�l����`�v�I�X���������Ă����̂ł͂Ȃ������̂��B����������@�̓��[�j���ɂ͉\�ł��������A�X�^�[�����ɂ͋��\�Ȕ@�Ӗ_�ɓ]�����₷���댯�Ȏ�`�ł������B�ӔN�̃��[�j���͂�����`�����݂��ɂȂ��p�������Ȃ������̂ł͂Ȃ������̂��B�X�^�[������@�ƃg���c�L�[��@�̍��́A�ǂ��炪�������Ƃ����߂����Ắu��ΐ��^���v�_�c�Ƃ͊W�Ȃ����Ƃ̂悤�Ɏv����B�^���_�ɂ�����C���̍��ł͂Ȃ��낤���B�u�^���v�̉������́A�����D���ȋC�������X�^�[������@�̐ꔄ�ł����āA���������ȋC�������g���c�L�[��@�ɂ����Ă͉��������̂ł���B�^���ړI�Ƃ��̗���ň�v���Ă���̂Ȃ�u���낢�����Ă݂Ȃ͂�v�Ǝv������B�������A�g���c�L�[��@�̏ꍇ�u�������q�v�̍ۂ̑g�D�_�E�^���_��⊮���Ă����K�v������Ƃ͎v���邪�B
�@���łɂ����Ō����Ă����ƁA�����̕����Ƃ��āA���Ȃ̎咣�̐��������u�����咣����v�̂��X�^�[������`�ł���A�\�t�g�Ɏ咣����̂��u�Ȋw�I�Љ��`�v�҂̑ԓx�̂悤�ȓ��܂�������A�����ӌ����咣����҂ɑ��Ĉ��ՂɃX�^�[���j�X�g�Ă�肷��X��������悤�Ɍ�����B����̓I�J�V�C�B��
���Ƃ��\�t�g�Ƃ��̓X�^�[������`�Ƃ͉��̊W���Ȃ��B�咣�ɂ����鋭��̕t�����͂��̐l�̋C���̂悤�Ȃ��̂ł���A�ǂ���ł��낤�Ƃ��A�v�͌�������ӌ��E�ٌ��E�����̑�����M���M���̐��荇�킹�܂Ō����ɍs���̂��A�͂����
�Č��͓I�ɖ��͖\�͓I�ȉ����̎�@�ʼn����������Δh��ߏo���Ă����̂��ǂ������A�X�^�[���j�X�g���ǂ����̕���_�ł͂Ȃ��낤���B�X�^�[��
�j�Y���ƃg���c�L�Y���̌����I�Ȗʂł̑���͂��̂悤�ȂƂ���ɂ���ƍl����̂������ł��B�����l����ƁA�{���C�Y���͓T�^�I�ȃX�^�[���j�Y���ł���A�s�j���̃\�t�g�X�}�C���͌��ۂ��A�����W���������̃X�^�[���j�Y���ł���A�����ɓ��{�̃g���c�L�Y���̔r�������������������ȃg���c�L�Y���ł���悤�Ɏv���� |
�@�P�D�R�O���A�Q�n�����n�P���̕ČR�ˌ���ŕĕ����_�w���ˎE�i�W���[�h�����j�B
�@�Q�D�P���A�S�w�A�́A����i�v��n�����A�����`�i��S���w�����N���𐴐��J�����ŊJ�����B�P�T�O�O���̊w�������W���ăf���Ɉڂ�A�A�����J��g�قɍR�c���s�����B
�@�Q���A���Y�}�̑���u�O�q�v�ɏ��̃X�^�[�����ᔻ�B
�@�Q�D�T���A�S�w�A�����ς��A�C�M���X�c��ɑ��ăN���X�}�X���̌����������~�̐\�����ꌈ�c���s�����B�S�w�A�����ρA�V�����č���g�}�b�J�[�T�[�ɉ���̉i�v��n�����Γ���\����B
�@�Q�D�P�T���A�V�����č���g�}�b�J�[�T�[���C�A�S�w�A��Q�O�O�����H�c�ōR�c�f���W�J�A�s�w�A�ψ����ߕ߂���B
�@�Q�D�Q�R���A����Ԋҗv�����J����A�S���U�疼���W�A�w���͂Q�疼�Q���B
�@�Q�D�Q�R���A�����t�����E�B
�@�Q�D�Q�S���A���������ݓ��t�ٓ��t�ł���ƋK�肵�A���̊O�𐭍��]�����������߂��B
�@�Q�D�Q�T���A�ݐM����t�����B
�@�R�D�P���A�����e�w��\�R�疼����N���X�}�X�������������Β�������J���A�p����g�ق֍R�c�f���B
�@�R�D�T�|�U���A�S�w�A�����ς��A�l�E�܌������������j���c�A���������j�~�̂��ߑS�g�D�������ďW��E�f����������`�Ԃœ����������\�B�R�D�W���A����w���A�p��g�قɐ����������R�c�f���B
| �y��Q���s�}��c�̍����z |
|
�@�R�D�X���A���ڂ����ׂ��������������Ă���B���̓��Ɨ��P�O���A�P�V���̎O���Ԗ�S�O�O���̑�c�����W�߂ĊJ���ꂽ��Q���s�}��c�́A�u�Z�S���v�Ȍ�̓}�����̎w���Ԃ�ɑ���ᔻ�ƒNj��̏�ƂȂ�卬���Ɋׂ����B���̎��s�ψ��̊�Ԃ�́A�͂�����Ƃ����}�����h�����c���d�q�E���{�̂Q���A���Ԕh�͐��{�E�����E�����E��Ԃ̂S���A����Ɉ����m���q�ł������B�c��̑��c�i�V���E���䏺�v�E�E�ЎR���Ƃ��E��c��O�Y�E�Ŋ��E���R�E�����E�R�{�����E�����Y��̊v�V�h�i�}�i��`�ҁj���A���̊Ԃ̓}�����̕���o�߂ɂ��ӔC�m�ɂ���Ɣ���A���̂��ߓ}�������\���ďo�Ȃ��Ă������E�{�{�E�t������炪�d��ŗ�������������ꂽ�̂ł���B
�@���̎��̖͗l�̈�[�Ƃ��Ď��̂悤�Ȃ��Ƃ�����B��������_��Վ��������k��ŁA���䏺�v���A������g���b�N�����̈Ö�ɂ��@�����ƕ������œ}�̏��u���B�����Ɣ������Ă����B���ꂪ��}�������O���֎����o������Ƃ��āA���̎��}��������K��ᔽ�ɂ��ψ����I�̌��i���R�Ƃ���悤�Ƃ��Ă����悤�ł���B����{���Y�}�����̏،��(��c��O�Y)�ɂ��A�s�ψ���ł̂��̒Nj��ɑ��āA��₪����̎����́A����G�����Y�������ɂ��悤�Ƃ��đ_���Ă���B����ŁA������܂Ƃ��ɉ������悤�Ƃ����琔�疜�~�̋����K�v�ȂB�������A�����������͓}�ɂ͂Ȃ��B������A���̖��͂���Ȃɂ������Ă��̂ł͂Ȃ��ɁA����N��ӔC�҂ɂ��Ă��邩��A�����ł����ď[�����c���āA�͂����肳���飂ƁA�q�ׂĂ���B����ɑ��������̑@���]�ƈ��́A����������s�ˎ����������N�����������҂̐��ӔC�҂ɂȂ��āA��̉������ׂ��飂ƍR�c���Ă���B�������A���̒Nj��͍����~�݂ƂȂ荡���܂ňł̐��E�ɂ���B
�@���̎��̓s�ψ���̑I���ł́A�{���̉����r���āA���S�w�A�ψ��������̔ᔻ�h���s�ψ��ɂP�X�����P�O���A����ɎŊ���s���L�ɑI�Ԃ��ƂɂȂ����B���̎��̓����s�}��c�̌��c�ẮA�}�w�����ւ̔ᔻ�⊯����`�ւ̔��Ȃǂ������ł��o�����B
�@���̌��ʂɑ��A�{���́u�����̔F�߂Ȃ����c�͖������v�Ƃ��ċ��������B�{���́u����W�����v�_�̑̎��́A����������@�̏ꍇ�ɂ��̖{�����I�悷��B�u�����̔F�߂Ȃ����c���������v�Ƃ���A�}�������`���������������̂ł͂Ȃ��B�}�����ւ̃C�G�X�����o���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���������j���܂��āA�����}�����̢����W������_�̐������˂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@���̌o�߂����Ē��ڂ����ׂ����Ƃ�����B�����Ă̑S�w�A�������̎w���҂ł���������E�����炪�A���̎��_�œ����s�}�ψ��ɂȂ��Ă���A���ɕ��䂪�ᔻ�h�Ƃ��ė�������Ă��Ă��邱�Ƃł���B����E������́A���̊Ԉ�т��ċ{�{�O���[�v�̎P���Ɉʒu�����ĉ����ē��c�n���s���̎w���Ɉًc�������A�}��������ɂ��Ђ����獑�۔h�Ƃ��ċ{�{�O���[�v�ƕ��������ɂ��Ă��Ă������Ƃ��l����ƁA���̍��������オ�I������Ƃ������Ƃł��낤�B���̎����̕���́A���c�n�ɂ��{�{�n�ɂ��}�����Δh�Ƃ��Ĉʒu���Ă�����c�O���[�v�Ƌ������A�u�Z�S���v�E�u��V��}���v�̌o�߂Ői�s������{�{�O���[�v�n�̋{��v���̓����ɑ��Ĕ��t���n�߂Ă������Ƃ��m���B���_�I�ɂ��A�{�{�����S�ƂȂ��ċN�����Ă����u�}�͑��āv�̌���K��Ƃ��v���W�]�ɑ��Ĉӌ����قɂ��Ă������l�������Ă���B���Ȃ݂ɁA�����͋{�{���ɃV�t�g�����X��X�̗���ɂ������悤�ł���B
�@���̎��̓����҂̈�l���c�i�V���́A���a�S�V�N�W���������̊ᣂŎ��̂悤�Ɍ���Ă���B
| �@������s�ψ�����Ƃ������̂��N����_�Ƃ����̂́A�傫�������܂��Ɠ�ł��B������ΎO�ł��l�ł�����܂����A��{�I�Ȗ��͓}�������`�̖��Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂���A��}�������`�̓��e�̒��ɂ́A��͂�ߋ��̌��������Ɩ��m�ɂ��Ȃ��Ⴂ����Ƃ������Ƃ����R�܂܂�Ă����ł��B�����O�����A�������Ƃ������ƂłȂ�������ɂł��Ȃ��A�O��I�ɒNjy���Ȃ�������Ȃ��Ƃ����p���ł��ˣ�A����ЂƂ́A���_�I�Ȗ��Ƃ��āA�V�j�̂��̂��̂ɂ��̌��̐ӔC������A���������̂܂ܐ����������Ƃ����Ă����āA�����̔ᔻ�ł͂����Ȃ��Ƃ������ł��ˁB�傫����������̓�ł����A�}�������`�Ɖߋ��̑����ƌ����悤�Ȗ��A����͗������ݍ����Ă��܂����A�����ʼnߋ��̐ӔC�̒Njy�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA��̂ގu�c���Ȃ��\�I������ł���A�����Ɠ����ɁA��͂苤�Y�}���Ăт�����������Ƃ��Ȃ����߂ɂ́A��l��l�̓}�������ۓI�ȏ�ɂ��Ă��A�����Ȃ��̂ɂ��Ď����̓��ōl����ƌ������R���Ȃ���A��������܂�ΑS����܂����Ⴄ�Ƃ������ƂȂƎv���܂��B�]���āA�e�@�ւȂ�}���l�l�������̓��ōl����A���������}�ɂ��蒼���Ȃ�����ʖڂ��Ƃ�����肪�o�Ă����ł���B |
|
 (���_�D����)�@�{���́u����W�����v�_�̑̎��ɂ��ā@ (���_�D����)�@�{���́u����W�����v�_�̑̎��ɂ��ā@ |
�@�{���́u����W�����v�_�̑̎��́A����������@�̏ꍇ�ɂ��̖{�����I�悷��B�u�����̔F�߂Ȃ����c���������v�Ƃ���A�}�������`���������������̂ł͂Ȃ��B�}�����ւ̃C�G�X�����o���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���������j���܂��āA�����}�����̢����W������_�̐������˂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B
|
 (���_�D����)�@����E������̋{���h�Ƃ̍ŏI�I���ʂ̓����ɂ��� (���_�D����)�@����E������̋{���h�Ƃ̍ŏI�I���ʂ̓����ɂ��� |
�@���̌o�߂����Ē��ڂ����ׂ����Ƃ�����B�����Ă̑S�w�A�������̎w���҂ł���������E�����炪�A���̎��_�œ����s�}�ψ��ɂȂ��Ă���A�ᔻ�h�Ƃ��ė�������Ă��Ă��邱�Ƃł���B����E������́A���̊Ԉ�т��ċ{���O���[�v�̎P���Ɉʒu�����ĉ����ē����n���s���̎w���Ɉًc�������A�}��������ɂ��Ђ����獑�۔h�Ƃ��ċ{���O���[�v�ƕ��������ɂ��Ă��Ă������Ƃ��l����ƁA���̍��������オ�I������Ƃ������Ƃł��낤�B
�@���̎��A���̕���E������́A�����n�ɂ��{���n�ɂ��}�����Δh�Ƃ��Ĉʒu���Ă�����c�O���[�v�Ƌ������A�u�Z�S���v�E�u��V��}���v�̌o�߂Ői�s������{���O���[�v�n�̋{��v���̓����ɑ��Ĕ��t���n�߂Ă������Ƃ��m���B���_�I�ɂ��A�{�������S�ƂȂ��ċN�����Ă����u�}�͑��āv�̌���K��Ƃ��v���W�]�ɑ��Ĉӌ����قɂ��Ă������l�������Ă���B |
�@�R�D�P�W���A�s�w�A�A�����������ʼnp����g�قɍR�c�f���A��\���Q���B�R�D�Q�O���A�S�w�A�E�쌛�A�����ܒc�́A�p��g�قɍR�c�B�R�D�R�O�|�R�P���A����w������S���ρk�O�@��فl�A�N���X�}�X�������������Γ����������������I������������������B
�@�R�D�R�O�|�R�P���A����w����X��S���ρk�O�@��فl���J�Â���A�N���X�}�X�������������Γ����������������I������������������B�S�����v�R�Q�x���A���������S�P�O���B�g�D�����o�[�Ƃ��āA���������Q�Q���A����{���R�X�A����C�Q�T�A�����w�|��P�P�A���H��P�P�A������Q�T�A�@����P�T�A����R�V�A����T�A��������Q�O�A���q���S�A�q���Z��R�A����A�s����A���{���A����J���R�A�R���R�B�n������Ƃ��āA������T�A����Q�O�A�����ّ�R�O�A���u�ЂQ�O�A���s��Q�O�A���O��T�A�_�ˑ�Q�O�A�V����P�O�A�R����P�O�A���Q��T�A���Q�O�A�L�����T�B
�@�S�D�P�|�R���A�S�w�A��P�P���ψ���O�Q�@��قŊJ����A�S���̐V�w�N���}���Ă̊j�����D�j�푈�̐����Γ������w�߂��ꂽ�B�N���X�}�X������������S�͑j�~�A�l�E����s���B
�@�S�D�Q�V���A��ꎟ����s��(�����Q�R�O�O�A�D�y�P�T�O�O�A���s�P�P�O�O�A���̑��S���e�n)�B
�@�T�D�P���A���[�f�[�Q���B
�@�T�D�R���A�S�w�A�����̂T�D�P�V�����錾�B���S�^���l�グ�������f���B�T�D�T���A���S�^���l�グ���ΑS���w�������N���A�����W��k����J�쉹�l�ɓs���w����疼�Q���A���d�F���܂Ńf���B
�@�T�D�W���A�R�J�E�R�[���A���{�ł̔̔��J�n�B
�@�T�D�P�P���A���S�̏������Γ����x���B
�@�T�D�P�T���A�C�M���X���{�̓N���X�}�X���Ō������������s�����B
�@�T�D�P�U���A�S���̑�w�ōR�c�W�������A�T�D�P�V���A�S�w�A�́u�N���X�}�X�������������v�����ő哝��s����g�D���S���U�O�̓s�s�ōR�c�W����J�����B�����ł͂Q���T�O�O�O�����Q�����A�ō��̓������ƂȂ����B��͖�w���U�O�O�O���̂��傤����f���A���̑��̊e�n�ł����s�̂S�O�O�O�����͂��߁A�����ĂȂ��K�͂ŏW������ꂽ�B���̂T�D�P�V����s���̑g�D�̎d���́A�S�w�A�̂W���ρA�X���Ō`������A���쓬���Ȍ�����ł̓�����ʂ��čĊm�F���ꂽ�A��w���^���̑S����ē���s��������̓T�^�I���H�ł���A���̌ケ�̌o���́A�w���^���̖͔͂Ƃ��Ē莮������邱�ƂɂȂ����B
�@�u���a�̒�R���s�g�^��(13) CIA�̌��E�ݐM��̓o���v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�T���A���q�푈�������ΑS���w�������N�s���f�\�B5���̑����N���ł́A�S��170�Z380������35�������Q�������B�����ł�11��5000���̊w��������J��O���y���̓��O�߂����A��O�̏W��ƂȂ����B�W��ɂ͗��o�ɎЋ��A�������A�����g�A�����n�]��\�����A���A���ۊw�A�A���]�A�S���A�S�ꔄ�A�������A��������J�g�A��w�����Ȃǂ����b�Z�\�W���A�������K�w���狭���x�����������B
�@�T.�P�V���A�N���X�}�X�������������B
�@�T�D�Q�P���A���Y�}�̎u�c�d�j�������B
�@�T�D�Q�Q�|�Q�R���A�S�w�A�攪���ϑ���B
�@�T���A����w����Q��S�����J�Â���A���q�푈�������A���a�i�쓬�������c�B���e�c�I���u7���푈��@���v��N�A��P��B�S���ψ����E�������j�A���ψ����E���猖�A���L����،[��B
�@�T�D�Q�W���A���쌻�n�����B�S���߂�����f���s�i�Ɉڂ�A�O�h�S�w�A���@�����ƌ������Փ˂�����|�ƌx�_�ɑj�܂ꂽ�B�w�������͎���ɕ������ւƒǂ�����A�Б��T���h�C�b�`�K���̂܂ܗ���w���ʂւƌ��������B��W��������A�f�����́A�W�O�U�O�f����Q���f��������Ԃ��āA����w�O�œ}�h�ʂƂ�������w�ʂɏW�܂��đ����I�ɑߕߎ҂����l�Ȃǂ̈��S�m�F�����A�X������A����w����䒃�m���ւƌ��������B�o�����킹�Ė�P�O�O���̕����҂��o���A�w���S�W�l���ߕ߂��ꂽ�B
| �y�S�w�A�P�O����z |
|
�@�U�D�R�|�U���A�S�w�A�P�O����J����A�Q�V�O���̑�c���A�W�O�O�����Q�������B���q�푈���������Ŕj�𒆐S�Ƃ��镽�a�i�쓬�����i�����c�A�K������i���a�ƓƗ������j��������B�S�w�A�͂��̑��Łu�O�Ղ̍Č��v�𐋂����ƌ����Ă���B���͂X����H���̈Ӌ`���Ċm�F���A��w������`�I�X�������߂��B
�@���́A��X�g���C�L�����ړI�͗ǂ����A�������`�Ԃ��Ƃ�ׂ��ł͂Ȃ��B���̎�i�ɂ���ĕ���ށB��������W����x�̌`�Ԃ��Ƃ��āA�吨�̊w�����W�߂Č��c���s�����ق������ʂ����飂Ƃ���E�����Δh�̎咣���A��^���ɂ����閳�����I�ȕ��L���_�ł���A��̓I������ς���w�͂�ӂ闝�_�ł��飂ƋK�肵�đނ��A���X�����͂Ȍ`�Ԃ��Ƃ�Ƃ�قǑΌ����鐨�͂Ƃ̖����͉s���Ȃ邪�A��X�̎���Ɍ��W���鐨�͂��傫���Ȃ飂Ɠ����̈Ӌ`���m�F���A�w���^�����Ǝ��ɍ��ۍ�����͂���\�͂������A���j�𗧂ĂĂ����Ƃ������������u�������B
�@���̍��ɂȂ�ƁA�w���זE�̑啔���́A���Y�}�̕��j�͐������Ȃ��Ƃ��Ēn��ψ���̎w�����悤�Ƃ����A�S�w�A�̕��j�����������Ƃ݂Ȃ��Ă����B��������w���זE�͍זE�@�֎���}���N�X�����[�j����`��s���Ă������A���̋@�֎��̗��_�W�J�̕��ɋ������Ă����B
�@�u�S�w�A��10�����ʕv�̊�́u��A�̕��a�i�쓬���̐��ʂ����������߂�ׂ��v����ڂƂ��Ă���A���̂T�_�����q�Ƃ��Ă����B
| �P |
�@���ۏ�̓����́A���a���͂ƍ��ۋْ��������߂������͂Ƃ̑Η��ɂ���A�O�҂���҂ɂ������ėD�ʂɗ�������B |
| �Q |
���q�푈�����ɂ������Ē��ړI�Ō���^����������߂����A���a�i�쓬������`�I�C���Ƃ���B�����֏����ƃ����p�B |
| �R |
�ݐ��{�̔����I�{���̖\�I�B |
| �S |
���͂ȓ����`�Ԃ��Ƃ�Ƃ�قǁA�푈���͂Ƃ̖����͉s���Ȃ�A�����̎���Ɍ��W���镽�a���͂͑傫���Ȃ�B�������I�ȕ��L�_�͌��ł���B |
| �T |
�S�w�A�̂���������ȗ͂̌���́A��̉Ȋw�I���́A�������i�H�̖����A���������̈ӎu����A�Ⴓ�Ə�M�ƕq���A���̉s���s���͂ɂ���B |
�@
�@�t���V�`���t�̃X�^�[�����ᔻ�A�n���K���[�������X�ɔ����Ռ��ɂ��Ă͎��̂悤�ɕ]���Ă���B
| �@�u��N�\���n���K���[�ɂ����鎖���́A��X�̖����ƎЉ��`���݂̂����ł̐����I�o�ϓI������̔��f�ł��邪�A�鍑��`���͂̊댯�Ȋ��Ƃ��������A�����̉����̂��߂̓w�͂��J�n����A�Љ��`���Ƃ̐V�����W���������Ă��A�ꎞ�I����ɂ�����炸�A���E���a���m�ۂ��邤���ŐϋɓI�����������Ă����v�B |
�@���̎��̐l���ŁA�ψ����E���R����i����j�A���ψ����E�����O�i����j�A���c����i�����ّ�j�A���L���E����c���b�i����j���I�o����A���̑��X�c���E�����Y�E�q���炪�S�w�A�����A���L�ǂɓ���A�Ȍ�S���w���^���̎w���ɂ����邱�ƂƂȂ����B
�@���̑��œ}�̎w���ɏ]������h���s�ނ��A����͏��L�������߁A���̌�͑�������_�Ƃ��đS�w�A���嗬�h�̂܂Ƃߖ��ƂȂ��Ă����B���ꂪ���{���Y�}��V��}���O�̍��̓����ł���B���̍��A��́u�U�O�N���ۓ����v��S���l�m�����X�ƑS�w�A�Ɋ��W�����ƂɂȂ�A�V���������Ƃ��y�o���Ă������B
�@���ɎQ��������Ȋ����Ƃ����́A���I������A���_���h���s���A���̂悤�ȑ�����N���Ȃ���Ă���B
| �@�u�v�����^���A���E�v���̑��i�K(���V�A�v���j�́A�鍑��`�̍ł��ア������s�˔j�������ƁB���i�K(�R�~���e��������)�́A���E�v���̋��_����\���G�g�i��̉ۑ���܂߂���ŁA���ۍ����I���t�@�b�V�����������������A�Ǘ������͂��������ƁB��O�i�K(����)�́A�\�A�ΎЉ��`�A�ΐA���n���v���鍑��`���q�푈�̎吨�͂���A�����J�鍑��`�̍��ۓI�Ǘ����ƁA�鍑��`�����Ԃ̖����̌�����ʂ��āA�鍑��`�����̑S�ʓI��̉����͂���A�e���̊v����e�Ղɂ��邱�Ɓv�i�u���a��������P�v���a�m���ց@�\�@�����̍��ۏ�̓����ƕ��a�i�쓬���̐��E�j�I�Ӌ`�v����w���@�֎��w���a�̂��߂Ɂx57�N8���j�B |
|
 �i���_�D���ρj�@�{���n�}�����ɂ�锽�g���c�L�Y���^���ɂ��ā@ �i���_�D���ρj�@�{���n�}�����ɂ�锽�g���c�L�Y���^���ɂ��ā@
|
|
�@�Ƃ���ŁA�{���n�}�����́A���̌ケ�̑S�w�A�}�i��`�O���[�v���g���c�L�X�g�Ă�肵�Ă������ƂɂȂ邪�A�Ȃ�A���̎����}�������S�w�A�Č��Ɍ����ĉ���L���ɑΏ������Ȃ��������ƁA�}�̈ӌ�������œ����Ă����Ǝv���鍂��h���s�ނ������Ƃɂ��Ă̎w���I�ӔC������ɖ₤�Ƃ����̂����ʂ̊������낤�Ƃ͎v���B���A���̌�m����͂���������̓I�Ȕ��Ȃ͕������Ă��Ȃ��B�ނ���A�E���I�w���őS�w�A�Č������[�h���悤�Ƃ��Ď��s�����Ƃ����j���������c���Ă���B
|
|
 (���_�D����)�@�S�w�A�^���̎O����̎n���ɂ��� (���_�D����)�@�S�w�A�^���̎O����̎n���ɂ��� |
�@���̌o�߂����Ă݂�Ǝ��̂悤�Ɍ�����̂ł͂Ȃ��낤���B���̓����̃|�X�g���䎞��̓}���w�������Ƃ̂����̋}�i��`�I�����́A��̑��ʂ���̓����ւƌ��������Ƃ��Ă����B��͋{���n�{��v���̐i�s�ߒ��ɑ���A���`�̗���̊m���ł���A���͐�s���Č������ꂽ���{�g���c�L�X�g�A���̐퓬�I�w�������Ǝ捞�݂�ʂ����S�w�A�ւ̐Z���ɑ����@���ł������B�S�w�A�Č��h�́A�����ւ̑Ή��Ƃ������Ƃ��v���Ƃ������ɑS�w�A�^���̍č\�z��͍����n�߂Ă������悤�ł���B
�@�������āA���̎����̓}���w�������Ƃɂ́A�S�w�A�Č��}�i��`�h�Ɠ��{�g���c�L�X�g�A���h�Ɩ����h�Ƃ����O���������������Ă������ƂɂȂ�B��V�����^���S�O�N�̌��Ɖe�Q�T�o��͎��̂悤�ɋL���ē����̏𖾂炩�ɂ��Ă���B
| �@��m���P�X�T�V�N�̉Ăɓ�������ɂ��������̎���Ŋm�F�����̂����A���̂Ƃ��̏o�Ȏ҂͊w�A�D���傩�瓇���Y�Ǝ�(�����M)�A���傩��{�����ÁA����C��̂S���ŁA�₪�ău���g�Ɗv�����ւƕʂ�Ă��������o�[�̌��z���M�ł�������B |
�@���������Y�݂̋ꂵ�݁D��т̎����ł������Ǝv����B
�@�Ƃ���ŁA�{���n�}�����́A���̌ケ�̑S�w�A�}�i��`�O���[�v���g���c�L�X�g�Ă�肵�Ă������ƂɂȂ邪�A�Ȃ�A���̎����}�������S�w�A�Č��Ɍ����ĉ���L���ɑΏ������Ȃ��������ƁA�}�̈ӌ�������œ����Ă����Ǝv���鍂��h���s�ނ������Ƃɂ��Ă̎w���I�ӔC������ɖ₤�Ƃ����̂����ʂ̊������낤�Ƃ͎v���B���A���̌�m����͂���������̓I�Ȕ��Ȃ͕������Ă��Ȃ��B�ނ���A�E���I�w���őS�w�A�Č������[�h���悤�Ƃ��Ď��s�����Ƃ����j���������c���Ă���B |
�@�U�D�Q�P���A�ݎE�A�C�[���n���[�哝�́A��]��k�Łu���ĐV���㗈��v�̋��������B
�@�U�D�Q�P���A�S�w�A�͉���̉i�v��n���ɍR�c���Đ��S���̊w�����x�����O�Ƀe���g���͂��č��荞�B
�@�U�D�Q�R���A����ŁA�w�����Ŏw���I�Ȋw�������̑�ʏ��������\���ꂽ�B�ފw�����P�P�����܂ނQ�P���ɒ����������Ȃ��ꂽ�B�ފw�����ɂ́A�w����̎n�܂�̊w������ψ����̒��V�����A�S�w�����ψ����̑���`�j�A�S�w�A����ψ����������ē����F�A�u�Q�E�Q����v�̍��������E���Ă����ψ�����s�̔C���Ă��鏬�X�I�j���܂܂�Ă����B�ł́A��c�S������c�c���⌤�A�ψ������������c�ɑފw�����������ꂽ�B�������ɁA���ԕ��A��ԕ��̊e���s���A�e�w��������́A�s�������ɑ��u�����P���v��g�݁A�n���X�g��A���ƃ{�C�R�b�g�̐������錾�����B
�@�V�D�Q���A�S�w�A��P�Q���ρk�Q�@��فl�A���쓬��������n���̓V���R���Ƃ��đS�͓���������B
�@�V�D�T���A���̂̊e�{���������J�Ì���B
| �y��O�����쓬���O�i�A���Δh�w������n�˓��z |
|
�@�V�D�W���A�Ăэ����n�g���̋������ʂ��s���A�ċx�ݒ��ł��������w���͘J���҂Ƌ��ɂ������A�x�����ƑΛ������B���̎����\���̊w�����A�L�h�S�����|���Ċ�n���ɓ˓������B��ČR��n���ɏ��߂ē��{�l�����R�Ɠ˓�������ƋC�����������B��n�ւ̐N���͓��R�̂��Ƃƍl���Ă����s�w�A�ψ����������y�������Y���w�����Ƃ����B�������w�����Ă����X�c���E�����f��������n�O�ɏo��悤�w�����Ă���B
�@�@�֏e���悹���ČR�W�[�v���Q�䌻��A�i�ߊ������n���ɓ������҂�����ΎˎE���Ă悢�Ɩ��߂��Ă����B�Λ��͒��߂��܂ő����A����c���⒲�B�ǁi���ʓ����ҁj�A�x�@�Ƙb���������B�u�{���̑��ʂ͒��~����B�o���͓����Ɉ����グ��B�ߕߎ҂͏o���Ȃ��v�Ƃ������Ƃœ����͏I������B
�@�V�D�X���A���쌻�n�����B�����n�g���j�~��W��Ћ�����s���Ƃ��čs��ꂽ�B�J�̒��A�S�w�A�A����N�ψ���������P�Q�C�O�O�O�����Q�W�B���̓����������s�X��ƂȂ����B���̍��̓�������A����N�ψ������������g���̖��͂�����Ǝ��ɑS�w�A�Ƃ̍s�����d������悤�ɂȂ��Ă������B�����ɁA���쓬�����}�h����w�����I�ȋ������͂��܂����B
�@�X�D�Q�Q���A��̐킢����Q�P���ȏ���o�������̓��A�ČR�����n�˓��҂��ߕ߂���A�J���ҁA�w���Q�R�����ߕ߂���A�J���҂S���A�w���R���̂V�������ۏ��Ɋ�Â��s������ɔ����Y�����ʖ@�ᔽ�ŋN�i���ꂽ�B�y���s�w�A�ψ��������̈�l�ł����B���쎖���ŋN�i���ꂽ�V���̔퍐�ɂ͑��]�ٌ�c���S�ɑ吨�ٌ̕�c���������ꂽ�B�퍐���̎咣�́u���ۏ��Ɋ�Â��ČR��n�̒����͓��{�����@�����ᔽ�ł���A��n�N���͖��߁v�Ƃ�������ŁA�u���̍ٔ��͌��@�ٔ����v�Ƃ��ėՂB���̎����́A�T�X�N�R�D�R�O�������n�ق̔����i�ɒB�ٔ����j�ŁA��ČR��n�̑��݂��̂��̂����@�ᔽ�ł���A��n�ւ̐N���͖��߂ł��飂Ƃ�����ɒB������������ꂽ���Ƃʼn���I�ȈӖ����������B
�@��ɒB������̎�|�͎��̒ʃ��B
| �@�ČR�̓��{�����͌R���Ȃ��^���Ԃ���킪���̈��S�Ɛ������ێ����邽�߁A���q���ނȂ��Ƃ��鐭���_�ɂ���č��E����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ČR�̒��������A�̋@�ւɂ�銩���܂��͖��߂Ɋ�Â������̂ł���A���@�����ꍀ���O�i�ɂ���ċ֎~����Ă����͂̕ێ��ɊY�����Ȃ���������Ȃ��B�������ČR�́A�Đ헪��K�v�Ɣ��f�����ꍇ�A�킪���ƒ��ڊW�Ȃ����͕����Ɋ������܂��댯������A�������������킪�����{�́A���{�̍s�ׂɂ��A�Ăѐ푈�̎S�Ђ��N���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ����ӂ������{�����@�̐��_�ɜ���B�킪�����A�O������̕��͍U���ɑ��鎩�q�Ɏg�p����ړI�ŕČR�̒��������e���Ă��邱�Ƃ́A�w������R�o���`���̗L���ɂ�����炸�A���@�����O�i�ɂ���ċ֎~����Ă����͂̕ێ��ɊY��������̂ł���A���ǂ킪���ɒ�������ČR�́A���@�セ�̑��݂������ׂ��炴����̂ƌ��킴��Ȃ��B�ČR�����@�����Ɉᔽ���Ă���ȏ�A��ʍ����̓���@�v�ȏ�̌����ی���鍇���I���R�͑��݂��Ȃ��B�y�ƍߖ@���d���Y�����ʖ@�����K��́A�Ȃ�l���K���Ȏ葱���ɂ��Ȃ���ΌY�����Ȃ����Ȃ��Ƃ��錛�@��O�\����Ɉᔽ�������ł���B |
|
�@�V���A����{�g���c�L�X�g�A����������������S�l���̂R���̂����A���c�p���͑��c�Ƃ̑Η��őg�D�𗣒E�B
�@�W�D�U���A��R�����֎~���E���J���ꂽ�B�S�w�A�͑������E���ȗ��A��ɂ��̉^���̐擪�ɂȂ��Ď��g��ł������A��������͓I�Ɋ��������߂��B�S�O�O���̊w�����Q�������B���̎��}�����́A����s���̈�v�_�����߂邽�߂Ƃ������ڂł̕��L��`�ɂ�鉸�a���w�����Ȃ����Ƃ����B�S�w�A�͂���ɔ�������A�W�������ׂ��A��������I�ȕ��L�_�A�P�Ȃ�J���p��A��`�ɔ�����ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ǝ咣�����B
�@�W�D�Q�V���A���C�����q�͌������ɏ��߂�"���q�̉�"�_�B
�@�W�D�Q�W���A�\�A���嗤�Ԓe���e�i�h�b�a�l�j�̎����ɐ����B
�@�W�D�R�O�|�R�P���A����w����\��S���ρA��O�����E���̊�@���������������E������@���������Ȕᔻ�B
| �y���Y�}�́u���{���Y�}�}�͑��āv�����\�����z |
|
�@�X���A�����Ɂu���{���Y�}�}�͑��āv�����\���ꂽ�B�����P�S�������J�Â���A�u�}�͑��āv���̑����ꂽ�B���̍��q�͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B
| �@�u���{�͍��x�ɔ��B�������{��`�ł���Ȃ���A�Ē鍑��`�ɔ��ΐ�̂��ꂽ���]�����ł���A���ʂ̊v���͖����̊��S�Ɨ��A�����`�i��̂��߂̐l�������`�ł���A������Љ��`�v���ɋ}���ɔ��W������v�B |
�@�}�����_���J�n����A�����s�ψ���͂܂������ɔ��Ό��c���o���Ă���B�u�}�͑��āv�����{�Ɛ莑�{�Ƃ̑Ό����y�����A�Љ��`�ւ̓��̖��m�Ȓ�N�������Ă���ȂǂƔᔻ���A���Ăɔ��̑ԓx���������B�A���A���̎��̕��ʂ��猩��ƁA�\�����v�_�ɋ߂����n����ᔻ���Ă���悤�ł���B�\���h�́A�}�͑��Ă̑Εď]���|�����Ɨ�����v��(�����H��)�ɑ��āA���Ɛ聁�Љ��`�v����Βu�����B�\���h�̊ϓ_�ɂ��āA���c�v�����͎��̂悤�ɕ]���Ă���B
| �@�u�����A���̍\���h�H���́A���鎩���_�ɗ����Ȃ�����A�v���_�Ƃ��Ă͕��a��������Ƃ���t���V�`���t�H���̉����ɂ���A�v���Ɣے�̋c���c���a�v���_�������B���̌���ŁA�}�́������h�Ƃ��̔��}�́��\���h�̊Ԃɂ͐�ΓI�����͑��݂��Ȃ������B�����ɁA���̗��҂̋��ʓ_�̂Ȃ��ɂ����A�ނ炪�A�v���Ɓ����E�v�����f���ēo�ꂵ�������v���I�����ɂ������āA�����̓G�Γ}�h�Ƃ��ė��������_���I�K�R����������
�v�B |
�@�����s�ψ���͓����Ɂu�}�͑��āv�̒��Ɋ܂܂�Ă���K�� �ɑ��Ă��A����́u�}�������`�̊g��ł͂Ȃ��ďk���v�ł���A�u�����A���ɒ�����C�ψ���̈���I�Ȍ����̊g��v�ł���Ɣᔻ�����B�������������͂��̎��S���e�n�̓}�ψ���ɓ`�d���Ă���A���̗l�q����������Ă��A�}�́A���T�W�D�P���̑�P�V��g�咆�ςňꃖ����ɗ\�肵�Ă�����V��}����I���ւ̎��g�݂������ɋ}築������邱�Ƃ����肵�Ă���B
�@�j�̘_���́A�w������ł����Ƃ��s�����ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�A�w���^�����}�����w���ɂ���Č������Ō����Ă�������ł������B
|
�@�X�D�P�|�R���A�S�w�A��\�O���ρk�����J����فl�A�����������֎~��������̂��߂̍s�����N�A��E�ꎵ�A���E�ꓝ��s��������B
�@�X�D�P�V���A���q�푈�������E�����������֎~���葦�������������v���S���{�w�������N�f�[�A�S��28�s�s7���l�Q���B�X�D�P�W���A���R�S�w�A�ψ������\�A�x�������ǂƉ�A�s���e���R�c�A�ߕ��v���i20���ߕ��j�B
�@�X�D�Q�O���A���Y���P�b�g��1���̔��ː����B�@
| �y��O�����쓬�����i�A��n�˓��w�����ߕ߂����z |
|
�@�X�D�Q�Q���A�x�����́A�����U�D�Q�V���|�Q�U���̍��쒬�̊�n���ʂɂ�����A��n���ɗ��������ĖW�Q������Ƃ������R�ŁA�Q�R���̊w���D�J���҂�ߕ߂����B���̑ߕ߂́A���čs������Ɋ�Â��Y�����ʖ@��Q���ɂ����̂ł������B�S�w�A���쎛���L���A�y���s�w�A�ψ������X���̊w���A�J���҂P�S�����ߕ߂���N�i���ꂽ�B���̎����́A��ɓ����n�ق̔����i�ɒB�����j�ŁA��ČR��n�̑��݂��̂��̂����@�ᔽ�ł���A��n�ւ̐N���͖��߂ł��飂Ƃ�����ɒB������������ꂽ���Ƃʼn���I�ȈӖ��������ƂɂȂ����B
|
| �y��O�����쓬����i�A�R�c������������z |
|
�@�S�w�A�͒����ɍs�����N�����A�Q�O�O���̊w�������S�V���̘J���҂ƂƂ��ɁA�x�����ɉ��������R�c�����B�[��ɑS�w�A�g�咆�����J����A�S���I�ȓ�����g�D���邱�Ƃ����肵���B�X�D�Q�R���A�S�w�A�A���쓬���W�ґߕ߂ɂQ�T�����g�A�Q�W�����g�R�c�s�������肵�A�A���x�����ɍR�c�f�����d�|����B
�@�X�D�Q�T���A�S�w�A�Q�R�O�O���̍R�c�f�����g�D���ꂽ�B�Q�O�O�O���̕����x������������P�����A�Q���������A�\�����ɏd�y���킹���B�������A�S�w�A�͓����̖g��[�߂��A�Q�U���A�Q�V���Ɨ��đ����Ɍx�����ւ̍R�c�f����g�D���J�g�ƂƂ��Ɏ�v�w�Ő^���ƃJ���p������W�J���Ă���B
�@�X�D�Q�W���A�������������E����s���e�����������k����J�l�Ɋw�����܂߈ꖜ���Q���AIUS�̃��b�Z�[�W�͂��A���s�E���E��B�ł��w���E�J���҂����N�B
�@�X�D�Q�V���A���s�ł��R�疼�̊w���̌��N���A�s���f�����s���A���̓��ɋ��s��K��Ă����ݎ���������}���Ă���B
�@�X�D�Q�W���A�S�w�A���g�̌��N�s���B�@�X�D�Q�W���A�s���e���R�c���g�D����A�L�ĂȍR�c�������g�܂ꂽ�B����J�őS�w�A�D���]�D��n�_���D�������D�Ћ����}�ɂ��P���]�̍������J����A�e���ɍR�c���Ă���B
�@�X�D�Q�X���A�S�w�A�ً}�g�咆���ς��A�ߕߎґS���ߕ��ɏ����̈���Ɛ����A�P�P�D�P�����N���Ăт�����B
|
�@�P�O�D�S���A�\�A�����E�ŏ��̐l�H�q���X�v�[�g�j�N�P�����O���ɏ悹�邱�Ƃɐ����B
�@�P�O�D�T���A���R�S�w�A�ψ����AIUS�̗v���ō��ۓ���s���̂���AA�����I���O�����ɏo���B
�@�P�O�D�P�W�|�P�X���A�S�w�A�攪��g�咆���ρA���E�ꍑ�ۓ���s���X���[�K����������B
�@�P�O�D�Q�P�|�Q�V���A�w���n���V�T���N�L�O�̑���c�� �B
�@�P�O�D�Q�W���A����̋g���ꐭ�A���A���؈ꗝ�e���������A�Ɋj��������i����B
| �y���{�g���c�L�Y���^���̂��̌�̗���z |
|
�@�P�O�����A���c����𒆐S�Ɋw���D�J���ҁD�C���e���w�Łu�ُؖ@������v������ꂻ�̋@�֎��u�T���v�����s���ꂽ�B
�@�g���c�L�X�g�^���́A�^���̓������哱�����߂����āA���邢�͂܂��g���c�L�[�H���̕]�����߂����āA���邢�͊��������ɑ���Ή��̎d���Ƃ��}�^���_���߂����ăS�^�S�^�����Η��������Ă������ƂɂȂ�B��������i�ƃg���b�L�[��`�ɂ�郌�[�j����`�̌p���Ɣ��W���߂������c���i�I���o��j��Łu���{�g���c�L�X�g�A���v�Ƃ��̋@�֎��u��S�C���^�[�i�V���i���v�����������B���̗��ꂪ��Ɂu���{�v���I���Y��`�ғ����v�ƂȂ��Ă������B�i���{���Y��`�J���ғ}����S�C���^�[���{�x����������{�g���c�L�X�g�A�����P�Q�D�P���A���{�v���I���Y��`�ғ����i�v�����j�ւƌn�����Ă����j�B
�@���̎����S�w�A���̋}�i��`�I�w���}�������Ƃ̈ꕔ�͂��̒����Ɍĉ����A�}���Ƀg���c�L�Y���ɌX���Ă������ƂɂȂ����B�������A���{�g���c�L�X�g�A���̉^�����j�Ƃ��āu������p�v�ɂ��Љ�}�E���Y�}�̓�������̐������_�������h�J���I��@���̗p���Ă������߂��A���O�̉^���Ƃ��č������̈ꐨ�͂Ƃ��ė�������Ă���悤�ɂȂ�̂͂��̌�̂��ƂɂȂ�B�u������p�v��
�́A�ΏۂƂȂ�g�D�ɉ������A��������g�D�̐�������s����p�ł���B
|
 �i���_�D���ρj�@�g���c�L�Y���a���̊ϕ��ɂ��� �i���_�D���ρj�@�g���c�L�Y���a���̊ϕ��ɂ��� |
�@�V�����^���������g���c�L�X�g�Ă�肷��ƂȂ�A���{�g���c�L�X�g�A�����ŔɌf�������̒���������ɒl���A��ɒa������u���g�Ƌ�ʂ���K�v������B���������Ӗ��ɂ����āA������́A���{�g���c�L�X�g�A���̌n�����u���v�g���c�L�X�g�n�ƌĂсA����ɑ��u���g�n�����u���v�g���c�L�X�g�n�Ƃ݂Ȃ����Ƃ����͂��́u����v�Ƃ������B���{�g���c�L�X�g�A���̌n�������ɐV�����ő�̒��j�h�Ɗv�}���h�Ƃ������Z�N�g�����܂�Ă���A���ɒ��j�h�̕��Ƀu���g�̍������Ȃ���Ă������ƂɂȂ�̂ň��̍����������Ă��v�����Ȃ��ʂ����邪�B
�@���̃O���[�v�̓����Ƃ��ė��_�������d������Ƃ������ƂƁA�\�͓I��@�ɂ�鑼�}�h�r������p����Ȃ�����悤�Ɏv����B�����S�邱�Ƃ͈ȉ��̓_�ł���B��q�����悤�Ƀg���c�L�Y���Ƃ́A���[�j���ɂ���Ĕᔻ���ꑱ����ꂽ�قǂ�
���L�̉p���ȉ^���_����Ƃ��������^����ڎw���Ă������Ƃɓ������F�߂���Ǝv����B�Ƃ��낪�A�킪���Ŏn�܂����g���c�L�Y���́A���̗��_�̉s����}���N�X��`�̎a�V�Ȍ������Ƃ������̖ʂ�]�����邱�Ƃɂ�Ԃ����ł͂Ȃ����A���̌�̉^���W�J�̒ǐՂŘI��ɂȂ�Ǝv���邪�A�ӌ��̑���C�Ŗ\�͓I�ɉ������镗���������^�����Ɏ������߂̖ʂ�����悤�ɂ��v����B���邢�́A�Z�N�g�Ԃ̑Η��ɉA�d�I��@�ʼn��������Ă������Ƃ��ӂɉ�Ȃ��ʂ��F�߂���B���̕��Q�͓}�̃X�^�[���j�Y���̎��ƍD��̂��̂ł���A���{�̍����^���̍Đ��̂��߂Ɍ������Ă����˂Ȃ�Ȃ��d�v�ȕ��̖ʂł��邱�Ƃ������Ďw�E���Ă��������B |
| �y��W�O�U�O�D�f�����o���[�h����̑Η������z |
|
�@�P�P�D�P���A�u�W�O�U�O�D�f�����o���[�h���������đS�w�A���ɑΗ����������Ă���B��R�����֎~���E���̌��c�Ɋ�Â����ۋ����s���f�[�Ƃ��āA���{�S���e�n�P�O�O�����ŏW��D�f�����s���A���̎Q���҂͖�W�O���Ɖ]��ꂽ���A�S�w�A�͂W�P��w�P�W�P������ŏ\�����̊w�����Q�����A����A�ĉp�\�O����g�قɌ��c������A�����w�܂Ńf���B���̎��A�S�w�A�������őΗ������������B�S�w�A�����h�̃W�O�U�O�D�f���w���ɑ��āA�ꕔ�̊w��������͂�������ۂ����B�S�w�A�����́A��K���I����s�ף�A�����s����ł���Ƃ��Ă���������������B�ӔC�Njy�͂Q���̒���(����D�_�ˑ�)�ɋy�є�Ƃ����B
�@���̍��A�S�w�A�w�������ɂ́A����݂̏�̓A�����J�鍑��`�̊j�푈�̐�����w�������ꍑ�ۋْ��͌���������B�]���āA����ɑ��Ă͌���Ȍ`�Ԃœ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ƃ��������h�ƁA��Љ��`���͂̋����ɂ���č��ۋْ��͊ɘa������A�]���đ�O�^���͕��L�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ƃ��������h�̑Η����������Ă����B���������F���̈Ⴂ���s�����j�ɂ����f���A��W�O�U�O�D�f�����o���[�h����A��X�g���C�L�����ƕ�������Ƃ����Η��܂ň����N�����Ă����B���̉��a���H�����{���n�}�������w�����Ă����B
| �@��P�P���̍��ۍs���f�[�ɍۂ��A���Y�}�{���̓W�O�U�O�D�f���͂��Ȃ����j�����Ă��B�Ƃ��낪�A�S�w�A�͂���������ăW�O�U�O�D�f�����������A�]�]�]����h(����c��w�O���[�v)�́w��O�Ƌ��ɓ������߂Ɂx�Ƃ����̂ŁA�p���[�h�������Ƃ�A����N�̓I�[�v������w�����Ƃ��āA�̂ǂ��ɕ��D�f����������(�T�V�D�P�P�D�P�S����ǔ��V�����)�B |
|
 (���_�D����)�@�W�O�U�O�D�f���܂ŋK������{���H���l (���_�D����)�@�W�O�U�O�D�f���܂ŋK������{���H���l |
| �@�S�w�A�w�����̓W�O�U�O�D�f�����w�����A�{���n�������ǂ������Ӑ}�ɋ����Ă�������~�߂����悤�Ƃ���B�����ɁA�S�w�A�^�����E���I�w���œ������悤�Ƃ���{���́u�W�O�U�O�D�f���K���w���v�������ɍ���Ă���B���Ă݂�A���̌�̖����n�̉��a���o���[�h�f���͕K�R�̎Y���ł��������ƂɂȂ�B |
�@�P�P�D�U���A�S�w�A���A�X�G�Y���Ɋւ��ĉp���̌R���s����~��v���A�G�W�v�g���{�ƃJ�C����w�������シ�鐺�����\�B
�@�P�P�D�P�R���A�S�w�A��P�S��g�咆�ς��J����A�P�P�D�P�s���𒆐S�Ƃ���j�������Γ���������ƂƂ��ɁA��E�����Δh��̒����ψ��Q���i���{�A�ԍ�̑���E�_�ˑ�R���r�j�A���ρi������j����C�����B�����̢�E�����Δh��́A��X�g�ł͂Ȃ����ƕ�����A��W�O�U�O�f���ł͂Ȃ��p���[�h��Ǝ咣���A���X�ɓ����Η�������Ă����̂������ł������B���쓬���ȗ��̎嗬�E���嗬�̑Η����\�ʉ������B�@
�@�P�P�D�P�T���A�S�w�A�����ώQ��������A���Ɨ��l�グ���Α��c�J�ÁA�l�グ���Γ����̑S������������B
�@�P�P�D�P�T�|�P�V���A�S�w�A��\���S���ρA�S�w�A�̏�镔��S���ƕ��a�i�쓬�����j�m���B
�@�P�P�D�P�U���A�S�w�A��\�A�Ε]�����̋����œ����g���L���Ɖ�k�A���E�l�w�������N���ɋ��͂�v���B
�@�P�P�D�Q�Q�|�Q�R���A�����S���w�Z�זE��\�҉�c�A�}�����쐬�̉^�����j���h�w���ɑ��閳���j�ƕΌ��h�Ɣᔻ�E�ی��B
�@�P�P�D�Q�S�|�Q�T���A�S���������\�҉�c�k����l�A�n���K���[���c�A���S������ēP�����c�A�P�Q�D�T�S�������N���Ăт�����B
�@�P�P���A�u��������v������P���i����w���S�����s�ψ���镔�ӔC�ҏW�E���M�F�������j�A������v�A���c�G�Y�j�B�P�Q���A�u��������v������Q���i���M�F��،[��A���c�M�Y�A�������j�ق��j�B
�@�P�P�D�Q�R�|�Q�T���A����w����R��S�����k�����J����فl�A���E���A���������c�A�����ɇ��E��������@�����̎��Ȕᔻ�̑��B�u����w�����L�ǍזE�ӌ����v����N����A11.1�������֎~���ۓ���s���f�[������Γ��������ᔻ���J�n����B�����g�D�S��x����疼�Ɣ��\�B�S���P�O�Q�x���A����������P�疼�B���Z������������B�g�D�����E���c���A���c�A�����A�Γc�A�����A���炪�w�����ɏA�C����B
�@�P�P�D�R�O���A�S�w�A�ً}�����ς��A�P�P�E�P�����������A�P�Q�D�S�Ε]���A�P�Q�D�U����e�����Γ���������B
�@�P�P���A���X�N���ŎЉ��`�v���S�O���N�j�T�B�u��C�����D���̍��ۉ�c�o�ȁB
| �y���{�v���I���Y��`�ғ����i�v�����j�̒a���z |
�@�P�Q���A���{�g���c�L�X�g�A���́A���{�v���I���Y��`�ғ����i�v�����j�Ɖ��̂����B���̗���ɂ͐����i�i����j���̍������W���Ă���B���{�g���c�L�X�g�A���́u������p�v���I��t���Ă��A���Ȃ�̉e���͂������Ă������{���Y�}���s�{�ψ��̐����i�����T�V�D�S�����Ɂu�A���v�ɉ������Ă��邱�ƂɂȂ�A���̐����Ă��炽�߂č��c����A���c���A�����i�A���J��𒆐S�ɂ����v�����̌����ւƌ��������ƂɂȂ�����ł���B���̎��_������{�g���c�L�X�g�^���̖{�i�I�J�n���Ȃ��ꂽ�ƍl������B���̗���łT�W�N�O��A
�S�w�A�̋}�i��`�I�����Ƃɑ��ăt���N���������Ȃ苭�͂ɐi�߂��Ă������ƂɂȂ����B
�@�A���A�v�������́A��������������������S�^�S�^�������Ă������ƂɂȂ����B�P�ӂŌ���A����قǗ��_�������d������Ă����Ƃ���
���Ƃ����m��ʁB |
�@�P�Q�D�S���A�S�w�A�E�S���w�����ÂŢ�Ε]���E���勳��i�죓������s���A�S���̋���n�w���T�����e�n�ŏW����J�Â��A�����̒����W��k����J�쉹�l�ł͂P�O�O�O���̊w�����Q���������ȁE�s���ɍR�c�f���B
�@�P�Q�D�U���A�ČR�̉���s���e�����ΑS���w�������N���A�����W��k�����J�����l�ɓ��勳�{�����߂Q�T�O�O���Q���A�đ�g�قɍR�c������A�V���܂ł̃f���łR���ߕ߁A�S���W�J���ŏW��E�f���B
�@�P�Q�D�P�O���A�ɓ��V��R�Ō����B���c�锖�V�̖ÁE���V�o���d���Ɗw�K�@�勉�F�̐S�����̔����B
�@�P�Q�D�P�T���A�u�S�w�A�ʐM�v��O�\�ꍆ�������ċx���A�V�N�x��藝�_�@�֎����s�Ɣ��\�B
�@�P�Q�D�P�V�|�P�W���A�S�w�A�g�咆���ρA����ߔe�s���I�Ŗ��A���E�̌������x���A�Ε]���Γ���������������B
�@�P�Q�D�Q�O���A�S������ψ������c��u�Ζ��]�莎�āv�����F�B�P�Q�D�Q�Q���A�����g���Ζ��]�蔽�Γ����́u��펖�ԁv�錾�B
�@�P�Q�D�Q�S���A�m�g�j�A�e�l�������J�n�B�P�Q�D�Q�W���A�m�g�j�E���{�e���r�A�J���[�e���r���������J�n�B
| �y�u���g���g���̖d�c�z |
|
�@����I�ɍČ����ꂽ�S�w�A�͂��̍��}�h�������߂Ă������ƂɂȂ����B �v�����̌����́A�����w���}���O���[�v�̋}�i��`�h���h�������B
�@�P�Q���A�S�w�A�嗬�h�̍ō��w�����ƂȂ��Ă������A���c�A�����G���i���吔�w�Ȃ̑�w�@�w���j�̎O���́A�{���n�����̉E�h�I�������猈�ʂ��A�Ǝ��̓}�h�������߂��������̍��A���l�̍����̉ƂŐV�}���g���̂��߂̃t���N�V�������������ӂ��Ă���B
�}�����h�֎~�K���ɑ��鎩�o�����ᔽ�������ĂȂ����Ƃ��Ă������ƂɂȂ�B���̋͂��R���̃X�^�[�g�����N�̃u���g�����̖G��ƂȂ����B��u���g�̖閾���O�v�̓����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̎��̂��Ƃ𓇎��͌�N���̂悤�ɒǑz���Ă���B
�@����ɁA�w�X�^�[������`�x���P�Ȃ��v�z�ł͂Ȃ��\�A�Ƃ�������ȍ��ƈӎv�̎����ƁA���̕��������ꂽ���̂Ƃ̔F���ɓ��B��������A�w�X�^�[������`�x�����͍ő��ς����鑶�݂ł͂Ȃ��A�œ|���ׂ��Ώۂł���A�~����Ƃ���́A����ɑ���V�����O�q�̑n�݂ł���B���̗���ɗ��������c�́A�����ɁA�������e�ՂȂ�ʌ��ӂ������āw�V�����O�q�x�̏����ɒ��肵���B�P�X�T�V�N�̕��̈�����A���̍��c�̂��ߐ��c�Ǝ��A�����Ăr������ꏊ�����A�X�N��A���c�̊D���}���˂Ȃ�Ȃ��������̉��l�̎��̈���ł������B
�@����A�}�l�Ƃ��Ă̐��c�́A���̓}�̍s�������͂��˂Ȃ�ʌ̂ɁA�Z�S����̓}�������̖ڕW�ł�����������V����Ɍ����אS�̑g�D�����s���A�ł��N���̑�c���̈�l�ɂȂ����̂���i����c�v�ȒǓ��L�O���W��̓����̒Ǔ����j�B |
�@�ނ�́A���{�g���c�L�X�g�A���h�̃I���O�ɉ����Ȃ������O���[�v�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ邪�A���̍��g���c�L�[�y�уg���c�L�Y���Ƃ͉����̂ł���̂��ɂ��Č����ɒ������J�n���Ă������悤�ł���B�������ɘR�ꂸ�A�ނ���܂����̎��܂œ}�̃X�^�[������`�I�Ȏv�z����̉e�����ăg���c�L�Y���ɂ��Ă͕����Ԃł������B���̎��A�Δn���s�E���c����̒���̏�������Ȃ���֒f�̏��g���c�L�[����{���Â�悤�ɓǂ܂��
�������ƂɂȂ����B���E���́A�u���j�̏،��u���g�v�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@�u�ꖇ�ꖇ��̂��낱��������v���ł������B�����ĉߋ��ɂȂ������̂ł͂Ȃ��B����̐��E�ɔ��肤��v�z�Ƃ��������v�B |
�@���o�́u���̗������̐؏��F�҂̂Q�O�O�V�D�P�O�R���t�����R�́u�R�l�̐�y�v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�u�P�X�T�U�N�̓�����w���A���͗��j�w�҂�ڎw���Ă����B��������w�Ɠ����ɁA���̎��v�䌚���̒��ɂ��������j������̕����ɏo���肵�n�߂��B�܂��}���N�X��`�����|�I�ɒm���l�E�w�����������A���ł����j�w������Ύ���̒n�ʂɂ��������ゾ�B
�@�����ɂ́A�p�X�̎���̕��͋C���c�������g�A�����ň��|�I�ȃJ���X�}���U�������y�������B�T�O�N�̔����b�h�p�[�W�w���^�����ɍF�s�ފw�ɂȂ��đ匟�œ���i�݁A��̑�w�������Ȃǂł͖���A����̓N�w�����Ƃ��Ċw���^���ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ�A�L�����B
�@�ނɑ�w�����ŃR�[�q�[�ɗU��ꂽ�B�������A�Ƃ��Ԃ���ƁA�w���{���Y�}�͂������߂��B����זE�ł�����x�{���̃}���N�X��`��������B�Q�����Ȃ����x�ƌ����B�܂��P�W�̎�҂ɂƂ��ẮA�v���������Ȃ��b�ł��邪�A�R�����������͂��������B���̌�̐l���s�H�̕��p���߂�o��ƂȂ����B
�@�T�U�N�ɂ͊w���^�����Ăяグ���ɏ��n�߂Ă����B���{���Y�}����w�זE��ʂ��Ċw���^�����哱����̂ł͂Ȃ��A�w���������̓I�ɉ^�����N��������̎n�܂肾�B
�@�����̓���זE�ɂ͏G�ˁA�r�ˁA�ٍ˂��L�����̂悤�Ɍ��W���Ă����B���ł����c�_��Ƃ����A���̌�A�������鎀�Ɏ���܂Ől���s�H�����ɂ��邱�ƂɂȂ�j�������B�@�܂ł��藎����ዾ�������Ȃ����c�X�Ƃ��Đl��������邻�̐l���ɂ͒N�����M�������������B
�@�ނɗU���ĉ��l�ɂ��邨���̉ƂɁA���w�Ȃ̑�w�@�w�������������G���ɉ�ɍs�����B�����͎R���ꗝ�Ƃ����y���l�[���ŁA����זE�̋@�֎��ɏՌ��I�Ș_���������A�^���Ƃ̊Ԃł͐_�i�I�ȑ��݂������B���{�̍����^�������������̂́A�P�ɓ��{���Y�}�̂����ł͂Ȃ��A�{�Ƃ̃\�A�������������Y��`�^���𗠐������炾�Ƃ����B�ڂ����������A�Ƃ͂����������Ƃ��B
�@���Â��ɗ��ʼn�X�̓g���c�L�[�ɂ��Č�荇�����B���V�A�v���̎w���҂̈�l�ł���̂ɁA���G�X�^�[�����ɒǂ��ă��L�V�R�ňÎE���ꂽ�l�����B�g���c�L�[����͍��ۋ��Y��`�̉߂����w���A�ނ̃G�s�S�[�l�������ɂ���l�C���^�[�ւ̎��X�ȗU���ɂ͉�X�͉����Ȃ������B�����͌�ɁA�J�i�_�Ő��w�����ɂȂ����v�B |
|
 �i���_�D���ρj�@�u���g�����O��̓����ɂ��� �i���_�D���ρj�@�u���g�����O��̓����ɂ��� |
�@�c��a�v���͢���{���Y�}�j��̒��Ŏ��̂悤�ɁA�u���g�����O��̔w�i������Ă���B
�@�����̎�̓I���H�̒�����A����Ɋ�Â����_�I�T�����Ƃ����āA�����ɁA�Q�O���I�̖��@����X�^�[������`�̎������玩�����������Ƃɐ��������w���B�́A���͂�A�}���N�X�ɂ���đn�n���ꂽ�A�v���I���_�Ƃ��̎v�z�A�ނ玩�g���g�������ē����v���I���H�A�����ăv�����^���A�[�g�̉���ɂ��l�Ԃ̋��ɂ̊J���ɑ���ƔM��ȊO�ɁA�@���Ȃ錠�Ђ��F�߂Ȃ������B
�@�ނ�́A�S�O���邱�ƂȂ��A�Ȃ��炭���Y�}�w�����ɂ���āA�x�[����킳��Ă����}���N�X��`�A���̊v���I���_���̂����̐ێ�ɓːi�����B�����āA�}���N�X�̐l�ԊJ���̊v���I�v�z�Ɨ��_�A���̎�̓I�ȓN�w�Ə�M�Ǝ��H�A���{��`�Љ�̋���ȃ��J�j�Y���̓��O�������́A�w�ꍑ�Љ��`�x�_�ƕs���Ɍ��т�����i�K�v���_�ɑΒu����ׂ��A�S���E�ɂ킽��v�����^���A�i�v�v���Ɋւ���v���I���_�A���݂̃��V�A�E�\�r�G�g�Љ���w�Љ��`�x�Ə̂���Љ��`���̂��̂��⏬���Ɗ����i��̗��_�ɑΒu����ׂ��A�}���N�X�ɂ���āA�͂��߂Ē�N���ꂽ���Y��`�Љ�̑s��ȓW�]���X���w�ю��w�͂��J�n�����B
�@�S�Ă����̂��Ƃ́A�P�X�T�V�N�������l�܂���������P�X�T�W�N�ɂ����āA�͂��߂͂��ǂ��ǂ����A��ɂ͔����I�Ȍ`���Ƃ��čs��ꂽ�B�w���B���A�T�V�N�̂P�P�D�P���q�푈���������ۓ���s���A����̑�������ƕs���ߕߔ��Γ�������A�T�W�N�̂�������ȋΕ]��������x�E�@���Γ����ɂ�����A���{�u���W���A�W�[�Ƃ̐��ʂ���̑Ό��̊J�n�Ƃ����i�K�֑O�i���Ă䂭�A���R���钆�ŁA�����̗��_�I�]�����͂����������̂ł��飁B |
|
| �y�u���g�̖閾���A�ŏ��̃P�����z |
|
�@�u���E���c�E�����̂R���̔閧��c�v�͎��̃����o�[���l�����A���ꂪ��̃u���g�̊j�ƂȂ����B����זE�̐��c�_��A�����G���A�y���{�Y�A�؏��F�B����זE�̕ЎR���v�A����C���B���̐��{���X�B�ނ�́A���{�g���c�L�X�g�A���h�̃I���O�ɉ����Ȃ������O���[�v�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B�A���A���{�͓�҂ł������悤�ł���B
|
| �y�R���ꗝ�_���̏Ռ��z |
|
�@���̍ŏ����u���g���A���[�j���E�g���c�L�[�H���ɂ�鍑�ۋ��Y��`�^���̌������Ɏ�肩����A���_�W�J���n�߂��B�R���ꗝ�i�����̃y���l�[���j�̘_��
�u�P�O���v���̓��Ƃ����̓��|���ۋ��Y��`�^���̗��j�I���P�v�i��Ɍ��������u���g�̌��T�ƂȂ����ƌ����Ă���j�Ɛ��c�_���u�v�����^���A���E�v�����ˁI�v���f�ڂ������{���Y�}����זE�@�֎��u�}���N�X�E���[�j����`�v��X��������オ�����̂��T�V�D�P�Q���̑�A���̖�ł������B
�@���̢�R���ꗝ�_����́A���Ȃ蒷��ȕ��ʂŁA���V�A�v���Ȍ�̍��ۋ��Y��`�^���̓W�J����Ղ�����ő������A���̏�œ��{���Y�}�̉^�������n���I�ɔᔻ�I��������Ɖ]���X�P�[���̑傫�ȋc�_��W�J���Ă����B
�@�{�����莮�����n�߂Ă����u�܂��̓u���W���������`�v���̐��s�Ɖ]����i�K�v���_�v��ے肵�A���{�ɉ�����v���^���̐��E�j�I�Ӌ`���u���E�v���ւ̍Ő�[��S���v�Ǝw�j�����Ă����B���̏�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �@��w�G�͗D���A�����͗x�Ƃ����ȃX���[�K���ɂ���ăY�u�Y�u�̑�O�ǐ���`�Ɋv�����������߁A���ۓI�ȁw���a�Ɩ����`�x�̃X���[�K���ɂ���āA�v�����^���A�[�g�̑O�q�I���������������Ă��܂����̂ł�������B |
�@�R���_���́A�{���哱�̉E���I�}�^���ɑ���s�p�I�ȃA���`�̊ϓ_�ƂȂ����B���̘_�����A�S�w�A�}�i��`�҂����ɏՌ��I�ȉe����^���Ă������ƂɂȂ����B���̎R���_���̉�����ɕP���採�i�؏��F�j�A�|�����v�i����o�j�炪�u���g�@�֎��u���Y��`�v�Ɏ��X�Ƙ_���\���A���ꂪ�u���g���_�ƂȂčs�����ƂɂȂ�B���̎��_�ł͢�R���ꗝ�_��������_�I�ȕ���ɂȂ�A��ɓ��{���Y�}����זE�����𒆐S�Ƃ��āA���̉e�����ɂ������w���B�����S�ƂȂ��Č�q����u���g�����ւނ������ƂɂȂ�B�@
�@���̘_�����ʂ���������I�����ɂ��āA���c�v�����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�����A�v�����͂��̎R���_�����w�g���c�L�\�̃m���J�~�H�x�A�w�u���g����j�ς̌��T�x�ƍ��]�����B�������A���̘_�����ʂ����������͌���I�ł������B���̘_���͓����}���_���̃��N���݂͂����d�v�ȓ��e���ӂ���ł����̂ł���B���̕\���ɂ���w�v�����^���A���E�v�����ˁI�x�Ƃ�����̃X���\�K���Ɏ�����Ă���悤�ɁA�_���͂��ꎩ�̂��A�K�������ڔ}��ɂ��ēW�J���ꂽ�����}�������̗��j�I�Y���ł���ƂƂ��ɁA�}�������ɂЂƂ̕������ƌ��W����^���邽�߂́A������ׂ��}�h�����ɓq����錾�ł���A����͓���זE�̓��O�ɋ���Ȕ������܂����������B
�@�_���́A���ɁA�Y�ꋎ��ꂽ���E�v���������邽�߂ɁA���V�A�v���Ȍ�̍��ۋ��Y��`�^���j��S�ʓI�ɐ����A�}���̉E���I��������ᔻ���A���ɁA���v���̑㖼���Ƃ��ꂽ�g���c�L�\�ɂ���w��ŁA�X�^�[�������ȏ��́w10���v���̓`���x��ł��ӂ��A���[�j���̊v���I�w���̐������w�сA�w�{���V�F���B�L�}�̐������퓬�I�`�����Č��x���邱�Ƃ��Ăт����A��O�ɁE���V�A�E�{���V�F���B�L��p�Ɋւ���}�������̗��j�I���P���w�Ԃ��Ƃɂ���āA������ׂ��}�������ɔ����悤�Ƃ����B
�@�܂��A�_���͓}�������ő�܂��߂ɉ������Ă����j�̘_���ɂ������āw�����`�v�����Љ��`�v�����A����ނ���\�����ǂ��A�Ƃ����_�c����O���������͂邩�ɂ͂ȂȂ����s�Ȃ��Ă���x�Ƃ��āA���̓]�|�����j�̘_���̕s�ѐ����������ᔻ���āA�v���^���ɂ���������}�������ɂ��������Ɨ��ꐫ���������v�B |
|
|
�y����v���_���j�E�㉺�Q������������z
|
�@���̍��A��c�k��Y���`�Ţ���v���_���j�㉺�Q������匎���X���犧�s���ꂽ�B�����͓����̍��h�^��������̔������悭�A��c�E�s�j�Z��o���̑��|����ƂȂ����_�ő傫�ȈӖ������B�Ƃ��낪�A��c�E�s�j�����͂��̌��ł��w�����č����Ɏ����Ă���B����ɂ��A�������́A���c�͐ɂ��ނ炭�͂��̖��������݂܂Ő�łɂ����܂܂ł���B���F�̓}�j�Ɩ����A��������_�q�����邱�ƂȂ���A�����炭�����̓��{�v���_�����j�̂Ƒ��e��Ȃ����߂ł��낤��Ǝw�E���Ă���B
�@�Ƃ��낪�A�ŋߔ����������Ƃ́A��c�ƕs�j�����̘J��������グ���Ƃ���Ă������A���ۂ͈Ⴄ�悤�ł���B�u��c�E�s�j�w���v���_���j�x�o�Ōo�܂̗��b���i�^���j�ɂ��āA�{�n���̃z�[���y�[�W�̔��e���e�v���Љ��B
�@
�@�Γ����ώ��Ƌ{�n���̊ԂɌ��킳�ꂽ�莆�R�ʂƏ��]�ɂ��A����v���_���j�㉺�Q����o�Ōo�܂ɂ��Ď��̂悤�ɖ��炩�ɂ���Ă���B �Γ����́A��c�E�s�j�����w���v���_���j�x�̏o�łƔp���̌o�܂�m��Ȃ��l�������悤�ł������M���Ă����܂��Ƃ��āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B��������ӖĊT�v�������B�ڂ����͋{�n����T�C�g����Y�}���A�Љ��`�����l�����Ŋm�F���������B
|
�@�@�u�^���j�����v�P�S���i�S�W�`�S�X�Łj�ɂ��G��Ă��܂����A����́A����s���A�������A�R��t���A����`�F�A���ƂŁu�����{�̕��́v��������J���A�������\����ɂ킽�铢�_�̐��ʂ𐢂ɑ���o�������̂ł��B�ꓯ���܁Z�N�ȗ��̎�������������āA������Ɩʔ������_�������܂����B���̍��͂܂���������̏�c�k��Y���M�^���܂������A����ȉ��ܖ��͂T�O�N�i�K�̍��۔h�̊w����ψ��ŁA��c�N�͊w�����̈ψ��̈ꖼ�ł����B���_�̐��ʂ����N���܂Ƃ߁A����̖��`�ŏo�ł���͂��̂��̂ł����B
�@�Ƃ��낪�A���삪���x�M�ň���ɐi�����Ȃ��̂ŁA�҂�����Ȃ��匎���X���₩�܂��������n�߂܂����B�����Ă܂Ƃ߂悤�ɂ����ꂼ��̎҂����Ԃ��Ȃ��A���]�̈��Ƃ��ď�c�ɂ�点�A�ނ̖��`�ŏo�ł��悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B�匎���X�̏��ђ��q�́A��c�Ȃ�Ė����̐l���ł͍���Ƃ����Ĕ����܂������A��c�͑��낱�тł��B�����āA�����������̑g���̏��L�����Ă�������������Ă�悢�@��䂦�A�s�j�̖��������Ăق����Ɛ\���o�A�ꓯ������悩�낤�Ə��������̂����ۂ̌o�߂ł��B
�@�������āA���_��M�L���Ă�����c�N������N�ɑ����Ď��M���邱�ƂɂȂ����̂ł����B�w���v���_���j�x�̏o�Ŏ���͂��̒ʂ�ł��B���̖{�̍ޗ��Ɏg�p�����������́A�܂��w��������̏�c�N�������Ă���킯�͂Ȃ��A����ȉ��ܖ��������Ă������̂���Ă��܂��B�������ނƂ��̒�s�j�N�O�̌l�I�v�����傫������A�����̖��`�ɂ��Ă��ꂵ���͂Ȃ��B���������e�I�ɂ͓����̍����_�d�̈�̐������������̂Ƃ��āA�������Ģ���I��̂��̂ł͂Ȃ��B
�@�������āw���v���_���j�x���P�X�T�U�N�P�Q���Ɨ��N�P���ɏo�ł���܂����B����́A���ɂ悭����A�������ŏ�c�ƕs�j�͂�����ɗL���ɂȂ����̂ł��B�u����̗��_�v�Ƃقړ������̂��Ƃł��B����ȊW�ŏ�c�̌����p�[�e�B���A����͂��ߑS�����o�Ă��܂��B���̌o�߂ɂ��āA�{�{�͓G�ӂ�����Ă�����������܂��A�����͗����������Ă��܂����B�����u����̗��_�v�ɎQ�����Ȃ������̂́A�Ƃ��ɋ{�{�Ɍ����Ă��āA���̖����o��ƁA�����Ă��邾�낤�Ɣ��f��������ł��B
�@�Ƃ��낪�A���̌�̌o�܂͕s���ł����A��c�͂��̌����O���[�v���痣�E���A�{�{�h�ɈƂ��������Ă��܂��܂��B���̌�{�{���W���̐����Lj��ɂ܂ŏ��i���܂����B�{�{�N�́w���v���_���j�x�ɑ��čŏ�����s���������ł��傤���A���܂Ă����Ƃ���A���ɂ��т�����炵�āA�Z������Ȕᔻ�����A�w���v���_���j�x��ł𔗂�܂����B���̂Ƃ��Q�l�́A���̎��������̂܂܂ɍ������ׂ��������̂ł����A�܂�Ŏ��Ȃ̒���ł��邩�̂悤�ɐ�ő[�u���Ƃ�܂����B����ƂƂ��Ă̖����ɖ���������������łȂ����Ƒz�����܂��B��ł���ɂ��ẮA��c�Z��͓��`�㎄�����̗������Ƃ����ׂ��ł��傤�B�܂�Ŏ��������Z��̒���̂悤�ɐU�������̂ł��B�������Ȓj���Ƃ����l������܂������A���̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ��������ȗ��j������܂��B
�@�t������A�}�̊ێR�^�j�ᔻ�̈Ӗ��́A�ێR���_�ɂ���ē}�́u�_�b�v�������ƂԂ��Ƃ��A�{�{�N�͒����������A���̂��Ƃɂ���Ĕᔻ�L�����y�[�����ׂ���Ă���C�����܂��B
�@ �ŋߊ��̕s�j�́w���{���Y�}�̗��j�ƍj�̂����x�����߂܂������A���̃S�}�J�V�Ɛ����I���ӔC�͂���������ł��B������V�O�ɂȂ�܂������A���̗��_�̐Ȃ��Ƃ́A�~������̂ł��B�}���N�X�A�Ƃ��Ƀ��[�j���̌��ȂǂƁA�ނ̌����̂́A�����Ⴂ�ł��B�ŋ߁A���V�A�ŁA�P�W�X�P�N�`�P�X�Q�Q�N�̃��[�j���́g�m��ꂴ�钘��h�����s����܂����B�g�m��ꂴ��h�Ƃ������́A���\���͂����Ă�������Ƃ����ׂ��ŁA���������̑S���Ƃ͓��ꌾ���Ȃ����̂ł����A������\���ꂽ�S�Q�O�_�̕������A���S�Ȃ��ǂ����悩�낤�Ǝv���܂��B���[�j���́A���낢��ԈႢ�����A�w�}���Ƃ��Ă��܂����A�����㗈�̋{�{��s�j��ƍ߂��邽�߂ɍs�������l���łȂ����Ƃ�m��ׂ��ł��B
�@�Q�l�́A�}�j�̂����A������ɓs���̂悢���������𑊑���������ł��B����ȁg���̂����h���葊��������Ă���悤�ł́A�g����w���A����Y��Ȃ������h�l�Ԃ̕W�{�ɂ��ꂻ���ł��B�����Y�}�ɂ́A�}�j�͋{�{���W���̊m�����N�_�Ƃ���Ƃ������ꂪ����܂��B�{�{�ȑO�̓}�^���̂����A���̐ϋɖʂ͑������邪�A���ɖʂɂ͐ӔC��Ȃ��͈̂��̌��葊���_�ł���܂����A���葊���_�ɂ��������ꍇ�A���̓}�^���̐��ʂ͂ǂ̂悤�ɋ敪�����̂ł��傤���B�@
|
|
 �i�����E���_�j�@�u�w���v���_���j�x�̏o�łƐ�Ōo�߂Ɍ������c�̐l�ԓI������ɂ��� �i�����E���_�j�@�u�w���v���_���j�x�̏o�łƐ�Ōo�߂Ɍ������c�̐l�ԓI������ɂ��� |
�@�Γ����͍��h�C���e���Ƃ����i������ł��낤���A�W�X�Ǝ������������b�Z�[�W���Ă���B�������������ɕ�����₷���|��Ƃ����Ȃ�B��c�́A�Γ�����T���̐�y�}���̋Ɛтނ��Ē�s�j�Ƃ̋����Ƃ��āu���v���_���j�v�𐢂Ɍ��`���Ă����B�{���ł���A�㏑���ŏo�Ōo�߂���ׂ��Ƃ�����Ӑ}�I�ɂ͂�����Ă���B�܂�A�g���r�̖��g���Ȃ����͎蕿�̉��������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̖{�̕]���͍����A�e�E�����c�E�s�j�̐��������߂邱�ƂɂȂ����B�ō��w���ҋ{�������ɍD�ރ^�C�v�ł���Ƃ������Ƃł��낤���A���̌㗼���͋{���̉��ɓ��荞�ݏo���K�i�����l�߂Ă��������̒n�ʂɂ���B
�@�����������A���������荇���̏o����`�l�m���}�����ɌN�Ղ��Ă���Ƃ������Ǝ��̒p���ׂ����Ƃł���B��͂肱�̃��C���͓���}���ԈႦ�Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��B
| �w���v���_���j�x�ɂ܂�闠�b�B�@���e�ҁF������@�T�D�Q�U�� �����������f���� |
�@��c�E�s�j�w���v���_���j�x�o�Ōo�܂̗��b���i�^���j�ɂ��āA�{�n��������Y�}���A�Љ��`�����l�����̔��e���e���܂Ƃ߂Ă݂܂����B�{�n����ɂ͎���ł������肤����ł��B
�@�Γ����́A��c�E�s�j�����w���v���_���j�x�̏o�łƔp���̌o�܂�m��Ȃ��l�������悤�ł������M���Ă����܂��Ƃ��āA�{���̏o�ł̌o�܂ɂ��Ď��̂悤�ɖ��炩�ɂ��Ă��܂��B��������ӖĊT�v�����܂����B
�@��^���j�����v�ɂ��G��Ă��܂����A����́A����s���A�������A�R��t���A����`�F�A���ƂŁu�����{�̕��́v��������J���A�������\����ɂ킽�铢�_�̐��ʂ����ɂ��Ă��܂��B�ꓯ���T�O�N�ȗ��̎�������������āA������Ɩʔ������_�������܂����B���̍��͂܂���������̏�c�k��Y���M�^���܂������A����ȉ��ܖ��͂T�O�N�i�K�̍��۔h�̊w����ψ��ŁA��c�N�͊w�����̈ψ��̈ꖼ�ł����B���_�̐��ʂ����N���܂Ƃ߁A����̖��`�ŏo�ł���͂��̂��̂ł����B
�@�Ƃ��낪�A���삪���x�M�ň���ɐi�����Ȃ��̂ŁA�҂�����Ȃ��匎���X���₩�܂��������n�߂܂����B�����Ă܂Ƃ߂悤�ɂ����ꂼ��̎҂����Ԃ��Ȃ��A���]�̈��Ƃ��ď�c�ɂ�点�A�ނ̖��`�ŏo�ł��悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B�匎���X�̏��ђ��q�́A��c�Ȃ�Ė����̐l���ł͍���Ƃ����Ĕ����܂������A��c�͑��낱�тł��B�����āA�����������̑g���̏��L�����Ă�������������Ă�悢�@��䂦�A�s�j�̖��������Ăق����Ɛ\���o�A�ꓯ������悩�낤�Ə��������̂����ۂ̌o�߂ł��B
�@�������āA���_��M�L���Ă�����c�N������N�ɑ����Ď��M���邱�ƂɂȂ����̂ł����B�w���v���_���j�x�̏o�Ŏ���͂��̒ʂ�ł��B���̖{�̍ޗ��Ɏg�p�����������́A�܂��w��������̏�c�N�������Ă���킯�͂Ȃ��A����ȉ��ܖ��������Ă������̂���Ă��܂��B�������ނƂ��̒�s�j�N�O�̌l�I�v�����傫������A�����̖��`�ɂ��Ă��ꂵ���͂Ȃ��B���������e�I�ɂ͓����̍����_�d�̈�̐������������̂Ƃ��āA�������Ģ���I��̂��̂ł͂Ȃ��B
�@�������āw���v���_���j�x�͂P�X�T�U�N�P�Q���Ɨ��N�P���ɏo�ł���܂����B����́A���ɂ悭����A�������ŏ�c�ƕs�j�͂�����ɗL���ɂȂ����̂ł��B�u����̗��_�v�Ƃقړ������̂��Ƃł��B�����u����̗��_�v�ɎQ�����Ȃ������̂́A�Ƃ��ɋ{�{�Ɍ����Ă��āA���̖����o��ƁA�����Ă��邾�낤�Ɣ��f��������ł��B
�@�Ƃ��낪�A���̌�̌o�܂͕s���ł����A��c�͂��̌����O���[�v���痣�E���A�{�{�h�ɈƂ��������Ă��܂��܂��B���̌�{�{���W���̐����Lj��ɂ܂ŏ��i���܂����B�{�{�N�́w���v���_���j�x�ɑ��čŏ�����s���������ł��傤���A���܂Ă����Ƃ���A���ɂ��т�����炵�āA��c�Z������Ȕᔻ�����A�w���v���_���j�x��ł𔗂�܂����B���̂Ƃ��Q�l�́A���̎��������̂܂܂ɍ������ׂ��������̂ł����A�܂�Ŏ��Ȃ̒���ł��邩�̂悤�ɐ�ő[�u���Ƃ�܂����B��ł���ɂ��ẮA��c�Z��͓��`�㎄�����̗������Ƃ����ׂ��ł��傤�B�܂�Ŏ��������Z��̒���̂悤�ɐU�������̂ł��B�������Ȓj���Ƃ����l������܂������A���̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ��������ȗ��j������܂��B
�@�ŋߊ��̕s�j�́w���{���Y�}�̗��j�ƍj�̂����x�����߂܂������A���̃S�}�J�V�Ɛ����I���ӔC�͂���������ł��B������V�O�ɂȂ�܂������A���̗��_�̐Ȃ��Ƃ́A�~������̂ł��B�Q�l�́A�}�j�̂����A������ɓs���̂悢���������𑊑���������ł��B�����Y�}�ɂ́A�}�j�͋{�{���W���̊m�����N�_�Ƃ���Ƃ������ꂪ����܂��B�{�{�ȑO�̓}�^���̂����A���̐ϋɖʂ͑������邪�A���ɖʂɂ͐ӔC��Ȃ��͈̂��̌��葊���_�ł���܂����A���葊���_�ɂ��������ꍇ�A���̓}�^���̐��ʂ͂ǂ̂悤�ɋ敪�����̂ł��傤���B�@
�@�ȉ��A�����������Y���Ă����܂��B�Γ����̓C���e���Ƃ����i������ł��낤���A�W�X�Ǝ������������b�Z�[�W���Ă���B�������������ɕ�����₷���|��Ƃ����Ȃ�B��c�́A�{���ł���A�㏑���ŋ����I�o�Ōo�߂���ׂ��Ƃ�����Ӑ}�I�ɂ͂�����Ă���B�܂�A�g���r�̖��g���Ȃ����͎蕿�̉��������Ă��邱�ƂɂȂ�B�ō��w���ҋ{�{�����ɍD�ރ^�C�v�ł���Ƃ������Ƃł��낤���A���̌㗼���͋{���̉��ɓ��荞�ݏo���K�i�����l�߂Ă��������̒n�ʂɂ���B�����������A���������荇���̏o����`�l�m���}�����ɌN�Ղ��Ă���Ƃ������Ǝ��̒p���ׂ����Ƃł͂Ȃ��낤���B��͂肱�̃��C���͓���}���ԈႦ�Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��B |
|
|
| �y�S�w�A�̍Č�����鍶�E���h�̍R���̑������l�z |
�@����{�v���I���Y��`�������j��͎��̂悤�ɋL���Ă���B
| �@����쓬������T�V�N�t�̃N���X�}�X���A�G�j�E�G�g�N�ʂł̐����������Γ����A�����Č������֎~���E���A�P�P�D�P���̌������֎~���ۓ���s���ƁA�S�w�A�̉^���͂T�V�N�����ς����a�i�쓬����W�J���Ă������B���̂T�V�N�����ς��ɂ킽���ēW�J���ꂽ���a�i�쓬���́A���̓����̓��{�̘J���Ґl���̕��a��`�I�C���Ɉˋ����A���܂��A�\�A���Y�}�Q�O����H���Ƃ��Ă̕��a�����H���ɂ̂��Ƃ�A���̘H���𑣐i������^���Ƃ��Đ��������̂ł���B���������Ă��̓��{�̊w���^���͕��a�����H���̐퓬�I�ȍ��̗��Ƃ��Ĉʒu���Ă����Ƃ����悤��B |
|
 (���_�D����)�@����a�����H���̐퓬�I�ȍ��̗��Ƃ��Ĉʒu���Ă����S�w�A�^����l (���_�D����)�@����a�����H���̐퓬�I�ȍ��̗��Ƃ��Ĉʒu���Ă����S�w�A�^����l |
�@����{�v���I���Y��`�������j��̎w�E���颕��a�����H���̐퓬�I�ȍ��̗��Ƃ��Ĉʒu���Ă����S�w�A�^����Ƃ͋ɂ߂ĕ��G�ȕ\���ł��邪�A�I�m�ł�����B�������A���̔w�i�������f�^�����ł���̂ł�������������Ă��������B�]���A���̢���G����̉�͂��ׂ���Ă��炸�A���Ȃ������ϓ_�͌X���ɒl���邾�낤�B
�@���Y�}�̢�T�O�N������r��Ŕ������������h�ƍ��۔h�̂ӂ��̗���́A�Z�S���ł����č��۔h�̏����ɋA�����B�������Ȃ���A�����h�ƍ��۔h�͂ǂ��炪�E�h�ō��h�ł���̂����ʂ���Ƃ���ɕϒ���������B�Ȃ������������ɂȂ�̂��Ƃ����ƁA�����}�����̐��ςɃ_�C���N�g�ɊW���Ă��邩��ł���B���̐k���n�̊j���ׂ��Ă����{���́A�������h�����̊Ԓ��͍��h�Ɉʒu���Ă����B���̎��S�w�A�����͋{���h�Ɉʒu���Ă����̂ł��̐퓬�I���h�������p���ꂽ�B�Ƃ��낪�A���b�h�E�p�[�W�ȍ~�����}�����������֖��q���A�k���@�ւ����A�C�O���玝���������V�H���͖ڂ��܂�������̍��X���������H���ł������B�S�w�A�������h�͂��̕��j�ɏ]���A�Ή��т����邢�͎R�x�����n�����ɓ˓������B�Ƃ��낪�A�����h�����X������ƍ��x�͍��۔h���E�X�����n�߁A���E�̗��ꂪ�t�]����n���ƂȂ����B���̌��ۂ́A�������j���}���}���Ȃ�ʎ��������Ɋ�Â��Ă��邱�Ƃɋ���Ƃ����l�����Ȃ��B
�@���������Ӗ��ŁA���۔h�̔��핽�a�����Ƃ́A�����h�̕��������Ƃ͕ʋO�����ӎ����������Ȃ���܂����^���ł��邱�ƂɂȂ�B�������A���̒��ɁA��X�̉E�h�n�����ƍ��h�n���������݂��Ă����B���͍X�ɂ��ꂩ���₱�����Ȃ�B���̓����n�����h�^�����j�Y�������A�P�X�T�T�T�N�̘Z�S���ŋ{��v�����ŋ{����h���}�����ɓo�d�����A�{���͂���܂ł̢���h���ߑ�������Ȃ���̂Ď�̂Ђ��Ԃ����B�I���ȉE�h�n�^���֓]�������n�߂��̂ł���B����ɂ�荑�۔h�̖ʁX�͏�������҂ƒ�R����҂̓�h�ɕ��邱�ƂɂȂ�B�E�h�n�͐V�}�����ɋA�����}���̓o������삯�オ���Ă������ƂɂȂ����B���h�n�͓����^���Ɉ��z��s�����V�����^���̑n�o������ɓ���Ă������B
�@�P�X�T�T�T�N�̘Z�S���O��̑S�w�A�^���́A�����h�̔j�Y�A���۔h�̗��Y�Ƃ����ے莖�ۂɒ���ł����B�V�}�����{���H���ɂ��S�w�A�w���́A���������������T�[�r�X�@�֘_����������݁A�퓬�I�����Ƃ��Ă̑S�w�A�^���̓`���ɑ���j��U���ɏo�Ă����B�܂�����ɗ������������̂����{�g���c�L�Y���^���ł���A����ɍ������Ȃ������c���ꂽ�퓬�h���u���g�^����n�o���Ă������ƂɂȂ�B���̓�h���V�����^���Ə̂�����悤�ɂȂ�A����D�萬���悤�ɂ��Ă��̌�̍��h�^�������[�h���Ă������ƂɂȂ�B
�@�Q�O�O�U�D�X�D�Q�P���ĕҏW�@������q |
| �y�S�w�A�������Ăѐ퓬�I�����h����������z |
|
�@����{�v���I���Y��`�ғ������j��́A���̂悤�ɋL���Ă���B
�@���̍��A�w�������Ƃ̐����ӎ��͋ɂ߂Đ�s�ł������B�S�w�A�͂T�O�N����̒Ɏ�A�Z�S���V���b�N���������Đ����I�Ɉ��肵�A�g�D�g��̋C�^���݂Ȃ����Ă����B�S�w�A�̉^�����x���銈���Ƒg�D���锽��w�������͐��m�Ȑ����͕s���ł��邪�A�����Ƃ���疼�ʂ͌��W���Ă����ł��낤�B�����āA�e��w�ɂ͂قƂ�Ǔ����̊w���זE���g�D����Ă����B���̐������_��w�ł͂T�O������P�O�O���͉��炸�A�ǂ�ȑ�w�ł��P�O���ʂ̓����Y�}�������Ď�����A�`�f�A�T�[�N�������w�����Ă����B
�@�w�������Ƃ����́u�Q���Ȃ��v�������͓����ɂ��̓����ł̐����I�����̐i�s���Ă����B�W���ρ\�X���H���������čČ����ꂽ�S�w�A���A�T�V�N�̑���쓬���̑������߂����Ă܂��ŏ��̕������o������B�����n�g���j�~�����͌��n�̔��Γ����̐퓬�I���͑j�~�H���Ƃ����S�����Ŏx�������S�w�A�A�����n�]�A�Љ�}�̗͂ɂ���ď������A�ČR�Ɠ��{���{�͊g���𒆒f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���쓬���͏���������n�����Ƃ��ė��j�̋��������������Ă��B���ɁA���̓����̂Ȃ��ł̊w�������̐퓬�I�Ō��g�I�ȓ����Ԃ�͓��{�����ɒm��n��A�S�w�A�̖����ꋓ�ɂ����߂邱�ƂƂȂ����B
�@�����̗v���̕]�����߂���A�c�����L�ǔh�ƌ��n�w�����h�̑Η������������B�c�����L�ǔh�͋{�����єz���n�߂������}�����̑����ɑ���A�S�w�A�^�������a�I���a�i��^���ɏ]�������߂悤�Ǝ咣���n�߁A���n�w�����́u�J�_�w�v�����ɂ�鐭���I�����̌o�����X�ɋ��߂悤�Ƒ��������B�����͓}�����h�\�S�w�A���L�ǔh���嗬�h�ł��������A���̓��a����`�����͂����ɏ����h�ɓ]��������̌��n������S�����O���[�v���S�w�A�̎嗬���`�����邱�ƂɂȂ�B�������āA�U�O�N�����̑S���A�ɂ܂ŘA��Ȃ�S�w�A���嗬�h������A�����A�_�ˑ�Ȃǂ����_�ɂ��Č`������邢���ۂ��A�嗬�h�͓���𒆐S�ɐ��I�ɂ͈��|�I�����őS�w�A�̃w�Q���j�[���������A�����ɂ�����S�w�A�嗬�h���`�����ꂽ�B
�@�S�w�A�嗬�h�͂P�P�D�P�����̑������߂����Ă��̓����ɐ����I����������͂��߂��B�퓬�I���́A���a�i��^����퓬�I�ɓ��������Ƃ��Ă��A��Ǝ��ݍ���Ȃ��Ƃ����C�����点�n�߂��B����ɁA�����̍j�̘_���Ƃ����ŃX�^�[���j�Y���ւ̕s�M�����������̂点�Ă������B�퓬�I���́A���a�����H�����̂��̂��X�^�[���j�Y���̘g���ɂ��邱�Ƃ��C�Â��n�߂��B
�@�������A����I�Ɏ�̓I�Ɋw�����������ĕ��a�����H�����痣���������͂́A�i�q�̊w�������ւ̉���ł������B�����i���T�V�N�̏����A���{�g���c�L�X�g�A���̑��݂�m���ĘA�����Ƃ�A���ɉ������A���s�Ńg���c�L�X�g�^�����J�n���Ă����B���́A�����}���ɂ����čs�������ɂ��Ă������J�i��A���ɉ��������A���̂��Ƃɂ���ċ��s�̒n�ɍŏ��̃g���c�L�X�g�̊j���`�������B���͋��Y�}���s�{�ψ���̕{�ψ��ƂȂ��Ċw�Ε����̃|�X�g�ɏA���A���傤�ǂT�V�N�̕��a�i�쓬��������Ȃ���A�����{�w�A�̎w�������o�[�ƐڐG�����B���͊w���}�������ɑ��Đ^�������畽�a�������̘_�����d�|�����B�������_��ӐM���Ă����w���w�������o�[�́A���̗��_�ɂ���ĕ��a�������_�������Ȃ��܂łɕ��ӂ���Ă��܂��̂��o�����āA����ɐ��̎咣�̐�������F�߂�悤�ɂȂ��Ă������B
�@�����A���s�̊w���^���̎w�����őS�w�A�����̐��{���܂��͂��߂ɐ��A���J�̍H��ɂ���ăg���c�L�Y���Ɋl�����ꂽ�B���{�͊w�������o�[�̂Ȃ��ōŌÎQ�ł���A���̊w���^�����\���Ă����̂ŁA���{�̊l���̓g���c�L�Y���^���ɂ����Č���I�ɏd�v�ȈӖ����������B���{�͏o�g�̗����ّ�w�̋��Y�}�זE�̒��Ɏ���Ƀg���c�L�Y���̉e�����g�債�Ă����A�����炻�̒��S�����o�[���g���c�L�Y���Ɋl�����Ă������B�����āA�T�V�D�P�Q���̍זE����ł́A�P�P�D�P�̑������߂����ĕ��a�����h�Ƙ_�����A���a�������̌��c���x��������̂������𐧂����B
�@�����ّ�w�w���זE�̕��a�������̌��c�͑S���I�ɂ��擪������t���V�`���t�H���ւ̌��R���锽���̓˔j���ł������B���a�����H���̓X�^�[��������̃t���V�`���t����\�����V���ȃX�^�[���j�Y�������̐��̑��H���̒��S���ł������B�]���āA�����w���}�������̕��a�����H���Ɍ��R�Ɣ��������Ƃ́A�w�������̔�X�^�[�����������I�ɔ�������Ƃ��Ӗ������B�����̍j�̘_���̎����ł͑Η��͖����ꍑ��`�̃R�b�v�̒��̑Η��ł������B���ꂪ���a�������ɂ���ăX�^�[���j�Y���ᔻ�����ۓI�����œW�J����[���ɂ������ƂɂȂ�B
�@�i�q�̉���͂܂����̂悤�ɂ��āA�w���^���̎w�������o�[���������Ă������a�����H���ւ̋^��ɑ��āA�K���I�A�v���I���ꂩ��̔ᔻ�Ƃ��Đ��s����A���s�ɂ����Ă͂��̐��ʂ��m�F���ꂽ�B�����ق̌��c��˔j���Ƃ��āA���s�A���Ő��A���J�A���{��̓��_�̐�������w�������Ƃ����́A�������������悵�Đ��i���Ă����퓬�I���a�����̂��߂̉^�������Ȕᔻ�I�ɑ������Ă������Ƃɂ���ăg���c�L�Y���ɐڋ߂����B
�@���̌X���͂i�q�̉������̓I�ɐ��������������ɂƂǂ܂炸�A�e�n���w�A�ɂ����ċ��ʂ��Č����錻�ۂł������B�e�n���w�A�Ƌ��_������̎w�������o�[�͎��H��ʂ��Ă����Ƃ��[���ɕ��a�i��H���̕ǂɒ��ʂ��Ă����B���a�����ɑ��鍪��I�Ȕᔻ��ʂ��ăX�^�[���j�Y������̗������J�n������������q�ϓI�ɏ�������Ă������B
�@���������̂Ƃ��̊w�������o�[�̃X�^�[���j�Y������̗����͌����Ĉ�l�ɂȂ��Ƃ���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�����ɂ͓����ł������̐����X���ɕ�������Ƃ������ۂ����������B���̕�������̓I�ɓ����̗�ł݂�ƁA�l�̃O���[�v�����肠���Ă������B
| �P |
�S�w�A���L�ǃO���[�v |
�@���R�A�X�c��B���̃O���[�v�͍Ō�܂ŕ��a�����H���Ɏ��������E�h�ł������B���Ȃ݂ɂ����͂U�O�N���ۓ�����A�����ȓ]�����Ƃ��Ă������ƂɂȂ�B |
| �Q |
���勤�Y�}�זE�̎w���� |
�@���A���c�A�x���A�R���ꗝ��B���̃O���[�v�͑S�w�A�^���́g�A�̍ō��w�����h�ł��肩�u���g���������ꂽ�Ƃ��̎w�������`������B���̃O���[�v�͑S�w�A�嗬�h�̂Ƃ��đ�\���Ă����B���܂��A�w�������Ƃ��X�^�[���j�Y�����痣�E���邽�߂̎v�z�I�A���_�I�C�j�V�A�`�u���������琶��Ă��Ă����B |
| �R |
������O���[�v |
�@�A������B�{���̎w��������i�Ⴂ�w�ł���A�U�O�N���ۂɂ����đS�w�A�ƃu���g��������i�q�ɑ�������Ƃ��Z�N�g�I�C�j�V�@�`�u���Ƃ��Ă����̂ł���B |
| �S |
�s�w�A�O���[�v |
�@����A�S�ˁA�y����B���R�A�X�c�畽�a�����h�������Ƃ������ᔻ���A�����s�w�A�Ɉ˂�A�ō��h�Ɉʒu���Ă����B |
�@���A���J�̎w���̂��Ƃɐ��{�͂��̕����𗘗p���Ċe�n��̎w���I�����o�[���g���c�L�Y���֊l������H��������߂��B�����̉���A�S�ˁA�y����A���k�̍����͂����������̐��{����̍H��ɂ���ăg���c�L�Y���ɐڋ߂��Ă������B�T�W�D�T���̑S�w�A��P�P����ɂ́A�i�q�n�̃O���[�v���`�����ꂾ�����B |
|
�@�������́A�u��T�����̂P�A�V�����n���u���g�E�v�����n�S�w�A�̎����v�ɋL���B
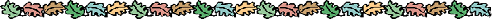



 (���_�D����)
(���_�D����)


![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)