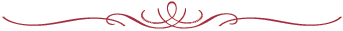
| �����ېV�̎j�I�ߒ��l�i�Q�\�Q�j�i�ɓ��̐����̈�A����c���I������ɓ����ˎE�����܂Łj |
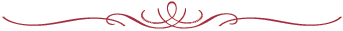
| �P�W�W�X�i�����Q�Q�j�N�̓��� |
| �y���R�}�̎w���҂����������Ɛ��E�ɖ߂�z |
| �@���@���z�ɔ�����͂ɂ���āA������ǂ��Ă����A�܂������ɂ������̑����������A���Ă����B�͖�L���A��䌛���Y�A�����Ȃǎ��R�}�̎w���҂����������Ɛ��E�ɖ߂�A������ׂ����I���̂��߂̏����𐮂��n�߂��B |
| �y���R���t�z |
| �@���c�́A���R�}�Ȃǖ��}�Ƃ̑Ë��Ȃǟ|���l���Ȃ������B���@���z�̗����A���قŊJ���ꂽ�ߎ`��̐ȏ�A�u���{�͏�Ɉ��̕��������A���R�Ƃ��Đ��}�̊O�ɗ����A���������̓��ɋ��炴��ׂ��炸�v�Əq�ׁA�V�R���钴�R��`�̐錾�����Ă����B����ɂ�蒴�R���t�Ɖ]���邱�ƂɂȂ�B �@���c�́A���G�ɑ��锃���A�������݂�}�����B�哯�c���^���̎句�҂ł������㓡�ۓ�Y�ɒ��M��b�̈֎q��^���ĉ^�����̂�h�邪�������A��������̖��}�������i�}�̑�G�d�M���O����b�Ɍ}���ď�������Ƃɂ����点���B�Ă̒�A���}���Ɏ��R�}�͎l���ܗA�Ăѓ��`�Ɋׂ����B |
| �y��G�O���̐��ʁz |
| �@�U���A��G�O���́A�������{�n�܂��Ĉȗ��̕����������L�V�R�Ƃ̊Ԃɒ������邱�Ƃɐ��������B��G�O���̐��ʂł������B��G�O���͂��̗]��������ăA�����J�A�C�M���X�Ȃlj��ėƂ̏������A�V��������Ƃɂ̂肾�����B�������A���̓��e�Ɂu�O���l�ٔ����̔C�p�v�̏����������Ă������Ƃ��A����̕����̓I�ƂȂ����B�����A���}�̒����犪���N���������Θ_�́A������X�ɓV�c�Ƌ{���ɔ�щ��邱�ƂɂȂ����B�t���ł��R�p�A�㓡������ɔ������B��ނȂ�������ڑO�ɂ��ĐV���͔j��������Ȃ����ƂɂȂ����B �@�P�O�D�P�W���A��G�O���́A�A�r��_���Ă̐N�ɂ��v���ɂ��Б����������B |
| �y���c���t�����z |
| �@���c�́A���Ǎ����̐ӔC���Ƃ��đS�t���̎��\���O������b�ɕ�悷�邪�A�V�c�͍��c�̎��\���̂ݍ̔[���Ă��Ƃ͂��ׂċp�����A�O�������ėՎ��̑�����b���炵�߂��i������O���b����t�j�B �@�P�Q�D�Q�S���A������b�R�p�L���ɑ喽�~�������B�O�����t�͒��p���̖�ڂ��I���A�ސw�����B |
| �y��R��A�R�p���t�z�i��R��F��ꎟ�R�p�L�����t�i�C�F1889.12-1891.5�j�j |
| �@�P�Q�D�Q�S���A�O��ڂƂȂ�R�p���t���g�t���ꂽ�i�P�W�W�X�D�P�Q�D�Q�S�`�P�W�X�P�D�T�D�T�j�B�R�p�́A�u���̕��فv�Ǝ��Ȃ�]�������A���̎��͘S�łȌ��͎�`�ҁA������`�҂ł������B���t�̎�v�|�X�g�́A���ς�炸�F���E���B�̏o�g�҂ɂ���Čł߂��Ă����B�ɓ��������M���@�c���A���������`���呠��b�B���R��b�E��R�@�ށA�C�R��b�E�����]���B |
| �y�g��_�{�n���z |
|
�@����22�N(1889)�A�����V�c���ޗnj��g�쒬�Ɍ���V�c���J��u�g��_�{�v(�悵�̂���)��n���B�Гa�͏��a7�N(1932)�̉��z�Ŗ{�a��q�a�ȂǑS�Ğw����A�����ɂ͌��������̍I�b�V�l���J��ێЂR�Ђ�����A�g���_�Ђ���ڂ��ꂽ�V�c���͌㑺��V�c�����������̂Ɠ`�����Ă���B�c�̂��{����
�ĉz�̑��P�Q�w �`
�@��������ł��B
|
| �P�W�X�O�i�����Q�R�j�N�̓��� |
| �y���C�R�����剉�K�z |
| �@�R���A��P�C�R�����剉�K���A�m��������тōs��ꂽ�B�N������G�R�𗤊C���ʂŌ}�����Ƃ����ݒ�̉��A�����V�c�����c�ɑ�{�c���\�����B |
| �y���I���z |
|
�@�V���A����{�鍑���@�̌��z�̍ہA�P�N��ɑ��I�������{���A�c����J�݂��邱�Ƃ��閾���ꂽ�B�I�����́A�O�c�@�ł͒��ڍ��łP�T�~�ȏ��[�߂�Q�T�Έȏ�̒j�q�Ɍ��肳��Ă����B���̂��߁A�n���U�O�O�~�ȏ�̓y�n�������Ă���n��i�c����Q���R���V���ȏ�j���N���P�O�O�O�~�ȏ����鍂�����������͕x�T�w���ΏۂƂȂ����B�i�����̎��i���A���ɔ[�߂�ŋ����P�T�~�ȏ�̂R�O�Έȏ�̒j�q�j�B�����̓��{�̑S�l���͖}���S�O�O�O���l�A���̂����L���҂͂S�T���l�i�S�T���R�S�V�S�l�j�A�l���̋͂��P�D�P�R�Q���ɉ߂��Ȃ������B �@���I���̓��[���͂X�Q���B�I�����i�̂Ȃ��҂܂ŊS�������A�e�n�̉�����ɒ��O���l�ߊ|�����Ɖ]���Ă���B �@���I���̌��ʂ́A���R�����^�����x���Ă����_���R�}�Ƒ�G���i�}�̈����B�O�c�@�R�O�O�c�Ȃ̂����A�m���͂P�O�X���A�����P�X�P���B�}�h�ʂ̓���́A���}�̗������R�}���P�R�T�c�ȁA�������i�}���S�R�c�ȁA���킹�ĂP�V�W�c�ȂƂR���̂Q�߂����{���͂���߂邱�ƂɂȂ����B���R�̎R���L�����{�X�Ƃ���˔����{�n�̑听��V�X�A�����n�̍������R�}���T�A���̑��������S�T�B �@���i�}�ł́A����s�Y�i�R�Q�E�O�d�I�o�j�A���{�B�i�R�T�E���R�I�o�j�A�c�������i�S�X�E�ȖؑI�o�j�A���R�}�ł́A���]�����i�S�Q�E���I�o�j�A�A�؎}���i�R�R�E���m�I�o�j�B���m���ł́A�P�悪�g�c�̎����E�|���j�A�Q�悪�їL���ƕЉ����g�A�R�悪�A�؎}����4�c�ȑS�Ă����R�}���Ɛ肷��Ƃ������|�I�����������Ă����B |
| �y����鍑�c��z |
| �@�P�P���A�R�p���A�V�c�̖��̂��Ƃɑ�P��鍑�c������W�����B�c��̊J��Ƌ��ɖ������@�����{�Ɉڂ���A�ȍ~���{�͌������ɓ���B�鍑�c��O�c�@�ɏW�܂�����c�m�͂R�O�O���B�J�@���̓��̓���J�̋c�������ӂł͐����̌Q�W�������Ɉ��A��j���Ə������M�C�����ł��グ���A�c����j�������̔M�C�����͂B���̃j���[�X�͐��E�ɑœd����A�Ⴆ��C���X�g���C�e�b�h�E�����h���E�j���[�X��ł́A���N�i���R�j�̍����~�J�h�i�V�c�j�̍��ɑ����ĊJ���ꂽ�c�ƕ��Ă���B�����ېV�ȗ��Q�O�N�]��A�ߑ㉻���}�s�b�`�Ői�߂Ă������{�́A���ɉ��Ă̋c��x��������A�A�W�A�ōŏ��̋c��J�Âɑ��������邱�Ƃɐ��������B �@���鍑�c��ɋc�Ȃ��߂��̂́A���R�}�n�P�R�O���A���i�}�n�S�P���A���{�n���S�P���A�����T���A�������S�T���ł���B���{�̗͂����炩�ł��������A�R�p�͐��{���͂ł��̗������߂����Ƃ���B �@����J�ݎ��̎��R�����̃��[�_�[�͔_�ޏ��Ƒ�G�d�M�ł������B�_�͏O�c�@�ł͂Ȃ��A�M���@�Ƃ��ĎQ�����Ă����B�O�c�@�ɋc�Ȃ������Ȃ��A����A���ĂȂ��_�A����ɂ́A�������Ǝ��́u���i�}�v������Ė�}�Ƃ��ĉ^�����Ă����u��G�d�M�v�����݈ʂ�Ⴂ�A�c��ɎQ�������B���́A��l�́u���}�v�����Ƃ��A�ޓ����g�A�����ɂ��R�����Ȃ��ŋc��ɎQ�����Ă����B |
| �y�R�p�̕x���������\�Z�Ă�����ĕ����z |
| �@�R�p�̏��̎{�����j�������ׂ���A���̎��T�v����{�̍��y�ƓƗ�����邽�߂ɂ́A���{�����ł͂Ȃ��A�A�W�A���Ӓn��ł̌R���I�e���͂̍s�g���K�v�ł���Ƃ��āA���C�R�ɋ���ȗ\�Z�������Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ƌ������A���{�͂W�W�O�O���~�̖c���\�Z�Ă��o���Ă����B���̕x��������ɁA�c��^�������甽���Η����邱�ƂɂȂ�B�A�؎}����́A�c��Ǝ��̗\�Z�Ă����A���{�ĂɂW�O�O���~�̍팸�ƁA�d�łɋꂵ�ޔ_���̂Q�O�����ňĂ�ł��o�����B�X�ɁA���]�������A���{�Ƌc��͑Γ��ł���ׂ����Ǝ咣���A���@�U�V���̖@����̕s����˂��ēO��I�ɍR�킵�悤�Ƃ����B �@�������ė\�Z�Ă����_�ƂȂ�A�c��͂̂�������r�ꂽ�B�R�p�L����ꎟ���t�Ƌc��̖��}���͌������Ό������B���{�͖����ȗ��̋��Ђł��������V�A�̓쉺��h���ׂ��C�R�����𐄐i����ӎu����������A���}���́u���͂̋x�{�v��W�Ԃ����B���҂͝h�R���A�c��͂قƂ���P�������B���{�Ƃ��Ă͉��U�Ƃ������̎�����������A���m���̋c������U�Ƃ������ʂŏI��点�邱�Ƃ͊O�ʓI�ɂ�낵���炸�Ƃ������f�������ĉ��̎�͈Њd�Ƃ��ĈȊO���ǎg���Ȃ��܂܁A�c���͈ꎞ���f�ƂȂ����B���ǁA�@�R�p���\�Z�팸�ƍs�����v����Đ܂荇�����E�����B �@���������̗��ŁA���{�Ɩ��}�̊ԂőË��H�삪������ł����B�R�p�͓y���h�̊t�����g���āA�������R�}�̓y���h�Ɍ����d�|�����B�܂��A�C�����ɏ������Ă����O�����������@�����A�傢�ɗ͂������B���R�}�ł͒|���j�i��̊O�����E�g�c�̎����j�Ȃǂ�����ɑΉ��A����\�Z�Ă͑啝�ɏC���������D�ŏO�c�@��ʉ߂����B���Ȃ݂ɐ��̎��R�}���ًg�c�͔_�̑��߁E�|���j�̎��q�ŁA�_�Ɠ������m���̏o�g�ł���A�_��̎��R�}�̌����́A�g�c���o�Č��݂̎����}�ɂ������Ă���B |
| �@���̎��̖����̔˔��u�r���}�̑Η��́A�吳�E���a�̊����h�u�r�}�l�h�̑Η��ւƈ����p����Ă����B���̎��̎��R�}�Ɖ��i�}�̑Η��͋}�i�h�Ή����h�̑Η��Ƃ��ďh�A�̔@������܂������p����Ă����B�܂�́A���̎����ꂽ���^�����{�����j�̌����ƂȂ��Ă����B |
| �y�u����j�փX������v���z�z | |||||||||
|
�@�P�W�X�O�i�����Q�R�j�D�P�O�D�R�O���A�R�p�L�����t�́A�u����j�փX������v�i�ʏ́u���璺��v�A�p: Imperial
Rescript on
Education�j��V�c�̒���`���Ŕ��z�����B�����Ɋւ��@�߁E�����ł͂Ȃ��A�V�c���g�̌��t�Ƃ����Ӗ���������A�V�c���g�̏����������L����A������b�̏����͕�������Ă��Ȃ��B���z�̌�ɂ́A���{�̂��ׂĂ̊w�Z�ɉ����i�z�z�j����A���̌�̋��琧�x�̍������Ȃ����ƂɂȂ����B
�@�����P�T�N�̌R�l���@�A�����Q�Q�N�̑���{�����@�A�����Q�R�N�̋��璺��̎O�T���������{�̃C�f�I���M�[�ƂȂ�A�傫�Ȃ������傤��ς��Ă������ƂɂȂ�B �@���ẮA�ɓ������̉��ő���{�鍑���@�E�c���T�͂̋N���ɂ����������t�@���ǒ����̈��B�i���킵�j�Ɛ����ږ⊯�ɂ��Ď��u�i�������A�V�c�E���{�ɏ����u�������E�j�̌��c�i�t�i�Ȃ����ˁj�ɂ���ċN�����ꂽ�B�V�c�e���_�҂Ƃ��Ēm���Ă������c�i�t�́A�����ېV��̐������̗���Ɋ�@��������A���{�×����̓`���I���_�̊m���̕K�v���o�����B�����V�c�ɐi�������Ƃ���A���B�ƌ��c���C�ɏA�����ƂɂȂ����B �@�u���璺��v�̌������쐬���ꂽ���A���B�͋��璺�ꂪ�v�z��@���̎��R��N���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��d�����A���Č��c�i�t�͍��Ɛ_���I�ȋ��T�Ƃ��邱�Ƃ��d�����A���������Ƃ���Ă���B�ŏI�I�ɁA����ւ̍F�s��v�w�̘a���A���@���_�A���F�A�ߋ`�A�����A�`�E�S�ȂǂP�Q�̓��ڂ�b���̏����Ƃ��A�V�c�������������|�Ƃ��邱�Ƃ��r���A�b��������ɕ키�`���ł܂Ƃ߂��邱�ƂɂȂ����B �@������b���������]�́A���璺�ꂪ�]��ɂ����ƒ��S��`�ɕ�߂��āu���ێЉ�ɂ�������{�b���i�����j�̖����v�ȂǂɐG��Ă��Ȃ��Ƃ����_�Ȃǂ���Ԃݑ�璺����N�������B�A���A�������̑�b�ޔC�ɂ��������Ȃ������Ƃ���Ă���B �@���z���N�̂P�W�X�P�i�����Q�S�j�N�A�����ӎO�ɂ�鋳�璺��q�狑�ہi�s�h�����j�����������ɁA��Ɏ�舵���|�̌P�߂�������ꂽ�B���N�A���w�Z�j����Փ��V���K��i�����Q�S�N�����ȗߑ�S���j��A�P�X�O�O�i�����R�R�j�N�ɒ�߂�ꂽ���w�Z�ߎ{�s�K���i�����R�R�N�����ȗߑ�P�S���j�Ȃǂɂ��A�w�Z�ȂǂŎ��T������ꍇ�ɂ͕�ǁi�N�ǁj����邱�ƂƂȂ����B�P�X�O�V�i�����S�O�j�N�ɂ́A�s�����p��ɖ|�A���̂ق��̌���ɂ����X�Ɩ|�ꂽ�B �@���a����ɓ���ƍ�������̎v�z�I��b�Ƃ��Đ_�������ꂽ�B���璺��z���A�V�c�c�@�̐^�e�i�ʐ^�j�ƂƂ��Ɋe�w�Z�̕���a�E����ɂȂǂƌĂ����ʂȏꏊ�ɕۊǂ��ꂽ�B���k�ɂ́A���璺��̕��͂����u���邱�Ƃ��������߂�ꂽ�B���ɐ푈�����̒��ɂ����āA�P�X�R�W�i���a�P�R�j�N�����Ƒ������@�i���a�P�R�N�@����T�T���j������E�{�s�����ƁA���璺��́u�R�l���@�v�A�����v�z�ƂƂ��ɓV�c�����ƃC�f�I���M�[�̎x���Ƃ��ė��p���ꂽ�B �@�哌���푈��A�A�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ� (GHQ/SCAP)�����璺����莋�������ׁA�P�X�S�U�i���a�Q�P�j�N�A�����Ȃ͕�ǁi�N�ǁj�Ɛ_���I�Ȏ�舵�����s��Ȃ����ƂƂ����B�P�X�S�V�i���a�Q�Q�j�D�R�D�R�P���������{�@�̐���ɂ���ċ��璺��̓��e���ے肳�ꂽ�B �@���̌�P�X�S�W�i���a�Q�R�j�D�U�D�P�X���ɁA�O�c�@�Łu���璺�ꓙ�r���Ɋւ��錈�c�v�A�Q�c�@�ł́u���璺�ꓙ�̎����m�F�Ɋւ��錈�c�v�ɂ��A�u���{�I���O���匠�N���тɐ_�b�I���̊ςɊ�Â��Ă��鎖���́A��{�I�l���Ȃ��A���ېM�`�ɑ��ċ^�_���c�����̂ƂȂ�v�Ƃ��āA�u�R�l���@�v�A�u��\�ُ��v�A�u�N�w�k�Ɏ���肽�钺��v�ƂƂ��ɔr���E�������m�F���ꂽ�B �@���璺��̌����͎��̒ʂ�B�i���i�͂�������㕶�A���i�͂�������㕶��j
|
|||||||||
|
|||||||||
| �y�R�p���t�����E�z |
| �@���̓��t�̑������Ă��邠�����A�ɓ������͊t�O����R�p�ɑ��ċc����@�Ƃ��Ă���߂ċ������ʎw�����������A���ǎR�p�͂����p���邱�ƂȂ��܂܁A�����E�����B�A���A�R�p�͂��̌���e���͂��s�g�������邱�ƂɂȂ�B |
| �@�W��y���Ж@����i�W����W�����j�B |
| �y�����_�{�n���z |
|
�@�ޗnj������s�A�����_�{�B�����Q�R�N�n���B
�@�����Q�Q�N�A�_���V�c��炢�A�n�����ԗL�u��芀���{���ɐ_�Бn���̐��肪�N����A�����V�c�͂�����ς��c�тɂȂ��A���s�䏊�̓�������{�a�A�_�Óa��q�a�Ƃ��ĉ������ꂽ�B�~�n�i�{��j�͍b�q������̖�P�R���̑傫���i��T�R�������u�j�B�{��͐M�̐X�Ƃ��Ď���Ă���B���a�P�T�N�ɋ{��g���������s��ꂽ�ۂɁA��V���U��{�̎����A�����ꂽ�B
|
| �P�W�X�P�i�����Q�S�j�N�̓��� |
| �y���R�}�̕���z |
|
�@���R�}�́A�c���ŎO�H���ɕ����ꂽ�B�@�E�d�h�i���]������j�A�A�E��������h�i�_�ޏ��A�A�؎}����y���h�̘H���j�A�B�E�鍑�z�e���h�i���ԓ�h�j�B�c��n�܂��ĊԂ��Ȃ����̎����A���R�}���͢�l���ܗ���̕���̊�@�Ɋׂ����B �@�P�D�P�X���A���R�}�̐��݂̐e�_�ޏ����A�ˑR�A�}�𗣂��Ɠ}�@�֎��̢���R�V����ɔ��\�B �@���Q�D�Q�O���A���R�}�y���h�����{���ɐQ�Ԃ�A���̌��ʁA���{�Ď^���P�R�T���A���P�O�W���ƂȂ�A�Ë��I�ȗ\�Z�Ă����������B����͓����̐��{�\�Z�Ă��U�T�O���~���팸���A�P�V���̌��ō�Ƃ����ܒ��ƂȂ��Ă����B �@���]�������̎��R�}�d�h���s�k�����B���Q�D�Q�P���A���]�͋c�������E�����B�ȍ~��x�Ɛ����̕���ɖ߂낤�Ƃ͂��Ȃ������B |
| �@���]���� �@�P�W�S�V�E�O���S�|�P�X�O�P�E�����R�S�B�y���ˏo�g�B�t�����X���w��A�����O��w�Z���ɏA�C���邪�A������O���l�o�d�ⓚ��ɂ�薾�����{�̕ۈ��Ǖ����������B���̌�A���_�V���Ⓦ�����R�V���Ŕ˔����{�ւ̍R�c������W�J�B���I���ɗ�������}����o�n�����I�B���}���̐Ǝ�i�������Ⴍ�j����c�������C�B��ɐV���̔����A�����}�̌����Ȃǂ�ʂ��āA���R�����^���̌[�ւɓw�߁A���m�̃��\�[�Ə̂��ꂽ�B |
| �@�A�؎}�� �@�P�W�T�V�E�����S�|�P�W�X�Q�E�����Q�T�B�y���ˏo�g�B����@�g��̌[�֎v�z�̉e�����Ĕ_�ޏ��̗��u�Ђɓ���A���R�����v�z�E���_�̎w���҂̈�l�Ƃ��Ċ����B���I���ɓ��I�B�������{�̐ꐧ�ɐl����`�̗��ꂩ�甽�Ί������s���A��������R�_��ȂǑ����̒����������Ă���B�P�W�X�Q�i�����Q�T�j�D�P�D�Q�R���A�A�؎}���͂R�T�̎Ⴓ�Ő����B |
| �y�z�Ŗ��ɂ��Ă̓c�������̓��t�ɑ��鎿�⏑�A���≉���z |
| �@�c�������́A1891�i����24�j�N�ȗ��T��ڂ�1897�i����30�j�N2���̍z�Ŗ��ɂ��Ă̗^�}���t�ɑ��鎿��ł���B���̎���Ɏ����ŁA3����2�ق𑣂������̌�A���{�̓��ُ����o����邪�A����ɔ[�������A�����ēx����ɗ��B���̌�A���{�͑������R�z�Œ�����̐V�݂\����Ɏ���i�эK�Y�j�B�c����������v�ɗL�Q���i�Ƃ��~������V�ɕt���⏑���]�ڂ��Ă����B �i�⑫�A�ʏ́y�c�������̑����z�Ŏ������������l�z�̢�c�������̑������R�z�Ŗ��ɂ��Ă̎��^��j�@ |
| �y��S��A�������t�z�i��S��F��ꎟ�������`���t�i�C�F1891.5-1892.8�j�j |
| �@�T�D�U���A�l��ڂƂȂ��ꎟ�������t���g�t���ꂽ�i�P�W�X�P�D�T�D�U�`�P�W�X�Q�D�W�D�W�j�B��ꎟ�R�p�L�����t�̓|���A�g�t�̑喽���~�������͎̂F�h�̗̑��ō����Ƃ̏������`�ł������B�{�������͎̍��ɒ������Ƃ�~���Ȃ��������A�ɓ������ƎR�p�L���̋������߂ɂ����ċ��ۂ��o���Ȃ������B���������Ă��̓��t�ɂ́u�����v�Ƃ��Ĉɓ��A�R�p�̎p�������܌����邱�ƂɂȂ�B �@���ڂ����l���Ƃ��āA�F�h�̏������`�A�����]���B�_������b�ɗ����@���A���M��b�E�㓡�ۓ�Y�B���R��b�E��R�ށA�C�R��b�E���R���I�B �@�����̓��t�����́A�F���F���ɘa���邽�߂Ɉɓ����Ђ˂�o��������ł���B�����ɍ���̑�؋��C���A�@���ɔ����̓c���s���A�����ĊO���Ɍ����b�̉|�{���g�𐘂��Ē����F��Z�����悤�Ƃ������A����͋p���Ċt���̔˔����́i���Ȃ킿�A�C���E���R�A�����E�����A�����E�i��j�̔��������ƂɂȂ�B���{�͂����ɓ���A�ɓ�������ɕ���đ��c��̂͂��܂�܂��A�̋��R���ɋA�����Ă��܂��Ă���B
�@�P�P�D�Q�U���A�O�c�@���K�J����B�������{�́A�x����������Ɋ�Â��\�Z�Ă��o�����B���ӌ��Ԃ̈ɓ������������Ƃ̐��{�́A�c��ɑ��Č����������H��������Ă���B���{�}�i���}�j�͎^���������A���}�i���R�}�A���i�}�j���D�����߂Ă���A�u���͋x�{�v������ɍΏo�\�Z�z�̂P�����i��W�X�Q���~�j�̍Ώo�팸���������B �@�O�c�@�\�Z�ψ���ɂ����ĊC�R��팸���ꂽ�̂ɕ��������R�C���́A�u���N�͎F�����{�ȂǂƔl����A�䂪�������̗��^�𗈂�����͎F�����{�̂��A�ɂ��炴�邩�v�Ɠ{�������i�u�ؗE�����v�j�B�c��̕����͒��_�ɒB���A�������{�͓V�c�ɏ�t���čىA�P�Q�D�Q�T���A���t�͋c����U�ɓ��ݐ����B �@���{�͂��̗���ׂ����I���ɑ��A�励�������Ȃ����B�����V�c�́u�����v�������o���i����Y�����[�������p���Y�x�ۋǒ���ӔC�҂Ƃ��āA�{���m���������Ė��}���҂̗��I�^����W�J�����B�A���A�I�����ʂ́A���}���������A�������{�̖ژ_�ׂ݂͒����B�ɓ��͂��̌��ʂɐ�]���A�����@�c�������E���A�i����������E�����B �@�ɓ��͂��̏�ŊJ���邽�߂ɂ͎��琭�}�g�D���s�������Ȃ��Ɗm�M�����B�������A����͓V�c�Ɉԗ�����A��ڍ��ɋA���邱�ƂɂȂ�B�t���̗����_�������Ȃǂ��ق��Ă͋��炸�A�c��͐��{��Njy���A�T�D�P�P���A�M���@�͐��{�e�N���c�Ă��W�W�U�W�ʼn����A�T�D�P�T���A�O�c�@�ً͋}���c�Ő��{�e�N�Ă��o���A�P�T�S�P�P�P�̑卷�ʼn������B �@���ɏ������t�͕i����������E����������b����p����B����ł��܂荇���͂����A���Ǒ����E���������邱�ƂɂȂ�B�̐S�̂Q�T�N�x�\�Z�ẮA�O�c�@�ƋM���@���Η��������̖̂����V�c�̒��قɂ���Đ��������B |
| �y�鐭���V�A�ɓ��e���֎n���J�n�A��Î����z |
| �@�P�W�X�P�N�A�鐭���V�A�A�V�x���A�S���v��̒��H���J�n�����B���V�A�c���q�E�j�R���C�Q���́A�V�x���A�S���̋N�H���̓r���ɋɓ����@�����˂ė����A��ÂŌx���ɓ����Ă����Óc�O�������Ɏa��t������Ƃ������Q�������������Ă���B �@�����A�R�c���`�i�����悵�j�i�@��b�琭�{��]�́A���ƐӔC�Ƃ��ĔƐl�����Y�ɂ��ׂ��Ƃ��čٔ����Ɉ��͂��������B�Ƃ��낪�A�Y�@�㕉�����x�ł͎��Y�ɂł��Ȃ��������ƂƁA�O���̍c���ɑ����Q�ӔC�̋K�肪�����Ă����ꗶ���邱�ƂƂȂ����B�����Ҍ���R�@���i���݂̍ō��ْ����j�́A�@���̊g����߂����݁A���{�̗v�����t���Ȃ������B |
| �y�����z�Ŏ����̎n�܂�z |
| �@�P�X�Q�S�N�A�֓��k���n���łP�X�Q�P�N�ɑ����Ă��̔N����^�����������A�n����A�������т������z�R����y�o����z�łɂ���ēc���ɔ�Q�����������B�P�W�V�V�N�A�É͍z�Ƃ��������R�Ŗ{�i���Ƃ��n�߂Ĉȗ��A�n���쉈�݂ł͔_�앨�̗����͂�Ȃǂ��������ł����B�n��̔�Q���ꓯ���A�A����Y���Đ��{�ɒQ�菑���o�����B�H���A�u���₩�ɍz�ŏ��Q�̓����u����B�����炸��ΔJ�뒼���ɍz�Ƃ��~�����߂�v�Ɨv�]���Ă����B �@�c�������́A�u�������R�z�ʼn��Q�̋V�ɕt�����⏑�v������ɒ�o���A���{�̓��ق����߂��B����ɂ�莖�������ɂȂ����B����͎������������U�����ׁA���{���ق��o���ꂽ�̂͌�ɂȂ邪�A�T�v�u��Q�̌����m���Ȃ炸�B�����������Ȃ�B��w�z���̗��o�h�~�̏������Ȃ���v�Ƃ̓T�^�I�Ȋ������ق��ׂ��ꂽ�B�i�u�J�����ŖS�j�v�Q�Ɓj |
| �y�����ӎO�s�h�����z | ||||
| �@�u�����ӎO�s�h�����v�B | ||||
�@�u�����̃��[�c�����������v�́u���������ߗ������v�����̂悤�ɋL���Ă���B
|
| �P�W�X�Q�i�����Q�T�j�N�̓��� |
| �y��T��A��ɓ����t�z�i��T��F��ɓ��������t�i�C�F1892.8-1896.8�j�j�A���{�c���E���c�����b����t�i�C�F1896.8-1896.9�j |
| �@�P�W�X�Q�i�����Q�T�j�D�Q�D�P�T���A��Q��O�c�@�I���B�ۈ����œ�����ǂ��A�o�ŏ��ᔽ�œ�������Ă��������͎ߕ�����㒼���Ɏ���̏O�c�@�c���A�C������Ƃ��ēȖؑI���悩��o�n�A���I�B�ɓ����t�̊O���E�����@���̍H��ɂ�����ǂ���Q��ڋc���ɑI���B �@�P�W�X�Q�i�����Q�T�j�D�W�D�W���A�T��ڂƂȂ��Q���ɓ����t���g�t���ꂽ�i�P�W�X�P�D�W�D�W�`�P�W�X�U�D�W�D�R�P�j�B�ɓ��\���]�\�R�p�L���B�O����b�ɗ����@���A�_������b�E�㓡�ۓ�Y�A���M��b�E���c�����B���R��b�E��R�ށA�C�R��b�E�m��i�́B �@�ɓ������́A�R�p�A�����̓���t�ɂ����鑤�ʎw���Ɏ��s���A����͔͓I�ȁu�c���p�v����l����K�v�ɔ���ꂽ�B�ɓ��͊��ɒ��R��`��W�Ԃ��錳�V�̈���ł���A���V����̎x���������t����K�v���������B�����ŁA�R�p�̓��t���������A�a�X�����������B�������āA��ɓ����t�́A���V�Ƌc��̗����𑀂�Ƃ����Ȍ|������~���Ă������ƂɂȂ����B �@�������A�c��c�͍��������߂��B��S�c��ɂ����āA�ɓ��́A���}�̎x�������t����ׂ��w�͂������A�B�R�p���t�ȗ��h�_���r�߂Ă���c��͐��{�̌������ƂȂǕ����������ʁA�Ƃ���ɉ��i�}�𒆐S�Ƃ��ē��t�s�M�C���o����Ɏ������B�R�p��M���Ƃ��钴�R��`�҂����͂�������т��A�c��Ƃ̍R����[�߂悤�Ƃ����B�ɓ��͂��̔��݂�������邽�߂ɏْ��ɗ��炴��Ȃ��������i�ْ�����j�A�����ɓV�c�̐M�C�Ă���ɓ��Ƃ����ǂ��A���т��т��̈З͂��s�g���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B �@�������āA������T�c��i�P�W�X�R�D�P�P�D�Q�W�[�P�Q�D�R�O�j�A��Z�c��i�P�W�X�S�D�T�D�P�T�[�U�D�Q�j�͉��U�Ɏ������U�őΉ������B�ɓ��́A�q�����̈ɓ����㎡���t���L�������g���Ď��R�}�Ƃ̗Z�a�ɓw�߁A���R�}��P�Q�O�c�Ȃɖ������R�O�c�Ȃ��ċc��ߔ����𐧂��悤�Ƃ����B���}�ŁA�����{�̋}��N�ł�����i�}��莩�R�}�ɐڋ߂̃`�����X������Ɠ��B���{�Ǝ��R�}�ڋ߂̑f�n�����X�ƒz���グ���Ă������B�s�������A�������A���ŁA�C�R�g�����s���B |
| �y�O���E�����@���z |
| �@�����@���i�P�W�S�S�`�P�W�X�V�j�͘a�̎R�ˎm�ɒB����Y�@�L�̂U�j�B��{���n�̓��{�ϊv�ɖ������T�R�В��A�C�����ɎQ������B���n�ɂ��̍˔\�A���ɏ��˂������]������A�u��{�����łȂ��Ă��H���čs����͉̂��Ɨ����̂݁v�ƕ]����Ă���B���n�ÎE�̂��点�����Ƃ��A�ÎE���w�������Ƃ݂���l�����̏h�Ɏa�荞��ł���Ƃ̃G�s�\�[�h�����B �@�Q�U�̂Ƃ��ɕ��Ɍ��m���ƂȂ���A��C�푈�Ɍ��ŁA�ސE���A�o�g�n�ł���a�̎R�˂ɖ߂�A�R�����v�ɓw�߂��B�����A�p�˒u�����Ȃ�������A�����̍�����a�̎R�˕����A���{��̋ߑ㉻���ꂽ�R���ɂȂ��Ă������낤�Ƃ����Ă���B �@�����́A�F���h���̐ꐧ�����ɔᔻ�I�ł����B�ނ͓y�����ɗF�B�������������߁A����푈�̍ہA�_�ޏ��痧�u�Ђ̃����o�[�̋����v��ɎQ�������Ƃ��ē����T�N�̌Y���Ă���B �@�P�W�W�R�i�����P�U�j�N�͖Ƃɂ��o�����A���N�ԃ��[���b�p�����A��S�s���Ɍ��@���w�ԁB�A����͊O���Ȃɓ���B���̌㒓�Č��g�A�R�����t�_������b�A�O�c�@�c���A�ɓ����t�O����b�Ȃǂ��C���A�����푈�O��̍���ȊO���ɂ�����B�����A�������Ɏ��g�݁A���O���G�d�M�����܂��Ă������ߒ��͂��I�m�ɍ��ۏ��ǂݎ��B�P�X���I�㔼����n�܂�����p�鍑�ƒ鐭���V�A�̃O���[�g����[�X�́A�ɓ��ɂ����ĐV���ȓW�J�������n�߂����Ƃ���A��p�鍑�͎����̓��m�̌��v����邽�߂ɁA���{�̐헪�I���l�𗘗p����ɈႢ�Ȃ��ƌ������B���̎�r�ɂ���āA�C�M���X�Ƃ̕s�����������E���O�@���P�p�𐬌������A�Ɨ������{�Ƃ��Ă̗�����l�����A���̋��������Ƃɓ����푈���O��ʂ���x������B���ꂪ�A�����闤���O���ł���A�ނ͖�������̑�\�I�ȊO�����ƌ����Ă���B �@������̍������_�̕���ɔY�܂��ꂽ�B�����́A��������̑I���̐�����ē��I�����A������l�̋c���t���������B�����͐����ɂ�����_���ɁA�O����͎������܂Ȃ��Ƃ�����p�鍑�c��̗ǎ����A���{�̍���ɂ͊��҂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ�m���Ă����B���{�Ăɂ��ẮA�Ȃ�ł����Ƃ�����}�̗��ꂪ�A���ʓI�ɂ͍��v�Ȃ��Ƃ�������A�������̂���܂ł̉ߒ��Ŕނ͌��Ă��Ă����B�u���ǂ��v�Ƃ����ςݏd�˂ł͂Ȃ��A���I�Ȋ��S��`�ł����ĊO���҂̊�����W���邾���łȂ��A�\���̉肳���E��ł��܂���}��A���������������W���[�i���Y���ɑ��ė����͌������i�Ƃ����������̊��j�������Ă����B�����ɂ��Ă��A�F���h���̐����̃^���C�ƁA���̐���̕肩��A��}��W���[�i���Y���������{�I�ɁA�ُ�ɓ����Ƃ������Ƃ�������Ȃ��ł͂Ȃ������B�������g���t���ɂ����āA�F�����̉e�����Ă����̂ŁA�����ł���Y���Ă����B |
| �P�W�X�R�i�����Q�U�j�N�̓��� |
| �P�W�X�S�i�����Q�V�j�N�̓��� |
| �y���w�}�̗��z |
| �@���̍��A���N�����̑Η����������A�̃A�W�A�N���ɑR���Ē��N�ւ̐i�o���͂�����{�ƁC���N���Ƃ݂Ȃ����Ƃ̑Η�������I�ǖʂɊׂ����B���N�����ł́A���ɂ���鐨�́i����}�j�Ɠ��{�Ƃނ���ŋߑ㉻���͂��낤�Ƃ��鐨�́i�Ɨ��}�j�Ƃ��Η������B �@�P�W�X�S�D�Q���A���N�Ŕ_���̔����ł��铌�w�}�̗��i�b�ߔ_���푈�j��������B���̓��w�}�Ƃ����̂́A�E�����E�����̎O�̏@�����������킹�����̂ŁA���w�Ƃ����@���̂��Ɠ����Ꝅ��������Ă����܂����B �@���N���{�́A�W�O�O���̕��ł����Ē������悤�Ƃ����̂����A���w�}���ɕԂ蓢���ɂ����B���w�}�͒��N���{�R�����т��єj��A�U�D�Q���A���ɒ��N���{�͍����ŋN���������w�}�̗�����߂邽�߂ɁA�@�卑�����R�̔h����v�������B�����́A��X�Ȃ�͂��P�O���Œ������Č�����A�ƍ��ꂵ�A���N���{�ɏo����v���������B�����͐�Ɍ��߂��u�����V�Ï��v�����āA�ƒf�Œ��N�ɔh������B���ł́A�o���̍ۂɂ́A�O�����đ��荑�ɕ����ŒʒB����ւ��Ƃ������̂ɁA���f�Œ��N�ւƏo�������B �@�u�����v�Ɛ�㑀�Z�͋������̕ی�𖼖ڂɏo�����h���ɓ��ݐ�B���R�ɐ旧�U�D�P�Q���A���{�R����c�͐m��ɏ㗤�A���̕��͂��|�ɒ��،��g�E�咹�\��́A���ւ̏@��W��p�����A�����R����{�ɂ���ċ쒀���邱�Ƃ���{���{�ɗv������悤�A�\��������J�n�B �@���łɒ��N�ɂ����錠�v�Ă������{�́A���������͂�����ƂƂ��ɕ��͂������B���̍����ƂȂ����̂����{���g�ٌx���̂��߁u�����u���v�ƒ�߂�ꂽ�ϕ��Y����ł������B���{�͒��N�����������v�𐴍��ɒ�c���ċ��ۂ����B |
| �@�����푈 �@�����ӎO�w���{�y���{�l�x�i��\�I���{�l�j �@�u��d�V�w���{���i�_�x |
| �y���p�ʏ��q�C���z |
| �@�P�W�X�S�D�V�D�P�W���A�C�M���X�Ƃ̏������ɐ������ē��p�ʏ��q�C���A�̎��ٔ����P�p�ɑ�������B��p�鍑�́A���N�����ɂ�������{�̌R������ɓ����͌x���I���������̂́A����ȏ�ɒ鐭���V�A�̒��N�����i�o�ɑ��Čx���I�ł������B��p�鍑�́A�����̌R���͂̃�������m���Ă���A�ނ���A���������ɗ���鐭���V�A�̒��N�����ւ̖�S�������ٓI�ƌ��Ă����B����āA��p�鍑�́A���N�����ɂ�������{�̗����i�삷����j��ł��o���A���p�ʏ��q�C�������B�@�������ĉp���̉��������҂������ԂƂȂ�B |
| �y�����푈�z�i�u�����푈�l�v�j |
| �@�V�D�Q�T���A���N���{�͑咹�ɉ������A���̓�ۂB �@�V�D�Q�X���A�哇�`���̗�������{�R����c�i�펞�Ґ��̂��ߎ���j�́A��R�E�����̐��R��j�����A�����Q�T���ɂ͊C�R�̑��V�������L�����Ő����C�R�ɑ������L�����̊C���������B�搧�U�����ꂽ���߉��킵�Đ����͒���ǂ��������i���̂��ƁA�u��融������v���N����j�B�����̈�A�̐킢�́A�u���N���{�̈˗��ɂ��v�Ƃ����X�^�C�����Ƃ��Ă����B �@�P�W�X�S�D�W�D�P���A���N�i�������N�j���߂����ē��{�Ɛ��i�����j�̑Η�����a��I�ɂȂ�A�����ɐ����ɐ��z�����ꂽ�B�������āA�����푈���u�������B�Η͂ɏ�����{�R�͂X���ɕ���A�P�P���ɗɓ������̗������̂��A�k���E�V�Â����������B�C�R�����{�C�R�A���͑���g�D���āA�X���A���C�C���ɏ������Đ��C��������B�X�D�P�V���A���C�C��ŁA���͏����̎O�������O�Y�Վ��Y�͕m���̏d���̒��ŁA����ʂ������R�����Ɂu�艓�͂܂����݂܂��v�Ɛ���U��i�����B���̂��Ƃ́A�u�����������_���Ȃ��v�Ŏn�܂�u�E���Ȃ鐅���v�i���X�ؐM�j�쎌�A���D�`��ȁj�ɉ̂��A�u�������܂���艓�́v�̌��t�́A�[�����{�l�̐S�ɍ��ݍ��܂ꂽ�B �@���P�W�X�T�i�����Q�W�j�D�P���̈ЊC�q�U���Ő����̌ւ�k�m�͑���S�ł������B�ߑ�I�ȌR���������{�R�́A���N���疞�B�i���̒������k��j�ɐi�o���e�n�ŏ����������߂��B(1894-95�A����27�`����28�N) �@���Q���~�A�����̌o������̂Q�D�T�N���ɑ����B�Վ��R������ʉ�v���n�݂��ꂽ���A���̍����͂T�Q�����R�����A�Q�S������������A�P�O�������ɏ�]���Řd��ꂽ�B�폟�ŐA���n��p�Ɣ������R���U�疜�~�ċ��{�ʐ����m�������B�������A��x�c�����������K�͂����ɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ������B����ɂ��ȍ~�A��鐭���V�A�̋��У�ɔ����ĕx�������H�����X�Ɉ���i�߂邱�ƂɂȂ�B �@���̊ԁA�����V�c�́A��������L���ɐi�߂đ�{�c�������A��U�c����펞�c��Ƃ��ċ�����v�F�������Ȃ����B���R�}�Ɛ��{�̒�g�����R������̂ɂȂ�������̂͂��̂��납��ł���B���{�̈ɓ����㎡�́A���R�}�y���h�̗їL���ƐڐG�A�P�P���ɂ͌��R�ƒ�g�̎�ӏ��\�����B |
| �P�W�X�T�i�����Q�W�j�N�̓��� |
| �y���֏��z | |||||||||
�@�P�W�X�T�i�����Q�W�j�N�A���͍~�����A�����E�t���O�ōu�a��c���J���B�ɓ��Ɨ����@���O�����S���Ƃ��ĂS�D�P�V���A�u�a������������i���֏��j����̓��e�̎�Ȃ��͎̂��̒ʂ�B
�@����ɂ��A�����́A���N�̓Ɨ���F�ߏ@�匠��������A���z�̔��������x���킳��邱�ƂɂȂ�A���{�Ƃ̊Ԃɉ��ĕ��݂̒ʏ����܂�s��������������邱�ƂɂȂ����B���ꂪ�A���{�̒鍑��`�I�C�O�N���̑�������ƂȂ����B �@�����푈�̌��ʁA�u����鎂�q�v�Ƃ������ꂽ���鍑�̎�̂Ԃ�𐢊E���Ɏ������ʂƂȂ��� �B�ȍ~�A�����̐��������i�d�j�̓��������܂邱�ƂɂȂ�B�t�ɓ��{�́A���ɒ鍑��`���ƂƂ��Đ��E�j�ɓo�ꂵ�Ă������ƂɂȂ����B�嗤�i�o�̑�����������A�����ƌނ����֑��ݓ���Ă������ƂɂȂ�B �@���t�J�f�B�I�E�n�[���́A���̂悤�ɕ]�����B
|