| 2.26事件史その4、決起考 |
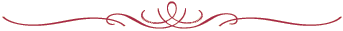
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここでは、「2.26事件史その4、決起考」をものしておく。 2011.6.4日 れんだいこ拝 |
| 2.26日 |
| 【2.26未明蹶起の様子】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.25日夜半から26日未明、帝都東京は30年ぶりという記録的な大雪であった。思えば、赤穂浪士討入、桜田門外の変の時もそうだった。日本を揺るがす大事件が起きる時は、何故か激しき雪が降る。 安藤輝三大尉、野中四郎大尉、香田清貞大尉、村中孝次大尉、磯部浅一一等主計、栗原安秀中尉、中橋基明中尉、丹生誠忠中尉ら尉官クラスの陸軍皇道派青年将校22名に率いられた反乱軍1483名が、前夜からの雪の中、完全武装で整列した。指揮将校の訓辞を受け実弾を渡された。 反乱軍兵士の所属は次の通り。
決起前日の2.25日夜、点呼が終了した後に安藤による訓話が行われた。安藤は先ず黒板に富士山の絵を書き、チョークを横にしてその富士山を塗りつぶした。
下士官以上の同志の標識として三銭郵便切手を各自随意の場所に添付することを定め1日分の食料を持ち出発した。反乱軍は、政治家と財閥系大企業との癒着が代表する政治腐敗や、大恐慌から続く深刻な不況等の現状を打破せんとして「昭和維新断行、尊皇討奸」、「君側の奸を除き、天皇親政を実現するため」を名目に決起し、首相官邸や侍従長邸ほか重臣私邸を襲撃、首都中枢部(首相官邸、陸軍省、参謀本部、警視庁など永田町一帯)を占拠した。これを世に云う「二・二六事件」と云う。事件後しばらくは「不祥事件」、「帝都不祥事件」とも呼ばれていた。 反乱軍は、連隊の武器で装備を固め、陸軍将校等の指揮により出動した。歩兵第1連隊の週番司令・山口一太郎大尉は黙認し、歩兵第3連隊の週番司令・安藤輝三大尉自身が指揮をした。反乱軍は概ね抵抗を受けることなく襲撃に成功した。但し、総理官邸、渡辺大将私邸、高橋蔵相私邸及び牧野伯爵逗留地では、警備の警察官・憲兵の激しい抵抗を受け、これら警察官、憲兵を殺害又は重傷を負わせている。また、渡辺大将は拳銃で応戦したとされている。 決起部隊の行動が始まった時間について、松本清張の「昭和史発掘」は次のように記している。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
主な中心人物は以下の7名
その他、歩兵第1連隊、歩兵第3連隊、近衛歩兵第3連隊、豊橋陸軍教導学校などに所属する中尉、少尉クラスの将校が多数加わっている。反乱軍の構成は将校20名、元将校2名。以下、准士官2名、下士官88名、兵1357名。 |
| 【三宅坂周辺完全制圧】 |
| 2.26日午前3時30分、歩兵第3連隊の安藤輝三大尉は、第6中隊の兵、機関銃隊4箇分隊、機関銃4挺など204人を率いて連隊を出発した。午前4時20分、丹生誠忠中尉が率いる歩1部隊は、香田清貞大尉、磯部浅一、村中孝次、竹嶋継夫中尉、山本又(予備少尉)らを加えた下士官兵170人で営門を出発し、陸相官邸、参謀本部、陸軍省を警戒し、官邸入出を制限、監視下におくことを伝えた。物々しく機銃陣地が随所に作られた。こうして1400名の決起部隊が政治―軍の中枢である霞が関から三宅坂周辺を完全に占拠した。陸軍省、参謀本部の幕僚たちは、皇居の反対側の九段の憲兵司令部や偕行社などを仮住まいとして対峙することになった。 |
| 【野中隊/警視庁襲撃】 | |
| 午前4時30分頃、クーデターが一斉に開始される。野中四郎大尉指揮の約500名からなる警視庁襲撃部隊が、野中の「攻撃目標は、赤坂、警視庁!、合言葉は士気団結!出発!!」の号令と共に営庭を出発した。 5時頃、 同庁司法省側および桜田門側道路数カ所に機銃陣地が作られ、同庁の出入り口を封鎖し、要地に歩哨をたてて監視した。電話交換室内にも兵を配置して外部との連絡を遮断した。警備にあたっていた特別警備隊に機銃を向けて威嚇した。 常磐稔少尉は野中四郎大尉と共に警視庁特別警備隊長らに蹶起の趣意を告げ、警察権の発動を停止させた。警視庁全体を制圧し、「警察権の発動の停止」を宣言した。当時、警視庁は特別警備隊(現在の機動隊に相当する)を編成しており、反乱部隊にとって脅威とされた。警察は、事件が陸軍将校個人による犯行ではなく、陸軍将校が軍隊を率いて重臣、警察を襲撃したことから、当初より警察による鎮圧を断念し、陸軍、憲兵隊自身による鎮圧を求め、警察は専ら後方の治安維持を担当することとし、警視庁は「非常警備総司令部」を神田錦町警察署に設けた。 松本清張の「昭和史発掘」は次のように記している。
余談ながら、この警視庁占拠には、後の5代目柳家小さん師匠がいた。「これは演習じゃないんですか?」と聞いたところ、誰も何も答えなかったというエピソードが残っている。 |
| 【鈴木隊/後藤内務大臣官邸を襲撃】 |
| 歩3の鈴木少尉は下士官・兵60名を率いて後藤内務大臣官邸を襲撃した。後藤内相は親軍的な官僚だったが、統制派寄りの人物であった為に襲撃対象にされた。軽機3挺を持した襲撃隊は警備の警官・看守等を拘束し、官邸内外を捜索したが、後藤内相は不在のため難を逃れた。部隊はそのまま内相官邸を占拠した。 |
| 【香田、村中、磯部隊/陸軍大臣官邸占拠】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「川島陸相訊問調書。 2.26日午前5時やや前、武装した将校三名が下士官若干名を率い、陸軍大臣官邸に来り、まず 門衛所におった憲兵、巡査を押え、官邸玄関にて同所におった憲兵にむかい、「 国家の重大事だから至急大臣に面会させよ」と強要した。憲兵は官邸の日本間の方に進むことを静止したけれども、彼等は日本間に通ずる扉を排して大臣の寝室の横を過ぎ、女中部屋の方へ行く。この時 「あかりをつけよ」 との声が聞えた。事態の容易ならざるを感知して、大臣夫人が襖の間から廊下を見たところ、将校、下士官、兵が奥にむかって行くのが見えたので、夫人はなにごとならんとそちらへ行く。憲兵は大臣夫人の姿を見て「危険ですからお出にならん方がよろしい」と小声にて述べたるも、夫人は「なんてすか」とこいいながら彼等を誘導し 洋館の方に至る。夫人は 「夜も明けない前に何事ですか」と問いたるに「国家の重大事ですから至急大臣にお目にかかりたい」という。夫人は 「主人は病気で寝ているから夜明まで待たれたい」 と 述べ、「待てない」 応酬す。夫人は 「名刺をいただきたい」 旨述べたるに、香田大尉の名刺を渡す。夫人はこれを大臣にとりつぐ。この間、憲兵が大臣寝室に来て、「危険の状態だから大臣は出られない方がよろしい。そのうち麹町分隊より大勢の憲兵の応援を受くるから寝ておってくれ」と言うので、大臣はしばらく臥床して状況を見ようとする。夫人は 「 寒いから応接間に案内いたします。暖まるまでお待ち下さい」と述べるに対し、「待てない、ドテラを何枚でも着て来てもらいたい」と 言う。夫人は憲兵に応接間の暖炉に火をつけさせる。この頃、総理大臣官邸の方向に 「万歳」 の声が聞え、ホラ貝の音がする。これを聞いた彼等は夫人にむかい 「 相図が鳴ったから早く大臣に来てもらってくれ」という。憲兵は憲兵隊に電話しようとするも、「ベル」 が鳴るとすぐ押えてしまい、十分目的を達し得ない。書生を赤坂見附交番に走らせようとしたけれども、門の処で静止せられて空しく帰って来る。隣接官舎 (事務官、属官、運転手、馬丁小使等居住) 方に通ずる非常ベルが鳴らぬので、女中を起こしに走らせる。これは目的の官舎に行くことが出来たけれども、官舎からは一向に誰も来ない。麹町憲兵分隊からもまだ来ない。その内に彼等はまたやって来て 「 早く来てくれ 」・・陸相に対しと 急がす。夫人は日本間と洋間との境のところにて 「 それでは襖越しに話して下さい 」 と 述べる。彼等は靴のままで日本間の方へ行くのを躊躇するので、「 さっきはそのままで奥の方へ行ったではありませんか。それでは敷物を敷きましょう 」と いうと、彼等は 「 応接間の方へ来て下さい 」 と いって応接間の方へ引返して行った。これまでの間において書生および女中の見聞せるところによりて、門の周囲および庭内には多数の兵がおり、また門前には機関銃を据えおることもあきらかとなる。しこうして兵などに聞けば演習なりと言いおれりと。大臣はホラ貝も鳴り、呼びにやった人も来ず、なにか大きな演習でもやったのかと思うけれども只事でもないようにも思われ、状況の判断はつかぬけれども ともかく会うことに決心し、袴をつけて机の前に座し一服しようと思う。その時 彼等も切迫つまって大臣夫人にむかい 「 閣下には危害を加えませんから早く来て下さい 」 と 言う。大臣は一服吸いつつある時、小松秘書官 ( 光彦・歩兵少佐。29期・四十歳 ) が来た。多分門衛の憲兵が塀を乗り越えて知らせに行ったのであろうと思う。秘書官は玄関で将校と話して来たらしく、「 閣下、軍服の方がよございます 」と いうので軍服に着がえる。憲兵は三名ぐらいに増加していたらしい。それから便所に行き、憲兵は面会を止めたけれども彼等に面会するために談話室に入った。室のなかでは将校三名がなにか書いており、ほかに武装の下士官が四名いた。憲兵三名が大臣を護衛していたが、憲兵を室のなかに入れないのでやむなく室外でいつにても内に飛びこめる用意をしていた。当時廊下入口および玄関には下士官がおって警戒しておった。 大臣が室に入ると将校三名 ( 内二名は背嚢を負い拳銃を携帯す ) は 敬礼し、歩兵第一旅団副官香田大尉であります。歩兵第一聯隊付栗原中尉であります。と 挨拶す。他の一名はなんとも言わなかったので「 君は誰か 」と 問えば「 村中です 」と 答えた。大臣は「 今時分なんの用事で来たのか 」 と たずねたところ、今朝襲撃した場所を述べる。「 ほんとうにやったのか 」 と たずねたところ「 ほんとうであります。只今やったという報告を受けました 」 と 答う。「 なぜ そんな重大事を決行したのか 」 と たずねたのに対し、「 従来たびたび上司に対し小官らの意見を具申しましたが、おそらく大臣閣下の耳には達していないだろうと思います。ゆえに ことついにここに至ったのであります。すみやかに事態を収拾せられたいのであります。自分たちの率いている下士官以下は全部同志で、その数は約千四百名であります。なお満洲朝鮮をはじめ その他いたるところにわれわれの同志がたくさんおりますから、これらは吾人の蹶起を知って立ち、全地方争乱の巷となり、ことに満洲および朝鮮においては総督および軍司令官に殺到し、大混乱となりましょう。しこうして満洲および朝鮮は露国に接譲しておりますから、露軍がこの機に来襲するの虞おそれがあり、国家のため重大事でありますから、すみやかに事態を収拾せられたし 」 と 言い、「 蹶起趣意書 」 なるものを朗読する。ついで 通信紙に筆記した希望事項「陸相への要望書」を読む ( 現物は川島大臣保管 )
大臣とのその他問答は次の通り。
午前六時過 (時間不正確 ) 、次官が来る。軍務局長と軍事課長とは来ない。後に、軍務局長、軍事課長は事件の突発を知り登庁しようとしたけれども途中阻止せられて、憲兵司令部の方へ行ったことが判明する。また小松秘書官に両師団、警視庁、憲兵司令部に状況の通報を命じ、特に占拠部隊と相撃をしないように注意せしめる。 斎藤少将は大臣や叛乱軍幹部のいる室に入って来て、大臣とのやり取り後、隅の方の 「 ソファー 」 に 腰を掛ける。その後は同少将とあまり話さなかったが、少将は幹部の栗原と話していたようである。歩一の小藤大佐 ( 恵・20期、47歳) は山口大尉 (一太郎・歩一中隊長・33期、35歳) を 案内者としてやってきたが、時間等は明瞭でない。また 時間の記憶はないが、伏見宮邸から加藤寛治大将( 軍令部長・軍事参議官ののち昭和十年十一月後備役・海兵18期、65歳) から電話で当方面の事情をきき、また「君はどうする」というので「今から参内して侍従武官長に会い、事態を収拾せなければならぬ」と答える。また真崎大将が官邸に来たから 「よく話してくれ」といい、大臣は洗面をすませ、握飯を食い、卵をのみ、勲章をつけ、宮中にあがる準備をする。出かけようとすると片倉少佐 ( 衷・軍務局付・31期) がやられて自動車がないのでしばらく待つ。自動車が帰って来たので午前9時すぎ、参内のため出発する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本清張の「昭和史発掘」は次のように記している。
|
| 【栗原隊/首相官邸襲撃】 |
| 総理官邸襲撃の全体の指揮を栗原安秀・歩兵中尉(歩兵第一連隊機関銃隊)が執り、約300名の部隊を率いた。第1小隊を栗原中尉、第2小隊を池田俊彦少尉が、第3小隊を林八郎少尉が、機関銃小隊を尾島健次曹長、他に対馬勝雄・歩兵中尉(豊橋陸軍教導学校)を指揮者とした。 午前4時、営庭に将校・下士官・兵が整列し、4時半に出発した。首相官邸前に到着したのは午前五時少し前。各指揮官の命令で一斉に着剣し、栗原中尉は拳銃を手に自ら先頭に立ち小銃隊を引き連れ官邸に乱入した。官邸には警備の警官4名が配置されていた。拳銃を所持していたのみであるが果敢に抵抗した為、村上嘉茂衛門巡査部長を官邸内で殺害した。土井清松巡査は林八郎を取り押さえようとして殺害された。清水与四郎巡査が庭で、小館喜代松巡査が官邸玄関で拳銃で応戦するが、襲撃部隊の圧倒的な兵力により殺害された。 その間、岡田の義弟で総理秘書官兼身辺警護役をつとめていた松尾伝蔵・予備役陸軍大佐が電灯を消しに走り回った後、反乱将校らの前に自ら踊り出て銃殺された。松尾はもともと岡田と容姿が似ていた。松尾は兵に「首相閣下ですか?」と問われ、首相の身代わりとなる覚悟をしていたのか「いかにも・・・」と答え、兵に庭に連れ出され、「天誅!」の絶叫と共に射殺された(松尾の死には他にも説があり、庭に据えられた重機が日本間に連射され、中にいた松尾は壁により掛かったまま射殺されたとも云う)。銃撃によって前額部が大きく打ち砕かれ容貌の判別が困難になったため将校らは岡田総理と誤認し目的を果たしたと思いこんだ。岡田首相は、寝室から風呂場、女中部屋の押入れへと転々と隠れ難を逃れた。新聞は、岡田首相殺害と報道した。 一方、総理生存を知った総理秘書官福田耕と総理秘書官迫水久常らは、麹町憲兵分隊の小坂慶助・憲兵曹長、青柳利之・憲兵軍曹及び小倉倉一・憲兵伍長らと奇策を練り、翌27日、事件中の警戒厳重な兵士の監視の下で首相官邸への弔問客が許可されると岡田と同年輩の弔問客を官邸に多数入れ、変装させた岡田を退出者に交えて官邸から脱出させて難を逃れている。 |
| 岡田啓介首相の娘婿で、当時、首相秘書だった迫水久常(さこみずひさつね)氏が30年後の公開を条件に語った岡田首相救出の舞台裏や、事件勃発直後、事態収拾に右往左往する軍首脳部の混乱ぶりなど、事件の渦中にいた当事者ならではの臨場感ある貴重な証言テープが国立国会図書館に保管されており、2002(平成14).11月、公開された。首相不在という権力の空白のなかで、事件はどのように経緯し、収束に向かったのか貴重な歴史資料になっている。 迫水久常(1902~1977) 昭和期の官僚・政治家。鹿児島県に生まれ、東京大学を卒業。岡田啓介の娘婿。大蔵省に入省後、首相秘書官となり、2・26事件の際に岡田首相を救出した。鈴木貫太郎内閣の内閣書記官として終戦工作に従事。戦後、衆議院議員に当選。後に参議院に転じ、池田内閣の経済企画庁長官・郵政相を歴任。 |
| 【中橋隊/高橋蔵相私邸襲撃】 | |
| 別部隊が首相官邸の岡田啓介、赤坂の高橋是清・蔵相私邸、四谷の斎藤実・内大臣私邸、荻窪の渡辺錠太郎・教育総監私邸(陸軍大将)、麹町の天皇側近の鈴木貫太郎・侍従長官邸、神奈川県湯河原の牧野伸顕前内大臣を次々に襲撃した。斎藤実・内大臣、渡辺錠太郎・教育総監、高橋是清・蔵相の重臣が殺害された。鈴木貫太郎・侍従長は重傷を負い、岡田啓介・首相は襲撃を受けるも、義弟の私設秘書松尾伝蔵大佐と間違えられ、からくも脱出した。 | |
| 高橋蔵相私邸襲撃の様子は次の通りである。中橋基明歩兵中尉が指揮を執り、斉藤特務曹長と近衛師団司令部付大江曹長を引き連れ、部隊130名で、午前4時に非常呼集がかけられ兵舎前に整列した後、4時半に出発。午前5時、赤坂表町3丁目の高橋是清蔵相私邸に到着した。高橋蔵相は予算の軍事費、国債費の比重が極端に偏りすぎているとして軍事費を削る等をして財政を健全にしようとしていたことが反感をかっていた。中橋は表門から、中島莞爾歩兵少尉は東門の塀を乗り越えて邸内に入った。警備にあたっていた警官は銃剣を突きつけられつつ監視され、まったく身動きがとれなかった。家人を脅して、蔵相の部屋に案内させ、2階の部屋でまだ就寝中の高橋是清を発見すると、中橋基明は掛蒲団を撥ね除け、「天誅!」と叫びつつ拳銃数弾を発射し、中島莞爾は軍刀で高橋の肩を斬りつけ、さらに右胸部を突き刺した。5時15分に、兵は引き上げ陸相官邸へ向かっていった。 松本清張の「昭和史発掘」は次のように記している。
|
| 【安藤隊/鈴木貫太郎侍従長官邸襲撃】 | ||
鈴木襲撃は安藤みずから志望した。安藤は、公判調書で次のように述べている。
「よく知っている」のは鈴木邸を訪れたからであり、その後ろには尊敬する鈴木を殺さねばならないのなら、みずからの手で、という安藤の苦渋の選択がみてとれる。 |
||
| 2.26日3時頃、帝都眠る寒空の下、非常呼集が行われた。普段はラッパが鳴らされるが、その日は各班の班長が起こして回る、という常と違う方法だった。準備をしている兵士たちに配れたのは乾パンや牛缶詰など一食分。そして一人60発の小銃弾。空砲でない実包である
。4時前、兵士たちが営舎前に集合し編成が発表された。第6中隊は、3個小隊に分けられた。編成が終わると、安藤は「弾込め」を命じ、やがて抜刀して号令した。「気オ付ケー!中隊は只今より靖国神社に向かって出発する。行進順序建制順、右向ケー右!前エー進メ」。安藤中隊は営門を出、行進を開始した。この時点で兵士たちはまだ目標を知らされていなかった。彼らが自分たちの目的を知ったのは、一時間ほどしてからのことであった。全員に企図を黙っていた訳ではない。その前日、25日に安藤は病欠の一人を除いた全下士官を中隊長に集め決意を披瀝した。「昭和維新を断行するため、歩一、歩三、近歩一を主体とする行動部隊は明早朝を期し要路の顕官重臣を襲撃し、以て国内の暗雲を一掃せんとす。当第6中隊は侍従長鈴木貫太郎閣下の襲撃を担当する。攻撃開始は明早朝5時と規制された」。安藤は続ける。「諸官の中に、その信ずるところによって、中隊長と行動を共にすることはできないと考えるものは遠慮なく立ち去って欲しい。それは絶対に卑怯ではない。むしろ勇気ある行動だと思う。これから二分間瞑目の時間を持つことにする。その間に立ち去りたいものは、静かに席をはずして部屋を出て欲しい」。 安藤は目を閉じ約束の時間を過ごした 。再び目を開けたとき、そこには誰一人欠けることなく揃っていた。最後まで決起に悩んだ安藤は、「去る者は卑怯ではない」とまで心遣いを見せたのだが、その心遣いは無用であった。クーデターで最も避けるべきは事前の情報漏洩であるが、安藤とその部下たちに限ってはその心配はいらなかった。これが事変の最後において「中隊団結の極地」 とまで称される、安藤輝三大尉率いる第6中隊の下士官であった。部隊は、首相官邸にほど近い侍従長・鈴木貫太郎海軍大将の邸へと向かった。 |
||
午後9時、第六中隊下士官集合。点呼終了後、階下の広場で中隊長よりの訓示が行われた。中隊長は、訓話を始めるにあたって先ず準備された黒板に富士山の絵をかき、次に白墨を横にして富士山を塗りつぶした。
安藤大尉は次の命令を下した。 1 かねて相沢事件の公判に際し、真崎大将の出廷による証言を契機とし、事態は被告に有利に進展することが明かとなれり。 2 しかるに この成行きに反発する一部左翼分子が蠢動し、帝都内攪乱行動に出るとの情報に接す。 3 よって 聯隊は平時の警備計画にもとづき、主力をあげて警備地域に出動し、警備に任ぜんとす。 4 出動部隊は第一、二、三、六、七、一〇の各中隊とし、機関銃隊は一六コ分隊を編成し、各中隊に分属せしむべし。 5 柳下中尉は週番司令の代理となり 営内の指揮に任ずべし。 |
||
| 週番司令安藤大尉より聯隊主力に出動命令下達。中隊主力は、二中隊一部、三中隊、六中隊、七中隊、十中隊、機関銃隊主力。この六中隊は二コ小隊編成で、第一小隊長に永田曹長、
第二小隊長に堂込曹長。 午前3時、中隊非常呼集。 午前3時30分、舎前整列、編成の下達。中隊は三個小隊に編成、第一、第二、第三 ( 機関銃隊 )。 編成終了後、安藤大尉の号令 「 弾込メ 」。安藤大尉は抜刀して「 気オ付ケーッ!中隊は只今より靖国神社に向って出発する。行進順序建制順、右向ケー 右!前エー進メ 」。喇叭吹奏、行進。「中隊は只今より靖国神社参拝に向かう。 第一、第二小隊の順序、指揮班は中隊長に続行」。 午前3時50分、営内出発。衛兵の部隊敬礼を受けて営門を出て隊列が歩一の前にさしかかった時、走ってきた乗用車が止り 渋川善助がでてきて安藤大尉に、「愈々決行ですか、御成功を祈ります」。渋川は至極落付いた表情でそういった。隊列は以後粛々と進み、乃木坂、赤坂見附を通過。 |
||
| 鈴木貫太郎侍従長官邸襲撃の様子は次の通りである。鈴木貫太郎侍従長を襲撃したのは歩兵第3連隊の安藤輝三大尉で、その第6中隊の兵と、機関銃隊4箇分隊、機関銃4挺、計204名をもって午前3時半に連隊を出発した。 4時50分頃、麹町区三番町の鈴木侍従長官邸に到着した。安藤の部隊が侍従長邸付近を50mほど過ぎた道路上の表・裏門に機関銃を据え、警官隊の襲撃に備えた。部隊を二つに分け、一隊を安藤が、もう一隊を永田露曹長が率いた。「第一小隊は官邸の外まわりの警戒、第二小隊は邸内の警戒、第一小隊の第三分隊及び第二小隊の第一、第三分隊は突撃隊となり侵入し、目標の探索に任ずべし」。 午前5時、軽装に身を固めた中隊が愈々襲撃を開始した。攻撃は正門、裏門の両方に別れ、指揮班は表門組の第二小隊のあとに続いた。表門は脇門が開いており、安藤らの一隊はそこから廷内に侵入した。まず安藤大尉が門前を警戒していた二、三人の守衛に開門を要求、彼等は応じる気配がないので直ちに取抑え、この間携行してきた竹梯子を塀に立てかけ先兵が内に飛込み瞬く間に門扉をあけた。外で待っていた第二小隊がドッと侵入、続いて指揮班も入った。この時取抑えた守衛たちは守衛詰所のキリヨケに手をかけてブラさげ監視をつけた。家屋内に浸入すると、中は真暗なので用意してきた懐中電灯をつけ、念入りに各部屋を探索しながら奥に進んだ。一方の裏門は勝手口だった。兵士は銃剣の先で勝手戸を突き破り、錠をはずして侵入した。邸内は広く、なかなか侍従長を発見できなかった。先頭の奥山分隊は震える女中を尻目に、どんどん奥へと進む。襖を銃剣で開け、三つ目に差し掛かった。侍従長の寝室である。寝床は二つあり、一つには年配の女性がただ正座して兵士たちの方を見ていた 。鈴木貫太郎夫人、たかである。「寝床はまだ温かいぞ!近くにいるから探せ」。空(から)の寝床に手をいれて奥山軍曹が怒鳴った。兵士たちは襖を開け、次の部屋へ移った。八畳間 。奥山分隊長は何事かを察知したのか、銃剣で押し入れの襖を突き刺した。「イタッ!」。奥山軍曹の予想は当たった。そこに、寝間着姿の鈴木侍従長がたっていた。「見つかったゾー!」という兵士の叫びを聞き、他の者たちも駆けつける。 「あちらにおられるのが閣下ですか」と堂込曹長が聞く。隣の部屋には十数人の兵が侍従長らしき人物を取り囲んでいた。下士官の一人が侍従長を畳の上に引き倒した。「マテ、マテ、話せば判る」。駆けつけた十数名の兵士たちを前に、両手を挙げて鈴木は言った 。奇しくも、五・一五事件で殺害された犬養首相と同じ台詞である。堂込曹長は、「閣下は俺が撃つ」と兵に言って、「閣下、昭和維新断行の為、一命を頂戴します」、「奸賊覚悟しろ!」。拳銃の引き金を引いた。二発発射され、一発は侍従長の耳、もう一発は胸に命中した 。 永田曹長も加わり計4発が打ち込まれ、鈴木侍従長は三発を左脚付根、左胸、左頭部に被弾し前のめりに倒れ伏した。 安藤は屋内に侍従長が見つからないので一端外に出ていたが、銃声を聞いてその方向に急いだ。一番奥と思われる部屋にくると電燈がついていて、そこに十五、六名の兵隊が半円形になって包囲する中に目指す鈴木侍従長が倒れていた。上半身から血が流れ出し畳を赤く染めている。安藤大尉はその光景を見るや侍従長をすぐ寝室の床に移動させた。侍従長は重傷ではあったがまだ息があった。奥の間のすぐ手前が侍従長夫妻の寝室で、部屋の隅で兵士に押さえ込まれていた鈴木の妻・たか夫人が床の上に正座していた。安藤大尉は徐ろに夫人に向かって蹶起の理由を手短に説明した。「まことにお気の毒なことをいたしました。我々は閣下に対しては何の恨みもありませんが、国家改造のためにやむを得ずこうした行動をとったのであります」、「御賢明なる奥様故、何事もお判りのことと思いますが、閣下のお流しになった血が昭和維新の尊い原動力となり、明るい日本建設への犠牲になられたとお思い頂き、我らのこの挙をお許し下さるように」。「では何か思想的に鈴木と相異でもあり、この手段になったのですか。鈴木が親しく陛下にお仕え奉っていたのをみてもその考えに間違いはなかったものと思いますが」。安藤大尉は静かに制して「いや、それは総てが後になればお判りになります」。沈黙が続いた。ややあって夫人は、「あなた様のお名前を」。「歩兵第三連隊、歩兵大尉安藤輝三」。「よくわかりました」。 「中隊長殿、とどめを」と下士官の一人が促した。安藤大尉が軍刀を抜き、「甚だ失礼ではありますが閣下の脈がまだあるようです、止めをさせて頂きます」と言って軍刀の先を侍従長の喉に当てると、たか夫人が「お待ちください!」と大声で叫び、「ああそれだけはどうぞ・・・・・・。老人ですからとどめは止めてください。どうしても必要というならわたくしが致します」と気丈に言い放った。ここの下り別節では、下士官の一人が侍従長の首に拳銃を押しつけ、安藤に「とどめを刺しましょうか」と聞く。安藤大尉は侍従長に両膝をついて一礼し、夫人に蹶起趣意を述べようとした時、堂込曹長が「中隊長殿、武士としてのとどめを」と言い、安藤が軍刀を抜きかけたとき、夫人の鈴木たかが「放って置いてもまもなく死ぬから、それだけはやめて欲しい」と懇願した、となっている。 安藤大尉はしばらく考え、「ではそれ以上のことは致しません」といいながら軍刀を納めた。「とどめは残酷だからやめておけ」と制止し、そのままに捨て置くことにした。安藤隊は、結局夫人のこの哀願に躊躇し止めを刺さなかった。このことが幸いして、鈴木侍従長は一命をとりとめた。たか夫人の、危急の臨んでも物怖じしない姿勢が際立っている。危急の際に動じないこの姿勢が侍従長を救ったと言っていい。これはたか夫人だけのことではなく、同じく海軍大将で殺害された斎藤実内大臣の夫人も夫を庇おうとして負傷している。さすがに「武人の妻」として芯の強さを示したことになる。 安藤自身の調書では襲撃のクライマックスをあっさりとしか記していないが、安藤の当番兵で、共に表門から突入した前島清伍長は当時の状況をもっと詳細に述べている。 「鈴木貫太郎自伝」は次のように記している。
安藤大尉の「鈴木貫太郎閣下に敬礼する。気をつけ、捧げ銃(つつ)」と号令で、安藤隊は鈴木侍従長に向かって捧ゲ銃の敬礼を行い、午前5時30分、部隊は侍従長官邸を引き上げた。以上が安藤輝三大尉中隊による鈴木侍従長襲撃の顛末である。死亡確実とみられた鈴木侍従長は一命をとりとめ、後年総理大臣として再び歴史の部隊に姿を表すことになる。 |
||
| 鈴木貫太郎 の人となりは次の通り。 安藤らが襲撃目標とした鈴木貫太郎はもともとは海軍軍人。慶応三年生まれ。昭和十一年には六十八歳という(当時としては)高齢である。日露戦争に従軍し、軍令部部長、連合艦隊司令長官も経験した海軍の重鎮である。昭和四年に侍従長となり、昭和天皇の側近(皇道派に言わせれば「君側の奸」)として過ごしてきた。後に大東亜(太平洋)戦争最末期に天皇自らの懇請によって首相となる。 安藤はこの襲撃以前に面識があった。昭和九年、日付ははっきりとはわからないが事件の二年前、安藤が鈴木のもとを訪ねている。安藤は民間人三人をつれ革新政策について鈴木の話を聞きにきた。詳細は不明だが鈴木によれば次の三点を挙げて反論したという。その第一は、軍人が政治に進出し政権を壟断することに対して、これは第一、明治天皇の御勅諭に反するものである。もともと軍備は国家の防衛のために国民の膏血を絞って備えられているもので、これを国内の政治に使用するということは間違っている(中略)。第二の問題は、貴君は、総理大臣を政治的に純真無垢な荒木大将でなければいかんといわれるが、一人の人をどこまでもそれでなければいかんと主張するすることは、天皇の大権を拘束することになりはしないか。日本国民としてこういうことはいえないはずだ。もしこれ数人のなかからといえば、陛下のご選択の余地がある。一人の人を指定するのは強要することで、天皇の大権を無視するということになる。これが貴君たちのいい分のうち第二の不当な点である。こうしたことは日本国民の口にすべからざることだ。第三は、今陸軍の兵は多く農村から出ているが、農村が疲弊しておって後顧の憂いがある。この後顧の憂いある兵をもって外国と戦うことは薄弱と思う、それだから農村改革の軍隊の手でやって後顧の憂いのないようにして外敵に対応しなければならんといわれるが、これは一応もっとものように聞こえる。しかし外国の歴史はそれと反対の事実を語っており、いやしくも国家が外国と戦争するという場合において、後顧の憂いがあるから戦ができないという弱い意志の国民ならその国は滅びても仕方があるまい。しかしながら事実はそうではないのだ(中略)。その証拠に日清、日露の戦役当時の日本人をご覧なさい、あの敵愾心の有様を、親兄弟が病床にあっても、また妻子が饑餓に瀕していてもお国のために征くのだから、お国のために身体を捧げて心残りなく奮闘していただきたいといって激励している。これが外国に対する時の国民の敵愾心である。しかるにその後顧の憂いがあるから戦争に負けるなどということは、飛んでもない間違った議論である、私は全然不同意だと 。 鈴木は、日露戦争を肌で知っている。鈴木の話は安藤の心に染み渡った。「今日は誠に有難いお話を伺って胸がサッパリしました、よく解りましたから友人にも説き聞かせます」と言い、喜んで帰って行った。そればかりが、「他日また教えを受けたい」とすら述べ、帰り道で友人に「鈴木閣下は噂を聞いているのと実際に会ってみるのでは全く違った。見ると聞くとは大違いだ。あの人(鈴木)は西郷隆盛のような人で懐が大きい」と激賞している 。安藤の鈴木への尊敬の念はその後も消えず、座右の銘にしたいから、ということで鈴木の書を欲し、鈴木は安藤の要望に応えて書を送っている。安藤は今、その鈴木の眠る邸の前に、武装した兵士を引き連れてやってきた。 安藤処刑後、鈴木は記者に対して次のように評している。
|
| 【坂井、高橋、麦屋、安田隊/斎藤實内大臣私邸襲撃】 | |
| 斎藤實内大臣私邸襲撃の様子は次の通りである。坂井直中尉、高橋太郎少尉、麦屋清済少尉、安田優少尉らが率いる部隊210名は、4時20分に営門を出て青山1丁目、信濃町、四谷仲町のコースで午前5時少し前に四谷区仲町3丁目の斎藤実内大臣私邸に到着、襲撃した。麦屋少尉が重機等をもって邸外を警戒する中、坂井中尉が表門から、安田少尉は裏門から侵入していった。警備にあたっていた警官は銃剣を突きつけられつつ監視された為に身動きがとれなかった。斉藤内大臣が寝室から出てきたところを対峙し、夫人は「撃つなら私を撃ちなさい」と夫をかばい重傷を負い、斉藤実は殺害された。計47ヶ所に銃弾を撃ち込み、さらに数十ヶ所も斬り付け、遺体からはもはや流れる血もなかったと云う。殺害後、裏門から出たある将校は警戒中の麦屋隊の下士官、兵らに返り血を見せ、「見よ、国賊の血を!」と叫んでいる。 5時15分、引き上げ、坂井・麦屋は主力を率いて陸軍省付近へと向かう。 内大臣斎藤實の養子である斉藤斉の妻の弟、有馬頼義(直木賞作家)が、向かいの屋敷の窓から襲撃の様子を目撃して次のように記している。
|
| 【高橋、安田隊/渡辺教育総監私邸襲撃】 | ||||||
| 渡辺教育総監(陸軍大将)私邸襲撃の様子は次の通りである。教育総監渡辺錠太郎大将郎を襲撃したのは、内大臣斎藤實私邸を襲撃して別れた一隊で、指揮者は、高橋太郎少尉、安田優少尉と、下士官以下兵30名。高橋少尉以下は、斎藤邸から赤坂離宮正門まで出て、そこで、田中部隊のトラックに乗り荻窪に向った。記録では渡辺邸に着いたのは6時過頃となっている(松本清張の「昭和史発掘」では7時頃)。間髪入れず玄関に機銃を乱射した。すると中から警備に当たっていた憲兵2名が拳銃で応戦、仕方なく裏口へ回り込み屋内に侵入した。その際夫人は「軍人としてあまりに乱暴ではないか」と身を挺して制止したが、蹶起部隊は構わず乱射、庭には機銃が据えられ、これまた猛射。渡辺大将は拳銃で高橋、安田らに応戦したが、全身数十ヶ所に銃創、切創を受け死亡した。6時30分、襲撃隊は陸軍省方面へと引き上げていき、先に分かれた坂井隊と合流した。 渡辺教育総監宅と二軒隣の並びに住んでいた渡辺教育総監の長女政子が次のように証言している。
娘のシスター・渡辺和子が著書の中で何度も父・錠太郎について言及している。累計230万部を超え、平成期を代表する大ベストセラーとなった「置かれた場所で咲きなさい」(幻冬舎)でも、二・二六事件当日の渡辺邸の様子が以下のように綴られている。
渡辺錠太郎は、愛知県小牧の農家に生まれた。生家が貧しかったために、小学校もろくに通えなかった錠太郎は、友人の教科書を借りて独学で学び、陸軍士官学校を受験したという。初の本格評伝となる新刊「渡辺錠太郎伝」(小学館)の著者/歴史研究者の岩井秀一郎氏が、「小卒」から「陸士」へ入ったことの意義を次のように解説している。
錠太郎は、ドイツ留学を経て第一次世界大戦中に欧州に派遣され、戦争がもたらす惨禍に強い衝撃を受けている。帰国後まもなく錠太郎が記者たちに語った言葉が残っている。
渡辺錠太郎は「戦争を避けるための軍備」の重要性を説いてまわっていた。陸軍の要職にありながら、「非戦=避戦」を説いていたことになる。その錠太郎は軍に対し独自の論理を持っていた。「渡辺はその自由主義的発想や深い人文社会学的知識(給料の殆どは丸善の書籍代)は、頑迷固陋な陸軍に新風を吹きこみ近代化を促進させたことは間違いなく、天皇機関説においても昭和天皇と同じ考えでありました(機関としての天皇でよい)」云々。1・軍の権限を侵すような外からの干渉は一切拒絶する。2・軍も他の国政機関の持つ権限には干渉しない。3・軍備は国家予算によって賄われるので、陸相を通じて軍の意見を入れて、政府と協力の上、政府の決定した予算枠内で軍備を整えなければならない。4・軍の要求を強引に通すことは日本の政治体制の崩壊につながる。5・青年将校の行動は軍秩序の破壊に他ならない。6・天皇機関説排撃運動にも疑問を持ちかけ、「国体明徴などとあまり騒ぐのはよくない。これをつきすすめると、南北朝の正閏問題にまで遡ってしまう」と述べ、青年将校等の憤激を買っていた。事件の7ヵ月前、磯部たちが私淑する青年将校の拠り所である真崎大将を蹴落として教育総監に就任したと見られ、これらが渡辺大将が襲撃される要因であった。 |
| 【渡辺錠太郎の次女/渡辺和子証言】 | |
2016.12.31日、渡辺和子さん、生前に語った2・26事件 父を殺された瞬間、そして「赦しと和解」」参照。「2・26事件」で殺された教育総監渡辺錠太郎の次女(4人兄弟の末っ子)渡辺和子さんが逝去した。事件時の様子を次のように証言している。
|
| 【河野隊/牧野元内府(湯河原伊藤旅館別館)邸襲撃】 | |
| 牧野元内府(湯河原伊藤旅館別館「光風荘」)襲撃の様子は次の通りである。 河野寿・航空兵大尉が指揮を執り、予め民間人の渋川善助 夫妻と偵察のため伊藤旅館本館に宿泊。牧野伯の動向を確認後一旦東京に戻る。当日、水上、宇治野、黒沢、宮田、中島、黒田、綿引らがハイヤー2台に分乗し、4時頃、湯河原に到着。前内府の牧野伸顕が宿泊する湯河原の伊藤屋旅館別館「光風荘」を襲撃した。玄関、裏手に機銃を据え、河野大尉が「電報、デンポウ」と叫んで台所の戸をたたくが、開く気配がないので蹴破ることとした。異変に気づいた警備の警官(皆川巡査)が玄関先に様子を見に行ったところ、扉がドンドン叩かれており、慌てた警官は皆に知らせようと奥へ走ろうとしたその時、扉が破られて、拳銃を持った河野大尉らが乗り込んできた。「牧野のところまで案内しろ」と脅された警官は両手を上げ奥に向かって歩き出し、河野らも後に続いた。その時、警官は振り向き様に隠していた拳銃で発砲した為に河野大尉は胸を撃たれ、河野に続いた宮田曹長も首を打たれた。直後、皆川巡査も撃たれたが即死には至らず倒れながらも発砲を続けた。水上の号令で機銃が乱射され、皆川巡査は殺害された。旅館に火を付け、牧野を探したが、焼け跡には牧野の死体はなかった。牧野伸顕は、「女はかわいそうだから逃がす」とされたことに乗じて、岩本屋旅館の岩本亀三らにおぶさって難を逃れた。「牧野伯はお付の女中(森鈴枝)の機転で女物の着物を かぶり勝手口から脱出、塀を乗り越えて裏山に逃れた」。河野大尉はこの後3.5日、入院中の病院で自殺を図る。 松本清張の「昭和史発掘」は次のように記している。
歩3の鈴木少尉は下士官・兵60名を率いて後藤内務大臣官邸を襲撃した。後藤内相は親軍的な官僚だったが、統制派寄りの人物であった為に襲撃対象にされた。軽機3挺を持した襲撃隊は警備の警官・看守等を拘束し、官邸内外を捜索したが、後藤内相は不在のため難を逃れた。部隊はそのまま内相官邸を占拠した。 |
|
| 事件では都内の首相官邸や警視庁が襲われ、閣僚らが暗殺されたが、同じ日に湯河原町でも別動隊による襲撃があった。老舗旅館「伊藤屋」の元別館で現在は資料館の「光風荘」(同町宮上)が現場となった。光風荘には当時、前内大臣の牧野伸顕伯爵が家族らとともに静養で訪れており、そこを河野大尉ら8人が襲撃。「廊下を歩いている時に(護衛警察官の)皆川さんが拳銃で(襲撃してきた河野寿大尉を)撃った。河野さんも皆川さんを撃ち、2人とも廊下で倒れた」。牧野伯爵は難を逃れたが、護衛警察官が殉職、急襲した河野大尉も被弾する(後に自決)など死傷者が出た。光風荘は火を放たれ焼かれるが、翌37年に再建。長らく企業の保養所として使われていたが、2003年に資料館として開館した。室内には河野大尉が自決に用いた果物ナイフなど関係者の遺品をはじめ、当時を伝える新聞など約200点が展示される。 牧野伯爵を救出した消防団員の故・岩本亀三さんの孫の寿一さん(59)は「祖父はあまり事件の話はしなかった」とした上で「人を殺すことは良くないが、(事件を起こした人々の)思いは分からなくはないと話していたことがあった」と振り返る。決起の背景には、東北地方の農家の惨状に対する政府への不満もあったとされる。だが陸軍の青年将校らが「昭和維新」を叫び、暴力革命を図ったこの事件を転換点に、時代は本格的な戦争に突入していった。寿一さんは「(来館を通して)当時何が起こったのか、それぞれに考える機会にしてほしい」と話す。 |
| 【栗原、中橋、田中、池田隊/各新聞社襲撃】 |
| 栗原中尉、中橋中尉、田中中尉(野戦重砲第七連隊)、池田少尉らは、それぞれの最初の襲撃を終えた後、軍用トラック3台に兵60人と機銃3と共に分乗し、各新聞社を襲撃した。中でも、東京朝日新聞社(東朝)には午前8時55分ごろ到着し活字ケース等を破壊し夕刊の発行が不可能になった。引き上げの際、栗原中尉は、「国賊朝日新聞は多年自由主義を標榜し重臣ブロックを擁護し来れり。今回の行動は天誅と思え」と叫んだ。他にも日本電報通信社、国民新聞社、報知新聞、東京日日新聞、時事新報社に現れ、蹶起趣意書を新聞等に掲載するよう強要した。 |
| 【襲撃成果】 | ||||||||||||||||||||||
この日の襲撃の結果は次の通り。
暗殺だけでなく、陸軍省や参謀本部など陸軍の中枢、警視庁、首相官邸など日本の中枢そのものが決起部隊によって占領された。 |
||||||||||||||||||||||
|
襲われた6名の重臣のうち3名が海軍出身の重鎮(岡田、斎藤、鈴木)であったことから海軍将兵の憤りは尋常ではなく、命令下り次第陸軍と一戦を交える気構えにいやがおうにも包まれて行った。 |
| 【襲撃リスト漏れの怪考】 |
| この日の襲撃リストから外されていたのは木戸幸一と近衛である。この不思議を確認しておく。 |
|
木戸 幸一(きど こういち) |
| 1889年(明治22年)7月18日、東京赤坂において侯爵木戸孝正の長男として生まれた。父の木戸孝正は、明治の元勲である木戸孝允の妹治子と長州藩士来原良蔵の長男である。
学習院高等科では原田熊雄、織田信恒などと同級だった。近衛文麿は1学年下に当たる。「学習院高等科から出た者は、東京の大学が満員だから全部京都大学へ行けというような話」があり、木戸、原田、織田は京都帝国大学法科大学政治学科に入学し、河上肇に私淑した。 1915年(大正4年)、同校卒業後は農商務省へ入省した。農務局で蚕糸業改良の調査から水産局事務官、工務局工務課長、同会計課長、産業合理局部長などを歴任する。商工省では臨時産業合理局第一部長兼第二部長を務め、吉野信次と岸信介が起案した重要産業統制法を岸とともに実施した。農商務省が農林省と商工省に分割の際は、商工省に属することとなる。 1930年(昭和5年)、友人であった近衛文麿の抜擢により商工省を辞し、内大臣府秘書官長に就任。 1936年(昭和11年)2月26日-29日、日本の陸軍皇道派が起こした2.26事件の際、杉山元や東條英機をはじめとする陸軍統制派と連携して事件の処理を行い鎮圧に成功している。その功績を昭和天皇に認められ中央政治に深く関与するようになる。 1937年(昭和12年)、第1次近衛内閣で文部大臣・初代厚生大臣(1938年1月11日就任)。 1940年、近衛と有馬頼寧と共に「新党樹立に関する覚書」を作成し、近衛新体制づくりに関わった。 1940年から1945年(昭和20年)に内大臣を務め、従来の元老西園寺公望や元・内大臣牧野伸顕に代わり昭和天皇の側近として宮中政治に関与し、宮中グループとして、学習院時代からの学友である近衛文麿や原田熊雄らと共に政界をリードした。親英米派でも自由主義者でもなかったが、親独派として知られた。几帳面な官僚主義的性格の持ち主で、天皇の信頼は厚かった。 木戸は初期こそ東條内閣を支えたが、大東亜戦争の戦局が不利になると和平派重臣と提携して東條を見限り、和平工作に傾倒した。 東條内閣、小磯内閣の総辞職を経た戦争末期には、重光葵と2人で終戦工作に取り組み、6月には和平方針案の「木戸試案」を作成、鈴木貫太郎内閣の面々や陸海軍に和平方針を説いて回るなど、和平派の中心人物の一人として動いた。徹底抗戦を主張する陸軍に「木戸試案」を納得させたことで和平への動きは大きく高まることになった。その反面、暗殺計画が持ち上がるほど本土決戦派から疎まれた木戸は、8月15日未明には、横浜警備隊長であった佐々木武雄陸軍大尉を隊長として横浜高等工業学校の学生らによって構成された「国民神風隊」によって、平沼や鈴木と同様に自宅を焼き討ちされた(宮城事件)。 |
|
敗戦後にGHQによって戦争犯罪容疑で逮捕された。極東国際軍事裁判(東京裁判)では、昭和天皇の戦争責任などに関して、自らの日記(『木戸日記』)などを証拠として提示した。東京裁判期の日記と併せ公刊されている(東京大学出版会)。日本語で372枚にも及ぶ宣誓供述書で「隠すところなく、恐るるところなく」、いかに自分が「軍国主義者と戦い、政治的には非力であったか」を述べ、当時の政府や軍部の内情を暴露して天皇免訴に動いた。しかし、結果的には連合国との開戦に対して明確に反対しなかったことから、イギリス代表検事であるアーサー・S・コミンズ・カーからは、「“天皇の秘書”であるなら、親英米派であった天皇の意向に沿って行動するのが道徳であろう」として、「不忠の人間」であると強く批判された。結局、木戸の日記や証言は天皇免訴の決定的証拠にはならず、東條の証言によって天皇の免訴は最終的に決定することになった。 『木戸日記』は、軍人の被告らに対しては不利に働くことが多かったため、軍人被告の激しい怒りを買うことになった。武藤章や佐藤賢了は、巣鴨拘置所と法廷を往復するバスの中で、木戸を指差しながら同乗の笹川良一に向かって「笹川君! こんな嘘吐き野郎はいないよ。我々軍人が悪く言われる事は、別に腹は立たんが、『戦時中、国民の戦意を破砕する事に努力してきました』とは、なんという事をいう奴だ。この大馬鹿野郎が」と吐き捨て、それを聞いていた橋本欣五郎も「本来ならこんな奴は締め上げてくれるんだが、今はそれもできんでね」と罵り、木戸もこの時ばかりは、顔を真っ赤にして俯きながら手持ちの新聞紙で顔を覆い隠したという。その木戸も終身禁固刑の判決を受け、服役する。木戸に対する判事団のジャッジは、荒木貞夫・大島浩・嶋田繁太郎と並んで11人中5人が死刑賛成、といったわずか1票差で死刑を免れたという結果だった。 |
| 1955年(昭和30年)、極東国際軍事裁判において終身刑のA級戦犯となったが、健康上の理由から仮釈放され、大磯に隠退する。後に青山のマンションに転居する。1969年(昭和44年)、傘寿の際には、昭和天皇から賜杖を下賜されている。また『木戸日記』については1967年(昭和42年)に大久保利謙早稲田大学講師を相手に政治談話として内大臣時代(1940年-1945年)の話を録音しており、1974年(昭和49年)製作の海外ドキュメンタリー『秘録 第二次世界大戦』でもインタビューに出演している。1977年(昭和52年)4月6日、宮内庁病院で胆汁性肝硬変のため87歳で没した(享年87歳)。遺骨は東京都府中市多磨町の多磨霊園に埋葬された。 |
| 【軍隊における階級】 |
|
軍隊における階級は、大きく「兵」、「下士官」、「士官」にわけられる。陸軍の下士官は階級の低い順に伍長(海軍では二等兵曹)、軍曹(海軍では一等兵曹)、曹長(海軍では上等兵曹)があり、7-12名ほどの兵が属する「分隊」の指揮を任せられる(。「分隊」は陸軍の指揮の最小単位であり、各種の行動において下士官は兵の先頭に立って指揮を行うことを求められる。また、下士官は職業軍人である。普通の兵が徴兵により2~3年の兵役を終えると一般社会に復帰するのに対し、下士官は終身雇用が原則である。ただし、その定年は40歳前後である。 「兵」が軍隊における最下級の階級である。陸軍の「兵」には階級の低い順に二等兵(海軍では二等水兵)、一等兵(海軍では一等水兵)、上等兵(海軍では上等水兵)、兵長(海軍では水兵長)がある(なお、海軍には二等水兵の下に三等水兵、四等水兵という階級が存在した)。軍隊における人口の圧倒的多数を占める。これは必ずしも職業軍人というわけではなく、徴兵により2~3年の兵役を終えると社会復帰する場合が多い。 |