「年の始まり、月の始まり、日の始まりを正月と云う。元々、月様が、泥海の中より、正しい人間、正しい世界を造られたことを云う。正しいことを正と云う。暗がりの世を照らす月様は、先に立ってこの世界を造られた理をもって、この世界をこの日とは云わず、この「よ」(夜、世)と云う。
正月し元日とも云いて今に祝う。
三日の祝いは、身の内の温み、水気、息の三つの理による。世界も同じ事で水と火と風となる。身の内の温み、水気、息の三つに十分の守護あれば不足なし。逆は身の内に不足できる。よって、身の内の悩みを看るに脈を看(診)る。脈とは、この三つの「やく」をいう。この世界は皆な三つの理、三つずつの理あり。天地人、上中下然り。月も三日月が始まりなり。三日目でなくば見えかけぬとは、人間でも子が宿っても一ヶ月、二ヶ月の内は、人から見ては解らん。三ヶ月目から、一寸見えかけるのも同じことなり。三日の祝いの理は、火、水、風の三つの理をもって祝うなり。
鏡餅一重ねの理は、月日二柱の御身輝く理にて、鏡(かがみ)と云う。餅の鏡は天地なり。天地は丸きものなり。丸きは正しきなり。ゆえに夫婦心丸く柔らかにして、仲良く揃うて暮す心を供えるなり。
「みき」と云うは、正しき真っ直ぐなる気(き)を供うるなり。故に木の直なる元を幹と云い、横に出るを枝という。木の実を供うるは、最初人間食物の始めが木の実であったことによる。
ゆずり葉を用いるのは、代々親は子を産み、子は親となりて、子孫に世を譲り行く理を表している。
正月十五日まで十五日の間をしめの内と云うは、月様十五日となれば満月と成り給う、人間もまる十五歳となれば一人前なり。正月元日より十五日迄の祝いと云うは、元始まりの理を忘れぬ為、人間に親神様が教え下されて今に形を行うものなり。
注連縄は七五三なり。七は天神七代、五は地神五代の五倫五体、三は産み広めの「お産」の理なり。七は、元々いざなみの命様が、奈良、長谷七里の四方の間を七日一回りにて、人間を産み降ろし下された理。五は、人間最初は五分より生じて五尺となる理。三は人間を三度産み降ろし下された理。この理によってて、着物七襦袢五帯三を身の内にまといて居る。七五三を張りて年徳大善神と祭り礼拝する。年徳は、十二ヶ月三百六十日は皆な月日の守護にて一年の内に五穀野菜綿糸一切御与え下され、又立ち木魚鳥まで人間の為に御守護下さる故に、この恩徳を受け年々立つものである。
世界でいう天神七代は、これを神々七人のように思えど違う。これは、な、む、あ、み、だ、ぶ、つ、の理であり、くにとこたちの命様よりたいしょく天の命様までの神々をいう。この七柱の神が道具となっておつとめした理をいう。地神五代というは、これも世界の神々のように思えども、自身五体というて、皆な銘々の身の内の事、五体の人間のできた事を云う。
注連縄の「しめ」とは、しめることなり。縄の「な」は、くにとこたちの命様月様のことを云う。「わ」は丸く取り巻くことをいう。これは、月様が、この世界を輪の如くに取り巻きて、しめていられる理なり。よって注連縄は左縄に縫うものなり。その形は、月さまの本体、頭一つ、尾一筋の大竜の形なり。
正月には門松を立てる。門松は、雄松雌松を左右に立てる。女松男松は夫婦の理を示している。しめなわを張りて、年徳大善神と祭り、礼拝するは、年徳とは、十二ヶ月、三百六十日は皆な月日の守護にて、五穀、野菜、綿、糸、一切をお与え下され、また、立木、魚、鳥まで人間の為に守護下されるゆえに、この恩徳を受け、毎年門松を立て、祝うなり。
松と云うのは、三代、芽の芯の立つのを「待つ」と云う理にて、三年目に芽が出て芯の立つまでは古い葉が落ちることなし。木の芽は、一年が人間一代と同じ理。門松は、三段なるを理とす。我が身夫婦で一代、子の夫婦で二代、孫の夫婦にて三代なり。世の芽を出すにて「嫁」と云う。また、孫の代となりて云う時は、二代を「父母」(ちちはは)、三代を「ぢぢばば」と云うなり。我が身より前後を「父母」、「祖父母」、子孫と云いて五代のものなり。
数の子を用いるは、元々いざなぎ、いざなみの二神が、今のおぢばの甘露台を神々の身体の真ん中として、なむ/\(南無南無)と三日三夜に子数九億九万九千九百九十九人を宿し込まれた理をもって用いるなり。豆を用いるは、無事にてこの世をまめに送らそうとの神の思し召しの理をもって用いるなり。鰊(にしん)というのは妊娠の理にて、にしんと云う。
七日、十五日に粥を食するは、人間元泥海より昇りたる理にて、かゆとはかいにて海なり。
七日七草は、元々人間は九億九万年泥海中に住まいたる時は、海草等を食べて通りた理をもって食するものなり。
十四日の年越しという理は、十四日で月は満月とはいえぬ。十五日は満月なり。人間も十四才では一人前とはいえぬ。十五才より一人前なり。これで十四日を年越しというなり。正月元日より、十五日の間をしめの内と云うは、月様十五日となれば満月と成り給う。人間もまる十五歳となれば、一人前に成るゆえなり。
十五日に小豆の粥を食べるは、人間は元々泥海中で住まいしており、その後に泥海より登りたる理を表している。かゆとは海底のことにて、海なり。
正月祝いのこの深き理の話し。全国の神社が一番活気ずくのは正月。神社によっては、経費の大部分がこの正月でお供えが上がる。なぜ日本人が神社にいくのか。それには深く深く理由がある。つまり、人間の元始まりの理を忘れぬように、元の神、実の神、月日二柱を忘れぬようにとこの行事をおこなっている。それほど大切な行事である。正月元日より、十五日の間の祝いと云うのは、元始まりの理を忘れぬ為に神が人間に教え下され、今に形を行うものなり」。
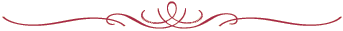
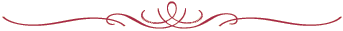
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)