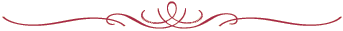
| れんだいこ版元の理教理その2、成人編 |
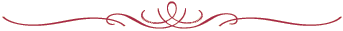
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.12.31日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「元の理一括文」で一覧にしたが、ここでは「れんだいこ版元の理教理その2、成人編」を解読する。まことに「元の理」は汲めども尽きぬ世にも珍しい人類創世記であり、いかようにも解き分けられる不思議な物語である。西欧学的インテリジェンスに慣らされた者には何のことかちんぷんかんぷんであろうが、まずはとくとご照覧あれ。 2006.1.24日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【れんだいこ版元の理教理その2の1、人間作り編】 |
| 28 | 人間作りは、大和の山辺郡(ごうり)の諸屋敷の中山氏(うじ)の屋敷で行われた。月日両神が見ると、いざなぎい、いざなみ、くにさづちい、月よみの道具衆がいた。月日両神が天下り委細よろづを仕込み始めた。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 人間作りが「大和の山辺郡(ごうり)諸屋敷の中山氏(うじ)の屋敷」で行われたと云う。 | ||||||||
| 「大和の山辺郡(ごうり)諸屋敷の中山氏(うじ)の屋敷」で「人間作りの際に寄せ集められた神々」が、いざなぎい、いざなみ、くにさづちい、月よみの道具衆であったと云う。この四神の四作用こそ人間機能の中枢中の中枢と云うことになる。その中にくにさづちいの女性の型、月よみの男性の型の仕込みがあり、性の型の違いによる性差がよほど重要なことであったと拝察させていただくことができよう。 | ||||||||
| 親神の「諭しと指図」、人間及び世界の「一手一つ」の重要性が示唆されている。 |
| 29 | いよいよ神の人間創造が始まった。男雛型のいざなぎと、女雛型のいざなみが呼び寄せられ、月日両神がそれぞれの胎内に入り込み、人間を拵える守護を教え込まれた。三日三晩の間に「み」の胎内に南無南無と九億九万九千九百九十九の子種が宿された。これが最初の創造の試みであった。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| ここで、「事始めに於ける夫婦始めの宿し込みの理」が諭される。この理が「元の理」に於いて始発の理となっており、至極当然当り前の基本として位置づけられていることを、そのように拝聴すべきであろう。「夫婦始めの宿し込みの理」を説く教理は、世界の諸神話との比較では相当に希少なのではなかろうか。この認識の仕方に着目し、「元の理」のひいては日本神話の貴重な財産であると拝させていただく。 | ||||||||
| この時の「九億九万九千九百九十九匹の子数」を仮に「九九九の理」と命名しておく。これは、「一の位の9.十の位の9、百の位の9、千の位の9、万の位の9で、億の位の9」の数字が続いていて、「十分の数に一つ足りない、という理がこもっている」と口伝されている。「九の数字の重なり」の意味につき、「九という数は三の三倍であり、親神が人間創造に当たって如何に長い年限にわたって苦心されたかという親心を示す」と拝察されている。九には、人間身体の九つの道具、おつとめ鳴物の九つの道具、九度の別席順序等の意味があると解され、理の上の数とも見做されている。「人間は何か一つ足りないから必死で働くが、十分になると怠けて働かなくなる、のもこれによるとも考えられる」云々(松谷武一/H15.05.22日「元の理と世界たすけ」参照)。 | ||||||||
| 「九億九万に 九千人 九百九十に 九人」につき、これは、五七五七七の歌の形式にあてはめるとき、九千九百九十万の部分をいれることができないために、その部分が略されたのではないかと思われる。 | ||||||||
| 「或る時、梅谷様より、仲田様、山本様などに、『人間は九億九万九千九百九十九人の人数と聞かせられるが、中に牛馬におちている者もあるとの事なれば、人間の数は現在増えておりますか、又減っておりますか』と尋ねしところ、『そんな事は知らぬから、これから神様へ伺わん』と申して、教祖様の御前に伺い、仲田様より右の次第申上げしに、暫らく御伺いの体にて、『それは増えてあると仰る』と仰せられて、それより、その次第をお聞かせ下さるには、『元は九億九万九千九百九十九人の人数にて、中に牛馬におちて居る者もあるなれど、この世はじめの時より後に、生き物が出世して、人間とのぼりている者が沢山ある。それは、鳥でも獣でも、人間を見て、あゝ羨ましいものや、人間になりたいと思う一念より、生まれ変わり出変わりして、段々こうのうを積むで。そこで、天にその本心をあらわしてやる。すると今度は人間に生まれて来るのやで。そういう訳で人間に引き上げて貰うた者が沢山にあるで』と仰せられ、一同感服して御前を退がりしと云う」。(「人間の数に就て」、「正文遺韻抄」諸井政一著(道友社発行)153ページより※逸話集より) |
| 30 | 道具衆は「互い立てあい助け合い」で相和しながら各自の役割を勤めた。その様は、「神楽づとめ」の際の十人のつとめ衆の挙措で表現されている。「互い立て合い」且つ相和しつつ、手振りがそれぞれ皆な異なるそれぞれの働きの理を表現して振り踊る。この最初の宿し込みで目出たく今日の人間が生み出されたのではない。この後、幾度もの試しが為されることになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このことが「み神楽歌の序歌」で次のように詠われている。
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「夫婦始めの理」に続いて「夫婦の理」が諭されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教祖は、道具衆をお屋敷内在中の人物に割り振っている。これを確認しておく。
|
| 【れんだいこ版元の理その2の2、人間試作編】 |
| 31 | しかし、これですぐにも目出たく今日の人間が生み出されたのではない。幾度もの試しが為された。男ひながた「うお」と女ひながた「み」が呼び寄せられ、三日三晩の間に「み」の胎内に南無南無と九億九万九千九百九十九の子種が宿された。これが、最初の創造の試みであった。 | |||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||
| ここで、「三日三晩(三か三よさ)の理」が諭されている。これが、集中して事を行う場合の型となっていると悟らせていただくことができよう。 |
| 32 | それから三年三月の間、うをとみいの二人はおぢばにとどまっていた。やがて、お腹の子供がだんだん大きくなってきて、母親・みいのお腹がふくれあがって、はちきれそうになった。やがて時みちて、母親のみいと父親のうをは、日本中に生みおろしに出かけた。 |
| ここで、「三年三月の理」が諭されている。これが、事を実らせる場合の型となっていると悟らせていただくことができよう。 |
| 33 | 出産の様子は、「み」が泥海の砂地をみつけては子を生み、「み」が生むと「うお」が寄って一人一人の子に息をかけたと云う。その、人間が生みおろされたあとに今日土地ところにお宮ができたので産土神と云われる。 |
| ここで、「息をかける理」が諭されている。ここの件(くだり)で、「今に諺にも『親の息勢かからぬと子は育たない』と云われる所以がここにある」と諭されている。 | |
| ここで、「産土神の理」が諭されている。 |
| 34 | まず、おぢばの周りの奈良、初瀬7里の間を7日かかって産みおろし、残る大和国を4日にて産みおろし、山城、伊賀、河内三カ国を19日にて産みおろし、合わせて30日かかって子供の半分が産み下ろされた。残る国々に45日かかって産みおろした。それ故に、75日を帯やと云う。 | |||||||
| ここで、「産みおろし7日、75日帯やの理」が諭されている。 | ||||||||
奈良は今の奈良市、初瀬は奈良県桜井市内の地名を云うとされている。山城は京都府南部、伊賀は三重県西部、河内は大阪府東部で、いずれも大和国のすぐ隣の地域を云う。山澤良助筆「和歌体十四年本」(「此世始まりの御噺控」)が次のように記している(「こふきの研究」64頁)
|
| 35 | だが、この時産み落とされた子は一様に五分と小さく、このものは五分五分と成人して九十九年生きた後、三寸になったところで、全てこの世から出直し(死去)していった。この時父親いざなぎも身を隠すことになった。 | |
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||
| この件で、「五分五分成人の理」が諭されている。日本の尺貫法の基本の1尺は約30,3cm。1尺の十分の1が1寸で3cm余。その百分の1が1分で尺貫法の最小の単位である。1分は約3mm。5分は15mm(1.5cm)、3寸は約9cmになる。「五分」という言葉には、日本の諺に「一寸の虫にも五分の魂」とか「喧嘩口論は話し半分、五分五分に聞くのが良い」とか云われているように元の理にかかわる意味も込められている。 | ||
|
「五分五分と成人をして」とは、ほんの小さなものが長い年月をかけ少しづつ成長、進化をしたことを喩えていると捉えることができよう。現在でも「一寸」を「ちょっと」と言い、ほんの少しを喩えて言うのに用いられている。 |
||
| ここで、「九十九年生きの理」が諭されている。 | ||
|
ここで、「三寸の理」が諭されている。 「九十九年」を経て最初「五分」の大きさであったものが「三寸」6倍まで成長している。この「三寸」も一寸を約3㎝と考えると約9㎝である。「舌先三寸」の言葉がある。 |
||
| ここで、「この時父親いざなぎも身を隠すことになった」とあり、「父親いざなぎの身隠しの理」が諭されている。雄性のいざなぎの方が早く身を隠していることになる。これを寿命のことと拝すれば、現在の人間も男性よりも女性の方が平均寿命が長いことが頷(うなず)けよう。 |
| 36 | こうした経過を見て、月日両神の工夫と思いが更にかけられた。親神様から一度教えて頂いた守護によりいざなみの胎内に又、前と同じ子供が同じ数だけ宿った。いざなみは次の出産に向かった。十月経って産み下ろされ、再び九億九万九千九百九十九の子を産んだ。 |
|
ここで、「一度教えて頂いた守護の理」が諭されている。これを現代用語で云えば「雌性のみでの有性生殖」となる。いざなみは、「一度教えられた守護により」いざなぎの雄性の生殖細胞を体内に持っていたことになる。現在の生物にもそのような形で生殖を行う生物が存在するのであながち荒唐無稽なことではない。 |
|
| ここで、「十月産み下ろしの理」が諭されている。二度目の宿し込みが行われ、臨月になるのを待つ間、みいは十月間、おぢばにいた。最初の産み下ろしが三年三月だったが、今度は大幅に短くなり十月となっている。最初は産み下ろすのに七十五日かかっているが今回はその表現がない。 |
| 37 | このたびは日本国中に産みにまわり、同様に生んだ子に息をかけていった。その時の生みおろしのあとに、いま日本国中の墓地(はかち)ができている。これは五分より始まり、五分五分と成人し前より大きく三寸五分まで成長したが、やはり九十九年生きた後、全てこの世から出直し(死去)していった。 |
| こたびは日本中に生みに廻り、生んだ子に息をかけた。やはり五分から生まれた子供たちは、九十九年たって三寸五分になり、またみんな亡くなった。 | |
| ここで、「墓地の理」が諭されている。 |
| 38 | こうした経過を見て、神の工夫と思いが更にかけられ、いざなみは次の出産に向かった。結局三度出産したことになる。 | |
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
| 39 | 三度目も、同じ数の子種を宿し十月経って産み降ろした。今度は更に大きく四寸まで成長した。三度目の産み下ろしは原地に為され、その場所は、土地ところの参り場所となっている。「一宮・二墓・三原」と云われて、それぞれ人間の参り所となっている所以がここにあり、皆な元の理に因縁のある場所だということになる。 |
ここで、「三度の宿しの理」が諭されている。三度めも、最初、二度目と全くおなじ順序と方法で宿し込み、生み卸しされて、母親の息をうけ、やがて三たび九十九年たち、子供たちは四寸まで成長した。和歌体十四年本(山澤本)は次のように記している。
|
|
| ここで、「一宮・二墓・三原の理」が諭されている。三度目の出産後、母親のみい(いざなみのみこと)も隠れ、子供たちも後を慕うように出直していった。最初の生み卸しの地に神社が創られ、宮となり、子を生みおろした理で神社を「産土(うぶすな)の神」と云う。これにより、生みおろされた子供たちは氏子(うじこ)と云われる。二度目の生み卸しの後に墓地が創られ、三度目の生み卸しの後が各地の詣り場所になっている。人間が手をあわせる詣り所は皆なこの元の理によっている。 |
| 40 | いざなみはにっこり笑うと、「これまでに成人すれば、いずれ五尺の人間になるであろう」と言い残して身を隠すことになった。三寸から始まり三寸五分、四寸と次第に大きくなった人間の成長に手ごたえを感じとられたからであった。三度目の子供もいざなみの後を慕うようにして出直し(死去)していった。 | |||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||
| ここで、「五尺の人間の理」が諭されている。五尺は、明治時代に一尺=303.0303㎜(曲尺)と定義されており、約30cmと考えると1.5mである。 | ||||
| ここで、「母親いざなみの身隠しの理」が諭されている。雌性の元である「いざなみのみこと」が、「これまで成人すれば、いずれ五尺の人間になるであろう」との言葉を遺して「にっこり笑うて」身を隠している。 |
| 41 | ここまでの月日親神のお働き、それによるご守護は並大抵のことではなかった。このことを深く知り、感謝申し上げるのが人の道である。 | |||||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||||
| ここで、「心尽くしの理」が諭されている。親神の「人間創造と世界創造」は、「心尽くし」てのものであったことが分かる。よって、かたじけなくも有り難いことであるということになる。この理から「親神の心づくしの思い」を深く悟らせていただき、「心尽くし」を受け継がねばならないと云う諭しになる。 |
| 42 | こうして人間の命は十全の守護によって生かされている。その身体は神の貸し物と心得るべきである。大事に扱い使うのが人の道である。これを貸し物借り物の教理と云う。 | |||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||
| ここで、「貸し物借り物の理の理」が諭されている。創造された人間及び世界は皆な親神の働きによる「十全の守護」を受けている。これを「親神より貸しもの」、「人間よりの借りもの」と受け止め有難いとして深く感謝しつつ大事に扱わねばならないと戒められていることになる。これを「貸しもの借りもの」教理と云う。 |
| 【れんだいこ版元の理教理その3、道中編】 |
| 43 | その後、人間は長きにわたり生まれ変わりの旅に出向くことになった。この間様々な虫や鳥や獣畜類に生まれ変わり、実に八千八度の転生を繰り返すことになった。 | |
|
ここで、「八千八度の転生の理」が諭されている。この転生論につき、次のようなお諭しが伝えられている。
|
| 44 | その果てに、一匹の「めざる」がこの世に生まれた。これに神名が付けられ「くにさづち」と云う。この「めざる」が身ごもった。その胎内から男五、女五の生命が産み出された。この新たな人間は最初五分から生まれ出て、五分五分と次第に成人していった。 |
| ここで、「めざるの理」が諭されている。この時の「めざる」も現在の類人猿等の所謂哺乳類の猿ではない。まだ、水中に生息するやがて猿に進化するものあるいは猿の様な生き物として拝する必要がある。ここまでの生命体が全て水棲生物であるのは後の段落に記されている。 | |
| 「めざる」の胎内に男五、女五の生命が宿った理が、神楽づとめの男人衆、女人衆の人数と一致している。 |
| 45 | この成長に応じるかのように、世界の自然環境も整い始めた。子供が八寸になった時、初めて泥海に高い低いができ始めた。一尺八寸になる頃には泥海も漸く固まり、海と山、天と地が区別できるまでになった。 |
| ここで、「海山天地創造の理」が諭されている。ここで留意すべきは、このように人間創造、成人の歩みと自然環境の変化が連動していることの教示であろう。この悟り方も「お道教理」の重要な要素の一つであるように思われる。 |
| 46 | その後、人は一尺八寸から三尺になるまでに、一腹に男一人女一人の二人ずつが生まれて行くことになった。次いで、三尺に成人した時、初めて言葉を話せるようになり、一腹に一人ずつ生まれるようになった。そして、次第に五尺の人間へと辿り着くことになった。この間、実に九億九万年を水中で暮らしていた。 |
| ここで、「水中暮らしの理」が諭されている。人間の祖先が九億九万年間を水中暮らししていたと云う。現代進化論的に頷ける諭しではあるが、驚くべき的確な教示であるように思われる。 |
| 47 | 人間が五尺に成人したときは、人間の住むに都合がよいように、海山、天地、世界もはっきりとできあがった。そこで水中の生活をやめて、ここに漸く陸上がりを果たせるようになった。現在のような陸上生活はそれ以来のことである。 |
| ここで、「陸上生活の理」が諭されている。「水中から陸上へ」の変遷は現代進化論に照らして整合的である。 |
| 48 | 人間は三尺から五尺になるまで、食物(じきもつ)を食いまわり、唐天竺まで廻り行くことになった。この間、五尺に成人するまでに、この世界、天地海山、食物までもが人間の成人に応じてできた。 |
| ここで、「食物(じきもつ)を食いまわりの理」が諭されている。 | |
| ここで、「唐天竺」が登場している。元の理での「唐天竺」は地理的なものに留まっており、「マイナ-的な唐天竺論」までには至っていない。 |
| 49 | しかし、これでも人間の完成が為されたのではない。陸に上がった人間は六千年間、智恵の仕込を受け、三千九百九十九年間、文字の仕込を受けることになった。 |
| ここで、「智恵の仕込み、文字の仕込みの理」が諭されている。 | |
| 人間の生命と他の生物との命の連続が語られている。思案すると進化論的過程を述べているところも着目される。 ちなみに地球史を大まかに見ると地球誕生より約百四十億年が経過しているとされている。生命が誕生した始生代が約38憶年前、生物が陸上へと生活の場を移した古生代石炭紀が始まるのが3憶5900万年前、哺乳類に猿が誕生し、その猿が世界へ移住し始めたのが新生代第三紀の中新世で、約2300万年前、人類の誕生と二足歩行を獲得したのが、鮮新世で約500万年前である。人類が農耕牧畜を開始し、最初の文明が現れるのが、有史時代第4紀完新世(沖積世)で約1万年前である云々。 |
| 50 | これが元始まりであり、月日親神は、人類を我が子と思い常に気にかけてくだされている。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| ここで、「世界中一列は皆兄弟論」が諭されている。 |
| 51 | 月日親神は、人類が心勇んで陽気づくめに暮らすよう、心がいずまないよう願っており、そう諭している。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| ここで、「陽気づくめの理」が諭されている。「陽気づくめ」は「陽気遊山」、「陽気暮らし」と同義であると思われる。その大事な要素として「心が勇む」こと、「世界の心が勇む」ことが肝要と諭されている。 |
| 52 | こうして創造された人間であるのに、月日親神の思惑から外れて心得違いで道を踏み外している。月日親神は、「人間創造の元一日」に立ち返るよう促している。 | |
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||
| ここで、「元一日の理」が諭されている。 |
| 53 | 月日親神は、心得違いを埃(ほこり)と諭し、日々の掃除で払うよう諭している。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| ここで、「埃論」が諭されている。 |
| 54 | 月日親神はこたび、中山みきを神の社(やしろ)と定め、親神の思いを「元始まりの理話し」として説き聞かせることになった。 | |
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||
| ここで、「人助けたら我が身助かるの理」が諭されている。 |
| 55 | 月日親神は、生みの子らが、人類の故郷であるぢばの地で、甘露台を中心として踊る一手一つの神楽づとめをすることで、神の理を味わい、親神の心に添って生き直すよう諭している。 |
| ここで、「神楽づとめの理」が諭されている。 |
| 56 | 月日親神は、親神の諭しを聞き分け、聞き分けた者が親神の願う神人和楽の陽気世界への世直し、世の立替えに向かうよう促している。 |
| ここで、「神人和楽の陽気世界への世直し、世の立替えの理」が諭されている。 |
(これは参考文であり、今後どんどん書き換えられていきます)
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)