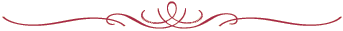
| 「元の理」一括文 |
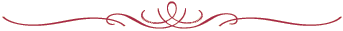
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.10.27日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、みき教理の精華である「元始まりの理話し譚」(「泥海こふき」とも云う。以下、「元の理」と言い換える)を開陳しておく。これに関する解説は「泥海こふき論評」で、「元の理」そのものの解説は「泥海こふき逐条解説文」で為すことにする。 「元の理は、教祖がお筆先の中でも記しているが、総合的な話は信徒に対する口記で説かれていたものと思われる。教祖は、主だった信徒に筆記するよう促し、でき上がったものに目を通したが、満足するものはなかった。つまり、正式の定本はない。その後の応法の理過程で隠匿され、細々と語り継がれる運命を辿った。戦後になって復元が叫ばれ、自由に説ける時代を迎えたが、教祖が満足しなかった諸本を教理として聞き分ける体裁のまま今日に到っている。ここに、れんだいこが、「れんだいこ版元の理」を認め、世間の耳目を得てみたい。 2007.12.25日 れんだいこ拝 |
| 【れんだいこ版元の理一括文その1、創造編】 |
| 1 | 既に長い時間が経過していた。見渡せば、一面泥海であった。 | |||||
このことがお筆先で次のように誌されている。
|
||||||
| 2 | 泥海には多くのどじょうが棲んでいた。 | |||||
このことがお筆先で次のように誌されている。
|
||||||
| 3 | この泥海世界に月様と日様が居られた。月様と日様は、泥海の中に大龍、大蛇のお姿をしてお現れになっていた。これを月日両神と云う。この月様をくにとこたちの命(みこと)、日様ををもたりの命と申し上げる。人間、世界をはじめられた親神(おやがみ)様である。 | |||||
このことがお筆先で次のように誌されている。
|
||||||
| 4 | ある時、月日両神は「味気なし」と思し召され、「一つ人間というものを拵えて、そのものが陽気遊山して喜ぶ様を見て自分も楽しみたい」と思い立った。 | |||||
このことがお筆先で次のように誌されている。
|
||||||
| 5 | こうして「世にも珍しい企て」が始められた。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| 6 | 併行して世界も同時に創造されることになった。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| 7 | 月日両神が泥海を見澄ますと、どぢよ、うお、その他様々な生物がいた。それらの特徴と働きの特質を見抜き、人間作りの道具にしようと思し召された。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
| 8 | こうして、月日両神の心尽くしての人間創造が始まった。構想が練られ、いよいよ人間作りの台となる素材集めに向かわれることになった。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| 9 | 月日両神はまず最初に、鱗(うろこ)のない、見目形が台になりそうな「うお」と「み」に注目した。どちらも、神の構想素材に相応しい顔と皮膚をしており、「このものを雛型として人間を拵(こしら)えたらよかろう」と思いつかれた。人肌のすべすべ滑らかさと見目形はこの素材に負っている。かくて「うお」と「み」が人間の台となった。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| 10 | 月日両神は最初に「うお」と「みい」を見定めて呼び寄せた。「うお」と「みい」は一筋心でやって来た。その心根が御心に叶った。月日両神は「うお」と「みい」に人間創造の事業計画を打ち明け、「貰い受けたい」と伝え協力を願った。「うお」と「みい」は当初断ったが、懇々と諭され、神と「うお」と「みい」との真剣な談じ合いを経て、「役立ってくれるなら後々まで祀る」と諭されるに及び承知した。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| 11 | 月日両神はこれを食べて賞味された。これが「男の台」のひながたになった。これより「うお」を「岐魚」(ぎぎょ)と名づけ「岐様」(ぎさま)と敬称することになった。後の人間創造の際に、「岐様」の胎内に月様が入り込むことにより仕込みされ、「岐様」は生命の片方の原理である「水気」の役割、特に「よろづ眼胴うるおい」の働きに責任を負うことになる。神名「くにとこたちの命」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆が大竜で表される獅子面を被る。 | |||||
| 12 | 月日両神は「み」を食べて賞味された。これが「女の台」のひながたになった。後の人間創造の際に、「み」の胎内に日様が入り込むことにより仕込みされ、「み」は生命の片方の原理である「火気」の役割、特に「よろづぬくみ」の働きに責任を負うことになる。神名「おもたりの命」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆が大蛇で表される獅子面を被る。 | |||||
| 13 | 人間創造の元となる台は「くにとこたち」と「をもたり」で、種と苗代の役割を担った。 | |||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||
| 補足 |
「岐様」の鰭(ひれ)に五つの筋(すじ)があった。これが五本の指となった。最新の生物科学は、「人間の祖先にあたるシーラカンスのような魚の胸びれや尻びれが、段々と手足に進化変化し、サンショウウオかトカゲのような姿で陸に上がった」としており、符号している。
|
| 14 | 神が次に為されたことは人間のその他の機能の仕込みであった。四方八方からこれに相応しい素材集めに向かわれることになった。「しゃち」、「かめ」、「うなぎ」、「かれい」、「ふぐ」、「くろぐつな」の六魚が選ばれた。それぞれに「うお」と「み」同様に人間の道具になることを承知をさせ、食べて賞味された。 | |||||||
| 15 | 「しゃち」が乾(いぬい、西北)の方角からやって来た。この者は変にシャチコ張り、勢いの強い特性によって、骨を始めとする「よろづ突っ張りの役目」に使われることになった。且つその特性が生殖機能としての「男一の道具」に使われ、これが「うお」に仕込まれた。こうして男雛型ができあがった。神名「月読みの命」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆の男性が鼻高面をつけ、背中にシャチを背負う。 | |||||||
| 16 | 「かめ」が巽(たつみ、東南)の方角からやって来た。この者は皮が強く、ふんばりも強くて容易に転ばない特性によって、皮膚を始めとする「よろづ繋(つな)ぎの役目」に使われることになった。且つその特性が生殖機能としての「女一の道具」に使われ、これが「み」に仕込まれた。こうして女雛型ができあがった。神名をつけて「くにさづちいの命」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆の女性が女面をつけ、背中に亀を背負う。 | |||||||
| 17 | 人間創造の機能の最初を「月読み」と「くにさづち」が担い、「月読み」が男性生理と骨つっぱり、「くにさづち」が女性生理と皮つなぎの役割を担った。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 18 | 「うなぎ」が東(ひがし)の方角からやって来た。この者は精が強く、頭の方へも尾の方へもスルスルとぬけて行く特性によって、「よろづ飲み食い出入りの道具」に使われることになった。神名をつけて「くもよみの命」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆の女性が女面を被る。 | |||||||
| 19 | 「かれい」が未申(ひつじさる、西南)の方角からやって来た。この者は身が薄く、風をおこすのに都合がよい特性によって、「よろづ息吹き分けの道具」に使われることになった。神名をつけて「かしこね」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆の男性が男面を被る。 | |||||||
| 20 | この四神が「最初の一の道具」となった。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 21 | 「くろぐつな」が西の方角からやって来た。この者は勢いが強く、引っぱっても容易にちぎれない特性によって、「母親の胎内からの引き出しを始めとするよろず引出しの道具」に使われることになった。成長の機能はこれにより、「立毛(りゆけ)の一の道具」としての地位が与えられている。神名をつけて「をふとのべの命」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆の男性が男面を被る。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 22 | 「ふぐ」が丑寅(うしとら、東北)の方角からやって来た。この者は食べるとよくあたって、この世との縁が切れるものである特性によって、母親の胎内からの切り離しを始めとする「よろづ切り離しの道具」に使われることになった。「ふぐ」に仕込みされ、へその緒切り」を始めとして生命の誕生から息の引き取りの世話をさせることにした。「世界のはさみ」としての地位が与えられている。神名をつけて「たいしょく天の命」として祀られることとなった。神楽づとめの際には、つとめ人衆の女性が女面を被る。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 23 | 月読みを男の台に、くにさずちを女の台に、これに「くもよみ、かしこね、をふとのべ、大食天」の機能を備えさせて働きの道具が皆な揃った。これらを合わせて「六台始まり」と云う。かんろ台の六角形はこの理によっている。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 24 | 月日両神は泥海の中にたくさんいた「どじょう」を食べられて賞味し、その心根(こころね)を味わい、人間創造の際の「種」とした。これで、人間作りの全ての機能が備えられた。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 25 | さて、ここまで準備が整ったからには、その受け皿としての身の台を拵える必要があった。こうして次に、男の雛型として想定されていた「うお」が呼び寄せられ、「種宿しこみ」の役目が諭され、「いざなぎの命」の神名が与えられた。併せて、女の雛型として想定されていた「み」が呼び寄せられ、「苗代」の役目が諭され、「いざなみの命」の神名が与えられた。この「いざなぎの命」と「いざなみの命」が夫婦としての役目を担い、命を生み出すことになる。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 26 | かくて、人間創造の雛型と道具衆が全員揃った。これを併せて十全の守護と云う。この守護は、月日親神の世話取りで生み出されているものであるから、人間は月日親神の守護を学び、深く感謝しつつ日々を生きるのが人の道である。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 27 | とはいえ、道具衆が揃っただけでは人間が創造される訳ではない。月日両神の「諭しと指図」が為され、道具衆がそれぞれの役目を「一手一つ」になって果たすよう指示された。こうして幾度も「談じ合い」が始まり幾度もの「練り合い」で息合わせが試された。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
| 28 | 人間作りは、大和の山辺郡(ごうり)の諸屋敷の中山氏(うじ)の屋敷で行われた。月日両神が見ると、いざなぎい、いざなみ、くにさづちい、月よみの道具衆がいた。月日両神が天下り委細よろづを仕込み始めた。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 29 | いよいよ神の人間創造が始まった。男雛型の「いざなぎ」と、女雛型の「いざなみ」が呼び寄せられ、月日両神がそれぞれの胎内に入り込み、人間を拵える守護を教え込まれた。三日三晩の間に「み」の胎内に南無南無と九億九万九千九百九十九の子種が宿された。これが最初の創造の試みであった。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 30 | 道具衆は「互い立てあい助け合い」で相和しながら各自の役割を勤めた。その様は、「神楽づとめ」の際の十人のつとめ衆の挙措で表現されている。手振りがそれぞれみな異なりつつも「互い立て合い」相和しつつ、それぞれの働きの理を表現して振り踊る。この最初の宿し込みで目出度く今日の人間が生み出されたのではない。この後、幾度もの試しが為された。 | |||||||
このことが「み神楽歌の序歌」で次のように詠われている。
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
| 【れんだいこ版元の理一括文その2、試し編】 |
| 31 | 宿し込みも、産まれ出しも、月日親神のお働きによる。子種は、三年三月の間、母親「いざなみ」の胎内に留まり、実に七十五日かけて子数のすべてを生みおろされた。 | |||||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||||
| 32 | 出産の様子は、「み」が泥海の砂地をみつけては子を生み、「み」が生むと「うお」が寄って一人一人の子に息をかけたと云う。今に諺にも「親の息勢かからぬと子は育たない」と云われる所以がここにある。その、人間が生みおろされたあとに今日土地ところにお宮ができたので産土神と云われる。 | |||||||||
| 33 | まず、おぢばの周りの奈良、初瀬7里の間を7日かかって産みおろし、残る大和国を4日にて産みおろし、山城、伊賀、河内三カ国を19日にて産みおろし、合わせて30日かかって子供の半分が産み下ろされた。残る国々に45日かかって産みおろした。それ故に、75日を帯やと云う。 | |||||||||
| 34 | だが、この時産み落とされた子は一様に五分と小さく、このものは五分五分と成人して九十九年生きた後、三寸になったところで、全てこの世から出直し(死去)していった。 | |||||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||||
| 35 | この時父親「いざなぎ」も身を隠すことになった。 | |||||||||
| 35 | こうした経過を見て、月日両神の工夫と思いが更にかけられた。親神様から一度教えて頂いた守護により「いざなみ」の胎内に又、前と同じ子供が同じ数だけ宿った。「いざなみ」は次の出産に向かった。十月経って産み下ろされ、再び九億九万九千九百九十九の子を産んだ。 | |||||||||
| 36 | このたびは日本国中に産みにまわり、同様に生んだ子に息をかけていった。その時の生みおろしのあとに、いま日本国中の墓地(はかち)ができている。これは五分より始まり、五分五分と成人し前より大きく三寸五分まで成長したが、やはり九十九年生きた後、全てこの世から出直し(死去)していった。 | |||||||||
| 37 |
こうした経過を見て、神の工夫と思いが更にかけられ、「いざなみ」は次の出産に向かった。結局三度出産した。 |
|||||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||||
| 38 | 三度目も、同じ数の子種を宿し十月経って産み降ろした。三度目の産み下ろしは原地に為され、その場所は、土地ところの参り場所となっている。「一宮・二墓・三原」と云われて、それぞれ人間の参り所となっている所以がここにあり、みな元の理に因縁のある場所だということになる。今度は更に大きく四寸まで成長した。 | |||||||||
| 39 | 「いざなみ」はにっこり笑うと、「これまでに成人すれば、いずれ五尺の人間になるであろう」と言い残して身を隠すことになった。三寸から始まり三寸五分、四寸と次第に大きくなった人間の成長に手ごたえを感じとられたからであった。 | |||||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||||
| 三度目の子供も「いざなみ」の後を慕うようにして出直し(死去)していった。 | ||||||||||
| 40 | ここまでの月日親神のお働き、それによるご守護は並大抵のことではなかった。このことを深く知り、感謝申し上げるのが人の道である。 | |||||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||||
| 41 | こうして人間の命は十全の守護によって生かされている。その身体は神の貸し物と心得るべきである。大事に扱い使うのが人の道である。これを貸し物借り物の教理と云う。 | |||||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
| 【れんだいこ版元の理一括文その3、道中編】 |
| 42 | その後、人間は長きにわたり生まれ変わりの旅に出向くことになった。この間様々な虫や鳥や獣畜類に生まれ変わり、実に八千八度の転生を繰り返すことになった。 | |||||||
| 43 |
その果てに、一匹の「めざる」がこの世に生まれた。これに神名が付けられ「くにさづち」と云う。この「めざる」が身ごもった。その胎内から男五、女五の生命が産み出された。この新たな人間は最初五分から生まれ出て、五分五分と次第に成人していった。 |
|||||||
| 44 | この成長に応じるかのように、自然環境も整い始めた。子供が八寸になった時、初めて泥海に高い低いができ始めた。一尺八寸になる頃には泥海も漸く固まり、海と山、天と地が区別できるまでになった。 | |||||||
| 45 | その後、人は一尺八寸から三尺になるまでに、一腹に男一人女一人の二人ずつが生まれて行くことになった。次いで、三尺に成人した時、初めて言葉を話せるようになり、一腹に一人ずつ生まれるようになった。そして、次第に五尺の人間へと辿り着くことになった。この間、実に九億九万年を水中で暮らしていた。 | |||||||
| 46 | 人間が五尺に成人したときは、人間の住むに都合がよいように、海山、天地、世界もはっきりとできあがった。そこで水中の生活をやめて、ここに漸く陸上がりを果たせるようになった。現在のような陸上生活はそれ以来のことである。 | |||||||
| 47 | 人間は三尺から五尺になるまで、食物(じきもつ)を食いまわり、唐天竺まで廻り行くことになった。この間、五尺に成人するまでに、この世界、天地海山、食物までもが人間の成人に応じてできた。 | |||||||
| 48 | しかし、これでも人間の完成が為されたのではない。陸に上がった人間は六千年間、智恵の仕込を受け、三千九百九十九年間、文字の仕込を受けることになった。 | |||||||
| 49 | これが元始まりであり、月日親神は、人類を我が子と思い気にかけている。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 50 | 月日親神は、人類が心勇んで陽気づくめに暮らすことを願っている。心がいずまないよう諭している。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 51 | こうして創造された人間であるのに、月日親神の思惑から外れて心得違いで道を踏み外している。月日親神は、「人間創造の元一日」に立ち返るよう促している。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 52 | 月日親神は、心得違いを埃と諭し、日々の掃除で払うよう諭している。 | |||||||
このことがお筆先では次のように誌されている。
|
||||||||
| 53 | 月日親神はこたび、中山みきを神の社(やしろ)と定め、親神の思いを「元始まりの理話し」として説き聞かせることになった。 | |||||||
| 54 | 月日親神は、生みの子らが、人類の故郷であるぢばの地で、甘露台を中心として踊る一手一つの神楽づとめをすることで、神の理を味わい、親神の心に添って生き直すよう諭している。 | |||||||
| 55 | 月日親神は、親神の諭しを聞き分け、聞き分けた者が親神の願う神人和楽の陽気世界への世直し、世の立替えに向かうよう促している。 |
(これは参考文であり、今後どんどん書き換えられていきます)
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)