| 「おじばは、泣くところやないで。ここは喜ぶところや」。 |
| 「ぢば一つに心を寄せよ。ぢば一つに心を寄せれば、四方へ根が張る。四方に根が張れば、一方流れても三方残る。二方流れてもニ方残る。残ったところに太い芽が出る」。 |
「187、ば一つに」。
| 「明治十九年六月、諸井国三郎は、四女秀が三才で出直した時、余り悲しかったので、おぢばへ帰って、何か違いの点があるかも知れませんから知らして頂きたい、とお願いしたところ、教祖は、『さあさぁ小児のところ、三才も一生、一生三才の心。ぢば一つに心を寄せよ。ぢば一つに心を寄せれば、四方へ根が張る。四方へ根が張れば、一方流れても三方残る。二方流れても二方残る。太い芽が出るで』、とお言葉を下された」。 |
|
「191、よう、はるばる」。
| 「但馬国田ノ口村の田川寅吉は、明治十九年五月五日、村内二十六戸の人々と共に講を結び、推されてその講元となった。時に17才であった。これが、天地組七番(註、後に九番と改む)の初まりである。明治十九年八月二十九日、田川講元外八名は、おぢば帰りのため村を出発、九月一日大阪に着いた。が、その夜、田川は宿舎で、激しい腹痛におそわれ、上げ下だし甚だしく、夜通し苦しんだ。時あたかも、大阪ではコレラ流行の最中である。一同の驚きと心配は一通りではなく、お願い勤めをし、夜を徹して全快を祈った。かくて、夜明け近くなって、ようやく回復に向かった。そこで、二日未明出発。病躯を押して一行と共に、十三峠を越え竜田へ出て、庄屋敷村に到着。中山重吉宅に宿泊した。その夜、お屋敷から来た辻忠作、山本利三郎の両名からお話を聞かせてもらい、田川は、辻忠作からおさづけを取次いでもらうと、その夜から、身上の悩みはすっきり御守護頂いた。翌三日、一行は、元なるぢばに詣り、次いで、つとめ場所に上がって礼拝し、案内されるままに、御休息所に到り、教祖にお目通りさせて頂いた。教祖は、赤衣を召して端座して居られた。一同に対し、『よう、はるばる帰って下された』、と勿体ないお言葉を下された。感涙にむせんだ田川は、その感激を生涯忘れず、一生懸命たすけ一条の道に努め励んだのである」。 |
|
「道三郎氏の話(その四)、ねをうしなうても とらん」 。
| 「熊吉は、明治十年ごろから、おぢばへお詣りに行き、ひのきしんもつとめさせてもらっていました。それで高井直吉、宮森与三郎さんらとは、一つ鍋のものを食べた仲間だったのです。高井、宮森のお二人はおぢばにつとめ、奥野熊吉は大阪へ出て働きました。しかし、道の為、神さまの為を思う心に変わりありません。お道も大きくなり、世界との交渉が盛んになると、それなりに応法の道も通らねばなりません。だが熊吉は、御存命の頃のままの信仰です。だから、時にはあんなことしてと思うこともあったようです。ある時、私に、ご本部のある先生のところへ手紙を出せといって聞きません。私も困りまして、どうしたものかと思い、街の易者に占てもらいました。これは、神前に刀を抜く珍しい卦(け)や。例えいかなる理由があろうとも、神にお仕えするものに太刀振ったら、天罰覿面(てきめん)といわれますで、と注意されました。それで書かんでいますと、もうお前に会わんといって、自分の隠居所へかえってゆきました。そのあと間もなく警察から電話がかかって、熊吉が電車にはさまれて怪我をし、病院へ運ばれているから、すぐ来いといって来ました。行ってみると、父は包帯にまかれて、真白になっていました。だが元気でした。オレが間違っていた。神さまにお詫びしているね。ご本部のやり方について不足をもっていたことは私の間違いだった。神さまはな、根をうしなうても、とらん、と教え下された。たとえおぢばの建物が藁屋であっても、入母屋であっても、ぢばの理は一分一厘の狂いがないと仰せられるのだ。ぢばは人間の生れ故郷、神さまのお心のこもっているところ、一分一厘のくるいもないのだ、それを忘れていた。神さまは、このことを教え下さろうとして、私の身上にお知らせ下された。もう、いいね、家へかえるわ、と言って父は病院を出、家にかえりました。教祖のお話し『世界中で、人間をこしらえたところは、ここより他にないで。あるというなら尋ねて行ってみよ。神はいつでも行司に立っているで』」。 |
|
清水さんが中山玉恵さんより聞かせて頂いた御話し「お屋敷に勤める者の心構え」、昭和十三年九月号みちのとも御母堂様追悼号「印象深き数々のお言葉」清水くにゑより。
| 「或る時、お前の様なつとめ方でどうする。縦横十文字に勤められる位置にいるのやから、もっとしっかりつとめにゃならん。教祖様は、『この屋敷へは二代三代なおその上の従兄弟・はとこ迄連れて帰ってある、引き寄せてある』、と仰った。『因縁なくて、このお屋敷につとめさして貰う事はできん。しかしつとめ方によっては一代ぎりの者もある。また二代三代の理の者もある。また末代の理の者もある』、と仰せられた。勤めさせて頂こうと思えば、どんなにも勤めさせて頂けるのだから、もっとしっかりとつとめよ、と諄々とお仕込みを頂きました」。 |
|
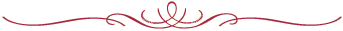
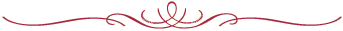
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)