| 第95部 |
1970年~ |
昭和45年~ |
その後のお道の歩み |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元)年.9.24日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「天理教が教派神道連合会を退会し神道と決別」以降の歩みを確認しておく。
2007.11.30日 れんだいこ拝 |
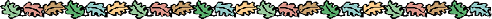
| 【天理教が教派神道連合会を退会し神道と決別】 |
1970(昭和45).4.30日、天理教が教派神道連合会を退会し、神道と分かれた。中山慶一表統領が「神道ではない」と宣言。
|
大西玉が、岡山市神崎町のほんぶしん本部の西部神屋敷で逝去。
8.30日、天理教青年大会(東京会場)が武道館で開催される。2万5千人が参集する。
教祖90年祭の前年、韓国には約70万人の信者と約2千ヶ所の教会、大統領公認の大韓天理教団が作り上げられていた。ところが、教祖90年祭直前に、かんろだいを撤去し、明治教典式御目標(鏡その他神道一式用具)を祀れ、命令が下され大混乱に陥る。その後数年のうちに信者が十分の一に激減。
この年、日蓮正宗の国教化をめざす創価学会の政教一致路線が世論の批判を浴び、公明党との「政教分離」を表明する。
| 1971(昭和46)年 |
「一日修養会」始まる/災救隊発足 |
|
1.26日、少年会本部年頭幹部会におけるお話し。
|
「親(理の親)という言葉で言い表されるお方は、親神様しかおられないということなのであります。 親(理の親)という言葉で意味するお方は、教祖以外にはおられないということなのであります。(中略)
私たちの親(理の親)は、親神様・教祖以外におられないのです。私たちがその〈親という〉言葉を用いましても、真の底から親(理の親)になってしまってはいけない」(みちのとも
昭和47年3月号 所収)。
|
|
|
| 1974年、八島英雄氏が天理教本嬬原分教会会長就任。 |
| 1975(昭和50)年 |
西ドイツで天理教展覧会開催 |
| (宗教界の動き) |
| この年、斎藤年男が天理神乃口明場所系から造反し、甘露台霊理斯道会を打ち出している。 |
| 【教祖90年祭】 |
|
1976(昭和51).1.26日、教祖90年祭執行。
|
| 【天理教本部が「稿本天理教教祖伝逸話篇」を出版】 |
| 天理教本部が「稿本天理教教祖伝逸話篇」出版される。教祖が温(あたた)かな親心をもって道人を教え導かれたお言葉の逸話二百編を収録している。 |
|
| 同年3.25日、八島氏が「私の教理勉強」を出版。1977年、東京教区世田谷中央支部長に就任。 |
この年、渡辺秀子がほんみち天理三輪講系から造反し、神之打分場所を打ち出している。
| (宗教界の動き) |
| 「靖国神社国家護持貫徹国民協議会」が「英霊にこたえる会」へと改称。 |
|
| 1978.4月、八島英雄氏が天理教本部批判を展開する。 |
|
| 昭和34年に出版されていた芹沢光治良氏の「教祖様」が善本社版で出版される。平成7年10版。 |
| 【元天理教本嬬原分教会会長の八島秀雄が櫟本分署跡保存会を発足させる】 |
1979年、当時の天理教本嬬原分教会会長の八島秀雄氏が1970年代後半に教団批判を展開し始め、この年、櫟本分署跡保存会を発足させ代表となっている。八島氏の履歴は「八島教学事件考」に記す。
「保存会について」の櫟本分署跡保存会趣意書は次の通り。
| 天理教教祖中山みき様が立教四十九年(明治十九年)二月十八日(陰暦正月十五日)から十二日間三月一日まで拘留された最後の御苦労の場所「大阪府奈良警察署櫟本分署跡」は九十余年の風雪にさらされ老朽化がすすみ今にも崩れ落ちそうになっていました。立教百四十二年(一九七九年)二月二十五日天理教本嬬原分教会八島英雄を代表者とする同憂の士が櫟本分署跡保存会を結成し全国の教友知己に復元修理、資金カンパを呼びかけて保存運営をはかり、二年後ようやく復元修理が完成しました。それに並行して崩壊寸前となっておりました当時の倉庫一棟を改修して「櫟本分署跡参考館」を開設し、教祖に関するあらゆる資料の収集に努めてまいりました。教祖のひながたを理解して教祖の思召に添う陽気づくめの世界を建設するためには、教祖御在世当時の時代背景、教祖の教えと当時の国家政策との違いから生じた迫害弾圧の歴史に学ぶことが大切だと考え参考館を解説したわけです。さらに教理の正しい理解と認識をすすめ教祖の真実の姿を知って伝道への意欲の昂揚を進めるために、教理講座の開設、史跡見学会、資料解説研究会を行ってまいりますうちに、資料の保存室や複製コピー場、納得のいくまでねり合う研修室、国々所々までへもたすけ行く教育活動の研修活動の研修資料館建設が必要になって参りました。世界中一れつは皆兄弟やと万人たすける道を教えられた教祖のひながたを辿り、一人残らずのものが喜べる陽気づくめの世界を建設するための世直しをしていく同志をつのり一人でも多くの方々の御賛助を得たいと念願しております。
|
|
6月下旬、天理教教会本部が、三島町に対し、三島神社移転を正式要請した。この日、天理教役員代表の内統領の中山正信(天理教真柱の分家筋)、真柱室長の喜多秀義、表統領の清水国雄の三氏が当時の三島区長/稲田利也氏の自宅を訪問し、三島神社移転の申し入れを行った。
宗教界で初めて里親会を結成した。その後、名称が天理教里親連盟と改称する。
| 【里親会結成】 |
| この年、天理教は宗教界ではじめて里親会を結成し(その後名称を天 理教里親連盟と改称)、今では唯一天理教だけに宗教系里親会が存在する。近年の虐待児童の増加に伴い家庭的養護の必要性が叫ばれる中、その担い手である養育里親(養子縁組を前提にしない里親)の世界では、天理教里親が15
~ 20%を占めているという。世間で養育里親や専門里親(被虐待児童等に特化した養育里親)の重要性が認識され、その法整備が行われる以前から、天理教では「おたすけ」の精神によってそれらがすでに実践され、むしろ行政の方が後追いしてきたと言えよう。 |
|
| 「57年12月23日、郡山大教会(奈良県)の部下教会である広島県の�竜安芸分教会長が広島市信用組合大河支店に押し入り、やはり現行犯で逮捕されているのである」。(「天理教・その堕落と悲劇」p21) |
|
|
| 「東西礼拝場の建設や、百年祭の準備に忙しい昭和59年1月5日の早朝、本部直属教会長たちによる年頭会議が開かれる、おめでたい日を選んで、長崎県の肥長大教会長が天理詰所(宿舎)で首吊り自殺をはかったのだ」。(「天理教・その堕落と悲劇」p20) |
| 「昭和59年5月28日、船場大教会(大阪市)の部下教会である埼玉県の大請分教会長が、東京・足立区の平和相互銀行千住支店(当時)に包丁を持って押し入り、強盗傷害の現行犯で逮捕されている」。(「天理教・その堕落と悲劇」p21)) |
| 「同じ年(昭和59年)の10月25日、今度は山名大教会(静岡県袋井市)の部下教会である静岡県の鮎��ケ瀬分教会長が天理の山名詰所で飛び降り自殺をはかった。この日は、東西礼拝場落成の日であり、前日には親神(人間創造の神)が人間を宿し込んだ地とされるぢばの証拠であるかんろだい(甘露台)据えかえの儀が行われ、翌日は秋季大祭という天理教の三大慶事が重なった、とりわけおめでたい日であった」。(「天理教・その堕落と悲劇」p20) |
|
|
| 「60年の春ごろから一部関係者の間で問題視されていた、いわゆる中野大教会(滋賀県)問題であった。親教会の教会長の自殺未遂、ヤクザの介入など、話題は多いが、すべての原因は詰まるところカネに対するルーズさんあった。中野大教会問題とはいえ、問題をおこしたのは、部下教会である。つまり、中野大教会傘下に南濃分教会(岐阜県)があり、その部下に浪越分教会(愛知県)がある。問題はこの浪越分教会で起こった。浪越分教会の会長であった山田晴久氏は、(中略)いわくつきに人物であった。今回の問題の発端は、もともと彼が信者のために墓地の造成を手がけることに始まったのだが、墓地管理だけでは事業的に赤字が増えるばかりで、どうしようもないため、さらに不動産を手がける傍ら、ヘルスセンターをつくるというように、事業の幅を広げていったことであった。だが、しょせん素人のやること、(中略)59年までは、その借金も12億ぐらいだったらしい(中略)その結果、借金のカタに、浪越の部下教会までが担保に入れられ、責任を感じた親教会の南濃分教会長が自殺未遂をするに及んで、問題が表面化してしまった。そして、昭和60年3月半ば、浪越の部下教会長ら十数人は、天理教本部へ押しかけ、真柱が帰ってくるところを待ち受けて、”直訴”に及んだのであった。そこで、彼らは土下座して、浪越分教会長の不始末のせいで、自分たちの教会が担保に入れられているという窮状を訴えたのである。この浪越分教会の借金は、最終的には58億円に及んだといわれるが、そのうちの約40億円がいわゆる「悪しき金融業者からの金」だったと見られている。本来であれば、いくら本部で直訴などしても、本部が救済に入ることなどないのだが、この件に関しては、借金の取り立てに、ある暴力団が間に入って動いたこともあって、本部がその借金を肩代わり、暴力団に金を渡して、騒ぎを食い止めたといういきさつがあった。天理教本部は、その上で、中野大教会以下の各教会長を罷免、それ以上、問題が表面化しないようにしたのであった」。(「天理教・その堕落と悲劇」p97) |
| 「中野問題以後、本部は心配になって、全国の大教会の借金の有無の総点検をやった。その結果、全天理教の教会の借金は、中野大教会を除いて、約100億円あったと言われている」。(「天理教・その堕落と悲劇」p100) |
| 「日野大教会は現在、山添理一前会長が実権を握っているのですが、この前会長についてはなにしろ袖の下を使って、上に取り入り本部役員になったと一般に噂されているぐらいで、悪い噂がいっぱいという人物なんです。この前会長時代に、日野大教会は滋賀県の山中に大きな敷地を買って、そこに大神殿を建てた。その費用を、カネに余裕のない部下教会に割り当てたのです。当時は、さらに教祖100年祭に向けて、本部へのお供えもしなければならない時期でしたから、各教会は非常に苦しい状況だったわけです。しかし、日野大教会側の言い草は決まっていて、『親のいうことはハイと素直に聞け!』という天理教の金科玉条を持ち出し、命令に逆らえば教会長の資格はないということで、クビを切られてしまう。そうなると、その教会長一家は路頭に迷うわけです。つまり、大教会に生活権まで握られているから、すべての命令に対してはイエスとしか答えられない。そこで、彼ら教会長たちは窮余の策として、自分の土地や建物を担保に入れて、金を借りまくり、サラ金や高利貸しにまで手を出さざるをえなくなる。ところが、利息も払えない。その結果、暴力団が借金の取り立てにくる。とうとう、部下の教会は逃げ場を失って、最後の手段として天理教の真柱に自分たちの窮状を訴えるために直訴したわけです」その金額が、全体で36億円であったというのだが、結局、天理教はその36億円を天理教の”御用銀行”である地元の南都銀行に立て替えさせたのである。そして、部下教会は、今度は南都銀行に、借金の返済をするという形にしてのであった。(中略)つまり部内で36億円という借金を生み、暴力団が介入、真柱への直訴騒ぎまで起きたにも関わらず、本来、そうした問題を起こしたことに対する責任が問われる山添理一前教会長は何も処分されず、逆に天理参考館�館長に就任、出世までしているのである」。 |
|
|
| 1985(昭和58).5月、真柱を中心とした本部の最高幹部が密かに三島神社移転の計画案を練っていることが判明した(「突然、神霊が出現する!」)。 |
|
| 「教祖100年祭の準備も、ほとんど終わろうという昭和60年11月7日、天理教の幹部役員(本部員)3人が、大阪国税局の税務調査を受け、合計約8000万円の脱税を指摘され、約2500万円の追徴税を課せられていたことが明るみに出てしまったのだ。つまり、本来なら役員個人の支出として計上すべき子弟の学費や結婚式費用を、非課税の宗教法人会計で処理していたというのである。当時の報道によれば、その事件の概要は、以下のようなものである。<大阪国税局の調べなどによると、申告漏れを指摘されたのは、天理教本部で教団の運営に当たっている責任役員18人のうち3人。57年から59年にかけて全国各地の教会で行なった講演の謝礼金の一部や、役員個人が関係した出版料収入などを申告していなかった。また、東京の大学に進学したり、海外留学したりしている子弟の学費や結婚式の費用を宗教法人の会計から支出し、役員個人の申告から覗いていたが、同国税局は「子弟の教育費などは親である役員の個人的な支出であり、役員に同額の所得があったものとみなすべきだ」と課税対象として認定した」。(「静岡新聞」昭和60年11月7日) |
|
| 【櫟本分署跡保存会代表の八島秀雄が造反】 |
12月、櫟本分署跡保存会代表の八島秀雄が、教会の機関紙ほんあづま202号で、教祖百年祭を機に応法の理である神道教理や儀礼を廃止し、教祖が教えた通りに「かんろだい」を目標にして各教会でおつとめを行い、みかぐらうたとおふでさきに基づいて教育せよと提唱した。翌年、教会長職を罷免されることになる。
同12.29日、表統領の代理と称する東本大教会役員三名が本吾嬬分教会へ来て、「ほんあづま」の記事は教祖の教えには合っているが、教会本部の教え「天理教教典」に外れているから、既刊の「ほんあづま」数十万冊をすべて回収して、教会長を辞任して、真柱にお詫びしろ」と迫った。八島氏は、「真柱に心配かけた事は詫びるが『ほんあづま』の回収も、教会長辞任も承知できない」と物別れになった。八島氏の履歴は「八島教学事件考」に記す。 |
この年、伊藤幸長が天理神乃口明場所系から造反し、天命庵を打ち出している。
| (お道の教勢、動勢) |
| 1985.11.24日、お社を「かんろだい」形状のもに変えることを決定し2、後にその決定を実行した。韓国社会おける反日感情が高まり、これへの対応策として、神道のお社と類似していると批判されたお社を「かんろだい」の形状に変更した。 。お社の形状変更に賛成するグループは「大韓天理教」として残り、それに反対するグル―プは「韓国天理教連合会」を結成して「大韓天理教」から離れた 。 |
| 【本嬬分教会長にして櫟本分書跡保存会代表の八島秀雄が罷免される】 |
| 教祖百年祭の直前の前年12月、「ほんあづま」202号で、教祖百年祭を機に応じる法の理である神道教理や儀礼を廃止し、教祖が教えた通りに各教会でおつとめを行い、みかぐらうたとおふでさきに基づいて教育せよと提唱したことを理由に、教団本部は櫟本分書跡保存会代表でもある八島秀雄を、本人に通告せぬまま本嬬分教会長の職を免じて他人を任命した。教団本部による教会乗っ取りであった。八島氏が教会から立ち退かなかったため、分教会長と宗教法人天理教との間で裁判が行われるという珍しい裁判が始まった。八島氏は、これを機に、教祖の教えとその伝記出版のため教会本部より独立。 |
| 【教祖百年祭執行】 |
| 1986(昭和61).1.26-2.18日、教祖百年祭執行。 |
|
| 「そのおめでたい百年祭も終わりに近づいた昭和61年2月14日、天理教本部にとって由々しき事件が起きたことは、ほとんど知られていない。その日、日光大教会(栃木県)部内のある教会の団参一行は、天理へのおぢば帰りを終えた後、鳥羽伏見で一泊、帰路につくことになっていたのだ。ところが、その団参の引率者が入水自殺を遂げるという事件が起こったのである。天理の本部での自殺でなかったことが、教団本部にとってはせめてもの救いであったというべきかもしれないが、自殺の原因は、地元に帰れば、また立教150年へ向けての”きりなしふしん”(お供え金)が待っていると思うと、家路に向かうのが憂うつであり、その苦労を思い悩んでの結果であったと関係者の間では囁かれている」。(「天理教・その堕落と悲劇」p26) |
|
| (宗教界の動き) |
| 中曽根康弘首相は靖国神社参拝を見送り、「元A級戦犯の合祀は相手国を刺激する」と発言。 |
|
| 「昭和62年1月26日、立教150年を10ヶ月後に控えた春季大祭に、天理を訪れたブラジルからの団参の責任者が、翌27日、拳銃密輸容疑のため岡山市内の宿泊先で手入れを受け、拳銃数丁と実弾数発を押収されるという事件が起きたのだ。その日流れたテレビのニュースでは、天理教の名前こそ出なかったが、事件を知らされた天理教本部関係者・M氏は、『拳銃に限らず、海外の天理教関係者による密輸は、そう珍しいことではない』と指摘した」。(「天理教・その堕落と悲劇」p30) |
| 「2月18に日午後9時35分ごろ、東京都葛飾区にある天理教本田分教会から出火、木造平屋建ての同教会兼住居のうち、教会部分(70平方メートル)を焼き、高山朝治分教会長(76)と長男のプレス工・節男さん(55)の二人が焼死するという事件があった。翌日の「読売新聞」には、本田署の調べとして次のように書かれていた。<出火場所は、教堂とトイレの境付近とみられるが、火の回りが異常に早く、二人が焼け死んでいる場所が不自然などの点があり、同署できょう19日現場検証して調べる>その結果、本田分教会では、その火災の前にも出火があり、そのときは近所の人たちが消火器を持って駆けつけ、火を消したため大事には至らなかったという騒ぎを起こしていることがわかったのだ。そして、近所の人たちが帰った後、改めて内側から鍵をかけ、二人は石油をかぶった後、火を放って焼身自殺をしたわけであった。亡くなった高山分教会長は、何十年もの間、上級の本畑分教会(東京)に日参するほど信仰熱心で有名だったが、上級の会長の「私たちのまことの表しようは、(本部に)おカネをお供えする以外にないんだ」という姿勢が続く中でのカネ集めに、信者たちが音を上げ、家庭内も揉め、関係者に「ホトホト、お道(信仰)も嫌になった」と漏らすようになっていたという。「火事のあった日の午後も、同じ葛飾区内の布教所に行って、”カネ、カネ、カネといわれるばかりで、もうホトホト嫌になってしまった”と、弱音を吐いていた矢先の出来事でした(東京の教会長S氏)」。(「天理教・その堕落と悲劇」p31) |
| 「カネがらみではないが、天理教関係者にとって衝撃的だったのが、62年6月5日、香川県木田郡の天理教本田中分教会・佐々木徳雄教会長(49)が修行のため小屋に監禁していた女性(22)を死に至らしめたという事件であろう。地元の「四国新聞」(昭和62年6月7日)には、以下のように報じられた。<A�子さんは先月ごろからノイローゼ気味となり、両親が佐々木に「娘の体の調子が悪いので、精神修行してくれないか」と頼み、先月29日にA�子さんを預けた。佐々木は教会兼自宅でA子さんの面倒を見ていたが、A子さんが品物を壊したり、走り回ることから、両親に連絡して、1日、A���子さんの手足を縛って教会東側のトタン小屋(幅2メートル、奥行3メートル)に閉じ込め、外から施錠。食事は佐々木や両親が運び込み、きちんと食べさせていたが、最近は食欲がなくなり、牛乳やプリンなどを与えていた。佐々木が5日午後7時すぎ、様子を見たところ、A子さんがぐったりしていたので119番通報した。調べに対して佐々木は、「両親から相談を受け、精神修行するためA子さんを預かった。しかし、A子さんが走り回って危ないので、けがをしてはいけないと思い、両親に話して小屋に入れた」などと自供。同署(高松東署)では、さらにA子さんを閉じ込めていた5日間の詳しい状況などを聴いている>彼女の両親は20年ほど前からの天理教信者で、本田中分教会に通っていたという。ちなみに、彼女が閉じ込められていた小屋は、ふだんは物置として使用されていたもの。当時、香川県では30度を超える真夏日が続いており、彼女は急激な脱水症状を起こしたとみられている。直接の原因は急性心不全であった」。(「天理教・その堕落と悲劇」p34) |
|
|
| 1988(昭和63)年、天理教祖百年祭後、天理教本部が、本部神殿東前にあった三島神社を本部神殿東前から三島町のはずれに移転させた。この経緯につき、天理教真柱を取り巻く極く一部の本部員が極く秘密裏に練り上げ、膨大な予算をかけて準備をし事を遂行したと云われている。神社移転後、首謀者の一人の天理教教会本部内統領・中山正信本部員が出直した。数年後、教団最高責任者の真柱が身上で倒れ、8時間にも及ぶ心臓の大手術を二度にまでわたって受けられることになる。もう一人の首謀者である真柱室長・喜多秀義本部員も、神社移転後、時を経ずして脳溢血で倒れ再起不能となった((「突然、神霊が出現する!」))。 |
1990年、大本教の三代教主・直日が死去。以降、本部(四代教主聖子)・大本信徒連合会・宗教法人愛善苑の三派に完全分裂(第三次大本事件)した。
| 【清水国雄/天理教表統領証言】 |
| 1991年5.31日、清水国雄/天理教表統領が、東京地方裁判所に於ける証言で、「櫟本分署跡で教祖のひながたの真実を明らかにすることは天理教の信仰の根幹に関わる」、「櫟本分署跡の修理保存は、天理教信仰の根幹に関わるから、させることはできない」と述べた。続いて「八島教学を公式に異端と言った者は一人も居ない。真柱を始め、教会本部の教義及び史料集成部も、天理大学、天理教校等公式機関で八島を異端と言った者は居ない」と述べ、この発言が、本部に帰って他の本部員たちに責められ、憩の家病院で静養する身となった。 |
| 【芹沢光治良出直し】 |
1993.3..23日、芹沢光治良永眠(享年96歳)。
「芹沢光治良文学館」
http://www.hi-ho.ne.jp/kstudio/kojiro/
|
芹沢光治良 (セリザワ・コウジロウ)(1896-1993)
1896(明治29)年、静岡県沼津市我入道に生れる。第一高等学校から東京帝国大学経済学部を卒業。在学中高等文官試験に合格。卒業後、農商務省に勤めるが官を辞してフランスのソルボンヌ大学に留学。卒業論文完成直後、結核に倒れ、フランス、スイスで療養生活を送る。1930(昭和5)年、帰国して書いた『ブルジョア』が綜合雑誌「改造」の懸賞小説に当選して作家生活に入る。『巴里に死す』、『一つの世界――サムライの末裔』など多くの著書があり、大河小説『人間の運命』で日本芸術院賞、芸術選奨を受賞。日仏文化交流の功労者としてフランス政府からコマンドール(文化勲章)を受章。日本ペンクラブ会長、ノーベル文学賞推薦委員などを務めた。1986年から、毎年書下ろし小説を刊行。1993(平成5).3月、死去。 |
|
| 1994年、証人として出廷した永尾広海本部員は、「八島は『みちのとも』連載当時から異端だ、私が罷免した」と罷免の正当性を述べた。が、「二十五年前のゲラ刷り原稿を目の前に突き付けられて、青くなって立往生し、心臓の不調を訴えて、憩の家病院に逃げ込んだ」。 |
| 1995(平成7)年 |
阪神・淡路大震災救援活動/おつとめ復元50年 |
|
| 1995.4月、結審。八島に対する立退き要求の訴えは東京地裁で却下の判決が下った。本部の控訴はなく結審した。(詳細は「八島教学事件考」に記す) |
| なお、並行して、櫟本分署跡保存会、事務局長川本しづ子が会長をつとめる本常一分教会も、審判会も行なわず会長罷免して裁判になったが、罷免申立てした東本大教会長中川うめ子が証言台で立往生して、東本大教会長と処分した天理教代表役員表統領が謝罪金を出して和解した。現在は東本大教会より独立し、教祖直属の本常一分教会長川本しづ子になっている。 |
| (お道の教勢、動勢) |
| 9.28日、永尾廣海本部員の死が報ぜられた。 |
1997(平成9).1.26日、「国々の教会で教祖の教えたかんろだいつとめ」と真柱指針する。
憩の家で、ひのきしんを行おうとする人たちの受け入れ窓口として「ひのきしんセンター」が設置された。外来受診者の車いすの介助や受付手続きの援助、入院患者への移動貸し出し図書サービス、環境美化などの活動が展開されている。
| 【教祖誕生200年祭執行、中山善司が4代真柱就任】 |
| 4.18-4.26日、教祖誕生200年祭執行。最終日の4.26日、「真柱継承式」が行われ、3代真柱の長男中山善司が4代真柱となる。先代真柱が健在なうちの真柱継承は初のケース。かんろだいつとめの指針行われず。
|
1999(平成11).3月、天理教教会本部が、天理教教会本部神殿の東側に隣接する元の三島神社の宮池であった鏡が池を埋める。鏡が池は、教祖が親神と人間との板挟みになって苦悩の揚げ句、何度も身を投げようとされた逸話で知られる教理上重要な遺跡である。これを埋めたことになる。何の必要があり埋めたのか定かでない。
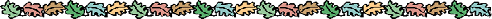



 (私論.私見)
(私論.私見)
