
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.12.17日
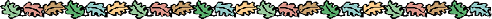
2月、松村吉太郎が、内務省社寺局の呼び出しで東京へ向う。
| 【、お指図】 |
3.6日、お指図。
| 「不自由の処たんのふするはたんのふ、徳を積むといふ、受け取るといふ、これ一つ聞き分けにやならん」。 |
|
| 【、お指図】 |
3.9日、お指図。「松村吉太郎の伺い」。
| 「さあさあ尋ねる事情々、事情は余儀なく事情尋ねる。どうしてかうとも云えん。今の道、事情重なりてから、叉一つかうと云う。まあ一時のところ、見合して、さあ暫くと云う」。 |
| 「さあさあ事情は定めておいて、事情は暫くと云う。精神の理を定めて、一寸暫くと云う」。 |
|
| 【、お指図】 |
3.10日、お指図。「教祖御霊殿本部北寄りで六間に八間の建物建築致し度きにより願……続いて願い」。
| 「さあさぁまあ/\十年経っても、未だ教祖建家無いとは更々思うな。心掛けるまで親里という/\。親は子思うは一つの理、子は親を思うは理。この理聞き分け。何でもぢばという理が集まりて道という。親の内は地所さい拡がりたら十分。建家住家して居りても、多くの子供戻るぢばのうてはどむならん」。 |
|
3.10日、教祖御霊殿建築願いが出される。本席は、「足伸ばすぢばをつくれ」と指図し、却下する。その意は、「5年祭の時には農家を借りて納屋に藁を敷いて寝たではないか、その信者達が不自由しないように、足を伸ばして居られるように、教理をゆっくり学べるように、信者の詰所を造れ」というところにあった。これにより詰所建設が始まることになった。
| 【、お指図】 |
3.18日、お指図。
| 「身の内の障り、痛み悩みは、神の手引きと諭したる。さあさあ楽しめ楽しめ」。 |
| 「澄んだ道から澄んだ心が鏡やしき。澄み切ったもの、曇りあっては世界映ろうまい。少しでも曇りあっては、世界は丸曇り」。 |
|
| 【、お指図】 |
5.5日、お指図。
| 「指図は神がするのや。人間の理を以て諭するやないで」。 |
|
| 【、お指図】 |
5.13日、お指図。
| 「いかなる事も神一条の道、神一条の理を立てるという事は前々諭したる」。 |
|
| 【、お指図】 |
5.22日、お指図。
| 「夜も寝られん程会議しても(指図通り)用いねばどうもならん。旬が来たなら刻限と言う、刻限は旬を外さんための刻限」。 |
| 「刻限いつともわからん筆に止めた理より便りにさへすれば何も云(い)うことはないなれど、刻限の指図くるくる巻いておいてしまい、紙の色のかわるほど放っておいてはどうもならん」。
|
| 「扉を開いての働き、一代ではあろうまい。後々続いて又代という。後々代、それなくばなろうまい」。
|
|
| 【、お指図】 |
6.4日、お指図。
| 「皆、指図用いらねば一つ治まらん。又屋敷合わんようでは、とても/\一つ世界治められん」。 |
|
| 【、お指図】 |
8.3日、お指図。
| 「神一条の道では功を積んだ者がそれだけの理という。楽々の道は未だまだ早い」。
|
| 「この屋敷高い低いの区別はない」。
|
|
8.19日、お指図。「藪の北方田地一町三反余買い入れる事御許し下さるや願い」。
| 「さあさぁ尋ねるところ/\、地所/\という。一時大望と言うである。大望と言うや大望なれど、成る時成らん時一つ、一つ成る時見分けて、無理にどうせい言わん。成る時成らん時、そこで旬と言う。一つ年を待って事情という、多くの中戻り来る。地所狭い。これは追々指図以て運ぶ。それはどうせにゃならんと聞かし難くい。長い心/\これだけ/\年限経てばこれだけ、又これだけと言う。又一時事情というは小首を傾げて事情。そこで話す/\、今年に出けねば又来年。無理してはならん/\。年々あちら一寸こちら一寸大きい成る。皆大木の大きく成るようなもの。これだけ一寸指図しておこう」。
|
「押して、買い入れは御許し下されますや」。
| 「さあさぁこれは強(た)ってと言うは許さんではない。数々ある。年限経ったらふしから芽が出る。無理は一寸も出けん。無理してはどうもならん」。
|
|
| 【、お指図】 |
9.15日、お指図。
| 「あちらこちら眺め、義理を思うからどうもならん。神一条の理と人間と人間の理をよう聞き分け。人間の理を病んで神の理を欠いてはならんという」。
|
|
| 【、お指図】 |
10.11日、お指図。
| 「(神が)入りこんで話をすれば、人が代わりてあるだけやで。理は同じ一つの理である」。
|
| 「何でも彼でも伝わる理を拵えておかねばならん。神の指図という。皆な同じ事を諭すのや」「又後々続く理を拵えておかねばならん。続かんような事では、この道遅らすか、曇らすかの道より見えやせんで/\」。 |
|
| 【、お指図】 |
10.14日、お指図。
| 「さあさあ余儀なく事情である。最初ほんの掛かり、十分これで十分と思うた日がある。あちら狭うなる、人々こちらどうする、あちらどうする、地所一条運びがたない。余儀なく事情、地所替えて、旬を見て、心に任せおこう/\」。
|
|
|
| 「私(※中山もと様)の祖母は教祖の長女である”おまさ”さんでした。”おまさ”さんは、私の数え十七歳の時に出直されました(明治二十八年十月二十七日、陰暦九月十日)。”おまさ”さんは男まさりの明るい元気な人でした。お酒も多少いけました。教祖は”おまさ”さんのお酒のいけるところから、『絹糸のくだはまいても、き綿(ぼろ綿)のくだはまくのやないで』とお笑いになったそうです」。(「くだを巻く 」、平成五年十月発行「教祖の御姿を偲ぶ 改訂新版」上村福太郎(道友社新書)159ページより) |
|
| 【神道応法派と教祖派が紛糾】 |
| 11.13日、10年祭の直前のこの日、会議が開かれ、真之亮、平野樽蔵ら神道応法派が再度神社を造りたいと主張した。山本利三郎、上村吉三郎、中田かじら教祖派は、お指図を楯にこれに反対した。会議は紛糾し、休憩となったその時、突如として山本利三郎が亡くなった。 |
| 【、お指図】 |
11.13日、お指図。
| 「大層要らん、子供ずつないめはすっきり掛けん。ずつなみは見て居られん。皆心に嬉しいすれば嬉しい受け取る。受け取る理は世界成程と言う」。
|
|
| 【、お指図】 |
11.14日、教祖十年祭が近づくに当たり、改めて「教祖のご普請お許し願」が出され、これに対して、次の「お指図」が為されている。
| 「親という、子供という、子供十分さして親が楽しむ。子が成人して親が大切、楽しみと楽しみ、という」。 |
| 「どうでもこうでも、地所集め掛けたるところ」。「未だ不都合やで々」。 |
| 「先々育てて成人したら、どんなところからどういう事出けるら知れやせん。(中略) もう十分子供成人したなら思うようになる」。 |
(お許しになられなかった)。「教祖殿はひながたの学び舎である。建ち家もそのまま、便所もそのまま、風呂場もそのまま、それが狭いと云うなら、仕える者の詰所を造れ」との指図となった。教祖殿を神社式に大きく造り変えることを禁止した。
|
|
| 「山田伊八郎先生は、『お道に議論なし』と仰せられた。明治二十八、九年、上村吉三郎会長逝去されてのち、教紀紊乱(きょうきびんらん)というても差し支えない混沌たる時代で、ときどき議論がましいことがあったが、先生は一向に相手にせられず、席を立ちて避けられたのが例であった。『人の気のたったときに、話したところが無益や、心静まりて初めて聞えるのや』と語られた。いつも遠大な精神で快活に通られたのである」。(元敷島理事・森井熊吉記)「道に議論なし」、道友社新書15「先人の遺した教話(三)根のある花・天理教敷島大教会の二代会長/山田伊八郎」134-135p) |
|
| (道人の教勢、動勢) |
| 1.21日、上田嘉治郎が出直し(亨年66歳)。天保1年(1830)、大和国山辺郡園原村(現・奈良県天理市園原町)生まれ。明治9年(1876)、娘・ナライトの病をきっかけに入信。 |
11.24日、山本利三郎の死後10日目、上村吉三郎(敷島の初代会長)が出直し(亨年58歳)。
(詳解は「上村吉三郎」に記す) |
| この頃、中田かじ(仲田儀三郎の妻)も遺体で発見された。 |
| 中山おまさ。文政8年(1825)生まれ。教祖の長女。豊田村の福井治助に嫁ぐが、明治11年(1878)復籍、分家。1895(明治28)年、出直し(享年71歳)。 |
| (当時の国内社会事情) |
| 1895(明治28).8.6日、台湾総督府条例制定される。第一回帝国議会。教育勅語の発布。 |
| (宗教界の動き) |
| 平安遷都1100年記念に平安神宮創建。祭神は桓武・孝明天皇。 |
| 府県社以下神職登用規則。日清戦争戦死者合祀招魂社臨時大祭。 |
| 内村鑑三『余は如何にして基督信徒となりしか』。 |
1895(明治29)年、教派神道連合会(略称「教派連」)が「神道同志会」として発足した。当初の加盟教団は出雲大社教、御嶽教、黒住教、實行教、神宮教、神習教、神道大成教、扶桑教。その後、1899(明治32)年に神道本局、神理教、禊教が加盟して名称を「神道懇話会」と変更。さらに1912(明治45)年、金光教、神道修成派、天理教が加盟して「神道各教派連合会」と改称した。1934(昭和9)年、名称を「教派神道連合会」と変更して今日に至っている。その間、加盟・退会・名称変更・解散する教団があり、現在では出雲大社教、大本、御嶽教、黒住教、金光教、實行教、神習教、神道修成派、神道大教、神理教、扶桑教、禊教が加盟している。目的は「神道教化の活発な展開を図り、道義に基づく、文化日本の建設に寄与して、世界平和の確立に貢献すること」(規約第4条より抜粋)で、2月、8月をのぞく毎月の定例理事会をもって活動を進めている。
また教派連に加盟している教団の若手リーダーが中心になって活動している「教派神道連合会青年会議」は、1990(平成2)年に「教派神道連合青年会議」として発足し、1996(平成8)年から現在の名称を冠している。その目的は、それぞれの教団の垣根を超えて次世代を担う人たちが交流することによって、教派連の目的を達成するための自己啓発、相互啓発をはかるところにある。この教派連青年会議が中心となって、1995(平成7)年には教派連結成100年の記念イベントが開催された。その年の5月、記念式典・祝賀会。同11月、記念シンポジウム「21世紀を担う神道」開催。その結果の一端は「教派神道連合会結成百周年記念誌『いのりとつどい』」に結実し、全国の主要図書館などに寄贈された。(「教派神道連合会」参照)
|
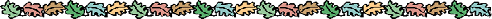



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)