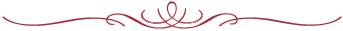
| �i���[�h�j�L�a���܂ł̃��V�A�Љ�^���j |
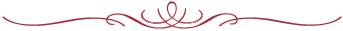
�@�X�V���^�Q�O�Q�P�i�����R�P�D�T�D�P�h�a�����^�h�a�R�j�D�U�D�Q�T���@
�@������ȑO�́A�u���}�m�t�����v�ɋL���B
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
|
�@���c���Y���́u���V�A�v���j�i�͏o���[�V�Ёu���E�̗��j�v�V���[�Y�̈���Ƃ��Ė{���𐢂ɏo���ꂽ�̂́A���ł��P�X�V�O�N�j�i�u���́u���c�{���V�A�v���j�v�ɓ]�ځj�A�u�f�J�u���X�g�̗��v���Q�Ƃ���B�i�����ǂݎ�蒆�ł��j |
| �y�u�X�e���J�E���[�W���iStenka Razin�j�̗��v�̉e���z |
| �@�܂��A�u���[�W���̗��v���m�F���Ă����B���[�W���̐������́A�u�X�e���J�i�X�e�p���j�E�e�B���t�F���B�`�E���[�W���v�ŁA�ʏ́u�X�e���J�E���[�W���v�Ɖ]����B�P�U�R�O�H�`�P�U�V�P�N�ݐ����A�P�U�U�V�N�C�܂������h����n���̊J��_�����Ђ����Ĕ������������A�ꎞ�̓J�X�s�C�k������т��́B�̂����{�R�ɂ�Ԃ�A�Ƃ炦���ď��Y���ꂽ�B���V�A���w�u�X�e���J=���[�W���v�̎�l���ł���A���V�A�̔_�������w���҂Ƃ��ď̂����Ă���B�u���[�W���̗��v�ɏڂ����̂ŊT�v�͂���ɏ���B �@�u���[�W���̗��v�Ƃ͗v����ɁA�P�U�S�X�N�A�A���N�Z�C��i�P�U�Q�X�`�V�U�j�������ł̔_�z���̋����ɑ����R�̗��ł���A�R�T�b�N�̎Љ�I�s�����ق���`�Ő��{�ɋ|�����������ƂɂȂ�B�h����A���H���K�삩��J�X�s�C�ɏo�����A���V�A�݂̂Ȃ炸�T�t�@���B�[���y���V�A�Ƃ�������B�P�U�V�O�N�ȍ~�̐킢�́A�_���A���H���K�여��ٖ̈��������h���@�l�E�`�����@�V�l�E�o�V�L�[���l������������Ƃɂ��A����܂ł̗��D�ړI�̖쓐�W�c���甽���͎v�z����b�ɂ��������R�ւƕω����A�_���푈�ɔ��W�����B �@�������A���ǂ͐��{�R�ɒ�������A���[�W�����d�҂̓��X�N���Ɍ쑗���ꃂ�X�N���̐Ԃ̍L��ŗ���A������ؒf���ꂽ��Ɏ��藎�Ƃ��ꏈ�Y���ꂽ�B�P�U�V�P�D�P�Q�D�Q�U���A�c�}����������A���[�W���̗��͏I�������B�X�e���J�E���[�W���͌��͂ɗ������������p�Y�Ƃ��ď̂����邱�ƂɂȂ�A�u�X�e���J�E���[�W���̉́v�Ƃ��Č��`����Ă������ƂɂȂ����B |
| �y�t���[���[�\���̐N���z |
| �@�P�V�S�O�N�A�����V�A�̃C�M���X�l�W�F�[���Y�E�P�C�X���R���A���V�A�n���̃O�����h�}�X�^�[�ɂȂ�A���X�N���ƃy�e���u���N��n�ՂɃt���[���[�\���v�z�y�����Ă������B���g���n�p���Ƀt���[���[�\���ɓ���Ă����s���[�g�����̌䐢�ł���A�s���[�g�����̗����̂��Ƃɕz���������s��ꂽ�B �@�P�V�T�O�N�A���U���Ă������[�\���x���ꂷ�邽�߁A���X�N���Ɂu���E�f�B�X�N���V�I���v���b�W���ݗ����ꂽ�B �@����G�J�e���[�i�Q�����A�[�֎v�z�̉e���ŁA���[�\�����y�Ɉ�����B���̉e���ŁA�M����R�l�̑��������[�\�����ɂȂ����B �@�P�V�X�S�N�A�t�����X�v���u�������ČN�吧�̊�@���������G�J�e���[�i�Q���͋}篁A�t���[���[�\���S���b�W�������悤�������B�P�V�X�V�N�A��ʂ��p�������q�̃p�[���F���P�������[�\���֎~�߂߂����B���̂R�N��A���[�\�����ł��郄�V�����B����݂�̃O���[�v�ɈÎE�����B �@�P�X���I�����A�A���N�T���h���P�������ʂ��A���[�\�����͂̋����|�[�����h�����_���邽�߁A�������[�\���֎~�߂������B |
| �y�i�|���I���̉ʂ����������z |
| �@�P�W�P�Q�N�A�i�|���I���R�����X�N���ɐN���B �i�|���I���R�̗D�����œy��p�ɂ���ċt�]�������V�A�R�́A�nj����ă��[���b�p�ɂ��������B���Z�ł������M���N�́A�����̖ڂŐꐧ���������ꂽ�������݂��B�t�����X����h�C�c������R�ɂ���ׂ��M���́A���̂Ȃ��Ŏs���̎��R��m�����B���V�A�͉��Ƃ��������ꂽ�����B���̂܂܂ł́A���̓Ɨ����₪�Ă��₵���Ȃ�B�ꐧ�����Ɣ_�z���͔p�~���˂Ȃ�ʁB�푈��������ċA�������M���N�����́A���v�ɂ��đ��k���������B�u�ꐧ�����Ɣ_�z���͔p�~�v�������e�[�}�ƂȂ����B |
| �y���V�A�ł̔閧���Ђ̓����z |
| �@�P�W�P�U�N�A�u�~�ϓ����v�Ƃ����閧���Ђ��y�e���u���N�ɂ���ꂽ�B���S�ɂȂ����̂́A�j�L�[�^�E�������B���t�i�P�V�X�Q�|�P�W�U�R�j�A�Z���Q�C�E�g���x�c�R�C���݁A�A���N�T���h����������B���t�E�A�|�X�g���Z��A�A���N�[�V�L���i�P�V�X�R�|�P�W�T�V�j�Ȃǂ������B
��������߉q�t�c�̏��Z������M���ł���B�̂��ɁA�I�����t���R�A�~�n�G����t�H�����B�W���A�p�[���F����y�X�e��(�P�V�X�R�|�P�W�Q�U)�炪�Q�������B �@�ނ�͂�������i�|���I���푈�̎Q���҂ŁA�푈�̂��Ȃ��ɔ_���o�g�̕��ɐڂ��Ă��̔ߎS�Ȑ����̎����m�����B����ƂƂ��ɊO�����Ƀ��V�A�Ɣ�ׂ�ꡂ��ɐi��ł��鐼�������̐����E�Љ�����������B��������ނ�͗�����ꂽ�c�����V�A�́q�~�ρr������Č��Ђ�������B �@�P�W�P�V�N�A�u�~�ϓ����v�̖�Q�O�O�������X�N���ɉ���āu���������v�Ɖ������A�K��u�݂ǂ�̏��v���������B����̓h�C�c�����I�N�̐����I�Ȕ閧���Ёu�g�D�[�Q���g�u���g�v�̋K����Ă����������̂������B����͊v���g�D�̋K��Ƃ�����蔎���N���u�̋K��ɋ߂������B �@�ނ�͔_�z���Ɛꐧ�̔p�~�Ƃ����_�ł͈�v���Ă������A�����̃��V�A�������N�吧���{�s����̂��A����Ƃ����a���ƂȂ�̂��Ƃ����_�ł͈ӌ��������ꂽ�B�܂���i�Ƃ��ĕ����I�N���̗p����̂��ۂ��A�I�N�̂����Ǝ����ɂ��Ă��ӌ��������ꂽ�B �@�P�W�Q�P�N�A���̂悤�Ȉӌ��̑���ƁA���������̌��Ђ̑��݂ǂ̃X�p�C���@�m���Ă���A���̓����̊����͐��{�ɓ������Ƃ킩���āA�����o�[�͋U�����U�����B�����ăy�X�e���𒆐S�Ƃ��������Ђƃj�L�[�^�E�������B���t�𒆐S�Ƃ���k�����ЂƂɂ킩��A���ꂼ��ʂ̍j�̂��������B �@������Ђ́A���R�Nj�̂���샍�V�A�̃g�D���`���ɖ{����u���A�y�X�e���卲�̎w�����ɏ����̃��V�A���a���̌��@�Ƃ������ׂ��u���X�J����v���E�_�v�����������̌��Ђ̍j�̂Ƃ��č̑������B�_�z���p�~�Ƌ��a���̎�����ړI�Ƃ��Ȃ���A�Վ����{�͒����W���I�ȓƍٍ��Ƃ�����B�M�⌾�_�̎��R�͔F�߂邪�A���Ђ̎��R�͂�邳�Ȃ��B�M�������������������͂���ɂ悭�Ȃ��Ƃ����B��ɂ��̌��ЂɃX���u�������̘A�M��ڎw���q����X���u���Ёr����������B �@�k�����Ђ́A��s�̃y�e���u���N�ɖ{����u���A�m�E�l�����r���t�͗����N�吧��ڎw�����@���Ă�������B�������B���t�̂��������@�̓A�����J���O���̌��@�����f���ɂ������̂ŁA�哝�̂̂����ɍc������������N�吧�ł������B������c���ƂȂ���͈̂��̎��Y�̂�����̂ɂ������A�A�M���Ɛ����Ƃ邱�ƂɂȂ��Ă����B�������Q�R�N���炱�̌��Ђɂ����C���[�G�t�A�x�X�g�D�[�W�F�t�Z��狤�a���x���҂��������A�ӌ��͕����ꂽ�B |
| �y�u�f�J�u���X�g�̗��v�z | ||
| �@�P�W�Q�T�D�P�P�D�P�X���A�c��A���N�T���h���ꐢ(1777-1825)���s�K��̃^�K�����N�ŋ}�������B�ނɂ͎q�������Ȃ������Ƃ��납��A��p�҂ɂ��ċ{��̂Ȃ��ł��߂��B�c�ʌp���������Ĉꎞ��ʂ̊��Ԃ��������B�������̒�̃R���X�^���`������͐l�]���������B��ʂɂ͂��ꂪ�c�ʂ����Ǝv��ꂽ���A����ɂ͂��̈ӎu���Ȃ������B���ǁA���̉��̒�̃j�R���C���(�P�V�X�U�|�P�W�T�T)����ʂɏA���A�V��j�R���C�P���ƂȂ����B �@���̊ԁA�O�T�Ԃقǎ�Ԃǂ����B�M���̏��Z��������Ȃ�k�����Ђ̃����o�[�͂��̊ԌR���I�ȃN�[�f�^�����킾�Ă悤�Ƃ��Ėd�c���Â炵�Ă����B�Ƃ��낪�A�X�p�C�ɂ���Ď��������̌v�悪���{�ɕ���Ă���Ƃ����\������A�����ɂ����Ĕނ�͏\���ɏ����̐���ʂ܂܌��V�@�L��ł̖I�N�����Ă����B �@�P�Q�D�P�S���A�k�����Ђ́A���V�@�Ƌ߉q�t�c���A�V��ɒ����̐鐾���������I�N�̓��Ƃ��āA�ꐧ�Ɣ_�z���̔p�����f���ĕ����I�N�����킾�Ă��B���V�A��łP�Q�����Ӗ�����f�J�[�u������ɏ\�}���i�f�J�u���X�g�j�Ɩ��t�����A�u�f�J�u���X�g�̗��v�Ɖ]����B���V�A�ł̏��߂Ẵc�A�[�ɑ��镐���I�N�ƂȂ����B �@�w���������́A��s���������A��������ĉ�����B�I�N�ɓ��ӂ����̂́A�x�X�g�D�[�W�F�t�̎w�����郂�X�N���A���̖C���Ɨ�������킹�ĂR�O�O�O�l�������B����ɑ��āA���{���Ɏc�����R���͂X�O�O�O�l�����B�����R�̓l���@�͔Ȃ̌��V�@�L��ɕ��w���Ђ��Đ����B�����R�͗L�\�Ȏw���҂��������B���w��������͂��������g���x�c�R�C�̓I�[�X�g���A��g�قɓ����A��Ƃ̎��l���C���[�G�t���E���������邾���������B �@�����R������ɂ����y�e���u���N���~�����[�h���B�b�`�A�X�`���������i�ߊ��͔������ɂ���ĎˎE����Ă��܂����B���Ƀj�R���C�ꐢ�͓��������ӂ����B���S�ȖC�����n�܂����B�����R�͏����|��A���ł̔���l���@�͔Ȃ̐Ⴊ���ɐ��܂����B�����͎��s�ɏI������B �@������Ђ����܂������Ȃ������B�P�Q�D�P�R���A�����Ńy�X�e�����ߕ߂��ꂽ�B�P�Q�D�Q�X���A�ނɑ����Ďw���ɏA�����Z���Q�C�E�������B���t�E�A�|�X�g���̗�����P�O�O�O�l�̃`�F���j�[�S�t�A�����I�N�������A�D���Ȑ��{�R�ɂ���ĊȒP�ɒ������ꂽ�B �@�I�N�̒�����ʖ@�삪����A�T�V�X�l�������ōق��ꂽ�B���������M���ɑ���R��Ə����͌������A�j�R���C�ꐢ���݂�����u��ɓ��������B�w���҂̃y�X�e���A���C���[�G�t�A�������B���t�E�A�|�X�g���A�x�X�g�D�[�W�F�t�E�����[�~���A�����ă~�����[�h���B�b�`���ˎE�����J�z�t�X�L�[�̂T�l�͍i��Y�A�d�J���Ȃ�тɏI�g�Y�R�P�l�A�L�����Y�W�T�l�������B�����̎҂��V�x���A�k�Y�Ȃ������Y�ƂȂ����B�����Ɋ֘A������Ƃ��đߕ߂��ꂽ���̂͂T�O�O�l�����B �@�P�W�Q�U�D�S���A�j�R���C�P���́A���������[�\���֎~�߂z�����B �@�h�C�b�`���[�́u���V�A�v���T�O�N�v�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
|
| �y�u�f�J�u���X�g�̗����̌�̔g��v�z | |||
|
�@�ނ�̌��ǂ��ĂX�l�̍Ȃ��M���̐g�������Y���̂Ăĕv�̌��ǂ��A�V�x���A���������B�Ȃɂ��������ꂽ���̌����������Ȃ��o�▅�́A�{����͂Ȃꂽ��A�S�������肵���B�������Q���������āA���Y�n�ɂ����āA�����Ō����̎����������t�B�A���Z�������B�V�x���A�̃f�J�u���X�g�̒��ɂ́A���犈����w�p�����ɗ�ގ҂������B�E�E�E�ނ炪���͂��ă��[���b�p�E���V�A�ɖ߂邱�Ƃ������ꂽ�̂͂T�U�N�̂��Ƃł���B
�@���l�A���N�T���h���S��v�[�V���L��(�P�V�X�X�|�P�W�R�V)�́A�V�x���A�ɂ���F�l�ɂ͂��܂��̎��𑗂����B
�@�V�x���A�̗��Y�n����I�h�G�t�X�L�[������ɂ��������B
|
| �y�v�[�V���L���ƃf�J�u���X�g�z | |||||||||||||||||||||||||||
�@���V�A�̓V�ˎ��l�v�[�V���L���̓f�J�u���X�g�Ɛe�����Ă����B�v�[�V���L���͂��̎��l�Ƃ��Ă̊��o����ꐧ�̏d���������Ă����B�y�e���u���N�łP�W����Q�P�܂ł��A���ƕ����̂Ȃ��ɂ������Ȃ���A�v�[�V���L���͂���̐���̐��_���A�������̎��ɂ��������B
�@�Ƃ����u���R�̎^�́v�͐N�����̈����̎��ł������B �@�v�[�V���L���́A�F�l�������閧�̌��Ђ������Ă��邱�Ƃ͒m���Ă����B�������A����͂����ĉ������Ȃ��������A�F�l���������������Ȃ������B���ɐ₵���v�[�V���L���̍˔\��F�l�����͈��ɂ����̂��낤�B�@���������͂̑��͗e�͂����Ȃ������B�ӂƂǂ��Ȏ��������N���A���{�̓y�f���u���N����샍�V�A�̐A���n�ی�ǂɓ]�������B�J�����W���A�W���R�t�X�L�[�瓖��̎��l�ł���A���c�F�C�̋����ł��������l�����̌��Y�����Ȃ�������V�x���A���肾�����B���l�͔������R�[�J�T�X�̕����̂Ȃ��ŁA�����Ɨ��̑���������Ȃ���w���X�����ƃ����h�~�[���x�w�o�t�`�T���C�̕����x�������A���w�G�t�Q�[�j�C��I�l�[�M���x�ɂƂ肩�������B���܂��܃I�f�b�T���烂�X�N���̗F�l�ɂ��Ă��莆�̂Ȃ��Ŗ��_�_�Ɏ^�����邱�Ƃ��������̂��]���ɂȂ��āA�Ɗ�����ăI�f�b�T����ǂ��A�~�n�C���t�X�R�G�ɂ������B�����Łw�{���X��S�h�D�m�t�x������ꂽ�B �@�f�J�u���X�g�̖I�N�̒��O�A�v�[�V���L���͗F�l����y�e���u���N�ɂ���悤�Ƃ̎莆�������ďo�������̂����A�����̗��R�łЂ��������Ă��܂����B�����\��̂悤�ɗ����Â�����A�v�[�V���L���͖I�N�̑O��A���C���[�G�t�̉Ƃɂ����͂��������B�@���R�ɂ���ĖI�N�֎Q�����Ȃ��������A�ߕ߂��ꂽ�f�J�u���X�g�̏����i�̂Ȃ��ɁA�v�[�V���L���̎��������Δ������ꂽ���Ƃ���A����͓}���ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A����߂Ċ댯�Ȏv�z�̎���ł���Ƃ��ꂽ�B �@�j�R���C�P���̓v�[�V���L�������₵���B�P�W�Q�U�D�X�D�W���A���X�N���ɂ����v�[�V���L���͍c��̉��䏊�ł���`���[�h�t�m�@�ɏo�������B�����ŁA�c��ƃv�[�V���L���̌����肪�ׂ��ꂽ�B
|
|||||||||||||||||||||||||||
| �y�x�����X�L�[�́u�N�w���ȁv�z |
| �@�f�J�u���X�g�^�����傫��������V�A�̕����J���^���ł������B���̍��A���Y�m�`���c�B�ƌĂ�钆�Y�K���o�̒m���l�w���o�����������B�M���o�̃f�J�u���X�g�⊯����q�t�̎q����Ȃ郉�Y�m�`���c�B�B�́A�ꐧ�����Ɣ_�z���̔p�~���\�z�����B���̗���́A���V�A�̌[�ւƃq���[�}�j�Y���^���ƂȂ����B�ނ�́A���V�A�̒x�ꂽ�F���Љ�����������B����ɁA�����I�����`�ɓ��ۂ����B�u�ǎ��Ɛ��`�̖@���A�_�z���̔p�~�Ƒ̔��̋֎~�A�@�̌����ȓK�p�v��ڎw�����B�x�����X�L�[�A�Q���c�F���炪����������n�߂��B �@�ނ�́A���[���b�p�̃��l�T���X�̑�����������낤�Ƃ��Ă����B����͂����ăs���[�g�����̑I����������̓��ł������B�����A�x�����X�L�[�̓s���[�g�����D���������B����𐼉��h�Ɖ]���B�����A�s���[�g�����m�肵�Ȃ��l�������������B�s���[�g���͈ȑO���炠�����ǂ����̂��Ă��܂����B���V�A�̕s�K�͂�������͂��܂�Ƃ����B���ꂪ�X������`�ł���B �@�P�W�R�U�N�A�`���A�_�[�G�t(1794-1856)���A�u�e���X�R�[�v�v���Ɂu�N�w���ȁv�\�����B�`���A�_�[�G�t�͂��ČR�l�������M���ŁA�f�J�u���X�g�I�N�̂Ƃ��A���܂��܍��O�ɂ��Ĕ����ɉ����Ȃ������B�h�C�c�ŃV�F�����O�ƌ�F�ł������قǂ̊w���������B�u�N�w���ȁv�́A���V�A�̉ߋ��͋ł���A���݂͑ς��������A�����͑��݂��Ȃ��B���V�A�͐�������Ǘ����Ă������߁A�u���Ɨꑮ���痝���̋�Ԃ��ł����̂��ƌ������B�f�J�u���X�g�ȗ��A���V�A�̂Ȃ��Őꐧ�ɑ��邱��قǂ͂����肵�������͂Ȃ������B����͈Ŗ�ɂЂт����ꔭ�̏e���̂悤�ɒm�I���V�A���o���������B�`���A�_�[�G�t�͍c��ɂ���ċ��C�Ƃ���A�������̂������Ȃ��Ɩ�����ꂽ�B �@�u�N�w���ȁv�́A�����h�ƃX���u�h�̑Η��̂��������ɂȂ����B���V�A�̏����������̐i����ǂ��̂��A����Ƃ����V�A�Ǝ��̓���i�ނ̂��́A����Ȍキ�肩�����_������邱�ƂɂȂ�B�A���A�������悭�m���Ă���҂̕����������ăX������`�҂ɂȂ����ʂ�����B�x�����X�L�[�����̒��O�Ƀh�C�c�ɍs���������ŁA�h�C�c����t�����X����悭�����Ȃ������̂ɑ��A�X������`�҂̃L���[�t�X�L�[�̓h�C�c�œN�w���w���A�z�~���R�t�̓p�������������B���h�͓����T�[�N���Œ��ǂ��_�������Ă������A�ǂ�����_�z���ɂ͔��������B�ނ����T�ɑ̐��Ɣ��̐��Ɗ��肫���đΗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ⴄ�̂́A�X���u��`�҂��L���X�g�҂������̂ɑ��A�����h�̑��������_�_�҂��������Ƃ��B |
| �y�Q���c�F���̎Љ��`�z | |
| �@�Q���c�F��(1812-70)�́A�ꐧ���V�A����S���̎��R���߂ĒE�o�����B���̂Ƃ��Q���c�F���͐����h�������B���[���b�p�e�n�Ŕނ́A���V�A�ł݂��Ȃ����R���y���ޘJ���҂ɋ��ق̖ڂ����������B�܂���N�������P�W�S�W�N�̃��[���b�p���v���̔g��ނ̓C�^���A�̊e�n�ƃp���Ō����B�p���ł͎Љ��`�ƃu���W���A���Ό������B�u���W���A�̏����ɔނ͐�]�I�ɂȂ����B�u���W���A�̎��R�ȍ��̋��a���Ƃ����̂́A�l�Ԑ��̑r���ł͂Ȃ����B�Q���c�F���͎v�����B���V�A�̓��[���b�p�Ƃ͈��������i�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ꐧ�����̔ے肪�Љ��`���Ƃ���A���V�A�̎Љ��`�͐V�����Љ��`�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����̓��[���b�p����x��Ă��邪�A���ꂾ�����R�Ȃ̂��B �@�Q���c�F�������[���b�p����u�c���L�^�v���ɏ��������������̌��t�́A���ネ�V�A�̊v���Ƃɋ��ʂ����M���ƂȂ����B���V�A�̎Љ��`�̓��[���b�p�̂���Ƃǂ����Ⴄ���B���V�A�ł͎Љ��`�̒S���肪�_���Ȃ̂��B���[���b�p�̎Љ��`�����̒S����Ƃ��ăv�����^���A��������܂łɂ͐F�X�Ɖ�蓹���������A���V�A�ł͓��͂܂��������B�Љ��`�̌����͔_�������̂̂Ȃ��ɐ����Ȃ��炦�Ă���B�u���V�A�ւ̐M���������I�j�ł��玄���~���Ă��ꂽ�̂��v�i�w�t�����X�ƃC�^���A����̎莆�x�j�B �@�P�W�S�S�N�A�j�R���C�P���́A���_���l���������̂̃J�n���X���x�̔p�~�����݂��B����ɂ��J�n���X�Ƃ������O�͌`���I�ɏ��������A���x���̂͑��������B���V�A��ƃt�B���[�h���E�h�X�g�t�G�X�L�[�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�P�W�T�O�N�A�Q���c�F���ɑ��ċA�����߂��o���ꂽ�B���A�Q���c�F���͂�������ۂ��Đ��U�̖S���҂ƂȂ����B���F�I�K�����t�ƈꏏ�Ƀ����h���Ɏ��R���V�A�����������A�G���w�|�������i���A�Y���F�Y�_�x�i�k�ɐ��j�A�V���w�R�[���R���x�i���j�s���A�ꐧ���{�����e���A���V�A�����ʼn��������Ă��鎖����֎~���ꂽ�����f�ڂ����B�����͔閧���[�g�Ń��V�A�ɉ^�т��܂�A�����̓ǎ҂��������B �@�u�����h���X���u��`���v�Ƃ����_���́A���̂����Ƃ����W�J���ȕ����œ��ꂳ�ꂽ�B����䂦�A�Q���c�F���́A�X���u��`�҂�K�D�A�N�T�[�R�t�����Ƃ��A�w�R�[���R���x����ɂ��̎��𓉂�ŏ������B���V�A�̎Љ��`�̓Q���c�F���ɂ���đb��u���ꂽ�̂ł���B |
| �y�w���^���̔g�z |
| �@���̊ԁA�w���̓���������̂����Ƃ��q���ȃo�����[�^�[�ƂȂ����B�P�W�U�O�N�ォ��W�O�N��܂ł̂P�O�N�Ԃ͌[�ւ̎���ƂȂ����B �@�P�W�U�P�N�A���{�͑�w�̎��R�𐧌�����@���߂��B����ɂ��A�����W��֎~���ꂽ�B���Ɨ��̖Ə����傫����������A�e�w���ɂ��Q���Ƃ��ꂽ�B��w���ǂ́A���̋K���u�����v����������̂����߂�����B�X�D�Q�R���A�y�e���u���N��w�Ŋw���̑�W������ꂽ�B�Ɗw�������͑��ނ�g��ŁA��w�̖���o���B���ꂪ�A�y�e���u���N�ɂ�����ŏ��̊X���f���ł������B�l�t�X�L�[��ʂ���f�������B�R���Ɗw���Ƃ̏Փ˂���������悤�Ƃ��Ă����w�����������w�������́A��w�ʼn��߂Ęb�����������邱�Ƃɂ��āA�w����擪�ɂ��Ĉ����Ԃ����B��w�ł̘b�������͂����A�w���͌R���̏o�������߂��B�����̑ߕߎ҂��o���B�ߕߎ҂̎ߕ���v�������w���́A����ɏW����������B �@�������đ�w�����͎n�܂����B�U�Q�N�͂قƂ�ǂ̊w���������ꂽ�B��w���ĊJ�����̂͂Q�N��̂P�W�U�R�N�̉Ă������B���̊ԁA�w�������͂������̎���u�`���������B�I�n�A�w���̉^�����x�����Ă����u�T���������j�N�i������l�j�v���̕ҏW���`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�͎���u�`�̑���₾�������A���ǂ͋����Ȃ������B�X���Q�R���̊w���W��ɁA�C���w�Z�̐��k�����������āA�R���ɂ��K����W���Ă��ꂽ�C���w�Z�̋����������t�����҂��ꂽ���A��������ǂ̔��ɂ������B�w���^���ɂǂ������ԓx���Ƃ邩�ɂ���Ēm���l�����̎v�z�͊w���ɂ���ăe�X�g���ꂽ�̂��B �@�P�W�U�R�N�̃|�[�����h�i�������V�A�̂ł������j�v���ɂ���āA�ɂ킩�Ƀ��V�A�̖����ӎ������܂����̂ɏ悶�Đ��{�͊w���^�������������B������̎����ƈ����ւ��Ɋw���̎����͊��S�ɒD������ꂽ�B�w���^����������邱�Ƃɐ��{�͐����������A���̊w���^�����琬�����Ă������̂��A�₪�Đ��{�����������ƂɂȂ�B |
| �y���l��M�D�~�n�C���t�̐錾�r���u�Ⴂ����ցv�z | |
�@�P�W�U�P�D�X���̂�����A�y�e���u���N�s�X�̍L������ǂɁu�Ⴂ����ցv�Ƒ肷��錾�r�����\��ꂽ�B�r���͖��炩�ɑ������N�����Ă���w�����˂���ď�����Ă����B�u�N�����A�l���̎w���҂�v�Ƃ����Ăт����ŁA�r���͌N�吧�̔p�~��i�����B
�@�_�z����̔N�ɏo���ꂽ���̊v���錾�́A����Ȍ�̊v���j�̂̃L�[�m�[�g�ɂȂ����B���̐錾���������̂́A�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�̊w�F���������l��M�D�~�n�C���t��N. �V�F���O�[�m�t�ł���B�錾�̓����h���̃Q���c�F���̈�����ō����A�~�n�C���t���g�ɂ���č����Ɏ������܂ꂽ�B �@���̈ꕔ��������R�X�g�}�[���t�^�͑�O���i����@�ցj�ɔ閧�����B�~�n�C���t�͑ߕ߂��ꂽ���A���u�V�F���O�[�m�t�ɗ݂��y���Ȃ��悤��������̍s�ׂ��Ɓu�����v���A�P�Q�N�̋����J���ƃV�x���A����̔������ė��Y�n�ɑ���ꂽ�B�V�F���O�[�m�t�v�Ȃ͎��������߂��Ƃ��ăV�x���A�ɍs���A�P�T�N�𗬌Y�n�ő������B���炾�̏�v�łȂ��~�n�C���t�͂P�W�U�T�N�Ɏ��B |
| �y�u�_�z���p�~�v�z |
| �@�P�W�U�P�N�A�u����c��v�A���N�T���h���Q���̂��ƂŔ_�z�����p�~���ꂽ�B���̔w�i�ɂ́A�_�ƎЉ�̋}�i�I������ڎw���i���[�h�j�L�^���̗������������B�ނ�́A�v���̎�͂�_���ƌ����āA�u�y�n�Ǝ��R�v���X���[�K���ɂ��u�l���̒��ցv�������t�Ƃ��Č[�֎�`�I�^����g�D���čs�����B �@���̖@�߂ŁA�_�z�͉�����ꂽ���A�_�z�ɓy�n����ɓ�������ł͂Ȃ������B�ނ���A������ꂽ�_�z�́A�k�����߂̓y�n����ɓ���悤�Ƃ��đ��z�̎؍���������A���v����l�i���n�z����_��œy�n���L�I�ɍk�삷��z��I����l�j�A�ق��l�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̏�Ԃ��A���V�A�̐l����O�鐭�^���ɋ�藧�Ă�k���n�ƂȂ����B |
| �y�v�������`�҃`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�z |
| �@�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�����̓����̍ō������I���_�I�w���҂ł���A���[�j���ɂ������e����^���Ă���B�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�́A�_�z����߂��o��ȑO����A����͔_������̎�ɂ�邱�Ƃ�����Ă���A�ꐧ���{�ɂƂ��Ċ댯����܂�l���������B�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�͓N�w�A���j�A�o�ϊw�ɂ��Đ[���w�B�������A�w�����ォ��t�����X�Љ��`�ɐG��āA���V�A�̏����ɂ��Ă��A���������Ƃ����W�J���ȍl���������Ă����B �@�Q���c�F���͂P�W�U�Q�N�܂ŁA���V�A�ł���߂č����]���Ă������A���R��`�҂Ƃ̌�F����̋c��̂��Ƃł̐������A�ނ����Ȃ艸���Ȏv�z�̎�����ɂ��Ă��܂������炢������B���̓_�Ŕ_���̕����I�N�����҂��Ă����`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�́A�}�i�h�̂Ȃ��Ő�ΓI�ȐM�����������Ă����B���������v�z���`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�͌��R�Ə������Ƃ͂ł��Ȃ��������A�_���I�N���A�s�[�������閧�̕������ނ̎�ɂ����̂Ɗv���Ƃ̂��ׂĂ��M���Ă����B �@�P�W�U�Q�D�V���A�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�͑ߕ߂���A�y�g���p�����v�NJč��Ɏ��Ă��ꂽ�B�Q���c�F���ƘA�����Ƃ������ƁA�閧�̕����𗬂������ƁA���t�̈Ӑ}�����邱�ƁA�Ȃǂ��ߕ߂̗��R���������A�ǂ�����I�ȏ؋����Ȃ��A�X�p�C�̋U�ɂ���čٔ��͂Ƃ�����ꂽ�B�P�W�U�S�D�T���A�������������ĂP�S�N�̋����J���ƃV�x���A���Y�����܂����B�����Ƃɑ��錩�����߂Ƃ��āA�s�S�̍L��Łu���������D�v�������Ȃ�ꂽ�B �@�����Ń`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�͏����u�����Ȃ��ׂ����v���������B�ނ���єނ̎��͂̊v���Ƃ����f���ɂ����v���}���҂̕���ł���B���̏����͂��ꂩ�牽�\�N���̂������v���Ƃ̍��E�̖��ƂȂ����B���҂��܂�����̐^���ɑ��Đ����ł���A�Ɋ��̃V�x���A�ʼn��x���A�]������A���Ă��Ƃ���ꂽ���A����Ƃ��ĉ����Ȃ������B��]���̃`�F���k�C�V�F�t�X�L�[���V�x���A�̍����ŕǂɌ������Ė{��ǂ�ł���Ƃ������Ƃ��A���̎����ɂ���Ċv�����u���N���܂��̂������B�������v���̐��҂��A�͂邩�̋��̉Ƒ�����N�ɂP�|�Q��̕ւ肪��������́A����E��ŋ����Ă����Ƃ����B �@�P�W�W�X�N�A�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�͑ߕ߈ȗ��Q�V�N�Ԃ�ɂ���ƃT���g�t�ւ̋A�҂������ꂽ���A�ނ̑S�G�l���M�[�́A��R�̂��������Ŏg���ʂ�����A�̋��łS�J������������͂����c���Ă��Ȃ������B |
| �y�j�R���C�E�Z���m�E�\�����B�G�[���B�`�́u�y�n�Ǝ��R�v�z | |
| �@�P�W�U�O�N�̏��߂ɁA�����h���̃Q���c�F���̂Ƃ���֎Ⴂ�j������Ă����B�Q�T�̂��̒j�́A�j�R���C�E�Z���m�E�\�����B�G�[���B�`(1834-66)�Ƃ����ăy�e���u���N�̊����̎q�������B��������v���[�h���A�T���E�V�����Ȃǂ̃t�����X�Љ��`���w�сA�Q���c�F���̈��ǎ҂������B�N���~�A�푈�̔s�k�ɑ傫�ȃV���b�N�����ނ́A�����ƂȂ��ďォ��̉��v�ɑ傫�Ȋ��҂������Ă����B�������c��ւ̒��ڂ̃A�s�[���������ꂸ�A�������x�̓��ʂ̕��s�ɂ���]�����B�Љ��`�ȊO�Ƀ��V�A�̋~���͂��肦�Ȃ��Ɗm�M����ɂ��������B�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�̌o�ϊw�ɐ[����������āA�o�ϊw���w�Ԃ��߂P�W�T�W�N�Ɏ��E���ă��[���b�p�ɍs�����B�_�������̂���b�ɂ��āA���Ƃ̌o�ω����Ń��V�A���L�̑̐�������Ƃ����̂��ނ̈ӌ��������B �@�Q���c�F���ƃI�K�����t�͂��̏r�p�Ȍo�ϊw�҂ɑ����̊��҂��悹�A���V�A�̒��Ɋv���g�D�����鑊�k���n�߂��B���ꂪ�A�閧�̊v���g�D�u�y�n�Ǝ��R�v�̂��������ł���B�U�P�N�ɔ_�z����߂��o�邱�Ƃ��킩���āA�ނ͋}���ōj�̂�����͂��߂��B���M�҂̓I�K�����t�������B�������Q���c�F���͔閧�̊v���g�D�ɋC��肪���Ȃ��悤�������B �@�j�̂́A�v���̑g�D���܂��ア���Ƃ���A������c�̊J�Â̎咣�ɂƂǂ܂��Ă����B�P�W�U�Q�N�̏��߂���Z���m�E�\�����B�G�[���B�`�̓l�t�X�L�[��ʂ�ɑݖ{�����J���āA�������^���̋��_�ɂ����B�����Ƀ��X�N���A�J�U���A�m���S���h�A�y���~�Ȃǂɂ������u�T���������j�N�v���̓ǎ҂𒆐S�ɂ����T�[�N���̑g�D���Ɏ�肩�������B �@���{�̃X�p�C�Ԃ̓Q���c�F���̋ߕӂɂ������Ă��āA�����̎莆���������A�����������h�������Ƃ����m�点��œd���Ă����B�U�Q�D�V���A���̘A�����̑ߕ߂ɂ���ĂR�Q�l����������āA�u�y�n�Ǝ��R�v�̒������͒זł����B�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�̌��������̒��ɓ����Ă���B�C�^���A�̃A�i�[�L�X�g�̃}�b�`�j�̑g�D�_���̗p�����I�K�����t�̓}�K��ɂ���āA�זE�i���[�g�D�j�̂T�l�ȊO�̊��m��Ȃ��A�Ƃ����g�D�@���A�@�����悭������̂ƁA�����o�[�����Ȃ��Ĉ���������܂�o���Ȃ������̂ƂŁA�u�y�n�Ǝ��R�v�̎��͍̂����ł��悭���߂Ă��Ȃ��B�����c�����}���̒��ɂ́A�U�R�N�̃|�[�����h�����̒����ɍs�������V�A�R�̏��Z�������B�|�[�����h�����ɓ���I��`�������Ƃ����̂ŁA�R�l�̏��Z�A�����S���g�A�X�����B�c�L�[�A���X�g�t�X�L�[�͏e�E����Ă���B �@�u�y�n�Ǝ��R�v�̑g�D������čŌ�܂Ő�����̂́A�U�P�N�̃y�e���u���N��w�̃X�g�Ŋ���N�D�E�[�`����Z���m�E�\�����B�G�[�r�`�̒�A���N�T���h���������B�Z�̃j�R���C�͂P�Q�N�̋����J���̔������V�x���A�ɑ���ꂽ���A���Y�n�Ŕ�����g�D���Ȃ���P�W�U�U�N�̂Q���ɕa�����A��̃A���N�T���h���͖S�����đ�P�C���^�[�i�V���i���i���ۘJ���ҋ���j�ɎQ���������A�o�N�[�j���Ƃ��}���N�X�Ƃ��ӌ������킸�A���_�a�@�Ŏ��E�����B�u�y�n�Ǝ��R�v�̎�����̏��ł͂P�W�U�S�N�ł��邪�A�Ⴂ����̊v���ƂƃQ���c�F���Ƃ̌��ʂ̓A���N�T���h���́u�R�|���R���v�ւ̐≏�錾�ɂ���ĂȂ��ꂽ�B �@�P�W�U�U�N�̖��ɃA���N�T���h���̓Q���c�F���ƃI�K�����t�ɑ��Č������B
�@�u�y�n�Ǝ��R�v�́A�v���̐V�������オ�n�܂������Ƃ��������B |
| �y�P�X���I���V�A���w�ɋ���������z |
| �@���̎���̂P�X���I���V�A���w�Ɉ̑�ȍ�Ƃ������Ă���B�c���Q�[�l�t�A�g���X�g�C�A�h�X�g�G�t�X�L�[�Ƃ����������A���ꂼ��ɓ����̎Љ�����ނɂ��Ȃ��當�w���v�z��₤�Ƃ����\�}�Œ��삵�������B���̋��������݂͌��ɗ��ݍ����Ȃ��瓖���̐l�X�ɉe����^�����H�L�Ȏj��������ł���B �@�c���Q�[�l�t�i�P�W�P�W�`�P�W�W�R�N�ݐ��j�́A�Ⴋ���h�C�c�Ńo�N�[�j���Ɛe�����N�����Ƃ��ɂقǂ̌�F���o�Ă���B���̌��ƂƂȂ��n�����_�z�̐�����`���A���_�z���C�^��グ���B�ߕ߁A���ߌ�p���ɏo�ăt���x�[���A�w�����[�E�W�F�[���Y�A���[�p�b�T���A�]���A�S���N�[���Z���ƌ𗬂�����Ȃǂ̑��Ղ��c���Ă���B���V�A�����ƃ��[���b�p�����̋��n���̖������ʂ������B�P�W�T�T�N�A�c���Q�[�l�t�́A�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�ƃg���X�g�C�ɂ����B�P�W�T�V�N�A�c���Q�[�l�t�ƃg���X�g�C�̓t�����X�E�X�C�X�E�h�C�c�������Ă���B�P�W�U�P�N�A�m�����_�n�ψ��ɔC������邪�A�_���̌�����i��A�n��̔������A�P�N��Ɏ��C�B���̍��A�c���Q�[�l�t��K�˂邪�A�ނ̖��̎��P���Ƃ̘b��ł��̋U�P����ᔻ�������߁A�c���Q�[�l�t�����V�B���������ƂȂ�B�P�W�U�R�N�A�h�X�g�G�t�X�L�[�ɂ��ꍑ�̒����ƂƂ��čU������Ă���B��i�͂ǂ���������̎Љ������舵�������̂ŁA�P�삲�Ƃɑ傫�ȎЉ�I�����������N�������B�ߑナ�A���Y�����w�̕��Ƃ���A��\��Ƃ��āA�u�l���L�v�A�u���[�W���v�A�u���Ǝq�v�A�u�����n�v�A�Ȃǂ�����B���V�A�v���v�z�ɑ傫�ȉe����^�����B �@�g���X�g�C�i�P�W�Q�W�`�P�X�P�O�N�ݐ��j�́A�P�W�T�S�N�A�N���~�A�푈�ɏ��Z�Ƃ��ď]�R���Z�o�X�g�|���v�ǂł̐킢�ɎQ�����Ă���B��n�ł̑̌��́A�g���X�g�C�����a��`��W�J����w�i�ƂȂ�A�܂���N�̍�i�ł̐푈�`�ʂ̓y��ƂȂ����B�c���Q�[�l�t���l�ɃR�T�b�N�̐�����`�ʂ��A���_�z���C�^��グ���B�Љ�ƂɔM�S�ł���A����̔���ȍ��Y��p���āA�n���w�ւ̂��܂��܂ȉ������s�����B�g���X�g�C�̉e���͐����ɂ��y�сA���V�A�ł������{��`�ɉe����^�����B�P�W�W�P�N�A�h�X�g�G�[�t�X�L�[�̎����ɍۂ��A�ʎ��͂Ȃ��������A�e�F�ƍl���Ă����g���X�g�C�͗܂��B�A���N�T���h���R���ɕ�����ÎE�����v���Ƃ��������Y���Ȃ��悤�ɗv�����Ă�����B�ӔN�́A���V�A�������̋��`�ɐG��A�P�X�O�P�N�j��̐鍐�����B ��\��́A�u�A���i�E�J���[�j�i�v�A�u�푈�ƕ��a�v�A�u�����v�ȂǁB �@�h�X�g�G�t�X�L�[�i�P�W�Q�P�`�P�W�W�P�N�ݐ��j�́A�P�W�S�U�N�A������u�n�����l�X�v����]�ƃx�����X�L�[�Ɍ��܂���A�X������ƃf�r���[���ʂ����B���̌���z�I�Љ��`�T�[�N���̃T�[�N�����ƂȂ������߁A�P�W�S�X�N�A�����ɑߕ߂����B���Y����������A���Y�ԍۂœ��͂��^�����A�P�W�T�S�N�܂ŃV�x���A�ŕ����B���̒���́A�����L�܂��Ă����������\��`�i�Љ��`�j�v�z�ɉe�������m���K���i�C���e���j�̖\�͓I�Ȋv����ے肵�A�L���X�g���Ɋ�Â����̋~�ς�i���Ă���Ƃ����B������`�̐��҂ƕ]����邱�Ƃ�����B��\��́A�u�n�����l�X�v�A�u�߂Ɣ��v�A�u���s�v�A�u����v�A�u�����N�v�A�u�J���}�[�]�t�̌Z��v�ȂǁB |
| �y�u�Ⴂ���V�A�v�z |
| �@�v���͐��I�̉��͂������āA�l�̒��ɂЂ��ޔ\�͂������o���Ď��Ȃ�ʊJ�Ԃ������邱�Ƃ�����B�Q�O�̐N�s���[�g���E�U�C�c�l�t�X�L�[(1842-96)�̏ꍇ�������������B�P�W�S�Q�N�A�����̋M���̉Ƃɐ��܂ꂽ�ނ́A���X�N����w�̐��w�Ȃɍ݊w���A�w���^���ɎQ�����Ċv���ƂƂ��ăX�^�[�g������B�Q���c�F���ɂ���ĎЉ��`���������Ă���A���C�E�u�����A�v���[�h���A�t�����X�v���A�R�O�N�̃|�[�����h�����A�C�^���A�v���̗��j���w�B�̂��֎~�}���̔閧�o�ł����Ă���T�[�N���ɉ������A���ӂ��Ȃ����^���Ƃ��ċN���������ݓ��j�w�Z�ł̎Љ��`��`�ɂ�����������B���ꂪ�x�@�����h���S���[�R�t�̖��߂ŋ֎~�����ƁA�ނ͔_���ɓ������B �@�U�P�N�A�_���͉���߂Ŕ_��������߂������Ă����B�f���炵���A�W�����Ŕނ͔_�����X���������B�y�n�͓����N�����̂��̂ł͂Ȃ����B�n�傪���m���Ȃ��Ȃ�A���m����������ƁA�ނ�1�A���g���E�y�g���t�̂��Ƃ��ɂЂ����B�_���̒��Řb���Ȃ���ނ͔_�������ߋ����Ō����B�S����Ƃ̂������Ȃ����̂�ނ͂����Őg�ɂ����B�v���͎v�z�����̖��ł͂Ȃ��B�v���͑g�D���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_���ɂ��̗͂��Ȃ��̂Ȃ�A��������l�Ԃ���邵���Ȃ��B�@���j�w�Z�ŕs�����Ȑ�`���������ǂŁA�ނ͑ߕ߂��ꂽ�B�����A���X�N���̊č��͂������ă��[�Y�ŁA�č����ŔނɁw�Ⴂ���V�A�x���������A�O�Ɏ����o�����A��������Ă��܂����B�P�W�U�Q�N�̂T�����납��A���̃p���t���b�g�́A�^�������炷���߃y�e���u���N�ł�܂���A�}���ɒn���ɍL�������B �@�w�Ⴂ���V�A�x�͊v���}�̐錾���ł���B����͂��܂܂ŏo���ꂽ�閧�g�D�̐錾�̒��ł����Ƃ�����Ȃ��̂������B�u���V�A�͂��̑��݂̊v�����ɓ������v�Ƃ̏����o���ŁA���ܓ������s���Ă���̂́A��̓}�̊Ԃ̂ł����Ƃł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B��̓}�Ƃ͉����B��͋s����ꂽ�҂̓}�A���Ȃ킿�l���̓}�ł���B������͍c��̏��L�ɂȂ���B�l���̊v���^�������L�Ɍ������Ă���̂�m��ƁA�l���̖I�N�Ɏ����̑�\�҃c�@�[���������o���Ă���B���ꂪ�c��̓}�ł���B �@�Q���c�F���͑��h���ׂ����M�Ƃ����A�P�W�S�W�N�̊v���̎��s�ɋ����ė͂ɂ��ϊv��M���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����͌��̐���|�����߂ɂ́A�P�V�X�O�N��̃W���R�o������������������Ȃ��B���̐ꐧ�͏��B�̋��a�I�A���ɕς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̍ہA���ׂĂ̌��͍͂�����c�ƏB��c�̎�ɑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�w�Ⴂ���V�A�x�̂����Ƃ������I�ȂƂ���͌��͊l����̐��{�̐��������߂Ă���_�ɂ���B�u���{�̐擪�ɗ��v���}�́A�v���̐��������������́A���݂̐����I�����W�����i�s���I�����W�����ł͂Ȃ��j���m�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ���Čo�ϓI�A�Љ�I�����̊�b���ł��邾�����₩�ɂ��邽�߂ɂł���B�ƍٌ��͂�ێ����ĉ����̂ɂ������낢�Ă͂Ȃ�Ȃ��B���I�������{�̉e�����ɍs�Ȃ��Č��̐��̌쎝�҂����Ă͂Ȃ�Ȃ��v �@�t�����X�ŁA�P�W�S�W�N�v���̂��Ɗv�����{�͊����Ȃ��ŁA���C�E�i�|���I����I�o�����Ă��܂������Ƃ��A���̂�����ł���B���͏�����̊v���}�ƍق̎v�z���Q�O�̐N�ɂ���āA���V�A�̊v���ƂɎ�n����̂ł���B�u�Ⴂ���V�A�v�͓}�Ƃ��Đ������Ȃ��������A���V�A�E�W���R�o���̎v�z�͐����𑱂���B�U�C�`�l�t�X�L�[���Ԃ̃T�[�N���ɂ́A�₪�Ă��̗��_��听������Ⴂ�g�J�`���t�������B�U�C�`�l�t�X�L�[���ߕ߂Ɨ��Y�����肩�����Ȃ��玩���̎��͂Ɉ�Ă��T�[�N���̒�����e�����X�g���o�����A�{���V�F���B�L�ɂȂ�l����������B |
| �y�i���[�h�j�L�̒a�����̂P�A�s�[�T���t�z | |
| �@�|�[�����h�����̒����ɂ���đ̐��͈ꉞ�̈���̎���ɓ������B�y�e���u���N�̊w�������̋C���ɂ����ꂪ���f�����B�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[��h�u�������[�{�t�̋��_�������u�T���������j�N�i������l�j�v���͗����ڂɂȂ����B�w���������u�T���������j�N�v�����芷���ēǂG���́u���X�R�G�E�X���[���H�i���V�A�̌��t�j�v�������B�����ɐV�����p�Y�s�[�T���t���o�ꂵ���̂ł���B���̂Q�R�̔�]�Ƃ̓y�g���p�����v�ǂ̍�������v���l�ǎ҂̂��߂̌��e�����������Ă���̂��B��l�����͂��̃s�[�T���t(1840-68)���u����ׂ��q�ǂ��v�Ƃ������A�ނ����́A�N���Ƃ������́A�Â����́A����I�Ȃ��̂�S�ے肷��N�̗F�������B �@�s�[�T���t�͒n���M���̉Ƃɐ��܂�A�ꂩ��ߏ�Ȕ���Ĉ�����B�������猻�ꂽ�N���a�łQ�x���E��������݂��B�y�e���u���N��w���o��Ƃ����A�u���X�R�G�E�X���[���H�v���Ɋ�e���n�߂��B�h�u�������[�{�t�̓o��Ɏ��Ă������A�_�w���̃h�u�������[�{�t�ɂ���ׂāA�����ƃX�}�[�g�������B�h�u�������[�{�t�͊v���O��Ɍ�����悤�Ȓ���߂����q�ŏ��������A���R�Ȋw��M����s�[�T���t�͂���߂ė�ÂȕM�ŏ������B�ނ̓_�[�E����̐M�҂������̂��B�P�W�U�Q�N�ɑߕ߂���āA�S�N�����y�g���p�����v�ǂ̂Ȃ��ʼn߂������B�ߕ߂̌����́A�Q���c�F����i�삵�A�c�����镶�͂\���悤�Ƃ�������ł���B�m���̃X���H�[���t���R�����R��`�҂������̂ŁA�ނ͍����Œ�����Â��邱�Ƃ��ł����B �@�s�[�T���t�̎v�z�̓����́A����ւ̕��A�ł���B�v���ւ̌��g�̒��Ō������Ă��܂�������A�ނ͐N��遖��ɂ���Ď����ǂ��B�Ⴂ����̊�т́A���Ȃ̌l�I�����������̂ɂ��ウ�������Ƃ��������ɂ���Ďx�����Ă����B
�@�P�W�U�U�N�Ƀs�[�T���t�͎ߕ������ƁA���N�ăo���g�C�݂̊C������ʼnj���ł��Ď��B�ނ͉j������肾�����̂ɁA�Ȃ����������̂��낤�B����͈ˑR�Ƃ��ăi�]���B�����r�ꂽ�y�e���u���N�̊w�����������f�����ɈႢ�Ȃ��B�l���Ɛ��{�Ƃ̊Ԃɘa���͂��肦�Ȃ��B���{�̑��ɂ͐l�����炾�܂��Ƃ������Ŕ������������������Ȃ��̂ɁA�l���̑��ɂ͎v�l���A�s��������Ⴂ���オ����ƌ������s�[�T���t�̔����{�ӎu�Ǝ���̑����Ƃ��ǂ������g�D�����Ŏ������邩���A�s�[�T���t�͌����c���Ă����Ȃ������B����́A�Ⴂ���オ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ肾�����B���Ȃ̑������G���[�g�̖����Ƃ݂邩�A�O�ꂵ�����ȕϊv���i�������Ă������B |
| �y�i���[�h�j�L�̒a�����̂Q�A�C�V���[�`���z |
| �@�P�W�U�U�D�S�D�S���A�ċ{�a�̎U����I���Ĕn�Ԃɏ�낤�Ƃ����A���N�T���h���Ɉ�l�̐N���߂Â��ăs�X�g���˂����B�e�͓�����Ȃ������B��q�ɂ���ĐN�͎�艟������ꂽ�B�����̍���ɂ�����炸�A�Ɛl�͖��𖾂����Ȃ������B���h�l���A���Ă��Ȃ��Ƃ������h���̓͂��o�������ĐN�̑f�����킩�����B�h�~�g���E�J���R�[�\�t(1840-79)�Ƃ����ăT���g�t�̋M���̏o�Ń��X�N����w�𒆑ނ����j�������B�Ƒ�{���ɂ���āA���X�N���ɂ���j�R���C�E�C�V���[�`��(1840-79)�Ƃ����l���ƘA�������邱�Ƃ��킩�����B�������Ɍ������n�܂��Đ��S�l���߂炦��ꂽ�B�C�V���[�`���𒆐S�ɂ����u�I���K�j�U�[�`�A�v�Ƃ����g�D�����邱�Ƃ����������B�C�V���[�`���̓T���g�t�̏��l�̎q�Ń��X�N����w���o�Ă����B�����̊w���ƁA�u�y�n�Ǝ��R�v�̎c�}�������W�߂����̑g�D�́A�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[���V�x���A����E�������āA���O�Ŋv���w���̋@�֎����o���Ă��炤�v��𗧂ĂĂ����B �@�v���C�^�̑ޒ��̒��ɁA�s�[�T���t�̑I�������Ȏ咣�������Ƃ���A�C�V���[�`���̑I���͎��ȋ]���ł������B��͊v���̂��߂ɕ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƐM�����N���ނ̎��͂ɏW�܂����B����҂͑�w�𒆓r�ł�߂����A����҂͍��Y�̂��ׂĂ���t�����B�C�V���[�`���͂T�N��ɂ͔_���v���������ƋN����Ǝv���Ă����B���̊v���̂��߂ɂǂ̂悤�ȋ]��������˂Ȃ�ʂƐM�����C�V���[�`���͈��̃}�L���A�x���A���ł������B |
| �y�i���[�h�j�L�̒a�����̂R�A�l�`���[�G�t�z |
| �@�P�X�U�X�N�̓~�A���X�N���_�Ƒ�w�L�����o�X�̒r�Ŋw���̎��̂��������ꂽ�B�����̏e�n�ő��E�ł��邱�Ƃ����炩�������B�������ɑ{�����͂��܂�A�w�����C���[�m�t�Ƃ������Ƃ��킩�����B���҂ƌ�F���������l����������������A�����̑S�e�����������B �@�u���|���b�p�v���Ɠ����v���烍�V�A�x�������邽�ߔh�����ꂽ�l�`���[�G�t�Ƃ����j�����X�N����y�e���u���N�̊w���̊Ԃɔ閧�T�[�N���������Ă���B���̃T�[�N���͂T�l�g���P�ʂŁA���̃T�[�N���̂��Ƃ͂��������s���ł���B�T�[�N���̃����o�[���������ɔԍ��ŌĂэ��������Ŗ���m��Ȃ��B�����o�[�͗���ׂ��v���̂��߂ɂ��̏��������Ă���B�E���ꂽ�C���[�m�t�͂��̔閧�g�D�𖧍����������Ƃ����̂ŏ����ꂽ�̂������B�W�҂͑ߕ߂��ꂽ����@�̃l�`���[�G�t�͂��܂�Ȃ��B���܂�Ȃ��͂��ł���B�C���[�m�t�̎��̂��オ��O�ɔނ͍��O�ɒE�o���Ă��܂����̂��B �@���������u���|���b�p�v���Ɠ����v�ȂǑ��݂��Ȃ������B�l�`���[�G�t�̃t�B�N�V�����ɂ����Ȃ��B�������l�`���[�G�t�������Ă���u���|���b�p�v���Ɠ����v���Q�V�V�P���̓}���ɏ�����Ă���o�N�[�j���̏����͖{���ł���B�o�N�[�j���̓l�`���[�G�t�̃t�B�N�V�����Ɍ����Ђ��������Ă��܂����̂��B �@���O�Ɋv���̋��_��u�����ƍl���ăl�`���[�G�t���ŏ��ɃX�C�X�֍s�����̂́A�P�W�U�X�N�������B�ނ͎��ȏЉ��̂ɁA�閧�v���g�D�̐ӔC�҂ŁA�y�e���u���N�ƃ��X�N���ƂłQ��ߕ߂���A�Q��Ƃ��E�����Ă���Ă����̂��ƌ�����B �@���V�A�����ɂ�����v���̑ޒ��ƖS�������̂�т����ɁA�ӋC���オ��Ȃ������o�N�[�j����I�K�����t�ɂƂ��āA�l�`���[�G�t�͓d���̂悤�ȃV���b�N�������B�u���Ɋv���̉p�Y�����ꂽ�v�m�M�ɂ݂����ԓx�A�˂����߂�悤�ȉs���܂Ȃ����A�N�������������ɂ����Ȃ��I�݂Șb�p�ɁA�V�v���Ƃ����͊��S�ɂƂ肱�ɂ���Ă��܂����B�I�K�����t�͔ނ̂��ߎ��������A�o�N�[�j���͗��܂��܂܂Ɂu���[���b�p�v���Ɠ����v�̓}���������ď��������B����ɂ��Ă��A�X�C�X����A���Ă��̔N�̂����Ƀy�e���u���N�A���X�N���A�C���[�m���H�ɋ��_�����������W�߁A�n���o�ŏ��܂ŗp�ӂ����̂�����A�l�`���[�G�t�̑g�D�Ɣ\�͂͂������Ƃł͂Ȃ��B �@�C���[�m�t�̎E�Q��P�W�V�O�N�͂��߁A�ĂуX�C�X�ɂ���Ă����l�`���[�G�t�́A����ǂ͂��܂������Ȃ������B�P���Ɏ��Q���c�F�����Ǘ����Ă����v���������o�N�[�j������Ď�ɓ��ꂽ�Ƃ���܂ł͂悩�������A���p�[�`���Ƃ����ʂ̐N�v���Ƃ��X�C�X�ɖS�����Ă��āA�l�`���|�G�t�Ə̂���j�́A�P�x���ߕ߂��ꂽ���Ƃ��Ȃ��A�y�g���p�����v�NJč��Ȃǂ��A�܂������̂���b�ł��邱�Ƃ�\�I�����B���̘b���ċ����߂����o�N�[�j���ƃI�K�����t�́A�l�`���[�G�t�Ƃ̕t�������͂�������܂łƁA�ނ����������B �@�������ăX�C�X�ɂ͂���Ȃ��Ȃ����l�`���[�G�t�́A���V�A�閧�x�@�̎�����ł���Ă����X�C�X�����ɑߕ߂���A�g�������V�A�Ɉ����n���ꂽ�B���̂Ƃ��l�`���[�G�t�͂Q�T�B���V�A�ł̍ٔ��̂̂��A�ނ͒����ŃV�x���A���Y�̔�������������A�y�g���p�����v�ǂɏI�g�ċւ̐g�ƂȂ����B �@�������t�́w���j���ȁx�l�`���[�G�t�ٔ��́A���V�A�v���̗���̂�����]���_�ƂȂ����B�v�����u���N�����͂����ŗ����ǂ܂����B�s�[�T���t���u�v�l����v�����^���A�[�g�v�Ƃ������C���e���Q���`�A�����܂܂Ŋv���̐擪�ɗ����Ă������A�l���Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ�̂��B�w���T�[�N��������g�D�����l�`���[�G�t�͂܂������ł͂Ȃ����B�Ăуs�[�T���t�E�ɗ����߂��ċߑ㉻�w�Ŏ��Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@���̂Ƃ��A�s���|�g���E�������t(1823-1900)�́w���j���ȁx���[���̂悤�Ɋv���ւ̓����������B���̖{�́A�U�W�N����U�X�N�ɂ킽���āu�j�W�F�����v�i�T�j�Ƃ����G���ɂɘA�ڂ���ĂV�O�N�ɂP���̖{�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B�S�����̃������t�̂Ƃ���ɐN�������A�u���Ȃ��ɂ������҂������Ă��܂��B�v���̍j�̂������āA�o�ŕ��̎w�������Ă��������v�Ɨ��݂ɂ���܂ŁA�������t�́u���j���ȁv������Ȃɓǂ܂�Ă���Ƃ͒m��Ȃ������B�w���j���ȁx�́A�s�[�T���t�̎��R�Ȋw�����`�ƃ������̕s�݂ɑ���R�c�Ƃ��ď����ꂽ���̂������B�������t�����R�Ȋw�͔ے肵�Ȃ��B���R�Ȋw�͔F�߂�B���������R��`�͎v�z�̐����ɂ����Ȃ��B�l�Ԃ���̂Ƃ��ĉ��l�����߂Ă����Η��j�ɓ��肱�܂�������Ȃ��B���j�͏h���ł͂Ȃ��B����̍ō�������������C���e���Q���`�A���A���j��n������B���̑n�����i���Ȃ̂��B�����C���e���Q���`�A�́A���������j�̑n���҂��Ǝv���オ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�C���e���Q���`�A���m���̓����҂ł��肤��̂́A�����̐l����O���H����H�킸�œ����Ă���邨�����Ȃ̂��B�C���e���Q���`�A�͂��̕��O�ɕԂ��ׂ������I�`��������B�i���̑㏞���ׂ��Ƃ��������̂��B �@���́w���j���ȁx�̓l�`���[�G�t�����̃V���b�N�ɈӋC�������Ă����N�����ɂƂ��đ傫�ȋ~���������B�A�d�����s��������Ƃ����Ċv������]�̂킯�ł͂Ȃ��B���ꂪ���s�����̂͐�p�������������āA���������Ȃ��������炾�B�C���e���Q���`�A�̓������ɂ���Ė��O�ɂȂ����Ă���̂��B���̐l����O�ƈꏏ�ɂȂ�A�v���͉A�d�ł͂Ȃ��A���R�Ɛl���̗͂ɂ���čs�Ȃ�����ł͂Ȃ����B�w���j���ȁx�́A�v���I�N���l�`���[�G�t�̌ǓƂ����������B �@�������t�͒n���M���̉Ƃɐ��܂�P�W�R�V�N�y�e���u���N�̖C���m���w�Z�Ŋw�сA���ƌ�͓��Z�̋����ɂȂ萔�w�������Ȃ���A���j�E�Љ�E�N�w�̌����𑱂��A����Ƀ`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�̃O���[�v�ɋ߂Â����B�v���I�����ƂƂ������w���I�l�����������A�U�Q�N�ɂ͌��Ёu�y�n�Ǝ��R�v�̃����o�[�������B�U�U�N�A�A���N�T���h���̈ÎE���������̊֘A�ōs��ꂽ�v���Ӑl���̈�ĉƑ�{���ɂ���āA�`�F���k�C�V�F�t�X�L�[�Ƃ̘A�����Ȃ���������A��s�Ǖ��ɂȂ����B�w���j���ȁx���������̂͂��̒Ǖ��n�ɂ����Ăł������B �@�w���j���ȁx�������I����ƃ������t�́A�u�P���[�u���Ёv�������Ĕ_���̒��Ő�`����������Ă������p�[�`���̎�����ŒE�o���A�P�W�V�O�N�Q���Ƀp���Ɍ��������B�����Ŕނ̓p���E�R�~���[���ɎQ������B |
|
�@�u���O�̊��S�ȉ���ƍK���̒B���͑S�Ă�j�閯�O�̊v���ɂ���Ă̂݉\�ł���B���̂��߂Ɍ��Ђ͎Љ�̍Ж���ő���Ɋg�債�ۗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������邱�ƂŖ��O�̕s���Ɠ{��̊��E�܂̏���点�A��l�c�炸�I�N�ɗ����オ�点��悤�Ɏd�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�i���V�A�̊v���ƃl�`���[�G�t�̌��t�@�A�c���@�u���V�A�������閧���Ёv�j |
| �y�i���[�h�j�L�̒a�����̂S�A�u�l���̒��ցv�z |
| �@�P�W�V�R�N��ꂩ��A�y�e���u���N�A���X�N���A�L�G�t�A�I�f�b�T�A�T���g�t�A�T�}���A�n���R�t�̊w���𒆐S�ɐN���������X�_���ɓ���A�_���ɑ��ĎЉ��`�̐�`��������A�v���̕K�v��������肵���B���̉^���͗��V�S�N�̉Ăɍō����ɒB���A�Q���R�O�O�O�l�̐N���Q�������B�Q���҂̂R���̂P�����q�w���������B�u�������āv���߂��ĂV�S�N�̓~����N�����̑匟�����n�܂�A�������܂߂ĂV�O�O�l�ȏオ�ߕ߂��ꂽ�B �@���̉^���͑S�����R�����I�ɋN�������̂������B�g�D�炵���g�D�Ƃ����A�y�e���u���N�̃j�R���C�E�`���C�R�t�X�L�[(1850-1925)�𒆐S�Ƃ����w���O���[�v���낤�B���̃O���[�v�͂V�P�N����ɂł������A�������閧�g�D�ł͂Ȃ������B�N���Q�����Ă����܂�Ȃ��B�l�`���[�G�t�ɂ��肽�w�������́A�g�D��閧�ɂ����A�����ł͍��@�I�ȏo�ŕ������ǂ܂Ȃ������B���������ۂ́A�v�����ǂ��������@�Ŏ������ׂ������A���R�ɓ��_�ł���ꂾ�����B �@�u�l���̂Ȃ��ցv�^���͂V�T�N�ɂ͂قƂ�ǏI�����Ă��܂������A����͊v���Ƃ̓k��C�s�Ƃ������ׂ����̂������B��Ŋv���ƂƂ��Ēm����l���́A�قƂ�ǂ����̉^���������Ċv����`���w�B�̂��Ƀe�����X�g�Ƃ��Ė����Ȃ����N���t�`���X�L�[(1851-95)�͂��̉^������ڂ��āA����͐����^���Ƃ��������ϗ��I�ȉ^���������B�Љ��`�͏@���ŁA�l���͐_�������ƌ���Ă���B �@�u�l���̂Ȃ��ցv�^���ɎQ�������w�������́A��q�����`���C�R�t�X�L�[(1850-1926)�����[�_�[�Ƃ���O���[�v�̂ق��ɁA�O�̃O���[�v���������B�@���̉^�����@���I�ȉ^���Ƃ����邾�������āA���ۂɐV���@���̒c�̂��Q�����Ă����BA�E�}���R�t�Ƃ����A�\�͊v���ɐ�]�����l�������c�ɂ��A�l�Ԃɂ͂���ɂ��u�_�̉Ήԁv�������āA�אl���A���e�A�]���S�ƂȂ��Č����A�F��ɂ���āu�_�̉Ήԁv�������点�ΎЉ���͎��������Ƃ����̂����`�������B���̌�A�ߕ߂��ꂽ�}���R�t�͌����̂Ȃ��Ɂu�_�̉Ήԁv���F�肾���Ă݂���Ǝ咣���Ă�܂Ȃ������̂ŁA���_�ُ�҂Ƃ��Ďߕ����ꂽ�B�@ �@NN�c�ƌĂꂽ�̂́A�X�C�X�ɂ����������t�̏o���Ă���u�t�y�����[�g�v�i�O�i�j�𒆐S�ɏW�܂����O���[�v�������B�X�C�X�ɗ��w���ĎЉ��`�҂ɂȂ����w���̑����͂��̃O���[�v�ɑ������B �@��l�̃O���[�v�̓u���^���Ə̂��o�N�[�j���h�ł���B����̓L�G�t�ȂǓ���ƃ��X�N���ɉ����҂𑽂������Ă����B�u���^�[���Ƃ����̂̓u���g�i�I�N�E�Ꝅ�j���N�����l�Ƃ����Ӗ��ŁA�s���h�ł���B �@�`���C�R�t�X�L�[�h�������Ƃ��L���ɂȂ����̂�M�D�i�^���\��(1850-1919)��\�t�B�A�E�y���t�X�J��(1853-81)�̂悤�ȗL�\�Ȋ����Ƃ��������肩�A�s���[�g���E�N���|�g�L������(1842-1921)���Љ�I�n�ʂ��Ȃ������ĎQ�����Ă�������ł������B �@�u�l���̂Ȃ��ցv�͂���ɎQ�������N�ɂ́A�����������P��^�������A�_�������͐N����قƂ�lj����w�Ȃ������B�܂��܂��c���M���Ă����_�������́A�N��̐�`�����Ƃ��Ȃ����������łȂ��A�ނ���x�@�ɖ���������A�Ђ��������ē˂��o�����肵���B�N�����̐l���M�͑傫���h�炢�� |
�@�P�W�V�S�N�A�m�E�u�E�`���C�R�t�X�L�[���n�݂������Ђ̗L�̓����o�[�Ƀ}�[�N�E�i�^���\���ƃA���i�E�A�C���V���^�C������������B�A���i�͂��̔N�A�r���j���X�Ŋv���Ƃ̍זE�g�D�Â���ɖz�����A�A�����E���o�[�}���ƃA�����E�Y���f���r�b�`�����̍זE����Ă��B���o�[�}���́A�����h���Ń��_���Љ��`�������ĂĂ���A���ɂ��̌�̐��E���_���Љ��`�J���҉^���̋N���܂ƂȂ����B���̑g�D�́A�J���g���[���E�B������ɔ��W�I�ɉ������A�샍�V�A�̃��_���l����͂ƂȂ����B
| �y�i���[�h�j�L�̒a�����̂T�A�o�N�[�j���z | |
| �@�i���[�h�j�L�^���̓o�N�[�j���̎v�z�I�e�����Ă����B�o�N�[�j���̗����́u�o�N�[�j���v�́u���U�̊T�������v�ɋL�����B �@���V�A�̊v���I�N�́A���[���b�p�łł������Ƃ����V�A�ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��ƍl�����B�t�����X�v������p���E�R�~���[���֎���o�������V�A�Ō������Ƃ��n�߂��B�o�N�[�j�����_�̉e�����Ȃ���A���V�A�_���Ɋ��҂����B�������Ċw����́A�����̎g�k�Ƃ��Ĕ_���Ɍ������B �@�ނ�w��������Â������̂Ƀ}���N�X��`�ɑ����a�����������B�o�N�[�j���̉e�������������̂ŁA�N���|�g�L���͂�������A�������t���v���̂��Ƃ͎��R�ȋ����̘A���̎Љ�ł��邱�Ƃ����҂��Ă����B�P�W�V�Q�N�A�v���n�[�m�t���u���{�_�v���o�ł��A�R�O�O�O��������グ�����������A���V�A�̊v���Ƃɂ���ƁA�u���{�_�v�͎��{��`�Љ�̈������������̂ŁA�}���N�X�̊v�����_�͐������{��`�ɂ��Ă͂܂�̂ł����āA���{��`�ȑO�̃��V�A���͂ɂ͖𗧂��Ȃ������B�����̎��{��`���܂˂�K�v�͂Ȃ��Ƃ��Ă����i���[�h�j�L�̋����܂Ȃ������B����ɁA�}���N�X�h�̂����v����̃v�����^���A�ƍق͍��ƌ��͂��Ȃ������Ƃ���ނ�ɂ͂Ȃ��߂Ȃ������B�l�`���[�G�t�̉A�d�v���ƈႤ����I��ŁA�ނ�͐l����O�ɂ��v�������҂��铹�ɕ����������B �@�������Ȃ���A�u�l���̂Ȃ��ցv�̉^���͎��s�����B�o�N�[�j���͂����ɂ��v�����N����悤�ɑi�������A�_���͗����オ��Ȃ������B �@���̍��̃i���[�h�j�L�ɂ́A���V�A�v�����ǂ������v���ł���ׂ����ɂ��Ĉ�v�����l�����������B����̓��[���b�p�I�����v���ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�ނ�́A�N�吧�����a���ɂ���Ƃ��A�ꐧ���c��ɂ���Ƃ��̐����v�������قǏd�����Ă��Ȃ������B�Ⴆ�A�u�l���̂Ȃ��ցv�̍ٔ��ɂ�����ꂽ�R�[���t�͋��q�̒��ł�����������B
�@�i���[�h�j�L���������������̂́A�����͎��R��`�҂����͂Ǝ��������Ă�邱�ƂŁA�v���Ƃ̂��邱�Ƃł͂Ȃ��Ǝv���Ă�������ł���B�u�l���̂Ȃ��ցv�����s���āA���̂��߂ɍٔ��ɂ������Ȃ�����A�ނ�̐����I�v����ے肷��C�����͕ς��Ȃ������B |
| �y�i���[�h�j�L�z | |||||
| �@�P�W�V�O�N��̃��V�A�Ƀi���[�h�j�L�ƌĂ��v���^�����N�������B�i���[�h�j�L�Ƃ́A�u�l���i�i���[�h�j�̂Ȃ��ɓ������v���Ɓv�Ƃ����Ӗ����B�i���[�h�j�L�Ƃ������t�͂U�O�N�ォ�炠��ɂ͂������B�܂��u�l���̂Ȃ��ցv�̎n�܂�O�A�P�W�V�Q�A�R�N�ɃX�C�X����A���Ă����o�N�[�j���h�̐N���A�Â�������u���{�h�v�ƌĂ̂ŁA�Â����オ���Ԃ��āu�i���[�h�j�L�v�Ɩ��Â����B�����Ɂu�i���[�h�j�L�v�̗R�����L��B�������A��ʂɃi���[�h�j�L�Ƃ����A���ɂ����v���I�������Ёu�y�n�Ǝ��R�Ёv�Ƃ��̊v���Ƃ��w���B �@���̍��A�����I�ȓ}���قǏł肪�o�Ă����B���͂�����قǂ������}�ɏP��������Ƃ��A���͂Ƃ̓�����O�ʂɉ����o���Ȃ��ł����̂��A�Ƃ�����肪�o�Ă����B���{�̂͂������Njy�ɁA�e����ے肵�e�����Â��A�����Ɠ��S�̂Ȃ��ɁA�v���Ɛl���Ƃ̊W�ⓖ�ʂ̊v���ڕW�ɂ��ď\���ɍl�����Ȃ����f���݂ĂƂ��B �@�����̒Njy�ɑ����R����e���Ɉڂ�˂Ȃ�Ȃ������O���[�v�A�_���̂Ȃ��ɍ��𗎂������Č[�ւƃZ�c�������g����������O���[�v�A�s�s�J���҂̂Ȃ��ɐ�`������O���[�v�A���܂��܂Ȗ͍����V�O�N��̏I���ɂÂ����B�u�y�n�Ǝ��R�Ёv�̃����o�[�́A�E���������Ă����̂��B �@�u�y�n�Ǝ��R�Ёv�̃����o�[�́A�قƂ�ǂ��u�l���̂Ȃ��ցv�^���ɎQ�����Ă���B�g�D�̕K�v���������ނ�́A���V�A�ł͂��߂Ē�����s�̋@�֎����������}���������B�����̒��S�l���́A��q�����`���C�R�t�X�L�[�E�O���[�v�̃i�^���\���������B�������Ăł����O���[�v�́u�l���̂Ȃ��ցv�^����OB�ɂ��l������������B�v���p�K���W�X�g�Ƃ����v���̐�`����Ƃ��������h�ƃu���^���ɑ������������s�h�̗������܂�ł����B�}�̌��݂ƌx�@�̒Njy�̋����ɂȂ�ƁA�ߌ��ȘA���͕����������n�߂邵�A�X�p�C�ɑ��ĕ����`�������邱�ƂɂȂ�B�ۂ����ł����͂̐�[���ƂԂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̋C�̑�������łƂ��ɂ��̎�̏Փ˂��p�������B �@�e���́A�y�e���u���N���g���[�|�t���R�̎ˎE��������n�܂����B�P�W�V�W�D�P���A�m�����O�ɍT�����Ă�������Ғ��̂ЂƂ�̏������A�����̔ԂɂȂ��Ēm�����ɓ���ƁA�����Ȃ�s�X�g�����o���Ēm���ɔ��C�����B�Y�����Ő����Ƃ��s�҂��ꂽ���Ƃɑ���ԕ����B�m���͏d�����������ȂȂ������B�����́A�e�Ղɖ��𖾂����Ȃ��������A���ăl�`���[�G�t�̃T�[�N���ɑ����āA���Y�ɂȂ������F�[���E�U�X�[���b�`(1849-1919)�ł��邱�Ƃ����������B �@�Q���ɂ̓L�G�t�ŃI�V���X�L�[��}���������R�g�������t�X�L�[��_�����Ď��s�����B�R���ɂ͓������L�G�t�œ}���|�v�R�������������̃Q�C�L���O�j�݂�H��Ŏh�E�����B�W���ɂ̓N���t�`���X�L�[���閧�x�@�̒������[���c�F�t���R���y�e���u���N�Ŕ����A�h�E�����B�}�ƌx�@�͐H�����H���邩�̃f�b�g�q�[�g�������Ă���Ƃ��A�X�C�X����͂��G���͂Ђǂ����C�̂Ȃ����̂ɂȂ����B�e�n�̔閧�T�[�N�����߂��߂�����ȓ}�������ăr�����o���Ă���̂��g�D�̃��[�Y�����������B �@�X���ɂȂ��ăy�e���u���N�̑g�D���זœI�ȑŌ������̂𗧂Ē������A���N�T���h���E�~�n�C���t(1855-84)�͓}�̌��݂��߂����Ƃ��āA�P�O���������I�ɋ@�֎����o���n�߂��B���̋@�֎��ɂU�O�N��̊v���}�̖��u�y�n�Ǝ��R�v���̗p�����̂ŁA���̓}�����u�y�n�Ǝ��R�v�ЂƌĂ��悤�ɂȂ����̂ł���B���̑�P���ɃN���t�`���X�L�[�ɂ��j�̂����\���ꂽ�B �@�u�y�n�Ǝ��R�Ёv�̍j�̂́A�u�y�n�Ǝ��R�A���̓�̖��̂悤�Ȍ��t�́A�������у��V�A�̒n�ꂩ��͋������R�̓������ĂыN���������Ƃ��v�Ƃ̃A�s�[���Ŏn�܂�A���̂悤�ɐ錾���Ă���B
�@���̍j�̂��A���ɖ��ɂ���̂̓��[���b�p�ƈ���Ĕ_�Ƃ̖�肾�����B���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�j�̂͂���ɂÂ��B
�@�ȏオ�j�̂̂���܂��ł���B���̍j�͓̂����̊v���I�ȃ��V�A�̐N�̋C���������ɂ悭����킵�Ă���B�u�l���̂Ȃ��ցv�^���̎��s���狳�P�����݂Ƃ낤�Ɩ͍����������p����������B�������A�l����O�ƌ��т����Ƃ������قǐ��{����e�����A�L�͂ȃ����o�|�������ߕ߂���Ă������B |
| �y�����I�e�����Y���̗̏g�z | ||
| �@�P�W�V�O�D�S�D�Q�Q���i�I��S�D�P�O���j�A���[�j�������H���K�͔ȃV���r���X�N�i���E�����m�t�X�N�j�ɐ��܂��B���͍��������ł������B �@�P�W�V�Q�N�A�}���N�X�̎��{�_�����s�����B���V�A�ɂ�����u�}���N�X��`�v�́A���{�_�̃��V�A����s���ꂽ�P�W�V�Q�N����n�܂����B �@�P�W�V�U�N�A�u�T�O���̍ٔ��v�ŁA���_���̐l���̈ӎu�h�̓�l�̏����i�Q�b�V���E�Q���t�B�i���ƃx�b�`���E�J�~���X�J���j���퍐�l�Ȃɍ��点��ꂽ�B �@�P�W�V�W�N�A�g���c�L�[�����܂��B �@�P�W�V�X�N�A�i���[�h�j�L�}�i��`�h���A�u�l���̈ӎu�}�v���������A�u�����I�Ɍە����ꂽ�e�����Y���v�ɏ}������閧�A�d�c�̂����Ђ����B�u�l���̈ӎu�}�v�́A�S�O���O��́u�v���I�v�j���ō\������Ă����B�P�W�W�O�N��́A�u�l���̈ӎu�h�v����ĕ��r�����B �@�u�y�n�Ǝ��R�Ёv�̎w���I�n�ʂɂ������~�n�C���t�́A�c�銯�[��O���̒��ɋt�X�p�C�A�N���`�F�g�j�R�t�𑗂肱�ނ��Ƃɐ��������B����Ȍ�e���̐������������Ȃ����B�~�n�C���t�̏��f�ł́A���ܓ}����_���ɑ��肱��Ŋv������������ɂ͓}���̐������Ȃ�����B�����ŗL���ɐ키���߂ɂ͌��͂̒������ɑŌ�����������ق��Ȃ��B�������邱�Ƃɂ���Đl���Ɋ��C��^���悤�ƃ~�n�C���t�͍l�����B �@�v���n�[�m�t�́A�e���ɂ��ēO��I�ɔ������B�ނ͘J���҂̒��ł̐�`�ɏd�_�������@���ƍl�����B�~�n�C���t�h�ƃv���n�[�m�t�h�ƏՓ˂��\�ʉ������̂́A�P�W�V�X�N�t���炾�B�T���g�t����e�����X�g�A�\�����B���t������Ă��čc��ÎE������������A�u�y�n�Ǝ��R�v�Ђʼn������Ăق����ƌ������Ƃ��ł���B���������_�̖��A�g�D�Ƃ��Ă͎x���ł��Ȃ����A�X�̓}������������̂͂��܂�Ȃ��Ƃ����Ë��ɗ����������B �@�P�W�V�X�D�S�D�Q���A�i���[�h�j�L�}�i��`�h�i�\�����B���t�j���A���N�T���h���Q����_������B�\�����B���t�͂T���̏e�e����������ǂ�������炸�A���̏�őߕ߂��ꂽ�B �@������_�@�ɁA�i���[�h�j�L�u�y�n�Ǝ��R�v�́A�}�i��`�h�́u�l���̈ӎu�v�h�Ɖ����h�́u�y�n�����֔h�ɕ����B�v���n�[�m�t�́A����ȏ�e�����Â��邩�ǂ����}���Ō��������悤�ƒ�Ă��A�U���Ƀ��H���[�l�W�ő��J���ꂽ�B���ł́u�_������v�h�̓v���n�[�m�t�͂��߁A���F�[���E�U�X�[���b�`�A�p�[���F���E�A�N�Z�����[�g�Ȃǂ��������A�哱���̓~�n�C���t�A�t�������R�A�����]�t�A�W�F�����[�{�t�Ȃǂ̃e���h�̎蒆�ɂ���A�̌��̌��ʁA�e���h���������߂ď������B�v���n�[�m�t�́u���������ɗp�͂Ȃ��v�ƐȂ������ė����������B �@�W���A�}�i��`�h�́A�y�e���u���N�ɉ���ĕʂ̑g�D���������B�u�y�n�Ǝ��R�v�i�[�������E�C�E���H�[�����j�̃��H�[������������āu�i���[�h�i���E���H�[�����v�i�l���̈ӎu�j�Ƃ������������B�u�l���̈ӎu�v�}�� �P�W�V�X�N�P�O������W�T�N�P�Q���܂łP�Q���̋@�֎��u�l���̈ӎu�v���o�����B���̒��ɔ��\���ꂽ�_���ɂ���āu�l���̈ӎu�v�}�́A���Č��ꂽ�v���g�D�̂Ȃ��ōō��̒n�_�ɗ����Ă��邱�Ƃ��������B �@�u�l���̈ӎu�v�}�́A�i���[�h�j�L�ɃA�i�L�X�g���_�������A����������i�Ƃ��čc��E���{�������v�l�ÎE�A�c���ԁA�{�a�̔��j�Ɍ��������u�����ƃe���v���n���I�ɑg�D�����B �u�l���̈ӎu�v�}�́A���V�A�̊v���Ƃ��A�i�[�L�Y���̎��������������B�Љ�v���������ΐ��������͂��̌��ʂƂ��ċN����Ƃ����v�z���t�]�����B�܂������v�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ͍��̌��͂�|�����Ƃ��悾�B���͂�œ|����܂ł͊v���Ƃ̓}���w�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�y�n�Ǝ��R�v�Ђ������̂��Ƃ͏����ɔC�������A�u�l���̈ӎu�v�}�͌��͑œ|�̂��Ƃ̃v���O�����������Ă����B���͂�D�悵����}�͌��@�����c�����W����B����ɂ���Đl���̎�ɍ��ƌ��͂��䂸��n�����B�}���l���̗͂�g�D���A�l��������I�Ɋ������n�߁A�������͂��l�������Ƃ���B
�@�����ɂ́A�u�l���̂Ȃ��ցv�^���Ɍ���ꂽ�l���ւ̖ӖړI�ȐM�͂Ȃ��B�������A�u�Ⴂ���V�A�v�ɂ������悤�ȃW���R�o����`�͂Ȃ��B�ނ�ɂ͂܂��l�����U���Ă����Ƃ����l�`���[�G�t�̋L���������Ă��Ȃ������B �@�܂��ނ�ɂ͐��������������������Ƃ͂����A�o�N�[�j���̎v�z�Ɩ����ł͂Ȃ������B���@�����c�ɂ���Ĕ_���ɓy�n��������ꂽ���ƁA�e�n���͓Ɨ����Ď����̘A���ƂȂ邱�Ƃō��ƈ������������ƐM���Ă�������ł���B �@�������A�v���͔_����������邱�Ƃ����̔C���ł���A���v�����}���Ȃ��ƁA�u���W���A�Ɍ��͂���肷��Ƃ����v�z�́u�y�n�Ǝ��R�v�Ђ��炻�̂܂܈����p�����B�ނ�́u�l���̂Ȃ��ցv�^���̒��Ŕ_���̓G�̓N���[�N�i�x�_�j���ƌ��Ă��������A�u���W���A�ɑ��锽���͌������������Ă����B �@�u�l���̈ӎu�v�}�́A���͂ӂ��邽�߂̌R���Ƃ��ċ��ɓI�Ɋv���͐l���̎Q����K�v�Ƃ���ƍl���Ȃ���A���̂��������Ƃ��ăe���ɂ�錠�͂̉�̂����҂����B�e���ɐ[�����ݓ����ɏ]���āA�A�d�ɂȂ�A�l�����痣��A���ۂɂ̓l�`���[�G�t�̑g�D�����ɋ߂Â��˂Ȃ�Ȃ������B �@�u�l���̈ӎu�v�}�́A���͂̍ō��̋��_�ɑŌ�����������@�Ƃ��čc��̈ÎE����}���Ă����B���ꂪ�}�ɂ���Ċm�F���ꂽ�̂́A�V�X�N�W���ł������B���̑�_�ȍŌ�̐킢�����肳�ꂽ�Ƃ��A�u���s�ψ���v�̒��ł͑傫�ȓf�������������B����̓_�C�i�}�C�g�ƌ��܂����B�n�������̒��ɁA�Ζ��̎��������H�ꂪ�������邱�ƂɂȂ����B�c��ÎE�̂��߂̊���̔ǂ������B���ꂼ��̒n�_�Łu�Y�̎��s�v���������ꂽ�B �@�i�P�X�V�X�N�ȍ~�̎�ȁu�����ƃe���v�͎��̒ʂ�B���j�@�܂��c�@�[���̃N���~�A����A���Ă���r�����R�J���ő_�����ƂɂȂ����B�I�f�b�T�ɔh�����ꂽ�t�������R�A���[�x�W�F���A�L�o���`�[�c�̍�Ƃ����ʂɂȂ����B�I�f�b�T�ɍc��͗��Ȃ������̂��B�A���N�T���h���t�X�N�ł̓W�F�����[�{�t�̃O���[�v���A���[���̉��Ƀ_�C�i�}�C�g�߂邱�Ƃɐ��������B�c��̗�Ԃ����̏��ʉ߂���u�ԃ{�^���͐����������ꂽ�B�����������͋N����Ȃ������B�d�ɂ̌q�������ԈႦ���̂������B�Ō�̊֏��̓��X�N���������B�����ɂ́u���s�ψ���v�̐��s�~�n�C���t�A�\�t�B�A�E�y���t�X�J��(1853-81)�炪�A���H�ɋ߂��Ƃ��ĂS�O�b�̒n�������@�����B�P�P���P�X���A�Z���ɔ����ڂ�Ȃ���A����U�����B��Ԃ͉߂������j���ꂽ�B�������A�j�ꂽ�P���͉ݎԂŁA���Ƃ̂W���͒E�����������B�������c��͓�ꂽ�B�E���Ԃɂ͐���������������Ȃ������B �@�P�W�V�X�D�P�O�D�Q�U���A���t�E�_���B�h���B�`�E�u�����V���e�C���i�g���c�L�[�j���A��E�N���C�i�̃w���\�������m�[�t�J�ŁA���_���l���c�_�T�Ԗڂ̎q���Ƃ��Đ��܂��B �@�V�X�N�̖��A�e���s�ׂɂǂ����Ă��^���ł��Ȃ������v���n�[�m�t�́A�u�����ĕ����v�Ƃ����@�֎����o�����B�u�����v�Ƃ́A�_�����g�̎�ɂ��Ƃ����Ӗ��ł���B����ɂ��A�u�����ĕ����v�h�ƌĂ��B�ނ�̑������u�_���h�v�ł���A�_���̒��ł̐�`�Ƌ���𑱂��邱�Ƃ�����Ȃ������̂́A�ނ�ɂ͐l���ւ̐M�����܂�����������ł���B�v���͐l���݂����炪�N�������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����M�O���������B�u�l���̂Ȃ��ցv�̎v�z�����̂܂ܑ����Ă����B �@�ނ�͐�����������ɂ��邱�Ƃɔ��������B���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�����I���W�J���Y����r�����ނ�́A�X�e���J�E���[�W����v�K�`���t�̌^�̍��Ɖ�̂��l���Ă����B�_�Ɗv����v������l���̐��͐_�̐��ł���A�_�̐��́A���̌[�����v���I�C���e���Q���`�A�Ɏ��������Ƃ����B �@�u�����ĕ����v���������������ɁA������������ɂ���Ė\����A�u�����ĕ����v�h�͑����̓}���������Ă��܂����B�u�l���̈ӎu�v�}�̃e���̑���������A����ǂ��͂��̂܂܂ő������Ȃ��Ƃ����̂ŁA�w���҂����O�ɖS�������邱�ƂɂȂ����B �@�P�W�V�V�|�V�X�N�́u�P�X�R���̍ٔ��ŁA�W���̃��_���l���퍐�Ȃɍ��点��ꂽ�v�B |
| �y�i���[�h�j�L�l���̈ӎu�h���c��A���N�T���h���Q���E����z |
| �@�P�W�W�O�D�P���A�v���n�[�m�t�A�U�X�[���`�A�f�B�b�`����͍��O�ɋ������B�A�N�Z�����[�g�͎c���ăy�e���u���N�̑g�D���w�������B���̍��A�S�O�l����̊����Ƃ������B�u�����ĕ����v�h�͑S���I�ɓ��ꂵ���}�Ƃ͂����ȂȂ����B���ʖړI���������T�[�N���̘A���Ƃł������ׂ��������B �@�Q�D�T���A�c���ł���~�{�̐H���̏�������Ő������łT�l�̎��҂ƂT�W�l�̕����҂��o���B�c��͈ꏏ�ɐH������͂��̕o�q���x�ꂽ���ߊ낤����ꂽ�B������d�|�����̂́A�}���X�e�p���E�n���g�D�[�����B�ނ͎w���t�������̂��K���A�~�{�ɍ����Ƌ�E�l�Ƃ��č̗p���ꂽ�B���̘r�̂����E�l���̎������ŐM�p����{�a�̒n�����ɏZ�ނ��Ƃ������ꂽ�B�ނ̓_�C�i�}�C�g��ɉB������ď����Â~�{�ɉ^�B����ȏ��R�ɂȂ�Ɩڗ��Ƃ����Ƃ��ɔ��j�����s�����B���ΐ��ɉ����ĊO�ɏo���n���g�D�[�����́A�^���邱�ƂȂ����������������B �@�~�{�̔��j�́A���̕s�����ɂ�������炷�A�S���E�Ɂu�l���̈ӎu�v�}�̑��݂����点���B�u�l���̈ӎu�v�}�́A���l�S���A�e�ɗ����������q���_�r�f�̂悤�ɐ��Ԃ̖ڂɉf�����B�v���Ƃ����͌������̎��R��`�ɂ��܂���Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߁A�c��ÎE�𑱂���Ɛ錾�����B�P�W�W�O�N�ɂQ�x�A�ÎE�����݂�ꂽ���Q�ǂƂ����s�����B���̂��тɎc�菭�Ȃ������Ƃ��ߕ߂��ꂽ�B�g�D�͂ق���тĂ������B�y�e���u���N�̂ǂ�ȗ����̏��H�ł��m�����Ă����E���̖��l�~�n�C���t���ߕ߂��ꂽ�B �@�P�W�W�P�D�P���A�v��ʘA���̎莆���}�ɂ����炳�ꂽ�B�y�g���p�����v�NJč�����̃l�`���[�G�t�̎莆�������B�A�d�̊v���Ƃ͂܂������Ă����̂��B�����Ă�������łȂ��A�ނ͒E�����Ă�����x���ɉ���肽���ƌ����Ă����̂������B���܊č��̊Ŏ炽���𖡕��ɂ��āA�E�o�̉��������߂Ă����̂��B�������A�l���̈ӎu���ɂ��Ă݂�B�l�`���[�G�t�̊��o�͂��łɌÂ��Ȃ��Ă���Ƃ��āA�ނ��h�������B�@ �@�ÎE���s�̓����u�P�W�W�P�D�R�D�P���v�ƌ��߂�ꂽ�B�c��͏�n���K�̂��߃~�n�C���t�X�L�[������ɂ����̂ŁA���̒ʂ蓹�̂ǂ����ŏP�����邱�ƂɂȂ����B�����ꂩ��l�t�X�L�[��ʂ�ɔ�����}�[�����E�T�h�[�����ʂ肪�����Ƃ����̂ŁA���̂�����[�̉Ƃ��肽�B�ʂ�̉��ɍB�����@���āA������d�|����̂��B�B���@�肪�n�܂����B �@��ςȂ��Ƃ��N�������B�閧�x�@�̓����ɂ��āA���������̏��𗬂��Ă���A���u�̑ߕ߂̏��𗬂��Ă���Ă���������N���g�V�j�R�t�����܂����B�s���ӂ���A�t�X�p�C�ł��邱�Ƃ��I�������̂��B�}�͒T�m����������B�}�̔�Q�͋}���ɂӂ����B�}���˂Ȃ�Ȃ��̂ɔ���̐������͂��ǂ�Ȃ����A�B�����v���悤�ɐi��ł��Ȃ��B�Q���̏��߂Ɉψ���ŁA�ÎE�Ɠ����ɔ������N�����邩�ǂ����c�����B�ψ���ɂ͂��������Q�O�l���炢�������Ȃ��B�ǂ�Ȃɂ��Ă��S�̒P�ʂ̐l�Ԃ����������Ȃ��B�Ƃɂ������s����܂ł��B�@�`�[�Y�X����@�����B���ɒn�����d�|����̂���ꂾ�B�����n�������s������ǂ����悤�B����ɂ͂S�l�̓��e�҂��}�[�����E�T�h�[�����ʂ�̗��[�ɕ�����āA�͂��ݑł��ɂ��ē��e����悢�B��������܂������Ȃ�������A���̎��́A�����Z���ł����čZ����h���ƌ������̂̓W�F�����[�{�t�������B���̋����m��ʗY�ىƂ̃I���O�͓}�̑S���̐M�����Ă����B�v�����������Đ��{���ł�����ނ�u���Ď�ǂƂȂ�ׂ��l�Ԃ͂��Ȃ������B���̃W�F�����[�{�t���A���s���Q����ɍT�����Q���Q�V���ɑߕ߂���Ă��܂����B �@�������s���Ƃ����̂ɁA�n���͂܂��d�|�����Ă��Ȃ��B�l���̔��e�͂܂�����ł��Ă��Ȃ��B�Q�W���̖��O���Ĕ��e�̐������}�����B�W�F�����[�{�t�ɑ����Ďw�����Ƃ����̂́A�\�t�B�A�E�y���t�X�J���������B�M���̖��Ƃ��Đ��܂�A�����������ĕی��w�ƂȂ�A�u�l���̂Ȃ��ցv�̉^���ɎQ�����đߕ߂���A�ٔ��퍐�ƂȂ����ޏ��́A�����̏����v���Ƃ̓T�^�������B�F�������A�܂������炵���\��c���Ă���ޏ��͓G�ɑ��Ă͗e�͂Ȃ������B�@ �@�R���P���̒��A���e�ƒn�����ł��オ�����B�`�[�Y�X�̍B���ɒn�����d������ꂽ�B���e�҂��l�A��ăy���t�X�J���̓}�[�����E�T�h�[�������痣�ꂽ�B�`�[�Y�X�Ɏc������l�́A�����ꂩ��A���Ă���c�邪�`�[�Y�X�ɂ���������̂��A�{�^���̂��ő҂����܂��Ă����B�������ߌ�P�����܂���Ă��c��͗��Ȃ��B�ق��̓���I�炵���B�������߂��B����ɂ��Ă��y���t�X�J���͂ǂ��ŁA�c���҂��Ă���̂��B �@�Q�����������߂����Ƃ��˔@�A�C���̂悤�Ȕ����������������B�����Ԃ������ē����悤�Ȕ��������������B�Ƃ��Ƃ�������B��������͂ǂ����B�Ԃ��Ȃ��X�ɉ\�����ꂽ�B�G�J�e���i�^�͂ɉ������ŃA���N�T���h�����A�Q���̔��e���ďd���̂܂ܓ~�{�ɋA�����Ƃ����̂��B ���̉^�͉����ɓ��e���z�u���A�Ί݂���n���J�`��U���ē��e���w�߂��A���������Ƃǂ������������̂��A�y���t�X�J���ł��邱�Ƃ�m���Ă����͓̂��u�����������B �@���e�����߂ɓ������̂́A���B�T�R�t�������B�n�Ԃ��肪�ꕔ����ꂽ���������ŁA�]�҂ɂ����l�͂��������A�c��͖����������B���B�T�R�t�͂������ɕ߂炦��ꂽ�B�����̒��ŏ��Z�̂ЂƂ肪�c��Ɂu�������ł��傤���v�Ɛq�˂��B�c��͌������B�u�_�Ɋ��ӂ���B���͂ǂ����Ȃ��B�ނ͂ǂ�����v�Ƃ��ɏd�������j���w�����B��艟������ꂽ ���B�T�R�t�����B�u�_�Ɋ��ӂ���̂͂܂��������I�v �@�c��͐g���Ђ邪�����āA�܂��n�Ԃɏ�낤�Ƃ����B���̂Ƃ��A��Q�̓��e��O���l���B�c�L�[���߂Â��āA�ڂ̑O�̍c��ƂƂ��Ɏ������ׂ������ɔ��e�𓊂����B���������Ɨ������߂�ɉ���������ƁA�c��͋����ɓ|��Ă����B�o�����Ђǂ������B�����~�{�ɉ^�ꂽ���A�P���ԂƂ͐����Ă��Ȃ������B�O���l���B�c�L�[���[���A���������Ƃ����B �@�R�D�P���A�i���[�h�j�L�u�l���̈ӎu�v�h���A�c��A���N�T���h���Q�����A��s�y�e���u���O�i��̃��j���O���[�h�j�̃G�J�`�F���j���X�L�[�^�݂͊Ŕ��E����B�P�W�T�T�N�ɑ��ʂ��A�_�z������s�����A���N�T���h���Q���̍Ō�ł������B �@�������A�i���[�h�j�L�^���͋}���ɗ͂������B |
| �y�V�I�j�X�g�}�g�D���e�n�Œa������z |
| �@�P�W�W�O�N�A�V���A�ƃp���X�`�i�ݏZ���_���l�̔_�Ə]���҂�E�l���x������ψ���I�f�b�T�Őݗ����ꂽ�B�V�I�j�X�g�g�D��c�̂��A�r���j���X�A�~���X�N�A���{�t�A���b�V�[�j�A�R�u�m�A�K���[���A���̑����V�A�鍑�̏��s�s�ɒa�������B�P�X���I���ɂ����āA���萔��l�̓}����i����V�I�j�X�g�}�����V�A�Ŋ��������n�߂��B |
�@�P�W�W�P�N�A���V�A���{�̖ٔF�̉��ŁA�S���I�K�͂̃��_���l�����P�����s���Ă���B��������V�A��Łu�|�O�����v�i���_���l�s�E�j�Ɖ]���B���̔w�i�ɂ́A���V�A�̊e�n�Ɍ�������Ă������_���l���q�g�D�Ƃ��a瀂��������B
�@������ȍ~�́A�u�i���[�h�j�L�A�A�i�[�L�Y���A�}���L�V�Y���̌��������v�ɋL���B
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)