
更新日/2021(平成31→5.1栄和改元/栄和3).3.12日
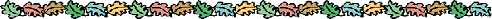
312年、「新羅本紀」、訖解尼師今(昔氏、310~356)三年、倭国王が使者を派遣し、王子のために花嫁を求めてきたので、最高官の娘を送った。
313年、高句麗が強大になり、楽浪郡を併合する。これにより朝鮮半島における中国の拠点がなくなった。
316年、 西晋が匈奴の侵攻によって滅び南北朝の時代に入る。これにより華北は五胡十六国の時代が始まった。華南には東晋が成立して六朝時代が始まった。
320年?、大和朝廷始祖となる神武天皇(=彦ホホデミ尊、崇神天皇)が(南九州から?)黒潮に乗り、熊野へ到達。大和へ新軍し制圧。邪馬壱国の豪族だった鴨氏の祖先が手引き(ヤタガラス)。邪馬壱国王家(=物部氏)の娘を娶り、垂仁天皇を生む。これは、王朝の交代と政略結婚による和合を意味する。唯ここに特筆すべきはその交替の状況である。「覇権交替」のときは、征服者は被征服者を処刑するか叉は追放するかが常套手段であるのに、この場合は様子が違う。天皇族は初代から政略結婚による同盟化を目指しており、それは、外航族と邪馬台国、その他勢力との「共立.談合」という形式での「合体」であった。このような覇権者の政治手段はその後、日本の歴史上度々見受けられる。
この「共立」という「談合」の手段は、古事記の神世時代から存在し、現代に至るまで存在し続けるわが国の政治的遺伝子となっているやに見受けられる。
343年、百済が馬韓を統一した。
344年、「新羅本紀」、倭国が遣使して、花嫁を求めたが、娘はすでに嫁にいったといって断る。 (第二代、垂仁天皇と考えられる。)
345年、「新羅本紀」、倭王は書を送ってきて絶交した。(後240...魏の使者、詔書.印綬を倭国にもたらす。倭王、使に因って上表し、恩詔に答謝す)
346年、「新羅本紀」、倭兵がにわかに風島にやって来て掠奪し、さらに進軍して、王都の金城を囲み 激しく攻めたてた。その後も大和朝廷は邪馬壱国同様(金氏、文.漢)の新羅に敵対的姿勢をとる。
356年、「新羅本紀」、奈勿尼師今(金氏)即位。以降、新羅は金氏の王朝となる。新羅が馬韓を統一する。「記.紀」、第三代、景行天皇即位。以降、成務天皇仲哀天皇と続く。
| 【「三国史記・新羅本紀」の倭の女王卑弥乎記述】 |
| 2~3 世紀、女王卑弥呼が隣国の新羅や中国の魏と国交していた。女王卑弥呼が史書に登場する最も古い記録は古代朝鮮半島の「三国史記・新羅本紀」に「阿達羅尼師今王二十年五月、倭の女王卑弥乎、使いを遣わし来聘す」と記されている。阿達羅尼師今王二十年を新羅王の年代記で調べると阿達羅尼師今は新羅第八代王で、二十年は西暦173年に当り二世紀後半のことと分かった。新羅建国は四世紀中頃、朝鮮南東部の辰韓12国を斯盧国が統一して建てた国だから、173年の記録はその前身斯盧国の時代とみられる。
|
364年、百済人久?ら、卓淳国をたずね、倭国との通交を求める(日本書紀神功紀46年)
366年、倭国の斯摩宿禰、卓淳国へ行き、使者を百済に送る(神功紀46年)
367年、千熊長彦(百済記には職麻那那加比跪)を遣わして新羅を攻める(神功紀47年)。
369年、新羅を攻め、比自ホ?(ひしほ)以下7ケ国を平定し、比利以下の四邑を降服させる(神功紀49年条)。高句麗を攻めるが敗れる。石上神宮の七支刀は、銘文から369年に百済王が朝鮮出兵の要請のために倭王へ贈った(下賜した)ものと見られる。
372年、百済の肖古王、久?らを倭国に遣わし、七枝刀1口、七子鏡1面をおくる(神功紀52年)。「泰和四年」(369)の紀年銘をもつ奈良県天理市の石上神宮の七支刀がこれにあたる。
382年、襲津彦(百済記には沙至比紀跪)を遣わし新羅を攻める(神功紀62年)。
391年、倭が、新羅.百済を破り、臣民とする(高句麗広開土王碑) 。「記.紀」、神功皇后(仲哀天皇の后)朝鮮半島の侵攻。神功皇后は後妻で二十歳代と考えられる。応神天皇(初子)を生む。神功皇后、難波の押熊王と対立し制圧。
392年、百済が高句麗に屈する。(三国史記)百済辰斯王倭国に対し礼を失う。紀角宿禰を遣わして詰問、辰斯王殺され、阿花王立つ(応神紀3年条、三国史記)。
397年、百済の阿花王、王子の直支を倭国におくり和を請う。
399年、倭、新羅に侵入し、新羅は高句麗に救援を要請する(広開土王碑) 。倭国は援軍を送って5世紀はじめ頃まで高句麗軍と戦ったがついに撃退されている。
400年、庚子(四〇〇)神功即位前期、神功征伐新羅。新羅王子を人質にする。(書紀)書紀に記録されているこの項により、「倭」の国王名が「神功皇后」であることが判明した。以下、「日本史年表」上で、倭王讃までの記録をたどつてみることにする。
400年、高句麗、兵を新羅におくり、倭を撃退。追撃して任那加羅に至る。(以上広開土王碑)
402年、新羅実聖王、奈勿王の子未斯欣を倭国に送る三国史記)。
404年、倭、帯方郡に出兵し、高句麗に撃退さる(広開土王碑)。
405年、百済阿花王没、王子直支を帰国させて即位させる(応神紀、三国史記)。
413(東晋.義熙9)年、神功皇后は東晋に遣使。方物としてテン皮や人参 など朝鮮半島の産物を献上(晋書安帝紀、太平御覧所引晋起居注)。
417年、百済王、東晋から使持節都督百済諸軍事鎮東将軍百済王を授けられる。
420年、劉裕(武帝)、東晋に代って、宋を建て(~479)南北時代始まる。宋、高句麗王を征東大将軍、百済王を鎮東大将軍に進める。以後は南斉、梁、陳と短命な王朝が続く。
421年、「宋書倭国伝」、応神天皇(倭王讃)、宋に遣使。応神天皇は三十歳。
424年、「宋書范曄列伝」。范曄、後漢書を著す。新たな資料を得て魏志倭人伝を訂正。前王朝時代 (東晋)の文献に従ったと考えられるので、邪馬台国はその文献に記された文字かもしれない。
425年、「宋書倭国伝」、応神天皇、宋に遣使。倭人伝、倭国伝等は通称、正式には魏書烏丸鮮卑東夷伝第三十倭人伝、晋書四夷伝倭人、宋書夷蛮伝倭国。
| 【三国志注】 |
| 400年代前半の頃、南朝宋の裴松之(372-451)が、魏略、魏書など210種に及ぶ文献を引用して補注をつくった。現在、原書が解逸する中にあって、この補注が現在貴重な資料となっている。 |
| 【「五胡十六国」時代】 |
西晋は、二代恵帝(在位290年~306年)のときから乱れ始め、 内乱と異民族の侵入によって滅び、317又は318年に一族の司馬睿(元帝、在位317~322)が江南に移って「晋」を再興した。南京を都とした。これを「東晋」という。司馬睿元帝は、揚子江流域以上南を確保し、江南の開発を進めた。詩の唐陶器淵明時、絵画の顧がい之、書の王義之などは、この時代のひとである。一方、華北の天地には、異民族が次々と入って来ていろんな国を立てた。これを「五胡十六国」という。
439年、北魏の太武帝によって華北が統一され、南北朝対立の大勢が成立した。 |
| 【「南宋」時代】 |
420年、江南では、軍閥の劉裕なる人物が東晋の天下を奪って、宋の武帝(在位420~422)と称した。これを「劉宋」と呼ぶ。その後、江南では、南斉(479から502)、梁(502~557年)、陳(557
~589年)の諸朝が相次いで交替し、三国時代の呉と東晋とを併せて六朝と呼ぶ。この南朝に対して、倭の五王といわれる「讃、珍、済、興、武 」の五人が相次いで入朝しているが、その大部分は劉宋内から479年に集中している。北魏は仏教を国教とした(北魏様式の仏像は今でも法隆寺などに残っている)。
なお、宋という国は、紀元前の周代の諸侯国の一つにあった宋(~前286)と、南北朝の南朝宋(420~479年)と、唐のあとの宋(960~1279年)があり、まぎらわしい。 |
| 【後漢書】 |
この時代、范曄の「後漢書」が著される。続いて沈約の「宋書」が著される。さらに後、*子顕の「南斉書」、李棒昉の「太平御覧」が著される。
398から445年頃、南朝.宋の宣城大守・范曄(はんよう、ハンカ、398~445)が後漢書を編纂する。構成は、本紀10巻(本紀9巻.后紀1巻)、列伝80巻、志30巻の120巻より成る。この書と史記、漢書、三国志を併せて前四史と称される。成立年時の詳細は明らかでない。
「後漢書倭伝」は通称で、「後漢書巻115.東夷伝.倭条」が正しい(「後漢書 列傳 卷八十五 東夷列傳」とする記述もある)。「東夷伝倭人伝」とも称される。この時初めて「邪馬台国」と記される。次のように記している。記事倭人伝との対照は「魏略倭伝逸文、後漢書倭国伝対照」に記す。
| 倭在韓東南大海中、依山島為居、凡百餘國。自武帝滅朝鮮、使驛通於漢者三十許國、國皆稱王、世世傳統。其大倭王居邪馬臺國。 |
| (倭は韓の東南大海の中に在り、山島に依りて居を為り、およそ百余国あり。武帝の朝鮮を滅ぼしてより、漢に使訳を通ずる者、三十ばかりの国ありて、国ごとに皆王を称し、世世統を伝う。その大倭王は邪馬臺国に居す。) |
| 樂浪郡徼、去其國萬二千里、去其西北界拘邪韓國七千餘里。其地大較在會稽東冶之東、與朱崖、儋耳相近、故其法俗多同。
|
| 土宜禾稻、麻紵、蠶桑,知織績為縑布。出白珠、青玉。其山有丹土。氣温●,冬夏生菜茹。無牛馬虎豹羊鵲。其兵有矛、楯、木弓,竹矢或以骨為鏃。男子皆黥面文身、以其文左右大小別尊卑之差。其男衣皆横幅結束相連。女人被髮屈紒、衣如單被、貫頭而著之。並以丹朱坋身、如中國之用粉也。有城柵屋室。父母兄弟異處、唯會同男女無別
。飲食以手。而用籩豆。俗皆徒跣,以蹲踞為恭敬。人性嗜酒。多壽考,至百餘歲者甚眾。國多女子、 大人皆有四五妻。其餘或兩或三。女人不淫不妒。又俗不盜竊,少爭訟。犯法者沒其妻子,重者滅其門族。其死停喪十餘日,家人哭泣,不進酒食,而等類就歌舞為樂。灼骨以卜,用決吉凶。行來度海,令一人不櫛沐,不食肉,不近婦人,名曰
「持衰」。 若在塗吉利,則雇以財物; 如病疾遭害,以為持衰不謹、便共殺之。 |
| 建武中元二年、倭奴國奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭國之極南界也。光武賜以印綬。安帝永初元年、倭國王帥升等獻生口百六十人、願請見。 |
| (建武中元二年(57年)、倭奴国(の使者が)貢を捧げて朝賀した。使人は大夫を自称する。倭国の極南界なり。光武帝は印綬を賜る。安帝の永初元年(107年)、倭国王の帥升ら、奴隷百六十人を献じ、願いて見えんことを請う) |
| 桓、靈閒、倭國大亂、更相攻伐、歴年無主。有一女子名曰卑彌呼、年長不嫁、事鬼神道、能以妖惑衆、於是共立為王。侍婢千人、少有見者、唯有男子一人給飲食、傳辭語。居處宮室樓觀城柵、皆持兵守衛。法俗嚴峻。
自女王國東度海千餘里至拘奴國、雖皆倭種、而不屬女王。自女王國南四千餘里至朱儒國、人長三四尺。自朱儒東南行船一年、至裸國。黑齒國、使驛所傳、極於此矣。
|
| 會稽海外有東鯷人,分為二十餘國。 |
|
又有夷洲及澶洲。傳言秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海,求蓬萊神仙不得。徐福畏誅不敢還、遂止此洲。世世相承,有數萬家。人民時至會稽市。會稽東冶縣人有入海行遭風,流移至澶洲者。所在絶遠、不可往來。 |
| (また、夷州(いしゅう)及び澶州(せんしゅう)がある。言い伝えでは、秦の始皇帝は方士徐福を遣わし、童男童女数千人を引きつれ、蓬萊の神仙を求め海に入ったがこれを得られなかった。徐福は(罰を受け)殺されることを畏れ、あえて還らず遂にこの洲にとどまった。代々ともども受け継ぎ数万家を有する。人民はときどき會稽の市に来る。会稽東冶の県人は海に入り行き、風に遭い流されて澶洲に至る者がある。絶縁の所に在るゆえ往来はできない) |
| ※ 沈瑩臨海水土志によれば、「夷洲在臨海東南,去郡二千里。土地無霜雪,草木不死。四面是山谿。人皆髡髮穿耳,女人不穿耳。土地饒沃,既生五穀,又多魚肉。有犬。尾短如●尾状。此夷舅姑子婦臥息共一大床,略不相避。地有銅鐵,唯用鹿格為矛以戰鬥,摩礪青石以作(弓)矢〔鏃〕。取生魚肉雜貯大瓦器中
,以鹽鹵之 , 歷 月所日 , 乃啖食之 , 以為上肴」也 。 |
| 「倭は韓の東南大海の中に在り。山島に依りて居を為す。凡そ百余国。武帝、朝鮮を滅ぼしてより使訳漢に通ずる者三十許国なり。国、皆王を称し、世世統を伝う。その大倭王は邪馬臺国に居る。楽浪郡徼はその国を去る万二千里、その西北界拘邪韓国を去ること七千余里。その地、大較会稽の東冶の東にあり、朱崖・タン耳と相近し。故にその法俗多く同じ。(略) 国には女子多く、大人は皆四、五妻あり、その余もあるいは両、あるいは三。(略) 建武中元二年、倭奴国奉貢朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。安帝の永初元年、倭国王帥升等、生口百六十人を献じ請見を願う。桓霊の間、倭国大いに乱れ、更相攻伐し、歴年主なし。一女子あり、名を卑弥呼という。年長じて嫁せず、鬼神の道に事え、能く妖を以て衆を惑はす。ここにおいて共立して王と為す。(略) |
|
「後漢書百官志・州郡条」。
| 「孝武帝初置刺史十三人 秩六百石 成帝更為牧 秩二千石 建武十八年 複為刺史 十二人各主一州 其一州屬司隸校尉 諸州常以八月巡行所部郡國 錄囚徒 考殿最 初歲盡詣京都奏事」。 |
| (孝武帝、初めて刺史十三人を置く 秩は六百石なり 成帝、更(あらた)めて牧と為す 秩は二千石なり。建武十八年(42) 複(ま)た刺史と為す 十二人、各(おのおの)一州を主(つかさど)る 其の一州は司隸校尉に属す。諸州(の刺史)、常に八月を以って所部の郡國を巡行し、囚徒を録し、殿最を考う 初歲に盡く京都に詣りて奏事す) |
| 後漢13州のうち12州に刺史を置き郡国を監察させた。1州だけは司隷校尉にその任を負わせた。その1州とは、洛陽を含むいわゆる首都圏であり、司隷校尉は所部の郡国のみならず百官への監察権をも持つ別格の存在だった。 |
|
| 【宋書】 |
439(元嘉16)年、宋の文帝の命によって宋書の編纂が始まり、何承天、山謙之、琲裴之(はいしょうし)、徐爰(じょかん)らの当代有数の文人たちによって継続されていた。487(永明5)年、南斉の武帝の命を受けた著作郎(歴史編纂の長官)・沈約(しんやく、441~513年、斉の著作郎(歴史編纂の長官))が翌年(元嘉17)に本紀10巻、列伝60巻を完成させた。502(天監元)年、志30巻ができあがった。宋書は全体として事実を簡にな記述しており、宋王朝の官府に集積されていた史料を実録的に記述している。
夷蛮、倭国の条がある。「宋書倭国伝」は俗称で、「宋書巻9 7.夷蛮伝.倭国条」が正しい。次のように記されている。
| 「倭國 在高驪東南大海中、世修貢職。高祖永初二年、詔曰 「倭讃萬里修貢、遠誠宜甄、可賜除授。」太祖元嘉二年、 讃又遣司馬曹達奉表獻方物。讃死、弟珍立、遣使貢獻。自稱使持節、都督、倭、百濟、新羅、任那、秦韓、慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王。表求除正。詔除安東將軍、倭國王。珍又求除正倭隋等十三人。平西、征虜、冠軍、輔
國將軍號、詔竝聽」。 |
| (和訳) |
| 「順帝昇明二年、遣使上表曰:「封國偏遠、作藩于外。自昔祖禰躬[偏手旁右環]甲冑、跋渉山川、不遑寧處。東征毛人五十五國、西服衆夷六十六國、渡平海北九十五國」。 |
| (和訳) 「昔から祖彌(そでい)躬(みずか)ら甲冑(かっちゅう)を環(つらぬ)き、山川(さんせん)を跋渉(ばっしょう)し、寧処(ねいしょ)に遑(いとま)あらず。東は毛人を征すること、五十五国。西は衆夷を服すること六十六国。渡りて海北を平らぐること、九十五国。(「自昔祖禰
躬?甲冑 跋渉山川 不遑寧處 東征毛人五十國 西服衆夷六十六國 渡平海北九十五國」。 |
宋書では、いわゆる倭の5王と言われる「讃、珍、済、興、武」について書かれている。倭の五王の中の珍に関係する記述が列伝の倭国条だけでなく本紀の文帝紀にもある。502年、梁の武帝、倭王武を征東将軍に進号(梁書武帝紀)と出ている。倭王武は以後記録がなく、従がって没年不明である。その5年後には突如として「継体天皇」が登場する。 |
| 【南斉書】 |
500年頃、南朝梁王朝の薫子顕(487~537)の撰により「南斉書」が編纂されている。58(59?)巻。成立年時の詳細はわからない。「南斉書は、6世紀前半に梁という国で作成」と推定されている。日本関係は東南夷伝に書かれている。 正しくは、「南斉書巻58.東南夷伝.倭国条」という。冒頭は前正史の記述を大きく妙略して引いたもので、また中国から見た倭国の位置や女王の存在などを記す。479年の倭国の遣使を記し、倭王武を使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍から、称号などが書かれている。南斉書倭国伝は次の通り。
| 「倭國、在帶方東南大海島中、漢末以來、立女王。土俗已見前史。建元元年、進新除使持節、都督倭新羅任那加羅秦韓(慕韓)六國諸軍事、安東大將軍、倭王武號為鎮東大將軍」。 |
| (和訳) 「倭国は、帯方郡の東南大海中に在り、漢末の時代以来女王を立てた。風俗は既に前史に見える。健元元年(343)に、進めて新たに使持節を除し、倭、新羅、任那、加羅、秦韓・(慕韓)の六国諸軍事、安東大将軍の都督とした。倭王の武は鎮東大将軍と号せしむ」。 |
|
| 【魏書】 |
| 北斉の御代、魏収(506から572年)が勅命を受けて撰述したのが「魏書」である。554年完。114巻、帝紀12巻、列伝92巻、志10巻。北魏のことを記した正史である。 |
|
507年、大伴金村ら応神天皇の五世孫と伝える男大迹(オホド)王、彦太尊(ヒコフト )を、越前の三国(福井県板井郡)から迎え、天皇の位につける。これが継体天皇である。(紀)「継体天皇」はその名の意味する如く、「倭の五王」で乱されていた天皇系統を元に戻し、正統に継統した天皇として表意されているように思われる。
ここで登場してきた「大伴金村」は、天皇政権の「欠史時代」「謎の時代」に終止符を打つ 重大な役割を演じていると思われる。大伴家は古代の中央豪族で、姓は連、のち宿禰。大和朝廷の草創期
に久目部.佐伯部などの隷属集団を統率して朝廷に仕え、大連となり軍事力をになう有力な氏族。壬申の乱には大海人皇子方に属し、御行.安間麻呂.旅人は大納言に昇進。のち新興勢力
の藤原氏に圧せられた。】【大伴金村は、大和時代の豪族。武烈天皇以下五朝の大連。室 屋の孫。皇位を左右する勢力を誇ったが、のち朝鮮半島の経営に失敗して失脚。生没年不
祥。】とある。
その出自を「新撰姓氏録」に捜したら、【1141 河内国 未定雑姓 大伴連 連 天彦命之後也 344】とあるのが見つかった。天彦命とは何者か。
情報に熊本県の「草部吉見神社」がみつかる。 【1、くさかべよしみ(草部吉見神社)熊本県阿蘇郡高森町草部2175 天彦命 日子八 井命の第一皇子・三郎神社の祭神
社殿の東方300mばかりのところに、石の玉垣で囲まれ た日子八井命の御神陵(ミササキ)がある(陵墓参考地)。摂社として、草部吉見神社か ら1・5Kmばかり西の菅道(スゲノサコ)に日子八井命の御子天彦命と天彦命の妃比命
をまつる三郎神社がある。】 これによると、「日子八井命の第一皇子」とある。また別の情報によると、大伴氏系図には 以下の如く、出自として「天忍日命」が置かれている。ー室屋ー談ー金村
天忍日命ー道臣命ー武日命ー武持(大伴氏賜姓)ー| ー御物 出自が異なるが、何れにしても天皇族の一員として記録されている。大伴は後代に賜った姓
名とすれば、本命は「金村」である。 |
| 【北魏分裂、西魏(535~557年)、東魏(534~550年)時代】 |
| 【北魏分裂、西魏(535~557年)、東魏(534~550年)時代】 |
| 北魏は分裂して、西魏(535~557年)と、東魏(534~550年)となる。西魏は、北周(557~581年)によって受け継がれ、東魏は、北斉(550~577年)によって受け継がれる。五胡十六国のあと、北魏、西魏、北周、東魏、北斉の五王朝がたつわけである。535年、北魏が滅びる。その後は短命な王朝が続く。北周が北斉を併合する。
|
| 【「隋」時代】 |
581年、隋が北周を滅ぼす。
589年、隋は、南朝の陳をあわせて南北を統一した。
隋の初代皇帝・楊堅(ようけん)。その父は、中国北部の遊牧騎馬民族「鮮卑」が建てた「北周」の大将軍・楊忠。楊忠の父は、同じく「鮮卑」が建てた「北魏」の将軍・楊禎。この楊氏は、後漢の楊震の末裔と称し、その先祖は前漢初期の楊喜と云われる。その父祖まで遡り、彼らが中原の居住民であって、「華夏」。
煬帝は即位後すぐに廃太子の楊勇を探し出して殺害。弟の漢王楊諒の反乱鎮圧殺害。質素を好んだ父文帝とは対照的に派手好み。大土木事業を大々的に推し進め、100万余の男女が徴発されて労苦にあえぐ。自身の行幸や首都の輸出入、軍の輸送などに人民を酷使。長城の修築に100万余の男女を徴発し、過酷な労役で多くの死者を出す。行幸を東西に繰り返し、国庫や民衆に多大な負担を負わせる。諸国の朝貢使節を頻繁に招き、民衆に多大な災難を招いた。
609年、裴世清が帰国。610年、「諸国の朝貢使節を頻繁に招く」。同年、113万人の兵士を徴兵し高句麗遠征に大敗。611年、4回目の高句麗遠征を計画するが遂に自軍の反乱に合う。自ら軍を率いて北方の突厥鎮圧に向かうも撤退。中国全土で反乱がピークに。616年、反乱鎮圧に殺戮政策をもって当たったが失敗。諫言や提言する臣下を殺戮。618年、酒色にふける生活を送り臣下によって殺害される。
|
| 【「唐」時代】 |
| 618年、隋が滅び唐が成立する。 |
| この時代、姚思廉の「梁書」、房玄齢の「晋書」、魏徴の「隋書」、張楚金の「翰苑」、劉知幾の「史通」、***の「旧唐書」が著される。旧唐書には「日本国は倭国の別種であり、もと小国の日本が倭を併合した」とある。新唐書日本伝には、神武以前の日本の統治者が「筑紫城」にあり、後に大和地方を治めたとある。 |
| 【梁書】 |
太宗の命を受けて、唐の著作郎であった姚思廉(ちょうしれん、?~637)の撰で「梁書」が編纂されている。636(貞観10)年に完成した。成立は唐の太宗の貞観三年(629年)とも云われている。本紀6巻.列伝50巻の57巻。四世―56年の歴史を記している。()。史料的価値は『宋書』より低いと見られる。梁書巻五四の諸夷伝に倭に関する記述がある。正しくは、「梁書巻57.東夷伝.倭条。56巻」。先行する倭に関係する記述を適宜に採録したものである。倭の五王名や続柄が「宋書」と異なっている。一支.臺與とある。「塚田敬章/梁書倭伝」。
| 「倭者、自云太伯之後。俗皆文身。去帶方萬二千餘里、大抵在會稽之東、相去絶遠」。 |
| (和訳)「倭は、自ら太伯の後裔だという。その風俗では皆な体に入れ墨している。帯方郡を去ること万二千余里、おおよそ会稽郡の東に在るが、とてつもなく遠く離れている」。 |
| 「從帶方至倭、循海水行、歴韓國、乍東乍南、七千餘里 始度一海 海闊千餘里、名瀚海、至一支國。又度一海千餘里、名未盧國。又東南陸行五百里、至伊都國。又東南行百里、至奴國。又東行百里、至不彌國。又南水行二十日、至投馬國。又南水行十日、陸行一月日、至邪馬臺國、即倭王所居 其官有伊支馬次曰彌馬獲支次曰奴往鞮」。 |
| (和訳) 「帯方郡から倭に至るには、海(岸)沿いに航海して韓国を過ぎ、東へ行ったり南へ行ったりしながら、七千余里で、初めて一海を渡る。海は広く、千余里。瀚海(広い海)と名づけられている。
一支国に至る。また一海を渡ること千余里、名は未盧国。また東南に陸行五百里で伊都国に至る。また東南に行くこと百里で奴国に至る。また東に行くこと百里で不彌国に至る。また南に水行すること二十日で投馬国に至る。また南に水行十日、陸行ひと月で祁馬臺国に至る。すなわち倭王が居る所である。その官には伊支馬があり、次は彌馬獲支といい、次は奴往鞮という」。 |
| 旅程は魏志を要約しながら引用したものですが、魏志に「海闊」という言葉はない。瀚海と呼ばれる理由を考えた結果、海が広いからだという解説が付け加えられた。「未盧」は「末盧」の転写間違い。「南水行十日陸行一月日至祁馬臺国」の、一月日の日は衍字、祁馬臺は邪馬臺の転写間違いと考えられる。 |
| 「至魏景初三、公孫淵誅 後卑彌呼始遺使朝貢、魏以爲親魏王、假金印紫綬。正始中、卑彌呼死、更立男王、國中不服、更相誅殺。復立卑彌呼宗女臺與爲王、其後復立男王、並受中國爵命。晋安帝時、有倭王賛。賛死、立弟彌。彌死、立子濟。濟死、立子興。 興死立弟武。齊建元中、除武持節、督倭新羅任那伽羅秦韓慕韓六國諸軍事、鎭東大將軍。高祖即位、進武號征東(大)
將軍。其南有侏儒國、人長三四尺、又南黒齒國、裸國、去倭四千餘里、船行可一年至」。 |
| (和訳) |
| 「文身國、在倭國東北七千餘里。人體有文如獸、其額上有三文、文直者貴、文小者賤。土俗歡樂、物豊而賤、行客不齎 糧。有屋宇、無城郭。其王所居、飾以金銀珍麗。繞屋塹、廣一丈、實以水銀、雨則流于水銀之上」。 |
| (和訳) |
| 「民種禾稻紵麻 蠶桑織績 有薑桂橘椒蘇 出黒雉真珠青玉 有獸如牛名山鼠 又有大蛇吞此獸 蛇皮堅不可斫其上有孔乍開乍閉時或有光射之中蛇則死矣 物産略與儋耳朱崖同 地温暖」 |
| (和訳)「住民は稲や紵麻を種まき、養蚕して織物を作る。ショウガ、肉桂、橘、サンショウ、シソがある。黒雉、真珠、青玉を産出する。牛のような獣がいて山鼠と呼ばれている。また、この獣を呑む大蛇がいる。蛇の皮は堅くて叩き切れないが、頭上に孔があり、開いたり閉じたりして、時に光を発する。この中を射れば蛇は死ぬ。産物は儋耳、朱崖とほとんど同じで、土地は温暖である」。 |
| 魏志に肉桂、シソという記述はない。新たな伝聞資料によると思われる。山鼠やそれを飲む大蛇、特に大蛇は詳しく、イルカ、鯨の類と蛇が合成された妖怪のようである。梁書は唐の姚思廉の編纂で、太宗の貞観十年(636)に完成したとされている。 |
| 「風俗不淫 男女皆露紒 富貴者以錦繍雜采為帽似中國胡公頭 食飲用籩豆 其死有棺無槨封土作冢」。 |
| 「風俗はみだらではない。男女は皆、頭に何も被らず、髷を結っている。富貴な者は色とりどりの美しい織物を帽子と為し、中国の胡の貴族の頭に似ている。飲食には竹を編んだり、木をくり抜いたりした高坏を用いる。死に際して、棺はあるが槨はなく、土を封じて墓を作る」。 |
| 隋書には、隋の時代に、その王が冠制度を始めたと書いてある。これは聖徳太子の冠位十二階を指していると思われる。食器に「籩豆を用いる」というのは魏志からの引用で、隋書にはカシワの葉を皿代わりにすると書いてある。 |
| 「人性皆嗜酒 俗不知正歳 多壽考多至八九十或至百歳 其俗女多男少 貴者至四五妻賤者猶兩三妻 婦人無婬妒 無盜竊少諍訟 若犯法輕者沒其妻子重則滅其宗族」。 |
| 「人の性質は皆、酒を嗜む。正月を知らない。長寿者が多く、多くは八~九十歳、あるいは百歳に至る。女が多く男が少ない。身分の高い者は四、五人の妻がいて、低い者でも二、三人の妻がいる。婦人は姦淫したり嫉妬したりしない。盗みをはたらくものはおらず、訴え事も少ない。もし法を犯せば、軽いものはその妻子の身分を奪って奴隷とし、重いものはその宗族を滅ぼす」。 |
| 「漢靈帝光和中 倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子卑彌呼為王 彌呼無夫壻 挾鬼道能惑衆故國人立之 有男弟佐治國 自為王少有見者 以婢千人自侍唯使一男子出入傳教令 所處宮室常有兵守衛」。 |
| 「漢の霊帝の光和年間(178~183)、倭国は乱れ、戦いあって年月を経た。そこで、卑彌呼という一人の女性を共立して王と為した。彌呼には夫はいない。鬼道をあやつって、衆を惑わすことができたため、国人はこれを立てたのである。弟がいて統治を補佐している。王となってから面会した者は少ない、千人の侍女が侍り、ただ一人の男子に出入りさせ、教えや命令を伝えている。住んでいる宮殿には常に兵がいて守衛している」。 |
| 後漢書では「安帝永初元年、倭国王帥升等、生口百六十人を献じ、願いて見を請う。桓霊の間、倭国大乱」になっている。それに魏志の記述「住七八十年、倭国は乱れ、相攻伐すること歴年」という記述が重ねられた。安帝永初元年(107)頃に、卑弥呼の一族が倭に移住したと考え、それに倭人伝の七、八十年を加えて、大乱は霊帝の光和年間(178~183)という結論が出された。「桓霊の間」で大乱は桓帝(147~167)と霊帝(168~188)にまたがっている。 |
| 「至魏景初三年 公孫淵誅後卑彌呼始遣使朝貢 魏以為親魏王假金印紫綬 正始中卑彌(呼)死更立男王國中不服更相誅殺 復立卑彌呼宗女臺與為王 其後復立男王並受中國爵命」。 |
| 「魏の景初三年(239)に至り、公孫淵が滅ぼされた後、卑彌呼は初めて使者を派遣して朝貢した。魏は親魏王と為して金印紫綬を与えた。正始中(240~248)、卑彌呼が死に、交代して男王を立てたが、国中が服さず、互いに誅殺しあったので、女王に戻して卑彌呼の宗女、臺與を立てて王にした。その後、また男の王が立ち、いずれも中国の爵命を受けた」。 |
| 魏志には景初二年(238)に卑彌呼が遣使したとされている。この頃、遼東、樂浪、帯方には公孫氏が存在し魏に抵抗していた。魏へ遣使することはできないので景初三年に修正された。しかし、魏へ遣使したと考えるから矛盾が出るわけで、卑彌呼は遼東の公孫氏に遣使したと考えれば景初二年でなんの問題もない。景初三年と考えると、魏の明帝は死去しており、魏帝は八歳の斉王芳と扱わねばならないし倭への下賜品を作っている時間もない。帯方太守の交代時間にも無理が出るという別の矛盾が吹き出す。魏志で壹與(壱与)となっている卑弥呼の宗女を臺與(台与)に改めている。魏志の邪馬壹国も邪馬臺國に改められている。唐代の認識では、都がヤマトとわかったことから、魏志の邪馬壹は転写間違いで、後漢書の邪馬臺が正しいという結論が出されていた。壹は臺の転写間違いなので、当然、壹與も臺與だと修正されました。実際には邪馬壹、壹與が正しい。このあたりは、「魏志倭人伝から見える日本、ファイル1」や「邪馬壹国説を支持する資料と解説」で説明しています。後の、中国の爵命を受けた男王とは、宋書に記された讃、珍、済、興、武という倭の五王のことです。 |
| 「晉安帝時有倭王賛 賛死立弟彌 彌死立子濟 濟死立子興 興死立弟武 齊建元中除武持節督倭新羅任那伽羅秦韓慕韓六國諸軍事鎮東大將軍 高祖即位進武號征東大將軍」。 |
| 「晋の安帝時(397~418)、倭王讃がいた。讃が死に、弟の彌が立った。彌が死に、子の済が立った。済が死に、子の興が立った。興が死に、弟の武が立った。斉の建元中(479~482)、武に持節督倭新羅任那伽羅秦韓慕韓六国諸軍事鎮東大将軍に任命した。梁の高祖(武帝)が即位し(502)、武の号を征東大将軍に進めた」。 |
| 晋の安帝の義煕九年(413)に倭王の遣使が伝えられている(晋書安帝紀)。王名は記されていない。倭王讃の遣使は、宋書倭国伝の、宋の高祖の永初二年(421)で、それに先立つ413年の遣使も讃(応神天皇、ホムダワケ大王)のものだと考えた。実際には一世代前の神功皇后の遣使です。421年の讃の遣使は即位の挨拶と考えられる。宋書、昇明二年(478)に倭王武の遣使の記述があるが斉や梁への武の遣使の記録はなく進号の記述だけである。しかし、梁代の職貢図に倭の使者の姿が描かれていて、脚絆や腕抜きという後の風俗につながる描写がある。 |
| 「其南有侏儒国 人長三四尺 又南黒齒國裸國 去倭四千餘里船行可一年至 又西南萬里有海人 身黒眼白裸而醜其肉羙行者或射而食之」。 |
| 「その南に侏儒国がある。人の背丈は三、四尺。また、南に黒歯国、裸国がある。倭を去ること四千余里、船で行くこと一年ほどで着く。また西南万里に海人がいて、身は黒く,眼は白く、裸でみにくいが、その肉はうまい。旅行者は射たりしてこれを食べる」(羙は美の俗字)。 |
|
| 【晋書】 |
646年(唐の貞観年20)年、時の太宗皇帝は、重臣の房玄齢((578―648)と皇帝政務秘書のちょ遂良(596-657)に晋書の定本をつくるよう命じ、そこで房玄齢を作業主任として8名の責任者が分担を決めて史料の採集登録にあたり、その下に多数の歴史館スタッフが調査.考証に従事し、648年に完成した。それまでの史書編纂がどちらかといえば個人的な業であったのに対して、いわば国家事業的に編纂されるところとなった。本書以降は、こうした国家的組織的な編纂事業ともなった。これを「晋書」と云う。「晋書」は、唐の貞観年間に編纂され帝紀30巻、志20巻、列伝70巻、載記30巻より成る130巻。一部に太宗皇帝自身が筆をとった個所があり、太宗勅撰の書とも云われる。西晋265から316、東晋317から402時代を語る正史である。この時代は貞観の治と称されるように、文化的にも政治的にももっとも安定した時期であった。
巻30東夷伝.倭人条に、倭関係の記事をのせている。武帝紀にも書かれている。邪馬台国についての記述がある。266年に倭人が来て、円丘・方丘を南北郊に併せ、二至の祀りを二郊に合わせたと述べられ、前方後円墳のおこりを記したものとされている。289(太康10)年の条には、「東夷絶遠三十餘國
西南二十餘國來獻」とあり、絶遠の国が日本であるといわれる。
| 「倭人在帶方東南大海中、依山島爲國、地多山林、無良田、食海物。舊有百餘小國相接、至魏時、有三十國通好。戸有七萬。男子無大小悉黥面文身。自謂太伯之後」。 |
| (和訳) |
| 「宣帝之平公孫氏也 其女王遣使至帶方朝見 其後貢聘不絶 及文帝作相、又數至。泰始初 遣使重譯入貢」。 |
| (和訳) |
晋書の太康10年(289年)の条には、「東夷絶遠三十餘國 西南二十餘國來獻」と記述されている。
晋書帝紀では邪馬台国を「東倭」と表現する次の記述がある。
| 「(魏)正始元年春正月、 東倭重譯納貢,焉耆、危須諸國、弱水以南、鮮卑名王、皆遣使來獻。天子歸美宰輔、又増帝封邑」。 |
晋書帝紀の武帝紀「(泰始)二年/十一月已卯、倭人來獻方物」、安帝紀「(義熈)九年/是歳、高句驪、倭國、及西南夷、銅頭大帥、並獻方物」。 |
| 【翰苑(かんえん)】 |
700年頃、唐初の張楚金(ちょうそきん、**~660年)編集の類書で、後に雍公叡が注をつけた。30巻とされる。張楚金は高宋(在位649から683)に仕え、則天武后(在位684から705)の時、配流先の嶺表で死亡。この本は、いろいろな書物から語句を集め、事類別に叙述しているが、南宋以後解散逸してしまった。「魏略」、「広志」を引用しており考証的価値が高い。1917年に東京大学の黒板勝美博士により、巻30「蕃夷部」の残巻と後述の写本が、太宰府天満宮の宮司、西高辻家に残存しているのが発見された。今日、まとまった形で残存している唯一のものである。
蕃夷(ばんい)部第30巻及び叙文のみが太宰府天満宮に唯一現存する。国宝とされ、1977年、菅原道真の1075年忌事業として竹内理三による釈文・訓読文が付けられて刊行された。第30巻蕃夷部は、匈奴・烏桓・鮮卑・倭国・西域などの15の子目に分けられている。翰苑のほとんどが失われてしまっている為に巻数については諸説ある。旧唐書張道源(著者の祖先)伝には30巻、新唐書芸文志には7巻と20巻の2説が併記され、宋史芸文志には11巻とされている。明治時代に内藤湖南によって30巻であることが明らかにされている。
類書とは、各種の書物の内容を編者の考える事項別に分類収録したもの。日本に唯一伝存している翰苑は9世紀に書写されたものであるが誤字や脱漏が多い。魏略の引用が多い。「翰苑卷第卅蕃夷部(倭國条)」は次のように記している。
倭國
憑山負海 鎭馬臺以建都 分軄命官 統女王而列部 卑弥娥惑翻叶群情 臺與幼齒 方諧衆望 文身點面 猶稱太伯之苗 阿輩雞弥 自表天兒之稱 因禮義而標袟 即智信以命官 邪屆伊都 傍連斯馬 中元之際 紫綬之榮 景初之辰 恭文錦之獻
倭國
山に憑き海を負い、馬臺に鎭し以って都を建つ。軄を分かち官を命じ、女王に統(す)べられて部を列す。卑弥は惑翻(わくほん)を娥し、群情に叶かなう。臺與は幼齒にして、方(まさ)に衆望に諧(かな)う。文身點(鯨)面し、猶(なお)太伯の苗と稱す。阿輩雞弥(あはきみ)は、自ら天兒の稱を表す。禮義に因りて袟(ちつ)を標す。即ち智信を以って官を命ず。邪国の伊都は、傍ら斯馬(しま)に連なる。中元の際、紫綬の榮あり。景初の辰、文錦の獻を恭(うやうやしく)す。 |
 (私論.私見) 翰苑(かんえん)考 (私論.私見) 翰苑(かんえん)考
|
「卑弥娥惑翻叶群情」の和訳読み下しが難しい。1例は「卑弥娥は惑翻(わくほん)して群情(ぐんじょう)に叶う」。古田氏は「第4章 四~七世紀の盲点 十一 歴代の倭都は「謎」ではない ーー『翰苑』をめぐって」で「卑弥は妖惑(ようわく)して翻(ひる)かえって群情に叶(かな)う」と読んでいる。れんだいこは次のように読みたい。「卑弥は惑翻(わくほん)を娥し、群情に叶かなう」。
翰苑(かんえん)探求のハイライトは「邪屆伊都 傍連斯馬」にある。これをどう読むべきか。1例は「邪は伊都に屆き、傍ら斯馬(しま)に連なる」。古田氏は「邪めに伊都に届き傍(かたわら)斯馬(しま)に連なる」と読み、「倭国の都は、ななめに伊都国に直接とどき、その向うに斯馬国が連なる、という、地理的位置に存在している」と解釈している。こうなると、倭国の都即ち邪馬台国は伊都国、斯馬国に近いところにあると云うことになる。翰苑(かんえん)文の解釈としてはそれで構わないが、そうなると魏志倭人伝その他の邪馬台国所在地記述と大きく異なることになる。これを踏まえて整合的に読むとすれば「邪国の伊都は、傍ら斯馬(しま)に連なる」ではなかろうか。即ち、「邪馬台国の出先監督国であるし伊都は、傍ら斯馬(しま)に連なっている」ではなかろうか。ここは単に伊都を語っていると読みたい。
「中元之際 紫綬之榮」は「中元の際、紫綬の榮あり」と読み、「後漢の中元年間(光武帝の末年)に金印紫綬の栄を受けた」と解する。受けた側の主体は邪馬台国と伊都の両方に掛かっていると解したい。「景初之辰 恭文錦之獻」は「景初の辰、文錦の獻を恭(うやうやしく)す」と読み、「魏の景初年間の辰にあや錦(にしき 斑布)をうやうやしく献上した」と解したい。
2013.3.19日 れんだいこ拝 |
|
太宰府天満宮蔵の翰苑の注記に広志が引用され次のように記されている。(「古田武彦氏の『謎の四世紀』の史料批判」参照)
| 「広志曰[イ妾]国東南陸行五百里到伊都国又南至邪馬嘉国百女国以北其戸数道里可得略載次斯馬国次巴百支国次伊邪国安[イ妾]西南海行一日有伊邪分国無布帛以草為衣盖伊耶国也」(字画は太宰府原本のまま) |
| (和訳) 「広志に曰く、「[イ妾](=倭)国。東南陸行、五百里にして伊都国に到る。又南、邪馬嘉国に至る。百女国以北、其の戸数道里は、略載するを得可(うべ)し。次に斯馬国、次に巴百支国、次に伊邪国。安(=案)ずるに、[イ妾]の西南海行一日にして伊邪分国有り。布帛(ふはく)無し。草(革か)を以て衣と為す。盖(けだ)し伊耶国也」。 |
魏志倭人伝の邪馬台国がここでは「邪馬嘉国」と書かれている。邪馬嘉国が邪馬台国と同じであるかどうかは分からない。「女王の都する所」云々の説明がこの文面に全くないからである。
広志の成立年代は、「晋(しん)の郭義恭撰、広志二巻」の存在したことが知られているので、四世紀頃、晋朝期の成立であることが分かる。その根拠は、1・「韓国・夫余・悒*婁ゆうろう」といった呼び方で朝鮮半島南半等を書いている(五世紀の宋書では「百済・新羅」等)。2・会稽(かいけい)郡南部たる「建安」の名が出ているので少なくとも永安三年(二六〇)の「建安郡」分郡以後の成立であることが明白である。3・「倭国伝」の内容からも三国志以後の成立であることが疑いない。陳寿は297(元康7)年に死んでいるので、広志の成立は早くとも三世紀末をさかのぼりえない。以上によって、広志は三世紀末~四世紀末間の成立であることが判明する。
広志には、もう一つの倭国記事がある(岩波文庫等にも紹介せられていない)。倭人伝にも「真珠・青玉を出だす」とある。両書の「倭国」は同一国であることがうかがえよう。
| 「白玉の美なる者、以て面を照らす可し。交州に出づ。青玉は倭国に出づ。赤玉は夫余に出づ。瑜玉・元玉・水蒼玉(すいそうぎょく)は皆佩用(はいよう)す」。〈『芸文類聚』巻八十三。『太平御覧』巻八百五は「瑜玉」以下無し〉 |
|
| 【隋書】 |
7世紀後半の656年頃、唐王朝の魏徴(ぎちょう、581~643)の撰により「隋書」
が著されている。成立は太宗の貞観10年(636年)で、85巻(帝紀5巻.列伝50巻
、のち貞観15年に撰した5代志梁.陳.斉.周.隋の10志330巻を加え、現行85
巻とした)。
その卷八十一列傳第四十六東夷に「俀國(たいこく)」の条(「隋書巻81.東夷伝.
倭国条」)がある。これを通称「隋書倭國傳」と云う。そこには西暦600年以来の4回
の遣隋使のことや推古天皇の治世の様子が記されている。隋では、魏志倭人傳を
通して古くから倭國の首都国・邪馬臺國のことや卑彌呼のことが知られていた。そこ
へ倭國からの遣隋使が首都国・大和(やまと)國から来たと名乗った。このことが、隋
書倭國傳に、「倭國は邪靡堆(やまと)を都とする。すなわち、『魏志倭人傳』の言うと
ころの邪馬臺(やまたい)である」と書かれている(都於邪靡堆則魏志所謂邪馬臺者
也)。これは、唐の時代になって魏徴が隋書を書く上で、魏の時代の女王の邪馬臺國
と隋の時代の大和政権の邪靡堆國とを識別していたことが判明する。
「隋書巻81.東夷伝.倭国条」には、「男女多く臂(うで・ひじ)に黥(げい)す。黥面
文身して、水に没して魚を捕る」と記述している。これは608(推古16)年の隋使・裴
世清(はいせいせい)の一行の見聞や観察を基礎にしたもので、7世紀初頭の倭人
社会についての貴重な資料である。また、「新羅 百濟皆以?為大國 多珍物 並敬仰
之 恒通使往來」、新羅・百濟は、みな倭を以て大国にして珍物多しとなし。並びにこ
れを敬い仰ぎて、恒に使いを通わせ往来す」とあり、当時の外交状況がみてとれる。
また、倭人が鉄を使用していたという記述がある。
|
隋は倭国のことを俀国と記載している。邪馬臺(ヤマタイ)は邪馬臺國をさす。この
記述は魏志倭人伝の記述を継承しており、邪馬臺国が倭国(俀国)になったと述べて
いる。邪靡堆とはヤマトのことである。また、「魏から斉、梁に至るまで代々中国と交
流していた」とも記載している。この記述は、邪馬壹国が継続して歴代の王朝と交流
を続けていたことを証言している。即ち、隋の時代まで、邪馬臺國(後漢書の表記)が
存在し交流していたことになる。 |
隋書俀国伝に、「600年と607年に、隋の文帝、煬帝に使者を派遣した倭王(阿毎
多利思北孤)と言う人物の記述がある。隋に到着した倭国(隋では俀国)の使者たち
に、「隋の役人」が聞き取り調査をしている。この時、使者たちは、「倭国王の名前、倭
国の風俗、倭王の妻の名前、倭王の後宮には侍女が六、七百人いる、太子の名前
は利歌弥多弗利である、倭国には城郭がない、倭国の位階は十二等ある、外官に
は軍尼が120人いる、倭国には阿蘇山があって、突然噴火して溶岩が天にとどかん
ばかりになるを、土地の習俗では異変とみなして祈祷祭祀を行う」等々語り、その内容
が隋書俀国伝に記述されている。注目されるべきは、当時の列島の最高権力者とし
ての倭王が「日本書記の推古紀に登場する厩戸皇子でも蘇我馬子」でなく「阿毎多利
思北孤」と記されていることである。その倭王が、倭の宗主国であった「南朝陳」を滅
ぼして中国を統一した「隋朝」に対して始めて使者を派遣しており、その時のやりとり
が記されている。 |
隋書倭国伝は次の通り。文中「倭国の都は邪靡堆(やまと)にあり、これは魏書に
記された邪馬台なり」は決定的な記述と拝察したい。
| 倭國、在百濟、新羅東南、水陸三千里、於大海之中依山島而居。 |
(倭国は、百済国や新羅国の東南に在り水陸を越えること三千里、大海中の山島
に依って居する) |
(倭国は、百済・新羅の東南、水陸三千里に在り。大海中に於いて山島に依りて居
る) |
| 魏時,譯通中國。三十餘國,皆自稱王。 |
| () |
|
(魏の時、中国に訳通すは三十余国。皆、自ら王と称す)
|
| 夷人不知里數、但計以日。 |
| () |
| (夷人は里数を知らず、ただ計るに日を以ってす) |
| 其國境東西五月行、南北三月行、各至於海。 |
| () |
| (その国境は東西五カ月の行、南北三カ月の行にして、各々海に至る) |
| 其地勢東高西下。 |
| () |
| (その地勢は東高西低である) |
| 都於邪靡堆、則魏志所謂邪馬臺者也 |
| (邪靡堆に都す。則ち、魏志謂うところの邪馬臺なるもの也) |
| (倭国の都は邪靡堆(やまと)にあり、これは魏書に記された邪馬台なり) |
| 古云去 樂浪郡境 及帶方郡並一萬二千里,在會稽之東,與儋耳相近。 |
| () |
(古より云う。楽浪郡の境及び帯方郡を去ること一万二千里、会稽の東に在り。儋
耳と相近し) |
| 漢光武時,遣使入朝,自稱大夫。 |
| () |
| (後漢の光武帝の時(25-57年)、遣使、入朝し、自ら大夫と称す) |
| 安帝時,又遣使朝貢,謂之倭奴國。 |
| () |
| (安帝の時(106-125年)、また遣使が朝貢、これを倭奴国という) |
| (又)桓、靈之間,其國大亂,遞相攻伐,歴年無主。 |
| () |
(桓帝と霊帝の間(146-189年)、その国大いに乱れ、遞に相攻伐し、年歴るも、
主無し) |
| 有女子名卑彌呼,能以鬼道惑衆,於是國人共立為王。 |
| () |
(女子有り。名は卑彌呼。能く鬼道を以て衆を惑わす。ここに於いて国人、共立し王
と為す) |
| 有男弟,佐卑彌理國。 |
| () |
| (男弟有り、卑彌を佐けて国を理む) |
| 其王有侍婢千人,罕有見其面者,唯有男子二人給王飲食,通傳言語。 |
| () |
(その王、侍婢千人有り。その面を見たることある者罕なり。ただ男子二人のみ有り
て、王に飲食を給し、言語を通伝す)
※魏志倭人伝では卑彌呼に仕えた男子は一人のところ、隋書では二人になっている
。書き間違いか、別の情報源があったのか不明。 |
| 其王有宮室樓觀,城柵皆持兵守衛,為法甚嚴。 |
| () |
| (その王、宮室、楼観、城柵あり、皆兵を持ちて守衛し、法を為むること甚だ厳なり) |
| 自魏至于齊、梁,代與中國相通。 |
| () |
| (魏より斉・梁に至るまで、代々中国と相通ず) |
| 開皇二十年,倭王姓阿毎,字多利思比孤,號阿輩雞彌,遣使詣闕。 |
(隋の開皇二十年(600)、倭王、姓は阿毎、字は多利思比孤、号は阿輩雞彌、遣
使を闕(けつ・王宮の門)に詣しむ) |
(倭王、阿毎多利思比孤(天帯彦あるいは天足彦:あまたらしひこ)、号は阿輩雞
彌(阿波王:あはきみ・けみ)、遣使を宮殿に詣らす)
※「阿輩雞彌」をどう読むべきか。
※旧唐書にも「倭國者 古倭奴國也」の一文がある。旧唐書中の「倭奴國」は「其王
・姓阿毎氏」とあるので、隋書中の「倭王・姓阿毎・字多利思比孤」の「倭王」とは「倭
奴國王」と符合していることになる。
|
| 上令所司訪其風俗。 |
| () |
| (上(文帝)、所司をしてその風俗を尋ねしむ) |
使者言 倭王以天為兄,以日為弟,天未明時出聽政,跏趺坐,日出便停理務,云
委我弟。 |
| () |
(使者言う、「倭王は天を以て兄となし、日を以て弟となす。天未だ明けざる時、出
でて政を聴き、跏趺して坐す。日出ずれば、すなわち理務を停め、我が弟に委ねん
と云う」と) |
| 高祖曰:「此太無義理」。於是訓令改之。 |
| () |
| (高祖曰く「これはなはだ義理なし」。ここに於いて訓してこれを改めしむ) |
| 王妻號彌,後宮有女六七百人。名太子為利歌彌多弗利。 |
| () |
(王の妻は雞彌(きみ・けみ)と号す。後宮に女六~七百人あり。太子を名づけて利
歌彌多弗利(りかみたふり)と為す) |
無城郭。内官有十二等:一曰大德,次小德,次大仁,次小仁,次大義,次小義,
次大禮,次小禮,次大智,次小智,次大信,次小信,員無定數。有軍尼一百二十
人,猶中國牧宰。八十戸置一伊尼翼,如今里長也。十伊尼翼屬一軍尼。 |
| () |
| () |
| 其服飾,男子衣裙襦,其袖微小,履如形,漆其上,繁之於。人庶多跣足。 |
| () |
| () |
| 不得用金銀為飾。故時衣橫幅,結束相連而無縫。頭亦無冠,但垂髮於兩耳上。 |
| () |
| () |
至隋,其王始制冠,以錦綵為之,以金銀鏤花為飾。婦人束髮於後,亦衣裙襦,裳
皆有●。 |
| () |
| () |
竹為梳,編草為薦,雜皮為表,縁以文皮。有弓、矢、刀、●、弩、●、斧,漆皮為
甲,骨為矢鏑。 |
| () |
| () |
| 雖有兵,無征戰。其王朝會,必陳設儀仗,奏其國樂。戸可十萬。 |
| 其俗殺人強盜及姦皆死,盜者計贓酬物,無財者沒身為奴。 |
| () |
| () |
自餘輕重,或流或杖。毎訊究獄訟,不承引者,以木壓膝,或張強弓,以弦鋸其項
。 |
| () |
| () |
或置小石於沸湯中,令所競者探之,云理曲者即手爛。或置蛇甕中,令取之,云
曲者即螫手矣。 |
| () |
| () |
人頗恬靜,罕爭訟,少盜賊。樂有五弦、琴、笛。男女多黥臂點面文身,沒水捕魚
。 |
| () |
| () |
| 無文字、唯刻木結繩。 |
| (倭国には文字はなく、ただ木を刻み縄を結ぶだけ)。 |
敬佛法,於百濟求得佛經,始有文字。知卜筮,尤信巫覡。毎至正月一日,必射戲
飲酒,其餘節略與華同。 |
| 好棋博、握槊、樗蒲之戲。氣候温暖,草木冬青,土地膏腴,水多陸少。 |
| 小環挂 ●項,令入水捕魚,日得百餘頭。俗無盤俎,藉以檞葉,食用手餔之。 |
性質直,有雅風。女多男少,婚嫁不取同姓,男女相悅者即為婚。婦入夫家,必先
跨犬 乃與夫相見。 |
婦人不淫。死者斂以棺槨,親賓就屍歌舞,妻子兄弟以白布製服。貴人三年殯於
外,庶人卜日而。 |
| 及葬,置屍船上,陸地牽之,或以小輿。 |
| 有阿蘇山,其石無故火起接天者,俗以為異,因行(禱)祭。 |
(阿蘇山あり、その石故無くして火起こり天に接することあり。俗、以ってこれを異と
なし、因って禱祭を行う) |
(和訳)阿蘇山があり、そこの石は故無く火柱を昇らせ、天に接し、俗人はこれを異
として、祭祀を執り行っている。
※倭国には「阿蘇山」という火山があり、その噴火は凶兆だとして祈りを捧げる風俗
が報告されている。 |
| 有如意寶珠、其色青、大如(雞)卵、夜則有光、云魚眼精也。 |
|
|
| 新羅、百濟皆以倭為大國、多珍物、並敬仰之、恒通使往來 |
|
(和訳) 新羅や百済は皆な倭を大国と見なしており、珍物が多く、並びにこれを敬
仰して常に通使が往来している。
※阿輩雞彌(あわきみ)は、続けて大業三年(607年)、使者を隋に送ったが、その時
の国書が有名な「日出ずる處の天子、書を日沒する處の天子に致す。恙なきや」云
々です。これに対し、隋の煬帝は「蛮夷の書に無礼あり。二度と奏上するなかれ」と
激怒しました。過去記事でも中国の朝貢制度の本質について書きましたが、それか
らすると全く許しがたい国書だったわけです。煬帝は皇帝としての顔を潰された思い
で怒りに打ち震えたのでした。一体何が「皇帝としての煬帝」を否定することになった
のかといえば、それは「天子」の文言です。
|
大業三年、其王多利思比孤遣使朝貢。使者曰:「聞海西菩薩天子重興佛法,故遣
朝拜,兼沙門數十人來學佛法」。 |
| () |
(大業三年(607年)、その王、多利思比孤、使いを遣して朝貢せしむ。使者曰く「
聞く、海西の菩薩天子、重ねて仏法を興すと。故に遣わして朝拝せしめ、兼ねて沙
門数十人来たりて仏法を学ばしむ」と) |
| 其國書曰「日出處天子致書日沒處天子無恙」云云。 |
| () |
(その国書に曰く「日出ずる處の天子、書を日沒する處の天子に致す。恙なきや」
云々) |
| 帝覽之不悅,謂鴻臚卿曰:「蠻夷書有無禮者,勿復以聞」。 |
| () |
(帝(煬帝・604年8月21日 - 618年4月11日)、これを見て悦ばず。鴻臚卿(こうろけ
い・外務大臣)に謂いて曰く、蛮夷の書、無礼なる者有り。復た以って聞することなか
れ!と)
※煬帝へ国書を届けたのは、遣隋使・小野妹子であり、この記録は日本書紀にも残
されている。それによれば、小野妹子一行が派遣されたのが推古15年(607)7月。
「十五年秋七月戊申朔庚戌、大禮小野臣妹子遣於大唐、以鞍作福利爲通事」。隋
ではなく大唐と書かれているのは間違い。唐の王朝が起こったのは10年後の618年
。唐は隋から皇帝を禅譲させて立てた国なので、当時の慣例で“大唐”と一括りで呼
んだのかもしれない。
|
|
| 【「日本書紀原文・訳文」。 】 |
「日本書紀原文・訳文」。
|
十六年夏四月、小野臣妹子至自大唐。唐國號妹子臣曰蘇因高。卽大唐使人裴世淸・下客十二人、從妹子臣至於筑紫。遣難波吉士雄成、召大唐客裴世淸等。爲唐客更造新館於難波高麗館之上。
|
| (十六年の夏四月(608.04)、小野臣妹子、大唐より至る。唐国、妹子臣を号けて蘇因高と曰ふ。即ち大唐の使人裴世清、下客十二人、妹子臣に從ひて、筑紫に至る。難波吉士雄成を遣して、大唐の客裴世清等を召す。唐の客の爲に、更新しき館を難波の高麗館の上に造る。
|
| 六月壬寅朔丙辰、客等泊于難波津、是日以飾船卅艘迎客等于江口、安置新館。於是、以中臣宮地連烏磨呂・大河內直糠手・船史王平、爲掌客。 |
| 六月の壬寅の朔丙辰(06.15)に、客等、難波津に泊れり。是の日に、飾船三十艘を以て、客等を江口に、新しき館に安置らしむ。是に、中臣宮地連烏磨呂、大河内直糠手、船史王平を以て掌客とす。 |
|
爰妹子臣奏之曰「臣參還之時、唐帝以書授臣。然經過百濟國之日、百濟人探以掠取。是以不得上」。
|
| 爰に妹子臣、奏して曰さく、「臣、参還る時に、唐の帝、書を以て臣に授く。然るに百済国を経過る日に、百済人、探りて掠み取る。是を以て上ること得ず」とまうす。 |
| 於是、群臣議之曰「夫使人、雖死之不失旨。是使矣、何怠之失大國之書哉」。則坐流刑。時天皇勅之曰「妹子、雖有失書之罪、輙不可罪。其大國客等聞之、亦不良」。乃赦之不坐也。 |
| 是に、群臣、議りて曰はく、「夫れ使たる人は死ると雖も、旨を失はず。是の使、何にぞ怠りて、大国の書を失ふや」といふ。則ち流刑に坐す。時に天皇、勅して曰はく、「妹子、書を失ふ罪有りと雖も、輙く罪すべからず。其の大国の客等聞かむこと、亦不良し」とのたまふ。乃ち赦して坐したまはず) |
|
秋八月辛丑朔癸卯、唐客入京。是日、遣飾騎七十五匹而迎唐客於海石榴市術。
|
| ( 秋八月の辛丑の朔癸卯(08.03)に、唐の客、京に入る。是の日に、飾騎七十五匹を遺して、唐の客を海石榴市の術に迎ふ。 |
|
額田部連比羅夫、以告禮辭焉。壬子、召唐客於朝庭令奏使旨。時、阿倍鳥臣・物部依網連抱二人、爲客之導者也。
|
| 額田部連比羅夫、以て礼の辞を告す。壬子(08.12)に、唐の客を朝庭に召して、使の旨を奏さしむ。時に阿倍鳥臣、物部依網連抱、二人を客の導者とす。 |
| 於是、大唐之國信物、置於庭中。時、使主裴世淸、親持書兩度再拜、言上使旨而立之。 |
| 是に、大唐の国の信物を庭中に置く。時に使主裴世清、親ら書を持ちて、両度再拜みて、使の旨を言上して立つ。 |
| 其書曰「皇帝問倭皇。使人長吏大禮蘇因高等至具懷。 |
| 其の書に曰く、「皇帝、倭皇を問ふ。使人長吏大礼蘇因高等、至でて懐を具にす。 |
| 朕、欽承寶命、臨仰區宇、思弘德化、覃被含靈、愛育之情、無隔遐邇。知皇介居海表、撫寧民庶、境內安樂、風俗融和、深氣至誠、達脩朝貢。丹款之美、朕有嘉焉。稍暄、比如常也。故、遣鴻臚寺掌客裴世淸等、稍宣往意、幷送物如別」。 |
| 朕、宝命を欽び承けて、区宇に臨み仰ぐ。徳化を弘めて、含霊に覃び被らしむことを思ふ。愛み育ふ情、遐く邇きに隔て無し。皇、海表に介り居して、民庶を撫で寧みし、境内安樂にして、風俗融り和ひ、深き気至れる誠ありて、遠く朝貢ふことを脩つといふことを知りぬ。丹款なる美を、朕嘉すること有り。稍に暄なり。比は常の如し。故、鴻臚寺の掌客裴世清等を遣して、稍に往く意を宣ぶ。并て物送りすこと別の如し」といふ。 |
|
時、阿倍臣、出進以受其書而進行。大伴囓連、迎出承書、置於大門前机上而奏之。事畢而退焉。是時、皇子諸王諸臣、悉以金髻花着頭、亦衣服皆用錦紫繡織及五色綾羅。一云、服色皆用冠色。
|
| 時に阿倍臣、出で進みて、其の書を受けて進み行く。大伴囓連、迎へ出でて書を承て、大門の前の机の上に置きて奏す。事畢りて退づ。是の時に、皇子、諸王、諸臣、悉に金の髻花を以て頭に着せり。亦衣服に皆錦、紫、繍、織、及び五色の綾羅を用ゐる。【一に云はく、服の色は、皆冠の色を用ゐるといふ。
|
| 丙辰、饗唐客等於朝。 |
| 丙辰(08.16)に、唐の客等を朝に饗たまふ。 |
| 九月の辛未の朔乙亥(09.05)に、客等を難波の大郡に饗たまふ。辛巳(09.11)に、唐の客裴世清、罷り帰りぬ。則ち復小野妹子臣を以て大使とす) |
| 九月辛未朔乙亥、饗客等於難波大郡。辛巳、唐客裴世淸罷歸。則復以小野妹子臣爲大使。 |
| この時の天皇は、女帝の推古天皇(在位593年~628年)。隋書では、600年時点での倭王の名を「阿毎・多利思比孤・阿輩雞彌」で、妻は「雞彌」太子は「利歌彌多弗利」と書いている。これにつき、「日本書紀の方がおかしい、創作である」とする説がある。その真偽如何。 |
| なぜ、2カ所の難波のうち伊予国なのか?風早郡難波郷は北九州の対岸であり、単純に小野妹子・裴世清一行の行程とマッチする。隋書の記録では秦王国に滞在後、十余国を経て、「ヤマトの海岸」に到着。②その10日後にヤマトの朝廷に呼ばれ、④倭王に謁見したとある。日本書紀では、一行は遣隋使小野妹子とともに来日し、6月15日、難波津に到着滞在、① 8月3日になって京に入り、② その10日後の8月12日、朝廷に呼んだとある。つまり、②の「ヤマトの海岸到着」は「京師(の海岸)到着」であり、①の「難波津」のことではない。ほとんど全ての研究者は、この矛盾を無視している。「難波津」は隋書に記される「又經十餘國 達於海岸」の「海岸」ではない。わかりやすく、日付のはっきりした動きだけを並べてみる。 |
|
『隋書』 上 : 『日本書紀』 下
A【又至竹斯國】【裴世清、筑紫に至る】(608年4月)
B【又東至秦王國】【客等、難波津に泊れり】(608年6月15日)
C【(京の)海岸に達す】【唐の客、京に入る】(608年8月3日)
D【後十日】、 【郊勞せしむ】(後十日。8月3日を含めば、8月12日)
【八月十二日】 【朝庭に召して使の旨を奏さしむ】(608年8月12日)
Bの「難波津」が、Cの「(ヤマトの)海岸」だと思い込んでいる。Bの「難波津」が、Cの「海岸」のことだというなら、そこに(6月15日)~(8月3日)、50日もの誤差が生まれます。常識(?)では、この難波津を大阪とする。その場合、B、難波津に到着後、そのさらに50日後に達した、C,京(ヤマト)の海岸、ってどこですか?すぐ近くの和歌山あたりの海ですか?奈良に海岸はありません。
※隋書の、裴世清を迎えた「海柘榴市」を難波(大坂)から大和川を遡った奈良県内のどこか、と解釈して納得している。隋書に照らした場合、裴世清は、川の上流を海岸と勘違いするほどの抜け作だったということになります。隋書、日本書紀双方の情報と和名抄の郷名から読み解くと、「秦王國」=「難波津」で、裴世清一行が倭王から迎えられたのは伊予の松山周辺。ただし、「難波津」は、津(港)のことで「秦王國」そのものは、難波郷を含むもっと広範囲の地域だと思われます。私は、現在の松山市~今治市~西条市が秦王國に当たると想定しています。
|
| 明年,上遣文林郎裴清使於倭國。度百濟、行至竹島、南望[身冉]羅國、經都斯麻國、迥在大海中。 |
| () |
| (翌(608)年、上(天子こと煬帝)は文林郎の裴世清を使者として倭国に派遣した。百済国を通過、竹島に行き、南方に〔体〕羅国を望み、都斯麻国を経て、遙か大海中に在り) |
| 又東至一支國,又至竹斯國,又東至秦王國, |
| () |
| (また東に一支(壱岐)国に至り、また竹斯(宗像?)国に至り、また東に秦王国に至る)
□A【裴世清、下客十二人、妹子臣に從ひて、筑紫に至る】(608年4月)
□B【客等、難波津に泊れり】(608年6月15日)
|
| 其人同於華夏,以為夷洲,疑不能明也。 |
| () |
| (その人、華夏に同じ。以て夷洲と為すも疑いは明らかにすること能わざる也) |
| 又經十餘國,達於海岸。 |
| () |
| (また十余国を経て、海岸に達す) |
| 自竹斯國以東,皆附庸於倭。 |
| () |
| (竹斯国より東、みな倭に附庸す) |
| 倭王遣小德阿輩臺,從數百人,設儀仗,鳴鼓角來迎。 |
| () |
| (倭王は、小德阿輩臺を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ) |
| (□秋八月の辛丑の朔癸卯に、唐の客、京に入る。是の日に、飾騎七十五匹を遺して、唐の客を海石榴市の術に迎ふ。額田部連比羅夫、以て礼の辞を告す) |
| 後十日,又遣大禮哥多,從二百餘騎郊勞。 |
| () |
| (後十日、大禮の哥多毗(かたひ)を遣わし、二百余騎を従え郊勞せしむ) |
| 既至彼都,其王與清相見,大悅,曰: |
| () |
| (既にして彼の都に至るに、その王(倭王)、清(裴世清)と相見て、大いに悦びて曰く、)
|
| 「我聞海西有大隋,禮義之國,故遣朝貢。我夷人,僻在海隅,不聞禮義,是以稽留境内,不即相見。今故清道飾館,以待大使,冀聞大國惟新之化」。 |
|
|
| (我聞く、海西に大隋有り、礼儀の国なりと。故に遣わして朝貢せしむ。我は夷人にして、僻りて海隅に在り、礼儀を聞かず。是を以て境内に稽留し、即ち相見えず。今、ことさらに道を清め、館を飾り、以て大使を待つ。願わくは大国惟新の化を聞かん」) |
| 清答曰:「皇帝德並二儀,澤流四海,以王慕化,故遣行人來此宣諭」。 |
| () |
| (清、答えて曰く「皇帝の德は二儀に並び、澤は四海に流る。王、化を慕うを以って、故に行人を遣わし、ここに来たり。宣べ諭さしむ」と) |
| 既而引清就館。其後清遣人謂其王曰:「朝命既達,請即戒塗」。 |
| () |
| (既にして清を引いて館に就かしむ。その後、清、人を遣わし、その王に謂いて曰く「朝命は既に達せり、請う、即ち戒塗せよ」と) |
| 於是設宴享以遣清,復令使者隨清來貢方物。 |
| () |
| (ここに於いて設宴を享け、以って清を遣わし、復た使者をして清に随いて来たりて方物を貢せしむ) |
| 此後遂絶。 |
| () |
| (この後、遂に絶ゆ) |
|
是に、大唐の国の信物を【庭中に置く】。時に使主裴世清、親ら書を持ちて、両度再【拜みて使の旨を言上】して立つ。
□丙辰(608年8月16日)に、唐の客等を【朝に饗たまふ】。
□九月の辛未の朔乙亥(608年9月5日)に、客等を難波の大郡に【饗たまふ】。
□辛巳(608年9月11日)に、【唐の客裴世清、罷り帰りぬ。則ち復小野妹子臣を以て大使とす】。
日本書紀と隋書の二書を並べることでより見えてくる。日本書紀では、我が国が裴世清一行を迎えた場所を「難波津」であると記している。この「難波」は「大阪」と思い込まれているが、この頃までの大阪には難波はない。平安時代の倭名類聚抄の国名・郡名・郷名にも記載がない。では、どこに「難波」が比定されるかというと、現在の香川県の津田町一帯。この地は、仁徳天皇の京都が置かれたあの難波であり、これは、そこから見た瀬戸内の景色を、島名入りで詠んだ天皇の歌によって証明される。大坂からは見えない景色。では、裴世清一行は北九州を船出して讃岐へ入港したのか? 違う。もう一箇所(全国で2カ所)、四国に難波郷がある。それは愛媛県。
|
| 隋書と日本書紀を読み比べると、隋書には裴世清が謁見した天皇(性別の記述なし)が、煬帝を念頭にへりくだった挨拶をするシーンがあるが、日本書紀では、裴世清が一方的に煬帝の国書を奏上するだけ。「裴世清、親ら書を持ちて、両度再拜みて、使の旨を言上」し、奏上が終わると「阿倍臣、出で進みて、其の書を受けて進み行く」で、天皇からは一言のお言葉も頂いておりません。爰妹子臣奏之曰「臣參還之時、唐帝以書授臣。然經過百濟國之日、百濟人探以掠取。是以不得上。
於是、群臣議之曰「夫使人、雖死之不失旨。是使矣、何怠之失大國之書哉。」則坐流刑。
時天皇勅之曰「妹子、雖有失書之罪、輙不可罪。其大國客等聞之、亦不良。」乃赦之不坐也。
|
| 「阿輩雞彌」の訓みは、(おほきみ、おおきみ)と読むのが通説。「阿輩臺」は何故か、(あほたい)とか(あへと)とか色々です。まれに(あはだい)とか読む方もいらっしゃいます。(あへ)は「安倍」のことだという説です。これは、ヤマトで裴世清を迎える役を仰せつかった四大夫(まえつきみ)の一人に「阿倍鳥(あべのとり)臣」がいるためです。つまり、「アヘト」は「アヘ(之)トリ」。阿閉(安倍)氏は生粋の阿波氏族です。私は繰り返し「阿輩」(あは)=「阿波」説を提唱しておきます。この「邪靡堆」は、魏志倭人伝いうところの「邪馬臺」だと書かれている。 |
|
魏志倭人伝上の「邪馬臺國」、すなわち卑弥呼の都は「神山町」であるという主張が強い。八倉比売神社の鎮座する徳島市国府町。仁徳天皇の記事では、天皇が淡路島で詠まれた歌の景色からみて、そこに詠まれる「我が国」(つまり倭のこと)は、最低でも香川県を含む東四国海岸部の範囲であると書きました。また、式内社「倭大国魂神社」の鎮座や、古事記での大国主命の物語の解読から、「倭」は吉野川上流である「旧美馬郡」とする主張もなされており、もちろん私もそう結論しています。
平安京以来、都に御所が置かれ、東京には皇居が置かれ、天皇が代替わりしても都は移動しませんが、それ以前はオオキミが変わるたびにその宮都は移動していた。
伊波礼琵古命は那賀須泥毘古との戦いを経て、その邇藝速日命から大王位を譲位され、初めて高天原と下界「ヤマト(倭)とナカ(那賀)=葦原中国」の統一王となり初代天皇を名乗った。
|
|
| 【隋書琉球伝】 |
| 流求國,居海島之中,當建安郡東,水行五日而至。土多山洞。其王姓歡斯氏,名渇剌兜,不知其由來有國代數也。
彼土人呼之為可老羊,妻曰多拔荼。所居曰波羅檀洞,塹柵三重,環以流水,樹棘為藩。
王所居舍,其大一十六間,刻禽獸。多鬥鏤樹,似橘而葉密,條纖如髮,然下垂。國有四五帥,統諸洞,洞有小王。
往往有村,村有鳥了帥,並以善戰者為之,自相樹立,理一村之事。男女皆以白紵繩纏髮,從項後盤繞至額。
其男子用鳥羽為冠,裝以珠貝,飾以赤毛,形製不同。婦人以羅紋白布為帽,其形正方。
織鬥鏤皮并雜色紵及雜毛以為衣,製裁不一。
綴毛垂螺為飾,雜色相間,下垂小貝,其聲如珮。綴鐺施釧,懸珠於頸。織藤為笠,飾以毛羽。有刀、●、弓、箭、劍、鈹之屬。
其處少鐵,刃皆薄小,多以骨角輔助之。編紵為甲,或用熊豹皮。王乘木獸,令左右輿之而行,導從不過數十人。
小王乘机,鏤為獸形。國人好相攻撃,人皆驍健善走,難死而耐創。
諸洞各為部隊,不相救助。兩陣相當,勇者三五人出前跳噪,交言相罵,因相撃射。如其不勝,一軍皆走,遣人致謝,即共和解。
收取鬥死者,共聚而食之,仍以髑髏將向王所。王則賜之以冠,使為隊帥。無賦斂,有事則均税。
用刑亦無常准,皆臨事科決。犯罪皆斷於鳥了帥;不伏,則上請於王,王令臣下共議定之。獄無枷鎖,唯用繩縛。
決死刑以鐵錐,大如箸,長尺餘,鑽頂而殺之。輕罪用杖。俗無文字,望月虧盈以紀時節,候草藥枯以為年歳。
人深目長鼻,頗類於胡,亦有小慧。無君臣上下之節,拜伏之禮。父子同床而寢。男子拔去髭鬢,身上有毛之處皆亦除去。
婦人以墨黥手,為蟲蛇之文。嫁娶以酒肴珠貝為娉,或男女相悅,便相匹偶。婦人産乳,必食子衣,産後以火自灸,令汗出,五日便平復。
以木槽中暴海水為鹽,木汁為酢,釀米●為酒,其味甚薄。食皆用手。偶得異味,先進尊者。
凡有宴會,執酒者必待呼名而後飲。上王酒者,亦呼王名。銜杯共飲,頗同突厥。
歌呼蹄,一人唱,衆皆和,音頗哀怨。扶女子上膊,搖手而舞。其死者氣將絶,舉至庭,親賓哭泣相弔。
浴其屍,以布帛纏之,裹以葦草,親土而殯,上不起墳。子為父者,數月不食肉。南境風俗少異,人有死者,邑里共食之。
有熊羆豺狼,尤多豬雞,無牛羊驢馬。厥田良沃,先以火燒而引水灌之。
持一插,以石為刃,長尺餘,闊數寸,而墾之。
土宜稻、粱、●黍、麻、豆、赤豆、胡豆、黑豆等,木有楓、樟、松、楠、杉、梓,竹、籐、果、藥同於江表,風土氣候與嶺南相類
俗事山海之神,祭以酒肴,鬥戰殺人,便將所殺人祭其神。或依茂樹起小屋,或懸髑髏於樹上,以箭射之,或累石繁幡以為神主。
王之所居,壁下多聚髑髏以為佳。人間門戸上必安獸頭骨角。
大業元年,海師何蠻等,毎春秋二時,天清風靜,東望依希,似有煙霧之氣,亦不知幾千里。
三年,煬帝令羽騎尉朱寬入海求訪異俗,何蠻言之,遂與蠻倶往,因到流求國。言不相通,掠一人而返。
明年,帝復令寬慰撫之,流求不從,寬取其布甲而還。時倭國使來朝,見之曰:「此夷邪久國人所用也」。
帝遣武賁郎將陳稜、朝請大夫張鎮州率兵自義安浮海撃之。至高華嶼,又東行二日至●嶼,又一日便至流求。
初,稜將南方諸國人從軍,有崑崙人頗解其語,遣人慰諭之,流求不從,拒逆官軍。
稜撃走之,進至其都,頻戰皆敗,焚其宮室,虜其男女數千人,載軍實而還。自爾遂絶。
|
| 【南史】 |
南史は、唐王朝の李延寿(?)の撰。79(80?)巻。北史と同じく唐の李延寿による唐の高宗(650~683年)の時代と推定される。構成は。、本紀10巻、列デカン70巻からなる。正しくは、南史巻79.夷
伝下.倭国条のこと。
| 「倭國、其先所出及所在、事詳北史。其官有伊支馬、次曰彌馬獲支、次曰奴往?。人種禾稻、紵麻、蠶桑織績。有薑、桂、橘、椒、蘇。出黑雉、真珠、青玉。有獸如牛名山鼠、又有大蛇呑此獸。蛇皮堅不可斫、其上有孔、乍開乍閉、時或有光、射中而蛇則死矣。物産略與?耳、朱崖同。地氣?暖、風俗不淫。男女皆露?、富貴者以錦?雜采為帽、似中國胡公頭。食飲用?豆。其死有棺無槨、封土作家。人性皆嗜酒。俗不知正歳、多壽考、或至八九十、或至百歳。其俗女多男少、貴者至四五妻、賤者猶至兩三妻。婦人不??、無盜竊、少諍訟。若犯法、輕者沒其妻子、重則滅其宗族。晉安帝時、有倭王讚遣使朝貢。及宋武帝永初二年、詔曰:「倭讚遠誠宜甄、可賜除授。」文帝元嘉二年、讚又遣司馬曹達奉表獻方物。讚死、弟珍立、遣使貢獻、自稱使持節、都督倭百濟新羅任那秦韓慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王、表求除正。詔除安東將軍、倭國王」。 |
| (和訳) |
| 「齊建元中除武持節都督、倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事、鎭東大將軍。梁武帝即位、進武號征東大 將軍。其南有侏儒國。人長四尺、又南有黒齒國、裸國。去倭四千餘里、船行可一年至、又西南萬里有海人、身黒眼白、裸而
醜、其肉美。行者或射而食之。文身國、在倭東北七千餘里、人體有文如獸、其額上有三文、文直者貴、文小者賤。土 俗歡樂、物豐而賤、行客不齎糧。有屋宇、無城郭。國王所居、飾以金銀珍麗。繞屋爲塹、廣一丈、實以水銀、雨則流
于水銀之上。市用珍寶。犯輕罪者則鞭杖、犯死罪則置猛獸食之、有枉則獸避而不食、經宿則赦之」。 |
| (和訳) |
|
| 【北史】 |
650年頃、北史は、唐王朝の李延寿の撰。帝記録12巻、列伝88巻の100巻。編者の生没年時は明らかでない。完成は、唐の高宗(650~683年.在位)の御代の659(顕慶4)年、奏上。24史のうちの一つ。「北朝の北魏の魏書、北斉の北斉書、北周の周書、隋の随書の四朝書、242年間」の四史を簡約し、北朝北魏から随までの歴史を一つにまとめたもの。「北史、四夷伝の内の東夷の項目は、高句麗、百済之国、新羅、流求国、俀国」。「北史、四夷伝、東夷の項目、俀国条は隋書俀国伝とほぼ同一」である。巻94四夷伝の第八十二倭国条に、倭関係の記事が見られるが、ほぼ梁書随書によったもの。南史倭国出んに、倭国は、其の先の所出及び所在の事、北史に詳しいとあることでわかる。隋書俀国伝は636年に完成している。邪馬台国関連の記述は、魏志東夷伝倭人の条を抜粋して記述しているので、魏志倭人伝の内容以上の目新しさはない。「堆」という字が使われている。
「倭國在百濟新羅東南、水陸三千里、於大海中、依山島而居。魏時譯通中國三十餘國、皆稱子。夷人不知里數、但計以 日、其國境東西五月行、南北三月行、各至於海。其地勢東高西下、居於邪摩堆、則魏志所謂邪馬臺者也。
又云、去樂 浪郡境及帯方郡、並一萬二千里、在會稽東、與tan[偏人旁右澹]耳相近。俗皆文身、自云太伯之後。計從帯方至倭國、 循海水行、歴朝鮮國、乍南乍東、七千餘里、始度一海、又南千餘里度一海、闊千餘里、名瀚海、至一支國。又度一海千餘里、名末盧國。又東南陸行五百里、至伊都國。又東南百里、至奴國。又東行百里、至不彌國。又南水行二十日、 至投馬國。又南水行十日、陸行一月、至邪馬臺國。即[イ妥]王所都。漢光武時、遣使入朝、自稱大夫。安 帝時又遣 朝貢、謂之[イ妥]奴國。靈帝光和中、其國亂、遞相攻伐、歴年無王。有女子名卑彌呼、能以鬼道惑衆、國人共立爲王。無夫有二男子、給王飲食、通傳言語。其王有宮室樓觀城柵、皆持兵守衛。爲法甚嚴。魏景初三年、公孫文懿誅後、卑彌呼、始遺使朝貢、魏主假金印紫綬。正始中、卑彌呼死、更立男王、國中不服、更相 誅殺、復立卑彌呼宗女臺與爲王、其後復立男王、並受中國爵命、江左歴晉宋齊梁、朝聘不絶、及陳平、至開皇二十年、 [イ妥]王姓阿毎、字多利思比孤、號阿輩[奚隹]彌、遣使詣闕」。 |
| (和訳) |
| 「大業三年,其王多利思比孤遣朝貢。使者曰:「聞海西菩薩天子重興佛法,故遣朝拜,兼沙門數十人來學佛法。」國書曰:「日出處天子致書日沒處天子,無恙。」云云。帝覽不悅,謂鴻臚卿曰:「蠻夷書有無禮者,勿復以聞。」明年,上遣文林郎裴世清使倭國,度百濟,行至竹島,南望耽羅國,經都斯麻國,迥在大海中。又東至一支國,又至竹斯國。又東至秦王國,其人同於華夏,以為夷洲,疑不能明也。又經十餘國,達於海岸。自竹斯國以東,皆附庸於倭。倭王遣小德何輩臺從數百人,設儀仗,鳴鼓角來迎。後十日,又遣大禮哥多?從二百餘騎,郊勞。既至彼都,其王與世清相見、大悦、曰:「我聞海西有大隋、禮義之國、故遣朝貢。我夷人、僻在海隅、不聞禮義、是以稽留境内、不即相見。今故清道飾館、以待大使、冀聞大國惟新之化。」清答曰:「皇帝徳並二儀、澤流四海、以王慕化、故遣行人
來此宣諭。」既而引清就館。其後清遣人謂其王曰:「朝命既達、請即戒塗。」於是設宴享以遣清、復令使者隨清來貢方物。此後遂絶」。 |
| (和訳) |
| その国境は東西に五カ月の行程、南北に三カ月の行程、各々が海に至る。その地形は東が高く西が低い。邪摩堆で暮らす、魏志に則れば、言うところの邪馬臺である。 |
https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=418314
唐の李賢は後漢書の「邪馬臺」の記述の注記として「案今名邪摩惟音之訛也」(案ずるに 今の名は邪摩【惟】「ヰ」の音の訛りなり)と記している。李賢は「邪摩惟」という文字は、「北史」において「邪摩堆(タイ)」と記載されているので、これに対比する意味で使い、「邪馬臺(タイ)」の意味するところは古えの「ヤマヰ」であると述べていることになる。『壹』の字は、古代の上戸音では「ト」とも「イチ」とも読まないが、惟、堆、推、維と、時代により、史書により、変わっていった。原書の音は壹「ヰ」の音であったと推定できる。「ヰ」の音をあらわすのに、古代中国人は様々な当て字を使っていたと思われる。「ヰ」は、「倭」、「委」の音である。 |
|
| 【通典】 |
801年、杜佑の「通典辺防第一・倭」は次のように記している。
| 「齊王正始中 卑彌呼死。立其宗女臺輿爲王、其後復立男王、並受中國爵命。晉武帝太始初、遣使重譯入貢」。 |
|
| 【旧唐書】 |
945年頃、旧唐書(舊唐書、くとうじょ)は五代晋王朝(936-946)時代(後晋)の劉ク(887~946)の撰。199巻上。史書(中国の正史)で、唐の成立(618年)から滅亡(907年)までについて書かれている。
第百九十九巻「日本國」の条(「東夷 倭国・日本」)に粟田真人の証言に基づいて次の意味のことが書かれている。
| (日本國者倭國之別種也。以其國在日辺故以日本爲名或曰倭國自悪其名不雅改爲日本。或云日本舊小國併倭國之地)。 |
| 「大和朝廷の日本國はかっての倭國とは別種の国である。大和朝廷は日出ずる国であるという理由で日本を国号とした。あるいは、大和朝廷は倭國の呼び名が雅(みやび)ではないのを悪(にく)んで、これを改め日本とした。日本はもと小国で分国していたのを併合し國としている」 |
西暦704年、粟田真人は帰国の途にき、白村江の戦い(663年)で捕虜になっていた者を連れて途中五島列島に漂着するも無事帰朝している。 |
旧唐書 東夷伝倭国条 日本国条文は次の通り。
| 原文 |
倭國者、古倭奴國也。 |
| 和訳 |
倭国は古(いにしえ)の倭の奴国なり。 |
| 原文 |
去京師一萬四千里、在新羅東南大海中、依山島而居。 |
| 和訳 |
唐の都から一万四千里、新羅の東南の大海中に在り、山島に依って生活している。 |
| 原文 |
東西五月行、南北三月行。世與中國通。 |
| 和訳 |
広さは、東西に五ヶ月の行程、南北に三ヶ月の行程であり、代々、支那と通じている。 |
| 原文 |
其國、居無城郭、以木為柵、以草為屋。 |
| 和訳 |
その国には、居住地に城郭がなく、木で柵を造り、草葺き屋根の居宅に住んでいる。 |
| 原文 |
四面小島五十餘國、皆附屬焉。 |
| 和訳 |
倭国の四方に小島が50余国がある。皆な倭国の傘下にはいっている。 |
| 原文 |
其王姓阿毎氏、置一大率、檢察諸國、皆畏附之。設官有十二等。 |
| 和訳 |
|
| 原文 |
其訴訟者、匍匐而前。 |
| 和訳 |
争いごとが起こると、這って前に進み出て訴えを起こす。 |
| 原文 |
地多女少男。頗有文字、俗敬佛法。 |
| 和訳 |
その地には女が多く男が少ない。人は頗る文字を知り、一般に佛法を敬っている。 |
| 原文 |
並皆跣足、以幅布蔽其前後。 |
| 和訳 |
人は皆な裸足で、幅の広い布の衣装を前後に被せるように着こなしている。 |
| 原文 |
貴人戴錦帽、百姓皆椎髻、無冠帶。 |
| 和訳 |
貴人は錦(めん)の帽子をかぶり、百姓たちはマゲを結い冠帶をしていない。 |
| 原文 |
婦人衣純色裙、長腰襦、束髮於後、佩銀花、長八寸。 |
| 和訳 |
婦人の衣装は鮮やかな色のスカートに、長い腰襦袢で、髮を後ろに束ねており、銀でできた花のカタチの簪(かんざし)をさしている。 |
| 原文 |
左右各數枝、以明貴賤等級。 |
| 和訳 |
|
| 原文 |
貞觀五年、遣使獻方物。太宗矜其道遠、敕所司無令歳貢、又遣新州刺史高表仁持節往撫之。表仁無綏遠之才、與王子爭禮、不宣朝命而。 |
| 和訳 |
|
| 原文 |
至二十二年、又附新羅奉表、以通起居。 |
| 和訳 |
貞観二十二年に至り、また新羅に附して、表を奉り、もって起居を通ず。 |
| 原文 |
日本國者、倭國之別種也。以其國在日邊、故以日本為名。 |
| 和訳 |
日本国は倭国の別種なり。その国、日辺に在るをもって、故に日本をもって名と為すと。 |
| 原文 |
或曰:倭國自惡其名不雅、改為日本。 |
| 和訳 |
或いは曰く、倭国自ら其の名の雅ならざるを憎み、改めて日本と為すと。 |
| 原文 |
或云:日本舊小國、併倭國之地。 |
| 和訳 |
或いは曰く、日本は旧と(もと)小国、倭国の地を併すと。 |
| 原文 |
其人入朝者、多自矜大、不以實對、故中國疑焉。 |
| 和訳 |
その人の入朝するは、多自く(おおく)矜大にして、実をもって対へず。故に中国、これを疑う。 |
| 原文 |
其國界東西南北各數千里、西界、南界咸至大海、東界、北界有大山為限、山外即毛人之國 |
| 和訳 |
その国界の東西南北は各々数千里、西界南界は皆な大海に至る。東界北界は大山ありて限りと為す。山の外は毛人の国となる。 |
| 原文 |
「長安三年、其大臣朝臣真人來貢方物、朝臣真人者、猶中國戸部尚書、冠進德冠、其頂為花、分而四散、身服紫袍、以帛為腰帶。真人好讀經史、解屬文、容止温雅。則天宴之於麟德殿、授司膳卿、放還本國」。 |
| 和訳 |
|
|
| 西暦701年、日本では文武天皇の時代、「大寳律令」が完成した。これは、日本が唐に学んで法治国家となったことを意味する。西暦702年、大和朝廷は第八次遣唐使に大寳律令をもたせた。このとき遣唐使は初めて倭國からではなく日本國からの朝貢であると名乗った。正使は大寳律令の編纂に加わった粟田真人(あわたのまひと
640頃-719)。真人は東夷人でありながら容姿端麗であり、中国のエリート官僚(科挙の上位合格者)のように「四書五経」を読み、自ら文章を書くとして唐(則天武后の武周)で絶讃されている。
図は明の時代の 1532年に描かれた『四海華夷總圖』です。「日本國」と「大琉球」との間に「倭」が描かれている。粟田真人の証言は重視されていて、中国は、日本國はかつての大国である女王國・倭國とは異なると認識するようになった。なお、中国では南は重要な方角だった。歴代皇帝は南を向いて座った。人に何かを教えることを「指南する」と言う。武官である魏の使者が東をことさら「南」と書き替えて報告することは許される行為ではなかった。詳しくは https://www.asoshiranui.net/yamataikoku/ 第一章『魏志倭人傳』と『記紀』の科学 で述べる予定です。 |
| 【太平御覧(たいへいぎょらん)】 |
984年頃、宋代初期、北宋の太宗(2代)の勅を受けて李棒昉(りほう)徐鉉ら14名による奉勅撰として「太平御覧」(たいへいぎょらん))が編纂された類書である。全1000巻。諸々の書物から記事や文章を抜粋した上で分類排列している。太平御覧は「魏書を引用して掲載している」が、引用した魏書は、文体から「王沈(おうしん)の魏書」(AD250-266)と考えられている。魏志原書の「王沈の魏書」は、魚豢(ぎょかん)による魏略(AD265)、郭義恭(かくぎきよう)による広志(Ad266-280)と共に魏志倭人伝とほぼ同一の記述をしている。年代的には王沈の魏書が一番古い。魏略、広志は王沈の魏書を転載したものと考えられている。魏略は文章をかなり切り詰めて書いてあり、王沈の魏書や魏志倭人伝と文章の書き方が、かなり異なっている。広志は年代が新しい。
この書が類書の中では最も良書として名高いが、その引用にはやはり原文を簡略にした箇所も多い。後代の史書/晋書、梁書などが、倭人の出自に関しては一致して「太伯之後」という文言を記している。ただ「旧語を聞くに、自ら太伯(たいはく)の後という」の文章が両書にあって、倭人伝にはない。
本伝は現存二ケ条746字の逸文であるが、通常は宋の慶元版第782四夷部三.東夷三.倭条に引かれたものを参照する。三木太郎氏は魏志倭人伝の世界で、これまで倭人伝の要約に過ぎないとされていた御覧魏志の内容が、実はかなり具体性をもっており、異本である可能性が高いと指摘するところとなった。魏略の全文は既に散逸してしまっているのでその全体像を明らかにすることはできない。御覧魏志に注目されるのは、御覧が義略の系譜をひくものではないかとの期待にある。三木太郎氏は、その著書魏志倭人伝の世界により究明を試みている。これにより氏は、義略御覧魏志倭人伝の成立順序を解明している。今日残されている尤も古い御覧は南宋蜀の刊本である。通説は、「御覧」そのものの成書は北宋太平興国8年(984年)とされるが、氏によれば「御覧魏志」と、「南斉書倭国出」(6世紀、蕭子顕撰)、「梁書倭伝」(7世紀)、「晋書倭人伝」、「随書倭国伝」、「宋書倭国伝」と関係しており、推定するのに、魏志倭人伝より早い時期の書ではないかと説く。「魏略」→「御覧魏志」→「魏志倭人伝」が成立順序と推論している。 |
太平御覧が引用している魏書の全文。次のような特徴がある。
魏志倭人伝では冒頭の言葉が倭人となっているが、太平御覧では倭国になっている。倭国とは「倭人の住んでいる地域」という意味で、朝鮮半島南部から日本列島までの地域を指している。後漢の時代、100余りの国に分かれていたとあるので必ずしも統一国家を意味していない。倭とは倭国(倭地)を表す場合と倭人を表す場合の二通りがあった。しかし、魏志倭人伝では、親魏倭王の金印を授けた倭王の領土を倭地と表現していて紛らわしい。倭王の領土外の倭人を倭種と記述している。おそらく、誤解を避けるため、金印を授けた倭王の領土である倭について記述したことを明記するため、当初の倭国から倭人に変えたものと推察できる。
魏一行が辿った国として「又」という字で、行程を繰り返していたことを明確に示している。したがって、奴國、投馬國等には実際に行っていないという「伊都國放射読み」は成立しないことがわかる。
【至】という字は実際には行っていないという説があるが、魏志倭人伝では對海國、一大國、末盧國、奴國、不彌國、投馬國、邪馬壹國に【至】と記載されており、【至】という字を以って、これらの国々に全く行っていないという解釈は成立しない。また【至】という字で実際に訪れていないことを区別した史書は皆無である(半沢栄一;邪馬台国の数学と歴史学)。一方、太平御覧では、狗邪韓國と伊都國だけ【到】という字が使われ、他の国には【至】が使われている。これはなぜであろうか?おそらく、別格表記ではないだろうか?
i)魏志倭人伝では、「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日・陸行一月、官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳、可七萬餘戸。自女王國以北、其戸數道里可略載、其餘旁國遠絶不可得詳。次有斯馬國、----次有奴國、此女王境界所盡。【其】南有狗奴國、」とある。【其】南とは直前の奴國を指していると解釈する人がいるが、奴國を含む単文は「此女王境界所盡」で結言していると読むべきで、直前の言葉ではなく、この文節の主題を表す「係りの言葉」である邪馬壹國もしくは女王國を指していると解すべきである。
ii)太平御覧では奴國の記述はなく、「其屬小國有二十一,皆統之女王。之南又有狗奴國,」としかない。したがって、太平御覧では、狗奴國は「係りの言葉」である邪馬壹國の南にあったと記載している。
iii)魏略では「女王之南 又有狗奴国」とあり、狗奴國は、女王國の南にあると記載してある。
iv)後漢書では「女王国より【東】、海を渡って千余里で拘奴国に至る。みな倭種であるけれども女王には属していない」とあり、魏志倭人伝の「東の記述」で、倭種の国が、実は狗奴國であったと訂正している。
以上、魏略、太平御覧の記述から、魏志では狗奴國の位置について、奴國の南ではなく、女王國の南にあったと記載されていたことがわかる。東亜古代史研究所 塚田敬章氏など、漢文のプロ達も同様の解釈をしている。しかし、後漢書では、東と記載されており、食い違いがある。南と東のどちらが正しいかは、女王國の比定地で判断できるであろう。
女王國を広大な連合国として考える人がいる。この根拠は「南【至】邪馬壹國、女王之所都、水【行】十日・陸【行】一月」という文で、邪馬壹國を女王之所都、女王國は使譯が通じる三十國で構成されていると解釈している。魏志では「使譯が通じる三十國」が女王國だとは記載していない。魏が交流していた国(例えば北部九州以外に紀年銘鏡が発掘された地など)と女王が支配していた国が同一であるとは限らない。太平御覧では「邪馬壹國--------其屬小國有二十一、皆統之女王」とあり、女王の権力が及ぶ連合国として21か国あり、邪馬壹國の小国として女王が統べていると読める。「其屬小國」とは魏志記載の斯馬國から奴國までの21か国のことか。「其屬」とは係りの言葉であり、「邪馬壹國に属する」という意味である。
|
|
| 「太平御覧所引 魏志倭人伝」。魏志倭人伝とは、微妙に本文が違う。 |
| 魏志曰く、倭国在帯方東南大海中、依山島為旧国百余小国、漢時有朝見者、今使譯所通其三十国。 |
| 魏志曰く、倭国は帯方の東南大海の中にあり、山島によりて国をなす。旧の国は百余の小国にして、漢時に朝見するものあり。今、使訳して通じる所、其の三十国なり。 |
| 従帯方至倭、循海岸水行歴韓国、従乍南乍東到其北岸狗邪韓国七千余里。 |
| 帯方より倭に至るには、海岸に沿って水行し、韓国を経てあるいは南し、あるいは東して従い、其の北岸狗邪韓国に到るまで七千余里。
|
| 至対馬国、戸千余里、大官曰卑狗副曰卑奴母離。 |
| 対馬国に至る、(戸)千余里。大官は卑狗といい、副は卑奴母離という。 |
| 所居絶島方四百余里、地多山林無良田、食海物自活乗船南北市糴。 |
| 居るところ絶島にして、四方は四百里、地は山林多く、良田なし。海物を食べて自活し、船に乗りて南北に市糴する。 |
| 又南渡一海一千里、名日瀚海、至一大国置官与対馬同地方三百里、多竹木叢林。有三千許家。亦有田地、耕田不足食、方行市糴。 |
| 又、南に一海を渡ること一千里、名を瀚海という。一大国に至る。官を置くは、対馬と同じ。地は四方三百里。竹木叢林多く、三千ばかりの家有り。また田地あるも耕田して食べるに足らず、まさに市糴を行う。 |
|
又渡海千余里至未盧国戸四千、濱山海居人善捕魚水無深浅皆能沉没取之。
|
| 又、海を渡ること一千里余り未盧国に至る。戸は四千。山海に浜して居し、人よく魚を捕まえるに、水の深浅となく、皆よく沈没してこれを取る。 |
| 東南陸行五百里到伊都国、官曰爾支、副泄謨觚柄渠觚有千余戸。 |
| 東南に陸行すること五百里、伊都国に到る。官は爾支といい、副は泄謨觚柄渠觚という。千余戸有り。 |
| 世有王皆統属女王、帯方使往来常止住 |
|
世に王有り、皆女王に統属する。帯方の使は、往来するに常に止住する。
|
| 又東南至奴国百里、置官曰先馬觚、副曰卑奴母離。有二万余戸。 |
| 又、東南して奴国に至ること百里。置官して先馬觚といい、副は卑奴母離という。二万余戸有り。 |
| 又東行百里至不彌国、戸千余、置官曰多模、副曰卑奴母離。 |
| 又、東行して百里不彌国に至る。置官して多模といい副は卑奴母離という。 |
| 又南水行二十曰至於投馬国、戸五万、置官曰彌彌、副曰彌彌那利。 |
| 又、南に水行して二十日、於投馬国に至る。置官してと彌彌いい副は彌彌那利という。 |
| 又南水行十日、陸行一月至耶馬臺国、戸七万、女王之所都、其置官曰伊支馬、次曰彌馬叔、次曰彌馬獲支、次曰奴佳鞮、其属小国有二十一、皆統之。 |
|
又、南に水行して十日、陸行して一月、耶馬臺国に至る。其の官を置くに伊支馬といい、次は彌馬叔といい、次は彌馬獲支といい、次は奴佳鞮という。その属する小国は二十一あり皆これを統べる。
|
| 女王之南又有狗奴国、男子為王 其官曰拘右智卑狗者 不属女王也。 |
| 女王の南に又狗奴国ありて男子を王とする。其の官は拘右智卑狗といい、女王に属さざるなり。 |
|
自帯方至女(王)国万二千余里。
|
| 帯方より女王国に至るには、万二千余里なり。 |
|
其俗男子無大小皆黥面文身、聞其旧語自謂太伯之後。
|
| 其の俗は、男子は大小となく皆黥面文身し、其の旧語を聞くに自ら太伯の後なりという。 |
| 又云自上古以来其使詣中国、草伝辞説事、或蹲或跪、両手據地、謂之恭敬、其呼應聲曰噫噫、如然諾矣 |
| 又云う、上古以来、其の使いは中国に詣ると。草に辞を伝え事を説くには、或いは蹲り、或いは跪き、両手は地によって恭敬という。其の呼応の声は「噫噫」といい、然諾の如し。 |
| 倭国本以男子為王、漢霊帝光和中倭国乱、相攻伐無定乃共立一女子為王、名曰卑彌呼、事鬼道能惑衆、自謂年已長 大無夫壻、有男弟佐治国。 |
| 倭国は、もとは男子をもって王となす。漢霊帝光和年間、倭国は乱れ、相い攻伐し定らず、一女子を共立して王となした。名を卑弥呼という。鬼道を事とし、よく衆を惑わす。自ら云う年すでに長大なるも夫婿なしと。男弟ありてたすけて国を治める。 |
|
以婢千人自侍、唯有男子一人給飲食伝辞出入、其居處宮室楼観、城柵守衛厳峻。
|
| 婢千人をもって自ら侍らしめ、だた男子一人ありて飲食を給し、辞を伝え出入す。其の居処の宮室、楼観、城柵、守衛は厳峻である。 |
| 景初三年公孫淵死、倭女王遣大夫難升米等言帯方郡、求詣天子朝見、太守劉夏送詣京師。 |
| 景初三年、公孫淵死して、倭女王は大夫の難升米らを遣して帯方郡に言せしめ、天子に詣でて朝見せんことを求む。太守劉夏は、送りて京師に詣らしむ。 |
| 難升米致所献男生口四人女生口六人班布二疋、詔書賜以雑錦采七種、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠鉛丹之属付使還、又封下倭王印綬。 |
| 難升米の献ずるところは、男生口四人、女生口六人、班布二疋を致す。詔書してもって雑の錦采七種、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠・鉛丹の属を賜い、使に付して還らしめ、又倭王に印綬を封下せしむ。 |
| 女王死大作冢殉葬者百余人、更立男王国中不服、更相殺数千余人、於是復更立卑彌呼宗女臺挙年十三爲王、国中遂定。 |
| 女王死して、大いに塚を作る。殉葬されるもの百余人。更に男王を立てるも国中服さず、更に相殺すること千余人を数える。ここに於いて、また更に卑弥呼宗女の臺挙、年十三を立てて王と為し国中ついに定まる。 |
| 其倭国東渡海千余里、復有国皆倭種也、又有朱中儒国在其南、人長三四尺 去倭国四千余里、又有裸国、黒歯国、復在其東南 船行可一年至。 |
| 其の倭国の東、海を渡ること千余里にして、また国あり、皆倭種なり。また朱(中)儒国が有りて其の南に在り人長三、四尺。倭国を去ること四千里余り。また裸国、黒歯国有りてまた其の南に在り、船行すること一年にて至るべし。 |
*漢文の欠字は、本文内で括弧にて補い、明らかな誤字は訳文にて太字にて訂正を示した。
*参照 「邪馬台国研究総覧 三品彰英 編著(1970)」 「魏志倭人伝の世界 三木太郎 著(1979)」 |
| 【新唐書】 |
| 新唐書は、北宋王朝の宋祀(998~1061)の撰。220巻。東夷 日本。 |
新唐書 東夷伝 日本条は次の通り。
| 原文 |
日本、古倭奴也。去京師萬四千里、直新羅東南、在海中、島而居。 |
| 和訳 |
日本は古への倭の奴なり。唐の都から一万四千里、新羅の東南に当り、海中に在り、その島で生活している。 |
| 原文 |
東西五月行、南北三月行。國無城郛、聯木為柵落、以草茨屋。左右小島五十餘、皆自名國、而臣附之。置本率一人、檢察諸部。 |
| 和訳 |
|
| 原文 |
|
| 和訳 |
(中略)誠享元年(六百七十年)、使いを遣わして高麗を平らぐるを賀す。後梢(や)や夏音を習い、倭の名を悪み、更めて(あらためて)日本と号す。使者自ら言く、国日出づる所に近ければ、もって名を為すと。或いは曰く、日本は乃はち(すなはち)小国、倭の併す所と為る故に其の号を冒す(おかす)と。使者情をもってせず、故にこれを疑う またみだりに誇ることあり。其の国 およそ方数千里 南・西は海に尽き、東・北は大山を限る 其の外は即ち毛人という。 |
| 原文 |
其俗多女少男、有文字、尚浮屠法。其官十有二等。其王姓阿毎氏、自言初主號天御中主、至彦瀲、凡三十二世、皆以「尊」為號、居筑紫城。 |
| 和訳 |
|
| 原文 |
彦瀲子神武立、更以「天皇」為號、徙治大和州。 |
| 和訳 |
倭国に、彦瀲(ひこなぎさ)の子の神武が立ち、改めて「天皇」を号して、大和州に向い統治した。 |
| 原文 |
次曰綏靖、次安寧、次懿德、次孝昭、次天安、次孝靈、次孝元、次開化、次崇神、次垂仁、次景行、次成務、次仲哀。 |
| 和訳 |
次は綏靖、次は安寧、次は懿德、次は孝昭、次は天安、次は孝靈、次は孝元、次は開化、次は崇神、次は垂仁、次は景行、次は成務、次は仲哀。 |
| 原文 |
仲哀死、以開化曾孫女神功為王。次應神、次仁德、次履中、次反正、次允恭、次安康、次雄略、次清寧、次顯宗、次仁賢、次武烈、次繼體、次安閑、次宣化、次欽明。 |
| 和訳 |
|
| 原文 |
欽明之十一年、直梁承聖元年。次海達。次用明、亦曰目多利思比孤、直隋開皇末、始與中國通。次崇峻。崇峻死、欽明之孫女雄古立。次舒明、次皇極。 |
| 和訳 |
|
| 原文 |
咸亨元年、遣使賀平高麗。後稍習夏音、惡倭名、更號日本。使者自言、國近日所出、以為名。或云日本乃小國、為倭所并、故冒其號。使者不以情、故疑焉。又妄夸其國都方數千里、南、西盡海、東、北限大山、其外即毛人云。 |
| 和訳 |
後やや夏言を習い、倭名を改めて日本と為す。使者の云うには日出づる所に近き故の改名なりと。或いは云う。日本はすなわち小国で、倭の地を併せ、その号を冒す。使者は情を以てせず、故にこれを疑う」。 |
|
裴世清は日本訪問の報告書で、「東して周防灘の「秦の王国」から瀬戸内海の十余国を経て、海岸(難波の津)に達す。竹斯(筑紫)の国より東はみな倭に附庸す」と書いている。
三国史記倭人伝の文武10(670)年12月の条、「倭国改めて日本と号す。自ら云う、日出づる所に近し。以て名と為すと」。 |
| 【資治通鑑(しじつがん)】 |
北宋の司馬光が編纂した編年体の歴史書で、1084年に成立、収録範囲は、紀元前403年から、959年までの1362年間となっている。
| 「詔起劉仁軌檢校帶方州刺史,將王文度之衆,便道發新羅兵以救仁願。仁軌喜曰:「天將富貴此翁矣!」於州司請唐暦及廟諱以行,曰:「吾欲掃平東夷,頒大唐正朔於海表!」仁軌御軍嚴整,轉鬭而前,所向皆下。百濟立兩柵於熊津江口,仁軌與新羅兵合撃,破之,殺溺死者萬餘人」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「左驍衞將軍白州刺史沃沮道總管龐孝泰,與高麗戰於蛇水之上,軍敗,與其子十三人皆戰死。蘇定方圍平壤久不下,會大雪,解圍而還」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「仁願、仁軌等屯熊津城,上與之敕書,以「平壤軍回,一城不可獨固,宜拔就新羅。若金法敏藉卿留鎭,宜且停彼;若其不須,即宜泛海還也。」將士咸欲西歸」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「今平壤之軍既還,熊津又拔,則百濟餘燼,不日更興,高麗逋寇,何時可滅!且今以一城之地居敵中央,苟或動足,即爲擒虜,縱入新羅,亦爲羈客,脫不如意,悔不可追。況福信凶悖殘虐,君臣猜離,行相屠戮;正宜堅守觀變,乘便取之,不可動也」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「十二月,戊申,詔以方討高麗、百濟」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「九月,戊午,熊津道行軍總管、右威衞將軍孫仁師等破百濟餘衆及倭兵於白江,拔其周留城。初,劉仁願、劉仁軌既克眞峴城,詔孫仁師將兵浮海助之。百濟王豐南引倭人以拒唐兵。仁師與仁願、仁軌合兵,勢大振。諸將以加林城水陸之衝,欲先攻之,仁軌曰:「加林險固,急攻則傷士卒,緩之則曠日持久。周留城,虜之巣穴,羣凶所聚,除惡務本,宜先攻之,若克周留,諸城自下。」於是仁師、仁願與新羅王法敏將陸軍以進,仁軌與別將杜爽、扶餘隆將水軍及糧船自熊津入白江,以會陸軍,同趣周留城。遇倭兵於白江口,四戰皆捷,焚其舟四百艘,煙炎灼天,海水皆赤」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「詔劉仁軌將兵鎭百濟,召孫仁帥、劉仁願還。百濟兵火之餘,比屋凋殘,僵尸滿野。仁軌始命瘞骸骨,籍戸口,理村聚,署官長,通道塗,立橋梁,補隄堰,復陂塘,課耕桑,賑貧乏,養孤老,立唐社稷,頒正朔及廟諱;百濟大悅,闔境各安其業。然後脩屯田,儲糗糧,訓士卒,以圖高麗」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「劉仁願至京帥,上問之曰:「卿在海東,前後奏事,皆合機宜,復有文理。卿本武人,何能如是?」仁願曰:「此皆劉仁軌所爲,非臣所及也。」上悅,加仁軌六階,正除帶方州刺史,爲築第長安,厚賜其妻子,遣使齎璽書勞勉之」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「十月,庚辰,檢校熊津都督劉仁軌上言:「臣伏覩所存戍兵,疲羸者多,勇健者少,衣服貧敝,唯思西歸,無心展効。臣問以『往在海西,見百姓人人應募,爭欲從軍,或請自辦衣糧,謂之「義征」,何爲今日士卒如此?』咸言:『今日官府與曩時不同,人心亦殊。曩時東西征役,身沒王事,並蒙敕使弔祭,追贈官爵,或以死者官爵回授之弟,凡渡遼海者,皆賜勳一轉。自顯慶五年以來,征人屢經渡海,官不記録,其死者亦無人誰何。州縣毎發百姓爲兵,其壯而富者,行錢參逐,皆亡匿得免;貧者身雖老弱,被發即行」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「臣又問:『曩日士卒留鎭五年,尚得支濟,今爾等始經一年,何爲如此單露?』」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「陛下留兵海外,欲殄滅高麗。百濟、高麗,舊相黨援,倭人雖遠,亦共爲影響,若無鎭兵,還成一國。今既資戍守,又置屯田,所藉士卒同心同德,而衆有此議,何望成功!自非有所更張,厚加慰勞,明賞重罰以起士心,若止如今日以前處置,恐師衆疲老,立效無日」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「上深納其言,遣右威衞將軍劉仁願將兵渡海以代舊鎭之兵,仍敕仁軌俱還。仁軌謂仁願曰:「國家懸軍海外,欲以經略高麗,其事非易。今收穫未畢,而軍吏與士卒一時代去,軍將又歸;夷人新服,衆心未安,必將生變。不如且留舊兵,漸令收穫,辦具資糧,節級遣還;軍將且留鎭撫,未可還也」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「八月,壬子,同盟于熊津城。劉仁軌以新羅、百濟、耽羅、倭國使者浮海西還,會祠泰山」。 |
| (和訳) 「」。 |
| 「麟德二年、封泰山、仁軌領新羅及百濟、耽羅、倭四國酋長赴會、高宗甚悦、擢拜大司憲」。 |
| (和訳) 「」。 |
|
12、宋史 491巻 外国 日本国 元王朝 脱脱(1314~1355)著
13、元史 208巻 外夷 日本国 明王朝 宋レン(1310~1381)著
14、新元史 250巻 外国 日本 中華民国王朝 アショウユウ(1850~1933)著
15、明史稿 196巻 外国三 日本 清王朝 王コウショ(1645~1723)著
16、明史 322巻 外国 日本 清王朝 張廷玉(1672~1755)著
17、清史稿 164巻 邦交六 日本 中華民国王朝 趙ジニ(1845~1927)著
18、清史 159巻 邦交六 日本 中華民国王朝 張其キン(1900~)著
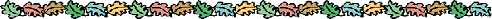



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)