
| 第2部 | 對馬国から不弥国に至るまで |

更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).1.10日
これより前は、「郡から狗邪韓国に到るまで」に記す。
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここでは、対馬国、一大国、末盧国、伊都国、奴国、不弥国に至る行程とそれぞれの国の風情を検証解析する。 2006.11.27日 れんだいこ拝 |
|
|
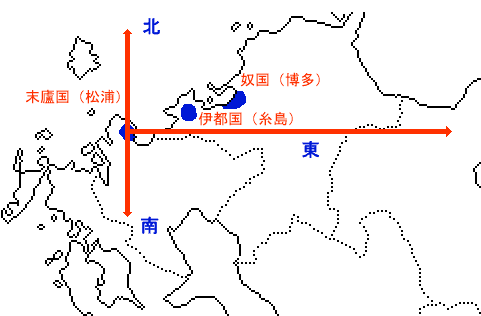 |
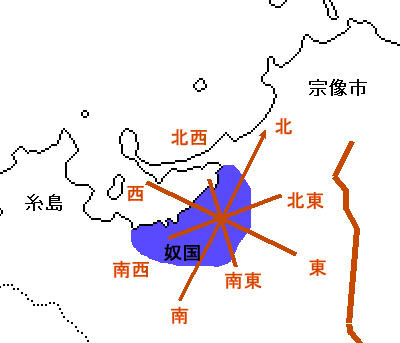 |
| 「邪馬台国の比定地」より上図を転載させていただいた。比定地の部分は要らないが、他にこのような方位関係を記した位置地が見当たらず貴重と心得る。然るべき地図が手に入れば変更する予定であるが、それまでの暫くの間ご了承願います。 2003.9.13日 れんだいこ拝 |
| 始めて一つの海を渡ること千余里、對島国に至る。 |
| 其の大官は卑狗と曰い、副は卑奴母離と曰う。 |
| 居る所は絶島で、方四百余里可り。 |
| 土地は山険しく深林多く、道路は禽や鹿の径の如し。 |
| 千余戸有り。 |
| 良田は無く、海の物を食べて自活し、船に乗りて南北に市糴す。 |
| 【総合解説】 |
| 狗邪韓国から対馬国へ至る行程が、六文意にて述べられている。これを仮に第二行程と為す。 逸文魏略は、「始度一海千余里 至対馬國 其大官曰卑狗副曰卑奴 無良田南北市糴」と記している。 |
| 【逐条解説】 |
| 「始めて一つの海を渡ること」について |
|
既に述べたように、私説は、第二行程は狗邪韓国の特定の港から始められるのではない。狗邪韓国へは「到」っており、「到」が使用されている以上ここからは進んでいないと理解すべきとする。朝鮮半島と対馬海峡との間のこのコースは、かなり早い速度で西から東へ海流が流れており、狗邪韓国の金海付近から渡ろうとすると、船は大きく東に流されて、対馬に着くことができない。魏使は、恐らく、郡を出て、狗邪韓国入りしながら、潮流を考慮に入れた頃合いの港より対馬へ向かったことと思われる。 |
| 「千余里」について |
|
この第二行程が千余里とされていることを検討しておく。この航路がはっきりしないので、一里当りの基準も正確には導きだされない。この海峡幅は55kmであり、仮に、「狗邪韓国」辺りから出発したとして、今日の地理における朝鮮半島のプサンから対馬浅茅湾迄の距離を求めると、約100kmになる。ということは、第二行程でも、100km÷1000里として、概ね一里当り約100mを求めることができる。どちらも水行の場合の基準であるが、第一行程の「一里=80〜100m」と合致していることになる。 |
| 「對島国に至る」について |
|
「對島国」は、紹與本では「對馬国」、紹煕本では「對海国」となっている。隋書では「都斯麻」とも書かれている。「對馬」の音表記は「つま」、「つしま」と読めるかどうか。隋書では「都斯麻」とあり、これなら「つしま」と読める。表意的には「馬韓に対する島」と読める。「對海国」の場合は、大陸側から見ての表記と考えられる。語義的に解読すれば、對は漢音でタイ、呉音でツイ(ヰ)、海はカイ、馬は漢音でバ、呉音でメ、どう読んでもツシマとはならない。”ツシマ”は港となる島の義で津島と記すなら問題ない。しかし、「對島国」ないしは「對海国」と記されている。 いずれの説に従うにせよ、ここでいう「對島國」が、今日の対馬であることには異論ないものと思われる。これを「比定地4、対島国」とする(2011.8.14日現在認定)。古事記上巻、第六段「二神の国生」の条に、「次に津島を生みたまひき。亦の名は天之狭手依比賣と謂ふ」とあるのが、この對島国のことであると思われる。但し、対馬には、「和名類聚抄和名抄」の時代から現在に至るまで、上県郡と下県郡とが存在する。このどちらを「對島國」とするのか、魏の使節がどこの港に寄港したのか、その比定地は不祥である。いずれにしても、この後の「一支国」の「方三百里可り」に比較して「方四百余里可り」とあるので、これに整合せねばならない、という条件がある。上県郡は北島を指し下ノ島と云い、下県郡は南島を指し上ノ島と云うようにややこしい。通説は、南北二島よりなる対馬全島を指すが、上ノ島を云うとする説もある。その根拠は後述する。 ※「和名類聚抄」は、「和名抄」と略されることが多い。10巻本と20巻本とがある。10巻本は源順(911〜983)の撰。20巻本の方も、平安時代末期迄には成立していたとみられる。本書は、意味によって分類された現存最古の百科事典的性格を持つ漢和辞典となっている。 |
| 補足/対馬の神社について | ||||||||||||||||||
|
対馬には次のような神社がある。参考までに確認しておく。
|
| 補足/対馬の遺跡について | ||||||||
|
対馬の遺跡は、良好な入り江に面して農耕にいくらか適した平地を控えたところにまとまってみられる。その分布は上県郡に多く、特に浅茅湾沿岸に集中している。対馬には次のような遺跡がある。
|
|
|
|
第二行程の方位が記載されていない点について考察を要する。私見ではあるが、倭人伝においては、方位の記載がないのは自明であるからという理由によるのではないように思われる。むしろ特定のル−トに拠らず複数の地点より出発し得る場合、又は複数の到着地となる場合においては、つまりルートが複数であった場合に限り方位の記載がなしえなかったことにより、敢えて記載が為し得なかったものと了解し得るのではなかろうか。 |
| 「居る所は絶島で」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「方四百余里可り」について |
|
「方」とは、通説は面積のことであるとされる。私説もこれに従う。異説として、「方」を四辺形あるいは方形の一辺の長さと考える説、周囲の長さとの説もある。「方**里」を、一辺の長さと見るか、周囲の長さと見るかで、四倍の違いを生ずることになる。私説は、後に「倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え或は連なり、周旋五千余里可り」とあり、周囲の長さは「周旋」と表記されている節があるので、「方」を「周囲の長さ」とは見ない。「一辺の長さ」と見ると、400里とは一里100mの400倍つまり40kmとなり、仮にこれを正方形求積すると40×40=1600km2となり、対馬の面積に合致しない。因って、これらの説には首肯できない。 ちなみに現在の対馬は、南北約80km.東西約15km有り、面積約709km2(682km2説もある)である。「方」の意味からして、対馬全島を指すのであれば細長い地形となり叙述と合わなくなることから、ここでは上ノ島(南島)を指しているものと考える説もある。この上ノ島に限ると壱岐島より一回り大きい257km2であり、次に出てくる一支国の方三百里との比率が整合することになる。「古事類苑」所引「日本実測録」によれば、「其の南部を上の島(下県郡)と称し、東西二里二十八町(11km).南北五里二拾町(23km)」と記してあり、現代の地図と比べても正確な記述であることが判る。 |
| 「土地は山険しく深林多く」について |
| 深林とは、深い照葉樹木の森に覆われていたと解釈することができる。 |
| 「道路は禽や鹿の径の如し」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「千余戸有り」について |
| 戸とは、まさに戸であり人数ではない。人数は一世帯当り仮に10人として×戸数となる。戸と家の違いに家のところで確認する。 |
| 「良田は無く」について |
|
倭の地の特色は稲の国ということにあった。従って、撰者も又田というものに対する関心が深く、諸国を通じてこの観点からの記述を意識的に為しているように思われる。対馬国の場合には、「良田は無く」ということであるから、文字通り田地が乏しい様子が推測される。 |
| 「海の物を食べて自活し」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「船に乗りて南北に市糴す」について |
| 南北とは、倭国と朝鮮を指していると思われ、「市糴す」とは、市場で米穀を買入ることを云う。つまり、物々交換による交易をしていたものと推測される。 |
| 又、南へ、一つの海を渡ること、千余里。名づけて瀚海と曰う。 |
| 一大国に至る。 |
| 官は亦卑狗と曰い、副は卑奴母離と曰う。 |
| 方三百里可り。 |
| 竹木叢林多く、三千許りの家有り。 |
| いささか田地有り、田を耕せども猶食うに足らず、亦南北に市糴す。 |
| 【総合解説】 |
| 対馬国より一大国へ至る行程が五文意にて述べられている。これを仮に第三行程と為す。 (逸文)魏略は、「南度海 至一支國 置官与対同 地方三百里」と記している。 |
| 【逐条解説】 |
| 「又」について |
|
「又」を分析すれば、「又」は起点になりうる表現であることを了解しておく必要がある。他に、「従り」、「始めて」、「至」も同じ様に解釈出来る。既に述べたように「到」という字によって導きだされた国は起点にならないという違いがある。 |
| 「南へ」について |
| 既にのべた様に、恐らく星座の位置から割り出す方位法であったと推測するので、定点から目的地に向う方向には誤りはないものの、使節が実際に行程する道中における方位は概略であった、と理解する。この場合は、「定点から目的地に向う」記述であるので誤りはないと思料する。 |
| 「一つの海を渡ること」について |
| 「千余里」について |
| 対馬国より一大国に至る行程つまり第三行程につき検討を加えたい。現在の航路に置き換えて見て、仮に、対馬浅茅湾(対馬の下島.上島の間の小海峡)から壱岐勝本(壱岐島北端)迄の距離を求めると約80kmとなっている(対馬厳原から壱岐国の郷乃浦までは 65キロとなっている)。倭人伝では、これも千余里と為しているので、同様にして一里当りを求めると約80mとなる。従って、ここまでの第一、二、三行程を一括すれば、一里当り65m〜100mとして考えられていることになるであろう。尤もすべて水行距離としてであることが注意されねばならない。 |
| 「名づけて瀚海と曰う」について | |
|
対馬海峡のことを云う。海峡幅45キロ説もある。 |
| 「一大国に至る」について |
|
「倭人伝」の刊本、紹煕本は「一大國」としているが、紹與本、梁書、 北史、翰苑では「一支國」と記載されており、通説は「一支國」に従う。私説も又「一支國」説に従い大過ないものとする。これを「比定地5、一支国」とする(2011.8.14日現在認定)。隋書、通典も「一支國」とするが、対馬から東と書かれていることから壱岐ではなく、沖ノ島の可能性もあるという余地を残している。ちなみに古事記では「伊伎」、日本書紀では「壱岐」、国造本紀では「伊吉」と表記されている。 「一支國」を、現在の壱岐島(長崎県壱岐郡)に比定することに異存ないものと思われる。現在の壱岐島は、南北約14km.東西約12kmで面積約139km2である。「古事類苑」記載「地部」の項によれば、「東西凡そ三里余、南北凡そ四里余」とある。 壱岐島は、対馬とは対照的に比較的穏やかな起伏の少ない低台地が広がり、その間に若干の広さをもった水田が点々としている。勝本.郷ノ浦.芦辺.石田の四町で一郡をなしている。沿岸には対馬暖流が流れ、イカ.イワシなど各種水産資源の豊庫となっている。壱岐島の東南部に広がる深江田原が島内でもっとも広い平野であり、代表的な遺跡は、芦辺町原の辻遺跡と勝本町のカラカミ遺跡である。他に、壱岐島で最古のものと考えられている吉ケ崎遺跡(郷ノ浦町片原触)等がある。 |
|
但し、魏の使節が壱岐島のどこに寄港したのか、その比定地は不祥である。 |
| 補足/古事記の「伊伎」、日本書紀の「壱岐」考 | |
古事記は次のように記している。
|
| 補足/壱岐の神社について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壱岐には次のような神社がある。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【補足/壱岐の遺跡について】 | |||||||||
壱岐には次のような遺跡がある。
|
| 【補足/「壱岐のお国自慢」について】 |
|
現在の壱岐の島の特色として、漁業と農業、観光の島として知られる。2004年3月から壱岐市となり、近年、豪華客船「飛鳥」や「ビーナス」「日本丸」が寄港するようになり往来が楽になっている。次のようなお国自慢がある。古事記に記された歴史の古い島であり、古事記発祥の地とも云われる。古事記編纂の前に対馬と共に壱岐から卜部氏5人が奈良朝へ招聘され神代の部を語ったとされている。稗田阿礼は壱岐系との説もある。玄海の宝来島として古来から宝の島の伝承がある。住吉神社発祥の地、月読神社発祥の地、内海湾の初日の出は「日本」国名の起源となったとの説がある、邪馬台国発祥の島 その証拠に紀元前からの”一大国”の王都、「原の辻」遺跡がある。「春一番」名の発祥の地(郷ノ浦、元居公園に記念塔)。離島には珍しい温泉の湧く島。「天一柱」(あめのひとつはしら)と言われ国生み神話で御柱があったとされる島云々。
|
| 「官は亦卑狗と曰い、副は卑奴母離と曰う」について |
| 「方三百里可り」について |
|
ここで、対馬と壱岐との面積について考察しておくことも意味があると思われる。「方四百里」と「方三百里」の差は約1.3倍差であることになるが、対馬の実際の面積は約709km2であり、壱岐の実際の面積は約139km2であることからすると、約5倍の面積差があることになる。このことから考えると、「方四百里」と「方三百里」の記載は不正確であることになり、この不正確さは、倭人伝の記載全体を覆うこの程度の信憑性として理解すべきものであるのか、当時の測量技術的な問題として面積についてのみ限定的にとらえるべきものであるのか、又は「方」についての解釈の仕方が間違っているのかのいずれかに見解が分かれるところであるように思われる。但し、対馬を上ノ島と考える異説もあり、この場合であれば257km2であり、約1.84倍差となることから問題を生じない。 |
| 「竹木叢林多く」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「三千許りの家有り」について |
|
倭人伝記載の「家」表示は、他の諸国が「戸」で表示されているにも拘わらず、一支国と不弥国の項においては「家」表記されている。「単位が違うのは、交易が行われる夏季と行われない冬季とで人口が変化する流動的な集落構成だったためではないか」の説がある。 |
|
「戸」と「家」とどう違いがあるのか判然としない。さしあたりは同じように解釈して差し支えないものと思われるが、「戸」と「家」の表記区別は単なる表記修辞と見做すより、「戸」文化と「家」文化の相違なのではなかろうか。 |
| 「いささか田地有り」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「田を耕せども猶食うに足らず」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「亦南北に市糴す」について |
|
古代の朝鮮半島と北部九州を結ぶ航路は二つあった。唐津湾から壱岐対馬を経るルートと、もう一つは博多湾から出発して壱岐対馬を通るルートである。 |
|
又、一つの海を渡ること、千余里にして、末盧国に至る。 |
| 四千余戸有り。 |
| 山海の水ぎわに居る。草木が茂盛し、行くに前が見えず。 |
| 人々は好く魚や鰒を捕らえる。水の深い浅い無く、皆沈没して之を取る。 |
| 【総合解説】 |
| 一大国より末盧国へ至る行程が、四文意にて記されている。これを仮に第四行程と為す。いよいよ今日の日本列島本土に上陸したことになる。 |
| 逸文魏略は、「又度海千余里 至末廬國 人善捕魚 能浮没水取之 東南五百里 到伊都國 戸万余 置官曰爾支 副曰洩渓 柄渠 其國王皆属女王也」と記している。 |
| 【逐条解説】 |
|
「又、一つの海を渡ること」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「千余里にして」について |
|
一支国より末盧国へ至る行程を第四行程と考えると、この間も又「千余里」と記載されている。魏の使節の上陸地を廻っては、1.「呼子」港説、2.唐津港説、3.佐世保港説等々がある。通説の比定地を現在の航路に直して、仮に壱岐勝本から唐津迄の距離を求めると約50キロ、壱岐の石田から唐津までの距離は約40キロ、壱岐の南端から東松浦半島北端の「呼子港」を考えた場合には約30キロとなる。これを一里当りに直すと50m、あるいはそれ以下ということになる。 |
| それでは末盧国をどこに比定するのかということになる。私説は、第三行程が千余里であり、第四行程も又千余里と記載されている以上、第三行程の距離と等間隔にあたる地への比定が条件とされるとしたい。となると、この距離を半径としてコンパスで円を描き、該当地を確認せねばならないことになる。これによれば、西は長崎県の五島列島から、東は福岡県の宗像郡あたりまでの北九州沿岸の任意の地点に比定することが可能となる。正確には、この任意の地点より、この後に続く伊都国の比定地との整合性を持つ地点ということになるであろう。 2011.8.15日再編集 れんだいこ拝 |
| 「末盧国に至る」について |
|
語義的に解読すれば、「末盧」は通常「マツロ」、古事記では、マツラ(末羅)と読まれる。 マツラはマヅラに通音し、はじめ末羅であったが、のちに松浦の字をあててマツラと呼ぶようになった。日本書紀巻第九、神功皇后摂政前紀仲哀天皇九年三月ー四月の条に「因りて竿を挙げて、乃ち細鱗魚を獲つ。時に皇后の曰はく、梅豆邏國と曰ふ。今、松浦と謂ふは訛れるなり」とある。 |
| 「末盧国比定地諸説考 | |||||||||||||||||||||
| 末盧国比定地諸説を考察する。通説は、現在の佐賀県東松浦郡.西松浦郡.北松浦郡の地一帯に当てており、1・松浦半島の北端の呼子港を停泊地に予定する「呼子説」と2・「唐津説」、3・糸島郡前原町の「三雲、井原、平原付近」説に分かれる。しかし、通説のこの比定地では里程が合わない。そこで、異説を登場させることとする。外にも東寄りに4・神湊説、5・「福岡説」、西寄りに6・「佐世保港説」、7・西彼杵(にしそのぎ)半島説、8・「伊万里港説」等々がある。 いずれにせよ、通説の末盧国=松浦半島唐津市説は、距離的な直線最短コ-スであることを踏まえて、たまたま「マツラ.マツロ」と「マツウラ」との音訳比定に拠っていると思われるが、1・里程が合わないという欠陥、2・当時の海岸線を想定した場合、糸島水道に隔てられた島である可能性、3・見かけの距離とは別に潮流の関係で航路となりにくいという理由により、比定地の間違いとして共通の認識となるべきであると思われる。 1、通説は次の通りである。
他に、東寄り説、西寄り説がある。これを図示する。
松浦県(まつらがた)に関して、万葉集に次の歌がある。
二番目の歌は万葉集巻15にある歌で、「天平8年丙子夏6月、使を新羅に遣はしし時、使人等各別を悲しみて贈りて答へる、また海路の上に旅を慟み思を陳べて作れる歌、また所に當りて誦詠へる古き歌」という詞書がある。松浦は当時新羅や中国へ船出する港であった。 |
|||||||||||||||||||||
| 補足/「当時の海岸線」について | |||
| 私説は、次のことを重視する。「当時の海岸線」に対して一考せねばならない。かって、盲目の詩人宮崎康平氏による「まぼろしの邪馬台国」が上宰され、邪馬台国ブームを盛り上げることに一役を買ったが、同氏の邪馬台国ほか諸国の比定については評価がかんばしくないものの、その著書の中で指摘された、当時の「海岸線の復元思考」は価値ある一石であったと思われる。同氏曰く、現在の海岸線と邪馬台国時代のそれを区別することが肝要であり、仮に弥生海岸と名付けられたそれは、現在の地図でいう等高線の5〜10メ−トル辺りの範囲はかっては海域であり、後次第に陸化していったものであるものと推測される云々。 その著書「幻の邪馬台国」の該当部を抜粋すると、次のように述べている。
|
| 補足/「当時の船と海流の関係」について | |
高木彬光氏は、その著書の中で、帆船航路による「神湊到着説」を唱えている。氏は、自然地理学的な事実の認識の重要性を指摘し、魏の使節が訪れた時期の考察と、使節が乗ったと思われる船とその航路の推測に情熱を傾け、概略次のように述べている。
こうして、氏は、末盧国を北九州北岸の「神湊」に比定することとなる。 東京商船大学名誉教授・茂在寅男氏も「神湊説」を有力説とする。氏は、壱岐・対馬の現在にも伝わる船の下に帆を張るという変わった帆の使い方=潮帆(しおうぼ)に注目して、当時の帆船もそうであったと推定する。潮帆は、潮夕(ちょうせき)と海流が強いための工夫から生み出された帆船であり、壱岐からの黒潮の分派の流れに乗って辿り着くところを比定すれば「神湊」は自然推力で辿り付く事のできるヶ所になるという。雑誌ムーの2001.11月号の「猪群山ストーンサークルは卑弥呼の墓だった」(山上智)によれば、この地の「年毛(としも)神社」所蔵の古文書に「古来、この辺りは万津浦(まつうら)と呼ばれていた」と記す文書があると云う。 |
| 【れんだいこの比定する末盧国とは】 |
| 末盧国をどこの地に比定するかが肝心となる。末盧国は倭国の玄関口に当り、これをどこへ持って来るかで後の地名比定も大いに影響を蒙る訳であるから、軽率には定めがたい。私説は、末盧国を「糸島郡前原町の三雲、井原、平原付近から神湊、宗像までの範囲」と比定して、魏の使節到着地を神湊ないしは宗像に比定することとする。これを「比定地6、末盧国」とする(2011.8.14日現在認定)。壱岐勝本より神湊迄の実際の距離は約**kmである。一支国よりの里程及び伊都国との整合性より導きだされる比定であり、こう考えて疑問を残さない。これを史料により裏付けると、古事記中巻の、神功皇后新羅征討のくだりに、「亦筑紫の末羅県の玉島豊に到り坐して」という記述があり、筑紫国における末羅県の存在が確かめられてもいる。 通説は伊都国に比定する地であるが、伊都国については後に述べるように内陸地を確信しているので、この土地こそ末盧国と比定することとしたい。この地域には標高416mの高祖山があり、456から768年に大和朝廷の命によって吉備真備が対新羅戦争の爲怡土城を築いたことで知られており、この地は、東に博多平野、北に糸島水道、西に糸島平野を擁しており宮城所在地としての地勢的条件を備えているとされる。 それでは、「福岡説」ではどうなるのであろうか。壱岐勝本より福岡市迄の距離は約75kmであり、これを一里100m前後で里程を求めると約750里となり、道中迂回しながらの航行であったとすれば千余里の記述とさほど齟齬をきたさないことになる。魏使の諸国歴訪を踏まえた航行コ-スとしては糸島半島以西辺りへ向かうことも充分考えられることと思われる。音訳比定としては、「マツラ.マツロ」と「マツバラ」も近く、「マツバラ」を松原と読めば、博多湾には百地松原、西隣の今津湾には生之松原等類似音地名には事欠かない。 |
| 「方位の記載がない」ことについて |
|
ここでも一大国から末盧国までの方向が記載されていない。第二行程と同じく、「複数の地点の出発地乃至複数の到着地」になっていたものと思われる。 |
| 「末盧国には官名の記載がなされていない」ことについて |
|
末盧国には官吏の記載がない。 |
| 末盧国には官吏の記載がないことにつき、後の伊都国との絡みにおいて、末盧国が実際には伊都国の統治下に置かれていたことを推測させる。後の42小節の邪馬台国の下りで「女王国より以北には、特に一大率を置き検察す。諸国これを憚る。伊都國で常治し、他の国でも置かれている刺史の如きものである」なる記述が出てくる。これによると、「一大率」(いちだいそつ)が一大(壱岐)国、末盧国、伊都国から邪馬台国間を検察していたことになる。一大率が伊都国に置かれていたことにより末盧国には官が不要であったと考えられる。こうして、末盧国は行政的には伊都国の官の管轄下にあり、外交面でも一大卒の検察下にあったとみることにより末盧国官吏不在が整合的に理解される。「官の名前が書いてないのは使者が上陸しなかったことを思わせる」なる解釈が見受けられるが、使者の上陸有無と官の不記載は関係なかろう。別説に「魏志倭人傳に出てくる末盧(まつろ)國は女王國に属していません。末盧國には加盟国としての官も副も記録されていないからです」がある。私説は、「女王国より以北には、特に一大率を置き検察す。諸国これを憚る。伊都國で常治し、他の国でも置かれている刺史の如きものである」に添って解したい。 2011.8.13日再編集 れんだいこ拝 |
| 「四千余戸有り」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「山海の水ぎわに居る」について |
|
いずれにしても、山が直接海岸にせまっているという地形であることを表現しているものと思われる。 |
| 「行くに前が見えず」について |
|
この記述をうっかりして見過ごしがちであるが、これを倭国の特徴に対する的確な表現として捉える必要がある。魏の使節からみて、他の諸国に比較してみた場合、対馬は深林多く、一支国は竹木叢林多く、末盧国は草木茂盛であることが大きな特徴であったものと推測される。このことは又倭国全体の共通項として認識しておきたいように思われる。 |
| 「人々は好く魚や鰒を捕らえる」について |
|
通説は、「好く」を「好んで」と解釈しているが、この個所は、「魏略」や「御覧魏志」では、「善捕魚」となっており、このことから考えると「好(能)く魚や鰒を捕らえる」と理解されるべきだということになる。 参考までに記すと、この魚や鰒を捕らえる倭人の能力は伝統的であったようであり、「水停まりて流れず。中に魚を見るも捕ることを得ず。倭の網をよくするを聞き、東に倭人国を撃ちて千余家を得、秦水の上に置きて魚を捕らしめ糧食を助く」(後漢書鳥桓鮮卑列伝)とある記述もこれを証左している。 |
| 「水の深い浅い無く」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「皆沈没して之を取る」について |
| 字義による記述通りとする。神湊、宗像の古来からの伝統として今もなお「海女、海男」による素潜り漁が息づいている。 |
|
東南へ 陸行すること 五百里にして、伊都国に到る。 |
| 官は爾支と曰う。副は泄謨觚.柄渠觚と曰う。 |
| 千余戸有り。 |
|
世々王有るも、皆女王国が統属す。 |
| 郡使が往来するとき常に駐まる所なり。 |
| 【総合解説】 |
| 末盧国より伊都国へ到る行程が、五文意にて記述されている。これを仮に第五行程と為す。 (逸文)魏略では、「其國王皆属女王也で伊都國の王は皆、女王に属す」とある。 |
| 【逐条解説】 |
| 「東南へ」について |
|
ここで「東南」の正確さが問題となる。恐らく、使節の位置している定点と星座と目印の山との按配から指標している方位と思われる。この場合、正確な方位と看做すべきか、概略の方向として理解すべきかが問題となる。 |
| 「陸行すること」について |
| 「陸行する」をどう解するべきか。 |
| 奇妙なことに従来この「陸行すること」について考察されることがない。恐らく、通説による末盧国松浦半島、伊都国糸島半島辺りの比定により漫然と見過ごされてきたものと思われる。倭人伝の里程の記述の仕方を総見すれば、水行が自然であれば単に水行と記述されており、陸行が自然であれば単に陸行と記述されておると思われる。そういう意味において、第一行程「郡より狗邪韓国」、二行程「狗邪韓国より対馬国」、三行程「対馬国より壱岐国」、四行程「壱岐国より末盧国」はいずれも水行であった。この第五行程「末盧国より伊都国」にして初めて陸行が記述されているのであり、陸行で行くのが自然であったか、もしくは陸行でしか行けなかったものと推測される。 ここまでの諸国へ至る記述の仕方と伊都国以降の諸国へ至る記述のそれとを比べて見て、単に「陸行すること」とあるのは、上述の如く考えるべきであるということを力説したい。つまり、伊都国はどうやら内陸地にある国であるという推測が成り立つのである。こう理解しないと「陸行すること」の意味が見えてこないことになる。 これに従えば、第六行程「奴国へ到る道」、第七行程「不弥国へ到る道」には、水行陸行の別無く単に方位と里程のみが記されており、これは逆に水行陸行どちらでも行き来できたことが推測される。こうして、第八行程「投馬国へ到る道」は水行とあるからには、当然同じ見地により、水行で行くのが自然か叉は水行でしか行けないと解するべきであろう。これによると、第九行程「邪馬台国へ至る道」の「水行十日陸行一月」は、水行で十日の里程、陸行で一月の里程という両行程の道行又はそのいずれかであったものと思われる。 以上の総見により、伊都国へ至る陸行の記述は、明らかに伊都国が内陸地に存在していたことを証左しているものと推測し得る。この点については、通説も異説もなべて間違っており、伊都国の比定は最初からやり直さねばならないものと心得る。れんだいこのこの私説が卓見として評価される時が来るだろうか。 2011.8.13日再編集 れんだいこ拝 |
| 「五百里にして」について |
| 通説の末盧国唐津市付近より通説の前原町付近を求めると約25キロとなる。500里は長里で200km、短里で50kmとなり、短里に従ってさえ、この25キロは、これまでの里程感覚80mから100mとされるその半分の距離にみたない。ということは、ここでも通説の前原町の比定が間違っているのではないかということを推定させる。但し、この「五百里」は陸行であるから、これまでに求めた水行の一里100m基準がそのまま通用するかどうかは判然としない点は残る。 |
| 「伊都国に」について | |
|
「伊都国」は「イト」又は「イツ」と読まれる。語義的には、イは胆嚢の古語。ト(甲類)は処、戸、門で場所を表す接尾語、区画相互の間を遮断し、その出入りのために設けた施設、門を構え、戸を設ける。また、河や海などの両方がせまって、地勢的に出入口のようになっているところをもいう(字訓)。「イツ」は厳に通じ、「神聖な」「神霊の威光」といった語感がある。この国は、代々伊都之尾羽張神の治める国として知られる。伊都之尾羽張神は、又の名を尾羽張神といい、海や川の航行.長い剣をつくる技術にすぐれていた。
|
| 「伊都国比定地諸説考」 | ||||||||||
|
この伊都国をどこの地に比定するかも重要である。通説は、1・筑前怡土郡.早良郡、現在の福岡県糸島郡地方に比定する。他に2・赤池村説、3・伊都国豊前市説等がある。
|
| 【れんだいこの比定する伊都国とは】 |
| 私説は、伊都国の比定につき「陸行=内陸説」に随い、未だ現地へ行っていないが吉野ケ里遺跡を中心とする現在の佐賀県鳥栖市付近、朝日山付近、神埼.三田川.中原地域等佐賀市北方地域の筑紫平野の一角を占める佐賀平野の東部、即ち鳥栖市から佐賀郡にかけての背振山地南麓一帯とする。これを「比定地7、伊都国」とする(2011.8.14日現在認定)。神湊から吉野ケ里までの500里を里程感覚80mから100mで計算すると約40kmから50kmになる。実際の距離は**である(これは後日確認し書き込みたい)。 |
| 【吉野ケ里遺跡考】 |
| 吉野ケ里遺跡は、神埼郡三田川町.神埼町に位置している。吉野ケ里丘陵は、これらのうち神埼.三田川.中原地域に含まれる。この地域は、高位.中位の丘陵が山麓部から南の平野部へ舌状に細長くのびる地域である。これらの丘陵上には、姫方遺跡、船石遺跡、切通遺跡、二塚山遺跡、横田遺跡、三津永田遺跡など弥生時代の墓地を主体とする著名な遺跡が数多く立地する。吉野ケ里遺跡は丘陵上すべてが甕棺墓地といわれる吉野ケ里丘陵の南部に位置する。地理的に自然の要害を為し、また生産力も豊かなこの地域を時の権力者が把握することは、内政的にも対外的にも重要な政治課題でもあったことと思われる。 その特徴は、弥生時代中期から後期(前1〜後3世紀)の日本最大規模の環濠集落(まわりを大きな濠で囲まれた集落)と、弥生時代中期(前1世紀)の巨大な墳丘墓である。吉野ケ里遺跡の発見は、日本の歴史上最大の謎とされる邪馬台国の時代の倭人伝に記された日本の状況を解く鍵を遺跡の上で初めて具体的な形で具現したことにある。とりわけ環濠集落にはその一画に物見櫓の跡及び重要な遺構として外濠の外側に建てられた高床の倉庫群が19棟以上、その建物一つをとっても一般の倉庫の2から4倍の容積があり、広い地域の物資を集積、保管する公的な蔵であると認められる概要を示している。 まさに倭人伝の一説「租賦を収む。国の邸閣(倉庫)有り。国に市有り、有無を交易し、大倭にこれを監せしめる」の記述に相応する観がある。吉野ケ里遺跡の近くには他に姫方遺跡、船石遺跡、切通遺跡、二塚山遺跡、横田遺跡、三津永田遺跡等があり伊都国を構成していたであろう遺跡に事欠かないこともこれを裏付ける。 |
| 吉野ケ里遺跡が凡そ卑弥呼の時代に照応していることが魅力的である。但し、問題は、邪馬台国とすべきか伊都国とすべきか、その他とすべきかの判断が問われている。私説は、卑弥呼の時代の遺跡にして、内陸部にして、
「租賦を収む。国の邸閣(倉庫)有り。国に市有り、有無を交易し、大倭にこれを監せしめる」の記述に相応するとすれば、まさに伊都国として相応しいと読む。 2011.8.15日再編集 れんだいこ拝 |
|
伊都国へ到る迄の記述の仕方と伊都国以降の国々の記述の仕方には相違がある。伊都国以前は「方角、距離、国名」の順に記されているのに対し、伊都国以降は「方角、国名、距離」の順に記載が為されており、距離と国名の順序が入れ替わっている。邪馬台国研究史の中で初めてこのことを指摘し一石を投じたのは榎一雄氏であった。云われてみればなるほどの違いである。邪馬台国研究史上に占める榎氏の功績はここにある。これを仮に「榎氏の第一指摘、国名記述の順序差」と命名する。 |
| 「榎氏の第二指摘、放射説」について |
|
榎氏はこれをどう解いたか。その著「魏志倭人伝の里程記事について」は、これまで魏志倭人伝に表われた方位方角と距離の読み方は、連続式(この説を直進説又は続進説という)に末盧国、伊都国、奴国と読み進み疑いを持たなかった。しかし、歴然と記述が違う以上解読も異ならねばならない。そこで、伊都国以降の奴国、不弥国、投馬国、邪馬台国は伊都国を起点として読み進められるべきだ主張するところとなった。つまり、邪馬台国への行程を伊都国を要として放射線状に読むことを提言した。これほ「放射説」と云う。 |
|
私説は、狗邪韓国の項で説明した通り、一般に中国古文の中で、同じ個所で「至」と「到」が同文で出現した場合には区別して使用されており、当然区別して読まれなければならないという観点に立つ。その区別は、 「至」は、「通行途次の場合に使われ、至る先は経過点を表す」のに対し、「到」は、「逗留地であり、次の行程上の起点地ではないという含意を持つ到着地を表わす」という違いがあるとしたい。 |
| 「官は爾支と曰う。副は泄謨觚.柄渠觚と曰う」について |
|
官は、元来、将帥が携行する祭肉を置く軍の聖所で将官をさす。のち司るところのあるものを官と称した(字統)。帯方郡からの使に応対した官であろう。「爾支」は、「ニシ」、「ニキ」(稲置)。「泄謨觚」は「シマコ(島子)」、「カツ子」、「セモコ」、「イモコ(妹子)」、「エイモコ」、「セツモコ」などと読める。「柄渠觚」は「ヒココ」、「ヘクコ」、「ヒホコ」、「ヒャウキョコ」などと読める。不祥である。「觚」は「彦」の「ヒ」が関係しているとの説もある。あるいは、「妹子」などの「子」とも推測されている。 |
| 「千余戸有り」について |
|
伊都国の戸数は、この国の重要さからみて千余戸は少なすぎるのではないかという説がある。魏略逸文の方には「戸万余」となっており、私説も又、伊都国の重要な立場から見て、「万余戸説」に従うのがよいと思っている。あるいは、末廬國や奴國より戸数を少なく記述する根拠があったと看做すべきだろうか。 |
| 「世々」について |
| 「代々」という意味であろう。 |
| 「世々王有るも」について |
| 「世々王有る」は、「代々王がいる」と解する。「王」の存在を明記しているのは、この伊都国と邪馬台国と狗奴国の三国だけであることが注目される。 |
| 「皆女王国が統属す」について |
|
「皆女王国が統属す」につき、通説は、伊都国王は女王国に従っていたと解釈するが、「皆女王国が統属す」を逆に「女王国を統属す」と読んで、伊都国王を女王より上の立場に見ようとする説もある。 |
| 「郡使が往来するとき常に駐まる所なり」について |
| 「郡使が往来する」とあり、伊都国が外交的に重要な役割と地位を占めていたことが伺われる。「駐まる所」の解釈も一定していない。「必ずここに立ち寄る」という意味と解する。その機能は、「後の太宰府の先駆けのような、今日の外務省兼入国管理事務所のようなものだったらしい」(倉橋日出夫「古代出雲と大和朝廷の謎」)。 |
|
東南へ、百里で、奴国に至る。 |
| 官はし馬觚と曰い、副は卑奴母離と曰う。 |
| 二万余戸有る。 |
| 【総合解説】 |
| 奴国へ到る行程が、三文意にて記述されている。これを仮に第六行程と為す。 |
| 【逐条解説】 |
| 「水行、陸行の別が記載されていない」ことについて |
| 奴国行きについて「水行、陸行の別が記載されていない」。 |
| 通常このことについては注目されないが、既に述べたように、私説によると、水行、陸行いずれにても可であったことを意味していると解釈する。してみれば、奴国の比定地はこの条件を充たさなければならないことになる。 2011.8.13日再編集 れんだいこ拝 |
| 「東南へ」について |
|
放射説以前の通説及び伊都国起点放射説の場合は、伊都国よりの方位と見る。 |
| 私説は、「至、到論」の規定により伊都国を起点としていないとする。故に末盧国よりの方位と受けとめる。となると、伊都国と同方位の東南と云うことになり、伊都国の手前地ということになる。しかし、伊都国は陸行とある。とすれば奴国も陸行地となる。そういう意味で陸行、水行の説明がないのであろうか。となれば、末盧国から伊都国の間の末盧国よりの地点に存在していたとしか比定できないことになる。ここの判断が非常に難しいところである。
2011.8.15日再編集 れんだいこ拝 |
| 「百里で」について |
|
「百里」とは非常に近い距離にあることになる。これまで準じてきた短里で計算すれば約10kmということになる。これを伊都国よりの行程と見るのか末盧国よりの行程と見るのかが問われている。通説は、伊都国を前原町付近としているので、奴国=博多(福岡)付近に比定すると約20kmとなる。100里は長里で40km、短里で10kmとなり、短里に従っても20キロはその倍の距離になることになる。通説の比定地では、末盧国より伊都国へ至る場合には記載された500里の半分に足らず、伊都国より奴国へ至る場合には記載された100里の倍の距離になる。いかにも杜撰な結果になっているが怪しまれない。私には、通説の比定地が間違っていることにより、こうしたチグハグなことが平気でまかり通っていることになっているのではないかと思われる。 |
| 魏志倭人伝の原書である王沈の魏書、梁書、北史には、「又」という字が加えられている云々。これにつき考証を要す。 |
| 「奴国に至る」について |
|
「奴国」は一般に「ヌ国」と読まれるが、これを「ノ国」と読んで野の意味に、又は「ナ国」と読んで「なの県」を表わすなど諸説がある。後世、儺県(なのあがた;博多附近)とされており、倭人伝において「ナ」と読まれる記述は「那」や「灘」であると解釈することが出来る。 |
|
○、博多説 通説は、博多説が代表している。「奴国」を筑前那珂、「なの県」.那の津、糟谷郡の一部辺りの「博多湾沿岸地域全体」と考えると、今の福岡市博多付近が中心ということになり、金印の発見で有名な志賀島の「漢委奴国王」の刻みと符合することになるとされる。その範囲は、福岡県の筑紫、早良、粕屋などの郡と福岡市を流れる那珂川.御笠川流域を含んでいるとされる。この辺り一帯が古名で那賀郡と称されており、那賀=ナガに通ずるものとして奴国とは那賀の国の略と考えることも出来る。 遺跡としては、春日市の須玖遺跡、岡本遺跡があり、これを中心とする。 千メートル級の背振山を源として北流し博多湾にそそぐ那珂川の東側、御笠山の間の台地にあって福岡平野のほぼ中央に、高さ30から40めーとるの須玖丘陵が突き出ている。この丘陵地帯から、おびただしい甕棺墓と土こう墓、箱式石棺墓が集中し、三十数面の前漢鏡のほか、銅剣、銅矛、銅戈など青銅器品、ガラス製壁.ガラス製まが玉と管玉等が多数出土している。その豪華さは他に較べるものがなく、奴国の王墓と推定されている。原田大六氏は「奴国王の環境」、「邪馬台国論争」等で、須玖遺跡を奴国の墓域であると唱えている。 この地域にあって特筆すべきことは、青銅武器の一大生産地であったと思われることである。最も古い鋳型は、金印発見の志賀島の勝馬で出土し、それは弥生中期のものとされている。次には、春日市大谷遺跡から出土した銅剣、銅矛、銅鐸の鋳型、そして、この春日市から福岡市博多区那珂まで伸びる丘陵で、続々と鋳型が出土して、その丘陵地帯は鋳型丘陵とも呼ばれている。 |
|
○、中津市説 伊都国豊前市説は奴国を中津市に比定する。中津平野の東の外れには宇佐市があり、全国八幡社の総本宮である宇佐神宮が祭られていることが、その説を裏付けるとされる。 |
| 【れんだいこの比定する奴国とは】 |
| 私説は、奴国の比定地を末盧国より伊都国へ向かう同じ方位の途次に末盧国より凡そ100里の里程にあったと推測される 国とする。ここで云う100里はこれまでの一里100mに従えば凡そ10kmであるから、神湊より10km前後の国ということになる。これを「比定地8、奴国」とする(2011.8.14日現在認定)。 |
| 補足/金印について |
|
那珂郡志賀島出土の漢委奴国王印について、三宅米吉氏は、明治25年に、この金印を「漢の委の奴の国の王」と読むことを主張し、金印の出現をもってこの地域に奴国があった証左とした。通説もこれに従う。但し異説も多く、その一つは、「漢の委奴の国の王」と読まれるべきで、そうなると「委奴国」であり「奴国」ではないことになり、従って「奴国」を志賀島に比定する史料にはならないとする。 |
| 補足/「漢の当時の奴国」について |
|
邪馬台国共立政権が樹立される以前の時代の推定であるが、この奴国が倭国の王権を代表していた時期があったものと思われる。 |
| 「官はし馬觚と曰い、副は卑奴母離と曰う」について |
| し馬觚とは何者か。 |
| 「二万余戸有る」について |
| 字義による記述通りとする。伊都国は「千余戸有り」なので、奴国は伊都国の20倍の人口があることになる。ちなみに投馬国5万余戸、邪馬台国7万余戸と記されている。 |
|
東へ、百里行くと、不弥国に至る。 |
| 官は多模と曰い、副は卑奴母離と曰う。 |
| 千余家有る。 |
| 【総合解説】 |
| 不弥国へ到る行程が、三文意にて記述されている。これを仮に第七行程と為す。 |
| 【逐条解説】 |
| 「東へ」について |
|
「奴国」より「東へ」と受け取る。 |
| 不弥国行程も水行陸行別不記載である。私説は、「至、到論」の規定により奴国よりの方位と受けとめる。水行陸行別不記載の理由は、奴国へ到る行程の時に論じたが、水行、陸行いずれにても可であったことを意味していると読む。よって、「奴国より水行もしくは陸行で百里」が不弥国となると読む。ここの判断も非常に難しいところである。
2011.8.15日再編集 れんだいこ拝 |
| 「百里行くと」について |
|
私説は、奴国より100里とみなす。通説に従えば、不弥国は、奴国福岡説より東の宇美町付近となる。奴国福岡説からの距離を求めると約5キロとなる。100里は長里で40km、短里で10kmとなり、短里に従った場合でも、この5キロはその半分の距離になることになる。末盧国より伊都国へ至る場合には500里の半分に足らず、伊都国より奴国へ至る場合には100里の倍の距離になり、今度は又半分に足らずということになる。通説の比定地を支持する者はこの辺りを学問的に説明する義務があると考えるのは私一人であろうか。結論として、やはり比定地が間違っているのではないかということになる。 |
| 「行く」について |
| 字義による記述通りとする。 |
| 「不弥国に至る」について | |
|
語義的には、フは時の経つこと、地域を経過すること、機織のたて糸(字訓)であり、ミは処、水、辺、海(大分県古地名の語源と地誌)。中継地点として機能していた國と解釈できる。不弥国は「フミ」と読まれる。又はヒヲミと読む。「不弥」を「海」ないし「産み」(神功皇后伝承で、応神天皇を産んだとするもの)と解する音訳比定が通説となっている。 通説は、福岡県の粕屋郡宇美町説、嘉穂郡穂波町説、大宰府附近説、鞍手.宗像郡津屋崎町説.糟谷各郡の一部、福岡市博多区と北九州市門司区の間の港湾説等々を説く。 |
|
|
○、福岡県の粕屋郡宇美町説 古事記に「宇美」仲哀天皇紀、書紀に「宇み」神功皇后紀、筑紫風土記逸文に「芋野」とある地である。神功皇后が応神天皇を出産した地と伝えられている地であり、神功皇后、応神天皇などを祀る宇美八幡宮がある。江戸時代の新井白石、本居宣長、鶴峰戊申、明治以降では、白鳥庫吉、内藤湖南、吉田東互、和歌森太郎などの学者がこの説を唱えている。音訳比定によっている。 宇美町は粕屋平野にあって、宇美川、多々良川、須恵川の三つの川が博多湾に直結してをいる。宇美川流域には、前方後円墳の「光正寺古墳」を始めとして、多くの古墳が点在している。亀山遺跡には、福岡地区で発見された中で最も大きい亀山型石棺墓があり、それは、亀山神社の社殿脇にある墳丘にあって、2メートルを越える大きな三枚の板状の石が組み合わせてあって、この墓は、弥生時代の後期の宇美流域を支配した首長の墓だとされている。宇美川流域には、この他にも大小四基の円墳のある「神領古墳群」、五基の円墳と一基の前方後円墳をもつ「浦尻古墳群」、粕屋平野最大の円墳をもつ「七夕池古墳」などがあり、多々良周辺では青銅器の鋳型も出土している。 2000.8.1日付け読売新聞によると、光正寺古墳の埋葬施設から、副葬品として弥生時代終末期(2世紀後半から3世紀前半)の土器が出土していたことが31日わかった。邪馬台国時代に、畿内のホケノ山古墳(奈良県桜井市)などと並んで、九州でも古墳が出現していたことが確実となった。同古墳は全長52mの前方後円墳。今回の発見で不弥国時代の王墓である可能性が強まった。 |
|
|
○、嘉穂郡穂波町説 延喜式、和名抄に、穂波郡(現在の飯塚)とある地である。音訳比定によっている。粕屋郡宇美町を少し離れた遠賀川上流に位置している。穂波町の近くの飯塚市立岩遺跡が根拠となっている。明治の歴史家菅政友、那珂通世、久米邦武などが、この説を説いた。現代でも、原田大六、鳥越憲三郎、山尾幸久、児島隆人、高橋徹の諸氏は、この説をとっている。
|
|
|
○、福岡県宗像郡津屋崎町説 宗像神社福岡県宗像郡玄海町の所在地に近く、沖ノ島に渡る玄海町神湊に隣接津屋崎町とする説もある。「魏志倭人伝なぞ解の旅;桂川光和氏」は、「深い入り江になつた、良い港があるため、江戸時代には廻船の寄港地として栄えた」として津屋崎説を唱えている。
|
|
|
○、太宰府市説 太宰府政庁がおかれた太宰府市を比定する説がある。この説を白鳥庫吉が唱えている。め較より朝倉郡朝倉町付近を比定する説もある。 |
|
|
○、朝倉郡朝倉町付近説 朝倉郡朝倉町付近を比定する説もある。 |
|
|
○、志賀島説 |
|
| ○、異説として、国東半島の北端国見町付近を比定しているものがある。全国八幡社の総本宮である宇佐大社が祀られている。宇佐大社下の福岡県玄海町の辺津(へつ)宮はイチキシマ姫神、大島の中津宮はタギツ姫神、沖ノ島の沖津宮はタゴリ姫神を祀り、イチキシマ姫神、タギツ姫神、タゴリ姫神を合わせて宗像三神と云う。 |
| 【れんだいこの比定する不弥国とは】 |
|
不弥国の比定地について、私説はこう考える。不弥国へ至る条件として、1・海に関わる地名であり、2・奴国より「東」へ向う地であり、3・奴国から水行、陸行どちらとも可能で、4・「百里」の行程、5・共に「家」表記されていることで一支国と文化的共同性が認められる、という5条件を充足させる必要がある。そうすると、志賀島説はまず方位の点で難がある。私説は定まらないが一応博多説を採る。これを「比定地9、不弥国」とする(2011.8.14日現在認定)。 |
| 「官は多模と曰い、副は卑奴母離と曰う」について |
| 多模とは何者か。 |
| 「千余家有る」について |
|
戸数を表わす単位に千余家と「家」が出てきている。この「家」表記は、他には一支国に出てくるのみである。私説は、これは偶然ではなく、不弥国が一大国と文化的共同性があることを示唆しているものと推測する。同時に、こういう記述の書き分けができるということは使節が現地へ足を入れているからであると解する。 |
これより後は、「投馬国から邪馬壹国に至るまで」に記す。
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)