
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2).9.13日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
この時期の仏教伝来を廻る蘇我氏と物部氏の政争も大いに注目されてしかるべしであろう。以下、これを検証する。古代史に於ける漢学伝来、仏教伝来は近代史に於ける洋学伝来、シオニズム伝来の好一対を為している。古代の日本人は、漢学、仏教とも能くこれを咀嚼した。近代日本人は洋学もこれを能く咀嚼した。残念ながらネオ・シオニズムに対しては余りにも無防備過ぎる様に思われる。それはともかく、古代日本が、如何に漢学と仏教を受け入れつつ咀嚼したのか、その経緯を検証しておくことにする。
専ら「ウィキペディア」の各項その他を参照し、一部はそのまま書きつけている。今後、更に練り直すつもりである。
2006.12.21日 れんだいこ拝 |
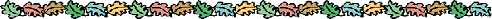
| 【第28代、宣化天皇が即位】 |
| 536(宣化天皇元)年、継体天皇の第二子にして母は尾張目子媛(おわりのめのこひめ)、先の安閑天皇が亡くなったとき、その子供が居なかったために同母弟の宣化天皇が即位した。蘇我高麗の子の蘇我稲目が臣下としての最高位である大臣の地位に就任。同年、天皇の命により凶作に備えるため尾張国の屯倉の籾を都に運んだ。この御世に於いて、筑紫の官家の整備を行い、大伴金村に命じて新羅に攻められている任那に援軍を送った。即位が69歳と遅く、在位が3年余りと短いため、あまり主立った事績は無い。
|
| 【第29代、欽明天皇が即位】 |
| 540(欽明天皇元年)、欽明天皇が即位。蘇我稲目が引き続き大臣となり、娘の堅塩姫(きたしひめ)と小姉君(おあねのきみ)の二人を欽明天皇の大妃、妃として天皇家と姻戚関係を結ぶ。堅塩媛は七男六女を産み、そのうち大兄皇子(後の用明天皇)と炊屋姫(後の推古天皇)が即位している。小姉君は四男一女を産み、そのうち泊瀬部皇子(後の崇峻天皇)が即位している。続く用明天皇に対しても娘の石寸名(いしきな)を妃とさせ、外戚関係に入る。 |
|
2016.9.29日、「象徴の行為としての「国見」/天皇の歴史(8)」。
天皇、皇后両陛下が、岩手国体総合開会式などに出席するため、岩手県を訪問し、東日本大震災の被災地で復興状況を視察された。震災後、初めて訪れた大槌町の「三陸花ホテルはまぎく(旧浪板観光ホテル)」では、出迎えた千代川茂社長に、天皇陛下が「頑張りましたね」とねぎらいの言葉を掛けられた。このニュースに接し、天皇陛下の生前退位(譲位)へのお気持ちの表明の中の次の一節を思った。
| 「私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行(おこな)って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井(しせい)の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした」。 |
「象徴」という言葉はWikipediaでは次のように説明されている。
象徴(しょうちょう)とは、抽象的な概念を、より具体的な事物や形によって、表現すること、また、その表現に用いられたもの。一般に、英語 symbol(フランス語 symbole)の訳語であるが、翻訳語に共通する混乱がみられ、使用者によって、表象とも解釈されることもある。
- 例
- ハトは平和の象徴である - 鳩という具体的な動物が、平和という観念を表現する。
- 象徴天皇制 - 日本国憲法第1条では「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」と規定される。
|
例示されたように、天皇陛下が日本国憲法第1条を踏まえて発言されていることに意味があるのではなかろうか。「日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」とは、端的に言えば日本という国のアイデンティティということであろう。それを皇国史観では「国体」と呼んだ。そして、小堀桂一郎日本会議副会長は「生前退位は国体の破壊に繋がる」としたのである。⇒2016年9月
5日 (月):「国体」とはどういうものか/天皇の歴史(4)
今上天皇は、「日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅」を「象徴的行為として、大切なものと感じて来ました」と言っておられるのだ。これは古代において、「国見」と呼ばれた行為を連想させる。デジタル大辞泉は「国見」を次のように解説している。
| 「天皇や地方の長(おさ)が高い所に登って、国の地勢、景色や人民の生活状態を望み見ること。もと春の農耕儀礼で、1年の農事を始めるにあたって農耕に適した地を探し、秋の豊穣を予祝したもの。「天の香具山登り立ち―をすれば」〈万・二〉
」。 |
用例の歌は、万葉集冒頭の第二首の舒明天皇作と伝えられている歌である。
| 大和には群山あれどとりよろふ天の香具山登り立ち国見をすれば国原は煙立ち立つ海原はかまめ立ち立つうまし国そあきづ島大和の国は |
小学館「日本古典文学全集萬葉集」は次のように訳している。
| 大和にはたくさんの山々があるが、特に頼もしい天の香具山に登り立って国見をすると、広い平野にはかまどの煙があちこちから立ち上がっている、広い水面にはかもめが盛んに飛び立っている。本当によい国だね(あきづ島)この大和の国は |
香具山から見れば、いわゆる大和が一望できると思われる。ただし藤原京は天武朝に計画され、持統朝に実現したと考えられている。⇒2008年1月 2日 (水):藤原京の造営)したがって、舒明天皇が藤原京を眺めたということではない。
|
2016.10.26日、「舒明天皇と皇統/天皇の歴史(10)」。
舒明天皇は万葉集2番歌、いわゆる国見の歌の作者として知られる。⇒2016年9月29日 (木):象徴の行為としての「国見」/天皇の歴史(8) 舒明天皇は推古天皇を継ぐ第34代天皇で、系譜は以下のようである。先代が推古天皇、次代が皇極天皇で、女性天皇に挟まれる形である。
推古天皇は、在位36年余だったが、628年4月15日に崩御した時、継嗣を定めていなかった。蘇我蝦夷は群臣にはかってその意見が田村皇子と山背大兄皇子に分かれていることを知り、田村皇子を立てて天皇にした。すなわち舒明天皇である。蝦夷が権勢を振るうための傀儡にしようとしたという説と他の有力豪族との摩擦を避けるために蘇我氏の血を引く山背大兄皇子を回避したという説がある。また近年では、欽明天皇の嫡男である敏達天皇の直系(田村皇子)と、庶子である用明天皇の直系(山背大兄皇子)による皇位継承争いとする見方もある。いずれにせよ、政治の実権は蘇我蝦夷にあったと言える。しかし、舒明天皇の皇后が次の皇極天皇であり、大化の改新を実行した孝徳天皇を挟んで斉明天皇として重祚している。百済救援のための航海中に亡くなるという対外的にも波乱の時代であった。斉明天皇下の百済救援政策が、白村江での大敗という存亡の危機をもたらした。そして「壬申の乱」という内政上の大転換に至るのである。
日本書紀の系図上、天智、天武の両天皇の父であるから、古代史におけるキーパソンということになる。万葉集の巻頭に、雄略天皇の次に舒明天皇が置かれている。編者の意図はどうことだったのだろうか?Wikipediaでは、編者について、次のように解説している。
|
万葉集の成立に関しては詳しくわかっておらず、勅撰説、橘諸兄編纂説、大伴家持編纂説など古来種々の説があるが、現在では家持編纂説が最有力である。ただ、万葉集は一人の編者によってまとめられたのではなく、巻によって編者が異なるが、家持の手によって二十巻に最終的にまとめられたとするのが妥当とされている。万葉集二十巻としてまとめられた年代や巻ごとの成立年代について明記されたものは一切ないが、内部徴証から、おおむね以下の順に増補されたと推定されている。
- 巻1の前半部分(1 -53番)…
- 原・万葉集…各天皇を「天皇」と表記。万葉集の原型ともいうべき存在。持統天皇や柿本人麻呂が関与したことが推測されている。
- 巻1の後半部分+巻2増補…2巻本万葉集
- 持統天皇を「太上天皇」、文武天皇を「大行天皇」と表記。元明天皇の在位期を現在としている。元明天皇や太安万侶が関与したことが推測されている。
- 巻3 - 巻15+巻16の一部増補…15巻本万葉集
- 契沖が万葉集は巻1 - 16で一度完成し、その後巻17 - 20が増補されたという万葉集二度撰説を唱えて以来、この問題に関しては数多くの議論がなされてきたが、巻15までしか目録が存在しない古写本(「元暦校本」「尼崎本」等)の存在や先行資料の引用の仕方、部立による分類の有無など、万葉集が巻16を境に分かれるという考え方を裏付ける史料も多い。元正天皇、市原王、大伴家持、大伴坂上郎女らが関与したことが推測されている。
- 残巻増補…20巻本万葉集
- 延暦2年(783年)頃に大伴家持の手により完成したとされている。
|
ただし、この万葉集は延暦2年以降に、すぐに公に認知されるものとはならなかった。延暦4年(785年)、家持の死後すぐに大伴継人らによる藤原種継暗殺事件があり家持も連座したためである。その意味では、万葉集という歌集の編纂事業は恩赦により家持の罪が許された延暦25年(806年)以降にようやく完成したのではないか、と推測されている。万葉集は平安中期より前の文献には登場しない。この理由については「延暦4年の事件で家持の家財が没収された。そのなかに家持の歌集があり、それを契機に本が世に出、やがて写本が書かれて有名になって、平安中期のころから万葉集が史料にみえるようになった」とする説
などがある。
|
| 【仏教導入を廻って蘇我稲目と物部尾輿の争い発生する】 |
552(欽明天皇13)年、百済の聖明王の使者が欽明天皇に金銅の釈迦如来像や経典、仏具など経論数巻を献じ、上表して仏教の功徳をたたえた。これが仏教伝来の始まりとされている。異聞として「538(欽明天皇3)年説」も有るが、欽明天皇の即位は540年であることからするとオカシナことになる。538年なのか欽明天皇3年のどちらなのかはっきりしない。
天皇は仏像を礼拝の可否を群臣に求めた。稲目は「西蕃諸国々はみなこれを礼拝しており、日本だけがこれに背くことができましょうか」と答えた。これに対して大連の物部尾輿と連の中臣鎌子は、「わが国の王は天地百八十神を祭っています。蕃神を礼拝すれば国神の怒りをまねくでしょう」と反対した。
天皇は、稲目に、仏像を授けて試みに礼拝することを許した。稲目は小墾田の私宅に安置し、向原(むくはら)の家を寺にして仏像を安置して礼拝した。この時より向原の家は日本最初の寺となった。その後、疫病が起こり、民に死する者が多く出た。尾輿と鎌子は蕃神礼拝のためだとして、仏像の廃棄を奏上し、天皇はこれを許した。仏像は難波の堀江に流され、伽藍には火をかけられた。すると、風もないのに大殿が炎上してしまった。しかし、これで仏教が完全に排除された訳ではなく、翌553(欽明天皇14)年、海中から樟木を引き上げて、天皇は仏像2体を造らせている。
稲目は財務に手腕を振るい、王辰爾を遣わして船賦を数えて記録させた。また、天皇の命により諸国に屯倉を設置している。仏教受容問題に権力闘争が重なり、蘇我氏と物部氏は激しく争った。決着はつかず、蘇我稲目と物部尾輿の争いは子の蘇我馬子、物部守屋の代へと引き継がれた。 |
561(欽明22)年、新羅からの使者が訪れている。この折、難波の庁舎で「掌客(おさむるつかさ)」として先導役を務めた人物が「額田部連」。
| 【蘇我稲目が逝去】 |
|
570年、稲目が死去した。物部氏は天皇の許可を得て稲目の寺を焼き払った。家は焼けても仏像は燃えなかったため,仕方なくこれを難波の堀江に投げ込んだ。しかし,疫病はなくならず天災も続いた。後に推古天皇はここ向原の地を宮とした。小墾田の宮に移った後は豊浦寺(とゆらじ)となった。
物部尾輿が仏像を投げ捨てた池と伝わるのが難波池。当時ここは難波の堀江とよばれていた。投げ捨てられて池に沈んでいた仏像は信濃の国から都に来て,この池の前をたまたま通りかかった本田善光(ほんだよしみつ)という人物によって発見される。長野の善光寺縁起によると,仏像は聖徳太子の祈りに一度だけ水面に現れたが再び底に沈んだままとなっていた。しかし,本田善光が池の前に来ると,金色の姿を現し,善光こそ百済の聖明王の生まれ変わりであると告げる。善光はこの仏像を背負い信濃にもどり自宅に祀った。これは善光寺の創建に関わる話である。
|
| 【敏達天皇即位】 |
| 572(敏達天皇元)年、敏達天皇が即位。物部尾輿を父、弓削氏の女阿佐姫を母とする物部守屋(もののべのもりや、?-
587)は、 大連に任じられた。蘇我馬子は敏達天皇のとき大臣に就任。馬子はこうして大臣兼外戚として権力をふるった。 |
| 【隋が中国を統一】 |
| 581年、隋(ずい)が建国され、中国の新王朝となる。後漢代の有名な官僚・楊震の裔と称する楊堅(諡「文帝」)が魏晋南北朝時代の混乱を鎮め、西晋が滅んだ後分裂していた中国をおよそ300年ぶりに再統一した。文帝の治績の最大のものとして称えられるのが、科挙(正式には貢挙)の実行である。南北朝時代では九品官人法により、官吏の任命権が貴族勢力の手に握られていた。科挙は地方豪族の世襲的任官でなく実力試験の結果によって官吏の任用を決定するという極めて開明的な手段であり、これをもって官吏任命権を皇帝の元へ取り返すことを狙った。文帝の治世をその元号を取って開皇の治と呼ぶ。文帝によって整備された諸制度はほとんどが後に唐に受け継がれ、唐274年の礎となった。都は大興城(長安、現在の中華人民共和国西安市)。国姓は楊。 |
| 【仏教導入を廻って続く蘇我と物部の抗争】 |
584(敏達天皇13)年、百済から来た鹿深臣(かふかのおみ)が弥勒菩薩(みろくぼさつ)石像一体、佐伯連が仏像一体を持っていた。それを馬子が請うてもらい受け仏殿を建ててそれを収めた。敏達(びだつ)天皇が崇仏に同意したこともあって,蘇我氏対物部氏の対立が再び激化する。
司馬達等と池邊氷田を派遣して修行者を探させたところ、播磨国で高句麗人の恵便という還俗者を見つけ出した。馬子はこれを師として、司馬達等の娘の嶋を得度させて尼とし善信尼となし、更に善信尼を導師として禅蔵尼、恵善尼を得度させた。馬子は仏法に帰依し、三人の尼を敬い、石川宅に仏殿を造って仏法を広めた。
585(敏達天皇14).2月、大臣・蘇我馬子は病になり、卜者に占わせたところ父の稲目のときに仏像が破棄された祟りであると言う。馬子は敏達天皇に奏上して仏法を祀る許可を得た。天皇はこれを許可したが、この頃から疫病が流行しだし多くの死者を出した。
3月、排仏派の物部守屋と中臣勝海(中臣氏は神祇を祭る氏族)が「蕃神を信奉したために疫病が起きた」と奏上し、敏達天皇は仏法を止めるよう詔した。守屋は寺に赴き、仏殿を破壊し、仏像を海に投げ込ませた。守屋は馬子ら仏法信者を面罵して、三人の尼を差し出すよう命じた。馬子が尼を差し出したところ、守屋は尼の衣をはぎとって縛り上げ尻を鞭打った。しかし、疫病は治まらず敏達天皇も守屋も病に伏した。人々は仏像を焼いた罪であると言い合った。
同年6月、馬子も病が癒えず奏上して仏法を祀る許可を求めた。敏達天皇は馬子ひとりのみこれを許し三尼を返した。馬子は三尼を拝し、新たに寺を造り、仏像を迎えて供養した。 |
| 【用明天皇即位】 |
同年8月、敏達天皇が崩御した。葬儀を行う殯宮で馬子と守屋は互いを罵倒しあった。馬子は佩刀して誄言(しのびごと)を奉った。守屋は「猟箭がつきたった雀鳥のようだ」と笑った。守屋が身を震わせて誄言を奉ると、馬子は「鈴をつければよく鳴るであろう」と笑った。
敏達天皇の次には馬子の推す橘豊日皇子(欽明天皇の皇子、母は馬子の姉の堅塩媛。聖徳太子の父)が即位した(用明天皇)。用明天皇は、「神道を尊び、仏法を信ず」(日本書紀)とあり、仏法を積極的に導入した。
586(用明天皇元)年、守屋は敏達天皇の異母弟・穴穂部皇子と結んだ。 穴穂部皇子は炊屋姫(敏達天皇の后)を犯そうと欲して殯宮に押し入ろうとしたが、三輪逆に阻まれた。怨んだ穴穂部皇子は守屋に命じて三輪逆を殺させた。馬子は「天下の乱は遠からず来るであろう」と嘆いた。守屋は「汝のような小臣の知る事にあらず」と答えた。
|
| 【蘇我馬子と物部守屋の公然抗争始まる】 |
| 蘇我氏は以降、用明天皇、崇峻天皇、推古天皇の4代に仕え、54年に渡り権勢を振るい、蘇我氏の全盛時代を築くことになる。用明天皇の異母弟の穴穂部皇子は皇位を欲しており、大いに不満であった。穴穂部皇子は守屋と結び、先帝の寵臣の三輪逆を殺させた。 |
| 【聖徳太子の登場】 |
| 蘇我稲目の娘堅塩媛を母とする橘豊日皇子(後の用明天皇)を父とし、欽明天皇を父とし蘇我稲目の娘小姉君を母とする穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)を母とする蘇我氏と強い血縁関係の「厩戸王」(574.2.7ー622.4.8)又は豊聡耳(とよさとみみ)、上宮王(かみつみやおう)、後の聖徳太子が政局に登場してきた。古事記では上宮之厩戸豊聡耳命と表記される。日本書紀では厩戸皇子のほかに豊耳聡聖徳、豊聡耳法大王、法主王と表記されている。聖徳太子は後世につけられた尊称である。子には山背大兄王らがいる。 |
| 【蘇我馬子派が物部守屋派を滅ぼす】 |
587(用明天皇2).4月、用明天皇は病になり、三宝(仏法)に帰依することを欲し群臣に諮った。仏教の受容を巡って排仏派の物部守屋、中臣勝海と崇仏派の蘇我馬子とが激しく対立した。守屋と中臣勝海は、「国神に背いて他神を敬うなど、聞いたことがない」と反対した。馬子は詔を奉ずべきとして、穴穂部皇子に豊国法師をつれて来させた。守屋は大いに怒ったが、群臣の多くが馬子の味方であることを知り、河内国へ退いた。
俳仏派の中臣勝海は彦人皇子と竹田皇子(馬子派の皇子)の像を作り呪詛した。しかし、やがて彦人皇子の邸へ行き帰服を誓った(自派に形勢不利と考えたとも、彦人皇子と馬子の関係が上手くいっておらず彦人皇子を擁した自派政権の確立を策したとも言われている)が、その帰路、舍人迹見赤檮に襲われた。守屋は物部八坂、大市造小坂、漆部造兄を馬子のもとへ遣わし、「群臣が我を殺そうと謀っているので、阿都へ退いた」と伝えた。
同年4.9日、用明天皇が崩御した。馬子は、敏達天皇の皇后であったトヨミケカシキヤ姫(豊御食炊屋姫、後の推古天皇)を、守屋は穴穂部皇子を推挙し両者譲らなかった為、次期天皇の擁立をめぐって戦闘状態に入った。蘇我氏と物部氏の対立は宗教対立からやがて武力衝突へと発展する。いよいよ互いの権力争いに決着をつけねばならなくなった。
6.7日、馬子は、トヨミケカシキヤ姫の詔を得て、用明天皇の皇子である14歳の廐戸皇子(うまやどのおうじ。後の聖徳太子)を味方に付け、優位に立った。
同年6月、馬子が先手を打ち、守屋が推す穴穂部皇子を誅殺した。翌日、宅部皇子を誅した。7月、馬子は群臣にはかり、守屋を滅ぼすことを決め、諸豪族、諸皇子を集めて守屋討伐の大軍を起こした。厩戸皇子もこの軍に加わった。討伐軍は河内国渋川郡の守屋の館を攻めたが、軍事氏族である物部氏の兵は精強で、稲城を築き頑強に抵抗した。討伐軍は三度撃退された。
これを見た厩戸皇子は、白膠の木を切って四天王の像をつくり、戦勝を祈願して、勝利すれば仏塔をつくり仏法の弘通に努める、と誓った。馬子の軍は奮い立って攻め立て、守屋は迹見赤檮に射殺された。更に守屋の子らも殺され、守屋軍勢は敗退した。これにより、大豪族であった物部氏は没落し、蘇我氏一族が進捗した。守屋の一族は葦原(物部氏の領地)に逃げ込んで、ある者は名を代え、ある者は行方知れずとなった。後に守屋の弟が召しだされて石上氏を名乗ることになる。 |
| 【崇峻天皇即位】 |
| 同年8月、馬子は、泊瀬部皇子を皇位につけ(崇峻天皇)、娘の炊屋姫は皇太后となった。聖徳太子にも妃を送り込み、皇室との絆を更に強いものとした。曽我氏の専横政治が始まった。 |
588(崇峻天皇元)年、馬子は善信尼らを学問をさせるため百済へ派遣した。
591(崇峻天皇4)年、崇峻天皇は馬子と諮り、任那回復のため2万の軍を筑紫へ派遣し、使者を新羅へ使わせた。
| 【崇峻天皇暗殺される】 |
|
592(崇峻天皇5).10月、天皇へ猪が献上された。崇峻天皇は猪を指して「何時か猪の首を切るように、朕が憎いと思う者を斬りたいものだ」と言った。政治の実権が馬子にあることに対して漏らした崇峻天皇の不満の言葉であった。馬子は崇峻天皇の言葉を知るや、天皇を謀殺することを決意する。
同年11月、馬子は東国から調があると偽って、東漢駒に崇峻天皇を弑させた。東漢駒は馬子の娘の河上娘を奪って妻とした。怒った馬子は東漢駒を殺させた。
|
| 【推古天皇即位】 |
|
593年、馬子は皇太后であった豊御食炊屋姫を擁立して皇位につけた(推古天皇)。史上初の女帝である。厩戸皇子(聖徳太子)は皇太子となった。
|
| 【廐戸皇子が摂政となり、仏教奨励政策を推進する】 |
|
593(推古天皇元).4.10日、厩戸皇子(聖徳太子)は摂政となり、馬子は聖徳太子と合議して政務を執り始めた。以降、仏教を奨励し、冠位十二階や十七条憲法を定めて中央集権化を推し進め、遣隋使を派遣して隋の優れた制度、学問を輸入していくことになる。
同年、太子は物部氏との戦いの際の誓願を守り、摂津国難波(現在の大阪府大阪市天王寺区)に四天王寺を建立した。物部氏の領地と奴隷は両分され、半分は馬子のものになった。馬子の妻が守屋の妹であるので物部氏の相続権があると主張したためである。半分は四天王寺へ寄進された。
|
| 【廐戸皇子が、仏教興隆の詔「三宝興隆の詔」を発す】 |
|
594(推古天皇2)年、21歳の聖徳太子が、仏教興隆の詔「三宝興隆の詔」を発し、日本各地に寺を建立した。595(推古天皇3)年、高句麗の僧彗慈が渡来し、太子の師となり、隋が官制が整った強大な国で仏法を篤く保護していることを教えられた。596(推古天皇4)年、馬子は蘇我氏の氏寺である飛鳥寺を建立した。
|
| 【遣隋使を派遣する】 |
| 600(推古天皇8)年、倭王アメのタリシヒコ、初めて遣隋使を派遣した。同年、新羅征討の軍を出し、調を貢ぐことを約束させる。
|
| 【斑鳩宮造営開始】 |
|
601(推古天皇9).2月、聖徳太子は、現在の奈良県北西部に斑鳩宮(いかるがのみや)の造営を開始する。
|
| 【新羅征討軍が派兵され失敗する】 |
|
602(推古天皇10)年、再び新羅征討の軍を起こした。同母弟の来目皇子を将軍に筑紫に2万5千の軍衆を集めたが、渡海準備中に来目皇子が死去した(新羅の刺客に暗殺されたという説がある)。後任には異母弟の当麻皇子が任命されたが、妻の死を理由に都へ引き揚げ、結局、遠征は中止となった。この新羅遠征計画は天皇の軍事力強化が狙いで、渡海遠征自体は目的ではなかったという説もある。
|
| 【聖徳太子が「冠位十二階」を制定する】 |
603(推古天皇11).12.5日、いわゆる「冠位十二階」を定めた。 氏姓制によらず才能によって人材を登用し、官位の任命を天皇が行うことにより天皇中央集権を強める目的であったとされる。冠位十二階制は、日本で初めてつくられた冠位制であり、この後の諸冠位制を経て、様々な紆余曲折を経て律令位階制へ移行していった。
12階とは、「1・大徳 (だいとく、紫)、2・小徳 (しょうとく、紫)、3・大仁 (だいにん、青)、4・小仁 (しょうにん、青)、5・大礼 (だいらい、赤)、6・小礼 (しょうらい、赤)、7・大信 (だいしん、黄)、8・小信 (しょうしん、黄)、9・大義 (だいぎ、白)、10・小義 (しょうぎ、白)、11・大智 (だいち、黒)、12・小智 (しょうち、黒)。 |
| 【聖徳太子が「十七条憲法」を制定する】 |
|
604(推古天皇12).4.3日、聖徳太子がいわゆる「十七条憲法」(「聖徳太子の憲法17条の研究」)を制定した。豪族たちに臣下としての心構えを示し、天皇に従い、仏法を敬うことを強調している。(津田左右吉などはこれを後世の偽作であるとしている)
|
| 【隋の文帝が死去し、楊広(測位後煬帝)が後継する】 |
604年、文帝は死去し、楊広が後を継ぐ(以後煬帝)。第2代煬帝時代、煬帝は質素を好んだ文帝とは対照的に派手好みで、父がやりかけていた大土木事業を大々的に推し進め、完成へと至らせた。主なものが首都・大興城の建設と大運河を大幅に延長して河北から江南へと繋がるものとした。
この時代に隋高戦争がぼっ発する。隋の大陸統一により、百済と新羅は冊封を受け髄秩序に恭順の意を表したが、脅威を感じた高句麗は隋の敵突厥と結んで隋に対抗しようとする様子を見せた。このため、隋は100万に及ぶ大軍を起こしこれを三度目にわたって攻撃したが失敗し、隋滅亡の最大原因となった。第二次高句麗遠征からの撤兵の途中に起きた楊玄感の反乱を期に、全国的に反乱が起きるようになる。煬帝自身は行幸の途中で、江都に留まり、反乱鎮圧の指揮を執ったが、もはや手の付けようのない状態に陥いる。 |
605(推古天皇13)年、完成した斑鳩宮へ移り住んだ。
| 【遣隋使が再度派遣され、小野妹子が奏上する】 |
|
607(推古天皇15)年、小野妹子、鞍作福利を遣隋使として隋に送った。国書には次のように記していた。(「隋書」卷81
列傳第46東夷*?國」)
| 「日出處天子致書日沒處天子」 |
| 「日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す」。 |
この国書は、太子が大国隋と対等の外交を目指していたことを窺わせるが、隋の皇帝煬帝をして、「無礼である、二度と取り次がせるな」と大いに不快にさせた。当時、隋は高句麗との戦争を準備しており、背後の倭国と結ぶ必要があり、翌年、隋は返礼の使者である裴世清を倭国へ送った。
|
612(推古天皇20)年、堅塩媛を欽明天皇陵に合葬する儀式を盛大にとり行った。堅塩媛は皇太夫人と尊称され、諸皇子、群臣が誅した。蘇我氏の絶大な権勢を示した。
| 【聖徳太子が「三経義疏」を制定する】 |
| 615(推古天皇23)年、太子は仏教を厚く信仰し、この年までに三経義疏を著した。 |
| 【隋滅亡】 |
| 618年、煬帝は近衛軍団により殺害される。これにより隋が滅亡する。その後は唐が中国を支配するようになる。朝鮮3国はこぞって冊封を受けた。 |
| 【聖徳太子が「国記、天皇記、臣連伴造国造百八十部併公民等本記」を官選する】 |
|
620(推古天皇28)年、聖徳太子は蘇我馬子と議して、天皇記、国記、臣連伴造国造百八十部併公民等本記などを官選した。日本書紀の推古28年の是歳条に次のように記されている。
| 「皇太子・嶋大臣共に議(はか)りて、天皇記(すめらみことのふみ)及び国記(くにつふみ)、巨連伴造国造百八十部併せて公民等の本記を録す」。 |
大和王朝御代下の初の官選史書となる。但し、645(皇極4)年の乙巳の変の際、蘇我蝦夷(蘇我馬子の後継者)の邸宅の焼き討ちで国記、天皇記が焼失したとされている。国記は燃失する前に戦火の中から出されたとの伝があるが現存していない。日本書紀の皇極4年6月条に次のように記されている。
| 「蘇我蝦夷等誅されむとして悉に天皇記・国記・珍宝を焼く。船史恵尺(ふねのふびとえさか)、即ち疾く、焼かるる国記を取りて、中大兄皇子に奉献る」。 |
2005.11.13日、奈良県にて日本書紀の記述を裏付ける蘇我入鹿の邸宅跡が発見され、今後の発掘しだいでは天皇記、国記の一部が発見される可能性があるとされている。詳細は「聖徳太子の国史編纂指令経緯考」で確認する。
|
| 【聖徳太子と蘇我氏の対立】 |
| 推古の子の竹田王子は病弱で若死すると、推古は間人王女の子(聖徳)を天皇にはしなかった。間人王女は推古の母の堅塩姫のライバルだった小姉君の子だったので敵対心があったのだろう。蘇我とは無関係の田村王子を推す。蘇我氏に否定的な日本書紀などの記述によれば、聖徳太子は、皇室の周辺に国政を天皇中心に改革せんとし、次第に蘇我氏と対立し始めた。
|
| 【聖徳太子逝去】 |
|
622(推古天皇30)年、斑鳩宮で倒れていた太子の回復を祈りながら太子の妻、膳大郎女が2.21日に没し、その後を追うようにして翌日太子は亡くなった(享年49歳)
太子は当時最大の豪族である蘇我馬子と協調して政治を行い、隋、高句麗、百済の進んだ官司制をとりいれて天皇の中央集権を強化し、新羅遠征計画を通じて天皇の軍事力を強化し、遣隋使を派遣して外交を推し進めて隋の進んだ文化、制度を輸入した。仏教の興隆につとめ、冠位12階、17条憲法。『国記』、『天皇記』の編纂を通して天皇の地位を高めるなど大きな功績をあげた。 晩年策定せしめた歴史書は「先代旧事本紀」(せんだいくじほんき)として伝えられている。それによると、ニギハヤヒの命の系統が正統であり、現在の天皇家が傍流であるかまの如くの記述となっている。
|
623(推古天皇31)年、新羅の調を催促するため馬子は境部雄摩侶を大将軍とする数万の軍を派遣した。新羅は戦わずに朝貢してきた。
| 【蘇我馬子と推古天皇の確執、馬子逝去、蝦夷が後継する】 |
624(推古天皇32)年、馬子は元は蘇我氏の本居で天皇家の領地となっていた葛城県の割譲を推古天皇に要求した。推古天皇は「自分は蘇我氏の出で、大臣は伯父だから大臣の求めはなんでも聞き入れてきたが、これだけは聞き入れられない」と拒否された。
626年、蘇我馬子が死去した。馬子の葬られた桃原墓は、奈良県明日香村島之庄の石舞台古墳のことだとする説が有力である。 また、同古墳の西数百mの位置にある島庄遺跡についても邸宅の一角だったとする説がある。馬子の後をその子の蘇我蝦夷が継ぐ。入鹿(そがのいるか、645.7.10 )は、父の大臣・蘇我蝦夷の晩年、父に代わって国政を掌理する。 |
| 【舒明天皇即位】 |
推古天皇は、死の寸前に、二人の皇子を別々に病床に呼んだ。二人とは、聖徳太子と蘇我馬子の娘の刀自古郎女(とじこのすらつめ)の間に生まれた山背大兄王と敏達天皇の孫にして舒明天皇と蘇我馬子の娘の法堤郎媛(ほてのいらつめ)の間に生まれた田村皇子であった。蘇我蝦夷は次の天皇に田村皇子を推し、境部摩理勢(馬子の弟)が山背大兄王を推し対立する。境部は蝦夷によって倒され、蝦夷は田村皇子(古人大兄皇子)を即位させることに成功する。しかし、これが山背大兄王との対立を決定的なものに発展する。
628(推古36)年、33代推古天皇が死去する。皇位継承者は田村皇子(たむらのみこ、後の舒明天皇)と山背大兄王に絞られた。この時、蘇我蝦夷が田村皇子擁立に動いた。その後の流れが山背大兄王の自刃ということになる。
629年、馬子の子・蝦夷(えみし)と孫の入鹿が、田村皇子(古人大兄皇子)を第34代天皇として即位させる(舒明天皇、在位629ー641)。入鹿は、蝦夷の屋敷を上の宮門、自分の屋敷を谷の宮門と称した。自分の子供たちを王子と呼ばせ始めた。
630年、舒明天皇が初の遣唐使送る。
631年、百済皇子の豊王章(ほうしょう)が来日。
639年、舒明天皇が初の官寺、百済大寺建設を命じる。
|
| 【皇極天皇即位】 |
|
641(舒明天皇13).10.9日、舒明天皇が死去した。
642(皇極天皇元年).1.15日、舒明天皇の後、継嗣となる皇子が定まらなかったので、敏達天皇の子・押坂彦人大兄皇子の子・茅渟王(ちぬのおおきみ)の第一皇女、母は吉備姫王(きびひめのおおきみ)の寶女王が第35代天皇として皇極天皇が即位した。推古天皇から一代おいて即位した女帝で、諱は寶女王(たからのひめみこ、たからのおおきみ)。和風諡号は天豊財重日足姫天皇(あめとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと)。
同年、舒明天皇を滑谷岡に葬る。蝦夷が息子入鹿との双墓を造る。
643年、舒明天皇を押坂陵に改葬する。
皇極天皇は、はじめ高向王と結婚して、漢皇子を産んだ。 後に舒明天皇の皇后として、中大兄皇子(のちの天智天皇)、間人皇女、大海人皇子(のちの天武天皇)を産んだ。
|
| 【蘇我蝦夷-入鹿が聖徳太子派を弾圧する】 |
聖徳太子の王子の山背大兄王が次期皇位候補として暗躍する。
643(皇極天皇2).11.1日、 蘇我入鹿が山背大兄王を攻め、数日後に王は自殺した。蝦夷(えみし)と入鹿はが邪魔になる山背大兄王ら上宮王家の人々を自殺に追い込んだとされる。次のように伝えられている。
皇極二年十一月一日、蘇我入鹿は、巨勢徳太臣(こせのとこだのおみ)と土師娑婆連(はじのさばのむらじ)を使って、斑鳩に住む山背大兄王らを襲った。山背大兄王は、馬の骨を拾って寝室に投げ置くと、隙を衝いて妃や子供たちを連れ逃げ出し、生駒山中に逃げ隠れた。斑鳩の宮に火をかけた巨勢徳太臣らは、焼け落ちた宮の灰の中に骨を見つけ、山背大兄王が死んだと確信し、軍を解き退散した。
山背大兄王らは、生駒山中に4~5日の間、潜伏していた。臣下の者が山背大兄王に、こう進言した。『今、軍を整え戦えば、勝つ事は必至です。どうか戻って戦いましょう!』。しかし山背大兄王は、彼にこう告げた。『あなたが言うように、今戦えば勝つのは必然だ。しかし私の一身の争いのため兵を挙げ、万民を煩わし苦労をかけるのはいかがなもか?後々に民衆が、私の起こした争いのために父母を失ったなどと言うのは、心苦しいのだ。戦いに勝てばそれでいいのだろうか?私の身一つ失うことで、国家の安泰が得られるのであれば、私は死ぬことなど恐れるものではない』。
ある日、生駒山中に潜伏していた山背大兄王らは見つかってしまう。入鹿はたいそう驚き、すぐに軍を挙げ、生駒山に向かわせた。その頃、山背大兄王らは山から降り、斑鳩寺(法隆寺)へと移っていた。そして臣下にこう告げた。『一身のために、無駄に百姓らを殺したくはないのだ!この身一つ、入鹿にくれてやろうではないか!』。ついに山背大兄王は、子供・兄弟ら親族、妃や妾らとともに自害し、ここに上宮王家は滅亡へと至った。 |
山背大兄王とは、一体どのような人物だったのか。山背大兄王は聖徳太子の息子であり、聖徳太子は31代用明天皇(ようめい)と穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)との間に生まれた。用明天皇の母は、蘇我蝦夷の祖父である蘇我稲目(そがのいなめ)の娘である堅塩姫(きたしひめ)であった。穴穂部間人皇女の母も、同じく稲目の娘である小姉君(こあねのきみ)であった。従って、聖徳太子は、蘇我氏と非常に強い血縁関係にあり、聖徳太子も、その息子である山背大兄王も蘇我系の皇族であったということになる。 |
| 【蘇我氏の専横】 |
|
皇極天皇のが在位中、蘇我蝦夷が大臣として重んじられ、その子・入鹿が自ら国政を執った。共に甘かしの岡に居宅を構え、蝦夷の家を「上の宮門(みかど)」、入鹿の家を「谷(はざま)の宮門」と呼び、その子女を「王子(みこ)」と呼んでいた。
|
| 【南都六宗】 |
政界のこの動きに合わせて、元興寺や興福寺を中心にして法相宗を始めとする南都六宗のいわゆる学問仏教が盛行していた。 南都六宗とは、奈良時代に平城京を中心に栄えた仏教6宗派(三論宗、法相宗、倶舎宗、成実宗、華厳宗、律宗)の総称で奈良仏教とも云う。当時からこう呼ばれていたわけではなく、平安時代以降平安京を中心に栄えた「平安二宗」(天台宗、真言宗)に対する呼び名である。
民衆の救済活動に重きをおいた平安仏教や鎌倉仏教とは異なり、これらの六宗は学派的要素が強く、仏教の教理の研究を中心に行っていた学僧衆の集まりであったといわれる。つまり、律令体制下の仏教で国家の庇護を受けて仏教の研究を行い、宗教上の実践行為は鎮護国家という理念の下で呪術的な祈祷を行う程度であったといわれる。ただし、中国に渡り玄奘から法相宗の教理を学び日本に伝えた道昭は、このような国家体制の仏教活動に飽きたらず、各地へ赴き井戸を掘ったり橋を架けるなどをして、民衆に仏教を教下する活動を行ったとされる。なお、同じく民衆への教下活動を行った行基の師匠も道昭であったといわれる。南都六宗は、宗派というよりもお互いに教義を学び合う学派のようなもので、東大寺を中心に興隆して勉強し合っていた。(「ウィキペディア南都六宗」参照)
南都六宗各派については「南都の六宗」が詳しいのでこれを参照し、暫くこれを転載させていただく(「南都六宗」)。 |
中国仏教は13の学派に分かれて生まれた。これにより学派仏教と呼ばれる。それぞれ仏教学の順序に従って学び、兼ねて学ぶことも許されていた。中国13宗とは次の通り。
| ● |
毘曇(びどん)宗 |
|
 |
成実(じょうじつ)宗 |
|
 |
律(りっ)宗 |
|
 |
三論(さんろん)宗 |
吉蔵(549年 - 623年) |
 |
涅槃(ねはん)宗 |
|
| ● |
地論(じろん)宗 |
菩提流支(508年 - 535年) |
 |
浄土(じょうど)宗 |
道綽(562年 - 645年) |
 |
禅(ぜん)宗 |
菩提達摩(? - 536年) |
| ● |
摂論(しょうろん)宗 |
真諦(499年 - 569年) |
 |
天台(てんだい)宗 |
智顗(538年 - 597年) |
 |
華厳(けごん)宗 |
杜順(557年 - 640年) |
 |
法相(ほっそう)宗 |
|
 |
真言(しんごん)宗 |
|
これらの中で、隋唐代に教団的色彩を持つに至るのは、 天台宗と 天台宗と 禅宗である。 禅宗である。 涅槃(ねはん)宗は日本では天台宗三明院門流として継続することとなった。
南都六宗(なんとろくしゅう)は、奈良時代の六つの学派仏教で次の通り。 涅槃(ねはん)宗は日本では天台宗三明院門流として継続することとなった。
南都六宗(なんとろくしゅう)は、奈良時代の六つの学派仏教で次の通り。
 |
法相(ほっそう)宗 |
唯識学派。 |
 |
三論(さんろん)宗 |
|
| ○ |
倶舎(くしゃ)宗 |
|
 |
成実(じょうじつ)宗 |
|
 |
華厳(けごん)宗 |
|
 |
律(りっ)宗 |
|
奈良時代には特定宗派のみを奉じる寺院は少なく、南都六宗も独立した宗派というよりは互いに教義を学び合う学派の役割が強く、東大寺を中心に興隆し教学を学び合った。
|
| 【中臣家の登場】 |
|
644(皇極天皇3).正月、中臣鎌子が神祇伯に任命されている。これが、中臣鎌子の初見となる。中臣鎌足は、唐突に歴史に登場している。
|
644年、蝦夷と入鹿が甘樫丘に邸宅を建設する。
644(皇極天皇3).正月、蘇我倉山田石川麻呂の次女が中大兄皇子の元に嫁ぐ。この女人が、後の持統天皇や大田皇女(おおたのひめみこ、大津皇子の母)を生む遠智娘(おちのいらつめ)となる。
| 【大化の改新(「乙巳の変」)、蘇我入鹿一族滅亡】 |
|
645(皇極4、大化元).6.12日、入鹿が、藤原鎌足と中大兄皇子(後の天智天皇)によって皇極天皇の御前で誅殺されると云う事変が発生した(「乙巳の変」)。この日は、三韓(高句麗、百済、新羅)が揃って進調すると云う重要な儀式が行われる予定となっており、馬子が参内するのを見越しての暗殺計画が実行された。蘇我倉山田石川麻呂が気脈を通じていたと云われる。
6.13日、父の蘇我蝦夷も自殺し、この間109年間権力の頂点で栄華を極めた蘇我氏本宗家は滅亡した。近年では、改革の主導権争いを巡る蘇我氏と皇族や反蘇我氏勢力との確執が暗殺のきっかけになったとする見方もある。蘇我氏が集めていた古文書は全て焼き捨てられた。
2005.11.13日、奈良県明日香村において、蘇我入鹿邸跡とみられる遺構が発掘された。
蘇我入鹿の名前は中大兄皇子(後の天智天皇)と中臣鎌足(後の藤原鎌足)によって、これまでの名前を資料とともに消され、卑しい名前として彼らが勝手に名付けたものであるという説が浮上している。
|
|
「竹田恒泰氏かく語りぬ」(投稿者:Legacy of Ashesの管理人 投稿日:2014年 6月21日)。
http://www.fujitv.co.jp/takeshi/takeshi/column/
koshitsu/koshitsu75.html
「乙巳の変」の本当の首謀者は誰か?
第35代皇極天皇の時代に起きた「乙巳(いっし)の変」は、古代における重大事件のひとつとして、必ず歴史の教科書に書かれています。乙巳の変とは、中大兄皇子(なかのおおえのみこ)と中臣鎌足(なかとみの・かまたり)が蘇我入鹿(そがの・いるか)を暗殺する事件のことです。この事件がきっかけとなり、「大化の改新」が行われます。中大兄皇子が事件の首謀者であるというのがこれまでの考え方でしたが、近年は別に首謀者がいて、中大兄皇子は実行者の一人に過ぎないという考え方が有力になりつつあります。先ずは、日本書紀に記された事件の背景と経緯を確認してみましょう。
第33代推古天皇のもとで摂政として政務を取り仕切っていた聖徳太子は、推古天皇の次に天皇に即位するものと考えられていましたが、推古天皇よりも先に命を落としてしまいます。すると、皇位継承をめぐって争いが起きました。聖徳太子の息子である山背大兄王(やましろのおおえのおう)が有力視されたことは当然ですが、聖徳太子の影響力によって力を落としていた蘇我氏がこれに反対し、結局は押坂彦人大兄皇子(おしさかひこひとおおえのみこ)の子、田村皇子(たむらのみこ)を天皇に擁立しました。第34代舒明天皇です。舒明天皇が崩御すると、またしても皇位をめぐって紛議が起きました。このとき、再び聖徳太子の子、山背大兄王に即位の可能性がありましたが、蘇我氏がまた妨害し、舒明天皇の皇后が即位し、推古天皇についで二番目の女帝、第35代皇極天皇が成立したのです。舒明天皇、皇極天皇と蘇我氏の思うままの天皇が成立し、蘇我氏の権力はいよいよ強いものとなり、蘇我蝦夷(そがの・えみし)が蘇我入鹿に大臣の位を譲ると、入鹿は山背大兄王の住む斑鳩宮(いかるがのみや)を襲撃して、殺害します。山背大兄王が暗殺されたことで、聖徳太子家は親子二代にして滅びてしまいました。そして、運命の皇極四年(六四五)六月十二日。この日は飛鳥板蓋宮(あすかいたぶきのみや)で高句麗・百済・新羅の使者を迎えて三韓が大和朝廷に忠誠を誓う儀式が行われることになっていました。日本書紀に記されたこの時の事件はあまりに有名です。皇極天皇の子である中大兄皇子は中臣鎌足とともに、儀式の最中に蘇我入鹿に斬りかかる計画を立てていました。儀式が始まり、皇極天皇の前で上表文が読み上げられると、中大兄皇子は入鹿の頭と肩を斬りつけました。血まみれになった入鹿は、皇極天皇の御座にすがり、「まさに日嗣(ひつぎ)の位にましますべきは、天子(あめのみこ)なり。臣(やっこ)、罪を知らず」と、自らの無実を訴えたと日本書紀は記します。そして、中大兄皇子は天皇に、入鹿が皇位を狙っていたことを述べました。驚いた天皇は黙って奥へ入っていき、入鹿にはとどめが刺されたのです。入鹿が息も絶え絶えに訴えた無実の主張は、中大兄皇子の次の発言を予期していなければ発することができないはずですし、血まみれになりながらこれだけ長いセリフを述べたとは到底思えないので、これは後世の創作と考えられます。実際は「うー」といいながらうずくまったのではないでしょうか。天皇の息子が、外交的な儀式の途中、天皇の前で、白昼堂々と大臣を殺すわけですから、これは一種のテロであり、大変なことです。現在に置き換えれば、国賓を招いた宮中晩餐会で、天皇陛下の前で、皇太子殿下が内閣総理大臣を殺害するようなものです。そして、入鹿が殺害された翌日には、入鹿の父親の蝦夷も自害に追い込まれ、以降、蘇我氏は完全に没落することになります。さらにその翌日には、皇極天皇が、日本史上初となる生前譲位をおこなって、第36代孝徳天皇が即位しました。
これまで、「乙巳の変」の首謀者は中大兄皇子とされてきましたが、それについては次のような反論があります。先ず、当時は若年で天皇に即位した例はなく、二十歳の中大兄皇子が即位できる可能性はありませんでした。したがって、この時点で中大兄皇子が自ら入鹿を殺害する動機がはっきりしません。また、もし殺害後に中大兄皇子が速やかに即位すると、天皇になるために入鹿を殺害したと周囲からいわれることになりますから、その動機もなかったと考えなくてはならないでしょう。すると、中大兄皇子と中臣鎌足は事件の実行者であるも、二人とは別に事件の首謀者がいると考えることは自然なことです。乙巳の変の首謀者は、入鹿が殺害されることにより、もっとも利益を得た人物、孝徳天皇ではないかと考えられています。次の第37代斉明(さいめい)天皇の後、中大兄皇子は即位して第38代天智(てんじ)天皇となりました。
天皇になるにはhttp://www.fujitv.co.jp/takeshi/takeshi/column/koshitsu/
koshitsu68.html
天皇の即位儀礼
国家公務員試験に合格すれば、誰でも国家公務員になることができます。また会社の取締役会で代表取締役に選任されれば、誰でも社長になることができます。そして、国会の首班指名を受けて天皇に任命されれば、誰でも内閣総理大臣になることができます。しかし、天皇は試験に合格したり、誰かが決議したり、誰かが任命したりしてなるものではありません。天皇になることを即位といいます。即位の時期は時代とともに変化してきました。古くは天皇の崩御(ほうぎょ)(天皇が亡くなること)によってのみ皇位の継承がおこなわれましたが、六四五年に皇極天皇が生前譲位(せいぜん・じょうい)(生前に天皇の位を譲ること)をしてからは、譲位の道が開かれ、以降多くの例を数えます。しかし、明治天皇から現在まで、譲位の例はありません。明治時代に成立した皇室典範は、皇位継承は天皇の崩御によってのみ行われることを規定し、以降、譲位による皇位継承は行われなくなりました。昭和二十二年に皇室典範は廃止され、新たな皇室典範が制定されましたが、皇位継承の時期については旧法を引き継いでいます。
また、即位の方法も時代とともに変化しています。ただ、天皇が天皇になるためには、特別な儀式をいくつも経なければいけないことに変わりはありません。天皇になることを、古い言葉で「践祚(せんそ)」といいます。践祚とは、「皇位を践(ふ)む」ことで、具体的には天皇が天皇であることの証「三種の神器」を継承することがその趣旨です。(三種の神器については、第7回「皇位のしるし・三種の神器」、第15回「神器各論①八咫鏡」、第18回「神器各論②草薙剣」、第22回「神器各論③八坂瓊曲玉」参照) 古くは践祚をもって天皇に即位したことになっていましたが、桓武天皇以降は、践祚の儀の後に、日を隔てて即位の儀を行うようになり、現在に至ります。践祚の儀が神器の継承でしたが、即位の儀は、天皇に即位したことを広く内外に示すことを趣旨とします。践祚の儀と即位の儀を済ませると、一応形上は天皇に即位したことになりますが、実はまだこの段階では、本当の天皇ではありません。本当の天皇になるには、もうひとつ絶対に避けて通れない重要な儀式があります。それが「大嘗祭(だいじょうさい)」です。
江戸期までは旧暦十一月の二回目の卯(う)の日、明治以降は新暦の十一月二十三日に毎年、新嘗祭(にいなめさい)という宮中祭祀が行われていますが、天皇に即位して最初に行われる新嘗祭を、特に「大嘗祭」と呼び、通常の新嘗祭とは区別しています。大嘗祭は天皇一代につき一回限りの祭りです。この大嘗祭を行うことで、天皇の体に天皇霊が宿ると考えられています。それによって天皇が天皇になるわけです。そして、その天皇霊とは、有力説によれば、天照大御神の孫で、天孫降臨した邇邇芸命(ににぎのみこと)の御霊(みたま)であるとされています。ですから、歴代の天皇には、同じ御霊が宿っていることになります。(邇邇芸命については、第47回「天孫降臨(古事記、第十四話)」参照) 大嘗祭は、大嘗祭のために建てられた悠紀殿(ゆきでん)と主基殿(すきでん)という建物の中で行われます。それぞれ皇祖の天照大御神をお迎えする神座に御膳をお供えし、五穀豊穣を感謝し、国家と国民の安寧を祈念するお告文(つげぶみ)を天皇が読み上げ、天皇が神と共に御膳を食する直会(なおらい)をすることにより、天皇が神と一体になると考えられています。したがって、三種の神器を継承する践祚の儀を行った段階で形式的に即位したことになり、次に即位の儀を行った段階で、社会的な意味における天皇が成立し、そして最後に天皇の体に天皇霊を宿らせる大嘗祭を行って、宗教的な意味における天皇、つまり本質的な天皇が成立するのです。践祚の儀、即位の儀、大嘗祭の三つの儀式を通じて、段階的に天皇の即位が成立することになります。
ところで、今上天皇は、昭和六十四年一月七日に昭和天皇が崩御あそばした日に、践祚の儀に当たる「剣璽等継承の儀」(けんじとう・けいしょうのぎ)を済ませられ、践祚あそばしました。そして、一年間は昭和天皇の喪(も)に服され、その喪が明けた平成二年十一月十二日に即位の儀に当たる「即位の礼」で、天皇に即位されたことを広く示され、そして同年十一月二十二日夕方から二十三日未明にかけて大嘗祭を済ませられました。 |
|
| 【孝徳天皇即位】 |
| 645(大化元).6.14日、皇極天皇は、目の前の入鹿誅殺のショックから皇位を譲り、弟の軽皇子(かるのみこ)が即位した(孝徳天皇、在位645-654)。皇極天皇には皇祖母尊の称号が奉られた。皇太子に中大兄皇子が就き、左大臣に安倍内麻呂が、右大臣に蘇我倉山田石川麻呂。中臣鎌足は内大臣。実験は、ミン法師、高向玄理(たかむくのげんり)が国博士。都を難波に遷し、律令制の導入に向かうことになる。
|
同年、孝徳天皇は、仏法興隆の詔を下し、十師(後の内供奉十禅師)を置き、衆僧を教導して仏法を修行せしめられた。
| 【古人大兄皇子粛清】 |
|
蘇我入鹿が皇極天皇の後継にとしていた古人大兄皇子は皇位継承の意志がないことを伝え吉野で出家する。同年9月、蘇我氏の血を引いている古人大兄皇子が謀反を謀ったとして密告され、中大兄皇子は、吉野に逼塞していた古人大兄皇子を討った。古人大兄皇子は、蘇我本宗家が擁立せんとしていた皇子であり、その皇子が消されたことになる。
|
同年12月、孝徳天皇が朝廷の都を難波長柄(ながらの)豊崎に遷都する。
646(大化2).正月、いわゆる「改新の詔(みことのり)」が発布される。
646(大化2).3月、皇太子の中大兄皇子が、使いを立てて天皇に奏請。
|
「昔の天皇の御世は天皇と人民が一体となるように治められていましたが、現在では天皇と人民が離れてしまって、天皇のご意志によって政治が行われていません云々」。
|
| 【惟神(かむながら)の道】 |
|
647(大化3)年、4月、孝徳天皇の詔(日本書紀巻第25)。
| 「惟神(かむながら)も我が子(みこ)治(し)らさむと故(こと)寄させき。是を以って、天地(あめつち)の初(はじめ)より、君(きみ)臨(しら)す国なり」。 |
|
| 【7色13階の冠制が敷かれる】 |
|
647(大化3)年、7色13階の冠制が敷かれる(「冠位十三階制」)。これに反対する左右大臣を殺し、翌年冠位19階を制定し、新左右大臣を立てた。左大臣の安倍内麻呂は暗殺され、右大臣の蘇我倉山田石川麻呂は、兄弟の蘇我の日向によって殺された。
649(大化5)年、冠位十九階に改められている(冠位十九階は、冠位十三階を基本とし、中間の冠位を細かく分けた)。
|
同4年、学問僧を三韓に遣わした。
| 【蘇我倉山田石川麻呂失脚事件】 |
|
649(大化5)年、異母弟の蘇我臣日向に蘇我倉山田石川麻呂が謀反を起こそうとしていると密告され、孝徳帝は糾問の使いを送る。「私自身が帝に直接弁明する」と答えるのみだったため、同3.24日、追討の軍勢が差し向けられる。石川麻呂は長男・興志と共に山田寺に籠もり、最期まで自らの潔白を帝に表明する機会を探っていたが叶わず「三の男、一の女」と共に自害した。「山田大臣の謀反」に連座して23人が処刑された。この事件は中大兄皇子と中臣鎌足の陰謀であったとされている。
|
中大兄皇子の妃となった娘遠智娘は、大田皇女(伊勢斎宮となった大来皇女、大津皇子の母)、鸕野讚良皇女(後の持統天皇)、建皇子(夭逝)を、またもう一人の姪娘は御名部皇女(御名部内親王。高市皇子妃。長屋王の母)と阿閇皇女(後の元明天皇。草壁皇子妃)を産んでいる。
649(大化5).3.17日、左大臣・安倍大臣が逝去する。同3.24日、蘇我臣日向(ひむか)(身刺)が、皇太子の中大兄皇子に、「異母兄の蘇我倉山田石川麻呂の謀叛の動き」を讒言する。石川麻呂は、一族もろとも自殺する。
653(白雉4)年、道厳、道昭以下多数の学問僧を遣唐使に附して唐に遣わした。廃仏を唱えた中臣氏が仏教に帰依し、鎌足は山階陶原の家に精舎を建てて維摩会を始めたので、宮中においても無量寿経などの講経や御斎会、仁王般若会などの法会が行われ、仏教は次第に朝野に信仰されていった。
|
| 653(白雉4)年、孝徳天皇の御世、皇太子中大兄が難波より倭京に遷ることを奏して許されなかった。中大兄皇子と孝徳天皇の間に溝ができていく。中大兄皇子は、皇祖母尊(前天皇皇極)、妹の間人(はしひと)皇后、弟の大海人皇子らと飛鳥河辺行宮に移ったとき、これに同行する。この時の日本書紀の記事には「皇弟」とある。中大兄皇子を始め全ての皇族が、難波の皇居に住む孝徳天皇の意志に逆らって皇后、大和の飛鳥河辺行宮に移ったことになる。
孝徳天皇は難波に一人残され寂しく暮らすうちに,皇位を捨てて山背の山崎(京都府乙訓郡大山崎町)に移り住むことを考えるようになる。「鉗着け 吾が飼う駒は 引出せず 吾が飼う駒を 人見るつらむか」(逃げないようにと首に鉗を付けて飼っていた駒を誰が引き出して見たのか)と詠っている。
|
| 奈良県高市郡明日香村に飛鳥稲淵宮殿跡、石舞台古墳がある。稲淵の本宮殿跡については、書紀孝徳天皇の653年、中大兄皇子が難波宮から飛鳥宮に戻られ一期間を過ごされた飛鳥川辺行宮に比定する説がある。祝戸の駐車場建設予定地となったことで発掘調査が実施され、計画された建築遺構で南北約170m、東西約60mの広さであることが分かっている。同村島庄にある石舞台古墳は、現在は明日香を代表する史蹟のひとつとして知られるようになっている。書紀推古天皇の626年の条に「大臣薨せぬ。仍りて桃原墓に葬る」とあり、この大臣が蘇我馬子を示しているとされ、有力な被葬者候補となっている。 |
| 【孝徳天皇崩御】 |
654(白雉5).難波の都で孝徳天皇は病になる。この知らせを聞いて中大兄皇子や皇極天皇,大海人皇子,間人皇女らは見舞いに出かけている。しかし,10.10日、孝徳天皇が崩御した。有間皇子はこのとき15歳。孝徳天皇がいなくなり,子の有間皇子は次の天皇の候補者として表に出されるようになる。
天皇の不豫に際し、皇太子と共に難波に赴く。この年か翌年、長男高市が生れる。
|
太子町磯長谷の治定三陵は推古天皇磯長山田陵(山田高塚古墳)、用明天皇河内磯長原陵(春日向山古墳)、孝徳天皇大阪磯長陵(山田上ノ山古墳)。
推古天皇磯長山田陵(山田高塚古墳)は東西59mx南北55mの三段築成方墳で二基の横穴式石室の存在が推定されている。同陵には推古天皇と共に敏達天皇と推古天皇との皇子である竹田皇子が合葬されているとされている。すぐ東側にある二子塚古墳を推古天皇の真陵とする説もある。古事記では大野岡上から科長大陵への改葬の記述があり、改葬前の大野岡上について橿原市の植山古墳を比定する説がある。
用明天皇河内磯長原陵(春日向山古墳)は一辺約60mの方墳で、書紀によれば崩御後の七月に磐余池上陵に葬られた後、推古天皇元年九月に河内磯長陵に改葬されたと記されている。用明天皇は蘇我堅塩媛を母とする推古天皇の同母兄で、その皇統は続くことなく聖徳太子から山背大兄皇子で途絶え、押坂彦人大兄皇子を経て舒明天皇に移り、敏達天皇の皇統に復している。
孝徳天皇大阪磯長陵(山田上ノ山古墳)は竹内街道沿いにある径32mの円墳。孝徳天皇は茅渟王の御子で皇極天皇の同母弟で、乙巳の変の後に本来の皇統である中大兄皇子が皇極天皇からの譲位を辞去したため、皇極天皇の譲位を受け即位されている。孝徳天皇の御代に半島の三韓からしばしば使者が訪れている。北方の蝦夷対しては越に渟足、磐舟の二柵を築いて防備されており、これが史料に見える城柵と柵戸の初めになる。
|
| 【斉明天皇即位】 |
| 655(斉明天皇元).1.3日、皇極天皇が飛鳥板蓋宮で斉明天皇として最即位した。これを「重祚」と云う。政治の実権は皇太子の中大兄皇子が執った。冬
- 飛鳥板蓋宮が火災にあったため、飛鳥川原宮に遷った。後、飛鳥の岡本に後飛鳥岡本宮を造りそこに遷った。岡本宮が火災に遭い、吉野宮を作った。 |
同年5月の条。「大空に竜に乗った者がいた。姿は唐人に似ていて、青い笠をかぶり、葛城山から生駒山に飛び、身を隠した。牛の刻になって、住吉から西に向かって飛び去った」。
657年9月,日本書紀が、18歳の有間皇子が狂人のふりをしたと示している。皇子はその治療のため紀伊の牟婁(むろ)の湯にでかけた。都に戻った有間皇子は斉明天皇に「その場所を見ただけで病気が治る」と牟婁(むろ)の湯(和歌山県西牟婁郡白浜町湯崎温泉)のことを報告した。この言葉を聞いた天皇は大変喜んでいる。
658(斉明天皇4).7月、 僧の智通と智達が勅をうけて新羅の船に乗って大唐国に行き、玄奘法師から無性衆生義(法相宗)を受けた。10月,斉明天皇は有間の皇子の薦めにより、中大兄皇子らとともに牟婁(むろ)の温湯に船を使って行幸した。5か月前に中大兄皇子の子の建王(たけるのおう)が8歳で亡くなっているが,言葉が話せなかった皇子で斉明天皇はたいそうかわいがっていた。この行幸は悲しみをいやす旅でもあった。旅の途中,この孫のことを歌に詠んだ。「水門(みなと)の 潮(うしお)のくだり 海くだり 後も暗(くれ)に 置きてか行かむ」。(斉明天皇と建王は越智崗上陵(おちのおかのえのみささぎ)奈良県高市郡高取町に合葬されている)
| 【有間皇子粛清事件】 |
658(斉明天皇4)年、11月のある日(3日か)、天皇らが飛鳥を離れている時、都に残って留守役を勤めていた蘇我馬子の孫の蘇我赤兄(あかえ)は有間皇子の市経(いちふ-奈良県生駒町)の家を訪ねた。赤兄は有間皇子に天皇の3つの失政を語った。1、天皇が大きな倉庫に人々の財を集めている。2、大がかりな土木工事を行い,長い用水路造りを行っている。(「狂心の渠(たぶれごころのみぞ)」とよばれていた)。3、船で石を運んで丘を築き,人々を苦しめている。これを聞いた有間皇子は赤兄が自分に好意を持っているといたく喜び,「我が生涯で初めて兵を用いるべき時がきた」と言った。
2日後(11月5日か),今度は有間皇子が赤兄の家を訪ね,謀反の相談をしていると有間皇子の脇息(きょうそく-座ったとき体をもたせかけるためのひじかけ)が壊れてしまう。これは不吉なことと知り,謀反の相談を中止し,この話はなかったこととして互いに秘密を厳守することを誓って帰った。有間皇子が帰った後,赤兄は物部朴井連鮪(もののべのえのいのむらじしび)に命じて都の工事の人夫を率いて有間皇子の家を取り囲ませた。
11.5日、 蘇我赤兄が有間皇子の謀反を通報し、有間皇子は就寝中であったが起こされ,守君大岩(もりのきみおおいわ)ら4人とともに捕らわれた。このことは牟婁の温湯にいる天皇に早馬で知らせた。有間皇子は赤兄の裏切りによるものだと知ったが,赤兄は中大兄皇子を助ける重臣の一人であり,自分とともに謀反を起こすはずがないと気づくのに遅れた。赤兄の家を訪ねたことは事実であり,どう弁明しても逃れられないと悟った有間皇子は,抵抗せず,天皇のいる牟婁の温湯へと送られていった。護送の途中,磐代(いわしろ-和歌山県南部町)で休息中に次の歌を詠んだといわれている。「磐代の浜松が枝を引き結び 真幸(まさき)くあらばまた還り見む」(磐代の松の枝を結んだ 幸いにも無事に帰ることができたらまたこれを見よう)。11月9日夕刻,中大兄皇子が捕らわれて護送されてきた有間皇子に「なぜ謀反を企てたのか」と問うと,有間皇子は「天と赤兄と知る。私は全く知らない。」とだけ答えた。2日後の11月11日,有間皇子は藤白坂にて処刑された。まだ19歳の若さであった。供の4人の内2人の塩屋・魚と新田部米麻呂が斬り殺され,残りは流罪となった。 |
659(斉明天皇5).3月、 阿倍比羅夫に蝦夷国を討たせた。阿倍は一つの場所に飽田・渟代二郡の蝦夷241人とその虜31人、津軽郡の蝦夷112人とその虜4人、胆振[金且]の蝦夷20人を集めて饗応し禄を与えた。後方羊蹄に郡領を置いた。粛慎と戦って帰り、虜49名を献じた。
659年、中臣鎌足の息子として藤原不比等が誕生する。
660(斉明天皇6).3月、 阿倍比羅夫に粛慎を討たせた。比羅夫は、大河のほとりで粛慎に攻められた渡島の蝦夷に助けを求められた。比羅夫は粛慎を幣賄弁島まで追って彼らと戦い、破った。
660年、百済滅ぶ。王族は日本へ。
日本書紀によれば、しばしば工事を起こすことを好んだため、労役の重さを見た人々が批判した。
対外的には、朝鮮半島の諸国と使者を交換し、唐にも使者を遣わした。蝦夷に対し、三度にわたって阿倍比羅夫を海路の遠征に送った。
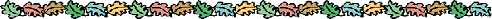



 (私論.私見)
(私論.私見)
