
| 日本神道の歴史2、神道のその後の歩みについて |

(最新見直し2015.12.17日)
| 【「古代天皇制時代の日本神道信仰」について】 |
| 神道は元々我が国古来の当時の世界認識の仕方であると同時に共同体を維持し、部族を束ね治める政道の手法でもあった。氏神信仰の下での祭政一致を特徴としている。ここでは、その後の神道の歩みを見て行くことにする。中国史書に「元百余国」と記されている日本歴史はやがて部族の群雄割拠時代から統一国家形成に向かう。この時、各地の豪族別信仰が維持されながら且つ統一王朝的な諸機構をも生み出して行くこととなった。ここに日本史の特徴が認められる。統一王朝の最初が出雲王朝と思われる。留意すべきは出雲王朝御世の王権は絶対主義的圧制のものではなく、各地の豪族との合議的な政体であったことである。年に一度、諸神が出雲の地に参り祭政一致政治を行っていたと伝えられている通りのものである。この折の、宗教的祭祀、合議的政治、神楽、お国自慢こそ日本政治の原形として今に伝わっている。この御世に於いては、神道が政治に溶け込み渾然一体となっていたと思われる節がある。これ以降の神道は、時代の最高権力者となった出雲王朝王の王権を最高祭祀者とする祭政一致に組み込まれて具現することとなる。この時代の神道を「惟神の道」と云う。後の神道と区別する意味で古神道と命名しておく。古神道の概要については、「日本神道の歴史1、発生史及び教理について」、「日本神道の歴史2、出雲神道、出雲大社考」で確認している。 2010.09.30日、2013.11.29日書き換え れんだいこ拝 |
| 【古代史最大政変の「国譲り政変」について】 | |
| この御代の晩節に古代史の最大政変が絡んでいるように思われる。いわゆる「国譲り政変」である。記紀神話の重要なメッセージは次の箇所にあるように思われる。その頃までの国土を支配していた出雲王朝系の諸神を国津神と云う。この国津神系出雲王朝に対して、外航族が渡来して王権簒奪を画策する。この時、外航族は、出雲王朝系神道が聖域的な最高神として崇めていた高天原の天照大神を僭称し、出雲王朝系の諸国津神に服従を説いて回った形跡が認められる。こうして、渡来族は、天照大神の権威をもって出雲王朝に服従を説き、局地戦を交えつつ次第に平定していった。これにより渡来族は、天津神系と称すことになる。しかしながら、古神道の時点で高天原の天照大神信仰が確立されており、渡来族を天津神系と称すことは剽窃でしかないが、その後の歴史はこれを是として行く展開を見せることになる。ここが留意を要するところであり、この視点を確立しないと古代史の錯綜が解けない。 天津神系天照王朝僭称の渡来系の王権簒奪劇が国譲り史である。その概要は出雲王朝史の国譲り譚に記す。この政変で重要なことは出雲王朝は滅びたが、滅び尽されたのではなく、生き延びたということである。これが次のように伝えられている。
興味深いことは、「国譲り政変」の特徴は、西欧史のユダヤ対反ユダヤの抗争史の如く天津神系が国津神系を戦争一辺倒により征服し、勝者側が敗者側を所払いしたのではなく、結果的に「大和」式に和睦手打ちしたことにある。こうして、国譲り政変後、天津神系天照王朝僭称の渡来系がいよいよ日本の地に大挙して踏破してくることになった。これを天孫降臨と云う。九州の高千穂の峰に降り下ったと伝説されている。渡来族は各地の国津神を平定しながら、機が熟したと見るや邪馬台国の地であった大和の東征に向かう。これが神武天皇東征譚となっている。こうして、新たな支配者として神武王朝時代が始まる。が、神武王朝は政権上の支配権を握り、各地の国津神系諸神を組み敷いたものの常に政体が安穏ではなかった。ここに崇神王朝が登場し、有力な国津神を取り込み協和する新政体に転ずることにより世にも珍しい旧王朝と新王朝の妥協権力としての大和王朝を生み出して行くことになった。ここに日本式政治の型の特質が定まり、このDNAがその後の日本政治史を貫いていくことになったと思われる。 このことが、日本神道のその後の変容に大きく関係している。「国譲り政変」にも拘わらず、国津神系世界に連綿と形成発展されてきていた古神道はそのまま生き残り、やがて天津神系神道が確立されるに及び摺り合わせされていくことになった。以下、その歴史を見て行くことにする。 2010.09.30日、2013.11.29日書き換え れんだいこ拝 |
| 【「仏教伝来」について】 |
| 丁度有史の頃になるが、天津神系天皇の時代になって、在地の日本神道に抗する形で、主に仏教や儒教を代表とする外国宗教が移入されてくることになった。専ら天津神系が外国宗教を持ち込んだ形跡があり、このことは天津神系の出自の外来性を窺わせるものとなっている。このことは、天津神系神道が、国津神系神道に対して、神道教義では征服できなかった、ということを意味しているようにも思える。それほどに、古神道は侮り難いものがあったのではなかろうか。神道はこの時も応法化しつつ生き延びて行く。仏教、儒教という外来信仰が鳴り物入りで移入されたものの、古神道は見事な対応能力を見せたことになる。「無教祖・無教義・無戒律・無偶像」の古神道の生命力は強かったということになろう。 神道という言葉そのものは、用明天皇の在世した6世紀の頃に使われ始め、その後定着していったようである。それ以前には、「神教、古道、本教」などと表現されることもあった。なぜこの頃において、在来の信仰を、格別に神道と表現せねばならなかったのか。日本書紀の第31代用明紀に「天皇仏法を信じ、神道を尊ぶ」とありこれが初出となる。この頃、天皇の仏教信仰化が為されることにより初めて神道が対自化されていったということであろう。興味深いことは、最初期に於いては「仏法、神道が並列化」されていたのが、孝徳紀に「天皇仏法を尊び、神道を軽んず」とあるように、次第に仏教を主教とするように変遷していったことである。 数百年の年月を掛けて、仏教が次第に第一国家宗教の座へと登壇化していったことが判明する。以降、代々の天皇の仏法帰依が常態化し始め、古代日本型祭政一致に仏教又は儒教が組み入れられていくことになった。かくて、仏教、儒教に対する日本古来の信仰を分別する必要が生じ、それまでの祭政一致政治手法を神道として識別するようになったものと看做される。 |
| 【「日本神道と仏教の確執と折り合い」について】 |
| 仏教が遂に国立祭壇化される時代に入った。しかし、仏教の伝来から日本型統治システムである祭政一致への登壇の背景には、重大な政争が絡んでいた。専ら豪族蘇我氏がこの政策を推進したが、最後の決戦の舞台がやってきた。土着的国津神系の代表的豪族として影響力を温存していた物部氏が、渡来豪族系の蘇我氏らの仏教化政策に立ちはだかった。物部氏は、「まさに今改めて蕃神を拝みたまはば、恐らくは国神の怒りを致したまはむ」(欽明紀)、とか、「何ぞ国神に背きて他神を敬びむ」(用明紀)と述べ、頑強に抵抗したことが日本書紀に記されている。 587年、用明天皇が崩御すると、遂に蘇我馬子と物部守屋との間に武力衝突が起る。この政争で守屋側が破れたことにより、物部氏の没落と共に古神道の衰退が決定的となった。これより以後、神道は歴史の表舞台からは遠ざけられ、替わって仏教が権力統治政道の第一道具として利用されて行くことになった。 蘇我氏と物部氏の戦いにおいて、蘇我氏側の聖徳太子の果たした役割には大きなものがある。聖徳太子は、対物部戦で戦いに勝利すれば寺院を建てると四天王に誓願を立て、勝利したことにより難波に日本最古の官寺として四天王寺(大阪市天王寺区)を建立した。引き続いて法隆寺を建立する等仏教保護政策を推進した。 604年、聖徳太子は、十七条憲法を制定し、「和の精神」を鼓吹しつつ天皇を中心とする中央集権体制の確立を目指した。更に、それまでの神仏並行から仏主神従の神仏習合の時代へと転換させていった。 645年、大化改新が発生し、中大兄皇子・鎌足公らが飛鳥板蓋宮にて蘇我入鹿を誅殺、蘇我蝦夷は自殺。皇極天皇が軽皇子に譲位し孝徳天皇が誕生した。 |
| 【その後の神道の変遷について】 |
| この間、出雲系神話に代表される古神道及び神社は消滅したのではない。それは地下に潜っていった。この流れで修験道が生み出された。 天皇家神道は、仏教と並存しながら存続していく事になった。この時点で、神道は祀り神道と教理神道に分岐し、それぞれが生き延びていくことになった。祀り神道は、皇室祭祀、神宮・大社祭祀、神社祭祀、民俗祭祀に分かれて行った。教理神道は仏教、儒教、陰陽道、道教と複雑に絡みながら、独立神道系と混合神道系に分岐しつつ変遷していく事になる。 |
| 【「役行者修験道」について】 |
| 修験道は,日本古来の縄文神道、出雲神道を濃厚に受け継いだ山岳信仰にシャーマニズム、仏教、神道、道教、陰陽道などが結びついたものと考えられる。この道を切り開いたのが葛城山の役小角(役行者)であり、以降、修験者は全国各地の霊山をご神体として、山岳修行で体得した験力を用いて呪術宗教的活動を行い、古神道を伝えていくことになった。 大峰の金峰山、熊野、日光、白山、富士、木曽御岳、伯耆大山、石槌山、彦山、出羽の羽黒山等々各地に修験道が成立した。 |
| 【「壬申の乱」について】 |
| 672年、天智天皇が没すると大友皇子が跡を受け継いで即位(弘文天皇)した。これに対して、大海人皇子が物部、海部(あまべ)、尾張というかっての出雲王朝系の一族の支援を受けて勝利し、翌673年、天武天皇として即位するという壬申の乱(じんしんのらん)が発生している。天武天皇は天智系から王朝を奪った天皇であると考えられる。 これらの背景には常に天津神系と国津神系の内部対立があった。かっての「大和」式の手打ちが遠因していたとも考えられる。天智天皇と天武天皇の御世の間の政変もこれに起因しているように思われる。 天武天皇没後、天智天皇の娘にして天武天皇の妃の菟野讃良皇女 (うののさららのひめみこ)が即位し持統天皇となり、出雲、物部の本拠地である石上神宮の宮司の祖先の系図を没収するという事件が起っている。このことは何を意味しているのか。 日本書紀は、天武天皇の下命によって編纂を始めたが、天武天皇が存命中には完成せず、その後の持統天皇と藤原不比等によって完成された。ここにも、天津神系と国津神系の内部対立が窺える。日本書紀は、天智朝の意図が働いた正書であるとする背景がここにある。古事記、日本書紀は、その編纂を通じて各地の国津神系の土俗的信仰や神話を天津神系の立場に添って整備し直して行った。ここに記紀編纂の眼目があったと思われる。 大和朝廷は、律令制にもとづく国家組織整備していった。この過程で、神祇(じんぎ)制度が制定され、国家祭祀が体系化されていった。中央には神祇官が置かれ、国家の祭祀を統轄した。神々は、大八島国(おおやしまぐに)の生成、日神天照大神(あまてらすおおみかみ)の誕生、その子孫ニニギノミコトの国土への降臨という王権神話を軸とする国家神話の中に組み込まれた。それと歩を一つにして皇祖神天照大神をまつる伊勢神宮が整備された。国々の主要な神社は官社に列せられて毎年朝廷より幣帛(へいはく)が奉られ、国家祭祀の中に位置づけられていくことになった。 |
| 【「神仏習合」について】 |
| 8世紀初頭、仏教界に大変革の波が押し寄せこれに神道が絡んでいくことになる。この時期、最澄の開いた天台宗、空海の開いた真言宗が勃興するが、共に仏教を鎮護国家の国家宗教として体系化していった。 724年、聖武天皇(文武天皇の長男)が即位し、741年、各国に国分寺(こくぶんじ)、国分尼寺(こくぶんにじ)を建設する。752年、奈良の大仏が完成する。その後、仏教はますます隆盛した。なお、諸国の神社に付属する寺院を設け、そこに僧侶を置き「神官寺」としていった。伊勢神宮の大神宮寺を始め、次々に建立された。有力な神社(御祭神)に朝廷から神階が与えられたのもこの頃からのことである。 奈良時代に始まる神仏習合は神道信仰に大きな影響を及ぼした。神は仏法を守護し仏法による救いを願っているとの「仏神一体」的観念のもとに、神社への神宮寺の設置や神前読経が行われるようになる。この神仏習合の先駆者となったのが八幡神である。大仏建立を支援するとの託宣を下して中央に登場した宇佐の八幡神は早くから仏教と習合し、平安初期には八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)と称された。これは、仏教側からの神道に対する攻勢的事象であると考えられる。 860(貞観2)年、山城の石清水(いわしみず)八幡宮に勧請されてからは祭神が応神天皇とされ、伊勢神宮につぐ第2の宗廟として朝廷より重んじられた。 |
| 【「延喜式」の神名帳について】 |
| 平安初期の927年に集成された「延喜式」の神名帳(官社帳)には、官社として認定されていた神社が2861社(3132座)記されている。ここに記された神社を「式内社」(これ以外を式外社)と云う。国家的祭祀の際、神祇官より幣帛が奉られる神社が官社すなわち式内社で、中央の神祇官が遠方の官社まで出向くのが何かと大変であるという理由のため、「延喜式」制定の折に神祇官が直接奉幣する「官幣社」と、国司が奉幣する「国幣社」に分けた。そしてさらに「大社」と「小社」に分けられた(「神道の歴史」参照)。 10世紀初めより11世紀初めにかけて、朝廷は、特に尊崇する「22社」を選んで殊遇した。伊勢神宮を始め、式外社の岩清水八幡宮などが含まれてる。この他に一種の社格として、国内で最上位の地位を占めた神社に「一の宮」、次に「二の宮」、その次には「三の宮」という呼称をつけていった。これは、国司が任国の国内の神社へ奉幣する際の順番にもほぼ対応していた。更に、巡拝をするかわりに、国府近くの一つの場所に諸神をまとめて合祀し、「総社」とした。 以上が、天皇朝時代の「権力型新神道」の変遷史の概要である。 |
| 【「伯家(はっけ)神道」について】 | |
| 10世紀後半、65代花山天皇(984-987在位)の御世、皇子の清仁親王が創家した白川家に始まる社家神道の一つとして「伯家(はっけ)神道」が始まった。その神道形態は、823年間に亘り明治2年まで皇室祭祀に取れいれられてきた。「伯家」とは、神祇官の長である「伯」を代々世襲してきたことからの通称で伯王家とも云われる。古代の神祇伯は、「大中臣氏、忌部氏、橘氏」が主流であったが、1046年(藤原時代後期)から白川家の世襲になっている。その後、室町期に吉田神道(卜部神道)が台頭し鼎立するようになった。江戸時代には、白川と吉田両家が神職免許の授与を担当した。吉田流が仏教的要素を取り込んでいるのに対し、白川流は純粋神道的であるところに特徴が認められる。作法も吉田流より簡素である。 | |
「★阿修羅♪ > 雑談専用20」の石工の都仙臺市氏の2006.11.5日付け投稿「天皇に成る爲の極めて重要な行法。祝(はふり)の神事」の関連の下りを転載しておく。
|
|
「● 第二章 伯家神道が明かす神道の深層 皇太子が天皇になる修行「祝(はふり)の神事」 」。
|
| 【「本地垂跡説、両部神道と山王一実神道」について】 |
| 平安時代の末期頃になると、民衆の側から新宗教が興り、そのいずれもが、我が国古来よりの神道復活とも云える教義を掲げ、活発な活動を繰り広げることになった。暫くの間表舞台から退いた神道は、神仏習合即ち神と仏とを一体のものと解釈を踏まえつつ、新派の習合神道を生み出すこととなった。その代表的なものが、本地垂跡説の両部神道と山王一実神道である。興味深いことに、真言宗に両部神道が絡み、天台宗に山王一実神道が絡んで、それぞれ教義形成されるに至る。そういう事情で、両部神道は真言神道、山王一実神道は山王神道、天代神道、日吉神道とも呼ばれる。これはある意味で、地下に潜った古神道の応法化の動きとも云える。 紀伊半島南端の熊野三山が「蟻の熊野詣」といわれるほど熊野詣が盛んとなり、都の人々の信仰を集めたのはこの頃である。それは表向きは熊野の神が観音や弥陀(みだ)の垂跡で、熊野の地はこれらの仏の浄土と考えられたからであった。次第に山伏修験道が確立され、熊野信仰は先達(せんだつ)によって全国に広まった。この山伏修験道は、仏教神道混交ながら神道を復活させている気配がある。 律令体制の衰退と武家政権の登場は神信仰の上にも新たな機運をもたらした。武家政権下にあっても神祇祭祀は治世の要道として重視されたが、なかでも八幡神は源氏の氏神ということで重んじられ、広く武門の守護神として著しい発展をみせた。 |
| 【「本地垂迹説の教理展開、理論神道」について】 |
| 鎌倉幕府の基本法である「御成敗式目」の第一条に「神社を修理し祭祀を専らにすべき事」とあるように、鎌倉幕府は神仏を保護した。源氏の氏神である鶴岡八幡宮(石清水八幅宮より勧請)は幕府の守護社に位置づけられ、そこに奉行人を置いて神社事務にあたらせた。幕府と神社の関係の深さがうかがえる。そして寺社奉行を設置し、社寺関係の事務に専従させた。このことは、武家政権は、永らく地下に潜っていた神道の復活によって支えられていた面が有るのではないかという推測を可能にさせる。 両部神道と山王一実神道という二つの道から始発した本地垂跡説は、鎌倉時代から室町時代にかけて教理面を確立していった。本地垂迹説とは、本地、本体は仏教で云う仏や菩薩であるが、衆生を救済する為に、我が国では神という仮の姿をもって現われる(仏を本地,神をその仏が姿を変えてこの国土に垂跡(すいじゃく)したものとみる)説であり、鎌倉時代に盛んになった仏主神従説のことを云う。この本地垂迹説は、平安、鎌倉、室町時代の頃における神道世界において主流的な流れを占めた。権現というのも、仏が衆生救済の為に仮に神として現われたとする、本地垂迹説により生み出された思想である。 本地垂跡思想のひろがりは、鎌倉時代における神道論(理論神道)の発生を促した。何々神は何々仏の化身であるといったような、本地垂迹説との関係が個々に特定されるに至る。例えば、伊勢は、天照大神の本地を大日如来とみて、内宮・外宮を胎蔵界・金剛界にあて、ゆえに大日本国は大日の本国の意味だと説く密教系の両部神道を生んだ。日吉(ひえ)の神こそ根本仏たる釈迦如来の垂跡で日本第一の神なりとする天台系の山王(さんのう)神道も生んだ。他にも八幡は釈迦あるいは阿弥陀如来、賀茂は正観音の垂迹というように、具体的に定められていくことになった。又、後年、両部神道からは法華神道が、山王一実神道からは三輪流神道、御流神道、雲伝神道などが派生しているがこれらがみな一様に本地垂迹説に則った教理を展開している。 |
| 【「伊勢神道」について】 |
| その鎌倉時代に、本地垂迹説に対抗し、日本の神の方が主体であり、仏は従とする神主仏従説が登場して来た。伊勢外宮の祠官であった度会(わたらい)氏によって創唱された伊勢神道がそれである。伊勢神道は、仏教的説明をさけ道家や儒家の思想に依拠しながら伊勢の外宮の神こそ宇宙の根源神なりと説いた。その為、外宮神道(外宮神学)とか、度会神道とも呼ばれた。 度会神道の教義の根幹は、外宮の主祭神である豊受大神を天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、もしくは国常立尊(くにとこたちのみこと)と同一であるとし、外宮の権威を高めるところにあった。伊勢神宮では内宮が天照大神を祀っているが、度会神道は外宮を内宮と対等か、それ以上の格を持つものとして位置づけたことになる。 鎌倉時代末期の頃に、度会行忠(ゆきただ)、常昌(つねまさ)、家行(いえゆき)などの有力人士によって、教義面での整備が行われ、組織的な大成が為された。伊勢神道は、南北長時代に吉野朝(南朝)の重鎮、北畠親房に多大な影響を与え、神皇正統記をはじめ数々の書が親房の手により著わされていった。親房は、仏を主として神を従とする神仏習合思想である本地垂迹説に対して、神主仏従の反本地垂迹説を唱えた。やがて、南朝が足利尊氏の率いる北朝に敗れ、衰退して行くと、南朝方と結びつきを深めていた伊勢神道も次第にその勢いに衰えを見せ始める。 南北朝は、1336年から1392年まで約60年間続く。この時代、国家の統一力は失われ、社寺は保護されず、官社への奉幣もままならず、荒廃する神社が多かった。室町幕府の社寺関係制度は、鎌倉幕府のそれを踏襲していたが、社寺の事務の複雑化に伴って、神社の事務をつかさどる社家奉行と寺の事務をつかさどる寺家奉行が置かれた。一般庶民の神社信仰は盛んで、伊勢講や熊野講などの有名神社の「講」組織がいくつもできたのはこの時期である。 |
| 【「南朝と北朝の神道」について】 |
| 1392年に明徳和約によって、それまで天皇の証明である三種の神器を保持していた南朝の後亀山天皇より北朝の後小松天皇に渡され、この100代目の後小松天皇の時に、以降は南朝と北朝とが交互に天皇になる(賎睥)ことで合意した。が、実際には北朝が皇位継承してきたという史実がある。近代国家となった明治維新以後の明治、大正、昭和、そして今上天皇は北朝系系譜である。 何故、明徳和約は守られなかったのか、それは当時、室町幕府三代将軍、足利義満が、この和約を反古にして、自分が天皇になろうとしたと云われているが、その真相は不明である。この不明さが混乱を生んでいる。現天皇家まで北朝系が継いできているが、明治維新で徳川幕府が江戸城を無血開城した後、明治天皇が皇居として入城した際、皇居前に楠木正成の銅像を置き、それ以後も明治、大正天皇共に吉野を訪問している。しかし、楠木正成は、南朝の後醍醐天皇側に付いて足利尊氏と戦って討死した武将であり、すなわち南朝側に与した武将が北朝系の天皇によって銅像にまでして称えられる背景がややこしいことになる。一体いかなる意味が隠されているのか。 |
| 【「三輪神道」について】 |
(サイト「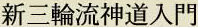 」に詳しいので参照する) 」に詳しいので参照する)鎌倉から室町時代の中世神道の一派。源流は奈良天平期から平安初期にかけて活躍して玄賓僧都から始まる。鎌倉末期、高野山・上醍醐で修業して大和の大神(おおみわ)神社に属する三輪平等寺を開いた慶円(1140-1222)上人により確立された。後に大御輪寺(今の若宮社)を開いた叡尊が継承し室町期に大いに発展した。奈良県の大神(おおみわ)神社を中心に成立した神道の一派で単に三輪流とよばれることが多い。後世、三輪流神道とも呼ばれた。 教義は、真言密教と陰陽五行説に依拠する両部神道思想から日本書紀神代巻を解釈し、天照大神と三輪大明神の同体説を唱えているところに特徴がある。天津神と国津神との融合、古神道の奥義の称揚。 能楽「三輪」が作られ、「思へば伊勢と三輪の神、思へば伊勢と三輪の神、一体分身の御事」と謡っている。「三輪流神道深秘鈔」は、「天を極め、地を究めて、以ってその栖とす。法体周遍す。草木国土ことごとく皆我栖也。……かようの御神ゆえ、諸神に超すぐれたまひて無二無双の御神なれば八百萬の神をも治めさせたまひて、神徳も天地萬物に通達して、無上無極の至尊なり」と述べている。 |
| 【「吉田神道」について】 |
| 室町時代末期になると、伊勢神道に替わって、更に明確に神主仏従の反本地垂迹説の立場に立つ神本仏跡(しんぽんぶっじゃく)説を唱える神道が出現した。京都吉田神社の示司官・卜部吉田兼惧により創唱された吉田神道がそれである。吉田神道は、日本固有の惟神の道を主張し、天照大神、天児屋根命から直伝、相承した絶対本質的な神道の意から、元本宗源神道、唯一宗源神道(唯一)などとも云う卜部(うらべ)神道を生み出した。 つまり、吉田家に伝わる神道こそ天地開びゃく以来唯一伝わるところの、正統で、かつ全ての宗教の本源としての道であると称した。神道の下に仏教、儒教、道教などを融合し、吉田兼惧は神祇管領長上(じんぎかんりょうちょうじょう)と称して地方神社の組織化に乗り出し、以後吉田家は幕末にいたるまで全国の神社の総帥の地位を占めた。 その教義においては、「吾が日本は種子を生じ、震旦は枝葉を現わし、天竺は花実を開く。故に、仏法は万法の花実たり、儒教は万法の枝葉たり、神道は万法の根本たり」(「唯一神道名法要集」)とする。いわゆる「三教枝葉花実根本説」や、「吾が唯一神道」は、「天地を以って書籍と為し、日月を以って証明と為す」(「唯一神道名法要集」)という藤原鎌足の言を根本思想に据えている。 また、吉田神道では、大元尊神という根源的な神を、記紀神話における天御中主神、国常立尊と同一視して最高位に奉戴した。そして、吉田神社の神社の南方に、日本最上神祇斎場という施設を建て、その中央に大元宮を設けて、大元尊神を祀った。その周囲に、伊勢の内宮、外宮をはじめ、八百万の天神地祇の社殿を設け、日本国中の神々を勧請、この地を日本「神道」のいわば総本山としたのである。 その他、吉田兼惧は、伊勢の内宮、外宮の神が吉田の宮に飛び移ったと主張し、これを朝廷に認めさせたり、吉田家の先祖である卜部家の格を高める為に、天児屋根命を祖神とする中臣(藤原)家の家系図を取り込むなどした。その力は、神祇官の長としての神祇伯たる白川家をもしのぐものとなり、遂には室町幕府の承認を得て、神職としては最高の権威迄幟つめた。こうして、吉田神道は、室町時代から江戸時代にかけて一大勢力として発展する。 |
| 【「織田信長、豊臣秀吉の安土桃山時代に窮乏した社寺を保護」について】 |
| .織田信長、豊臣秀吉の安土桃山時代、戦国時代以来窮乏した社寺が保護された。しかし信長の延暦寺焼き討ち(日吉神社も焼かれた)に見られるように、両氏とも兵力を持って政治干渉する社寺に対しては容赦なく弾圧した。また柴田勝家は秋田地方の社寺に刀狩を命じている。一方信長は伊勢神宮の造営費を寄進している。社寺への信仰と社寺の政治干渉の排除は、この時期以降の武家政治の特徴となっている。 信長は検地を行ったが、秀吉も天下統一後直ちに、信長より厳しく検地(太閣検地)を行い、いかなる社寺領も全て検地竿入れし、領地没収の上、朱印状による石高をもって、これを全国の社寺に寄進した。この時代の社寺政策が次の徳川幕府の基礎となる。(「神道の歴史」参照)。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)