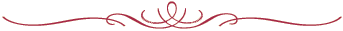一九七六年二月五日午前一時四○分。毎日新聞社(東京・竹橋)の四階にある編集局は、東京都内と周辺に配達される最終版(一四版)の締め切り時間も過ぎ、ほっとした雰囲気に包まれていた。社会部デスク(副部長)の原田三郎(元毎日新聞論説委員)は、アメリカの通信社UPIから外信部にロッキード事件の第一報を伝える原稿が入っていたのを知らなかった。
社会部では、突発事件に備えて、毎夜5~6人の記者が宿直していた。最終版の締め切りが終わると、ささやかな「宴会」が開かれる。「お疲れ様、それではささやかに……」というような風景は、毎日がプロジェクトとでもいうべき新聞社では常態であったであろうことは想像に難くない。「宴会」が始まって間もなく、外信部のデスクが、UPIから流れた未翻訳の1枚のテレックスを持ってきた。
<米上院外交委員会の多国籍企業小委員会は四日、公聴会を開き、米ロッキード航空会社が多額の違法献金を日本、イタリア、トルコ、フランスなどで続けていたことを公表した。小委員会が明らかにしたリストによると、数年前から一九七五年末までに七○八万五○○○ドル(約二一億円)が日本の右翼、児玉誉士夫氏に提供されていた。さらに三二二万三○○○ドル(約一○億円)がロッキード社の日本エージェントの丸紅へ支払われている>
どういうことか? 右翼として名を知られていた児玉誉士夫が、ウラの顔としてロッキード社の秘密代理人になり、巨額の報酬のもとに、航空機の売り込み工作を行っていたということである。この時点で、最終版の輪転機は既に回り始めていたから、朝刊には間に合わない。原田は、一面トップ級のニュースだと直感した。果たしてライバル紙(朝日、読売)は、朝刊でこの記事をどれだけの大きさで扱っているか?心配で、原田は帰宅せずに会社に泊まった。幸いにして、朝日は二面の扱いで、五段の記事だった。原田は、内心「助かった」とホッとした。
国税庁記者クラブは、原稿の材料はほとんどが発表物だったので、特ダネ競争のない「仲良しクラブ」で、サナトリウム(療養所)と呼ばれていた。当時の毎日新聞国税庁記者クラブを担当していたのは、田中正延、通称ショウエンという記者だった。田中は遊軍の愛波健から、電話でロッキード問題が、税務上の処理の問題として表面化する可能性を示唆された。田中は、個人所得税を管轄している直税部の担当者に、何が問題なのかを確かめた。答は、ロッキード社資金について、児玉が税務署に申告しているかどうか、ということだった。
ロッキード事件が、児玉の脱税の可能性からスタートしたことにより、国税庁記者クラブは、サナトリウムから地獄の三丁目に変じた。一丁目は、無数の事件に追われる警視庁記者クラブ。二丁目は、超大型事件を摘発する東京地検特捜部を担当する司法記者クラブ。三丁目は、両記者クラブよりつらい、地獄の行き止まりの意味だという。
児玉誉士夫は、東京地検特捜部が、戦後狙い続けていた人物だった。毎日新聞の司法記者クラブのキャップ・山本祐司は、検事から、児玉の逮捕は国会議員20人の逮捕に匹敵する、と言われていた。二月五日の毎日新聞の夕刊の一面トップは、ロッキード事件の第一報だった。紙面の2/3を割いて、「ロッキード社が“ワイロ商法”」「エアバスにからみ48億円」「児玉誉士夫氏に21億円」などの大見出しだった。朝日新聞も、一面トップの扱いだった。両紙とも、児玉の顔写真を載せていた。この段階で、事件の中心人物が児玉であることを示すものだった。
東京国税局査察部には、昭和24(1949)年の発足以来、各界主要人物の資産に係わる膨大な資料が蓄積されている。その中で、政界、財界、闇社会などの主だった人物が所有する株、金融債、資金源、預金口座などのカネの動きを記録した極秘ファイルは「特別管理事案」にまとめられ、その中でさらに重要人物が抜き出されて「特別管理A事案」として保管されていた。「Aファイル」と呼ばれるものである。児玉誉士夫の資産資料も、「Aファイル」として保管されていた。