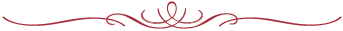
| 履歴その4、実業家・代議士模索時代から初当選の頃 |
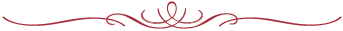
更新日/2018(平成30).6.19日
| 1941(昭和16) 年、角栄23歳 |
| ◎兵役解除、病気回復した角栄は、大正元年生まれで角栄より6歳年長のかって一緒に仕事をし、警視庁に勤めていた中西を訪ねた。 | ||
| 10.8 | ◎中西の紹介で飯田橋2丁目にあった建築業者坂本氏の家の一部を借り受け、田中建築事務所を開設した。角栄は、ここで建築設計、機械の基礎の計算、建築工事請負などの事務所を開き、事業を再開する。中西は、中島飛行機や早稲田大学の仕事を請け負っていたが、その仕事の一部を廻してくれた。理研との仕事を復活させた。この時家主の坂本家には娘はながいた。はなは娘を連れて離婚し坂本家に戻っていた。ここで、角栄は、はなと運命の出会いをしたことになる。 | |
| 12.8 | 【太平洋戦争始まる】真珠湾攻撃とともに第二次世界大戦に突入。 | |
| ◇理化学研究所とは | |
|
1917(大正6)年、角栄が生まれる前年、3月、渋沢栄一氏ら財界人の提唱で「総合科学研究所」の機運が高まり、政府や皇室、産業界の支援を受けて東京・駒込に設立された。設立のきっかけは、タカジアスターゼで有名な高峰譲吉博士が、アメリカから帰国して、「これからの世界は理化学工業の時代になる。日本も研究所を設立する必要がある」と提唱、これに実業界が応えたことによる。資金は天皇の御下賜金、政府の補助金、実業界の寄付金調達によった。設立目的として「学問の力で産業の発展、国運の発展を期す」と記した。初代所長は菊池大麓。設立当初より戦前の日本を代表する学者が寄った。戦後社長になる物理学の仁科芳雄博士の他にも、物理学の土星型原子モデルで有名な長岡半太郎、当時の世界最強磁石「KS鋼」を発明した本多光太郎、ビタミンB1を分離した農芸化学の鈴木梅太郎が在籍し「理研の三太郎」と呼ばれた。レーダーに捕まらない合成樹脂の飛行機を考えた航空機の大家の今富祥一郎、後に日本医師会会長になる武見太郎、池田菊苗。ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹、朝永振一郎両氏も理研で研究の礎を築いた。 敗戦で理研コンツェルンはGHQにより解体された。また原子核物理学者の仁科芳雄氏が開発した円型加速器「サイクロトロン」はGHQから軍事研究の嫌疑を受け、東京湾に沈められるという事件もあった。 戦後、理化学研究所法の施行により特殊法人化され、施設は埼玉県和光市に移った。現在の理研は脳科学や遺伝子解析、発生・再生学、放射線の高度利用などの先端分野に力を入れる。研究拠点は国内に計7カ所あり、研究スタッフは約2000人に上る。「横浜研究所」(横浜市鶴見区)は、日本有数の「ゲノム研究拠点」として国内外に知られる。日本原子力研究所と共同で兵庫県内に建設した大型放射光施設「SPring―8」は、和歌山市・毒物カレー事件の亜ヒ酸の鑑定に使われ、注目を浴びた。 |
|
角栄が次のように回想している。
|
| 1942(昭和17) 年、角栄24歳 |
| 3.3 | ◎桃の節句のこの日、角栄は、家主の娘坂本はな(八十子)と結婚。はなは当時31歳、8歳の年上で離婚歴と9歳になる女の子の連れ子がいた。角栄は、はなさんのつつましやかな挙動と、内に秘められた芯の強さに惚れた。このはなが糟糠の妻となる。結婚時、次のような「三つの誓い」をさせられた、と伝えられている。この約束が角栄とはなとの夫婦の契りとなった。
|
||
| ◎結婚と同時に飯田橋の電車通りに面した間口20間の材木屋の店と倉庫を買い、ここに事務所を新築し、事業を拡大させていく。 | |||
| 11月 | ◎長男正法誕生。 | ||
| 1943(昭和18) 年、角栄25歳 |
| 12.1 | ◎坂本組の業務も引継ぎ、田中土建工業株式会社を設立。資本金は19万5千円。妻の実家の坂本組を改組しての出発となった。 | |||||
この時代の角栄について次のような証言が遺されている。
|
||||||
| ◎軍関係の工事などを受け日曜祭日もない忙しさとなる。理研にも食い込んだ。理研幹部星野一也らが窓口となった。理研の最初の注文は嶋田専務からの水槽、鉄塔の設計依頼であった。次に、ガーネット工場の設計、続いて那須のアルミ工場の鉄筋コンクリート製ロータリーホルンの製作、群馬県沼田のコランダム工場の買収、新潟県の理研工場の建設、るつぼ工場の施行と云う風に注文が舞い込んだ。角栄は、これらの仕事を着実且つ精力的にこなして行った。田中土建は急成長し、1943(昭和18)年の年間工事実績で全国50社に数えられるようになる。 | ||||||
| ◎顧問に満鉄の副総裁を務めた人物を戴いた関係から「政界きっての寝業師」と云われていた大麻唯男との交際が始まる。田中土建の顧問として大麻唯男、白根松介、岩崎英祐の三人が居た。戦後は弁護士の正木亮(あきら)が加わる。 | ||||||
| 1944(昭和19) 年、角栄26歳 |
| 1.14 | ◎長女真紀子誕生。 | |
| 暮れ | ◎陸軍航空本部が理研工業の内地施設を満州や朝鮮に移すよう軍令を出し、田中が王子神谷町の工場施設一切の移設工事を引き受ける。総工費2400万(現在で約100億円)の大工事となった。軍の命令で興銀が着手金を支払う。 | |
| 1945(昭和20) 年、角栄27歳 |
| 2月 | ◎王子の理研ピストンリング工場を朝鮮の大田に移設する工事を請け負った角栄は、幹部5名を引き連れて韓国に渡る。請負工事総額2千万円、所要人夫延べ37万人の大事業となった。角栄は「私の履歴書」で次のように記している。
|
||
| 8.8 | ◎工事用木材買い付けのため朝鮮北部を駆け回り、夕方に京城に帰着。 | ||
| 8.9 | 【ソ連軍が国境を越えて進入】 | ||
| 8.15 | 【終戦】満鮮国境近くまで木材買い付けなどに飛び歩き、工事に取り掛かった。概要「工事費2400万円のうち、約1500万円送ったところで終戦になった。現地採用の社員百余人を広場に集めて、現地の全財産、資材を『新生朝鮮に寄付する』と宣言して、引き上げ準備に入った」。これによれば、900万円を手元に残したことになる。 | ||
| 8.18 | ◎汽車でプサンに向かう。概要「帰国直前の混乱の中、田中は直前に軍票を現金に換え、その大金を手に帰国したはずだ」(理研幹部星野一也)とあり、莫大な金を手にして帰国したことになる。 | ||
| 8.20 | ◎朝鮮・太田市から引き上げ。角栄一行7名は、プサン−舞鶴連絡線に運良く乗り合わせ出来帰国。「角栄」が「菊栄」と読み間違えられ、女子供優先にあやかったと伝えられている。舞鶴港ではなく予定を変更して青森港に着いている。 | ||
| 8.25 | ◎青森から汽車で東京に向かう。一面焼け野原の東京に佇む。幸いなことに飯田橋にあった事務所や住宅は無傷で残っていた。角栄は、この時の思いを次のように記している。
|
|
| ◎理研の社長・大河内正敏氏が科学・生産部門で戦争に協力したとの理由で戦犯として逮捕された。その日、角栄は、大河内邸に居て、共に巣鴨まで行き立ち入り禁止ギリギリのところまで見送った。そこまで行って大河内と別れの言葉を交わしたのは角栄と恩師の草間道之輔の二人きりであった。 | ||
| この頃の逸話と思われる。荒船清十郎(後の自民党代議士、衆院予算委員長)が、30歳代で埼玉県議会の議長を務め、県下一、二の山林地主として羽振りを利かせていた頃、ある日、若いくせにチョビヒゲをはやし、騎兵のような長靴をはいた男が「木を売ってくれ」と訪ねてきた。「売ってくれって、どれほど欲しいんだい」と尋ねると、「お前さんが持っている山の木全部だ」と云う。秩父で一軒しかなかった牛ナベ屋に一升瓶を持ち込んで一杯やり始めた。頃合に抜け出し、警察電話を使って新潟の警察に身元照会したら、「若いけれど仕事は出来る男で、信用してよろしい」という返事だった。そこで商談に入り杉と檜を売った。田中は切り出される木を見て、一目で見分け、良質の檜はどこ、杉はどことたちどころに送り先を決めて指示していた。その采配振りを見て、「こいつはただの山師では終わらん男だ」と舌を巻いた。角さんは俺の山で一儲けしたので、以来俺に一席設ける費用は全部あちら持ちにしてもらうことになった云々。 次のように逸話している。
|
||
| 10.9 | 【幣原喜重郎内閣発足】 | |
| 11月 | ◎理研の大河内正敏社長の紹介で以前から会社の顧問になってもらっていた進歩党顧問で町田忠治の側近だった大麻唯男と新橋の料亭・秀花で会う。大麻は、東条英機内閣の国務大臣を経験しており、政界の「寝業師」と呼ばれていた策士型の政治家で、町田忠治を担いで進歩党の根回し役をしていた。 「12.31日に、占領軍の命令で衆議院が解散になる。そこで、新たに進歩党を結成した。総裁には、一番早く300万円の資金を調達した者がなる約束だ。自分は町田忠治を押している。ついては、300万円献金してくれないか」。このように資金提供を申し出られ、「政治にカネがかかることは、素人の私にも分かります。戦後の民主政治、その為の政党政治を確立することが責務と思います」、「その3百万円(現在の20億円相当)、全部出させていただきましょう」と献金している。「頼まれれば、越後人はどこへでも米搗きに出向く」情があった。 |
|
| 12.18 | 【衆議院解散】この時角栄は、大麻から進歩党公認候補としての立候補を要請され、同意する。「あんたは、資金を出して政治家を助けるよりは、ぜひ自分で政治家になんなさい。君みたいな青年が戦後政治を担ってくれ。君は政治家に向いとる」。以後選挙運動を始める。「15万円出して1ヶ月間、黙ってお御輿に乗っていれば当選は請合う」と口説かれ、15万円をポンと出して出馬することになった、と伝えられている。 この時より数日後、政界の寝業師として鳴っていた大麻は、角栄を事務所に招き、九州弁で次のように口説いたと伝えられている。
|
| 1946(昭和21年) 年、角栄28歳 |
| 1月 | ◎田中土建工業新潟支店を柏崎に開設、選挙準備を本格化。「田中は若いのにヒゲを立てて、東京と柏崎を頻繁に往復していた。地元の知り合いを中心に、10人ぐらいの陣容だった」(新潟支店に勤めた山田栄)。 | |||
| 3.14 | ◎進歩党公認で立候補。定員8名のところ37人の乱立となる。この時新潟鉄工から本間幸一氏が田中の秘書として移ってきている。二田小学校の恩師草間先生も応援に駆けつけている。 この時、大麻の紹介で選挙参謀を依頼していた塚田十一郎氏が、選挙資金を渡した途端に角栄と同じ選挙区から自由党公認候補として出馬し、裏切られることになった。他にも各地区の選対責任者が次々に立候補した。政界の権謀術数、一寸先は闇を地で行く寝耳に水の事態出来であった。 角栄はモーニング姿で居住まいを正して登壇した。演題は「若き血の叫び」。「自壊一歩手前の祖国を、民主主義精神によって生かす政治家の政策綱領は、空念仏やお題目であってはいけないッ」で始まり、「若い私の命を賭けた実行力を信じてください!」で結ぶ演説をしていた。最初の立会演説会は野次にあって立ち往生させられている。
|
|||
| ◎この時、選挙活動の途次で佐藤昭と運命的な出会いをしている。佐藤昭から応援弁士の紹介を得ている。 ◎この時、戦前の衆議院議員、貴族院議員を務めた立志伝中の人物高鳥順作に挨拶回りをしている。角栄の次のような述懐が残されている。
高鳥修は、この時のことを祖父から次のように聞かされている。
|
||||
| 4.10 | 【第22回衆議員総選挙(大選挙区、2名連記制)】 「敗戦の痛みをしばし忘れたり 花吹雪浴び投票に行く」。女性運動家で後に津田塾大学学長になる藤田たきがこう詠んだ。 角栄は、得票3万4124票の11位の次点で落選。塚田十一郎氏は5万8812票で4位当選。生涯でたった一度の不覚となったが、支持者の前で、次のような落選の弁を述べている。
敗因は、佐藤三千三郎候補も理研をバックにしていた為、票が割れたこと、御輿を担ぐはずであった参謀役の塚田や地区責任者の吉沢、吉田らが、運動資金を手にすると自ら立候補し、角栄組織が分裂した。肝心の選挙参謀がこのていたらくで苦労することになった。 角栄は、落選はしたがこの選挙で多くの知己を得た。「まったくよい勉強になった」とこの落選を振り返っている。次のような言葉も残している。
|
|||
| 5.22 | 【第一次吉田内閣成立】 | |||
| 秋頃 | 大下英治著「*友・小佐野賢治の昭和戦国史」(講談社)では、この頃、正木亮弁護士の紹介で、角栄と小佐野賢治が出会っている。二人が飯田橋の田中土建事務所を訪れた、と云う。この時、正木は次のように述べている。
|
|||
| 11.3 | 【日本国憲法公布】施行は翌年5.3日。 |
| 1947(昭和22) 年、角栄29歳 |
| 3.31 | 【衆議院解散】第一次吉田内閣は、「憲法内容を民意に問う必要がある」とのGHQの意向を受けて衆議院を解散し、総選挙となった。 ◎この時角栄は果然、進歩党が改組した民主党公認で立候補した。新潟3区で出馬したが5議席に11人が立った。前回の教訓から「選挙は人任せでは駄目だ。政党人を頼むと何をされるかわからん」として自前選挙に乗り出し、柏崎と長岡に田中土建の出張所を設け、100人近い社員を採用し稼動させている。いわば選挙の組織化、事業化発想であった。 後の国家老秘書・本間幸一は、この時の事を次のよう回顧している。
|
|||
◎この時角栄は、「若さが誇る熱と意気にものをいわせ」一日9会場を駆けずり回り、全部で90余の言論戦をこなした。演題は「祖国愛に訴える。その際の演説の一節は次の通り。
|
||||
◎この時角栄は、「辺境の地」へ足を踏み入れることをいとわなかった様子が伝えられている。当時の選挙参謀の一人は次のように伝えている。
|
||||
◎この時、早稲田大学の大塚学生課長が、雄弁会の幹事長・新井明(後に、日本経済新聞社代表取締役社長、会長となる)氏に角栄の応援演説に向かうよう依頼している。その理由は次のようなものであった。
戦後、早稲田大学の校舎は老朽化し、あるいは戦争中に焼夷弾で焼かれたりなどして、雨漏りで授業ができないほどだった。大学は業者に修理を依頼するが、どの業者も仕事を引き受けようとしなかった。何しろインフレがすごいので、資財の値上がりを待っていたほうが儲かった。そんなとき角栄の会社が契約通りの価格で仕事を請け負ってくれた。こうしたことがあったので角栄は信用され、その一部始終を見ていた大塚学生課長は田中角栄に恩義を感じていた。 大塚学生課長の要請により、早稲田大学雄弁会が立ち上がった。こうして早稲田雄弁会の10名ほどの面々が三班に分かれて新潟三区を遊説して廻ることとなった。 魚沼地区で、「若造だが、なかなか魅力がある」との声が出始め、勝手連的な動きが生まれた。柏崎清水谷に「田中党」を名乗る青年層がメガフォン片手に、無報酬の田中支援活動を繰り広げた。これが越山会のルーツとなる。 |
||||
| 4.25 | 【新憲法下初の第23回衆議員総選挙(中選挙区、単記投票制)】角栄、初当選。定数5名中の3位当選で、3万9043票を獲得していた。旦四郎(自由前)49555票、神山栄一(民主新)49350票、田中角栄(民主新)39043票、清沢俊英(社会前)37020票、稲村順三(社会前)26260票。 「今までの保守系にあきたらず、革新には二の足を踏むような人が、みな田中に入れた。若いしバリバリしたやり手に新鮮な魅力を感じたのだろう」(後塩沢町の助役・長尾信二)。同期に中曽根康弘、鈴木善幸、園田直、石田博英、倉石忠雄(以上連続14期当選組)、桜内義雄、根本竜太郎、松野頼三ら。衆院建設委員になる。 この時社会党が大躍進し、第一党(143議席・片山哲委員長)になる。自由党が第二党(131議席・吉田茂)、角栄の所属する民主党が第3党(124議席・芦田均)、国協党が第4党(29議席・三木武夫)、共産党が4議席、農民党4議席となった。 新潟日報は、初当選の抱負を次のように伝えている。
|
|||
| 5.3 | 【新憲法施行】 | |||
| 5.24 | 【社会党の片山哲を首班とする連立内閣(社会党・民主党・国協党)が誕生】 ◎田中の所属していた民主党は、連立に傾く芦田・与党派と自由党と手を組もうとする幣原・野党派に分かれて抗争していた。党内は連立の芦田派が優勢であったが、田中は、この時幣原派に属している。 |
|||
| 5月 | 後に角栄の女参謀となる佐藤昭と夫が上京。 | |||
| 7.10 | ◎衆院本会議に、初当選の新人ながら民主党を代表して初登壇、自由討議を行う。「議会政治のあり方」、「経済政策のあり方」、「戦後復興のあり方」を演題とする。これについては、「自由討議」で詳述する。 | |||
| 初夏 | ◎6.2日に国際興業を発足させた小佐野賢治氏(後の社主)が顧問弁護士の正木亮を仲介人として角栄に会いにきた。この二人も運命的な出会いとなった。 | |||
| この頃、金満津の芸者・辻和子の旦那となる。 | ||||
| 9.8 | ◎長男の正法死去(5才)。角栄は次のように述懐している。
|
|||
| 9月 | 「キャサリン台風」の襲来で関東、東北、北海道にかけて、死傷者、行方不明者3600人を超える大水害が発生した。利根川、荒川など多くの河川が決壊する。角栄は、行政機構の適切な対応を求めて次のように質問している(山岡淳一郎「田中角栄を歩く」参照)。
内務事務官が次のように答える。「過去においては、多少、いろいろのことが風評にせられておりますけれども、最近においては農林省の治山方面と内務省でやる砂防という点については、常に連絡を取っておるので、この五ヵ年計画においても……」。田中は曖昧な答弁に「現場感覚」で突っ込む。
角栄は、復旧工事にかかる「人、モノ、金」の内実に迫った。内務事務官が次のように答える。「第一問につきまして内務省の機械力または人的資源は十分だと思います。しかしながら利根川の決壊口は、この際は一刻も争うという意味から、やはり民間のご協力をもって時日の短縮に専念している状態で、今後も内務省の直轄工事でやるという意思は毛頭ありません。平時の災害復旧にも直轄と請負の二本立てで準用していきたい。労務関係につきましても、被災地では災害者が非常な熱意を示されまして、早期復旧のためには不眠不休で応援するという涙ある申し出がありますので、被害者のご援助を得て、労務については不足を感じておりません」。 角栄は、この質問に並行して、選挙区の刈羽郡、柏崎市を流れる鮫石川水系の砂防工事を手始めに河川改修や道路整備の「請願」を次々と出した。請願は憲法に認められた権利であり、国会議員の紹介で出された請願が議院で採択されれば、内閣に送られる。内閣はその処理を報告しなければならない。請願はれっきとした国への「発注」だ。「角栄は、紛れもなく戦後の民主化の落とし子だった」。 |
|||
| 9.25 | ◎衆院本会議「自由討議」の場で、「中小企業振興対策」演説。 | |||
| 10月 | ◎片山哲内閣は、炭鉱国家管理法案を成立させようとしたが、国会は紛糾した。この時田中は、「黒い石炭を赤くするな」と叫んでこの法案の成立に反対する急先鋒の役割を果たしている。 | |||
| 11.28 | ◎炭鉱国管法案決議の際、幣原派は造反して反対票を投じ、民主党を脱党して僅か28名の「同志クラブ」を結成した。佐々木秀世、根本、原健三郎らと共に田中も同調し移籍する(民主党の分裂)。幣原率いる同士クラブ28名は斎藤隆夫派らの無所属議員8名を加えて民主クラブを結成し、その後吉田茂が率いる日本自由党112名に合流、その他を加えて152名で民主自由党を結成していくことになった。この民主自由党が院内最大勢力となり政局を動かし始める。 | |||
| 12.4 | ◎国土計画委員会で、建設院設置法案の審議に参画。片山首相に「家を与えずして何が民主主義か!」と追及。 |
|||
| 12.5 | 角栄は、衆議院本会議で、片山首相に「建設院」のあり方を次のように問うている。(山岡淳一郎「田中角栄を歩く」参照)。
省への格上げを視野に入れた弁舌からは、叩き上げの迫力が伝わってくる。片山首相が次のように答える。「行政整理はなかなかの大問題でありまして、機構の改革と経費の節減と人員の調整問題でありまして、この三つをにらみ合わせてやるのですからなかなかの大事業であります……。人員の問題及び整理の問題は、小出しに部分的に出しまして、いくらかでも進歩を図っていきたいと思っております」。田中は、やおら庶民が塗炭の苦しみを舐めさせられている「住宅問題」を突きつけ、家とは何か、持論を展開した。
片山首相が答える。「住宅問題ばかり考えますと、今後30年かかり、40年かかるということになりましょう。農民問題ばかり考えますと、農村の文化建設には30年かかるというでありましょう。個々別々に立場を主張されると、きりがありません。国全体の経済の隆盛を考えて、住宅問題を好転せしめたい。復興事業の重大性を考え、(建設院を)内閣直属の外局に置くのでありまして、内閣総理大臣の責任においてその発展を期したい」。角栄は「建設院」の位置づけに切り込み、厖大な建設事業に立ち向かわねばならない建設院が、内閣の外局では心もとない。法律の文言を示し、建設院の責任者は国務大臣を充てよと次のように弁じている。
片山首相は、次のように答弁している。「私の考えは、そういう形式にとらわれないで、いままで官僚は形式にとらわれて外局だから軽くみたように思うが、重要な問題には十分力を入れて発展を期したい。この問題には、もう十分力をいれております」。 「総理大臣と一年生議員の討論は、どちらに軍配が上げられようか。建設行政の本質を押さえてひた押しに押してくる田中を、片山はもてあましたようだった」と評されている。 |
|||
| 経済安定本部の「河川総合開発調整審議会」が、日本発送電株式会社に委託して、只見川筋の調査に入る。この調査では、福島県側の本流案が打ち出される。 | ||||
| 角栄は、代議士1年生の時から、予算編成にも強い関心を持って目を光らし、バランスを重視していた。 |
| 1948(昭和23) 年、角栄30歳 |
| 2.10 | 【片山内閣総辞職】(社会党左右両派の内紛が原因)。 | ||
| 3.10 | 【芦田内閣成立】社会・民主・国民共同3党の連立政権。 | ||
| 3.12 | 【民主クラブを結成】幣原率いる同士クラブ28名は、斎藤隆夫派らの無所属議員8名を加えて36名で民主クラブを結成した。 | ||
| ◎一年生代議士の角栄が会計係を担当することになった。同時に民自党選挙部長及び新潟県支部幹事長に就任。この頃、田中土建工業の業績はすこぶる順調で新潟、長岡、福島、九州の福岡へ支社を持ち、資本金も500万円に増え、都内でも三本の指に入る有望会社に成長していた。その資金能力が期待され、会計係になったものと思われる。 | |||
| 4月 | 【昭和電工事件】大手化学肥料会社/昭和電工の社長が、政府の復興金融公庫の融資欲しさに政治家や官僚に賄賂をばらまいたとされる疑惑が持ち上がり一大騒動に発展する。 | ||
| 5月 | 【第一次保守合同】◎幣原率いる民主クラブ28名が、吉田茂が率いる日本自由党112名に合流、その他を加えて152名で民主自由党(総裁吉田茂、幹事長山崎猛)を結成。第一次保守合同と云われる。この時、民主クラブは日本自由党の僅か四分の一勢力でしかなかったが、吉田は対等合併の配慮を見せている。この民主自由党が大発展していくことになる。 角栄がこの合流劇に歩調を合わせた背景には、「社会主義は終わった。これから先は通らない。先の読めるのは保守党だ」、「偉くなるには大将の懐に入ることだ」との判断が働いていたと伝えられている。 |
||
| ◎田中は、党選挙部長、県支部幹事長の役を引き受ける。田中は、異能異才を発揮し、選挙事情を網羅した全国選挙地図を作成している。議員の生年月日、学歴、家族構成、人脈、資金力、選挙区の人口構成、有権者数、支持率、その地区の産業構造、所得水準、選挙参謀の動きまで調べ上げていた。全国の選挙区の情報、情勢がインプットされたことになる。 このデータ・ベースをもとに選挙戦略を定め、仲間の代議士に示唆していくのが大好評を博した。「選挙に経営の手法を取り入れたところが斬新だった」(三浦康之「頂きに立て!田中角栄とR・ニクソン)とある。 |
|||
| ◎この頃、角栄が30万円入りの紙封筒を持って同期議員たちに挨拶回りしている。 | |||
| 10.7 | 【芦田内閣崩壊】後継首相を廻ってあひるの水かき始まる。次期総裁は野党第一党の民主自由党(民自党)の総裁/吉田茂が就任するのが憲政の常道のところ、GHQの意向に必ずしもイエスマンしないのを嫌い、GHQ民政局のチャールズ・ルイス・ケーディスが民自党幹事長の山崎猛を首相にするよう指示する露骨な介入をして来た。これを受け、民自党内の反吉田派が山崎を首班担ぎ出しに画策し始めた。 | ||
| 10.13 | ◎10.10日、総務会が開かれ、GHQの筋書きによる山崎擁立に向けた議事が進行し吉田の総裁辞意表明が為されようとしていた。ところが、この時一年生議員田中角栄が「ちょっと待った。会長、発言を求めます」と立ち上がった。発言の認可を得た後、次のように主張した。
次のように続けた。
角栄は、山崎首班の流れが、従来のGHQと政府の手続きの手順と異なると指摘し、ケーディスの介入が個人的なものではないかと推理して見せ、吉田総裁の見解を仰ごうとした。ここから議論の流れが一変し、「吉田首班で行け!」、「GHQの遣り方は間違っている」という結論になった。角栄は、この時よりGHQより睨まれ、吉田茂には愛でられることになった。 |
||
| 10.19 | 【民主自由党の少数単独政権で第二次吉田内閣成立】角栄は、この時法務省政務次官になる。議院歴1年余の周りが羨む人事で、これまでの数ある功績と「総務会発言」が認められての論功行賞的抜擢であった。吉田首相の「あのチョビひげを生やした若いのを、どこかの政務次官にはめ込むように。チョンガリ(浪曲)風の声からしてなかなか宜しい‐‐‐そう、その田中君をだ、どこかの政務次官に起用してくれたまえ」と時の副総理・林譲治に命じ、ツルの一声で決まったと云われている。こうして弱冠29歳の角栄が法務政務次官に抜擢された。後日の判明で、幣原と池田セイヒン(池田成彬・三井財閥の大御所)の推薦もあったと伝えられている。
|
||
| 11.23 | ◎炭鉱国管法案の反対運動の際、百万円を収賄した疑惑が生じ、角栄の自宅、田中土建などが東京高等検察庁によって家宅捜査を受ける。 | ||
| 11.24 | ◎角栄が、法務省の記者団に次のように弁明する。
|
||
| 11.27 | ◎田中土建工業を取り仕切っていた「刎頚の友」入内島金一が逮捕された。 | ||
| 11.28 | ◎法務政務次官を辞任。 | ||
| 12.12 | ◎衆議院運営委員会が11対7で、角栄の逮捕許諾請求を可決、本会議も承認する。 | ||
| 12.13 | ◎次官就任後二ヶ月足らずで、炭鉱国管疑獄事件で業者から100万円(現在の4千万円相当)受け取った疑いで、他の2名の代議士と共に逮捕される。 GHQの差し金説もある。片山内閣が炭鉱国有化を狙って提出した臨時石炭管理法案を廻って議会は紛糾。田中はこの法案に反対する急先鋒となったのはいいが、業者から百万円を収賄した容疑をかけられ逮捕された。しかし、田中は百万円の受領事実は認めたものの、賄賂としてのそれではなく工事請負代金として受け取ったと主張し争った。逮捕前の弁として「心境は悠々たり、天地のごとしだ。容疑の点には反証があり、業者からの小切手、百万円は事業の金だ」。 角栄は、取調べの検事に対し、次のように弁明している。
弁護士正木亮氏も動き、後無罪となる。 |
||
| 12.22 | ◎角栄、収賄罪で起訴される。角栄は、次のようにタンカを切っている。
|
||
| 12.23 | 【衆院解散】内閣不信任案が可決され衆院解散。角栄は、総選挙告示と同時に小菅刑務所から獄中立候補。秘書の曳田照治が立候補届を出す。「ギカイ カイサンス タノム タナカカクエイ」の電報を主な後援者に届けた。しかし、立候補声明は出したものの保釈決定がおりず、やきもきさせられた。秘書の曳田照治が走り回ってようやく保釈許可を得た。 | ||
| 商工大臣公邸での「尾瀬・只見・利根総合開発調査懇談会」席上で、新潟県土木部長が、分流案を提起する。 |
| 1949(昭和24) 年、角栄31歳 |
| 1.13 | ◎選挙戦最中の投票日まで残り10日のこの日保釈となった。GHQから保釈取り消しの強い要請があったが、小林裁判長は、「判決の宣告までは無罪なのだから、政治家は選挙で死命を制せられるべきだ」としてハネつけた逸話が遺されている。 秘書の曳田と二人で上野から選挙区の魚沼郡六日町へ向かう。既に、選挙は後半戦に入っていた。この時、田中土建工業の経営が悪化していた。信濃川の護岸工事を請け負っていたが、インフレで資材が値上がりし、土木作業員への給金も支払えないほど経理が窮迫していた。役員の一人であった入内島氏より、概要「金は全てはたいても30万円しかない。これで選挙はできるだろうが、使ってしまうと田中土建は潰れる。選挙を取るのか、田中土建を取るのか」と迫られている。田中は、政治の世界を選んだ。 この時の角栄の様子が次のように伝えられている。
増田氏の「伝説の角栄」は次のように記している。
この時、吹雪の中を可能な限り駆け回った。小千谷の立会演説会の時には吹雪で上越線が不通となった。角栄は他の候補者が思いとどまる中を鉄橋伝いに片貝町まで足を運び、演説会場へ向かった逸話が伝えられている。1.18日付けの朝日新聞記事は次の通り。
なお、この時会場の雰囲気に合わせて、浪花節をうなり、それが受けに受けたとも伝えられている。角栄は、各地の演説会場で次のように熱弁した。
この時、「あのもんだいはどしたッ」のヤジに、当初は防戦に追われていたが、聴衆の「チョンガリ(浪曲)でも聞かせてくれ」の声援にこたえて浪曲浪花節の一席で切り替え、特に「杉野兵曹長の妻」の一席が大いに受けた、とも伝えられている。 |
||||||
| 1.23 | 【第24回総選挙】角栄は得票数4万2536票を獲得し2位当選。逆境の選挙であったにも関わらず順位も獲得投票数も上げたことになる(前回票に3500票上積み)。旦四郎(民自前)56570票、田中角栄(民自前)42536票、稲村順三(社会前)32492票、小林進(革新新)30611票、丸山直友(民自新)30386票。 この選挙後、官僚出身者と党人を混交させたいわゆる吉田学校が急速に勢力を増していくことになる。池田隼人や佐藤栄作氏が初当選。田中は政界2年ほどのこの頃連絡将校のような働きを見せていくことになる。この選挙で、新潟4区から田中彰治が当選。以降『爆弾男』の異名をとる議員活動に向かう。 ◎建設委員、決算委員を務める。 ◎鈴木善幸が、48.1月「全農派有志議員クラブ」→同2月「革新新党準備会」→同3月「社会革新党」を経て、選挙後に民自党に入党。 |
||||||
| 2.16 | 【2.11日、第二次吉田内閣が総辞職】、【2.16日、第三次吉田内閣が組閣】。この時池田隼人蔵相、増田甲子七を官房長官に抜擢した。民主党連立派から2名入閣。単独政権の基礎を築くことに成功した。 池田隼人は47年に石橋湛山蔵相の抜擢で大蔵省主税局長から事務次官に抜擢され、このたびの選挙で初当選したが、いきなり蔵相に抜擢されたことになる。これには田中角栄、吉田の娘婿浅生太賀吉、根本龍太郎の「池田さんこそ、適任ではないでしょうか」の後押しがあったことが判明している。池田は認証式のあと「政界に出て、一番最初に狩を受けたのは、きみだ。君への感謝は忘れない」と角栄に言ったことが伝えられている。 この時より官僚政治家の登場となる。主なメンバーは、池田隼人(大蔵次官).佐藤栄作(運輸次官)、岡崎勝男(外相次官)、増田甲子七(北海道長官)、大橋武夫(戦災復興院次長)、前尾繁三郎(造幣局長)、西村直己(高知県知事)、遠藤三郎(農林省総務課長)、坂田英一(食糧配給公団総裁)、福田篤泰(総領事)、吉武恵市(労働次官)らであった。 |
||||||
| 2.19 | ◎建設常任委員になる。 | ||||||
| 5.13 | ◎炭管事件初公判。 | ||||||
| 5.16 | ◎建設委員会理事になる。 | ||||||
| 9.15 | ◎建設委員会地方総合開発小委員長に就任。この頃議員立法活動に専念。これについては「議員立法」に詳述する。 | ||||||
| 10.1 | 【中華人民共和国成立】 | ||||||
| 10.24 | ◎建設委員会で、地方総合開発小委員会報告を行い、この報告がわが国の国土総合開発の基本構想となる。 | ||||||
| 10.28 | ◎決算委員会理事になる。 | ||||||
| 政府が、「アメリカの海外技術調査団OCIに調査を依頼。調査結果、翌年に本流案全面支持を打ち出す。 |