| 「こうして9000キロメートル以上にわたる全国新幹線鉄道網が実現すれば、日本列島の拠点都市はそれぞれが1〜3時間の圏内にはいり、拠点都市どうしが事実上、一体化する。新潟市内は東京都内と同じになり、富山市内と同様になる。松江市内は高知や岡山などの市内と同様になり大阪市内と同じになる」。 |
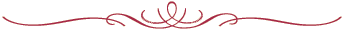
| 【建設省関係】 | 議員立法 |
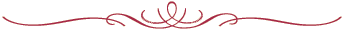
(最新見直し2011.04.30日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 日本の法律の多くは内閣立法であり、官僚が法案を作成している。このため、日本の国会は立法府としての機能を十分に果たしておらず、三権分立という民主主義の根幹に問題をかかえている。このことに照らすと、角栄の議員立法歴には瞠目すべきものがある。 角栄は、1947(昭和22)年の初当選後、戦後復興関連の議員立法に執念を燃やした。自ら提出者として成立させた議員立法は、初当選からの10年間に25法、42年間の議員生活を通じて実に33法、同僚議員との共同提出や協力して成立させた関連立法は84法、直接、間接に作成した法律は100件以上を数えている。この記録は前代未聞であり、凡百の政治家の真似できないところである。この記録は今後も破られそうにない。 角栄は、土木建築畑出身の専門性を発揮し、建築士法、住宅金融公庫法、公営住宅法を手始めにダム法、道路法、港湾法、河川法へ向う。次に、高速道路法、新幹線整備法、地域開発法へ向かい、次第に国土総合開発という観点からの必要事業を手掛けて行き、数多くの実績を残していることが分かる。同じ議員立法でも、最近のそれはちまちましており、国家百年の計に資するものがどうか判然としないものが多い。その点で、角栄の公共事業関係議員立法による一連の社会基盤整備が、昭和30年代から40年代へかけての高度経済成長の基盤となり、国富増進に資したことは疑いない。 その角栄は後に、金権利権土建屋政治家として批判を浴びせられることになった。しかし、角栄が手掛けた以下の議員立法に通暁すれば、角栄が私利私欲の為に働いた訳ではないことが判明しよう。これを論より証拠と云う。しかるに日共系、立花系は何を論拠としてか悪徳政治家呼ばわりして、角栄の政治的業績を葬ってきた。今や、このことを批判的に総括する必要があろう。 角栄は、これら全ての業績を集約する形で日本列島改造案まで進む。そこには国土の均衡的発展を要とする国家百年の計があった。昭和40年代後半からクローズアップされてきた公害、環境問題への対策が甘かった欠点は有るが、角栄健在なら必ずや更なる叡智を発揮していただろう。 しかし如何せん、例の批判合唱から始まるロッキード疑獄により手かせ足かせを嵌められ、国政関与ができなくされてしまった。以降の日本の舵取りは、それまで蓄えられた国富の食い潰し政策であり、まともな指針を打ち出すことが皆無となった。今日、公共事業が目の仇にされ、与野党マスコミ問わずそれを合唱している様は、国家が自分の首を絞めて恍惚の法悦している愚に似ている。 2005.9.7日、2009..6.20日再編集 れんだいこ拝 |
| 【角栄の議員立法考】 | ||||||||||||
|
角栄が議員立法として成立させた法案は33件にのぼり、この抜群の記録はいまだに破られていない。そして、その法案の多くは「生活関連及び国土開発とその為の特殊法人」に関するものである。角栄は数多くの議員立法を手がけた不世出の異能政治家であったことになる。 これにつき、増山榮太郎氏は「角栄伝説」の中で次のように述べている。
云うは易く行いは難しい。議員立法には、超人的な勉強と卓越した能力が必要とされる。関連法規全てを熟知し、その地平に立って新たな法律を作らなければならない。もしそれが的外れであったり、穴だらけのザルであったなら、第一役人達が横を向いてしまう。役人を納得させ、あたうならば協力させ、手伝わせる手腕が必要とされる。加えて責任を取る者でなければついて来ない。角栄は非常なる勉強家であったし、それらの能力を発揮したからこそ数々の議員立法が可能となった。
「文芸春秋」(昭和56.2月号)での田原総一朗氏のインタビューに次のように応えているのも注目される。
角栄は、昭和44年組当選議員(小沢・羽田・梶山ら)の祝いの会での挨拶で次のように述べている。
田中は、後になって田中派の若い議員が来るたびに、地方のことは地方議員に任せればよい、君達は立法府の議員なのだから議員立法に取り組みなさいと勧めている。佐藤昭子は次のようにコメントしている。
猪瀬直樹氏の「死者達のロッキード事件」より引用する。
かく本人の述べるように、角栄は初当選からの10年間に25法の議員立法を実現、42年間の議員生活を通じて33法、生涯に陽の目を見させた議員立法は72件、直接、間接に作成した法律は100件以上という空前の業績を為している。事実、後にも先にも出ない、不世出の記録保持者となっている。
早坂茂三氏も次のように云う。
この一連の議員立法が後の公共事業(道路、港湾、鉄道、住宅)の法的根幹になっていく。つまり骨格作りとなった。角栄のこうした裏方的社会基盤整備に向けた国土開発は、池田首相の高度経済成長路線と相まって車の両輪の如く日本経済を発展させていくことになった。
|
| 【田中角栄の議員立法及び傾注立法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角栄以前の立法として、1945(昭和20)年、国土計画基本方針、1946(昭和21)年、復興国土計画要綱、1947(昭和22)年、国土計画審議会が策定されている。 *印は、議員立法ではないが、角栄の関与、目配りのある法律、事項である。主として、「治山、治水、治雪」を念頭に具体的には住宅、道路、港湾、ダム、新幹線、都市開発に努力傾注していったことが分かる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【住宅法について】 |
| 「住宅公団10年史」(昭和40年刊)には次のように記されている。「戦争は日本の多くの都市に、壊滅的な破壊をもたらしたところで終結した。210万戸の住宅が失われ、しかも復員や海外からの引き揚げで64万戸ほどの世帯が増加し、住宅不足は420万戸に達すると云われた。住宅の状況は絶望的であった」。 |
| 【河川法一部改正について】 |
| 旧河川法では、橋も鉄橋も仮設物としてしか認可されていない為、国が堤防のカサ上げをする河川工事の際には、仮設物設置者の費用負担で一緒に位置を上げねばならなかった。それを「河川の所有者である国が負担する」ことにした。 |
| 【全国総合開発計画(「全総」)について】 |
| 1950年、国土総合開発法が制定されている。内閣提案の形をとっているが、角栄の議員立法であった。後に日本列島改造論を唱えることになるが、その淵源はこの議員立法時代に発している。国土審議会が設置され、建設省の最高幹部・下河辺淳が会長となり審議を指揮することになる。 当初は、特定地域の開発計画の策定、推進に重点がおかれていた。これが後に文字通りの全国レベルの国土総合開発に発展する。1954(昭和29)年、経済審議庁計画部から国土総合開発法に基づく全国総合開発計画として「総合開発の構想(案)」が発表され、目標年次を1965(昭和40)年としていた。1960(昭和35)年、池田内閣は「国民所得倍増計画」を策定。この中で太平洋ベルト地域の工業開発を重視した「太平洋ベルト地帯構想」が打ち出された。1961(昭和36).6月、通商産業省が工業適正配置構想を示し、続いて「地域間の均衡ある発展」を図ることを目標とした「全国総合開発計画」の草案が閣議了解され、1962(昭和37).10月、正式に閣議了解された。これにより、1965(昭和40)年から始まるとされていた第一次全国総合開発計画(略称「全総」)が前倒しで実施されることになった。これが第1回目の全国総合開発計画となる。1970年まで続いた。 以下、第2次全国総合開発計画(略称「新全総」)が1969(昭和44)年、佐藤内閣の時、130兆~170兆円規模で策定された。1985年まで続いた。第3次全国総合開発計画(略称「三全総」)が1977(昭和52)年、福田内閣の時、370兆円規模で策定された。1987年まで続いた。この頃までは国土総合開発法の精神が正しく律されていた。ところが、第4次全国総合開発計画(略称「四全総」)が1987(昭和62)年、中曽根内閣の時、1千兆円規模で策定された。この大盤政策はそれまでの有益型公共事業を不要不急型公共事業へと変質せしめて行った。2000年まで続いた。第5次全国総合開発計画(略称「五全総」)が1998(平成10)年、橋本内閣の時、「21世紀の国土のグランドデザイン」と銘して実施された。投資総額は示されなかった。 |
|
2005(平成17).7.29日、国土総合開発法が改正され国土形成計画法(平成17年7月29日法律第89号)に転換する。同法は「開発中心主義からの転換」を主眼としており、ここれにより過去5回実施された全国総合開発計画(全総計画)が終焉させられた。これに代わる新しい国土形成計画の全国計画が2007年にも決定される予定であったが、音沙汰なしとなっている。 |
| 【電源開発促進法について】 |
| 1951年、火力や水力の発電施設を整備する為の電源開発促進法を議員立法している。 |
| 【道路法について】 | |||||||||||||
|
角栄は、電源開発促進法の後、道路法の議員立法に向かった。次のように述べている。
角栄は、「道路三法」と呼ばれる1・道路法、2・ガソリン税法、3・有料道路法の制定に孤軍奮闘した。角栄は、道路網整備に於いて誰も考えないことを考え、実行するアイデアマンでもあった。
角栄は衆院建設委員会の「道路に関する小委員会」小委員長に就いて「道路法」抜本改正の議員立法に取り組んだ。
4月、角栄は他の二人の議員とはかって旧道路法の全面改正による戦後道路行政の骨格を決める「新道路法」を提案、委員会答弁まで引き受け、この年6.10日に公布させた。その第1条には、「この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する
ことを目的とする」と記した。国道を1級国道と2級国道に分けた。道路建設の決定に大臣だけでなく道路審議会を関わらせることにした。地方からの陳情をきき易くする仕組みでもあった。
ヴァーチュアス・サイクル(好循環)の受益者負担論を畳み掛けて、運輸・石油業界を黙らせてしまった。
田中は、井上の報告に膝を叩いた。 1952(昭和27).12月、第15回国会に、田中は他の25人の議員とはかって、ガソリン税法を議員立法で提案した。百日間にわたる長期論議が行われたが、結局、このときの提案は衆議院は通過したものの、参議院で野党と大蔵側委員の強い反対論がある中での審議中、いわゆる「バカヤロー解散」で審議未了になった。
この時の相手の一人として後の民社党委員長・春日一幸氏と角栄の遣り取りが、小林吉弥氏の著作「角栄一代」(77P)に記載されている。角栄は、局面が困難になると、大蔵省に乗り込んでいき、「君達、日本再建の基礎は、道路だ。頼むぞ」と大蔵官僚に根回ししていった。
1956(昭和31)年、建設省が日本に高速道路を建設するため世界銀行から招聘したワトキンス調査団が訪日し、次のように指摘した。
当時の日本の道路は道幅が狭く舗装されておらず、世界的水準から見れば以上なほど遅れていた。
同時に、田中角栄はこの経過で昭和23年に独立して間がない新興官庁たる建設省に、政治家としての大きな拠点をつくることになった。法案成立の過程で若手の建設官僚とともに知恵をかき汗を流すことで、誼を通じることとなった。この当時の若手建設官僚たちは、以後長く「政治家田中」に一目置くことになり、信奉する者も生まれることになった。
ちなみに2002年のガソリン税の総額は5兆5千億円である。防衛費の2倍をこえている。しかもこれは国の正規の予算ではなく、すべて特別会計である。これに一般会計の公共事業費が加わる。角栄失脚後の政治は角栄の政治歴史哲学を欠き、土建利権性に目を着け群がることになった。
こうして手掛けられた道路行政が、角栄亡き後、冬の季節を迎えることになる。これより以下は、「民営化考」で考察する。 |
|||||||||||||
| (「2003年度近畿大学法学部卒業論文」所収の黒瀬侑・氏の「角栄の功と罪」参照) 2007.2.3日 れんだいこ拝 |
|||||||||||||
山崎オンラインの「榊原英資スピーチ」に気になる記述があるので批判しておく。ここで榊原氏は、有料化制で高速道路網を整備して行った田中角栄方式に対して次のように批判している。
この一語で、榊原英資なるものの本質的粗脳さが分かる。本来であれば、論の流れは、有料化制で高速道路網を整備して行った田中角栄方式を批判するのであれば、それに代わる方式を対置せねばならない。これをせぬままに山崎式無料化論を持ち上げている。高速道路無料化の意義を説くのに、田中角栄方式批判を介在させる必要はない。時期と次元の違うものを対比させ、わざわざ田中角栄方式を批判している。癖のある御仁だと云うことになる。 どういう必要で田中角栄方式批判を持ち出したのか意図不明であるが、その上で次のような正論を説いている。これを転載しておく。
これは正論である。かく正論を述べたうえで、次のように角栄批判をしてスピーチを終えている。
山崎式無料化論を支持する為に何の因果で「田中角栄が作った奇妙な土建国家にいつまでも浸っているのか。それが今度の無料化VS民営化論」で云うのかが意図不明である。普通には、「中曽根-小泉式民営化論にいつまでも浸っているのか。それが今度の無料化VS民営化論」とすべきところを意図的故意に角栄批判にすり替えている。マジに云っているのだとすれば精神分裂気味の御仁と云うことになる。こうい御仁に国政の要職を任せられる訳がない。 2011.1.22日 れんだいこ拝 |
| 【新幹線整備計画】 | |||
角栄は、高速道路の普及に歩調を合わせて新幹線の整備行政をも推進している。議員立法ではないが大いに旗振り役を演じていた。これについては資料を入手し大論証するものとする。その新幹線整備計画は次の通り。
|
| 【水資源開発促進法】 | |
| 角栄は、日本に於ける水資源の重要性を認識し、「利用者負担の原則」を打ち出して、水資源開発促進法から水資源開発公団法、治水特別会計法に取り組んだ。水資源開発促進法は、昭和36年に、角栄自身が衆院水資源開発と区別委員長になり、建設、通産、農林、運輸など、各省の縄張り争いを苦労して調整し、纏めた。 治水特別会計法創設の際には、大蔵省が「特定の財源を持たない特別会計は、財政法によって作ることが出来ない」と反対した。角栄はこれに対して、「水は最大の財源だ。水の使用者が利水料を払うべきだ。ただ農業だけは既得権があるから免除するだけだ」という論法で、説得に成功した。 角栄は次のように述べている。
|
| 【小泉政治の「角栄政治破壊」考】 |
| 小泉改革で廃止が決定している「日本道路公団」、「首都高速道路公団」、「日本鉄道建設公団」、「日本住宅公団」、「本州四国連絡橋公団」など、すべて角栄が成立させたものだ。小泉政治は、意図的に角栄政治の遺産を壊し続けている。 小泉政治は何故に角栄政治の遺産を壊し続けているのか、これを考察せねばならない。 2005.10.30日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)