*ツィッターなどに発表した文章を書き直したものです。このHPが初出です。
11月8日夜、「2013年川口大三郎さんを偲ぶ会」が東京都・自由が丘・オカランズでありました。川口大三郎さんといっても知っている人は、今ではわずかでしょう。川口大三郎さんは、1972年11月8日、革マル派という集団が支配していた早大一文(第一文学部)学生自治会執行部によってリンチ殺害された早大一文学生です。当時、自治会執行部が自治会員を殺したということで、非常に大規模な自治会再建運動が起こり、多くの学生が反革マル自治会再建に立ち上がりました。しかし、内部対立や革マルの反撃などで、運動は約一年後に収束しました。
昨年は逝去40年で全早大規模での偲ぶ会が開かれたそうですが、これには私は参加していません。昨年の会は人数も多く、必ずしも参加者の話をじっくり聞く雰囲気では無かったので、今年は一文だけの会を企画したとのことです。当時、私も運動に参加していたので、案内が届きました。
参加者は当時の再建自治会委員長樋田毅さんはじめ20名あまりでした。会は午後6時から始まり、全員がそれぞれの思い、その後の人生を語りました。20数名全員が語り終わったところで午後9時になり、会は終わりました。(樋田さんの名前を出すことは、本人の了承を得ています)
多くの人が、川口君事件は自己の一生を決めたでき事だと語りました。私にとってもそうです。さまざまな思いが参加者から語られました。あれはプラハの春のような民主化運動だった、四十年たっても、まだあの運動の意味を総括しきれない、総括しきれなくてもいい、一生思い続けていきたい等々。
会では、さまざまな人の消息も伝えられました。事件当時私と親しかったK君が昨年12月うつ病で自殺したことを知って、衝撃を受けました。会自体はたいへんよかったと思います。幹事さんご苦労様でした。
次は、当日の私の発言の一部。
川口君事件は私にとってもその後の人生を決定した出来事でした。私の政治的立場は、その後あまり変わっていない。事件との問題意識でいうと、辻元清美代議士が2003年に不当逮捕されたことがありました。その時、「辻元清美さんら四人の不当逮捕に抗議する有志の会」というHPをK君(自殺したK君とは別人)らと立ち上げました。HPに管理者名はないが、作成・管理は私です。当時の同種のHPはほとんど消滅しましたが、このHPは記録のため今も残してあります。
http://homepage3.nifty.com/tujimoto/
川口君事件の経過などは、正しく伝えられていないと思います。鴻上尚史という劇作家が数年前に『ヘルメットをかぶった君に会いたい』という事件と関連する小説を書きました。内容は、川口君事件で指名手配された革マル女性活動家の初々しかった頃の映像を彼がみて、その女性を探すというものです。鴻上尚史自身が匿名で2ちゃんねるにスレッドを立ち上げ、情報集めをしました鴻上尚史が川口君事件にあまりに無知で、その態度にも安易さが感じられたため、私も彼のスレッドに多少書き込みをしました。『ヘルメットをかぶった君に会いたい』に、このスレッドの書き込みが一つだけ載っていますが、あれは私が書いたものです。
事件当時、私を一番殴ったのは(革マル)一文自治会副委員長のO(会では実名)でした。そのOはいまでは×××(会では名を言う)の筆名で少しは知られた評論家です。暴露してやろうかとも思いましたが、本人が言うべきことだからと思いとどまっています。(Oのことはかなりの参加者も知っていて、彼のことで会は盛り上がりました。)
ここから後は、私のその後の感想です。川口君事件の総括をする前に、まず事実関係の資料集めをしなければならないと思います。事件の資料集を作りたいが、そのためにはまず川口君の墓参りをしてから、という気持ちがありました。しかし、お墓の場所がわかりません。幸い、当日川口君と同じクラスの参加者がいて、お墓の正確な場所を教えて貰えることになりました。虐殺反対という運動の初心を失わないためにも、墓参りから始めなければならないと思っています。
会では、参加者の多くが、今でも革マルは絶対に許せない、と語りました。私も、1990年代ぐらいまではそういう気持ちでした。しかしここ数年は変わってきました。
私は中国研究が職業ですが、殴られたから、殺されたから絶対許せない、では日中関係は成り立たちません。中国研究では私は殺した側(の子孫)だから許す許さないの問題は日本側から言い出すことではないと思い触れませんが、事件について言えば、ある一定の段階で革マルもある種の犠牲者だったと許すことは必要だと思います。しかしそのためには何をしなければならないでしょうか。
私は現在、社会主義理論学会の役員もしています。研究集会などに革マル系の出版社こぶし書房が時々出店に来ます。友好的に対応しているつもりです。厳しい出版事情の中彼らも苦労していると思い、意味があると私が思うこぶしの本は摂南大学の図書館に入れています。私なりのささやかな実践です。
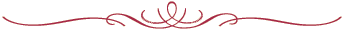
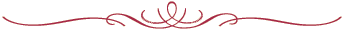
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)