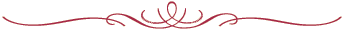
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.11.22日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「れんだいこの川口大三郎君虐殺事件考その2」を記しておく。
2022年.11.22日 れんだいこ拝 |
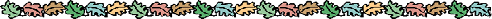
「「川口大三郎君リンチ虐殺事件」考その1」へ続く。
(「「川口大三郎君リンチ虐殺事件」考その1」)
| 【反革マル派連合「早大行動委」が結成される】 |
「早大行動委」結成のための情宣活動資料は次の通り。
| 全学行動委員会連合準備会情宣部/行動委通信「1.8集会に総結集せよ」。 |
| 早大全学行動委員会連合(準)「1.8集会貫徹!文学部キャンパス解放!」。 |
| 一文自治会臨時執行部「戦闘宣言 1.8総決起-文学部解放を克ち取れ!-早大管理支配体制を解体せよ!」。 |
|
| 1973.1.7日、全学前段階総決起集会。 |
| 1.8日、年明けのこの日、前年来相次いで結成された各学部の自治会代表者が勢揃いした全学自治会総決起集会が開かれ、反革マル派連合の「全学行動委員会」(早大行動委)が結成される。一文行動委他約100名が初めて黒ヘルメットを着用して「端緒的な自衛武装を開始した」。以降、黒ヘルを着用する。この段階の早大行動委は革マル派の角材と投石に対して素手で立ち向かっている。自衛武装がやや拡大されて6月段階の二連協の自制した武装論に繋がる。素手で角材や投石と闘う中で多数の負傷者を出しながら、否応なく反暴力を拒否しつつ自衛武装の地平に立ち至った。 |
| 日付なし、一文行動委員会連合(準)「1.8集会の成果にふまえ1.12団交要求集会を準備せよ!」。 |
| 日付なし、二文有志「革マル派の敵対を粉砕し、団交に勝利せよ!」。 |
| 【反革マル派セクトが次々と登場し始める】
|
| この頃、かつて政経学部を拠点としており、革マル派との党派闘争に敗れ追放され、この当時、神奈川大学を拠点としていた社青同解放派、ブントが革マル派追及の波に乗じてキャンパスに登場するようになり、革マル派との本格的抗争に入り
WAC(早大行動委員会)に助太刀する。中核派のレポも頻繁に登場していたが高田馬場駅前集会までが限度でキャンパス登場はしていない。 |
| 【民青同の行動が急速に沈静化する】 |
| 川口君事件当時、7自治会が存在し、その内の6を革マル派、1を民青同(法学部自治会)が握っていた。川口君事件以降、民青同は革マル派追放の闘いに共同してきていた。しかし、全学行動委員会(早大行動委)が結成された頃から、民青同の革マル派糾弾運動が潮を引き始めた。 |
 (私論.私見) 「民青同の戦線撤退」について (私論.私見) 「民青同の戦線撤退」について |
これも奇怪な動きであった。れんだいこの知り得た情報(確か風邪で病院に出向いた際、当時の早大民青同幹部と偶然に待合室で出会い、その時の手振りを交えながらの直言である)によると、「上からの指示で手を引くことになった」と云う。民青同が運動から引くことにより早大行動委が裸になり、結果的に「早大解放の闘い」が挫折することになる。
この現象を如何に見るべきか。共産党中央指示は、結果的に革マル派の窮地を救ったことになる。共産党中央は、早大が学生運動のメッカになるよりは革マルの暴力支配による他党派締め出しの方を良しとしていたことになる。これが裏の実態であったことになる。れんだいこの日共批判は、この時の動きの変調さ等々から下地が醸成されている。 |
| 【早大行動委が各学部自治会の奪権運動に取り組み始める】 |
| 1.11日、政経学部、学部団交。 |
| 1.12日、団交要求集会。 |
| 1.13日、一文で、一文自治会臨時執行部、選挙管理委員会、クラス連絡協議会の連名でクラス自治委員選挙が告示された。臨時執行部側が約100名の隊列を編成して、革マル派のバリケード突破し、選挙会場を確保しクラス委員を選出していった。。 |
|
自治委員選挙を開始した際、一文自治会臨時執行部派は文学部キャンパスのスロープ上で革マル派を実力で突破して、裏山手前にあった木造校舎を占拠して、選挙の場を確保した。革マル派より人数が圧倒的に多かったから可能であった訳で、且つ自制的であれ実力行使で「暴力」を使っていた。革マル派はそれを総括して17日には角材や投石用の石を用意し、屋上から机すら投げ落とそうとした。これに抗するのに「暴力反対」と言うだけでは、日々進行するこの状況の深刻さを止められなかった。
|
| 1.14日、各学部の自治会委員選挙で小ぜり合い。 |
| 1.16日、政経学部で学部団交。800名の政経学部学生と学部による初団交が大隈講堂で開かれた。学部当局は、反革マルの自治会(学生5500人)が学生の総意により組織されたものとは認めないと突っぱねた。 |
| 【革マル派の反攻とテロにより「早大行動委」の負傷者が続出し始める】 |
| 1.17日、一文で革マル派の自治委員総会。それに対抗した「早大行動委」部隊が革マル派と二度にわたって衝突し、十数名が負傷する。 |
この時、「暴力への視座」と云う自省のビラが残されており、「戦術上の必要最小限の自制された暴力」は使うとある。「自己絶対化しない暴力」として位置づけていた。「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年1月17日」の「暴力への視座」と云うビラが次のように主張している。
| 我々は一貫して戦術上我々の方針を貫徹するのに必要最小限の暴力を使ってきたのであり、文学部に我々が入るのを阻止しようとした革マルに対しても、文学部内に統一選挙場を獲得するという目的に合致しないといって、個人レベルでの革マルとの殴り合いは避けてきた。これは我々の目的意識をもった最小限の暴力という原則を貫いたものであり、宗教的な非暴力ではないし、個人的な怒りを即、物理力としての暴力に結びつけるという革マル派諸君がどっぷりと浸った安易な発想(敵に対して何を行なっても良い)とは無縁のものであった。満身の怒りを持ちつつ、それを個人の怒りから止揚し、目的意識を明確にして行使された暴力であった。我々は一貫して思想の違いを認めつつ運動してきたのであり、革マルに対しても戦術上の暴力以上の暴力、つまり革マルだから殴るなどというようなことはありえず、大衆の面前(決して密室などではなく)における自己批判以外は行なわない。もしこの原則を貫ければ我々は川口君を虐殺した革マルの『思想の異なる人間に対して自己又は自己の党派を絶対化した上で罰する』という発想法を乗りこえられるだろう。もしそうでないなら単なる腕力の強弱に終ってしまうだろう。 |
|
1.17日、期末試験混乱。早大政経学部の団交決裂。
| 【大学当局が文学部ロックアウトで革マル派の窮地救出】 |
| 1.18日、文学部、ロックアウト。これに抗議する「早大行動委」などが機動隊と衝突、1名逮捕される。 |
| 【中核派700名が本部正門突入を図るが機動隊-革マル派連合に阻止される】 |
1.18日夕刻、中核派700名がキャンパス内の革マル派350名目がけて本部正門突入を図り、本部キャンパスに入ろうとしたものの多くが逮捕され、残った約200名ほどが本部正門から突入、革マル派大部隊に襲われ敗走した。それ以降、中核派は早稲田大学に登場していない。
直後、中核派が機関紙前進で、「わが部隊は地下鉄早稲田駅から本部キャンパスに向かう途中、機動隊に阻まれ、多数が逮捕された。本部キャンパスにたどり着けた者はわずかだった」として「KK連合」(革マルと警察の連合)非難を開始した。読売記事「早大でも乱闘騒ぎ」その他を参照すれば、「中核派60名(うち女性11名)が凶器準備集合罪、公務執行妨害で逮捕、革マル派逮捕者なし」としている。 |
| 【「早大行動委」が革マル派と武闘、追い詰める】 |
 |
| 1.19日、この日、革マル派の文連総会、政経学部の学生大会が開かれようとしていた。午後3時40分、黒ヘル(11・8行動委など)60名は革マル派が3号館で開いていた文化団体連合会総会に乱入しようとし、3千名の一般学生も革マル派に出て行けと投石、革マル派は旗竿で逆襲しようとしたが、一般学生と黒ヘルに蹴散らされ、商学部11号館に追いつめられた革マル派が投石などで対抗した。そこへ鉄パイプで武装した革マル派が学外から応援に現れて、11号館から出て来た革マル派と合流し、行動委員会や他の学生たちに襲い掛かった。約30分間にわたる乱闘で負傷者が続出した。この時、政経学部の紙谷君(20歳)が革マル派によって投げられた重い物で頭蓋骨陥没骨折の重傷。その後の乱闘でも30数名が負傷した。 |
| 【「早大行動委」と革マル派とのゲバルトが続く】 |
| 1.19日、早大全学行動委員会連合(準)「危篤一名、病院収容者35名 革マル派ノンヘルテロ部隊、闘う学生を鉄パイプで無差別に襲う!!」。 |
|
1.20日頃、一文行動委(準)「革マルの宗派的戒厳令を突破し、闘いの巨大な前進を!」。 |
| その後も「早大行動委」と革マル派とのゲバルトが続く。 |
| 革マル・ノンヘルテロ部隊が2J生などを襲撃する。 |
| 【大学当局が本部キャンパス全学ロックアウト措置に入る】 |
| 1.20日、大学当局が理工学部をのぞき全学ロックアウトに転じた。この措置が、非勢の革マル派に息継ぎを与えることになった。且つ施設管理権で排除されたのはいつも「早大行動委」側で、革マル派の全国動員精鋭武装部隊は学生会館から排除されなかった。その学内集会は許可され機動隊が常にそれを守った。大学当局が革マル派の武力支配を温存し活用した形跡が認められる。 |
1.21日、読売新聞が次のように発信している。
| 第一次早大騒動の時に阿部賢一元総長が示した紛争解決に対する熱意と努力が、いまこそ大学当局に必要だろう。 |
|
| 【厳戒の中、期末試験実施へ。政経学部の混乱が続き試験中止】 |
| 1.21日、早大緊急会議が開催され機動隊要請。厳戒の中、期末試験実施へ。 |
| 1.22日、政経学部の期末試験がスタートしたが、反革マル派の学生が政経学部で団交を要求してバリケードを作り、朝から追及集会。大学は機動隊を導入、15名逮捕。政経学部の試験は中止され、メドたたずの事態となった。 |
| 【この頃のビラ(日付なし)】 |
この頃、以下のビラ(日付なし)が配布されている。
| 一文臨時執行部「規約改正委員会創出に向けて!」。 |
| 一文自治会臨時執行委員会「臨執声明」。 |
| 二文臨時執行部「二文の自治会員へ」(1.22二文学生大会への革マルの誹謗に対する反論)。 |
| 第一文学部臨時執行部「緊急アピール 全ての学友は1.23学生大会に結集せよ」。 |
| 全学行動委(準)「『個人テロはあたりまえだ・・』醜悪な居直りと敵対を繰り返す革マル糾弾!」。 |
| 山内武「後期試験をボイコットし百家争鳴・百花斉放の嵐を!」。 |
| 無署名「革マルは決して許されてはならぬ!」。 |
| 哲学科3年河田一「我々の運動と今後の方針について」。 |
| 無署名「分離試験を粉砕せよ!」。 |
| 早大<一一・八>抵抗運動「革マルは滅亡寸前だ!」。 |
| 4号館にタムロする有志「告発 死者を冒涜するクラ討連内樋田グループを告発する」。 |
| 四年有志「四年卒業を口実にした当局の闘争破壊を許すな!」。 |
| パルメザン四人組「犠牲の収斂!」。 |
| 学生運動と自治に関する有志会議「自治会を独占させないための具体的対策を!」。 |
| 1文2Hの反革マル宣言「我らが自治運動を語る」。 |
| 無署名「暴力への視点」。 |
| 無署名「革マルの川口君虐殺断固糾弾!」。 |
| 早稲田大学部落問題研究会「カクマルの川口君虐殺を糾弾せよ!」。 |
|
| 【「早大行動委」が各学部自治会の奪権闘争本格化に向かう】 |
| 1.23日、一文学生大会、1500名で開催。第一文学部学生自治会臨時執行委員会の議案書を採択し、期末試験を阻止する1週間ストライキを決定した。第一文学部学生自治会臨時執行委員会「1.23学生大会スローガン」。第一文学部学生自治会臨時執行委員会「試験強行阻止!スト貫徹! 1.23学生大会勝利万歳-自立した自治会運動の創出へ」。 |
| 1.23日、本部キャンパスが平穏化し、法、商学部が期末試験。 |
| 1.24日、一文行動委員会中心にピケスト突入。革マル派とこぜりあい。大学当局、試験延期。政経試験も延期。早大教育学部が反革マル系自治会を承認。 |
| 1.24日頃?、一文行動委連合(準)「革マルの敵対を粉砕し、ストライキ実行委の結成をもって、一週間ストを貫徹せよ!」。 |
| 日付なし、早大一文行動委員会「学生大会の勝利を真の勝利とする為に更なる闘いを準備せよ!」。 |
| 日付なし、一文自治会臨時執行部「1.26自治委員集会に結集しよう!」。 |
| 日付なし、一文選挙管理委・一文臨時執行委・一文クラス協議会「公示 新クラス委員選出=新執樹立に関する臨執決議」。 |
| 1.25日、一文で、臨時執行部が招集する学生大会が開催され、自治委員総会成立のための定足数(全学部生の5分の1)を大幅に突破する1542名が参加した。大会で、事前に公表していた暫定規約を賛成多数で採択した。正式な自治会規約については自治医院を中心としたクラス討論の積み上げによって決定していく方針も承認した。 |
| 1.25日、教育学部、学生大会。 |
| 1.26日早朝、革マル拠点などが捜索される。 |
| 1.26日、早大一文が30日まで試験中止。教育学部もストに突入。政経学部長らが混乱の責任をとり辞意。 |
| 1.27日、一文行動委員会「革マルの敵対を打破し自治委員会総会に勝利せよ!」。 |
| 【一文で自治委員総会が開催、投票で新執行部が選出】 |
| 1.27日、一文で、学生大会で採択された暫定規約の下で自治委員総会が開催された。一文自治会臨時執行委員会「1.27自治委員総会議案書」と会計報告(1973.1.27現在)、第一文学部自治会仮規約。各クラス、専修ごとに選出された65名の自治委員が勢揃いし、その投票で新執行部が選出された。臨時執行部委員長の1年J組の樋田毅/氏が委員長、1年J組のY、2年T組の野崎泰志/氏が副委員長、フランス文学専修3年の山田誠/氏が書記長に選出された。執行委員に日本文学専修3年の岩間輝生氏ほか。 |
| 【手配中の阿波崎、村上、佐竹の3名が事前通報逮捕される】 |
| 1.28日、手配中の阿波崎文雄、村上文男、佐竹実の3名が横須賀市の臨海公園「空母ミッドウェー寄港阻止集会」に参加のところ、革マル組織からの110番通報により横須賀署員が駆けつけて任意同行され、黙秘・指紋採取拒否のため、警視庁公安一課職員が確認して逮捕された。これでリンチ殺人犯人とされた5人全員が逮捕された。「歯ブラシなど身の回り品を持っており、前回と同じく計画的に逮捕されたもの」。
|
| 【「早大行動委」のその後の各学部自治会奪権闘争】 |
| 1.29日、一文、第二回学部団交。日付なし無署名「1.29学部団交(レジュメ)」。 |
| 1.29日、教育学部スト突入。政経学部が第2波1週間のストに突入。 |
| 日付なし、一文執行委員会「我々は断固主張する!」。 |
| 日付なし、2J行動委「一文解放を妨害し、レッテルはり、下宿テロを行なう「革マル派」を断固糾弾する!」。 |
| 1.30日、一文、学生大会。第二波の1週間スト可決。 |
| (資料)一文自治会執行委書記局「1.30学生大会議案書」。日付なし、一文自治会執行委員会「72年度最終自治委員総会議案書」。2Hクラス無署名「第二波一週間スト 新執行体制の強化確立」。一文自治会執行部書記局「あした早く起してお母さん!連日早朝ピケットに参加し、キャンパスを埋め尽くせ!」。 |
| 1.31日、社会科学部、学生大会。 |
| 1.31日、一文自治委員総会が開催され、試験無期延期、ストさらに続行。 |
| 1.31日、二文自治委員会総会成立。2.1日、無署名「1.31 二文自治委員会総会報告」。 |
| 【「早大行動委」系が次々学生大会、団交に漕ぎ着ける】 |
| 2.1日、一文学部で、学部団交。 |
| 2.1日、一文日本史専修行動委員会「カクマルまたも自主管理を破壊す」。 |
| 2.1日、LAC一文行動委連合「全学スト実を創出せよ」。 |
| 2.2日、一文自治会執行部書記局「『ソドムとゴモラ再び!』-抑圧の大伽藍を紅蓮の炎で焼き尽くせ!」。 |
| 2.2日、政経学部で、学生大会が開催され3カ月ストライキを可決。社学部団交、教育学部団交。 |
| 2.3日、入試中ロックアウト。 |
| 2.3日、政経、教育で学生大会。教育学部自治会が試験ボイコット延長。 |
|
| 2.4日、革マル総指揮者逮捕される(氏名その他詳細不詳。誰のことか?)。 |
| 【一文で学部団交(1973・2・5団交)】 |
| 2.5日、一文で学部団交(1973・2・5団交)。十人委員会が総長団交を実現するよう教授会に要請する旨の確約書にサインする。 |
| 【一文教授会が「新年度の自治会費代行徴収の要請書」提出を催促】 |
一文教授会は、1973・2・5団交において「新年度の自治会費代行徴収の要請書」を学部に提出するよう申し入れて来た。これは学生自治会の根幹に関わるもので大激論になり執行部としては結論が出ず、1973・2・6学生大会(流会)議案書には以下のようにある。
(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年2月6日」)
| 我々は彼らの要求に対し、当面正式な自治会として教授会に代行徴収を要請する。しかしながら、代行徴収に関する我々内部における論議が何らかの形で煮つまるまで、我々自らの手で自治会費を凍結しておくつもりである。 |
この学生大会に、BACHグループが独自の議案を提出しようとしていた。それにも自治会費代行徴収について意見が述べられている。事前にそれを知った執行部は驚愕し、上記のような妥協案でしか今回は乗り切れないと申し入れた。苦渋の思いでその削除が要請され、BACHグループは忍耐力を示しその削除に同意した。今日残っているその議案書の最後のところは黒塗りになっている。この問題は大議論になって結論が出ずにこのような折衷的な議案提出に至った。
|
 (私論.私見) 「自治会費受取り」をまごまごする理由なぞないのに (私論.私見) 「自治会費受取り」をまごまごする理由なぞないのに |
| 今日判明することは、大学側が4月からの新入生の自治会費の代行徴収の要請書を新自治会に言ってきたのは、新自治会を承認する予定であった事を示していることである。学生自治会にとって「承認か自立か」と云う主体性議論はあったとしても、「自治会費受取り」をまごまごする理由なぞない。私論を述べれば、この船には乗って良い、否乗るべきだったのではないのか。 |
| 2.5日、政経スト実行委にゅーすNo2「子羊からの脱皮宣言」。 |
| 2.6―7日、一文で学部集会。 |
日付なし、BACHの有志グループ「2.6学生大会議案書」。
日付なし、2F有志「行動方針修正案」。
日付なし、一文行動委「対案 80日間ストライキ実現」。
日付なし、一文団交実行委員会、二文新入生歓迎委員会結成。 |
| 2.7日、早大政経学部が卒業試験レポートで。 |
| 2.8日、一文、卒業予定者分離試験実施。 |
| 【総長団交要求総決起集会開催。法学部執行部と法学部行動委員会が対立】 |
| 2.8日、10号館で総長団交要求総決起集会。ストに反対する法学部執行部に法学部行動委員会などから反論。 |
| 【大学当局が各学部の再建自治会を認めず膠着する】 |
| 革マル派自治会はリコールされたものの、大学当局は再建自治会を認めなかった。予算もつけなかった。再建自治会派と大学当局、革マル派との鬩(せめ)ぎあいが続くことになる。 |
| 【一文教授会が「自治会再建についての見解」を発表、郵送】 |
2.8日、一文教授会・教員会が、「自治会再建についての見解、自治会承認の条件=四項目」を発表、3年生以下の学生の自宅や下宿先に郵送した。「自治会の民主性を保障する最低限の条件であり、学生諸君も当然とするところであろうと思う」と前置きしたうえで、次の四項目を列記していた。早大1文教授会が初めて公式に表明した、新自治会承認への条件だった。
| 一 |
クラス委員(自治会委員)選出のための公正な選挙管理委員会の設置。 |
| 二 |
選挙期間・方式等を予め提示した上でのクラス在籍者の過半数の出席を条件とするクラス委員選挙と公開の開票。 |
| 三 |
クラス委員総会における多数の支持を得た執行部の選出。 |
| 四 |
その執行部による全自治委員の総意を反映し得るような自治会規約案の提示と、全自治会員の絶対多数による承認。 |
読売新聞が、概要「絶対多数による承認という厳しい条件付きであり、新自治会を認めない方針の模様」、「今度の教授会見解は、新自治会を事実上否定して白紙に戻そうというもの」と否定的に報道した。真相は、「再び革マル派が勢力を盛り返してきても、同じ条件を示して公認を拒否する、という先を見通したものだった」とする見方もできるものだった。これに対して、一文教授会・教員会が、それは誤解であり条件さえ整えば承認するつもりであると報道機関に抗議し訂正を申し入れている。「教授会が承認一歩手前であった事がはっきりする」の解説がされている。
一文教授会・教員会の「自治会再建についての見解」に続いて二文教授会・教員会、政経学部教授会、教育学部教授会、社会科学部教授会もほぼ同様の自治会承認条件を提示し、臨時執行部による再建自治会を承認する機運が生まれ始めた。 |
2.10日、早稲田大学新聞173号「更に混迷続く学内状況 武装衝突、機動隊常駐さる」。
| 【この頃のビラ(日付なし)】 |
この頃、以下のビラ(日付なし)が配布されている。
| 第一文学部執行委員会新入生歓迎実行委「春越えれば!2.13集会に向けて」。 |
| 一文執行委員会「総括集会に向けて」(*2月中旬の討議資料?)。 |
| 第一文学部自治会執行部「手をねじこね、ゆがんだ笑みを作ったりせんでくれ!」。 |
|
2.19日、早大当局が入試前のロックアウトを決定する。
| 【阿波崎が傷害罪、村上が暴力行為で起訴(保釈)。佐竹は容疑不十分で不起訴】 |
| 2.19日、東京地検が、近藤、武原と同じく阿波崎、村上、佐竹も完全黙秘を続けたが、阿波崎文雄を傷害罪で、村上文男を暴力行為で起訴した(保釈)。佐竹実は「現場には居たが暴行参加を裏付ける証拠が得られなかった」と容疑不十分で不起訴処分。「物証がほとんどなく、級友への暴行容疑による「別件逮捕」も、被疑者たちの完全黙秘により川口大三郎殺害に結び付けることはできなかった」として保釈されている模様である。 |
| 【田中敏夫(24)前委員長が収監される】 |
| 2.22日、田中敏夫(24)前委員長が収監される。1971年秋の反帝学評との抗争による凶器準備集合罪で逮捕・起訴され懲役8カ月の判決を受けた後控訴していたが、1973.2.14日、高裁で控訴棄却となったため収監された。田中は川口大三郎殺害には関知していないと言っていたが、警視庁公安部は被疑者の一人とみて、新宿区弁天町の自宅を「被疑者不詳、不法監禁、殺人、死体遺棄」の容疑で家宅捜索した。 |
| 【春休暇に入る。入学試験始まる】 |
| 2.23日、ロックアウトの“狭き門”下で早大48年度入学試験始まる(3/2まで)。受験生へのビラ配り、機動隊と衝突。 |
| 【この頃のビラ(日付なし)】 |
この頃、以下のビラ(日付なし)が配布されている。
| 日本史三年有志「一文専攻学生に訴える!たちあがった一、二年生を見殺しにするな!!」。 |
| 一文教養演習正岡ゼミ「涙で訴える!革マルさんの・・・」。 |
| 仏文科のCMNo1 |
| 哲学3年有志より「文学部全学友へのアピール」。 |
| 「まめまき大会」。 |
| 第一文学部自治会執行委員会「3/8自治会連絡会議(4号館)へ向けて」。 |
| 一文執行委員会「われわれは何をめざすのか」。 |
| 1Tクラス「後方よりの通信」(当時発行されていたクラス誌) |
|
| 【全学団交実行委員会(準)の「一文自治会執行委員委殿 招請状」】 |
| 3.9日、全学団交実行委員会(準)「一文自治会執行委員委殿 招請状」。 |
3.10日、第一文学部学生自治会執行委員会・新入生歓迎実行委員会「君達にとって早稲田とは!」。
| 【早稲田大学新聞174号が座談会「川口君虐殺問題」掲載】 |
| 3.10日、早稲田大学新聞174号が座談会「川口君虐殺問題 11.8のつきだしたもの <虐殺糾弾>の原点」掲載。参加者は第一文学部自治会&二J行動委員会のN(原文は実名、以下同じ)、第二文学部学生自治会臨時執行部のK、政治経済学部学生自治会執行委のU、全学行動委員会(準)のH、ワセダ統一救対のI。
|
| 【全学団交実行委員会が結成される】 |
3月半ば、各学部に作られた行動委員会、団交実行委員会を集合する全学団交実行委員会(以下、「団交実行委」と記す)が結成された。「団交実行委」は大学本部などに度々押しかけ、大学職員や教員とま小競り合いを繰り広げた。但し、この頃より、穏健派と急進派の溝が生じだしていた。
3.13日、第一文学部団交実行委員会「11.8川口君糾弾闘争の更なる質的深化に向けて-団実委への招集にかえて」。 |
| 【革マル派全学連前委員長/馬場素明が逮捕される】 |
| 3.28日、立川署と警視庁公安部が、前年の11.10日に引責辞任した革マル派全学連前委員長/馬場素明(25)を逮捕した。容疑は、3.25日、自衛隊本隊移駐阻止集会の立川市曙町で起きた反帝学評との抗争事件での凶器準備集合罪と暴力行為の疑い。
|
| 【一文自治会再建派の新執行部が自治委員総会を開催し入学式対応を協議】 |
| 3.31日、翌日に入学式を控えたこの日、一文自治会再建派の新執行部が自治委員総会を開催し、入学式対応を協議した。1年生の10クラス、2年生の11クラス、3年生も日本文学、日本史、仏文、文芸、哲学の5専修の自治委員が出席した。執行部は、入学式会場の記念会堂前で集会後、整然と会場に入り、新入生たちに学内自治の現状を説明した後、「総長団交の確約」を取りたいと提案した。これに対し、「一文団交実行委」は、演壇占拠による入学式粉砕、そのまま村井総長団交に持ち込むという強硬策を対案した。激論となり参加者の意見も両極に割れた。 |
| 【入学式、総長挨拶の最中に黒ヘルが壇上に乱入】 |
| 4.1日、「団交実行委」の強硬方針を採択した「4.2実行委員会」が、新入生連帯と総長糾弾闘争への全学総決起集会を開催した。 |
| 4.2日午前11時、早稲田大学入学式で、総長挨拶の最中、約150名の黒ヘルが壇上に乱入した。会場は騒然となり、村井総長は守られながら非常通路から脱出した。入学式は午前の部の段階で入学式中止となった。この間、革マル派は式場外で集会していた。 |
| 4.3日、学部入学式も延期。夕方まで両派が集会。 |
| 【「一文4.2集会」】 |
4.2日、「4.2集会」。この集会の内容は不明。関連する次のビラ(日付なし)がある。
| 一文自治会執行委員会「第一文学部の全ての学友諸君よ 4.2集会に総結集を」。 |
| 一文執行委員会「4月方針(案)」。 |
| 無署名「4.2集会基調(案)」。 |
|
| 【革マル派と中核派が高田馬場駅周辺で乱闘】 |
| 4.2日、革マル派が、高田馬場駅前に集結した中核派約250名を襲撃し、乱闘で地下鉄が止まる騒動となった。(乱闘の様子は不詳) |
| 【一文教授会が新入生に対して自治会承認のための五原則を提示】 |
|
4.3日、一文教授会が新入生に対して自治会承認のための五原則を提示した。
| 第一文学部教授会:五原則の承認条件 |
| 1 |
新執行部が、学生大会決定事項につき、学部投票の方法で、学部自治会員過半数の支持を確認すること。 |
| 2 |
クラス委員(自治会委員)選出のための公正な選挙管理委員会の設置。 |
| 3 |
選挙期間・方式等をあらかじめ明示した上での、クラス委員選挙、及び公開の開票。 |
| 4 |
クラス委員総会において多数の支持をえた執行部の選出。 |
| 5 |
執行部による、全自治会員の総意を常時反映しうるような自治会規約案の提示と、その全自治会員による絶対多数による承認。 |
(1)の学部投票が前回の四項目より増えている。
なお、この告示は「新入生諸君へ」となっており、在学生が「暴力排除・学生自治の問題」に積極的に取り組んでいる折から、「新入生諸君の健全な自治会再建への努力を期待してやまない」と結ばれている。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年4月3日」)
第一文学部教授会は、革マル派の統一学生大会教室使用を許可せず、逆に新執行部を激励するような、以下の文書を1973・4・9に送付した。 (「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年4月9日」)
| 第一・第二文学部教授会・教員会は、すでにあきらかにしてあるように、全学生過半数の支持、公正な委員選挙、自治会規約の制定などを含むいわゆる『五原則』にのっとった自治会再建への動きを高く評価しており、またこの五原則を無視した自治会再建運動はありえないと考える。 |
|
| 【革マル派が「早大行動委」テロを満展開し始める】 |
| 4月から学内外において革マル派からの学生自治会執行部への個別テロが全面的に始まった。 |
| 4.4日、革マル派が鉄パイプで本部16号館乱入、「早大行動委」を襲撃した。一方的な襲撃となり、無防備な「早大行動委」の負傷者30数名(頭蓋骨陥没1名、重傷10名)。以降、「早大行動委」系負傷者続出の狼煙となった。 |
| 【革マル派が文学部キャンパスで検問始める】 |
この頃より、革マル派が「一文自治会常任委員会」を名乗り、101番教室を仮自治会室として一文キャンパスに常駐し、スロープ付近では毎日、革マル派が検問し始めていた。この情況下で、一文キャンパスには再建自治会と革マル派自治会が「共存」し始め、それぞれがパンフを持って各教室廻りをするようになった。革マル派のパンフは、最後の方で「11.8川口君死亡事件」という表題で、「痛苦に自己批判」したと触れた後、こう続けていた。
| この問題を『暴力支配の結果』として意図的に歪め、常任委員会の追い落としのために政治的に利用し、そのためには自治会規約すらも踏みにじり、『第二自治会』をデッチ上げようとした諸君達の自治会分断策動に対しても断固として対決して来たのである。 |
|
| 4.5日、本部前で、「4.4革マル鉄パイプ襲撃弾劾集会」。偵察に来た革マル派1名が包囲される。 |
| 4.9日、文学部で、授業初日は討論会。二文で小競り合い。 |
| 4.10日、革マル派が、代々木駅で集団登校中の「早大行動委」に鉄パイプ攻撃。負傷10数名、重傷3名。革マル派の個別的テロが一文執行部を標的に始まった。 |
| 【革マル派が攻撃の矛先を第一文学部教授会に向ける】 |
新入生歓迎運動後の頃、革マル派は、攻撃の矛先を第一文学部教授会に向け、次のようなビラを大量に捲いた。
| 一文当局は、かの虐殺者=日共・民青、中核派、社青同解放派学生と背後で結託した、デツチ上げ『新執』を尻押し、その『自治会再建運動なるものに協力せんとしている。何一つ闘争課題を掲げず、ただただ『反革マル派』のためにのみ狂奔し、当局の『五原則』に屈服して『自治会承認』要求運動にうつつを抜かす『新執』僭称派を積極的に利用しながら、一文自治会を『当局の意のままに動く』自治会=御用自治会化することを狙っているからに他ならない。 |
この頃より、革マル派が、クラス集会への襲撃や個人テロを頻発させるようになった。これに恐怖を感じる者が運動から遠ざかり始めた。その一方で、革マル派と敵対するセクトと共同しての対抗暴力論を主張する声も出始めた。 |
| 【革マル派が再建自治会派の集会、学生大会潰しを策動する】 |
| 4.11日、革マル派が「統一行動」集会開催(約100名)、続いて一文で「4.9告示」糾弾集会。 |
| 4.13日、教育学部学生大会、革マルの妨害で成立せず。 |
| 4.14日、新入生連帯討論集会、革マルの妨害で出来ず。 |
| 4.17日、一文・二文学生大会成立。総長団交要求を決議。その後、大学当局に再団交を確約させる。全理事、学部長の出席を要請する。 |
| 4.21日、再建自治会派が、新学期最初の一文学生大会を文学部で一番大きな181番教室で開催した。革マル派が押しかけ、ハンドマイクを奪い、コードを引きちぎるなどの妨害行動に出た。再建自治会派は、会場を本部キャンパスの15号館に移し再開させた。定足数の900名を確保し学生大会を成立させ、新執行部確立の自治委員選挙実施等の方針を決議した。一文学生大会成功。 |
| 【社青同解放派約200名が本部キャンパスに登場】 |
| この間、社青同解放派約200名が本部キャンパスに登場し、「我々は文学部の学生大会を側面支援する為にやって来た」とアジ演説し始めた。革マル派は、「社青同解放派のテロ部隊を呼び込んで文学部学生大会を強行開催している」と激しく非難した。一文再建自治会派は、執行委員会の名前で、「我々は社青同解放派とは無縁である。本部キャンパスに乱入し、一文自治会の学生大会支援を勝手に標榜したことを強く批判する」と声明した。この学生大会を機に、革マル派の暴力が一気にエスカレートした。樋田委員長の旧友の自治委員/林茂夫も登校できなくされた。こういう「登校不能者」が各クラスで急増した。 |
| 4.22日、両派による投石や放水騒ぎ。 |
| 4.23日、二文学生大会後、早稲田通りを高田馬場まで500名でフランスデモ。 |
| 4.23日、教育学生大会、革マルの妨害で流会。 |
| 4.24日、一文自治委員協議会。 |
| 【政経学部教授会の告示】 |
4.24日、4.21日の一文学生大会の日に革マル派が学生大会会場を襲撃し攻防戦になった事、また社青同解放派・反帝学評の200人の部隊が本部キャンパスに登場した事をもって、政経学部教授会の告示「騒乱と暴力行為について」が発出された。「開き直り」告示と云われる。「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年4月24日」は次の通り。
| まず、暴力追放運動のことである。事件の責任を自認した革マル派が、相かわらずゲバ棒を振う集団行動を続けたことは言うまでもなく悪い。けれども、暴力に報いるに暴力をもってするのは、自家撞着であろう。だから、これに対抗して立上った学生諸君のなかに、自分たちのほうから暴力をしかける武装集団が生まれたのも、遺憾至極であった。どんなに正当な理由があるにしても、静穏であるべき学内に暴力をもちこむことは、主張がどうあろうと絶対に許されるべきことではない。(中略)それなら大学は、この状態をなくすためになにをしたか、そのつど告示を出して、集団の暴力行為を非難するだけだったではないか、と問う者がいる。だが大学に、これ以上のなにができたであろうか。大学は暴力に対して無力であり、無力であることに誇りを感じている。 |
|
| 【革マル派が4.28全国集会。以降、革マル派が再び支配権を確立し始める】 |
| 4.28日、革マル派220名が「4.28全国集会」の前集会開催。 |
| 【第一文学部学部長が次々と交代する】 |
| 5月、前年12月の第一文学部の団交後、浅井学部長が辞任し本明学部長が翌年3月末まで、その後を印南学部長が引き受けていたが突如辞任し、辻村敏樹学部長が就任した。教務担当主任に岩波哲男、志波一富が就き安定した。この頃には革マル派による文学部キャンパスの暴力支配が復活し、学部投票の実施が困難になっていた。 |
| 【早大行動委が文学部団交開催するも革マル派乱入で団交中止】 |
| 5.2日、一文で、再建自治会派が文学部181番教室で文学部団交を開催した。500人の数の力による非武装自衛で革マル派を突破し成功した。革マル10数名が「統一団交」を叫びながら壇上に乱入し乱暴狼藉を働いた。これにより学部側が団交継続を拒否し団交中止を余儀なくされた。その後も集会を開くたびに似たような事態が繰り返された。 |
| 【革マル派の暴力的敵対で文学部団交が流産させられる】 |
| 5.4日、一文再建自治会側が自治委員協議会を開催し5.2団交を総括した。 |
5.7日、反革マルの一文自治会臨時執行部の80名が学部との団交へ向かっていたところ、全都的動員をかけていた革マル派30名が角材や鉄パイプで武装して襲撃し、殴りあいとなった(文学部で衝突、2名負傷)。これにより次の団交が阻止された。
この日、スロープ下で一文執行部・一文行動委も角材で応戦すると云う武器を持った100人規模の集団戦に初めて突入、そこへ革マル派の増援鉄パイプ部隊が襲撃して来てバラバラにされ、大学はロックアウトを宣言して団交は流れた。革マル派は何としても新執行部の承認はさせない方針だった。
新入生を迎えた新年度の大きな目標は、所定の手続きで新入生を含めたクラス自治委員を選出し、そこから新執行部を再度選出、それを大学側に認めさせる事が第一の課題であった。一文教授会も革マル派の学生大会には教室を貸さず新執行部を支援、4月9日には「高く評価する」とまで告示で表明していた。他学部でもそれぞれ前進しつつあり、二文学生大会成立後、その足で高田馬場駅までの数キロメートルを、500人で早稲田通りを行進すると云う、前代未聞の無届け「フランス・デモ(両手を広げて手をつなぎ道路を埋め尽くす)」を成功させたりしていた。そこへ晴天の霹靂のように起きたのが、全学行動委員会(WAC)・全学団交実行委員会(準)による総長拉致団交であった。 |
| 【大学当局の一文学生自治会承認如何見解】 |
5.7日の一文学部団交をめぐる角材と鉄パイプによる集団乱闘についての記者会見で、押村襄学生担当理事は、一文の新執行部を唯一の交渉団体として認めていた。「川口大三郎の死と早稲田大、1973年5月7日」はつ意義の通り。
| 旧自治会執行部をリコールした執行部は規約もなく、自治委員の選挙もしていないので新執行部とは認めていない。しかし一文の執行部は現在ある交渉団体としては唯一のものなので、新執行部と呼びたい。
|
一文教授会・大学側の承認条件と意欲を見る限り、一文学生自治会の意思と力量が評価され、第一文学部自治会はほぼ承認の段階に達していた。最後の関門の自治会規約は既に4月上旬に完成しており、新入生を含む自治委員選挙を行った上で、新年度新執行部を選出すれば教授会の言う「五原則」をクリアできるのが確実で、それを待って大学側は承認する予定であった。
|
| 【「早大行動委」が非常手段で総長を拉致し団交に及ぶ】 |
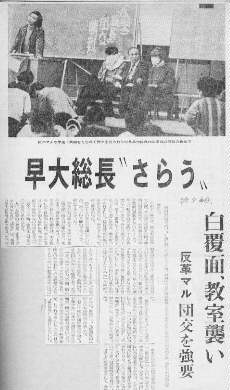 |
5.8日午前11時過ぎ、川口君リンチ殺人事件から半年目に当たるこの日、「5.8 総長拉致団交」を演出した。「早大行動委」30名が、学生組織を代表していない任意団体の全学団交実行委員会の名で、新宿区西大久保の理工学部54号館404号教室で化学工業論の講義を行っていた村井総長を捕捉し、白覆面の10人が村井総長を連れ出し、黒い布をかぶせて車に乗せ、本部キャン法学部の8号館前入口に座らせ“誠意ない”と吊るし上げした。その後、法学部8号館301教室に拉致した。
午後2時過ぎ、約2000名の学生が集まる。行動委は、リンチ殺人の後に村井総長が学生と話し合う姿勢のない事を非難、再度の吊るし上げとなった。学生らは革マル派追放、各学部の新執行部の承認を要求したが、村井総長はのらりくらりとかわし続けた。この間、革マル派200名が村井総長救援に押しかけたが「早大行動委」が撃退した。 |
| 5.9日、村井総長に「5.17日の正式団交開催(再団交)」を約束させ“釈放”した。革マル派との衝突が予想される事態となった。その後、早大キャンパスは平穏化した。但し、再建自治会派内に穏健派と急進派の亀裂が深まり、行動委、団交実行委は武闘路線に向かい始めた。 |
総長拉致を実行した者が後に語っている。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年11月19日」)
| はじめは理工にルートがあるから『やりましょうか』、『いいね』みたいな話から始まった。(中略)総長を8号館に連れていって座らせ、僕がアジった。実際の団交の司会進行は、団交実行委員会にやってもらった。始まったら学生が集まってきた(編注:新聞では3000人位とある)。あの時、革マルは文学部に部隊をかき集めていた。こちらは学生がいっぱい来ているから襲われる心配はなかったけれど、とりあえず革マルは部隊を文学部に溜めていた。革マルもどうしたらいいかわからなかったと思う。団交の中身については、極端に言うと『やりましょうか』と言って『いいですよ』みたいな軽いノリで、あまり深く考えていなかった。団交実行委員会の方で考えていたのかどうか。総長を引っ張り出して、大衆の前でいろいろ疑問を解消して、最低でも謝ってもらいたいなというふうには思っていましたけれど。(編注:5.17団交の確約を反故にされたことを受けて)あの状態でそのまま続けた方が良かったという意見もある。だけど、まぁ、しょうがないな~という感じもある。やっぱり大学当局を信じすぎたところがあるのかな。 |
|
 (私論.私見) 早大行動委の総長拉致批判考 (私論.私見) 早大行動委の総長拉致批判考 |
総長拉致が次のように厳しく批判されている。
| 1 |
話の中身に自治会再建運動との関連は何も語られていない。 |
| 2 |
団交の中身について「軽いノリで、あまり深く考えていなかった。 |
| 3 |
団交確約の反故について「大学当局を信じすぎた」。 |
| 4 |
団交実行委が全学を代表していないと言われた理由への反省の弁がない。 |
| 5 |
全学行動委・全学団交実行委(準)は、自治会建設運動やそれを認めようと努力しつつあった大学側の意欲をよそに、突然、総長を拉致し強引に団交を行った。そしてそれに失敗し、全学の自治会再建運動を破局的な状況におとしいれた。 |
| 5 |
文学部では前日に予定された一文団交を革マル派が角材や鉄パイプを持参して介入し、初めての双方で100人規模の乱闘があった。それ故に5.8日も革マル派は部隊をそこへ常駐させていた。一文の新自治会活動潰しを横目に総長拉致は行われたと言えよう。自治会再建のあの重大な局面で、それとは無縁にこの程度の動機で総長を拉致し、全学的論争を惹起し、挙句は団交確約を破棄され全学の運動をアパシーに投げ込み、そこを革マル派が総攻撃で突き、全てが武力制圧の段階に一気に入った。学生大衆を集める自己陶酔的な劇場的行動にしか関心はなく、それが現実に5.17日に襲撃されて多数の負傷者を出した事への謝罪の言葉一つすらない。 |
|
上記の観点は如何なものであろうか。総長拉致は悪乗りかもしれない。しかし、この種の運動はこういう悪乗りをも包摂しながら次の高みに向かうべきものではなかろうか。例えば、運動の成果物である目前の「5.17日総長再団交」の防衛隊結成に精力的に向かい、学内を「5.17日総長再団交」ム-ド盛り上げへ指導するのが上策だったのではなかろうか。
これを実践した経緯があった上で、「自治会再建のあの重大な局面で、それとは無縁にこの程度の動機で総長を拉致し、全学的論争を惹起し、挙句は団交確約を破棄され全学の運動をアパシーに投げ込み」と批判するのなら分かる。肝心なこの時に傍観者的な評論批判は運動的に害にはなっても実にはなるまい。私はそう思う。 |
| 【5.17日全学総長団交是非の全学的な論争起る】 |
総長が文書で確約した5.17日の全学総長団交を是とするか非とするかの全学的な大論争が巻き起こった。こうした拉致と言う違法的手法を是認するかどうか、実際問題として17日の再団交に参加するかどうかが焦点だった。一文執行委員会でも行動委系の委員とその他の委員の間で激論になった。各クラス討論でも種々の意見が出され紛糾した。その中で、最も正確にこの論争を書き残した1文哲学4年クラスの討論ビラが残っている。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年5月8日」 )
5.8団交に関して
一致点:執行部の下に位置付けられている特別委員会である一文団実委が自治会執行部の確認なしに勝手な行動をした事は、当然批判されなければならない。この一致点は一文団実委が行動原則を逸脱した事に対する批判であるが、その結果ーつまり村井が確約したことーに対する評価は別れてくる。
| 『各学部執行部は一貫して総長団交を要求したのにそれには何ら答えることなく、全学団実委なる実体のない私的機関に確約するとは、明らかに自治会無視、学生団結に対する分断策動である』 |
| 『確かに当局にそういう狙いがあったかもしれない。しかし、実際、総長が出てくることを約束させたことは成果である。それも積極的に利用すべきである。この機会をとりにがすと次にそういう機会を望むことはむずかしい』 |
| 『近視眼的に見れば、それも云えるが、自治会再建、存立を展望すれば、そして東大闘争の教訓、つまり何ら学生の意志を反映していない全共闘の”団交"に応じようとした加藤総長代行は最終的に代議員選出による正式団交代表団に応じざるを得なかったことを見るならば、全学の自治会が一致して議長団を追求すべきだ』 |
|
5.17団交については意見は三つに別れた。
| 1 |
総長が確約した相手は全学団実委(準)という実体のないものである以上、自治会が無条件で参加することは無原則的である。独自に全学と協議して団交を追求すべきだ。自分も5・17に参加しない。 |
5人 |
| 2 |
それでも行動委に主導権をとられないために参加すべきだ。 |
3人 |
| 3 |
条件は彼らが執行部を認めている以上、拒否することはあり得ない。 |
1人 |
|
|
これに対して、「一文執行委員会(有志)と一文団交実行委員会」名義のビラは以下のように主張していた。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年5月8日」)
| 概要/5.17総長団交こそは、我々の闘いに決定的な飛躍をもたらすであろう。一文での態勢固めを目的として実行委員会を結成しよう。それは停滞を打破し一層の大衆化への契機となるのであり、闘いを閉鎖化する傾向=闘いの代行化を取り除くことでもある。実行委員会の実効性については、自治会執行委員会とクラスから選出された自治委員会による組織は代行化の弊害を生むことから、最大限広汎な学友によって担われる実行委という大衆的共闘機関の創出こそが最も強力である。こうした大衆機関は、困難な状況下にある文学部においてとりわけ必要である。革マルの暴力的抑制下にあって、クラス活動はもとよりキャンパスに入ることもおぼつかないという文学部で、クラス・個人に分断されんとしている闘いを結合し発展させていくためには、もはや形式的な団結の象徴である執行委員会だけでは決定的に不充分である。 |
この観点は、運動を前衛化させることにより、これまでの自治会再建運動を乗り越える意思を脈づかせている。哲学4年のクラス討論での「団実委は実体のない私的機関」論と団実委の「形式的な団結の象徴である執行委」論が真っ向から対立している。ここに自治会再建を願った多くの学生と全共闘生き残り世代との間の亀裂と衝突が記録されている。これ以降、雪崩をうって崩壊していくことになる早稲田解放闘争の分水嶺をはっきりと見て取れる。
|
「早大行動委」の総長拉致事件につき、岸沼秀樹「左翼名鑑」(「彼方」5号所収)が次のように記している。
| 一九七三年五月七・八日WAC(注・早大行動委。早大生の反革マル大衆組織で黒ヘルメットを着用。ノンセクトが主体であったが、解放派や中核派などセクトも加わっていた)を中心とした反革マル系部隊は、革マル派を打ち破り、村井早大総長を引き出して大衆団交し、五月十七日の再団交を確約させ、一時、反革マル系が勝利するかと思われた。だが、十七日当日、総長は団交の約束を破棄し、集まっていた反革マル系学生は導入された機動隊によって多数の負傷者を出して追い散らされた。この日をもって早大での革マル派の勝利は確定した。 |
|
| 【一文自治委員協議会が概ね団交参加の結論を出す】 |
5.10日、一文自治委員協議会が開催され、以下のように概ね団交参加の結論を出す。この段階でも一文の新自治会組織はこれだけの団結と機能を示していたことになる。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年5月10日」)
5.17団交に向け、一文では各クラスの意見を集約するための自治委員協議会が開かれた。『一文有志の記録』によれば、参加したのは1年生13クラス、2年生12クラス、3年専修5(編註:いずれも旧学年)であった。ここでも5.8『総長』団交を実施した「全学団交実行委員会」の実体、存立基盤が問題となった。協議会では、5つの原則を確認した上で団交に参加する趣旨の決定がされた。
| 1 |
学大等による大衆的な団実委の結成。 |
| 2 |
各クラスから1名の団交実行委員を選出。 |
| 3 |
各執行部、団実委で話し合い、全学団交実現に関する要求項目、運営方法について協議し、意志一致をする(5・17にはこだわらない)。 |
| 4 |
以上の点を守ることにより、各学部自治会の闘いを踏まえ、全ての自治会の確認の元に行う。 |
| 5 |
5・8団交の主催が全学団交実行委という実体のない名称を使用し、準備について大衆的な確認をとらなかったことを自己批判すること。 |
|
|
| 以降、革マル―大学当局―機動隊連合で「早大行動委」潰される |
| 【早慶連帯化が企図されるが機動隊-革マル派連合によって阻まれる】 |
| 5.12日、早慶交流集会。慶應義塾で、学費値上げ反対闘争を行っている慶応大学生と連帯、第三次早大闘争を全国的に闘うことを決議。早朝、革マル派は慶応大学スト団交実行委に無差別鉄パイプテロ(5名負傷)。早慶学生300名が早稲田に向かったが、機動隊に阻まれ東大で集会。夜、革マル派30名が8号館を鉄パイプで襲撃、4名負傷。 |
| 【革マル派の武装襲撃頻出する】 |
| 5.14日、革マル派が、4、8、16、22号館などに7度の襲撃。この日、法学部学生大会がはじめて開かれたが、民青執行部リコールが可決されるや、10名の定員不足を理由に流会とされる。 |
| 5.14日、この混乱の時期、翌月に武装を決意する「一文二年生連絡協議会」が初会合を行う。 |
| 夕方、一文再建自治会委員長/樋田が22号館(8号館?)前で革マル派に鉄パイプで襲撃され、重傷を負う。 |
| 【大学が5.17日総長団交中止を通告】 |
5.16日夕刻、明日の総長団交へ向けて全学で意見の集約と組織化が進んでいたが、押村襄常任理事が記者会見を行い、団交中止を通告してきた。その理由として、「行動委学生との話し合いにおいて議題や団交の方法について意見が一致しなかった」、「15日に開かれた革マル派の全国集会には900名が参加。この人数で団交が実力粉砕されれば大混乱となる」、「行動委系の全学団交実行委は、全学生を代表しているとはいえない」との3点を挙げた。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年5月16日」)
この時点で、行動委系が武装慎重派と、ノンセクトラジカルとしての武装派と、諸党派を含む全共闘的武装派の三派にきしみ出し、これを束ねる指導者が居なかった。諸党派を含む全共闘敵武装派が全学行動委WACの武闘方針を仕切り闘争を本格化させるが、6月末までに数回の革マル派との部隊衝突を繰り返した後、次第に劣勢となり、やがて元の木阿弥キャンパスに戻っていくことになる。
|
| 【革マル派が総長団交粉砕を企図して全国動員】 |
| 5.15日、革マル派全国動員(500名)で本部集会。 |
| 5.16日、5.17総長団交粉砕を叫ぶ革マル派の集会。村井総長が5.17日総長団交を撤回した。 |
| 【革マル派が早稲田一帯を制圧、総長団交流産する】 |
| 5.17日、革マル派がキャンパスは無論、早稲田一帯を制圧した。「早大行動委」など500名が夕方正門前で集会。校内に入ろうとするや革マル派が鉄パイプ攻撃。1000名に膨れた学生は再度構内突入を図ろうとしたが機動隊に規制され、500名が外堀公園に連行された。かくて、「5.17日総長再団交」ならず。 |
5.17総長団交予定日、非武装の一文デモ隊約300名が、大隈銅像脇で、後ろから革マル派の鉄パイプ部隊に襲われ、多数の負傷者を出した。
「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年5月17日、革マル派に襲われ、機動隊に阻まれ、団実委は身動きとれず」が次のように記している。
| デモ隊は多数の負傷者を出しながら再結集し学内デモを再開した。デモ隊は遥か遠くの四谷駅側の外堀公園まで一時間以上かけて機動隊によって規制されて運ばれた。当時、沿道の市民が拍手して応援した。早稲田解放闘争は新聞・テレビの全国版で連日報道されていた。渋谷駅などで臨時執行部がカンパ要請活動を行うと1日で数万円が集まった。デモ隊は公園に着くまで「早稲田解放、革マル粉砕」を声を限りに叫んだ。一部は四谷の公園から再び電車に乗って本部前に引き返して結集し、デモを再開し再び四谷まで連行された。 |
|
| 【一文学生の奮戦考】 |
一文学生の意思は強固なものがあった。これを確認しておく。
| 1972・11・28 |
全学に先駆けた第一回学生大会で臨時執行部を樹立 |
| 1972・12・5 |
第一回学部団交 |
| 1973・1・23 |
第二回学生大会で新執行部を樹立し一週間のスト決議 |
| 1973・1・27 |
第二回学部団交 |
| 1973.1.30 |
第三回学生大会で第二次一週間ストライキ決議 |
| 1973・2・5 |
第三回学部団交 |
| 1973・4・10 |
新年度に入っても、学生大会予定(代々木駅頭で革マル派に襲撃されて中止) |
| 1973・4・21 |
第四回学生大会成立 |
| 1973・5・2 |
文学部181大教室に500人が集まって第四回学部団交 |
| 1973・5・7 |
予定された学部団交は革マル派の武力介入で角材と鉄パイプ(革マル)で乱闘になり中止、ロックアウト。 |
この短期間に学生大会と学部団交をこれだけやった学部は他にはない。そして、総長拉致団交の後、1973・5・10には「旧1年生13クラス、旧2年生12クラス、旧3年専修5クラス」が集まって自治委員協議会を開催して、紛糾の末だが条件付きで5・17総長団交に参加することを決議し、実際にも1973・5・17の日には約300人の長蛇のデモ隊列を成し、三度まで四谷駅まで機動隊に連行された。ここまで団結していた学部は他にはない。 |
| 【社青同解放派、ブント連合がキャンパスに登場し革マル派を粉砕する】 |
神奈川大学を拠点としていた社青同解放派は、川口大三郎事件の革マル派の責任を追及する姿勢に出て、共産主義者同盟(ブント)と共に早大行動委員会(WAC)に助太刀した。
5―6月、 社青同解放派、ブント連合が早稲田大学キャンパスに登場し、革マル派全国部隊を3度にわたり粉砕する。革マル派は社青同解放派の拠点神奈川大学襲撃を計画する。
5.18日、総長団交中止の翌日、反帝学評約200名人が文学部中庭・学生会館・3号館前のキャンパス内数カ所でで革マル派を襲撃。以降、6月末まで全学行動委WAC、戦旗派、叛旗派と連合して、本部キャンパスを舞台として革マル派部隊と連続的にゲバルトを演じた。この日、東京駅で学生ゲバ。早大乱闘の帰り襲う。乗客巻き添え。
|
5.19日、革マル派に阻止されて文学部キャンパスに自治会執行部は入れず、早大乱闘で10人ケガ、重体。
| 【法学部自治会執行部が改選され、再び民青系が選出された】 |
| この頃、法学部自治会執行部が改選され、再び民青系が選出された。 |
| 【「負けるな早稲田」集会開かれる】 |
| この頃、「負けるな早稲田」集会開かれる。豊島公会堂に650名参加。自衛武装問題で路線分岐鮮明に。 |
教育学部の選管委結成される。
5.24日、高田馬場駅周辺で情宣中の一文自治会メンバーが革マル派に襲われる。
5月下旬、11.8当日リンチ殺害に関与したと推定される田中公郎、若林民生、後藤隆洋、水津則子ら革マル派メンバーの文学部構内への復帰が目撃されている。
| 【一文執行部から自衛武装論が出てくる】 |
5.27日、早慶戦の神宮外苑で、一文自治会執行委員会と一文団交実行委員会連名のビラがまかれた。「18日の革マルと反帝学評との衝突について」〈追記〉で暴力について次のように正面から論じている。これが自衛武装と云う概念が一文執行部から出てくる最初の日となった。「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年5月19日」が次のように記している。
| 5月18日の事態について。まず基本的に我々とは関係のないこと、そして我々の運動の原則とは逸脱していることを確認しよう。勿論我々は革マルに対して一文のキャンパスを暴力的に制圧されているという現状を踏まえるならば、自らの運動は自らで守り抜く、一人に対するテロは全員に対するテロと見なすという立場から、最低限自らの命を守るため、革マルの情宣集会を一切許さないという立場から、大衆的な暴力的な反撃を展開する必要があることは言うまでもない。僕たちは一般的に暴力を否定しない。軽々しく暴力追放などという遠ぼえなど言わない。今、暴力は復権されなければならない。強いられた存在の一つの行動様式として、暴力=肉体性の発現はあるのだから、そういう行為は、共同性の一形態であるだろう。 |
この意味するところは、執行部主体の活動における暴力(編註:武装による自衛、あるいは革マルに対する反撃)は、運動を推進するためには必要であるとする意志の表明であった。 |
| 【本部キャンパスで各党派の大規模な部隊同士の戦闘展開される】 |
| 5.29日、全学行動委(WAC)総会で武闘路線が明確になり、5.30、6.4、6.30と連続して諸党派も入り乱れての、本部キャンパスにおける大規模な部隊同士のぶつかり合いに向かった。5.30には戦旗派(赤ヘルメット)も登場して、反帝学評(青ヘルメット)と連合して革マル部隊を撃退している。 |
全学行動委WAC・諸党派は、5.30、6.4、6.30の本部キャンパスでの昼間の激闘は全て勝ち抜いている。だが、学生会館を拠点とする革マルは24時間体制で部隊を維持した。「第三章 自衛武装の諸相」は次のように記している。
| 大学は彼らのロックアウトルールに自ら反して、一貫して革マルの全国動員の精鋭部隊を学生会館から退去させず、それが早稲田解放闘争の武闘期の勝敗を決める。 |
|
5.31日、早大乱闘でまた重体。
| 【全学行動委WAC・叛旗・反帝学評と革マル派の部隊衝突】 |
6.4日、反革マル派の全学行動委WAC・叛旗・反帝学評と革マル派の双方合わせて約300名の部隊衝突となる。偶然そこに居合わせた松井今朝子の『師父の遺言』には以下のようにある。これが6.4日に前後して三回起きた衝突の一つ、演劇博物館前の激突である。
| 早稲田ならではの魅力的な空間は演劇博物館だったが、ある時そこで浄瑠璃本を読んでいたら、外が何やら騒然とし始めた。二階の窓から覗くと玄関前の十字路にそれぞれ赤、白、黒、黄色のヘルメット集団がスクラムを組んで激突寸前という状態である。演博の館員はその瞬間何を思ったか『危険なので閉館します。皆さんは出て下さい』とこちらを追い出しにかかった。私ほか数人が扉の外へ出た途端、ヘルメット集団は堰を切ったように突進して鉄パイプで互いに殴り合いを始め、そこら中で血が流れ出すわ、校舎の窓からは火炎瓶が降ってくるわという惨状の中で私たちはうろたえて逃げ回るはめになった。(松井今朝子『師父の遺言』pp68〜69) |
| この日、革マル派はなぜか白と黒と黄色のヘルメットだった。黒は行動委、黄色は共産党系の民青が着用するもので、何らかの陽動作戦の意味があったのかもしれない。(「第三章 自衛武装の諸相」) |
| 運送車両のガス欠により現場にヘルメットが届かないというアクシデントもあり、この衝突から脱出する際、全学行動委のメンバー数人が塀から転落するなどして負傷した。とくに一文では行動委のリーダー的存在が加療のため入院となり、その後の運動に大きく影響することとなった。特筆すべきは、ノンヘルだった団実委と行動委のメンバーの後から現場に着いたクラス単位で活動していたメンバーが、ヘルメットをかぶり、鉄パイプで武装していたこと、また、黒ヘルの他一文の行動委は「LAC」と記したオレンジ色のヘルメットを着用したことだった。(「川口大三郎の死と早稲田大学、 1973年6月4日」) |
| 「この日、私は4号館に待機の大衆部隊の指揮と防衛に当たっていた。私は途中で偵察に出て、ヘルメット無しのWAC部隊を6号館付近で見たし、11号館での攻防も見た」。最後に大衆部隊を率いて北門から撤収した。 |
|
6.5日、早大で武力衝突。警察が管理強化を要望。
6.6日、警視庁が、革マルの拠点早大、反帝の拠点日大を捜索。
6.8日、警視庁が先制攻撃で早大など捜索し爆弾や鉄パイプ押収(ゲバルト封じ第2弾)。
| 【自治委員選挙態勢作り作動】 |
6.11日、早稲田大学第一文学部学生自治会執行部が自治委員総会を本部キャンパスで開き、新しい自治委員選挙の態勢作りに入った。全学行動委員会・諸党派と革マル全国動員武装部隊が、数百人で入り乱れて本部キャンパスで白兵戦を演じるようになった5.30日以降の戦争状態の最中においてである。だが、そうした集会自体の防衛が必要なほど、革マル派の無差別の武装襲撃は激しくなっていた。それでも尚、私達は学生自治会としてクラス討論とクラス決議に基づき(岡本厚氏の証言)、大衆的・組織的に最後まで闘い続けた。
他学部の状況はどうであったか、簡単に記述する。
| 教育学部 |
1973・1・24 |
唯一の交渉団体として認める。 |
| 1973・2・22 |
総意に立つものとして承認する。 |
| 1973・5・ |
団交。第一文学部の自治会再建運動は、まで順調だった。 |
| 1973・6・21 |
新執行部が確立した時点で自治会承認する。 |
| 政経学部 |
1973・1・26 |
自治会再建学生投票を有効と認める。 |
| 1973・4・24 |
残りは第五項目だけ。着実に前進するように。 |
| 第二文学部 |
1973・2・10 |
現在の臨時執行部を承認する方向へ努力する確認書に署名。 |
| 1973・3・13 |
五原則提示(一文と同じもの)。諸手続きを含めた学生自身による自治会再建が推し進められてゆく事を切に望む。 |
| 1973・4・23 |
二文学生大会。500人で早稲田通りを高田馬場駅までフランス・デモ。
|
運動の起きなかった理工学部、革マル派の拠点であった商学部と社会科学部を除くと、他の三学部でも自治会再建運動は、勝利一歩手前であったと言っていい。結果的には商学部と社会科学部に革マル派の自治会が残存し、他は自治会そのものが消滅した。法学部だけは民青系自治会がそのまま生き残り、その後2000年代に入って、自ら自治会解散決議を行った。
|
| 【全学集会『負けるな早稲田・大集会』】 |
6.13日、豊島公会堂で全学集会『負けるな早稲田・大集会』開催される。この時、二文臨時執行部・教育学部執行部から「自衛武装」の問題提起があった。
| 集会の模様を詳しく残しているのは早稲田キャンパス新聞179号で、サブタイトルに『自衛武装問題、路線分岐鮮明に』とあり、リードにも『集会での発言内容は、自衛武装の必要性を、行動委のみならず自治会執行部が強調したこと、民青系との路線分岐が鮮明になったことが注目される』とある。 |
|
| 【川口君の2J級友が革マル派の拉致から逃れる】 |
| 6.13日20時頃、文学部正門前で2J級友(11.8日当日に川口大三郎を連れ戻そうとして暴行を受け、これまで裁判に証人として出廷してきた)が、革マル派に同派が拠点とした第一学生会館の方向に拉致されかかり、幸いにも逃れることができた。級友は、この事件が影響して次の公判を欠席している。 |
| 【早大ザック集団がバリケード構築。機動隊導入で67名が逮捕される】 |
| 6.14日、朝の早大でザック集団がバリケード構築。早朝機動隊導入で67名が逮捕される。総長連行事件で黒ヘルの早大生に逮捕状。
|
この頃、社学自治会費が革マル系常任委へ下る。
| 【「猫に鈴をとやせネズミ」の檄】 |
6.17日、一文拡大行動委を超えてより広く一文大衆部隊として鉄パイプで武装を呼びかける決意をし、「猫に鈴をとやせネズミ」を書き、「M氏と一文執行委員/私」が意思一致して手分けして一文武装要員のリクルートに入った。これが事実上のX団の萌芽であり、6.17日の初会合はそれによって成立した。「一文執行委員/私」が次のように証言している。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年7月2日 」)
| 執行委員会での果てしない自衛武装是非論議は皆も承知で、徐々に自衛に傾いていた。私は、行動委・団実委への2月以来の批判は変わらないが、その総長拉致と革マルの本格的武装攻撃によって、事態がここまで危機的になったので、もはや最後の自衛武装によって運動と仲間を守る以外にないと呼びかけた。 |
<何故武装か>
個体としての己の生を誰も代行的に他人に生きてもらうことがありえないように、個体としての己の意思・思想・感性の表現を己のこととして貫き、決して疎外させ代行させることなく、自らの言葉を以って語っていく、——これが最低限の原則ではないのか。とすれば、己の表現を物理力をもって奪われている時に、己のゲヴァルト空間を確保し抵抗すること以外にどんな道があろうか。己のことばを表現を己から疎外させ誰かに代行させてはならない。同じ意味で、己の自衛権をゲヴァルトを己の肉体から疎外させ誰かに代行させてはならない。セクト主義的引き廻しを許さないと言う観点から言っても、種々のセクトやWACなどのゲヴァルト代行は、運動の自立をさまたげるだけに留まらず、思想的にも運動の敗北を決定的にするであろう。 |
|
| 文学部拡大行動委LAC・オレンジ・ヘルメット部隊は7・2の文学部中庭集会までその色を使用した。その後に集まった「やせネズミ」集団はヘルメットをオレンジからグレーヘルメットに変えた。 |
6.25日、樋田氏が多数の学友に伴われて集団登校をやって革マル派の殴る蹴るの集団暴行に遭った。だが何とか学友の人数で守られてキャンパスから脱出した。(『彼は早稲田で死んだ』、p149、文庫本p167)
| 【一文二連協が自衛武装想定を確認する】 |
6.25日、二文に続いて一文の新2年生有志約30名が、「2年生連絡協議会」(以下、「二連協」と記す)を開催し、組織の在り方について、「閉ざされた組織、突出した組織ではなく、クラスのメンバーに運動の目的や手段について説明し、共に闘っていく運動体」としたうえで、緩やかな「自衛武装」が討論され、「自分たちの運動を守るための防衛手段として、武装も想定する」ことを確認し下記の決定を行った。
| 自主的運動を保障するための手段として武装を位置づける。武装の行使については、各自の独自性は認めるものの組織的に決定していくこと、テロ・リンチはせず大衆の目前での公然たる暴力であること、目的が確認された暴力であること等の定義が検討された。 |
|
6.30日、早大でゲバルト、全学休校。
| 【一文二連協が自衛武装集会開催】 |
7.2日、「一文二連協」が、文学部中庭で、最初となるヘルメットを被り角材で自衛武装しながらの集会を貫徹させた。この7.22文学部中庭集会は、自治会一般学生が合議によって「竹竿・角材とヘルメットで武装した」全学において最初の集会となった。
集会に参加した学生はハンドマイクで、「私達は好き好んで武装したのではありません。革マル派の暴力支配の復活の中で、武装を余儀なくされているのです」と訴えた。この時、革マル派の妨害はなかった。一文拡大行動委はオレンジ・ヘルメットで参加した。
| 7月2日午前9時頃、一文二年生連絡協議会(二連協)を中心とする一文学生約25名とそれを支援する全学行動委(WAC)約30名が、7月5日の学生大会のための情宣として文学部キャンパスに登場し、スロープ上などにバリケードを築き、黒・オレンジなどのヘルメット、旗ざお、鉄パイプ(WAC、野崎註)で武装し、学内デモをおこなって気勢をあげた。登校した学生で1年生を中心とした40名余りが中庭での集会に加わり、多くの学生が集会を取り巻く中で一文の2年生が次々にマイクを持ち、武装登場の理解を求め、7月5日の一文学生大会への参加を呼びかけた。この間に一文の部隊は40名程にふくれあがり、中庭での武装デモを繰り返したあと、12時頃隊列を解いて理工学部方面へ引き上げようとした。しかし文学部正門付近に待機していた機動隊が一文の部隊を取り巻いて規制し、外濠公園まで連行した」(川口大三郎の死と早稲田大学、1973年7月2日)。 |
この日の武装登場をキャンパス新聞は次のように評価した。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年7月2日」)
| 二連協を中心とするクラス活動家が11・8以降初めて公然と旗ざお、鉄パイプで武装し(WAC、野崎註)、党派の支援なしに武装情宣を独自で貫徹した点で、小規模ながらも質的には画期的な意味があったと考えられる。 |
「一文有志の記録」には2日の総括として、次のようなコメントが記されている。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年7月2日」)
| ほぼ達成。文キャンを120~130(人)で制圧できれば、40、50(人)のZ(革マル派、野崎註)では敵対できない。大衆の渦で埋め尽くすということには限界。Zは全国部隊の時しか展開できない。 |
|
| この日は革マル派は朝から意表を突かれたのか、6.30まで連続して3回撃破されて動員部隊がいなかったのか、全く反撃はなかった。 |
7.4日、革マル派が、池袋の中核派アジト四ヵ所を襲撃。
| 【樋田委員長が病み上がりの登校で武装反対を主張】 |
| 7.5日、樋田委員長が病み上がりにも構わず登校し、15名の委員全員が揃っての執行委員会を開催し、「一文二連協の武装問題」の是非を廻って討議している。樋田委員長は、「私はその後も一貫して武装に反対し続けた」と記している。 |
「樋田委員長の病み上がりの登校での武装反対主張」が次のように不販されている。
| 樋田氏の出版記念会の席上で、「あなたが武装に反対したから、早大闘争は敗北した。今からでも遅くないから謝ってくれ」と学友の一人から詰め寄られたそうだが(映画プレスリリース・パンフ、p17)、その思いには一理ある。そう言った学友はX団の組織化を始めたもう一人のM氏だと思うが、彼に対して「武闘派のまま生きた者」というラベルを貼っている(同上)。そう云うラベル貼り自体が正当防衛権を否定する権力側の論理だと気がつくべきである。 |
|
一文日本史3年行動委員会準備会の最初のビラはこう記す。
| 革マルの組織をあげた反撃・学校当局との闘いをも組織しての自治会再建への闘いの中で、新自治会の防衛を全学友のクラスの団結中に一般化してしまうことは、闘いの困難さと緊急さに対して余りにも無知であり、無責任であり、無力であると云わねばならない。 |
次の用に評されている。
| 結局この予言は当たっていた。新自治会の防衛を非暴力主義で「クラスの団結中に一般化」しようとしたのは、無知で無責任で無力であった。しかし、新自治会の防衛を自衛武装で試みたX団と二連協の”ICHIBUN
80”も、確かに無知で無力であったが、確かな敗北の痛みだけは手元に残った。 |
|
 (私論.私見) 今日から見て自衛武装論の質を問う (私論.私見) 今日から見て自衛武装論の質を問う |
今日から見て自衛武装論の質を問いたい。5.29日、全学行動委(WAC)総会で武闘路線が明確にされて以降、革マル派の武闘に対抗する全学行動委の武闘が生み出されていった。が、今日判明するのは、樋田委員長の武装反対論、一文二年生連絡協議会(二連協)の一部の党派に頼らない武闘対抗論のみの正義弁が流布されている。この流れが運動を牽引したことにより、元の木阿弥に戻ったのではないかと問う論が欲しい。
本来は、キャンパスからの革マル派支配一掃を命題とする、早稲田の伝統的な各党派が共存するキャンパス内るつぼ運動論を掲げ、その為の全共闘運動による闘争を理論的にも武闘的にも敢行すべきだったのではなかろうか。総長団交、図書館占拠闘争は、この観点から是非を問われるべきで、樋田委員長の武装反対論、一文二年生連絡協議会(二連協)一部の党派に頼らない武闘対抗論からの否定的にのみ語る闘争論は俗に片手落ちではないのか。この立場からの川口君事件はまだ日の目を見ていない。してみれば、川口君事件はまだ総括の全域には至っていないと云うべきだろう。 |
| 【専修大学生・山代康裕が暴力行為の疑いで逮捕される】 |
| 7.6日、警視庁公安部は、専修大学生・山代康裕(21)を暴力行為の疑いで逮捕した。6.13日20時頃、文学部正門前で2J級友(11.8日当日に川口大三郎を連れ戻そうとして暴行を受け、これまで裁判に証人として出廷してきた)にさらなる暴行を加えた容疑。暴行に加わったのは3名で、矢郷順一(一文)も含まれる。彼らは級友を革マル派が拠点とした第一学生会館がある方向に拉致しようとしたが、幸いにも逃れることができた。しかし、この事件が影響して級友は次の公判を欠席している。 |
| 【再建自治会新執系が文学部で武装情宣】 |
| 7月初旬頃、再建自治会新執系が文学部で武装情宣。「早稲田解放集会」開かれる。 |
| 【7・13二連協・X団中庭武装集会】 |
二連協の学友が1973・7・2、竹竿武装中庭集会を計画し、それが成功したので7・13中庭集会へと進んだ。全学行動委(WAC)や全学団交実行委が総長団交を拒否され、6月期の全面的武力衝突を経て拡散・分解していく最中に、クラス活動家レベルの私達は逆に自衛武装を決意していった。
| 川口君の虐殺事件を機に、『反暴力』を掲げてこれまで一緒に闘ってきた同じ二年生の仲間たちが、防衛のためとはいえ、『武装』することを決めたのだ。療養中だった私は、その経緯を後になって知り、激しいショックを受けた。(樋田毅『彼は早稲田で死んだ』、p148、166) |
|
「執行委員の呼びかけで集まった20名ほどの集団」がX団で、X団創出過程が次のように語られている。
| そもそもWACの前身は、政経学部のPAC、文学部のLAC、教育学部のEAC、法学部のJACなど各学部に作られた行動委で、それを統合したのが早大行動委WACである。その主な構成員は、在校生および二次闘争(1969年全共闘運動、野崎註)からの復帰組で、革マルによる攻撃に対抗する防衛を役割とした。ことに4月以降、個人攻撃も含め過激になった革マルの武装攻撃に対して、情宣、学大などで登場する際には、行動委に周囲を守られないと執行部は一文キャンパスに足を踏み入れることもかなわなくなった。まだ1月の段階ではヘルメットの着用をめぐる意見の食い違いもあったが、鉄パイプによる攻撃が日常化するに及んで、ほとんど議論の余地はなくなった。さらに、二次闘争の世代にとって武装は既成事実であり、そこへ背後の党派の支援が加わるとなれば、さらに本格化、先鋭化が進むことは必然だった。そうした旧世代の影響の色濃い武装闘争へ傾斜していく一方で、独自の防衛部隊を作る動きもあった。執行委員の呼びかけで集まった20名ほどの集団で、独自の武装訓練等を行い、一文キャンパスへの復帰を果たすことを目論んで活動した。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年5月29日」) |
| 7・2中庭集会の後、竹竿だけでは対抗できないので、それから私達は三段組み鉄パイプの試作に入り、10人分まで用意できた。工事現場から、長い鉄パイプを何本か拝借し、夜中に工具で製作した。その数に規定されて私が指揮した7・13の中庭集会での非公然遊撃部隊は10人にとどまった。この段階で私達はWAC(全学行動委員会)やLAC(一文行動委員会)とは分離し、賛同した皆と相談してヘルメットの色をグレーにした。黒(WAC)でも白(革マル)でもないのである。これが鉄パイプで武装した早大第一文学部武装遊撃隊X団の誕生である。正式名称はなく、それゆえに「X」または「X団」とだけ呼んでいた。 |
X団を構成したのは旧1年生と旧2年生の8クラスの有志と執行委員1名の20名ほどだった。合議制をとる連絡協議会の即時性の弱さ、党派の競り合いの場となった行動委員会の限界を越え、自衛武装を肯定的にとらえて現状を打破しようとする有志の集まりだった。全員が鉄パイプを握ることを肯定(決意)していた訳ではなく、サポートに徹しようとした者も含まれていたし、途中で活動を中止した者もいた。X団初の対外活動がこの日13日だった。二連協の集会を潰しに来る革マルの襲撃に備え、鉄パイプを握って体育局に潜んでいた。結局革マルの優勢に出番はなく、退却せざるを得なかった。また、X団とは別のグループが、袋に入れた自らの糞尿を革マルに投げつける作戦を実行した。これは、成田紛争で使われていた糞爆弾になぞらえたものだった。
(詳しくは「L*の登場、L*=X団、X団の動き、X団の夏休み合宿」と一文アーカイブにある)(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年7月13日」) |
|
| 【革マル派が「一文二連協」集会を襲撃、負傷者続出】 |
7.13日、革マル派約150名(大学側の資料では約200名の全国精鋭部隊)が、再建自治会新執系「一文二連協」が文学部中庭で約80名参加(その内の約20名が武装)の武装集会を襲撃し、逃げ遅れたり逃げ惑う者を徹底追尾し鉄パイプで容赦なくメッタ打ちにして、重傷者を含む8名の負傷者を続出させた。
この時、スロープ下の正面付近出派、叛旗派(ブント系)本隊の武装部隊が守りを固めていたが、わずか5分間で彼らも襲撃され多くの負傷者(重傷者8名、野崎註)を出している。 |
自衛武装に反対の樋田委員長らと民青系の学友は「集会を見守る」という位置付けで、集会の周辺に佇んでいた。グレーヘルメット部隊10名がミルクホールのある31号館を背に正門に向かって一列横隊になり、正門前の叛旗派と革マル派の鉄パイプ戦闘に介入寸前だった事は、バリケードで塞がれたスロープ脇の階段下の死角でもあってほぼ誰にも気づかれていない。当時は今のスロープ脇の樹木や細長い建物やアリーナはなく、記念会堂前のスロープ横は正門から31号館まで野球場くらいのガランとした広場だった。偵察班が「来たぞー」と駆け寄って報告、私たちは潜伏の地下から這い出した。
革マル派はボストンバッグを正門の外から次々と投げ込み、別働本隊が正門内でそれを開けて三段組み鉄パイプを組み立て、前面では腕に甲を付けた鉄パイプなしの防衛部隊が叛旗派を防いでいた。やがてカーンカーンと甲高い鉄パイプ同士の激突音がスロープ下で鳴り響いた。私たちが這い出した体育局地下のその窓は小さく、一人一人時間がかかり、全員が横隊になって私が号令をかけようとした瞬間、叛旗派は敗走して革マル部隊がスロープを駆け上がってしまった。私達は中庭での惨状を予期しながら、無念の撤退をした。撤退途中で私は右足首を捻挫した。(「川口大三郎の死と早稲田大学、1973年7月13日」 |
| 全学的後退局面で最も果敢に状況を引き受け、脆弱ながら最後まで組織的に抵抗したのは、第一文学部の一般学生約80名であった。叛旗派(吉本隆明の思想的影響下にあった政治党派で、行動規範は文学的原理に近い。)約20名が支援。全学行動委員会WACは支援参加する予定だったが当日になって来なかった。非公然鉄パイプ戦闘部隊10名、その後方支援:レポ部隊5名(携帯電話のない時代、偵察員は公衆電話に駆け込んでレポセンターに連絡した)、レポセンター2名(電話のある仲間の一人の下宿を拠点として本部とした)、救対2名、そして別動女性部隊5名の「X団」、公然竹竿部隊約20名、公然集会約40名の「二連協」。この”ICHIBUN 80”の物語を知る者は少ない。X団の武闘訓練は、お茶の水の明治大学構内、日大文理学部キャンパスなどで行った。明大全共闘・日大全共闘の生き残りによる部隊訓練だった。また、その基礎訓練として信濃忍拳を三多摩の或る小学校体育館で毎週夜間行い、夏休みには静岡県の伊豆市辺りの山村で信濃忍拳の合宿に参加した。体育館での夜間訓練で評論家・劇作家の菅孝行と一緒に練習したのを覚えている。また、X団で夏合宿を河口湖で行い、秋以降の方針論議を行った。全学行動委員会WAC部隊が6月の革マルとの激突に勝利したものの、運動の位置付けを失い拡散した後、その無党派の一部が11月の図書館闘争の準備に入っていた夏に、X団はまだ闘うつもりで自衛武装の訓練と合宿を行っていた。 |
| 【一文再建自治会派の執行部で武装議論を延々と続ける】 |
| 夏休みに入る直前まで、一文再建自治会執行部で武装議論を延々と続いた。結局、結論を出せないまま分裂し、機能停止し始めた。 |
7.16日、5.17被告団の第1回公判開かれる。
9月、夏休みが明けた9月になって、革マル派は都内各地で他党派や全学行動委(WAC)を連続的に襲撃した。これらを受けて早稲田大学は後期最初の日から、「学外の党派闘争」を理由に「不測事態」が予想されるとして異例の集会禁止措置と共にロックアウトした。
9.9日、中核派と革マル派が西武池袋線保谷駅構内で集団会戦している。
9.10日頃、5・17被告団第2回公判開かれる。
| 【社青同解放派と革マル派が神奈川大で集団会戦】 |
9.14-15日未明の午前1時45分頃、反帝学評(青解派)100名が、神奈川横須賀での空母ミッドウェー母港化阻止集会に参加すべく拠点校の神奈川大3号館と宮面寮に泊まっていたところへ、覆面姿の革マル派150名が鉄パイプで乱入し、乱闘で双方で21名が負傷、市内11の病院に運ばれ4名が入院した。
この乱闘の最中、反帝学評(青解派)がレンタカーで動向視察していた革マル派2名を捕まえ、鉄パイプで滅多打ちにして殺害し、現場から5km離れた浄水場裏に遺棄した。午前10時30分、保土ヶ谷区川島町の横浜市水道局西谷浄水場裏の小道で、金築寛(東大、23歳)と清水徹志(元国際基督教大生、24歳)の死体が見つかった。この事件はそれまで中核派と革マル派の間だけで行われていた内ゲバ殺人に、社青同解放派を参加させる契機となった。革マル派は中核派と社青同解放派の2党派間抗争を引き受けていくことになる。
次のように情況解析されている。
| 自治会再建運動が完全に学外状況に支配された日である。もはや学内の学生自治会再建運動の論理と希望は名実ともに党派と大学当局によって圧殺された。その理由は構造的暴力のレベルが上がったからに他ならない。死者二名を出した革マル派は、それ以降、党派であれ私達のようなノンセクトやノンポリであれ、同レベルの構造的暴力で対応して来るのは目に見えている。ここに、全学の自治会再建運動は行き詰まって失速し、同時に夏休み中も武闘訓練に明け暮れていたX団のその防衛任務も消失した。この段階で”X団”は終わった。 |
|
| 【革マル派30名が日本橋の三越本店屋上で「早大行動委」襲撃】 |
| 9.16日、革マル派30名が、中央区日本橋の三越本店屋上で、川口事件を追及する反革マル派のWAC(早稲田全学行動委の略称)を鉄パイプで襲い、8名が暴力行為、凶器準備集合罪の現行犯で中央署に逮捕された。屋上には一般客500人がいた。革マル派は、この日の午後横須賀で開かれた同派の集会で「WACを三越で粉砕した」と声明している。 |
| 翌9.17日の毎日新聞夕刊に、「16日の三越デパートの事件は、革マル派に早稲田を追われた反革マル派が混雑にまぎれて人目のつかないデパートに結集、17日以降の早大奪還作戦を練ろうとしたのを、事前に察知した革マルが先制攻撃をかけた」とする警視庁の見解が掲載された。革マル派の諜報能力の高さを知るべきだろう。 |
9.17日、早大ロックアウト。新学期早々、警告無視の集会。
| 【革マル派が鶯谷駅で中核派を襲撃(鶯谷駅会戦)】 |
9.17日、革マル派が鶯谷駅で中核派を襲撃(鶯谷駅会戦)。国鉄鶯谷駅ホームで、京浜東北線南行き電車に乗ってきた中核派150名が降り、上野公園口の改札口近くへ向かったところ、上野公園口から革マル派50名が乱入、乱闘となり、5名が逮捕された。
1973.9.18日付毎日新聞が次のように報じている。
| 概要/革マル派全学連の前川健委員長が、記者会見で、早大奪還をねらっていた中核派を粉砕するために行った。四分五裂になっている現在の学生運動を統一するためには、他党派を徹底的につぶしていかなくてはならないと、他セクトとの内ゲバを続けていく方針を語った。 |
1973.9.18日付毎日新聞の記事の中に次のような記述がある。
| 早大では昨年11月8日、同大生、川口大三郎君(当時20歳)が革マル派のリンチ殺人にあって以来、同大を最大の拠点とする革マル派に対して中核、反帝系の各セクトが『右翼改良主義=革マル派との対決は階級闘争の前進に不可欠』と叫び、革マル派の追い出しと”早大解放“を闘争課題にしている。 |
|
| 【田中角栄首相が閣議で江崎国家公安委員長に「早大リンチ殺人の犯人検挙はまだか」と異例の質問】 |
| 9.18日、田中角栄首相が、閣議で、「早大リンチ殺人の犯人検挙はまだか」と異例の質問を江崎国家公安委員長に対して行っている。 |
 (私論.私見) 田中角栄首相が閣議で「早大リンチ殺人の犯人検挙はまだか」と質問考 (私論.私見) 田中角栄首相が閣議で「早大リンチ殺人の犯人検挙はまだか」と質問考 |
| この情報が隠蔽されており、ネット検索で出てこない。れんだいこ的には、田中首相の姿勢が窺えて興味深い。ネット空間には、こういう本当に知りたい情報が出てこない胡散臭さがある。この現場でも確認できる。 |
9.18日、警視庁がゲバルト続発で早大など捜索。正門で厳重チェック。
9.27日、早大でゲバルト、10人ケガ?。警視庁が早大会館を2度目の捜索。
| 【革マル派が再びキャンパスの支配権を確立する】 |
| 9月末頃、「早大行動委」の奮戦もここで力尽きた。以降、キャンパスに革マル派が再度支配権を確立することになった。 |
 (私論.私見) 革マル派が再度支配権を確立考 (私論.私見) 革マル派が再度支配権を確立考 |
| 「革マル派が再度支配権を確立」が大学当局と機動隊に守られてのなりふり構わぬ制圧であったことは、当時の一連の史実であろう。早大総長が一貫して反革マル共同戦線派により結成された自治会の承認を渋り、団交への出席も最終的に拒否し、革マル派の肩を持ち続けた。早稲田大学と革マル派の癒着、蜜月関係が長く続いて行くことになった。この関係が、「平成6年、奥島孝康が早大総長に就任するまで大学当局と革マル派の蜜月は続く」ことになる。 |
| 【一文の樋田委員長/山田書記長連名の反革マル自衛武装批判ビラが播かれる】 |
10.3日、一文再建自治会委員長/樋田、書記長/山田の連名による反革マル自衛武装批判の「一文四千の学友諸君!」ビラが播かれる。文面の一部は次の通り。
| 一連の内ゲバ事件をしつかりと、とらえ返し、『革マル』の『暴力』、そして諸セクトの武装介入をいかに克服していくのかをこの手でしっかりと掴みとろうではないか!。 |
その次のビラのタイトルは、「神奈川大学『内ゲバ殺人』事件を口実とした早大闘争のすり替えを許さない」で、武装路線への批判をさらに強めていた。文面の一部は次の通り。
| 中核派、解放派、叛旗派などは、当初から革マルとのゲバルトを主張しつつ早大闘争に介入し、とりわけ行動委員会を中心に一定の影響力を持って来た。革マルのテロ攻勢が激化するにつれ、彼らの主張が正当であるかのような幻影が僕たちの一部に焦りから生じ、それが彼らとの共同行動、あるいは“自衛武装”を主張する諸君を生み出したのである。(中略)『武装路線』は闘争の歪曲であり、学生から運動への主体的関りを奪い去るものとして厳しく批判せざるを得ない。 |
|
 (私論.私見) 「樋田派の反革マル自衛武装批判ビラ」考 (私論.私見) 「樋田派の反革マル自衛武装批判ビラ」考 |
| 樋田毅・氏著「彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠」で知らされることになったが、「一文の樋田委員長/山田書記長連名の反革マル自衛武装批判ビラ」がかの局面で適切だったのかどうか、私には疑問がある。革マル派の暴力テロ再燃に対する有効な手立てを編み出してヒューマニスト足らんとするのなら分かるが、編み出さぬままの「反革マル自衛武装批判」は利敵理論になりかねないものではなかろうか。 |
10.10日頃、5・17被告団第3回公判。裁判官、起訴理由の釈明求む。
| 【革マル派が全国12箇所で中核派拠点襲撃(第2次中核村襲撃)】 |
| 10.20日未明、革マル派が、全国12箇所で中核派拠点を襲撃する(第2次中核村襲撃)。この際、襲撃側の若林民生(二文自治会元委員長、11/13処分対象者/除籍)が逮捕、勾留される。但し、この時点では若林の川口大三郎殺害への関与は判明していない。(1974年4月22日参照)
|
| 【警視庁公安部と本富士署が川口君リンチ殺人事件で革マル5名逮捕】 |
10.21日、国際反戦デーのこの日、警視庁公安部と本富士署が、川口君リンチ殺人事件での川口大三郎監禁致死の容疑で革マル4名を逮捕した。警察が早大第一学生会館など革マル派の拠点を捜索し、この時の捜査で、川口君をリンチ致死せしめた革マル派の下手人の一人である二文自治会委員長/村上文男(25歳)、二文自治会副委員長/武原光志(23歳)、一文自治会書記長/佐竹実(23歳)の3名を宮下公園で再逮捕、一文自治会会計部長/阿波崎文雄(26歳)を自宅で逮捕した。服役中の全学中央自治会委員長/田中敏夫(24歳)にも逮捕状が執行され、翌22日、別件で服役中の横浜刑務所内で逮捕された。
10.23日、川口君リンチ殺人事件で、別件で横浜刑務所に服役中の田中敏夫が監禁致死容疑で逮捕された。逮捕されたメンバー5名が起訴され、1名(佐竹)が分離公判となる。 |
| 【革マル派の事件関係者5名が追加公開指名手配される】 |
| 10.31日、革マル派の4名(級友への暴行で保釈中の一文学生/近藤隆史(24歳)、一文自治文化厚生部長/水津則子(23歳)、一文自治会組織部長/後藤隆洋(25歳)、矢郷順一(25歳)、緑川茂樹(22歳)、他1名の計6名(革マル自治会幹部がほとんど)にも逮捕状が出され公開指名手配された。東京新聞および産経新聞によれば、別事件で逮捕された革マル派の者の中に川口大三郎殺害に関する供述をした者がいて、逮捕・指名手配に結びついたという。 |
| 【11.8一周忌前の(続)自衛武装議論】 |
11.8一周忌前の頃、一文自治会が、内部が武装の是非をめぐって分裂する中、久しぶりに執行委員会を開いた。6名の委員が出席し、川口君の一周忌追悼集会を全国の学生総決起の場にしようという提案を廻って議論が伯仲した。既に呼びかけの声明文案が用意されており、採決で「賛成3、反対2、保留1」となった。樋田委員長が「こんなに重要な問題を全執行委員15人の半数にも満たない6人の出席では決められない」と主張したところ、賛成派が欠席した執行委員2名分の委任状を見せ、「これで賛成は5名、投票参加者も過半数になる」として、採決を有効とさせた。これにより、「11.8川口君虐殺一周忌追悼集会を早大全学・全国学友の総決起で勝ちとろう」と題したビラが大量に播かれた。呼びかけ人が第一文学部自治会執行委員会、教育学部自治会執行委員会、第二文学部自治会臨時執行委員会有志の連名になっていた。
武装問題について次のように書かれていた。
| 私達は、決して『革マルせん滅』を目的に闘っているのではない。しかし私たちの仲間である活動家たちが革マルのテロルによってせん滅され、負傷していくのを、私たちは黙って見ているわけにはいかない。その意味において私たちは『反暴力』ではないのであり、運動を保障していくものとして、われわれの運動の利害をかけて闘争破壊者に対する自衛武装を断固として主張するものである。 |
樋田委員長ほか3名の執行委員が非暴力、非武装の方針に拘り、一文自治会の執行委員会としてでなく「川口君一周忌追悼集会一文実行委員会」を新たに作り活動を始めた。岩間氏らの日本文学専修4年の有志が「11.8集会参加決議と題したビラを配布した。文面の一部は次のように記されている。
| 私達は一部の武装路線には断固反対する。(中略)全く不本意ながら集会は分裂して行われようとしている。分裂は避けねばならないが、彼ら一部武装闘争路線派があくまでも学外セクトの導入に固執するならば、私たちは共に集会を持つことを拒否せねばならない。 |
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「私達は一部の武装路線には断固反対する」は一見、正論のように聞こえる。しかし、この時の「暴力反対」、「学外セクトの導入反対」は闘う学友を見殺しにする結果になったのではないのか。闘う者が助けられないのなら、闘う者が寄ってこなくなるのは当然である。それを思えば、当時のキャンパス事情の正義としては革マル暴力に対峙する自衛能力を持つ方向にリードするのが自然であり、「暴力」であれ「学外セクトの導入」であれ足らずのところを補うのは必要な事であり、それを逆に動いてはいかんだろう。少なくとも多数決採択された決議には従うのが筋で、議論が足りないのなら議論を続行させ意志の練り合いをせねばならない。そういう経緯を得ての決議には従うのが筋だろうし、従えないのなら辞任の方が賢明だろう。結果的に、11.8一周忌前での陣営内部の分裂で、川口君事件闘争は元の木阿弥に戻ることを運命づけられたのではなかろうか。 |
| 【第20回早稲田祭】 |
大学当局と革マル派が牛耳る早稲田祭実行委員会と「早稲田祭実施にあたっての五原則」合意により「1973年第20回早稲田祭」が催された。この早稲田祭は1996年の第43回まで毎年続く。
11.5日、「対立とけぬ早稲田大学。『追悼』と『祭』が立ち並ぶ」。 |
11.6日、早大また緊張。川口君死亡一周年でロックアウト。
| 【田中敏夫前委員長が自己批判書提出】 |
「田中敏夫自己批判書」を知る前、次のようにコメントしていた。
| 「続いて、早大全学中央自治会委員長・田中敏夫も自己批判し、11.13日、『田中敏男の自己批判書』が提出されている。佐竹自己批判書に続いて田中自己批判書をも確認しておこうと思うのだがネット検索で出てこない。これは偶然だろうか。れんだいこは、他にも重要な文書に限り却って出てこない例を知っているので驚きはしないけれども」。 |
「 1973年11月11日(日) 供述により明らかになった事件の経緯。監禁致死罪で革マル派4人起訴
」によると、11.7日、田中前委員長が佐竹に先立って自己批判書「川口君事件に対する私の態度と反省」を書き、転向を表明している。 してみれば田中前委員長の自己批判書が口火を切ったことになる。1973.11.12日付読売新聞は次の記事を発信している。
| 田中の自己批判書はさる7日『川口君事件に対する私の態度と反省』と題して書いたもので『暴力の行使は人間性を腐敗させる』など、佐竹とほぼ同じ内容。田中は事件当時の早大革マル派の最高幹部だが、組織との関係について『学生運動から足を洗う』と述べているという。 |
|
| 【川口君虐殺一周年闘争前夜の情勢】 |
11.7日、川口君虐殺一周年前夜、早大が緊迫する。革マル派は全国から約1200名を動員して本部キャンパスで総決起集会を開催し、高田馬場駅までデモ行進した。
11.8日、早大当局がロックアウトを強行し本部キャンパス内での集会が不能にされた。大学当局は革マル派の正門向かい側の大隈講堂前での集会を許可していた。同派の「川口君追悼集会」がヘルメット姿の約500名で開催され、その周囲をジュラルミン盾の持つ機動隊が囲んでいた。反革マル各派が学内突入狙ったが、機動隊が立ちはだかり、抵抗、投石、警官ともみ合うが構内に入ることができなかった。以降、機動隊が常駐化した。この日、警視庁が先制の革マル派書記局を捜索している。 |
| 【川口君虐殺一周年闘争】 |
11.8日、樋田委員長らの「川口君一周忌追悼集会一文実行委員会」は正門前に集まろうとしたものの機動隊の規制に押しやられるようにして近くの鶴巻公園に向かい約300名で集会を始めた。午後、新宿体育館に場所を移して約600名で追悼集会を再開した。政経学部自治会、法学部自治会との共催となった。
分裂した側は、「一文自治会執行委員会」を名乗って約300名が一文キャンパス北側の通称「箱根山」の空き地で追悼集会を開催した。日本文学専修グループは独自に大学近くのキリスト教施設/早稲田奉仕園で集会した。新聞は、革マル派が復権した早稲田の情況を伝えている。 |
| 【早稲田における革マル派による暴力支配追放運動が頓挫する】 |
| 以降、早稲田大学全学行動委員会などは、まだ闘う姿勢を見せ、図書館占拠をおこなったものの、早稲田大学と機動隊に守られた革マル支配を打ち破ることはできず、この時の「早稲田における革マル派による暴力支配追放運動」は頓挫する。 |
| 【佐竹が犯行を自供、自己批判書を発表】 |
11.8日、元一文自治会書記長・佐竹が犯行の一部を自供し始める。「川口大三郎の撲殺遺体のカラー写真を眼前に突き付けて自白を迫った」と云われる。
11.9日、取調官に提出し、自供に至る心境の変化を明らかにするとともに、党派間の暴力行使の中止を訴える自己批判書が発表された。その自己批判書が、「左翼」に開示されているのでこれを転載しておく。
自己批判書
川口君を死に追いやった本人として、そして当時一文自治会の書記長をやっていた責任ある者として、私が完黙をやめ私の社会的責任を明らかにする心境になったのは、以下の理由によるものです。
それは彼の死に直接関係した私が、自己の社会的責任を明らかにすることによって、故川口君の冥福を心から祈ると同時に、川口君のお母さんに深く謝罪したいと考えたからです。さらに、現在の党派関係の異常性とそこにおける暴力的衝突を見るにつけ、かかる現状を深く憂い、二度とこのような不幸な事態がおこらないよう強く切望しているためでもあります。私は川口君の問題を真剣に考えている全ての人々に次のことを強く訴えたいのです。現段階の党派関係は明らかに異常といえます。このような現状の中で、党派闘争に暴力を持ち込むことに関して、真剣に慎重に再検討して欲しいのです。暴力の行使に際限はありません。そしてその結果は予測をはるかに越えるものがあります。
現に私は川口君を死に追いやろうなどとは、もちろん夢にも考えていませんでした。しかし結果はあまりにも悲惨なものでした。私は、私と同世代の人間的にも未熟な若い人々が暴力を行使することになれてしまうことが最も恐ろしいのです。傷つけ、傷つけられることを厭わない人間になることが真の勇気ではないと思います。人間の生の尊厳なくして人間の解放はないはずです。今こそ、この原点に立ち帰るべきです。
確かに、現在の党派関係と党派闘争を正常に戻すことは非常に困難なことでしょう。容易にできる問題ではないと思います。それは大きな努力が必要でしょう。しかし誰かがやらなければなりません。私はそのことを、川口君の問題を真剣に考えている全ての人々にやり遂げて欲しいのです。私の冒したような重大な過ちが再びおこらないことを強く切望するからです。社会の矛盾を変革するために自己犠牲的な活動を展開している人々が、お互いを傷つけあうことほど不幸なことはないと考えるからです。
現在、私は川口君という将来ある一人の青年を死に追いやってしまった自己の人間的未熟を痛切に反省し、あわせて川口君の霊が安らからんことを祈っています。川口君、そして川口君のお母さん、ほんとうにすみませんでした。
昭和48年11月9日 佐竹実 ㊞
|
 (私論.私見) 佐竹自己批判書考 (私論.私見) 佐竹自己批判書考
|
佐竹自己批判書はそれなりのものであったが当時の情勢には何らの意味も持たぬ「何をいまさら弁」でしかなかった。
2015.6.20日 れんだいこ拝 |
|
監禁致死容疑で逮捕、取り調べを受けていた佐竹実が川口君殺害を自供した。自供によると、革マル派は対立する中核派とのセクト争いから、昨年11月8日午後2時頃、文学部構内で友人と立話をしていた川口君を「お前は中核派のスパイだろう」と佐竹ら5人が文学部127番教室に連行、村上らの指導でイスにしばりつけたうえ鉄パイプで殴るけるのリンチを加え死亡させた。佐竹は、10.21日に逮捕されて以来完黙を続けてきたが、8日を前にした週明けに革マル派の弁護士を解任、8日の東京地裁での拘留理由開示の公判も辞退して自供を始めた。これによってすでに逮捕されている二文自治会委員長の村上文男ら4人の起訴もほぼ確実になり、指名手配中の元一文自治会組織部長の後藤隆洋ら6人の逮捕に捜査の的が絞られることとなった。自供に至る経緯については滝田洋・磯村淳夫著「内ゲバ~公安記者メモから」に詳しい。次のように解説されている。
| 「自己批判書の日付けが、死者・川口の一周忌の翌日ということは、警視庁公安部(あるいは東京地検公安部)が“一周忌”のチャンスをとらえ、加害者・佐竹に精神的攻めを加えた結果とも見られる。佐竹をはじめ川口君事件被疑者に対し警視庁公安部は、カラーの遺体写真をも眼前に突きつけ、日夜の調べ(攻め)を強行した」。 |
佐竹は自己批判書を取調官に提出。リンチの模様について絵をかいて説明するなど詳しく自供したが、遺体の運搬については「自分は関係しなかった」と主張した。
|
佐竹自己批判書に対し、革マル派の「共産主義者」32号、木曾淳士(黒田寛一)は次のように批判している。
| 「公安当局の弾圧のもとで、暴力一切を否定するというブルジョア的人間観を注入されこれを粉砕し得ず、そうすることによって裏切り者となった」。 |
1974.6.28日付読売新聞記事は次の通り。 |
| 【川口君1周年闘争】 |
| 11.9日、「もう争いはやめて!」。川口君の母が1周忌の訴え。川口君追悼デモで犠牲者。大阪の中核派の元学生死ぬ。「機動隊に殴られた」。 |
| 【事件関係者の自供相次ぐ】 |
| 11.10日、川口君リンチ殺人事件で、革マル幹部が自供「イスに縛りメッタ打ち」。 |
11.11日、東京地検が、先に逮捕していた革マル派4名(二文自治会委員長/村上文男(25)、武原光志(23)、佐竹実(23)、阿波崎文雄(26))を監禁致死罪で起訴した。
量刑につき次のように解説されている。
| 「東京地検は当初殺人罪の適用を検討したが、川口君の死に慌てていたという証言があったことから、川口君を殺すつもりはなかったと判断し、監禁致死罪を適用した。また、警視庁は逮捕監禁致死罪で逮捕したが、東京地検は川口君を長時間におよび教室に閉じ込めたことから監禁致死罪に当たるとして逮捕罪を省いた。なお、逮捕罪とは、他人の両手両足を捕らえた場合など、短時間の拘束に対して適用される」。 |
|
| 田中敏夫前委員長は、「一人の命を奪ってしまったことを一生かけて償っていく。二度と学生運動はしない」と転向表明をしており、犯行への参加や指示・命令した証拠がないため処分保留になった。佐竹は自己批判書を取調官に提出。リンチの模様について絵をかいて説明するなど詳しく自供したが、遺体の運搬については「自分は関係しなかった」と言っている。 |
| 11.12日、川口君リンチ殺人事件で、Sら2人が自己批判・ 「転向声明」。佐竹はその後「分離公判」となり、報道関係にも非公開で審理が進められた。 |
川口サトさんのコメントは次の通り。
| 被告たちが遅まきながらでも、自分たちがやったことが間違っていたと自己批判したことはうれしい。これをきっかけに、ほかの活動家の人たちも、運動の中から暴力を締め出すよう努力してほしい。大三郎が死んでまる一年たった今は、被告たちに対して憎しみより、むしろ被告たちの母親に対する同情の念の方が強い。(1973年11月12日付読売新聞) |
|
| 11.12日、警視庁公安部は、村上文男、武原光志、若林民生を暴力行為と傷害の疑いで再逮捕する。容疑は1972年10月17日21:00、早大文学部34号館253教室に早大社会科学部3年A君(21)を連れ込み「おまえも共青(日本共産主義青年同盟)だろう。自己批判しろ」と言って、殴る傘で突くなどして15日間のケガをさせたというもの。 |
11.13日、東京地検公安部が、田中前委員長(24)は川口君リンチ殺人事件で事件現場にいなかったとして処分保留した。次のように報じられている。
| 東京地検は、監禁致死容疑で警視庁が逮捕した元早大一文自治会委員長・田中敏夫(24)を12日夕、処分保留のまま釈放した。田中は川口君事件の指揮、命令をした疑いがあるとされ、10月22日に逮捕されたが、事件に関与しなかったという見方が強くなったため釈放となった。田中は、別の内ゲバ事件で横浜刑務所に服役中を逮捕されたので、釈放と同時に身柄は再び同刑務所に移された。(1973.11.13日付け毎日新聞) |
|
| 二文自治会委員長/村上文男氏は、「BLOG-C 第293号=『彼は早稲田で死んだ』」によれば、獄中で、「一部の未熟な分子の仕わざ」呼ばわりで切り捨てることで党派の責任を逃れるべく弁明した革マル派党中央の姿勢に憤慨し、「僕を疎外した組織を僕は絶対に許すことができない」、「革マル派に革命などやらせてはならないと思う」と記しているとのことである(「梯明秀との対決」(こぶし書房、1979年刊))。 |
| 【相次ぐ自己批判声明に対する革マル派、中核派の対応】 |
こうした自己批判への革マル派の対応は、滝田洋・磯村淳夫著「内ゲバ~公安記者メモから」に詳しい。それによると革マル派は次のように声明し批判している。
| 公安当局の弾圧のもとで、暴力一般を否定するというブルジョア的人間観を注入されこれを粉砕しえず、そうすることによって裏切り者となった」。(革マル派機関紙「共産主義者」32号) |
中核派は次のように論評している。
| 佐竹・田中は留置場以外に安全なところはないと観念し警察に保護を申し出た。だがこれは転向でも何でもない。佐竹の脱落にさいしての論理は革マルの“党派闘争の論理と倫理”なるものと寸分違わない」。(中核派機関紙「前進」660号)。 |
|
| 【村上文男、武原光志、若林民生が別件の暴力行為と傷害の疑いで再逮捕される】 |
| 11.12日、警視庁公安部は、村上文男、武原光志、若林民生を暴力行為と傷害の疑いで再逮捕する。容疑は1972.10.17日21:00、早大文学部34号館253教室に早大社会科学部3年A君(21)を連れ込み「おまえも共青(日本共産主義青年同盟)だろう。自己批判しろ」と言って、殴る傘で突くなどして15日間のケガをさせたというもの。
|
| 【黒ヘルが早大図書館占拠闘争】 |
11.19日午後8時頃、第一文学部と政経学部からなる早大黒ヘル十数名(14名)が本部キャンパス正門脇の早大図書館に乱入し、屋上からマイクで、大学に対し早稲田祭の中止(虐殺者の祭典・早稲田祭を即時中止せよ!)と総長団交を要求(早大当局者・村井総長は、5.17団交からの逃亡を自己批判しただちに全学団交に出席せよ!)し立てこもった。大学側は「学外へ出なさい」とマイクで再三にわたり警告、警視庁機動隊と戸塚署員約百名が学内外に待機した。学生らは屋上から図書館内の書籍を投げたりして抵抗し、攻防4時間の末に14名全員が不退去罪で逮捕された。
翌日、行動委委員会系グループが本部キャンパスでデモと集会を開き、村井総長の「5.17日団交再開確約」違反を批判する図書館占拠闘争を支持声明した。その後、叛旗派などのセクトと合流し、革マル派が準備中の看板を破壊するなどした。行動委員会系の表立った集会は、この日が最後となった。 |
総長拉致に続く早大図書館占拠闘争当事者の後日談がある。(川口大三郎の死と早稲田大学、1973年11月19日)
▼発想の元。この話の始まりは8月の末くらい。6月のゲバルト(編注:6・4の革マルと衝突で勝利したことを指す。勝利したが、学内に拠点がないので優勢を保持できなかった)の反省があり、何をもって闘わなくちゃならないかを考えたら、徹夜集会や1・19、総長団交みたいに軸があれば学生が集められる。革マルは人が集まる機会を閉ざしているから、人さえ集められれば、確率的にも物理的にも私たちが勝てるというふうに考えた。
▼人集め。後退局面なので個別に話した。団交なんかの時は「みんなでやりましょう」って言えば「みんなでやりましょう」なんですが、後退局面で負け続けているような状況になると、「やりませんか」と言って個々に説明しないと無理なんです。そうなるとどうしても情報が漏れる。それが党派に漏れちゃって、党派と交渉しなければならなくなった。交渉には一切関わらなかったけれど、党派との約束なんかもしなくちゃならない。そうなると期日も限られてきますよね。当日、学内で部隊を待機させていた党派があったけれど、15人だった。それぐらいの人数だったらこちらでも集めるのは難しくない。人数の話ではないんですよ、早稲田でやっていくためには。だからあまり党派とはやりたくなかった。
▼メンバーの顔ぶれ。政経行動委(P A C)を中心にしたメンバー構成になりました。半分以上が政経、あとは一文、教育、社学です。人数も多くなかったから、政経とそれ以外に分けて分担してオルグしました。(編注:政経8人、一文3人、教育2人、社学1人)。
▼実行期日。やると決めた11・19は、早稲田祭を中止させるリミットに近かった。目標としてはもっと早い時間、昼間のうちにやるつもりだったけれど遅くなった。集合場所の明大の生田がロックアウトだった。青解(ママ=社青同解放派)が封鎖していたの。それで遅くなった。いろいろ調べて、図書館に入りやすい時間帯があることがわかっていて、昼を外すと少し遅くなる。期日を延ばすという選択肢はなかったから、結局ああいう結果になったんですけれど。意図としては、学生を集めてやればなんとかなるかなと、それ以上のことはあまり考えていなかった。こういう形で人を溜めてやるような形の闘争をやろうとしたものだから、外にも人を確保しておかなければならない。そうした人員もいました。 |
これをやった動機として次のように証言されている。
| 人さえ集められれば、確率的にも物理的にも私たちが勝てるというふうに考えた。意図としては、学生を集めてやればなんとかなるかなと、それ以上のことはあまり考えていなかった。 |
これにつき次のように批判されている。
| これは第二次早大闘争の運動スタイルそのものである。建物占拠などの象徴的行動で耳目を集める、その後の事は考えていない。総長拉致団交もそうだった。何をもって勝てるとしているのか空無である。既にして一般学生も含めて多数の流血の惨事となっている政治的場面に演劇空間を演出して登場し、そこで主役を演じて自己陶酔して終わる。学生大衆を単なる観客として踏みつける政治の演劇化と言うべきである。 |
図書館占拠した際のビラは次の通り。(川口大三郎の死と早稲田大学、1973年11月19日)。
▼全員に告ぐ、全員に告ぐ、全員に告ぐ--我々は虐殺者の中枢を占拠した。
▼川口君虐殺徹底糾弾 虐殺者の杜を占拠せよ。
▼虐殺者の祭典:早稲田祭を怒りをもって粉砕せよ。
▼総長村井の5・17団交からの逃亡糾弾!全学総長団交へ出てこい。 ▼当局-革マル-民青(民青・日共教職組)の三位一体となった早大管理支配体制解体。 |
| 概要「我々のこの闘いが広汎な学友の共感と共にあることを確信し」、「早大4万学生大衆が心中密かに望んでいた直接行動であったと確信している。」、「川口君虐殺を真に糾弾するひとりの無党派学生大衆として」、「学生大衆自身の自衛武装の第一歩がここに印されたのだ」。 |
|
11.21~26日、革マル系の早稲田祭開催さる。民青同系の法学部祭開かれる。
この頃、5・17被告団第四回公判。結審近し。検察側曖昧な態度に終始す。
11.24日、火炎びん11本 大学祭の早大で見つかり押収される。
11.26日、大隈講堂でボヤ。早稲田祭に反革マル派いやがらせ。
11.27日、川口君リンチ殺人事件に関わる鉄パイプ乱入で捜索/東京都渋谷区。
12.16-17日、警視庁公安部は、佐竹の自供などから、小石中也(22)(一文)ら6名を監禁致死容疑で全国に指名手配した(指名手配者は計12名に)。
12.21日、川口君リンチ殺人事件で、拉致・殺害当日の深夜に目撃された、遺体の搬送に使われたと思われるオレンジ色の自動車は、革マル派活動家が所有する46年式のマツダ・ロータリークーペと特定された(読売新聞12月21日付夕刊)。
「「川口大三郎君リンチ虐殺事件」考その3、1974年以降」へ続く。
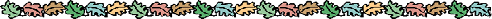



 (私論.私見)
(私論.私見)
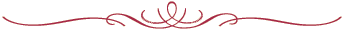
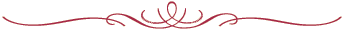
![]()

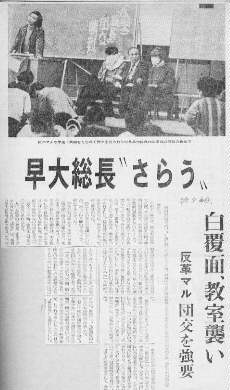
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)