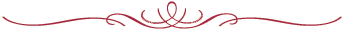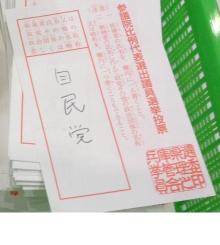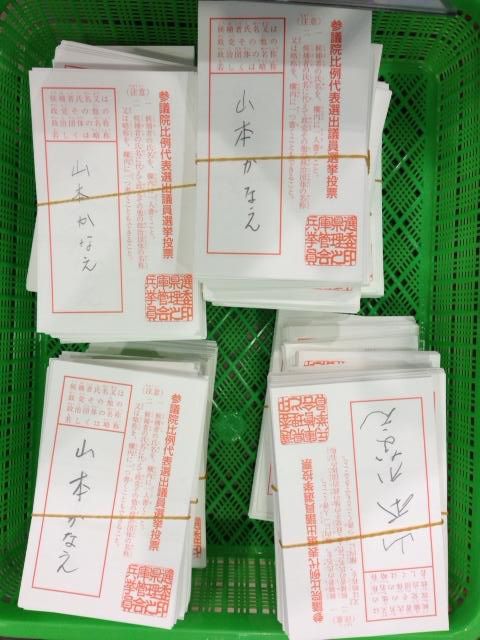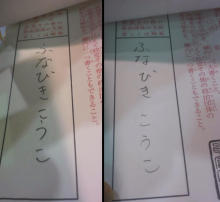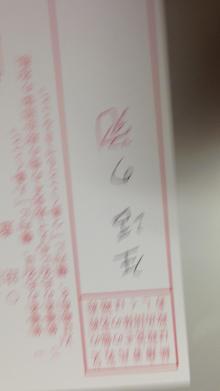神奈川の18ヶ所の選挙区の開票速報を解析してたら、不可解な現象に気づいた。投票総数だけ見てると勝った自民党が多いのは当たり前だから気づきにくいが、開票速報の得票数から算出できる【得票率】が自公候補だけ右肩あがりに増えていくのだ。
普通は得票率は最初から最後までそれほど増減するもんではないはず。無作為に箱の中の票を1割位取り出して数えたらその選挙区の大体の傾向がわかるから、出口調査ってのは成り立つ訳で・・。勿論誤差ってのは存在するから出口調査は万能ではないので競っている場合開票中にひっくり返る事が多々ある。そういう訳で得票率が緩やかに上下するのは自然なのだ。だから他の候補の得票率が緩やかに上下しながら横ばいで推移するのは自然に見える。だがなぜか自公の候補の票の比率だけが右肩上がりになっている選挙区が多い。1区2区3区は顕著だ。
4区はみんなの党の目玉候補の「あさお慶一郎」で圧勝が予想されてか自民候補の不可解な右肩上がりが見受けられない。どの候補の得票率も開票が進んできても概ね横ばいである。これが自然だ。そうでないということは開票途中で自民票が水増しされている可能性が見て取れる。もしくは途中にごっそり自民票が大量に追加されているかもしれない。
18の選挙区の内、実に7つの選挙区で不可解な得票率の上昇が確認できた。(1区2区3区5区6区7区14区)全国の選挙区でこういう不可解な上昇のみを続ける選挙区を見れば、もしかしたら不正選挙が行われた選挙区を割り出すのに役立つかもしれない。
最初は未来の候補と自民の候補の比較をしていてあまりに得票率の開きが膨らんでいくので変だなと思っていた。票を数えれば数える程未来の候補支持率が下がって、自民党の支持率が上昇するとでもいうのか?同じ日に投票された票だぞ?だから未来の党の得票が自民に書き換えられているのかと感じた。だが比較対象を自民VS未来だけに絞るのはフェアではないと思い直し、他の候補も全て含めて調べ直した結果、18箇所の選挙区で得票率が右肩上がりを続けているのは自公候補だけだとわかった。つまり他の党の候補はほとんど最初から最後まで横ばいを続けるのだ。そして横に伸びるのは統計学的には極めて自然な事だ。
画像を見れば分かるが自公が右肩下がりを続ける選挙区は見当たらない。不正が行われた可能性を真っ向否定する人からすれば偶然と言われるだろうが、逆に右肩下がりの選挙区がひとつも無いのだからやはり変だと言わざるを得ない。ちなみに右肩上がりを続ける7選挙区以外は自公も横這いする選挙区ばかりである。自公以外にこの様な不可解な右肩上がりを続ける候補がいないのも余計に懐疑心を駆り立てられる。
以下に6区~18区までの残り全ての選挙区のグラフを貼り付ける。是非今言った事を確認してみてほしい。
↓唯一自民じゃなく公明候補の選挙区。途中までみんなの党と競ってるが中盤不可解に上昇気味。かなり異常な右肩上がりをする7区。綺麗に上がりすぎ。激戦区だから水増し票が多いのだろうか?
自民じゃないがTPP大好き江田憲司の選挙区。誤差の範囲と判断し右肩上がりのひとつには数えなかったが、緩やかに上がって行き最後に数%あがっている。選挙に強い候補ということで少なめの水増しが行われたと見ることもできる。
唯一民主が勝った選挙区。実質、民主笠ひろふみVS自民:中山のりひろ。珍しく自民が負けた選挙区。この自民候補がどういう候補だったか調べたらおもしろいかも?!
11区は小泉進次郎の選挙区・・・。上昇続けている訳ではなく、上下してるので推移は特に問題無いと思うが、なんともいえん異常に高い得票率がなんとも不気味。そんなに11区の国民は頭弱いのかな?
全体的に横ばいで正常な開票だろう。
12区同様全候補横這いを続ける自然な推移。多分正常な開票。
ここが特に綺麗に右肩上がりになっている。他の候補が右肩下がりに見えるのは多分自民が異常に増えている為。つまり自民得票率があがれば当然他の候補の得票率は押されて下がり気味になっていくが、多分自民抜きでグラフ作れば綺麗な横ばいになると思われる。ここも激戦区だから水増し量が多いのかな?
圧倒的な地盤の河野太郎の選挙区。他の政党が候補を立てない程の強さを持っているのだろう。操作してない為か2人ともほぼ横ばい推移。
途中グイっと上昇してる部分があるがちょっとなんとも言い難いかな。少し水増しした可能性もあるが誤差の範囲と判断・・。
最後の18区だが、多分正常な開票がなされればこの18区の様に全候補の得票率がほぼ横ばいに並ぶはずだ。統計学上こういう推移が一番自然だ。
無論この解析だけでは不正選挙が行われた決定的証拠にはならないが、かなり不可解なのは間違い無い。一体どんな手法で手を加えられたかはわからないが、ネット上に散見する多数の疑惑情報の一つとして不正の全体像を解明する参考になればと思いUPした。