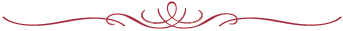日本語版(改訂版 P192)
「月よりの神言」は初版が平成3年10月5日に出版。平成7年4月1日に改訂版(増補版)。
高知県安藝郡田野町二三七二番地、須藤紫郎の長女。小学校を卒業して奈半利町の藤村製糸に勤務後、高知市に出て川村叔母の菓子製造の手伝い後、大阪の市岡元町四丁目上平四丁目上平鉄工所の家事手伝い。高知に帰り、近所の清岡喜一に嫁ぐ。喜一はインド洋に行く六千トンの商船の舵手で海軍に徴用された三百五十人の船員のうち
船長とボースン長と喜一の三人が生き残り今度は二千トンの船に乗ると出かけました。喜一が戦死。誕生二カ月の子供をおいて里に帰された。あるお婆さんの導き。伊予の国の石鎚大権現。天理教港高分教会。高知市五台山竹林寺三十一番文殊菩薩。岡山の五流尊瀧院。善通寺。 岡山県倉敷市林修驗道総本山五流尊瀧院十二社。
杵が男の道具、臼が女の道具。夫婦が餅をついたら、こをつける。
その後で 大和の天理の中山みきでございます。
天理教でなかったらこの世界はすくわれん時が来たぞ。大和に入れ。みきが待っておる。大和に入れ。何もかも水の様にとけていく。みきはお前が大和に入る日を一日千秋の思いで待ちかねておるぞ。「かみがでゝなにかいさいをとくならバ
せかい一れついさむなり一れつにはやく
たすけをいそぐからせかいの心もいさめかけ」とお前が世に出て話をする事をみきにいわしてある。
天理教の船場大教会の港高分教会の会長の樫尾さんの世話になり昭和三十五年五月十八日天理に参り船場の詰所でお世話になりました。主任の赤木さんは昔の人は六カ月別科を出られて十柱の神々の十全の守護を説かれたので
良いお助けが出来ましたが今は十全の守護を
説かれなくなりました。
<P66> 赤木の言う通りぞ。甘露台を据えたわけが
十柱の神々、天理天体の働きがわかると