最近、「戦前のおふでさき」と称して、教会本部公刊のものと比較して、大正13年8月に、木下松太郎氏が出版(木下真進堂)した「おふでさき」が紹介されている。これは、昭和9年にも再版された。元々「おふでさき」は、教祖がしるされたとき、17綴りに分けられ、それぞれの表紙に、号数及び〔年号〕が記入された。それを、担当したのは、中山秀司氏と山沢良助氏といわれている。普通、我々が「おふでさき」といっているのは、〔昭和3年〕中山正善2代真柱が、教会本部から公刊したもので、即ち教祖が、特に原本として、残すよう意図された正冊中山本と、いわれるものである。この正冊に対して、正冊と同じ歌の一部、又は正冊にないお歌(号外)を、高弟にそれぞれ与えられたものを、外冊(げさつ)と称されている。詳細は、二代真柱著「外冊おふでさきの研究」(復元第22号~26号参照)。
「おふでさき」は、明治16年3月、官憲に没収されるのを防ぐため、焼却処分したことにして、秘密裡に保存され、又、心あるものによって筆写されてきた。(当然、筆写の又筆写も、頻雑に行われてきたのであろう) このような状況下において、所謂木下本(便宜上)の内容を、検討する必要があると思われる。問題は、2,8,12,16,17号,17号追歌、その他の一部が、数の多少も含めて、正冊と異なると、指摘されているところだ。
さて、木下本のおおよその印象として、次のようにいえる。
| 1 |
同じ歌(もしくは、類似した歌)が、同書の中で、重複して出てくる。(特に8号の31~52)。 |
| 2 |
無作為に混入しているため、お歌の筋(意味)が、通りにくくなっている。 |
| 3 |
今までに、紹介されたことのない「号外」が、収録されているように、みられる。 |
| 4 |
付録として「甘露台三下り」がある。 |
次に、号を追って、みていくことにする。
〈2号〉26は、別に問題にならない。
〈8号〉31~52は、他の号にある歌が、無作為に混入しているため、話の筋道が通らないため、恐らく筆写の又筆写によってか、複数の写本を、参考にしたために、22首が、参入しているようだ。只、この中で、38,39,40の3首は、中山本や、これまでの号外にないもので、
これは考察に値する。
| 38 |
このやしき このよのおやが でてるから
おびやさんしき ゆるすことなり |
| 39 |
このゆるし もとなるおやの しょうこふに
おびやゆるしは たすけみちあけ |
| 40 |
このやしき もとのかみがみ でてるから
にんげんはじめ もとのいんねん |
この一連のお歌は、おびやさんしき(あつけんみよう)(注1)を、歌ったもので、十柱の神々の、存在を伺わせる意味のある歌である。同じ歌が辻家文書や、市川栄吉(城法2代)文書にもみられる。
〈12号〉
| 157 |
このはなし 月日の心 ばかりやで
にんけん心 あるとおもうな |
| 158 |
このことを みな一れつ ハしんちつに
をもてたのめば どんな事でも |
木下本では、同じ2首が、157-158,181-182 と、2カ所に出てくる。しかし、中山本では、この2首は同号の末尾、181-182に、1回だけである。最近の、おふでさき研究では(2台真柱も指摘している)、この181-182のお歌は、本来156の後に来るものだと考えられている。12号が、書き終えられて、表紙がつけられた時に、中山本において、綴り間違いをしたものらしい。
〈16号〉
| 80 |
もふけふは じゅうぶんに ひもつんだから
どんなしごとも はやくかゝるで |
| 81 |
このしごと なにをするやと おもふかな
つきひせかいを おりまわりする |
| 82 |
いちれつを おりまわりをば したならば
どこでつきひが つれてでるやら |
| 83 |
つきひより まわりかけたる ことならば
まてしばし ないしよこはやいで |
| 84 |
いままでの はなしといふは なににても
いひきたる ことばかりやで |
「おりまわり」とは、どういう意味なのだろうか? 号外として教祖は、この一連の歌を高弟の一人に、与えられたのだろうか? 中山本や、号外にはみられない。
〈17号〉
| 77 |
しんじつの いとをしと をてくるものは
すえではかみが まちうけている |
77の〈いと〉は、初めての言葉である。号外なのか?(これをばな いちれつこころ しあんたのむで という、中山本17号75の後に、最終歌として出てきている)余分のようにも思える。
〈追歌〉
明治18年(教祖88歳の御時)酉5月より、お書き取りとして、5首の歌が載せられているが、明治15年正冊17号が書き終えられてから、3年後に、又このような歌が読まれたのだろうか?
〈甘露台三下がり〉
「これは、甘露台地場定め(明治8年)以降の、教祖の作である」として、同書の末尾に紹介されている。この三下りは、他の高弟の書物の中に、たびたび、散見するものである。こかんさんの作とも言われており、今後の研究が待たれる。
以上、木下本の、号を追ってみてきたが、「おふでさき」は、逸話にも伝えられているように、「書いたものは、豆腐屋の通い帳を、見てもいかんでと言って、親神が、耳に聞かせて下された」と、教祖が述べているので
、かなり厳密にやっておられて、正冊中山本の権威は、高いと言わなければならない。只、この木下本は、号外等も、あるようなので、正冊本を読む上で、参考になると思えば、いかがでしょうか。
|
| 『参考資料』 |
| 甘露台三下り |
| これは、甘露台地場定め(明治八年)以後の教祖の作である(こかんさんとの説もある)辻家文書にも見られる。 |
一下り
一ッ、ひのもとやまとにて やまべごほりのしよやしきに
二ッ、ふしぎこのたびうまれこに あたえあるのがめづらしい
三ッ、みつかめへよりかんろふが てんよりをりたとゆふわいな
四ッ、よにくだりたるかんろふが じみよふぐすりであるわいな
五ッ、いつもくすりはあるかいな これはさきなるためしやで
六ッ、むねのわかりをせふこふに てんのあたへがあるのやで
七ッ、なにかてんりがかのふたら めづらしたすけるものや
八ッ、やしきのうちへはいるなら いかなものでもこいしなる
九ッ、このたびまではしらなんだ もとなるぢばやおやさとや
十ド、このたびいちれつに むねにたづねてくるわいな |
二下り
一ッ、ひろくもんよりさしかけて ほんやのもよふしよふかいな
二ッ、ふしんするならぢどりから みさだめつけにやいかんでな
三ッ、みればよふばがじやまになる どこへなほしてよかろ
四ッ、よふばひとつでいかんでな みいつゆうつはせにやならん
五ッ、いつまでしやんしてみても いづれよおばがじやまになる
六ッ、むりにとれゑとゆはんでな こころさだめてとるがよい
七ッ、なんでもたちものとりはらい あとへたてるがよいほどに
八ッ、やしきないとはおもふなよ もとのやしきがあるほどに
九ッ、このうらにいつまでも おいてもらふとおもへども
十ド、このたびぜひがない やかたもらふてたちかへる |
三下り
一ッ、ひろくのにたきばしよふを はやくぢどりをするがよい
二ッ、ふしぎふしんであるからに うちのまゝにはならんでな
三ッ、みないちれつは かみがしはいをするはどに
四ッ、よりくるひとのあれこれと はながけするであらふから
五ッ、いつもだん/\くるとて たいぎするのやないほどに
六ッ、むりにどなたにも たのみかけるやないほどに
七ッ、なんでもしんじつかみさまの まじわりさしてもらいたい
八ッ、やがてふしんにかゝれども たのみもかけずとめのせず
九ッ、ここまでだん/\ひはたてど じつにわかりたものはない
十ド、このたびしんじつに たしかりやくがみえました
昭和九年 十月 一日 印刷
昭和九年 十月 五日 発行 |
(注1)〔おびやさんしき〕
(おびやさんしき)については、「こふき話」(2代真柱著「こふきの研究」参照)の和歌体14年本(山沢本)に次のように記述あり。
うむときの しゆごくださる かみさまハ
たいしよくてん これなるかみハ |
99 |
たいないの ゑんきるかみで ほふけさま
をふとのべへの かみさまなるは |
100 |
うむときに ひきだしのかみ しんごんで
うみだしたあと しまいつなぎハ |
101 |
くにさつち このかみさまハ ぜんしゆで
このさんじんハ あつけんみよふ |
102 |
この三かみをびや いゝさいごくろふて
をびやゆるしハ はらをびいらず |
103 |
もたれもの 七十五日このあいだ
どくゆみいらず このさんしきを |
104 |
ゆるしあり つねのからだで けがれなし
をびやゆるしハ このやしきにて |
105 |
ゆるしだす これハこのよの にんげんを
はじめかけたる をやのやしきで |
106 |
このゆるし さんぜんせかい このよふに
ほかにあるまい むまれこふきよ |
107 |
にんげんを やどしこみたる やしきなる
しよこあらハす たすけみちあけ |
108 |
| 胎内の縁を切る-たいしよくてん-法華様(日蓮) |
|
| 子供を引き出す-をふとのべ-真言 |
|
| 産んだ後の始末のつなぎ-くにさづち-禅宗 |
|
| この三神を総称して(あつけん明王)という。 |
|
それでは、あつけん明王とはどのような神(仏)なのであろうか。石崎正雄氏は、『こうきと裏守護』(天理大和文化会議、一九九七年)の中で、「あつけん明王」が仏教の仏名なのか、こうき本独自の守護神の名前なのか、現在でわかりません「310-311頁」。あつけん明王については、若き神こかんに降りた神がまさにそれであった。
明治二年五月半ばに、高弟松尾市兵衛の息子が重い身上になった。六月になって、教祖とともにこかんも市兵衛宅へ出張したが(他に同行したのは、飯降伊蔵、仲田左衛門、西田伊三郎)、その五日目にこかんに神がかりがあった。「正文遺韻抄」によると、こかんに下りてきたのは「あつけんみやうおう」であった。この神(仏)は荒ぶる神(仏)であった。市兵衛宅へ出向いた教祖一行を叱責するのである。(「正文遺韻抄」、69頁) ここに付せられた説明によると、「あつけんみやうおう」が教祖に対して高慢の強い市兵衛宅からすぐに引き返せ、と命令しており、その結果、教祖は一同とともに駕籠に乗って帰宅したとある。市兵衛の子息は、まもなく亡くなった。教祖は、こかんと上田ナライトにあつけんみようの神名を授けられたという。しかし二人は、をびやの神でありながら、一身ぐらしを期待された。これは、如伺な意味か?
又こかんは一方で、くにさづちのみことという神名を持っていた。 |
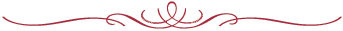
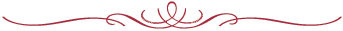
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)