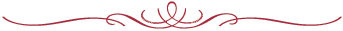
|
お筆先の意義考 |
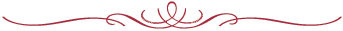
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年.2.25日
| 【お筆先の意義考】 |
| お筆先は、天理教教祖中山みきの「坐りつとめ地歌」、「御神楽歌」に継ぐ重要教典であり、1869 (明治2)年から1881 (明治14) 年にかけて断続的に執筆された。教祖みきは、お筆先の中で、云うところの神の思惑、その思想、世界設計基準を余すことなく吐露している。そのお筆先は凡そ「神意伝え」と「諭し」の二種類の御言葉から成り立っている。「神意伝え」は、「宣明」、「つとめ」、「真柱」、「予言」、「神意一般」、「神言」、「元の理」から成り立っている。「諭し」は、「埃−病論」、「貸物借物論」、「用木論」、「秀司論」、「屋敷論」、「上−高山論」、「日本−唐論」、「その他諭し」等々に区分される。これらの教理が、これまでのところ言及されていないが古代出雲王朝系の伝統的な和歌体で、且つホツマツタエ的韻文で書かれている。「坐りつとめ歌」、「御神楽歌」が「神楽、手踊りのつとめ」の地歌として意味があるのに対し、お筆先は「筆先の責め」と「話しの台」のお諭しとして記されている。 天理教教典には他に、みきの口伝逸話、みきの道すがらを学ぶひながたを綴った教祖伝も教典と云えるかも知れない。これに本席のお指図、真柱伝、天理教史、その他諸文書が加わって天理教教典が構成されている。 お筆先は、ユダヤ教の旧約聖書、キリスト教の新約聖書、仏教の仏典、儒教の論語に匹敵すると思われるが、それらが共通して教祖自身が書いたものではなく弟子たちの共作であるのに比して教祖直筆である。価値がいやましに高いと云うべきだろう。みき思想の世界史的偉大性に注目するなら、直筆お筆先には至宝の価値があるといえよう。 2005.6.29日 れんだいこ拝 |
| 【お筆先の筆取りのご様子】 | |
稿本天理教教祖伝逸話篇「22、おふでさき」が次のように記している。
|
|
|
|
| 【お筆先の効能】 | |
大和の国倉橋村の山本与平の妻いさは、明治15年、不思議な助けを頂いて足腰がぶきぶきと音を立てて立ち上がり、年来の足の悩みをすっきり御守護いただいた。がその後手が少し震えて、なかなか良くならない。少しのことであったが、当人はこれを苦にしていた。それで、明治17年夏、おじばへ帰り教祖にお目にかかって、その震える手を出して、「お息をかけていただきとうございます。」と願った。すると教祖は次のように仰せられた。
教祖は、このように諭された後、おふでさき17号全冊をお貸し下された。この時以来手のふるえは一寸も苦にならないようになった。そして生家の父に写してもらったおふでさきを生涯、いつも読ませていただいていた。そして誰を見ても熱心ににをいをかけさせて頂き、89歳まで長生きさせていただいた。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)