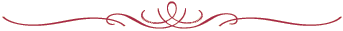
| 元の理効能考、お諭し考1、天文学、和暦の理 |
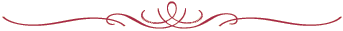
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.11.27日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「元の理効能考、お諭し考1、天文学、暦の理」を確認しておく。ここで、「元の理」の元々の教理を確認しておきたい。この種の試みはまだなされていない気がする。「My Library Home 」の天佑會「眞()の寶()(上巻)」その他参照。 2007.12.25日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【天佑會「眞()の寶()(上巻)」】 | |
天佑會「眞()の寶()(上巻)」。
|
| 【一年中節の理 】 | ||||||||
冬至(十一月中)、夏至(五月中)、春彼岸(二月中)、秋彼岸(八月中)、三月節の節句、九月節の節句。冬至より春彼岸までを冬、春彼岸より夏至までを春、夏至より秋彼岸までを夏、秋彼岸より冬至までを秋と云う。
|
| 【一日の刻限の理】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時、旬、刻限と云う事が一番大切なり。時計は龍頭と云うて月日也。
|
| 【十二支の理】 |
| 十二支の動物は人間に成るすぐ前のものである。一番人間に近づいたものなり。人間が最初は五分に生まれ、長き年限の間に八千八度生まれ替わり、その道中を色々のものに変化して通って来た。神様もその間、皆な通って下された。そこで、「ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い」と云うような十二支の名がある。人間ではなく、神様が、この十二支にご変化下されたものゆえ、その理が獣類にある。人間もこの年に生まれた者は、因縁として大体この性質がある。しかしこれは大大体の事で大あらめの事なり。 神様は、人間をここまで育てあげる為に、実に容易ならん永い間の御苦労を下された。神と云うものは、人間の姿にでも龍にでも大蛇にでも何にでもなる。人間の智恵では到底思い計る事のできない御力、いわゆる通力のあるものが神である。この世に昔より大きな恐ろしいものは皆な月日が色々の者に変化して居られるなり。或いは悪気を戒め、善道に導き下された天地開闢の時は八十夫婦揃うた。これが八方八社の理であ。この時に開闢の時の親様はくにさづち様、月日様の思召しにより、これは女猿と変化して出たと仰せ下さる。猿王権現と祭っているはこの神である。産の王と云う神様なり。 最初五分の人間が四寸に成長してより八千八たびと云うて鳥や獣(けもの)をくぐる。最初は魚の形、魚でもうろこやひれのないものからうろこのある泳ぐ魚となった。魚から鳥となった。鳥でも段々発達して鷲や鶴のようになってから獣となる。獣類も段々生まれかわり死にかわり発達して、馬とか牛狗とか云う様なものになって人間と成った。最初魚から鳥に変化する第一歩はあひる。あひるは前世は魚故に前世をよう忘れん、水をよう離れん如くで人間も何程結構な話聞いても好きな道で怪我をする如きもので、それが即ち前世因縁故、これを立て替えるのがお道一条、人助ける善の方へ心を向け力を入れるに従って心の成長発達変化して悪が取れる。 又人間が八寸に成人した時、泥海中が水と土とが分りかけ一尺八寸の時、海山天地日月分りかけ三尺にて物を云いかけ、五尺に成人した時、海山天地世界も皆なできたと仰せ下さる。段々と成人に応じて食物(じきもつ)、立毛(りゅうけい)も、不自由なきように与え下されて、水中を離れて陸地に上がりて住むようになり、万づの事を人間に入り込んで教え仕込み下された。 一回りを七日間とするは、元奈良長谷七里四方の間に七日間に産み下ろしの理。三十日にて山城、伊賀、河内、産み下ろし、三十日を一と月と云う。大和国内に産み下ろしの人間が日本の人間故大和魂という。天理から人間と現わしてこの世に産み出して世界万物御作り下されたる親様の御苦労は容易でない。「ようこそここまでついてきた、実の助けはこれからや」と仰せられる。 人間の元祖のくにさづちの命、女猿。この者は三寸にて生まれ、八寸と成長する。その子らが夫婦となり、さらに宿し込み給う。その子らは三寸五分より生まれ、一尺八寸に成長す。その子らが夫婦となり、さらに宿し込み給う。その子らは四寸に生まれ、三尺に成長す。この時、世界高低と水の三つに分かれる。その子らが夫婦となり、さらに宿し込み給う。その子らは八寸に生まれて五尺と成長す。この時、世界全く開闢す。それより九千九百九十九年間即ち天保九年、戌年にて一世年限満ちる。天地開闢してより六千年の間は神代。この間は人間に万の事を教え仕込み下さる年限、又神様も何でも人間を殖やそうとして居らるゝ時なり。 この世の元創まりは泥の海と仰せられ、泥々とした水土の別れもなく、月日と云うもなく、人間もなく、世界もなく、只茫々とした泥の海にて北もなく、南もなく、東と云うもなく、西と云うもなく、只今のおぼろ月夜の如きもうろうとして真っ暗でもなく、明るい事もなく、その中に二神あり。これ今日の月日二神なり。月様が、国床を見定められて、御立ち昇り、国の床を御立て下されし故、くにとこたちの命と申し上げる。夜となく昼となく泥海中を御照らしなされましたが泥海中に只呆然と神が居たばかりでは何の楽しみもない、神と云うて敬うものもなく気のいずむ事なり。これより我々両神心を合わせ、どうか手足の付いた重宝な人間を拵え、物を言わし、又世界を開闢して、その人間に我ら両神心を入れ込み、物を教えて守護すれば、日がら刻限立つことならば、この人間に陽気遊散をさせ、又その他何事も見らるゝ事と、その人間に入り込んで世界の陽気を見よとの御相談月様より日様になさる。 日様も御同意にて殊のほか御面を笑み給い早速御承知に相成る。思いが足ったと云う理でおもたるの命と申し上げる。又女は子を育つる役故、上より種を授かればその身が重くなる理。又この理を以って人間も男より全ての指図を出す。女はこれに応じて働くのが順序となり、又女は夫の云う事にはそむいては成らんと云う事も皆なこの神の理から出る。 又日様が後より御現われ日を照らし給いし故、人間夫婦も女は男より年下と云うも順序となる。又その人間には何と何を食わしてどう云う事をさせよとの御相談、紋型の更になき人間を拵えるには雛型となる種、苗代の道具がなくては作れぬところから、泥海中を見澄まし給い、いざなぎいざなみ様御二方を見出され、これを人間男女の雛型と定め、又六社の神様を一々御承知の上貰い受け、その御心味わいを見て人間の道具と造り仕込み給う。 いざなぎの命様には月様の御神魂入り込み給うて、天を象り夫の理として父となり給い、いざなみの命様には日様入り込み給うて、地を象り婦人の理として母と成り給い、創めて人間と云うものをこの世に生み出された。故に人間は正しく月日の子である。月様の御心に入り込み男の魂となり、女は日様の御心に入り込み給うて女の魂と成る故男女は身心違う。なと云うて月様男一人、むと云うて日様女一人、なむなむと宿し込み下さる。 例えば人間でも世の中に只一人や二人あるだけでは何の楽しい事も面白い事もない。多人数あってこそ、その中に陽気も生じ楽しみある。又親だけにて子が一人もなくば寂しい。楽しみもないと同じ。人間を拵えるに、八方八神を集めて型を造られたる故に人間は神の八方と云う。かの昔よりのしきたりにて伊勢の大神宮を始め各神社の神楽として獅子を舞う法式は、月日様泥海中に現われ人間を作り世界開闢する為に上に上がり下に沈み御苦労下されたる泥海中より御立ち上がり給いし元々の有様を象りたる理と悟るべきなり。又八柱の神様には一旦月日に御承知の上飲まれ給うて月日は皆な食ってしもうて、その心根味わいを見てその性を人間と御造化下されしものなり。故に八方の神様は元々の御姿はなくなり、これより次第に御変化下さる人間始め万物に変化下されしものなり。故に人間の身体は即ち八社の神様の御変化成し下されたる、その実体なる事を知るべきなり。よって人体と神様と別々でなき事を知るべし。月日は天に御心現わし万物に御心入り込み段々御変化なし下されて八柱様も皆な同じ人間を成長さす為に御苦労下さる。人間の心一つを楽しみて居て下さるが神なり。道具の神様はその道/\だけ日夜御苦労下さるは、これを御楽しみとして御働き下さる。 食事の時はくもよみの命が表に立ち、おおとのべの命が裏にて飲み食いできる故、この二神の御働き聞く事、物云う時はたいしょくてんの命に立ちて、かしこねの命表にてできる。言葉はこの二神の御働き。色情の時はつきよみの命だけではできん。くにさづちの命御二方の働きによる。月日二神は見る事御骨折御働きなれど、この二神は何れの働きにも入り込み給わさればできぬ。つきよみの命は月様の一の道具神、くにさづちの命は日様一の道具神。 かしこねの命、たいしょくてんの命は天に御座る。即ち顔頭に御住まい下さり月日に添い給う。くにさづちの命、つきよみの命は地の低い所に御住まい下さり、色情の大切なる御守護ある。この如く月日様より皆な使うて御座るものなり。故に人間は勝手の事に神様を使う故迫るなり。人間のものは只心一つだけなり。心は無形のものなり。交合の時はつきよみの命、くにさづちの命代理にて、十柱の神共に御働き下さる。見る時は月日様代理となり給い、十柱の神御働き下され、物言う時はこしこねの命代理となり給い、食事の時はくもよみの命代理となって十柱の神共に御守護下さるなり。 |
| 【一年と一月と同一の理】 | |
| 十二時辰(じゅうにじしん)とは、近代以前の中国や日本などで用いられた時刻割のことで、1日をおよそ2時間ずつの12の時辰(じしん)に分ける時法である。十二辰刻(じゅうにしんこく)、十二刻(じゅうにこく)、十二時(じゅうにじ)とも呼ぶ。時辰、辰刻、刻、時は、いずれも本来は単に時間、時刻という意味の言葉だが、十二時辰制のもとでは1日を12に分けたそれぞれのおよそ2時間を意味し、刻・時はまた任意の2時間を表す単位としても使われる。時刻は定時法の場合で、不定時法では季節によりやや変動する。 漢語では「子時」(しじ)などと呼ぶが、日本では「子の刻」(ねのこく)、「子字」などと呼ぶのが普通である。十二時辰の名称は書経や詩経といった古書に散見されるが、十二にまとめられたものは春秋左氏伝の昭公5年「故有十時」に対する杜預の注釈において見られる。
その名称のうち太陽の位置に関すると考えられるものは日出・隅中・日中・日昳・日入である。日の出、日の入り、南中する時間が中心であり、隅中は太陽が東南隅を過ぎて日中に近づいた時間であるといわれ、日昳は太陽が西へ傾くことを意味するとされる。また空の明るさに関するものが平旦と黄昏と考えられ、日の出前あるいは日の入り後のいわゆる薄明の時間帯に由来する。 一方、古代中国人の食事の時間帯に由来するのが食時と晡時で、古人は1日2度の食事を日の出後と日の入り前にとったとされる。またその他に鶏鳴は文字通り鶏が鳴く時間帯に、人定は人が寝静まった時間帯に由来すると考えられる。 各時辰のおよそ2時間の始まる時刻を初刻(しょこく)、中間を正刻(せいこく・しょうこく)と呼ぶ。1日の始まりの0時は、十二支の第1である子の正刻となる。つまり、1時間早い23時が子の初刻で、子の刻の始まりである。子の正刻つまり0時を正子、午の正刻つまり12時を正午と呼ぶ。日本では各正刻に鐘を鳴らした。その回数は、正子・正午には9回で、それから時辰ごとに1回ずつ減る。そのことから、子の正刻(午前0時頃)を「九つ」、以下2時間毎に順に「八つ」、七つ、六つ、五つ……と呼んだ。3時は八つになるので「八つ時」という。因みに3時頃食べるものを「おやつ」と言うのは、これが語源である。「暮れ六つ(むつ)」は夕暮れを知らせる。 時報を「9」回の鳴鐘から始めるのは、陰陽師が暦とともに時間も管理していたことに由来する。陰陽道では奇数を縁起のよい陽の数とし、その極値が9であることによる。以降、次の時辰は9を二つ重ねて18、さら次は三つ重ねて27とするが、鳴鐘は十の桁を省略して8、7としている。2時間おきでは不便なため、半刻(1時間)後を、丑の初刻から順に「九つ半」「八つ半」……と呼んだ。いずれも、12時間後に同じ呼び名の時刻が来るため、区別するためには「夜九つ」、「昼九つ」などと呼んだ。「おやつ」の語源の「(昼)八つ」は不定時法下では変動するが、およそ14時である。 室町時代から江戸時代間での日本では、不定時法が主流だった。不定時法では常に、日の出は卯(日出)の正刻、日没は酉(日入)を正刻とする。このため、夏場は日の出が早く日没が遅くなり、逆に冬場は日の出が遅く日没が早くなることから、昼夜それぞれを6等分した時辰の長さ、つまり昼の1刻間と夜の1刻間は同じ長さにはならず、冬の昼間や夏の夜間は短くなり、冬の夜間や夏の昼間は長くなる。これを平均して2時間である。したがって正子・正午以外の時刻も季節により変動した。 方位との関係。正子の太陽の方位は北つまり十二方位の子(し)、正午の太陽の方位は南つまり十二方位の午(ご)である。地球上の南北線を子午線(しごせん)と呼ぶのは、このためである。同様に、東の方位は「卯」(ぼう)、西の方位は「酉」(ゆう)であるので、東西線を「卯酉線」(ぼうゆうせん)と言う。これらの関係は、他の正刻については正確ではないが大まかには成り立つ。 |
| 【一年と一月と同一の理】 | |
|
| 【一年の理、四季の理】 | |
|
| 【身の内の中と節の理】 | ||
|
| 【天、地、星の理】 | |
|
| 【月の出入の理】 | ||||||||||||||||||||
| 朔日と云うは、月様夜の九つ子の刻より始めて宵の四つ亥の刻に至りて四分の光明を放ち給うを云う。朔日の昼と十五日の夜と表と裏なり。 晦というは月様全光悉皆な黒くなり給うて月籠りというなり。*日というは朝六つ卯の刻より宵六つ酉の刻を云う。十五夜ば宵六つ酉の刻より朝六つ卯の刻迄を云う。 |
||||||||||||||||||||
八日の昼と二十三日の夜と表と裏なり。 朔日は朝六つに出て暮六つに入らるゝが、一日に四分づつ遅れて三日には朝五つ二分に出で、夕の五つ二分に入らるゝ故、夕方には糸目程の月を拝む。十五日迄刻限四分宛遅れて十六日より四分宛早まる故、元の朔日には朝の六つ時となる。此四分と云うは一刻の四分にて一刻は時計の二時間百二十分の四分四十八分宛なり。又月は一日四分宛光を増して、十五日六十分満月となる。 |
| 【満潮干汐の理】 |
| 朔日十五日朝六つ宵六つ満潮。夜九つ昼九つ干汐なり。八日二十三夜夜九つ昼九つ満潮。朝六つ宵六つ干汐なり。
この世は月様の御神体。北に頭を取り、東より南西と四方くるりとしめる世界なり。真は神なり、心なり。その真の気が即ち味なり天地なり。大海の潮(汐)は天地の息なり。天地の息には呼吸と云うて一日一夜に二度宛(づつ)の息あり。即ち、月の息は、潮満ち掛けて来る又日の息には汐干くなり。月の息はこれ元素地に下さりて、潮緩み溢れて殖ゆる。日の息はこれ元素地に上りて塩沈む。これによって満ち干きするものなり。この潮の差し引きには刻限四分づつ違い日々に有り。天地の自由用にて人間有り、世界有り。それには万物有る大海の潮汐の満ち干きも月の出に満ち上がり、月の入るには同じく潮満ち上がる。これ月は万物を司る元にして、人間、鳥畜類、魚貝の類、草木等に至るまで天の月様の養い下さる。 潮汐の味を世界へ潤わせ給う故に、大海の塩水が引く也。故に月の天井には必ず汐干きとなりて引く。併して東西南北の違いにより満ち干の刻限少しは違う。違うだけ月の出入りも遅き早きあり。即ち十五日の月の出は夕の六つ時にて潮の満ちるも夕六つ時なり。月天井は夜九つ時なり。この時に全く潮干る底なり。然れども世界の広き事なれば、東洋と西洋とは月の出入りも時刻も違い有る故、満ち干きも違い有る也。 月の出入りにつれて満ち干をするものなれば、その所では月の天井には必ず潮干る也。刻限の違うは日々日の出の時が違う故。月日には夜昼同じ様に照らし下さる故神の守護に違いはなけれども、例えば朝寅の七つに日の出る所と卯の六つに出る所と五つに出る所とある如く。日の入りも申の七つに入る所も六つに入る戌の五つに入る所と有る故、潮満ち干きも同じ。又東西南北によって少しは違い出来る世界の真の地は元の子として神として一として天地世界の元也。 |
| 【八方八色の理】 | ||||
「八方八色の理」が次のように云われている。
|
| 【五音之元の理】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いは水で月様。ろは火で日様。はは続ぎ、くにさづち様。せは勢せいと云うてつきよみ様。すはくもよみ様。んはかしこね様、六くと云うて心である。んは五音の本ではない。これが五音にて皆な戻る。十二音ずつ四つ四十八文字。一日ができて一と月ができ、一月ができて一年、一年ができて一代ができ。四つの理、五柱とかしこね様なるが月様には必ず日様が御添いなり。つきよみ様にはくにさづち様、くもよみ様にはおおとのべ様、かしこね様には必ずたいしょくてん様、故に八方の神となるなり。 木火土金水、咽、舌、歯、唇、歯茎、身の内の方と字の理から説く方とあり。身の内から説く四十八文字は皆な身の内にあり。又世界で説くのは空海上人が一つの歌に綴られ仏法の経文にかたどりたるが、文字はそれより以前からあったもの。 親神様の教えは言葉に理があるのは言葉が先にできて文字が後にできた故、天地開闢以来幾千年の間、人間によろずの事を仕込み下されて天理から名がつき言葉ができて居る故に言葉が元なり、名に理がある、言葉に理が有る也。文字は種々様々の品を分ける為のもの故、言葉は理があって、言葉あり、言葉あって文字あり、仏教が一の枝、文字が二の枝と仰せられた。故に世界に昔から云うて居る事の理が天の理から出て居る。名もついて居る、神様は云うていれども元知らぬと仰せなり。 「世上で云うとか諺に云うのも歌に謡うのも皆な神様が云わすのや、歌わすのや、歌の流行するのでも世上は歌で知る、又夢を見るのも月日なり」と仰せられる。 例えば病人の諭しでも其の人の云う言葉の理を分ける、神が云はすと仰せらる、言葉一切天理をはずれては云えん、無きもの故(又病む時は言葉がなまる)云う事となり、ふりに現わるる所で皆な見分けるなり。 |
| 【地球と月、太陽の関係】 |
| 地球は、太陽から最適な距離に位置しており、地球上の気温は−34℃から+49℃の範囲で推移している。地球が太陽からもう少しでも離れていたら、生物は凍死してしまう。逆に太陽にもう少し近ければ、皆な焼け死んでしまう。太陽から地球までのわずかな距離のズレが、地上での生命の生存を不可能にする。地球は太陽から適切な距離を保ちながら、時速107,823kmの速さで、太陽の周りを回っている。地球は地軸を中心に自転しながら、地表全体を毎日適切に温め、また冷やしている。月の大きさも適切で、月は地球と絶妙な距離を保ち引力を保っている。月の引力が海に潮の満ち干きを起こし、海水がよどまないようにしている。また月の引力が、海水が陸上にあふれ出ることがないようにしている。 |
| 宇宙全体が、同じ法則に従って動いている。重力は場所によって強さが違うものではない。どこでも一定である。光の速度も一定である。地球は24時間で自転している。地球の自転は、さまざまな力学的要因が作用して、原子時計で計測すると、24時間よりほんのわずか早かったり、遅かったりしている。そのために数年に一度、「うるう秒」を設けて、世界時計を調整している。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)