| 人間の身体が出来てくると云うのは、知らぬ間にお腹に宿りて、十ヶ月の間、眼も出来てくれば鼻も出来、耳も出来てくれば、口も出来、手も出来てくれば、足も出来、男と女と云う身体も出来て来る。これ皆、親の見るまでに出来てある。
人間の身体は、我がことと言うていれども、誰も知らぬ間に出来たものである。物を食べ、物を聞いているといえども、知らぬ間に大きくなって、十五歳になれば、一人前に成ってくる。立毛造りているのも、人間は修理、肥えしていれども、種を蒔けば知らぬ間に芽が出来、葉が出来、花が咲き、実が入ってくる。世界にあるもの、草木、鳥、畜類、万物が出来てくるのも、夜が明ければ昼となるのも、これ皆不思議と云うていた。このように、知らぬ間に成ってくることを天の理と云う。
大雨降るというのも、大風吹くと云うのも、旱魃[干ばつ]、地震、雷、津波、流行病が流行ると云うのも、これ、皆人間思案でなるものではない。神様の残念、天の理で成ってくるものである。
人間の難儀と云うは、夫婦が離れ、親子が離れ、兄弟が離れ、貧に成ろうまいと思うても、貧になり、病に成ろうまいと思うても、病にかかる。難儀するのも、不自由するのも、これみな知らぬ間に成ってくるものである。これ、人間の考えで成ってくるものではない。残らず、天の理に添うてないものである。神の残念と云う。難儀すると云うのも、良いことにあうと云うのも、これ皆人間の心が天の理に添うてあるのと、ないのとによって、成ってくるのが、天の理と云うのである。
|
| 人間元々泥海の中にて出来たる理
この世界は、元々人間も無く、世界も無く、泥の海。その中より月日二神は先に立って、八柱の神様を道具に使うて拵えた。これは元々も、今も少しも理は変わらん。
その訳は、元々泥海の中から出来た証拠に、今人間が出来るにも、男、女の夫婦から子が腹に宿る。その子は、明るい所で出来るのではなく、腹中の暗がりの中から出来るものなり。また、母の胎内では、子袋の水の中で出来て、十月十日の日待ちて生まれ出るものなり。これも理は変わらんものなり。
次に、九億九万年の間水中の住まいしたとある。その証拠に人間銘々の足の裏に土踏まずと云う所がある。人間は、三尺にして物を言い始めたとある。これも今人間は三歳に至らねば言葉の使い分けが出来ぬも、同じ理なり。
五尺になって天地が分かりて、人間も陸に上がりたとある。その証拠に、算盤の玉でも、五つ置いたら必ず上へ納めてしまわねば、動かされぬのも理は同じ。その人間は、陸へ上がってから、天からじきもつ(食物)を与えられたとある。これは、人間は子を産むにも、子の生まれ出るまでは、乳が出ぬもの。子がこの世へ生まれ出ると、直ぐに乳房に乳は降りて来るものなり。
また、人間陸へ上がってから、神が段々とよろずのことを教え、仕込んで通りた。これは、人間が子を産んで、一人前の知恵がつくまで親が仕込みをするのと、同じ訳なり。
理の解らん者は、九億九万年の水中の住まいの元の理を聞くと、その時は天地と云うものが無く、夜昼の一日と云う区別もなければ、一ヶ月と云う月も出来ん。すれば、春、夏、秋、冬の四季も出来ん。それになにゆえ、九億九万年と云う年限は、どうして勘定したものであるかのように思う。それは、最もなることなれど、ここによくよく理を聞き分けねばならんと云う。
この度の教えを、親がされるのは、この世始めてから説いて聞かしたことのない、誰も知らぬ話しを説いて聞かすものである。これまで、人間のしていること、知っていることも、皆な神が教えて来たのであるから、これまでに神が教えて通ったこと、今までに知っていることは聞かすにおよばん。教えるにいたらん。知らぬことや、ないことを教える。人間を造り、世界を造り、今に生きて守護している親神が、諭すのであると仰せられる。
この世を造り、人間を拵えたる元の親が、表へ現れ、おやさまに入り込み、口を借りて委細を説き聞かすとある。神の諭しに千に一つも違うたことはない。親神は間違うたことは教えぬ。しかしながらそれだけでは、得心出来ようまい。よって、よくよく理を聞き分けねばならぬ。
今人間が、母の胎内に宿りて、一ヶ月経って、二ヶ月、三ヶ月と勘定して、もうこれで、と月目であるから、生まれると云うような覚えがあって、生まれた者は、一人もあろうまい。生んだ親と宿した親より他に知ろうまい。その親が云う限りは、それを本当に思わねばならぬもの。これも同じこと。無い人間を造りた親が説かれる限りは、これに間違いは、さらになきものなり。
|
| 天と地と云う訳
天は、人間の成人に応じて段々高く離れ、転じたものゆえ、天と云う。地は元々より、じっとしてあるものゆえ、地と云う。
また、人間の頭より上の天には、水がある。土を掘ると、大抵の所、水が湧く。その天の守護は、水の徳、水の位。水は世界にこの上もないものゆえ、天と地とをくるめて天と云う。天だけを見て天と云うは、人間の話しなり。
|
| 日輪、月倫と云う理
日輪、月輪と云う理は、日輪様は女である。人間も女のお腹から、子が出来てくる。その子が一日一日と、理が出来てくるので、その理によってお腹の子が、日々に成人してくる。地は、日輪様の身体である。地から出来てくるものは、一日一日と理が出来てくる。その理が巡りて来るので、日々の立毛、草木に限らず、虫けらに至るまで、世界のありとあらゆる万物残らず、日々成人してくることを日輪と云う。
日々三十日積めば、一ヶ月と云う。十二ヶ月に積めば、一年と云う。その年が重なってくると、如何なる木でも大木となる。これ皆日輪、月輪の理によって、人間も成人するなり。それゆえ、この世界にあるもの残らず成人することを、日輪、月輪と云う。
|
| 星の理
人間は、万物の霊長と云うて、神様の次には、人間が来る。その人間と云う所以は、その心である。み、は神様のもので心一つが我がの理。そこで、銘々の心、これ本心と云う。この本心が、天に貫きて光りを放つ。その光りが大きくなるのと、小さくなるのとは、徳の厚き、薄きによりて違う。これ本心ゆえに、ほしと云う。
この度、かぐらづとめを教えるは、これも、これまで無いことを始めかけるなり。これは、元、十柱の神様の姿の型をもって、つとめをする。神楽両人は、二柱の神様の姿、くにとこたちの命様、をもたりの命様、の型を取り、男神は男の面、女神は女の面を被りつつ、つとめの手振りも、元の道具の型のまなびをして、ようきづとめをすることなり。この人数十人、鳴り物九つをもって神様を勇めることなり。
この鳴り物の九つは、琴、三味線、胡弓、太鼓、小鼓、笛、摺鉦、ちゃんぽん、拍子木。以上九品。三品、身に付く理。六品、世界六台始まりの理。六台とは、木、火、土、金、水、風の六つなり。合わせて九つ、これ心の苦を忘れると云う理なり。すなわち、この人数九人なり。合わせて十九人にて、かぐらづとめをする。
また、その後、この九つの鳴り物を合唱して、六人にて十二下りのようき踊りのつとめをすると云うのは元泥海中にて、人間を造られた時、陽気遊びするのを見ようと、人間世界をお造り給うた理によって、元の姿を型取り、神のお心を勇めるなり。
すなわち、悪しきを払うて、ようきの心と入れ替えて願うならば、神の心も人間も同じこと。人間身の内は、神様よりの借りものなるがゆえに、神様が勇みて守護下さるなり。
|
| 百姓たすけの理
百姓たすけは、第一には、雨乞い。第二には、芽だしの札。第三には、稔り十分の札。第四には、虫払いの札。この札のお守りは、千枚すって一座のつとめにかける。また、第五には、作物肥えのさずけなり。この肥えと云うのは、糠三合、灰三合、土三合、合わせて九合を調合して用いるときは、肥やし一だの替りとなる。この肥え九合をもって一だとし、百だずつを一座のつとめにかける。これら皆施しするべし。最もこのつとめは、かぐら十二下り手踊りようきづとめなるべし。
これ月日二神が引き出しの守護の神様、をふとのべの命様をもって、お働き下されるなり。このたすけを親神へ願うことなら、神の教えを守り、慎むべし。もし、人道に反する時は、その効き目さらに無きものなり。
|
| 龍と大蛇の理
この世の元始まりは、泥の海。その中に龍と大蛇がいたばかり。人間もなし、何もなし。それでは、楽しみがないから、龍より大蛇に相談した世界なり。人間を拵えて、陽気遊山の楽しみを見ようとて、龍が国床を立って、国を見定めたゆえ、くにとこたちのみこと(国常立命)と云う。また、国見定命とも云う。
龍は、水を吹き、大蛇は火を吹く。水と火とのこの世界。天はりゅう。地は大じゃ。天は水深きゆえ、青みがかる。龍は夜の守護。それゆえ、露が降りると云う。地は大蛇ゆえ、下ほど温みがある。大蛇は昼の守護。そこで昼は、暖かいと云う。また、大蛇の十二の頭、一時に、替り替り火を吹き下さるから、世界暖かいと云う。
そよふく風は、月様の息。差し引く潮は日様の息。天と地とは、月日様。火と水とは、潮と風。これが真の親様。 すなわち、天と水と風と月様。地と火と潮と日様が、一つでも欠けたるならば、例え、身体は備えていても、一時も過ごすことは出来ぬものなり。
|
| 十二支の理
十二支の動物は、人間になる直ぐ前のもので、一番に人間に近づいたものなり。人間が最初五分から生まれ、永き年限の間に、八千八度の生れ変り、色々なものに変化し、通って来た。また、神様もその間、皆通って下された。そこで、ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。と云うような、十二支の名があるなり。人間ではなく、神様が、この十二支にご変化下されたものゆえ、その理が獣類にある。
人間もその年に生まれた者は、因縁として、大体この性質がある。その人それぞれにて、性質が異なるなれど、十二支の神様に対する因縁性質、この理は必ず多少はある。また、神様は、人間をここまで育てあげる為には、実に容易ならん、永い間の御苦労を下されたものなり。
例えば、人間が、犬くらいの時代には、神様は、馬とか、虎とか、獅子とか云うようなものに、ご変化下されていた。それで恐れて、人間は治まった。また、竜と云うのは、くにとこたちの命様が、龍にご変化下さったゆえに、金銭には龍が書いてある。そして、成人して人間と仕上げた上は、神様は元の神に成り給う。神と云うものは、人間の姿にでも、龍にでも、大蛇にでも、何にでもなる。人間の力では、到底はかることの出来ないお力、いわゆる、神通力のあるものが、すなわち神である。
このように、昔より導き下され、そして、天地が開けた時には、八十夫婦揃うた。これは八方八柱の理。この天地開けた時の親様が、くにさづちの命様。月日様の思召しにより、この神様が女猿とご変化された、さんの王という神様なり。
|
| 十二支の訳
日様の頭十二支の方にありて、一時替り替りの守護下さる、その頭の名なり。これをそのまま読めば、幸運となり、逆さに読めば、逆運となるなり。
ね、を、うし、のうても、とら、う、んを開いて、たつ、て行く、その、み、が、うま、れて来る程に、ひつ、ねんせ、ざる、な、とり、ても、いん、で、い、る程に。
ね、に、い、るもの、いん、で、とり、ても、 さ、って、ひつ、ねん、うま、れたその、 み、が、たた、ん、う、んを、とら、れて、うし、のうてしまう。
|
| 人間身の内の理と世界の理
月日様は、人間を拵え下され、その人間に合わせて、世界を拵え下されたゆえ、身の内にあるものは、世界にすっかりある。身の内のことを詳しく解れば、世界の何ごとの理も皆解るなり。
頭は天にて、胴は地なり。その証拠に頭は冷たく、胴、足温ければ、身に不足なし。世界も天は寒い、地は暖かい。土地の高い所は、寒いけれども、低い所は、温いもの。天は月様にて水気なり。地は日様にて温みなり。
両眼は月日なり。左の手は、くにとこたちの命様。右の手は、をもたりの命様。また、両足もその理と同じ。手足の十本ある指の親指は月日。後なる八本は、八柱の神様なり。
心は神なり。いかなる悪人にても、元の性質は正しきものなり。その証拠に、人の物盗むにも、抜けつ、隠れつするは、元の正しき心が咎めるからなり。その正しき心が神なり。
人間の息は、世界のもや、霧のようなもの。身体の水気は水。温みは火。爪は世界の鉱山。睫(まつげ)は世界の松。髭は世界の立毛。頭の毛は世界の大木。前の毛、腋毛は世界の木の節。その他の毛は、世界の用木にならぬ、雑木なり。
口は世界の谷川、谷川に水は絶えぬも同じ理。口には、どこからともなく水は湧くものなり。身の内の血筋は、世界の川。身の内の四十八ヶ所の脈は、世界の湯の湧く所。すなわち原油なり。身の内の怒り病は、世界の地震。腫れ病は、世界の水つき。熱病は世界の日照り。お腹の鳴るのは世界の雷なり。臍は世界の渦潮。夜昼の区別あるのも、身体の前後区別あるのも、理は一つなり。
背筋は、世界の天の川。背筋の両脇は、七夕なり。大骨十二本は、一年の月の数。小骨三百六十本は、日数なり。節七十二は、土用七十二日の理。人間生まれ出しは五分からにして、五分五分と成人したとある。今でも、一寸の虫にも五分の魂と云う。また勝負の勝ち負けなしを五分五分と云うなり。人間を計る物差しは、竹の差しが始まりなり。
また、女の月役は、世界の草木が、花が咲いて稔るのと同じ。月役がありて、子が宿るものなり。この世の元は月様。ね、が一番元ゆえ、人間も子が宿るのが始まり。月様宿り下さるゆえ、月とまると云うなり。
|
| 妊娠十月十日の理
人間宿りてから、生まれ出るまでの十月十日の間は、十柱の神様それぞれの守護なり。
一ヶ月目は、くにとこたちの命様の守護で、水一滴の守護により、体内に宿り、この間に芯なる眼が宿し込まれる。
二ヶ月目は、をもたりの命様の守護で、血の固まりが出来て来る。
三ヶ月目は、くにさづちの命様の守護で、筋、皮をお造りになられる。三ヶ月目までは、まだ人間も、畜類も、鳥も、魚も、形は同じなり。それは元、泥海の時より、八千八度生まれ替った理からくる。
四ヶ月目は、月よみの命様の守護で、芯なる骨をお造り下される。この時期、初めて人と動物の区別がつく。
五ヶ月目は、くもよみの命様の守護で、飲み食いの道をお造り下される。
六ヶ月目は、かしこねの命様の守護で、耳、鼻、喉、呼吸器などをお造り下される。
七ヶ月目は、たいしょく天の命様の守護で、六ヶ月目までに出来た九つの道具を切り、整えて下される。
八ヶ月目は、をふとのべの命様の守護で、知能が整い、身体を引き伸ばして下される。
九ヶ月目は、いざなぎの命様の守護で、種の守護を下される。
十ヶ月目は、いざなみの命様の守護で、苗代の守護を下される。
最後の十日は、十柱の神様がそれぞれの守護を一日ずつ、両親の心と合っているかどうか、調べて下される期間なり。この十柱の守護に欠ける所がなかったなら、何不足無しに安産さして頂くことが出来るなり。
|
| 人間心と魂と云う理
人間の心と魂と云う理を説き分けする時には、魂と云うものは、人間身の内に納まってあるものである。心と云うものは、人間の心の使い方を云うのである。眼で見る時には、眼で見る所へ心は行くものである。手でする時には、手でする所へ心は行くものである。足で行く時には、足の行く所へ心は行く。口で云う時には、口で云う所へ心は行く。耳で聞く時には、耳で聞く所へ心は行くものである。また、船を動かす道具を、ろ、と云うてある。その取りようの加減で船は、どちらにでも動くものである。
どんなことする時でも、心で思う所へ心は行くものである。ここと思う所へ心は行くゆえ、使い方を、こころ、と云うのである。心が行ってない時には、何ごとも出来ないものなり。
|
| 神の裏守護
人間が地に上がってから、仕事の仕込みが六千年、その間道具衆の魂も、人間の生態受けさしてこの世に出し、よろずのことを皆教えた。 仕事の仕込みが六千年も、何ゆえそんなにかかったか。それは、九億九万九千九百九十九人と云う人数に対する仕事の仕込みゆえ、多くの人数に教えて通るには、中々容易な、苦心ではなかった。
まず、神様は、人間は物を食わずにおられぬから、一に食う物を与えなければならぬ。人間に物を教えるのだから、人間の生態受けさして、そこへ神が入り込んでやらなければ、神と人間と直接に話すことは出来ない。それゆえ、をふとのべの命様に、人間の生態受けさして、心に神が入り込んで、百姓、作り方一切を教えた。
しかし、食う物をちゃんと揃えたが、食う物を与えても食うすべが解らん。これでは、ならぬから、くもよみの命様に、人間生態受けさして、心に神が入り込んで、こうして食べる、ああして食べると云う、食う一切を教えた。
それから、くにさづちの命様に、人間生態受けさして、心に神が入り込んで、木綿類を一番初めに教えた。最初から、細かいこと教えても出来ぬから、最初は荒いことからぼちぼち教えて、段々成人し、追々今にどんなことも出来るように、神が守護してくれたのである。着る物一切は、この神に入り込んで教えた。
月よみの命様には、人間の生態受けさして、心の神が入り込んで、つっぱり、踏ん張りの仕事を教えた。
たいしょく天の命様には、人間の生態を受けさして、切れる方の刃物一切を教えた。同じ金に違いないが、切れぬ方と切れる方とは違う。こうしてずっと仕事を教えた。
しかし、ずっと教えても今度廻って行くころには、忘れて、何べんでも同じことばかりしている。数の少ないものなら、覚えているが、数の多いものは、記して置かなければ忘れてしまう。これでは成らぬから、何か記しをしてやったら忘れはしないだろうと、ものの印に文字と云うものを教えた。従って、くもよみの命様に、人間生態受けさして、心に神が入り込んで文字、一切を教えた。この文字の仕込みより、今までの年限は、外国の方は六千年、日本の方は四千年余り経ちてある。
また、くもよみの命様は、色々の物を噛み分けて、色々な薬も教えた。これは、医者の道を教えて下された。医者のねんずる、神農の魂は、くもよみの命様。百姓が雨乞い等で願う竜王、水神、文殊菩薩、薬師如来と云うは、皆同じ、くもよみの命様。名はいくつもあるが、その時々の働きによって名を呼んだ。
元々無い人間を始めてから、書物の出来るまでの年限は、中々広大もない年限であった。その道中の道すがらを神が説いて聞かす。これは、書物には一つも出してない。
また、この書物には、色々戒めしてあれども、毎々悪戯が栄える。これは、神道と云うのは、ようき一方であるゆえ、悪戯が栄えるのであろうとの考えから、この世界より他に地獄極楽は無いが、なれどもあると云うて、人間心和らげる為、仏法を広めた。しかし、その仏法でも、段々悪戯が栄えるから、余程どうしようかしらんと思うた。
月日がかまわなんだら、元の泥海になる。そこで、色々思案した。なれど、折角ここまでにしたものをと思い直して、つけかけた道であるから、幾年かかるともつけずに置かれん。
また、元々は、根から始めて、枝は、後。また、よろずの仕込みは、枝先から神が守護して仕込んできた。そこで、枝には味わいがある。それゆえ、珍しいことは、皆外国から初めてくる。それを見たら日本の者は、直ぐ真似をするやろう。元々あみ出しかけは、皆枝先からである。そこで味のもったものは、皆枝先でなくば出来ようまい。
このよろずの教えの仕込みが済んでしまうのと、また元々約束の年限経つのを待ちかねて、月日が天降る。今度は、ねの廻り口、終いの教えであって、今がこの世の始まりなり。
元々無い世界、無い人間を始めかけた時も、今度の教えも同じこと。これでようようと定まったなら、万劫(ばんごう)末代もう二度と変わらん。また、これまで人間は、建て流しの館と同じこと。内造りは、一つもしてない。今度は、神が内造りにかかりているなり。
|
| 八方の八柱の神様 身体と世界の守護
天地、月日、水気、温みも同じこと。月日両神は、万物の親、万有の集合の大源。月日のお入り込みなくては、六柱の神様お働きは出来ぬ。陰陽和合、すなわち、月日より万物は生まれ出て、各々形を現わし、この世に命が有るなり。
冬は、身の内にては、整える理。世界にては、治まる理。春は、身の内にては、養う理、世界にては、恵む理。夏は、身の内にては、生育の理、世界にては、繁る、成長、生育の理。秋は、身の内にては、立ち働く理、世界にては、熟する理、実が入る理。草木も、根があって、木があり、花が咲き、その花の中に実がのる。この四つが四きなり。天理は冬から始まり、春、夏、秋なり。
人間は、月日の魂より、生まれたる分身なり。人間の身体は、八柱の神様のお心の現われなれば、八柱の神様が入り込み、お住い下さるがゆえ、身体の自由用自在が叶う。神様は、人間の心にのって、お働き御守護下さるなり。
|
| 身の内の東西南北
人間の身体においての東西南北は、左が北、右が南、前が東、後ろが西。人間は、東向きに成っている。
身の内における四季とは、頭が冬、顔が夏、腹が春、背が秋。この頭に付いたものが眼、耳、顔に付いているものが、鼻、口。腹に付いているものが、臍、一の道具。背に付いているものが、手、足。合わせて十二あり。これは十二ヶ月の理。
人間は、天のじきもつを身の内に入れるから、生きていける。天地と身体のつづきの道は臍。臍は、くもよみの命と同一なり。腹は、芯なり。一の道具も、飲み食いのかすの出る所。口から入って、腹を通り、大小便に通じるまでが、春の理。この三つで一季。春は、養いの神。
背は、立ち働く理。例えば、手で仕事をする、背で負う、足で運ぶが如く、総て、働き引き出しの理。秋は、働きの理。
鼻、口の働きは夏。顔は夏。眼、耳の働きは冬。頭は冬。首より上は五倫の心の働きなり。
身体は一年の理。手足を使うは、一と月の理。心は一日の理。左は北、くにとこたちの命様ゆえ、左一切は男の理なり。右は南、をもたりの命様ゆえ、右一切は女の理なり。
|
| 指の理
左親指は、 くにとこたちの命様の理。 冬至、 子の刻。
右親指は、 をもたりの命様の理。 夏至、 午の刻。
左人差指は、月よみの命様の理。 秋の土用、戌亥の刻。
右人差指は、くにさづちの命様の理。 春の土用、辰巳の刻。
左中指は、 をふとのべの命様の理。 秋の彼岸、酉の刻。
右中指は、 くもよみの命様の理。 春の彼岸、卯の刻。
左薬指は、 かしこねの命様の理。 夏の土用、未申の刻。
右薬指は、 たいしょく天の命様の理。 冬の土用、丑寅の刻。
左子指は、 いざなぎの命様の理。
右子指は、 いざなみの命様の理。
一年の理も、一と月の理も、一日の理も身体にある。両手一杯の輪は、一年の理。両手の中指と親指と合わせて一杯の輪は、一と月の理。片手の人差指と、親指の輪は一日の理。また、一と月の理は、十五夜、満月の理。この満月を二つに分けると、左の片手は、二十三夜の月、下弦の月。右半分は、八日の月、上弦の半月なり。ゆえに、左の親指より、二十三夜の月は、夜の子の刻より上がり給い、右の親指八日の月は、昼の午の刻より上がり給う。
冬は、左親指と右薬指。春は、右中指と人差指。夏は、右親指と左薬指。秋は、左中指と、人差指なり。
一本の指に、節が三節あるのは、元々泥の海の時、五分から三度生まれた理。十本の指、合わせて、三十節あるのは、一と月三十日の理。また、五本十五日まで満月。人間身の内五体は、火水風三つに留まるゆえ、三五、十五節あり。それに平手の三大節を合わせて、十八節。十八は陰陽四季で、土用の理。両手合わせて三十六節は、一年三百六十日。手足、合わせて七十二節は、四季土用七十二日の理。また、親指は一つに折れ、子指は三つに折れ、五角になれば、我が円くなる。四角の内は角が立つ。
左人差指は月よみの命様で、月様の一の道具神。右人差指はくにさづちの命様で、日様の一の道具神ゆえ、親指には、人差指が何時も添うて一番力になる指なり。月日は親様ゆえ、いずれの指にも親指が添うて用を成すが如く、親様が入り込み下さらねば、道具神様の働きは出来ぬものなり。
|
| 八方八色の理
八方の神様の色で、万物が染まるなり。
青は、月様。海、晴天の色。万物の青いと云うのは、水と云う理にて月様の理、苦労と云う理。宇宙、海、川は青い。また、山々が青々としているのも、総て水より現れ、くろうと云う理が栄えているものなり。
黒はたいしょく天の命様。鳥でも鴉(からす)、九官鳥の如く天然自然のもので、黒きもの総て。
水色は、くもよみの命様。萌黄(もえぎ[黄と青の中間色、黄色がかった緑色])も同じ、萌え出ずる色目だし、草一切の色。浅黄(あさぎ[薄い黄色、淡黄色])とも同じ。草木、立毛、春の萌黄、浅緑が緑なり。緑が秋になれば黄色となり、柑子色(こうじいろ[赤みがかった黄色、だいだい色])となる如く皆夫婦の理。
緑は、くにさづちの命様。木の葉、竹など、緑色一切。
赤は、日様。火照り、光り、一切赤い色。あかいと云うは、皆日様の理。青と赤は、陰陽夫婦の理。
白は、かしこねの命様。白は風。水青く、風白くと云うて、風で皆物が白くなるなり。雪は、六花(りっか、ろっか)と云うてかしこねの命の理。
黄色は、をふとのべの命様。秋の草木、立毛の色。
柑子色は、月よみの命様。黄色が濃くなって柑子色、すなわち、黄色に赤が合えば柑子色となる。水気が去るに従って、黄色、柑子色、赤と色が変る。
また、紫は、青六分、赤四分が真正の紫。月日和合の色にて、色の王と云う。緑は、青と黄色の合色。宇宙万物の色合いは、八色より、濃淡に変化されてある。また、白は風、無色ゆえ、太陽の光りは七色と云うなり。
真の原色は、青、黄、赤、緑、白の五色なれど、陰陽合わさる八方の神様の理にて、八色に分かれる。
人体、世界万物は八色により、合色され、それぞれその神様の理を知るなり。
例えば、人体の頭は、あおじと云うて、月様の色。髪の黒は、たいしょく天の命様。顔の赤は、日様の色。顔に赤み無く、真っ白く、青いが如きを薄情の相と云うのは、火の気、誠を失った埃ある色。顔色黒きは、欲が深いゆえ。細かく行けば、顔でも八色が現れる。皆その心使いが現れるなり。また、身体や、総てのものでも、本色を失って、色々と濃淡に変色すれば、その理を知るなり。
また、人間の眼には、鮮やかに見えねども、一日のうちでも神様の刻限によりて、世界の色が変わると仰せられる。
夜の十二時から、二時までは、青。夜の二時から六時までは、黒。最も暗く、暗黒の時。明け方の六時から八時までは、水色。朝の八時から十二時までは、緑。昼の十二時から二時までは、赤く、明らか。午後の二時から六時までは、白。そよそよと風起こりて、一日でも最も明白な時。夕方の六時から八時までは、黄色。夜の八時から十二時までは、柑子色。神様は一日も、一年も、一代も、同一に守護下されるなり。
|
| 八方の八柱の神様、人間に入り込み日々の守護
男神五柱は、人間に取りては、男の理。一家にとりては、夫の理。女神五柱は、人間にとりては、女の理。一家にとりては、妻の理。男神は男の心に入り込み女神は女の心に入り込み、世界も、身の内も同一に守護下される。皆人間の自由用が、神の働きである。神様と身の内を別々に思うていては、天理は解らぬものなり。神は、身の内にいるなり。
身の内が出来て、一日が出来る。元々人間がこの世に、生まれ出たゆえ一日が出来る。始まる。一日ができて一年が出来、一年ができて六十年が出来る。一日は魂、一年は身体、一代は世界。
一日の刻限にては、
午前二時より午前六時までは、たいしょく天の命の理。
明け方の六時より八時までは、くもよみの命の理。
朝の八時より昼十二時までは、くにさづちの命の理。
昼十二時より午後二時までは、をもたりの命の理。
午後二時より夕方六時までは、かしこねの命の理。
夕方六時より八時までは、をふとのべの命の理。
午後八時より夜十二時までは、月よみの命の理。
夜十二時より午前二時までは、くにとこたちの命の理。
一と月にとれば、
三日の午後十二時より、八日の午前十二時までは、たいしょく天の命の理。
八日の午後十二時より、十日の午後十二時までは、くもよみの命の理。
十一日の午前十二時より、十五日の午後十二時までは、くにさづちの命の理。
十六日の午前十二時より、十八日の午前十二時までは、をもたりの命の理。
十八日の午後十二時より、二十三日の午前十二時までは、かしこねの命の理。
二十三日の午後十二時より、二十五日の午後十二時までは、をふとのべの命の理。
二十六日の午前十二時より、三十日の午後十二時までは、月よみの命の理。
一日の午前十二時より、三日の午前十二時までは、くにとこたちの命の理。なり。
一年にとれば、
一月二十一日より三月二十日までは、たいしょく天の命の理。
三月二十一日より四月二十日までは、くもよみの命の理。
四月二十一日より六月二十日までは、くにさづちの命の理。
六月二十一日より七月二十日までは、をもたりの命の理。
七月二十一日より九月二十日までは、かしこねの命の理。
九月二十一日より十月二十日までは、をふとのべの命の理。
十月二十一日より十二月二十日までは、月よみの命の理。
十二月二十一日より一月二十日までは、くにとこたちの命の理。
一代にとれば、
一歳より十五歳までを、よう(幼)。十六歳より三十歳までを、じゃく(若)。三十一歳より四十五歳までを、そう(壮)。四十六歳より六十歳までを、ろう(老)と云う。
天は冬が始まり。十五歳までは、冬の理。冬の間は草木に色無きと同じ。十六歳より三十歳までは、春の理。春は、芽が生じ、一代の内で最も花やか美麗なる時。花が咲き、色気が満ると同じ。三十一歳より四十五歳までは、夏の理。夏は、繁る知恵盛り。また欲が強くなると同じ。四十六歳より六十歳までは、秋の理。秋は、実がのる時と同じ。
一代は子の四つのしきゆえに、八方の神が、しき、十二支、十二刻、十二ヶ月を五年ずつ三つ寄せて十五年を一期とする。五年と云うは六十一ヶ月。一ヶ月は閏月、五年を十二合わせて六十年、一年の閏年を加えて六十一年が還暦となり、順戻るなり。
一日は十二時、一年は十二ヶ月、一代は六十年。一日と一年は同一の理。一刻すなわち二時間と、五年とは同一の理。五年と一ヶ月も同一の理。一代は、十五年で一期。六十年でしきゆえ、すなわち一年と同一の理なり。
|
| 一年、中と節の理
冬至より、春彼岸までを冬と云う。春彼岸より、夏至までを春と云う。夏至より、秋彼岸までを夏と云う。秋彼岸より、冬至までを秋と云うなり。冬至とか、土用とか、彼岸とか、中とか、節とか云うことは、その時期、刻限が、すなわち神様の守護の四きであるから、その神様の理をみるなり。
身の内にとっては、節々がせつ、そのふしふしの間が中。心の理にとっては、神様が心にのって働いて下さる時は、せつ。人間は心を使わず、あるいは、寝ている間とかすべて身を使わず、働かぬ時が、ちゅう。人間がどうせいでも、神様が守護下さっている間が、中。例えば食事をなす時は、節。食事後は、中。また、大小便の時は、節となる。指でも、ふしの所はせつ。その間は、ちゅう。全身皆同じ。
人間は、中なれば埃は出来ぬが、節という間に、埃が出来るゆえ、二十一ふしと云う。身の内の二十一ふしは、眼に二つあって一つの節。耳二つあって一つのふし。鼻一つ、口一つ、首の骨の節一つ、両手に六つのふし、背筋に腰骨の節一つ、両足に六つのふし。腹の臍のくくりの節一つ。大小便のところ二つ。以上、身の内の大節なり。人間は、他の動物とは異なりて、皆身体、心の使い道の、自由用自在が叶うゆえ、その使い方にて埃を造るなり。
|
| 八方の八柱の神様 誠と埃
人間身の内は借し物、心一つが我がの理。心一つ一つで心と云う。また、一つの心は八つに働く。欲しい、惜しい、恨み、腹立ち、可愛い、憎い、欲、高慢、これが心の働きと云う。その働きには、裏と表がある。使いよう、使い場所、使い道が間違えば、埃となる。
冬は子に入る、欲しいの欲。春は恵む、恨み、隔ての欲。夏は繁る、燃える、惜しむ欲。秋は稔る、高慢、取り込みの欲。
誠は冬の理。知恵は夏の理。金銭は春の理。力は秋の理。誠が表に現れて、知恵は裏なり。知恵が金銭を使い、金銭が力を使う。
欲しい、惜しいの根を切るは、誠、分け隔て無くして、心を繋ぎ、恨み、嫉み、りんき、妬みの心を起こさざるは、金銭。悪口、中ごと、笑い、謗りの心を使わざるは、知恵、自慢、我慢、高慢の心を捨てて人を立てる心を、力と云う。
欲しいと云う心の埃を去れば、心に誠と云うものが出る。
惜しみの埃、出し惜しみ、負け惜しみなどの心と人を憎む心を去って、知恵と云うものが出来る。すなわち、理を悟るとは知恵なり。諭す、考えるは、知恵。
我が身可愛い、分け隔ての心、人を恨み、人を妬むと云う心を去るから金銭が出来る。
高慢、我慢などの埃、人を立てず我が身だけ立て、我が意を突っ張ると云う心を去るから、力が出来る。すなわち、これが心の力なり。人を助ける、教える道の力なり。最も身体の力は、その内にあり。
以上神の心、宇宙の真理に叶えば、いか程でも心次第に、徳は備わり、神より授かる。金銭も、知恵も、力も神の貸し物。日々常に使う心、その使う心一つが我がの理。心の理によって、その理が与わるなり。
|
| 言葉の理
神様の教えで言葉の理があるのは、言葉が先に出来て、文字が後に出来たゆえなり。天地が開けて以来、幾千年の間、人間に神がよろずのことをお仕込みくだされて、天理から名が付き、言葉が出来ているゆえに、言葉が元なり。言葉には、理があるなり。文字は種だね、様々の品を分ける為のもの。
言葉に理があって、言葉あり。言葉あって文字あり。仏教が一の枝。文字が二の枝と仰せられた。ゆえに、世界に昔から云うていることの理が、天の理から出ている、名も付いている。神様は、云うていれども、元知らぬ。と仰せなり。
|
| いろはの文字と本字
世の人は、いろはの文字は後から出て、本字が先に出来てあると思うゆえに、本字を書くことが偉いように思っているが、これは大いに心得違いである。いろはの言葉を、文字にするから違う。
この世界の人間が出来、物を云いかけた時より、この四十八音はあるものなり。よって、いろはの文字を文字の上からみれば、つまらぬように思えども、決して、文字だけで見るべきものではない。これは、言葉の元なり。文字が先か、言葉が先かと云えば、云うまでもなく、言葉がありて文字は出来たるなり。人間生まれ出るにも、言葉を先にあげてるなり。 かなと云うのは、たやすきことをかなと云うなれど、かと云うのは、日様のこと、大地のことなり。なとは、月様のこと、天のことなり。
この四十八のいろはの文字さえ知っておけば、いかなる本字にても、仮名さえ打ってあれば読める。いろはの字引さえあれば、いかなる文字にても引き出される。ゆえに、本字を書いて、その字に仮名を付けるのに、かなをその字の上につけるものなり。あくまでも仮名の文字の方が、本字より上のものなり。このいろは四十八文字は、言葉の元にて、要なり。
今その一つの例をあげれば、文字を書く時に、用いる墨もすみ、ものの隅もすみ、火をおこす炭もすみ、物事の片付いた済みもすみ、水の濁りたるを澄ますのもすみ。また、文字に書く時の紙もかみ、神もかみ、上もかみ、また、酒などを熱くしたのを、かんと云い、時の寒いのを、寒という。
この通り、ことは変われど、仮名の文字に書けば一つなり。書き記せし本人にすれば解れども、他の人が見れば解らん為に、火の焚く炭はこう、文字を書く時の墨、物事の片付いた済み、水の澄んだは澄みとして、手本として拵えたのが本字である。これは銘々に身体ありて、それぞれに説明ついてあるのも、同じ訳なり。
|
| 五倫五体の元
首より上の心の働きを、五倫、首より下の働きを、五体と云う。上下、天地、男と女も五倫五体なり。上、天、男が五倫なり。下、地、女が五体なり、五代なり。たいと云うも、だいと云うも同じことなり。五倫は天、五体は地ゆえ、男は天、いざなぎ、女は地、いざなみなり。いざなぎ、いざなみは、男と女で、夫婦なり。夫婦交合の時は、男は天、女は地なり。これ、五倫五体なり。すなわち、五行と同一なり。
五行とは、木、火、土、金、水なり。五行から分かれたものを、きのえ(甲)、きのと(乙)、ひのえ(丙)、ひのと(丁)、つちのえ(戊)、つちのと(己)、かのえ(庚)、かのと(辛)、みずのえ(壬)、みずのと(癸)の十干(じっかん)の干支(えと、かんし)なり。
五倫五体の五倫とは、五柱の神様の心にて、天においては、月輪、日輪、源助星、破軍星、明けの明星、の五倫なり。五体とは、五柱の神様の働きにて、くにとこたちの命様、をもたりの命様、くにさづちの命様、月よみの命様、くもよみの命様の働きなり。
ゆえに、五倫五体十干とは、
月輪様は、くにとこたちの命様、土にて、つちのえ、つちのと。
日輪様は、をもたりの命様、火にて、ひのえ、ひのと。
源助星は、くにさづちの命様、金神にして、かのえ、かのと。
破軍星は、月よみの命様、木神にて、きのえ、きのと。
明けの明星は、くもよみの命様、水神にて、みずのえ、みずのとなり。
きのえ、ひのえ、つちのえ、かのえ、みずのえ、この五つのえは、天、男なり。きのと、ひのと、つちのと、かのと、みずのと、この五つのとは、地、女なり。五輪五体重なりて、十なり。これ、夫婦なり。この十干が重なりて、ふうふと交わりは、六仏六代の理なり。これは、陰陽和合のきなり。風なり。六台とは、木火土金水風。火と水があって風になるゆえ、夫婦と名の付く元なり。
また、十干十二支の十干は、幹で、元なり。十二支は、枝なり。 仁義礼智信(じんぎれいちしん)の理
仁は、月様の情けより出る。人を慈しむ、養い育てると云う親心。
義は、かしこねの命様から出る。云うたことを違わぬ、約束をしたことを違えぬと云う心。
礼は、月よみの命様から出る。君に忠、親に孝行をすると云う、人を大切にする心。すなわち、互いに人を立てる心。
智は、たいしょく天の命様より出る。これは、互いに知り合うと云うて、我の知ったことは人に教える、互いに知りてゆくと云う心。見分け、聞き分け、噛み分ける心。
信は、くにさづちの命様より出る。互いに睦まじく、繋ぎ合う、親しむと云う心。すなわち、人を繋ぐ心。
木火土金水と云うも、地水火風空と云うも、仁義礼智信と云うも、同じ五行の人道である。これは、儒教から出ている言葉で、孔子に月日が入り込んで教えられたのだが、その元が解らなんだ。また、四書、五経等も同じである。
かしこねの命様は、義の神様、交際、義理の道も同じ。この神様から、義と云うことが出ている。すべて、みな月日二神より出る徳なれど、義は月日より、かしこねの命様にお任せしてあるなり。しかしこれは、余り片寄ると偏屈になる。いわゆる、仁すぐれば弱になる、義すぐれば偏屈になる。また、礼、智、信も同じなり。
|
| なむあみだぶつの心
仏教では、なむあみだぶつと唱えているが、それは、生まれてから死ぬまで、休みなく体を貸し与えて下されている神様への、お礼の言葉である。その訳は、
な 水のような低き、やさしき、たんのうの心。
む 温かき心で、人と我が身を隔てなき、慈悲の心。
あ 隔てなき愛をもって、人と人を繋ぐ心。
み 誠の心をもって、人の思いを立て、人の身を立てる心。
だ 善と悪との仕分けの心、人の心をよく悟る心。
ぶ 言葉は優しく、人の耳に喜びを与える心。
つ 心に悪しきことを思えば、思いっきりよく、切り替える心。
なむあみだぶつうを一家にたとえると
な くにとこたちの命様の理で夫。亭主より、な、と云い出し、云いつける理。
む をもたりの命様の理で妻。夫の仰せに従い、む、と答え、飲み込み受ける理。
あ くにさづちの命様の理で、女一の道具の神様なり。亭主の働きで得た繋ぎ物を待って、妻子が、あ、と口を開け開く理。
み 月よみの命様の理で、男一の道具の神様なり。ものの、みを与え、みを入れ、みを立て養う理。
だ くもよみの命様の理で、人間を胎内に宿し込み下さる時の理。また小便、大便を、だ、と通じ下される理。
ぶ かしこねの命様の理で、ぶ、と妊娠する理。また日々、ぶうぶうと息をする理。
つ たいしょく天の命様の理で、胎内の肉縁を、つ、と切り下さる理。また死ぬ時、息を切る理。
う をふとのべの命様の理で、胎内より引き出し下さる理。また、運良く、う、と生まれ出る理。
|
| 正月祝いの理
年の始まり、月の始まり、日の始まりを正月と云うのは、月様は泥海の中より、正しい人間、正しい世界を造られたことを云うなり。正しいことを正と云う。また、暗がりの世を照らす月様は、先に立ってこの世界を造られた理をもって、この世界をこの日とは云わず、このよと云うなり。また、元日とは、日様のことなり。
三日の祝いは、これは人間元々、さんで生み広められて、日々身の内は温み、水気、息の三つでもっている。また世界も同じこと。火と水と風とは、大なり。身の内、温み、水気、息の三つが、十分の守護あれば不足なし。この三つが変われば、身の内に不足出来る。よって、身の内の悩みを見るに、脈を診る。脈とは、この三つのやくを云うなり。
この世界は、皆三つの理。三つずつの理あり。天地人とか、上中下とか、また、月も三日月が始まりなり。三日目でなくば見えかけぬとは、人間でも子が宿っても一ヶ月、二ヶ月の内は、人から見ては解らん。三ヶ月目から、一寸見えかけるのも同じことなり。三日の祝いの理は、火、水、風の三つの理をもって祝うなり。
鏡餅一重ねの理は、月日二柱の御身輝く理にて、かがみと云う。餅の鏡は天地なり。ゆえに夫婦心丸く柔らかにして、仲良く揃うて暮す心を供えるなり。
みきと云うのは、正しき真直ぐなる、きを供えるなり。ゆえに木の元は幹と云う。横に出たるを枝と云うなり。木の実を供えるは、最初人間の食物の初めは、木の実なり。
門松は、お松、め松を左右に立て、しめなわを張りて、年徳大善神と祭り、礼拝するは、年徳とは、十二ヶ月、三百六十日は皆月日の守護にて、五穀、野菜、綿、糸、一切をお与え下され、また、立木、魚、鳥まで人間の為に守護下されるゆえに、この恩徳を受け、毎年門松を立て、祝うなり。
門松は、お松、め松は、男神女神の夫婦二神より出来たる理を示すものなり。また、まつと云うのは、三代、めの芯の立つのを待つと云う理にて、三年目に芽が出て芯の立つまでは、古い葉が落ちることなし。木の芽は、一年が人間一代と同じ理。
また、門松は、三段なると理とす。我が身夫婦で一代、子の夫婦で二代、世の芽を出すにて、嫁と云う。また、孫の代となりて云う時は、二代をちちはは、三代をぢぢばばと云うなり。我が身より前後をちちはは、そふそぼ、子孫と云うのは、五だいのものなり。
譲り葉を用いるのは、代々親は子を産み、子は親となりて、子孫によをゆずり行くと云う理なり。
しめなわは七五三なり。その七は天神七代、五は五倫五体、三は産み広めのさんの理。世界で云う天神七代は、これを神々七人のように思えども、大いに違う。これは、なむあみだぶつのくにとこたちの命様から、たいしょく天の命様までの神々を云う。この七柱が道具となった理を云う。地神五代と云うは、これも世界では、神々のように思えども、自身五代と云うて、皆銘々のこと、五体の人間の出来たことを云うなり。
また、七は、元いざなみの命様、奈良、長谷七里の四方の間を七日一回りにて、人間を産み降ろし下された理。五は、人間最初五分より生じて五尺となる理。三は人間を三度産み降ろし下された理。
しめなわと云うのは、しめとは、しめることなり。なは、くにとこたちの命様。月様のことなり。わは、丸く取り巻くことを云うなり。これは、月様が子の世界を輪の如くに取り巻きて、しめて居られる理なり。よってしめなわは、左縄に縫うものなり。その形は、月様の本体、頭一つ、尾一筋の大龍の形なり。
数の子を用いるのは、元々いざなぎ、いざなみの二神が、今の甘露台を神々の身体の真ん中として、南無南無と三日三夜に子数を九億九万九千九百九十九人宿し込み、腹に入れたる理をもって用いるなり。また、にしんと云うのは、妊娠の理にて、にしんと云う。豆を用いるのは、無事、まめにこの世を送らそうとの、神の思召しの理なり。
七日七草は、元々人間は九億九万年泥海中にて住まいしたる時は、海草などを食べて通りた理なり。
十四日の年越しと云う理は、十四日では月は満月とはいえぬ。十五日は満月なり。人間も十四歳では一人前とは云えぬ。十五歳より一人前なり。これで十四日を年越しと云うなり。
十五日に粥を食べるは、人間は元々泥海より登りたる理にて、粥を食べるなり。かゆとは海底のことにて、海なり。
正月元日より、十五日の間をしめの内と云うは、月様十五日となれば満月と成り給う。人間もまる十五歳となれば、一人前に成るゆえなり。
正月元日より、十五日の間の祝いと云うのは、元始まりの理を忘れぬ為に神が人間に教え下され、今に形を行うものなり。
|
| 着物の理
着物、襦袢(じゅばん)、帯は七五三なり。七は着物、五は襦袢、三は帯なり。着物を一反七つに裁つは、七は切れると云う理にて、身にまとう物を切ると云うのは、切ると云う理なり。これ、たいしょく天の命の理なり。五は襦袢にして、五体にまとうは、はんぶんと云う理。襦袢、すなわち十はんにて、五つに裁つなり。これ、くもよみの命の理なり。三は繋ぎにて縄なり。結ぶ、繋ぐと云う理なり。一筋を左右より二つ結びて三となる。縄と帯とは同じことなり。これ、くにさづちの命様の理なり。ゆえに女は、お産の時、安産の許しを受けることををびやと云う。をびやは、くにさづちの命様の司りにして、さんの王と云う。
しは七、たいしょく天の命様。めは五、くもよみの命様。なわは三、くにさづちの命様。この三神は何れも女神なり。この三しなを、女の身代と云う。ゆえに三品の着物、襦袢、帯は、女の大切なるものなり。
|
| 島台(婚礼その他のめでたい儀式のときの飾り物)の理
大和の国にて、国式の祝いと云うて、婚礼酒宴の座にて、第一の祝いとする島台の理。これは、人間は結婚を始めとするゆえに、祝うべき大事なる祝いと云うなり。
日本の国は、島なり、台なり、また、水の中なる浮島、敷島なり。それゆえ、しまだいと云うなり。
浪人夫婦の翁(おう)とおうな(女)に、翁は熊手、おうなは箒(ほうき)を持って掃除をする形を現わしたるは、この世の掃除をするほど、清き、目出度いことはなし。人間身体、胸の内を掃くとは、はくにて、白く清らか奇麗にするなり。
また、男の心にて積む埃は大きく、女の心にて積む埃は細かい。男の埃は第一、欲しい、腹立ち、憎い、高慢の四つありて、男神が戒め給う。女の埃は第一、惜しい、恨み、可愛い、欲の四つありて、女神が戒め給う。互いに、男は荒き埃、女は細かき埃を払いて、胸の内を掃除するなり。ゆえに、男は熊手、女は箒を持つなり。このようにして、胸の内を悪しきを払うたら、お前百まで、私九十九まで、共に白髪となるまででも、と云うように長生きして、子の代、孫の代を安心して楽しむ理なり。
鶴亀を用いる理は、鶴はたつると云うて、男一の道具なり。亀は繋ぎの理にて、女一の道具の理なり。鶴は千年。亀は万年と、古より唱えて、年を祝いするものなり。
松竹梅を用いる理は、松は、三代、めを出さぬ先は、古い葉が落ちぬものにて、三代めの芯の立を待つと云う理にて、誠目出度きものなり。竹は、一年にて親と同一となるゆえ、親子たけだけと云うて、忠節揃いしものなり。梅の実、結びたるは人間の子の宿りたる理なり。ゆえに、梅は増える理にて、目出度く祝うものなり。
|
| 酒の理
酒を飲むについては、余程の理がこもっている。これは、人間は元々泥海の中で住まいをして、天地分かれてより、この世へのぼりたものなり。皆々他人と云うはさらにない、実の兄弟なり。その実の兄弟の理をして、酒を飲むなり。
茶を飲んだ茶碗でも、水を飲んだ時でも、そのままでは人に出せない。必ず濯がねば気が悪い。ところが酒ばかりは、飲んだ盃をそのまま向うへ差し出しても、別に何とも思わん。また、飲み差しの盃を人に出しても、差し障りなし。なかなか他のものは、水も、茶も、酒も同じようなものなれど、それは出来ぬもの。
また、人間の元はぎぎょ(岐魚)と云うさかな。これは、いざなぎの命様のお姿。これ人間の父親なり。それから出来た人間ゆえ、皆々実の兄弟なり。よって、酒さえ出てあれば、野菜でも、山菜でも、さかなと云うなり。酒が出てなかったら、さかなとは、云うまい。いざなぎの命様はぎぎょと云うさかな。これ人間の父親なり。この理をもって、さかなのことを、とと と云う。我々は父親のことをとと、とも云うも、この理をもって云うなり。
酒を飲んで、腹を立てたり、嘆いたりするようでは、酒を飲んだとは申せぬ。酒は実の兄弟の理をするのであるから、勇まねばならぬ。さけによって人と諍いをしたり、暴れたりするは、酔うたのではない。この酔うたと云うは、この世は夜から始まった世界、段々と、至る如く月様の世界なり。月様は水なり。その夜の月様の心に添うたことを、ようた、と云うなり。
|
| 世界一れつ兄弟の理
人間の上では、人種を分ける。しかし、元々人間はいざなぎ、いざなみの命様の種、苗代一つのもの。今も同じこと。火、水、風は、皆昔から一つのもの。一人、また一国ごとに月日様はあるものではなし。昔も今も同じこと。一れつ兄弟には少しも変わりはなし。
世界並では、外国人は目が青い、毛が赤いと云っている。それは、皆人間の上で分かるようにして下されたもの。人間、一種一腹の者でも同じ者はない。これは皆、分かりよいようにしたもの。人種、人名は、人間がつけたものなり。
|
| 甘露台の地場の理
今、中山氏の屋敷の内に、甘露台を据える所の地場を、世界中の人間のおやさとなると云うのは、元泥海中より月日二神現れまして、いざなぎ、いざなみを引き寄せ、くにさづち、月よみ、くもよみ、かしこね、たいしょく天、をふとのべ、合わせて八つの道具雛形をはかり集めて、また、九億九万九千九百九十九人の三寸なるどじょうを魂と定め、初めて夫婦を交合して、この人数を三度まで宿仕込み給う所ゆえ、三千世界の人間は、皆この地場が親里なり。
今ここに月日のやしろとなりて、月日二神の心が入り込み給いて、よろずたすけを教えて下さると云うのは、無い人間や無い世界を拵え給うて、何の形も無き道具雛形を見出し、造りたるも同じことなり。
この度もまた、無きことや知らぬことを云うて聞かして、珍しきたすけをするゆえに、疑い心無理なれど、これ疑えば、御利益うすし。人間は、あざないもので、我が身の元始まりを知らず。この世の地と天とは実の親。それより出来た人間である。すなわち、月日二神の懐に住まいするゆえに、人間のすることは、月日の知らぬことはなし。
人間は皆々神の子なり。身の内は、借り物なり。これまでは、病と云えば、医者、薬、拝み、祈祷と云うたなれども、病の元は心から。この心得違いと云うのは、欲しい、惜しい、恨み、腹立ち、可愛い、憎い、欲、高慢。これ八つの心得違いとなり。これ我が身の内の埃種なり。
十五歳までの子供の悪しき病、不時災難は、両親の心の置き所が違うゆえ、心を直す意見なり。親は幹。根なり。子は枝なり。根さえ良くば、枝は益々栄え、花が咲き、実を結んで、楽しみなり。根悪しくば、枝が枯れること、これ天の理なり、自然のことなり。痛みや、悩みはその人の患いでも、家内に一人患えば、他人も心をくばり、心を労して患うなり。そして、その人に心を引かれて、家業も十分勤まらず、ゆえに家の患いとなる。これ、家内の人達の心に埃積もり重なるゆえ、月日二神のご意見、立腹なるべし。
をや神様に助けを願うことならば、神の教えの道を守りて、家内の人々皆互いに我が心を顧みて、十五歳より今までの心得違いを懺悔して、その後は、神の教えの道を守り、嘘と追従、欲に高慢無きようにして、必ず人を他人と思わず、皆兄弟と思うて、互いに助けをする心と真実より入れ替えて願えば、その心を月日二神が受け取りて、よろずたすけを下されることなり。
|
| をびや許しの理
人間は神の貸しもの、身の内の自由用は、をびやたすけを思案してみよ。をびや許しは、この屋敷に願い出て、をびやつとめにかけた御供(ごく)を三つ戴けば、腹帯いらず、もたれものいらず、七十五日の毒忌みいらず、常の体で汚れ無し。三日目より、常の通りに働きが出来るなり。また、産み月を早めて九ヶ月、延ばして十一ヶ月にでも自由用自在のことなり。すなわち、人間の安産するは月日二神の守護にして、三神を使うてお働き下されるなり。
始め、母の胎内より、縁を切り出し給うお働きは、たいしょく天の命様にして、仏法にては、法華宗なり。また、胎内より、引き出しの安産下さるのは、をふとのべの命様にして、仏法では、真言宗なり。後終いの皮繋ぎ下さるのは、くにさづちの命様にして、仏法にては、禅宗なり。世界の動物は、みなこの神の御苦労にて、月日二神がこの三神をもってお働き下さるなり。
人間折々難病するは、これ病の重さにあらず。常におのれが気随(きずい)、気ままにして、親に逆らい、夫に口答えして、嫉妬深く、また口先ばかりにて、心に人道を守らぬゆえに、流産、難産の憂いを見るなり。これは、おのれの心が違うゆえ、月日二神のご意見、立腹なり。
|
| 赤き着物の理
今ここに月日の社となり給う中山みきが、赤き着物を着るは、天の証悟(しょうご[悟りを開くこと])の如く、月日、天に現れてしょうご下さるのは二神の眼なり。眼に明らかなるがゆえに、世界中は大いに明らかなり。すなわち、赤き着物には、二神のお心が籠り給うゆえに、万事を見るなり。
この月日の社となり給うみきは、人間の同じ身体なれども、魂は、元泥海の中にて人間をお造りなされた時、母親の雛型と成り給う。いざなみの命様の魂なり。ゆえに、どこの者でもたすけたいばかりの心なり。
それゆえ、元の泥海からの約束の如く、九億九万九千九百九十九年の年限満ちたるがゆえに、元始めの地場を現わし、人間として生まれ給う。すなわち、みきを雛型として、月日二神の心を入りこみ、みきの口を借りて、元始まりの話しを教えて下されるゆえに、おや里なり。また、世界中の人間の産土の地場なり。
この生まれ故郷へ参りて、親神にたすけを願うことならば、月日の社となり給うたみきの心を見て、雛型とし、八つの埃を払い慎み、その人道を生涯にたしなむと云うて願うなら、月日二神がその心を受け取り、たすけはむろん、善悪共に神様より返しをすること、間違いはさらになし。
人間に、病と云うてさらになし。皆銘々の心の埃が現れて、病、悩みとなる。人間は、死に行くと云うなれど、死するにあらず、借り物を返すばかりのことなり。
この訳を衣服に例えて話しする。いか程大切なる衣服にても汚れ、垢付きたならば、我が身に着て心悪しく、早速脱ぎ捨てて解きほどき、水で洗うて、日で干して、仕立てあげたら、着て気が宜し。
人間も我が身の五体は神よりの借り物。心の埃積もるがゆえに、神を脱ぎ捨て去り給うなり。我が身の身の内三寸の胸の内を洗うには、神の教えを我が身に聞き、心に治め、胸の内をよく洗うて願えば、神様はこれを受け取り給うなり。
この世界に、神や仏のお姿を木、金、石などにて造りたけれども、これ皆人間の造った物なり。
人道を守る為に、善悪を諭し導き下さるのが神なり。また、我が心のめどう(目処)なり。この世の火と水とは一の神、風も神、いかなる悪しきも払うなり。
|
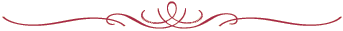
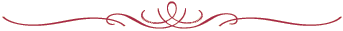
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)