|
かくて、教祖は、日々にお話あり、それを取次たる者をして、筆に誌せしめられたのであり、皆、取次にお聞かせ下さるのであります。又、“おふでさき”の終わった頃から増える刻限話や、錦の仕事場たる本席の刻限話等も、〝こふき〟に関係あるものと考えられ、〝こふき〟方法にて、取次をお仕込み下されていることと、察せられるのであります。又、観点を替えて、〝こふき〟と称せられる写本の現れ初める頃は、丁度、“おふでさき”の停った頃であります。忘れるから筆に誌しておいたとお教え下され、親しくお筆をおとり下された“おふでさき”は、教祖の八十四、五才たる明治十四、五年頃に停り、その頃から、〝刻限話〟が増してくること、並びに、聴聞の信者層にも、筆の執れる人が増してきたこと、等から推量して、〝こふき〟は“おふでさき”に次いでなされた〝教話伝達〟の方法と考えられるのであります。
従来〝こふき〟に対しては、〝古記〟の文字を多く用いられて来ました。しかし、この文字は、当初から使われていたのではなく、寧ろ、後年になってから、使われ出したと思われる節が多く、必ずしも、〝こふき〟のお言葉は、〝古記〟と当てるとは、限らないと思うのであります。〝此世始まりのお話〟が〝こふき〟話の初めにある所から、その頃の信者中の有識者が、〝古事記〟等の連想より、〝古記〟との文字を当て、その文字によって、〝こふき〟話が代表称名とされて参ったように思われるのでして、十八年本の小松本に使われていた当字(あてじ)に、〝明治二十年以後ノ古記ヲ貫書(ぬきがき)ス〟とありましたように、明かに、古記は〝古い記〟というよりも、〝こふき〟の音を写したものであり、写音の当字にすぎないと、考えられるのであります。
以上のような諸要件から、私は、所謂〝泥海古記〟は、〝此世始まりのお話〟を指すという、従来からの常識なり、今日迄の私自身の解釈に、あきたらぬものを感じたのであります。これは、〝古記〟の文字にとらわれ、その字義にとらわれて〝こふき〟の語義となした憾(うら)みを感じたのであります。〝こふき〟の音を〝古記〟の文字に写したという事よりも〝古記〟の文字にとらわれて、〝こふき〟の意味を極限したと考えるに至ったのであります。そして、〝古記〟は〝こふき〟の写音であり、文字には大した意味を考えぬ方が本来の意味を生かすものであり、先にのべた〝こふき〟の内容なり、対象を〝取次の仕込み〟において考えるとき、寧ろ、〝こふき〟は口で述べられたお話を〝記(しる)〟された書き物を意味し、“おふでさき”に対しての〝こふき〟、即ち、教祖の親しく筆を執られた書物に対して、教祖が口で述べられ、取次を仕込む上から、筆執り学人(ふでとりがくにん)として、一は取次に筆を執らしめ、一は取次の話の台本とされたものと考えられるのであります。即ち、親しく誌された“おふでさき”に対して、口授して書き取らしめられた〝記(き)〟を〝こふき〟と呼ばれたものであり、強いて字を当てれば、〝口記〟の方が寧ろ、本来の意味を写す文字ではないかと考えるのであります。
以上、半年にわたりました〝こふき〟についての叙述は、この字義を探ろうと考えたからなのであります。そして、〝口記〟に及び、教理説述の方法として、〝口に、筆に、或は行いに〟と述べてあります教典の説明に、更に加えて、〝口授されて書き取らされた〟〝こふき〟の一方法が考えられ、かく考えますと、“おさしづ”も亦(また)、〝こふき〟の一つであると考えられるに至ったのであります。(後略)
昭和三十二年七月発行「〝こふき〟の研究 成人譜 その三」(中山正善)153〜159ページより
|
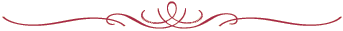
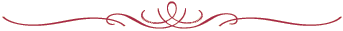
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)