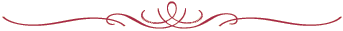
| 元の理教理考、「こふき」御執筆史考 |
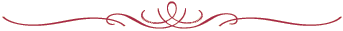
更新日/2025(平成31→5.1栄和改元/栄和7)年1.16日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「元の理」の「「こふき」御執筆史」を確認しておく。 2007.12.25日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【門外不出の「元の理」考】 | |
大正14.11月、奈良県丹波市町(現在の天理市)の天祐社から「非売品」、「門外漢に禁ず」として「泥海古記」が刊行された。同書の序には次のように述べられている。
天理教本部は、この秘本を悦ばず、後に信徒達から回収し焼却処分している。教祖の教義の要である「天地人間創造の元初まりの理話し譚」(「泥海こふき」とも云う。以下、単に「元の理」と記す)が何ゆえ、天理教本部から隠されたのか。ここに「元の理」の凄みがあると窺うべきだろう。 2007.12.25日 れんだいこ拝 |
| 【「こふき」の漢字当て字は「古記」か「口記」か考】 | |||
| 二代真柱は、「こふきの研究」で、「古記」とみなすよりも、「教祖直伝の口授の記」と云う意味での「口記」とみなすべきとの見解を打ち出している。しかしながら決着つけ難しではなかろうか。人類のはるか昔の創造譚とすれば「古記」であろうし教祖直伝の口授の記とすれば「口記」であろう。れんだいこは、「古記」説を採りたい。なぜならば、「こふき」と書かれてきた経緯に於いて、「こふき」は「古記」の意味であったと思えるからである。 | |||
「こふき」は「口記」、「古記」の他に「鴻基」(物事の根本)とする説もある。以下、「『こふき』は鴻基-物事の根本」を参照する。おふでさきを長年研究されてきた芹沢茂氏は、「こうき」について、次のように述べている。
「鴻基」につき、古事記に記述されている。これを確認する。(岩波文庫版P15の訓み下し文、現代語訳)。
これを踏まえると、「こふき」は「口記」、「古記」よりも「鴻基」の方が正鵠を射ているのではあるまいか、と云う。これは卓見であるようにも思える。 |
| 【「こふき」御執筆史考】 | ||
|
1881(明治14)年、当時教祖は「こふきを作れ」と急き込まれた。この年から1887(明治20)年にかけて、各先生方が教祖の「元の理」話を綴り32種以上の筆録本が作成された。教祖が読んでご満足されるものはなかったと伝えられている。
内訳は、1881(明治14)年、12種類。明治15年から明治16年、8種類。明治17年から20年にかけて12種類、合わせて32種類となって伝存していると云う。これらの筆録本には和歌体と散文体(一般には説話体といわれる)があり、内容もそれぞれ特徴があり一様ではない。明治16年本(「復元」第15号掲載)からは説話体ばかりとなる。(明治14年より20年に至る間に書かれたものが数十種存在し、製作の年代によって14年本とか16年本とか呼ばれている) このうち、教内に広く普及したのは、160首からなる「泥海古記」の題名の「明治14年和歌体本」(「復元」第14号掲載)である。別に161首からなる「明治14年3月これを記す、山沢良助」の表記のある山沢本があり、中山正善の「こふきの研究」(天理教道友社、1957年)に復刻されている。 作成次第を確認しておく。中山正善「ひとことはなし その三」に書かれてある高井猶吉の追懐談は次の通りである。
これによると、山沢良次郎、仲田佐右衞門、高井猶吉の三名に「こふき話」の筆記要請が出され、山澤良治郎は和歌体で、仲田佐右衞門は説話体で教祖に提出されたとある。但し、山澤良治郎本は現存し、仲田佐右衞門は不明である。 1881(明治14)年、秀司の協力者として働く山沢良次郎が、和歌体の「この世始まりのお話控え」(「山沢本こふき」)160首又は161首をまとめている。これが最初のものと思われる。しかし、それは日暮れゆう貞の影響があり過ぎており、教祖が良しとするものではなかった。 1883(明治16)年、桝井伊三郎が散文体の「桝井本こふき」をまとめている。しかし山沢本の影響を残したもので、教祖はこれも良としなかった。よって定本の地位を獲得したものはない。 後に、「中山眞之亮のこふき本」(「明治14年本説話体/中山眞之亮 題名なしの泥海古紀」)」が纏められている。これについて、次のような「高井猶吉の伝」とされる「高井家資料38P」が遺されている。
「元の理」の定本はない。教典第三章「元の理」が定本の如く扱われているが、これを定本と呼ぶことはできない。その内容が「こふき話」全体に比してあまりにも簡略すぎている。もとより口伝も含めて諸本の裏守護の話し等々のどこまでが、教祖のお話し下されたものか、後の高弟の任意な付け足しなのか、判じ難い具合にはなっている。そういう訳で、今日に至るまで、「定本めいたもの」が登場しているが、定本とは云い難い。これが、「元の理原文」に対する正当な受け止め方であろう。ど、教義上での位置を確定しなければ、荒唐無稽とも思われる話がある。 |
| 【「こふき」諸本リスト】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認されている「こふき」本は、1881(明治14)年、12種類。明治15年、明治16年、8種類。明治17年から20年にかけて12種類、合わせて32種類となって伝存していると云う。その詳細は不明である。判明次第に、以下に書き込みしていくことにする。
他にも公開されているものとして、「日本無双書物」、「この世始まりのお噺(はなし)控え」、「神の古記」、「古記」、「天輪王命」等の題名を付した諸本が作られている。梅谷文書、高井家資料、山田伊八郎文書、松永好松遺稿が言及している。(村上重良「ほんみち不敬事件」34P参照、詳細は別章【お道の理論研究】の「別章【元の理】」に記す)。 まだ公表されていない鴻田忠三郎文書、木村家文書など、書き残されて保存されている貴重な「こふき諸本」がある。「仲田儀三郎版こふき」も焼却とされているが保存されている可能性もあろう。桝井本に欠けていて、意味が通じ難い箇所につき、上田本、宮森本、梶本本、喜多本等がある。 |
| 【「仲田儀三郎版こふき」考】 | ||
| 興味深いことは、数ある教弟の中でも取次第一と云われた教理派で、伊蔵と共にみきの教えを説き続けようとした第一等の人だった仲田儀三郎の「こふき」の内容と行方である。仲田は「教祖の最後のご苦労」を共にし、いちのもと分署での過酷な取調べに遭い、出獄後も死の床に就いていた。その仲田は、死の床にあ
って、「教祖のお待ちくださる『こうき』をまとめてから死にたい、どうか増野はん、わしが話すから筆をとってくれないか」と、「こうき」を書きあげることに執念の人となった。増野正兵衛は、元長州の萩藩の士族で、教弟の中ではもっとも筆達者と云われていた。増野は、仲田の口述を筆記しながら、「こうき」の内容が今までのとは大きく違うことに当惑し、伊蔵のお指図を仰ぐこととなった。伊蔵は、「『こうき』は、いろいろな者がまとめているが未だ完全なものはない、急いでやってくれ」(「兵神版おさしず」)と指図した。 こうして、1886(明治19).4.9日、「仲田版こふき」が書きあげられることになった。6.22日、ほぼ書きあげられたと同時に仲田は息を引き取った。享年56才だった。「仲田版こふき」には後日談がある。仲田の死の直後、長男の岸松が、その「こふき」を読んだところ、「こんな恐ろしいものがあったら大変や、どんなわざわいが及んで来るやらしれん」と、父の棺の中へ埋葬してしまったと云う。 一体、「仲田版こふき」の内容はどのようなものであったのか。数ある「こふき」物とは画然別のものだったと証言されているが、であれば余計に知りたくもなる。れんだいこは、教祖の真意に最も叶っていたものであった可能性があると推理している。残念ながら、「お道」の理論家は陸前と続いているが、こういうところへの関心は向かわない。 その後、応法の理の時代に入り、教団は自ら進んで「こふき」の廃棄の道へ踏み入った。復活するのは戦後になってであり、1949(昭和24)年に天理教教典が裁定された際に第三章で「元の理」として登場している。しかし、この「天理教教典式元の理」が定本の地位を獲得し得るものかというととても心もとない。当人が云うのは変だけれども、「れんだいこ式泥海こふき」の方がまだしもの感がある。 |
||
「仲田本の派生本」(写本)らしきものがある。天研第13号の井上護夫氏の研究ノート「木村林蔵の五種のこふき関連文書」中の「三、神之古記 明治拾六未歳
四月上浣書之」の項に次のように記されている。
次のように解説されている。
|
||
| 【「元の理」とダーウィン系進化論との整合性考】 |
| 「虫、鳥、畜類などと、八千八度の生れ更りを経て~」という記述は「進化論」を想起させる。ダーウィンの「種の起源」が出版されたのは1859年、日本語版は1896年。天理教の立教は西暦では1838年、おふでさきの御執筆は1869(明治2)~1882(明治15)年。人類の歴史について調べたところ、「およそ10億年前・有性生殖のはじまり。約1万年前・人類が火を使った生活を始めた。約5千~4千年前・文明ができ始めた」というのが最近の研究成果。西暦1800年代、世界の人口は10億人に達したと言われている。「元の理」のお話の最後、「六千年は智慧の仕込み、三千九百九十九年は文字の仕込みと仰せられる」という記述と一致する。「元の理」は間違いなく教祖が語られたもの。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)