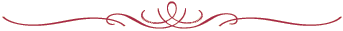
| みかぐらうた(御神楽歌)その2、十二下りのお歌/立ち踊り |
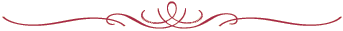
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.10.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「みかぐらうた(御神楽歌)その2、十二下りのお歌/立ち踊り」を確認しておく。かに、「御神楽歌」全文(但し翻訳文)を誌す。れんだいこは、「御神楽歌は、日本宗教史上最高の傑作中の傑作の和歌教歌」と評価させていただく。入信から講の結成の道筋、自己助かりから世界助けへの理論と実践の道筋、その為のつとめを芯とせよとの思し召しを日本古来よりの伝統的な和歌形式で説いているところに特徴が認められる。これをもう少し詳しく説明すると、人生のよろず悩みを抱えての入信から始まり、身情事情解決の道筋の悟り、「お道」の形成の方向、その際の道人の心構え等々につき実にやさしく且つ内容豊かに歌い上げている。道人がこの教えに一筋にもたれて通るなら、豊かな実りが約束され、難渋が救われ、遂には謀反と病の根を切り、更に世界助けに向かうことにより国々所々が治まり平和な世の中になることを詠っている。まさに教祖流の「世直し」であり、「人々の心の入れ替え、胸の掃除を通じての世の立て替え(社会の再創造)」を指針しているところに特徴が見られる。 今日定式されているこの形式が教祖の教えたそれであったかどうかとは別であるが、原型は維持されていると考えるべきではなかろうか。御神楽歌の凄さは、お道の発展のみならず、あらゆる組織、事業体の形成経営に資する普遍的な教示となっているところにある。心して学ぶべしではなかろうか。 2011.04.14日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【神楽づとめの手踊り、御神楽歌「十二下り」】 |
| 「座りつとめ」に対し「立ち手踊り」で表現される際の御歌である。1年12ヶ月の暦になぞらえて、道人の成人の歩みを御歌で表現している。一下り目から六下り目までの前半部は、主として個人としての信仰の立脚を歌う。七下り目から十二下り目までの後半部は、主として陽気暮らし世界創出に向けての道筋や道人の布教に於ける諭しとなっている。実際の踊りつとめも二部構成になっている。 その思想の深さは驚きであり、普遍的ともいえるあらゆる組織原理ひいては社会原理の方程式を伝えているやに見える。れんだいこの思案はまだこれを読み解くのに覚束ない。(後半の推敲がまだできていない) |
| 【一下り目】(Song One) | |
| 一ツ | 正月 こゑ(肥え)の授けは やれ珍しい |
| First | At New Year, the Suzuke of fertilizer: How remarkable it is! |
| 二ニ | にっこり 授けもろたら やれ頼もしや |
| Second | Smilingly, being bestowed the Sazuke:How promising it is! |
| 三ニ | 散財心を定め |
| Third | Keep the mind of a three-year-old child! |
| 四ツ | よのなか(世の中又は大和方言で「豊に」) |
| Forth | Then, a rich harvest. |
| 五ツ | 理を吹く |
| Fifth | The providences shall come forth. |
| 六ツ | 無性にでけまわす |
| Sixth | Unlimited abundance everywhere. |
| 七ツ | 何かつくりとるなら |
| Seventh | If you grow and reap whatever you wish, |
| 八ツ | 大和は豊年や |
| Eighth | Yamato will be blessed with a rich harvest. |
| 九ツ | ここまでついてこい |
| Ninth | Now come hither and follow Me! |
| 十ド | 取りめが定まりた |
| Tenth | Then the full harvest will become fixed. |
| (解説) 一下り目と二下り目が手毬(まり)歌となっている。毬つき歌というよりはむしろお手玉歌の節回しのように思われる。この時代においては非常に盛んであった。 | |
| (教理) 「1・お道信徒の最初の歩みとして、入信祝い」をお歌で表現している。歳時記風に正月から説き始め、お道の信仰が「授け」を受けることから始まることを示唆している。入信することにより「物の豊かさのご守護」を貰うことができると歌っている。お道では、授けを受けた者を「用木」(ようぼく)と云うが、用木は第一に「散財心を定める」よう諭している。「散財心」とは、世間常識的な物欲から離れた財の活用を云うものと思われる。従って、「散財心を定める」とは、物心崇拝的蓄財の執着心を捨て、我が身も財貨も「世の為人の為に使い散じる気持ち」になるというこを意味し、これが肝要と諭されている。今風に言えば、ボランティア精神、縁の下の力持ち、革命精神の称揚という意味合いである。この心さえ身に付ければ、そこから筋道が拓けて無限に広がり、何をしても良い結果に繋がる。この道筋に世の「真の豊かさ」が始まると説く。この道に向かうのがお道信仰であるということになる。まさに字義通りの「有り難い教え」のように思われる。が、少し思案すると、我が身に直接的な福運を呼び込む為の信仰とは対蹠的であるように思われ興味深い。 | |
| 【二下り目】(Song Two) | |
| 一ツ | とんとんとんと 正月踊りはじめは やれ面白い |
| First | Tong! Tong! Tong! The beginning of the dancing at New Year: How delightful it is! |
| 二ツ | 不思議な普請 かかれば やれにぎわしや |
| Second | This marvelous construction once it is started: How lively it is! |
| 三ツ | 身につく |
| Third | Nourishment will be put on you. |
| 四ツ | 世直り |
| Fourth | The world will change to prosperity. |
| 五ツ | いづれもつきくるならば |
| Fifth | If all come and follow Me, |
| 六ツ | 謀反の根えを切ろふ |
| Sixth | I will cut off the root of rebellion. |
| 七ツ | 難渋をすくひあぐれば |
| Seventh | If you help others who are suffering, |
| 八ツ | 病の根を切ろふ |
| Eighth | I will cut off the root of illness. |
| 九ツ | 心を定めゐやうなら |
| Ninth | If you keep your mind determined, |
| 十デ | ところの治まりや |
| Tenth | Peace shall reign everywhere. |
| (解説) | |
| (教理) 「2・お道信徒の次の歩みとして、身上事情のご守護と心定め」がお歌で表現されている。「授け」を受けたら次に「踊り」に取り掛かるよう示唆している。その際「面白い」のが肝要とも示唆している。その「踊り」と平行して「不思議な普請」に取り掛かるよう促している。その際「賑わしい」のが肝要とも示唆している。この二つの意味から、「踊りと普請」こそ道人の肝要な勤めであることが分かる。 この二つが身につけば、「世直し」の始まりである。これに精進すれば、無用な争いや謀反が立ち消えることになる。困っている人の身上事情たすけに向かえば、助ける側の者の病も治る。この理を深く悟り、この道に向かう「心定め」するのが道人(みちびと)足る所以の要諦であり、「真の治まりの道」と諭されている。ここで気づくことは、お道の信仰が、単に頭脳内への教義の読誦ではなく、それをより身体的な踊りで確認しつつ、更に協働的な普請へと押し広げられていることである。非常に行動的といおうか立体的な信仰であることが分かり興味深い。 | |
| 【三下り目】(Song Three) | |
| 一ツ | ひのもとしょやしきの 勤めの場所は世の元や |
| First | At Shoyashiki in the homeland of the Sun, This place for the Service is the origin of the world. |
| 二ツ | 不思議な勤め場所は 誰に頼みはかけねども |
| Second | This marvelous place for the Service,
though I ask no one to build, |
| 三ツ | 皆な世界が寄り合うて でけたちきたるがこれ不思議 |
| Third | All gathering together from the world,
the construction has been accomplished. How miraculous it is! |
| 四ツ | ようようここまでついてきた 実の助けはこれからや |
| Fourth | With much effort, you have followed Me thus far; True salvation will begin from now. |
| 五ツ | いつも笑われそしられて 珍し助けをするほどに |
| Fifth | Always ridiculed and slandered,
still I will realize remarkable salvation. |
| 六ツ | 無理な願ひはしてくれな 一筋心になりてこい |
| Sixth | Never make an unreasonable prayer!
Come to Me with a single mind! |
| 七ツ | 何でもこれから一筋に 神にもたれて行きまする |
| Seventh | Whatever may happen, from now on,
I will go single-heartedly leaning on God. |
| 八ツ | 病むほど辛いことはない わしもこれからひのきしん |
| Eighth | There is nothing so trying as illness; so from now on, I, too, will devote myself to hinokishin. |
| 九ツ | ここまで信心したけれど 元の神とは知らなんだ |
| Ninth | Though I have believed thus far,
I did not know that You are the original God. |
| 十ド | このたび現われた 実の神には相違ない |
| Finally | This time, You have revealed Yourself.
No doubt You are the true God. |
| (解説) | |
| (教理) 「3・お道信徒の次の歩みとして、教理とつとめとひのきしん」がお歌で表現されている。お道信仰の目標(めどう)は「つとめ」と「つとめの持続」であることが示唆されている。ここまで信仰が進むことにより「本当の助け」の展望が拓ける。世間から嘲笑され謗られようとも、しっかり神にもたれて、無理な願いをせずに利害得失から離れた「一筋心」で信仰しなさい。そうすれば、神の自由自在の働きが始まり不思議なことや珍しい助けが起ると示唆している。「病むほど辛いことはない」と述べ、そういう際には気弱にならずむしろ「ひのきしん」に向かいなさいと諭している。「ひのきしん」とは、日々の寄進の意であり、それは普請労働であり多寡では無い真心込めた金銭ないし物資の寄進のことを云う。結びで、お道が根本に据えている神は元の神、実の神である。この神の思いを聞き分けすれば効能がもたらされる、と諭している。これが、お道の理論構造であり、平明に語られているが万巻の書の教えに勝るとも劣らない。かく拝するべへきではなかろうか。 | |
| 【四下り目】(Song Four) | |
| 一ツ | 人が何事云おうとも 神が見ている気をしずめ |
| First | Whatever others may say,
God is watching, so be at ease! |
| 二ツ | 二人の心を治めいよ 何かのことをもあらわれる |
| Second | Settle the minds of the two of you in one accord! Then any and everything shall be realized. |
| 三ツ | 皆な見てゐよそばなもの 神のすること為すことを |
| Third | All of you close to Me,
watch whatever God acts and works! |
| 四ツ | 夜昼どんちゃん勤めする そばもやかましうたてかろ |
| Fourth | Night and day, dong! chang! we perform the Service; The neighbors may feel it noisy and annoying. |
| 五ツ | いつも助けがせくからに 早く陽気になりてこい |
| Fifth | As I am always in haste to save you, quickly become joyful and come to Me! |
| 六ツ | むらかた早くに助けたい なれど心がわからいで |
| Sixth | Villagers I wish to save at once,
But they do not understand My heart. |
| 七ツ | なにかよろづの助けあい 胸のうちより思案せよ |
| Seventh | Helping each other in any and everything,
ponder over it from your innermost heart! |
| 八ツ | 病のすっきり根は抜ける 心はだんだん勇みくる |
| Eighth | All illness shall be completely rooted out,
and step by step your hearts will become cheerful. |
| 九ツ | ここはこの世の極楽や わしも早々(はやばや)参りたい |
| Ninth | Here is paradise on this earth. I, too, wish to go quickly to worship. |
| 十ド | このたび胸のうち 澄みきりましたがありがたい |
| Finally | This time, my innermost heart has become completely pure. How grateful I am! |
| (解説) | |
| (教理) 「4・お道信徒の次の歩みとして、心の澄ましと練りあいを経て陽気、助け合いに向うべき信仰のあり方」がお歌で表現されている。お道信仰に必須なものは「心を治めること」、「陽気になること」、「助け合うこと」、「心が勇むこと」であることが示唆されている。お道信仰の道中で世間から謗られることもあろうが、夫婦が心を合わせて陽気にしっかりつとめなさい、お道のつとめは賑やかなので周囲の者に迷惑かけようが、助けの通り道であるから心配するに及ばない。お道信仰を非難する者も含めて「なにかよろづの助けあい 胸のうちより思案せよ」。人と人とは「助け合い」に向かうべきである。ここのところが深く思案でき得心がいくに応じて、病が快方に向かい次第に元気が出てくる。「ここがこの世の極楽や」。この極楽の地と心境を目指して参拝に来るようにと促している。このことが分かると心の中がすっきり澄み渡り、それが有り難い、と諭している。 | |
| 【五下り目】(Song Five) | |
| 一ツ | 広い世界のうちなれば 助けるところがままあろう |
| First | As this world is so wide, there may be various places to save people. |
| 二ツ | 不思議な助けはこのところ おびやはうその許しだす |
| Second | Miraculous salvation at this place, I grant you safe childbirth and freedom from smallpox. |
| 三ツ | 水と神とは同じこと 心の汚れを洗ひきる |
| Third | God, the same as water,
washes away the dirts from your minds. |
| 四ツ | 欲のないものなけれども 神の前には欲はない |
| Fourth | Though there is no one who is free from greed, before God there is no greed. |
| 五ツ | いつまで信心したとても 陽気づくめであるほどに |
| Fifth | However long you may continue to believe,
your life shall ever be filled with joy. |
| 六ツ | むごい心をうちわすれ やさしき心になりてこい |
| Sixth | Forgetting away a cruel heart,
come to Me with a gentle heart! |
| 七ツ | なんでも難儀はささぬぞへ 助け一条のこのところ |
| Seventh | Assuredly I shall never leave you in suffering, because this is the place of single-hearted salvation. |
| 八ツ | 大和ばかりやないほどに 国々までへも助けゆく |
| Eighth | Not only in Yamato, I will go also to other countries to save you all. |
| 九ツ | ここはこの世の元の地場 珍しところがあらはれた |
| Ninth | This is the Jiba, the origin of this world.
Indeed a remarkable place has been revealed. |
| どうでも信心するならば 講を結ぼやないかいな |
|
| Since firmly we are determined to believe, let us form a brotherhood. |
|
| (解説) | |
| (教理) 「5・お道信徒の次の歩みとして、じばの理、陽気づくめ、匂い掛け、お助け、講の結成」がお歌で表現されている。お道の教えを広めるべく「匂いがけ」に向かいなさい。この道は「安産とほうそ」助けから始まった。心の汚れを洗い、欲から離れて、陽気な心になり、優しい心になるように。「助け一条」になるなら難儀はささない。信仰が深くなれば、国々所々世界中へ助けに行きなさい。お道信仰を強めるために「講を結ぼやないかいな」と講の結成の必要を諭している。 | |
| 【六下り目】(Song Six) | |
| 一ツ | 人の心と云ふものは 疑い深いものなるぞ |
| First | Human minds are so deeply doubtful. |
| 二ツ | 不思議な助けをするからに いかなることも見定める |
| Second | As I work miraculous salvation, I discern any and everything. |
| 三ツ | 皆な世界の胸のうち 鏡の如くに映るなり |
| Third | The innermost hearts of all in the world, are reflected to Me as in a mirror. |
| 四ツ | ようこそ勤めについてきた これが助けのもとだてや |
| Fourth | I am pleased that you have followed to join the Service. This Service is the fundamental way for salvation. |
| 五ツ | いつも神楽や手踊りや 末では珍し助けする |
| Fifth | Always performing the Kagura and Teodori, in the future I will work remarkable salvation. |
| 六ツ | むしやうやたらに願いでる 受け取る筋も千筋や |
| Sixth | You make prayers thoughtlessly. The ways of My response are also a thousand. |
| 七ツ | なんぼ信心したとても 心得違いはならんぞへ |
| Seventh | However eagerly you may believe, never entertain wrong thoughts! |
| 八ツ | やっぱり信心せにゃならん 心得違いは出直しや |
| Eighth | After all you must continue to believe.
If you entertain wrong thoughts, you are to start anew. |
| 九ツ | ここまで信心してからは ひとつの講をも見にゃならぬ |
| Ninth | Having believed thus far until now, you should be shown your merit. |
| 十ド | このたび見えました 扇の伺いこれ不思議 |
| Finally | This time, it has appeared. The invocation of the fan,
How marvelous it is! |
| (解説) | |
| (教理) 「6・お道信徒の次の歩みとして、正しい信心と講の結成」がお歌で表現されている。神楽、手踊りが大事で、「これが助けのもとだてや」。つとめを続けているうちにきっと珍しい助けが為される。但し、お道の教理に添ったものでないといけない。いくら信仰しても「心得違い」は最初からやり直しせねばならない。信仰が深くなると道人たちで信心の発展系としての講を結成せねばならない。いくつもの講を早く見たい。「扇の伺い」はこれは不思議である、と諭している。「九ッ」の「こう」を「効」と受け取る筋もある。 | |
| 【七下り目】(Song Seven) | |
| 一ツ | 一言話しはひのきしん 匂いばかりを掛けておく |
| First | A single word can be hinokishin. I simply sprinkle My fragrance around. |
| 二ツ | 深い心があるなれば 誰も止めるでないほどに |
| Second | As My intention is so profound,
no one should prevent it. |
| 三ツ | 皆な世界の心には 田地のいらぬ者はない |
| Third | There is no one in the world,
whose mind does not desire to own a field. |
| 四ツ | 良き地があらば一列に 誰も欲しいであろうがな |
| Fourth | If there is a good field,
everyone equally will desire to own it. |
| 五ツ | いづれの方も同じ事 わしもあの地を求めたい |
| Fifth | It is the same with everyone, I, too, wish to own such a good field. |
| 六ツ | 無理にどうせと云わんでな そこは銘々の胸次第 |
| Sixth | I wish to get the field by any means,
no matter what the price may be. |
| 七ツ | なんでも田地が欲しいから 与えは何ほどいるとても |
| Seventh | I wish to get the field by any means, No matter what the price may be. |
| 八ツ | 屋敷は神の田地やで 蒔いたる種は皆なはえる |
| Eighth | As this Residence is the field of God,
every seed sown here will sprout. |
| 九ツ | ここはこの世の田地なら わしもしっかり種をまこ |
| Ninth | Since this is the field of this world,
I, too, will sow the seed devotedly. |
| 十ド | このたび一列に 種を蒔いたるその方は 肥を置かずに作り取り |
| Finally | This time, I am glad to see that all of you equally have come here to sow the seed; Those who have sown the seed, shall reap a rich harvest without fertilizing. |
| (解説) | |
| (教理) 「7・お道信徒の次の歩みとして、真の種まき、匂い掛け、ひのきしん」がお歌で表現されている。「一言話し」で、とりあえず声を掛け、僅かでも話を取り次ぐ「匂い掛けひのきしん」が始まりで肝心だ。しっかり思案したものがあるならば、誰も邪魔できるものではない。世界中の人は皆田地を欲しがっている。同じ田地なら良いほうが良かろう。例えて云えば、お道はそういう最良の田地なのだ。無理に誘うのではなく、このことを理解して貰いなさい。「屋敷は神の田地やで 蒔いたる種は皆はえる」。この神の田地に種を蒔け。自らが手本となって種を蒔きなさい。その先は実り豊かである、と田地に例えて諭している。これを福田思想とも云う。 | |
| 【八下り目】(Song Eight) | |
| 一ツ | 広い世界や国中に 石も立ち木もないかいな |
| First | In this wide world and its many countries, are there no stones or standing trees? |
| 二ツ | 不思議な普請をするなれど 誰に頼みはかけんでな |
| Second | Though I carry out marvelous construction, I never ask a favor of anyone, |
| 三ツ | 皆な段々と世界から 寄り来た事ならでけて来る |
| Third | All coming together from the world one after another, it will be accomplished. |
| 四ツ | 欲の心を打ち忘れ とくと心を定めかけ |
| Fourth | Forgetting away the mind of greed, set out to determine your mind firmly! |
| 五ツ | いつまで見合わせ至るとも うちからするのやない程に |
| Fifth | However long you may hesitate,
it will never be accomplished by yourselves. |
| 六ツ | 無性やたらに急き込むな 胸の内より思案せよ |
| Sixth | Never hasten so thoughtlessly! Ponder over it from your innermost heart! |
| 七ツ | 何か心が澄んだなら 早く普請に取り掛かれ |
| Seventh | When your mind becomes somewhat purified, begin the construction at once! |
| 八ツ | 山の中へと入り込んで 石も立ち木も見ておいた |
| Eighth | Having entered into the mountains, I have already seen the stone and standing trees. |
| 九ツ | この木切ろうかあの石と 思えど神の胸次第 |
| Ninth | Whether to cut down this tree or to take that stone, it entirely depends upon the heart of God. |
| 十ド | このたび一列に 澄み切りましたが胸の内 |
| Finally | This time, the hearts of all equally have become completely purified. |
| (解説) | |
| (教理) 「8・お道信徒の次の歩みとして、本普請に取り掛かれ」がお歌で表現されている。「適材適所の世界作り」、「真の治まり難渋助け、適材適所の世を創る」ことの大事さが諭されている。世間から人材を探し出そう。お願いするのやない、同心の同志を求めるのや。世界中の各地から次第に同志が結集するに応じて何事もできる。欲の心を抑え捨て去り、世界たすけの精神を修めるのが肝心や。次に自主性が肝心や。得心したら世界たすけに乗り出そう。急ぐばかりではいけない。思案を練ることが肝心や。「何か心が澄んだなら 早く普請に取り掛かれ」。船出に当たって、みんなの心を澄ますことが肝心や。かねてより世間の中へ飛び込み人材の調査をしておけ。そして必要な人材を寄せよう、と諭している。 | |
| 【九下り目】(Song Nine) | |||
| 一ツ | 広い世界を内廻り 一せん二せんで助け行く |
||
| First | Clapping around throughout the wide world, and cleansing human hearts once and twice, I will advance the work of salvation. |
||
| 二ツ | 不自由なきやうにしてやろう 神の心にもたれつけ *みかぐら歌の明治14年本では、「ふじゅうなきよにしてやろう」となっている。現在の「やう」とは「様」で、「よ」とは「世」で、意味が大きく変わる。元は社会改革意図の強いものだったことが分かる。 |
||
| Second | Against any hardship I will protect you; so lean closely on the mind of God! |
||
| 三ツ | 見れば世界の心には 欲が混じりてあるほどに |
||
| Third | Looking into all minds of the world, I find greed intermingled. |
||
| 四ツ | 欲があるなら止めてくれ 神の受け取りでけんから |
||
| Fourth | |||
| 五ツ | いづれの方も同じこと 思案定めてついてこい |
||
| Fifth | It is the same with everyone. Determine your Mind and follow Me. |
||
| 六ツ | 無理に出ようといふでない 心定めのつくまでは |
||
| Sixth | I never compel you to go forth,
until you determine your own minds. |
||
| 七ツ | なかなかこのたび一列に しっかり思案をせにゃならん |
||
| Seventh | Indeed, this time all of you equally must ponder over it deeply. |
||
| 八ツ | 山の中でもあちこちと てんりん王の勤めする |
||
| Eighth | Even in the mountains here and there,
the Service of Tenri-O is performed. |
||
| 九ツ | ここで勤めをしていれど 胸のわかりた者はない |
||
| Ninth | Though people are performing the Service here, no one understands My heart. |
||
| とても神名を呼びだせば 早くこもとへ訪ね出よ |
|||
| Now that you are calling the name of God, come forth quickly to the original home! |
|||
| (解説) | |||
| (教理) 「9・お道信徒の次の歩みとして、心定めのつとめ、布教」がお歌で表現されている。いよいよ世間の救済活動に向かう。「一せん二せんで助け行く」。神の心にもたれるなら自由自在が働いて不自由ない。世間は欲にまみれているので神の自由自在が働かない。この理は誰も同じで思案を定めるのが肝心だ。この心定めがついてからお助けに向かいなさい。この間「てんりん王の勤め」が大事である。しかし、本当にお道教義が分かって勤めしているのか心もとない。本当の話を聞きたければ、「早くこもとへ訪ね出よ」、と諭している。 | |||
「みかぐらうた”一せん二せん”について」(平成十三年一月発行「御存命の頃」高野友治著(道友社刊)219ページより)。
(平成十三年一月発行「御存命の頃」高野友治著(道友社刊)164ページより)
|
|||
| 【十下り目】(Song Ten) | |
| 一ツ | 人の心と云うものは ちょとにわからんものなるぞ |
| The human mind cannot understand truth easily. | |
| 二ツ | 不思議な助けをしていれど 現われ出るのが今始め |
| Second | Though I have been working miracles of salvation, this is the first time that I reveal Myself. |
| 三ツ | 水の中なるこのどろう 早くいだしてもらいたい |
| Third | This mud in the water,
I wish you to take it out quickly. |
| 四ツ | 欲に切りない泥水や 心澄みきれ極楽や |
| Fourth | Greed is fathomless like muddy water. When your mind is completely purified, then comes paradise. |
| 五ツ | いついつまでもこのことは 話しの種になるほどに |
| Fifth | Forever this shall become the seed of stories. |
| 六ツ | むごい言葉を出したるも 早く助けを急ぐから |
| Sixth | Though I have spoken such severe words, it is because of My haste to save you. |
| 七ツ | 難儀するのも心から わが身恨みである程に |
| Seventh | Suffering comes from your own mind. So you should reproach yourself. |
| 八ツ | 病はつらいものなれど 元を知りたる者はない |
| Eighth | Though illness is so trying, no one has ever known its origin. |
| 九ツ | このたびまでは一列に 病の元は知れなんだ |
| Ninth | Until this time all of you equally
have been ignorant of the origin of illness. |
| 十ド | このたび現われた 病の元は心から |
| Finally | This time, it has been revealed.
The origin of illness lies in your own mind. |
| (解説) | |
| (教理) 「10・お道信徒の次の歩みとして、心澄みきれ極楽や」がお歌で表現されている。お道信仰の眼目は、欲の心を棄てて心を澄まし、親神の思いに叶うことにある。「欲に切りない泥水や 心澄みきれ極楽や」。時に厳しいことを云うのも「早く助けを急ぐから」であり、致し方ない。当り障りのないことばかり云っていては助けができない。「病の元は心から」であり、この理が分からないから難儀が起っている。今までこのようにはっきりと述べた信仰はないであろうが、このことを深く諭すのが肝要である、と諭している。 | |
| 【十一下り目】(Song Eleven) | |
| 一ツ | 日の元しょやしきの 神の館のぢば定め |
| First | At Shoyashiki in the homeland of the Sun, the Jiba, the abode of God, is to be identified. |
| 二ツ | 夫婦揃うてひのきしん これが第一もの種や |
| Second | Husband and wife working together in hinokishin; this is the first seed of everything. |
| 三ツ | 見れば世界が段々と もっこ荷うてひのきしん |
| Third | I behold more and more people coming from the world, and bearing straw baskets in inokishin. |
| 四ツ | 欲を忘れてひのきしん これが第一肥えとなる |
| Fourth | Forgetting greed we work in hinokishin.
This becomes the first fertilizer. |
| 五ツ | いついつまでもつちもちや まだあるならばわしもいこ |
| Fifth | Forever continues the carrying of earth.
If yet it continues, I, too, will go. |
| 六ツ | 無理に止めるやない程に 心あるなら誰なりと |
| Sixth | Do not unreasonably stop anyone!
I welcome any and everyone who is willing. |
| 七ツ | 何か珍しつちもちや これが寄進となるならば |
| Seventh | How remarkable this carrying of earth is,
When it serves as a contribution to God! |
| 八ツ | 屋敷の土を掘りとりて 所替えるばかりやで |
| Eighth | Digging up the earth of the Residence,
you just carry it from one place to another. |
| 九ツ | このたびまでは一列に 胸がわからん残念な |
| Ninth | Until this time, no one has ever understood My heart; How regretful it is! |
| 十ド | 今年は肥え置かず 充分ものを作り取り やれ頼もしや有難や |
| Finally | This year, without fertilizing, we reaped a sufficient harvest.
Oh, how delighted we are! How thankful we are! |
| (解説) | |
| (教理) 「11・お道信徒の次の歩みとして喜び勇んでひのきしん」がお歌で表現されている。世間へ向けてのお道の発展に応じて「神の館ぢば本部」の整備に向かう。この事業を道人の「ひのきしん」でやるのが良い。夫婦力合わせての「夫婦ひのきしん」が肝心で理想だ。欲を忘れての「もっこひのきしん」が一番功徳がある。この道中を喜び勇んで通るなら、例えて云えば肥料なしに作物が充分にできるようなことになる。お道信仰は頼もしいし有り難い。 | |
| 【十二下り目】(Song Twelve) | |
| 一ツ | 一に大工の伺いに 何かの事も任せおく |
| First | Initially to the invocation of the carpenter, I have any and every detail. |
| 二ツ | 不思議な普請をするならば 伺いたてて云いつけよ |
| Second | When you begin the marvelous construction, give instructions after invoking My will! |
| 三ツ | 皆な世界から段々と 来たる大工に匂いかけ |
| Third | From all over the world, carpenters are coming one after another. Sprinkle My fragrance o them! |
| 四ツ | 良き棟梁があるならば 早くこもとへ寄せておけ |
| Fourth | When you find good masters,
quickly bring them to this original home! |
| 五ツ | いづれ棟梁四人いる 早く伺い立てて見よ |
| Fifth | In the future four masters will be needed. Quickly invoke My will! |
| 六ツ | 無理に来いとは云わんでな いずれ段々つき来るで |
| Sixth | I never compel you to come forth.
Yet you will come along one after another. |
| 七ツ | 何か珍しこの普請 しかけたことならきりはない |
| Seventh | Ever so remarkable is this work of construction; Once begun, there shall be no end to it. |
| 八ツ | 山の中へと行くならば 荒き棟梁連れて行け |
| Eighth | When you go into the mountains,
take with you the wood master! |
| 九ツ | これは小細工棟梁や 建前棟梁これかんな |
| Ninth | Here are the fine work master,
the framing master and the planer. |
| 十ド | このたび一列に 大工のにんも揃い来た |
| Finally | This time, all the members of carpenters have assembled. |
| (解説) | |
| (教理) 「12・お道信徒の次の歩みとして四人の棟梁と共に」がお歌で表現されている。世界たすけを家の普請に例え促している。「よふぼく」、「だいく」、「とうりょう」、「つちもち」などの言葉は、すべてふしんに関係する用語である。後に「さづけ」を渡す本席となられた飯降伊蔵(教祖の高弟)が大工の棟梁であったことにも関係があると思われる。事実「みかぐらうた」は飯降伊蔵本席をモデルとして歌われているといっても過言ではないほどである。世界普請の仕切りは大工に任せている。この後の世界普請に向かうには大工と相談して為せ。寄り集う大工に「匂いかけ」し、良い棟梁を見つけたら寄せよ。棟梁は4名必要である。この仕組みえしっかり確立されればお道は磐石となる。この事業にはきりはない。困難待ち受ける世界には荒き棟梁が相応しい。その他小細工棟梁、建前棟梁と要る。今や大工が揃い踏みしている。さぁ、臆することなく世界普請に取り掛かれ、と諭している。 | |
![]()
| 【「お歌」考】 | |
このたびの「み神楽歌」の御作成について教理では次のように説く。
|
「みかぐらうたについて」(昭和二十年十二月号みちのとも「みかぐら歌について」山澤為次より)。
|
|
「おてふりについて」(「復元」第22号、「教祖様のお話」梶本宗太郎より)。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)