| 1首 |
よろづ世の 世界一列 見はらせど
胸のわかりた 者はない |
Looking all over the world and through all ages,
I find no one who has understood My heart. |
| (解説) 「よろづよ」とは「万代(世)」と書き、過去数千年にわたる人類の歴史のすべてを云う。世界は「世の中」。「一列」は「全て、総て」。「見はらせど」は「見渡せど」。「胸」は「神の思い」。「わかりたものはない」は「分かった者がいない」。 |
| 以上より、「世間を見晴らせど、親神が思っている胸の内やこの世の本当の真実を分かった者はいない」と云う意味になる。神の思いが分からない為に、人の世の不幸や災難、社会の乱れが生じているとの裏意味がある。 |
| 2首 |
その筈や 説いて聞かした ことハない
知らぬが無理でハ ないわいな |
So should it be, for I have never taught it before,
It is natural that you know nothing. |
| (解説) 「その筈や」は「その筈である」。「説いて聞かしたことハない」はそのまま。「知らぬが無理でハないわいな」もそのままの理解で足りる。 |
| (意訳)「それも道理で、神はこれまで親神が思っている胸の内、この世の本真実を明かされなかった。だから人々がこれを知らぬのも致し方ないない」。 |
| 3首 |
このたびは 神が表へ 現われて
何かいさい(委細、一切)を 説き聞かす |
This time I, God, revealing Myself to the fore,
teach you all the truth in detail. |
| (解説) 「このたび」とは、天保9年10.26日の教祖みきの神がかり、神のみき貰い受けを通して、大和の中山家において、みき教祖が月日のやしろと定められた刻限のことを云う。もしくはお筆先をご執筆始められた明治2年正月頃とも考えられる。「神が表へ現れて」とは、教祖を生きた社として神が入り込み、教祖を通して天啓を下すことを意味している。天啓とは、神の意思の発動であり、神みずからが特定の人間を選び、一人称で語りかける希有の現象を云う。「なにかいさいをときゝかす」の「いさい」(委細、一切)とは、いつ、どこで、どのようにして、何のために、この世人間が創造されたのか、この世の一切はどのようにして成り立っているのか、その元なる原因を詳しくの意である。「説き聞かす」は「説き聞かせて明かす」の意。 |
| (意訳)「このたび神が現れて、人類の創世記、この世の仕組み、人の在り方の元真実、本真実について教えることになった」。「天に口なし、人を以て言わしむ」という古語がある。 |
| 4首 |
この所 大和の地場の 神がた(館)と
いうていれども 元知らぬ |
You are calling this place the Jiba, the home of God, in Yamato;
but you do not know of its origin. |
|
(解説) 「この所」はそのまま。即ち今、仮甘露台が据えられている大和国山辺郡庄屋敷村の中山家のある場所(現在の奈良県天理市三島町、天理教教会本部のある場所)を指す。「大和の」もそのまま。「地場」(ぢば)は、古来「神の降りる所」という意味がある(梅原猛氏の説)。「元の理」では、親神が人間の元種を宿し込んだ人間の本源場所を云う。現在、本部の礼拝場の中心に雛型かんろだいが建っている所が「ぢば」とされている。かつての中山家の一室であった。「神がた(館)と」は、み神楽歌の十一下り目「ひのもとしよやしきの 神のやかたのぢばさだめ」と歌われている「神のやかた」であり、「かみがた・神館」と縮まったものと解釈される。他に「神方」、「上方」という読み方もできる。「いうていれども元知らぬ」はそのまま。その「元」を誰も知る者はないの意。
|
| (意訳)「神が現れたここ大和の地場は厳正な神の館である。そのように云われて入るが、この世の元の本真実まで知っている者はいない」。 |
| (注) み神楽歌の原本が残っておらず、その表記は後の世に書かれたものであり、原本通りであるのかどうかは分かっていない。しかし、よろづよ八首については、同様のお歌がお筆先に書かれており、教祖直筆の原本が残っている。その原本によれば、このお歌の「ぢば」は「しバ」と表記されている。「しば」とは芝と書き、当時の大和方言では「神聖な場所」を意味した。その意味でこのお歌を訳し直すと、 「この場所周辺は、昔から国のまほろばと云われ、日本の歴史が始まった場所として神聖な場所であり、親神が降臨され給う神の館屋敷であると云われているが、その元というものを誰も知らないであろう」と云う意味になる。 |
|
ここで、天理市の石上神宮に触れておく。同宮を氏神とする物部氏は現在の天理市一帯を根拠地として栄えた元々の王家であり大氏族であった。石上神宮の祭神は、布都斯御魂大神、布留御魂大神。布留はニギハヤヒの別名とされている。山辺の道の終点に当たる三輪山にも同じニギハヤヒ(大物主命)が祀られている。元々、大和一帯を治めていたのはこのニギハヤヒの命であったといわれている。物部氏はそのニギハヤヒの直系である。ニギハヤヒの命が生駒山の東側山麓の日下(くさか)に降臨したとする伝説があり、太古に西方から移住した一族の長であったとみられる。生駒山は一名ニギハヤヒ山とも呼ばれていた。物部氏はその後、6世紀後半に至って蘇我氏との権力闘争に敗れ全国に離散する。その祖先が天神から授けられたと伝えられるのが、「十種の神宝」(とくさのかんだから)と「魂振り(たまふり)の神事」である。この魂振りこそは日本の真の伝統を受け継ぐ神事と云われる。魂が清められ振るい立つとき、病気災難は雲散霧消する神秘が現れるとする神事である。教祖の教理はこうした古代日本の故事伝説を生き生きと踏まえていることが注目されねば正しい理解にはならないと思われる。石上神宮の一隅に国宝の神楽(かぐら)殿が遺っているのも偶然ではない。後の天理教祖・前川みきが大和神社の近くに生誕し、石上の氏子である中山家に嫁がれたことは決して偶然ではない。大和神社の祭神は、大和大国魂大神(=ニギハヤヒ)であり、しかも教祖の生母は、代々大和神社の巫女(みこ)を出してきた長尾家の出である。 |
| 5首 |
このもとを 詳しく聞いた ことならバ
いかなものでも 恋しなる |
If you are told of this origin in full,
great yearning will come over you, whoever you may be. |
|
(解説) 「このもとを詳しく聞いたことならバ」はそのまま。「なぜこの場所を地場や神館と呼ぶのかということの元というものを親神から詳しく聞いたことならば」。「いかなものでも恋しなる」はそのまま。
|
| (意訳)「元の本真実の話を詳しく知れば知るほど、どんな者でも元の本真実が恋しくなる」。
|
| 6首 |
聞きたくバ 訪ねくるなら 云うて聞かす
よろづ委細(一切)の 元なるを |
If you wish to hear and will come to Me,
I will tell you the truth that this place is the origin of any and everything. |
| (解説) 「聞きたくバ訪ねくるなら云うて聞かす」はそのまま。「よろづ委細(一切)の元なるを」はそのまま。「いさい」とは、この世の元始まりから神が表へあらわれて「たすけ一条の道」をつけるまでの親心の委細、あるいは一切。 |
| (意訳)「この世の本真実、あらゆる全てのものの根元を告げる有難いこの話を聞きたければ、訪ね来るが良い。来れば、何から何まで詳しく明かしてあげよう。一から十まで何なりとたっぷりと十分に聞かせよう」。 |
| 7首 |
神が出て 何か委細(一切)を 説くならバ
世界一列 勇むなり |
When I, God, reveal Myself and teach you everything in detail,
all people in the world will become cheerful. |
| (解説) 「神が出て」はそのまま。「何か委細(一切)を説くならバ」はそのまま。「世界一列勇むなり」もそのまま。 |
|
(意訳) 「神が出現して、この世の本真実、あらゆる全てのものの根元を説いたなら、聞けば聞くほどもっと聞きたくなり、聞けば聞くほど勇むことになる」。裏意味として、どのようにして「陽気づくめ」世界の「普請」を進めるかについて、その順序と仕組みの委細をも明らかに説き聞かされており、これを聞けば聞くほど生命の曇りが晴れ勇気が出てくることを語っている。
「勇む」は、親神の思いを聞き分け、陽気つとめで始めて陽気づくめになり、ひのきしんをし、助け合い世界の創造に向かう姿を云う。「ひのきしん」は「ひとすじ心」になって「天恩・人恩に報じる心」で為すもので、「夫婦揃うてひのきしん」、
「欲を忘れてひのきしん」が良いとされている。
「勇む」ためにはプラス思考が必要となる。プラス思考は生命思考であり健康思考であるお道の教理によって翻然とする。即ち、生かされているという原点に戻って、神様が身の内に入り込んで働いてくださっている守護の理に目覚めることで、神の理そのものに心を合わせて生きる道が拓ける。「勇む」の反対は「いずむ」であり、マイナス思考に落ち込む状態を云う。不平不満、不足、憎しみ、恨みなどはすべてマイナス思考となる。お道の教理に反する方向へ向かえば向かうほどマイナス思考が強まる。
例えば、見事な集団生活をするので有名なアリには胃袋が二つあるといわれている。。一つは本物の胃袋で、自分の体に栄養を補給するために使う。もう一つの方は口と胃の中間にある袋で別の名前がついているが、食べたものを入れるのは胃と同じである。この、もう一つの袋に入った食べ物は液体として蓄えられる。この栄養液はお腹をすかした仲間のために使う。アリの様子を見ると、一匹が他の一匹に近づいて、触角で相手を撫ぜていることがある。これは「私は空腹です。もし君が食べ物を持っているなら分けてくれませんか」と求めている。そこで求められたほうのアリが第二の袋に栄養液の蓄えがあったら、二匹のアリは体を持ち上げて、口移しに一方から他方へ栄養液を吐き出して、相手はこれを飲み込む。このようにしてアリは助け合って生活している。いわばアリには二つの胃袋があって一つは自分のために使い、他の一つはみんなのために使っている。 |
| 8首 |
一列に 早く助けを 急ぐから
世界の心も 勇さめかけ |
As I hasten to save all of you equally,
I will set out to cheer up all the minds of the world. |
| (解説) 「一列に早く助けを急ぐから」はそのまんま。「世界の心も勇さめかけ」はそのまんま。 |
| (意訳) 「親神は、この世界中の人間の全てを、一人も余すことなく助け上げたいと思い、その助けを急いでいる。その為の世直し、世界の立て替えを願っている。世界の人々を勇ませて共同で神人和楽の世界に誘おうとしている」。裏意味として、この親神の御意思を知り、用木となって働くよう促している。この意を拝し汲み取るのがお道信仰である |
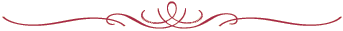
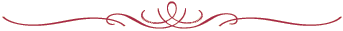
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)