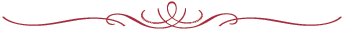
| 「お道教学」総論 |
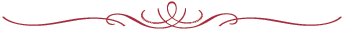
更新日/2016.7.8日
| 【「お道教学」総論その1、お道教学の構造考】 |
| 「お道教学」とは、天理教の教祖中山みきによって始められた理論と実践の集大成したものを指す。通常「天理教学」とも云うが、教組みきの教えと天理教団のそれには明らかな違いがあるので、識別する意味で教組みきの教えのものを「お道教学(又は教理)」と表現する。対照的に天理教団のそれを「本部教学(又は教理)」と呼ぶことにする。従って、「天理教学」なる表現は「お道教学(又は教理)」と「本部教学(又は教理)」を同視したやや曖昧模糊の感が否めない。 「お道信仰」は、「助けでも拝み祈祷でいくでなし」、「この世にかまい憑き物化け物も、必ずあると更に思うな」(十四号16)という御言葉で端的に云い表されているように、「呪術・祈祷信仰的助け」によらず、むしろそういう呪術的信仰の仕方を否定して新たな「聞き分け思想的助け」に向かうことを特質としている。お道の「助け」は、個人の救済に止まらず社会変革まで指針させている。それは極めて実践的な救済理論と云える。 個人救済の第一は、肉体的な心身の病に対するものであり、「お道」ではこれを「身上たすけ」と云う。個人救済の第二は、人の社会生活の苦労、悩みに対するものであり、これを「事情たすけ」と云う。「お道」の個人救済は、「身上たすけ」と「事情たすけ」の二本立てからなる。 「お道信仰」の白眉なところは、この「個人助け」に止まらず、身上、事情の根源にある観念の歪みを諭し、聞き分けを促し、更にそれらの背後にある世の在り方の歪みを本来のあるべき姿へ改造ないし変革を志していくよう促すところにある。この境涯に立つのを「心定め」と云い、その改心志士達が「講」を結び、回天社会変革運動に乗り出すことを指針させている。その際の社会変革運動の芯となるものが「かんろだい思想」であり、「かんろだいつとめ」である。 「お道教学(又は教理)」は、凡そ以上のような理論構造となっている。してみれば、これは宗教でもあり、思想でもあり、政治でもあり、社会運動でもあると云えよう。宗教から始まり社会変革運動にまで達するこの論理構造を是認するならば、「お道教学(又は教理)」の評価は一重に「かんろだい思想」、「かんろだいつとめ」の内実如何にかかっていることになる。世上のそれらと比較しての優劣が問われていることになる。 創教期においてみきが目指したものは、みき在世当時の周囲のどの宗派のそれよりもより生活有益的な且つ実効性のある「根底的且つ理詰め筋道的な新信仰」の創造であった。その苦吟は、神懸かり以降二十年の歳月を費やしている。結果的に、当代随一の内容を持つばかりか世界のどの宗教のそれらと比較しても遜色のない否よりましに値打ちのある信仰の樹立に成功した。「お道教学」の秀逸性がこの観点から検討されることはまま為されているものの、未だ不十分である。それ程に高みの思想を形成していると見なされるべきだろう。 「お道教学」の実践構造を簡略に説明すると次のように表現することができる。教祖みきの諭しを以って始まるが、その際「説き分け、聞き分け」が重視される。この時、「埃(ほこり)論」が中心になる。れんだいこが意訳すれば次のように云える。人はこの世の生業(なりわい)で世俗にまみれるうちに否応なく汚濁し、為に身心が淀む。典型的な埃として「八つの埃」が挙げられている。「埃(ほこり)論」は古神道的「禊(みそぎ)論」の系譜を引いているように思われる。 「禊(みそぎ)論―埃(ほこり)論」は、他の教義の諭しと比較した場合、難解さを持たず簡略明快である。仏教的な業理論、因縁論で諭さず、ユダヤ―キリスト教的な罪論、罰論でも説かず、底抜けに明るい。拭えば洗われるものとして、容易に切り替えができるものとしての「日本的埃(ほこり)禊(みそぎ)論」で説いているところが斬新である。更に云えば、心身の淀みに対して、これを成人を促す好機としての「神の手入れ」として受け止め、再生つまり「新たなる出直し」に向かうよう説き聞かしており、論理式的に見て弁証法構造になっているところも素晴らしい。 これを納得した者は、お道の連れ合いになり、更なる「談じ合い、練りあい」が要請され、その間「たすけ」の実践に向う。こうして「成人」化を目指すことが促されている。信仰の根本に「弁証法的成人論」が据えられていることはもっと着目されるべきであろう。 「お道教学」の組織構造を簡略に説明すると次のように表現することができる。まずは、「無理な願いはしてくれな、一筋(すじ)心になりて来い」から始まる。このことはまず「発意」が重視されていることを示している。始発に於いて、個人的な我執からくる欲得勘定の道ではないことを言い聞かせ、これを受け取る者が道人になることができる、と示唆しているように拝することができる。 そのように受け止めるよう心構えと決意を促す。その際「自由、自主、自律」がキーワードとなっていることが新鮮である。次に、「この所、万(よろづ)の事を説き聞かす。神一条で胸の内より。分かるよう胸の内より思案せよ。人助けたら我が身助かる」と述べ、「思案を深めること」、「共生的助け合いへの転身」の重要性を説く。 圧巻は、「元の理」を説き明かしたことである。「お道教学」の眼目はここにあり、これに由来する。「元の理話し」は全く独特の語りで、人間存在の根本的意義、役割、使命、目的等々を説き明かしている。いわゆる例え話で為されているが、その際の「理合い」の探求は科学的でさえある故にいつの世にも通用し古くならない。 次に、「元の理」の学びと思案と実践を高める為の行として、「おつとめ」と云われる「み神楽歌」の「謡いと踊り」の確立へと向かう。「元の理」による「おぢば」と云われる人類発祥の地に「かんろだい」が据えられ、この聖地「かんろだい」を取り巻いて為される「かんろだい神楽づとめ」が、「おつとめ」の最高儀式となる。いわば、ここが「お道信仰」の船着場であり、精華である。 この間並行して「急き込み」のままに直筆で書き付けられた平仮名体の和歌が残されている。これを「お筆先」と云う。更に、高弟との問答集「お指図」がある。更に、「お話し」、「お諭し」がある。いずれも深遠な内容を当時の農民が理解できるよう咀嚼して言葉を紡いでおり、道人の思案が深まるよう促されている。これらが全て「この世治める真実の道」であるとして心意と理論と実践の三位合一を促している。 2003.8.26日再編集、2010.08.26日再編集 れんだいこ拝 |
| 【「お道教学」総論その2、お道教学の秀逸考】 |
| 「お道教学」の秀逸性は語り尽くされていない。それは少なくとも日本の古神道、日本式仏教、中国式陽明学、西欧マルクス主義の四視点から比較精査されねばならないと考える。以下、素描しておく。 「お道教学」の日本古神道との繋がりはまだ解析されていない。れんだいこは、元始まり譚の「泥海古記」の由来も含め、古神道との符合を感じる。「お道教学」は、「古神道教理のみき版」ではないかと思っている。例えば、埃論は古神道の祓え清め思想のみき版ではないか等々。これは別の機会に考察したいと思う。 「お道教学」の偉大さは、奇しくも同時代に勃興した西欧のマルクス主義に比肩して恥ずることのないところに認められる。というか、人間洞察と自己変革、世直し、世の建て替え理論の結合ぶりはマルクス主義を凌ぐ弁証法的道筋で披瀝されているとも云える。実践性という意味では、マルクス主義が理論と実践の間に乖離が見られるのに対し、「お道教学」では見事に関連している。まず、人間の本源的平等性を知るという観点を確立し、次に、「人の喜び楽しむように生まれついたこの私」という風に生命哲学を説き、次に、思想の成人化を促し、「助け合えば勇む。争えばいずむ。ここまで育ったこの私」、「人を助ける心は真の誠、一つの理で、助ける理が助かる」(おかきさげ)として生き甲斐の社会化へ出藍(止揚)させ、更に、「難渋助けて谷底せり上げの道」として万人平等社会の創出へ向けての社会変革を意欲させ、更に、「万人喜び勇む陽気づくめ暮らしの世界、共生かんろだい世界の創造」を指針させている。 道人に要求されるのは、この目標(めどう)に向けての主体的実践としての「つとめ一条、たすけ一条」であり、「自他共に陽気世界の創出を楽しむ相互関係」を目指させている。この過程を「成人理論」で説き明かし、精進の階梯として向自化させている。その原点として、「かんろだいづとめ」を創造し、委細をこれに込めている。 「お道教学」の思想的秀逸性は次のことにも認められる。仏教の到達した最高教理として転輪王信仰があったが、仏教の場合、転輪王の難渋を助けるという働きにすがり、助けてもらうという祈祷という形で信仰が生みだされていた。曼荼羅信仰とはそういう類の信仰であった。みきは、この転輪王信仰を継承し、これを更に能動的に止揚させた。これを信仰する者一人一人が転輪王になって積極的にたすけ一条に徹し、世界を陽気づくめの世に替えるという世直し運動と結合する形での転輪王信仰へと昇華させている。つまり、心構えを切り替え、行いを切り替え、世の有様を切り替えるという「心・知・行三位合一思想」を打ち出している。陽明学の知行合一思想とも重なっており、中山みきの思想性の高さがここにある。 この中山みきの本当の凄さは次のことにある。まずみき自身が手本となるひながたを見せ、云うことと行うことの一致を指針させている。自らの生の軌跡つまり「ひながた」でもって、その思想の高みを道人に甘受させるべく、まさに手取り足取り粘り強くねんごろに諭し抜いている。この合一技は余人を以っては為しえない。そのことにある。道人は、このみきのひながたを辿る。これにより、お道は、「ほん何でもない百姓家の女」が通って見せた、「何時でも、何処でも、誰でも万人が通れるひながた」を辿ることになる。これら全てが「お道教学」である。その評価は今後ますます高くなると思われる。 2003.8.26日再編集、2010.02.21日再編集 れんだいこ拝 |
| 【「お道教学」総論その3、八島氏の教示考】 | |||
八島氏は、「ほんあづま」(№422、2004.4.5日)の前書きの中で次のように述べている。参考になるので転載しておく。
八島氏は、「ほんあづま」(№422、2004.4.5日)の前書きの中で次のように述べている。参考になるので転載しておく。
八島氏は、「ほんあづま」(№423、2004.5.5日)の前書きの中で次のように述べている。参考になるので転載しておく。
2003.8.26日再編集、2005.6.26日再編集 れんだいこ拝 |
| 【「お道教学」総論その4、古神道との通底性考】 |
| 「中山ミキ思想の古神道との通底性考」に記す。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)