| 第89部 |
1915年~ |
大正4年~ |
2代真柱に中山正善が就任 |

更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.8.22日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「2代真柱に中山正善が就任」を確認しておく。
2007.11.30日 れんだいこ拝 |
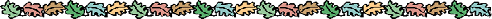
1915(大正4).1.8日、山沢摂行者が斎主、松村吉太郎が副斎主をつとめ、真柱の葬儀が執り行われた。
1.21日、二代真柱中山正善が9歳8ヶ月にして管長職に就任。奈良教務支庁の山澤為造が管長職務摂行者に就任。これにより、山澤が教団の代表者となった。前真柱未亡人・中山たまえが、真柱の後見役を務めることになった。
| 【大平宗平「新宗教」発刊】 |
| 4.1日、大平宗平「新宗教」が発刊される。5.8.19日号まで続く。 |
| 【大平隆平と奥谷文智の応酬】 |
「新宗教」の大平隆平と「みちのとも」記者/奥谷文智の応酬が興味深い。奥谷文智の文「事情なければ心が定まらぬ」(「道の友」8月号)は次の通リ。
| 松村教正の御入監後、前管長夫人よりは逸早く『御神楽歌』を差入れられ続いて間もなく拙著『天理教祖観』が東京から到着したので、直ちに之をも差入れた。教正は独房の中にあつて読書を唯一の楽として居られるらしいが、その書物も教正からの希望で、大概は本教に関するものばかりである。必ずや獄中私かに教祖を偲び奉り、深い教理の修養に耽らるゝ事であらう。『教祖に帰れ』とは数年以前から屡々耳にする処である。或る者はその声に和して慌て者が火事に出会つたやうに『天理教革命の声などゝ叫び出したりして居る。教祖が豊田山に埋れておいでになると思へばこそ、そんな小細工も弄して見なければならん、なんぞ図らん教祖は生き通しである。豊田山には御遺骸があるばかりだ。見よ教祖は我等の凡眼にこそ見えね、儼然として白日の中に立つて世界をろくぢに踏み平らすべく大車輪の活動を日夜継続し給ふではないか。初代管長公の御帰幽も、広池博士の引退も、松村教正の収監も天理教徒の惰眠を鞭撻し給ふ教祖の御働きである。神の啓示である。 |
奥谷は、天理教の革命を訴える大平に対して、大正初期の初代真柱出直し、広池辞任、松村吉太郎の収監もご存命の教祖の働きであり、神の啓示であると説いている。それに対する大平の反論は次の通り。奥谷式「教祖の働き」と捉えず、「教祖の腐敗堕落」と捉え、天理教教団に対して「教祖立教の精神に立ち返るべく覚醒」を促がしている。
| 君は自分達(或るいは自分だけかも知らない)を痛罵して或る者はその声に和して、慌て者が火事に出会つたやうに『天理教革命の声』などゝ叫び出したりして居ると云つて居るが、そんなら君が今年の五月号か六月号かに書いた教祖に帰れと云ふ一文は一体どう云ふ動機で書いたのですか?既に教祖に帰れと云ふ其処に教祖と離れたる何等かの点がなければならぬ筈である。而かもそれと同一の目的を以つて実際に教祖の精神の復活者が表はれるや之を喜んで迎ふべきに、却つて堂々たる天理教の機関雑誌の記者にも似合はず自己の人格を無視し同時に相手の人格を無視した冷罵を浴びせかけて得々然として居るのは何の為めであるか? |
|
4.25日、前年の昭憲皇太后の諒閻(りょうあん)の為に延期されていた本部神殿落成祝祭執行。山澤が奉告祭の祭主を務める。神道派が教内を完全制圧したことを意味する。
|
| 6.27日、本部員・松村吉太郎が10年前の賄賂密告「小川事件」により、未決で捕らえられ奈良監獄署に収監された。 |
|
| 6月、天理教北大教会(茨木基忠会長)で、茨木基敬様(旧長公)の天啓のもと、北の軍艦として部内の巡教で教えを徹底する中、借財を返済し救済の広がりがあった。「御水の御伝へ」の啓示書は、初代真柱が出直された理由を、青地が推測している無理なお供えを強要したことよりも、基敬の神の言葉である天啓を受け入れなかったことが真の原因であると書いている。(天理大学の学会の報告資料より)
|
10.1日、諭達第8号。山澤為造が御大典記念に高等女学校設立及び布教等の強化を図る。
11月、二代真柱が天理教の真柱の公務開始。
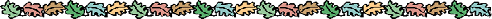
| (宗教界の動き) |
| 朝鮮に神社祭祀令。 米アレン女史バプティスト来日。カトリック札幌司教区設置。 |
1916(大正5)年、教祖三十年祭前後に天理教内に天啓者待望が醸成された。
1.24日、本部員増野正兵衛氏の長男で、「鼓雪」と号して文筆にも素晴らしい活躍をする増野道興が本部准員を命ぜられ、同時に道友社編集主任となった。二十六才という若さであった。この頃、「教勢の推移」と題して、大胆にして深刻な講演をし、天理教の過去、現在、将来について語るところがあった。
| 【教祖30年祭執行】
|
|
1916(大正5).1.25日、教祖30年祭執行。このときから陽暦で執行されるようになった。全国各地から15万余の信者が参拝した。この間大正三年から八年にかけて初代真柱様出直し、第一次世界大戦勃発があり、そうした真っ直中で祭典が行われた。
教祖30年祭に先立ち、お指図に基づいて図面が書かれ、本部神殿(現北礼拝殿)と教祖殿(現在の祖霊殿)が建築され東洋一の木造建築物が出現した。これを「大正普請」と云う。大正三年に初代真柱様がお出直しになり大変な時期で、疲弊した日本の中で一生懸命に先輩の先生方が普請に伏せ込まれた時代となった。
「この三十年祭の一年前、初代真柱の中山真之亮が出直した。一部の信者のあいだでは、本部神殿の新築のため各級教会を”搾取”しすぎたので、親神の怒りにふれたのだと、まことししやかにささやくものもあった」、「教組30年祭の当時、その莫大な費用をひねり出すために、山のような借財をかかえこんだり、貧窮に落ち込んだ教会もすくなくない」(青地、p.225)とも評されている。
この時、それまでの「かんろだいのつとめ」に代わり、世上の理である天皇の先祖を神とする「天理王命のつとめ」(「あしきをはろうて、たすけたまへ、てんりおうのみこと」)をつとめる。これに対して、天理中学校長の広池が「一列すましてかんろだい」のつとめこそやらねばならない、述べている。かんろだいのつとめこそが本当のものである。拝み祈祷のこんなおつとめは教祖の精神に叶わない、と述べ、校長を罷免される。本当に教祖の教えを説いた人たちが、年祭りのかどめ、かどめで排除されていく」(八島英雄「ほんあづま」№438)。
山沢為造が、「教祖が教えた『天理王命のつとめ』が弾圧にあってつとめられなかったのを復活してつとめる」と称して、ヤタの鏡の模造品を天理王命の御分霊として、「天理王命のつとめ」をつとめる教義に改めた。
|
3.18日、松村吉太郎保釈される。3.30日、松村が、権大教正、天理教教庁幹事、天理教会本部役員、教師懲戒委員長、教師検定試験委員、大阪教務支庁長、満州布教管理者、天理教教校幹事、天理中学校校長等の役ま辞職届けを本部に提出する。
この頃、飯降政甚の二度目の負債問題が発生し、松村吉太郎の「親が道に尽くしきり、子をして路頭に迷わすのは、まことに情に忍びない。子の道を立ててやるのが親の霊に報いる道」との論で、飯降家の建物を管長名義で保存登記し、私費を投じて差押さえ処分を解除した。
6.3日、ロシア革命
7.5日、松村吉太郎の小川事件公判が始まり、検事が懲役3年を求刑する。8.9日より弁論に入り、8.22日、天野裁判長が無罪を宣告する。検事控訴。
| 【井出くに事件】 |
8月、井出くにが「二代目教祖」を名乗って分立した。井出は罷免される。三十年祭で天理教本部に参拝し、「自分こそ教祖の再来である」と主張する。教祖殿にあがり教祖殿の前で人助けを始めようとするが2名の本部員によって廊下を引きずり出され怪我をする。宿屋・福井屋に泊まる。そこで、中山みきの曾孫にあたる福井勘次郎(まさの孫)が入信し彼の世話をうけるようになる。兵庫県三木町高木村に住む。井出くには「播州の井出くにむほん」として知られ、「二代教祖」、「播州の親様」などと呼ばれるようになる。
「井出くに事件」につき、芹沢光治良著「神の微笑」(P185~186)は次のように記している。
|
今度存命のみきから聞いたのだが、親神が世界人類をおさめるのには、はっきり確定した刻限(時間表)がある。それに従って、中山みきは明治二十年二月十八日に現身をかくして(死して)存命の親様として働かれた。三十年祭(大正五年)には、神が表に現れると予言した通り、存命のみきは兵庫県三木長の主婦、井出国子の魂にたのんで、親神のおもわく通り活動して、世界助けをはじめた。その第一歩として井出国子をつれて天理教本部に伴ない、教祖殿に座らせて、初めて公に生きた働きをはじめた。これは、みきが生前予言してあるのに、天理教本部は「欲と高慢」から、神意をたしかめることなく、存命のみきを井出国子とともに、多くの男の腕力で教祖殿から引きずり出して怪我させるとともに、その説くところは邪道であると、教団に布告した。中山家は、飯降伊蔵の亡き後、その後継者ナライトを受け入れず軽んじた。予言通リ教祖三十年祭に教祖の代理人と称する「井出国子」が現れたが、教団から排除された。井出国子(教祖の三女・おはるの魂とされている)は、「播州の教祖」といわれるようなすばらしい働きをして八十五歳でこの世を去った。
・・・存命のみきは、井出国子が敗戦三年後、八十五歳で逝くまで、親神のはからいどおり、素晴らしい働きをして、しかも、信者をつくらなかった。その後、存命のみきは天理教が百年祭を迎えるまでは、鏡屋敷にもどって、誠のある人の信仰を助けていたが、教団の偏狭な考え方のために、親神のおもわくを生かされないことが多かった。
|
|
|
「モリジロウ」氏の2022年6月29日付け「天理教の大正3・4・5年頃の混乱」を参照する。
大正4年には小川事件(天理教一派独立に関係する贈収賄容疑で松村吉太郎が逮捕・収監された事件、後に無罪)、天理中学校長でもあった広池千九郎博士(歴史学者、教育者、法学博士であり、モラロジー(道徳科学)の提唱者)の辞任もあり、翌5年の教祖三十年祭を控えていた時でもある。教祖三十年祭と言えば“井出クニ謀叛”の時である(「播州のおやさま」)。この時期、教団の中心人物である松村吉太郎は奈良監獄に収監されていた。 |
10.26日、朝夕の「天理王命のつとめ」の中に、明治29年の秘密訓令によって廃止されていた「あしきをはらうて」を神楽つとめに加える。
12.26日、朝夕のつとめの形式が現在のように定まる。
| 【湖東大教会の北海道開拓史考】 |
「北海道開拓倶楽部」の「[鹿追]天理教団体」を参照する。
| 北海道開拓の想像を絶する困難を乗り越えるのに宗教が大きな力を発揮した。キリスト教、仏教教団の開拓は知られるが、天理教団の北海道開拓に果たした役割はあまり知られていない。天理教は北海道の開拓に大きく貢献しており、北海道の開拓もまた天理教団の復興に貢献している。天理教団は発祥地である関西と首都東京を除くと最大の教会を北海道に持っている。「幕末三大新宗教の一つ金光教団の滝上開拓」例に負けず劣らず「天理教の鹿追開拓」があり、これを確認する。
天理教は、奈良県天理市に本拠を置き、市全体がバチカンのような宗教都市になっている。この天理教が、北海道には950の教会があり、大阪、兵庫、東京につづく数となっている。早田一郎(天理大学附属天理図書館天理教文献室)氏は、天理教教会所在地録(立教173年版)の北海道教区に部内教会を持つ大教会の数が多いことを指摘してる。現在、全教の大教会は159カ所のところ、北海道には95もの大教会が記されている。これは全大教会の6割に及び、他の県(教区)でこんなに多い所は見当たらない。明治20(1887)年代から30年代の北海道民は多かれ少なかれ開拓と所縁のある人であった。開拓のため入植した人が布教師になったり、開拓の先住者を頼って布教師が北海道にやってきたり、北海道の伝道の初期は「開拓」と切り離せない。
■教団の危機を救う難関切抜策
昭和42(1967)年3月発行の初代湖東大教会長を記念した「佐治登喜治良」が天理団体入植経過を次のように紹介している。大正の初期、天理教の信者で林紋三郎という者が、ある年たまたま親戚回りを兼ねて本部参りをしたとき十勝平野の肥沃と広大さについて時の大教会長佐治登喜治良に話した。当時、湖東大教会は大きな赤字を抱えて解決に困っていたので、これが動機となり、会長はこの北海道開拓を決意し、所有権を狸得し、その土地売却代金を教会に寄付してもらい難関切抜策として天理教団体移住を図った。
大正4(1915)年5月、早速調査員森井治三郎と大久保紋助の2人が渡道し、十勝のクテクウシ原野を調査後、全国の信者から開拓希望者を幕ったところ150人ほどの申し出があった。現地の役所へ申し込んだところ、71戸の回答が来たので、人選にかかり、上松駒三郎以下、滋賀4戸、山形7戸、新潟14戸、福島2戸、宮城3戸、長野3戸の計33戸、これを「東北団体」と呼ぶ。一方、池戸信吉の岐阜1戸、福岡22戸、熊本2戸、長崎1戸、佐賀7戸、大分4戸の主として築紫郡内の者38戸を「九州団体」と呼ぶ。上松駒三郎と池戸信吉がそれぞれの団体長に指名された。大正5(1916)年3月、「東北団体」が出発した。
大正5(1916)年3月30日、上松駒三郎を団長とする「東北団体」が残雪の十勝クテクウシ原野に第一歩を踏み入れた。これが天理団体入植の第一歩となった。翌日から森井、大久保等先発隊の指揮により1号宿舎の設営を急いだ。同年4月末日、池戸信吉を団長とする九州団体38名が現地に到着した。当時1戸分5町のところ、クテクウシ原野は寒冷地でもあり10町歩と決定、クテクウシの北鹿追と中鹿追東区、および笹川の一部を含む総面識710町歩(710ヘクタール)が開墾予定地として存置されていた。最初の計画は8カ月だったが4カ年を要した。札幌の藻岩宜教所の信者で、道庁の開拓指導員の経験ある佐藤芳吉を招き、原野開拓の指導を受けた。二つの団体は東北人と九州人との異った地方の寄り集りだったので診談、奇談の続出であったが、同じ信仰の同志でありたちまちに親しみを深めた。やがて3号宿舎も完成、事務所は3号宿舎に侭いた。東北団体と、九州団体とは互いに負けまいと競って開拓に精を出した。大変な苦労を強いられたが天理教の強い信仰心で乗り切った。天理教団体は、開墾を成功させ、その土地の売却代金を、天理教湖東大教会に寄附して大目的を果した。成功後、ある者はその土地の小作人となって営農を続け、ある者は帰郷するなどさまざまであった。
■藤田商店の温情
開拓期の北海道の商人と言えば悪徳なイメージが強いが、清水町の藤田商店の温情によって運営費に窮した天理団体が救われたというエピソードが『佐治登喜治良』に語られている。それによると、藤田は、貸付金の返済が滞納されているにも拘わらず翌年も食料、肥料を貸してくれた。「藤田の主人は侠気のある男だった」。後に大正14(1925)年、その地に鹿追宣教所が設けられたとき藤田は大時計を一個寄贈した。今も「献納、藤田商店」と書いた時計が鹿追の会長室に架かっている。十勝清水の藤田商店は今も栄えている。
■北海道の伝道の初期は「開拓」と切り離せない
さまざまな困難が伴ったが、天理団体は貸与地の開墾に成功した。時は第1次世界大戦による空前の穀物景気の最中、教会はこの土地をすぐに売り、教会の再建を果たした。天理教本部は成墾地を教会へ献納する手続きを急ぎ、一括して北海道製糖株式会社へ譲渡することに決した。土地売却代金5町歩平均2350円で700ヘクタール売却した。その収入は大きかった。この金で湖東大教会は大正9(1920)年8月26日の負債を支払い、未納金を完納している。ちなみに翌年の3月15日に株価は大暴落、北海道の地価は二束三文になった。間一髪で売り抜けたことになる。
|
|
| (当時の国内社会事情) |
|
3.7日、第一次世界大戦。
|
| (宗教界の動き) |
| 倉田百三「出家とその弟子」。 西南学院大( バプティスト)。 |
|
2.9日、出口王仁三郎が、直霊軍の別動隊『白虎隊』を組織。4月、大和畝傍山に参拝。6.25日、兵庫高砂沖の「神島」開き。この直後開祖出口直の筆先に「王仁三郎の霊が天のみろく様である」と出る。
|
3.5日、松村吉太郎の小川事件二審公判が始まり、再び無罪。小川が大審院へ上告し、4.26日、上告棄却される。これにより、松村吉太郎が本部役員など公職に復帰する。
10.28日、独立10周年記念祭。
| (道人の教勢、動勢) |
| 8.21日、山田伊八郎が出直し(亨年69歳)。嘉永1年(1848)3月14日、大和国十市郡倉橋村出屋鋪(現・奈良県桜井市倉橋出屋敷)生まれ。明治14年(1881)、山中忠七の娘こいそ(いゑに改名)との結婚により信仰が始まる。教祖より赤衣 本席よりおさづけ(明治20年9月)。城島分教会(現・敷島大教会)理事・2代会長 別席取次人。(『稿本天理教教祖伝逸話篇』101「道寄りせずに」 84「南半国」) |
| 11.11日、喜多治郎吉が出直し(亨年66歳)。嘉永5年(1852)7月8日、大和国添下郡伊豆七条村(現・奈良県大和郡山市伊豆七条町)生まれ。明治1年(1868)12月、眼病を患い入信。明治10年(1877)、矢追家より喜多よしの婿養子となる。誠心講(後の治道大教会)講元・島ヶ原分教会(現大教会)4代会長。 |
| (宗教界の動き) |
| 熱田神宮・出雲大社・橿原神宮を勅祭社とする。有島武郎『カインの末裔』。 聖書文語完訳。日本使徒教団設立。 |
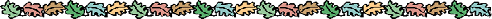



 (私論.私見)
(私論.私見)
広池博士は自らの至らなかった点を反省もし、後々、モラロジー(道徳科学)を提唱され、教団を離れた。、大正10年には松村吉太郎の倍化運動が行われ、一気に分教会数が増えた。また、この頃からハッピを着ることが広がったようである。「迎合派」の完全勝利であり、勢いに任せて今の体制に続く組織の骨組みが固まった時期でもあるように感じる。4年後には大正期が終わり、昭和元年に教祖四十年祭、二代真柱の東京帝国大学入学となり、現在の天理教に続いていくことになる。 広池博士の辞任に関しては桜井良樹氏の論文が詳しい。「『大正四年の二つの資料』」。
「異説や異端の毒やほこりを不幸にしてのみこんでしまった者の戯言」が、「本部に異を唱えるものは全て排除で、「異説・異端」には一切、受け入れない体制が整った時期であるともいえる」。


![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)