| 1908年~ |
明治41年~ |
天理教一派独立を認可される、その後の
歩み |

更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.6.21日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「天理教一派独立を認可される、その後の歩み」を確認しておく。
2007.11.30日 れんだいこ拝 |
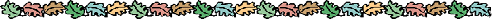
(以降未整理、今暫く借用分あり)
1.16日、天理中学校設立認可。
2.4日、天理教校(本科・別科)設立認可。(天理教校別科、9月26日入学式、入学者41人、校長: 初代真柱、科目は教義・神祇史・倫理・礼典・修辞作文・宗教法令・宣教実習、6ヶ月生、以後2月と9月入学、満20歳以上)
3.20日、第5回一派独立請願書提出。7.1日、真柱と松村吉太郎が度々上京し奔走したが、7.4日、西園寺内閣総辞職の為頓挫した。最後の力を振り絞って折衝し、好転する。
8月、出口なおと王仁三郎が金明霊学会を「大日本修斎会」と改称する。一時御嶽教と関係したが、12月 綾部に帰り、教団組織化に着手する。
| 【天理教一派独立を認可される】 |
天理教独立請願史は次の通り。
|
|
内務大臣 |
|
| 第1回 |
明治32年8月 |
西郷従道侯爵 |
|
| 第2回 |
明治34年6月 |
内海忠勝男爵 |
|
| 第3回 |
明治37年8月 |
芳川顯正子爵 |
|
| 第4回 |
明治37年12月 |
芳川顯正子爵 |
|
| 第5回 |
明治41年3月 |
|
|
|
11.27日、1899 (明治32)年からの独立請願運動による5回目の独立請願書を提出したところ、天理教が神道本局の傘下から離れ、教派神道13派のーっとして一派独立を認可される。並行して一派独立のための
教内の環境づくりが進む。内務省秘乙第54号、内務大臣法学博士男爵・平田東助名で「書面願之趣許可す」(内務大臣・平田東助)(「天理教一派独立戊申詔書宣布」)。これにより、天理教は天皇制政府公認の神道教団となった。天理教管長は、勅任官の待遇を受け、閣下と敬称されることになり、本部に天理教庁が設置され、各級教会は大教会、分教会、支教会、宣教所の4段階に改変されることになった。
5回目の独立請願に対して、神道本局は漸く独立を許可したことになるが、「天理教教典」第一章敬神章には、「天地地祇の神を代表する、天照大神を含む天皇の先祖十柱の神を総称して『天理大神』という」と記されたように、天理教は、教派神道の一派として国家神道下で公認宗教の座に連なることができたことになる。「神道直轄天理教会本部」は「天理教教会本部」と改められた。
大正5年における『北海道ニ於ケル宗教』が、「天理教」の項で、教典と祭神について次のように伝えている。
| 教典ハ、敬神・尊皇・愛国・明倫・修徳・祓除・立教・神恩・神楽・安心ノ十章ヨリ成ル。祭神ハ、国常立尊・国狭槌尊・豊斟淳尊・大苫辺尊・面足尊・惟根尊・伊弉諾尊・伊弉冊尊・大日霊尊・月夜見尊ノ十神ナリ。信徒ハ日ノ寄進ヲ以テ罪障消滅・福徳増進ノ功力トス。 |
|
| 【真柱の真之亮が天理教管長に就任】 |
| 11.28日、真柱の真之亮が天理教管長に就任。初代真柱が管長の公務開始。教会本部に天理教庁開設。 |
この頃、初代真柱が次のように述懐している。
| 「わしの父は、生前苦労ばかりの道を通り果てた。わしとしては、いかにもして死んだ父に満足してもらいたいと、一日も忘れた日はなかったが、これで幾分の満足をして頂けるであろう」(「稿本中山真之亮伝」、復元第38号374頁)。 |
|
11.30日、教会の名称を、大教会(信徒10,000戸以上)、教会(信徒5,000戸以上)、分教会(信徒2,000戸以上)、支教会(信徒500戸以上)、宣教所(信徒100戸以上
)に組織分けする。
12.1日、天理教教規及び規定を制定し発布する。
| 【教会本部役員、教庁幹事及び録事を任命】 |
| 12.14日、教会本部役員、教庁幹事及び録事を任命する。本部員は次の通り。桝井伊三郎、梅谷四郎兵衛、高井猶吉、諸井国三郎、板倉槌三郎、宮森与三郎、喜多治郎吉、山中彦七、上原佐助、山沢為造、上田民蔵、飯降政甚、島村菊太郎、増井りん、深谷源次郎、松田音次郎、松村吉太郎、増野正兵衛、土佐卯之助。 |
| (道人の教勢、動勢) |
| 1908(明治41).9月、松村吉太郎を韓国布教管理者に任命し、釜山に開設されていた釜山宣教所内に韓国布教管理所を設置した。その後、日韓併合に伴って、韓国布教管理所を釜山からソウルに移転して朝鮮布教管理所と改称した。 |
| (当時の国内社会事情) |
| 7.1日、郡制が施行される。 |
| (宗教界の動き) |
| 天理教神道本局より独立。独フランシスコ会。イエズス会。聖心会。 |
1908(明治41)年、井出国子に親神が降臨する。次のように証言されている。
| 「身体が振動し自分で止めることができなかった。目が見えない日、口をきくことが出来ない日、目も見えず、口をきけない日が暫く続いた。目が見えない時は、一日中座ったままで、口のきけない時に倍働いたので、不自由は感じなかった。やがて、"人間世界を助けてやってくれ、世界がおさまるようにしてくれ"という声がどこからともなく聞こえ、何もしないでいると、手がくっつき人の手を借りないと日常生活に困るようになり、ひと助けを決心した。それからは、絶えず全身が振動し、無意識に言葉が出るようになった」。 |
|
2.19日、天理教独立報告祭。
| 【天理教独立公認取消し請願書が提出される】 |
| 3.23日、第25帝国議会に、天理教の独立公認取消し請願書が提出され、請願委員会を満場一致で通過した。 |
7.26日、小川の代理人として橋本勲名義で、真柱宛に独立報酬金請求の催促状が届けられた。8.15日、松村が橋本と面会し、金の無心を交渉する。これが、後々に事件の複線となる。
11.24日、【本部】教祖20年祭の大仮祭場、風のため倒壊(神殿ふしん 始動へ)。
| (道人の教勢、動勢) |
| この年、天理教校別科が開設された。実行科と信念科が創設され、天理教教師の養成を精力的に行うことになった。後に、実行科が「ひのきしん科」となり、ひのきしん活動が重視され強力に推進された。 |
| (当時の国内社会事情) |
| 1909年、新聞紙法(新聞紙条例1875廃止、皇室の尊厳の冒涜、政体変壊、国憲紊乱、安寧秩序妨害、風俗壊乱)公布される。生徒の道義的観念練成・徳育(文訓令)。
|
| (田中正造履歴) |
| 1909(明治42)年、69歳の時、渡良瀬川改修工事計画が出される。「被害破道に関する質問書」を書き、友人島田三郎議員らの名前で衆議院に出す。 |
| (宗教界の動き) |
| 鈴木大拙アメリカから帰国。北原白秋『邪宗門』キリシタン評価。山岡光太郎メッカ巡礼。 |
| 1909(明治42)年、井出国子に、1日に100人にもなることがあるほど助けを求める人が参拝し始め、人を迎えるために建物を建てた。暫くして、三木の警察から催眠術を使っていると疑われ、10日間拘留された。釈放されると助けを求める人が押し寄せ、また、出頭命令が届き、拘留と釈放が繰り返されることが1年1ケ月続いた。お助けを求めるものの中には、無法者がいて、そのものが裁判所に送られたことをきっかけにして、井出は住み続けることができなくなった。 |
| 1910(明治43)年 |
天理教婦人会創立/船場教会、ロンドン布教へ
|
1.9日、【本部】天理教(天理)陽徳院設立の旨通達。
1.26日、春季大祭より祭典日を陽暦に変更。
| 【婦人会結成される】 |
1.28日、先の明治31.3.25日、増野いと様の御身上願いの時のお指図で婦人会結成が指針されてより12年後のこの日、中山たまへ(初代真柱夫人)を初代会長とし、この芯の下で婦人会が創立された。これが婦人会の「元一日」となった。
天理教婦人会につき、次のように解説されている。
| 「天理教婦人会は、教祖のひながたを辿り、会員相互の心の成人を目的とするところから、常に心の成人の機会をつくり、また教内の事業に一手一つの合力で尽くす中に婦人の成人の道を見出したいとの願いから、当時の社会事業の課題として設立をみた天理養徳院の事業に力を注ぐことになった。初代会長が養徳院々長という立場の上からも、以来、婦人会と養徳院の関係は、近年に至るまで密接なものがあった」。(「天理教婦人会の創立」参照) |
|
10.23日、【本部】初の『天理教教会名称録』発行。
11.1日、【本部】海外布教規定発布(内務大臣の許可を得たもの。海外布教者の資格は「教師職級十級以上ノ者」、「年齢満二十五歳以上ノ者」、「身体健全品行端正ナル者」。
| (道人の教勢、動勢) |
| 7.1日、桝井伊三郎(嘉蔵‐伊右衛門から改名)が出直し(去年61歳)。嘉永3年(1850)2月12日、大和国添下郡伊豆七条村(現・奈良県大和郡山市伊豆七条町)生まれ。文久3年(1863)、母キクが夫の喘息の病をきっかけに帰参、伊三郎を連れて帰るようになる。翌元治1年、キクの危篤を三度のお屋敷詣でで助けて頂き熱心になる。妻は(西尾)ナラギクで結婚時、仲人の教祖より「おさめ」という名を付けて頂き改名。かんろだいてをどりのさづけ。(『稿本天理教教祖伝逸話篇』10「えらい遠廻わりをして」 16「子供が親のために」) |
| この年、北浦源次郎(27歳)がおさづけの理拝戴、翌年から布教開始。北浦氏の履歴は次の通り。1884(明治17)年、6.26日出生。1976(昭和54)年、10.27日、出直し(享年96歳)。大正4年
(1915)、天理教校別科第14期に入学。教校にはおやさま直弟子の教員が揃い、その上、在学中の半年間、高安大教会役員・芦田松次郎氏から毎夜、特別講習をうけ、頭脳明晰の氏はその教話をすっきり暗記した。芦田役員自身も熱心に研究をつづけ、高井猶吉・宮森与之助らの許に通って仕込みをうけた。北浦氏は別科修了後、すぐに布教開始、高南宣教所設立、以来60余年間、終生布教に没頭し、元の理のお話を信者たちに熱情をこめて説き続け、不思議なお助けが続出した。
|
| (当時の国内社会事情) |
| 1910年、[警視庁内部に特別高等課設置]される。韓国併合。第二期国定教科書( 儒教的家族倫理・家族国家観)。倫理を修身に改める( 大学予科)。
|
| 同年、大逆事件。 |
| (田中正造履歴) |
| 1910(明治43)年、70歳の時、関東大洪水。政府の治水政策を正すため関東各地の河川を実地に調べる。 |
| (宗教界の動き) |
| 神社合祀反対( 南方・柳田) に政府合祀強制せずと言明。靖国神社遊就館 (勅令192)。 |
| 1910(明治43)年、7.13日、井出国子が城崎温泉にいるところ裁判所から出頭命令が届き、帰宅した翌14日、予審裁判にかかった。予審判事からは、「人助けをすることは何の罪にもならないので意の向くままにして良い」と言われた。 |
1911(明治44)年しかしながらこれで救出の安定がはかられた訳ではなく,翌1911 (明治44) 年 には天理H教独立公認取り消しし案が議会へ~Æ:U~I
されるなど,以後も信者に対して明治政府への随JI演を強 調せざるを得なかった。政府からの公認を得るために, 教典の一つであった泥海古記を回収・廃棄し教義を変え天皇制に追随した明治教典を作成し,教育勅語の普及に努力するなど,天理教は自らの信仰を守るために,はからずもみきの教えを妨げげた形で妥協していかねばならなかった。
|
1.27日、【本部】天理教婦人会第1回総会。
|
| この頃、ナライトが胃腸の病となり、ナライト宅にお運び場所を普請され、竣工後は、そこでおさづけを渡される。 |
9.10日、【本部】鑵子山に天理教校校舎を新築 建坪は本館、教室2棟など293坪。講堂は旧神殿(明治21年につとめ場所に増築したもの)を移築。9月14日、
教校別科第7期から使用。
10.27日、【本部】神殿建築起工式 「五箇年の普請」の始まり。仮本殿(神殿、礼拝場=きり なしふしんのためか、一時「仮」という言い方がされた)、 教祖殿のほか祖霊殿、教庁、真柱宅も同時建築。
| 【茨木基敬神懸り、造反】 |
この年秋頃、天理教教会最大手の北大教会を率いる初代会長の茨木基敬が造反した。本席の死から4年目のこの頃、身体に原因不明の異常が生じ、天理教会本部近くの北大教会詰所内の自邸で病床に伏すようになった。この頃、北は、教祖30年祭に伴う本部の「大正普請」の呼びかけに対し、「信者に必要以上に金銭的な負担を掛けるのはいかがなものか。無理に寄付金を集めれば、その金に信者の惜しいという埃がついているので神も喜ばない」と、本部員で唯独り強行に反対していた。
この年の11.18日真夜中、病床にあった茨木基敬が神がかりする。当時、初代本席の飯降のお指図により二代目本席として上田ナライトがいたが、新たな天啓者の登場が教内を揺るがすことになった。但し、上田ナライトは精神変調を伴う病気を理由に本席の務めを失効させていた。
茨木基敬は娘の病気がきっかけで天理教に入信した。1891年、北分教会初代会長となる。以前から予言を的中させるなど噂されていた。1911年、突然神がかりし病に伏せる。やがて天啓を伝えるとして信者の間で評判となり、教会本部から問題とされる。1918年、基敬が免職される。免職となった親子は奈良市富雄に移り、一時期、天理教茨木本部と称していた。
自らを飯降伊蔵に続く天理の天啓者と捉え続ける。現在、真道会と称して信者が各地に点在するが教団としての活動は行なっていない。参考文献として、弓山達也「天啓のゆくえ―宗教が分派するとき」。 |
豊嶋泰國「天理の霊能者」P109が次のように記している。
| すでに天理教の本部員(本部役員)に登用されていた茨木基敬に天啓とされる現象が起こったのは、本席の死から四年目の明治四十四年の晩秋からであった。その頃より身体に原因不明の異常が生じて、天理教本部近くの北大教会詰所内の自邸で病床に臥すようになった。腸出血から始まった病勢は進み、強度の神経痛をともなって日夜苦しみ悶えていたのである。当時、天理教教会本部では教祖三十年祭にともなう「大正普請」と呼ばれる本部神殿の建築計画を進めていたが、茨木基敬は「信者に必要以上に金銭的な負担をかけてはならない。また無理に寄付金を集めれば、その金には信者の惜しいという埃がついているので神も喜ばない」などと、本部員としてただ一人強硬に反対していた。そのため、本部からは白眼視されていた。 |
|
| 当時の本部を代表する調べ役の本部員が派遣され、胸調べすることとなった。やって来たのは、増野正兵衛(道友社初代社長)、喜多治郎吉(島ケ原大教会4代会長)、諸井国三郎(山名大教会初代会長)、梅谷四郎兵衛(船場大教会初代会長)であった。胸調べの結果、茨木基敬の天啓ぶりが示されたが、結果的に本部は「芽が出る前に潰す」方針を決定した。茨木基敬は気が違ったとの理由で免職処分に付された。大正7年に正式に処分される。 |
| (道人の教勢、動勢) |
| 1911(明治44)年、石西計治(いそにしけいじ)が出直し(享年66歳)。1846(弘化3)年、生まれ。 |
| (当時の国内社会事情) |
| 天皇南朝正統論決断・吉野朝・北朝5天皇削除→教科書→1945( 皇国史観)。 |
|
| (宗教界の動き) |
| 黒住教・天理教満州で布教開始。日本ハリスト教会260。ものみの塔聖書冊子教会設立。 |
| 1911(明治44)年、井出国子が中山みき死後二十五年祭の時、天理教本部に自分の写真と切手を送って無視される。 |
3.5日、諭達第5号。中山新治郎真柱が、三教会同を受け、国民道徳と社会風教の改善をはかる。
| 【おぢばでかんろだい建設の地盛り行われる】 |
| 6.1日、おぢばで、かんろだい建設地の地盛り、地搗(っ)きひのきしんが行われた。敷島大教会の山田伊八郎は、この日は真柱邸の当直に当たっていたが、その勤務を梶本様母堂にお願いして、長男倉之助と共に終日(午後5時頃まで)参加した。6.12日、盛り土の上を更に六尺余(約2m)コンクリートで固め、その上部中心に六寸角(約18cm)高さ1尺2寸余(約36cm)の石材を据えた。 |
10.7日夜、仮神殿で立柱奉告祭。丸柱は10本で直径 2尺3寸、角柱は40本で1尺5〜8寸。木曽、北山、高野、 津山、伊賀、土佐、伊予、筑前から檜材が陸路・海路を
へて続々親里へ。10.8日、【本部】神殿立柱式。
| 【おぢばでかんろだい建設の地盛り行われる】 |
| 11.28日、【本部】神殿上棟式。上棟式奉告祭のあと屋上で工事員の祭典。 「同祭典は先づ工事長の祝文に始まり、式礼、槌打、歌司、 弓取……と云う順序にて終りを告げたる……かくして婦 人会役員、各教会役員等を屋上に案内したるが、七十尺 以上の高台とて、皆な肝を寒ふして観覧したり」(道の友) 。明治天皇崩御のため質素に行おうと一般信者には知らされなかったが、いつのまにか知れわたるところとなって多数が参集、にぎやかに執り行われた(天理教の百三十 年)。 |
| (道人の教勢、動勢) |
| 3.11日、上原佐助(幼名・政太郎、のち儀七)が出直し(亨年63歳)。嘉永3年(1850)4月4日、備中国小田郡笠岡村(現・岡山県笠岡市)生まれ。家業を捨て伯父上原佐吉を頼り大阪へ行き、生家笠原家より上原家の養子となり佐助を名乗る。明治7年、川合とよ(のちにさとと改名‐笠岡大教会設立・初代会長)と結婚。明治13年(1880、)にをいをかけられ、翌年初参拝。明治18年、店をたたみ、家族と別れ(さとらは笠岡へ)東京布教に出る。教祖より赤衣(明治16年)、本席より「清水のさづけ」(明治24年)。東分教会(現大教会)初代会長。(『稿本天理教教祖伝逸話篇』127「東京々々、長崎」) |
| (当時の国内社会事情) |
| 7.30日、明治天皇崩御(享年59歳)、乃木殉死。皇太子嘉仁が皇位を継承し、大正と改元。美濃部天皇機関説。 |
| (宗教界の動き) |
| 原敬が神道、仏教、キリスト教代表者と懇談。仏教大学(浄土宗)。三教会同開催。「三教会同と天理教」を発行(ほぼ現在の「天理教教理」ができる)。神社数19万余→11万余に整理。上智大学(
イエズス会)。新教8派日本基督教同盟結成。日本カトリック新潟 i教区設置。日本聖公会中部教区設置。 |
| (当時の対外事情) |
| 1912(明治45)年、韓国併合。 |
2.24日、広池千九郎が天理中学校長となる。(~4.4月、退職)
| 【大西愛治郎が造反】 |
| 7.15日、後に「ほんみち」を開教する大西愛治郎(33歳)が、「甘露台の踏み定め」をする。これが「ほんみち」発祥の日となる。大西は以来、「生き神、甘露台」を名乗るようになり、教内に軋轢を生んでいくことになる。「ほんみち」は、「甘露台人の理」と位置づけている。 |
8.15日、【本部】教祖殿上棟式。
12.16日、大西愛治郎が、和歌形式の教歌「甘露台古記」を天理教管長と直轄教会長全員に郵送する。以降、次々と送付し始め百余回に及ぶことになる。
12.25日、本部神殿の北礼拝殿が落成する(建坪926.87㎡、高さ23.6m㍍)。
| (道人の教勢、動勢) |
| 前川菊太郎。慶応2年(1866)生まれ。教祖の兄・杏助の孫。1913(大正2)年、出直し(享年48歳)。 |
| (当時の国内社会事情) |
| 1913年、無線電信法(一九二六年ラジオ放送開始)公布される。京大事件。
|
| (田中正造履歴) |
| 1913(大正2)年、73歳の時、8.2日、河川調査から谷中村への帰途、病に倒れ、9.4日、死去。遺骨は5か所に分骨し埋葬される。 |
| (宗教界の動き) |
| 内務省宗教局は文部省へ移管。(宗教局が内務省から文部省に移され、神社局とも完全に分離された) |
| 憲法学者で東京帝国大学教授の上杉慎吉の「皇道概説」が出され、昭和初期には陸軍の正統憲法学説となっていった。 |
| 官国弊社以下神社祭神・神社名等細目(内省6)。神社奉祀調査会官制(勅令)。官国幣社以下神社神職奉務規則が制定される。 |
| ほんみち開教(天理教系)。 |
| 世界仏教大会。 |
| 多田等観チベット入国ラマ僧となる→24帰国『西藏撰述仏典目録』『西藏大藏経総目録』。 |
| 1914(大正3)年 |
| 大正3年、第一次世界大戦の勃発。 |
4.1日、諭達第6号。
| 【北礼拝場と祖霊殿(当時は教祖殿)新築落成】 【本部】教祖殿新築落成、 |
4月、北礼拝場と祖霊殿(当時は教祖殿)新築落成。皇太后崩御につき本部神殿落成は謹慎して執行する。
小さな家から始まった祈りの場はどんどんと増築される形で規模を拡大した。これは大正普請と呼ばれる。膨大な費用をともなった。天理教施設の竣工昭和初期に教祖殿、南礼拝場と東西の回廊が竣工。昭和後期に西礼拝場と東礼拝場が完成し、おおよそ現在の姿になった。4つの礼拝場がつくる大空間の広さは3157畳。ちなみに浄土真宗東本願寺御影堂は927畳。東回廊は船大工、西回廊は宮大工が棟梁。梁を支える部材に、前者は釘を使っているので釘隠しがあるが、後者は見当たらない。宮大工らしく継ぎ手で接合している。大正ふしん完了(建坪123.57㎡)。 |
4.24日、昭憲皇太后が崩御。同日、諒闇中のため略遷座式執行。
8.25日、諭達第7号発布。日独開戦につき挙国一致で尽力するべく心構えを述べる。
| 本教徒にして出征の命に接したる者は、借物の教理を自覚して、身命を惜しまず以て一切の軍事行動に従うべく云々。 |
| 【初代真柱・中山真治郎が出直し】
|
| 12.31日(大晦日)、中山正善が数え11歳のとき、初代真柱(中山眞之亮、真治郎)が出直し(享年49歳)。背中に出来たできものが原因であった。前年末に待望の本部神殿(現在の北礼拝場)が落成し、大正5年には教祖5年祭を執行すると云う喜びの旬の最中での真柱の出直しは、天理教内に大きな衝撃を与えた。北大教会の茨木基敬が「この年の暮れは越せん」と予言しており、その通りに出直したと伝えれれている。 |
| この年、初代真柱の控え柱の前川菊太郎が出直している。 |
|
正善がただちに管長(二代真柱)に就任した。但し、まだ10歳の子供であるから、山澤為造が管長摂行者に就任し天理教を指導した。初代真柱の奥方御母堂(たまえ)は39歳である。教団上層部は何でもかんでも、とにかく二代さんを立派に育て上げ、体制を整えたいと頑張っていた時代ともいえる。 |
| 【岩井尊人の関わり】 |
この年、岩井尊人(大正期に増野道興、小野靖彦、広池千九郎らと共に活躍した論客の一人)が、東京帝国大学在学中、「道の友」に連載開始。その論考は1938(昭和13)年まで103篇にわたっている。1915(大正4)年、「天理教祖の哲学-みかぐらうた新研究」を刊行している。「惟ふに言語の極致は詩歌である。(中略)教祖が数へ歌に形を採られたのは之の内発的の必然性によっていると思ふ」。1928(昭和3)年、「泥海古記 附注釈」を刊行している。神道の在来神と同名の神名との相違を明確にし、天理教教義の独自性を強調しつつ、泥海古記の象徴的理解の重要性を説いている。1932(昭和7)年、「英訳天理教概要」(the
outline of tenrikyo)を刊行している。1933(昭和8)年9.10日号の天理時報によると、、岩井の英訳「みかぐらうた」が明本京静によって吹き込まれてレコ-ドとなり、世界宗教大会出席のため渡米していた中山正善2代真柱の手元に送付され、開催地のシカゴでは、岩井の「英訳天理教概要」と英訳「みかぐらうた」レコ-ドが紹介され、天理教教義の顕揚に大きく貢献した。
岩井は、幼少期から中山家に出入りしており、中山正善の大阪高等学校進学も岩井の進言から実現したという。大学卒業後は三井物産に勤め、1926(大正15)年までロンドンに赴任した。1936(昭和11)年には、2.26事件の後に組閣された広田内閣の文部大臣/平生*三郎の秘書官を務めた。その頃、急速に台頭した陸軍が政治介入を強め、その圧力を受ける文部省と天理教本部との間で思想統制を廻って緊迫した交渉が続いた。2代真柱は、対応を協議する過程で岩井に助言を求めている。岩井は、諭達第8号草案に加筆訂正するなど深く関わっている。
金子圭助氏は次のように評している。
| 尊人の本業は何んと言っても実業家であったであろうが、『道の友』に繁く寄稿し、そのことによって天理教教義を深く理解した。深く理解しただけに終らせず教義を真正面から論述し、その時その時の趨勢を鋭くキャッチし、信者の陥りがちな陥穽に警鐘を鳴らしたり、啓発したりしつつ、氏の立場から本教の方向をリ-ドした。尊人ほど世界的視野を持ち幅の広い、かつ透徹した知識による分析は誰にも真似のできることではない。 |
|
| (道人の教勢、動勢) |
| 11.12日、増野正兵衛が出直し(亨年66歳)。嘉永2年(1849)3月1日、長州萩(現・山口県萩市)生まれ。明治17年(1884)、妻いとが明治14年にソコヒを患い、失明寸前となった時、幼なじみからにをいをかけられたのがきっかけで入信。その年初参拝。本席よりおさづけ(明治20年5月4日)。この年
本部青年会で図書館設立への胎動。 |
| (宗教界の動き) |
| 明治41年、天理教独立。 |
| 神宮祭祀令(勅令9)・神社祭式全国神社祭式を宮中儀礼の場として統制(勅令3)。官国幣社以下神社祭祀令、同祭式が公布された。すでに、教育勅語戊辰詔書の拝読も定着しつつあり、国家神道はこのころ確立したということができる。 |
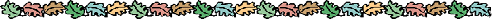



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)