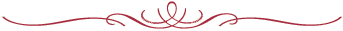
| 増野鼓雪考 |
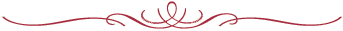
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.12.27日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「増野鼓雪考」をしておく。 2007.11.30日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【増野鼓雪の履歴】 |
| 増野鼓雪の鼓雪は雅号で、本名を道與と云う。明治23.2.13日、父を正兵衛、母をいととして出生した。その出生に先立って、本席が、正兵衛氏に「不思議な子を授けてやると神様がおっしゃっています」と云われたと伝えられている。 増野家は代々長州の旧萩藩の藩士。父の正兵衛は、1884(明治17)年、妻いとがソコヒを患い、失明寸前となった時、幼なじみからにをいをかけられたのがきっかけで入信。その年初参拝。1887(明治20).5.4日、本席よりお授けを受ける。1889(明治22).12.31日、お屋敷に移り住む。仮住居として、安達源四郎(照之丞)方の離れ座敷を借り、道與はここで生まれた。 6歳頃、管長邸に起居し、天理教校、東京改正中学、天理教校、明治大学文科へと進んだ。 明治42.9月、本部に勤め、10.9日、20歳の時、松村吉太郎本部員の息女つると結婚(大正2年、つるが出直す)。松村吉太郎は義父に当たることになる。 大正5.1.24日、27歳の時、道友社編集主任を命じられ、同時に本部准役員に登用された。 大正6.5月、松村吉太郎の息女(つるの妹)八重子と再婚。 なぜなら、増野鼓雪は松村吉太郎の娘つると結婚し、つるが出直し後、の八重子と再婚している。 大正7.11.26日、29歳の時、本部役員に登用される。大正7年1月に茨木基敬父子が免職された後の同年秋に本部員に29歳の若さで登用されている。 大正9年、天理教校長に任ぜられる。 大正10.3.23日、敷島大教会会長に任ぜられる。 大正14年、道友社社長に任ぜられる。 昭和3年、出直す(享年39歳)。 文筆と講演録が「増野鼓雪全集」(全23巻)に収められている。 |
| 【増野鼓雪思想】 | ||
| この頃、増野鼓雪が、本部の動きとは別に独自の見識を深め、次々と所説を発表している。西山輝夫著「増野鼓雪の信仰と思想」より転載しておく。 | ||
|
「沈思雑言」と題して次のように述べている。
|
||
「教義の尊重」と題して次のように述べている。
|
||
|
「理性の効用と弊昏」と題して次のように述べている。
|
||
「世の立て替えの動因」と題して次のように述べている。
|
||
|
「おたすけ活動が根本」と題して、次のように述べている。
|
||
「おたすけがあがらなくなったということに対しての発言」。
|
||
「里の俗人」と題して、次のように述べている。
|
||
「無理を聞く」と題して、次のように述べている。
|
「空さんのホームページ」の「「北の理」シリーズ、 昭和二年一月五日のお詞」の中の増野鼓雪関連を転載しておく。
|
| 「天理青年必読「疾風怒濤の時代(1)」 木村牧生(西村輝夫)著」 、「天理青年必読「疾風怒濤の時代(2)」 木村牧生(西村輝夫)著」、「天理青年必読「疾風怒濤の時代(3)」 木村牧生(西村輝夫)著」、「天理青年必読「疾風怒濤の時代(終)」 木村牧生(西村輝夫)著」参照。 | |
|
|
増野道興(当時26歳)氏の大正五年八月号のみちのとも寄稿文。
|
|
大正七年、本部員/増野道興の意見。
|
|
|
「ひのきしん」という課目が正科として取り入れられたのは、増野氏が初めて校長になって指導した第二十四期からである。これに対して多少面白くないと感じた者もいたらしい。あるとき氏はこう言った。 「お前たち、ひのきしんしたくなかったらしなくてもかまわぬが、その後お前たちがどうなるか考えてみろ」。「お前たちは、土持ちしたらひのきしんで、それでいんねんが切れると思っているが、そんなら土方は毎日いんねんが切れていることになるな」。こんな調子で、生徒の常識、固定観念をかき回し、混乱に落し入れ、そこで各自に考えさせた。また考えさせる力を持っていた。教理を決して説明しなかったし結論を言わなかった。そこで生徒はいつも黙って考え込んで、休憩時間になってもたばこを吸うのを忘れる者が少なくなかった。しかしこんなことは、要するに方法にすぎない。ただともかく氏は、常識や人間思案に覆われた人間の心の茂みの中を分け入り、土足でズカズカとその中に芦を踏み入れようとしていたのである。道は真剣勝負であり、体裁も何も要らないというのがその信念であった。人間思案を破壊すれば、そこに真実に触れてくるものがある。では真実に触れたとき、人間はどうなるか。「そのとき人間は、怒るか、泣くか、笑うか、三つのうち一つだ。これ以外は皆うそだ」。実際増野氏は、人を怒らせ泣かすことの多かった人であったかもしれない。しかしそれでも恐れずに、頭ではなく心に向かって常に勝負を挑んだ。氏に向かってある人がこう言った。「先生のように、やることなすことすべて当たるのなら、相場師になったら良かったですな」。そのとき氏は胸を張ってうそぶいた。「なあに、俺は人間を相手に相場を張っているのだ」と。 しかし、こんなところに氏の教育の秘密があったわけではない。信仰の世界にそんな秘密などない。もしあるとすれば、別科第二十四期生を送り出した際、次のように述べたところにあるのかもしれない。「……心霊の開発ということのみを目的としては、大きな燃えるような信仰が生まれてこないことを実地の上から知ることができた。それで今度は、できるならば今一歩進めて、一切を神様にお任せ申して、神様によって教育していただこうと思うのである。これは、ちょっと考えると甚だ無責任のようであるが、自己というものの意義を真実に自覚した方々は、私の申すことは十分理解していただけると思う……」。この「一切を神様にお任せ申す」という信仰の中に、実は氏の面目があったと見るべきである。しかしこれには、多少の解説がいるかもしれない。例を挙げていうと、こういうことがあった。第二十五期生に対して、氏はあるときこう言った。「二十四期では、在学中に三分の一くらいが身上を頂いた。今度は二十五期だが、お前たちはこれでいくと半分は身上になるだろうな」。そして、あっけに取られている生徒に、なおもこう続けた。「しかし、お前たちは別にびくびくしなくてもいいし、勝手なことをしてもよい。俺は監督なんかしない。ほったらかす。神様が監督してくださるだけだ。しかし、もし俺が本当に誠真実になれば、お前たちは片っ端から、皆バタバタと倒れてしまうな」。氏は信じていたのである。人間が真にさんげに徹し、真実の心定めをすれば、その心に必ず喜びが湧く。喜びが湧くということは、神様にその心を受け取ってもらった証拠である。神様に受け取ってもらえると次に何が起こるかというと、必ず困難が起きてくるのである。それが、神様の近づいてこられるしるしだと。困難というのは、人間にとって身上事情を意味する。すでに「一切を神様にお任せ申した」以上は、氏は生徒に何も要求しなかった。ただ責任者である自分が、真実を供えるだけであった。それは、生徒に代わってするものであったに違いない。すると神様は必ず生徒に身上のしるしを付けて仕込んでくださる。単なる人間から、神のようぼくとして生まれ替わるよう急き込んでくださる。だから自分としては、そのように神様が働いてくださるよう、真実さえ尽くしていけばそれで良いのだ。おそらくこれが底流にあった信仰信念であったに違いない。そのためには、容易ならぬ心定めがあったと想像されるのであるが、それはもはや、詮索すべきものではないであろう。信念がそこにある以上、氏の態度は極めて単純であった。何を生徒に対して話そうとしたのか。それは一つしかなかった。「誠真実になれ」ただこれだけであった。氏は、頼るべきものは心一つであるということに徹底していた。形の上の教会というものなど信じていなかった。もとより教会の数というものも、頼るべきものではなかった。もし頼るべきものがあるとするならば、名称の理の芯である教会長の心一つ、布教師、ようぼくのお心一つだけであった。その心が人間思案に覆われ、物質に追い回され、真実を喪失しているならば、それは教会でもなければ、布教師でもない。もとより神様の働きがあろうはずがない。言わんや神一条であるはずもない。その心一つを起こし、その心を真実にすること、それだけが信仰の目的であり、これが四十年祭の本当のささげ物であらねばならぬと信じていたのである。だから氏は別科生に向かっても、やたらに布教せよというようなことを口にしなかった。それは、当時の気風が布教へと向かっていたから、そうした反論的な態度になったとも思われるのであるが、本当は誠真実の心をつくることを忘れて布教してみたところで、信仰の世界においては何もできるものではないと信じていたからである。外なるものから内なるものへ。そうした方向の転換の中に、氏は「よなおり(世直り)」の意味を見いだそうとしていた。「よなおり」とは、世の中の客観的状態が立て替わるのではなく、一人ひとりの心が立て替わるということであり、この意味で「よなおり」とは、実は「天理教のよなおり」であった。「よなおり」したらそこに神一条の世界が開け、神意が悟れ、理の働きを如実に受けることができる。そして再び不思議なたすけも続出するであろう。そのために、人間として成すべきことは、ただ一つ、誠真実の心をつくることだけである。これが氏の主眼とした、いかにして神の働きを得るか、ということの内容であった。そのために破壊すべきもの、それと戦わねばならぬものとして、二つのものを見いだしていた。一つは、あまりに教会中心的、形式的に堕しつつあった当時の思潮と、もう一つはあまりに理知的、客観的に流れようとしている教理研究の態度であった。前者に対しては教会の行き詰まり、困窮を神のてびきとして、その中からぢば中心主義の神意を悟らしめ、また人間思案の枠から引っ張り出して再び混沌の中に投げ込むこと。すなわち、安定した教会生活、教会思想から、どう転ぶか分からない不安の中へ人々を投げ込むことであった。後者に対しては、教理はあくまで主観的なものであり、真実の心をつくるためのものであるということを強調し、教理即実行の世界へ突入せしめようとした。誠真実の、神に対する関係が神一条ということであると考えていた氏は、神一条の実現を四十年祭の目的としていたことが分かるのである。そしてそれは、氏にとっては復元であったに違いない。この実現のためには人間思案および新しい思潮との対決が必要であった。この対決とその推移が、実は四十年祭の主要テーマであったといって差し支えはないであろう。 |
|
|
「増野鼓雪の生死論」(「増野鼓雪全集」15巻の302-305P)。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)